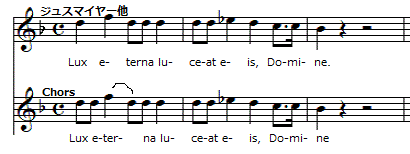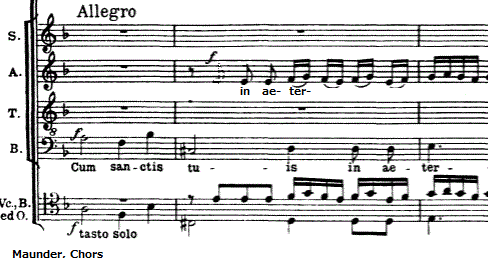Agnus Dei
歌詞
Agnus Dei,qui
tollis peccata mundi: 神の小羊、世の罪を除きたもう主よ、
dona eis requiem 彼らに安息をお与えください
Agnus Dei,qui
tollis peccata mundi: 神の小羊、世の罪を除きたもう主よ、
dona eis requiem 彼らに安息をお与えください。
Agnus Dei,qui
tollis peccata mundi: 神の小羊、世の罪を除きたもう主よ、
dona eis requiem sempiternun 彼らにとわの安息をお与えください
この曲もすべてジュスマイヤーの作なのであるが、意外な力作としてSanctus
,Benedictusと違い、後世かなり高く評価されている。「モーツァルトのレクイエム」からジュスマイヤー的要素を取り除いてしまったモンダー版でさえ、(マイナーチェンジはなされているが)ほぼジュスマイヤーの版を踏襲している。(ちなみにC.WolffはMOZART'REQUIEM p111で「モーツァルトのレクイエム」全体における主題の統一性を強調するあまり、Lacrimosaの第26~27小節のソプラノがやはりIntoroitの最初のフーガのテーマを使用していると書いているが、これはただの偶然なのではないかと思う。それは歌詞と合っていないから) ←Agnus Deiの冒頭のバスパート ←Intoroitの冒頭のバスパート (これは無論歌詞の繰り返しに対応したものではある) Recordareでもやはり擬似的なロンドが認められるが、こちらの方が各フレーズは短く、構成はより緊密である。各フレーズは出るごとに調性が異なるなど、変化が施されているために飽きが来ない。①転調が絶妙である ●各版の相違 <Levin版> <Druce版> VIDEO
<Chors版> VIDEO
Communio 歌詞 (ジュスマイヤー版対応)
sop.soloLux ae ter na lu -ce at e - is, Do Lux ter lu -ce at e Do
主よ、彼らを永遠の光でお照らしください。
sop.soloCum San ctis tu is in ae-ter Cum San ctis tu is in ae-ter )
聖者たちとともに永遠に
quia pi あなたは慈悲深くあられるのですから
Requiem aeternam dona eis Domine: 主よ、永遠の安息を彼らに与え 絶えざる光でお照らしください。
fuga Cum San ctis tuis in aeter
finale qui a pi
sop.solo
Te de hym nus De Si et ti bi redde vo inJe‐ ru chorus Ex- au o- me a d te o- ca - ro ve
Ky ri- e e le son Chri ste ele -
(太字は歌詞のアクセント、下線は音楽的アクセントのあるところ)
この楽章はIntoroitの②、③(当サイトのIntroitのページをごらんください)とまったく同一なので、ここではこの楽章で問題となるアクセントの問題とフーガの扱いについて考えてみたい。モーツァルトが書いたIntoroitとKyrieのところでは歌詞のアクセントと音楽的アクセントのほとんどがが一致しているが、ジュスマイヤーの補筆したCommunioでは両者の間でかなりのズレがある ことがわかる。エ テ ルナ となるべきところがエ テルナ となってしまっており、語学的アクセントと音楽的アクセントとがずれている。ここはしかしやむを得ないところだろう。さすがにモンダーもランドンもバイヤーもここはいじっていない。VIDEO VIDEO ク ームサンクティス となってしまう。だからここは二重フーガの対旋律の方はモンダー版とChors版ではin aeternumで始まっており、Cumとtuisにアクセントがくるジュスマイヤー版の欠点は是正されている。 (aeternumのter-に純粋にアクセントがくるようになっている)同じ歌詞がまったく異なった形で作曲されるという結果になってしまった(アイブラーのレクイエムでは、これをあえて行っている)。 もしモーツァルトがC.Wolffの言うように全曲を特定のテーマで統一しようという意思を持っていたと考えるならばこれは返す返すも大きな失敗ということになるだろう。