|
歌詞(対訳はWikipedia「レクイエム」より)
- ①Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 主イエス・キリストよ、栄光の王よ、
- libera animas omnium fidelium defunctorum 死せる信者の魂を
- de poenis inferni, 地獄の罰と深淵からお救いください。
- et de profundo lacu; 彼らの魂を獅子の口からお救いください。
- libera eas de ore leonis,
- ②ne absorbeat eas Tartarus, 彼らが冥府に飲み込まれぬように
- ne cadant in obscurum. 彼らが暗黒に落ちぬように。
-
- ③Sed signifer Sanctus Michael 旗手たる聖ミカエルが
- representet eas in lucem sanctam, 彼らの魂を聖なる光へと導きますように。
-
- ④quam olim Abrahae promisisti かつてあなたがアブラハムとその子孫に
- et semini ejus. 約束したように
|
この曲は上記歌詞①〜④に分けられる。①の部分はほぼホモフォニックであるが、②〜④はすべてフーガである。フーガが三つも続くのに飽きが来ないのはさすがにモーツァルトという感じ。
①の部分で目立つのが第3小節のアウフタクトからのRex gloriaeを合唱が付点リズムで二回繰り返して叫ぶところ。この小節だけ突出してフォルテとなり、弦楽器も突如としてユニゾンの激しい16分音符を奏で始める。これは第4曲Rex tremendaeの付点音符のオンパレードとの共通モチーフで、「Rex(王)」を表現する付点音符の技法である。これはモーツァルトがテキストの特定の歌詞に特定のモチーフを用いようとする(これをライトモチーフという。後にワーグナーがよく用いたやり方)意図を持っていたことを示す。
ところで①と③でもまた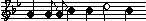 という共通のモチーフが使われている。①では左譜のようにまずg-mollでこれが現れ、第15小節で半音上がってAsdurとなってこのテーマがソプラノのみで出てくる。さらに第B♭mollで再々度現れる。 という共通のモチーフが使われている。①では左譜のようにまずg-mollでこれが現れ、第15小節で半音上がってAsdurとなってこのテーマがソプラノのみで出てくる。さらに第B♭mollで再々度現れる。
このテーマは③の部分でさらにフーガの主題となってソロカルテットによって4回現れる。つまり都合7回もでてくるわけだ。これだけ同じテーマが執拗に出現するのになぜかその繰り返しを感じさせない、不思議な曲である。
②のフーガではモーツァルトお得意の弦のユニゾンによる伴奏がついている。これまでK339のヴェスペレなどで用いられてきたやり方である。(モーツァルトはチェロバスパートしか書いてはいないが、ここの弦が総出でユニゾンとなることは自明である)
さて問題は④である。この歌詞は伝統的にフーガで歌われる。そのせいかどうかはわからないが、この部分のテーマはM.ハイドンのレクイエムと「モツレク」、そしてアイブラーのレクイエムの3曲がそっくりなのである。それではここでこれら3曲のこの部分の評定をやってみましょう。(下譜参照)
 ←モーツァルトのレクイエム ←モーツァルトのレクイエム
 ←M.ハイドンのレクイエム ←M.ハイドンのレクイエム
 ←アイブラーのレクイエム ←アイブラーのレクイエム
M.ハイドンのQuam olim〜は一番単純である。オーケストラは弦楽器が合唱をcolla
parteになぞるだけであり、要所要所でトランペットとティンパニーが入るようになっている。最後はチェロバスのみがオルゲルプンクトとなっている。まあ、一番簡素な古典派時代のフーガといえる。(但し2回目のQuam
olimでは最初の部分だけ申し訳程度にヴァイオリンが対旋律をつけている)
モーツァルトの場合はもっと複雑で、合唱のフーガに対してオーケストラは弦楽器が協力して合唱のテーマとは何ら関係のない独自のリズムを自己完結的に奏でる。(下のMIDIで確かめてください)
この部分の弦楽器パート
こうした芸当ができるのはモーツァルトならではであろう。(但しモーツァルトはチェロバスパートしか書いていない。それをここまでに書き上げたジュスマイヤーの手腕はもっと賞賛されてよいだろう)
それではアイブラーの場合はどうかというと、これがたいしたものなのである。前半のQuam
olimこそM.ハイドン同様、オーケストラは弦と木管楽器のみでcolla parteに合唱をなぞるだけだが、主題の展開のさせ方からしてたとえば途中で主題の鏡像テーマを出すなど、聴くものを圧倒する。そのできばえはとてもM.ハイドンの比ではない。また後半のオルゲルプンクトもより大規模である。
さらにすばらしいのは二回目のQuam olimのところではオーケストラがド派手に変化することである。今度は金管楽器が大活躍をし、要所要所にトランペットとティンパニーが入る。(さすがの「モツレク」も前半と後半はまったく同一である)弦楽器も今度はもっと歌わせてくれといわんばかりにcolla parteに甘んじず、独自のメロディを奏でている。
正直いってこれは「モツレク」よりもすばらしい。この曲を聴いただけでもアイブラーがいかに天才であったが明らかである。M.ハイドンなど足元にも及ばない。(現在の知名度ではM.ハイドンの方がはるかに上であるが)アイブラーのレクイエムは「モツレク」の影に隠れてしまって損をしているとつくづく思う。
<各版の相違点について>
この曲もやはりモーツァルトが合唱部分とチェロバス部分のすべてを書いており、大枠は定まっている。曲の性格上、おそらくジュスマイヤーとしてはこの曲の補筆が一番楽だったのではないかと思われる。この曲に関しては各版ともにそれほど大きな相違はない。ちょっと聴いた限りでは細かい点の相違はわかるがそれがどうなの?って感じ。
バイヤーはその版の序文の中でジュスマイヤー版で使用されている第7〜10小節のシンコペーションの部分に言及し、こうしたシンコペーションはモーツァルト的ではないとしてすべて割愛している。しかしこれは少々行き過ぎのような感がある。実はDomine Jesuにおいてはこのジュスマイヤーのシンコペーションが魅力の一つなのであり、これをすべて捨ててしまって単純なリズムにしてしまったのはいただけない。モンダー版ではさすがにバイヤーのやり方はやり過ぎと見たのか、ジュスマイヤー版とバイヤー版の中間的なリズムをとっている。
<補遺;オルガンポイントの効果について>
④の部分は、第61小節よりオルガンポイントに入る。モツレクの聴きどころの一つであるが、この部分はチェロとコントラバスが分離されていることに注意。(これはモーツァルト自身の指示である) オルガンポイントを奏でているのは、チェロバスと合唱バスのみである。チェロがないことにより、コントラバスのみの時に出現する、あの独特の”乾いた音”が出されているのだ。

|