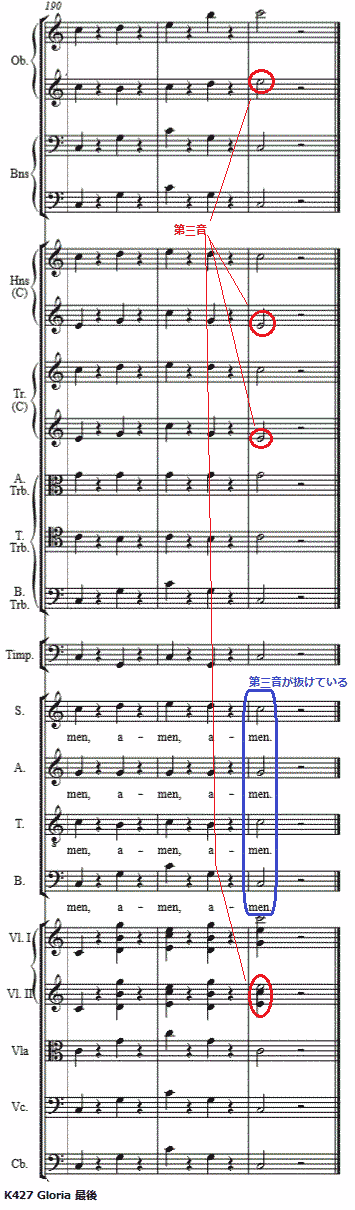Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
恐るべき御稜威の王よ、
救われるべき者を無償で救われる
慈悲の泉よ、私をお救いください。
この曲ではモーツァルトお得意の合唱とオーケストラの完全なる分離が見られる。そして両者は明らかに対決した形で書かれている。(こうしたやり方はモーツァルトの他の教会音楽においてしばしば見られる) (+ファゴットとバセットホルン;但しこのMIDIではクラリネットで代用) の対位法の部分を聴いてみよう。付点音符付きの特異なリズムによる対位法で作られていることがわかる。(Rex tremendaeの対位法のところの合唱パート(第七小節より) (後にバッハやヘンデルがこうしたフランス序曲を模した曲を何曲も書いているのは周知の通り) モーツァルトはこの曲の冒頭の歌詞「Rex(王)」を象徴するためにあえてバロック期の伝統に従い、こうした付点リズムを用いたのである。 Rex tremendaeの弦楽器部分(第7小節より) 第3小節〜 <アイブラーとジュスマイヤーの違い> おそらくは、Tuba mirum 同様、木管楽器は後で付け加えるつもりだったのであろう。 モーツァルト自筆譜 冒頭 アイブラーの補筆に加筆 する形での補筆が必要だった わけで、ジュスマイヤーはそれをしたわけである。実際ジュスマイヤーは、Dies
iraeほどにはアイブラーの補筆を変えておらず、一部を除き、ほとんどアイブラーと同じである。<各箇所の違いについて> ・第1小節 ジュスマイヤー自筆譜 冒頭 ジュスマイヤーの補筆における最大の失敗 である(Maunderは、その著Mozart's Requiem p151-2において、「ジュスマイヤーの第1小節第2拍のこの和音は、第3小節からの合唱のエントリーを奪ってしまうから削除すべきである 」と述べている) 。たとえ従来通りのジュスマイヤー版で演奏するにしても、このぷぁ〜だけはカットすべきなのではないだろうか 、と言いたい。私が指揮者なら、断固としてそのようにするが。なぜ、名だたる指揮者がこのぷぁ〜をカットしないのか、不思議でならない(たとえば、ベートーベンの”第九”などは、各識者が相当にいじっているのに) 。楽譜はいじくらないというのがバッハ以降のクラシック音楽演奏の掟であるとはいえ、やはりよけいなモノは取り除いた方がよいのだ。ましてやジュスマイヤーの補筆した部分であるのだからして、そのくらいの可塑性はあってもかまわないと考えるが・・・・第2小節 この部分がイントロイト第7小節を想起させる ので、レクイエム全体を少しでも統一した動機で結び付けようという発想である(下譜)。なお、Chors版では、四分音符の木管楽器のみとなっている。・第6小節 金管楽器、ティンパニを含めて 、ド派手にやっている。王よ、王よ、と叫んできて、ここで一気にRex tremendae majestatis,恐るべき御稜威の王よ、 と四声で叫ぶのであるから、まあ通常はこのようになるのが当然であろう。(おそらくは、和音の不足は、オルガンで補なう前提なのであろう。実際、↓の演奏でもオルガンが活躍している) 。そして、第7小節になって、器楽バスのレ音が、どん、と入ってくる。この効果は独特で、個人的には、この版の好きである。VIDEO Landon版 15分39秒〜 モーツァルト自筆譜(=アイブラー) ・第7小節〜 Mozart’s Requiem p153)して延々と動いている(下譜)。Rex tremendae第7小節からのジュスマイヤー版(アイブラー)の弦楽器部分 Rex tremendae第7小節からのバイヤー版の弦楽器部分 ・第10小節 ・第12小節〜 第13小節〜 ジュスマイヤー版 第13小節〜 バイヤー版 第13小節〜 モンダー版 第13小節〜 Levin版 ・第15小節〜
これに対してBeyerは、言葉への関連付けが見られる。たとえば、ジュスマイヤーがRex tremendae majestatis qui salvandos salvas gratis (太字がトランペットとティンパニ部分、以下同様)としているのに対し、Beyerは、Rex tremendae majestatis qui salvandos salvas gratis とし、言葉との関連をより強調している(下譜)。
さらに、Maunder版やLevin版になると、下譜のように、Rex tremendae majestatis qui salvandos salvas gratis となり、トランペットとティンパニで作られる音楽リズムと言葉が完全に一致する。アイブラーとジュスマイヤーの相違部分 アイブラー 第16小節〜 ジュスマイヤー 第16小節〜 ・第18小節〜 senza tromboni と書いている。・第20〜22小節 モーツァルト自筆譜 第18小節〜 第20−21小節の第1ヴァイオリン(その他部分同様、第2、ヴィオラも)は、もともとはアイブラーが補筆した部分である ここは以下のように分かれる。
Maunderは、その著Mozart's Requiem p155において、以下のように述べている。 第20〜22小節。Blumeは、この部分はア・カペラで演奏されるべき、と主張している。そして彼は、モーツァルトの自筆譜における第1ヴァイオリンにおいては、休符の記号が見られる、と主張している。しかし、もしもモーツァルトがここでア・カペラ合唱を求めているのであれば、チェロバスのためのリピートされた八分音符を書くことはなかったであろう。K317の第27小節にあるように、モーツァルトは、そうした意図があったならばならば、完全にア・カペラで書いていただろう。イントロイトでの第46−7小節のように、彼が単純な弦楽器の伴奏を求めていたことは確かである。なお、アイブラーの加えた第21小節第4拍の7度和音は排除されるべきである。 合唱の第三音の抜けを、オーケストラが補っている
第22小節は、合唱がKyrieの最後同様、第三音が抜けた形になっているが、オーケストラが第三音を補う形となっている(これはモーツァルト自身の自筆譜がそうなっているために、すべての版で共通である。しかしBeyerだけは、第21小節の第1拍には第3音が抜けている))。
P.S. モーツァルトは別に第7〜11小節の合唱部分のスケッチを残している。これは現在演奏されているものとはかなり異なる。モーツァルトは合唱部分は完成しているのでこのスケッチが新たな補筆で生かされていることはないが、参考までにここにあげておきたい。上記スケッチのMIDI