| Musica Ficta and Harmony in Machaut's Songs* THOMAS BROTHERS |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |
| score Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image http://machikun.la.coocan.jp/medievalmusic8.htm p504 ほどなく、musica fictaは、垂直的なソノリティを構成するこのダイナミックな概念において、積極的な役割を演じることになった。静的概念における役割は続けながら。このinflectionは、不完全協和音程が獲得した指向的tendencyを高めることになった。再度、Marchettoは初期のソースで言った。 The diesis is a 5th of a whole tone, occurring when, for instance, any whole tone is divided in two in order to color some dissonance such as a third, a sixth, or a tenth striving toward some consonance マルシェットの特異性(全音の新たな分割、および他の場所で言及されている、それを記譜するための新しい記号)は、その時代の標準的な見方を曖昧にしない。 14世紀の理論家は、musica fictaを使用して不完全ソノリティを完全ソノリティに調整することを推奨している。これにより、一方の声部が半音で、もう一方の声が全音で進行する。 フランスの理論家たちはその慣行を説明しているが、イタリアの理論家たちは、少ししか語っていない。Prosdocimo de 'Beldomaは、それがどのように作用するかを、以下に説明している。(略) p505 イタリア人理論家のリードに従い、我々は、これを"proinquity" application として言及し得た。causa necessitatisとの類似を通して、それは、causa propinquitatisとなる。 今日、proinquity application が演奏慣行として伝統的に適用された立場の背後にはかなりの勢いがあり、その適用はすなわち、それを示す記号が欠如しておいてさえ、なされた。そしてそれほどの普遍性ゆえに、作曲家は、それを示す必要がなかった。 この立場は、現代の音楽学に深く根ざしている。それは、当時は自明だった慣行を再発見した Hugo Riemannによって、協力にブーストされた。 p506 Hugo Riemannにとって、しかし、問題は、単に失われた演奏慣行の詳細を回復しようとすることよりもはるかに大きかったことは明らかである。 Raymond Haggh は、リーマンは「初期の音楽をメジャーまたはマイナーの調性に可能な限り一致させるための編集者としての欲望に照らして読まれるべき」と述べている。中世後期の魔術が現代の耳のスタイルへの入り口の主要なポイントを提供するというリーマンのプロジェクトよりも優れたデモンストレーションはない。そして、「失われた自己証拠」と初歩的な調性の概念との強力な混合が20世紀を通してどれほど残っているかを知るために、それほど遠くを見る必要はない。 しかし、こうした現象に対する20世紀の関心が持続したにもかかわらず、14世紀の理論家は、propinquity applicationに関する無記名の慣習の存在を宣言または示唆さえしていない。 Tinctorisが有名にしたものとも遠く離れている。コンテキストが必要性を明らかにすれば、♭記号を表記することは当然なのである(この場合、コンテキストは間接的三全音となっている)。14 理論家は通常、上記の引用でProsdocimusが行っているのと同じように、soft bおよびhard bの記号を参照したmusica fictaの適用を論じている。 p507 実際に、ポリフォニー音楽において、記譜されていないinflectionsに対する何等かの慣習が14世紀には存在したというようなことについての、理論的に強力な証拠はない。 少なくとも、これは我々が、伝えられた音楽テキストを理解するためにあらゆる努力をすべきことを意味する。我々は、テキストが文字通り完全である(おそらく正しくはないだろうが)ことの可能性を真剣に受け止めるべきである。 自明の演奏慣行がなかったと主張し、それらをカバーする希望を放棄すべきだと主張するのは愚かなことである。しかし、ポリフォニー音楽の解釈が、演奏慣行の側面として、musica fictaに重点を置くことによっていかに広範囲に条件付けられているかを理解することは重要である。中世後期の印象的なポリフォニーの成果を理解しようとする我々の試みで実際に非常に重要であるかもしれない、演奏慣行のの概念が作曲慣行の微妙さを曖昧にする方法を見ていたい。 私たちが頼る論文は、通常、理論と教育学を強く組み合わせている。それらはしばしば前者よりも後者に傾いているが、両方の点でテキストは、基本的な問題を扱っている。それらは、音楽の初歩的で普遍的なファンダメンタルズをカバーしている。 このため、それらは高次の解釈では限られた用途しかない。これは、musica fictaの使用におけるニュアンスを解釈する場合に特に当てはまる。たとえば、論文は、近接的な調整が、♯または♭のいずれかで行われる可能性があることを明確にしている。ただし、2つの方法のどちらを選択するかは指示されていない。次の進行は、2つの方法のいずれかで調整できる(例1を参照)。 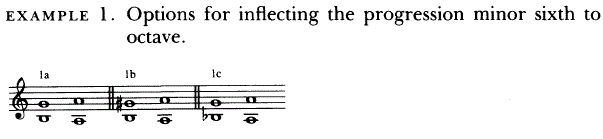 Margaret Bent and Andrew Hughes は、このジレンマを回避する方法を模索した。パフォーマンスの実践のコードは、 musica fictaよりも musica recta (つまり、伝統的なグィドの手の音程)を優先することを示唆している。これらにしたがえば、この例ではg-sharpではなくb-flatを選択することになる。しかし、理論的言説の調査と批評に基づいて、Karol Berger はこの推論の行に対して反対した。さらに、Bergerは、逆に、理論家はfa inflectionよりもmi inflectionを支持するように思われることを示唆する証拠を提供している。例1に当てはめると、彼の議論ではg-sharpを採用することになる。15 15 Berger discusses the matter, critiquing the position of Bent and Hughes, in Musica Ficta: Theories of Accidental Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino (Cambridge, 1987), 83-84, citing Bent and Hughes in note 64, p. 216. Berger's review of evidence suggesting mi preference over fa preference is on pages 139-50. p508 Bergerの洞察の確認は、実質的な資格とともに、写本の証拠の調査から明らかになる。16 16 Primarily that of the Machaut sources, but also evidence drawn from a survey of the chanson during the period ca. 1275-1475; see my Chromatic Beauty in the Late- Medieval Chanson, Chapter2 この例では、ソルミゼーション言語として、bフラットは、最低音(根音)の半音上を通るarrivalであるmi clausulaを産生している。(aを"mi"としてソルミゼーションする)。旋法用語でいえば、進行は、フリギア旋法あるいはdeuterus modeを示唆する。そして、現代用語でいえば、定式は、”下げられた導音”を意味する。 写本の証拠のパターンでは、下げられた導音が少数派であるとは限らず、その定式はむしろ、特殊なやり方において使用されている。 formes fixes(歌曲定型)の外観を定義する結節点(ouvert,clos,最終カデンツなど)の研究からは、マショーは、ouvertの位置に、ほぼ常に、下げられた導音を使ったことが明らかになっている。17 17 下げられた導音は、マショーの多声バラード、ロンド―、ヴィルレーにおいては、最終ポジションでは、決して使われていない。下げられた導音は、20の歌(署名による臨時記号とEへのarrivalのどちらでも)において、ouvertポジションで使われている。 ouvertポジションにおいて、完全協和音程のarrivalを不安定化するためにマショーが使った別の定式は、下げられたupper neighborを経由するcantusによる完全五度である。たとえば、b♭を経由したD/aや、fを経由したa/eなど。この定式はまた、最終カデンツではまったく避けられている。こうした考察は、マショーのソースの研究をベースとしている。 こうした点から、我々は、下げられた導音カデンツは、上げられた導音と比較して、試用的な解決である、と結論づけねばならない。下げられた導音は、不完全協和音程のarrivalが適しているのと同じやり方において、ouvertポジションのカデンツに適しているのである。18 p509 作者不詳として伝わっている。Pour tant se j'ay le barbe griseの作曲者は、通常とは異なるやり方で、この区別を利用している。典型的には、ロンド―における中間点のarrivalは、最終カデンツの一音上の位置しているが、Pour tant se j'ay le barbe griseでは、中間と最終カデンツの両者ともに、D/a/dでのarrivalとなっている。 両者のカデンツはそれぞれ、propinquity applicationsによって区別されている。中間カデンツでは、e♭が記号化され、最終カデンツではc♯が記号化されている。arrivalの異なった音程によるouvert-clos構造をマークする代わりに、このような前方指向を付与し、その結果で、最終カデンツを強化するなど、作曲家は、2を♭化するか7を♯化するかの区別を利用して、propinquity applicationを操作し、同じ結果を達成しているのである。 これらの観察から引き出される一般的なポイントは、臨時記号は、和声の階層を定義するために使われている、ということである。上げられた導音(♯)は、下げられた導音(♭)よりも強く、これにより、ouvertと下からの導音とが関連付けられる。 (こうして、15世紀の終わりの「フリギア効果」の出現を分析できるだろう。いずれにせよ、和声の不安定がその影響の重要な部分であることは明らかである。) 訳注;「フリギア旋法」のカデンツは通常、2での下方の半音(たとえばハ長調音階でレ音が♭化する)が所定の調号の下で自然に発生した場合にのみ使用され、2を♭化するか7を♯化(たとえばト長調音階でファ音が♯化する)するかを選択する場合、後者の解決が好まれた。Musica Ficta p141 したがってBerger が「14世紀の証拠、特にMarchettoとPetrusの証拠は、導音を選択する必要がある場合、fIatではなく、シャープであることが好ましい解決策であった」と主張する(Musica Ficta p143)時、私の役割は、それがより強いかどうか、そしてより一般的に使用されているかどうかという感覚において、♯が好ましい「解決策」であるとすることである。 ♭は特別な効果のために保持されているため、二次的なのである。マショーのバラードとロンドーの結節点での使用パターンは、内部カデンツでさえ、階層の区別が常に有効であるという考えをサポートするのに十分なほど一貫している。とにかく、これは我々がともに機能することができるという前提である。 Ars novaのポリフォニーにおける和声に関するSarah Fullerの研究は、和声的ジェスチャーの階層を定義するために臨時記号をどのように使用できるかについての理解をさらに深めるための良い土台を提供する。20 20 "On Sonority in Fourteenth-Century Polyphony: Some Preliminary Reflec- tions," Journal of Music Theory XXX (1986), 35-70 不完全協和音程から完全協和音程への進行が緊張と解決に関連しているという基本的な考え方に基づいて、Fullerは、さまざまな種類のソノリティを相対的な安定性と不安定性に調整しようとしている。 これにより、彼女は「、中立的あるいは特定の主張がないものから直接指向されたもの」(p。51)までの範囲で進行をランク付けしている。 p510 スペクトルの一方の端は「二重に不完全」なソノリティ(たとえば、D/F♯ / b、6/3が組み合わされているため「二重に不完全」)、もう一方は「二重に完全」な例(たとえばD / A / d 、五度とオクターブを組み合わせているため、二重に完全)である。両者の間に、混合ソノリティ(たとえばD/F / a)が入る。 inflectionは重要である。たとえば、(inflectionが絡む)D/F♯/ bは、D/F/bよりも確実に指向的である。それだけでなく、inflectionの存在そのものが、重要なイベントを示している。これは、本研究が最大限に活用しようとしている洞察である。厳密な構文システムを識別することは、Fullerの意図ではない。むしろ、彼女は、作曲家が和声を含むいくつかの基本原理を操作して作品を形作る方法を示すことを目指している。イベントは、構文の指示から行うのと同じように、コンテキストから意味を取るのである。21 21 しかし、実際の慣行では、客観的なタイプと特定の性質との関連は、曖昧さの影響と機能を限定するために、複数の要素が、ソノリティの効果と機能を作品内容において適格とするために、行動する。同書p44 ここで進められた特徴付けは、音楽の出来事に強制される固定したステレオタイプではなく、規範への有用なガイドとみなされるべきである。同書p45 その内容には、voice-leading, duration, mensural position,、そしてとりわけ、全体としての作品のピッチ構成が含まれている。 マショーによるモテットの分析で示されているように、これらの要因は、ソノリティと進行をどのように解析するかを決定する。 Machautの Nes que on porroitは、inflectionがそれほど重要な役割を果たさないバラードで、このアプローチが、サービス全体の設計で作曲家が扱う和声の側面を解明するのにどのように役立つかを示している。 ouvert, clos, 最終カデンツを持つバラードの音楽的分析が、例2でおこなわれる。voice eadings は通常とは異なる。すなわち、cantus and tenorは、contrary motionではなく、同方向へと進んでいる。そしてそれらは段階的ではなく、跳躍的に動いている。 一方、 arrival音程の位置に関しては、こうしたカデンツは、closと終止が1ステップ上に位置するouvertと適合されるという、標準パターンに従っている。 さらにまた標準的なのは、このパターンが作品全体の編成ピッチと完全に調和していることである。Cは明らかに、メロディ的にも(cantusを通して)、和声的にも( C/c/c と C/G/c)、強調されている。したがって、3か所の主要なカデンツのオープンステータスとクローズステータスを解析することについて、あいまいさはない。 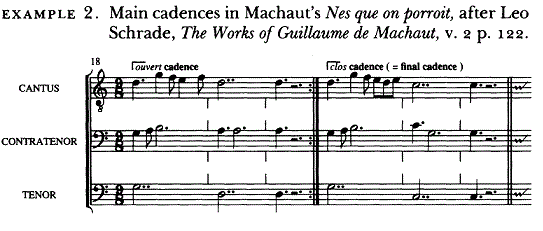 Songの中身においては、CとDの両者を強調する少数の明らかなdirected progressionsがある。 p511 特にそのいくつかは、弱拍の計量的位置で生じる。(たとえば、第4小節でのD/a/d、第8小節でのC/G/c)。私は、こうした内容が、これらの場合に、計量譜の位置が、他の点では明確で強力な和声の進行を損なうという示唆による和声事象の分析を示すに違いないというFullerの主張は認めることだろう。 我々は、3か所の主たるカデンツでの通常ではないvoice leadingsについて考慮すべきである。古典的パラダイムにおける強い進行は、2つの主たる声部間のステップによる反行を特徴とする。Nes que on porroit les estoilles nombrer のclosと最終カデンツの下降五度跳躍は、DT進行とは表面的には似ている。なぜなら、こうした跳躍は、和声的強さをもたらすと考えられがちだからである。だがそれはまちがいなのだ。むしろこうした進行は、14世紀の典型的な強いカデンツよりも弱いのである。音楽の雰囲気は、何よりもまず、cantusの8分の9拍子のゆったりとした流れによって調整される。 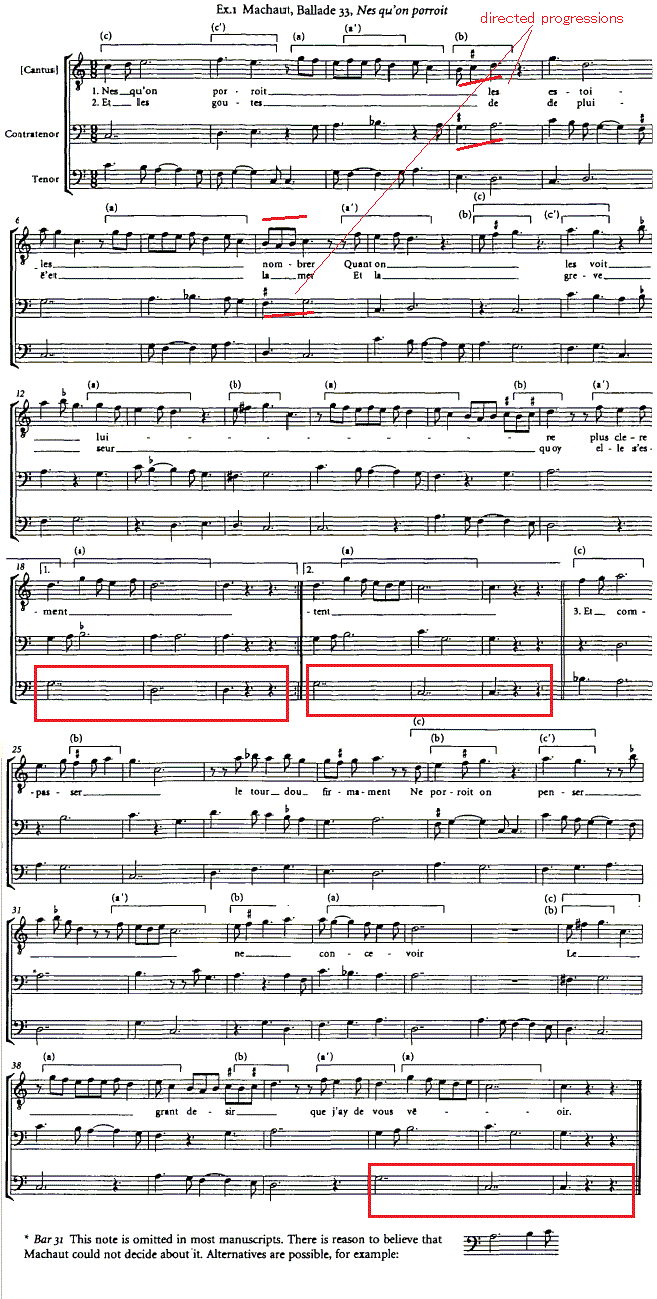 Guillaume de Machaut: Nes que on porroit les estoilles nombrer p512 B4 Biaute qui toutes autres pere(例4)23は、3つの結節点がそれぞれ同じピッチを強調する極端なカデンツパターンを中心に構築されている。 マショーはDを最低音に保ち、完全五度(D / a、ouvertの場合)と完全八度(D / d、ClosとFinal)の微妙なコントラストの手段によってのみ、ouvertとclosを区別している。 (1336年に、Petrus Frater dictus Palma Ociosaは、オクターブが五度よりも安定している音程の階層を体系化している。24) さらに、テノールはいずれの場合も跳躍によって進行し、先行するトーンがないため、3箇所のカデンツはすべて弱くなっている。 そして、cantus (recall Nes que on porroit)には導音がない。 それは悩まし気な組み合わせである。すなわちマショーは、大規模な前方指向を打ち消すかのように、同じ音程に3つの主要なカデンツを配置し、arrivalsが実際に、その前に来るものを何も結論付けていないかのように、それらを弱めている。 EXAMPLE 4. Machaut's Biaute qui toutes autres pere, MS Vg. 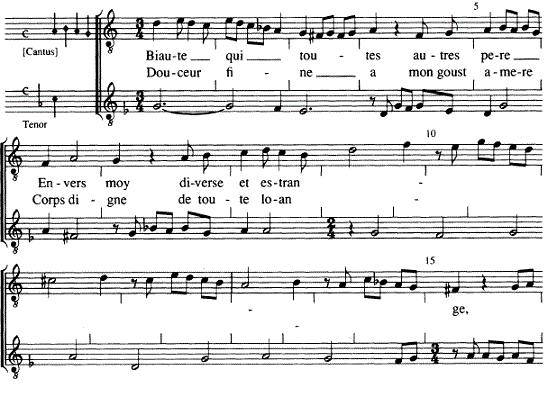 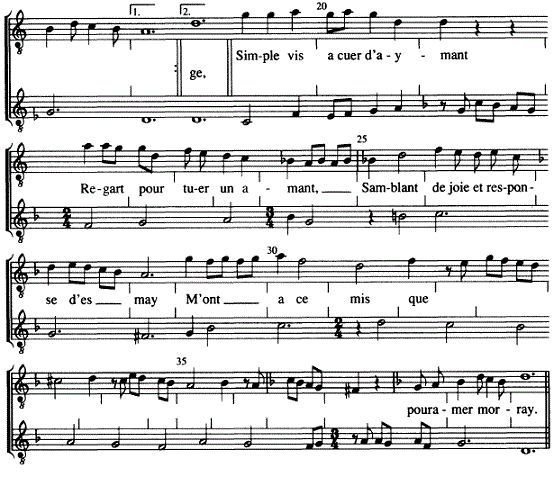 楽譜(B4) 写本 Biaute qui toutes autres pere ~ Guillaume de Machaut 色気がすごい あるいは、少なくともそれは状況を見る1つの方法であり、私はこれらのカデンツが、署名された臨時記号とともに、作品全体を通して音程の組織化に役割を果たす方法を提案しようと思う。 Biaute qui toutes autres pereは、MS Vg における旋法的な譜表の中断(臨時記号が譜表に付される)と音部記号の変更の規則が、この編集では、通常の「小節線」によって譜表と記号で示されていることを受け入れるのであれば、ほとんど意味がない。なぜならば、もしそうならば、ソースの新たな譜表が小節線の後に表示され、その記号は、その後、オリジナルの写本に従って、編集の各譜表で署名が繰り返されるからである。 たとえば、第36小節でcantusのbフラット署名を伴う音部記号の変化があり、これに続いて第38小節でbフラット署名を持つ新たな譜表が始まる。どちらも(上譜では)譜表を通る棒線で表され、b-flat署名が示されている。 ただし、MS Vgのスタッフの矛盾した記号によって署名フラットがキャンセルされた場合、その後、署名は編集で削除される(たとえば、第25小節のテノールでb Mensurstricheは、完全brevesの規則的な流れを示す。この曲は、各セクションの終止部分のメリスマにおいて、 perfect tempus と imperfect tempus を同時に使用することで有名である。 MS Vgでは、明らかに2人の異なるスクライブによる、cantusの始めに記された2つのbフラットが示されている。両方の標識を記すには十分な余地があったようだ。主要なマショーのソースは、この版で提示された臨時記号のほとんどを受け入れている。音楽テキストに関する主な疑問は、、cantusにおける第5-9小節でのbフラットの存在または不在であるように思われる。 p514 Dを強調した3か所の主たるカデンツ以外では、Gが、もっとも重要な音程として強調される。その結果としては、この作品は、結節点と内部の流れのデザインが互いに対立する、矛盾した方法で構築されていることになる。 p515 おそらくこれは主要なカデンツの相対的な弱さを説明している。すなわち、矛盾したこのコンテキストでは、以前に起こったことを結論付けられない。 そし3回の繰り返しは、カデンツがメインフローから外れているという発想を支持する。なぜなら、繰り返しは、ouvert-clos-finalパターンからの大規模な前方指向のパターンの間隔を否定するからである。 Dは、セクションの最後で繰り返されるという利点に関連付けられており、ポリフォニックフローによって暗示されるゴールをかなり満たしている。 Gは、パート1(AA'BのAに当たる)の一連のハーモニックイベントを通じてメインピッチとして強調される。 冒頭のソノリティはG / dである。 cantus形成は第7小節のGがarrivalのポイントであり、冒頭のdからの少し遠回りのゴールであることを明確にするのに役立つ。 第7小節のこのarrivalは、詩の第2行を分割するが、最初の主たる音楽フレーズの終了をマークする。なお、第4小節のダウンビートでのaが、フレーズのouvertの中央を表し、第7小節のGはそのclosの終了を表す。 Musica ficta(訳注;写本では、譜表としてすでにEに♭がついているので、厳密にはMusica fictaとはならないのではないか)は、この構造の定義に役立つ。すなわち、テノールのEフラット(m。3)は、D上の中間のarrivalのouvertの性質を決める導音となる。同時に、cantusのF♯は、Gへの強力なarrivalを示している。(臨時記号の効力がどこまで続いているのかが、常に問題となる。ここでは、cantusのF♯は、第6小節を通じて効力があると仮定する。テノールのF 第7小節が次に起こることによって確信される強いarrivalをマークするという感覚、第7→9小節でcantusがdに戻るため、2つの声部はどちらも、G/dの開始時のように正確に落ち着いている。これは、第9-16小節の勇壮なメリスマに入っていくために適したやり方と言える。 このメリスマでは、テノールのシンコペーションは、適度な緊張とリズムと和声を供与する。26 26 Richard Crocker は、テノールが1semibreve分(訳注;1四分音符分)前方にシフトした場合、このパッセージ隠された構造がどのように明らかになるかを私に指摘した。すなわち、もしも第 9小節の休符が削除され、テノールのGがcantusのDの下に配置されることになる。これは、cantusとテノールの間で、適切なdiscant流儀において、協和音程の連続を産生することになる。(下譜) 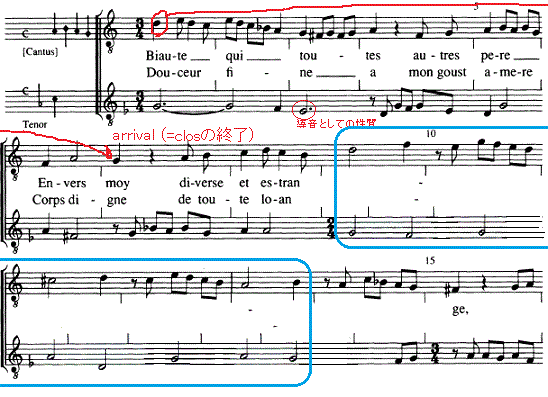 Gは再び、この不協和音、複数の記譜法のパッセージが、第15小節のF♯で明らかになるという事実によって強調される。F♯は、明確な方向感覚を表している。gはまた、第10小節の高い境界としてのその位置も強調されている。 そしてそれがouvert cadence(第30小節)のためのaの止まり木となる時、cantusは、ouvert とclos終止の間の伝統的な一音ずれた関係、a-Gを預言している。 パート2は、バラードの典型的な手順であるいくつかの強調された音程(C、B-flat、C)のdigressionで始まる。最終的に、Gの重要性は別の重要な箇所で再確認されている。ルフランを宣言するためのソノリティは、第28小節のF♯/aである。 「Rounding」(第10小節〜の繰り返しである第32小節〜)は、複数の計量的メリスマとclos終止の再宣言の若干のrevisionをもたらす。 p516 Biaute qui toutes aiutres pereを単一の支配的なピッチに単純化reduceすることはできない。あいまいなデザインでは、臨時記号によって提供された方向性のある階層的なシグナルが、重要な役割を果たす。27 27 Biaute qui toutes autres pereとJe ne cuit pas(B14)を比較してみよ(SchradeSchrade、ed。、p。85)。後者のバラードは、aを量的に強調している点で注目に値する。強調はされてはいるが、このaは、近接するbフラットを通じて二次的な音程として明確に確立されている。 clos と最後のカデンツは別として、Dは控えめに使用される。DはAへの暫定的なarrivalといくつかの重要なcシャープによって準備されるが。 ロンド―Comment puet (Schrade、154)は、Biaute qui toutes autres pereに非常によく似ている。ロンドーの(D / F-sharp / a)の中間は、最終ケイデンス(D / a / d)と同じ音程を強調している。少数のinflectionが、さまざまな領域ですばやく曲をリードする。すなわちDは、cシャープですぐに確立されるが、続いてすぐに、bフラットはaを強調し、b Dは最初のフレーズの結論にすぐに戻る。フレーズ2では、Biaute qui toutes autres pereのメリスマ的な流れと変わらない下降する流れのinflectionは、不安定性を示している。このフレーズのGへの結節点は、中間点でD / F-sharp / aへの方法を提供する。最後のいくつかのフレーズは、Dに戻る前にCを介して歌を担う。この歌は、作品の和声組織にフルに参加する「必須」のコントラテノールを示している。 この歌は、マショーがバラードに関心を持っていた時代の比較的早い時期に当たるようだ。おそらく、休符のない、実験的な嗅覚は、マショーがars novaの基本的にリズムが複雑な和声構成の彼の統率を柔軟にしたブレイクスルーを示している。 約75年後、デュファイは同様の概念を持った。 彼のバラードJe me complainsでは、dが強調され、cシャープはそれがメインピッチであることを強化している。28 バラードの3か所の主たるカデンツは a/aa で終わり(バラードには二者択一の第1と第2の終わりのパート1がない)、cシャープはAの上で3回鳴り響いて「半カデンツ」(mm。7、10、および28)を形成し、Aとの不安定性の関連を確認する。従来のcantus / tenorのフレームワークは、primus、secundus、およびtertiusとマークされた同音域声部のために、放棄されている。従来のdiscantカデンツは、不規則に散在している。そして、あたかも補償するかのように、Du Fayは明確に指示された半カデンツの計画を立て、D上の強いソノリティを規則的に置き、a / aaの主たる結節点に弱いarrivalを置いた。Biaute qui toutes autres pereと同様に、注意深く配置されたいくつかの臨時記号が、矛盾するデザインにおいて、重要な役割を果たしている。 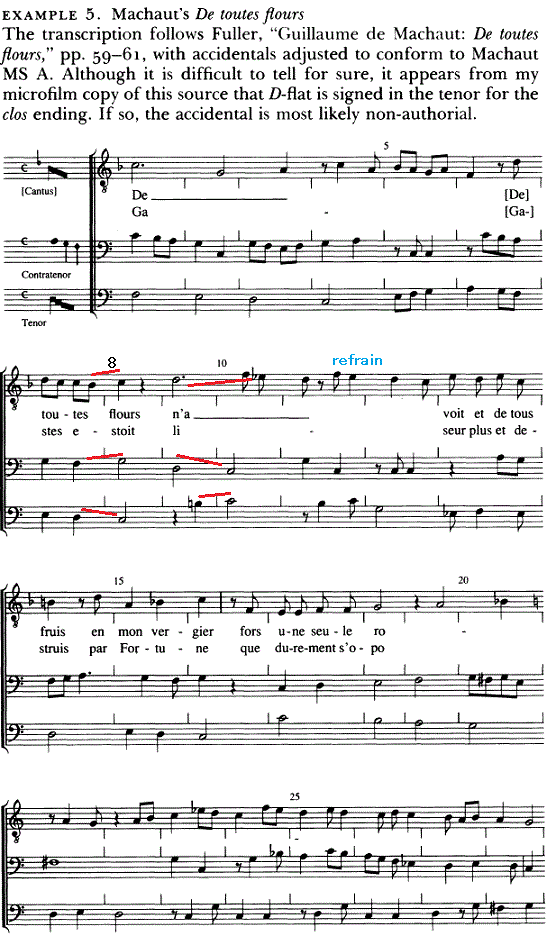 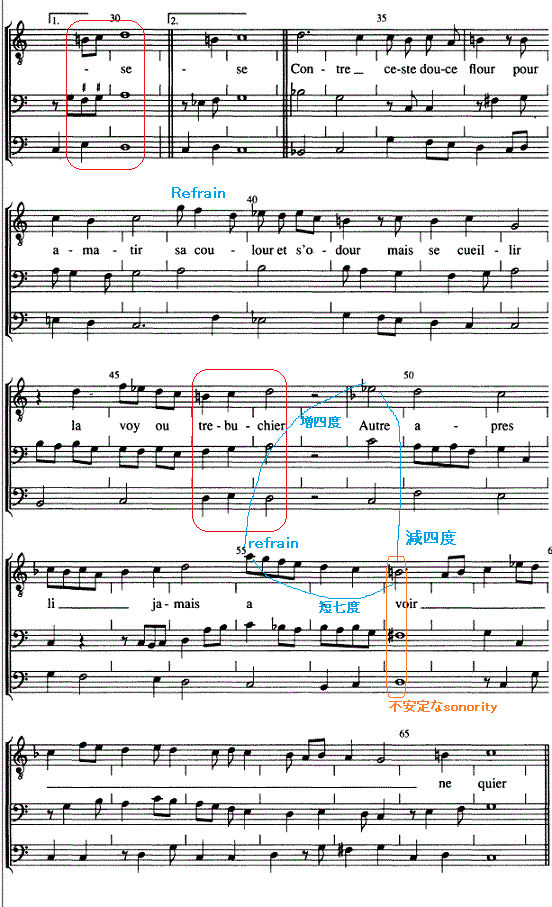 Guillaume de Machaut, B31 - De toutes flours (MS Vg) shahon B31 - De toutes flours は、主なソースを通じて安定している音楽テキストが、これらの慣習に関する現代の仮定と矛盾しているため、近接的適用(propinquity application)に対しての非記譜的慣習の中心問題を引きずっている。 p519 Dropping the assumptions, 我々は、テキストを、マショーの時代の和声言語の扱いについての彼の興味の洗練された表示として理解するかもしれない。曲はFullerによって解析され、その和声についての働きは、これまで見てきたように、臨時記号を解釈することから、1つの基盤を提供する。しかしながら、現在の研究による臨時記号に関する見方は、Fullerによって追跡されたそれとは基本的に異なる解釈を導く。29 曲は5つの主要ソースと4つの二次ソースによって伝播されている。 Fullerは特に、厄介な状況に注意を向ける(エディションの第15小節)。 一部の問題は特に厄介です。たとえば、フレーズ2の終わりのvergier(breve 15)では、2つの主要なソースのcantusに記譜されたBフラットは、カデンツで予期され、他のCエンディングで指定された通常のinflection(長六度D-B→オクターブC)と矛盾します。 Bフラットがcantusの「署名」として表されている他のコピーでは、フラットは指定されていません。これらのソースから演奏する訓練を受けた歌い手らは、Bナチュラルを確実に歌って、従来的なカデンツの進行を提供し、breve14でのBナチュラルの解決を満たし、作品の他のCカデンツと一致します。 vergierの表記Bフラットは、従来の演奏旋法を無効にしたいという誰かの明白な欲求を意味しますか? それとも、「署名」Bフラットの復元の時期尚早の兆候である筆記の失効ですか? 2番目の位置については、2つの主要なソースの特定の性質、他の場所での音声を主導するパターンとMachautの通常の慣行のパターンに基づいて良いケースを作ることができますが、他の見解を完全に排除することはできません。 14世紀の演奏慣行に対する私たちの理解は、私たちが望んでいるほどにはしっかりしていないことを認めると、矛盾や例外を受け入れる可能性が開かれる。 p520 特に、特異な作品では、臨時記号を追加したり差し引いたりせずに、テキストが文字どおりに解釈される可能性を真剣に検討することをお勧めしたい。 第15小節のbフラットは、2つの理由で興味深い。すなわちこのbフラットは、この音程がcに到達する前に、2小節分前のcantusでのb フラットが、懐疑的な筆記者によってどのように落とされた可能性があるかを理解するのは簡単である(そして、Fullerは、彼女がそれを含むソースの彼女の版からそれを落として、それを示している)。 しかし、記号の伝達は弱くない。 それは主要なソースではしっかりと伝えられており、二次的なソースでのみ落とされている(表1)。32 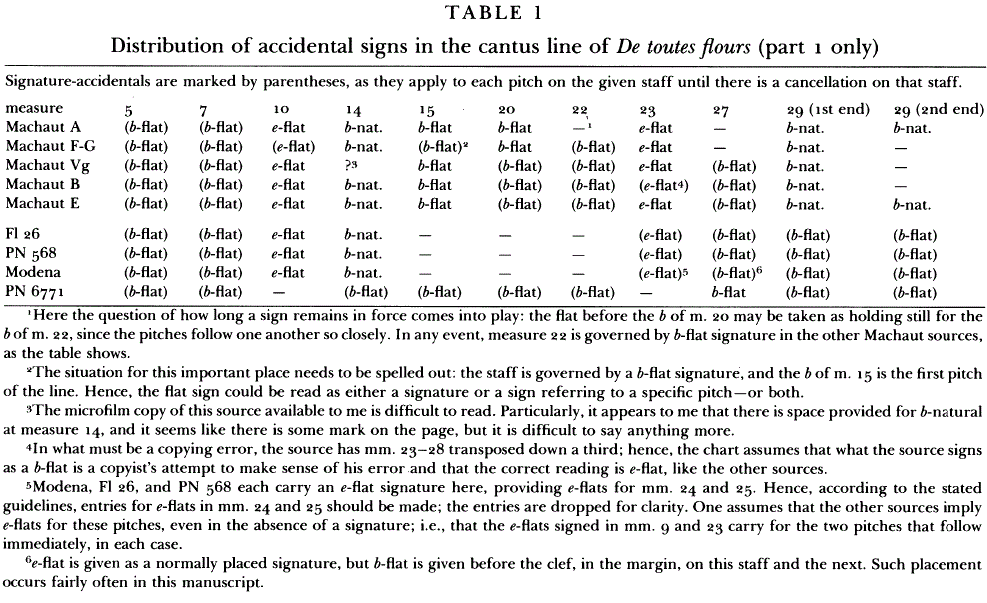 主要なMachautの写本はすべて第15小節でcorruptしているが、二次的な写本は信頼できる解釈を与える可能性は非常に低いようである。 (略) p523 主なソースは、多くの予想外のターンを伴う、非常によどみなく展開する作品を記している。二次的なソースのうち、フローレンス26、PN 568、モデナは、主要なソースに記されたinflectionのほとんどを保持している。それらは主に第15-22小節ののbフラットを欠いている。 PN 6771の筆記者にとっては、作品は月並みなものである。すなわち、e-flatは完全にsuperiusから消えている(チャートに示されているようにパート1だけでなく、作品全体を通して)。 明らかに、このバージョンの曲だけを我々知っていたならば、作曲家の構想の本質的な要素についての手がかりはなく、実際に、何回それが現存するポリフォニー作品を通して起こったのか、疑問に思うだけであっただろう。 厄介なb-flatは、曲の分析で容易に見出される。cantusは、c上で、最初の音楽フレーズ(mm.1-8)を開始し、終了する。そしてこのフレーズは、伝統的なカデンツcに似たもので終止し、声部は、二重の不完全ソノリティから二重の完全ソノリティへと反行進行をする。)  しかし、b♭署名がまだ、このピッチを管理しているため(すべてのソースでそうである)、arrivalとしては、比較的、弱い。ソースは、b そして、すでに今しがた見たように、いくつかのソースは、(第15小節のb♭のために)すぐにb マショーには、cへのすべてのarrivalを同じようにしたくなかった正当な理由があるかもしれない。最初のフレーズの間で、いくつかのイベントが、音程間の明確な階層の感覚を弱めている。 cantusはcから始まるが、テノールはFで始まる。そして、第6小節では、Fが再び強調される。カンタスはbフラットを介してcから離れることで、このFにかなり十分に到達する。中世後期の曲でよくあるように、ピッチは動的に予測できない形で編成されている(これはまた、そのフレーズまたは作品を特定の旋法性または調性に「イン」としてラベル付けすることが誤解を招く1つの理由である)。 p524 フレーズ2は、b p525 36 実際には、cantusのeフラット記号は、すべてのソースで、第9小節のdの直前に配置されており、フレーズを担っていることは、明らかである。これは実際、記譜されていない慣習における問題ではない。むしろそれは、記号がどのくらいの間有効なのかが分からないということなのである。 内部に配置された記号が、直接に先立つピッチにのみinflectionするという事実に対する理論的な証言にもかかわらず、多くの場合、inflectionはより長いストレッチを管理している。この問題については、Berger、Musica ficta、19-20を参照されたい。Tinctorisのみは、一つの音符以上にinflectionは支配が及ぶことを認めている。 e-flat / b マショーは、ピッチの編成のニュアンスを通して、時間の引き延ばしを形作することに興味があり、この意味で,De toutes floursは、Biaute qui toutes autres pereと同類となる。 Biaute qui toutes autres pereのように、,De toutes floursでは、パート1は華やかなメリスマで終わっている。cantusは、b♭を介して、さらに2回関わる。(第20,22小節)。2回目は、 the second time in another undermined progression to C/c. 和声的な緊張は、b Bフラット上に構築された新しいコードが、パート2で始まる。それは、パート1の素材からのdigressionを示す。その後にb パート1の素材へのパート2のその他の言及が続く。すなわち、e-flatとb 37 これは、ルフランを告げ、C上の最終的な解決を予測する役目を果たすouvertカデンツとして、この瞬間がどのように解析されるべきかを私は考える。これをフラーの、Dへの「調性指向におけるシフト」という解釈と、彼女の提案、「ルフランのタスクは、置き換えられたばかりのC-G-cソノリティを再確立することである」とを比較されたい。 p526 ルフラン自体は、和声的緊張のクライマックスを提供する。リフレインは、高いaaへの跳躍によって区別される(m。55、パート1の高い境界とm。39のgに続く)。また、ルフランはe-flat(第49小節)とb D / F-sharp / b これらの2つのバラードで、マショーはピッチ関係のニュアンスを介して大きなセクションを構成することに興味を持っていた。そして、propinquity applicationは、彼に、重要なツールを彼に提供している。少なくともこれは、私が分析したこれらの曲のバージョンを解釈する1つの方法である。38 臨時記号は、長いストレッチ時間にわたって緊張を維持する手段を提供している。この長さに関するSarah Fullerの視点は、彼女を重要な仮説に導いている。それは、私の見解では、ars novaのポリフォニーの中心に和声をもたらすというものである。「作曲技法のイシュー指向の歴史は、14世紀の作曲家の第一の任務が、新しいリズムの実践によって前へと強制される新たな和声的資源を支配・発展させることであったということを示唆している。」39 39"On Sonority in Fourteenth-Century Polyphony: Some Preliminary Reflections,"p38 . 補足として、作曲家たちは、彼らの音楽言語の非常に重要な部分となった和声構文の固有の柔軟性を利用する方法を学んだとも言えよう。 この構文の柔軟性から生まれるニュアンスは、我々が依存している大まかな伝播経路を曲が進むにつれて、踏みにじられてきた。 概念的な問題もある。すなわち、分析が、通常の慣行的な和声との類似によって過度に条件付けられている場合、14世紀の和声構文のニュアンスと柔軟性が完全に消えてしまう可能性がある。 p527 文献学の原則difficilior lectio potior標準(より難しい読みがより可能性がある )は、演奏慣行の分岐として、および理論家によって与えられた規則として、両者に従って進んだmusica fictaの主要な推力に反している。 これを認識すると、一般化された写本の証拠を作成することがより困難になる。続行する唯一の方法は、ソース、様式(地域および作曲家によって評価される)、理論、特に作品の証拠をできるだけ同時に分析することである。 Machautを研究することには、大きなメリットがある。ソースは豊富であり、優れている。我々は、マショーの様式をよく理解している。実証の程度に対応できる様式について一般化するのは難しいが。無秩序な状況、扱いにくい証拠に直面して、それは暫定的であるが、最終的には理論的な仮定の確実性に依存する。 後期中世のポリフォニーにおける臨時記号を取り巻く問題はさまざまであり、統一された単純な答えよりも、複雑な回答となるだろう。 確かに、演奏に対するいくつかのコードが、いくつかのケースにおけるいくつかの変異を決定した可能性はある。 臨時記号に関するこれのまたはその他の問題の研究が、調査の中心に写本の証拠を置く以外の方法でどのように進むことができるかを理解することは困難である。 中世の音楽理論をあまりにも多く取り入れようとする試みは、時代からの全くの距離感から生じ、その距離感は、概念的な疎外感(思考が非常に異質である)と視界の薄暗さ(画像が非常に不完全である)の両方に現れる。 そして、もっと微妙な問題がある。すなわち、あちこちで、さまざまな程度の率直さで、この音楽は後の音楽よりも理論的な抽象化に根ざしているという態度を検出する可能性がる。40 40 さらに、理論と実用的な音楽の間に線を引くことは、Apelがしたように、15thや16thの状況ではなく、19thや20世紀の状況を確信させる。The Function of Conflicting Signatures in Early Polyphonic Music," The Musical Quarterly XXXI (1945)p229 しかし、確かにこの時代の作曲家は、どの時代の作曲家でも同じように、慣習を操作したり反対したりする自由さえも楽しんだ。 このアカウントに現れるのは、1)臨時記号が音楽構文において重要な役割を果たす 2)この構文は厳密ではなく柔軟である、ということである。構文の柔軟性は、分析が難しい理由の1つとなっている。それは当時の音楽理論家が書いたようなものではありませんが、それは私たちが 中期後期の偉大な音楽的成果により近い時代の調和と慣習的な調律の調和の間の類似性には、明らかに、この類似性が誤解を招く可能性があるという根拠があります。リーマンはムジカを主に演奏練習の問題だと考え、その現象を見ていた 失われたテキストの構成要素として 調和のとれた言語を現代の考えに沿ったものにしました。腐敗を主要なテキスト上の障壁と見なし、私はトピックmusica fictaを、慣習のそれとは明らかに異なるピッチの概念に私たちを引き付けるのに役立つものだと思います 調性。構文の柔軟性に重点を置くと、認識と微妙さにつながります。繊細さが14世紀の音楽にとって重要な価値であることは驚くに値しません。大まかな伝達に直面し、それを解釈するための挑戦は、それをより高いレベルの解釈への実質的なガイドラインなしで発見し、識別する |