| Musica Ficta8 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| (ii) The method of correcting
cadences
これまでで、どの対位法的コンテキストがみせかけのステップの使用を必要とする可能性があるかがわかったので、2つの可能性があるときに、つまり、下声部または上声部のいずれかがinflectionし、または fa-またはmi-signを使用する時に、こうしたコンテキストどのように訂正されるかを我々は見出さねばならない。 この問題は、7と2の両方を含む最後から2番目のカデンツの和声の場合にのみ明らかに発生する。 明らかに、最後から2番目のハーモニーが7と5の場合も、最後のハーモニーが3の場合も発生しません。さらに、最後から2番目のカデンツのハーモニーに7と2が含まれている場合、追加の声で見られる他の唯一のステップは4または 5; 他のすべてのステップは不協和音程になるが、カデンツの構造的和音はすべて協和音程でなければならない。 pI40 この追加ステップが5の場合、ここでも選択は行われません。5は2と7の両方に対して協和音程のままであり、許容できる旋律敵音程(通常はIまたは5に)最終的な和音に進む必要があるため、明らかに7である。 それは、半音で8に移動する必要がある。 したがって、下声部または上声部をinflectionするかどうか、♭または 次に、7と2を含む音声のペアから始めます。ここでの選択は、上声部または下声部を活用するための好みによって決定された可能性をすぐに扱える。そのような好みの証拠はなく、逆に、ミュージシャンがどちらのパートでも自由に活用できたといういくつかの証拠がある。 Prosdocimus de Beldemandis がこの問題を検討した唯一の理論家であるように思われ、私はすでに(上記の第5章(ii)で)この問題に専念した彼のContrapunctusからの広範な節を引用しました。この節はカデンツの内容として、mi -against-fa にも同様に適用できる。 理論家によれば、どちらの解がより良い響きであるかに応じて、どちらの声部もinflectionされるかもしれない。両方の解決が同じように響く場合は、discantのinflectionがベターである。なぜなら、テノールの変更は、contratenorのような別の声部とクラッシュする可能性があるからである。 どちらのinflectionも同等にsweetとなる場として、discantのinflectionに対するこうした選好は、重要であろう。すなわち、ディスカントは、テノールよりも定式8-7- 8を含む可能性がはるかに高いのである。 また、カデンツの最後から2番目のハーモニーには常に7が含まれている必要があることを我々は知っているので、discant以外のパートには2または5があり、不協和音の7がinflectionの好ましい候補であると考えることは理にかなっている。 Prosdocimusは、そのようなinflectionがどこにより甘く落ちるかに関するルールを提供する可能性について懐疑的であった。 しかし、少なくともカデンツの内容においては、そのtaskは彼が思ったほど困難ではない。 カデンツの最後から2番目のハーモニーで7または2を使用するかどうかの選択は、常に、上声部または下声部のいずれかのパートを使用するか、♭または 調号がなければ、カデンツI(訳注; Prosdocimusは、DやG上のカデンツで、どんな選択があったかを、我々に間接的に伝えていた。(略) pI4I 明らかに、IがDまたはGだったときに、Prosdocimusが明示的に選択したのは、7を♯化することであった。これにより、導音の選択が不明確な1つのカデンツI、つまりAだけが残る。 いくつかの理由から、私はこの(IがAの)場合でも、7を♯化するのが、よりあり得る選択だっただろうと思われる。 Prosdocimusは、他の条件が同じであれば、discantがinflectionされるべきだと主張した。そして、7を含む可能性がはるかに高いのはこのパートなのである。 しかし、より重要な理由もそこにはある。 A上のカデンツは、protus(第1,2旋法)または移調されたdeuterus(第3,4旋法)を表す。 旋法の移調は、署名の臨時記号によって示される。その結果、署名にフラットがないパートのA-カデンツは、protusを表し一方、1つのフラット署名のあるパートにある同じ(A- )カデンツは、deuterusを表すことだろう。 後者の場合、2はシグネチャによってすでにフラット化されているため、(inflectionの)選択を行う必要はない。また、カデンツは、(♭化しているので)Aの移調バージョンとEの非移調バージョンで同じ「フリギア旋法」形式を持っている。 ただし、同様に、2を含む声部に♭署名がなく、A-カデンツが不規則に配置されたprotusを表す場合、D上の規則的位置にprotus-カデンツが持つ形式を供与すること、すなわち7を♯化することには、意味がある。 「フリギア旋法」のカデンツは通常、2での下方の半音が所定の調号の下で自然に発生した場合にのみ使用され、2を♭化するか7を♯化するかを選択する場合、後者の解決が好まれた。 この結論は、すべてのカデンツの最後から2番目の和音の絶対に不可欠な要素である2なのではなく、7のみであるという結果によって、さらに間接的、付加的にサポートされることがわかるだろう。 言うまでもなく、上記の結論は、古くは、受け入れられた2つの声部の完全に中立的なメロディと垂直的なコンテキストを前提としている。 実際の音楽では、状況によって好ましい解決策が不可能になる場合がある。たとえば、他の声部のステップを2倍にすることは、それがinflectionされないことを示すことになるだろう。なぜなら、inflectionは、メロディの動きの継続を意味し、平行する完全協和音程の禁止は、inflectionされた音符の1つの適切な解決を妨げたからである。 これまでの我々のの結論は、この時代の理論と一致するいくつかの単純な仮定から推論されている非常に推測的なものである。しかし、豊富な理論的な証拠は、(理論上の)カデンツでの導音が、実際に、当時の音楽家らによってinflectionされたことを示している。 この証拠を精査してみたい。♭署名を持たないA-カデンツやその移調されたものといった、もっとも野心的な例に注目して。 不完全協和音程から完全協和音程への進行についてのMarchettoの例において、例34,35でこれらが説明されている。両者の例における中間のところでは、五度で終止しており、とりあえず、無視しよう。 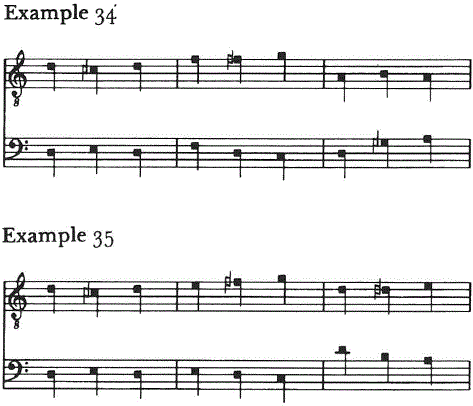 pI42 それらは、いずれにせよ、現在のディスカッションとは無関係である。なぜなら、I= Cで終わるから。つまり、そこでは、導音としての選択を提示ないステップとして終止している。 しかし、各例の1番目と3番目の進行は関連しており、D-カデンツに対する理論家の選択はCを♯化にすることであり、さらに重要なことは、A-カデンツに対する彼の選択は、2を♭化するのではなく7をシャープにすることだったことを示唆している。 (もちろん、各例の2番目のカデンツはオクターブカデンツではないが、例35の2番目のカデンツは、マルシェットが2ではなく7を活用することを望んでいることを示している。) さらにマルシェットのPomeriumの第4論文では、♯記号について、理論家のバージョンが明らかになる。 マルシェットは、the square b or the round bではなく、♯記号が、不完全協和音程から完全協和音程への進行において、計量記譜的音楽で使用されていると説明している。 94 マルシェットの♯記号が標準的なmi-記号と異なり、それは、全音を異なって(暗黙として)分割する意味であることを思い出していただきたい。したがって、我々は彼の議論から、フラットではなくシャープが、カデンツ進行における通常の選択であったと推測することだろう。 別の14世紀初頭の理論家、Petrus frater dictus Palma ociosaは、A、D、およびG上のオクターブに進む長六度の例を示し、それぞれのケースで7を♯化している。95 14世紀の後半に 匿名の著者は、「ここに(例36)示されているように、最後から2番目の音符と最後の音符の間の上昇の終わりにおいて、常に pI43 ここで言う理論家の”常に”は、カデンツの導音に対して、フラットではなくシャープを自動的に選択することを示唆している。この例でのG♯-aの進行は、特に明らかである。 また、 Philippus de Caserta は、フラットではなく、オクターブに進む六度のinflectionの固有の意味合いとして、あるいは五度に進む三度の意味合いとして、diesis(♯)の記号について語っている。97 したがって、14世紀の証拠、特にMarchettoとPetrusの証拠は、導音を選択する必要がある場合、fIatではなく、シャープであることが好ましい解決策であったという私の最初の結論を支持して主張する。 ただし、15世紀においては、A-カデンツに対する♭のでの解決への嗜好を論じる例が見出される。 Protdocimusは、彼のTractatus musice speculativeにおいて、E-Dに対するc-dの進行では、短六度を長六度にする必要があること、およびこれは、「昔のantiqui」ケースではc G-aに対するb-aの進行において、昔の、そして今の双方は、b-faによって、短三度を形成している。99 これは、Prosdocimusの見解では、2の♭がA-カデンツの通常の選択であったことを示しているかもしれない。 同じ2つの進行は、Ugolino of Orvieto とRa mos de Pareia によって議論されている。そして彼らはまた、c♯によってE-Dに対するc-dを修正し、♭を使うことで、G-aに対するb-aを修正する。100 ここで、Ramosが,Gとaの間のキーをa♭の代わりにG♯とした人物や、B-Aに対するG-aの進行を修正するためにG♯を必要とした人と論争したことを思い出されたい。彼はこの進行が、B ♭によって修正されることを好んだ。I0I 理論家はこの問題についての議論を続けた。 And if someone wished to say that there [at a] the protus was reborn , and the con ditions which D had should obtain also at a, and [that] since D was shown to have a whole tone I02 below and above itself , in the same way also a [should have a whole tone below and above] , we shall respond by saying that the argument does not succeed , since that [whole tone below and above] has G which assumes for its eJ f complete similarity beJ ow and above in the synemmenon tetrachord [that is , a-~-c-d] , but not a which has two whole tones beJ ow . _ . Therefore , that step [a] is deuterus , authentic as well as plagal , in the conjunct [that is , in the system with the soft b].I03 そしてもしも誰かがそこ[a]でprotusが再生と言い、そしてDがaでもまた得なければならなかった状態、そしてDがそれ自身の上下に全音を持っていることが示され、同じようにaが[上下に全音を持っているならば]、その議論は成功していない、といわねばなるまい。なぜなら、
Ramosの時代の音楽家らは、A-cadencesで使用する導音に同意できなかったことを示しているので、以上のパッセージ全体が非常に興味深い。Ramos自身はB♭を好んだが、彼は明らかに、、G♯を選んだ人々に対して論争を強いられた。 この文章は、双方が旋法的用語で議論したことを意味している。ラモスの反対者は、Aがprotusの終止音であると主張し、したがって、protusの低い導音をとるべきだと主張し、Ramos自身は、それが♭を伴う(つまり、シグネチャに1つの♭を含む)システムのdeuterusの終止であると主張した。 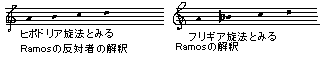 pI44 Ramosの議論は、♭署名がない場合、A-finalをどう解釈するかを明確に示さないために、水も漏らさぬ、というほどのものではない。 彼は後者のケースもまたdeuterusを表すと考えるだろうという印象を(決して確実ではない)得させるが、そうであれば、彼は少数意見である。 標準的な見方であるならば、♭のないAでの終止が、protusを表すものである 我々は、15世紀の間においては、♭署名がなかった場合に、A-カデンツでどの導音を選択するかについて、いくつかの不一致があったと暫定的に結論付けることができる。その不一致は、G♯を導音として使うprotusを示すのか、B♭をつけてdeuterusを表すのかという、カデンツについての旋法的解釈でのconflictingに由来している。 protusを示すようなカデンツについての解釈が一般的なものなので、導音としてのG♯の使用はまた、より一般的な選択肢となった。Ramosの時代からの理論的証拠は、いずれにせよ、選択肢があったときはいつでも、カデンツの導音にb-miを使用することを圧倒的に支持している。 I04 おそらく15世紀の第3四半期に編集された匿名のQuot sunt concordationes は、次のように述べている。 シンプルな曲にla-sol -laがあるときはいつでも、このsolは♯化してfa-mi-faとして歌う必要があります。 。 。 シンプルな曲にsol-fa-solがあるときはいつでも,このfaをシャープにしてfa-mi -faとして歌う必要があります...シンプルな曲にre-ut-reがあるときはいつでも,このutはシャープにしてfa -mi -faとして歌う必要があります。 。 。 counterpointでは、他の音符はシャープになりませんが、これらの3つ、つまり、(カデンツIIに当たる)sol、fa、およびutには注意してください。 I05 この著者は、カデンツの旋律定式8-7-8を明確に議論し、上下に全音を持つ自然なヘクサコードの3つのステップ(それぞれA. GおよびD)のみにそれを配置する。いずれの場合も、彼は私たちに、低い導音を生成するために、下の隣をシャープにする必要があると私たちに言う。 ちなみに、筆者の言葉は、♯化した7の8-7-8の定式が常にfa
-mi-faにソルミゼーションされる必要があることを示唆しているだろう。しかし、これは、D、G、またはAに8を使用するこのような定式も、そこに半音がなかったかのように、つまりそれぞれ、re-ut-re、sol-fa
-solおよびla
-sol-Ia、とソルミゼーションされたと主張した当時の理論家たちによって、はっきりと否定されている。.l06 同じ情報は、Quot sunt concordationes におけるように、GaffuriusのPractica musiceにおいても見られる。 多くの場合、laの下は、半音としてsolを歌います。 Salve Reginaの場合と同様に、特にA-la-mi-reで開始および終止するla sol laの進行において。 アンブロシアンが歌うのに慣れているG-sol-re-utで始まるsol fa solのsolとfaでも同じことが起こります。 107 同様に, Gonzalo Martinez de Bizcargui は、re-ut-re , sol-fa -sol , la -sol-la定式における低い隣のC, F 、 G を♯化することについて、書いている。 I08 pI45 カデンツ定式8-7-8を示すためのソルミゼーションシラブルの使用は、カデンツの導音をinflectionしなければならない時に、♯が通常選ばれるという、 私の主張に追加のサポートを提供する。 inflectionする前は、定式はprotusに対するre-ut -reであり、tetrardusに対するsol -fa-solであり、これらの中でのみ、導音の選択が存在する。 これらの両方のケースで、下隣がシャープになるとなれば、カデンツ定式がAで発生したときに何をすべきかを推測できる。 フラット調号がある場合、この定式がEで発生するときとは異なり、定式はmi-re-miでソルミゼーションされ、下隣はシャープ化されない。ただし、♭調号がない場合、定式はre-ut-reであり、これは、すでに知られているように、下隣の♯化を必要とする。 その結果、上で言及したガフリウスやマルティネスなどの一部の理論家は、Aで発生したときに定式をどう処理するかを明確に説明しているが、他の理論家は気にしていない。 たとえば、Johannes Cochlaeus は、カデンツre-ut -reとsol-fa-solで発生する暗黙の臨時記号的inflectionについてのみ話す。I09 これは、問題を議論する最も経済的な方法である。 そして、すでに示したように、それを完全に明確にすることで十分である。 Cochlaeus と同様、, Arnolt Schlick は、 A, G、 D下の黒鍵について、これらのステップのカデンツへの必要に応じて、話している。110 我々はすでに、これらの黒鍵のtuningが、彼にかなりの問題を引き起こし、彼がA-カデンツの実用的な導音が得られるように、A♭を十分に制御することを、すでに見てきた。 それがあまりよく響かなくても、彼がこの導音を持ちたいと思っていること、そしてすべてのA-カデンツが代わりに上からの導音を使用できるようにならないことは、彼には重要である。 上からの、ではなく下からの導音化についての豊富な証拠が、当時ずっと、あった。Pietro
Aaronは、I5I6年のLibri tres de Institutione
harmonicaで、音階のさまざまなステップでの8-7-8定式の説明に従って、この一般的な考察を行っている。すなわち、「全音によって終止することが示されたすべてのカデンツは、♯化されるべきである、ということがもっと知られるべきである」。112 ”♭記号を通して”歌われたカデンツ、あるいはE上のカデンツで起こっているように、もしも低声部が終止音に対して半音で下降していくのであれば、このような声部での♯化は、必ずしも必須ではない。。113 はっきりと♯化された下側からの導音を持つカデンツの例は、1545年のAaronのLucidario in musicaで論議されている。114 Aaronは、c- A-カデンツにおいての導音の♯化について、はっきりと記述している別の理論家は、Guersonである。 pI46 You should then sharpen mi from fa and fa from mi situated neewteb owt sols , and also ut placed between two res , and also sollocated between two las .II5 さらに、すべての完全協和音程を欲する不完全協和音程が、上行において、半音引き上げられるべきであるということは、知られるべきである。115 つまり、カデンツ進行の中間ステップsol.fa-sol、re-ut-reおよびla-sol-laをシャープにする必要がある。 Giovanni Maria Lanfrancoは、完全な(8-7-8)または中断された(8-7)であるカデンツ定式の例を提示している。それは、♭記号がない場合でのd,g,aa,dd上の8で、そして♭記号がある場合でのd,g,cc,dd上の8で、diesisの記号(♯)によって常に♯化された導音を伴っている。116 このように、彼は、1(訳注; La nfrancoが、特定の構成をカデンツとして扱うかどうかに関係なく、特定の最小限の自由を許容していることに注意されたい。特に、カデンツ定式に特徴的な繋留音が含まれていない場合。彼は以下の発言で上記の例をフォローしている。 そして、このように、このdiesisは、。 。 。 言われているように、同様の場所の他の部分に形成されるかもしれない。 私は「かもしれない」と言うが、ほとんどの場合、それが常に行われるとは限らないためです。 特にシンコペートされていない音符では繋留なしで、 Lanfrancoの同時代人、Stephano Vanneoも ,オクターブで終わるカデンツ定式において、8と1の両方が全音でアプローチされると、上声部において導音を♯化するidesisの記号が使われる、と主張している。彼は付け加える。 したがって、この重荷を捨て去り、揺らめく交差点を離れた人々は、(常にシャープを使用する)この黄金律を守り、それを記憶の宝庫に保管している。すなわち、ソプラノのあらゆるカデンツ(定式8-7-8)は、5つのやり方で作ることができる。 実際、最初はre-ut-re、2番目はmi-re-mi、3番目はfa-mi-fa、4番目はsol-fa -sol、5番目と最後はla-sol-Iaです。 これらのうち3つ、すなわち、re-ut-re、sol -fa-solおよびla-sol-laには、♯化の支援が必要です。 これらのうち3つ、すなわち、re-ut-re、sol -fa-solおよびla-sol-laには、♯化の支援が必要です。 ただし、両方のE-la-mi(つまり、Eとe上で)とA-la-mi-re(つまりB♭署名の下でaとaa上で)とE-la(すなわち、ee)上のla-sol-laはこの規則には従いません。なぜなら、これらの場では、テノールが半音のカデンツを得ているからです。119 「揺らめく交差点」への言及は、少なくとも初心者が、カデンツの導音に対してシャープまたはフラットのどちらを使用するかについての我々自身の不確実性を共有したことを示唆しているが、常にシャープを使用するVanneoの「黄金律」は、 他の理論家から学んでいる。 Vanneoは、上記の説明に従い、8がd、g、aa、またはddにあり、フラット調号がない場合、および8がG、c、d、g、cc、またはddにあり、♭調号が1つある場合、8-7-8の式で7をシャープにする必要があることを示す例を示す。 120 pI47 Vanneoの「黄金律」は、当時ずっと、その有効性を維持した。 Loys Bourgeisは、それを次のように表現した。 同様に、la-sol-Ia、sol-fa-solおよびre-ut-reなどのような上声部のすべての完全なカデンツは、半音で歌わなければなりません。 これは常に行われるべきではないため、私は特に「いくつかのカデンツ」について述べました。 a-la-mi-re からg-sol-re-ut [すなわち, a-Gあるいは aa-g]へのla-sol-laや mi-re-mi は、♭記号とともに歌われ、e-la-mi から d-la-sol-re [すなわち、e-d] へのla-sol-la や mi-re-mi は、それがカデンツではなかったかのように、全音で歌わるべきだろう。I2I Juan Bermudo formulates は、同様の手順を別の方法で定式化する。すなわち、短六度が1オクターブに拡大する場合、可能であれば上声部で(つまり、シャープを使って)修正する必要がある。 mi-against-fa不協和が生じるためこれが不可能な場合は、下声部で修正する(つまり、フラットを使用して)。 I22 最後に、Gioseffo
Zarlinoは、「他の声部が同じ音程で下降しない限り、終止音に上行する声部は半音を意図している」と説明している。123 7の♯化と2の♭化の選択のどちらかでは、前者が選択される。 要するに、15世紀の最後の四半期からの証拠は、私たちの元の結論を圧倒的にサポートしている。コンテキストが2をフラットにするか、7をシャープにするかの選択を残した場合、シャープ7を選択するのである。この結論に対する追加のサポートは、16世紀に提供されている。それらは、フラットとシャープの機能が異なっていたことを示唆し、前者はmi against fa iを修正し、後者はカデンツを提供している。 次に、Prosdocimus、Ugolino、Ramosの証言で、調号にフラットがなかった場合にA-カデンツで使用する導音が、15世紀の慣行にのみ適用されることへの不合意が存在したことを示したと結論付けるべきであろうか? それはそうかもしれないが、特に16世紀においても、シャープ的な解決策とフラット的な解決策の両方が受け入れられることを実際的な証拠が示しているので、私は彼らの証言を異なる方法で解釈しようと思う。I24 Ramosは、protusやdeuterusのどちらも示すこのようなA-カデンツの相反する旋法的解釈から不合意が生じたことと示唆した。 私は、このカデンツは通常、protusを表すと考えられていたと主張した。もちろん、これは、テノールが、a上に不規則に配置された調号がなく、移調されていないprotusとして想定された作品については正しい。 しかし、A上の内部的なカデンツで別の移調されていない旋法(たとえば、d上で規則的に配置あれた移調されていないprotusの場合)で想定された作品においては、必ずしも当てはまるものではない。このような作品では、これらの内部的なA-カデンツムの解釈は、contex tに依存している。 p148 d上の移調されていない通常のprotusを表す作品内で発生するA-カデンツは、我々の想像上においても、非常に一般的な例としてあり続けるが、基本的な旋法の安定したコンテキスト内で、第5旋法に重点を置く可能性がある。しかし、また、a上で移調されていない不規則に配置されたprotusへの一時的な移行を意味する。 初心者やhacksは、これらのすべてのケースを、統一された方法で解釈するが、敏感な音楽家らは、前者のケースでは(6番目の♭はprotusにおいては非常に一般的であり、その結果、基本的な旋法を過度に乱すことはないだろうからるため)フラットなアッパーリーディングトーンを適用すると思う。そして♯を用いる下からの導音が後者において用いられる。(なぜなら、これにより、一時的なシフトが別の終止音にはるかに強力に伝達されるため)。 <1540年頃のローマでの臨時記号論争> ローマでおよそ1540年頃に起こり、Ghiselin Danckertsによって記述された臨時記号についての論争が、関連する例を提供することだろう。I25 125 .Lewis Lockwood,‘'A Dispute on Accidentals in 5ixteenth-Century Rome',p24-40 抄訳 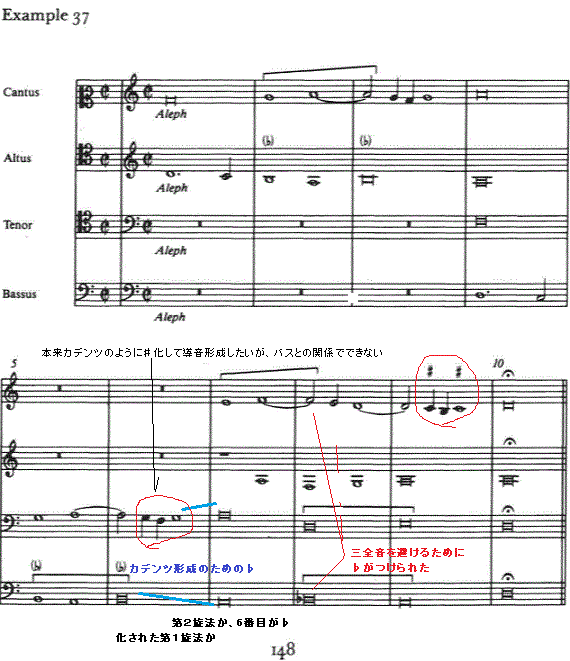 論争はJuan Escribano によるlamentationに関するものであり、その最初を、Ghiselin Danckerts が引用している(例37を参照)I26。この作品は、作曲家を含めて、あらゆる人によって、移調されていないされた第2旋法であると考えられている。 pI49 バスは、Bにおいてはことごとく、歌手は♭を入れて歌うことを欲した。テノールは、調号とは無関係である。テノール(歌手)が♭調号をつけることに反対したのか、バスが彼のすべてのBを♭化しようとしたのかははっきりしないが、Ghiselin Danckerts 自身は、彼の例のバスパートの唯一のB♭は明確に第8小節でマークしている。 論争についての議論において、Lewis Lockwoodは、バスが彼のパートで♭を望んだ理由の1つが、オクターブの前の六度を長六度にするためであると認識した。 I27 これは確かに、バス(に♭をつける)決定の最も可能性の高い理由だと思われる。 垂直方向のmi against faのために、彼は、バスパートの最後のB(第8小節)を♭化した。その前の第6小節でも彼は、♭をつけたかった。なぜなら、テノールバスの進行には、カデンツのすべての機能があるためである。そして第5小節の♭はおそらく、BとB♭の両方が連続して続くことを避けるために追加された可能性がある。 私は、カデンツ進行がどのように扱われたかについての論争の重要性を、2通りにわけて考えてみたい。 まず最初に、我々はここで、16世紀の音楽家らが、進行をカデンツのように扱うかどうかについて意見の相違がある可能性があることを示す。彼らは確かに、引用されたパッセージが、旋法上の終止の強いカデンツで終わることには、同意するであろう。 このカデンツは、cantusの導音をシャープにする必要がある。しかし、バスが、第5-7小節において、自身とテノールパートを含む進行を、(第10小節の)終止における五度でのカデンツように扱おうとしても(そしてそれは、第2-4小節でのcantusとアルトの進行でも同様である)、Danckertsは、それができなかった。 一方では、進行にはカデンツ構造が認められ、他方では、それらは、一定のカデンツ形成によって危険にさらされた連続性が、より大きなフレーズに埋め込まれている。 次に、そして私たちが現在検討している問題の観点から、この論争から導き出されるより重要な教訓は、音楽家らが、第2-4小節と第5-7小節をカデンツ進行として扱うのを欲するのであれば、彼らは、下側の声部を導音にするのではなく、上側の声部を(♯化することを)選んだことであろう、ということである。 その理由は、旋律的にも垂直的にも、引用されたフレーズは、始めから、protusの音域を投影し、強調しているためだと思われる。 バスとアルトのメロディの外観から、第7小節(そして第4小節)でのカデンツは決して終止ではなく、その四度下であることは明らかであり、それは、第8-10で確信するより前から明らかである。 導音での♯の使用は、ここでの場合、耳障りである。なぜなら、終止の四度下のステップを強調するように見えるため、そしてそれ自体が終止のように響いてしまうから。 一方、導音での♭の使用は、protusの五度上(ラ)での終わるカデンツのヒアリングとして、矛盾しない。なぜなら、この第1旋法においては、6番目の♭化は一般的だからである。 pI50 さらに、内部のA-カデンツを、テノールがa上に不規則に置かれた、調号なしで移調されていないprotus として想定された作品にも存在したprotus(第2旋法)として扱うかdeuterusとして扱うかには、ある程度の柔軟性があることが想像される。 もちろん、そのような作品の構造的に重要なカデンツは、protusを表すものとして扱われる必要がある。ただし、理由は何であれ、テキストによる表現であろうと単純な多様性であろうと、作曲家が、deuterusを表すものとして内部カデンツを解釈しようとした可能性は、排除できない。 <Aaron Toscanello in musica への「補遺」> Toscanello in musica への「補遺」で、アーロンはこのように解釈されるかもしれない事象に言及した。 ラウンドbの符号を明示的に使用してmi-against-faの不協和を修正する作曲家らの例の長いリストの中で、Aaronは、octave前に長六度を作成した記号を使用したものを含めた。 私は fifths , octaves , twelfths , and fifteenths ,を考えるだけでなく、彼のモテット Miseremini mei ,に示されているように、オクターブの前の長六度も考慮したRichafort に対してさらに明確にした。六度は、その曲では、コントラバスとコントラルトの間に出現し、それはマイナーであったために、記号♭を付けた。I28 . アーロンが言及したパッセージは、4つのパートからなるモテットの内部デュエットで発生し、そこのテノールは移調されていない不規則なprotus(モード2)であり、多数のA―カデンツがあり、その中で7は間違いなく♯化されている。 ただし、デュエットでは、作曲家が表現または多様性のために、2の♭化を明示的に要求した(例38を参照;第34小節)。I29 ここは明示的だが、第36-7小節のテノールとバスでのフレーズの最後でのカデンツは、暗示的に示されていることに、注意されたい。 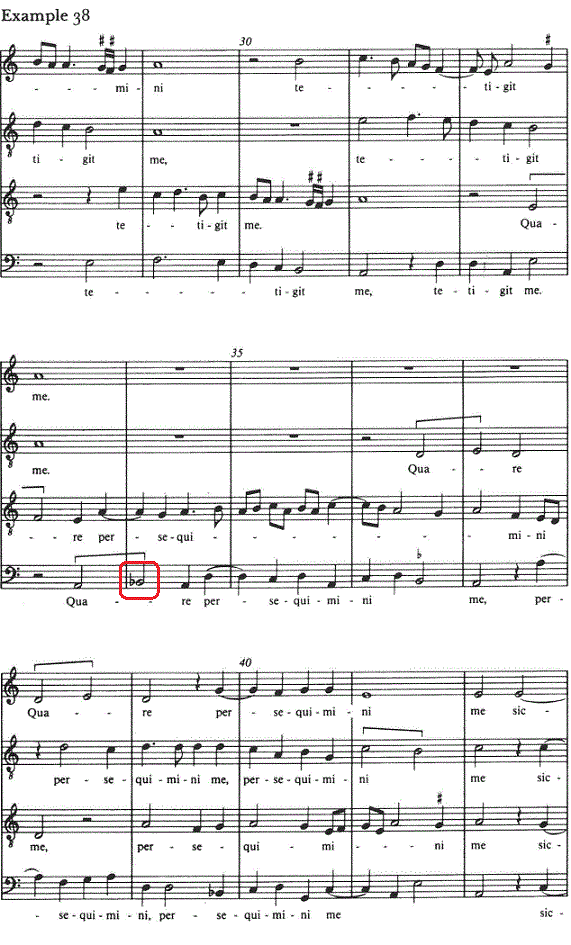 この種の考慮事項が、15世紀の理論家によるA-カデンツの適切な取り扱いに関する不一致につながった可能性がある。これはもちろん、経験に基づく推測にすぎないが、この推測が正しいことが証明されれば、これらの理論家の証言の有効性を15世紀だけに限定する強い理由はない。 Aカデンツで7を♯化することを推奨する理論家は、単純な真実を語っているとみなされるが、真実全体を語っているわけではない。 我々が求めているのは、その時代の最高の音楽家らの慣行の再構築である場合、私の暫定的な推奨事項が、内容に応じて、移調されていないシステムで発生するAカデンツ(および移調された同等物)を柔軟に扱うことである。上記の例のように。 実用的なソースで発生する臨時記号の将来の研究は、この勧告の有効性をテストすることだろう。 <二重導音の問題> 最後から2番目のカデンツハーモニーの3番目の声部に4が含まれていて、7が♯化にされている場合、4も同様に♯化して、7との完全四度を保持するか、4を♯化せずに垂直的三全音を許容するかという疑問が生じる。 p152 前の章で、不協和音程の音符の少なくとも1つが適切に解決されており、その前後に協和音程が存在する場合(つまり、miステップはdiatonic semitone を上に、および/または、faステップはdiatonic semitone を下にする)、単純な対位法でもmi-against-fa不協和が寛容される可能性があることを学んだ。したがって、4と7の間の三全音は許容できる。 しかし、最後の5に進んだ場合、最後から2番目の4を♯化理由がもう1つある。すなわち、2-1に対抗する4-5の進行では、五度への垂直的な三度の進行は長調になるべきだ、ということである。 したがって、最後から2番目のカデンツのハーモニーに、5へ進行する4が含まれている場合、そして7が♯化されている場合は、4も同様に♯化されると結論づけられるであろう。コンテキストがそれを許容している場合は。ただし、7に合わせる必要があるためではなく、三度から五度への二次的なカデンツ進行のために、4が♯化されることを強調する必要がある。 三度から五度への進行において、三度がメジャーである必要があることは、当時の最初から最後まで理論家によって主張されている。したがってこの時点では、二次的導音(4の♯)が時代遅れになったことを示唆する純粋な理論的証拠はない。 しかし、実際のソースは二次的導音が時代遅れであったことを示しているようである。 声楽モデルの16世紀のIntabulation(多声声楽曲を鍵盤楽器用に編曲したもの)では、二次的な導音ほとんどないようである。 I30 さらに、作曲家、楽派、または同世代作曲家が最後から2番目の4の♯化を避けたい場合は、この嗜好の変化を、4を5ではなく他の場所(3またはI)に定期的に解決するか、最後から2番目の4を完全に回避して5を優先することで示す必要がある。 したがって、カデンツの4の多くが5に解決せずに3またはIに解決する、または3パート以上の非常に多くのカデンツが4ではなく5を使用している場合、我々は、その理由が、4の♯化を回避するためだったとかなり確信するだろう。 このようなレパートリーでは、カデンツの4が二重になり、4の1つが5になり、他が解決すれば、このような場合でも4は♯化されずに残されていると想定することは理にかなっている。 すなわち、作曲家は、単に2 -1に対して7-8と4-3の通常のカデンツを使用し、4を二重にし、禁止されている平行を回避し、5に解決する。ただし、通常、4の♯化を回避するレパートリーで発生する2-Iに対して、7-8と4-5のカデンツで4を使用して何をすべきかを完全に明確にすることはできない。 一方、ここでは、”通常ではない”あるいは”古風な”二重導音カデンツが意図されていた。なぜなら、そうでなければ、作曲家は4の代わりに5を用い、あるいは、5ではなくその他の場に彼の4の解決をすることになったであろうから。 他方、問題のレパートリーにおいて、二次的な導音が完全に時代遅れになり、、作曲家は最後から2番目に4を使い、当代の音楽家が4を♯化するいうリスクを冒すことなく5に解決する。問題は、理論的証拠のみの基礎では解決することはできないのである。 pI53 カデンツの臨時記号は、その他の付加的な臨時記号のinflectionsを必要としするだろうか? 7-.miと4-.miの両方のカデンツ的inflectionsは、8-faと5-faに対して上向きに半音を適切に解決するので、旋律上の問題は発生しない。それらが作り出し得る唯一の問題は、7または4が別の声部で二重になり、八度(あるいはユニゾン)の対斜になる時の、八度(あるいはユニゾン)の垂直的なmi against fa である。 このような問題に直面した場合、あまり一般的ではない♭的解決を優先して通常のカデンツinflectionsをあきらめるか、付加的♯によって不完全八度を修正するかを選択できる。 追加の♯でinflectionされた導音によって、生成されたすべての不完全なオクターブを修正しても、理論家が以前に発見した、さらなるメロディや和声の問題を引き起こす♭の「連鎖反応」を引き起こすような問題は起きない。なぜなら、臨時記号を含んだ否定されるべき”連鎖反応”は、octave以外の音程で始まっていくからである。したがって、上記の両方の選択肢は可能となる。 Lanfrancoがこの種のコンテキストを念頭に置いていた可能性がある。彼は mi against fa を修正するために、フラットの使用とカデンツでのシャープの使用を対比した。彼は言った。 mi against fa の不協和(を修正する)のためには、♯を使用することになるだろう、と。 このLanfrancoの読みが正しい場合、これは上記の2つの選択肢のうち、♯を使用する方を支持する議論になっただろうが、それが正しいかどうかを知るすべはない。私はそのような問題の明確な理論的議論を見つけることができず、だから、それらを解決することができるように関連する実用的な証拠を発見しなければならないであろう。これに失敗すれば、我々は、どの解決が最適であるかの直感的感覚に頼る必要があるだろう。 私は、カデンツで最後から2番目の7または4を二重にすること(そしておそらくそれとオクターブの対斜を作成すること)が、ステップを♯化すべきではないことを示す作曲家の手段であったと信じようとした。 そして二重の7の場合、2の♭化を代わりに使用する必要がある。これは、♯化された導音が、半音での解決を示唆しているという確かに推論的な根拠に基づいていると思われるが、平行協和音程の禁止のために、二重化したステップの1つはそのような解決を得ることができない。 前章の終わりに、私は、当時の通常の慣行は、3つのフラット(B♭、E♭およびA♭)しか必要としないと結論付けた。 この章で、カデンツの導音の♯化について我々が学んだことの結果は、当時の通常の慣行(つまり、共通の調号の1つを使用し、♯の使用はカデンツの導音作成のためと、カデンツでの最終ハーモニーの長三度を作成するためだけすること)は、3,4の♯要求したに過ぎない、ということである。(C♯_、F#、G♯ _)の3つは7の♯化のため、4番目(上記に加えられるD♯)は、4の♯化のためである。 こうした結果が、musica fictaの最も一般的に使用されたステップに関する、以前に到達した結論(上記の第2章(V)で)と同一であることに、注意されたい。 p155 7 Canon and imitation 前の章で、私は、musica ficta ステップの使用を必要とする旋律的、和声的、および対位法的な内容を検討した。 この章で検討すべき問題は、当時の音楽が、そのようなステップの使用を必要とする作曲手順を採用したかどうか、ということである。 ますますユビキタスな模倣のテクニックに加えて、初期の声楽ポリフォニーは、作品に一度ならず現れる、同じ完全なメロディの使用含む特別なテクニックの集まりを発展させた。そのため、原則としてメロディーは1回だけ記譜されたにしても、実際には一度きりの使用ではなく、その繰り返しや変形は、書かれた「ルール」(カノン)によって指示されている。 ここで用語が使用される広い意味でのカノンは、異なる声部での同じメロディの使用(これは狭義の近代的意味での用語)と、同じメロディを同じ声部で連続して使用する(訳注;バロック期以降の意味でのフーガ)ことや、オスティナート、あるいはさまざまなcantus firmus技法をカバーしている。 カノンと模倣は、密接に関連する2つのmusica ficta問題を引き起こす。 まず、それぞれの外観で、メロディーの正確な音程を維持することを目的とする必要がある(同じまたは異なるピッチレベルで)のだろうか?その結果、和声または対位法的な理由でinflectionを強制的に導入する場合は常に、非カノン的、非模倣的な声部を導入することにならないか? 前の2つの章では、理論家が、垂直方向のmi-against-faの不協和または最後から2番目の調整の修正が必要な場合、音楽家らがどの声部をinflectionするか(高くか低くか、cantusfirmusか、それに対して書かれたcontrapunctusuか)について懊悩したことを示唆する証拠を提供しなかったことを確認した。 それどころか、我々が議論した証拠は、そのような状況では音楽家らの関心事についての疑問が、miステップとfaステップのどちらを使うかだけであるという私の信念を裏付けている。 この事実は、カノンまたは模倣声部でのinflectionsの使用に対する理論的禁令がないことと相まって、mi-against-faの無制限の使用や、そのような声部でのカデンツのinflectionの同意を論じている。 この結論を支持する追加の議論は、すべての声部がカノンである作品では、時々、カノンの声部をinflectionする以外に、我々には選択肢がないということである。なぜなら我々には、、 mi -against-fa の内容やカデンツを支配する規則が、カノンでは宙に浮いている、ということを信じる理由もないからである。 要するに、臨時記号のinflectionを必要とするmi-against-faやカデンツの状況に直面したとき、より多くの証拠が見つかるまでは、当時の音楽家は、通常の方法で、カノンまたはlmitatlonを扱っていた、と想定するのがよい、ということである。 p156。 カノンと模倣によって提起された次の疑問は、モデルのメロディを別のピッチレベルで再生するときに、正確な音程を維持する必要があるかどうか、ということである。この疑問に関連する理論的な証拠は、完全に確実な答えを出すには不十分である。 私が提供できるのは暫定的な回答のみであり、実際の証拠に直面して、将来的にテストおよび改善する必要がある。 Zarlinoは、一方で、fuga,consequenza,reditta(3つは同義語)を区別し、他方でimitaionesを区別している。しかし「音楽家らは時々、模倣をフーガと呼ぶことがあるので」、一般的な当時の使用に関する限り、区別は正確ではない。2 したがって、実用的なソースの特定の用語の使用は、Zarlino的感覚での「フーガ」か「模倣」が、作曲家の意図であったかどうかについての、特定の指示を提供できない。 どちらのタイプも、「strict」(legata)または「free」(sciolta)のいずれかになる。前者の場合、メロディ全体がそのまま複製される(用語の現代的な意味でのカノンを生成する)。後者では、モデルのメロディは、主題までのみ複製される。その後、声部は独立して進行していく(現代の用語では模倣)。 「厳格なfugue」と「厳格な模造品」はどちらも、別のパートを派生させる方法を説明する「規則」(カノン)のみで1つの声部として表記できる。「フーガ」と「模倣」の違いは、前者ではモデルのメロディーの音程を正確に再現する必要があることであり、後者では「ガイドの進行は、consequentによって、音程を考慮せず、ステップの複製の程度のみに対して模倣される、ということである。3 両方とも、カノンを使用することで、単一の声部に表記を減らすことができるため、両方の結果でガイドの音程が再現されるが、正確さは同じではない。 「fugue」では、再現された音程は、正確に同じサイズでなければならない(たとえば、ガイドの短三度は、consequentにおいても短三度でなければならない)。一方、「模倣」では、consequentは、ガイドのすべての音程を、正確なサイズに注意を払うことなく、再現する。(そのためたとえば、ガイドの短三度は、consequentによって、短にも長にも再生される)。 さらに、”fugue”において、ある声部がその他の声部に応答する音程は、ユニゾン、、四度、五度、オクターブとなる。”模倣”は、fugueのように、ユニゾン、、四度、五度、オクターブ、あるいはその他の音程となり、すなわち、二度、三度、六度、七度等でもまた書かれることになろう。 p157 Zaulinoの”フーガ”と”模倣”の間の区別は、モデルのメロディを別のピッチレベルで再現する時に、正確な音程を維持する必要があるかどうかという問題に直接関係している。Zarlinoの答えは、「フーガ」を書くときにはそうすべきだが、「模倣」を書くときはそうではない、ということである。 ガイドの最初の音符とその後の音符の間の音程がsecond , third , sixth 、seventh の場合、「模倣」が作曲家によって意図されていた可能性がある。 しかし、「模倣」と「フーガ」の両方が四度、あるいは五度であるかもしれないが、Zarlinoは、このような場合に、作曲家の意図を認識するための追加の基準を提供していない。 私の直観的な経験則は、そのようなカノンは、「フーガ」であるかのように解決しようとすることである。ただし、そのような解決によって、カノンが「模倣」として扱われるときに回避できない問題が発生する場合を除く。 この経験則の理由は、歌手がカノンを”模倣”として解決するよりも、「フーガ」として解決する方がいくらか簡単であるためである(「フーガ」であれば、彼はモデルのソルミゼーションシラブルを使用できるため、指定された音程で全体を移調するだけとなる。これに対して、「模倣」の場合、記譜されたものに対する想像上のclefを代替せねばならず、またモデルのそれとは異なったソルミゼーションシラブルを使わなければならない)。 その結果、演奏者は、最初にフーガ的」解決を試し、「フーガ的」解決が機能しなかった場合にのみ「模倣」的解決に頼るようになった。 つまり、そのconsequentsが、そのガイドの正確な音程を維持するために、臨時記号のinflectionsを要求する唯一のカノンは、ユニゾン、四度、五度、オクターブでのそれなのである。 Zarlinoの議論は、現代の狭い意味でのカノンに関するものであるが、その結果は、ここで用語を使用する広い意味でのカノンを含めること、つまり、オスティナートや、同じメロディーを同じ声部で連続して使用する場合のような現象を含めることへと、一般化される可能性がある。なぜなら、そのようなすべての現象の背後にある基本的な原則、1つの楽曲で同じ完全なメロディーを2回以上使用は、同じことだからである。 この基本原則のアイデンティティは、このファミリーに属するすべての作曲技法が、メロディーを1回だけ表示し、そのconsequentを導き出すための「規則」をメロディーに提供するという、省略された記譜法を用いることができたという事実によって協調されている。 もちろん、この一般化が正当であることを絶対に確認することはできない。それが理にかなっていることを維持することしかできない。 5 Zarlinoの「フーガ」と「模倣」の区別は、これらの用語の現代的な意味でのカノンと模倣の両方に適用される。もしも我々が、Zarlinoの時代の演奏家たちが、ガイドの音程を正確に2倍にしたら、consequentsは、模倣点で、四度、あるいは五度で、いつ入ったらよいのか? これは、E.Lowinskyによって出された、彼の16世紀音楽半音階解釈における過程であり、単に仮定に過ぎないことが強調されねばならない。 p158 模倣において、省略表記で提示されたカノンの場合とは異なり、作曲家は彼の意図を明確に示す機会があり、臨時記号なしでconsequentを続けさせることを選択した場合、彼の演奏家たちは、作曲家が望んだことが、Zarlinian sense では「フーガ」ではなく「模倣」であると結論付けたことだろう。7 ユニゾンまたはオクターブでの(現代的感覚での)「模倣」は、もちろん別の問題である。 Lewis Lockwoodは実際、Ghiselin Danckerts' の臨時記号に関するローマの論争において、正確なサイズの音程の保存がオクターブでの模倣において望ましいことが示唆された証拠を発見した。 8 以前の理論家は、Zarlinoの規範と模倣に関する議論の包括性にアプローチせず、その結果、彼の議論から得た結論が彼の時代のどれくらい前に有効であったかをある程度保証することは困難である。 しかし、これらの結論は非常に単純で(「ガイドの正確な音程を表現するために、consequentにおいて臨時記号の使用を要求できるのは、四度または五度のカノンだけである」)、それらは、中世とルネサンスの理論のいくつかの側面に、非常によく合う。(少なくとも、グイドの「親和性」の研究、最終的には音階の7つのヘクサコードで体系化された研究以来、音楽家らは、四度と五度離れたステップの、音程パターンの類似性が、その他の音程でのそれよりもはるかに大きいということに気づいた。結果として、カノンが、別の音程のときよりも四度や五度のときに「フーガ的な」解決を期待していた可能性がはるかに高かった)。こうしたことを、我々が、初期の声楽ポリフォニーの標準的な慣行を研究する時には、それらを少なくとも作業仮説として使用するかもしれない。 Zarlinoの同時代のNicola Vicentinoは、彼の論文の1つの章をカノンに費やした。 9 Nicola Vicentinoによれば、 '' second , third , sixth , seventh and ninth で作成されたカノンは他のものよりもモダンである。10、つまり、ユニゾン、四度、五度、オクターブによって作成されたカノンは、 Zarlinoの「厳格なフーガ」と「厳格な模倣」との区別の妥当性について、非常に間接的なサポートを提供する。 Vicentinoはさらに述べている。すなわち・・・ 「テノールがアルトと五度でカノンを作るとき、テノールがb♭である場合、アルトはb 我々は、ボローニャのGiovanni Spataroと、1529年のヴェニスのGiovanni del Lagoによって交換された手紙の中で、1550年代より前の質問に対する態度を垣間見ることができる。 Giovanni del Lagoは、10月8日の手紙の中で、Vincentinoと同じく、低声部の五度下の”フーガ”は、♭署名を持つべきであり、この主張は、より初期の理論家たちを参照することで、サポートされる、と論じている。そして例として、Adrian WillartのAve maris stellaのcantusとテノールを、そして同様にJacquet of Mantuaの5声モテットPlorabant sacerdotesを挙げている。 Spataroは、11月24日の手紙において、”フーガ”においては、ガイドの音程は、常に正確に再生されるとは限らない、と報告している。 彼が言及している箇所は簡単に特定できるが、ここで私たちが興味を持っている疑問にはまったく触れていない。概して、Zarlino前のカノンと模倣の理論は、我々の目的には大雑把すぎるが、少なくとも我々がZarlinoから導出した条件とは、矛盾することはない。 |