| THE FUNCTION OF CONFLICTING SIGNATURES IN EARLY POLYPHONIC MUSIC2 By EDWARD E. LOWINSKY |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| p227 "CONFLICTING SIGNATURES" や"partial signatures"は、単一のポリフォニー作品のさまざまな声部におけるさまざまな調号の使用に適用された用語である。 conflicting signaturesの使用は、13世紀から16世紀に限られている。3声部の作品においては、最下声部はしばしば1つの♭署名を持ち、2つの上声部は、そうした署名を持たない。時には、2つの低い声部が1つの♭署名を持ち、discantのみが署名がないこともある。 時には、低声部では2つの♭署名を持ち、discantは1つだけの♭署名を持っていることもある。低い声部よりもdiscantにおいてフラットが1つ多いことは、比較的まれである。 これらのconflicting signituresの意味と機能は何であろうか?いくつかの理論が提示されている。 Rudolf Fickerは、Bフラットの欠如は、グレゴリオ聖歌のメロディーが委託されたパートであることを示すためのものであると考えた。 Knud Jeppesenは、グレゴリオ聖歌のメロディーを使用しない世俗的な作品がチャントを基礎とした教会作品としての記譜の同じ特殊性を表すことを指摘して、この仮説を整理し、ある理論を示して、これを廃棄した。 その理論とは、discantは通常、テキストが提供された唯一のパートであるdiscantであるため、そこは歌われた唯一のパートであり、さらに、よく訓練された歌手は、必要な臨時記号を自由に適用することができた一方で、楽器で下声部を担当するミンストレルは、あまり訓練されていなかったために、特別に(臨時記号の)introductionを与えられなければならなかった、ということである。 しかし、Jeppesen自身は、単一作品の異なるコピーが、密接に関連した写本に含まれている場合でさえ、記譜法のこの側面で時々しか一致せず、筋道が立っていれば、こうした事が起こることはないだろう、と述べた。 p227 したがって彼は、conflicting signatures は、音楽の性質に基づく本質的な違いではなく、個々の声部の表記におけるグラフィックな違いのみを表していると結論づけた。この種の表記法は、当時の音楽がテキストと共に提供されるやり方を示すのと同じ種類の不注意と矛盾から生じていると彼は言う。 ただし、conflicting signatures はかなり頻繁に出現し、少なくとも3世紀続くソースで一貫して出現しているので、これ以上のストーリーがあることは間違いないだろう。 <Apel> ウィリ・アペルは彼の研究 "The Partial Signatures in the Sources up to 1450"で、新しい理論を提唱している。 彼は、非常に多くの初期のソースでの "partial signatures"の出現は、”1つの同じ作品内の2つの異なる調性領域を意味する。すなわち、低い声部では純粋にb♭領域であり、上声部ではb 言及された理論が広範囲にわたる実用的な効果を持っていることは、JeppesenとApelの編集方針から容易に理解できる。署名の矛盾を、筆記者側の不注意のみであると見なしているJeppesenは、当然のことながら、調号のない声部での編集上のフラットを多く追加する傾向がある。 アペルは、「現代のtranscriptionsとこの時代(13~4世紀)の作品の解釈では、補足的な臨時記号(bフラット)は許されない」と考えた。しかし、15世紀の音楽では、アペルは「別の慣習が見られた、つまり、実際には、署名のない声部では補足的な臨時記号が要求された」ことを見出した。 アペルはこれらの臨時のアプリケーションの新しい原則を策定した。彼はすでに述べた研究と彼の以前の論文8と彼の重要な著書"The Notation of Polyphonic Music, 900-I6oo"9でそれらを述べている。 アペルの臨時記号についての一般的な理論は、彼のconflicting signaturesの解釈と密接に関連しているため、前者の説明から始める必要がある。 p229 アペルは、4つの主要な仮定に基づいて彼の臨時記号についての理論を発展させている。 1つ目の仮定は、古い理論家は常に一般化する傾向があるため、古い理論家の著作には依存できないということである。その上、彼の主張では、ほとんどの理論家はイタリア人またはスペイン人であり、その原理はブルゴーニュ、フランス、または英国の音楽には適用されない。 「ごくわずかな規則を与えてくれる理論家から多くの支援を受けることは期待できません。」l0 アペルは、Ramis, Gafurius, Aron, Zarlinoなどの理論家の多くに言及している。 15世紀と16世紀に音楽理論が保持していた正確な立場を明らかにし、それが臨時記号の問題の解決にどのように貢献するかを明らかにするためには、特別な研究が必要である。 現在のところ、Apelが言及した理論家たちは、いくつかの自明な規則を供与するには程遠く、 voice-leading, counterpoint, and harmonic structureの詳細に向けられていた、と述べるだけで十分である。彼らは一連の例を示している。彼らは一般化していないが、特定の作曲家や作曲を引用している-それらの中で、ブルゴーニュ、フランス、およびオランダの起源の作曲家と作品である。 臨時記号理論への貢献がまだ十分に活用されていない多くの古い作家がいる。さらに、理論と実用的な音楽の間に線を引くことは、Apelがしたように、15thや16thの状況ではなく、19thや20世紀の状況を確信させる。 Apelの2番目の仮定は、臨時記号が実際に書き出されているオルガンのタブ譜が、それらを欠くボーカル音楽の臨時記号の扱いの前例と見なすことができるということである。 だが私は、この見解を支持できない。ボーカル音楽への臨時記号の適用は、主に各個別パートの声部連結に依存しているが、タブラチュアは声部連結の個性を保持していない。代わりに、通常、異なるパートの全体的な効果の要約のみを提供する(アドリブ的な要素が多い)が、それは、今日の交響曲の楽譜のピアノ版よりもはるかに自由である。 この要約は、楽器と演奏者の手の制限、および運指の考慮によって自然に調整される。タブラチャー作家は、合唱音楽の作曲家のそれとは非常に異なる条件と目的のもとで働いているので、彼の(器楽)作品は、声楽作品のパフォーマンスの基準と見なされるべきではない。 この事実は別として、アペルの方法は疑わしい。彼は musica fictaの使用を大幅に制限する傾向があった。彼は彼の傾向を支持するタブラチュア、すなわちドイツのオルガンのタブラチュアを選択した。 p230 彼はリュートのタブ譜を完全に除外している。その理由として、リュート音楽においては、古い調性と新しい調性の間の闘争では、新しいものが好まれたからである、としている。 彼は、リュートとポピュラー音楽との密接な関係と、導音の演奏を容易にする楽器の性質によって、これを説明している。 アペルはオルガンとリュートの間のもう一つの重要な違いに言及した。リュートの指板はフレットによって等しい半音に分割されたが、オルガンのチューニングには、major and minor semitonesの難しい区別があった。それは、かなりの音程と和音の遂行を単純に不可能にした。 当時のボーカル音楽は、オルガンと同様にリュート用に転写されていたので、It is exactly these limitations of the medieval and Renaissance organs that should have led Apel to include the lute tablatures. そして、2つの楽器の転写間の系統的な比較のみが、musica fictaの使用において、こうした制限の依存がどの程度あったかを決定的に示すことであろう。 Apelの3番目の仮定は、古い写本自体に現れるように、特にI450年まで、臨時記号の表記は一貫していたということである。彼は書いている。「作家は、必要な非常に多くの場所で臨時記号を付与したが、他の多くの場所でそれらを「省略」または「忘れた」と仮定することは、公正な調査の原則とは、相容れない」 。 しかし、それは実際の慣行と相容れている。これは、アペルが無視している理論家によって豊富に明らかにされている。 I523年の Toscanello in Musica の中で、特により初期の世代による臨時記号の挿入で示された不整合について長い議論を捧げているPietro Aron に言及するだけで十分であろう。 彼は、以前は決して書き留められなかった場所に臨時記号を書き留める当代の作曲家の数多くの例を挙げている。アロンは、以前存在していたかなり無計画な状態ではなく、一貫して明確に書かれた臨時記号の指示を要求した最初の理論家のようである。 I3〜I6世紀の音楽ソースでの臨時記号の一貫性は、当時の名前と単語のスペルの一貫性ほど期待できるものではない。綴りの不一致は、不注意だけでなく、多様性を積極的に享受したことからも生じた。 Nicola Vicentinoは、彼のL'antica musica ridotta alla moderna prattica(555)の序文で、ギリシャ人が言語を適切に使用していたという概念に対応する望ましい理想を、単語とスペルのさまざまな使用例で見ている。 公平な調査のための正しい原則を決定することは非常に困難である。原則としては、異なる時期を支配し、特定の慣行を導く可能性が高い概念と偏見を見つけて考慮することである。 アペルの4番目の仮定は、多くの音楽学者が共有するものであり、アペルは次のように表現している。 何度も何度も、編集者は、 "parte post"(あとから)の修正に頼るよう強いられてきた。すなわち、スコアの完了後、垂直関係において必要であることが判明した半音階的訂正である。 しかし、全体的に、1つのパートづつで書くことに基づいている音楽では、このタイプの修正を行う余地がないことは明らかである。 厳密に水平な特性を持たず、歌手(および現代のトランスクリプター)が"a parte ante"(予め)に、すなわち、♭や♯が必要な場で、問題の声部だけを考慮して判断できるようにしない限り、どんな規則も、問題を満足に解決できるとは、考えられない。 ここで我々は、musica fictaの議論における最も重要な誤解の1つに目を向けなければならない。これは、musica fictaに関する混乱の多くの原因となっている。 我々は、musica fictaを適用する際に音楽の垂直方向の側面を考慮することの実用性と必要性に関する疑問を払拭することができるだろうと期待する多くの理由を前進させる。 教会と宮廷音楽のすべての演奏においては、アンサンブルの監督を担当する高度な訓練を受けた音楽家と作曲家がいた。musica fictaによる声部の衝突の調整は彼の仕事の1つであり、多くの古いクワイヤーブックとパートブックは、フラットまたはシャープが監督または歌手自身のいずれかによって音符に追加されたことを示している。 mi contra fa (三全音)を禁止する規則の実際的な意味合いは、現代では正しく理解されていないようだ。 もしも15世紀と16世紀のほぼすべての音楽に関する本がソルミゼーションを扱っていたとしたら、それは合唱の歌唱におけるその非常に実用的な使用によるためであった。ボーカル音楽作品は、最初にソルミゼーションで、次にそのテキストで研究された。ニュルンベルクのJoannes Cochlaeus は、1511年の彼のTetrachordum Musicesにおいて、この慣行について、語っている。 p232 演奏には3通りのやり方がある。音楽は通常、3通りで演奏される。最初はソルミゼーションで、すなわち、音の名前で歌う。次に、それに属する歌詞とともにメロディを歌う。3番目には、歌詞もソルミゼーションもなしで歌う(器楽的演奏)。 同様に、Recanetum de Musica Aurea(I533)においてStephanus Vanneusは、Book I、Chapter 13で、歌の3つの方法を区別している。1つはソルミゼーション、2つ目はソルミゼーションなし、3つ目は歌詞である。 mi contra fa の禁止の意味は、極めて実用的なものであった。2つの声部が互いに、三全音あるいは減五度、あるいは増・減八度さえも寄り立つところはどこでも、ソルミゼーションの歌い手は、一方はmiを、他方はfaを歌わねばならない。こうした(ソルミゼーションによる)miとfaの同時の発声は、何かがおかしいという合図なのであった。 当時の歌手たちは、史上最も高度な訓練を受けた音楽家たちであった。彼らが歌っている間、彼らがお互いに耳を傾けても、対斜、三全音、および同様の不協和音を発見することができなかったなどと、どうして我々が仮定し得ようか? 確かに彼らは彼らの同時代人によってそうすることを期待されていた。Vanneusは彼のRecanetum、Book III、Chapter 37でこれを証言し、そこでポリフォニー複合体のさまざまな声部へのmusica fictaの適用について扱っている。 耳は最も頼りになる解釈者である。あなたをベストに保つ。良き歌手のパートを聴きなさい。彼は不協和音に気づくや、すぐに、耳に心地よくなるまで、音を♯化、♭化する。彼はそれを注意深く、斬新的に行う。ほとんど悟られない形で。ゆえに我々は、したがって、無知の芸術ignorant artが私たちを否定するものを、私たち自身の創意工夫ingenuityによって得ている。 p233 「無知の芸術 "ignorant art"」という表現によって、Vanneusはこの記譜が、どの音が♯化や♭化されるのかを完全に示すことができないことをほのめかしている。 「私たち自身の創意工夫 "our own ingenuity"」とは、当然ながら、優れた音楽家が演奏の最中に耳でmusica fictaを適用する能力を意味している。 Vanneusはアスコリ大聖堂の合唱団長であった。 彼の作品のタイトルでは、彼は"In Asculana ecclesia chori moderator"と名乗っている。 合唱団長としての彼の実務経験は、彼の証言を私たちの目的にとって二重に価値のあるものにしている。 この証言は、すでに進んでいる理由と相まって、歌手が彼の前に自分のパートしか持っていなかったため、和声の考慮がmusica fictaに適用されなかったという概念のすべてについて一度、配慮をする必要がある。 誤った前提から引き出された結論が満足のいくものである可能性は低い。アペルが示唆した規則について、正しいのは、彼が古い理論家から受け取ったものだけであった。彼らは、Bの♭化がuna nota supra laとして、または三全音の一部として示された時に、その♭化を要求している。そして、カデンツにおいては、導音の上昇を要求している。 Apelは1つの新しい規則を導入している。それは、Bが跳躍によって到達または終了したときのBの♭化を規定している。この新しい規則は恣意的であり、基盤がない。 もちろん、それは正しい結果を生み、その操作はたまたま理論家によって与えられた規則のそれと一致する。したがってApelの論文の例223では、彼は、三度のスキップでBに到達するために、Bをフラット化している。しかし、それは、対斜や増八度といった理由によっても、とにかく、フラット化されたことだろう。 そのような偶然がない場合、アペルの規則は、それ自体が非論理的な結果につながり、彼の主な目的、つまり編集上の臨時記号を最小限に抑えることとは逆になる。 この規則は、Exx.1a-d に(Apelの論文ではExx 242-4)見られるように、必要のない多くの新しいフラットの挿入をもたらす。 我々はここおよび他の例で、臨時記号の2列の例を示す。下の行は、何人かの現代のエディターの読みを示し、上の行は、musica fictaの通常の規則に従った独自の読みを示す。 Exx1 c-d でApelは、減三和音を生成している。Ex.1dでは、彼は、カデンツに必要な導音を排除している。 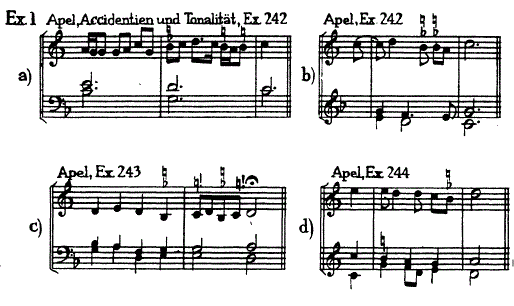 p234 これらの例では、我々は、固有のconflicting signitures領域に足を踏み入れている。Apelによる多くの不要な臨時記号の追加は、(臨時記号に対する彼の正反対の目的にもかかわらず)、成し遂げようとするconflicting signituresのまさにその効果を取り消してしまうことになる。これこそが、Apelが想定した”二種類の調性”の効果なのか?我々は以下のソースで、別の理論を提起しなければならない。 (略) これらを調べた結果、驚くほど素晴らしいタイムスパンがカバーされた。 単一の作品のさまざまな声部におけるさまざまな署名の使用の主たる理由は、非常に単純で、実践的なものであることが判明した。すなわちそれは、カデンツのタイプ、あるいはむしろ、カデンツがもっとも顕著な指数となるような和声進行である。 我々は、3パートの14,15世紀の作品における以下のすべてのカデンツにおいて、fauxbourdonの影響をみることができる。 p235 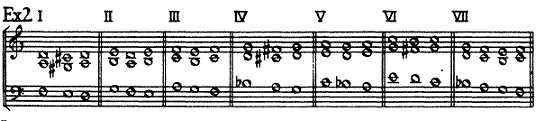 当然のことながら、これらは単に骨格にすぎず、実際には、あらゆる種類の設定で表示される。にもかかわらず、これらのいずれも、discantあるいは中間声部において、B♭を要求しないことは、明らかである。絶対に必要なのは、テノールのみにおいてである。これが、初期のポリフォニック音楽で頻繁に署名される カデンツをもっと詳しく調べてみよう。No.1はドーリア旋法のカデンツを、No.IVは移調されたドーリア旋法のカデンツを、No.IIはフリギア旋法のカデンツを、No.Vは移調されたフリギア旋法のカデンツを、NoIIIは典型的なリディア旋法のカデンツを、そしてNo.VIは移調されたリディア旋法のカデンツあるいはイオニア旋法のカデンツを示している。 もしも我々が、しばしば出現する形式においてリディア旋法のカデンツを取り上げれば、我々は、最低声部でB♭を要求し、最高声部でB これらのカデンツの性質が明確に理解されていなかったという理由だけで、多くの論文が、編集上の臨時記号の誤った適用の例でいっぱいになっていた。カデンツの同じ種類が加わった多くの例では、編集者によって、2つまたは3つの異なるやり方で扱われている。 我々が、これらのカデンツのコネクションを、調査下の何世紀ものソースにおけるconflicting signituresの実践とともに示すには、限界があることだろう。だが同時に、我々は、それぞれの初期のポリフォニーの調性的構造への洞察を得ることが出来よう。それは、musica fictaの規則の知的適用の基礎となるものである。 要するに、たとえ不完全だとしても、13世紀から16世紀までのカデンツの公式の発展の歴史は、我々の調査の副産物となることだろう。 バンベルク写本には、conflicting signituresで書かれた33のモテットが含まれている。それらは、和声進行やカデンツのタイプを表している。 Ex.3は、移調されたフリギアカデンツであるために、テノールにおけるB♭の必要性を示している。Ex.5は、C上のカデンツであるために、motetusにおけるB p236 Ex.4は、リディア旋法の特殊な使用であるために、リディア旋法の作品のmotetusにおけるB conflicting signituresはしばしば、三全音を避けるために、使われている。確かに、後続のF-C-F和音で三全音が解決された和音G-B♭-Eは、早くも13世紀(例6)に使用されたが、頻繁には使用されなかった。 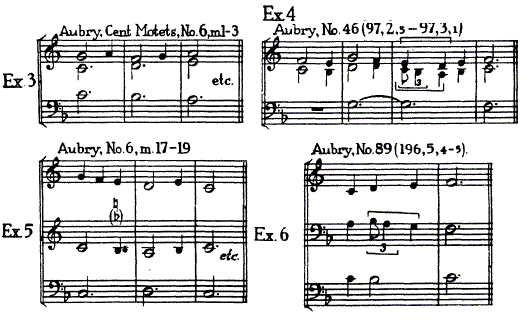 Exx.4と6の比較は、音声連結、対位法、そして和声の繊細な点への13世紀の音楽家の感性を供与する。三全音は、例4では悪く響く。そこでは、平行四度のcompanyにおいてむしろ露出がなされている。 Ex.6では、外側のパートでの平行進行があるが、motetusでは反行となっている。和声的な三全音の不協和音程を避けるために、テノールとmotetusにはB♭が使用されている。 Ex.4において、FはEminor和音から到達され、そのために、(導音を作るために)B Ex.6においては、最後から3番目において、不完全なB♭和声がB♭を要求している。その結果、低声部での根音の二重化のために、Ex.6は、テノールとmotetusの両方にB♭署名を持っている。 バンベルク写本の精査において、Apelは、この音楽において我々は、三全音やその他の和声的な荒々しさを認めなければならない、と結論づけている。”我々は、理論的な発言や500年後の時代の様式的な概念に矛盾すること以外の理由がないソースではっきりと現れている様式的な特徴の信用していく”。 p237 このことは、三全音は1750年頃には忘れられていたということを意味するのか?三全音は、古典音楽においては、完全に普通の音程ではないのか?そして、それは中世の音楽では「9世紀には早くも和声音程として」禁止されていなかったか?13 もちろん、初期の音楽には三全音の和音と三全音の進行が見られる。 しかし、これらは例外である。 バンベルグコーデックスの100を超える作品では、おそらく避けられない3つまたは4つの三全音が見つかるかもしれない。 例外を選び出し、そこから規則を導き出そうとするのは方法としては誤りである。 垂直方向と水平方向の進行で三全音(減五度と増四度)を回避する明確な意図を持って、ソース自体の臨時記号がどのように設定されるかを示す。 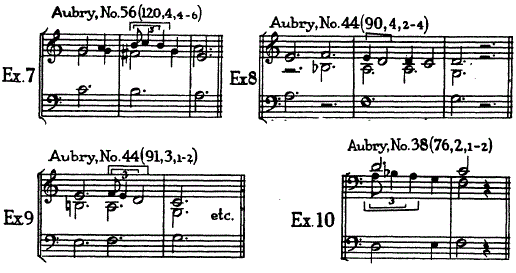 写本は、メロディ的、和声的三全音を避けるための明らかな意図を示すより多くの例を含んでいる。三全音が生ずると、それらは通常、作曲家が和声やメロディの法則を侵す選択をしなければならない、悩ましい状況となる。 Ex.11では、作曲家は、和声的三全音をメロディ的なそれよりも優先して使っている。一方Ex.12では、作曲家は、減五度の和声的音程に対して、三全音の跳躍を優先している。 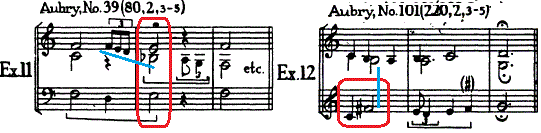 p238 musica fictaについて我々が例外的に考えることの多くが、上記のような厄介な状況から派生しているという事実にはあまり注意が払われていない。 言い換えれば、初期の音楽の作曲家は、編集をする現代の学者と同様に、彼が書いているまさにその時に、臨時記号に関する問題に直面していた。 音楽学者は、作曲家が三全音を避けることができなかったという単純な理由で、スコアから三全音を「編集」できない場合がある。我々が、偉大なる巨匠よりも平凡な作曲家が、そして偉大なる巨匠は彼らの円熟の時よりも若い時期の作品で、そのような厄介な状況に巻き込まれているのを見出すことに注目するのは適切である。 しかし、 "Quandoque bonus dormitat Homerus"は、ティンクトリスが述べているように(ホラチウスを引用して)、Faugues, Busnois, Caronなどの作曲家の作品に減五度があることを示している。 マショーの作品では、conflicting signaturesを持つ多数の作品がやはり見い出される。 その理由は、13世紀の音楽と同じで、上声部のB♭のシグネチャがない場合は、C上のカデンツが原因である。一方、下声部は、移調されたフリギア旋法と移調されたドーリア旋法のカデンツのために、B♭を要求する。 2声部バラードB16 では、非常に興味深い状況となっている。そこでは、第1セクションは Ex.13は、この種の音楽には、2つのメロディラインがbitonalityを持たないことを示している。tonal tracksを2つのメロディラインが進む場合には、bitonalityについて言われるかもしれないが、この音楽では、tracksは、何度も収束し、低い声部とのtonal unityがそれを要求する時にはいつでも、作曲家自身によって上部パートに加えられた臨時記号から明らかになっている。 p239 Leonard Ellinwood がFrancesco Landini の作品について彼の版で集めた154の作品の中には、conflicting signaturesを持つ28の作品がある。 これらの(conflicting signaturesの)機能は、B 音楽に関する有名な追悼である、3声部のマドリガル Si dolce non sond (Ellinwood, No. 12)は、テノールにBフラットを持っているが、 contratenorとsuperiusには調号がない。上のパートでは、C上のカデンツのためにB 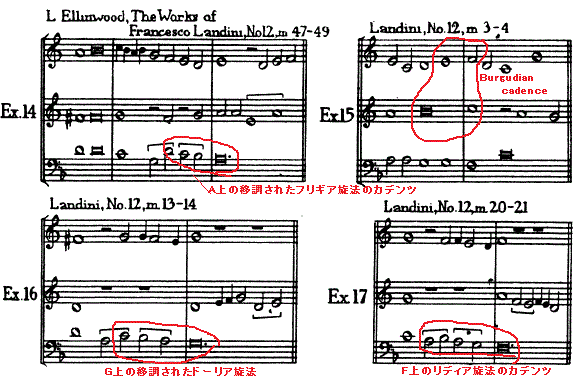 MachautやLandiniのような早い段階では、メロディと和声の構造が導音の原理によって支配されていることは明らかである。 上声部は主に上向きの導音を使用し、テノールは下向きの導音を使用する(たとえば、BフラットがAに下がる)。 p240 時々、 ランディーニの作品では、カデンツのタイプ以外に、 conflicting signatures を使用する他の理由が見い出される。De'! dinmi tu (wood No. 10)は、Ellinwoodの転写によると、上声部に調号がなく、テノールにBフラットがある。テノールは、移調されたドーリア旋法のメロディーを持っているが、そこでは、B♭が必要とはされていない、移調されていないドーリア旋法において五度高いコントラテノールによって、厳密なフーガとなっている。 同じマドリガルのリトルネッロは、3声のカノンであり、14世紀ではほぼ他に例がないものである。superiusとtenorはどちらも、G上で移調されたドーリア旋法であり、それゆえ、1つの♭記号を持っている。 Ellinwoodの転写では、テノールにはフラットがありますが、superiusにはない。 contratenorは五度でのカノンとなっており、そのために、調号が必要とされない。 カリフォルニア大学バークレー校は、この作品があるSquarcialupiコーデックスのマイクロフィルムを使用しています。その機関のブコフツァー博士は調号に関してこのソースを検討するのに十分であった。彼は報告する。 (略) p243 MachautやBamberg Codexを振り返ってみると、まだ考慮していないいくつかの作品を説明できるようになる。 Machaut作品のバラードNo.8は、上声部にBフラット署名があり、テノールにはEフラットのみがある奇妙な構成となっている。 テノールは、現代の和声学的な観点からでは、BフラットとEフラットの両方を持つ必要があるが、Bはパート全体で♭がつくことがないので発生しないので、Bフラットは必要ないのである。 バンベルクコーデックスのNo. 61では、上声部の2つのパートにBフラットがあり、テノールにはない。 p242 同じことは、No。74、No.4にも当てはまる。両者は、モテトゥスとテノールのBフラット署名に対して、トリプラムにシグネチャがない。理由は、Bフラットがトリプラムでは2回だけしか生じないからである。 1回目は(文字通りまさに)臨時記号で供与され、2回目は musica fictaの理由のため自明で、モテトゥスのBフラットと一致するためである。 Stainersが "Dufay and His Contempo- raries"で出版した15世紀前半の50曲の内、24曲はconflicting signaturesを持っている。 Binchoisによる3声部構成のシャンソンからの1つの抜粋は、そのような署名に関する私たちの理論の適用性を示すのに十分である。 下段の臨時記号はStainersによって与えられている。 上の行は修正を表し、このStainersが提案したオリジナルに戻っている。 Binchoisが、C上の繰り返しのカデンツのために、superiusでB-naturalを必要としていることは明らかである。そして、移調されたフリギア旋法上のAと移調されたドーリア旋法のG上のカデンツのための低い声部のB♭を必要としている。 ここでも、カデンツは、 この例では、ミクソリディア旋法から、移調されたフリギア旋法へと移行する、一般的な旋律および和声の発展への唯一のexponentとなっている。 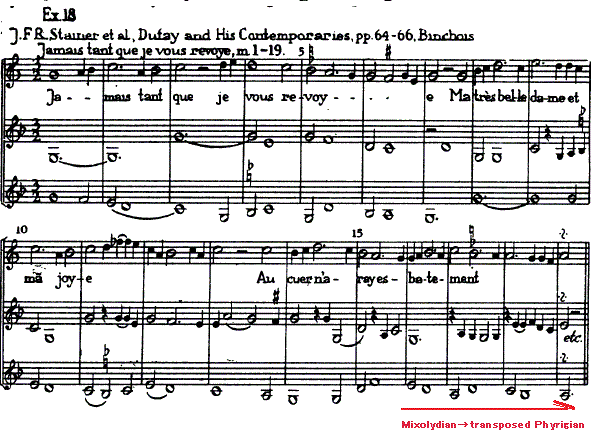 15世紀の音楽では、新しい4つの和声のカデンツが登場する(例I9a)。 それは、I5世紀とI6世紀の音楽の最も重要な定番公式の1つになり、今日ではあまり理解されていないものの1つになった。 p243 近代の編集者は、テノールのBフラットをなくすすることにより、最低声部と最高声部の間の対斜を排除しようとした。 このカデンツは、15世紀後半と16世紀後半に出現頻度が増加し、四度上または五度上に移調され(例g9b)、または開離和声(例I9c)となる。この和声の進行の元の形式は、ミクソリディアカデンツ(Ex。I9d)である。 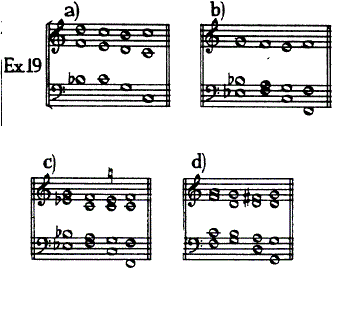 サブセミトーンのFシャープなしで、一連のF、G、Dマイナー、Gコードができる。最後のコードの前にサブセミトーンを使用することで、F、G、D、Gのコードで構成される興味深いカデンツに到達する。 このカデンツは、先行するカデンツと同様に、ドミナントのサイドからだけでなく、サブドミナントのサイドからもトニックにアプローチする。近代和声学の用語では、ミクソリディア旋法のカデンツの最初の和音は、サブドミナントのサブドミナント(ソシレ→ドミソ→ファラド)を表す。 実際の機能では、それは、近代のカデンツIV-I-V-Iでのサブドミナントとなる。近代のカデンツと比較して、ミクソリディア旋法タイプは、そのより大きな駆動力のために、独特の力強さを持っている。 カデンツIV-I-V-Iでは、トニックが最初に発生したときに一時停止が可能となる。ミクソリディア旋法のカデンツでは、FとGのコード間の距離と緊張が非常に大きいため、DとGのコードが緩衝材となる必要がある。 最後の和音の前に停止することができない公式IV-I6/4-V-Iをもたらしたのは、IV-I-V-Iカデンツの弱点に対する認識の高まりであったに違いない。ミクソリディア旋法のカデンツは、旋法的ポリフォニーにおいて、カデンツIV-I6/4-V-Iが長短システムで実行する機能と同じ機能を果たす。ミクソリディア旋法のカデンツは、フリギア旋法、あるいはドーリア旋法のカデンツと同じ頻度で移調されて現れる。 デュファイは彼のシャンソン Las! Que feray? を、2回移調したミクソリディア旋法で終止している。  p244 Stainer 版のすべての24のconflicting-signatureの作品は、説明されたカテゴリのいずれかに該当している。 しかし、カデンツはconflicting signaturesを使用する最も頻繁な理由ではあるが、それだけが唯一の理由ではないことを再度強調する必要がある。すなわち、時として、superiusのB 4つの和声のミキソリディア旋法のカデンツは、通常の位置であるいは移調されて、4つの和声のドーリア旋法のカデンツにおいて、対位法を保持している。 このカデンツは、ミクソリディア旋法として、ほぼ同時に出現している。例は、Trent CodicesのCopenhagen Chansonnier において見られる。 我々は、 3つすべての声部にBフラットがあるDufayのPour ce que veoir ne puis(Stainer、p。1I 3)のような作品を調べることで、conflicting signatures に関する調査結果の正しさをテストできる。 実際、我々は、このシャンソンには、D上の、A上の(移調されたフリギア旋法)、G上の(移調されたドーリア旋法)カデンツが含まれていることを見出す。ただしC上にはない。そのために、Bナチュラルは不要となる。 一方、移調されたドーリア旋法とフリギア旋法のカデンツに対するsuperiusでのB♭の使用は、デュファイの音楽に特徴的な、統一された調性に向かう傾向を示している。 移調されたドーリア旋法とフリギア旋法のカデンツに対するsuperiusで、B♭を頻繁するその他の作曲家たちもまたいるが、彼らはしばしばBフラットを臨時記号として書き込むことを好んでいる。 Trent Codicesは、Stainerの冊子で表わされた世俗的な音楽に、教会的pendantを提供している。conflicting signatures の使用における作曲者のポリシーはまったく同じである。 そのような性質で書かれた作品の主要なシェアは、デュファイとダンスタブルに属している。すべての場合において、これらの署名の働きは、Cでのカデンツを含むさまざまなカデンツを促進することにある。Stainer冊子とTrent Codicesの両方で、署名 この変化の理由は何か? アペルはその中で「「調性」のより強い感覚とより明確な表現」と「和声の基礎のより強いストレスに相当するb♭の「重い」領域に対する増加傾向」にその理由を見出している。 p245 この署名の変更につながる理由は、カデンツ公式の変更によって証明されているように、和声構造の段階的な変更にある。 最も重要な変化は、fauxbourdon cadenceからI-V-Iへのものである。例2-Iのカデンツは、例22-IIに置き換わることになる。 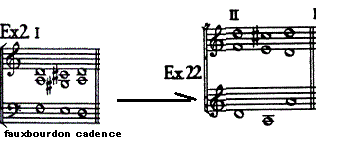 我々は、EやA上のフリギア旋法のカデンツを省略した。なぜなら、明らかに、例23のカデンツようなその使用は、問題外だからである。 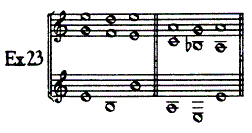 しかし、カデンツ形成が既述の変化を受けたまさにその時に、我々は、以下の例24のような新しいカデンツを見出すことは、興味深い。 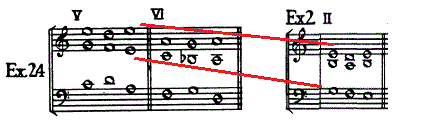 2つの上声部は、例2のフリギア旋法のカデンツの外声部と同じである。バスは、減五度とならないようになっている。言い換えれば、これらは新しい形でのフリギア旋法のカデンツなのである。新しいカデンツIVとVIが、中間声部に対して、B♭を要求することは、容易に理解できる。 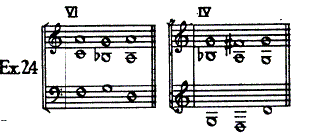 fauxbourdon形式の古いカデンツは、最低声部にB♭を要求し、さらに、新しい形とともに、さらにまだ使われている。それゆえに、 無論、カデンツの新しいtableにとって、同じことが古いものについても言える。公式は骨格であり、実践において、多くの異なった形式がある。 p246 カデンツIIは、たとえば、この特徴的な形式において、しばしば現れる。それは、最低声部にB♭がある。 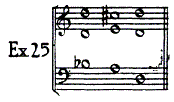 その他にも、新しい 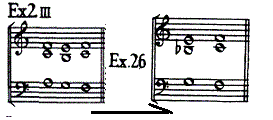 もうひとつの理由は、下2声部の互いのクロスの増加するfrequencyである。中間声部は、最低声部の役割を引き継ぐ時には、その声部が通常用意されているB♭を必要とするから、ということである。 Trent Codicesから公開されたセレクションの編集者が、新旧のカデンツの性質を理解できなかったため、あるいはconflicting signatures を処理する上で無力であったための失敗は、追加の臨時記号における誤った編集ポリシーにそれらを従わす原因となった。 Dunstableの3声部の Alma Redemptoris Materは、テナーとコントラーにフラットが1つあり、高音にシグナチャーがありません。高音域で発生するBナチュラルのほとんどは、システムや一貫性がなくても、理由なくBフラットに変更されます。 3番目のセクション(Virgo prius)には、trebleにI4の Bがあるが、編集者はI3をすべて不必要に♭化している。 同様に混乱した編集慣行は、conflicting signaturesで書かれた初期の音楽のほとんどすべての近代の再版に見られる。 |