| p80 (ii) The method of avoiding the tritone and diminished fifth tritone and diminished fifth は、全音階で生じる唯一の非和声関係なので、我々はそれらをどのように修正するかの問題を扱う必要がある。 移調されていないシステムでは、これらの関係は、Faと この事実に照らして、我々の時代を通して、我々は、あたかもF♯を使った可能性は存在さえしなかったかのように扱われた理論家が次々と問題を議論していることを発見して、驚かされる。結論は驚くべきであるが、大規模な証拠で支持され、したがって避けられない事実である。 すなわち、移調されていないシステムでは、F♯ではなく♭によって非和声的関係を正している。移調されたシステムでは、それに応じて動作し、常にフラットを使用する。シャープではない。すなわち、署名がフラット1つある場合、B♭-Eの非和声的関係は、Eの♭化によって、正されなければならず、署名が♭2つの場合は、E♭-Aでは、Fが♭化されて訂正されることになる。 音符に関連する証拠を列挙する以上のことをするのは面倒である。ガフリウスが全音を半音に分割することについて議論するときに、彼は、major semitoneの下にminor semitoneを置く方が便利だと説明している。つまり、♭の黒鍵のステップを使用する。 58 理由の1つは三全音である。それは、♯ステップでは決して修正されない。すなわち、いつでもどこでも、三全音の耳障りさを取り除くために、全音を分割する必要があります。major semitone をminor semitone の前に置くことは決して許可されない(つまり、♯の黒鍵ステップを使用する)。59 p81 それ以上に明確にすることはできない。我々がすでに遭遇している、 シャープはここでは三全音を補正するためではなく、導音を生成するために使用されているため、これは明らかに一般的な規則の例外ではない。 しかし私は、例外を提供していると思われる3つのテキストを見つけた。 HothbyのLa Caliopea legaleを伝える写本の1つは、三全音の一般的な議論に、これらの音程が♭またはF#のいずれかによって修正される可能性があるという考察を追加した。 この考察を示す例の1つは、F#をG上のカデンツの導音として使用している。これは、Hothbyが念頭に置いていることが明らかに、我々のルールの例外ではないことを意味する。 追加し、これらの間隔は71rまたはF#によって修正される可能性があるという観測を減少させました。つまり、Fが最初に来た場合は、♭を使用し、 この観察は、Gのリズムの主要なトーンとしてF#を採用していることを示しています。これは、Hothbyが念頭に置いていることは明らかに私たちの規則の例外ではないことを意味するが、少し前に、Martinez and Aaronによって状況は記述された。 別の例では、ただし、カデンツの進行状況とは無関係に、f#を採用している。すなわち、 Bonaventuraは、BとFの間の減五度を完全五度にしたいならば、F♯の見せかけのステップを使うことがよい、と説明している。E♭が ただし、問題のパッセージは、音程のサイズの説明に沿って発生することに注意されたい。そこでBonaventuraが行っていることは、メロディを改善する方法に関する実際的なアドバイスではなく、減五度と完全五度との間の違いの単なる分類であるだろう。 最後に、ラウンドb(♭)とdiesis( #)の記号のそれぞれの機能に関するLanfrancoの説明には、この興味深い節がある。「ソフトbが、squarebの歌での三全音を避けるために使用されるのと同じように、三全音の耳障りさを緩和するかもしれないdiesisは、より甘い協和音程を作成するために任意の順序で実践される。」62」 ランフランコは、ラウンドb(♭)とdiesis( #)の記号が異なる機能を果たすと考えている。前者は三全音を修正するが、後者は後で詳しく説明する用途がある。しかし、彼は、三全音の耳障りさを緩和するかもしれないとした部分に、diesis記号を用いて三全音を修正することもできると付け加えた。 これは、私が明確に、三全音と減五度が独自に♭を持って訂正されるという規則に矛盾するものを見つけることができた唯一のパッセージである。そしてこのパッセージでさえも、♭が通常、こうした目的のために使用されたことを暗示している。 ゆえに、我々は、Lanfrancoが、例外的な環境においてのみ、非和声的音程をただすために♯を許容していた、と結論付けるのがせいぜいである。彼が心に思っていた例外的な環境とは、正確に、Martinez and Aaronによって記述されている。すなわちそれは、♭が決して導入されることはない、 P82 しかしいずれにせよ、圧倒的多数派の理論家は、非和声的な旋律を修正する方法を説明するときに、♭のみに言及しているという事実において、そのような状況で♯が使用されたと思われる場合は、それらは例外的にのみ使用されたということはあり得よう。 非和声関係を修正したいのになぜフラットがシャープよりも好まれたのかという問題に対処する理論家はいないので、私はこの問題についていくつかの推測しか提供できない。offending な音程の旋法的なコンテキストがここで関連していたと思われる。 理論家たちは、soft bのさまざまな旋法での使用について頻繁に議論している。我々は、ジャック・ド・リエージュが14世紀初頭に、現在の標準である教義をすでに説明しているのを知っている。すなわち、♭はtritus(第5,6旋法(で非常に一般的であり、それはあまねく使用され(すなわち、調号として)ている。なぜならそれは、終止において、非和声的関係をただすものであるから。それは時々は、偶然に、protus(第1,2旋法)でも使われる。それはdeuterusではめったに使われない。(なぜなら、それは、終止において非和声関係を生成しないから)。しかし少なくともそれは、そこでは旋法を破壊することはない。それはtetrardus(第7,8旋法)ではもっとも控え目に使われる。なぜならそれは、protusへの変化(移調)となるからである。 さまざまな旋法でのソフトbの使用について理論家が私たちに言ったことは、♭だけが非和声関係を修正するために使用された理由を理解することを可能にする。 我々がすでに知っているように、♭は、一般的に、(それがないと)終止に伴う非和声的関係が特に耳障りとなるtritus(第5,6旋法)において使われた。 終止における♯化は、offendingな三全音がそうしたよりもより一層の混乱を引き起こした。 protus(第1,2旋法)は、♭が使用された2番目に一般的な旋法コンテキストであった。通常の、protusの終止音はdであった。(移調されていない場合)。不規則な場合、それは、aであった。(やはり移調されていない場合)。 終止における六度のステップが、定期的および不定期のprotusで異なっていたという事実は、我々の時代の音楽家たちを悩ませた。 Glareanは1547年に改革を試み、1558年にはZarlinoの承認を得て、その普及に成功した。その後、定期的なprotusでの♭の使用は、メロディの旋法的アイデンティティには影響がなく、通常の六度のステップが不規則なそれに変更された。 一方、F♯は、非移調のprotusを移調されたtetrardusに移して(transform)しまった。 deuterusに戻ると、我々は、♭がそこではめったに使われなかったことを思い出す。なぜならそれは、終止に伴う非和声関係を導入したからである。 しかし、♭は少なくとも、deuterusの旋法的identityには影響しない(∵非移調システムにおいては、 そして最後はtetrardusについてである。♭の使用は、ここでは避けられたことを思い出すべきである。なぜならそれは、移調されていないtetrardusを移調されたprotusにtransformするからである。 一方、F♯の使用は、旋法のアイデンティティに影響したようには感じない。F♯がカデンツの導音として導入されたと考えれば。なぜなら、そうでなければ、tetrardusでのF♯の規則的な使用は、tritus(そこでの終止における理論的な四度ステップは、既知のように、より頻繁に♭化された)から区別し得なくさせることになるからである。 p83 したがって、旋法を変更せずにF#を導入できる唯一のコンテキストはtetrardusのコンテキストであった。そこでは導音としての役割のみがあった。 したがって、非和声関係がどのように修正されるかを説明する理論家がF#の使用をまったく考慮しなかった1つのケースは、正確には、tetrardusにおけるカデンツ進行 疑問への別の答えは、Margaret BentとAndrew Hughesの主張で示唆されている。どちらの音符をinflectするかを選択する必要がある場合、中世の音楽家たちは通常、musica fictaではなくmusica veraを好んだことだろう。64 「臨時記号の適用の基本的な規則は、musica rectaがmusica fictaよりも可能であれば使われるべきである」とBentは強調している。 この主張が正当化された場合、♭またはF#を使用するという選択に直面した場合は、我々は前者を選択するべきである。なぜなら、♭は(他の「黒鍵」ステップとは異なり)musica veraに属しているためである。 しかし、実際には、「rectaの選好」が中世の音楽家たちに支配的であったことは決して確かではない。Bent and Hughes は、頻繁に遭遇する理論的陳述に基づいて、Prosdocimus de Beldemandisの最初の見せかけ音楽のルールでは、「ムジカフィクタは、必要な場合以外、適用されない」という効果を基礎としている。66 この種のステートメントは、フィクタステップよりもレクタを優先することを示唆するように解釈されるかもしれないが、意図的または恣意的にinflection(大部分、みせかけのステップを含む)で臨時記号を使用してはならないことを意味すると解釈される場合もある。ただし、非和声関係を回避したり、カデンツに適切な導音を提供したりする必要があるなど、従来の考慮事項によってこれらが必要な場合にのみ、本書の4〜7章で説明する考慮事項である。 確かに、Prosdocimus自身は、 recta への選好を前面に打ち出している。なぜなら、上で引用したmusica fictaの「最初の」ルールに遭遇して、彼は彼自身のものであると思われ、そして、彼がrectaへの選好を念頭に置いていない限り余計となる別の規則を追加したからである。「musica fictaは、それ自身を除いてカラー化されることができないいくつかの協和音程をカラー化するために、独占的に発明されました。」'67 しかし、Prosdocimusでさえ、 彼が低声部か上声部をinflectionさせるかどうかの疑問を考えた時に、それが垂直的な協和音程を”色彩化する”ための必要性によって強いられた時に、recta への選好について忘れていたことを考察するのは、興味深いことである。 したがって、”見せかけの”ステップへの”真の”選好が、当時の音楽家たちによって作られた選択肢を支配したことは、決して確かではない。 を忘れていることに注目するのは興味深いことである。 しかし、rectaの選好の規則の持つ主問題は、それが、調号なしに記譜された音楽においてなされた唯一の選択肢を説明できる、ということである。もしも我々が、なぜfa-stepがmi-stepよりも好まれたのかということを説明するための規則を使おうとすれば、移調されていないシステムにおいて確信されるような回答を得られることだろう。しかし、臨時記号とともに記譜された音楽において起こることを我々が考えるや否や、それはbreak downすることだろう。 p84 我々が学んだように、後者の場合において、非和声関係を修正するために♯ではなく♭ステップを用いるということには、十分な証拠がある。 ベントとヒューズは、臨時記号が、グィドの手全体を移調し、そしてそのような移調された手はmusica veraであると考えられていたと仮定した。したがって、musica veraステップへの署名内のものの上にさらに♭を作る。(たとえば、B♭署名で表記されたメロディでのE♭、またはB♭/ E♭署名でのA♭) 第3章の終わりに示したように、しかし、これは当てはまらない。すなわち、当時の音楽家らは、調号によって移調されたシステムが、musica veraを示すとは考えなかった。そして、B♭署名システムでのE♭、またはB♭/ E♭署名システムでのA♭に関しては、musica fictaのステップであると見なした。ちょうどそれらが移調されないシステムにおけるように。 ここで、ティンクトリスが、B♭/ E♭署名を持つ音楽におけるE♭とaの間の三全音がどのように回避され、これらの単語で許容されたのかの例を紹介していることを思い出してほしい。 「さらに、 通常のトーンや真の音楽においてだけではなく、不規則なトーンやみせかけの音楽でも、我々は三全音を避けるべきであり、上記の引用例のように、前に示した方法で三全音を使用します」。'69 a♭で訂正することを避けるべき彼の例で、彼がこれらの三全音を欲したことや、彼の言葉が、このa♭がveraよりもむしろmusica fictaに属すことを明らかにしていることは、疑いない。 それでも、三全音が完全五度になったステップの選択が、musica fictaステップよりもmusica veraを選好することによって支配されるのであれば、Tinctorisは、musica veraに属しているE さらに、移調されていないシステムでも、三全音を完全五度にする時にinflectionされるべき音符の選択が、見せかけのステップよりも真実を選好することによっては支配されなかったという証明はあきらかである。 Bonaventura da Brescia は、三全音がグィドの手の4か所にあることを我々に教えた。すなわち、F- 選択基準が、見せかけのステップより真のステップへの選好であったとすれば、明らかに、後者の2つの三全音は このように、Bent-Hughes理論は、♭が非移調システムでも移調システムでも非和声的関係を訂正するために選ばれた理由の確信的説明をしていない。一方、ここでの説明は、両システムに等しく働きかけている。 調号の機能は、旋法を移調することであり、我々が移調されていない旋法との関係でぎろんしてきたあらゆる考慮は、B♭の役割がB♭記号を持ったメロディにおけるE♭に引き継がれたりした移調システムにも有効であることだろう。 p85 (iii) The non-harmonic relations introduced by internal accidentals and the method of avoiding them ここで、移調されていないシステムに戻りたい。BとFの間の三全音でや減五度を修正するためのB♭の使用は、私たちがすでに知っているもの、すなわち減増オクターブなどの他に、新しい非和声関係を導入する。既知のB♭とEの新しいステップ間の三全音や減五度と同様に。これらすべてもまた、望ましくはない。 理論家らは、規則として、減八度+chromatic semitoneを禁止している。三全音と減五度もまた禁止されているのと同様に。 不完全なオクターブの禁止が理論の規則的な特徴となったのは16世紀だけであるが、それはずっと以前から行われていたようである。 当時、不完全オクターブが垂直音程で生じた時には、それは禁止されていた。 Glareanは、さらに、三全音と減五度は、「跳躍で使用されることはほとんどない」と述べ、減八度は「完全に回避されなければならない」と述べている。73 一方、これらのガフリウスの言葉が示すように、半音階の禁止は、一方では非常に強力であるが、ガフリウスの以下の言葉にもあるように、絶対的よりもやや少ないように見える。 ♭から Aaronもまた、Lucidario in musicaにおいて、 major semitoneは”自身で響くことはない”と宣言している。そして同書の他の部分で、以下の例を示す。 私たちはしばしば、作品において単一の行、あるいは単一のスペースに2つのbrevesやsemibrevesを書いた何人かの作曲家の誤った意見を検討しました。それらのあるものは♯化され、あるものはナチュラルに進行している。そして、これは、例が明らかに示すように、 square b ( この進行を含む例を次に示す(例2を参照)。アーロンは、対位法の規則に従って、cantus2番目のgを、カデンツの導音のように、♯化されねばならない、そして最初の音符はナチュラルのままである、さもなければ(ここが♯化されていれば)、テノールのcと非和声関係が生じる、説明している。77 これにより、望ましくないchromatic semitoneが生成される。それは、作曲家によって簡単に回避できたことだろう。もしもcantusの最初のbreveがaaであったならば。 p86 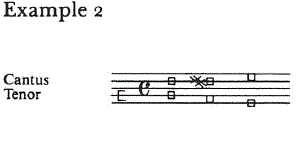 同じポイントは、RamosのMusica practicaの非常に類似した例で示されている。78 そして確かに、、ここで 半音階ステップの彼らの使用を批判された音楽家らが 、Marchetto da Padovaにまで遡ったことはあきらかである。 Lucidariumにおいて、Marchettoは、まさに同様の対位法的、カデンツ的進行によって、協和音程へと進行していく三度、六度のような不協和音程を半音化するために、全音を2つの半音に分割する2つの方法のうちの1つを例示した (see Example 3).。80  全音の2つの半音への分割は、べつの進行設定によって礼二されている。そしてここでもまた、Marchettoがこうした進行が完全にリスペクトされ得ると考えているという印象が持たれる(例4)。  Marchettus da Padova の場合、これら2つの例のセットには、2つの異なる半音のペアが含まれているが、これらの例を研究している当時のほとんどの音楽家らは、Marchettoがポリフォニック音楽の半音階の旋律的使用を許可していると正しく結論付けている。 そう。 p87 <permutatio> Inscribing medieval pedagogy: musica ficta in its texts p187参照 そして、確かに、chromatic semitone に対するMarchettus da Padova の寛容な態度は、彼が「permutation」の概念を説明するとき、再びはっきりと出くわす. Permutationとは、音符は譜表上同じ位置にあるが、音程が変化するソルミゼーションシラブルあるいは音符の名の変更のことである。permutatioとmutatioという用語は、実際には事実上同義語である。 これは、全音が分割される時に生じる。協和音程にとっては、diatonic semitone と enharmonic one [標準的な用語では、これらはそれぞれ chromatic と diatonic semitonesである]に、あるいはchromatic semitoneとdiesis ( #)(標準的な用語では、これらもまたそれぞれ chromatic と diatonic semitonesである)に。以下はその例である。  ここでもMarchettusが、メロディ的半音階的半音の使用を正当化するために、特定の対人対位法的理由を呼び出すことに注意されたい。 Marchetto and Zarlinoの間に、何人かの理論家が、半音階的半音の時折の可能性について言及している。常にその希少性を強調しながら。 たとえばHothbyは、複合的な半音階的な全音が、major and a minor semitoneを構成し、plainchantでは使用されず、ポリフォニーでも稀であることを我々に知らせている。83 そしてZarlinoは、半音階的半音について語っている。”この半音は全音階の属のメロディーの作成には使用されません。それにもかかわらず、作曲家らによって時々employされています。” 要するに、直接的な不完全なオクターブの禁則は絶対であり、その一方で、直接の半音階的半音は強力ではあるが、絶対というほどでもない。 その使用が対位法的規則によって正当化される場合、および、それが(上記のように)適切に全音を埋めるように解決される場合、それは導入される。ほとんどの場合は、全音階的半音によって、同じ方向に進んでいる。 理論家らは、間接的な不完全オクターブについては何も教えてくれない。おそらく、三全音や減五度と同じように、音符が介在すればするほど、それらをゲットするのはoffensiveになるのだろう。 一方我々、「間接的半音階的半音」とHothbyから呼ばれたものについて何かを学ぶ。彼は我々に、その他の理論家たちと同様、もしもFと p88 ゆえにこのケースにおいてもまた、半音階的半音を形成するFとの間に音符が介在すればするほど、後者はoffensiveになるのだろう。 先ほど説明した「新しい」非和声的関係(不完全なオクターブとその相応物)が、B♭を使用して非移調システムに導入され、BとFの間の「元の」非和声関係を修正し、対位法的、カデンツ的に動機付けされた♯によって生成されたchromatic semitonesであることを当面無視していることを思い出されたい。 これらの「新しい」関係を修正する必要があると仮定して、それらが修正される唯一の方法は、別のBbを使用することであることは事実上自明である。 その代わりにB 一方、一部の理論家らは、 減八度は、tritone and diminished fifthのように、フラットで修正する必要があると明確に述べている。 86 しかしこれは、内部のB♭の導入(B♭とE)によって産生された新しいtritones and diminished fifthsには当てはまらない。 この問題に関する興味深いコメントが、Domingo Marcos Duranによって提供されている。彼は、Eから Duranは、前者の選択が望ましいと指摘するが、一部の音楽家はしかし、別の方法で誤りを犯していると彼は指摘する。 Duranにおいては、 Duranの考察は、deuterus(第3,4旋法)での♭の比較的な希少性について我々が学んだこととそれらを結び付ければ、意味がある。すなわち、理論家によって議論された状況がほぼ生じて、旋法を完全に定義するE- 以下の結論は、Duranの議論から派生したものである。 まず第1に、FとBの非和声的関係の訂正は、B♭とEという、別の非和声的関係を生じさせるので、この問題の取り扱いは、「連鎖反応」の一種であるEの♭化によってでも、非和声的メロディ的関係を訂正するために1つの♭のみを使う通常の慣行の反対であるFの♯化でもない。 p89 第2に、おそらく、私たちはおそらく、そのような状況でBを♭化するかどうかの決定は、関係する音符の機能と相対的な構造上の重みに依存していた、と合法的に推測するかもしれない。もしもE-Bの関係が、F-Bの関係よりも構造的に重要であると理解された場合、Bは ナチュラルのままにされる可能性が高いし、逆もまたしかり、である。 この問題は、三全音を訂正しないでおくべきというPietro Aaronの状況についての議論で、さらに明らかにされている。これらの1つは、Fから 不完全五度は、それ自身が単独で生じると、三全音よりもエラーが少ない場合がある。明らかに、2つの中から選択する必要がある場合は、三全音を修正するよりも、完全五度を維持することが重要である。 アーロンの、問題を説明する3つの例では、五度は直接的なっていながら、三全音が段階的に満たされている。したがって、完全五度を好む彼のカテゴリー的な選択は、彼が歌うのがより困難な直接の非和声的音程を見つけたという事実からの結果である。 彼は言う。すなわち「歌手がb-mi acuteでfaを歌うと(すなわち、彼が♭で歌うと)、彼は、音符mi「E]の固有の音程に正しく下降できない」。89 我々はすでに、間接的な非和声的関係が直接的な関係よりも許容できると感じている多くの理論家を見つけた。デュランのように、アロンは、F-♭-E♭のような、1つの♭が次へ導いていく「連鎖反応」の可能性さえ考慮していない。 同様に、議論された問題をFのシャープ化によって処理することは、当時の理論家には起こらない。ゆえに、アロンのテキストは、私たちがDuranから導き出した最初の結論を、完全に 2番目の結論については、間接的な非和声的音程は直接的な音程よりも歌うのが簡単であるというアーロンの提案を含めるように充実させる必要がある。 両方の理論家から導き出された最初の結論は、つまり、FとBの間の非和声的関係の修正により、B♭とEの別の非和声的関係が生じるということであるが、四度あるいは五度離れたステップを含んでいる「連鎖反応」の一種である♭化したEには進まず、むしろ訂正なしの元の問題はそのまま残されていた。それは、明らかに、 Edward E. Lowinsky'の"secret chromatic art"の理論に基づいていた。この"secret chromatic art"は、16世紀のフランス^フランドル楽派のモテットに見出されるものである。Lowinskyによって公準となったその慣行は、”連鎖反応”の大規模な程度のものである。90 秘密社会や慣行を再建しようとする多くの試みのように、Lowinskyの理論は、は、原則的には、反証可能性のないものunfalsifiableである。 現存する理論的証拠が、五度の下降や四度の上昇の鎖に適用された暗黙の♭の使用をありそうもない慣行にすると指摘する懐疑論者に対して、信者は、16世紀初頭のいくつかの音楽実験において、そのような連鎖の存在を説得力をもって示すことによって、常に対応することができる。 p90 この点において、決定は、「'secretly chromatic' 」レパートリーの同様の実験的ステータスの妥当性の主張が見出されるかどうかをturn onすることだろう。 ただし、Lowinskyによって仮定された「連鎖反応」の存在は、音階の内容と調性システムに関する理論上のポイントを説明するために設計されたごく少数(おそらく2つ以下)の音楽実験で確実に示される可能性があることを強調する必要がある。しかしもしわれわれが当時の理論家たちを信じるなら、has no place in everyday musical practice. Lowinskyは、「連鎖反応」が通常の慣習であったことを示すために設計された音楽理論からの2つの例を示した、1つはNikolaus ListeniusのMusica of 1537 (see Example 6)92 であり、もう1つは、Matthaeus GreiterのElementale musicum iuventuti accommodum of 1544 からのものである(see Example 7)。 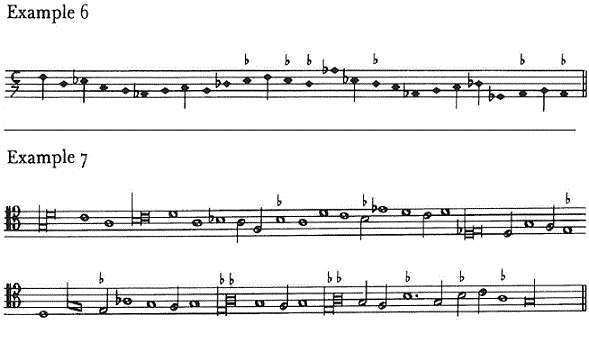 Listeniusの例は、彼が主張したように、「秘密の転調の技法の、明確で反駁できない証拠に相当するものを提供している」94。 同様に、Greiterの例は、“secret chromaticism"の原則を裏付け、1つの音符-「コードの音符」-上げる必要があるか、ほとんどの場合、♭化され、音程を含む一連の旋律と和声の進行を示す モチーフの移調によってしばしばサポートされる四度または五度のtranspositionは、作曲家が-臨時記号を記述することなく-転調の論理を強制し、その和声的で旋律的な進化を説得するために使用される。 Greiter's example‘corroborates the principle of “secret chromaticism" to the effect that,once one note -“the code note" -has been shown in need of being raised or,mostly,flattened,a chain of melodic and harmonic progressions involving the intervals of the fourth or fifth often supported by motif transposition is used by the composer to enforce -without writing the accidentals a modulation logical and convincing in its harmonic and melodic evolution'. 95 しかしこの例の解釈では、論文にある機能を無視している。ListeniusとGreiterの両者がmusica fictaの簡潔で非常に初歩的な解説を提供し、1つのcantus fictus、すなわち、見せかけのステップを使用するメロディのモノフォニーの例とともにそれを説明している。 このような例には、署名または内部にいくつかの臨時記号が含まれている必要がある。理論家が臨時記号を内部に配置し、そのような例のように、最も一般的な♭のinflectionsを使用することを選択した場合、彼が「'secret chromaticism'の技法を例示しているという印象を与えないようにする方法を想像することは困難である。 p91 一方、Duran and Aaronは、「連鎖反応」のフラットを導入する可能性を提供する音楽的文脈に直面したときに、音楽家らが実際に行ったことを教えてくれる。彼らの証拠は、定期的な実践の特徴としての「秘密の転調」に反対しているが、もちろん、時折の一般的な実験ではそれを除外していない。 上記の議論から、移調されていないシステムでは、ほとんどの旋律的非和声的関係がB♭によって修正されることになる。そして、調号とともに記譜されたメロディーでは、上記の非和声的関係とそれらを修正する方法はすべて定期的に移調されるため、旋律的音程を修正する場合、より一般的には、通常は常に「次のフラット」を使用することになる。つまり、もしも調号がなければB♭、B♭においてはE♭、B♭/E♭署名ではA♭となる。 さらに、これまでに議論された非和声的関係は、全音階的メロディーで発生する可能性がある唯一の関係であるということになる。他のすべての増および減した進行は、他のいくつかの(まだ開示されていない)理由で導入された内部的な臨時記号によるものでなければならない。そのような他の進行への言及は、理論的な文献では最もまれである。 我々はすでに,知っている。tetrardus(第7,8旋法)において、 Aaronは、この進行についての彼の議論の中で、望ましくない減四度が生じるために、 しかし、こうした言及は最も珍しい。 理論家によって定期的に議論されている唯一の非和声的なメロディの進行は、三全音、減五度、不完全八度となる。すなわち、これらは、全音階列において上昇し、あるいは、これらを修正するように設計された単一♭の導入から生じている。 したがって、メロディに沿っての臨時記号の使用に関する限り(そして、次の章で説明するように、メロディに沿ってだけでなく)、当時の理論家たちは、ほぼ独占的に すべての増減した音程から解放されたダイアトニズムを維持するのに役立つ使用法にのみ関心を持っている。 要するに、禁止された旋律の進行は、mi against faでソルミゼーションされた潜在的な完全音程を含んでいる。 mi contra faの表現ははるかに一般的であるが、垂直関係を議論する場合、次にこれらに向かわなければならない。 |