| Walter Frye and the Contenance Angloise4 |
| CHAPTER 6 The Masses of Frye Missa Flos regalis Missa Nobilis et pulchra Missa Summe Trinitati p125 Wa1ter Fryeのミサ曲はdiscantの原則に従って作曲されている。テノールとdiscantの間には、鋭い区別はない。 discantはほとんど装飾がないが。テノールはより長い音価ではじまるが、longが続くことは稀である。フレーズの終わりに向かって、そしてしばしば冒頭のすぐあとに、より活発化されるパターンは不変的である。旋律ラインはリズム的にシンプルであり、自由である。流麗なメリスマは、15世紀初期の大陸の作品の上声部を特徴づけている。 非和声的トーンは稀である。なぜなら、 discantにおけるそれぞれの音は、テノールとの関係で、和声的役割を担っているからである。 不協和音は、まれに現れるが、大部分の形式は繫留音であるが、一般的に Tinctorisによって作成され、さらに16世紀の理論家によって洗練された規則と互換性のある方法で、一貫して扱われている。
しかし多くの例において、不協和音の使用は偶然的で、コントロールされていない。不協和音についての理論的興味の不足は、フライの世代の英国の作曲家のほとんどすべてが、問題の実践的適用に明らかに無関係であることと一致する。 したがって、不協和音のパッセージは、Fryeの作品で起こる時には、16世紀よりもはるかに自由に扱われている。 3つのミサ曲は、様式的に似ているが、Missa Flos regalisは、他の2つNobilis et pulchraとSumme Trinitatiとは幾分異なっている。 Missa Flos regalisはまず4声であり、他の2つのミサ曲は3声である。 さらに、Flos regalisのcntntus firrmusは、他の2つのものがすべての有名なSarumの本の中に現れるのに対し、独特のソースから引き出されている。 p126 3つのミサ曲すべてがCREDOテキストの一部を省略しているが、2つの3声のミサ曲は“non erit finis" を含んでいる。Missa Flos regalisは、最後の「Et vitam venturi saeculi」を含んでいる。 Missa Flos regalisを区別するもう一つの点はAGNUS DEIで見られる。そこでは、ポリフォニーがすぐに始まるのだが、その他の2つのミサ曲では、最初の言葉はチャントになっている。 2つの3声ミサ曲は、テノールに対して書かれた2つのdiscanting voicesの技法を説明する。これらの声部のうちの1つは”contratenor”と呼ばれ、一般的には、この声部は、テノールと同じ音域を占めている。Missa Nobilis et pulchraでは、テノールとコントラテノールは互いに絶えず、交差をしている。 Summit Trinitatiのコントラテノールは、大部分がテノールの下に置かれているが、それにもかかわらず、かなり頻繁に、テノールよりも上に上がっている。テノールとdiscantは非常に稀にしか交差しない。したがって、2つの声部、テノールとコントラテノールコントラストは、ギメルを形成していると言われるかもしれない。 OH写本中のcantus firmus作品のギメルのようなサブ構造は、対位法の実践の直接の適用を表している。ギメルが2つの低声部の間で形成されることによって。 Bukofzerは、借用されたメロディーが中間声部であるMassesとモテットで、この特性を指摘している。 「こうして、OHのレパートリーは、英国のポリフォニーにおいて、gymelの重要な地位を強調している」と書いている。 1 それが英語のdiscantの不可欠な部分だったことは、Countertenorの議論に関連して、用語 "gemel"の使用によって見られる。 1Bukofzer Studies in Medieval and Renaissance Music p49 http://machikun.la.coocan.jp/bukofzer2.htm コントラテノールはテノールテナーの範囲を共有しているが、リズムに関しては、discantパートの方がより密接に結びついている。 どのパートもテノールよりもリズム的にアクティブでなければならないという事実は、一見、discant様式がテノールに対してnote-against -note の関係で依存するという基本的な考え方と矛盾しているように見える。 しかし、discantスタイルは、和音から和音までの単純な同時的動きを意味するものではない。 最も初期の形式のdiscantには次のものがあった。 両パートの正確な対応は、それぞれが、ひとつのordo、あるいは同じ数の音符に相当する同じ数の音符を含む。その時、第1または第2モードに対して第6モードが置き変えられ、そのために1つのlongaに対する1つのパートに2つのbreve がある。 言い換えれば、1つのordo、または2つのlongae内には、互いに、1つのパートに対する1つのパートの中に、いくつかの音符がある。理論的には、3つあり得る。実際には第6モードに対して第5のモードはめったに設定されていなかったが。さらに、少なくとも1250年以降は、テノールよりも活発な部分を持っているのがduplumの典型であった。 この同じ原則は、15世紀のイギリスのdiscantにも当てはまる。それは、和声額の進歩を意味するものではない。 discantの15世紀の理論から実際に続いていることは、テノールよりもdiscantに多くの音符がある場合には、plainsongと協和音程でなければならない、ということである。 Discant様式は、実際のメリスマ的上声部排除している。なぜなら、テノールに対する協和音程の数には限界があるからである。これらのすべての音程を描くことによって、作曲家はある程度、メロディラインを飾るかもしれない。 たとえば、テノールの音符は、1つまたは2つのbrevesに対して保持され、その間、discantingの声部は、(テノールに対して)三度から五度上へと移動する、あるいは六度からオクターブへと移動する。 したがって最上声部は、たとえdiscant様式内として、テノールよりも流麗であることができた。それがテノールと協和音程を保っている限りは。 これは、実際には、 Old Hall manuscriptの作品については正しい。しかし、重要なことは、コントラテノールが、テノールよりもリズム的により活発になっていることである。 英語の作品におけるdiscantとcontratenorパートの類似点は、理論の観点から容易に理解できる。カウンターテノールの理論的な説明は、この声部に対する英国の態度が、大陸とはかなり異なっていることを示している。 英語にとって、コントラテノールは、もう一つのdiscanting voiceであった。なぜなら、 “countir" とは、discantのmeneから外れて、逆さまになっている”からである。 p128 ゆえに、(英国においては)cantus firmus作品において、 コントラテノールは、テノールよりもdiscantの性格を帯びていた。大陸の作曲家の間では、コントラテノールは、テノールの役割を担っていた。 treble優位な様式が支配的であった15世紀初頭の大陸の作品では、テノールとコントラテノールは、和声的支持をするバスを共に結成し、流麗なメロディラインはむしろ休んでいた。 しかし英語の理論と音楽では、 "countering"声部は、もう一つのテノールとしての役割を果たすことはなかった。"countering"声部は、discantのさまざまなsightsから由来しており、そして、discanting voiceと同じ流儀において取り扱われた。Roy HenryのGLORIAのような、Old Hall 作品の多くで、コントラテノールがテノールよりもリズム的に活発化されているのは、おそらく、こうした理由のためである。 確かにそれは、常に旋律的な声部であるわけではないが、それは、テノールよりも滑らかな機能を可能にしているリズム的な活力を持っている。 一つの重要な点において、コントラテノールは他のdiscanting voiceとも異なる。 discantは通常、1つのsightに限られていたが、contratenorはsightsを変えて、テノールの上に上がるか下に下がることが許された。 したがって、コントラテノールは、他のdiscanting voicesと同じ一般的な規則に従うが、達成するためには、より包括的な機能を有する声部と解釈される可能性がある。コントラテノールは明らかに、テノールとdiscantの後に作曲され、それにを確認ように作られた声部であった。 countering voice は、2つの異なる技法によって特徴づけられる。より多くの典型的なものが、Frye のMassesからの多数のパッセージによって示されており、そこでは、コントラテノールは、和声をサポートする声部として働き、三和音を埋めている。それは他の2つの声にはない(三和音を構成する)音符であることを強いられているので、むしろ角張ったメロディラインを持っている。これは、フライの2つの3声ミサ曲で見られ、特に、以下のような例で見ることができる、 Missa Summe Trinilati GLORIA、mm。 20-30、mm。 156゜ff 、CREDO mm.'30-50; Missa Nobilis et pulchra GLORIA、mm 85ff、CREDO、mm 25-40、ACNUS DEI、mm. 1-15。 Missa Nobilis et pulchraから引用された最後のパッセージでは、コントラテノ―ルが、2小節分内に、1オクターブ+四度の音域があることに注意すべきである。この幅広い音域は、他の声部とは対照的な、コントラテノ―ルの特徴の1つであった。 p129 Pseudo-Chilstonによれば、コントラテノ―ルは、9つの音程“accords"を持ち(unison, third, fifth, sixth, eighth, tenth, twelfth, thirteenth, fifteenth.)、プレインソングを伴うユニゾンを加えて、4つがその上、4つがその下である。 6. Meech ,“Three Musical Treatises ,"pp. 260-61 http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye3-1.htm 5つの“accords"のみがオクターブ内にあり、discantの3つの規則的なsightsに属している7。 7. Meech ,“Three Musical Treatises ,"pp. 259 http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye3-1.htm Fryeの3声Massesのdiscantパートは、1つの音符だけでオクターブの範囲を超えているがそれはごくまれである。 (それは、discantがトニックの前の導音に降下するときに、カデンツ形式としばしば関連している)。4声のMissa Flos regalisのdiscantは10度に拡がるが、一般に音域は1オクターブ以内にとどまる。 フライの3声ミサ曲のコントラテノ―ルは、時にはdiscantのように、よりメロディックな声部としても機能する。 一般に、コントラテノ―ルとテノールの関係は、反行となっている。しかし、時にはコントラテノ―ルは、discant と平行進行となり、その間、テノールは比較的静かな動きになっていることがある。(例えば、Missa Nobilis et pulchraGLORIA、mm. 212-13、CREDO、mm. 110-13、「Osanna 1」、95-98、および「Osanna II」mm. 198-99・)。 このタイプのパッセージでは、和声進行は非常に制限されており、voice-leadingの結果から、常に同じ進行となる。テノールは真ん中にあり、2つの外側の声部の間での対比は10度であり、discant はテノールより上の六度から五度、三度までの範囲となり、コントラテノ―ルはテノールより下の五度から六度へ、そしてオクターブへと動く。(Example 5)  p130 これに似たパッセージは、15世紀半ばの英刻作品では非常に頻繁に発生し、フランドルの作曲家のスタイルに大きな影響を与えた。 それらは、シャンソン技法との関連でより詳細に議論されることだろう。 フライの4声のMissa Flos regalisでは、コントラテノ―ルの2つの主要な機能(discant的機能とバス的機能)は、ある程度は2つの声部に割り当てられているが、一方では「バス」と呼ばれ、一方では「contratenor」と呼ばれている。 バス声部は、デュエットの音を除いて、通常、コントラテノールの低音機能を維持し、四度、五度、八度の跳躍的な動きをする。 contratenorは、真のdiscanting声部の性質をより多く持っている。 この分業は必ずしも不変的に維持されているわけではない。 コントラテノ―ルは、和声構成に不可欠なあらゆる音符を取っていって、単純に声部を満たすようにもしているが、一般的には、バスよりもよりメロディ的性質を持っている。 discant の旋律的なスタイルは、声部の相互依存のために、必然的に幾分制限されている。純粋に装飾的なメロディ形象は完全に欠けており、それぞれの声部は、均一なリズムを維持している。音価の変化は比較的小さい。これらの制限のうち、テノールとの関係は、明確に定義された特性を明らかにする。個々のメロディーラインは、Example 6のように、時に完全に文字通りの繰り返しになる。フレーズは、いくつかの流儀で変化することがよくある。  Example 7では、contratenorのフレーズは正確に繰り返されるが、繰り返しの効果は、テノールパートのあまり重要ではない旋律とリズム的な変化によって不明瞭になる。  p131 このタイプの工夫は、スタイル全体の特徴である。最も頻繁に起こるのは、正確な流れやメロディーの繰り返しはないが、メロディーが常に1つの高い音または1つの音域の周りをめぐっている流れであり、それは、短期間に何度も繰り返される(Example 8)。  p132 フライの配列法は、ほとんど同じ手順に従う。時には、そ(のリズム)れは正確かつ、文字通りとなる。例9の両声部のように。 時にはそれはメロディー的に正確であるが、タクトが毎回違う点にリズム的にずれている(例10)。 しかし、より典型的なものは、メロディーが正確ではない配列である。例11の両方の抜粋において、図の第1のテーマは、第2および第3のものとは1つの間隔で異なる。  p133 例12では、第1の提示のリズム公式は保持されているが、メロディーラインはさらにずれる。 純粋にリズム的な配列は、最も特徴的なものである(例13)。 次の抜粋(例14)では配列技法は、4つの声部書法に適用され、そのうち3つの声部にはリズム配列がある。テノールとバスは同じパターンをしているが、いわゆるリズム的カノンと呼ばれるものである。その間、discantは、全く異なる形象を持っている。 contratenorだけが自由となっている。 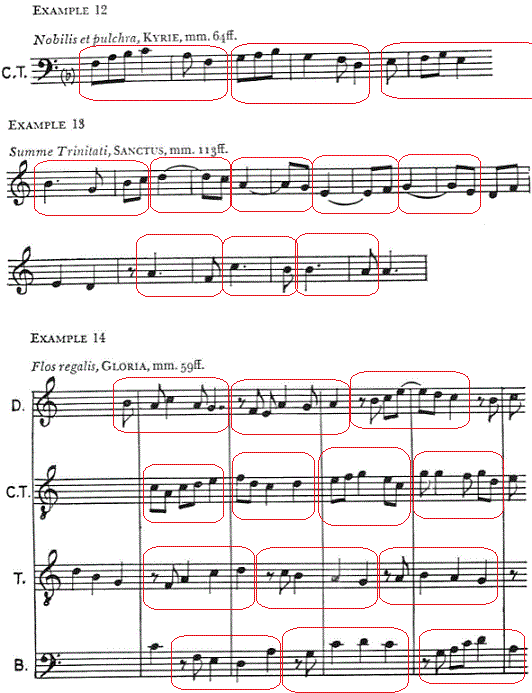 p134 これは、discant様式のまさにその限界が最も大きな利点になるような形式である。なぜなら、 音楽的効果を強化する矛盾したリズム・スキームの中で、すべての声部を互いに照らし合わせて設定することになるからである。 同様に、2つのパートが絡み合っているパッセージでは、効果的なリズム的なクロスアクセントに大きく依存している(例15)。 ハーモニーは静的であり、メロディーは同じ調子の音がつながるする点まで繰り返しているが、そのような交差や再交差、そして同時的な終止の忌避によって遂行された興味深い効果がある。 様式の特徴的な純粋な反復の形であるオスティナートでさえ、暗黙の規則性が決して適用されないように利用されている。 例16では、コントラテノ―ルが、オスティナート形象を持っている。 その上に、discantは、contratenorの形象に似せ、全体的にあたかも交差するように設定されたメロディーを持っている。  p135 Frye のMassesのすべての声部の範囲は、コントラテノ―ルを除いて、1オクターブまたは理論的には1sightに制限されている。ほとんどの場合、声部は、中間ではむしろあいまいな方面を追求するが、時にはFryeは、実際の旋律の振れ幅を抑える証拠を示している。メロディーが1オクターブを超えて直接的に上がったり下ったりする場所がいくつかある。しかし、そのようなパッセージは比較的まれであり、オクターブの跳躍を使用することによって、一般的に、より高い音域へのシフトが達成され、その後オクターブ内でメロディーラインが元に戻る。フライの作品ではほとんど型通りであるオクターブの跳躍は、同じ作品でほぼ常に現れ、1minimの給付後のオフビートに入って出現する。(例17)。 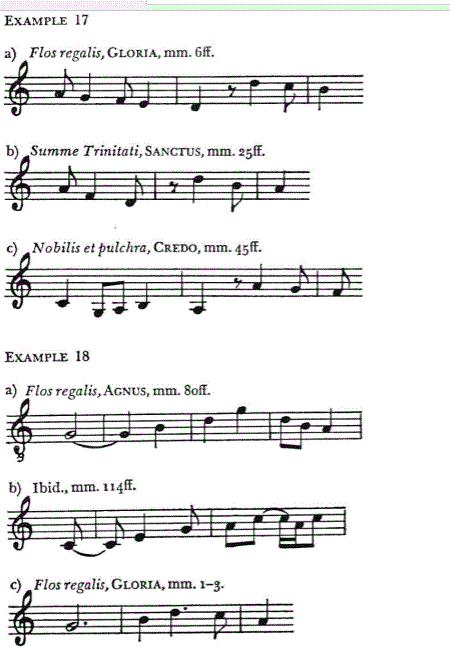 多くの英国のメロディーの三和音形式は、あまりにも頻繁に議論されて、ここでの多くは語れないが、フライの作品には、これらのフレーズが豊富にある(例18)。Missa Flos regalisの4つの楽章のすべてがモットー冒頭となっている。このタイプのメロディー公式は、ほぼ不可避的に、discantの実践からの結果となっている。なぜなら、discanting voiceは、さまざまな三和音の音符を使うことによって、持続的に、協和音程とテノールとの関係を維持することができるからである。たとえ、ほぼリズム的に活動していても。 p136 フライのミサ曲は、すべて循環ミサ形式で作られている。通常文の楽章は、テノールのcantus firmusを通してだけでなく、discantパートにしばしば生じるメロディ公式の意味合いによって、密接に統一されている。3つの全部のミサは、discantと同じくらいより低い声部を含むモットー冒頭を持っている。 2つのMasses、Flos regalisとSumme Trinitati は、最初の2つまたは3つの小節がモットーを構成する導入デュオで始まる。 Mlissa Nobilis et pulchraでは、すべての3つの声部が2つの小節のフレーズですぐに入ってきて、それは後続楽章の4つのすべてで繰り返されている。 モットー冒頭に対する厳格な固執は、特に15世紀の英国のミサ曲の特徴ではない。例えば、レオネル・パワーのMissa Alma redemptorisでは、モットーはACNUS DEIにはまったく現れず、他の楽章ではかなり変化している。同様に、おそらく英国起源のMissa Fuit homo missusのミサにおいては、モットーは最初のプレゼンテーションから大きく外れている。 しかし、一貫性してフライは、モットー使っていたかもしれないが、彼は3つのミサ曲のそれぞれに異なるリズムスキームを採用した。 Missa Summa Trinitatiは、全体的に、tempus imperfectum(2表紙)で書かれている。他の2つのミサ曲は、2拍子と3拍子の交互で書かれている。 Nobilis et pulchraのそれぞれの楽章は、tempus perfectumから始まり、中間部の不完全な部分への変化、そしてtempus perfectumの短い、一般的にリズミカルに活性化されたセクションを持つ。終止部位は、tempus perfectum(3拍子)である。 Missa Flos regalisは、楽章ごとに2つの部分に分割され、tempus perfectumで始まり、imperfectumで終始している。 このタイプのメロディーな公式は、ほぼリズム的に活動しているにも関わらず、トライアドの様々な音符を使用することによって、韻文の練習からほとんど必然的に、韻律の練習から生じる。トライアドの様々な音符を使用することによって、韻文の練習からほとんど必然的に、韻律の練習から生じる。 すべての3つのミサ曲では、cantus firmusとして機能する典礼チャントは、最初の楽章では無彩色で現れ、後続の楽章を通して、不変的にメロディ的なままである。 p137 2つの英国の循環ミサ曲、Mass Alma redemptoris materとMass Rex saeculorumについての関係において、両者ともに、堅く、かつ自由なcantus firmus の扱いが、非常に初期のころに戻り、両者の形式は、cantus firmus ミサ曲作曲の時代を通して続いたことが指摘されている。 Fryeは、彼のモテットSospilali deditにおいて、テノールのメロディーを自由に彩色したが、ミサ曲の作曲のためには、非装飾的形式を好んだように見える。 Missa Nobilis et pulchraでは、テノールは、各楽章の1つのセクションの音楽テクスチャから外されている。 これは一般的な手順であった。 しかし、いくつかのセクションは、テノールは続けられても、チャントの旋律をなくしている。 そのような2つのセクションは、1箇所の改変だけを有するACNUS DEIを除いて、5つのすべての楽章において正確に、同じポイントで、テノールメロディーの流れを中断している。 最初の楽章(Kyrie)では、 "Christe"の始まりと "Kyrie II"の始まりで、GLORIAでは "Domine Deus、Agnus Dei"と "Qui sedes"で、 CREDOでは「Et incarnatus est」と「Et ascendit」、SANCTUSでは「Gloria tua」と「Benedictus」、 そしてACNUS DEIでは、「Miserere nobis」にある。 これらのセクションはすべて、テノールとdiscantのデュオである "Benedictus"を除いて、テノールとコントラテノールのデュオで構成されている。 フライのMissa Nobilis et pulchraの顕著な特徴の1つは、KYRIEの長さである。次の楽章のための基本的な構造を確立しているこの楽章は、すべての楽章の中で最も長いものである。 KYRIEは232小節の長さです。 GLORIA230;CREDO220;Sanctus、215; AGNUS DEI、163。 フランドル地方の作曲家では、KYRIEは一般にGLORIAやCREDOよりもはるかに短く、通常はSANCTUSも同様である。長いKYRIESは、トロープス化されたテキストのため、英語のMass設定の特徴であった。例えば、Missa Fuit homo missus※では、KYRIE、GLORIA、CREDOは全く同じ長さで67小節である。 KYRIEは、英国の作曲家によっては全くポリフォニックに設定されていなかったが、KYRIEが含まれていたときには、ほとんどいつもトロープス化されていた。 Richard Cockx のMissa Sine nomine of BR 5557(BrusBR 5557)は、KYRIE にtrope Deus C'reatorを持ち、 Pseudo-Binchois のMassはトロープスOmnipotens paterを持ち、両者とも比較的長いKYRIESを持っている。 ※This is the anonymous English Fuit homo missus Mass, for the Nativity of St John the Baptist, celebrated on June 24th. St John's Nativity was celebrated six months before Christmas to emphasise his role as the precursor to Christ. This fine polyphonic setting takes chant setting the words 'Fuit homo missus a Deo, cui nomen Joannes erat' - there was a man sent from God whose name was John. The chant is sung in the Tenor which provides a structural scaffold for the whole Mass, which follows a macro-structure linking the Kyrie-Gloria-Credo and Sanctus-Agnus as structurally paired movements(Agnus Dei - Fuit homo missus Massより). p138 <KYRIE;Missa Nobilis et pulchra> 構造の観点からすれば、KYRIEはFryeのMissa Nobilis et pulchraの中では最も興味深い楽章である。 この楽章の分析から、音楽家を扱っているさまざまな構造的な工夫が、それらのどれもがぶつからないように注意深くお互いに設定されている。 完全に明確な正式な概要は、3部構造のKYRIEのテキストによって提供されている。このミサ曲にあるトロープス、Deus creatorは長いものであり、「Kyrie Eleyson」と「Christe Eleyson」のそれぞれのエクスクラメーションに対する完全な4行スタンザを持っている。 したがって、テキストは9つのstanzasに細分される。 3つの "Kyrie 1、3つは「キリスト」、3つは「Kyrie 1I」である。フライは、境界線がすべて隠されるように、このテキストを明確な区分で設定している。 3部のリズム構造で、 (tempus perfectum-imperfectum-perfectum) となっている。それはテキストの主要な分割とは一致していない。 Tempus imperfectum は、5番目のスタンザ、すなわち2番目の "Christe"に導入されている。tempus perfectumへの復帰は、9番目の最後のスタン、Kyrie IIの最後の "Kyrie"でのみ行われる。 Fryeは、プレインソングを3つのセクションに分けたが、挿入された音楽的なトロープスによって、対象があいまいになり、基本的に5声部のメロディーになった。 テキストのStanzas 1と2にはチャントの最初の部分がある。 スタンザ3はテノールを持たない。 スタンザ4は最初の音楽的なトロープスを持っている。 スタンザ5と6はチャントの2番目の断片を持っている。 スタンザ7は第2の音楽的なトロープスを、スタンザ8と9はチャントの第3の断片を含んでいる。 声部のグループ化さえも "Kyrie-Christe-Kyrie"のテキスト区切りを最小限にするように扱われている。最初の "Kyrie"はdiscantとcontratenorのデュエットで終了し、 "Christe"はcontratenorとテノールのデュオから始まる。「Kyrie 1」と「Christe」の間にはフル・カデンツがあるが、「Christe」と「Kyrie II」の間には明快なカデンツはない。なぜなら、「Christe」は、discantとテノールのデュオで終わり、その後のテノールとコントラテノ―ルのデュオは、最初のデュオからのスピンアウトだけだからである。 p139 コントラテノ―ルは、discantを置き換えて入ってきて、テノールは、discantが "Eleyson"の最後の音節でfinal longaを終わらする前から、新しいテキストを始めている。いずれの場合でも、主要なテキストセクションの終わりに合唱団のすべてのリソースが使われていない。 テキストそのものは手の込んだものであり、 "Kyrie"と "Christe"という言葉がスタンザの初めから省略さえされていたトロープス化の本来の目的からは程遠い。それぞれのスタンザの末尾にある "Eleyson" という言葉だけが、通常文のこの楽章の正式な構造を描写するのに役立つ。 まとめ。このKYRIEは、トロープス化されたテキストと音楽的にトロープス化されたcantus firmusによって支配されている。しかし、楽章の3部構造は、チャントやカデンツ、リズムスキーム、声部のグループ化を通して、あいまいになっている。 こうした様々な要素の関係は、以下のダイアグラムで示される。tempus perfectumはOで、tempus imperfectumはCで示される。テノールパートでは、cantus firmusは線で、自由な挿入は点線で示されている。縦線はカデンツを示す。 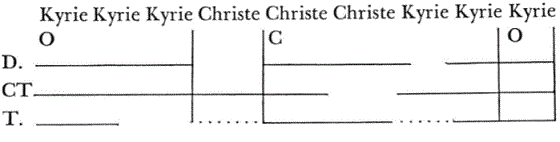 ほとんどのパートでは、KYRIEにおいて確立されたパターンは、ミサの4つの楽章の中で維持されている。テノールとコントラストの自由なデュエットは、対応するポイントで発生している。 しかし、KVRIEのような3部構造であるAGNUS DEIが、他の楽章よりも、元のスキームをより逸脱しているのは不思議である。 最初の楽章(Kyrie)では、テノールは "Kyrie 1"の1つのスタンザからのみ省略されているが、最後の楽章(Agnus Dei)では、テノールは、第2 "Agnus"全体から欠けている。 Tempus imperfectumは、第3"Agnus Dei"でのみ導入され、tempus perfectumへの復帰は最後の "Dona nobis pacem"で行われている。 p140 3拍子から2拍子への変化の明らかな順不同性は、この時期のほかの英国のミサ曲においてもみられる。 Oliver Strunkは、PowerのMissa Alma redemptorisについての彼の見解で、「Agnus Dei II」の中間部において、こうした変化が起こっていることに注目している。 Missa Alma redemptoris では、「Agnus 1II」は、Tempus imperfectumで始まり、Frye's MassのAGNUS DEIと同様に、「Dona nobis」でperfectumに戻る。.BR 5557のRicquardus Cockxのミサ曲は、 KYRIEとAGNUS DEIにおけるtempusの変化の誤った配置を示している。それは奇妙である。なぜなら、AGNUS DEI以外のそれぞれの楽章は、少なくとも、短いtempus perfectumのセクションで終止しているからである。しかし、最後の楽章では、Cockxは第3”Agnus"でtempus imperfectumを導入し、ミサの終わりで3拍子に戻ることはなかった。 FryeのMissa Nobilis et pulchraのためのcantus firmus としての役割を果たしているplainsong Responsoryは、メロディー的には無色であり、ポリフォニーミサのテノールのリズムや構成は全く恣意的であるが、チャントの元のフレージングは反映していない。 むろん、Nobilis et pulchraのテキストは、ミサ曲設定でのテノールによって歌われる意図ではなかったので、テキストによって決定されたフレーズを遵守する理由は無かった。 フライのテノールには、通常文のテキストが全面的に、デュエットに入っている。それがデュオとして、あるいはフレーズインチピットで扱われている時には。フライがチャント・メロディーの元のフレーズを無視することは、自由な挿入の配置において特に顕著である。 これらのうちの1つは、Responsoryのテキスト中の“ gaudia" という言葉の最後のシラブル上に書かれたメリスマの冒頭に現れている。この挿入は、 "Kyrie II." の最初のスタンザへのテノールパート全体を構成している。第2スタンザとともに、plainsongは、テノール声部に、挿入が生じた点で再び現れ、melismaは続けられ、 "mundi"という単語で終止する。このメリスマは、"Kyrie II." の第2節全体へのcantus firmus をもたらし、自由な挿入は、代替のメリスマのように見える。 p141 Dufay、Ockeghem、Obrechtの3つのCaput Massesによって、これと似た手法が実証されている。 Otto Gombosiは、これらの作曲家が、しばしば、色のつかないメロディーラインを保持していても、彼らが、前のフレーズの終止音としての1フレーズを最初の音を使用することによって、そして休符によって2つのフレーズを区切ることによって、それを歪めたことを指摘している。 Gombosiは、これらの工夫がDufayによって生まれたものであるかどうか、あるいは彼が英国作品の中でそれらを観察したかどうか、という疑問を提起した。 類似の形式の工夫、類似のメトリック・ライフが当時の英国の音楽で知られていたかどうか、当該の英国の作曲家のいずれかがそのような手順に貢献したものとして選別されたかどうかを確認することは、将来の研究者のの仕事として残るであろう。 フライの作品から判断すると、これらの工夫は、当時の英国音楽でも知られていた。おそらく、そのような実践をすべて帰することができる単一の作曲家はいなかったであろう。しかし、Fryeが公式な要素を扱うことが、Dufayやその後のフランドルの作曲家が深く負っていた英国の作曲家のグループと彼とを同一視していることは間違いない。 彼のMissa Nobilis et pulchraのKYRIEを詳細に分析することで、リズム的で公式な側面を設定することによって公式な輪郭を隠すことに対するFryeの傾向が示されている。KYRIEとAGNUS DEIの間の対称構造を立てる機会があっても、 Fryeは慎重にそれを避けたことが示されている。 これらの点で、フライは、15世紀初期の大陸の音楽の音楽的美学の支配から全く異なる姿勢を取っていることを明らかにしている。対称的なフレーズ、バランスの取れた周期的構造、および15世紀初期の音楽の頻繁なカデンツはすべて放棄されている。 フライのMissa Nobilis et pulchraに関連して議論された構造的および様式的特徴の多くは、彼の他の2つのMassesの特徴でもあり、それぞれについて詳細に記述する必要はない。 しかし、特別な考慮が要求されるそれぞれのミサ曲に特殊な点もある。 p142 <Missa Summe Trinilali> Missa Summe Trinilaliは、主にcantus firmus素材の取り扱いで区別される。。 KYRIEは存在しないので、チャントの配置はGLORIAで最初に定式化される。 GLORIAとCREDOの両方は、完全に色合いがなく、両方の楽章で同じリズム構成を持つ、完全なcantus firmus を持っている。SANCTUSも AGNUS DEI も、メロディーは完全には現れず、しかし一方から省略されたパートが他方には現れる。このように、いくつかの重複を伴って、cantus firmus 全体は、2つの楽章によって一緒に提示される。 SANCTUSでは、 "Pleni sunt"と "Benedictus"の間にテノールがあり、この時点から続いたテノールメロディの部分は省略されている。最後の楽章では、テノールは第2"Agnus ,"全体でなくなり、チャントに相当する部分は欠けている。 "Pleni sunt"と "Benedictus"から省略されたチャントのセクションは、第1、第3 "Agnus"によって供給され、 それは"Agnus II"から削除されたものは、SANCTUSの "Osnna" において現れる。。 cantus firmus の異なる断片を別の楽章に割り当てるこのテクニックは、同じテノールの使用によってミサ全体を統一する考えに直接対抗している。テノールのメロディーが単純に配分された場合、4つの楽章の関係は、本当にむしろ希薄になる。しかし、このフライのミサ曲においては、最後の2つの楽章が最初の2つのものと結びついているので、楽章はより緊密に結びついている。 Nobilis et pulchraのそれとは異なり、MissaSumme Trinitatiのテノールは、自由な部分を持たない。それは常にcantus firmusの素材に縛られている。 長時間の休符は、このミサ曲のテノールの部分だけで起こり、テノールを含むデュエットはほとんどない。 この点でも、MissaSumme Trinitatiは、テノールが時々休みとなるその他のミサ曲とは異なっている。 MissaSumme Trinitatiの cantus firmus は、匿名のモテットSalve Virgo mater (Trent 240)のcantus firmus と同一であるために、ミサ曲とモテットの間の関係に、疑問を投げかける。その同一視をしたBukofzerは、モテットが4つのミサ曲楽章のモットー冒頭を共有していることを指摘している。 p143 ミサ曲とモテットが近代的な "パロディー"の定義に入るかどうかにかかわらず、同じメロディーのリズムの定式化と同じモットー冒頭での使用は、それらの間の密接なつながりを示している。 トレント写本中の別のミサ曲、Le Rougeの Missa Soyez aprantiz(Nos。1031-35)は、2つのモテットとともにcantus firmus を共有している。ミサ曲は明らかに、フライのシャンソンSo ys emprentid のテノール上に書かれているが、そのシャンソンは、トレント写本において、contrafactum(替え歌) , Sancta Maria succurre (Nos. 990 and 1029)として見られ、加えて、同じテノールを持つモテットStella coeli extirpavitがある。 第2章で述べたように、これらはすべて、英国人作曲家によるポリフォニーの聖母マリアのアンティフォンである。それは、彼らが設定していた以外のテキストに属するcantus firmiを頻繁に使用していたが、おそらく、それはランダムな選択ではなかった。 毎日のマリア儀式は確かに、他の儀式の祭典にも影響を及ぼし、聖母モテットは、cantus firmiの選択を誤ったように見せているので、説明は特定のミサ曲と関連しているかもしれない。 同じcantus firmusを共有していたmotetsとMassesが、同じ特定のサービスを意図していたことが考えられる。英国人は、想定されていたよりも典礼的な妥当性についてより強い感覚を持っていたのかもしれない。 Benedicamus Domino が、特定のチャントのメリスマから頻繁に引き出されていたという Frank Harrison's の発見は、英国の典礼音楽がきわめて緊密に統一されていることを示唆している。13 そして、聖母モテットのためのcantus firmiの選択は、同じ理想によって動機付けられたかもしれない。 13. Music in Medieval Britain , pp. 74-76 http://machikun.la.coocan.jp/medievalbritain21.htm 2つのミサ曲、Nobilis et pulchra、とSumme Trinitatiは、Bukofzerが "イソリズム的"と呼んでいるものであり、すなわち最初の楽章におけるチャントのリズムの定式化は残りの楽章には不変なのである。 この点において、Missa Flos regalisはやや別物である。なぜなら、そのリズム構成は、楽章から楽章へと変化しているからである。 テノールの最初のセクションは、SANCTUSと "Agnus Dei 1"において、基本的に同じデザインが与えられているが、この類似性から離れて、チャントの取り扱いは全く自由である。 フレーズは異なる点で壊され、リズム的な形象は置き換えられている。 p144 ここでは、フライの他の2つのミサ曲のように、メロディーは明らかに色合いがない。 元のチャントが不明なので、メロディーが飾られていないことを確かめることは不可能であるが、ミサ曲のテノールは、色がつくことがない典礼チャントの出現を持ち、4つの楽章すべてにおいてメロディ変化なしで繰り返される。 cantus firmus は、Flos regalisのGLORIAとCREDOで完結しているが、SANCTUSとACNUS DEIのどちらからも省略されている。 このMassでは、それは、テノールが(Pleni suntとAgnus IIの間で)休んでいる時に、最後の2つの楽章で欠けているのと同じ断片である。 残されたセクションは、現代のtranscriptionにおける17小節で構成されており、最後の2つの楽章のどこでも説明されていないが、その欠落は、芸術的にはあまり問題にならない。なぜなら、このセクションが非常に似ているチャントには、多くの繰り返しモチーフがあるからである。たとえば最初の4小節は、チャント・メロディの直前のフレーズの2つの音符を除き、繰り返している。 Missa Flos regalisのある楽章から別の楽章へのdiscantパートには、テーマの類似性が非常に多い。最上声部でのメロディー素材の反復は、cantus firmusが欠けているセクションでは、特に興味深い。 例えば、 "Pleni sunt"では、SANCTUSにも "Agnus Dei I."にも見られるdiscantのいくつかのパッセージがある。 さらに、「Pleni sunt」からの1つのフレーズが、テノールが欠落している「Agnus Dei II」で順次処理されて再び現れる。 したがって、これらの2つのセクションはcantus firmusによっては連結されず、discantのメロディ素材によって連結されている。 (「Pleni sunt」、51-54頁とSANCTUS、14-17頁、ACNUS DEI、14-16頁、「Pleni sunt」mm。59-60とACNUS DEI、mm55-57とを比較せよ)。 voice grouping では、Fryeは一定のバリエーションを採用している。 2つのMasses、Summe Trinitati、Flos regalisには、すべての楽章のための導入デュオがある。 「Benedictus」や「Agnus Dei II」など、一部のセクション全体では、2声部しか設定されていない。 しかし、このようなデュオの使い方を超えて、Fryeは頻繁に音楽のテクスチャを2パートに減らしている。 Missa Summe Trinitatiでは、これはほとんど常にテノールをなしにすることによって行われるが、GLORIAの冒頭に向かって8小節分のdiscantとテノールがあr。 フライのミサ曲技法の最も特徴的なことは、様々な組合せによって形成されたデュオの非定型的な交代である。たとえば、 Missa Nobilis et pulchraでは、discantとcontratenorのデュオはcontratenorとtenorへ、あるいはdiscantとtenorはdiscantとcontratenorに置き換えられている。 4声のMissa Flos regalis ではもちろん、voice grouping の可能性がはるかに広いが、ミサ曲全体では、3声部分はただひとつのパッセージのみであり、大部分は、様々な組み合わせのデュオと4声のフル合唱である。テノールが休止すると、他の3声は、デュエットの連続を形成するために交替する。 すべての4つの楽章は、discantとコントラテノ―ルの導入デュオで始まり、ディスカウントとバスが続く。 GLORIAでは、 "Qui tollis"でのdiscantとbassのデュエットは、コントラテノ―ルとバスのそれで置き換えられる。それはまた変わって、discantとcontratenorの組み合わせになる。 この声部の交替によってもたらされる音域のシフトによって、著名なコントラストが意図されていることはめったにない。多くの場合、第2の声部同士のペアは、最初のペアからほとんど無自覚に現れる。 両方のデュエットには、共通の声部が常に1つある。なぜなら、Missa Flos regalisのテノールはデュオに参加していないからである。リズム的流れは鋭く壊れていることは稀であり、停止する直前の先の部分のうちの1つを置き換える第3の声部が先行することにより、しばしば影響が生じる。これは、例えば、CREDOの "Et incarnatus"で見ることができる。そこでは、低音が2つのbrevesに対してdiscantとcontratenorに参加し、contantenorとbassが続き、discantがドロップアウトする。 "Pleni sunt"はほぼ完全にdiscantとバスのデュエットで構成されている。最後の13小節だけが、ミサ曲全体での1箇所の3声部を構成するためのコントラテノ―ルを含んでいる。 Walter Fryeのこの4声ミサ曲は、とりわけ、世紀中頃の英国の作曲家のための二重唱技法の重要性を強調している。 3声のミサ曲では、テノールまたは任意の声部の省略は自動的にデュエットになる。 しかし、(4声作品では)テノールが4声テクスチャから取り除かれても、トリオとして残る。トリオはほとんど使用されず、故意にデュオの連続に分解される。 p146 このデュオ様式は、discantの実践と関連しているように思われる。 1つの声部を別の声部に置き換えた2パート書法の観点から、discantは教えられてきた。それは、どのパートにも適用できるが、様式は、2声作品に対してもっとも効果的である。 フライのメロディ書法が、discant理論における協和音程の暗示の理解を基にしていることが以前から指摘されていた。 より無目的なメロディーライン、配列技法、フレーズ内の1つまたは2つの音符の先取、テノールとコントラテノールのギメルのような関係はすべて、テノールへのdiscanting voicesのnote-against-note の関係から生じるスタイルの特徴である。 デュエット様式の育成は、Flos regalisのような4声のミサ曲の中でさえも、discantの理想が、15世紀の最も偉大な音楽形式の1つにおける表現を見つけるようになった程度についての等しく重要な指標である。 |