| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC4-01 |
| 2. ANALYSIS OF THE MUSIC p99 Fountains fragment の音楽は、5つの見出しの下で便宜的に議論されるだろう。 最初の4つは、ミサ曲に関連している。 (1)conductus様式 (2) 世俗的な歌の自由なtreble様式 (3)イタリアのデュエット様式 (4)イソリズムモテット様式で構成されたミサ曲 (5) イソリズムモテット特性 <(1)conductus様式> 最初で最大のグループ(1)はスコア記譜法で、SanctusとAgnusシリーズを含む。そして、それらは例外なく典礼的cantus firmiに基づいており、最大限に単純な様式で書かれている。 それらはOHの古い層の最も単純でおそらく最も初期の設定に対応している。 顕著な様式的保守主義は、写本の提案された日付に対する追加の議論 を提供する。 プレインソングは、breves and semibrevesにおいて、非常に平易に”和声化”され、minims が、自由な声部の中にあちこちに現れる。特にカデンツにおいて、リズム的単調さをなくすために。 p100 ある種の作品、例えば、Sanctus 第8番は、brevesとsemibreves で進行し、連結符が文字通りcantus firmus に移されている典礼旋律に非常に固執している。cantus firmus は通常、堅実なbrevesが使われている。 この種の非常に典型的な例については、読者は、Agnus No. 12 (= OH No.122 OH III,108)に言及するかもしれない。ここで最も外側の声部は、厳密に進行するプレインソングに対抗して動き、多くの平行五度や平行三全音さえ伴う非常に古風な”対位法”を供与する。平行三全音は、筆記者のエラーではない。それらは、両ソースにおいて同じ流儀で現れる。 響きのために、声部の1つは、同時に歌われなければならない追加の黒色音符によって、時には2つに分けられる。そして、1つの声部に、少なくとも2人の演奏者を要求する。しかし、追加はしばしば、 Sanctus No. 7,あるいは Gloria No. 3のように別の声部ですでに音符が二重になっており、そこでは、分割が最後に生じる。OHとLoMの類似の慣例は、時折見られる。 LoFと同様にOHに現れる作品は、必ずしも、臨時記号において、リズム的詳細、パート書法、さらには長さでさえも必ずしも一致はしない。 臨時記号の使用に関する一般的な規則を述べることはできない。 OH 97がLoF 9(Vol. III、20および[76])と比較される場合に見られるように、時には臨時記号は,LoFにおいて、より多数である。 逆に、OH 122(III. 108)の冒頭小節におけるg♯は、LoF 12には見られない。さらに、複写の問題で中世の書記の怠惰を示すいくつかのリズムの変異がある。 最大の違いは、Agnus No. 14の2つの変異の間に存在する。OHにおいて、2つのinvocationsだけが完全に書き出され、3番目のAgnusは最初のAgnusの後に歌われる。 LoFでは、3つinvocationsすべてが完全に書かれている。最初のinvocationはOHのそれと一致している。いくつかのリズム変異を除いて。他の2つのinvocationsはどちらも、OHの2番目のinvocationに関連しているが、詳細にはかなりの違いがある。 不思議なことに、OHの2番目のinvocationと最もよく一致するのはLo Fの3番目のAgnusのそれである。それぞれの設定は、両方ともtempus perfectusで書かれており、いくつかの小節で同じ音楽を持っているが、時々偏位がある。 p101 ミサ曲の様式的な保守主義は、 cantus firmusの扱いもまた、conductus様式において拡大している。OHでは、プレインソングは、大部分が中間声部に現れるが、時々は、世俗的な歌のスタイルでパラフレーズされて、上声部に出てくる。 後者の手順(プレインソングが上声部にくる)は、英国でますます好まれるようになった。そのために、15世紀半ばくらいまでに、状況は実践的に逆転した。このことは、Meaux Abbey MSによって示されており、そこでは、 cantus firmusが最も頻繁にtrebleに配置されている。 LoFでは、cantus firmus は決して上声部には現れないが、中央部全体に、gymel のように、あるいはmigrant cantus firmus のように、中声部とテノール声部とにおいて交互に現れることになる。 このように、LoFでは、cantus-firmus の扱いに関しては、英国の伝統に準拠している。 migrant cantus firmus の出現は、このテクニックが英国音楽にどれだけ広く採用されているかを示している。 次の表では、conductus 様式の9つのミサ曲が、それらのプレインソングの扱いとソースについて分析されている。 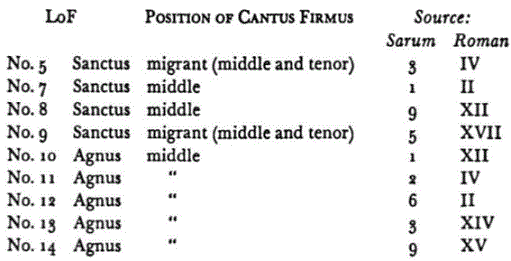 バチカン版の番号は、オリエンテーションのためだけにここに追加された。 LoFのプレインソングは常にSarumの使用に従い、Graduale Sarisburienseの後にここに番号が付けられている。 他のSarum bookは同じ順序や同じ数のプレインソングを供与していない。もちろん、チャントがポリフォニーに設定されていたわけではない。ポリフォニック音楽の写本は、選択されたプレインソングの設定を提示し、典礼の機会に従ってそれらをアレンジしている。 写本の元の順序を確実に表すLoFのAgnus の順番は、Sarum1で始まり、2 6 3と続いていく。OHの対応する順番が1 2 3 6であることは、偶然の一致ではないかもしれない。しかし、チャントの典礼的指定は決して不変ではなかった。 p102 Graduale Sarisburienseは、それぞれfestis majoribus duplicibusとfestis minoribus duplicibusとして、同じプレインソングを分類している。 我々の分析表は、7つの作品において、チャントが中間声部にあることを示している。 migrant cantus firmus は2作にある。そしてこれらの作品においても、それはテノール声部にmigrantする前には、中間の声部として始まっている。 (migrantではなく)1つの声部に固定されているcantus firmus の設定は、しばしば声部の交差を伴っている、そしてそれは時々チャントを最低声部とする。 このような交差は、即興的なdiscantに関するいくつかの論文で言及されているが、これらでは常に、チャントが基本的な声部であると想定されている。 LoFとOHのconductusミサ曲は、実際の即興演奏に対しては、おそらく、非常に単純である。cantus firmusの位置、そして特にmigrant cantus firmus は記譜を必要としているが、それでも即興演奏への近しさはそのリズム的な単純さにおいて、明白に現れている。 Sanctus no.5は、その最初の部分は以下の例1で示されている通りであるが、チャントはメロディの装飾なしで存在しているために、migrant cantus firmus の非常にはっきりとしたideaを我々に供与する。 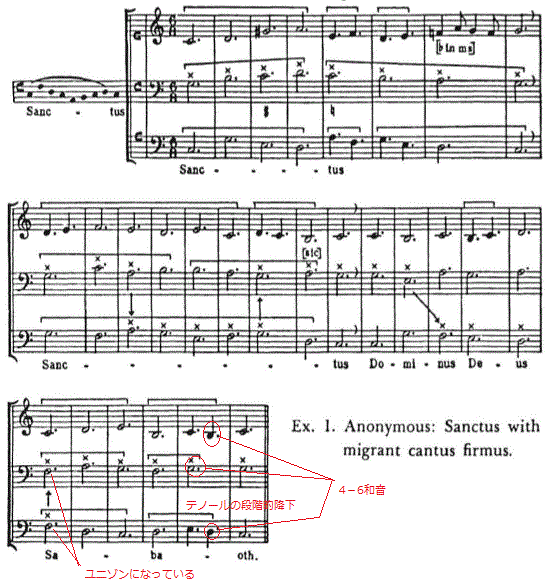 p103 譜例の最後のカデンツは、経過音で4-6和音を認めているので、コメントが必要である。OHでもLoFと同様に、このような終止は、cantus firmus が中声部にあり、繰り返し音で終わる設定において、まったく一般的である。ここでは、テノールの終止への段階的な降下は、その他のどのようなカデンツも除外する。 migrant cantus firmus の扱いに関しては、小さいが重要な細部に注意を払う必要がある。これは容易に見逃しがちである。 作曲家は、チャントの音符を、特別な注意を払って散布している。 cantus firmus がある声部から別の声部に交差するたびに、2声部は、その以降がはっきりとスムーズに聞こえるように、ユニゾンを含むようになっている。ただし、Dominusのパッセージは例外であるが。作品の残りの部分でも、すべての交差はこのようにして行われる。 文字通り「極めて重要」と呼ぶことができる点でのユニゾンの一貫した使用は、これまで全く正確な類似点が発見されていなかったmigrant cantus firmus への非常に慎重な、そして意識的なアプローチを表している。 チャントが連結されて作曲されなければならないことは、当時の追加的なやり方にはもはや従わないことは、言うまでもない。LoF 9やOH 96(III、18)に見られるように、その他の migrant cantus firmusを伴う作品は、“unison-crossings ,"を散発的にしか使用していない。 後者の作品OH 96(III、18Sanctus, Marie filius (Sanctus)) No.100 fol. 84Old Hall Manuscript 各論その1参照)は、prolatio maiorでtranscriptionされるべきなのだが、、LoF No.5との明らかな比較に役立つ。どちらの作品もmigrant 様式で同じプレインソングを扱っているが、結果は、同じ様式の限界内で、どれだけ広い範囲の可能性があるのかを私たちに理解させるのに十分なほどに、異なっている。 conductusミサ曲の和声は、正統ではない進行で組み合わされることがあるフルトライアドの頻繁な使用によって特徴付けられる。 LoF No.10の奇妙な半音階的開始は、OH 128、IIl(125 No.136(Fol. 105v))およびLoF 9(III、20 No.101 fol. 84v, Sanctus (Sanctus)) p20)と比較されるべきである。 これらのパッセージは、当時、和音思考の主要な構成要素の中にあった、音響と半音効果に対する高度に発達した感覚を示している。 プレインチャントのオリジナルな旋法が、和声進行に対してどのように直接的に対峙していたかを観察する必要がある。”旋法”と”和声”の間の齟齬は、実際には、もっとも吸収されたconductus設定の音楽的な特徴なのである。(訳注;conductusによって、両者の違いがわかりにくくなった、ということ) p104 それでは、作品の最初のグループはそのままにして、プレインソングの異形の問題を提起しなければならない。 LoFのcantus firmiがSarumの変異と一致することはすでに述べられている。これは、驚くべきことである。なぜなら、ファウンテンズ修道院はシトー派儀礼、つまりは修道院の儀礼を遵守していたのであり、それはSalisburyと Yorkの監督管区の儀礼とは異なっていたからである。 後者の間の音楽的違いは未だ検討されていない。そしてここで問題に加えられることができるのは、当面の素材に必然的に制限されることである。 チャントad usem Eboracensemは、現在Bodleian Library (MS lat. lit. b 8) にある、15世紀初頭のYork Gradual から収集できる。これはFrereによれば、その種の唯一の包括的な音楽的ソースである。 写本は、Yorkの変異がSarumとRomanのバージョンの間の中間的な立場をとり、時には前者と一致し、時々後者と一致することを示している。そして時には独自のやり方を取る。 Sarum useのある種の特殊性は、ヨークには見られない。ヨークの聖歌がLoFの音楽に影響を与えているかどうかを調べるために、LoFのプレインソングを、York Gradualのバージョン(fols .88 -90)と比較した。 結果は常に同じである。SarumとYorkの間に不一致があるときはいつでも、Sarum version はポリフォニー設定となっている。 LoF No.7の場合、証拠は紛れもない。このSanctusのローマとヨークのバージョンは実質的に同じであるが、cantus firmus は明確に、Sarum variantを採用している。 その一方で、シトー派とSarum uses については、英国起源のシトー派のGradualを特定できなかったので、何とも言い難い。しかし、その意味は我々の議論にとっては重要ではない。なぜなら、現在Stonyhurst Collegeにある英国起源のシトー派のmissalは、我々に、シトー派が少なくとも、オプションとしては、Sarum useを認めたことを我々に知らせてしめているからである。 写本は、序唱Prefacesのいくつかを記録しており、secuncum usum Sarumの銘記がその最後にある。 p105 これは、Cisterciansがイギリスのプレインソングの伝統をどのように考慮に入れたかを示す興味深い兆候である Fountains fragment は、ミサ曲の聖歌についてもその点を確認している。 この情報がなければ、写本の中の Sarum chants の存在が、この作品がFountains Abbey起源であったことを証明すると、容易に結論づけてしまったことだろう。この(この作品がFountains Abbey起源であったという)仮定は成り立たないことがわかった。 しかし、反対のことを主張することもできる。オリジンの場所は定かではないが、多くのcorrespondencesの観点から、それはOHのそれと同じであるかもしれない。いずれにせよ、ミサ曲の設定がSarumチャントを詳述しているという事実は、明らかに、Fountains Abbeyの歌手の妨げにはなっていない。 <(2) 世俗的な歌の自由なtreble様式> 第2のタイプの作品、自由なtreble様式のミサ曲は、Gloria No2でのみ代表され、それはOHではローランドに帰せられている。この作曲家ついては、何も知られていない。 このタイプによくあるが、作品はtrebleに言葉が置かれており、頻繁な旋律的な衝突と活発でかなり角張ったリズムで、2つの支持パートに対抗している。それらは、著者がOHの世代よりも古い世代の作曲家に属していたことを示唆している。 この作品は、シンコペーションされた不協和音に富むhocketセクションや、agimus tibi のセクションがさまざまなテキストを含む何らかの種類のda capoとして最後に戻ってくるという事実(それは、このタイプのミサ曲ではむしろ例外的である)のために、注目に値する。 <(3)イタリアのデュエット様式> 4声のグロリア16番(= 4番)は,3番目のグループに属している。このタイプでは、2つの上声部が声楽のデュエット、素早いdeclamationと頻繁な模倣を形成し、より持続的な2声またはそれ以上の楽器パートの伴奏に対抗している。 この様式は特に、イタリアのモテットと世紀の変わり目のミサ曲で発展した。フランスではそれほどではないが、OHのレパートリーが証明するように、英国の音楽家によって引き継がれた。 グロリア第16番のデュエットは、、リズム的模倣のほんの少しだけを除き、ほとんど模倣的ではない。そして、OHの4声部曲のように、多くの不協和音的なappoggiaturasが含まれている。声部はほとんど休符なしで続けられ、そして声部の交互の組み合わせでの試みはなされない。これは、イタリアの作品の特徴である。 断片的なLofのグロリアNo.6もまた、現存する声部の素早いdeclamationや、保存されているその旋法によれば、明らかに、この第3グループに入るだろう。 p106 それは、続くSanctusで取り上げられたfolioの残りとともに、右ページにある。その他の声部は、今は失われてしまった左側に記録されていた。そして、通常は、versoは最も高い声で始まるので、失われたsuperiusと現存する声部が、1つか2つの声部によって支えられた声楽デュエットを形成したと推測されるだろう。 <(4)イソリズムモテット様式で構成されたミサ曲> イソリズムミサ曲は、最初のカテゴリーに次ぐ、No.1、3、15からなる最大のグループを構成している。ここでもまた、OHのレパートリーとの密接な類似性があることがわかるが、イソリズムのテクニックは、これまで一般的に見られていたよりもはるかに共通的である。 序章のカノンと、TENOR内でのcancrizansの進行を規定する言葉の"canon"を伴なう厳格な4声のCredo Lo F No.15は、OHの作品との関連ですでに議論されており、ここで我々が関与する必要はない。 他の2つのミサ曲は、どちらもかなり拡張された作品であり、イソリズム原則についての修正が、注目に値する。 グロリアNo.1(プレート2を参照)は tenor とcontratenor の上にあり、どちらもテキストはなく、どちらもイソリズム的である。テノールの旋律的なデザインはグレゴリオ聖歌起源を示唆しているが、テキストによる指定がなく、メロディの識別は、進行する上でのの他の証拠がなければ、絶望的な作業になるでしあろう。幸いなことに、現在見られるように、この場合にいくつかのヒントが発見できる。 この曲のイソリズム構造は以下のように分析することができる。一組の下の声部は、それぞれ14小節づつの3つのtaleaeで構成されている。それぞれは1回のみ記譜されるが、2回分を表すことになる。つまり、taleaeは半分の音価で(それぞれ7つの小節で構成されている)、2回分存在する。1回分しか書かれていないが。though notated only once , must be stated twice ;after that the taleae are stated twice in halved values (comprising now seven measures each) , though they are written again only once. 全体のミサ曲設定は4つのcolores(それぞれ3つのtaleae)を含み、そのうちの最初の2つは次の2つに対して2:1になる。diminutionは作品を不均一な長さで2つの部分に分ける。上声部は、下声部の構造と部分的に一致し、部分的に重なり合う独自の構造を持っている。 Superiusとaltoは、テキストのあるセクションとないセクションが一貫して交互になっているという奇妙なデュエットを形成している。作品の最初の部では、テキストを含むセクションは自由に作曲されているが、テキストのない(メリスマ的または器楽用?)セクションはtaleaeと一致するイソリズムパターンを観察する。それ故、各声部は、交互セクションにおいてのみイソリズム的であるが、組み合わせにおいては、それらは厳密なイソリズム構造ではなくなる。 テノールのdiminutionに始まり、すべての声部は全体を通してイソリズム的であり、上声部の対における3つのイソリズム的な部分が下の声部の2つのcoloresと重なるというさらなる複雑さを伴う。 p107 イソリズムパターンを2つの声部に交互に分配するという奇妙な考えは、私の知る限りでは唯一の類似、すなわちOHのPennardによる4声のクレド(II、241 No.89 Credo(fol. 76v-77, Credo (Pennard)))だけである。 この作品は、2つの部に分けられる。非常に個性的なイソリズムテクニックの扱いを考えると、両作品は、共通の主題や旋律の特徴を持っていなくても、同じ作者によって書かれたと仮定する企てに駆られる。 (LoFの方の作品が)Pennardへの帰属が非常にか細い証拠に頼るであろうことは本当であるが、それでもその考えはもう少し追求されるのに十分に興味をそそるものである。 作者不明のGloriaがPennardによるものであれば、イソリズム手法の類似性以外にも何らかの関係があるはずである。直接的な音楽的類似性が存在しなくても、少なくとも典礼的なつながりがあるかもしれない。 PennardのCredoは、Trinity antiphon Te iure laudant(Ant。Sar。、293)に基づいている( OldHall Manuscript 各論その4参照)。そして、この(Lofの)グロリアが、(Pennardの)Credoと同じ祝祭のために作曲されたかもしれないと考える。 (Pennardの)Credoのアンティフォンが記録されているAntiphonalの場所に目を向けると、(Lofのこの)Gloriaのテノールのメロディーが、そのまったく同じFolioに表示されていることを発見できた。 このチャント、アンティフォンO beata et benedictaのversusは、単語Tibi laus、tibi gloria、tibi gratiarum actioを持ち、(Lofの)このグロリアで最初から最後まで引用されている。 PennardのCredoも、イソリズム的作品の慣習のように、単なる断片ではなく、根底にあるアンチフォン全体を述べていることは重要である。 さらに、Antiphonalとcantus firmusに記録されているチャント間の一致は非常に正確で、同じ旋法の別のプレインソングが使われたという可能性は、事実上除外された。最初の非常に暫定的なアイデアは、Pennardへの帰属を予想外に支持しているため、2つの作品は同じ作曲家によって (in festo Trinitatis)書かれたと考えられるかもしれない。 p108 Gloria No. 3は、同様に、イソリズム技法のかなり独特の変化を示している。それは、6つの音符からなる短いテノール、a g f g a gに基づいており、それは、14世紀の典型的なイギリスのモテットの典型的な方法であるostinato あるいは pes で、9回使われている。 6つの音符は、3つの音符とそれぞれ6小節からなる2つのtaleaeを形成しており、全体として18のtaleaeと9つのcoloresがある。基礎となる構造は、イソリズム手順へのpes の独特の同化として説明することができる。 この(pes とイソリズムの)興味深い組み合わせは、特にイギリスのテクニックを大陸の慣習に適応させたことから生まれた中世の音楽の多くのハイブリッド形式のうちの1つである。 contratenorは記譜されているのではなく、単に「規範」 hic tenor est arsis and contra sit tibi thesisによって暗示されている。このややあいまいな指示の意味は、作品のtranscriptionを通して明らかにすることができる。contratenorは、五度下のテノールの厳密なメロディの反転である。つまり、"arsis" は “thesis"となり、逆もまたしかり、である。 フォリオの右下隅にはもともといくつかの音符が含まれていて、それらは後で消去されてしまったが、不完全なものとして、それらのうちのいくつかはまだかすかに見えている。これらは、 contratenorの解決案として同定できる。実行可能なパッセージでは普通のことであるが、メロディがどのように進むべきかがすでにわかっている場合にのみ、reading が確実になる。 The unorthodox placement of the resolution on the side of the folio indicates that somebody must have written out the puzzle and that he or a later user must have thought better of it and erased it again so as to make the other singers use not only their throats but also their heads . 暗示されたcontratenorとは別に、グロリアは、写本でde se と記された別のものを要求する。このcontratenor は、その指示が主張するように、”テノールからの独立”なのである。それは、24小節から成り、custosあるいは繰り返しの「直接」の指示で終わる。 この声部は、テキストがなく、5回なければならず、最後の繰り返しは最後までに短くされる。それぞれの colorは、それぞれ6小節の4つのtaleaと重なり、対照的なペアとなって、a a' b b' :||となる独特の配置を取る。 最後に、trebleは、テキストを伴う唯一の声部であるが、それぞれが36小節の3つのイソリズム周期(最後の3小節は短い)に分けられる。結果は、3つの異なるレベルでの非常に複雑なオーバーラップとなる。trebleの1周期は独立したcontratenorの6つのtaleaeと1つ半のcoloresに対応し、そして低声部の6つのtaleaeと3つのcoloresに対応する。こうした配置は、イソリズム周期の分割にまたがる独立したcontratenorの一対のtaleaeによって、さらに複雑になる。 p109 pesを含むすべての作品において、和音は必然的に制限されているので、 Gloriaは3つの和音の間を飛び回る(だけである)。 それにもかかわらず作曲家は、制限内でかなりの多様性を達成した。 trebleは、イソリズムのリターンと一致するいくつかのイソメリックまたはそれに非常に近いパッセージを含んでいる。 Brit . Mus. Cotton MS Tiberius A VII. fol. 38 vの断片的なGloriaは、それが様式的には同じレパートリーに属しているので、isorhythmic massの議論をカットするかもしれない。将来、完全な版 が登場するかもしれないことを願って、incipitは、 残念ながらこれは一部しか判読できないのだが、ここで供与される(例2)。 写本では、どちらの声部も不完全である。 (略) p110 <(5) イソリズムモテット特性> 作品の5番目で最後のグループでは、我々はミサ曲を離れて、適切なイソリズムのモテットに目を向けたい。 LoF No.17と18の両方がこのカテゴリに分類される。 No.17の Humane lingua は、かなり短いpolytextualモテットで、高音域の活気のあるデュエットは、遅いテンポの一対のテキストのない楽器パートと対照的である。上声部の中にいくつかのhocket 書法があり、和声は、当時の多くの英国の作品のように、よく響くフルトライアドへの偏愛を示している。それは、三度がしばしば上声部にきらびやかに位置しているのである。 TENORはメロディ的に精巧な説明なしに、Sarumの Deo gratiasの全旋律を引用している。そしてこれに関連して、モテットの2つのテキストが、gratiasという言葉に近いことを示している。英国の中世の音楽の中を赤い糸のように走っている昔ながらの伝統の伝統は、ここでも明らかに証明されている。 奇妙なことに、TENORは、写本中において、その正当な指定を欠いている。代替の声部だけが、solus tenor et cantetur de [?] Deo gratiasと刻まれている。 二つのテノールのうちのsolus tenorは、プレインソングを産出しないものである。なぜなら、それは、tenorとcontratenorの必須音を新しい行にまとめたもので、3声に減じられたパフォーマンスをすることになるためである。誤った指定は、基礎的および代替声部の機能についての無理解をさらけ出している。 同様の無理解のさらけ出しは、イソリズム反復の記譜にもある。 モテットの2つのイソリズム周期は、それぞれ2回分を表し、diminution by threeで繰り返される、tenor と contratenor の2つのtaleaeと一致する。 Gloria No. 1でもそうであったように、筆記者は、減ぜられた音符の音値を減らした繰り返しを、まったく不必要に、書いている。どちらの場合でも、OHや当時の他の多くの写本と同じように、変化した計量記譜記号で短く明瞭に示すのがはるかに簡単であっただろう。 p111 イソリズムモテットの経験豊かな歌手にとって、オリジナルの記譜からTENORの様々なdiminutionsを使うことは、簡単なルーチンの問題であった。 LoFの筆記者は、変更のための特別なサインの場合のように、過度に用心深さを示している。 。 彼の態度は、LoFが、イソリズム的手順についての知識が当然のこととはされていなかった地方の雰囲気に起因していることを示唆している。 次のモテットAlme pater は、superius と tenor だけが現存している。その構造は単純である。すなわち、上声部の3つのイソリズム的周期は、テノールの3つのtaleaeに対応している。coloresはない。テノールメロディは、最後まで続いている。そのメロディは、七度のように、頻繁に跳躍をする。プレインソング起源であることは、否定されている。 さらにまた、テノールは、モテットテキストの最初の単語だけを持っている。そしてこの指定方法は通常、特別に作曲されたメロディーを示唆している。写本には休符はないが、テノールは12小節目で入ってくる。導入は、イソリズムスキームとは別に存在している。そのような導入デュエットは珍しくなく、Credo No. 15(OH III [68])にあるように、しばしばカノン的であった。 ここでもカノンを試して、失われた上声部が部分的に再構築されることができるかどうかを見ることは差し迫ったことだろう。確かに、現存する声部は、イソリズムセクションの始めまでスムーズにカノンを書くのに役立つ。カノン音声のエントリは、主題カタログにsignum congruentiae カノン的な導入とテノールのリズムデザインに暗示されている2番目の上声部の存在は、モテットが4声部作品であることに疑いの余地を残さない。 上記のコメントは、散在しているが、小さな断片から驚くほど大量の補足的な情報と新しい情報の両方を抽出することが可能である方法を示したであろう。 調査の方法は、保存された最初の旋法、順序、そして写本のレパートリー、様式、そこにある作品の構造を調べることであった。 これらの調査結果は、より大きなレパートリーの観点から見なければならない。そしてそれを統合することによって初めて、それらは意味を持つようになる。 LoFがOHを補完することはすでに知られている。しかし、綿密な調査の結果、作品の様式、 cantus.firmusの扱い、およびイソリズム的手順に関する広範な類似性が明らかになった。 p112 LoFは断片的作品を完成させるだけでなく、OHにその優れた特徴の1つを供与する一連の conductus Masses を拡げている。 OHは今度は、1つの作品の著者を論じ、そしてその他の作品への暗示を示唆している。 OHは、強い大陸の影響やイタリアのレパートリー(Zacharia's Gloria、OH 30)の直接の影響さえ証明している。 LoFでは、同じ影響は、イソリズム的な作品とイタリア風の作品の専売特許であるが、それらの和声と一般的な「音の地方なまり」は、それらがおそらく英国起源であることを示唆している。この推論は、 FountainsフラグメントがYorkで編纂された可能性のある地方主義のヒントによって支えられている。 こうした結論に達するためには、細かく分析して、明らかに無意味にでも詳細なものにすることが時々必要であったが、しかしあまりにも細かい針仕事の外観を持ち、そして、細部のしたり顔の列挙は、より大きな内容において、高められた重要性を仮定し、自身のより大きな内容を交互に反映する。 |