| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC4-1 |
| Holy WeekMusic and Carols at Meaux Abbey ��11�R 1. THE MEAUX ABBEY MANUSCRIPT ��X��15���I�̉p���̉��y�̒m���́A�ŋ߁A�Q�̎ʖ{�̔����ɂ��A�L���ɂȂ����B1�̓C�^���A�\�h�C�c�N���ł���A�����ЂƂ́A�p���N���ł���B�����́A0ld Hal! MS�̔����ȗ��̗ǂ��m��ꂽ�p���̃\�[�X�ւ̂����Ƃ��d�v���{���I�ȕt�����琬���Ă���B �ŏ��̕��́AAosta MS (Ao�j1�́A15���I�̑O���̑嗤�̉��y�̃R���N�V���������^���Ă���B�p���̍�i�͂قƂ�ǔr������Ă����B�p���̍�i���ʂɋL�^����Ă�����́AAo�������ЂƂ̑嗤�̃\�[�XMS lat. 471 of the Biblioteca Estense in Modena�Ƌ��ʂ��Ď����Ă���A���ڂ��ׂ������ł���B�����̓��e�̔z��ɂ����āA�Q�̎ʖ{�́A15���I�̌ŗL�̉p���y�h�̑��݂�F�߂Ă��邱�ƂɂȂ�B 1 'De Van�C�gA Recently DiscoveredSource of Ear1y Fifteenth-Century Polyphonic Music�Cthe Aosta MS�C" in Musica DisciPlina II ('948).5�E ��114 �@2�Ԗڂ̃R���N�V�����́A���̌����̑Ώۂł���AEgerton MS3307 of the British Museum�ł���B2 Gloria laus (imperfect at beginning) (Nos. 1-2) En rex venit(Nos. 3) Gloria laus (Nos. 4) Unus autem (Nos. 5) St. Matthew passion (imperfect at end) (Nos. 6) Mass (imperfect at beginning) (Nos. 7a-7d) St. Luke passion (Nos. 8) O redemptor (Nos. 9) Inventor rutili (Nos. 10) Rex sanctorum (Nos. 11) Alleluya: confitemini (Nos. 12) Salve festa dies(Nos. 13,13a) Crucifixum in carne (Nos. 14) Alleluya: Laudate pueri -(Nos. 15) Dicant nunc Judei -(Nos. 16) Alleluya: Salve virgo (Nos. 17) Audivi: Media nocte [2] -(Nos. 18�C9) O potores exquisiti (No. 51) Cantemus Domino(Nos. 52-53). 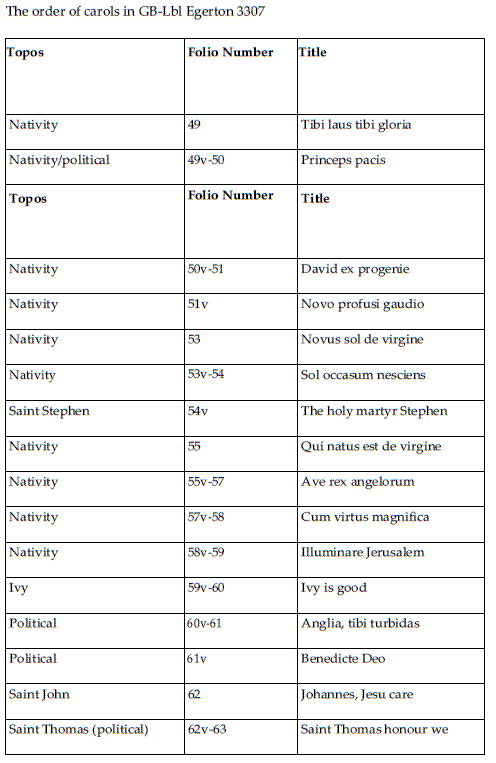 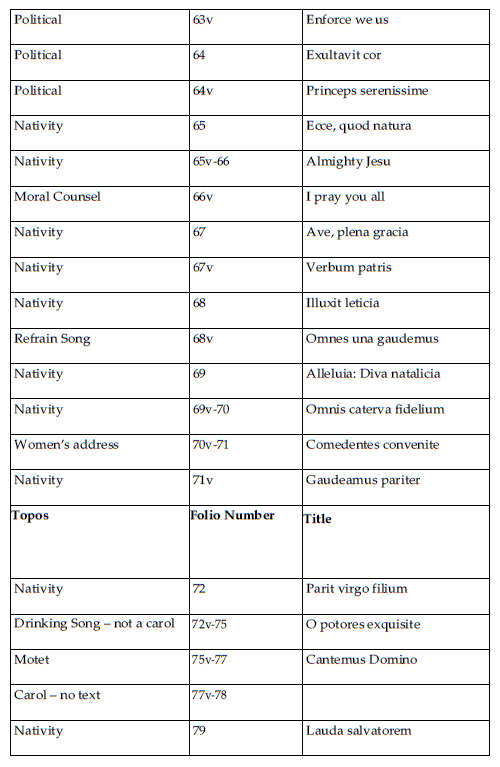 2�@Schofield (Part 1) and Bukofzer (Part 11)�C�gA Newly Discovered 15th-Century MS of the English Chapel Royal�C" in MQ XXXII (1946)�C5 09 and XXXIII (1947)�C38 . Part 1 contains a general descriptionand a thematic catalogue. Part II transcriptions of the Missa Brevis and the St. Luke Passion.The works will be cited here according to the thematic list�Cthough the numbering�Cas will be seenbelow is�C not alway. accurate. Egerton MS3307 of the British Museum�́A�����Ƃ���K�͂������[���p���N���̎ʖ{�ł���B���̋N���ɂ��ẮA��v�͌��Ă��Ȃ��BSchofield�́ASt. George's Chapel in Windsor�ō��ꂽ�A�Ƃ��Ă���B�Ȃ��Ȃ炱�̎ʖ{�́ASt. George���L�O��������ȃX�^���U�����q��Salve festa dies���܂�ł��邩��ł���B �������A����́A St. George���A�ʖ{�����ꂽ�ꏊ�ŋL�O���ꂽ���Ƃ��ؖ����邪�A�K�������AWindsor Chapel�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��BRichard L. Green�ɂ�錤���́A�p��̃L�������̕������AYork�ł��邱�Ƃ������Ă���B�ނ͂���ɁA�h�����L���������AMeaux Abbey in Yorkshire�ɑ����Ă���Hye (Hyth)���Ɍ��y���Ă��邱�Ƃ������B����̓V�g�[��̏C���@�ŁA���w��|�p�ɑ��鉇���Œm���Ă���A�ʖ{�����ꂽ�ꏊ�Ƃ��ẮA���蓾��̂ł���B�R���N�V�����͂���䂦�AMeaux Abbey MS (LoM)�ƌĂ�Ă���B Egerton�̋N���ɂ��Ă̓��_�͂܂��͂�����Ƃ������_�ɓ��B���Ă��Ȃ��B2�̎傽����n�́A�AMeaux Abbey in Yorkshire��St George�fs Chapel in Windsor�ł���B�@�������A���I�L�������ł���Ivy is Good���܂���쓌�C�݂�Hythe�n��Ƃ̊֘A����������Ă���B���̍Ō��verse�ɂ����āA���̒����Î�����whye�x�̖��O���܂߂Ă���iMcPeek�A1963:12�j�Bhttp://machikun.la.coocan.jp/egerton.htm �@Ao�̓��e�Ƃ͑ΏƓI�ɁALoM�́A�Q�̕�������Ȃ�B�ŏ��̕��́A���ꂳ�ꂽ�T��̃��p�[�g���[�ł���A�p���N���ł������A�c�O�Ȃ���A���ׂč�ҕs�ڂł���BAo���~�T�̒ʏ핶�ɏW�����Ă���̂ɑ��āALoM�̓T�畔���́A���T�̗�q�ɓ������Ă���B 2�Ԗڂ́A�܂������ʂ́A���Ɛ����L��������cantilenas���܂�ł���B���y����e�Ɋւ��āALoM�́A��蓝��͂���Ă��邪�A���n���I�ȃ\�[�X�ł���B�Ȃ��Ȃ�AAo�̉��y�̌|�p���x���ɂ͏�ɓ��B���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�n��I�Ɍ��肳�ꂽ���p�[�g���[�ɓ��ʂȗ��Q�W�����邩��ł���B �@�ʖ{�͂����炭�A�w�����[�U���̎����A���悻1450�N���ɏ����ꂽ�B����́ASelden MS(OS)�Ɠ�����ł���B��҂̓��e����Â����BLoM��OS�̓��[�h�L���@�Ƃ̊֘A������B���҂Ƃ��A���ׂč��F�L���@�ŏ�����Ă���A�Ƃ�����Ԃ┒�F��������B���҂Ƃ��ASarum�̍s��ɂ��Ă̓T���i���܂�ł���A����ƕ���ŁA�L��������cantilenas���܂܂�Ă���B ��115 �������Ȃ���A�����́A���y�z��ɂ����ẮA�قȂ��Ă���BOS�̓T���i����Ƃ��ă}���A�̃A���e�B�t�H������\������Ă���i�L�������ƃ����_���ɍ������Ă���j�̂ɑ��āALoM�̔z��́A���T�ɑ����A���炩�ɁA��T��I�Ȃ��̂Ƃ͈�����悵�Ă����B LoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)�́A��蒍�Ӑ[���v�悳��A��菇���������R���N�V�����ł���B����́A�T��I�ȖړI�i��1���j�ƃL�������`���ɂ���ē������ꂳ��Ă���A�X�R�A�L���@�̎g�p�ɂ���āA�O���I�Ɍ`������Ă���B�X�R�A�L���@�́AOS�ɂ������邪�A����قǑ����͂Ȃ��B �@LoM�iEgerton MS3307�j���̂R�̍�i�́Acantus collateralis��N���C���[�u�b�N�`���̎g�p�ɂ��A�L���@����ʂ̃p�^�[������͂���Ă���B �R���N�V�����̍ŏ��̏ꏊ�ɂ́A�����������@�ŏ����ꂽGloria laus et honor (Nos. 1-2)������B����́A�I���W�i���ł́A�W�t����Ȃ�gathering�ɂ����đ��݂��Ă���B���̍Ō�̂R�݂̂��������Ă���B ���y�̐����́A��1���̂��̑��̕����Ƃ͎�قȂ�B���ɁA�����L���A�����A�Ō��long�Ȃǂɂ����āB����䂦��i�͓���̏��L�ɂ���ď����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ���Schofield�̋^�O���x������B ����ɁA����́A�T�珇���ɂ͍����Ă��Ȃ��B���ׂĂɂ��蓾�邱�Ƃł͂��邪�A���̍�i�́A���Ƃ��Ƃ̃��p�[�g���[�ɂ͑����Ă��炸�A���̂��߂ɁA�L���@����ꗂ͗e�Ղɐ���������B ���̑��̕ʁX�̃p�[�g�ɋL������Ă���2��i�́A 0 potores (No. 51) �� Cantemus Domino(Nos. 52-53)�ł���B�����͂��Ƃ��Ƃ́A�R���N�V�����̍Ō�ɂ������B�Q��cantilenas(Nos.54 and 55)�́A���炩�ɁA�قȂ������L�ɂ��lj��ł���B O potores (No. 51) �� Cantemus Domino(Nos. 52-53)�́A���Ƃ��Ƃ̃R���N�V�����ɂ����āA�X�R�A�L���̎g�p�ɑ���܂�����Ȃ���O�ł���B�L���@�̕ω��̗��R�́A���̉��y�I�l���ɂ���B�����͗B��̌ŗL�̃��e�b�g�ł���A����䂦�A�N���C���[�u�b�N�L���@��v�������̂ł���B��O�I�Ȍ`���ƋL���̂��߂ɁA�����͏��L�ɂ���āA�Ō�ɒu����邱�ƂƂȂ����B ��116 �@�����Ȃ��זڂ�e�[�}�J�^���O�͐�����˂Ȃ�Ȃ��B�B��W���q�����Q�����n�܂�(fol 49)�C���A�Q�t����������Ȃ��B���̑�S�C�W�t������̔z���fols. 52 �� 56�ɊY������B�������K�^�ɂ��A����́A�Q��folio�̉��y���������Ă��邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��Bfol. 52�݂̂��������Ă���̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���̗t�́A�ʖ{�������������Ƃɔj��ꂽ����ł���BFol. 56�͒[����Ƃ��āA�ŏ����瑶�݂��Ă���B����́A�L������ Ave rex angelorum���A�Q�y�[�W�ɂ킽���Ă���Ƃ͂����A������E�ւƑ����Ă��鎖���������Ă���B ��̏��L�ɂ���ď���������ꂽ�Ō�̂Q��cantilenas�́A�����I�ɏ�������Ă���BNo.54 �̃e�L�X�g�̂Ȃ��o�����́A�ʖ{�̌������l�A�������s���S�ł���B��i��transcription�́A��P�̂悤�ɁA�����Z�N�V�����̂悤�Ɏn�܂��Ă���B 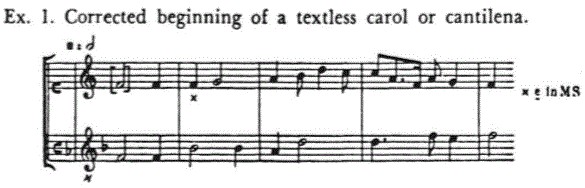 No.55��[Puer] natus hodie�̌��t�Ŏn�܂�R���X�^���U���܂�ł��邱�Ƃ��A�e�[�}�J�^���O�ɉ�������ׂ��ł���B���t�Ɖ��y�̑����́A������Ă��邪�A�K�^�Ȃ��Ƃɂ́A�����Ղ��炻�̕����͉����邱�Ƃ��\�ł���B�h�w���h�Ŏ�����Ă��鑱���́A�ʖ{�ɂ͓����Ă��Ȃ��B �@����́ALoM�iEgerton3307)�j���A�S�̓I�ɁA���̊��m�̉p���̃\�[�X�̊Ԃł��Ȃ�Ǘ����Ă��鏭����correspondences����W�߂��Ă���B����͂����炭�A����ȗ�q�̂��߂��������y�̃R���N�V�������A�������̕��ɂ���Ă��Ȃ������Ƃ��������ɂ����̂ł���B�قƂ�ǂ�concordances�̓L�������ł���A���̂����̂������́A�ł����ڂɊ֘A�����\�[�X�ł���OS�iSelden B 26�j�ōēx����Ă���B �ȉ��̃��X�g�ł́ASchofield�̎Q�l�����́A�T��̕����ł����������g������Ă��邪�A���݂̂Ƃ���A�S�̂̃��X�g��8�ȉ��̍�i���܂�ł���B 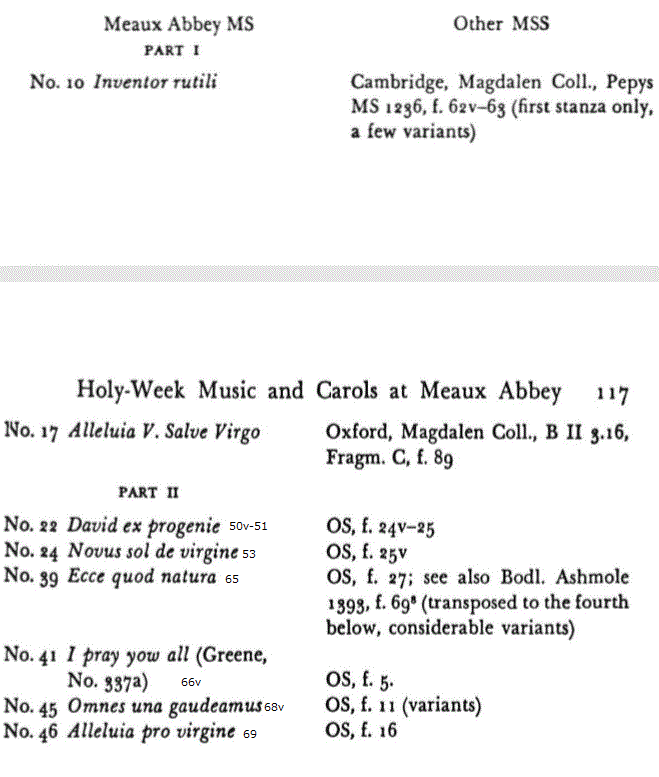 p117 �@��II����corespondences��OS�݂̂ł������Ƃ��킩��B��3�̏o�T���m���Ă���No.39�������āB �������A����͒��ڂ��ׂ���O�ł���B����܂ł̂Ƃ���A�R�̔łł̑��݂��m���Ă���B���LoM�iMeaux Abbey�j����̍�i������ł���B LoM�iMeaux Abbey�j��Pepys MS�Ƃ̊Ԃ̗\�z�O��corespondences�́A����Ȓ��ڂ��W�܂�B�Ȃ��Ȃ�Pepys MS�́ALoM�iMeaux Abbey�j�̓T��I���p�[�g���[�ƁA���n��I�Ȏʖ{�Ƃ��Ċ֘A���Ă��邩��ł���BPepys MS�������炭�A�k�C���O�����h�A1475�N���炳���̂ڂ�A��ʓI�ɂ��Ȃ�v���~�e�B�u�ȃX�^�C���������Ă���B�X 9�@Pepy�ʖ{���k���N���ł��邱�Ƃ��ADaphne M. Bird �ɂ���Ē�Ă���Ă���Bin her thesis �g A Review of Fifteenth.Century Church Music in England. with Special Reference to the Pepys MS 1236: �E Abslracts o( DisserlalioTIJ ... in Iht Univtrsity 01 Cambridge (194 2-43) . 32 LoM�iMeaux Abbey�j�Ɋ܂܂�Ă���Sarum Processional����̓T��I�e�L�X�g������Ă��邱�Ƃ́A�����[���B������Pepys MS�ł́A�Ⴄ���y���g���Ă���B Pepys MS�ł́A�����͗�q�ɑ��āA���������Ԃ�Ȃ��@�\�I�ȉ��y�̂悤�Ɍ����A���m�ȓT��̏����Ȃ��ɋL�^����Ă���B���̓T����correspondence�́ADom Anselm Hughes�ɂ���čŏ��ɋC�Â��ꂽ�̂����A�p���N���̋L�q����Ă��Ȃ��f�ЂŐ����Ă���B leaf��,�Â������������̂��߂ɔ����Ă��鑽���̋����̂�����1�ł���B �@���Ƃ��݂������p���I�ł͂Ȃ��Ă��i���@����ʂȂǂɂ����āj�A�����ăp�[�g�ɂ����ĉp�ꂪ�g���Ă��Ȃ��Ă��A���̉p���I������N���́A�����̐����I�o�����Ō���I�ɖ��炩�ł���B Salve festa dies��St . George in �̃X�^���U�́A ���̂��D�݂̉p���l���l���Apugil Anglorum�ƁA�}�ɒ��q��ς��ČĂъ|���Ă���B�ނ��]�����ʂ̃L������Enfors we us�́A�ߋ��̗��j���Ƃ��āAAgincourt�̐킢�ɂ��ċL�q���Ă���B �L������Saint Thomas honour we�́A�p���̏}���҃g�[�}�X�E�A�E�x�P�b�g���Acantilena Exultavit cor �͍�Ȃ��鉤�ł������w�����[5�����L�O���邽�߂ɕ������Ă���B�C���O�����h�̓��� - Schofield�́A�����炭�o���푈���������Ă���\�́AAnglia tibi turbidas�̃g�s�b�N�ł���A�����ăC�M���X�́A cantilena Benedicite Deo�ŁA�t�����X�Ƌ��ɁA�Ăь��y����Ă���B���̑�S�X�^���U�ł́AAnglia et Francia �C cunctaque imperia�Ə�����Ă���B carol Ivy is good and glad ��Ivy cult ����b�ɂ����A�p��̂��傠���̍D�܂����g�s�b�N�Ɋ�Â��Ă���B 2. HOLY.WEEK MUSIC AND OTHER SACRED COMPOSITIONS L1TURGICAL ASPECT �@Egerton MS3307�R���N�V�����̓T�畔���́A��Ƃ��Đ��T�̂��߂̂��̂��܂�ł���B�������̂��̂́A���܂��܂ȋ@��̂��߂̂��̂ł��邪�iNos.17-19�j�B �����ɑ��āA���e�b�gCantemus Domino (No. 52-53�@75v-77)���t���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A��Q���ɑ����Ă���̂ł͂��邪�A�T��I�e�m�[���̂��߂ɁA��P���Ɋ܂܂�Ă���B �@�����Ƃ��d�v�ȑ�1���̊O���I�����́A��i�̗���ꂽ�A�����ł���B���Ƃ��Ƃ̃��p�[�g���[�ɂ͑����Ă��Ȃ��m���D�P�͕ʂƂ��āA�S�̂̐��T�̃V���[�Y�iNo.2-16)�́ASarum Processional�̓T��I�����ŏo������B �T��@�\�ɂ��Ă̂�����������́A�Ɠ��̐����ł���A15���I�̃|���t�H�j�[���y�̂��̑��̉p���̃R���N�V�����Ƃ͂�������Ă���14�B����قǂɓT��Ɍ��i�ȃ\�[�X�Ƃ��ẮA13���I�̃N���E�Y����e�b�g�ɂ܂ők��Ȃ�������Ȃ��B�A���A�N���E�Y���́A�~�T�̌ŗL���ɑ����Ă���̂ɑ��āA�����̍�i�́A����ȋV���̂��߂̂��̂ł��邱�ƂɈႢ������B�T���́AEn rex venit �ƂƂ��Ɏ}�̎���Ɏn�܂�A���T��ʂ��āA�����Ռ��j����Dicant nunc Jude�ŏI���B 14�@�����̑嗤�̃\�[�X�ɂ����ẮA�T�珇���Ŕz�ꂽ��K�͂ȃR���N�V�����Ƃ��Ă̍�i�Q�����o�����Ƃ��ł���B ��119 �@���̏����͕ʂƂ��āA���ѕ��͋����[���B�Ȃ��Ȃ�A�`�����g���|���t�H�j�[�ʼn��t����邩��ł���B�v���C���\���O�̉��t�ɂ́A�͂�����Ƃ����K��������A�T��̂킸���ɑI�ꂽ���ڂ݂̂��A�p�[�g���y�Ƃ��Č��l�ɐݒ肳���B�����ɂ���āA�`�����g��Z�N�V�����Ƃ��đI�ꂽ���ڂ́A�t���R�[���X�ł͂Ȃ��A���l�̃\���X�g�ɂ����̂ł������Ƃ����������B ���������|���t�H�j�[�̂����ŁAMeaux Abbey collection�͖��炩�ɁA���j�]���ƂƂ��Ƀ\�����t�⍇�����p�[�g���y�Ɗ֘A�����Â��T��̓`����ۂ��Ă����B���������K���̐N�Q��13���I���琶�������A13���I�O���̍����|���t�H�j�[�̖u���݂̂Ƌ��ɁA��O�ł��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����h�ƂȂ����B Meaux Abbe�ŏj��ꂽ�A�p�[�g���y�ɂ������Ƃ������ȃO���S���I���̂̌`���́A�s��̃q���܂���versus�ł���B����͒ʏ�̃q���ƗL�ߌ`�����V�F�A���Ă������A�ω�����X�^���U�ƕs�ς�burden�̊ԁA���邢�́A������T��s�ׂ̃A�i���W�[�Arepetenda�ɂ́A�e�L�X�g�Ɖ��y�ł͑��Ⴊ�������B Sarum Processiona���̃��u���b�N�ɂ��Arepetenda�́A�ŏ��Ƀ\�����iLoM�ł̓|���t�H�j�[�j�A���ɍ����ɂ���āi�����炭�̓��j�]���j�J��Ԃ��ꂽ�B���̌�X�^���U�́A������repetenda�ƌ�ւŁA�\���|���t�H�j�[�ɑ������B���̎�̂��̑��̃\�[�X�̂悤�ɁALoM�́C���y�̃|���t�H�j�[�����݂̂��L�^���Ă���B �@Meaux MS�́AGood Friday service (Adoration of the Cross)�ɑ����Ă���Crux fideli�������ASarum Processiona�ɂ���ċ��߂�ꂽ���T�̂��ׂĂ̍s��p�q���̃|���t�H�j�[�ݒ���L�^���Ă���B ���̏ȗ��́A�����ׂ����Ƃł���B��X���_���X�^�u���̍�i����m���Ă���悤�ɁA���̃q�����܂��A�|���t�H�j�[�ʼn̂�ꂽ�B���̃R���N�V�����́A�����j������̒P��̍��ڂ��܂�ł��Ȃ��B����́A�D�̖ؗj�����畜���Ղ̓y�j���ւƏ��� (Nos. 10-12)�B P120 �����ɓ���break���Ȃ��Ƃ��������́AMeaux Abbey�ɂ����āA�|���t�H�j�[��Good Friday service����r������Ă����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B LoM�̘A�����́A���}�^�C���ȁi�}�̎���j�̂R�Ԗڂ�gathering�ł̂݁A���f����Ă���B�Ȃ��Ȃ��Ă��镔���́A���Ȃ̍Ō��Kyrie�̍ŏ����܂�ł������A�����炭�ʂ̍�i�́A���Ȃ̂悤�ɁA�g�傳�ꂽ��i�ł͂Ȃ��B �~�T�Ȃ�feriae��T���ɑ����Ă���A�V���[�Y�̉E�̏ꏊ�ɂ���B����䂦��X�́A���Ԃ̑��݂ɂ��S��炸�A�ʖ{�͐��T�̊ԂɃ|���t�H�j�[�I�ɉ��t���ꂽ�`�����g�̊��S�ȃV���[�Y�������Ă���A�Ɛ��_���Ă���B �@LoM�̔ނ̋L�q�ɂ����āASchofield�́A���łɃe�L�X�g��Sarum Processional�Əƍ����Ă���B�ނ̏����́A�����ł́ASarum use�̂��܂��܂ȓT�珑���瓯�肳�ꂽ��������v���C���\���O�ŕ���Ă���B �ȉ��ɂ����āA��1���̓��e�́A�T���̓��t�ɂ��������āA�O���[�v�Ń��X�g������Ă���B���t�̎w���̕t���I�Q�Ƃ�A���u���b�N�Ɍ�����悤�ɁA�����āA�v���C���\���O�̃\�[�X�ɑ��āA�o�ł���Ă��悤���Ȃ��낤���B���ꂼ��̗�ɂ����āA�`�����g���ǂ̂悤�Ɏg��ꂽ�������߂���Ă���B Palm Sunday �@En rex venit�iNo.�R�j�́A�����ƌ��݂� "tres clerici"�ʼn̂���R����versus���邢�́gantiphon"�ł���B���̃`�����g�́A�X�^���U�̂����������y�I�Ɋ֘A���Ă���悤�ɁA�s��̎^�̂ւ̂����炩�̐e�a���������Ă���B �`���͗�O�I�ŁA�e�L�X�g�͘A�����Ă��āA���y�͖{���I�ɑS�̂ɂ����Ă���B�U���ŏ�����Ă���3�̍����X�^���U�́A�����悤�ȓ��@����n�܂��Ă���B ���҂����悤�ɁA�ʖ{�ɂ́A�\��verses En rex venit�AHic est qui�A�����Hic est ille�������L�^����Ă���B�������ʂ̏ȗ�����A�����̓v���C���\���O�ʼn̂��Ă����Ɛ�������邩������Ȃ��B �`�����g�̃\�[�X�́AGrad . Sar .�C81�ł���B�����f�B�[�́A in stola �̌��t�������āA�S�̂�ʂ��ď㐺���Ōy���A�p���t���[�Y����Ă���B�����ł́A�����s�b�`�̂��߂ɁA�������Ɉꎞ�I�ɁA�����f�B��migrant���Ă���B �@Gloria laus et honor(no.1-2,4)�́A "septem pueri(7�l�̏��N�j�h�ɂ���ĉ̂���L���ȍs��^�̂ɑ��Ă̂Q�̈قȂ����ݒ�ł��邪�A�ʏ�̒j���Ə��N�̐��̑g�ݍ��킹�ɂ�����R���ݒ�ł���B�`�����g�̃\�[�X�́AGrad . Sar .�C83�ł���B p121 �ŏ��̐ݒ�́A�v���C���\���O�́A���ꂪ���S�ɕۑ�����Ă������́Amigrant���闬��ő��݂���B �������A�f�Ђ̖`���̌�������2�����́A�`�����g�̍��Ղ����������Ȃ��̂ŁA����͂����炭���̃Z�N�V������treble�Ŏg��ꂽ�B �������́A�v���C���\���O�Ɋ�Â��āA����ꂽ�������������邱�Ƃɂ���āA����������������邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B ���̍�i�̗l���Ŏ��������Ă���ꍇ�A����́A�ݒ���č\������댯��`�����ɁA���邱�Ƃ��ł���ᐺ���ɂ͓K������i��Q�j�B  �@��������A��i�͒P����conductus�l���ŏ�����Ă��邱�Ƃ��킩�邾�낤�B���̋L���@���g�p����Ă���Ƃ��������́A�����؋��ɂ���āA���̍�i�̗�O�I�ʒu���A�m�F�����B �@Gloria laus �̃e�L�X�g��2�Ԗڂ̐ݒ�i4�ԁj�́A��ʓI�ȃX�^�C���ł͍ŏ��̐ݒ�ƈ�v���Ă��邪�A����cantus firmus�̈������قȂ�B�`�����g�̎n�܂�́A�ʼn������ł͂�����Ǝg���Ă��邪�Arex Christe�Ƃ������t�̌�A���y�͎��R�ɑ����Ă���B���̌�̃X�^���U�A����Cetus in excelsis�͎��܁A���鐺���ŁA�����č��܂��ʂ̐����Ńv���C���\���O���Î����邪�A�����̗ގ��̂������́A�`�����g�Ɠ������@���g�p����ǂ�ȍ�i�ł��s��I�ɋN����̂ŁA���R�̂��Ƃł��낤�B ������ɂ���A��X�͂����Ŏؗp���ꂽ�����f�B�[�̈�т����ɂ��Ă͌����Ȃ��B�d�v�Ȃ��Ƃ́A�������̃J�f���c���v���C���\���O�̂���Ƃ͈�v���Ȃ����Ƃł���B p122 �@Unus aulem ex ipsis Caiphas(No. 5)�́A"tres clerici"�i3�l�̐��E�ҁj�ɂ���ĉ̂���antiphon or respond Collegerunt pontifices��vrse�ł���B�|���t�H�j�b�N�̐ݒ�́A�\���Z�N�V�����݂̂ō�Ȃ���Ă���B �`�����g�iGrad�BSar�B�A84�j�́A�قƂ�Ǒ����̂Ȃ�treble���ɂ���B �@Passio ... secundum Matheum�iNo. 6�j�́A�I��蕔�����s���S�ł���Bturbae�ƌ��t�́A�L���X�g�ƕ����L�҈ȊO�̐l�����Ɋ��蓖�Ă��Ă���i�R���j�B���Ȃɑ���ʏ�̘N���́A���̋Ȃɂ����Ă͎g���Ă��Ȃ��B Weekdays of Holy Week �@Mass (Nos . 7a-7d) �́AKyrie�i�s���S�Ȏn�܂�j�ASanctus�i�����Benedictus�j�A�����Agnus Dei���܂ށB�T���͊���ł���O�����A�ƃN���h�͏ȗ�����Ă���A�~�T�u���r�X�ƂȂ��Ă���B��i���T���ɉ̂��邱�ƂɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ́A�T���p�Ɏw�肳�ꂽcantus firmus������܂����������i���ꂼ��Grad�BSar�B9�A17 *�A�����18�E�j�B�`�����g�͂��ׂĂ̊y�͂ŁAtreble�Ŏg���Ă���B ���T�Ԃ̐��j�� �@Passio �E�E�E secundum Lucam�iNo. 8�j�BSt. Matthew Passion�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA���K�I��Passion�̉����Ɍ��y�����ɁAturbae�ƃe�L�X�g���l�̃Z�N�V�����݂̂���Ȃ���Ă���B�����̎��Ȃɂ����郂�m�g�[���̑�����declamatory�ȃp�b�Z�[�W�́A��ȉƂ��A�ʂ�tonus lecionis���̗p���邩�A���R�ɓT��N���̃X�^�C����͕킵�����Ƃ��������Ă���B ���P�Q�R Maundy Thursday �@O redemptor sume carnem (No . 9)�� "tres pueri�i3�l�̏��N�j"�ʼn̂�ꂽ�s��̎^�́i9�ԁj�ŁA�����ƌ��݂ɉ̂�ꂽ�Brepetenda�Ƃ������̃X�^�����́A�R���ݒ�ł���B���̑��̃X�^���U�́A�Q���Ȃ����S���ł���Brepetenda�̂݁A�`�����g����b�Ƃ��Ă���Bverses�͎��R�ɍ�Ȃ���Ă���i��5���Q�Ɓj�B Good Fryday �|���t�H�j�[��i�Ȃ��B ���y�j�� �@lnventor rutili�iNo. 10�j�ŁA�uduo clerici�i�Q�l�̐��E�ҁj�v�ɂ���ĉ̂�ꂽ�s��^�́B�����ł͑S�̂�ʂ���3���̂��߂ɐݒ肳��Ă���B�p���t���[�Y���ꂽ�v���C���\���O�́Atreble�ɂ���B ���ׂĂ�verse�͓��������f�B�[�������Ă��邪�A�`�����g�͒P�ɈقȂ錾�t�ŌJ��Ԃ����̂ł͂Ȃ��A����O���ɍ��グ���Ă���B���ʂƂ��ē�����5�́u�o���G�[�V�����v�܂��͘a�����̐ݒ�́A���Y���̑��l�Ȉ����ɂ����Ă��Ȃ�̑n�ӍH�v�������Ă���B��1�A3verse�̖`�����߁i��3�j�́A���������f�B���ǂ̒��x���l�ɕ\���ł��邩�m�Ɏ����Ă���B p124 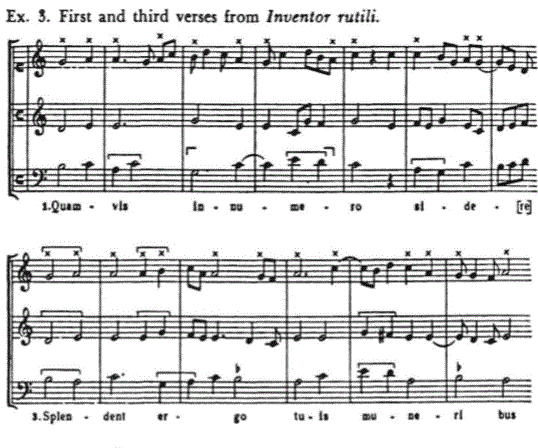 �@Rex sanctorum �iNo�E11�j�́A�utres clerici�v�ɂ���ĉ̂�ꂽ�s��^�̂܂��́ulitany�v�iProc�BSar�B�j�ł���Brepetenda�Ƃ���ɑ���6�̃X�^���U�ł́Atrenle���`�����g���ڂ����q�ׂĂ���iGrad�BSar�B�A114�j�B�����ł�6�́u�o���G�[�V�����v�̃Z�b�g�����邪�A�O�̃Z�N�V���������Δ�̈��������Ȃ��B �@Alleluia�AV. Co - temini Domino�iNo. 12�j�́A"duo clerici"�ɂ���ĉ̂���B2���̐ݒ�́A�\���Z�N�V�����݂̂ō�Ȃ���Ă���B�v���C���\���O�iGrad�BSarri 115�j��treble�Ɍ���Ă���B Eater Sunday �@Salve festa dies (Nos. 13 and 13a) ���Atres clerici�A"�s��̎^�̂ŁA�C�[�X�^�[�A���V���A�����đ��̍ՓT�̂��߂�5�̌��t�̃Z�b�g�������ɒ��ꂽ�B�`�����g�́A��͂�Atreble�Ŏg���Ă���iGrad�BSar�B�A116�j�B verses�ɂ́Atreble�Ƀv���C���\���O������Salve festa dies�iNo�B13a�B�J�^���O�ł͌��y����Ă��Ȃ��j�̂Q�Ԗڂ�3���ݒ肪�������A�����͂قƂ�ǂȂ��B�₩�Ȃ��̂ƒP���ȃo�[�W�����̃����f�B�Ƃ��r����̂͋����[���i��9���Q�Ɓj�B 2�Ԗڂ�repetenda�̖ړI�́A�����̌��@�ɂ���čŏ��̌J��Ԃ������͂邩�ɒZ�����A�S�����m�ł͂Ȃ��B����́A�Ȍ��ɂ��邽�߂ɁA�X�^���U�Ԃʼn̂��Ă���\��������B ���������Ȃ�A�J��Ԃ��͍����ɂ��|���t�H�j�[�̗�O�Ƃ��čs��ꂽ�ł��낤�B�����ł́A����͑�֓I�Ȃ܂��͓Ɨ�������i�ł��邩������Ȃ��B �@Crucifixum in carne (No. 14)�́Aantiphon Sedit angelus ��verse�ŁA �gtres clerici"�i�R�l�̐��E�ҁj�̂��߂̂��̂ł���B�v���C���\���O�́A3���̏㐺���ɂ���B �@Alleluia�AV. Laudate tueri�i 15�j�́A "tres pueri"�ɂ���ĉ̂��邪�A�����ł͓�Q���̂��߂ɐݒ肳��Ă���B��12�Ԃ̂悤�ɁA�\���Z�N�V�����݂̂��L�^����Ă���B���y�͎��R�ɍ�Ȃ���A�Ƃɂ����A�����2��Alleluia���m�̃o�[�W�������g���Ă��Ȃ��B p125 Easter Monday �@Dicant nunc Judei�iNo�E16�j�́Aantiphon Christus resurgens ��verses�������A"duo clerici"�ł���A�����ł�3���ŏ�����Ă���B����͂܂��ASalve festa dies�O��Easter Sunday �ł��̂�ꂽ��������Ȃ��B���̓T��̃����f�B�́Atreble�ɂ���B ���̑��̓T�� �@ Alleluia �CV. Salve virgo mater (No. 17)�́A Purification of B.V.M�̏j�Ղ��߂̂��̂ł���B�`�����g�́A1507�N��Sarum Gradual�iComm�BSanctorum��fo l�Bxliii�j�����Manchester��John Rylands Library��MS lat�B24�ifo l�B214V�j�Ɍ��o�����B�����f�B�́AAlleluia V. Dulce lignum�iGrad�BSar�B�A185�j�Ɠ���ł��邪�Atreble�̒��Ŏ��R�Ƀp���t���[�Y����Ă���B �@Audivi [vocem]�AV. Media nocte�iNo. 18��19�j�́A�������̐���}���A��Nativity�ɑ��鉞����2�̈قȂ�ݒ�iAnt�BSar�B�A567��576; Proc�BMon�B�A236�@�C�[�X�^�[�Ɋ��蓖�Ă��Ă���j�ł���B �ŏ��̐ݒ�i��7�̉����Q�Ɓj�́A�e�m�[���ɂ����āA�T��p�����f�B����т��ė��p���Ă���B 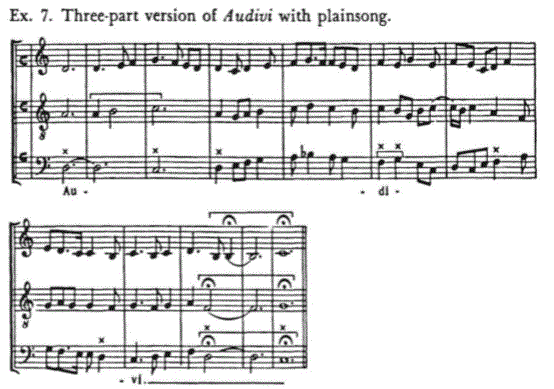 ����̓R���N�V������conductus�̈����̗B��̗�ł���B��Q�̐ݒ�i��S�j�́A�`�����g��p���Ă��Ȃ��B�Ăу\���X�g�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�Z�N�V�����݂̂��|���t�H�j�[�ɐݒ肳��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B 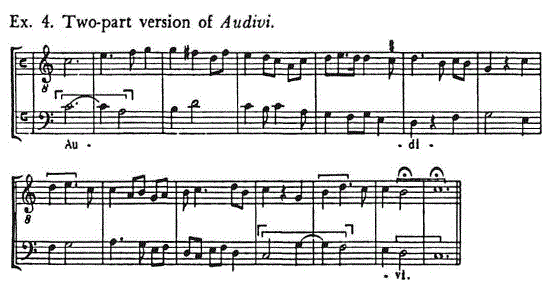 p126 �@Cantemus Domino socie(Nos. 52-53)�́A4���̃��e�b�g�ł���B�ꌩ����ƁA���X��LoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)�̃��p�[�g���[�̍Ō�̕����ł��邱�̍�i���A���̐��T�����Ɋ܂܂��ׂ����ǂ����͊m���ł͂Ȃ��B���̃e�L�X�g�́A�_���ł͂��邪�A�T��I�ł͂Ȃ�����ł���B �e�m�[���̎n�܂�́A�e�[�}�ʃJ�^���O�ɋL�ڂ���Ă���悤�ɁA��������Ă��邽�߂ɔ��Ǖs�\�ł��邪�A���ꂪ�������ꂽincipit�������Ă���Ƃ��������ɂ��ẮA���y����Ă��Ȃ��B G�cin celis etc. (sic in MS) is �iMS�ł�sic�j�Ȃǂ͂킸���Ɏ��ʉ\�ł���B����́A���l���̏}���҂̍~�a�ɂ��ĉ̂��Ă���A���e�B�t�H��G[audent] in celis �Ƃ��Ď��ʂ��邱�Ƃ��ł���iAnt�BSar 641;���[�}�ł͑����قȂ�j�B �@�`�����g�̑O��������Cantemus Domino�̍ŏ��̐ݒ�ɕ\������Ă���B 2�Ԗڂ̐ݒ�̃e�m�[���́A���Ɏw�����Ȃ��AEt quia pro eius amore�������Ƃ��ċ��������ׂ������`�����g�̌p��������̂��ǂ����̃q���g���Ȃ��B �����e�L�X�g��2�̓Ɨ������ݒ�Ƃ��Ď��J�^���O�Ƀ��X�g������Ă�����̂��A���ۂɂ́A1�̍�i�ł��邱�Ƃ��Acantus firmus�̕��z����킩��B����́A�����̃��e�b�g�ň�ʓI�ł������悤�ɁA2�̕�������Ȃ�A�ŏ��̕����͂R���q�A2�Ԗڂ̕����͂Q���q�ł���B�e�m�[�����������ꂽ�����ł́A���{��stem���������܂܂ŁA�A���� �̃X�y�[�X�͏������ʂ��炩�Ȃ�悭���ς��邱�Ƃ��ł���B�����̎����́A�����f�B�̒m���Ă���v���C���\���O���琄�_���āA���y�̑����Ȃ��A���������̍ŏ������̐��m�ȕ������\�ɂ��Ă���iEx . 13 below�Q��) �B  �@���̃��e�b�g�͔��ɒ������A���̂Ƃ��떢�m�F�̃e�L�X�g�Ɋ�Â��Ă���B �㐺���́ACarmen Paschale �ŁA�L����introit Salve sancta parens �̂��߂̃��f����ݒ肵��hymnographer Sedulius (4th-5th c . )�ɂ��elegy�̍ŏ���8�s��N�����Ă���B ��Cantemus Domino�́A�I���ɑg�ݍ��킳�ꂽ��� elegiac meter �ŏ�����Ă��āA�R���N�V�����̂����ōł������̎��I�Ŕ��I�ȃe�L�X�g�ł���B�ȉ��Ř_������悤�ɁAGoliardic drinking song �̏ꍇ�̂悤�ɁA�ʖ{�͌��t�̍ŏ��̊��m�̉��y�ݒ��`���Ă���B ���e�b�g��2�Ԗڂ̕������A�ŏ��̕����̃e�L�X�g���A�A������e�m�[�����ČJ��Ԃ����Ƃ́A�ނ����ł���B���ɁA�G���W�[�͑����̍�i�̂��߂ɁA�\���ȃe�L�X�g�����^���Ă���̂�����BSedulius �̎����A���y��i�ɂ��j�ɂ������āA15���I�ɂ͏\���ǂ��m���Ă����Ƃ��������́A���M���ׂ����Ƃł���A�iSedulius �j�̍�i���w���҂��琹�E�҂ɓn���Ă������Ƃ��Ӗ����Ă���B�i�G���̂�����́Ahttp://machikun.la.coocan.jp/twomedieval.htm p11���Q�Ƃ̂��Ɓj p127 �@�O�q�����A�T���i�̒��ߕt���̓T��̈ʒu�Â��̃��X�g�́ALoM�̉��y���T��̗v���Ɗ��S�Ɉ�v���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B Sarurn Processional�̃��u���b�N���A�����c�ɂ�鉉�t���K�肷�邽�߂̃e�L�X�g�̂��������Z�N�V�����́A��т��ă|���t�H�j�[����͏��O����Ă���B���̉����̂����A�\���Z�N�V�����A�ŏ��̒P��A������verse��������Ȃ���Ă���B����ɁA1�l�̉̎�̉��t�ɂ��\���Z�N�V�����̉��t�́A�����̂Ƃ͌��Ȃ��ꂸ�A�P�Ɂu�������ꂽ�\���v�܂��̓\���I�ȏW�c���t�ƌ��Ȃ��ꂽ�B �T��̏���ɂ����āAMeaux Abbey MS�́APepys MS�����͂邩�Ɍ����ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���B��҂͍�i�̕��тɂ�����T��̏��������邾���łȂ��A�ʏ�̓|���t�H�j�[�ƂȂ�悤�ȃ\���Z�N�V�������A�ʏ�͍�Ȃ���Ȃ��`�����g�̃|���t�H�j�b�N�����Z�N�V�����ƕ��u���Ă���B �T�[�r�X�̂��ׂĂ̕����ɍ����|���t�H�j�[��s���ɓK�p���邱�Ƃ́A15���I��ʂ��Ă̌��i�ȓT��̓`�������X�Ɏ�܂邱�Ƃ�\���Ă���B �@���y�E�T��̎��_���炷��ƁACantemus Domino��~�T�u�����B�X�A�����ĂQ�̎��Ȃ́A����ȕ��ނɓ���BSedulius�ɂ��G���W�[���A���e�B�t�H���Ƒg�ݍ��킳����poly-textual �ȃ��e�b�g�́A�T��I����̊O�ɗ����̂ł���A�����Ă��̓T��I�ȋ@�\�́A���ꂪ�����Ȃ��̂ł����Ă��A�A���e�B�t�H���ł̂��̋@�\�ɑ��āA�}�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B �@�~�T�́A�z�~�T�Ȃ̔��W�ɂ����ďd�v�Ȓn�ʂ��߂Ă���B����́A�C�M���X�N���̎ʖ{����m���Ă����ŏ��̃|���t�H�j�[�I�ȃ~�T�u���r�X�̓��t�����߂邱�ƂɂȂ�B �X�̊y�͂́A���b�g�[���@��J��Ԃ�cantus firmus�ɂ���Ăł͂Ȃ��A�p���t���[�Y���ꂽ�v���C���\���O�̓T��I�@�\�݂̂ɂ���Č��ѕt�����Ă���B �~�T�u���r�X�̓v���C���\���O�~�T�ł���A���ꂼ��̊y�͂́A�قȂ�`�����g�Ɋ�Â��Ă���B ���������āA���̏z�́A���y�I�Ȏ�@�����T��I��@�ɂ���ē��ꂳ��Ă���B���������I��@�̎g�p�ɂ���āA����ɁA�l���I�ȓ����^���Ă��邪�B �z�~�T�Ȃ̐i���ɂ����錈��I�ȃX�e�b�v�ł��鉹�y�I����̍l���̓v���C���\���O�~�T�ɂ̂݁A�ԐړI�ɓK�p�����B ����͓T�炩����I�l�@�ւ̓]�����Ӗ����A���l�T���X�̑ԓx�ɓ����I�ł���B p128 �@�Q�̎��Ȃ́A���j����ɋ����[���B�Ƃ����̂́A���̃^�C�v�̍ł������̃|���t�H�j�b�N�ȍ\�}���L�^�Ɏc���Ă��邩��ł���B ���y�w�ɕp�ɂɋN����悤�ɁA�u�ŏ��́v��ł��邱�Ƃ̓����́A���j�I�����̉ߒ��ŁA���̂������̍�i����������A�����Ď���Ɉ����������A������LoM�ł�2�̎��Ȃ���ĂђD���鎞�����邩������Ȃ��B ���Ƃ��ƁAObrecht�ɋA�����邱�Ƃ�����ALongueval�ɂ��ʍ���Ȃ��ŏ����̎��ȂƂ��Č����Ă����B�}�^�C���Ȃ́A1480�N���̓��t�ł���AModena �CEst. M5 lat . 455 �ɕۑ�����Ă��邪�A���̍ŏ������玟���ւƈڂ邱�ƂɂȂ����B LoM�ɂ�����悤�ɁAturbae�݂̂��|���t�H�j�[�ɐݒ肳��Ă���B�ʂ́i�����\�́j�قړ�����������̃}�^�C���Ȃ̒f�Ђ́AParis �C Bibl. Nat. MS nouv. acqu . 4379 (fo l. 1) �Ō������Ă���B ����́A�e�m�[���p�[�g�������������Ă���A�����āA�����̐��͊m���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�����炭3���j�B ���Ȃ̃|���t�H�j�[���t�������܂ꂽ�̂��͂킩��Ȃ��B Liber Generationis�ł̃p�[�g���y�ł̘N���́A14���I�Ƃ������������ɍs���Ă���B LoM�����2�̎��Ȃ́A������declamatory conductus style �ɂ����āA����炪�܂��`�����g�N�ǂ��炻��قlj�������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���B STYLISTIC ASPECT �@�T��̕����̉��y�I�ȃX�^�C���͒͂��邪�A�o���G�e�B�ɕx��ł��Ȃ��B�L���̓��ꐫ�ƕ��s���Ă���l���I���ꐫ�́A���p�[�g���[���Z�����ԓ��ɍ�Ȃ��ꂽ���Ƃ��������Ă���B Inventor rutili�iNo. 10�j�̋L���̍ۗ����������́A�R�����g�ɒl���悤�B�ʏ�̂悤�ɁALoM�ɂ����ẮA�X�R�A�`���ŋL������Ă��邪�A���Ƃ��A�ʖ{���X�R�A�`���ɂ����Ă��̑��̑����̍�i���L�^���Ă��悤�Ƃ��A�q���́APepys MS�ɂ����ẮA�N���C���[�u�b�N�`���ɂ����āA�ψق��ďo������B Pepys MS�͂���̏o�T�ł���A�X�R�A�L���@�͏��X�Ɏg���Ȃ��Ȃ������߁A�L���@�̕ύX���̂͂���قǒ��ӂ��ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤�B����ł��A�����̔z���ƃe�L�X�g�̕��z�͔��ɓƓ��ł���B�e�m�[�����ŏ��ɏ������߂��A�����Ă��̐����������t���e�L�X�g�������A��ƒ��ԕ��̐��͎肪���肾���������Ă���B ��129 ���̔��ɒ������z�u�����APepys MS�̕M�L�҂́A������X�R�A�L���ŏ����ꂽ�ʂ̃\�[�X����M�ʂ����Ɛ��_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�R�A����@�B�I�ɕM�L����ɍۂ��āA�ނ̓e�L�X�g�����鐺�� - �e�m�[�� - ����n�߂��B�����ăe�L�X�g�Ȃ��ł̑��̐����ɑ��ẮA�P�Ɏ肪������������B�ʁX�̃p�[�g�ł̋L���́A�e�m�[��������ł���ƁA����ĈӖ����Ă��܂��B �@�X�R�A�L���@�����ɕs�K�ł������ł��낤�T��O���[�v�̗B��̍�i�́A���e�b�gCantemus Domino�ł���B����́A�e�m�[���̂��߂̃X�R�A��1�̕��\���m�ۂ��A���̐����̋L���ŕK�v�Ƃ����X�y�[�X�̏�ɂ��̏����̎����I�ȉ����������L���悤�ɂ��邽�߂ɁA�M�d�ȃX�y�[�X�����Ȃ�̖��ʂɂȂ��Ă��܂����B �@���y�ɓ��ꊴ��^����ۗ������v����1�́A�@�ׂȋȐ��Ǝ��܂̃V���R�y�[�g���ꂽ�p�b�Z�[�W�ŁA�R���q�Ŏ�ɐi�s����K�x�ɗ���ő����I���ꂽ�������ł���B���̎��R��treble�̃X�^�C���́A��������v�Ȑ��������������I�ȉ̂���ŏI�I�ɔh�����Ă��Ă���B ��i���v���C���\���O���ؗp���邩�ǂ����́A�����f�B�̐��i�ɂ͂قƂ�lje�����Ȃ��B���������ł���A�`�����g�͐����I�ȃX�C�[�v�ɎQ�����āA�����ƃJ�f���c�@������ʂ��āA�̂̎���B���̒�^�����ꂽ�����́A�����Ȃ���i�ł����n�ǂ��邱�ƂɂȂ�B �����I�ȘZ�x�̃J�f���c�́A�قƂ�ǂ̃t���[�Y�̍Ō�ɂ����łȂ��A���ɂ̓����f�B�̕s���ȕ����Ƃ��Ă�����A�ō��Ɏx�z����B�v���C���\���O���g�p����Ă��Ȃ��ꍇ�́A����ɂ�������炸�A�������������݂���B ����䂦�A���R�Ō���ꂽ��i�́A��҂̃O���[�v�̃J�f���c���`�����g�̂���ƈ�v����Ƃ��������قǂɂ́A�����f�B�i�܂��͘a���j�X�^�C���ɂ͂���قLjႢ�͂Ȃ��B �`�����g���Ɨ����Ēm���Ă���ꍇ�ɂ̂݁A�ؗp���ꂽ�����f�B�̑��݂����o�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B ���y�̃��Y���I�ȓ��ꐫ�́A�R���q�̗D�ʐ����琶����B�Q���q�͍ŏ��ɂ͏o�����Ȃ����A���ԃX�^���U�̊ԑt�Ƃ��Ă̂ݏo�����A���̌�R���q�͍ĊJ�����B���邢�́A��Q���͑�K�͂ɂȂ�B���Ȃ킿�ACantemus Domino(Nos. 52-53)�̂悤�ɁB 15���I�̑O���̉��y�ݏo���悤�ȗD���������悤�ȃ��Y���͎��܌������Ȃ�A3/4��6/8�̊Ԃ̌��˂ɂ���Ă����������������邩������Ȃ��B�v�ʉ��y�̂��̓����I�ȃw�~�I�����ʂ́A���ڂ̕��u�ŁA�܂��͓�����treble����уe�m�[���ŋN����A����܂��͑����̕����ɑ������Ԃ̐��A�܂��͓Ɨ������V���R�y�[�V�����������L����B p130 �w�~�I���ɂ��J�f���c�̍��܂�́A�قƂ�ǂ��ׂĂ̍�i�Ɍ�����͂��ł���B �~�T�u���r�X��2�̎��Ȃ��������̍H�v�̎g�p�����Ȃ菭�Ȃ����Ă���B����͎��Ȃ�declamatory�Ȑ��i�ɂ���ėe�Ղɐ������邱�Ƃ��ł���B�~�T�ł́A�J�f���c�́A�K���I�Ȕ��q�̊����ȍו����A���邢�͏��X�ɒx�点�邱�Ƃɂ���ăA�v���[�`�����B�����āA�����I�a����ۂB �J�f���c�ōD�܂�Ă������1�̃��Y�������́A���s�l�x�ɂ����đ������ꂽ�Z�x�J�f���c�̊T�v�������Ă���Q�̐����ɂ����� ���̉��^�́A��Q�̕����ɂ����č̗p����Ă���A�����̗Ⴊ����B���Ȃ킿�A�����J���Ȃɂ�����悤�ɁB���̃J�f���c�̊�ɃV�t�g�������s���A�M�L�҂̌��ƊԈႦ�Ă͂����Ȃ��B�����́A���Y���I�ȋ��������łȂ��A�a���̑��l�������B�����邽�߂̏n�����ꂽ�H�v�ł���B�P�̐����ɂ�����x�ꂪ�A�o�ߓI��6/4�a�����Y������悤�ɁB �@���p�[�g���[�̍ł������ȗl����̗v�f�́A�a���̓��ꐫ�ł���B���̘a���͖��炩�ɁA�Z�x�̃R�[�h�l���̍��Ղ�ттĂ���B�p�ɂȘZ�x�ƎO�x�̕��s�┽�s�ł̌�ւ������́A13���I�㔼�ȗ��́A�p���conductus�l���̒��S�ƂȂ��Ă����B �����I�ȃX�R�A�L�������ɂ�邱�̗l���́A����ɁALo M�̉��y�̔w�i�ƂȂ��Ă���B15���I�O���ɂ́A�V�����\���̎��R��treble�l���Ƒg�ݍ��킹��̂ɏ\���Ȏ����ƃ��Y���̏_����������B���̋ߑ㉻���ꂽ�`�ł́A����́A���I��fauxbourdon�̐ݒ�Ƃ��ċL�q���邱�Ƃ��ł��邠���̑嗤�̍�i�Ǝ������v����B ���̃^�C�v�̍�i�ł́A���s�Z�x�a���̃����f�B�[�̋@�B�I�Ȕ��t�́A�l��������A��荂�����x���ɏグ���Ă���B���̗l���I�ȗl�����s�����P�Ȃ���R�̔��W�ł��邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�����炭����́A1430�N���ɑ嗤��Ȋ�����fauxbourdon�̗��s�ɑ���C�M���X�̉��y�̍ŏ��̔�����\���Ă���B fauxbourdon�́A�嗤�ł̗��s�ɕC�G����悤�ɂ́A�C�M���X�ł̗��s�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A���̎�Ȗ��́A�����́A�C�M���X���y�ɂƂ��ĖڐV�������̂ł͂Ȃ������B����́A�`���I�ȂU�̘a���̗l���ւ̐V���Ȍ��������^�����B LoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307�́A�����Ɏ�����Ă���fauxbourdon�l���f�����ŏ��̉p���̃\�[�X�̂悤�ł��邪�A�����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�����I�ɒ�^�����ꂽ�p�[�g���@�ɕϊ�����Ă���B p131 �@fauxbourdon�Ƃ����w���ɂ���ċ��߂�ꂽ���Ԑ����̑����́A�P��̍�i�ɂ����Ăł͂Ȃ��A�嗤�ɂ��铖���̃\�[�X�ł悭������B�@�J�f���c�̑O�̕��s�̘A���ɂ����Ă̂݁A�����I��fauxbourdon�̍��Ղ����邱�Ƃ��ł���B 0ld Hall MS��Fountains�t���O�����g�̃��p�[�g���[�ɂ́Afauxbourdon�̍��Ղ͌���ꂸ�A���̓����ɂ���āA�p�ꉹ�y�̏����̒i�K���������Ƃ��ł���B �����܂ł��Ȃ��A�Z�x�a����OH��LoF�ōL���g�p����Ă��邪�A�����������́A���₭�A���S���a�����ƌ�ւ���B����ɁAtreble�̓����@�͂܂��m������Ă��炸�Acantus firmus�́A��Ƃ��āA���Ԑ����ŒS���Ă����BLoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)�ł́A�`�����g�́Atreble�ɂ����Ăقǂɂ́A���قǕp�ɂɂ͌���Ȃ��B �@��^�����ꂽ�p�[�g���@�ւ�fauxbourdon�̕ϗe�́ALoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)LoM�ŒB�����ꂽ�����ł���A�嗤�̉��y�̂��܂��܂Ȓi�K�ŒH�邱�Ƃ��ł���B �u���S�[�j���y�h�̍�ȉƂ̍�i�ł́A2����i�Ƒ�R�̑����p�[�g�ւ̌�����fauxbourdon�́A3���̃t���ɋL�����ꂽ�����ւ̂�萸�I�ȃo�[�W�����ƕ���ŁA���ɂ͔�������B�����̑�ݒ��treble�Atenor�A�����2�̑��݂ɔr���I��contratenors�ō\������A1��fauxbourdon�itreble�̎l�x���ő������t�����j�Ƃ����w���ɂ���Ďw�肳��Ă����B�����ЂƂ́Aabsque fauxbourdon�Ƃ�������A���ׂċL������Ă���B �n�l���ꂽ�R���g���e�m�[���́Atreble�ւ̓z��I�]������������A�e�m�[���̏㉺���ړ�����B Benoit �ɂ��^��Lucis creator��2�̃o�[�W�����́A���̎��H�̎���ł���B Dufay�́Afauxbourdon�̌|�p���y�ւ̓����ɂ����āA����Ɉ���i�B�ނ̎^��Exultet celum laudibus�ł́A�ނ͖{���I�Ɂu�����v��i��2�̑�փo�[�W��������Ă��邪�A�`�����g�����ʓI�ɂ���treble�͕ύX����Ă��Ȃ��Bfauxbourdon�ݒ�́A�P���ȃe�m�[���������A�R���g���e�m�[�����Ɏc���Ă���B p132 ��荂�����x���̔ł́A�قȂ�e�m�[���ƁA�����o���ꂽcontratenor�����^����Bfauxbourdon�ݒ�̃e�m�[���́A���Ԑ����̑����������邽�߂ɁAtreble�ƘZ�x�i�ƃI�N�^�[�u�j��K�v�Ƃ��邪�A���̐��I�ł́A���͂₱�����������͎Ȃ��B �R���g���e�m�[���́A�[�U�̋@�\�ƃn�[���j�[�̃T�|�[�g�Ƃ�����d�̋@�\���ʂ����Ȃ���A�����treble�Ƃ̕s���S�����Ŏ��R�ɓ����B �`���̈ʒu��O�a���̊Ԋu�����D�ނR�����@�g��`���́Afauxbourdon����̏o���_����邪�A�J�f���c�������Č����ȕ��s�͂قƂ�ǎc��Ȃ��B fauxbourdon�͌|�p���y�Ɋg�傳�ꂽ�B �@LoM(Meaux Abbey MS�ōł������Ɍ����̂́A���̗l�����ƃp�[�g���@�̊g���ł���B �e�N�X�`���ƃp�[�g���@�͑z����̗Z�ʐ��������B2���p�[�g�̕��s�i�s�́A3�Ԗڂ̐����Ŕ��s�i�s�őΔ䂳��A�O���̐�����10�x�Ɋg�債�A�O�x�ɏW�܂�A���̂��߂ɁA�R���g���e�m�[���́A�Ǝ�����B fauxbourdon�Z�@�̌��т����嗤�ł��͂����肵�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�p���̘Z�x�a���l���́A�R�����@�̓��l�̗l�����Ɍ������X���ɂ��邩��ł���B LoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)�̂Q����i�ł����A�����̑�R������v�����Ȃ����Ȋ����^�̐ݒ�ł���B��т������s�i�s�̌��@���A�l�x����treble�̓�d�������O����̂ŁA�lj��p�[�g�͐T�d�ɍ�Ȃ����K�v������B �@�t�H�[�u���h���̗l�����猩��ƁA�J�f���c�̘a���̑��ʂ͔��ɒP���ł��邱�Ƃ��\�z�����B�n�[���j�[�Ɋւ��ē��ʂȏꍇ�ł���~�T�u���r�X�������āA�Â��Z�x�J�f���c�iVII6-I�j�́A���Ƃ������Ȃ��S����i�ɂ����Ă������A�قڐ�ΓI�Ȃ��̂ł���B�R���g���e�m�[���͂��ł��e�m�[����艺�Ɏ��R�ɓ��邱�Ƃ��ł��邪�A�J�f���c�ł͂����Ȃ�Ȃ��B �嗤�̍�ȉƂ́AV-I�i�s����邽�߂̂��̋@��𗘗p����B�����Ă���䂦�ɁA�p���̓����ȏ�ɁA�a���Ɍ������i���I�ȑԓx�𗠐�B ����d�����ɂ��ā� �a���̕ێ��`�̍X�Ȃ钛��́ALoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307�̒��̃J�f���c�̘Z�x�������A�i���f�B�A���@�ɂ����Ă̂ݑS���K�I�ɂȂ遦�j��d�����J�f���c�ɂȂ�Ƃ��������ł���B ���G���f�B�A���@�͂e���������Ȃ̂ŁA���K�Ɋ܂܂�鉹�����̂܂܂d���œ����ƂȂ��B ���̐��@�ł́A�����̓����͂����A14���I�㔼����15���I�����̉��y�̎��H�ōs���Ă����悤�ȁAmusica ficta�Ƃ��ĕ\������Ă���B p133 LoM(Meaux Abbey MS�GEgerton MS3307)�ɂ�����Վ��L���̎�舵���́A���ꎩ�g�A�����ɒl����B�����ł́A��d�����J�f���c��v�����邢�����̗���������Ƃŏ\���ł��낤�B �����́A���]����2�̏㐺���ƂƂ��ɁA�������ōł��p�ɂɌ���������邾�낤�B�ʏ�͒��Ԑ����ł�����̂́A���ʂ��I�N�^�[�u�����Ƃ���ɂ���B���̌��ʁA�����́A���K�I�ȕ��s�l�x�̑���ɕ��s�ܓx�œ����悤�ɂȂ�B����́A���s�ɂ�������炸�A�Z�x�a���̃J�f���c�̊��S�ɐ������`���ł���B ���ɋ����[���̂́A��d�����̉����̘a�����A�t���[�Y�̍Ō�ŕێ�����Ă���I�~�ł���B�t�F���}�[�^�ɂ���ă}�[�N����A���炩�ɔ��J�f���c�Ƃ��ċ@�\���āA����͒���Ɏ��̃t���[�Y�̎n�܂�ŁA���S���a�����ւƉ��������B �\�z�����a���i�s�̒��f�́ADufay�̍�i�ɂ����邠���̒��ڂ��ׂ��a���i�s�ɂ����炩�ގ����Ă���B�����́A�a���̐F�ʉ��l�ɑ���ӎ�����ъ��𑝂��Ă��邱�Ƃ������Ă���B �S����i�iCantemus Domino���n redemptor����̃X�^���U�j�́A���ɐV�������͉̂�����Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��S�����͒P�ɁA�Z�x�a���̃J�f���c�̉������d�ɂ������̂�����ł���B�s��I�ɔ������镽�s�I�N�^�[�u�́A�I�[�v���ɁA���邢�́A�����I�^�[���ɂ���ăJ�o�[�����B �@�~�T�u���r�X(Nos. 7a-7d)��4���J�f���c�́A�����������^�C�v�Ƃ͖��炩�ɈقȂ�B �~�T�Ȃ�3���ō�Ȃ���Ă���B �������o�X���C���͎��X2�ɕ�������B ���̂�����1�͐Ԃ������ŏ�����Ă���B�F�͂��̓��ʂȏꍇ�ɂ́A�v�ʓI�ȈӖ����������A�P�ɓ������\�ɋL����Ă��鐺������ʂ��邽�߂̎�i�Ƃ��Ė𗧂ɂ����Ȃ��B p134 �Ԃ������ŏ����ꂽ�p�[�g�́A�����Ă��Ă��A�s�ӂɌ��������肵�Ă���A���炩�ɕ⑫�I�Ȃ��̂ł���B���Schofield���M����悤�ɁA��Œlj����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ԃ��������a���ɕs���ł��邱�Ƃ���������ł���B ����炪�Ȃ���A�����̃J�f���c�́A�����I��6/4�a���ƂȂ����ł��낤���A����͖��炩�ɗǂ��Ȃ����Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A6/4�a�������Ƃ���6�x�a���ł��������Ƃ��������Ԑ����ɂ́A���炻�̍��Ղ��Ȃ�����ł���B���y�́A�ŏ�����A�R���A�S���a���̍����Ƃ��čl�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B ������4�����Z�N�V�����́A�e�m�[���̍Ō�܂ł̉��~�X�e�b�v���AV-1�i�s�������炷�o�X�ɂ���ĕ����ߑ�J�f���c�̎g�p�Ɋւ��ẮA�������ɑ��Ă���قǒ��ڂɒl������̂ł͂Ȃ��B ���̃^�C�v�͎��X�A���Ԃ̃J�f���c��1450�N�O�ɂ��������Ă���B�������A���I�̒��r���[�ɂȂ��ď��߂āA���ꂪ�ŏI�I�ȃJ�f���c�̎�Ȍ`���Ƃ��Ċm�����ꂽ�B�~�T�u���r�X�ł́A�����Sanctus and Benedictus�ł̂ݍŏI�I�ȃJ�f���c�Ƃ��Č����B�~�T�̑��̊y�͂ł́A����͖ڗ����Ȃ��ꏊ�ŋN����B �a���Ɋւ��ẮA�~�T�Ȃ͑��̃��p�[�g���[�����킸���ɍ��x�Șa���l���������Ă���B����͕K�������A���ꂪ����ɍ�Ȃ��ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ȃ����B �@�a�����p��̂�����̏d�v�ȑ��ʂ́A���a�����ƕs���a�����̈����ł���B15���I�̑O���̈�ʓI�Ȋ��K�ɏ]���āA�O�x�ƘZ�x�́A�C�ӂ̑g�ݍ��킹�ƌ�ւɂ����āA���R�ɏ������B����炪�ŏI�a���̒��ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����K��ɂ����āB ���a�����̍����́A���̉��y�ł́A���ɍ����B�s���a�����́A�T���āA�m�ۂ���Ă���B������̂��̂́A�e�m�[���ɑ債�āA�P�ꂠ�邢�͓�d�̌q������B 3���q�ł́A������perfection�̏��߂ɁA���邢�̓w�~�I���̃J�f���c�Ƃ��āA��2���Ɍ���邩������Ȃ��B��҂́A���ɓ����I�ȍH�v�́A�����o���ꂽ�W�Q�̌��ʂ������Ă���i3/2���q�̏��߂�3/4��2���ƂȂ�j�B appoggiaturas�̂悤�Ȋm�ۂ̂Ȃ��s���a�����A�A�N�Z���g��̌o�߉��Acambiata �� echappee �̂��܂��܂Ȍ`�Ԃ́A���Ɉ�ʓI�ł���A�����V���R�y�[�V�����p�^�[���Ō����B �����͒��ڂɁA�������ւ̉����ƂȂ�B �����ɐ����I�ł���A���Ԃ��Z���̂ŏ����͕K�v�Ȃ��B �s���s���a�����͕s��I�ɁA���Ԑ������Atreble�̉��l�x�ŁA�C�����ꂽ�Z�x�̃J�f���c�����t���邽�тɔ�������B �����ł���̓e�m�[���ɑ��ē�x�ƂȂ��ċ����B �Փ˂́A�����f�B�C�����琶���A�ΏƓI�ɁA�O���̈��̐i�s�����߂�悤�ɍ�p����B �@�T���āAMeaux Abbey MS�̉��y�́A�u���S�[�j���y�h�̉��y�Ɨl���I�Ɉ�v���A����Binchois�⏉����Dufay�̂���͂����炭�A�C�M���X�̍�ȉƂ̂��߂̃��f���Ƃ��Ė𗧂����BBinchois��Dufay��antiphons�Ǝ^�̂́A���ꂼ�ꂪ���R�ɍ�Ȃ���A���邢�̓`�����g�I�Ƃ��Ă��邪�A�����̂����₩�ȓT��@�\��ނ�̃X�^�C���ɔ��f���Ă���B Lo M Meaux Abbey MS�̓T��̕����́A���l�ɁA�T�[�r�X�̂��߂�Gebrauchsmusik�ł���A�ȒP��conductus���V�ŏ�����Ă���B ���̗l���͖͕�Ƃ͑�����Ȃ��B �d�v�Ȃ��Ƃɂ́A�ǂ�ȋV�����A�T���i�ƂȂ�悤�ɂ͍���Ă͂��Ȃ����Ƃł���B����́A�p���̉��y�ł͂悭�m���Ă��邪�B �͕�́AOldHall MS�̑����̍�i�ł͈�ʓI�ł���A���ۂɕs���ł���B |