| THE STYLE OF WALTER FRYE AND AN ANONYMOUS MASS IN BRUSSELS, KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK, MANUSCRIPT 5557 |
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9377246
| p191 ブリュッセル写本5557は、15世紀後半の最も重要な資料の1つである。 大部分が無傷で現存している当時の北部の唯一の台本であるだけでなく、明らかに、ブルゴーニュ公爵の Charles the Boldに劣らない偉大な礼拝堂のためにまとめられた。 ヨーロッパの最も贅沢な宮廷の1つを支配して、Charles the Boldは芸術のただの偉大な守護者以上の存在だった。彼は彼自身活発な作曲家であった。 彼の確立した洗練された趣味は、ブリュッセル写本の音楽の並外れた品質に反映されている。 Dufay とRegisによる偉大なミサ曲は、Charles the Boldの偉大な部下であったAntoine Busnoysの現存のモテットのほとんどと肩を並べている。 写本のもともとの核は、Trent 93/90のそれと並ぶ英国のミサ曲のクラッチを誇っている。 このソースはまた珍しく、約4分の3が、作者の名を残して現存している。 写本が切り詰められなかったならば、もっと多くが残存していたことだろう。 いくつかの作者不明の作品でさえ、署名が付いていることがほとんどである。しかし少しの追加を除けば、2つの作品だけが作者不明ののままである:Magnificatとfolios 90'v99rの3声のmass Sine nomine である。 p192 elevated companyの中のそのような主要なソースでは、どんな作者不明の循環ミサ曲も注目を集めるようである。そのスタイルの性質は何か? レパートリーの他の作品とどのような関係があるのか? それはどのようにして、ブルゴーニュの宮廷での私たちの音楽的趣味の認識を広げるのだろうか? そして何よりも、どこでそして誰によってそれは作曲されたのか? 作品をよく知っていると、そのような疑問はますます喫緊になる。ミサは非常に興味深い作品であることがわかったから。機能の大規模なネットワークは、写本の最初の5つのミサ曲のように、これが英国人の作曲家の仕事であるという結論に、圧倒的につながる。 しかし、親しみが深まるにつれて、はるかに詳細な像が現れる。スタイルと構造の両方において、ミサ曲は、15世紀半ばの英国最大のミサ曲作曲家、ウォルター・フライだけの作品と密接に関係する。 15世紀からの断片的で大規模な作者不明の音楽の存続は、個々の作品のauthorshipを証明するための非現実的な試みをしているように見えるかもしれない。それにもかかわらず、この大部分が曖昧なシナリオには、様式的輪郭を照らすような価値が十分に活用されるに値する、現存の、さらにいくつかのもっと適切な出来事も含まれる。 作者不明の循環ミサ曲と、フライに帰される3つの完全なミサ曲との間の様式的な類似性は、示唆に富んでいるが、それだけで共通のauthorshipの証明を試みるのは非現実的である。 しかし、1963年にReinhard StrohmがLucca Choirbookを発見したことにより、Fryeによる4番目のミサ曲からの断片的なKyrieが明るみになった。ブリュッセルの作者不明ミサ曲(90v-99r)とこの作品の間のより具体的な類似点は、Fryeのauthorship 、または少なくとも彼の元で密接に働いていた誰かしらの作家に非常にありそうなことである。 私は、ミサ曲のスタイルを、いくつかの段階で評価することを提案する。まず、それが英国であるという主張について考察します。そこから、Fryeの3つの完全な循環ミサ曲の様式を調べ、それらを作者不明のミサ曲や他の同時代のミサ曲と比較する。さらに最後では、ミサの様式に対する理解が深まっていることを背景として、断片的なミサ曲とフライのモテットSospitati deditとの構造的および音楽的なつながりを検討したい。 p193 ENGLISH ORIGINS 近年、英国の慣用句の「特徴」であると考えられていた機能の多くが、かつて考えられていたよりも広まっていたことが近年明らかになっている。その結果、大陸のソースにおける作者不明のレパートリーの中で「英国」の作品を特定することは、今ではこれまでよりはるかに危険なこととなっている。イギリスの作品は、もちろん、広く複写されていて、その影響は、特に初期の大陸のミサ曲レパートリーでは、イギリスのモデルと大陸の模倣を区別するのが難しいことが時々あった。 その一方で、15世紀半ばにイギリス風の考えを捨て去ることは、あらぬ方向に行ってしまうことになるだろう。大陸では、疑いもなく、英国音楽についての非常に独特の何かを見て、そしてそれを模倣することによって、または筆記者の場合には、地元の好みに合うように英語の作品を修正することによって、しばしば応答した。 ただし、英語の慣用句はいろいろ回っていったが、その多くが明らかに英語の作品であったことは依然として事実である。この事実は、英国のauthorship の外部証拠がある多くの作品を参照して説明できる。 大陸的に送られた作者不明の作品の中で、作者不明のブリュッセルのミサ曲(90v-99r)のような、主に英国の特徴であるそのような説得力のある本体を組み合わせたものはほとんどない。英国として最も頻繁に引用されている特徴であるprosula Kyrieはここでは欠けているが、明らかに代替的な演奏を要求する、作者不明のブリュッセルのミサ曲(90v-99r)の短いキリエの構造は、Lucca Choirbookのフライによる断片的な循環ミサ曲と密接に関連している。 さらに、作者不明のブリュッセルのミサ曲(90v-99r)は、BedynghamとStandlyによる作品を含む小規模なサイクルのより大きな族に属し、それらの多くは明らかに礼儀正しい、最も一般的な聖母マリアのお守りを目的としていた。 ほとんどのイギリスのミサ曲、そしていくつかの大陸のミサ曲と共通して、循環ミサ曲は、同じ計量的計画と同じような長調カデンツの連続が各楽章に続くという基本的なグランドプランを持っている。ほとんどのそのような循環ミサ曲のように、余分なデュオの標準的な配置を可能にするために、パターンは最後の2つの楽章でいくらか変化している(表1を参照)。 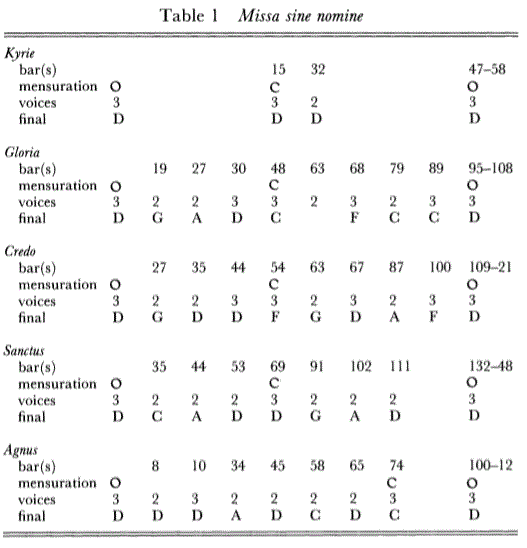 標準的な英国の手順に従って、テキスト設定のフレーズからフレーズへのスコアリングで交替することになることが多いこれらのデュオは、二重線または同時休符で分けられている。4 4こうしたやり方は、英国のミサ曲以外でも見出されないわけではない。はっきりとした英国の影響は、大陸では初期の循環ミサ曲に限られている。たとえば、Domarto's Missa Spiritus almus, Simon de Insula's Missa 0 admirabile commercium (Trent, Castello del Buonconsiglio, MS 88 (here after Trent 88), fols. 304v-311') and Ockeghem's Missa Caputなど。しかし、こうした作品においてさえ、そうした使用は、大部分の英国の循環ミサ曲ほど一定し、規則的なわけではない。 p194 (90'v99rの3声のmass Sine nomine の)Agnus Dei は、3番目の invocation で、 tempus imperfectum にシフトし、 'dona nobis pacem'で tempus perfectum に戻る。Textingは、discantus同様6、テノールとコントラテノールにおいて非常に特殊で、'sanctus' の2回だけのinvocations 7や、「qui tollis」で始まる8Agnusの歌詞づけは、標準的な英国のやり方で、プレインソングのincipitsを伴って、これら2つの楽章においてポリフォニーに先行するという当初の意図とは異なったものとなっている。 要するに、多くの学者がすでに指摘したように、この設定の多くの側面は、英国の起源を示唆しており、それを疑う明確な理由を提供するものはない9。 6 明らかに忠実な英国作品の複写を除いて、低い声部での完全なtextingは、大陸写本ではまれであるが、英国の慣習では、一般的にコントラテノールと流動的なテナーテノールラインのが好まれていた。 lines. This tendency has been noted by Alejandro Planchart, 'Fifteenth-Century Masses: Notes on Performance and Chronology', Studi Musicali, 10 (1981), p. 29, and Curtis, The Brussels Masses 7 これは英国のSanctus設定のほとんどの島内複写、および英国モデルに近い大陸の複写で見ることができる。 これは通常の大陸の複写では省略されているが、多くの英語の複写、および一部の大陸の複写では、incipitが提供されている。 このタイプの違いの明確な説明は、Bedynghamに帰されるMissa sine nomineからのSanctusの様々な複写に見ることができる。:Trent 93とTrent 90のreadingが、冒頭語の3回のinvocationを担い、オックスフォードのAdditional MS C87 (hereafter Add. は、2回のinvocationと1つのプレインソングのincipitしかない。 8 英語のSanctus設定の場合と同じ状況がここで得られる。ほとんどの島内での複写、および英国に先立つ大陸のreadingは、 'qui tollis'でポリフォニックの設定を開始している。 9 See, for instance, S. W. Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise (New Haven, CT, and London, 1964), p. 54; http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye2-1.htm R. C. Wegman, 'Concerning Tempo in the English Polyphonic Mass, c. 1420-70', Acta Musicologica, 61 (1989), p. 64, and Wegman's review cited above, note FRYE 'S STYLE Sylvia Kenneyが彼女の先駆的なWalter Fryの研究を書いてから今では四半世紀以上経っている。 discantについての過度の強調によっていくぶん損なわれ、その概念がその意味の多くを失うことになったけれども、Kenneyの様式分析は、にもかかわらず、フライの芸術の最も特徴的な面のいくつかの注目を集めた。 しかしながらKenneyは、フライの非常に洗練された様式を一緒に織り込んだ、作曲上の決定の魅惑的なところにもっと深く掘り下げることを大いに控えた。 p196 フライの音楽的意味合いの仔細さと想像性は、今日では、ほとんど認められていない。それでも、ここには並外れた能力と明らかに無限の想像力の音楽家(フライ)がいる。 多くの優れた芸術家のように、Fryeは、実際に非常に首尾一貫している様式的な枠組みの中で働いている間に、自由の感覚と発明を達成している。 Fryeの音楽におけるアイデアとリズムの絶え間ない相互作用と微妙なタイミング感覚への憧れは、それを知れば知るほどに、深まるばかりである。 フライのミサ曲の様式をスケッチする際には、最も小さい構成要素から始めて、そこからそれらが配置され結合されるさまざまな方法を説明するために進むのが賢明なようである。 フレーズは通常短く、強拍上のminimの休符によってしばしば中断される。次の半拍に声が再び入るとき、それはしばしば、Fryeの旋律の慣用句の非常に一般的な要素である3つのパターンのうちの1つである。 最初のものは、より長い音価が続くminimであり、続くのは多くの場合はsemibreveであるが、より長い音符であることもある(例5と7を参照)。 2つ目のものは、当時の音楽では一般的な、三度が続く二度を介した四度の跳躍である(例5を参照)。 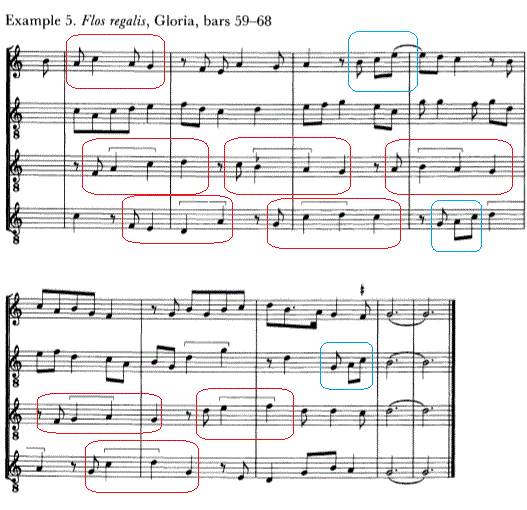 3つ目のものは、Kenneyが観察したもので11、「Fryeの作品の中では事実上の決まり文句であるが、声部がその音域の最低音になり、minim休符で中断されてオクターブ跳躍するものである(下譜)。  11 " Kenney, Walter Frye and the Contenance Anglois p135http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm Fryeで特に頻繁に見られるもう1つの一般的な慣用句、オフビートで始まる付点付きsemibreveもまた、minim休符の後によく導入される。 Summe trinitatiのAgnus Deiには、Fryeがハーフビートで完全breveで開始する例さえある(例2参照)。 Kenney は、旋律様式の制限された性質についてコメントした。彼女は、それはdiscantによって課された制約から生じたと見ている12。 12 " Kenney, Walter Frye and the Contenance Anglois p130http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm メロディ的考えはしばしば,時々正確に繰り返される(例えば、Summe trinitatiのSanctus、discantus bar 27) 。場合によっては、同じ形が2つの部分で厳密に模倣されて繰り返され、短いostinato効果が生じる(例4を参照)。  しかしながら、正確な繰り返しは、しばしばかなり表面的な方法で変化する繰り返しによって、はるかに数が多くなっている。たとえば、Summe trinitatiのAgnus Deiの36〜9小節では、同じフレーズが3回出現する(下譜)。最初のものは、その他2つとやや冒頭が異なるが13。 13 " Kenney, Walter Frye and the Contenance Anglois p134http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm 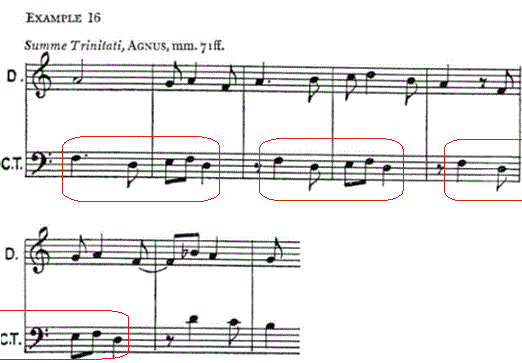 p197 Sanctus of Flos regalisの小節60-2では、より大きなリズムの変化が、両パートでの単純な上昇する三度の形が、それぞれの出現ごとにリズム的に変化するとき、より大きなリズム的多様性が導入される(例1)。 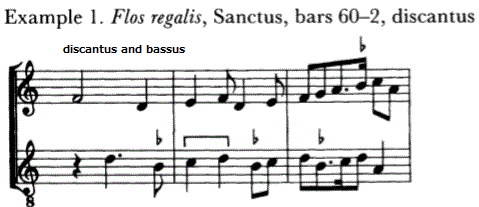 同様の例が、3つのミサ曲にまたがって引用された。作曲家は正確な繰り返しの期待値を設定しているので、微妙な変化の導入はすぐに耳を引き付ける。 他の場合には、あるパートでの繰り返しは、他のパートでの様々な活動によって偽装される。 Kenneyは、このことをGloria of Nobilis et pulchraの第121-5小節で述べている。そこでは、コントラテノールでほぼ正確に繰り返されている音型が、3つの異なる方法で述べられている。 14 14 " Kenney, Walter Frye and the Contenance Anglois p131 Kenney's barring is 153f. http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm  Agnus of Summe trinitatiの第40-3小節は、別の典型的な例を提供しており、そこでは、リズム的に曲がりくねったコントラテノールのラインによるdiscantusでの単純な繰り返し音型を散漫にしている(例2)。  さらに、メロディの繰り返しの原則は、単一の音符、または狭い音域の上限と下限の両方に繰り返し戻るという、より一般的な方法に現れる(例7を参照)。 その最も基本的な形式では、これはostinato効果を生み出す。そして、それはしばしば、続きの旋律発想に強い推進力をつける。 p198 こうした繰り返しの使用は、 Summe trinitatiにおいて生じている。そこでは、cantus firmusの多くの繰り返しのレ音は、それぞれの楽章を通しての規則的な間隔を作る耳でのtagになる。15 15 The same idea also occurs in the contratenor, for instance in the Agnus, bar 3. Curtis's view that Frye's 'interest in the cantus firmus. was not primarily connected with any distinctive melodic character it may have had in its normal form' should perhaps be questioned in the light of such structural exploitation of the contour of a borrowed melody. (See 'The English Masses', p. 71.) Closely similar figures occur elsewhere in Frye's work: see, for instance, Sospitati dedit, bars 26-8 and 49-50, and Nobilis et pulchra, Credo, bars 43-4 (see Example 21). 関連しているがより集中した効果は、デュオの2パート間で同じ音符の繰り返される交替を含んでいる。この効果は、間隔をおいて、デュエットパッセージに構造的な結束を与えながら、繰り返されることができる。Credo of Flos regalisからの例3のように。16 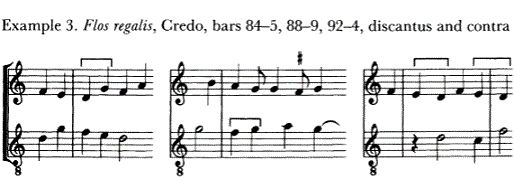 16 Bars 43-6 of the Credo of Nobilis et pulchra (see Example 21) provide a similar example. This passage was cited in the same connection by Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 134.http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm 新しいフレーズ設定を明瞭に表現するような後のやり方での模倣は、少なくとも、フライの様式には重要ではない。パートが休符の後でモチーフを共有するとき、それは常に、効果がしばしば、徹底的な動機の構造化よりもむしろ、アイデアの交換または短い反響のほうが多いデュオのパッセージとなっている。 フライのミサ曲の模倣は、フレーズ内の短いモチーフの交換を含む、通常はるかに細かいものである。このアプローチは、後の時代に普及した模倣を妨げることなく、音楽にまとまりのある感覚を与える(たとえば、Summe trinitati、Gloria、第46〜7小節を参照)。 Fryeが模倣に夢中になるとき、興味の多くはリズムであり、クロスリズムを設定する密接な模倣を伴っている(例4)。  リズムの細かい模倣の例は、 Gloria of Flos regalisの低声部と高声部の短いデュオのコントラストを明確にするのに役立つ。 第54小節では、perfectionの異なる主題においてではあるが、3小節前に、バスが前のデュオを始め、しかし、反対方向に動きながら、discantusが入ってくる。 p199 確かに、旋律的な繰り返しはフライの作品では一般的であるが、リズミカルなセルの繰り返しは、彼のスタイルにとってはるかに不可欠である。 最も音楽的に満足のいくこの例の1つは、Gloria of Flos regalisの最初の部分の驚くべきクライマックスである。そこでは、4声部のうちの3つで繰り返されるリズミカルなパッセージは、自由に変化するcontratenor altus と共に織り込まれる (see Example 5)。 Frye: Missa Flos Regalis - Gloria  Kenneyはまた、このパッセージの強力な効果について、「音楽的効果を強化する矛盾したリズム・スキームの中で、すべての声部を互いに照らし合わせて設定することになるからである」と述べた。17 17 Ibid., p. 134. The passage is quoted on p. 133. http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm p200 リズム的発想は、しばしばテクスチャから飛び出す。特に、ここでのように、それらが支配的な韻律と矛盾するときには。このような戦術は、Credo of Flos regalisのtempus perfectum のbar 42-3の二重分割のように、メロディラインに大きな勢いを与えることができる。これは、discantusを、最もリズム的に装飾されたパッセージの1つに推進する(例6)。 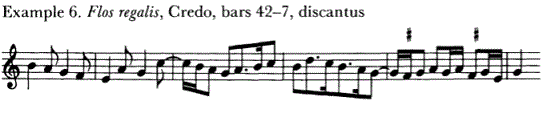 短いリズミカルな発想は、しばしば、1つの声部だけで、より一般的には声楽パートにわたって、それらが間隔を置いて繰り返される特定のパッセージにまとまりを与えるために、非常に賢く使用される。 典型的な例は、モテットSalve virgo materの第12-20小節に見られる。このモテットはおそらく、Summe trinitatiのオリジナルのKyrie のコントラファクタである。下降するcrotchetsが続く付点minimへの跳躍を含む9小節にわたる同じ音型が3回生じている。2回は、discantusにおいて、そして1回はコントラテノールにおいて。 p201 この音型はモテットの後半の3回(49〜50、54、63〜4)に現れるが、第11小節の最初のstatementと驚くほど似た対位法的内容において、まったく同じ形式で、最後の出現時にだけ見られる。 他の場合には、そのようなリズム的な音型は、他の素材によって分離された同様のパッセージを関連づけるために使用される。 リズムの繰り返しの直接的な聴覚的影響は、それが連結して組み合わされるCredo of Flos regalisの第56-9小節のように、構造的な明瞭度を与えるためにしばしば利用される。ここでは、tacticが焦点となる短いデュオパッセージに注意を向け、2つのフルスコアブロックを分割している。その当時の他の作曲家の作品のように、連結はめったに起こらず、この場合のように、通常は下方向に進んでいく。 リズム的な繰り返しはまた、同じ単純なリズム的発想(semibreve rest-semibreve-breve)の5つのステートメントがテクスチャをかなり引き締めているGloria of Flos regalisの最後(第138〜44小節を参照)のように、クライマックス的部分でのまとまりのある感覚を提供するためにしばしば導入される。 このような2回の繰り返しは、同じミサ曲のCredoの一部に鳴り響く終止を与えるのに役立つ。 1回目は2声的発想であり、discantus lineのメロディ形成が3小節後に反転するが、あまり目立たない2回目は、バスで最初に響いた音型のコントラテノールへの同様の反転が含まれている。 (例7)。 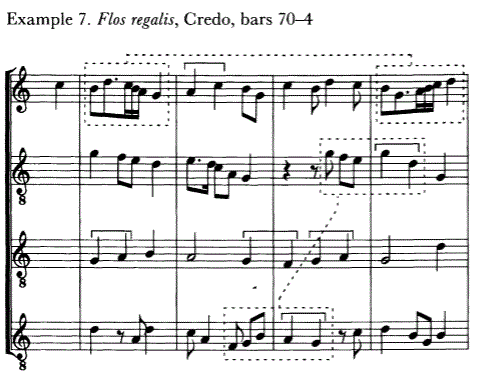 実際、構造を精通していることは、おそらくフライの芸術の最も印象的で洗練された側面である。非常に単純であることが多いメロディックでリズミカルな発想は、彼の同時代の多くの作品に欠けている結束感と構造的な平衡を供与する。 典型的な例は、Missa Summe trinitatiのCredoによって提供されている。 2小節目のテノールで最初に聞かれた短長と繰り返される音符のモチーフは、すぐにdiscantusで繰り返され、その後全体の楽章に浸透していく。冗長になることからかけ離れて、この単純なモチーフは、テクスチャーを飽和させて、単独で起こりそして完全に消えることによって、最大限の思考と抑制で扱われた。 p202 2つのセクションの冒頭長いデュオを除いて、この楽章はほぼ完全にスコア化されている。他にも非常に短い、デュオのパッセージが2つだけある。ここでも、フライは彼の内部バランスの把握を示している。両方の場合において、cantus firmusからレ音を繰り返すことを中心に展開するテノールラインは、レ音からラ音へ上昇しそして再び戻るdiscantusラインと対になっている。 Kenneyは、Flos regalisのデュオでは、同様に、広範囲に、Flos regalisのデュオにおけるdiscantus の構造的な繰り返しについて述べている22。cantus firmusの欠如は、デュオ内の素材のそのような再加工に特定の密着する力を与える。 22 Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 144. http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm テクスチャーの変化によって提供される構造的接合点のこの種の音楽的連接はかなり頻繁に発生し、そして様々な手段によって強調される。 同じ楽章の第2部は、第58小節にもう1つの良い例を示している。そこでは、18小節以上のデュオの導入の後、テノールのエントリが最終的にテクスチャを埋める。テノールが入るソ音は、デュオパッセージのカデンツの音符を提供する。それでもこれは、同じ小節の終わりで、ド音上のさらなるカデンツへの踏み台となる。到着感をさらに強調するために、同じ動きがすぐに両方のパートで繰り返されている(例8を参照)。  p203 減らされたスコアリングの最も明白な効果の1つは、続くフルスコアのパッセージを強調することである。 Fryeがこれを強く認識していたことは、上記の例のように、彼がその構造的な可能性を利用するさまざまな方法から明らかである。彼はFlos regalisにおいて特に独創的であり、そこでは4声のテクスチャ―が、他の3声のミサ曲で可能であるよりも大きなコントラストを可能にする23。 23 Kenney が指摘しているように、減らされたトリオセクションに対するポテンシャルは、ほとんど展開されない。 Kenney, Walter Frye and the Contenance Angloise, p. 145http://machikun.la.coocan.jp/walterfrye4.htm 特に成功した例はグロリアのパート2で見ることができる。そこでは、フルスコアが、さまざまな組み合わせのためのデュオの少なくとも40小節後に最後に導入されている。フルスコアの2小節(小節112)だけが、discantusが、全体のセクションの中で初めて、この音域の最高音である "e"になる。 クライマックス効果は、d''音まで上がったdiscantusとともに、最後のデュオの組み合わせがトップ2声部を含んでいたという事実によって特に強調されているが、それより高くはなっていない。 それが小節の最初の拍に置かれたことは、さらにもっと力強く、到達感を強調している。実際、e "は、他のどの場所でも、焦点を提供するための導入のためには、このミサ曲ではまれにしか使用されない。この可能性が利用される別の例は、Credoの第155小節である。そこでは、小節の冒頭でe''音が、楽章の終わりの前の4小節にだけ、到達の強い感覚を供与している。 Fryeは通常、フルスコアのセクションに強力な到着感覚を生み出すために、機能のネットワーク全体を利用している。そして、彼の微妙なペースとクライマックスの感覚は、ほとんどどんな場合でも説明できる。しかし、グロリアで論議された例が、典型的な4声のFlos regalisでは特に印象的である。先行するデュオの終わりに向かう動きの加速は、シンコペーションと、密接な模倣が組になり、第110小節で、フルスコアのための強い加速を作り出している。 p204 しかし、この時点に達するとすぐに、音楽は雄大なペースで印象的に広がっていく。すでに説明したe "音への上昇に加えて、到達感には、規則的なより長い音価によって、シンコペーションではないリズムによって強調されている。Discantusの繰り返されるb’音は、このエントリーをグロリア内の他のほぼすべてのdiscantusと関連させるために、より広い構造的機能を果たす。(bar 21と35)。そして、その他の重要な瞬間を裏付ける。(例えば、bar127-8)。 Fryeの様式の並外れた統合は、今や明らかであるはずである。それは、彼が彼の音楽的なリソースを完全にコントロールしたミサ曲ターとして際立っている特徴である。これらのミサ曲との親密さを深めることは、微妙で洗練された彼らの限りないfundで自分の賞賛を増すだけである。同じ心の産物としてはっきりと認識できるけれども、フライのミサ曲は,彼の独特の慣用句の異なる強調を示している。そのような区別は、3つの作品の相対的に時系列的なある発想を与えるのを助けるかもしれない。 1468年の、Charles the BoldとMargaret of Yorkの結婚のためのブリュッセル写本の核の編纂は、Rob Wegmanによって示されたように、少なくとも作品のterminus ante quem ( the latest time the event may have happened)を供与する。 おそらく驚くべきことに、3つのミサ曲にまたがるスコアの傾向を考慮すると、Nobilis et pulchraが、他の2つとは、それらの間の最も印象的なスタイルの違いにおいて、別物になる。 Summe trinitatiとFlos regalisの様式の一貫性と優雅さは、Nobilis et pulchraにはかなり欠けている。それは、比較すると、まだ本当に足を見つけていない作曲家の作品のように見える。 この、やや初期の作品としての印象は、コントラテノールのスタイルによって示される。これは、真のコントラテノールであるaltus et bassusで、 bars 13-14 of the Agnusにおけるように、継続的にテノールと交差、再交差している。そこでは、オクターブと四度以上にあり、非常に短いperiodにわたって、多くのgroundをカバーしている。 1450年代の、そしておそらくだいたいその時期に、ベディンガムによるミサ曲のような、その時代のそのような他のイギリスの作品と年代順に並べることは、適切であるように思われる。 p205 比較すると、Summe trinitatiのコントラテノールは、大部分がテノールの下に保持され、それが和音を支えている。このようなコントラテノールのふるまいの対比は、それ自体が時系列的な区別を提案するための粗っぽい特徴となるが、それらはテクスチャや動機様式に対するまったく異なるアプローチの徴候である。さらに、そのような対比を描くことにおけるそれらの価値は、他の示唆的な区別を示す同じペン(作者)からの作品を扱っているときに増加する。 これは当時としては、非常に進化した作品である。なぜなら、TrentC 88に関連するモテットSalve virgo materは、おそらく上記で概説したように、ミサ曲Summe trinitatiのキリエのコントラファクタであると思われ、1462年より後の作品と思われるからである。25 Flos regalisは、4声のためにスコア化されたごく少数の英国のミサ曲に属している。作者不明のミサ曲CaputやVeterem hominemは、無傷で現存している唯一の疑いのない仲間である。26 このスコアリングの一致は、何人かの作家に、作品間の密接な比較をする試みをした27。しかし、Flos regalisとその他の4声循環ミサ曲の間で、大きな類似性を見出すことは困難であった。 p206 Caputミサ曲は間違いなく大きな達成であるが、Flos regalisと比較するとその様式はかなり時代遅れに見える。 フライミサ曲の一貫性、ペーシング、構造およびより統合されたテキスチャーは確かにより後期に属し、そして2つのミサ曲が15年、さらには20年よりもはるかに短い期間で括れると考えるのは困難である。 Flos regalisは、1468年の祭典のために複写されたときには、当時かなり新しい作品だったようでである。 THE BRUSSELS ANONYMOUS MASS(90v-99r) 作者不明のミサ曲(90v-99r)(Sine nomine)を評価する際には、最初からFryeに帰せられるミサ曲からそれを決定的に区別する1つの基本的な構造上の特徴があることを認識しなければならない。フライに関しては、むろん、借用したメロディに基づいており、作者不明の作品は、自由に作られている。 この区別は、Fryeが彼の借りたメロディーに非常に忠実に執着しており、少なくとも2つの3声ミサ曲では、それぞれの声明について非常によく似たリズム形式を保っているので、さらに際立っている。 とは言っても、これらのミサ曲のテノールは、一枚岩ではなく、多くの初期の循環ミサ曲のような長い音符の形式ではない。実際、借用した行のリズムは、作者不明のミサのテノールと同じくらい、付随するパートの性格とほぼ同じくらいよく一致している。そして、その帰属なし作品はcantus prius factusの背景を欠いており、3声の帰属ミサ曲のように、少なくとも3つの中心的な楽章がかなり一定なパターンを取る構造的なグランドプランを持っている28。 この時代のイギリスのミサ曲に典型的であるように、グロリアとクレドの間の強い類似性は特に強く、楽章を超えて対応する主題の間の動機付けの関連は決して異常ではない。例えば、グロリア(30小節)とクレド(44)のフルスコアセクションで見られるように(例9)。 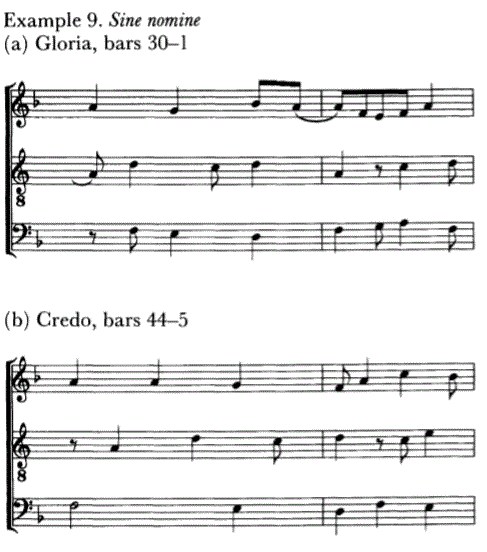 cantus firmusの存在または不在は、明らかに関係するミサ曲の機能と大いに関係がある。そして、確かに、prosula Kyrieを伴う大規模な祝祭ミサ曲は、控え目な、週日用の、あるいは随意の作品よりも、借用されたメロディーに基づく可能性がはるかに高いことは、確かに真実である。 p207 この重要な区別にもかかわらず、フライに帰せられたミサ曲から作者不明の作品に直接目を向けると、すぐにおなじみのgroundを感じる。表面の輪郭はすぐに認識可能である。 これは確かに、作品の本来の機能が、それが他の何かであることを要求しなかったためである。 旋律とリズム様式の類似点は至る所で明白である。 Fryeに帰せられたミサ曲(p。196参照)のように、フレーズは一般的に短く、拍の最小休符で分割されている。 Fryeのミサ曲に似たようなつながりからよく知られているパターンの1つを伴うこのような中断の後で、流れがしばしば始まる。長い音符が続くminim、二度→三度と上方向に移動する四度(例10)、あるいは声部がその範囲の最も低い部分に移動したときからのオクターブの飛躍(例14参照)など。 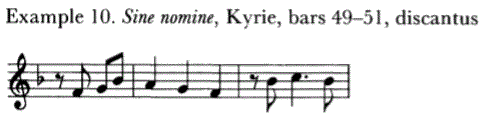 p208 このミサ曲の3声の制限されたメロディ様式とリズム統合は、フライに帰されるミサ曲よりもさらに顕著である。それでもフライはより控えめな規模で活動していますが、作者不明のミサの作曲家はしばしば、彼の建築感覚を強く感じさせる。帰属作品のように、旋律的でリズミカルな発想は、しばしば、クライマっクスの瞬間に注意を向けるか、賢明な繰り返しを通してセクションのまとまりを与えるかのどちらかで、構造的な主題を作るために計算されているように思われる。 旋律的な発想の正確な繰り返しは、時々、普及した韻律の範囲内ではあるが(例14参照)、それほど頻繁には起こらない(例11)。 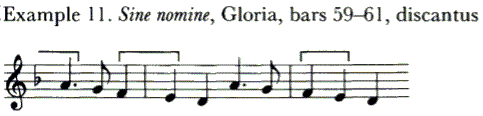 帰属ミサ曲のように、あるパートの繰り返しの効果は、ラ音からファ音の間でホバリングしている(例12)Credoの第13-15小節のように、コントラテノールの繰り返し音型が、テノールとdiscantusの間でのリズム的模倣に対抗している時には、他のパートの微妙な変化によって巧妙に覆い隠されることがある。。  単一の音符または音程に対するこの種のつきまとうような集中は、4つのミサ曲すべてに同様に散在している特徴である。 Agnus IIの同様の例は、discantusとtenorの両方で強烈に反復的な音型を使用しており、音楽をそのセクションの終わりに向かって前進させるダイナミックな効果を生み出している(例13)。 Fryeのミサ曲と同様に、同じ種類の音符または音程の周りをホバリングしているこの種のパターンは、明確な繰り返しよりもはるかに一般的である。 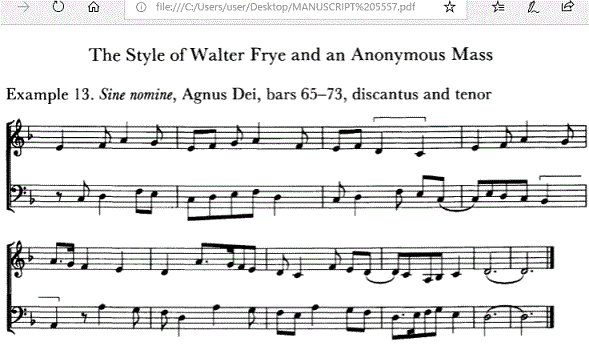 p209 作者帰属のあるミサ曲のように、様々な繰り返しは、しばしば マイナーなやりかたで起こり、正確な繰り返しよりも一般的であり、複雑な聴覚的インパクトを作る。正確な繰り返しは、しばしば耳を魅了し、継続され、他のパートを通して溶解し、発散している。大きなまとまりのパッセージを借用しながら。 例14は、Agnus Dei Iからのこの効果的な例を示している。  p210 正確に繰り返されるトロカイックな下降音型は、他の2つのパートもまた引っかかるように下降する一連の段階的な音型を動機付ける。その結果、力強い到着感覚に従った最後のカデンツが得られる。 フライのミサ曲のように、模倣はしばしば、構造的なバックボーンが考えられるパッセージを貸すことができるより徹底的な動機の統一の一部に過ぎない。 グロリアの第2部の終わりに向かって、特に効果的な事例がしょうじている。そこでは、discantusにおいて予見される短いモチーフが、その終わりに向かうセクションを動かして、他の2つのパートに広がる前に、テノール内で繰り返され、断片化されている(例15)。 この作品では、Fryeに帰する3つのミサ曲よりも、明らかな模倣が目立つことはなく、この3パートすべてを含む事例はまれである。繰り返しますが、それが現れる時は、それは普通はデュオのフレーズの中にあり、そこでは2パートを動機的に結び付けるのに役立ちつ。エントリ間の間隔が近い場合、まとまりの効果は特に強くなる。 このような綿密な模倣は、Sanctusの最初のセクションの終わりに向かって強力な原動力を生み出す。そこでは、興味深い5つのminim単位で降順に統一感覚が高められる(例16を参照)。 3パートすべての間の模倣的な交換は、ないわけではないが、非常にまれである(例えば、Credoの小節17-18のように)。 すでに引用された例を見れば、このミサ曲の動機的な相互関係への関心の大部分が、Fryeのものと同様にリズミカルであることを確認するすれば十分であろう。確かに、一般的には、リズミカルな繰り返しは、全4作品の中で最も基本的なまとまる力である。 作者不明のミサ曲では、フライの3曲のミサ曲のように、頻繁にシンコペーションされ、前の例のように基本韻律から遠ざかってリズミカルなパルスを揺らすことによって、注意を必要とすることがよくある。リズムの模倣の例は、明確なメロディのcorrespondenceがあるそれよりはるかに多い。そしてクレドは、2つのパートが短いリズムによって一緒に織り込まれる、第35-40小節で素晴らしい例を提供している。 p212 ここと多くの同定されたミサ曲の場合、このパッセージは構造的な影響を与えると計算されているように思われる。この場合には、以下の完全にスコア化された「Et incarnatus est」の設定を強調している。ここは、この楽章のセクションを決定づけるところである。 より特殊な事例では、Missa Nobilis et pulchraのSanctusにあるコントラテノール内の付点semibrevesの奇妙なシンコペーション的パッセージが、作者不明のマスの同じ楽章のテノール内の同様の事例によって反映されている(例17)。 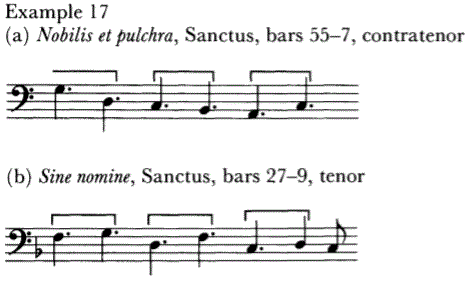 作者不明の作曲家は、Fryeと同じように、最も単純な音楽デバイスを使用して、彼のミサの一部に統一感を与えることができる。 Fryeが単調な短長の繰り返された音型とともに音楽的織物を織り込んだMissa Summe trinitatiのクレドのように、作者不明のクレドは、繰り返された音符によって同じくらいの、それほど雄弁ではないが、まとまりを得ている。 これらの大部分はラ音にあり、その後には常に、ファ音やミ音への下降進行が続く。そのような繰り返し音型は通常、第67-74小節のように、問題の音符ラ音への執拗な回帰を促す(例18)。 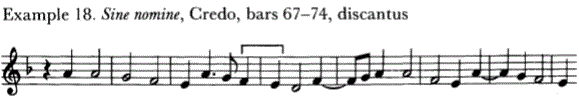 2つのケース 'Et resurrexit'(小節67)と 'Et iterum'(小節87)では、音型は同じ形式になるが、 'Et incarnatus'と 'et in unum'でのように微妙に変化させられている。 p213 テキストの歌詞づけを読み過ぎる誘惑にときどき駆られる。フレーズセットが単語 'et'で始まるこれらすべての場合(および 'et vitam'の場合)に注意する価値があるが。ソースでの強調は、さらに、一般的に非常に特殊である。実際、「クレド」でのラ音で始まる下降音型の繰り返しの使用は、より徹底的なモチーフの統一の一部を形成することが判明しており、Flyeのミサ曲の場合と同様に、この作品全体の中でも特に印象的な特徴となっている。同じようなモチーフはGloriaにおいても顕著であり、より少ない程度に全体のミサ曲の味付けとなる。 COMPARISON WITH OTHER MASSES Fryeによるミサ曲と、ブリュッセル写本における作者不明の組み合わせとの間の広範囲にわたる様式的な関係は、今や疑う余地がない。しかしそのような比較は、説得力があるが、単独では有用性が限られている。関連する、あるいは一般的なauthorship の提案は、当時の作品と照らし合わせてチェックする必要がある。Tinctorisが、15世紀半ばにイギリスの音楽が単調に統一された状態であるとさげすんで見なしたことについて、ここでは特に緊急と見なされるかもしれない懸念へのチェックも必要である。 ブリュッセルの作者不明者に関連するミサ曲を探すための最も明白なエリアの1つは、当初は、John Bedyngham(?-?1459/60)の作品であると思われるかもしれない。結局のところ、彼の名前は、Fryeの名前と共に、15世紀半ばの2人の主なイギリス人の一人として最も頻繁に言及されたものである。それでも、Bedynghamの2つのミサ曲は、Fryeのものやブリュッセルの作者不明のミサ曲とはほとんど似ていない。それらのテクスチャは全体的に密集しており、部分間の動機的な相互接続はほとんどない。そのような違いは、Trent 93と90のBedynghamのミサ曲のためのはるかに早い複写日付を考慮してほとんど驚くべきことではなく、10年から20年の年月が、作者不明のミサ曲とSumme trinitatiから(Bedynghamの)作品を分けたものと考えてよいであろう。 p214 実際、時系列は、ブリュッセル写本中のミサ曲の内容を見つけるための最も深刻な問題の試みを示している。それらを比較するために現存している1460年代の明らかな英語のミサ曲はほとんどない。写本自体の外にある可能性のある候補の1つは、StandlyによるStrahov写本の中のMissa sine nomineである。しかし、この非常に控えめな作品は、フライや作者不明ミサ曲からはまったく異なるモノである。フライや作者不明ミサ曲にあるのテキスト的関心やリズムや動機の洗練さをまったく欠いている。 リチャード・コックスやジョン・プラマーによるブリュッセル写本の2つの循環ミサ曲は、残念ながら、完全に現存するほとんど唯一の当時の英国のミサ曲である。しかし、これらのどちらもFryeまたは作者不明の作曲家による作品とも共通点があまりない。コックスのミサ曲はデュオのテクスチャーに対して比較的メロディ豊かな上声部を対抗させている。デュオのテクスチャーは大体同じ進行の一連の複雑な繰り返しから成り立っている。それは、音響とホモフォニックなテクスチャの驚くべき強調を伴っていることをアピールする作品である。動機と構造の卓越さにおいて、より洗練された組み合わせにアプローチすることはできないが。 PlummerによるSine nomine massは、その一方で、より後の日付ではないにしても、少なくとも発展の後期段階に属する。その精巧な細工の表層は、Eton Choirbookに含まれるものの先駆けである。 明らかに、様式の点で、精査中のミサ曲により密接に関係しているのが、PlummerのMissa Nesciens materの残りであり、その一部はロンドンの大手図書館、British Library Add.54324に残っている。 しかし、そこには少なくとも、フライと作者不明のミサ曲から非常によく知られている声部の間のリズム統合の提示があるが、類似性はせいぜい表面的である。さらに、cantus firmusを担うテノールは、フライのミサ曲では比較的稀な、比較的長い音符で動くことが多く、動機的統一の試みの提示はほとんどない。 p215 ブリュッセル写本と同じ時代から現存する唯一の北の方の写本は、もちろん、断片的なLucca Choirbookである。確かに、このソースの最も初期の段階は、大部分が英国のミサ曲からなり、明らかに1467 and 1469年の間で複写された。したがって、ブリュッセル写本の英国部分とちょうど同時期となる。 CaputやQuem malignus spiritusのようなこれらのミサ曲の中には、明らかにその起源自体よりはるかに早いものもあったが、当時はかなり新しいものもあった。それらは複写された。特に1つの作品は、フライと作者不明のミサ曲との比較の下で精査されている。Missa Alma redemptoris mater は、ルッカ写本では、Credo, Sanctus and Agnus が現存している。 cantus firmusの自由なパラフレーズは、この時期の4声の英国のミサ曲では一般的ではなく、この作品の表面に、そのcantus firmusの表現がstatementごとにリズミカルに変化するMissa Flos regalisのそれとある程度の類似性を与えるのに役立っている。 頻繁にシンコペートされたリズムスタイルはFryeを彷彿とさせる。だが、フライとは対照的に、繰り返しや連続的な楽想は、Reinhard Strohmが指摘したように、ある程度はPlummerのミサ曲を彷彿とさせるが、Fryeのテクスチャを非常に際立って結び付ける目的と統合を欠いている。 THE FRAGMENTARY MASS IN LUCCA しかし、 フライとブリュッセルの作者不明ミサ曲との一過性の類似点をはるかに超えるLucca Choirbook 中の別のミサ曲がある。それは、驚くことではないが、この記事の冒頭で述べたフライによる断片的な作品である。 それはKyrieのdiscantusラインだけが現存している。そのプロファイルはすでに議論された4つのミサ曲のそれらと完全に一致している。同じ絶え間ないシフトや強くシンコペーションされたリズムは、同じ音符への一定のリターンを含むおなじみの響きのパッセージで制限された音域にひっかかっている。 p216 元のテキスチャーの残りは失われているが、Brian Trowellは、(このKyrie断片のみのミサ曲の)discantusラインが、FryeまたはBedynghamのsong So ys emprentidのテノールに完全にフィットすることを巧みに発見した。 2声の作品は、歌のコントラテノールを少しパラフレーズすることによって完成することができることにも気付いたので、Trowellは、Kyrie全体の非常に説得力のある再構成にたどり着くことができた。結果的にこの作品は、歌全体の興味深いユニークなパラフレーズとなっている。 しかし、この作品には、ブリュッセルの作者不明のミサ曲とさらに密接に関連する側面がある。これらのもっとも直接的な特徴は、その構造である。 このKyrieとブリュッセルのミサ曲の両方は、Christeの2つの設定を持っていて、そのフォーマットは、最初のものから始めて、呼び出しが交互にある交替演奏を要求し、プレインソングを歌っている。 この特徴は、これらの作品を、初期のTrent Codicesや他の場で、多数のセクション構築された独立した9回のKyriesに関係している。循環ミサ曲におけるその適用(ルッカフラグメントが確かにその一部である)は非常に珍しいが。 この特徴だけでも、2つの作品の間のある種の関係を疑う理由として少なくとも一見したところではあるが、よく見るとそれらの類似性は、より明確に焦点を当てている。 2つの作品のヘッドモチーフ(例19を参照)は非常に似通っており、その冒頭音型はもちろん、15世紀の音楽全般で最も一般的な冒頭プロファイルの1つですあるが、例が示すように、最初のセクションだけでなく4つのセクションのそれぞれも、それぞれの場合で非常によく似ている。 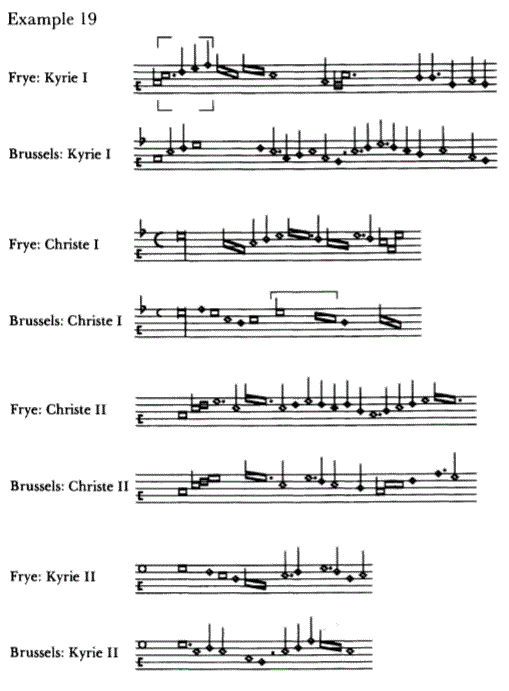 これは、第2Christeの場合に、特に明白である。そこでは、ブリュッセルの設定は、その長さの大部分を通してルッカのそれに類似した輪郭に従う。 ブリュッセルの作者不明のミサ曲の他の楽章は、一貫したヘッドモチーフを使用しているが、ルッカ写本のdiscantusのプロファイルとさらなる類似点を示している。そしていくつかのケースでは、これらはさらにKyrieのものより似ている。 その好例が、ブリュッセル写本での第1Agnusのinvocationの設定である。これは、例20のLuccaと比較される。同様の類似点は、他の楽章でも見られる。  p217 疑問はむろん、残っている。このような類似性は、どのようにして生じてきたのか? ある作品が別の作曲家によって他の人のモデルとして使用されたことは考えられるが、それらが異なる(人の)心の中で偶然に生じたと考えるのは困難である。 p218 もしこの可能性が許されれば、Frye のSo ys emprentidでのdiscantusへの依存を考えると、エミュレータはきっとブリュッセルミサの作曲家でなければならないであろう。しかし、同じソースの中でブリュッセルのミサ曲の質とFryeの組み合わせとの明白な類似性を考えると、このシナリオはありそうもない。 もう1段階進んで、2つの作品が同じ作曲家によるものであると認める場合、一方がもう一方に関係なく作曲されていると考えることは可能であろうか? これはありそうもないようだ。よく似た2つの循環ミサ曲を一緒に書いていた作曲家が、その時、彼の心に浮かんでいた無意識のうちに再利用された楽想を持つことができることはもちろん不可能ではないが。ここで重要なのは、これらの作品は同じ作曲家によるものであり、その作曲家はWalter Fryeだったということなのだ。 SOSPITATI DEDIT それでもジグソーパズルの2つの重要な部分が欠けている。第1に、ブリュッセルの作者不明のミサ曲は明らかに自由に作曲されているが、Fryeに帰せられたミサ曲は、先に述べたように、体系的に借用された素材に基づいている。そして第2に、ブリュッセル写本での作者不明作品の声部の配置が、フライの他のミサ曲のそれとは異なる。これらの問題の両方のcontextは、Fryによる別の作品、彼のモテットSospitati deditで見ることができる。 この作品も、もちろん、借用された素材を利用している。それはProse for the Feast of St Nicholasである。それは、 英国の長い伝統であるmigrant cantus firmus 設定とつながっており、声部間を自由に行き来している。 チャントは、声部から声部へとさまようことが許されるだけでなく、時々非常に希釈されるので、Sparksが示したように、それが実際に存在していることを証明することは困難である。極端な例、 Kyrie on Soys emprentidの事例では、Reinhard Strohmが指摘したように、完全に存在していた歌のパラフレーズであり、15世紀半ばの現存レパートリーでは唯一のものである。 p219 Fryeは、テノールの cantus firmusの基本原則をはるかに超えて、借用した素材のリワークに対するさまざまなアプローチをはっきりと理解することができていた。そして、ブリュッセルの作者不明のミサが、その広範な繰り返しと楽想の再加工によって、既存の音楽を見えなくしている可能性もある。また、既存の音楽を隠している。
最後にメロディスタイルに目を向けると、最も目立つ特徴は、ブリュッセルの作者不明およびルッカフラグメントのミサ曲でも使用されている一般的なヘッドモチーフの定式である。しかし、おそらくもっと重要なのは、Fryeが、既存の素材のサポートの有無にかかわらず、大規模で首尾一貫した音楽構造を作成する能力のある音楽建築家であったという見方である。 テノールをテクスチャーの最も低い声部に置いたブリュッセルのミサ曲の、声部のはっきりした、めったに重ならない音域は、フライに帰せられたすべてのミサ曲から、この作品を切り離している。 テクスチャー配置の観点から考えられた作品のうちで最も似た作品は、Missa Summe trinitatiであり、このミサ曲の声部は一般的な音域において異なっているが、15世紀後半の3声テクスチャの標準的配置に続いて、最下声部がコントラテノールとなっている。 ブリュッセル写本中のPlummerのミサ曲は、テノールをテクスチャの一番下に置くという作者不明のミサ曲の慣習に従っている。ただし、このミサ曲は他の点では非常に異なり、はるかに精緻な作品となっているが。 対照的に、作者不明のミサ曲は、その単純でリズミカルに統合されたスタイルと、ほぼ完全に異なる音域のテノール、mean、treble,の配置から、オールドホール写本でのスコア形式の単一楽章にまで遡る単純なdiscant設定の伝統に近いように見える。これもまた、このミサ曲を、Pepys Manuscript(同じく単純な、層状のテキスチャーの作品で占められていることで知られているソース)に現存しているSospitati deditと密接に結び付けている。 ミサ曲とSospitati deditによって共有されるc1 c 3 c 5の非常にまれな音部記号の組み合わせは、PepysのAlleluia設定の小さなグループでも見られる。実際、メロディとテクスチャーの輪郭に関して、Sospitati deditはさらに、 3つの既述のフライのミサ曲よりも作者不明のミサ曲への密接な族関係を示している。 2つの作品はそれぞれのパートで緊密に配置されたテキスト設定やいくつかの和音の詳細にも関連している。どちらも同じようにささやかな作品のように平行五度にはこだわらず、そして、声部交差の忌避は、不変的に、vii6-I型の進行(訳注;ランディーニ終止)に続くようなカデンツとなる。 p220 しかし、これを超えて、一般的なリズムと旋律のプロファイルは、帰属されたものや作者不明のミサ曲を調べた後、よく知られるようになっている。典型的なリズムの繰り返しを伴う高度にシンコペーションされたラインは、そのラインが短い時間内にひとつの音符に対して繰り返し行き来するような頻繁なパッセージと結びついている。 より詳細なレベルでは、例21で示されているタイプの、ひとつの音符を中心にした執拗な繰り返しの旋回は、ミサ曲における同様の音型を同時に呼び起こす。 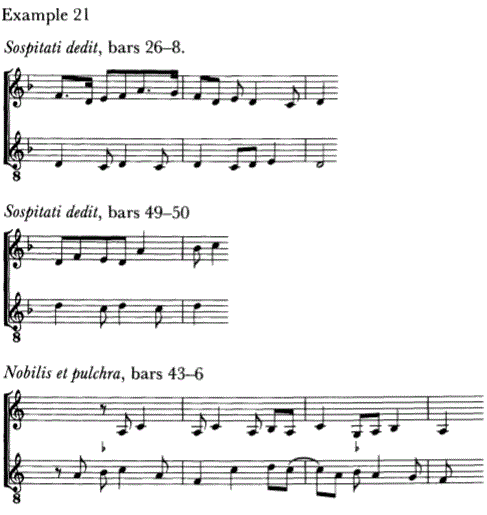 結論として、ブリュッセルの作者不明ミサ曲は、Walter Fryeによる関連する作品群の一部である可能性が非常に高いように見える。 しかし、ブリュッセル写本での立場を考えれば、こうしたニーズはほとんど驚くことはない。ここで我々は、 音楽における強い興味を持つ大立者に対して編纂されたソースを持っている。それは英国の王女との結婚を祝う儀式と関連した、フライを含めた英国ミサ曲の大規模な核をともなっている。 さらに、写本は少しずつ集められたが、作者不明のミサ曲は、同じ紙工場からの元の核のそれに明らかに関連した、そして同じ宮廷で使われた紙の上に複写されている。写本の元の核は、フライの芸術へのチャペルの認識、それが現れ、維持されるべき認識のために期待されるのと同じくらい明確な実例を供与する。 |