| Modal Discourse and Fourteenth-Century French Song: A 'Medieval' Perspective
Recovered? 2 Author(s): Sarah Fuller |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p85 THE MUSICAL READINGS クリスチャンバーガーが構築した精巧な理論モデルは、中世の音楽家らが楽譜に持ち込み、演奏に取り入れた mental habits の回復を中心的な目的としている。
特に彼の興味を引くのは、臨時記号の解釈であり、一貫して旋法とヘキサコードの決定要因にリンクしている。 「ドリア旋法での臨時記号の解釈は、相互に補完する旋法とヘキサコードの視点間の密接な相互作用によってstampされる」65 p86 既に指摘したように、記譜された臨時記号は、14世紀のポリフォニー内の旋法の操作に対するBergerの信念に対する特定の脅威を提供する。 その信念がどこに導くのかを完全に理解するために(彼の特定の定式化で)、彼の分析と転写を調べ、両方の観点からそれらを精査する必要がある。 彼が提案する音楽テキストと、彼が中世の歌手に帰属するパフォーマンス戦略の観点から。ここで議論するために選択された例は、必ずしも数が多くはないが、それらは代表的なものであり、彼の研究を通して繰り返される分析、理論的説明、転写のパターンを示している。 ソースに記された臨時記号に対するChristian Berger's の反応には、2つの動きが含まれる。 1つ目は、結果が旋法の固有性に反するか、inflectionの対位法的正当化が見られないか、またはその両方であるため、1つ以上の表記された臨時記号の「通常の」解釈の拒否である。66 2つ目は、臨時記号をヘキサコード構成のシンボルとして解釈し、それらの根拠に基づいて正当化することである。 <L'ardent desier> たとえば、3声バラードL'ardent desierのclosの終わりと2番目のセクションの始まりの接合部を考えてみよう。67 写本は、cantusがclosのcからf#に上向きに跳躍していることを示している。 次のフレーズ(例8a)の始めに。 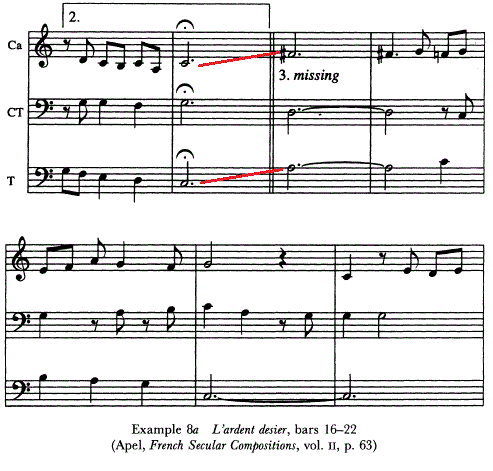 Bergerは、カントゥス旋律の三全音が”前のセクションとの関係をbreakする”、そして、”対位法的正当性がない(テノールがaに跳ね上がり、カントゥスgが少し遅れて行に来るため)”という背景で、f#に抵抗している。68 p87 彼は完全に全音階的な解釈を提供している。カントゥスfの'square b ' 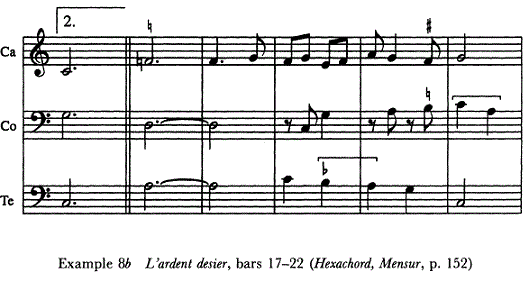 彼が認めているように、ここでサインが必要な理由を正当化するのは困難である。ソルミゼーションに精通している人なら、スクライブがカントゥスのこれらの十数音符をサインなしで残しそれらは自然なヘキサコード内によく収まるであろうことは理解することだろう。 Berger が考案する可能性のある説明は2つある。1つ目はカンタスの Both parts of this explanation seem contrived. この説明の両方の部分は不自然なようである。 第18小節のf#の不適切さについての彼自身の観察によれば(全音階基準で定義されている)、カントゥスの歌手は、記譜記号を通して明示的に指示されない限り、そのピッチをinflectionするようなことはない。 状況によっては、サインが「注意」になることはほとんどない。求められた結果が実際にそのピッチのinflectionでない限り、fの前に テノールへの影響については、第20小節に編集用のb-rotundum を導入してテノールのソフトなヘキサコードを考案したのは、筆記者ではなくベルガーであることに注意すべきである。 さらに、歌の声部はもちろん 、スコア形式においてではなく、各パートが別々に書き込まれている。 カントゥスの歌手が見ているサインがテノールの歌手が自分の役割をどのようにソルミゼーションするかの指示であると主張することは、 stretching credibility rather far to claim。 <Ane afagos> 論理の弱点に加えて、このゆがんだ説明は、バラードAne afagos (両方の独自のソースでL'ardent desier から近いフォリオにある)からの同様のパッセージにtransferableなものではない。バラードAne afagos では、コントラテノールは平行するcantusのinflectionをサポートしているのである(Example 8c).。 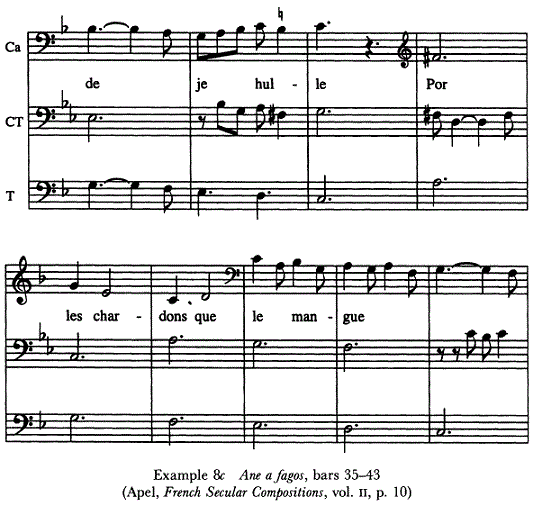 p89 <L'escu d'amours> これがad hoc(その場しのぎ)な理由の孤立したケースでないことは、作者不明のバラードL'escu d'amoursの冒頭へのBergerのアプローチにおいて示される。そこでは、 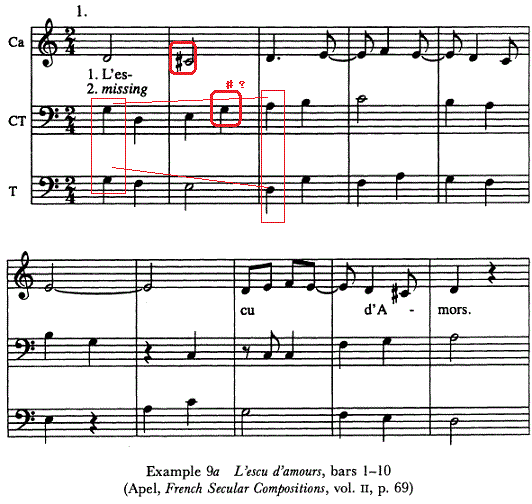 Bergerは、第2小節のc♯は生じ得るがそれはコントラテノールのG♯に必要な音符である、ということを許容している。 彼が拒否するこのinflectionは、Tenor-Contratenor のペアによって最初の3小節で実行されるGからD-aへの移動を妨害し、第3小節のDの五度上のaを過度に強調している。72 したがって、コントラテノールへの不利な効果のために、カントゥスの第2音の♯を額面通りに取ることはできない。 その意味合いは、cantusの後続から議論する必要がある。そのcantusは、最初の10小節ではc-fの四度内にとどまっているのであるが、第14小節以降では、(低い)やわらかいヘクサコードに移動している。 p90 「cantusの冒頭の 彼の編纂は全体的に全音階的であり、歌の冒頭はinflectionされていない(Example 9b)。 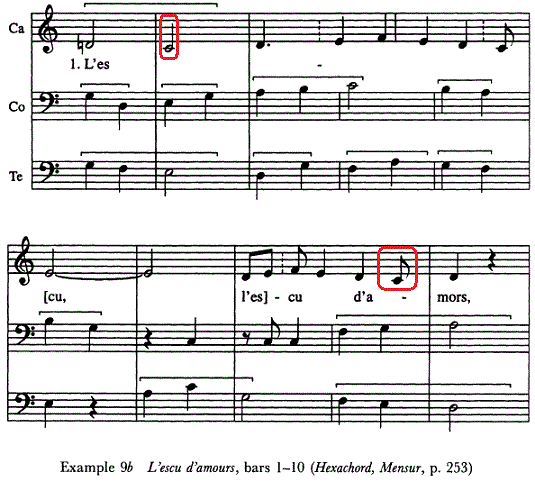 Bergerの例 ここでは、記譜法論理、対位法的知覚、分析的評決の規範がすべて引き伸ばされているように見える。カントゥスは最初の13brevesで自然なヘキサコード内にとどまるため、そして下部声部のソフトなヘキサコードへのその後の移動は通常のpermutationのみを含むため、スクライブが2番目のbrevesでのハード/ナチュラルなヘキサコードをシグナルする(コントラテノールの第2小節でソを♯化する)ことは、まったく余計だと思われることだろう。 p91 記号がなければ、cantusは問題なく、自然のヘクサコードでソルミゼーションされることだろう。 cの記譜された上昇は、第2-3小節でのcantusとテノールの間の長六度からオクターブへの進行を保証するものとして、対位法的に正当化され得る(例9c)。74 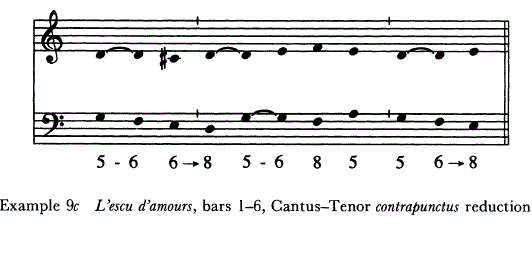 p92 このinflectionに対するBergerの拒否は、主要なcontrapunctusデュエット(カントゥスとテノールの間)に対する二次的な関係(テノールとコントラテノール間の関係)を優先し、カントゥスの歌手が彼のパートをどのように解釈するかを、他の別々に記された声部が決定することを示している。 第2小節での上昇したコントラテノールのG♯が基本的な調性関係を乱し、続くコントラテノールaの余分な突出をさせるような分析的判断については、正式なサポートはない。 なぜ第1〜3小節でユニゾンGから五度D-aへの tenor-contratenor の動きが、G-d 五度から長六度を通ってD-dオクターブへと進行する慣習的な cantus-tenor の対位法的進行よりも優先されるのか? 特に、いわゆる「二重導音カデンツ」がars novaの音楽で発生する頻度を考えると、コントラテノールaに対する過度の強調をどう保てるのか?75 75 (TENDENCIES AND RESOLUTIONS: THE DIRECTED PROGRESSION IN ARS NOVA MUSIC1 Sarah Fuller参照。cantusがc♯を歌えば、contratenorのGは必ず♯にならなければならないという問題がある。 L'escu d'amoursがD-ドーリア旋法に投射されるという仮説から離れて、第2小節でcを♯化させないBergerの説明、そしてヘクサコードマーカーとしてのcの前の 76 Hexachord, Mensur pp270-3 ,Bergerは、cantusのdの冒頭に <Fuiies de moy> また、Fuiies de moyでは、旋法整合性の先入観が、Bergerの表記法の解釈に決定的に影響を与えている77。この歌は、Cオクターブと五度でいったん終止するが、カントゥスには「signiture」がないために、旋法概念の理論についての問題が生じている。テノールとコントラテノールパートは、双方ともB♭とE♭の「signiture」を保持している。(例10a)。 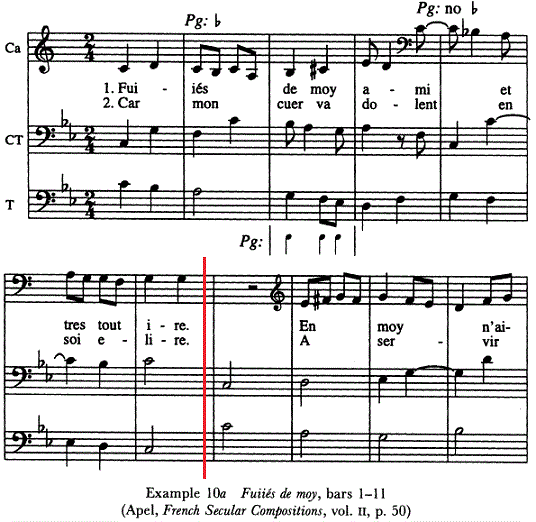 p93 Bergerの転写はカントゥスをより低い声部に合わせていて、そのために、すべてのeとメロディのほとんどすべての 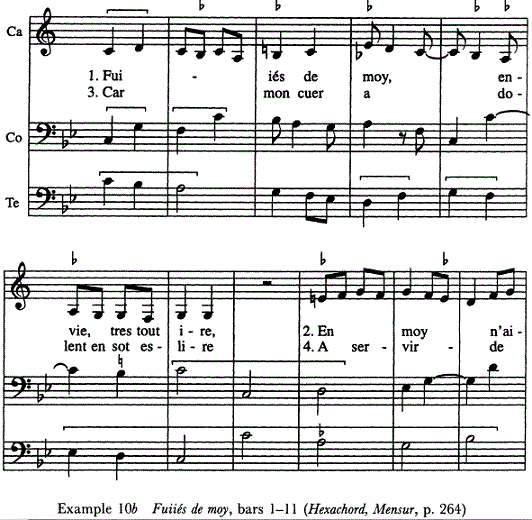 Bergerの例 この場合の彼の主張は、「カントゥスには署名がないが、BとEの2つのフラットの署名は、intellectualis transposicio [mental transposition](The Origin of the Coniunctap90)を通してcantusにも有効である」とのことである。79. intellectualis transposicio という用語を Berkeley Anonymous に帰するという脚注は、この概念に真に中世の風味を与えている。 しかし、Bergerが採用しているその感覚は、この用語がcantus行についての解釈に対する歴史的正当性を無効であるとするその創始者Berkeley Anonymous のそれとは本質的に異なっている。 p94 Berkeley Anonymous は、グイドの手では利用できなかったhalf-stepsを供給する音階内に挿入されたエキストラなピッチであるconiunctaeについての彼の思考の過程で、intellectualis transposicio と言う用語を導入している。80 80 理論家によって進められたconiunctaの2つの定義の1つは、それが適切な場所の上または下のある場所へのヘキサコードのintellectualis transposicio [mental transpositionであると指定しているThe Origin of the Coniunctap90 Berkeley Manuscript pp52-4 このintellectualis transposicio の概念を通して、新しいピッチとこれらのホームヘクサコードは、通常の硬い、自然の、あるいはやわらかいヘクサコードの概念的なtranspositionsとして合理化される。その合理化は、mental phenomena としての目的を果たす。挿入された半音は、全音音階の尊厳に挑戦することはできないためである。81 81 Berkeley Manuscript pp56-66 理論家は、Berlelyのconiunctaeの5つをintellectualis transposicio [mental transpositionとして、4つを自然なものとして特徴づけている。 それぞれの場合、理論家はconiuncta音程を示すために使われた記号を正確に指定している。彼は、第7coninuctaについて書いている。 p95 7番目のconiunctaは、dとeの間で受容され、それはe上でb-[rotundum](=e♭)で示される。そこでは、faが歌われることだろう。そしてこのヘクサコードはb♭で始まり、gで終わり、そしてそれは、naturalのやり方で歌われる。なぜならそれは、 cで始まるproprietasあるいはヘクサコードのより低い場への自然(ヘクサコード)な移調だからである。Berkeley Manuscript p62 理論家は決して、intellectualis transposicio という用語を、メロディの全体のtranspositionには適用せずに、個々のヘクサコードのみに適用する。標準的なグィドの手にはない音の必要性を正当化する場合に、彼はそれを局所的瞬間につなげるのだ。 cantusは実際にはC-Dorianとして読まれることを意図しているという自身の前提から進んで、Bergerは、 次のcantusの臨時記号、第9小節のeでの Bergerのe♭は、Berkeley Anonymousの言う7番目のconiunctaに当たる。理論家は、その音程は、e上のb-rotundum (=e♭)によって示される、と述べている。 ここには確かに、中世のソースへの取捨選択されたアプローチがある。Bergerは、Berkeley Anonymousのintellectualis transposicioの概念を、Fuiies de moyのcantusでの彼自身のポジションを強めるために、(非)適切に使用しようとしている。しかし彼は、7番目のconjuncta(e♭)がどのように表記され、理論家の教訓と彼自身の記譜の読みとの間の見かけ上の不一致を記譜するか無視するかについての理論家の明瞭な規定を無視している。84 理論的なソースの選択的かつ歪んだ解釈に加えて、Fuiids de Moyは旋法的に均質でなければならない、それはC-Dorianとなるに違いないという前提は、Berger自身のアプローチを損なうことになる。 p96 それは、検討すべき仮説として提示されるであろうが、この前提は、cantusについての彼の解釈が構築されている岩盤である。 しかし、(cantusが)他の2つの声部と同じ「調性領域」で認識されて読まれ、認識されるはずだった場合、なぜスクライブは、cantusに1つあるいは2つの♭”記号”を入れるべきではないのか? または、そのピッチが望まれたときに、なぜ彼は、単純に局部的なE♭を記すべきではなかったのか? 第9小節のeは実際にはfa(♭)が必要なのにわざわざmi記号 第9小節やその他の場所のcantusでは、Bergerのアプローチは、cantus歌手に対し、EやBでの臨時記号の読みにおいて、その他のパートの歌手とはまったく異なる規則を適用しているが、このような齟齬は非常に非論理的であるように見える。 Fuiiesの場合、 Oswald von Wolkensteinのcontrafactum、Wolauff gesell werjagen wohl.を通じて、15世紀初頭での受容感覚が得られる。85 contrafactumの2つのドイツ語のソースは、フランス語のソースのように、カントゥスを記しているが、テノールとコントラテノールの署名を省略している。そのため、元のバラードの調性は変わるが、Bergerが主張するようなCドリア旋法の方向ではない。 cantusが保存され、下の声部らの調性の性質が容易に変更される可能性があるということは、14世紀や15世紀初頭の音楽家が特定の旋法的なカテゴリーと結びついたようなポリフォニーソングのアイデンティティを認識した程度度合いへの疑義を抱かせることだろう。 L'ardent desierの場合と同様に、Fuiids de Moyの第2セクションは、この例において 、安定したcolosのピッチからtenor and contratenorでのヘクサコード外の三全音の跳躍を含む、inflectionされたソノリティとともに始まる。(例11a)。 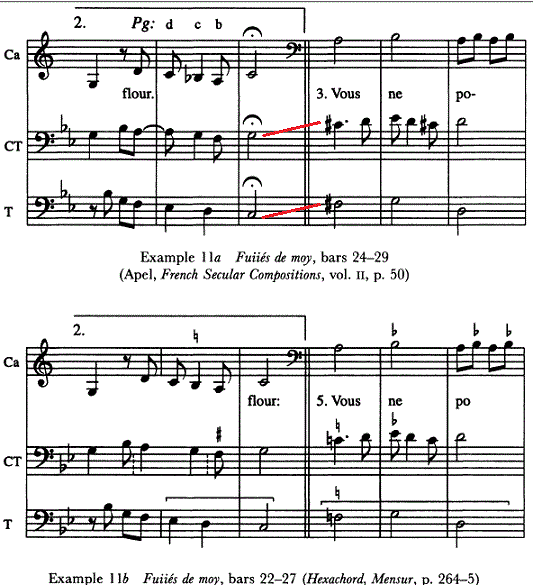 Bergerは tenor and contratenor それぞれのF#とc♯の標準的な読み取りに反対している。なぜなら、三全音となり、ソノリティの傾向が協和音につながらないため-正しく解決されないためである。86 p97 彼のtranscriptionは、 しかし、適切な解決策を構成するものに対する彼の基準はどの程度有効なのか? 一見すると、tenor F#は適切にGに移り、contenoror c#はdに移っているのだ。 contratenor の第29小節への第28小節の動きや、テノールがbreve Gから協和音Dに降りてきていることは、通常の対位規則の違反と見なすことはできない。 マショーと彼の同時代の人たちの作品では、協和音ソノリティの「よろめいたような」使い方は、障害となる。 再度言うが、Bergerの提起する反対は、”これらの臨時記号はヘクサコードソルミゼーションに対する記号を表さねばならない”という結論に対する人工的体制を構成することになる。87 p98 Christian Berger がFuiids de moyのこのセグメントでcontratenor and tenorがこのように歌うようにさせたプロセスは、独創的でもあり、またあり得そうもないことである。The mental processes Christian Berger attributes to those singing contratenor and tenor in this segment of Fuiids de moy, whereby they grasp the solmisation implications which he imputes to the written accidentals, are both ingenious and improbable. 要するに、Bergerは、closの後で上昇に直面したコントラテノールの歌手が、第24小節のlaが(ソフトヘキサコードの)reにmutatioされたと主張している。 しかし、次のセクションの(コントラテノールの)最終目標であるdは、miとソルミゼーションされなければならない!ために、 第25小節のc(やわらかいヘクサコードにmutatioされてsol )は、conjunct hexachordの組み合わせを歌手に警告するための テノールに関しては、 Berger はC→F 2番目の理由は明らかに怪しい。なぜなら、第31小節のE♭に沿った、第28小節の記譜されたテノールのb♭は、(両者とも、譜線に記されている。音部記号としてではなく)すでに、第30-32小節が、やわらかい、そしてより低いB♭ヘクサコードでソルミゼーションされるであろうことが、確かめられているからである。そのために、第25小節のFには、記号は必要ない。 cantusの説明もまた、怪しい。まず第1に、1つの声部の記号の内容を、個別に表記されている別の声部に転送する必要があるためである。次に、第26-7小節のcantusのb♭を想定しなければならないから。3番目には、cantusに関係するのはテノールのdisjunctヘキサコードシナプスではなく、第24小節のcantusのcでのreからsolへのpermutationを含むconjunctであるからである。90 p99 スクライブは、cantusにおいてb♭が第18小節で望まれる時にb-rotundumを書くことには躊躇しないので、彼は確かに、次のフレーズでは、直接のルートを選んだことだろう。そして、第26-7小節のbの前には、b-rotundumを置いた。もしも音を指定する必要があったのなら。 Berger は、ある時点でスクライブ(または作曲家)がcantusでのb♭のinflectionの明確な兆候を示し、その直後に、この直接的なコミュニケーション手段を避け、別の声部であるテノールの分離したdisjunct hexachords を含む非常に間接的な記号を選択している。 彼が自身の理論を適用して説明すれば、歌手は、臨時記号の単純な直接の読みから、ある記譜された声部から別の記譜された声部への意味の伝達を含む非常に複雑な精神的プロセスを含む読みに即座に移行しなければならなかったあろう。 信じられないほど一貫性のない行動を歌手に押し付けることに加えて、Bergerは、彼らがどのように記譜法にアプローチしたかについての奇妙な概念を暗黙のうちに促進する。 L'ardent desier、L'escu d'amours、Fuiids de moyなどの曲の分析で彼が想起する中世の歌手は、音で曲を再現するのではなく、記譜法が理論の教科書であるかのように記譜法を読む。彼の主な関心事は、旋法の完全性を維持することであった。 彼が、紙の上とスコアのパートとともに行った非常に骨の折れる長い説明は、中世の理論的記述や中世の記譜法に部分的に反するだけでなく、ありそうもない理論的理解や動機を中世の歌手に押し付けている。 レイナのレパートリーには、臨時記号に関するスクライブの正確さや意図の質問に訴えることができる、明確な14世紀の解説がない。 しかし、Bergerが彼の通常の旋法を適用する1つのパッセージについては、当時の解説が存在する。それは、Ugolino de OrvietoのDeclaratio Musicae Disciplinae (1430-5)からのbook .II, c. 34 からの短い2声の例である。 Ugolinoは、musica fictaが採用されている理由を説明するために、2つのコンパクトな2声の説明を考案している。 ”これらの説明例では、square and round bsが明確に示すmusica fictaの形成の原因を我々は把握しています。Round and square bは、不完全不協和音に与える完全性と、それらが表現する甘い調和を示しています。” p100 最初の例、Berger が彼自身に宛てた例では、Ugolinoは上声部で記された3つの臨時記号のそれぞれの論理的根拠を詳述している(例12a)92。彼の発言は次のようになる。 1つ前の音符の 最初のb-rotundumは、”不協和音を完全にする”(すなわち、不完全協和音)のではなく、それを色づけている。(訳注;causa pulchritudinisに当たる)。そして、その後の”完全(Aオクターブ)”にクローズしていく。♭がなければ、演奏者は、全音でre-mi(硬いヘクサコード)とソルミゼーションすることになっただろう。♭があれば、半音で、mi-faと彼は歌う。 2番目の 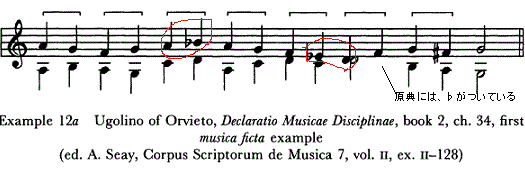 p101 Ugolinoの解説は、その前にある音程をinflectionするための記号があり、そのinflectionは不完全な協和音を色づけ(「色」)し、その後の完全音程とより近い音程の結合を形成することを目的としていることを明らかにしている94。ヘクサコード構造も旋法も、彼の説明や期待の地平線のどこにも現れていない。 Ugolino は、彼の例に必要なピッチの変化のすべての記号を提供したと公言しているが、Berger は、パッセージの旋法の読みに介入している(例12b)。 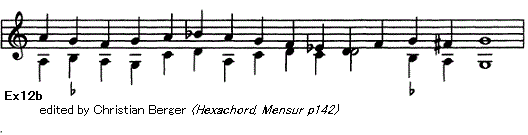 (Berger は旋法を重視するので)Gファイナルと1つのb♭がdiscantにある場合、旋法はG-ドリア旋法でなければならないので、下声部の2箇所のbはb♭として歌われる必要がある。 「明らかに、これらの要因は当時の即興演奏の慣行に非常に強く結びついている」と彼は宣言している。「これらの理論的例では、それら自体が機能している。」95 こうしたことは、 Ugolino の例の内容と性質を完全に誤解している。この章「De ficta musica」では、 Ugolino 自身が適切な演奏実践の基礎を築いている。彼の注意深く構築された例は、歌手に何をすべきか、そしてその理由を教えることを目的としている。それらは決して、歌手が演奏実践の事前知識を適用するように勧められる実践ではない。 Bergerはここで主導権を握り、 Ugolino の例に旋法的な解釈を課しただけでなく、それが属していない「実践的な音楽」の領域内でそれを解釈した。徹底的で派手な理論家である Ugolino が、この例を彼が願ったように記譜し、記載したことは疑いの余地がない。 重要なことに、BergerはUgolinoの2番目のイラスト(例13)については説明していない。これは、彼自身の考え方と一致させるのがはるかに難しいからだろう。  ↑Bergerはノーコメント このフレーズでは、上声部にはe♭とe p102 各声部内の変化するinflectionは、Christian Berger が、自身の解釈のほとんどのために粘り強く維持している一種の均一な旋法的テンプレート内でこのフレーズを解釈することをを妨げるものである。 上で論じた論文へのアプローチと同様に、Bergerは、音楽を用いた取捨選択的なプロセスを採用し、中世の視点の彼のイメージと矛盾するであろう資料は無視している。 Bergerは、Ugolinoの最初の方の例は自分の目的に合わせることができるので適切なのだが、旋法的パラダイムとの調整がはるかに難しい2番目の例はパスしている。 Ugolinoの最初の例に旋法的解釈を課すことは、その細心の理論家の明確な教訓とはまったく異質な原則を使用しており、アルスノヴァの歌の旋法解釈への自信を刺激することはできない。また、自身が説明したばかりのUgolinoの原則の要約声明に対するBergerの不注意は、歴史的な情報に基づいた視点を発見して実行するという彼の公言した目的に適合しない。 「これらの例から、心地よい調和が生成される、協和音の完全性と不協和音の色付けのためのmusica fictaの必要性が理解されます。」97 97 Musica Ficta p124-5 p103 逆説的ではあるが、(Bergerの)Hexachord、Mensur und Textstrukturは、旋法がars nova的なポリフォニックソング内の支配力であるという仮説に反対する精巧な議論として理解できる。 旋法がそのレパートリーで操作可能であった場合、その操作を識別するために、そのような複雑な推論、理論的教えのそのような詐称、またはBergerの研究において見られるような表記法を読むためのそのような精巧ではありそうもないプロトコルに頼る必要はないはずである。 表記された音の変化がそのように見え、musica fictaを説明する理論家がそれらを表現している場合、(Bergerがそれらを再解釈または抑制する熱意で暗黙のうちに認めているように)、多くの曲が旋法的規範から著しく逸脱しているのである。 REFLECTIONS ON HISTORICAL RECONSTRUCTION 著名なhistoriographerであるHayden White は、歴史の執筆に関する彼のエッセイで、metahistorical レベルでは、歴史的な物語は、「発見されたものと同じくらい発明された内容の言葉によるフィクションであり、科学におけるものよりも文学におけるそれらとの共通点がより多い形態」と見なされなければならない。」と語っている。98 彼は、個々の歴史家が採用した説明のパラダイムと作られた小説などの筋書き全体は、主にその選択と証拠の解釈を決定することによって、彼らのscholarshipの結果に大きな影響を与えると述べている。99 歴史的物語をイデオロギーやプロパガンダのステータスに還元するよりもむしろ、歴史的アカウントでの架空の要素として認識することは、「物事が実際にある方法」の「正しい」認識として認められているイデオロギー的先入観を捕らえる歴史家たちの傾向への潜在的な強力な解毒剤として役立つ。 100 「ホワイトの立場から見ると、ars novaのポリフォニックソングの旋法とヘキサコードに関するChristian Bergerの研究は、個人的な解釈と選択性がそれに関与しているためではなく、著者がどれほど深く認識していないか、認識していなかったために、そのルーツに欠陥があるように見える。彼自身の仮定、「物事はどうあるべきだったのか」という彼自身の感覚が、彼の中世の音楽史の定式化に印を押した。101 p104 彼のアルス・ノーヴァの歌の調査は、書かれた音楽理論の性質、作曲された音楽と理論的教訓との関係、および当時の歌手の精神についての(しばしば暗黙のうちに)特異な信念を実装している。 検討されていない前提として機能するこれらの信念は、理論家や具体的な表記法からの証拠を容認できない程度に歪めている。それらは結果を制御し、最終的に混乱させる。 14世紀のフランスの音楽家ら全員が、単一の視点からポリフォニーにアプローチしたというChristian Bergerの議論の中心は、書かれた理論が統一された教義を伝達するという仮定であり、それは簡単な散文で述べられている。 Lawrence Gushee は、中世の理論の適切な解釈には、個々の著者やテキストを取り巻く特定の文脈、目的、知的伝統についての考慮された判断が含まれることを強調した。 Susan Fast は、中世後期の理論論文における多層的で複雑な言説の分析によってこの教訓を強化した102。 たとえば、Jerome of MoraviaのTractatus de Musica 、Jacques of Liegeの Speculum Musicae、Quatuor Principalia、「Berkeley Treatise」、Johannes Boen's Musicaの詳細な比較は、個々のトピックへのアプローチの違いと、使われる用語の多様性の両方を明らかにしている。 それらの著者らは一般に、標準的な音楽要素(グィドの音階、3つの主要なヘキサコードタイプ、8つの旋法カテゴリなど)については同意があるが、これらの要素を説明する実際の方法と使用する用語はそれぞれ異なっている。 Christian Berger は、ポリフォニーの旋法と旋法/ヘキサコードの統合について統一された教義を主張し、中世の引用と現代の主張の複雑なパッチワークを通じてそれを組み立てている。 p105 パッチワークの方法論自体は、14世紀の理論家が、Bergerが構築した旋法理論を首尾一貫した方法で提示してはいないことを示している。 さらに、上で指摘したように、元の文脈から理論的引用を削除したバーガーBergerは、それらのいくつかにまったく新しい意味を与えている。 しかし、これらの論文を統合された状態で読んだり聞いたりした中世の音楽家らでさえ、特に理論家自身が複数の視点を頻繁に中継していないため、統一された理論的教義が染み込んでいたという考えでさえ疑わしいようである。 自身の研究を通して、Bergerは、14世紀のポリフォニック構成が規則に拘束され、法的にさえも、理論的教義に従っているかのように進んでいる。 この態度は、特定の書かれた臨時記号が、通常あり得ない音程が生じるために、または特殊な対位法的な正当化が進行を説明しないため、またはinflectionした音が旋法のproprietasに合わないため、といった理由で、音の上昇または下降を示すことができないという彼の主張で特に顕著である。104 理論家が実際にこの性質の分析原理を明確に表現しているという懐疑論はさておき、そのような考察は2つの前提に基づいている。すなわち、1つは、音楽理論の執筆は作曲の実践に向けられたものであり、もう1つは、彼らの教義は実際に作曲を制御したということである。 そのような前提の誤謬を理解するために必要なのは、対位法についての論文と、書かれたポリフォニーとを比較することだけである。 よく知られているように、対位法理論は、平行完全協和音を禁止し、許可された協和音の間の短い瞬間に不協和音を制限する(許可されている場合)。 しかし、ギヨーム・ド・マショーのような熟達した作曲家によるポリフォニックの歌の調査は、対位法の基礎内の平行完全音程と、メロディ表面を装飾し、対位法のフレームにさえ浸透する顕著な不協和音の両方を明らかにしている。105 p106 これらの点で、マショーの歌は、彼(彼自身の芸術性を高く評価している)が作曲した時に、文字に対する標準的な対位法の教訓を遵守したことをほとんど示唆していない。 ポリフォニー的即興での初歩的な指導と対位法の指導のつなぎは、精巧に書かれたポリフォニーとの関係を問題にしている。106 同様に問題となるのは、ポリフォニックソングの作曲プロセスと、理想化された理論面で動作し、伝統的な教えの堆積物に基づいて構築される総観的で思索的な論文との間のインターフェースである。 一部の理論家らは、音楽科学の理論的側面と実践的側面を明確に区別しているが、これらの発言自体は解釈が必要である107。 楽譜に理論的教義からの独立性を与えることを躊躇している(しかし構築されている)ために、Bergerは、存在の異なる領域に関係なく、理論と作曲、musicaとcantusをかなりカジュアルに膨らませている。 Berger自身の信念の力は、彼が14世紀のポリフォニーの見方の中で調性構造を一致させているという状況で特に明白である。 彼にとって、調性構造、特に旋法構造は、14世紀のポリフォニック曲の中心的な問題であり、作曲家だけでなく、曲を演奏した歌手にとっても重要な考慮事項なのである。 ポリフォニーに関する現存する14世紀の著作はないが、短い対位法マニュアルであれ、音楽思想の広大な大要であれ、それらは、ポリフォニーの調性構造に多くの考慮を向けている108。 p107 それらを読むと、むしろ、計量記譜法のシステムの完全な知識と音程への接近が、musica mensurabilisの理解、構成、および演奏に最も関連しているという印象を受ける。 中世当時では、音楽構成の秩序と一貫性に大きく関与する機能として、音関係と調性構造が音楽検証の基準として大きく浮かび上がってきた。 したがって、Bergerの調性構造へのこだわりは、現在のテーマと完全に一致しているが、彼が提示する強い(そして非常に凝集した)形でのこのこだわりは、率直に言って、私たちが持っている14世紀の音楽文化の痕跡に適合しない。 ポリフォニック作品は、旋法的に統一されているに違いないという彼の主張( Fuii's de moyの議論で例示されている)は、臨時記号の彼の独特の読みの多くの基本的な前提であり、歴史的根拠も欠いている。 プレインチャントな領域でさえ、14世紀の理論家らは、複数の旋法の特徴を示していると感じたメロディーについての話し方を認識し、考案していた。109 14世紀の歌の豊かなレパートリーを、その時代を単に反映する方法で理解しようとする試みは、価値はあるが不可能な探求なのである。 歴史的記録が要約的で断片的であり、現在の歴史的な偶然性は、一般的な知的パラダイムから個々の研究者の音楽的および物語的な傾向に至るまで、努力の多くのレベルで必然的に影響を与えるために、不可能なのである。 それにもかかわらず、中世の論文や音楽ソースの賢明な解釈を現在の懸念と統合して、学者のコミュニティが歴史的記録に基づいていると見なすことができるという観点から、14世紀のポリフォニーを表すことは確かに可能であるはずである。 たとえば、理論家がmusica fiictaについて実際に報告していることについてのレビューは、14世紀の歌の版で、Apel、Greene、Wilkinsによってフォローされた記譜された♯と♭についての解釈の一般原則を実証している。 さらに、曲において書かれたfictaによって生成された斬新な音は、Johannes Boenがb-faやmiを使って毎日のpraxisで達成できる素晴らしい可能性や、 comma と3つのminor semitonesの演奏としての音楽における「多くの新しい、前代未聞のこと」についての彼の予測を響かせる。110 そのような声明の熱狂は、14世紀のアルス・ノヴァの歌に惹かれた人々がその想像上の音の世界を受け入れ、音楽に旋法的妥当性または統一された厳格なシステムを課すことなく、これらの歌がどのように編集、実行、分析、そしてオリジナルな歴史的環境を認め・尊重するやり方で聞かれたかを調査し続けることを奨励するはずである。 |