| Musica Ficta7 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| 6 Contrapuntal progressions (i) Cadences p122 我々が扱う時代の初めから終わりまで普遍的に議論された進歩の1つは、不完全協和音程から完全協和音程への進歩であった。 I3I7 -I8年のLucidarium in arte musicae Planae で、Marchetto da Padova は発表をした。 一部の diaphonies または不協和音程は、耳と心に受け入れられるものと、受け入れられないものがあります。 許容できる主要なものは、3度、6度、10度です。 これら、およびそれらに類似するものは、反行で協和音程にアプローチすると、それらは協和音程のすぐ近くに位置するため、耳に受け入れられます。 2つの声部が不協和音程を形成する場合(つまり、不完全協和音程)、それらは反行で、求めている協和音に向かって移動する必要があります。 そして不協和音程はそれらがアプローチ協和音程に可能な限り近くになければなりません。 最後の文はここで重要である。すなわち、不完全協和音程は、反行で最も近い完全協和音程に移動する必要がある。より具体的には、一方の声部は全音で移動し、もう一方の音はdiatonic semitone 進行する必要がある。2 Marchettoの例で示されているように、短三度はユニゾンに縮小し、長三度は五度に拡大し、長六度はオクターブに拡大する。 3 明らかな理由により、マルシェットは短6度の使用方法を示していない。両方の声部がステップごとに移動する必要がある場合、短六度は四度に縮小する必要がある。 理論家のすべての例では、不完全協和音程のステップの1つがdiatonic semitoneによって完全協和音程に進むことができるように、半音階的に変化している。 後の理論家は、「美しさのため」(causa pulchritudinis)のような文脈で、みかけのステップが使用されていると言う。 たとえば、Franchinus Gaffuriusは、「みかけの音楽は2つの理由で発明された」と語っている。第一に必要のために 第二に、美しさのために」、前者の理由は、mi against faの禁則に関係している、と言っている。 pI23 ガフリウスは、後者の理由が何であるかは説明していない。彼は単に彼の読者に彼の論文の別の部分を紹介しる。それは不完全協和音程から完全協和音程への進行が議論中の問題の一つである。 5 しかし、すでにMarchetto は、そのようなmusica ficta の使用を「美」の概念と関連付けている。 「半音階」は‘'color of beauty と呼ばれます。これは、不協和音程のエレガンスと美しさ(つまり、不完全協和音程)のために、全音が全音階とエンハーモニック属に分けられるだけでなく、半音階にも入るので、不協和音程は、それに続く[完全]協和音程にアプローチする可能性がある。 両方の声部は、「半音階進行の」上下の一定の音程で全音の進行があるように進行することだろう6。 同様に、 Marchettoは彼のPomeriumで、ここで議論された目的のためにinflectionされたステップは「みかけの音楽」ではなく「colored」とより適切に呼ばれるべきであると主張し7、そして説明を続ける。すなわち、「音楽において、色合い(半音)は、時々、協和音程の美のために、作られる。ちょうど文法的修辞的色合いが文章の美のために作られるように。」8 一方の声部が全音進行し、もう一方の声部が半音進行し、不完全協和音程が反行で完全協和音程に進行しなければならない、そして、不完全協和音程のステップのひとつがこの目的のためにinflectionされねばならないという効果に対するMarchettoの規則は、当時の理論家によって繰り返された。 9。 しかし、一部の理論家は規則を変更した。Petrus frater dictus Palma ociosa は、不完全協和音程についての彼の例の中で(例27)、完全協和音程への固有の進行を示している。ここでは、不完全音程は、1つの声部が半音進行しながら完全音程に移動しているが、反行進行も、他の声部が全音を移動する必要もない。 したがって、規則はかなり緩和されている。 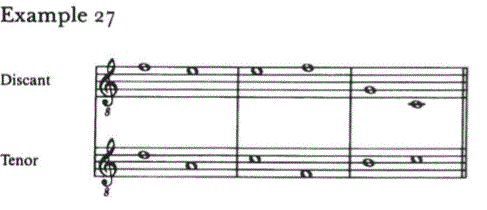 別の変更は、Prosdocimus de BeldemandisのContrapunctusの例によって暗示されている(例28を参照)。進行は、厳密な「Marchettan」ルールに従う。すなわち、2番目から3番目(f♯-gとa-G)、7番目から8番目の進行、10番目から11番目への進行である(赤)。残りの進行は、Petrusの緩和されたルールに従う。すなわち、5番目から6番目である。(青) 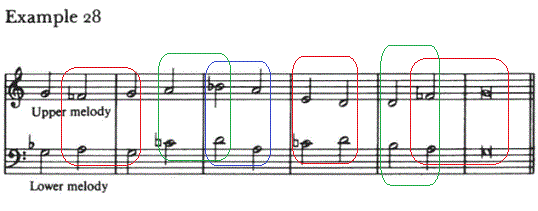 pI24 不完全音程からの2つの残りの進行、4番目から5番目の音程と、9番目から10番目の音程(緑)は、両方とも不完全音程に行くため、無関係であるように見えるかもしれないが、Prosdocimusは、このような場合にも可能な限り半音単位で進行し、必要に応じて最初の音程のステップをinflectionさせることを明示している。 この点を説明している理論家はもう1人だけいる。、Giovanni del Lagoで、1540年に、次のように書いている。「したがって、一般的なルールとして、不完全音程からより広い音程に上昇する不完全音程に進行するたびに、完全であれ不完全であれ、この[最初の]音程がminorである場合は、シャープ化する記号を使用してそれをmajarにすることになる。」12 Prosdocimusとdel Lagoは、この方法で不完全(音程)から不完全協和音程への進行を検討する数少ない理論家であることは明らかで、その結果、我々はおそらく、Prosdocimusの議論のこの側面を無視しても問題ないだろう。 だがこの例の残りの部分は、 Marchetto から知られている厳密な形式と、Petrusの修正された形式の両方で、不完全音程から完全協和音程への進行を管理する規則をサポートしている。 (ちなみに、この例はメロディックな問題ではなく、対位法的なものを示すように設計されているため、Prosdocimusの例の下声部にある、適切に「解決」されたメロディ的な直接の三全音の存在から結論を導き出すことはおそらく控える必要がある。 規則の両方のバージョンは、Ugolino of Orvietoの論文にも含まれている。 したがって、Ugolinoは、短三度がどのようにユニゾンに縮小するのか、そして、長三度がどのように五度に拡大するのかを説明している。両方の声部は、反行進行で段階的に進む13が、彼はまた、短三度から五度への進行を許容している。( G-D対シ♭-a)14. 他の場所で、Ugolinoは、2つの間の距離を減らすために、不完全音程から完全協和音程に進む際に、musica ficta stepsを使用する方法を示している(例29と30を参照)15 例29では、最初の不完全音程から完全協和音程への進行(f-gとa-G)は、おそらく、(臨時記号の)省略によってinflectionされない。なぜなら、(inflectionされた)同一の最後のもの(f♯-gとa-G)があるから。 3つ目(e♭-dとc-d)では、厳密なバージョンの規則を示している。 pI25 一方、2番目の進行(♭♭-aa対d-a)は、規則の緩和バージョンを示している。 Ugolinoが明確にコメントしているので、ここでフラットが別の理由では追加されていないことは確かである。「 確かに、最初の例に配置された最初のsoft b(♭)は、不協和音程[つまり、不完全協和音程]の完全性ではなく、その色彩化を示している。そして、その形の減価とともに、直接の完全性へのより緊密で即時の密着性も。16 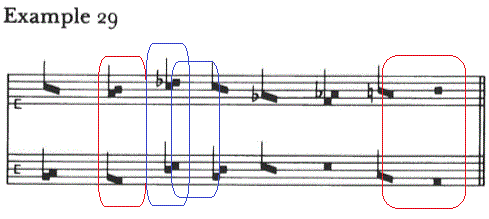 例30では、最初の例(e♭-d対c-d)、3番目(d-c対シ -c)、4番目(f♯-g対a-G)で、不完全音程から完全協和音程への進行は、規則の厳密なバージョンを示し、2番目の(d-a対f-e)の進行は、規則の緩和されたバージョンを示している。 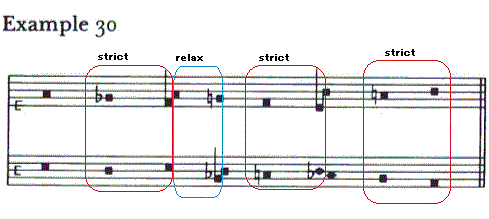 この論文の終わりに向かって、Ugolinoは、同じことを説明する別の例を示す(例3Iを参照)。7 ここで、最初の例、2番目、3番目、5番目の進行は、厳密なバージョンのルールに従い、4番目と6番目の緩和バージョンに従う。 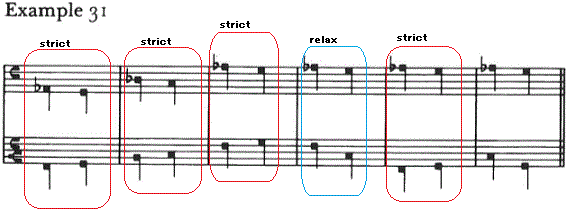 pI26 規則の両方のバージョンは、おそらく15世紀の第3四半期に編集された、Quot sunt concorationesの匿名の作成者によって議論された例にも含まれている。18 そこでは、三度から五度またはその他の完全協和音程に移動し、上声部が段階的に上昇する場合、三度をmajorにする必要があることがわかる。 I9 明らかに目標が五度の場合には、厳密バージョンの規則に従うが、目標が1オクターブの場合、緩和バージョンの規則に従う。同様に、六度がオクターブまたはステップごとに上昇する他の完全協和音程に進行する場合、六度をmajorにする必要がある。20 ただし、上記の進行を書き換えて、上声部がステップごとに下降するように(上行の代わりに)、三度と六度はminorにする必要がある。 2I 規則の両方のバージョンは、当時はずっと有効であった。Gioseffo Zarlinoの場合、長六度からオクターブ、長三度から五度、短三度からのユニゾンとなった。それはすべて反行において(つまり、厳密なバージョン)であるが、さらに、理論家は他の進行を考慮している。たとえば、長三度からオクターブに到達したり、短三度から五度に到達したりしている。この時代は、1つの声部が段階的に移動し、別の声部が飛躍によって進行したりした(つまり、緩和バージョンによって)22 pI26 規則の厳密なバージョンでは、2パート対位法の短六度から進行する適切な方法が提供されていない。 ここで、Ramos de Pareiaによると、指定されたチャントの上の単純なdiscanting([organzare ])を支配する規則の中から、次の規則を見い出す。すなわち、「長六度はオクターブに向かう。三度は五度に向かう。さらに、長三度は五度に行き、短三度はユニゾンに向かう。」23 Ramosの例では、短六度が五度に進み(♭-a対D-D,あるいはc-c対E-F)、1声部が半音で動き、もうひとつの声部は同じ音に留まっている。つまり、それらは規則の緩和バージョンに従う。 同様に、ガフリウスの対位法規則の1つは、「不完全協和音程から完全協和音程に近づくと、 ・・・直近の不完全協和音程の反行によって完全音程に進行する必要がある」。25 これは、もちろん、厳密なバージョンでは、これまでの規則によって支配される進行であるが、ガフリウスはまた、斜行進行での五度に行く短六度を含めている。26 RamosとGaffuriusの両者での意味は、各不完全協和音程から進行する最も適切な方法があり、長六度と同様、長短三度に対して、これは、その厳密なバージョンの規則として言及されたものに市販されるということである。その間、反行のステップが続くことができなかった短六度に対しては、斜行が許容される。 この証拠は、16世紀半ばにも見られる。27 たとえば、Zarlinoは次のように述べている。 さらに、不完全協和音程には以下の機能があります。すなわち、それらのextremitiesは、離れたものにではなく、最も近い完全協和音程に向かう傾向があります。当然のことながら、できる限り迅速かつ最良の方法で完璧を達成する傾向があります。したがって、不完全長音程は拡大しようとし、短音程は、その反対の傾向がある。 p127 ditone(長三度)やmajor hexachord(長六度)は、五度や八度に拡大する傾向があります。semiditone(短三度)や minor hexachord (短六度)は、ユニゾンや五度に収縮する傾向があります。これらの進行はすべて半音の音程を含んでいるため、これはすべての熟練した音楽家の響きの判断に対して、明白である。半音の音程は、まさに塩であり、調味料であり、すべての良いメロディと和声の原因です28。 I27 <まとめ> 不完全協和音程から完全協和音程の進行は、当時、最も一般的な(緩和した)形で、一声部が diatonic semitone で進行すべき規則や、不完全協和音程を形成するステップの1つがinflectionされるべき規定で支配された。これが半音の進行を生成するために必要な場合には。規則は、Zarlinoにおいて、この最も一般的な形式で見つけることができる。 規則を理解しやすくするために、不完全協和音程から完全協和音程へのすべての進行には、少なくとも一部に large semitone(Zarlinoのチューニングシステムではdiatonic semitone)のステップが含まれている必要がある。 明示であれ黙示であれ。 この目的のために、他の場所で説明されている方法で書かれていれば、半音階とエンハーモニックステップが非常に役立つことがわかる。.29 不完全協和音程から完全協和音程への最も完全な進行を説明するために、(より厳密になる)追加の基準が規則に追加された。すなわち、声部は反行進行し、一方の声部が全音的に移動し、もう一方の声部が半音的に進行する。 これは、短三度から進む最も完全な方法はユニゾンに対してであり、長三度から五度へ、そして長六度からオクターブへ、と進行する。 短六度に対しては、例外となる。なぜなら、厳格な規則に従って、2つの声部からなる単純な対位法では許容できない音程である四度が続く必要がある。それから進む最も完全な方法は、五度への斜進行である。 不完全協和音程から完全協和音程の進行を管理する規則はどの程度厳密に遵守されたか? この問題については、理論家の間でいくつかの不一致がある。 Gaffuriusの場合、この規則はカデンツでのみ絶対に必須である。「(対位法についての)第7の規則は、主張している。 最終的なカデンツまたはその他のケイデンスのように、不完全協和音程から完全協和音程にアプローチすると、最も近い不完全協和音程の反行進行によって完全音程に進む必要がある。'30 Zarlinoは不同意としている。 すべてを管轄する性質は、音楽のトレーニングを受けている人だけでなく、自己流に歌う unschooled and even farmers でさえも、長六度からオクターブへの進行に慣れているように思われる。まるで自然にそれらを教わったように。 すべての音楽家らによれば、こうしたことは、彼らの音楽全体を通して、カデンツで最も明白となる。 おそらくは、作品が終止になるので、カデンツが長六度からオクターブに進む唯一の場所であるというのが、Franchino [Gaffurio] が言いたかったことだろう。 しかし、私には、「オクターブに進行するのは長六度、五度に進行するのは短(六度)の性質である」という、私が彼から引用した発言との矛盾が明らかである。31 p128 もし我々がこれら二つの音程の性質に従うなら、私は、彼が不注意からそれを言ったと結論づけられる。 したがって、長六度から五度、短六度からオクターブに進行することは、正当ではない。なぜなら、 どちらの進行も、関与する協和音程にとって自然なことではないから。 32 ”性質”の議論は、Zarlinoがここで規範的なモードで書いており、それを説明するのではなく、音楽的慣行を正当化しようとしているということを、我々に許容する。とにかく、Zarlinoでさえいくつかの例外を認めている。 したがって、音楽家は、彼が他のことをすることができない場合には、第38章に記載されている規則に反して、長六度の後に五度を書くことになるだろう。もしも六度がシンコペーションされたsemibreveのsecond part にあれば。ただし、四度のsemiminimは、semiminimで短六度からオクターブに進行するかもしれない。なぜなら、semiminimがconjunct motion で三度に残れば、それは不協和音程になるかもしれないので。33 すべての音楽家が、不完全協和音程から完全協和音程への規則を常に義務的であると見なしたわけではないという別の示唆は、規則に関連するさまざまな問題についての長い議論の終わりに向けてLuigi Dentice によって提供されている。 Denticeの対話の対談者の1人は、tetrardus (第7,8旋法)では、Eを♭化すべきではない、この考慮事項は、tetrardus (第7,8旋法)でのC-DまたはG-Gに対するe-dの進行において、eを♭化する必要性を無効にする、ということを説明している。34 話者はこの例に従い、一般的な結論を出す。すなわち、「Mr Adrian Willaert , Mr Alfonsoらの支持を得て、六度と三度、長短の規則は、任意であり、義務ではない、と私は強く確信する」35 すべての音楽家が、不完全協和音程から完全協和音程への規則を常に義務的であると見なしたわけではないという別の示唆は、規則に関連するさまざまな問題についての長い議論の終わりに向けてLuigi Dentice によって提供されている。 Denticeの対話の対談者の1人は、tetrardus (第7,8旋法)では、Eを♭化すべきではない、この考慮事項は、tetrardus (第7,8旋法)でのC-DまたはG-Gに対するe-dの進行において、eを♭化する必要性を無効にする、ということを説明している。34 話者はこの例に従い、一般的な結論を出す。すなわち、「Mr Adrian Willaert , Mr Alfonsoらの支持を得て、六度と三度、長短の規則は、任意であり、義務ではない、と私は強く確信する」35 この結論は、Ghiselin Danckerts の興味深いfashionにおいて説明されている。Danckertsのこれらとの主な争いは、過度のinflectionによって旋法を破壊することである。36 特に理論家は言う。 それらの人々は、あまりにもうんざりしすぎて、ほとんどいつもいつもこれらの音符の上げ下げを適切で自然なイントネーションを超えて(私が言ったように)使い、特定のむなしい義務と彼らのルールに縛り付け、もっとも近い不完全協和音程から完全協和音程完全に行かなければならないと規定しています。 彼らがまれに、そして偶然に、それを使用したなら、これは信じられるかもしれません。しかし、このルールが通常通り、常に度の場においても遵守されていると、前述の小説作曲家がそうであるように、前述の旋法に過度の損傷を与えることになります。 37 ある意味では、 Danckerts は無論、正しい。すべての機会に、不完全協和音程から完全協和音程への規則を真に一貫して適用すると、音楽的に不合理な結果がすぐに得られ、一貫性は低くなるが、まさに半音階である音楽への適用は頻繁になる。 後者は、I550年のいくつかのcompositori novelliの大きな関心を呼び起こしたが、それは確かにその当時やそれ以前でさえ、音楽の規範を表していないことは言うまでもなかった。これらの考慮事項、およびここで示した理論的な証拠は、規則が選択的に適用されている必要があったことを示している。38 そして規則は、不完全協和音程から完全協和音程へと進行するときの半音の進行を規定しているため、つまり、現在見られるように、カデンツの必須のコンポーネントであるために、Gaffuriusが、この規則はカデンツにのみ適用されると信じていた理由はあると我々は考える。したがって、それを適用できるようにするには、当時のカデンツを構成したものについての明確な概念が必要である。 pI29 Johannes Tinctoris defined cadence as follows: ‘Cadence is a small part of any part of a song at the end of which is found either general repose or perfection .'39 ‘Repose' (qui む)may, but does not have to , signify ‘rest' , since Tinctoris's technical term for the latter sign is pausa . At least some musicians , however , interpreted Tinctoris to mean ‘rest ' here , as we may ascertain from Dowland ' s translation of Ornithoparchus: ‘Wherfore a Close is (as Ti ηctOT writes) a little part of a Song , in whose end is found either rest or perfection . Or tsiithe coniunction of voices (going diversly) in perfect Concord ,4I Returning to Tinctoris ' s definitions ,‘ perfection' , in turn ,‘is a closing of a whole song or of small parts there of. 42 Thus Tinctoris's understanding of the term ‘'cadence ' is no different from ours: it is a device signifying closure ,of the whole musical discourse ro fo its par t. No technical details are given , but ‘perfection' undoubtedly calls for a perfect consonance , while ‘repose' may involve a following rest , as we already know . Tinctoris's contemporary, John Hothby , adds a new element to our under standing of cadence : By ‘ 'cadences' one understands all the notes between one line and another . They follow the cadences of the words , of which there are principally three , namely , comma , colon and period ... As I said , the cadences of a song should be similar to the cadences of the words , so that if the cadence of the words is suspending , that is , the colon , the cadence of the song should be of a long [note value] of the final step [of the mode]. And if the cadence of the words is a smaller punctuation , that is , a grammatic comma , the cadence of the song should be moderate , not too long , and not too close to the final step. But if the cadence of the words is the period , that is , the end of the sentence , the cadence of the song should be on the final step or on the reciting pitch . 43 In short ,musical punctuation is analogous to verba l. There is a hierarch y of cadences , just as there is a hierarchy of textual punctuation marks ; both reflect the fact that the desired sense of closure may be greater or lesser . A more complete textual closure may be musically conveyed by a cadence ending on a longer note placed on the final of the mode or on its reciting pitch , while a lesser closure may employ a cadence ending on a shorter note value placed off the final. Many sixteenth-century theorists confirm this correlation of the textual and musical syntax . 44 Stephano Vanneo, for istace, says: pI30 provides us with a truly Rabelaisian list of terms synonymous with cadentia (p os 山叩 termz .natio ,conclusio , ft" n仏 copulatz.o ,reductz . o, pe てfec tt" o , St そr fraga tt" o ,。 ρtatz.o ,approbatz . o, du tt" nctz . o, termz .nt ι 5 ft" nalu , clausula) “and lifts his definition of cadence straight from Tinctoris , but includes the in sights we have gleaned from Hothby: Cadence, therfore , is a small part of any section of a song at the end of which is found either general repose or perfection . Or cadence is a certain close of this same section of song , just snai the context ofspeech the middle and final signs of punctua. tion . Experi enced musician s are eag er for the end of cadences to be made where also ends a part or clause of speech.47 Finally, Zarlino stresses that one makes cadence only where the phrase or period of the text ends . 48 Throughout our period , theorists tell us that the minimum of what is indispensable to create the sense of closure , the cadential effect , is a progression from an imperfect to a perfect consonance . The most fundamental rules of counterpoint prescribe a perfect consonance for the final harmony of a composition , and an imperfect consonance for the penultimate har . mony . The anonymous author of the influential Cum notum sU of the second quarter of the fourteenth century states: The eighth conclusion is that in his counterpoint the penultimate [harmony] should always be imperfect and this because of euphony . . . The ninth conclusion is that just as the counterpoint begins with a perfect [consonance] , so also should it end . The reason may be that if the song were finished with an imperfect [consonance] , the mind would remain in suspense and would neither repose until it heard a perfect sound , nor , consequently , would it be indicated that here is the end of the song. 49 These fundamental rules remain in force throughout our period .50 Clearly , however , not every imperfect-to-perfect progression will produce a cadential effec t. What can we learn , then , about the structure of cadences? Ugolino tells us , like so many others , that an y song must end on a perfect consonance , and he goes immediately on to show the best ways of approaching perfect consonances from imperfect ones , the ways we have already discussed . 5I The inescapable implication is that everything we have l~arned about the imperfect-to-perfect progression pertains to cadences . But are we not in a vicious circle here? We have reconstructed a rule which governed progressions from imperfect to perfect consonances and we have concluded that the rule applied only at cadences . We have concluded further that in order to know when to inflect an imperfect consonance one had to be able to recognize a cadence . But now we see that the essential characteristic of a cadence is precisely an imperfect -to-perfect progression governed by our rule. The only way to escape the circle is to find additional criteria which a cadence must fulfi l. One of these we have already identified: at least since the late fifteenth century some cadences may reflect various degrees of articulation of the text into clauses , sentences , etc. It may also be that theyinvolve a following res t. Now we shall search for other additional criteria. pI3I 対位法の基本的なルールの1つでは、最終的な和声は完全協和音程だけでなく、オクターブまたはその同等物である必要がある。 ガフリウスは言う。「その8番目と最後の規則では、すべての曲は、ヴェニスで慣習的に行われているように、ユニゾンで、またはオクターブまたは15度で、完全協和音程で終了する必要があると述べられている。どの楽派の音楽家らも、共通して、完全な和声的統一のために、これを遵守しているように」52 他の16世紀の理論家は、この点を確認している。 53 Zarlino は、音楽家は「各作品は1オクターブまたはユニゾンで終止し、他の音程では終了しないようにするという一定の規則を作った・・・規則は十分な根拠があり、それ以外の場合に終了する楽曲は、最終的な完全性を期待している観客を不穏な状態に置く。」と述べている。54 その場合、少なくとも15世紀後半以降、オクターブ(またはその同等物)は、カデンツの最終的な和音の不可欠な要素となった。 カデンツの構造については、Melchior Schanppecher's のI50I年のテキストから詳しく学べる。彼は、カデンツは2つではなく、3つのハーモニーで構成され、片方は 上下声部は、その性質公式を交換することもある。そのために、2つの声部は、ユニゾンから三度へと拡大し、それからユニゾンへと収縮する。55 ほぼ同時に、 Johannes Cochlaeusは、すべて3つのハーモニーからなっているカデンツの例を示した。octave(あるいはユニゾン)カデンツを作る2つの声部は、Schanppecher が望んだようにふるまうが、加えて、以下の公式もまた適用される。すなわち・・・ 上声部は、 要するに、カデンツを構成する声部の片方は pI32 The Close of the Ducantus made with three Notes. shall alwayes have the last upward. 3 The Close of the Tenor. doth also consist of three Notes. the last always descending. 58 These formulas may ,of course, be exchanged between the tenor and discant . or appear in other voices altogether. The theoris t' s examples show one of the voices moving __ .す__while the other 0_ 59 moves ... ι-e,..- or -n-‘ト ....... 理論家の例は、片方の声部は 同時に、Aaronは、 Libritres de institutione harmonica. で、カデンツへの長い議論をしている。カデンツ公式での片方の声部は この最後の点は、Toscanello in musica:で確認される。「七度の不協和音程は、つねに、octaveの前の六度に先行される。もしもカデンツが単純ではなく作曲されているならば。」61. むろん、単純なnote-against note書法では、不協和音程は存在しないが、 Aaronは”つねに”、2つ前の不完全協和音程前の不協和音的な繫留音は、減価された対位法でのカデンツの義務的な特徴である、と示唆している。 この点はVanneoによって確認されている。理論家は、単純な対位法のカデンツは、最も近い不完全協和音程から完全協和音程で終わり、両方の声部が反行進行で段階的に進んでいると語っている。 62 華やかな対位法ではしかしながら。最後から2つ目のものは、不協和音の繫留音に先行される。63 他のところで、理論家は、2種類のカデンツがあると説明している。単純なものと大華やかな対位法のものである。前者は noteagainst-noteであり、後者は、音価の不等性を認識し、細かい音符による修飾が見られる。 64 彼の言葉では、最後から2番目以前に不協和音程が必要であることに疑いの余地はない。「作曲家が、規定された規則によって最後から2番目の[協和音]の前に不協和音を置くことに慣れている、例にある華美なカデンツを我々に教えることはあり得るだろう。」65 marginal note は、この時点でテキストを強調する。すなわち、「華美なカデンツは、不協和音的なantepenultimaを必要とする。66」 不協和音は、片方の声部でantepenultimaにあり、もう片方の声部でpenultimaにある繫留音である。67 最後から2番目の協和音程に解決する不協和音的繫留音の必要性を確認する別の理論家は、デル・ラーゴである 68。 Del La go discusses also another important feature of cadences : In your compositions you will always make sure to complete the mensuration unit. whether temary. binary . or quartemary. with the penultimate note of the cadence. Thus . one should not compute the penultimate et ohntiw the following one which concludes the cadence or distinction. since there is the beginning of the mensuration unit there [on the final note of the cadence]. Similarly. one should finish the mensuration unit with the penultimate note of the harmony and not with the last one. because the penultima concludes the preceding mensuration unit. The last note is the end of the song and, therefore, it is not computed with another note. 69 pI32 The ‘mensuration uni t' (numero) is a larger note value containing a number of srnaller values prescribed by the rnensuration of the piece. Del Lago does not say which note value this is. but clearly. under the nonnal rnensuration signs. it cannot be srnaller than a sernibreve . since it rnust contain two . thre e or four srnaller values . and it may well be a still larger value. most likely a breve. perhaps even a long. A study ofrnusic by a given cornposer or even a whole generation of cornposers would easily tell us what this value was under a given rnensuration for the exarnined reertoire. What is important about the quoted passage frorn del Lago is that it tells us what we should be looking for when we undertake such a study. What del La go tells us is. in essence . that the rnetrical placement of the last note of a cadence matters. The ultima rnust fall at the beginning of a larger rnensural unit. say a breve or whatever we shall discover this unit to be . And this. of course . may be a significant new criterion allowing us to distinguish a truly cadential progression from other imperfect-to-perfect progressions . At mid sixteenth century. the richest insight into cadences is provided by the two most cornprehensive rnusic treatises of the time . those of Nicola Vicentino and Gioeffo Zarlino . Vicentino shows various fonns which the cadential fonnula e 0 e can take. 70 The formula can be rhythmicized ln three ways: as the ‘major cadence ' (cadentia rn~glJl.'or.e) ,(吋eT'.. 0 I8 as 山 'rninor c 出 nce '(c 仰 ntia ~inore) r(J) 午~- and as the 凶 irnal cadence' (cade 仰 aminima) Id) 中~J- . Each of these may be dirninished and ernbellished . The lesson which rnay be derived frorn these exarnples is that. first. the antepenultirna is a suspension resolving to the penultima. second , the ultirna appears on a strong beat (that is . at the beginning of a rnensuration unit). and third . the value of this mensuration unit can be a breve. sernibreve. or perhaps even rninim . The first two points confinn what we already know. the last one is new. Unfortunately. Vicentino does not supply the exarnples with tirne signatures and. consequently. we cannot be sure whether these different cadences can all appear under the sarne signature or not. just as we cannot be sure what the mensuration units irnplied by the exarnples are. These questions. however, can be answered when we study a given repertoire .The value of Vicentino's examples is again that they tell us what sort of questions we should ask when studying rnusic. These questions are: Can different mensuration units be exploited for cadential purposes (that is. can the ultima appear at the beginning of mensuration units of different value) under the same time signature? What are these mensuration units for each time signature? Vincentinoのカデンツの例においては、octaveで終わる2声は、 pI34 The most comprehensive treatment of cadences is offered by Zarlino in Le lstitutioni harmoniche , Part III , Chapter 53. 72 Absolute cadences conclude with a unison or octave. They may be written in simple , note-against-note , consonant counterpoint , or in diminished counterpoint employing a variety of note values and some dissonances. In either case , a cadence consists of at least three harmonies. The final unison must be preceded by a minor third , the final octave by a major sixth . In a diminished cadence , the imperfect consonance is preceded by a dissonant suspension. The melodic formulas involve 8-7-8 (= I-7-I) moving against I-2 I , 3-2-I , 6-2 I , 5-2-I , 4-2-I , I-5-I , 35I , 6-5 -I and 4-5 -I. Occasionally used is also the formula 67 I against 3-2-I , but these are cadences 'improperly speaking'. 73 All of Zarlino's examples in the chapter involve the common ~ -time and in most of the cadences the final harmony falls at the beginning of the breve mensuration unit , in some also at the beginning of the semibreve. In Chapter 6I , Zarlino gives examples of cadences in writing for more than two parts and , again , all the voice-pairs which end the cadence on the octave behave according to the precepts listed above. 74 <回避されたカデンツ> Zarlinoは、彼が「不適切なカデンツ」(Cadenze impropz'amente dette)と呼んでいるものにも注意を向けている75。つまり、今日で言う、「回避されたカデンツ」である。 これらでは、一方の声部は基本的な8-7-8(= 1-7一1)公式を持ち、もう一方の声部は、予期せずに、五度、三度さらに他の協和音程に行く。適切なカデンツ的解決が免れながら。 Zarlinoは書く。「声部が完全なカデンツにつながる印象を与えながら、代わりに別の方向に向かう時に、カデンツは回避される。」76。 次の章の例は、上記で記述された形式に加えて、回避されたカデンツは、通常8-7-8に対して移動する標準公式のひとつを構成するかもしれない。公式8-7-8は不完全であり、8以外の音に解決される間に。 (例えば、I-2-Iに対して8-7-3など)。 そして最後に、両声部は、通常、最後から2番目のハーモニーまでは正常に続くかもしれないが、最後のハーモニーでは、このような公式が、不規則に完成されることになる。(例32)77 すべてのケースで、最終ハーモニーは、   pI36 つまり、回避されたカデンツでは、最後から3番目と最後から2番目のハーモニーは規則的に振舞い、一方または両方の声部が予期しない方向に向かうため、最後のハーモニーのみが不規則になる。 導音を含む最後から2番目のハーモニーは規則的であるため、カデンツが規則的であれば、それがinflectionされる必要があると考えるのには十分な理由がある。 このような「回避されたカデンツ」(fuggir la cadenza)は・・・ 言葉が思想の最終的な結論に達していないとき、和音とテキストの中間の分割をするために使われる。美しいパッセージの真ん中にある作曲家がカデンツの必要性を感じているが、テキストのピリオドが一致していないために書き込めない場合や、挿入するのが正直ではない場合に有用である。 79 回避されたカデンツについては、あまり詳しくはないが、他の15世紀なかばの理論家によっても議論されている。デルラーゴは、「1つのカデンツのふりをして、このカデンツの終わりに、解決されるためにこのカデンツに行かないように協和音程に進むのは、時折、賞賛に値する」と語っている。80 Vicentinoは、「結論を回避するカデンツ(cadentie che fuggano la sua conclusione)例を示している.8 I これらは、デルラーゴの定義とZarlinoのより詳細な議論に完全に準拠している。 <中断されたカデンツ> さらに、Loys Bourgeois は、通常のカデンツ公式(8 -7)の前から2番目と最後から2番目の音符のみが含まれている「中断されたカデンツ」( (cadences rompues)に言及しており、8と7の間の半音を生成することが必要な場合は、これらの導音も♯化される必要があると述べている。82 また、Giovanni Maria La nfrancoは、7が常に♯になるさまざまなステップで、中断されたカデンツ公式8-7を例示している。83 pI37 理論家たちの注意を免れたように見える中断されたカデンツの重要な特徴は、その時代の音楽に精通している人には明白であろうが、計量記譜法単位の初めの強い韻律的位置における ‘penultima' の配置にある。(実際には、中断されたカデンツの最後のハーモニーとなる) したがって、中断されたカデンツは、もちろん、回避されたカデンツと同一ではないが、回避されたカデンツでも、半音的な導音が必要なことをサポートする追加の証拠としてBourgeoisの声明を使用できることでは十分に類似している。 カデンツを不完全進行→完全進行から区別する追加の基準をまとめてみよう。カデンツの理論的な議論を読むことで発見された基準である。 (1)カデンツは、音楽の全体またはその一部のある程度の終止を示す。 (2)カデンツは、句、文、段落などの単位への口頭によるテキストのアーティキュレーションを示す句読記号に類似しており、テキストのそのようなアーティキュレーションを反映している場合がある。 (3)カデンツは、その後の休符を含むこともある。 (4)オクターブ(またはその同等物)は、最終的なハーモニーにとって不可欠なコンポーネントである。単純な対位法では、カデンツは3つの連続するハーモニーで構成され、2つのパートがオクターブで終了し、特徴的な旋律の式8-7-8(= I 7 -I)が、I-2 -I、32I、4- 2-I、5-2-I、6-2-I、I- 5-I、3-5一1、4-5-Iまたは6-5-Iに対して進行する。言い換えると、8-7 8(またはI- 7 -I)に対する対位法には、最後のステップとしてI(または8)が含まれ、最後から2番目のステップとして2または5が含まれ、最期から3番目のステップとして8(またはI)が含まれる。例外的に、 8-7 8の式は6-7- 8に変更できる。これに対する対位法は、最後から2番目のステップと最後のステップに対しては2 -Iを含み、そしておそらく、最後から3番目の6に対しては、協和音程となる。減価された対位法では、最後から2番目の不完全協和音程の前に不協和音の中断があり、カデンツはもちろん、さらに装飾される。 (5)最終的なハーモニーは、16世紀初頭の''通常の計量記譜法”(misura commune; (6)カデンツは「回避」される場合がある。この場合、両方の構成声部の公式は、最初と2番目のハーモニーでは正常に振舞うが、最後のハーモニーでは予期しない手順になる。(一方の声部のみか、または両方において)。 公式が通常、最初の2つのハーモニーに対してふるまい、その後に続かない場合は、最後のカデンツのハーモニーが、計量記譜法単位の最初に配置され、”中断される”ことになる。すなわち、強いメトリカルな配置である。どちらの場合でも、導音は、規則的なカデンツに相当する終止への半音的進行が必要な場合は、inflectionされる。 pI38 上記の基準の最初の3つは、理論的には15世紀後半から出現し、残りの基準は16世紀初頭から出現する。また、不完全から完全への進行を管理する規則はカデンツでのみ適用されるべきであるというまさにそうした思想は、 規則が適用される進行を制限する何らかの方法が最初から機能していたとしても(規則を無制限に適用すると、特許が認められない結果になるため)、およそ I500年頃になって、やっとはっきりとするようになった。 カデンツは音楽言語のうちで最も保守的で変化の少ない機能に属し、そして、理論家がそれらを議論し始めるずっと前から、我々の基準が機能していたのかもしれない。 カデンツの完全な歴史はまだ書かれていない。現時点では、現代の演奏者または編集者は、特定のレパートリーの紛れもない(つまり、最終的な)カデンツを調査し、基準が適用されるかどうか、およびこの調査から追加の基準が導出されるかどうかを確認し、適切な基準を、レパートリー内で、カデンツを非カデンツ的な不完全から完全への進行と区別する時に使用している。 . また、カデンツは、テキストのさまざまな程度の句読点に類似しており、そしてそれを反映し、その結果として、旋法の終止音にメトリカルに強い位置にある長い音符で終わる最も規則的な、完全なカデンツ進行から、完璧なケイデンシャルな進行、回避され中断されたカデンツの多様性へのさまざまな「強さ」、「完全性」、または「最終性」となっている。 これは、カデンツ的、非カデンツ的不完全から完全への進行の境界線が多少ぼやけている可能性があることを示唆している。 進行は、すべてではないにせよ、カデンツの特徴を示すことがある。特定の進行をカデンツとして扱い、適切にinflectionさせるか、そのままにしておくかについて、(作曲家、演奏者、または編集者によって)決定を下す必要のあるグレーゾーンがある。 inflectionにおいて臨時記号の使用を必要とする可能性のある不完全から完全への進行以外の対位法的な内容もまた、カデンツ的である。 I520年代以降では、カデンツの最終音上のハーモニーが、三度を含んでいれば、三度が長三度になることを、我々は学んだ。私が知っているこの効果の最も早い発言は、AaronのToscanello in musicaに登場する。短十度や三度での終止は喜ばしくない、とAaronは主張する。 84 Spataroは、I524年5月23日に書かれたアーロン宛ての手紙で、このパッセージについてコメントした。短十度や三度は、実際には不快に聞こえないのではないかという彼の議論において、これらの音程の長調形式がさらに心地よく聞こえることを認め、こうした場合での三度のinflectionが、アーロンのように悪いものから良いものへの変化ではなく、良いものからより良いものへの変化であると結論づけている。 85 Toscanelloの「補足」で、アーロンは4声部構成の3つの例について説明している(例33を参照)。 86 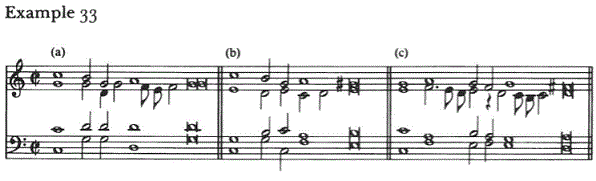 Accidentals, Counterpoint and Notation in Aaron's Aggiunta to the Toscanelloin Musica' MARGARET BENT参照 pI39 (「補遺」の)最初の2例は、スパタロがアーロンに送ったものを少し前に引用したものに適合させたものであり、アーロンがそれらについて述べた点は、最初にそこでスパタロが作成したものである。87 「補遺」の最初の2つの例は、同一のcantus parts を持ち、その他の声部の文脈だけが歌手に、cantus partsの最後の音符が, 1か3か(♯がつくかどうか)を決定させるのに役立つ。 3番目の例のcantus partsは、同じように終止するが、もちろん、彼はこの最後の音符をシャープにして、終止上、長三度(十度)を産生する必要がある。 同様に、Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto、figuratoで、アーロンはモードI -4でのカデンツのポリフォニックの例を示し、最終的なハーモニーで、ファイナルの3番目を明確にシャープにしている。 88 最後のハーモニーで3番目をシャープにする慣行は、La nfranco、 Vanneo、とVicentinoによって確認された。彼らは次のようにカテゴリー化した。すなわち、「休符の近くまたは最後にいくつかの部分を停止したいときは、常に作品が悲しみを求めている場合でも、この場では長三度となる。」 9I しかし、その慣行が1520年代より前に知られていたかどうか、もしそうであれば、どれくらいの間なのか、今のところそれは、推測の域を出ない。 上記の議論でわかるように、カデンツの終止音での三度の使用は、理論が大幅に時代遅れになっていたとは思われないため、この問題はおそらくほとんど重要ではない。 |