| TENDENCIES AND RESOLUTIONS: THE DIRECTED PROGRESSION IN ARS NOVA MUSIC1 Sarah Fuller |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
この論文を理解するためには、まず、ON SONORITY IN FOURTEENTH-CENTURY POLYPHONY: SOME PRELIMINARY REFLECTIONS Sarah Fullerを読むことが必要です
| p229 1357年に完成した基本的な音楽指導用のテキストであるJohannes BoenのMusicaは、14世紀半ばの音楽の教えと実践に関するより有益な論文の1つにランクされている。 彼の本の4番目の、協和音程のトピックに捧げられた長い章で、Boenは、五度とオクターブの前を心地よくさせるための、三度と六度の特に活発で思慮深い特徴について記している。 三度と六度で共有される相互互換性に加えて、最近では、3つの三度が互いに連続し、3つの六度もまたそうなって、類似性を高めている。 このように確立されている限り、非和声的な質にもかかわらず、三度と六度で不完全音程と判断されたcantusは、次の五度とオクターブに耳を引き付け、魅了する。 これは、[オクターブと五度の]の前に存在する三度と六度が、五度またはオクターブでのcantusの完全形を、長く期待されるためのより甘い完全形として表現できるようにするためである。以下のように。 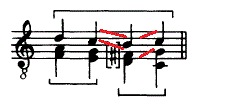 p230 それは、目的が達成されたら、進行が止まったのではないかと考えて、耳がその注意をやめないように、五度とオクターブの[平行の許容]を意味するものではない。 一連の不完全協和音程は、より安定した完全な協和の達成を先延ばしにすることにより、遅延が審美的により満足のいく結果になることを見込んでいるのである。 平行する不完全音程への認容は、Petrusのpalma ociosa(1336)によるdiscant tractなどにより、(Boenの)20年ほど前に明らかになっている。そして、感覚へのその直接的訴えとともに(”耳を引き付け、魅了する” ”耳がその注意をやめないように”)Boenの説明のしかたは、そして予告された到達のその隠喩は、14世紀の感覚を特に、示している。 14世紀の第1四半世紀のさまざまな書法は、不完全音程から完全音程への動きを含む対位法的構文への規則と選好を主張している。Jacques of Liegeは、1320年代の書法で、cacentiaという用語を導入することに関して、音程の進行のある種のタイプに言及している。 カデンツは、その現在の目的に関して、ある種のアレンジや、より完全な協和への不完全協和の自然な傾向に言及している。・・・協和音程へのリスペクトと共に、カデンツは、不完全協和が隣のより完全な協和を得んとせんとする時に生じている。上下したり、上行・下降したりしながら(すなわちそれは、声部の反行となる)。 不完全音程とその完全音程への解決は、最初の従属要素が階層的に優れた仲間と仮想的に融合されたユニットとなるように、実際には非常に緊密にリンクされている。 すべての協和は最高の完全性を達成し、ユニゾンやdiapasonで応答するだけでなく、たとえ不完全音程が完全協和の前にあっても、それは完全になる。なぜなら終止となるそれらは、事実上、同じになるからである。 p231 このように書かれた理論的な声明に先立って、1320年代に作られたRoman de Fauvelの3声のモテットは、その最後の進行において、不完全→完全進行の接合の強制への理解を示している。(例1) 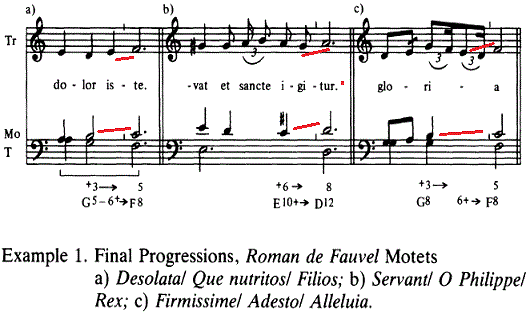 さらに、長三度と六度から五度とオクターブへの同時的進行は、14世紀の音楽で非常に普及しており、教科書的には「二重導音カデンツ(Burgundy cadence)」と称されている。 その名前は時代遅れの意味合いは持たないが、暗示的に、そのような進行に対して統一された役割と最終的な場を想定している限り、問題もある。 事実、X6/ 3からY 8/5への進行は、私が directed progressions と呼ぶ、より一般的な現象のサブカテゴリを構成する。このより一般化された定式化は、進行のタイプをカデンツ行動から分離し、進行が発生する可能性があるさまざまな状況のスタンスへの注意を促す。 (略) directed progressions とは、隣接する2つのソノリティの連続として定義できる。1番目は不完全で質が不安定、2番目は性質が完全で質は安定している。1番目はcontrapunctusの導音の基準にしたがって、2番目を解決する。5 隣接性の基準は、最初のソノリティの最低音が2番目の最低音から全音あるいは半音離れている場合に満たされる。 p232 多くの場合(すべてではないが)、1番目の最低音符は、2番目のソノリティの最低音符の上にある。contrapunctusの導音の指示は、ほぼすべて、短三度からユニゾンに、長三度から五度に、長六度からオクターブへというconjunctな動きを規定している。6 不完全→完全進行は、こうした基準からは外れるが、”指向された”、しかし緩和された効果としての機能として、やはり使われる。 最初は、不安定なソノリティがその後のゴールに対して”矯め”を作り出し、そして、14世紀の導音の基準によって、特殊な隣接した完全協和音程への解決を示す。 私はこの構文単位をT→Rとして記載するが、”T"は不安定なtendency elementを表し、”R"は、予期された解決を示す。両者の間の→は、”T"から”R"にに向かう傾向を示し、所与の”T"が、特殊な近接である”R"へと解決するような期待を示す暗示的シンボルとなっている。 p233 例2では、さまざまな特徴的な directed progressions が説明される。例2aとbは、伝統的なテノールの全音下降と2つの上声部の半音上昇を示している。 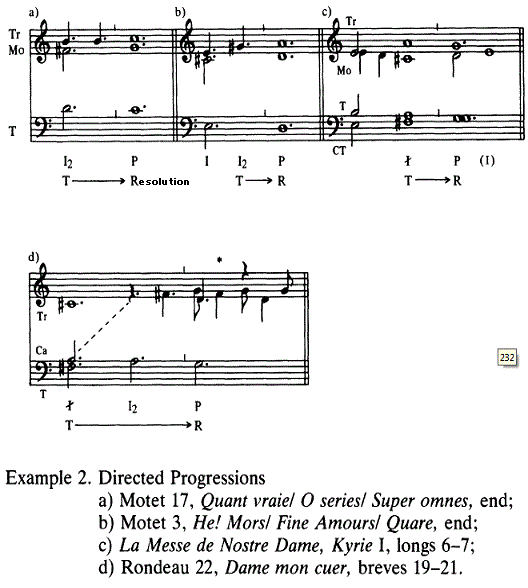 例2aにおいては、tendency elementは小節単位の最初に設定されているが、例2bでは、 "傾向(T)"は、inflectionした不完全音程から、より機動性のある二重の不完全音程へと性質が変化している。 安定したE-eのオクターブからinflectionした(バスと)長十度を形成するg#へのcantusの進行は、breveの2番目のパート(Mo)の緊張感を効果的に増加させる。9 例2cにおけるF♯-a-c#-a' の”T"のソノリティは、そのタイプにおいては不完全で、inflectionしているが、全音階的コンテクストにおいて、かなりの示唆的な推進力を生成している。 directed progressions のスペースが狭くなっていく配置は、例2a,bほど決定力はないように思われることだろう。なぜなら、最低声部が半音上昇をし、二重にinflectionされた平行五度での解決となっているから。 このような進行は内側に向かう(ここでは、短三度がユニゾンになる)が、例2aおよびbに示されている、より一般的な配置は、外側に向かっている。 例2cのようなスペースの狭い進行は通常、14世紀の作品にはない。10 例2dの「T」要素は、2cのように、closed positionで始まるが、cantus とtenorとで、配置を交換している。cantusは、テノールのF#を1オクターブ上と見做している。ここでdurationを延ばすと、「T」が著しく強調される。 これらのいくつかの代表的な例から抽出されるポイントは、 directed progressions は終止の度合いが異なり、その「T」成分は解決への暗示的な指向性 を実質的に変更することなく、進行の過程で変化する可能性があるということである。 終止を行う際、最後のT→Rの進行は、作品内の最終的な音の安息の軌跡を定義し、通常はすでに例証されている方向を確認する(例1、2a、2b)。このような使用法は、14世紀のみならずよく知られているので、煩わされる必要はない。 あまり知られていないのは、作品の開始時のdirected progression による最初の調性方向の定義である。directed progression を通じて到達したピッチ軌跡が最初のソノリティのものではない場合、効果は特に印象的である。 たとえば、マショーのモテットNo.3、He! Mors/Fine Amour/QuareはFソノリティで始まっているが、最初のarrivalはGへのdirected progressionであり、そのGが、最初の調性方向を設定している。(例3a、b)。12 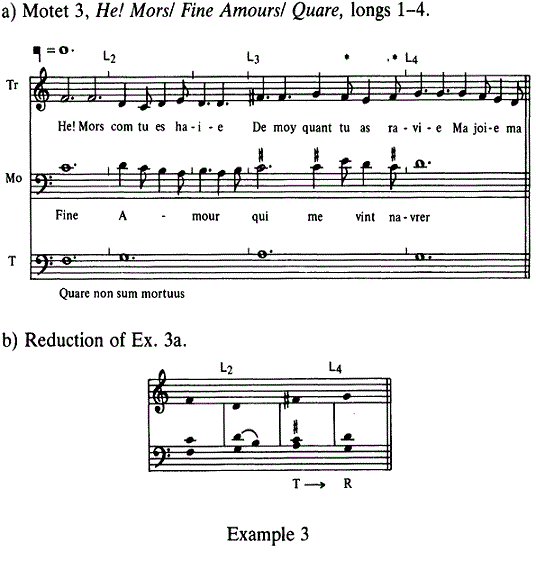 2声部において韻を踏んだテキスト行の最後は、Rを強化する。13 同様に、バラードB31De toutes floursの最初のフレーズは、Fソノリティで始まるが、強いdirected progressionによってアプローチされるC上の五度-オクターブで終止する。(例4)14 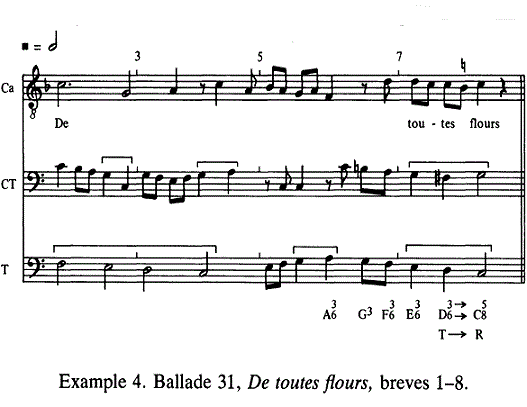 p234 最初とカデンツのソノリティの顕著なコントラストは、CとFのあいまいな関係に、チャイムを鳴らす。これは、バラードの最初のセクションの主要な旋律のアイデアである。15 Motet M3とBallade B31の両方において、最初のフレーズを終了するソノリティは、 directed progressionによって作成された解決への推進力のために、言及された推定基準の中心として最初のソノリティを上回る。 どちらのフレーズも、局所的に言及されたソノリティであることから直接始めるのではなく、調性の方向性の軌跡に向かって動いている。 Motet 4、De bon espoir / Puisque la douce / Speraviの冒頭では、最初の調性方向を設定する同様のプロセスが発生するが、それはより長いスパンにわたって行われ、directed progressionsの扱いにおいてのニュアンスを示す。 3つのフレーズのそれぞれは、directed progressionやそれを約束して終止する。(例5a)16 16 The symbol ">" marks ends of primary musical phrases in ex. 5b and other reductions 最初のところ 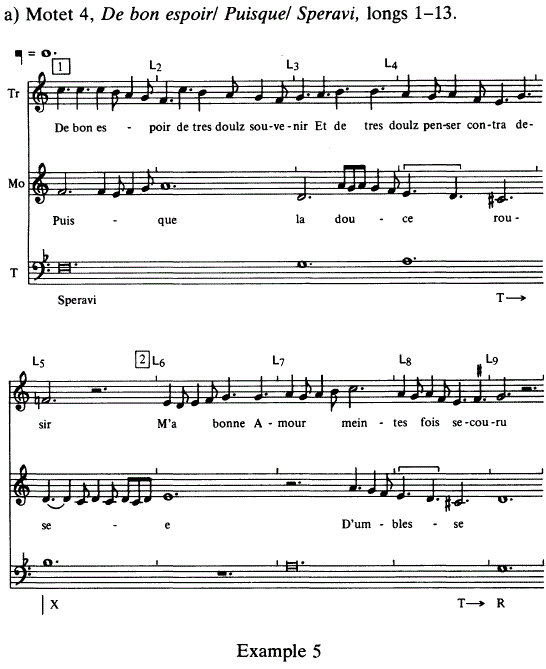 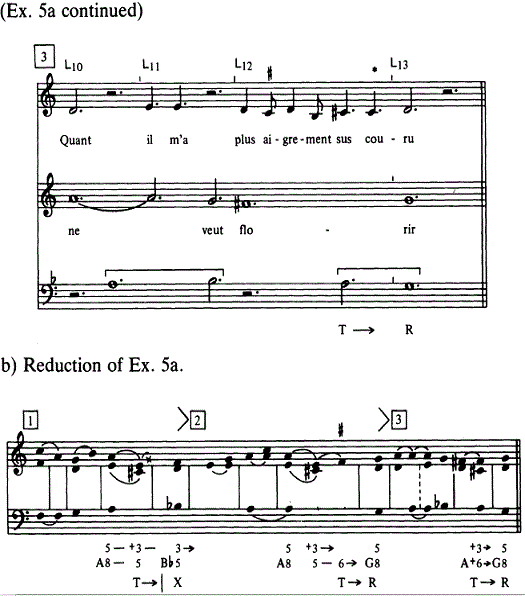 例5aの短縮の例5bに見られるように、「T」要素は基礎ピッチAで統一されているが、構成では、つまり、A上の音程形成では異なっている。これらの違いは、分離された解決への道と組み合わさって、directed progressions に不均等な重み付けをする。 p235 最初のフレーズの終わりは、directed progressionからは予期されないような方へと、逸れていく。(例5a、L4-L5)。 予想されたG-dへと拡張される五度の代わりに、b♭-dの長三度へとa-c#は平行して移動する。 さらに、L4のtriplumは、従来の「T」ソノリティで予想されるf#を回避し、代わりに,、(バスと)不協和音の七度となるgとなり、(その下のMotetはバスと)a-c#を形成する。七度を解決したfは この最初のフレーズを次のフレーズに向けて推進することに加えて、逸らされた進行はまた、 モテットを貫く、FとGの間の問題のある関係の最初の示唆を供給する。18 最初のtriplumのフレーズを終わらすf 最初のカデンツの異常を修復するかのように、2番目のフレーズは、従来のT→R進行でGにて終了している。そこに相当する上声部は、続くフレーズのエンディングの間で確かな関連づけを、テノールを介して、形成している。L8-L9とL4-L5を比較せよ)。 2番目のカデンツの「T」要素は、テノール上で、徐々に具体化する。L8から、Aソノリティは最初に完全化し、それからc#の導入で不完全化し、さらに、f♯の導入で、二重に不完全化する。L8の最後のsemibreve(f♯)でやっと、カデンツ進行が、それより前のフレーズにおいてのように迷わないようになることを再確認したことだろう。 p236 強い「T」ソノリティ(a-c#-f♯)がリズム的に解決されていないゆっくりとしたホケットの後に徐々に合体するとき、Gへの方向性は、3番目のフレーズ(L12-13)の終わりに疑いなく確保される。 p237 ここでは、ピッチ階層と調性への方向性の出現の相互明確化を含む、はっきりとした作曲戦略を認識している。 一連のフレーズは、解決の主たる目標として、G 8/5ソノリティを確立し、Aソノリティを従属的なサポートとして示している。そうした状況では、A→Gとなる場合も示されたことだろう。この閉じたセクション内では、冒頭のFソノリティは、あいまいに残されたままである。 M4De bon espoir / Puisque la douce / Speraviは、最後はFで終わるが、これはテノールのフレーズによって決定された結果である。19 作品が終わりに近づくにつれ、Machautは関係するソノリティを再構成し、そのために、Fは、解決の場としてGを置き換えるようになる。(例6a,b) 最後のところ 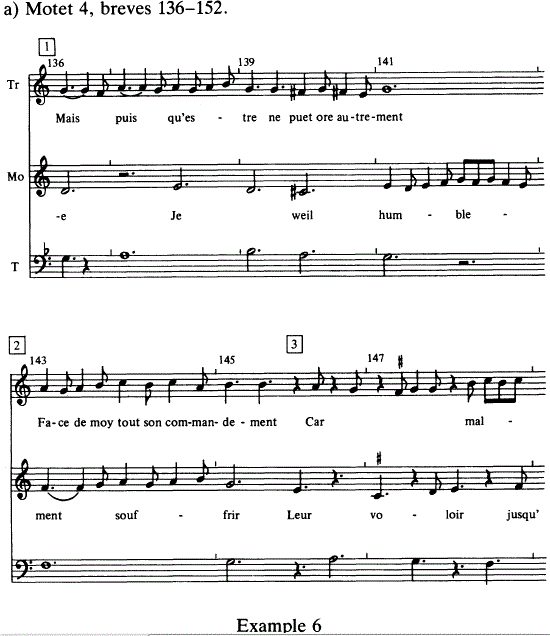 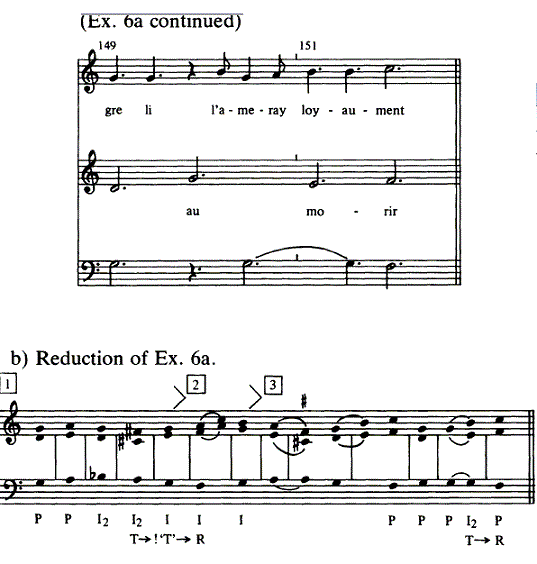 p238 もう一度、3つのフレーズが関係してくる。最初は、breve136でのtriplumの入りとともに始まるが、前のタレアとありつぎになっている。隣接するA sonolityは、明らかにGに到達しようとする平行した2つの6/3和音に直面している。 ここ、140-141brevesでは、決定的な動きが生じている。準備されたT(A)の六度がGのオクターブに滑り込むが、五度に解決されるべき三度は、(そのMoは)dではなく、eへと上昇する。Gソノリティはそれゆえ、その性質において変化し、(結果として生じた)不安定な六度は、(第143小節において)フレーズ2の最初のFオクターブ解決へと導く。20 20 例6bにおいて、transformされた解決(レではなくてミ)は’T’と表される。これは、半分はR,半分は新たなT要素である。 先行するGカデンツ(136breves)と141brevesのテノールのGへの強い平行的アプローチというコンテクストのために、順に解決を要求する不完全ソノリティへと期待された解決の変化は、特に注目すべきである。そのプロセスは、 p239 しかし、その再指向はまだ曖昧である。なぜなら、Fへの解決は、フレーズの冒頭と一致し、その性質において不完全だからである。 フレーズ2で終了する不完全なGソノリティは、Fに向けて構えているが、次のhocketはA-G-Fのテノールの下降にじわじわと合わせ、sense of centerをsuspendし、同時に140-44brevesの進行(A-G-F)をかすかに反映している 。 hocketは、Fに向かう調性方向を最終的に確認するFオクターブー12度)となる前に、完全から二重の不完全へとシフトするGソノリティで静まり、最終的にFへの調性の方向を確認する。 この最後のカデンツは、実際に、モテットの始まりのソノリティ(Fオクターブー12度)を復元している(例5aを参照)。 最後において、作品は(第147小節のG-d-g以降)完全に繰り返しをしており、冒頭のソノリティと最初の抽象構文単位を統合し、その単位ををA-G-Fに拡張した。 p240 M4De bon espoir / Puisque la douce / Speraviの最初のカデンツと3番目の減価タレア(曲の最後)は、T→R構文の、二重の可能性を示している。 このT→R構文は、終止を確保するのと同時に、終止の回避、延期、偏向、または進行の妨害による暗黙の再指向の可能性を提供している。 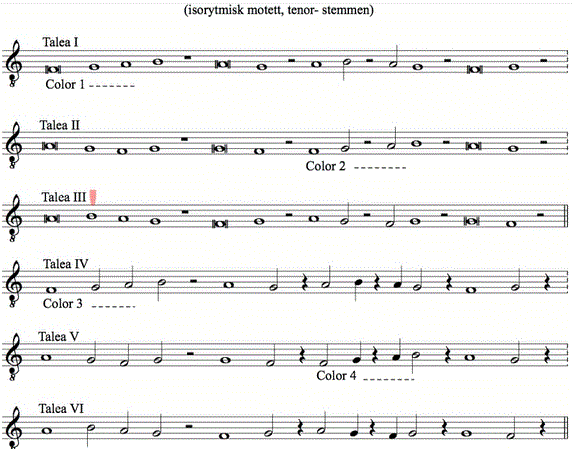 B25,Honte,paour,doubtanceの第2セクションは、既存のテノール、cantusで区切られない内容でのdirected progressionsについて、巨匠的扱いを示している(例7a,b)。 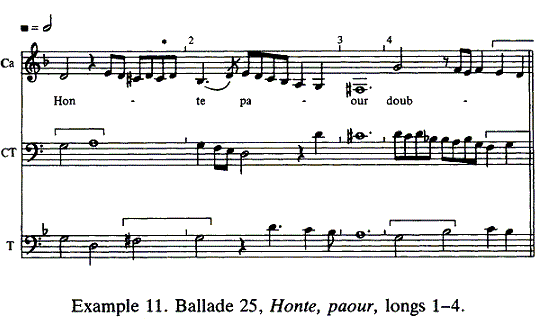 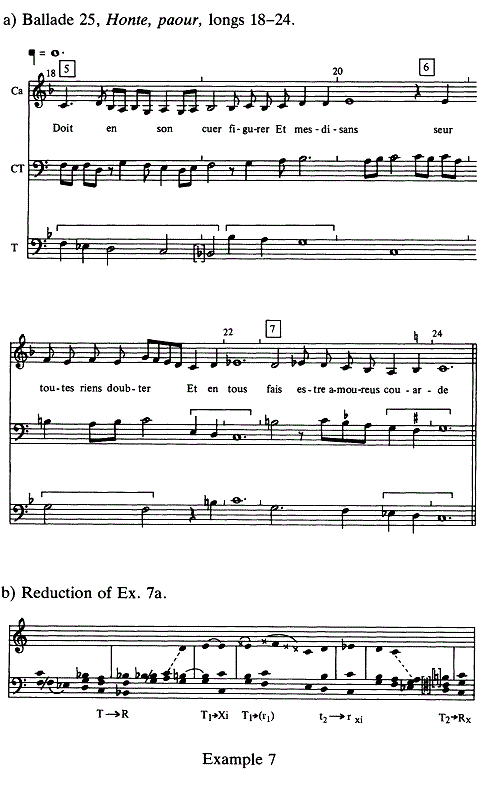 ルフラン前のカデンツ(第24小節)への音楽は、しばしば見られるようなリズムとvoie-leadingを介したT→R構文での崩壊によって促進されている。 第5フレーズは、その後がFオクターブ-五度となるべき二重不完全G-b 22 第19小節のGの後で循環的にFに戻ることになるであろうテノールが、直線的に降下していることに注意。(第19小節でオクターブ上がるが)。この進行は、結果的に、第21小節に持ち越されるが、一過性の遅延は、その終止への圧力を消すことになる。 T1に直接続いて、テノールとコントラテノールは、Cオクターブとなり、cantusは、eとなったままである。その時までに、cantusは第21小節でfを得て、下2声部での再度のG-b 第21小節のテノールとコントラテノールは、前に予見されたF-cとなるが、ここまでで、cantusはすでに、そのfがgからcへの経過的役割をする素早い下降となっている。 この第7フレーズは、D-b 最終段階では、フルに二重化された不完全準備によってアプローチされた完全Cソノリティである、リフレイン前のリズムに強く方向付けられた動きをします。 Cはバラードの最終的な音の中心に対して相対的にouvertとなるが、ここでの安定性は、ボイスリーディング、韻律、リズム、および完全なテキスト構文によって保証されている。 Cが最初に予想されるFへの解決に置き換わり、それから短三度コンポーネントによって濁り、最終的に明瞭な完全ソノリティとして現れる。その時、C方向へのシフトは、成就される。 振り返ってみると、リスナーはCソノリティ( "X"としての解決)に対する以前の弱いジェスチャーを、主要な事前のルフランのarrivalへの準備として理解する。 TからRへのこの一節の調子の向きをフレーム化する複雑なプロセスは、次のように説明される。 上記の説明は、initial tendency要素(T1,G-b p242 小文字と下付き文字と回りの括弧は、解決の非決定的な性質を示している。その結果、2番目の準備要素が導入される。不完全で、リズム的にも弱拍で。(t2,D-b Motet 4De bon espoir / Puisque la douce / Speraviの最初のカデンツジェスチャー(例5a)、またはBallade 25のフレーズ5の終わり(例7a)の特殊な「解決できない」性質は、予想されたピッチからの偏差だけでなく、安定したオクターブ五度が期待される不安定な不完全ソノリティの発生から由来している。 通常のdirected progressions の中で導入された同様の再配置も、リスナーの注意を引き、前向きの勢いを生み出す効果的な手段を構成している。 T-Rユニットのtendency要素が、フレーズの最後の、通常の最後から2番目の位置から削除されると、その結果は、変位として認識される場合がある。変位は本質的にダブルサイドになりがちである。 一方では、「T」要素は、通常の一時的なスロットから削除され、他方では、通常は構成が完全で品質が安定している期待されるソノリティタイプを置き換える。変位によって生成された前方衝動は、大部分は、和音タイプの平衡が予想された瞬間の、可動的な前方傾斜的なソノリティの出現に由来している。 Machautは、さまざまなコンテキストで、特に曲の始まりやフレーズの終わりにこのデバイスを利用している。 当然のことながら、14世紀のポリフォニーのほとんどは完全協和音程で始まる。 しかし、Motet 11Dame je suil Fins cuers doulz / Fins cuersは、不安定で不完全なソノリティから始まり、最初のフレーズが終わって初めて、確固たるarrivalとなる。(例8a、b)。 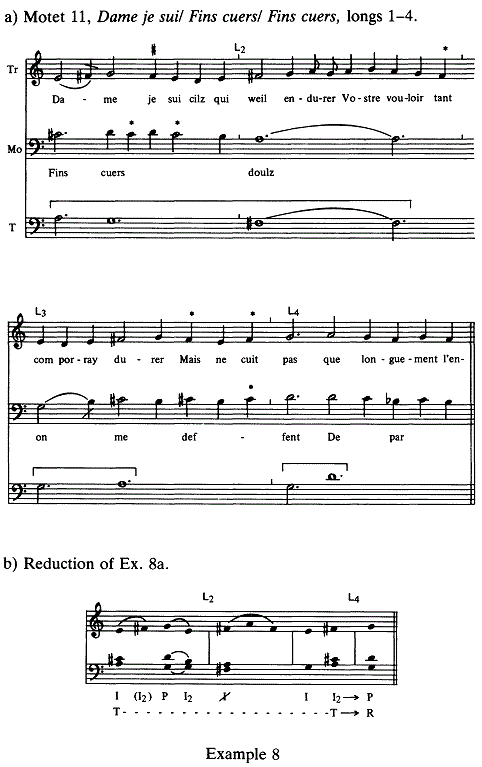 オープニングパッセージは、A、C#、およびF#と、G上の比較的安定したソノリティとを組み合わせた可動的にinflectionした(レド♯レド♯)ソノリティの間の交互配置に基づいている。 long4に至るまで、tendency ソノリティの解決は、相互作用する計量譜、メロディ的、およびテキストの要素を通じて従属している。 たとえば、breve 2のG 5/8は、進行中のテキスト行に含まれ、tenor mensural unitの内部にあり、性質が二重不完全(G3/6)にシフトし、同様の傾向にありながら異なった配置にある2つのtendency要素(最初と3番目のソノリティ)に挟まれて遡及的に聞こえる。その準備もまたやや弱く、仮定のf#はglideしたplicaになる。24 24. Although f# is possible, the singer might well anticipate g. 次のGソノリティ(long3)は不完全であり、不安定なパートナーの3番目のバージョンに引き継がれる。最後のGソノリティ、long4は、性質において完全でありで、tenor mensural unitの始まりにあり、それぞれ、motetus とtriplum のテキストの終止とcaesura(詩行の中間にある、耳で聞き取れる休止)と一致する。最終的な効果は、例8bに示されているように、位置が変化すると目的地をスライドするが、フレーズの終わりでのみ解決が得られる長期傾向ソノリティである。 p244 Rondeau 1、Doulz viaire gracieusは、同様に、別の不完全な実体にスライドアップした、最初にinflectionされた不完全ソノリティで驚かされる。(例9a)25。 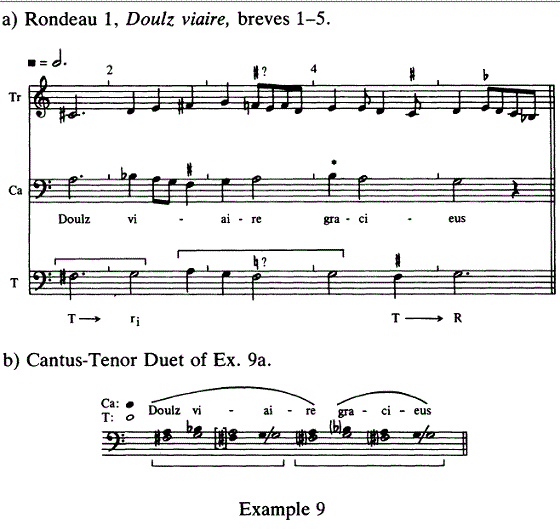 フレーズ全体は、F#-aの短三度に続く繰り返しのcantus-tenor counterpoint にフレーム化されているように見える。すなわち、三度で最初に平行に動き、それからユニゾンへと反行する動きである。26 最初のGユニゾンは、 単語内に位置しており、cantus-tenor 音程交換の中間点として定義されるようになるため、終止していく力が不足する。 2番目のGユニゾンは、その延長された継続時間と韻を踏んだテキスト行末から、カデンツウェイトを累積している。 breve5へのこのarrivalは、冒頭の緊張したソノリティによる確固たる解決予測と見なすことができる27。 27. F#-a の三度圧力がパッセージ全体で維持されるかどうかは、cantus-tenor のペアに対する triplum の影響を含む、厄介なテキストの問題である。breve 2でのtriplum f#は、明らかに下のcantusのF#を暗示するが、breve 3での triplum f 音程のこうした変化は、その部分で明示的にキャンセルされない限り、歌手がその保持を期待するであろうソルミゼーションやテノールラインの最初に記されたF#に反することになる。 triplumのスクライブが、breve 3のg’からの下降を見て、他の声部を無視して、前のシャープ(fをmiからfaに変換)をキャンセルした可能性がある。したがって修正されなかった表記上のエラーが生じてくる。 その解釈上の矛盾は、a)最初のフレーズの間隔の狭いF-g間のゆれにおいてF♯を保持しながらのテノールの「通常の」読みと、第3部分での記譜されたf 私の見方は、breve3のtriplumのfナチュラルを、うっかりミスと見なすことである。Dr. Bettie Jean Hardenは、このロンドーについての3パートの対位法の問題を取り上げ、triplumは、Cantus / Tenorデュエットではなく、テノールとだけの関係で作られたのだ、そして、演奏では省略された可能性がある、としている。 モテットとロンドーの両方で、解決の遅延と関連して、tendencyソノリティーの時期尚早な出現は、特別な強さと前方での勢いを、楽曲の冒頭にもたらす。28 28. Lucy Cross (1990: 218) also comments on the attention chromatic "extrahexachordal" intervals attract when situated at beginnings of pieces, and on their reinforcement of forward motion |