| Chromatic beauty in the late medieval chansons T.Brothers |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| p163 Fuions de ci and conflicting signatures Senleches: Fuions de ci 楽譜の最初のみ Iacob SenlechesのFuions de ciは、Eleanor of Aragon (d.1382)の死を悼んだラメントである。シャンティ写本、レイナ写本 、モデナAの3つの写本で伝えられている。51 p164 それぞれのソースは、”署名”の臨時記号が同じ配列となっている。すなわち、cantusがb ♭、テノールとコントラテノールがb♭とE♭である。シャンティ写本、レイナ写本には、どの声部においても、内部の記譜された臨時記号を持たない。一方、モデナAは、6か所の独自の♯(と 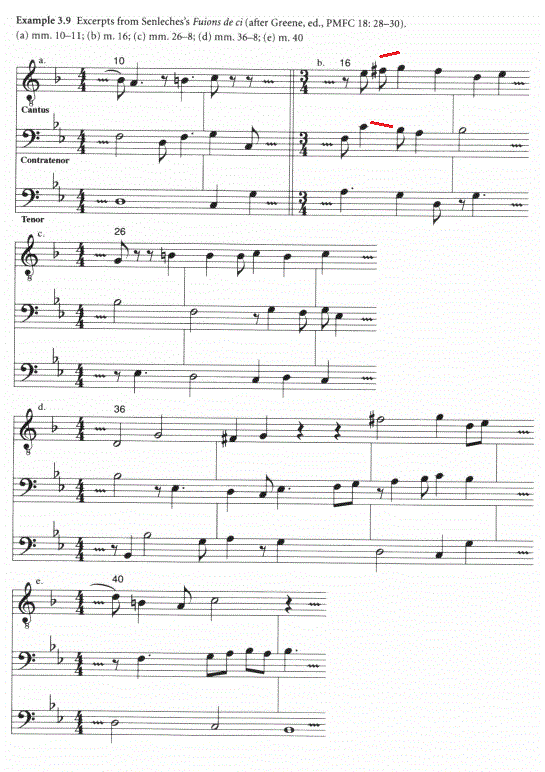 シャンティ写本、レイナ写本の間には、特に関連する明らかなパターンはない。そのために、2つの異なった解釈の評価が出てくる。(略) 典型的には、14世紀―15世紀初期のシャンソンにおいては、cantus声部は、テノールよりも1つ少ない♭を持っている。同様に典型的に、B-flatで終わり、強調をするソングは、Fuions de ciで使われている調号フォーマットを使用している。 conflicting signaturesに対する典型的なフォーマットにアプローチするには、2つの異なった方向からのやり方がある。まずは、なぜ、cantusにおいては♭がひとつ少ないのか、あるいは、テノール等にはエキストラな♭gあるのかを調べてみよう。この作品では、これらの疑問への回答が与えられる。すなわち、フォーマットは自動的に、カデンツ公式の有用な配列を産生し、カデンツヒエラルキーの目的のために役立っている。 第2章で我々は、導音が、ヒエラルキー的に、和声進行を区別するやり方において、どのように扱われているかを考察した。そうしたヒエラルキーは、作曲家の総合的計画の感覚に奉仕していた。 Fuions de ciにおいては、cantusにおけるe♭の欠如は、e 標準的調号フォーマットは、自動的に、この単純かつ効果的なカデンツ的ヒエラルキーを産生しているのである。 Senlechesは、パート1の最後のouvertでのD上の下げられた導音を、別の場でも使っている。(第15,31,34,43小節)。そこにはb♭上のカデンツが多くある。f上のカデンツは、パート2の到達における、選択的強力点を示している。(第29,39小節)。 例3.9で示されるように、モデナAには、b それゆえ、作曲家は、彼がカデンツ的ヒエラルキーをはっきりと定義する必要がなければ、付加的なinflectionsは要しなかったのである。conflicting signaturesに対する慣習的なフォーマットは、作曲家に、和声構成のための基本的ツールを与えたのである。 カデンツ的ヒエラルキーにおける精密な区別に価値を見出す繊細な作曲家を仮定すれば、モデナAに付加された♯は、そうでなければクリアなアレンジだったものに泥を塗ってしまったと結論づけできるのである。 p166 実は、テノールに付加的♭を加える伝統的フォーマットは、カデンツのヒエラルキーを産生するための方法として独自に生まれたのではなく、この現象のオリジナルな概念は、その後も廃れることはなかった。 テノールの”余分な”♭調号は、一般的に、シャンティ写本やOxford 213 の古い層において、miカデンツ(半音下降するカデンツ)を生じさせる。52 ここでの一般的なポイントは、伝統的なフォーマットに対して、和声的な説明を見つけ出すことである。53 Edward LowinskyやKarol Bergerといった学者らは、以前、同じ方向でこれを論じた。.Lowinskyは、署名フォーマットにおける変化が、カデンツ公式の変化とどのように関連していたかについて、強い関心を持っていた。54 Bergerは、テノールは一般的にcantusの下の完全五度の音域で動くので、垂直的な減五度の発生を避けるために余分な♭が使われた、と論じている。55(Musica Ficta p58-69) p167 Fuions de ciは、カデンツ的ヒエラルキーのレベルに対して、こうした和声的方向性をさらにステップアップして、示している。LikeLowinskyやBerger同様、私は、conflicting signaturesのメロディ的拡大には懐疑的である。 そこにはbi-modalityへの関心があり、ヘクサコードのマーカーとしての役割への関心がある。ヘクサコード的解釈への関心は、より流行し、おそらく、より広く受け入れられている。 connicting signaturesiにおけるヘクサコード的指向は、特に、Margaret BentとAndrew Hughesによって提唱された。56 理論家らは、調号は、調号が置かれた譜線にある間、指名された音を単にinflectionさせる、と言う。彼らは調号をinflectioninflectionの意味合いで説明し、調号と臨時記号の間の違いを、長さの問題として、説明する。 .BentとHughesは、それらを、ソルミゼーションをガイドするヘクサコード的マーカーとして解釈することで、調号から何か別のものを見出そうと模索した。 Bentは強調する。「♭記号は、 調号でフラット化された音符に対してもう一段フラット化された3つのヘクサコードの基礎的なrectaシステムの移調をもたらす」57 この見方においては、♭調号はe♭をさらに要求する。"rectaの音符”を作るために。ヘクサコード的移調についてのBentの発想では、E♭の調号はさらに、a♭の調号を要求することとなる。conflicting signaturesはさらに、異なる調号の声部で、重複しているが異なるヘキサコードの設定を通る動きを示す。58 こうした、調号に対するヘクサコード的指向は、inflectionに対する非記名システムを明らかにするための基礎となる。,BentとHughesは、 p168 もともと作曲家は、ヘクサコードを基礎としてではなく、カデンツ的ヒエラルキーにおける関心による選択をしていた。私は、E♭の選択はより弱く、不安定なカデンツを形成する決定を反映したことだろう、と論じている。その選択は、b♭記号に起因したヘクサコードシステムの移調とは無関係であった。 BentとHughesは、musica rectaとmusica fictaの間の区別が非常に重要であることを見出した。その間私は、その重要性が限定的であることを論じていた。読者はそれゆえに、inflectionsについての考えの2つの矛盾したやり方を知ることになろう。 根底にある概念の根本的な違いは、異なった音楽テキストを作りだす。そして、これらの音楽テキストでの臨時記号は、非常に異なったやり方で理解される。 理論的な記録の精査を基盤として、Karol Bergerは、「調号が、musica fictaの音程がmusica rectaの音程となるやり方でヘクサコードを移調する」という(BentとHughesの)考えへの反対を論じている。60(Manuscript Accidentals:Ficta in Focus 1350-1450 Andrew Hughes p83-4) 写本の精査をベースにすれば、私は彼に同意をする。Fuions de ciに対して、理論の意味合いを考えてみたい。cantusのb♭は、e♭をより要求する。しかし、この声部に、記譜されないe♭のバは明らかではない。そしてすでに見てきたように、e しかし、テノールの5つのaのうち、ほとんどは♭なしで歌われ、そして他もまた、♭付きで歌われた可能性は低い。これは、レパートリーを通して明らかである。すなわち、概して、テノールのE♭の調号は、a♭を暗示することはない。 理論が成り立つためには、それは、ある程度の一貫性のあるa♭を含むことによってサポートされることを期待せずにはいられないだろう。さらに、写本の照合は、その理論を支持する多様性の配列を生じていない。 たとえば、Fuions de ciのソースからは多様性はない。one could interpret along the lines of hexachordally implied accidentals made manifest; モデナAは♯がついているが、♭はない。 (略) p169 Lewis Lockwoodの仕事をその出発点として、Bergerは、議論を進めた。彼は、変異をより細かく制御できるようにするための手段として、臨時記号を2つのカテゴリーに分けた。 (その1つの)”慣習的な臨時記号”は、一般的に理解されていた演奏慣行の一部である状況を含むものである。一方で、(もうひとつの)の”非慣習的な臨時記号”は、記譜されていなければ、使われることがないものである。61(Musica ficta p162-88) 前者は、ソースからソースへと、日常的に変化する。なぜなら、そのinflectionが、記譜される必要がなかったから。あるスクライブはinflectionをはっきりと書き、別のスクライブは、当然と思われる臨時記号は省いた。 慣習が何であったかについての我々の感覚は、部分的には理論家から来ているので、このモデルは、理論を却下することを意味するものではない。もっとも重要なことは、写本の証拠を通して証明された理論である。(略) Fuions de ciが持つ変異は、ヘクサコード的分析を支持しないが、それらは確かに、気まぐれではない。それらは、我々の感覚からすれば明らかに慣習的である。Bergerの心証よりは広い感覚においてだが。 想像上の演奏慣行を破ることによって、慣習的そして非慣習的inflectionsのこうしたカテゴリーを採用することは、有用である。 慣習的なinflectionは、音楽理論の基本概念に対するそのやり方を見出したものであるが、非慣習的なinflectionsはそうではなかった。 モデナAの♯の背後のカデンツの論理を見出すのは、容易であるが、これらのinflectionが、シャンティ写本、レイナ写本によって伝搬されてきたinflectionのない版での作品を扱う熟練したパフォーマーには明らかだったであろうと想像するのは、少し難しいであろう。 たとえば、第16小節のf♯は、cantusとテノールの、六度からオクターブへの拡大につながっている。しかし、その拡大は、小節の弱拍部分においてであり、そしコントラテノールは、イヴェントを弱めている。 p170 第26-小節のb inflectionsは、カデンツの論理でサポートされているが、それらは、歌手らがinflectionされていないパートをルーチンに持っていくものの明らかなdocumentationを表すよりも、エディターの研究やアジャストメントを表すように見える。 GやC上の二次的なカデンツを強調することで、モデナAのエディターは、作品を、inflectionされない解釈のクリーンなヒエラルキーにおけるよりも、散漫にしている。彼の改訂は、近接的慣行を画一的にしようとしただけであるかもしれない。さらに彼の野心は、作品をより散漫にし、二次的なカデンツを強化することで不安定化する。いずれにせよ、そこには、より多くの臨時記号があるモデナAの編集パターンのいくつかの示唆がある。62 写本は、Matteo da Perugiaと関連しており、そして、強い編集者の手が入っていると考える余地がある。63 (略) p172 Sharps versus Flats より初期には♯が好まれ、のちに♭が好まれている証拠がいくつかある。 変化する嗜好の1つの兆候は、より古い層であるOxford 213 の第7冊子とより新しい層である、第1,4冊子のソングの間の比較を通した統計的シフトである。 第7冊子は、より古い歌が集中しており、この写本のもっとも古い音楽を保存している。20のそうしたソングのうちの4つはBaude Cordier(d.befbrel398?)の作であり、1つはars subtilior essay(De tous les biens, f.107v)である。67 ♯化した四度の顕著な使用を通して、Medee fuと関連した4つのソングは、ここにある。 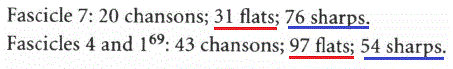 第7冊子のソングは♭の約2倍の♯を持っている。第1,4冊子では逆に、♯の2倍の♭がある。こうした傾向は、Baude CordierとDuFayiのソングを比べることで、ドラマティックにはっきりとする。 Baude CordierのソングはOxford 213 には7つある。1つには内部の臨時記号はないが、その他6つは、(合計で)27の♯と5つの♭を持つ。デュファイはさまざまな冊子で現れるが、特に第1,4冊子が重要で、10作が彼に帰せられている。これらのうち、2つは内部での臨時記号はなく、残りの8つのうちでは、♭が25、♯が3ある。少ないサンプリングではあるが、こうした比較によって、記譜された臨時記号の嗜好が見えてくる。 一貫性のないままに記録された演奏慣行によって、記譜上の証拠が汚染されているという疑いを完全に取り除くことは、決して可能ではないだろう。しかし、一貫した解釈やその他のパラメーターでの分析で、より完全に統合することができれば、作曲家がinflectionsをどのように行ったかについての、より確信的な記譜の傾向が明らかになるだろう。 問題の別のアプローチは、2つの一般的なメロディ形、ひとつは♯に特徴的、もう一つは♭に特徴的なものを比較することであろう。(例3.10) 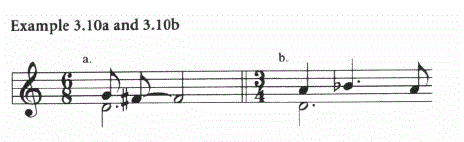 これらの音型は、多くのcantus行にて現れる。同じソングで両者を見出すことは稀ではあるが。これらは互いに皮相的な類似を示す。 p174 ♯音型は、Solage,70Velut,71Malbecque,72andLebertoul,73といったより古い作曲家らによって使われている。より新しい作曲家によってもこれらの音型は使われるが、おそらくそうした例外的使用は、古風な含意を示すものだったのだろう。これらの含意は、インパクトがあり、特殊な意味合いを持っていた。 一方、例3.10bの♭音型は、より若い世代と強く関連している。それは、シャンティ写本ではまったく現れないが、Oxford 213 の後半では現れる。77 1例は第3冊子で、その他は第4冊子で、特にBinchois,78Hugo de Lantins79,デュファイで。 ♯音型と♭音型を使い分けるポイントは、記譜法に関係している。例3.10では、計量記譜法は、♯音型では23 1400年頃の作曲家らは、1430年頃の作曲家のように、それぞれの計量記譜法の使い方において、自由であった。♭だろうが♯だろうが。しかし、1400年頃には2.3を選ぶ傾向があったのに対して、1430年頃には、3.2を選ぶ傾向になっていた。2.3は最終的には異色なものとなっていった。(たとえば、有名なL'homme armeのように). H.Besselerは、この変化をOxford 213 の古い冊子(5,6)と新しい冊子(4)の間の統計学的比較基礎として、解析した。81 第5,6、冊子においては、Besselerは2.3が8割であり、第4冊子では、3.2が66%であった。彼はまた、Escorial Aを引用し、そこでは3.2が91%であるという、劇的な新たなトレンドを主張した。 p176 こうした統計学基礎から、Besselerは、1440年までの間の様式的変化の解釈を提唱するに至った。彼は、3.2と、小節線的発想から自由な新たなより流動的なメロディプロファイルを関連させた。Strohmrhythmus,これが、この新たな様式に対する彼の用語である。例3.10bの府連リズムこそが、あらたな”カンタービレ”感覚の重要部分である。 Besselerは、2つの計量記譜法間の推移を、tempus perfectum diminutum (4)の使用を通じて遂行された、と考えた。 こうしたBesselerの主張はあまり認められなかったが、その分析は、現在の状況で非常に興味深いものである。なぜなら、計量記譜法における嗜好の変化は、Oxford 213 からの我々の集計で明らかになった♯から♭への思考の変遷を補うものであるから。 おそらく、計量記譜法と臨時記号の間の、この緩やかな関係性は、単なる偶然ではない。前者の変化は、Besselerが新たに思ったほどにはメロディ的慣用句を生じさせず、後者の変化は、全体のレパートリーの傾向として統一されるほどのことでもない。しかしこうした強調による根本的な変化は、一般的傾向として発展した両傾向を、条件づけたかもしれない。 例3.10の旋律音型は、問題の2つの計量記譜法に結びついているため、調査の焦点にくる。すでに述べたように、両音型の間の類似性は、皮相なものである。典型的には、和声的内容は、非常に異なる。♯を伴うシンコペーション的音型は、ダウンビートでの不協和音と、必然的に結びつく。例のように。ここではminim(増価された音価ではsemibreve)が、appoggiaturaとなっている。♯化された音程は、小節での協和音であり、通常は、近接したinflectionとなる。 3つのパラメーターが、互いに働いている。シンコペーションのリズム的緊張とappoggiaturaの不協和音は、近接したinflectionの和声的緊張を高める。 ♭音型は、まったく異なった構成となっている。最初の音はつねに協和音である。テノールはしばしば、cantusと平行六度で動き、時にはcantusが、留まったテノール上を、5-6-5あるいは3-4-3と動いていく。両者において、小節はおもに協和音であり、♭は装飾的につけられている。82 p177 それゆえ、2つの音型は、異なる効果を生み出している。これらの効果の時系列的な使い分けに何等かの意味合いを投影してみよう。 Oxford 213 の古い歌には、より新たな歌よりも、リズム的緊張が課されていることは明らかである。ars subtiliorは、こうした傾向のもっとも強い明治である。 より新しい歌のイディオムにおいては、よりリラックスした、より抒情的な、和音やリズムでより動きのあるメロディの流れの面に重点が置かれている。 これは、我々がBesselerから描いた一般的な点である。そしてそのようにして、我々は、例3.10の♭音型へのリズム的プロフィール ♯音型と♭音型は、2つの異なった様式的感覚の公式的な提示なのである。(♭音型の)付点音型のジェントルな強調は、そしてそれは、♯音型のよりアグレッシブなシンコペーションとは対照的である。 こうしたことを念頭において、Oxford 213 の集計に戻ってみよう。和声的緊張は、♯から♭への嗜好の変化を解釈するカギとなるだろう。近接したinflectionsにおける♭と♯の使い分けの働きによって、作曲家らは、ヒエラルキーとして、カデンツを互いに区別した。♯はclosの強い感覚を生じさせ、♭はouvertの特別な状況を生じさせている。その結果、♯は近接したinflectionsにおいては、♭よりもはるかに頻回に使われている。 例3.10aの公式は、シンコペーションや不協和音や和声的近接性由来の音楽的緊張の簡素な提唱であり、♭よりも♯に特徴的であることは、驚くべきことではない。 その他の恩恵におけるb♭(時にはe♭)を通したターンは、それが♯を歓迎するよりも♭を歓迎するであろう新たな抒情的インパルスの一部である。抒情主義と♭のこうした連関は、マショーのRose,lisを思い起こさせる。そして、それは、デュファイの実践における花との連関である。デュファイは、”美”のinflectionのポテンシャルを楽しんだ系統に属し、そして1430年代の彼の傾向は、この目的において、♯よりも♭を好むようになっている。 p178 一方、Baude Cordierは、アルスノヴァの良く確立された慣行とともに、ステップにおいてより一貫している。それは、♯の規則的な使用と、前方への駆動を維持する和声的緊張を含んでいる。(例3.8a参照)。  バンショワは、デュファイよりも若干前の世代である。Oxford 213 に残された彼のソングの臨時記号について、考えてみよう。写本は、計算すると、バンショワによる全部で28作のソングを含んでいる。これらのうち5つは、初期層に属している。 計量記譜法についてのBesselerの考察によれば、これらの5つすべては23であることがわかるが、それは、驚くべきことではない。そして臨時記号に対する我々の集計によれば、これらの5つのソングに対しては、Oxford 213 は32の♯があり、5つの♭があるだけであることも、驚くべきことではない。83 計量記譜法の選択において、バンショワは、古い冊子への規範的慣行と歩調を合わせている。♯への嗜好も同じように理解することができる。 ♯が、Amoreus suy とTant plus aymeのcantus(前者は6つの♯を、後者は7つの♯を持つ)に豊富なことは、特筆すべきと私は考える。84 そしてこの考察において、我々は、♯と♭のこの選択的な比較での最後のターンに到達する。 p179 cantusでの臨時記号の分析の制限は、解釈への可能性を開くだけのことだろう。制限は、cantusにおける臨時記号が特殊な状態であるという想定に従う。inflectionは、主要なメロディのデザインに取って代わる。cantusに注目して、我々は、首尾一貫した解釈で、以下の3つの成分を一緒に織り上げるためのより良い立場となる。 ①♯から♭へと変化する嗜好 ②cantusにおけるinflectionの特別な重要性 ③より理絡子下メロディ慣用句へのシフト。それは、2.3から3.2への計量記譜法の変化と関連している Amoreus suy とTant plus aymeのcantusの♯の豊富さは、特に、Oxford 213 のより新しい冊子でのバンショワによる23作のソングのcantusの♯の欠如と比べると、特にはっきりと目立つ。 このより大きなグループにおいて、1つのソングのみが、cantusにおいて3つの♯を持っている。2つのソングは2つの♯を持ち、その他は1つの♯を持つか、それを持っていない。こうした対照性こそが、Amoreus suy とTant plus aymeのそれぞれがバンショワの作品では初期の位置を占めていること、および、こうした初期の位置が計量記譜法の選択と♯の頻度・優位性の両者で反映されていることを、確かにする。 例3.11では、バンショワのAmoreus suy の省略形であるが、♯音型が2か所で使われている。 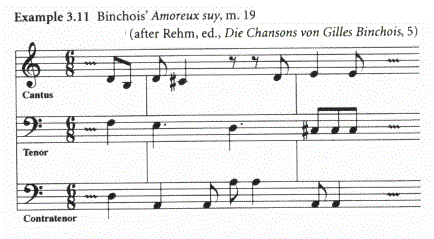 そして、Tant plus aymeのcantusでは、半音階が生じており(例3.12)、Oxford 213 の初期層のソングを思い起こさせる。  バンショワのTristre plaisirは、別の後期層である第3冊子に収容されているが、inflectionのインパクトが、必ずしもその量で決定されるわけではないことを示している。1つの♯が相当な緊張を醸しだしており、マショーの時代の古い作曲家を思い起こさせる類いである。 第8小節のcantusのf♯は、第5小節のテノールのF p180 このf♯とともに、cantusとtenorは長六度形成する。それは、理論的には、G/gへと直接解決されるべきなのだが、そうした解決は、ここではされていない。その代わり、行は上方へ跳躍する。その予想外の到達は第10小節のcで、そして第14小節のfでの結果となっている。cantusは、バンショワが彼の手慣れたスキルで作り上げた抒情的役割を担っている。そしてそれは、和声的緊張を生じている。 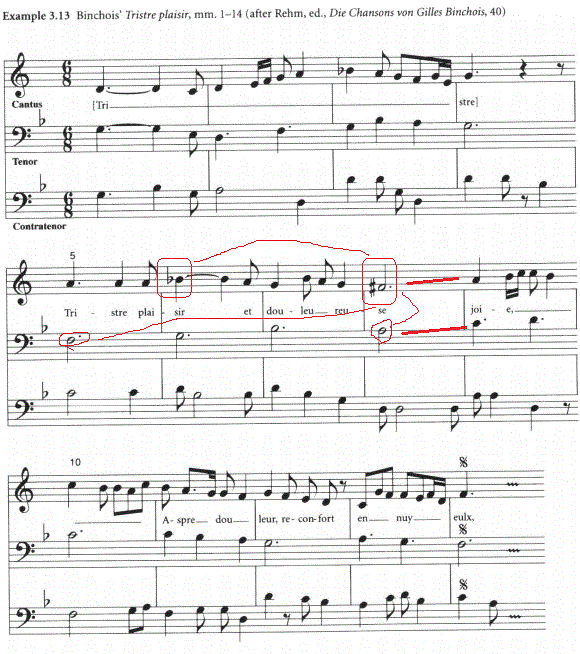 p181 3.2の計量記譜法で動くより新しい第4冊子において、バンショワは、cantus行に、引き続き数は少ないが顕著な♯を続ける。 2つのソングにおいて、♯は、繰り返しのsemibreve音型でinflectionされている(例3.14)。85 このAmours et souvenirにおいては、3.2の特徴的なエレガントな流れがある。f♯を通したターンは、突然であり、第9,10小節でf こうした繰り返しのsemibreve音型は、第2小節の付点音型のような、より後のメロディ慣用句の特徴を少し示している。 p182 バンショワやデュファイは、両者ともしばしば、繰り返しのsemibreves音型を使っている。しかし、デュファイはこのようなやり方で繰り返された音程のinflectionは決して、していない。86 バンショワはしばしばこれをしており、両者のこの小さな違いは、大きな観点からとは矛盾している。 3.2で動くOxford 213 でのデュファイのソングのうちでは、cantus行に♯を見出すことは稀であるが、いくつかの例外はある。87 一方、2.3で動く7つのソングにおいては、デュファイは、cantusの♯をうまく使う場合には、バンショワやより古い世代と歩調を合わせている。88 第4冊子の証拠は、バンショワがこうした慣行をより新しい慣用句において実現していたことを示している。彼は、それほどにはそれを使ってはいないが。デュファイは、そこから離れ、新たな発見をした抒情感性によりあった♭を使っている。89 p183 バンショワが実際、もしもデュファイよりも若干後の世代であったならば、その相違が考慮されたことだろう。あるいは、デュファイは多かれ少なかれ、彼の成熟したソングにおいて、♯をより抑制的に使う彼の傾向において、分離された存在だった。 マショーとデュファイの間の時代の臨時記号についての写本のdocumentationについては、以下のようにまとめられる。 ①マショーの音楽的遺産は、通常それに署名されているような世紀後半の存在を楽しんでいた。我々は、臨時記号についての彼の使用へのさまざまな言及を想像できよう。その他においても、マショーは、近接性を扱ったカデンツのヒエラルキーの発達に関与していたことだろう。 ②14世紀後半ばは、マショーを超えるものはほとんどない。数少ない例外は、 "musica ficta essay'と考えられるもので、散漫な様式の過激な示威である。その他のソングは、離れたフレーズやセクションにおいての、臨時記号の高い集中を特徴としている。 ③14世紀後半の主たる発展は広大なフレーズへの傾向で、時折、選択されたinflectionの顕著な使用を特徴とする設計とともにコーディネートされる。Medee fuは、Dで安定的に作られた作品で高い緊張点となるcantusにおけるg♯を特徴としている。 その他の作曲家らは、目立ち、外された♯をその最初のフレーズで使っている。この拡張性の流れで目立つようになると、inflectionが大きくなる。例外的に、Medee fuのような場合、それらの影響は、より長いスパンにわたって現れる可能性がある。 ars novaの時代には必ずしも一般的ではなかったが、近接したinflectionは、作品を前に進ませた。こうして、臨時記号は、grande balladeの世紀末の美学の発展に一定の役割を果たした。 p184 ④前に進ませるソースとしての♯からの和声的緊張の原則は、Oxford 213の古い層で、バラードだけでなく、Baude Cordierのお手軽なロンド―においても、規則的に発生している。次世代のバンショワやデュファイは、こうした慣行に従っている。 和声的緊張としての♯は、もっとも新しい写本ではより稀である。そこでは、和声的緊張生成を回避するcautusのメロディがより頻繁に発見される。Oxford 213で伝播されたもっとも新しいソング等(3 2)において、デュファイは、cantusのメロディを♯化したことはめったにない。Besselerに従えば、状況は以下のように解釈されることだろう。すなわち、近代のイディオムは、緩和された抒情主義への動きを示し、デュファイはそれを、こうした流れの中で、フラットを使用する方がより有益であると考えていた。 あああ |