| Musica Ficta9 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
|
Part III
Written and implied accidental inf1ection 8 Classes of accidental inflections in early vocal polyphony musica fictaという用語の音楽学的な使用法は、中世とルネッサンスの音楽が暗示的臨時記号を指すが、(それゆえに)ソースには記載されていない、という事実は、今では、まったく正しいことではないが、広く一般に流布されている。 これまでは、書かれていないが暗示的な臨時記号のinflectionの問題にあまり注意を払わずに、みせかけのステップの使用について説明してきた。それでも、当時の音楽によって要求されたすべての臨時記号のinflectionが、明示的に記されたわけではないという事実が、音楽学者がmusica fictaによって提起された問題に興味を持っている主な理由であり、それが今、私が議論したい事実である。 最初に検討する必要がある2つの非常に密接に関連する疑問は次のとおりである。 いくつかの臨時記号のinflectionが書き留められ、他のものが単に暗示されたのはなぜか?どの種類のinflectionを表記する必要があり、どの種類のinflectionを暗示することができたのか? 当時の理論家たちは、暗示の臨時記号の問題についてはめったに議論しなかった。彼らのほとんどにとって、問題は明らかに自明だった。そこで議論する価値のある問題はなかった。 14世紀後半に、匿名の著者がb.faとb-miの記号の意味を説明し、「一般に、それらを表記する必要はありません」と付け加えた。1 当時のほとんどの理論家は、暗示的な臨時記号に言及することを全く気にせず、同様の発言に限定した。15世紀後半Johannes Legrense は、チャントの♭と 我々現代人は、♭記号は、書かれていない限り歌わないと言うし、他の人は 次に、我々は、三全音を伴う第4旋法のイントロイトの詩篇を歌う必要があります。 少年や未開人の記号なしで歌うことが許されなければ、トランペットやベルの記号なしで食べることも許されません。♭記号は、minor semitone のソフトさのために、まったく甘いのですが、蜂蜜の方が甘くて、食べ過ぎると腹痛がします。したがって。♭と このカラフルな爆発の結末は、著者の意見では、♭記号は初心者向けに書き下ろされなければならないということであるが、経験豊富な音楽家たち向けではない。同様に、有名な一節で、ヨハネスティンクトリスは言う。 また、メロディックな三全音を回避する場合は、必ずしも、♭記号を追加する必要はありません。 むしろ、それが追加された場合、それは暗黒と言われています。それが追加されたと見られる場合、それは暗黒と言われてす。 p163 ティンクトリスの観察は、Legrense のそれと同様に、旋律の三全音のみに言及しており、和声および対位法的な文脈によって暗示される臨時記号も受け入れるように一般化できるかどうかは明らかではない。しかし、La Caliopea legaleにおいてJohn Hothbyは、「2番目または3番目(つまり、それぞれ♭と♯の「黒鍵」)が記号で明示的に明記されていない場合、または その意味合いは、垂直的に必要とされた臨時記号は、 mi against fa や水平的なそれと同様、必ずしも明示的に記譜される必要はない、ということである。 Bartolomeo Ramos de Pareia から巡って、我々はまた、E-Dに対するc-dの進行においてcが(半音)上げられるべきであると彼が説明するとき、カデンツの♯も書き留められる必要がないことを見出した。彼はすぐに、付け加える。「これを表現する場合は、次のように描写する必要があります。」 その意味するところは、このように表現されるかもしれないが、そうである必要はないということである。 <Aaron v.s. Zarlino> 同様に、16世紀初頭に、Pietro Aaron は、彼の Libri tres de institutione harmonica の中で、「diesis記号(♯)は、経験の少ない音楽家たちの利益のために、カデンツの導音で書かれている」と指示している。6 すなわち、より経験豊かな音楽家たちならば、そのような記号は必要ない、ということを意味している。、 AaronはToscanello in musicaでさらに言った。「あまり歓迎できない響きがする短三度をスムーズな響きである長三度に変更するためのdiesisの記号の使用について話しながら(Aaronは、ここではいわゆるピカルディの3分の1を念頭に置いているはずでである)、彼は以下のように付け加えた。 この記号は学習および経験のある歌手にはほとんど使用されていませんが、おそらく経験の浅い、頭の悪い歌手にのみ与えられています。適切な演奏は、この位置または適切なシラブルがなければ、得られないことだろう。なぜならmi-sol は自然に半音が入るので、こうした記号がなければ、経験の浅い、頭の悪い歌手は、書かれたものを耳の助けなしでは、歌えないだろう。7 Toscanello の補遺」では、Aaronはこれらの発言を大幅に増幅した。8 経験の浅い音楽家たちのみがこうしたコンテキストにidesis記号を必要とするようになったために、一般的慣行として、いわゆるピカルディの三度は無記名のままにできるようになったが、Aaronは、誤解の可能性を回避し、経験の浅い歌手を助けるために、とにかくこれらの臨時記号を書き留めることを勧めた。(Accidentals, Counterpoint and Notation in Aaron's Aggiunta to the Toscanelloin Musica' MARGARET BENTp306参照)9 Toscanello の”補遺”には、暗黙の臨時記号が現存する問題についての最も広範な議論が含まれている。 上記で言及したものに先行する関連するパッセージは、非常に興味深いものである。 10 アーロンは、臨時記号を記すべきかどうかという問題に関する限り、当時の音楽家たちの合意はなかったと証言している。一部の音楽家たちは、初心者のためだけに臨時記号を書き留める必要があったと主張している。 p164 アーロン自身の見解では、この最後の意見はメロディ的三全音を修正したフラットについてのみ正しいとされ、そこでさえ彼は、そのようなフラットを明示的に記した作曲家らを称賛した。 和声的なmi-against-fa を修正する臨時記号は常に書き記しておかなければならない、とAaronは思った。 このように、メロディ的な三全音と和声的なmi-against-fa の不協和が必要とした♭に関するアーロンの立場は、いわゆるピカルディ・三度が必要とする♯に関する彼の立場と同じであった。どちらの場合でも、理論家は、これらの臨時記号を表記する必要はないと考えた人々に反対した意見をまとめた。 アーロンが、”補遺”における導音の♯についての、単一の例を持たないことは注目に値する。そして、導音の臨時記号についても、まったく一例もない。(第6章(ii)で説明した、Richafortの♭は、octaveの前の長六度を作っていた)。 彼が導音のシャープは表記する必要がないと考えていた可能性がありますが、単純に”補遺”において見落としていた可能性の方が高い導音のシャープも明確に表記することを推奨することは、彼の立場と一致する。 Spataroもまた、1529年1月4日の手紙で、Giovanni del La goに宛てて、彼の時代の作曲に必要なすべての臨時記号が書き留められていなかったとは限らないと証言した。彼は、暗示的な臨時記号が議論された内容で、以下のように言っている。 したがって、楽器を上手に演奏するプレイヤーは、単に学識のない作曲家らによって作曲されただけではなく、特定の実践を通じて曲を演奏する、私はと言います。彼らは、記号がなされているものとして、それらを演奏します。 同様に、経験豊富な歌手もそうします。 多くの場合、彼らは作曲家によって作曲され、記号がつけられたものよりも優れた作品を歌っています。 Spataroには、作曲家が暗示するフレクションで偶然に気づいた演奏者の中に歌手と器楽奏者の両方が含まれているため、タブラチュアで暗示的な偶然の研究の貴重なタイプの証拠を見る研究者にサポートを提供しています。 Spataroは、作曲家が暗示したinflectionによる臨時記号を理解した演奏者の中に、歌手と器楽奏者の両方が含んでいるため、タブラチュアによって暗示的な臨時記号の研究の貴重なタイプの証拠を見る研究者にサポートを提供している。 当時の終わりに、Nicola Vicentino は、作曲家が必要なすべての導音の♯を書き留めることを強いられたので、このことは一般的な慣習ではなかったのだろう。13 一方、彼の同時代人、、Gioseffo Zarlinoは、作曲家がメロディ的に非和声になる四度、五度、オクターブ(訳者注;それぞれの三全音)によって暗示された臨時記号をあらためてマークすることは、余計なことだと思っていた。14 同様に、彼の意見では、カデンツの導音のための臨時記号の使用は、必ずしも必要ではなかった。おそらく、演奏者たちが、作曲家の意図を認識していたために。15 上記の理論的証拠は、ここで調査された全時代を通じて、性質と内容が非常に一貫しているため、この章の冒頭で尋ねられた疑問全体に有効であり、その時代全体にわたって有効である。当時の初めから終わりに至るまで、必ずしも臨時記号を書き留める必要はなかったのである。 p165 特に、メロディ的三全音を修正する♭は、書き留めずにおかれることが多い。ただし、対位法的なカデンツの理由で要求された臨時記号は、必ずしも明示的に表記される必要はなく、mi-against-faの不協和を修正するために必要なものでも、場合によっては省かれている。 さらに、これらの記号がないと、初心者は、経験豊富な音楽家らよりも迷う可能性が高いことがわかる。時代を経るにつれて、一部の理論家は、臨時記号を常に書き記すよう提唱しているが、彼らはそうした広範囲な慣行に反して、いくつかの臨時記号を記譜しないままとしている。 臨時記号が存在したというまさにその事実は、彼らが少なくとも時折はそれを使用したことを示している。つまり、ほとんどの音楽家らは、いくつかの臨時記号を書き記し、その他の場合は省略したのだが、正確にどれだけ表記し、どれだけ省略するかについては合意がなかった。 なぜ、いくつかの臨時記号のinflectionsは記され、その他はそうではなかったのか? 理論家らは、音楽的テクストによって暗示されたこれらの臨時記号を表記する必要はない(しかし禁止されていたわけではない)ことを、明らかにしている。 こうした態度は、暗黙の臨時記号の慣行について尋ねられるべき最も基本的な疑問と私が考えることを、速やかに提示する。すなわち・・・ <2つの領域> 当時の音楽における暗黙の臨時記号のnflectionsは、演奏にかかわらず不変であるべき音楽テキストの領域に属しているのか? あるいはむしろ、それらは、作品のアイデンティティを危険にさらすことなくテキストごとに変化する可能性がある演奏の領域に属しているのか? ここで提案されている音楽テキストと演奏の領域の違いは、何を表記する必要があるのか、何を表記する必要がないのかの違いとは同じでないことに注意してされたい。 音楽テキストのすべての必須な側面を表記する必要はない、という考えは、音楽表記の機能が、グラフィック形式で理想的な音楽テキストをfixしているという時代錯誤の仮定においては、puzzlingに見えるかもしれない。そういう態度は、 16世紀初期のドイツの理論にはいくつかの証拠が見つかるかもしれないが、それは、当時のほとんどの音楽家(そして18世紀後半までのほとんどの音楽家たちの見解)を表すものではなかった。16 当時の楽譜の主な機能は、分析のために完全な音楽テキストをグラフィカルに修正することではなく、演奏者に適切な指示を与えることであった。 こうした観点からすれば、本来は明らかに暗示されているものが明示的に表記されることは必要かもしれないが、必要ないかもしれない、という実用的な態度は、完全に自然なものであった。。 当時のポリフォニー歌手の音楽的訓練は、作曲家の訓練と同一であったので、そして作曲家は、彼らの作品を最初に演奏することが多かったので、彼らは、不完全な記譜で済ましていたのである。 さらに、当時の声楽ポリフォニーの記譜は、単純に、節約が必要だった。羊皮紙や紙は、当時からさらに長い期間にわたって、高価なものであった。17 p166 当時の声楽ポリフォニーが書かれたまさにその形式、クワイヤーブックやパートブックは、スコア形式よりもはるかに経済的で、必要な執筆スペースがかなり少なくて澄んだのである。 言語テキストのスクライブは、読者がすでに知っているような従来の省略形を使用することにより、スペースを節約できた。同様に、音楽のスクライブは、いずれにしても暗示されていることを書き留める必要はなかった。書かれた言語での略語の使用と、音楽を書き留める際に臨時記号を暗示にする慣習との間には、類似点があろう。 どちらの場合であっても、省略表記で表現された実用的な態度は、テキストの作者が、言語的テキストであれ音楽的テキストであれ、彼の略語を解読する特殊なやり方については無関心であったわけではないことは、強調されるべきである。 表記において、臨時記号のinflectionを明示的に指定するのではなく、暗示的にするという慣行が、そのようなinflectionが作品のテキスト、つまりさまざまな演奏においてそのアイデンティティを維持しているテキストに属しているのではなく、演奏の領域に属していたことを意味すると解釈されるべきではない。 そして(演奏における)ダイナミクス、アーティキュレーション、または運指のように、そうした(表記において、臨時記号のinflectionを明示的に指定するのではなく、暗示的にするという)慣行は、テキストのある実現から次の実現までかなり自由に変化したことだろう。 <Carl Dahlhausの論文> 当時の音楽の臨時記号的inflectionが、ここで音楽テキストの領域または演奏の領域と呼ばれているものに属しているかどうかという問題は、「Tonsystem und Kontrapunkt um I500」に関するI969年のCarl Dahlhausの論文によって特に緊急に提起された。 I8 Carl Dahlhausの出発点は、15世紀から16世紀初頭の音楽には、すべての非和声関係を回避することが不可能であるパッセージが含まれているという考察である。なぜなら、垂直方向のmi-against-fa不協和を修正すると、メロディ的な不協和が生じる、あるいはその反対になるため、である。 このような解決不能な競合はどのようにして可能となり、なぜ彼らは苦しんだのか、と彼は尋ねるのか? これを理解するには、彼が示唆するように、当時の対位法理論が、”完全八度”や”長六度”のような具体的な音程の名前ではなく、”完全”あるいは”不完全協和音程”のような抽象的な音程クラスの名前を使用して規則を策定したことに注意する必要がある。 垂直方向と水平方向の両方のmi-against-fa不協和、およびmi-against-fa不協和自体を回避する必要があるために生じた解決不能な競合は、特定の音程ではなく音程クラスに関するこのような抽象的な音楽的思考の結果であった。作品は、あたかも、完全五度かつ減五度の間の区別は存在しないものとして、想定された。 Carl Dahlhausの論点は、彼が提案した、音程クラスの面で想定された抽象的な対位法と具体的音程を扱う和声的対位法の間の区別に拠っていた。 彼は「私がここで、作品のアイデンティティを保持する不変的な音楽テキストの領域と呼んだものが属しているのは、前者である。後者は演奏の領域に属し、ひとつのrealizationから別のものへと変化する」と主張している。19 p167 残念ながら、I530年代より前からの対位法理論を注意深く読んでも、Dahlhausの区別はサポートされない。 もちろん、対位法のいくつかの規則が、音程クラスという面で、もっとも簡潔に表現されることは確かである。その他の規則は、具体的音程という面で定式化されていなければならなかったのだ。 ただし、後者の規則が前者の「補足」であると考えられていたという証拠はない。 15世紀初頭に、 Prosdocimus de Beldemandisが対位法の6つの規則を列挙したとき、彼は、 mi against fa の禁則についての彼の5番目の規則が、他の5つの規則に対して基本的ではない、または「補足的」であることを何も示唆しなかった。 20 さらに、「具体的な対位法」のlowly serpent は、「抽象的な対位法」のまさに中心部に近づく。その基本的な規則の1つは、Dahlhaus自身の説明によると、平行する完全協和音程の禁止である。 第5章(i)ですでに示したように、15世紀後半の理論家(Ramos、Gaffurius)は、2つの平行する五度のひとつが完全でもうひとつが減五度である場合に、この禁止が解除された可能性があると証言している。 当時の作曲家が「抽象的な対位法」の観点から作品を考案した場合、平行する協和音程の禁止に対するこの例外は理解できなかったことだろう。平行五度を書いて、これらが禁止されているのか許可されているのかを、彼らは知るすべはなかった。 しかし、Dahlhausの理論に対する最も根本的な異論は、それが内部的に矛盾しているということである。 Dahlhausは、15世紀の作曲家が彼の対位法を考案したとき、たとえば彼が「完全協和音程」の音程クラスの下でそのような五度を包含したため、彼が使用した垂直の五度の特別なサイズには無関心だったと私たちに信じさせている。 ただし、「完全協和音程」の一般的な概念は、五度音程に適用された場合、この五度のサイズを最も正確に特定するのに十分となる。完全協和音程のクラスに属する唯一の五度は、3つの全音と1つの半音からなる。 Dahlhausの仮説は、15世紀の対位法理論が「完全協和音程」ではなく、「五度」や「八度」などの音程クラスで操作された場合にのみ、内部的に一貫性がある。低い実証領域への無関心は、抽象化の表側である。 しかし、Dahlhaus が彼の慣習的な鋭敏さをもって、臨時記号のinflectionsを演奏の領域に委ねようとした彼の失敗した試みが解決することを意図していた以下の二つの問題を特定したことは否定できない。 その第1の問題は、水平的、および垂直的なmi against faの不協和の間の解決しがたい競合の存在である。 この問題は特に重要ではないのだが、それは、こうした競合が、一般的に信じられているほど頻繁には起こらないためである。 音楽学者らが今まで、このような競合が常に生じるという印象を持った理由は、彼らが、水平的あるいは垂直的な非和声的関係の禁則に対するあらゆる例外に気づかなかったことである(本書Chapters 4(i) and 5(i)参照)。 p168 もちろん、時折はこの競合が生じるが、作曲家がこの問題に無関心だったと結論づける理由はない。真の競合には、作曲家がいくつかの規則を無視して(作曲家の側の単純な技法の欠如か、伝播の仮定で、記譜されたテキストになされたエラーか)、自分のために提起した技術的な問題を解決できないなど、さまざまな個々の原因が含まれていた可能性がある。(解決不能な競合のDahlhaus自身の例として、Nicolaus Gombert の Mass Media vitaの‘~Agnus Dei' [see Example 39]がある。21 そこでは、 垂直のmi against fa は第45小節の最初において、寛容されている。なぜなら、作曲家は、アートフルな6声の連続が続くことを望んでいるから)。 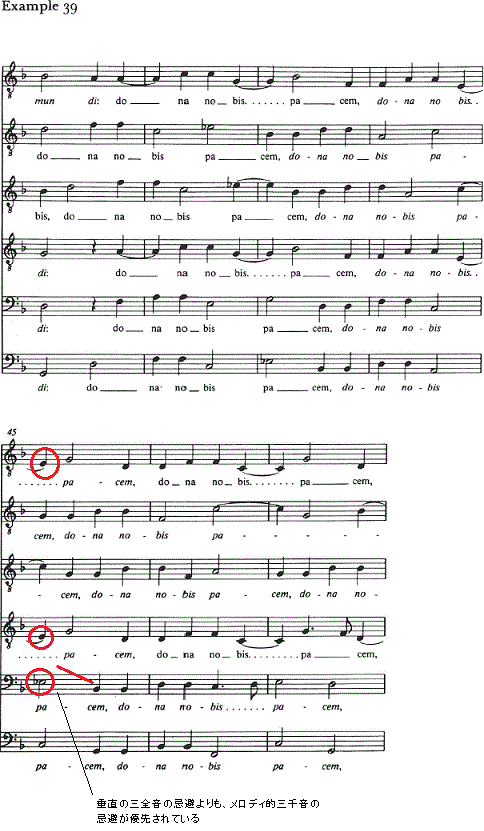 ダールハウスの仮説で取り上げられている2番目の問題は、より根本的なもので、暗示的な臨時記号が音楽テキストではなく演奏の領域に属しているという考えが魅力的であると思われる主な理由が、少なくとも臨時記号を必要とする一部のコンテキストが、代替的な解決を認めているためである。 これまで見てきたように、そのようなコンテキストには2つの異なるクラスがある。一方では、音楽家らが臨時記号適用するかどうかを迷うボーダーラインの状況がある。 (より多くの音符があると感じられた場合、メロディ的な三全音の方が不快感が少なくなる。三全音が不快であるかどうかが演奏家によって決まるという境界線の場合があることだろう。同様に、すべてではないが、カデンツに関連付けられている基準を満たす進行は、特定の進行をカデンツとして処理するかどうかを演奏家自身が決定する機会を彼に与える場合がある。そして、五度か四度の所与のカノンと模倣を正確に維持するかそうでないかの決定は、演奏家にゆだねられることになる)。 他方では、inflectionが必要であることに疑いのないコンテキスト(A-カデンツなど)があるが、そのinflectionの選択(♯か♭か)は任意となっている。 さらに我々は、当時の歌手たちが、テキストを実現させるやり方について、時折、不合意があったことを知っている。 Lewis Lockwoodは、I540年頃、多くのローマの音楽家たちを動揺させた臨時記号の問題に関する議論を魅力的に詳細に議論した。22 確かに、代替の解決策を認める状況は、臨時記号を適用する方法が1つしかない状況よりもはるかに頻度が低い。だから彼らは、規則ではなく例外を示す。 しかし、こうした例外のまさにそうした可能性は、考慮を要する。我々は、すべての臨時記号のinflectionsを、演奏の領域に委ねようとは思わないので、いくつかのケースでの二者択一での解決の可能性は、音楽テキストの領域と演奏の間のボーダーラインが、臨時記号のinflectionsのエリアを交叉することが示される。 当時の音楽でのもっとも臨時記号的なinflectionは、記譜されたかにせよ、暗示的であったにせよ、不変的な音楽テキストの領域にはっきりと属しているが、いくつかはそうではなく、変化する演奏の問題もまた存在していのである。 p170 臨時記号的にinflectionされたステップは、こうした点において、決して唯一なものではない。また、全音階ステップは、ボーダーの両側にある場合がある。 「抽象的な」と「具体的な」対位法の区別を文書化することはできないが、当時の音楽家たちが、シンプルな、note-against-noteの、作品の根底を供給する協和音程の対位法と、不協和音とリズム的ヴァラエティを伴った構造を装飾した減価された対位法の間の基礎的な区別をする面において、ピッチ構成について考えたことは、疑いない。 この区別は、装飾的な減価の表層が、基礎的な、note-against-noteの、協和音程構造を明らかにするために容易に取り除かれた理論と音楽自体の両方で十分に文書化されている。即興的な装飾(たとえば、カデンツでの)を可能にしたのは、この基本的な区別であった。 しかし、さまざまな装飾的な音符の存在から、基礎的な単純な対位法を形成しないすべてのステップは演奏家の領域に属するとは結論づけられないように、臨時記号的なinflectionsが単純にオプションであるということで、すべてのinflectionsが音楽テクストの観点からは無関係であると考えるべきではない。 Dahlhausの結論には、臨時記号的なinflectionsに関する限り、「”正しい”版を目指して努力するのは無意味である」という正当化はない。 それどころか、ほとんどの場合、多かれ少なかれ、不完全な表記法で解釈をしている演奏者によって正しく理解された、意図されたテキストに関しての暗示的臨時記号の問題を考えることは適当である。 当時のより優れた作曲家や演奏家たちは、正しい旋律、和声、対位法的な使用法に関する共通の様式的規範を共有していた。 作曲家、または音楽テキストの所与の版を編集した人は誰もが、これらの規範に従った解釈を示す演奏者を頼った。 ローマでの論争に巻き込まれた歌手たちが先ほど言及したまさにその事実は、独立した音楽のジャッジに従って、臨時記号的なinflectionsの適宜の使用が、個人の好みや恣意的まぐれの問題ではなく、合理的に議論され、一般的に共有された規範に基づいて裁定された可能性があることを示している。 関係するすべての音楽家たちは、音楽テキストはいかなる方法でも解釈されることができず、正しい解釈があったことを明確に想定していた。 いずれにせよ、16世紀初期には、演奏において実現された意図されたテキスト面での暗示された臨時記号の問題について考えることは、時代錯誤なことではないことが示された。そして、14,5世紀の音楽家たちが、この問題について異なって考えていたと強いて疑う理由も見出せない。 AaronのToscanelloへの"補遺”においては、臨時記号的なinflectionsは作曲家の問題ではなかった、と仮定することはできないだろう。 理論家が、意図されたテキストを理解しようと演奏家たちが試みていたことについて考えていたことは、特に、歌手たちが、作品の初見において、作曲家の意図を理解することを期待されたかどうかという疑問についての議論において、全体的に明らかである。 p171 Spataroに素直に追従したAaronは、経験豊富な音楽家たちがそれ(作曲家の意図を理解すること)を行うことができると信じていた人々に反対の論陣を張ったことが、思い起こされるだろう。SpataroとAaronのテキストは、暗黙の臨時記号の問題は作曲家の意図とは何の関係もなく、暗黙のinflectionは完全に演奏者の管轄下にあると主張したい人々に思考停止を与えている。 繰り返すが、表記の機能は、演奏者に適切な指示を与えることなのであった。音楽内容が臨時記号的なinflectionの必要性を暗示している場合、臨時記号を書き記すことは、余計で無駄なことであった。 しかし、すべての内容が、inflectionを等しく明確に暗示しているわけではなく(クワイヤーブックまたはパートブック形式では、メロディコンテキストで必要とされるinflectionの必要性を、カデンツ、特にハーモニックコンテキストで必要とされるものよりもはるかに簡単に見つけることができる)、また、すべての演奏家が同じように経験豊富であったわけではないので、厳密に言えば余計であったとしても、いくつかの臨時記号が役立つ可能性はある。その結果、それらは書き記された。 書かれていないが作品の音楽テキストによって暗示されている臨時記号は、編集された作品のテキストに明確に属しており、書かれたソースの臨時記号と区別する必要があります。 音楽テキストと演奏の領域の違いと、テキストの領域に完全にではなくほとんどが属している暗示的な臨時記号的なinflectionの理解の間で私が描いた区別は、テキストの領域内で、我々の編集の慣行に直接関連している。 Arthur Mendel は、'The Purposes and Desirable Characteristics of Text-Critical Editions 'についてコメントし、暗示的な臨時記号は演奏家の実践の問題であったので、現代の批判的な編集には含めるべきではないだろう。 24 もちろん、臨時記号的なinflectionが演奏の実践の問題であったことは事実であるが、それらが、不変的なテキストの領域に対する、変化し得る演奏の領域に属していた、ということにはならない。 暗示的なinflectionのほとんどが音楽テキストに属していること、および初期の音楽家が共有していた態度とは異なり、我々は、ソースにおけるinflectionsのはっきりとした説明が、編集者の避けられない責任であると、結論づけねばならない。 書かれていないが作品の音楽テキストによって暗示された臨時記号は、編集された作品のテキストに明確に属しており、そこでは、書かれたソースの臨時記号と区別する必要がある。 音符に関連した、直接的な譜線上のこうした暗示された臨時記号を置く標準的な編集上の慣行は、こうした機能をはっきりと節約的に実践し、それを改定する理由もない。 しかしさらに、編集者は、彼がオプションと考えるものから必須のものと考える、これらの暗示的な臨時記号を区別する手段を持つべきである。 たとえば、カデンツをどのように認めるかという私の議論から、そこには、ある演奏家たちがカデンツとして扱い、別の演奏家たちはそうではなく扱うような、ボーダーラインのケースがあるであろうことが考えられる。 こうしたオプショナルな暗示された臨時記号は、明らかに、必然的に暗示された臨時記号からは区別されるべきである。たとえば括弧を使って。 p172 最後に、特定のコンテキストでは、二者択一的な解決が可能になる場合がある。編集者は、たとえば、特定のA-カデンツで下側または上側の導音を許容できるが、そのような代替の暗示的な臨時記号を示す明確な方法を見つける必要がある。 たとえば、下側の導音に、音符上に♯/ ある音楽家たちが必要な臨時記号を書き記し、他の音楽家たちがそれらを書き記さないような暗示的なinflectionのグレーゾーンが実際に存在する理由は明らかである。 しかし、絶対に書かなければならない臨時記号のクラスが存在したかどうかを調べることは有用である。なぜなら、それらは音楽的内容によってまったく暗示されなかったからである。 そのような、絶対に書かなければならなかった臨時記号には、2クラスがあった。 第1は、作曲家が、本書で説明されているメロディ、ハーモニー、カデンツ、カノンとしての理由以外の理由で、慣例ではないという理由で使用できた、内部の臨時記号である。 原則として、少なくとも我々は、たとえ理論家たちが、非慣習的なことは規則に記されないために、相応の理由で一般にこの可能性を無視したとしても、ソース内の内部の臨時記号の一部がこの絶対に書かなければならなかったクラスに属する可能性を排除することはできない。 第2の絶対に書かなければならなかった臨時記号は、署名された臨時記号に関するものである。 署名された臨時記号は、非常に特殊な状況では、暗示されることもあった。こうした状況の1つは、Eでのみ、またはAのみでの♭記号の使用であろう。 Eでの♭署名は、このEがfaであり、完全四度下でのutを暗示する。つまり、E♭の下の(Bは)B♭を暗示する。同様に、Aでの♭署名は、このAがfaであり、完全四度下でのutを暗示し、長二度上(B♭)でのsolを暗示し、A♭の下のEはE♭を暗示し、A♭の上のBはB♭を暗示する。(訳注;それぞれBでの♭、B,Eでの♭がなくても、近代和声学がそのまま適用される) 署名された臨時記号が暗示される可能性がある別の特別な状況は、カノンでる。良い例は、デュファイのロンドー Entre vous , gentils amoureux 25であり、規範規則では、テノールが書かれたcantusから五度下で入ることが指示されている。 テノールと音域を共有するコントラテノールが♭記号を持っているという事実は、テノールもまた♭記号を持っている必要があることを意味する。(つまり、デュファイが、テノールを念頭に、cantusの音程の正確な複製をしたことを意味する)なぜなら、署名の結果として生じるこうした組み合わせは、この旋法の15世紀初期の作品としては通常のものであったから。コントラテノールのみが♭署名を持っていたという状況は、非常に珍しかったことだろう。通常、署名された臨時記号は、コンテキストによって暗示できななければ、書き出す必要があったのである。 p173 しかし、この結論は、当時の音楽にいわゆる ‘conflicting' or ‘partial' signatures が存在するため、修飾する必要がある。第3章(p69)で私は、「異なる声部で異なる署名を持つ作品では、旋法を定義する声部での署名の機能は、旋法の移調を実行することであったが、他の声部での異なる署名は、主にそれに対する完全五度を保証するために、主に旋法を定義するそれとともに'conflict'するものと捉えられるべきであろう」と示唆した。この'conflicting' signatures の見方が正しい場合、結論を修正する必要があるかもしれない。 旋法を定義するパートの調号に関する限り、それは有効である。なぜなら、従来はコンテキストによってこの署名を暗示するやり方が明らかではなかったためである。 しかし、これは‘conflicting ' signaturesにも有効であろうか?答えは、条件付で「いいえ」である。'conflicting ' signatureは、2つの方法で暗示される可能性がある。 まず、そのパートの署名に、それに関連した旋法を定義するパートの上下の音部の署名を支配する慣習が存在したため、その慣習を知っている歌手は、たとえば、彼のパートが、旋法を定義する声部の下にあるのを見て、念のために、彼の署名にフラットを追加するかもしれない。 次にに、同じ歌手が表記どおりに自分のパートを歌い始めると、旋法を定義するパートの同時のF(と三全音を形成しない)のために多くのBをフラット化する必要があり、署名にB♭を追加することにした。 (これは、偶然にも、Lockwoodにおいて議論された臨時記号についてのローマの論争でバスが行ったことであり、バスのアクションに反対した歌手が、旋法を定義するパートであるtenorの責任を負っていたことは注目すべきことである)。 しかし、'conflicting' signature が暗示される可能性のある両方のやり方は、内部の臨時記号なものが暗示される可能性のある方法とは多少異なることが観察されるだろう。違いは程度の問題である。内部の臨時記号は、曖昧さがはるかに少なく暗示される。'conflicting' signatureは 、暗示される可能性はあるが、曖昧さはほとんどない。 たとえば、バスのすべてのBが、上声部のFと競合する状況はまれである。通常、‘conflicting' signature は、certain degreeにのみ含まれる。この領域では、不完全な表記法を読んでいる歌手は、彼が暗示された内部の臨時記号の領域で頻繁にできるのと同じようには、彼がその意図を正しく理解していると確信することはできない。 我々は、当時の声楽ポリフォニーの生産、伝播、および演奏に責任のあるいくつかのクラスの人々を区別する必要がある。 生産側では、作品には(当然ながら)作曲者がいて、いくつかの異なった版がある場合、各版には、(必ずしもそうではないにしても)それぞれ編集者がいる。編集者は作曲者と同一であったかもしれない。伝播と演奏の側では、歌手だけでなく、筆記者や印刷業者もいた。 p174 これらの人々はすべて、実用的なソースで見つかった臨時記号に対してさまざまな程度で責任を負っていた可能性があり、ソースの臨時記号を評価するときに、それぞれの貢献を区別できると、我々にとっては、便利である。 この章の調査結果は、当時のの声楽ポリフォニーの実用的なソースで見つかったすべての臨時記号は、2つのクラスに分類されることを示唆している。 26 一部の臨時記号は、それを暗示する可能性がなかったため、作曲者または特定の版の曲を編集した人が書き記す必要があった。他の臨時記号は、作曲家または特定の版の編集者によって書き記された可能性があるが、作曲家または編集者によって暗示され、他の誰か、筆記者または実行者によって書き記された可能性もある。 したがって我々は、、”権威的である”ような”非従来的”なソースの臨時記号と、”権威的ではない”であろう”従来的な”それとを区別しなければならない。 最初のグループは、従来の音楽的状況や旋法を定義する声部の調号を訂正するために、そこにない内部の臨時記号を含んでいる。 2番目のグループには、上記の第4-7章で説明した理由で従来使用されてきたすべての内部の臨時記号と、‘conflicting ' signature臨時記号が含まれる。 すべてのソースの臨時記号を2つのクラスに分割することで、実りの多い少なくとも4つの領域が見られる。 最初に、ここで私が描く、内部的臨時記号のinflectionsの従来的使用と非従来的使用の区別は、調性言語の発展に関する将来の研究に影響を与える。 中世後期およびルネサンスの作品の慣行における非従来的な内部のinflectionsの使用と機能(構造的および表現的の両方)の研究は、真の半音階主義の発達の理解に貢献したことだろう。 そのような真の半音階主義は、従来的なmusica fictaステップの使用と区別する必要がある。その使用は、全音階的で、増価も減価もされていない音程を維持したいという願望から基本的に明らかに派生したものである。 従来的な、暗示的なinflectionの慣行は、どちらかといえば、半音階主義には反対であり、これら2つの現象を混同すべきではない。16世紀の真の半音階主義の成長が、すべての臨時記号を書き記すという理論家のますます頻繁な呼びかけの背後にある重要な要素であったというのは、疑わしいであろう。 第2に、作品での旋法を定義し、異なったパートで異なった署名を持つ”conflicting" signaturesの機能の間の区別は、初期ポリフォニーのモダリティのより正確な理解への道を開いている。 p175 第3に、特定のレパートリーにおける「従来的な」ソースの臨時記号の機能の調査は、 どのようにして、我々が知るこうした状況が、代替的解決がこの特殊なレパートリーで扱われたことを認めたかを知るようにa study of the functions of 'conventional' source accidentals in a given repertoire would allow us to learn how those situations which we know may have admitted alternative solutions were handled in this particular repertoire . Howard Mayer Brown は、この点に関して、ボーカルモデルのリュート インタヴォラトゥーラ(鍵盤楽器やリュートなどの独奏楽器用に編曲されたもの)の賢明な評価からどれだけ多くのことが学べるかを示している。 27 我々は、ボーカルポリフォニーのソースの臨時記号から、多くのものを学ぶことだろう。 我々は、理論的な証拠の助けを借りて、代替の解決法を許容したコンテキストのタイプを特定し、そのようなコンテキストが実際にどのように特定の時間および場所で実際に処理されたかを知るために、「従来の」ソースの臨時記号の証拠を最大限に活用する必要がある。 第4に、ここで描かれたすべてのソースの臨時記号を2つのグループに分けることは、初期の声楽ポリフォニーの批評家や編集者にとって興味深い意味を持っている。 ただし、これらの影響を詳しく説明する前に、編集者が何をすべきかという一般的な仮定を述べなければならない。 テキストの批評と編集者は2つの目標を念頭に置く必要がある。 最初に、彼は作品の完全な音楽テキスト、または作品のいくつかの連続した本物の版のテキストを現代の表記法で再構成する必要がある。 次に、編集者は、作曲者の希望とは関係なく、テキストの履歴を再構築する必要があります。この履歴には、すべての区別された真ではない版が含まれている。そうした作品は、文書化されて流通した。 概して、「最高の」真正なテキストのみを確立し、作品のすべての異なる真正および非真正な版を再構築するタスクを無視することを目的とした現在の編集慣行は、音楽への関心が作品の側面だけでなく、受容のそれからも興味を持つ歴史家の観点からは不十分である。28 各版について、表記されたテキストによって暗示されるすべての代替実現、当時の慣行について私たちが知っていることの観点から可能な実現を詳述し、代替の読み取りの相対的妥当性を評価することを目指す必要がある。 29 上記の前提を念頭に置いて、ここで、初期のボーカルポリフォニーを編集するためにこの本で提案された「非従来型」(「権威的」)と「「従来型」(「非権威的」)のソースの臨時記号の違いの意味合いに戻りたい。 この区別には、2つの潜在的な利点がある。 第1に、特定の作品の異なる版を区別できるようになること。もしもソースが、かなりの程度、”非従来的な”臨時記号において異なっているのであれば、それらは、作品の異なった版で伝播されたに違いない。なぜなら、”非従来的な”臨時記号における違いは、演奏においても、なくならないからである。 他方、”従来的な”臨時記号を持つソースの間の違いは、それがいかにドラスティックであろうと、ソースが作品の異なった版を伝播したことを示さない。なぜなら、そうした違いは、演奏においては、なくなってしまうか、少なくとも広汎にreductionされるからである。 このことは偶然にも、”関連したソースの方法論”に関するAllan Atlasの思想が、おそらく、ソースの臨時記号に関する限り、若干の改定がなされたことを示唆している。30 p176 Cappella Giulia chansonnier Atlasと一致するソース間の関係に関するAllan Atlasの研究は、ソースの臨時記号は、「それらを共有するソースが必ずしも関連していることを示すものではない、記譜上の特徴に属している。なぜなら、そうしたことは、2人以上の筆記者が互いにまったく独立して非常によく起こしていたからである」31と結論づけた。 この結論は、「従来型」のソースの臨時記号に関する限りは確かに正しいのであるが、おそらく「非従来型」のもの(には当てはまらないので、これ)を除外するように改訂する必要がある。 「非従来的な」臨時記号のソース間の違いは、「重要な変異」を構成している可能性がある。その違いは、「2人の音楽家または筆記者が互いに独立して作業することによって(それを非常によく起こしていたとは)考えられなかった」。32 誤解の可能性を回避するために、ここで強調しておきたい。「権威的な」の臨時記号は、作曲者または「編集者」のいずれかに由来する可能性があるために、この我々の分類は、異なった版の相対的な信頼性を評価するのには役立たない、ということを。 しかしそれは、我々が正確に、異なった版を区別するのには役立つ。そしてそのような区別は、各版の信頼性を評価するための必要な前提条件である。(我々がその他の基準からのアシストを求めるとすればそれは、たとえば、作曲家に対する特定の版を伝播している地理的、時系列的なソースの近さである。) ここで提案されたソースの臨時記号の分類の2番目の利点は、編集された作品の各版内で「非権威的」である可能性のある臨時記号から「権威的」である臨時記号を区別できることである。 筆記エラーまたは印刷エラーの可能性を除いて、「非従来的な」臨時記号は、その背後に、特定の版についての作曲家または編集者の権威を持っているが、その権威は、”従来的な”臨時記号にはない。なぜなら、伝播の過程で作曲者や編集者以外の誰かによって追加されたのではないことを確信できないためである。 もちろん、この2番目の利点は、特定の版の信頼性の問題を調べて、それが作曲者に直接由来することがわかった場合には、特に価値がある。 したがって、上記で区別された2つのグループに属するソースの臨時記号は、権威の程度が異なる場合がある。もちろん、書き記されたこれらの臨時記号は(作曲家によろうが編集者によろうが)、もっとも権威がある。 このグループに属する非従来的な内部的臨時記号のケースでは、かなりのcareがexercisedされたことだろう。すなわち、作曲家や編集者以外の人が、たとえば、実際には存在しないような垂直的なmi against faを予想して、誤って臨時記号を付け加えていただろう。この手のミステイクは、critical reportに属しており、編集されたテキストにはない。 p177 明らかに、ミステイクがないものとして、旋法を定義する声部の非従来的な内部的臨時記号や調号を受け入れることは、より容易いことだろう。それらがコンテキストに現れた時や、臨時記号を要求する問題を誰かが誤って予期した可能性がないようなところ、あるいは、それらが、作品の所与の版で2つ以上のソースに見られる時ならば。 その他すべてのソースの臨時記号(2番目の ‘‘従来型 ’、グループのもの)は、作品の演奏履歴に関連しているが、所与の版の作曲家または編集者が意図したテキストに必ずしも関連していない。 一部は、筆記者、出版者、または演奏家によってテキストの伝播において追加され、作成者(つまり、指定された版の作曲家または編集者)が意図したものではなかったと考えられる。 しかし、このグループのすべての臨時記号は、それらが現れるコンテクストによってある程度正当化されるので、著者が意図していないものを認めることはほとんどない。 このグループの臨時記号のうち、問題の作曲家または編集者に近いと我々が信じる独立した理由があるもの、および所与の版の複数のソースに現れるものは、もちろん、restよりも権威がある。 編集者は、このグループのすべての臨時記号を評価する必要がある。めったにないことだが、テキストの伝播で追加されたものから、著者が意図した臨時記号を区別できる場合には、後者を譜線上でのワークに含め、前者は、作品の演奏履歴を文書化しているcriticlal reportに移管させることになるだろう。しかし、ほとんどの場合、このタイプの臨時記号は、すべて譜線上のテキストに含める必要があるだろう。 テキストによる批判とより高い批判の両方に対するソースの臨時記号を分類することによって提供される利点の全面的な実証は、もちろん、現在のワークの範囲を超えている。ただし、サンプルの問題のいくつかの利点を説明するのには役立つ。 p180 <Dufay ロンド―Navre je sui d' un dart penetratif の解析> 例40(略)は、Heinrich Besseler によるギヨーム・デュファイのロンドーNavre je sui d' un dart penetratif を示している。critical reportの適当なセクションと共に。 ソースを一見すると、「非従来的な」臨時記号では、それらソースがかなり異なることがわかる。たとえば,Figure5 Ms.Oxford. Bodleian Library.Canonici Miscellaneous 213[O].fol.78vとFigure 6,Ms,Paris,Bibliotheque Nationale,Nouvelles Acquisitions Francaises 6771[ PR],fol. 98rは、テノールとコントラテノールに1つの♭署名があるが、それは、Emには欠けている。前2者は、”非従来的な”内部のe♭を第18,22,25,26小節に持っている(さらに、第23小節ではaa♭がある)が、Emではすべて欠けている。 p184 これらのすべての違いは、critical reportに正式に記載されているが、それらは解釈されないままになっているため、これらの違いの知識は、編集の対象となったユーザーにとってほとんど価値がない。編集を利用している音楽演奏者または歴史家は、臨時記号のinflectionsに関して、ソースが、曲の2つの異なる版で伝達されていたこと(1つはOとPRで、もう1つはEmで)に疑念を持つことができなかった。 ソースの臨時記号を「従来型」と「非従来型」のものに分類し、OとPRには存在するが、Emには存在しない非常に多くの臨時記号が、後者のクラスに属しているという認識だけが、我々をこの結論に到達させることができる。 2つの版の違いは非常に顕著である。 Emを使って演奏する歌手は、単一の♭のinflectionを行う必要はなかっただろう。 Emによって要求されている唯一の臨時記号的なinflectionは、第4小節のsuperiusとcontratenorの暗示的な導音f#とc#だけである。 対照的に、OかPRのどちらかを使って演奏する歌手は、もちろん、これら2つの導音に加えて、臨時記号のinflectionsの多くが、ほとんど書き記されている。いくつかは暗示的であるが。 もしも彼らがOを使って歌ったとしたら、彼らはおそらく例4I(略)に示されているinflectionを実行したことだろう。 34。 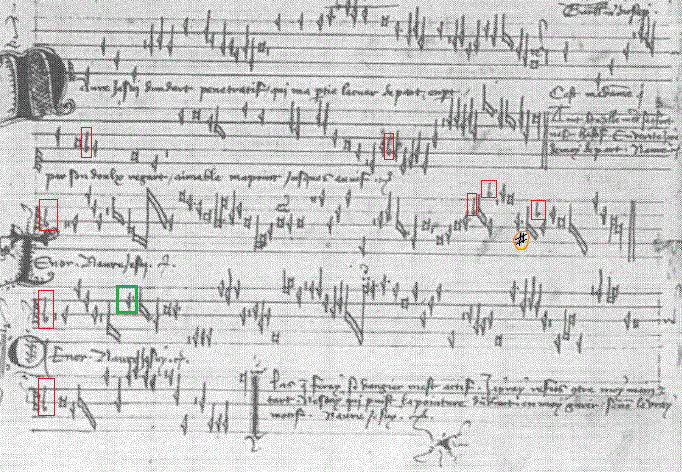 Figure5 Ms.Oxford. Bodleian Library.Canonici Miscellaneous 213[O].fol.78v 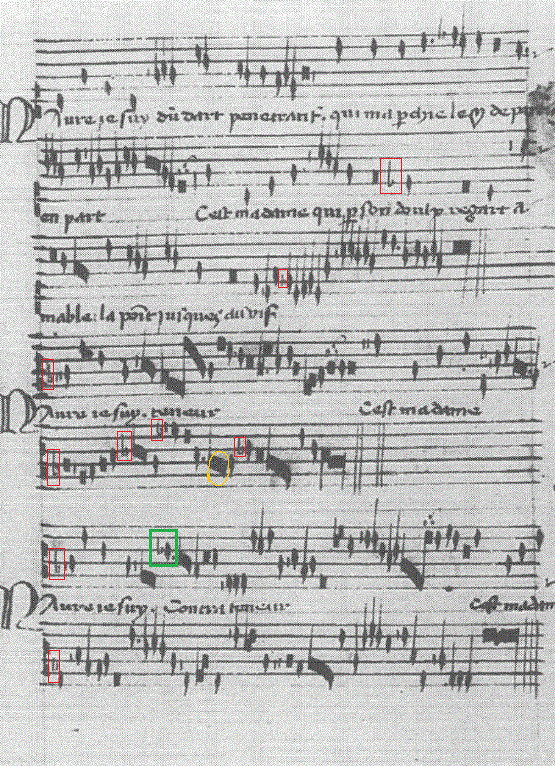 Figure 6,Ms,Paris,Bibliotheque Nationale,Nouvelles Acquisitions Francaises 6771[ PR],fol. 98r 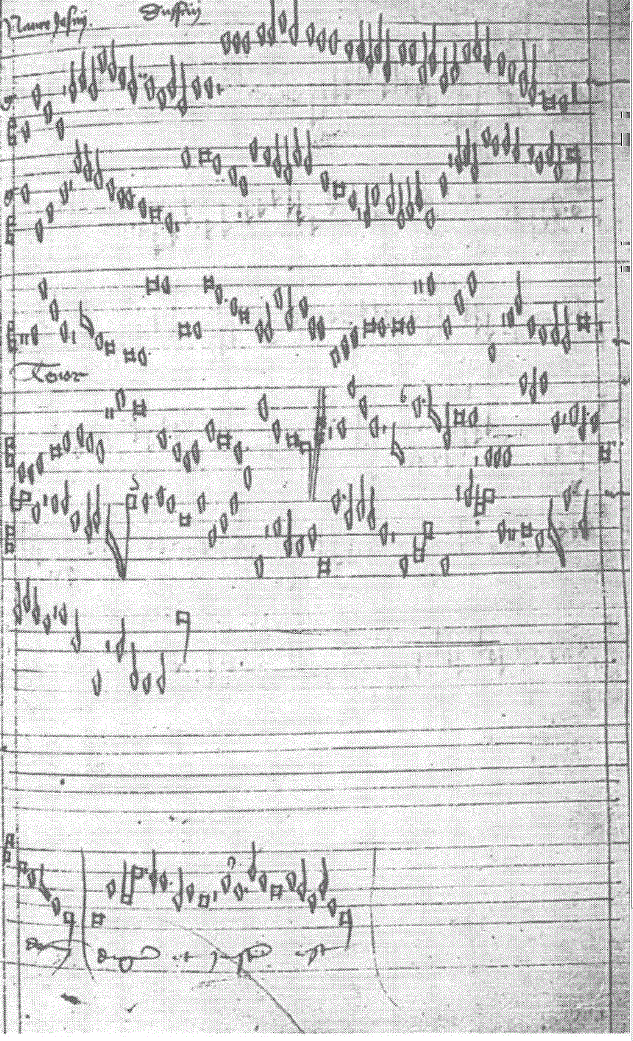 Fig7.Ms.Munich, Bayerische Staatsbibliothek,Latinus monacensis 14274(olim Mus.3232a;Cim.352c[Em],fol.96r p186 2つの例外を除いて、彼らがPRから歌った場合、彼らは(Oと)同じinflectionを行う。その例外の1つは、コントラテノールが第3小節で、PRではeが♭化されることである。 (♭はPRのコントラテノールには書き出されているため)。そしてもうひとつの例外は、テノールが第25小節で、PRではbを♯化( これについて完全に確信することはできないが、問題の2つの臨時記号は「非伝統的」であると見なされるべきであり、したがって、OとPRの違いは、演奏ではなくならないだろう。 もしも第3小節の♭が”伝統的”ならば、問題の伝統は、長六度の上方スキップを短六度にすることが規定されねばならない。そのような慣習が、デュファイの時代に存在した可能性を排除することはできず、その問題は写本の臨時記号の助けを借りて調査されるべきであろう。 Emの同じところでは、伝統の存在をサポートする糸口を示すかもしれない。すなわち、eの前にはfのところに配置された♭があり、それはつまり、eがmi( しかし、想定される伝統の問題が調査されるまで、すなわち、PRでのe♭は「非伝統的」である可能性が高いと想定すべきである。 同様に、第25小節でのbでのmiの記号(♯)を、カデンツでの導音としての♯化と見ることも出来るが、そのメトリックな配置やフレーズ内での位置を考慮すると、もしもそこに臨時記号がなければ、歌手がこのbを導音として扱うことはまずあり得ない。 我々は次に、2つの異なる版で伝播された作品に直面し、2つのマイナーな変異の存在のひとつは、ほとんど、演奏ではわからなくなったことだろう。 しかし、テキスト評論家の義務は、編集された作品の個別の版を整理したことにとどまらない。また、信頼性に関して版を評価する必要がある。 2つの版の相対的なメリットと権限を評価することは難しくない。 Oは約I420-36年頃におそらくヴェネツィアかその周辺でコピーされた。35 シャンソンを含むPRの.35レイヤーIIIは、およそI430 -40年頃に、おそらくフランスの書記によって、パドヴァまたはVenice.でコピーされた。36 p187 Emの2番目の層には、当時の歌が含まれ、1430年代から1440年代の初めに、ウィーン大学でI436年とI439年の間に教育を受けた司祭で書誌学者でもあるHerrnann Poetzlingerによってコピーされた。37 これらの事実だけで、Navre je suiのO-PR版はおそらく、作曲家の意図を表しているとするのには、十分であろう。 一方、Emで伝播された音楽テキストは、おそらく本物ではない。 (言うまでもなく、それだからといって、価値がないというわけではない。なぜならそれは、我々に作品の受容ついて何かを教えてくれるからである。そして、その存在は、批評版のレポートではっきりと記されるべきである。) 本物の版内の2つの変異は、より難しい選択を私たちに提示する。出所の日付と起源の場所の知識はここでは役に立たない。なぜなら、2つの写本は、作曲家の伝記の既知の状況に、時系列的にも地理的にも近いので、そのために、同等に良い主張をすることができるからである。 しかし、デュファイのシャンソンの最も信頼できる音楽テキストを検索し、その曲の解釈を試みた場合には、説得力のある選択を行うことができよう 。 より高い批評によって武装されて、我々は、テキストの批評のレベルに戻り、利用可能なバリアントから選択することができる。 (略) ロンドーのO-PR版について、2つの厄介な臨時記号なしで少し考えてみよう。テキスト同様、ルフランの音楽は、14小節分と15小節文の2つの半分に、それぞれ分けられる。それぞれは、2つのテキスト化されたフレーズとテキスト化されていないmelismaで構成されている。 両半分のそれぞれは、似たような始まりから聞こえてくる。それらは両方とも、c-e gの三和音のモチーフで始まる。そして、両方とも、3声部からなる模倣で、このモチーフを提示している。これら2つの機能(三和音モチーフと3声部からなる模倣)は、デュファイの時代ではまだあまり一般的ではなかったため、注目を集めるであろう。 しかし音楽の両半分は、相同であるだけでなく、互いに対抗もしている。すなわち、後半の最初のモチーフ(g-c-e-g)は、前半の最初のモチーフ(c-g-e-c)の裏返しである。 一度この対抗性に気づくと、両半分が、(g-c-e-g)と(c-g-e-c)での三番目のステップのバージョンもまた異なっていることがわかる。すなわち、前半はすべてにわたってe-mi(e p188 ロンドーにおけるe-faの構造的機能は、リフレインの両半分の間のコントラストを強調することであると考えられる。 38 38 D.Fallows Dufay p100 このsongsは、1430年頃に特殊化したデュファイの魅力を特徴化している。それは、特に、Cを基礎とした、長調と短調の三和音交替である。この問題はすでに、 Besselerによって、Terzfreieitと呼ばれていた、三度の動きである。13 Navre je suiにおいて、最初の声部のインターロックは、Cmajorの三和音を主張し、第3小節や第7小節のE♭の出現が、明らかになるようになっている。C上の三和音におけるこうした三度の動きは、デュファイの作品で現れ続け、彼の最後のミサ曲、Ave regina celorumでその頂点に達する。 さらに、コントラストが修辞的に動機付けられている可能性がある。つまり、e-faは構造的なだけでなく、歌において修辞的な役割も持っている。 39 ルフランの前半で、叙情的な主題は、彼のanatomyの本質的な構成要素が、それ自体を見いだす孤独な状態について説明している。すなわち、「私は、私の心臓を突き刺した貫通するダーツによって借りられています」。このような事故は戦闘中に発生する可能性が最も高く、デュファイの音楽的レトリックのトピックは、冒頭のモチーフに適切な武道的な三和音のトランペットのファンファーレである。 しかし、リフレインの後半では、我々は、戦闘や馬上槍試合のコートから愛のコートに移され、負傷した主人公の責任を負う騎士が誰であるかを知ると、モチーフが逆になる。 ”柔らかく、優しい一見で、それを素早く刺したのは私の女です。 '” 前半の”貫通するダーツ”は、女性の「 ‘ doulx regart' 」と同定されており、デュファイがこの曲の最初の「柔らかい」e(e♭)を伴うのは、この「ソフト」武器となる。(ちなみに、音楽の両半分の間で、対照的に、隠喩的に動くe-mi /e-fa を考慮すると、Emがテキストを持たないことは、確かに重要である) この解釈が受け入れられると、PRによって要求された第3小節のコントラテノールでのe♭は、デュファイの意図ではないことが明らかになる。それどころか、eの その結果我々は、、Oが、デュファイの意図に最も近いロンドーの解読を伝播しており、PRの変異は本物ではない、と結論づけられる。 つまり、この例が示しているのは、この章で提案されたソースの臨時記号の分類が、初期の声楽ポリフォニーの編集に関するテキスト批評家と、伝統的に、musica fictaと”真の半音階”を区別して私がここで呼んだものについての構造と表現の機能に関心のある重要な歴史家の両者の有用なツールになる可能性があることである。 |