| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC4-2 |
| Holy WeekMusic and Carols at Meaux Abbey2 p135 CANTUS-FIRMUS TREATMENT ほんのわずかな例外を除いて、典礼の部分の作曲は、ポリフォニー的な文脈で、想像上のリズムの計量的メロディとして現れるプレインソングに基づいている。メロディスタイルが関係している限り、自由に作曲された作品とパラフレーズの間に明確な区別をつけることはできない。 したがって、チャントとポリフォニック設定の関係についての議論は、プレインソングに依存しない作品の簡単なレビューから始めるのがよいだろう。 このカテゴリに完全に該当する作品は、Alleluya Laudate pueri(第15番)とAudivi(第19番)の2つである。両者は、 gymelsとして非常にスムーズなやり方で書かれている。 Audivi(例4)からの抜粋は、このスタイルを説明しているだけでなく、同じテキストからの自由でパラフレーズされた作品を比較することができるために選択されている(例7下参照)。 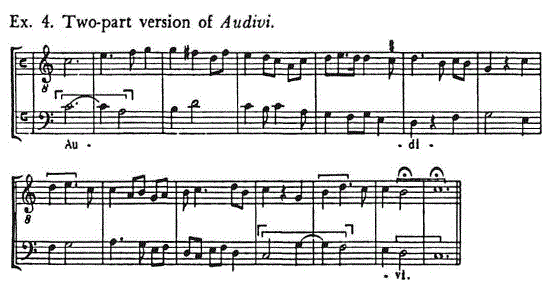 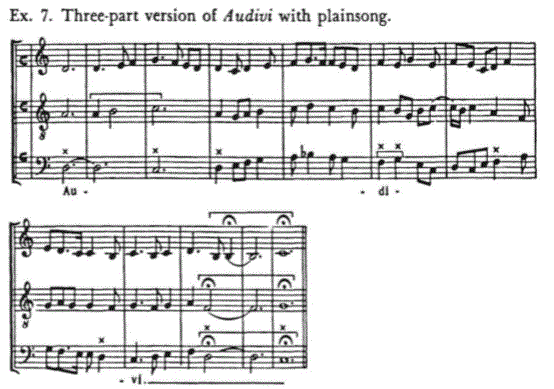 このカテゴリの他の2つの設定は、パートだけで、自由に作曲されている。 Gloria laus(No.4)の第2版は、おそらく最初の引用の後にチャントを放棄している。 プレインソングへの曖昧な言及はmigrant cantus firmusの下で議論されるであろう。 もうひとつの部分的に自由な作品は、ヒム0 redemptor(No・9)である。8つあるそのverseのうち、既知の典礼的なメロディとの関係はない。 p136 スタンザがメロディ的に異なるという事実は、それらが同定されていないプレインチャントに基づいていることはほとんどないということである。 交替で3.2.4声部で8つのスタンザを設定する場合、作曲者はconductusスタイルの限界内で、できるだけ多くのテクスチャを採用しようと努力してきた。 そこには4声で2つのスタンザがあるだけである。Stans ad aram (Ex. 5) と Laus perhennisである。それらは、4つの別々の譜表にスコア記譜法で書かれている、4つの独立した声部への唯一の2つのconductus設定を示すものとしての、非常に特別な興味がある。 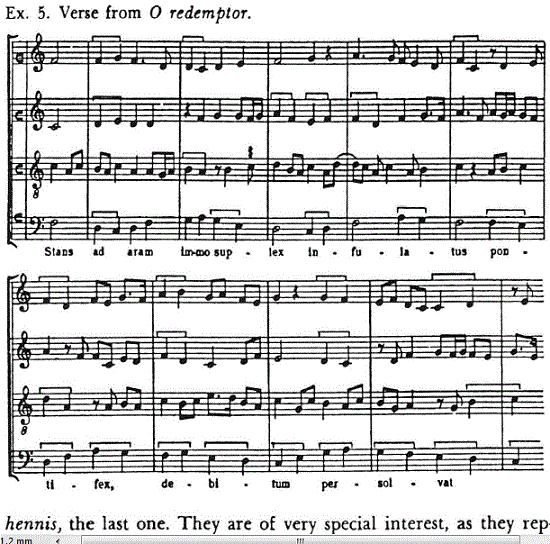 Ex.5から、4声書法はかなり不器用であることが見て取れる。なぜなら、実際のバスラインは、(デュファイの後期作品では進化していた)はまだ存在していないために、かなりの難しさを示しているに違いない。 テノールは他の声部とほぼ同じペースで、真のconductus流で動くが、声部のリズムの独立性は全体として扱いにくく、かなり詰まってしまう。 声は絶えず交差し、お互いの音域に入り込み、時には激しく衝突する。 こうした状況は、上声部の多くの短い休符が、実際にはリズム的な正当性を持たないことを示しているが、しかしそれは、パート処方の難局を解決するための手段に過ぎない。 p137 バスの音域の欠如においては、音域は非常に制限されている。4声のトータルの音域においては、12度を超えることはなく、テクスチャーは、ななめにさえ交差している。それぞれのパートは自身は、テノールと正しい進行をしているのに、あちこちでハーモニーのクラッシュが起こる。パートの積み重ねは、やぼったい効果を作ったが、音響の豊かさもまた、創造した。それは明らかに、作曲が目指していたものであった。 設定は明らかに、conductus様式や、現代のカデンツにまでまだ進化していなかったハーモニーのイディオムにおける4パート書法の限界を乗り越えた。2つの設定は非常によく似た六度コードのカデンツで終わる。 2つのPassionは、朗読の伝統的トーンをベースにしていないので、それらは、知られていないものを使うか、自由に作曲されている。後者の自由作曲が正しいとしても、デクラマシオン的様式は強く、tonus currensを示唆し、そこでは、音楽は限界的カテゴリーと自由な作曲の間の中間に置かれる。 システム的には、2つのPassionは互いに非常によく似ており、特にそれらのハーモニーの戻りや保持されたコードはそうである。これは、聖マタイ受難曲(Ex.6)からの抜粋であるが、聖ルカ受難曲のハ長調部分と比べてみるべきである。 p138 受難曲が通常、ミキソリディア旋法で、大部分はソやレで終止するのに対して、それらはドラマティックな理由(疑問文や感嘆文などのように)で、ラ音やファ(♯)のようなあまり結論的ではない音符で終止する。そうしたカデンツは、Ex.6の疑問文hec?において生じている。 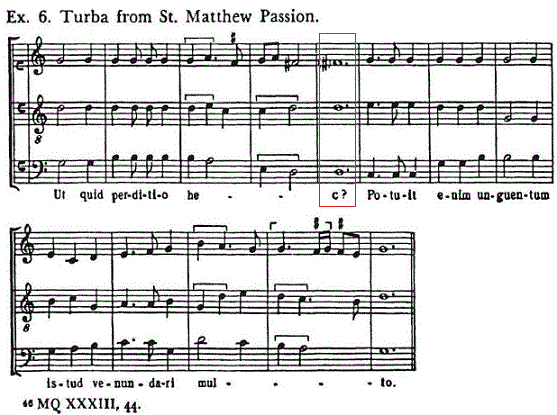 カデンツでの多様なinflectionは無論、直接、典礼的なrecitationから借用されている。極端なデクラマシオンのために、fauxbourdon様式はそれ自身を、受難曲において、その他のコレクションの作品よりも、よりオープンに示す。ある種のセクションにおいては、そのもっとも基本的形式においてさえ、繰り返される六度コードが現れている。47 47This simple forn of fauxbourdon was favored by Burgundian composers in the compositions of canticle see the settings of the Magnificat by Binchois . 受難曲の初期の様式は、このタイプのもっとも古くから知られた作品としての歴史的役割を演じている。しかし、発展したポリフォニー受難曲は、モデナ写本の聖マタイ受難曲において見られるかもしれない。後者の作品は、Ex.6の同じ言葉に含まれている抜粋において、アクセス可能である。 モデナ写本の受難曲は、少なくとも6声以上で書かれ、モテット流のテノールのcantus firmusを担っている。両作品は、繰り返し和音において言葉をdeclamationしているが、英国の作品を特徴づけている3拍子での鋭くリズム化したrecitationは、2拍子のデクラマシオンの進行に対し、イタリアの受難曲に広がってきている。あとの作品は、近代のカデンツの鷹揚な使用を行い、通常ではないフル音響に対して著明である。 典礼的部分の残りの作品は、さまざまなやり方で、プレインソングを取り扱う。motet Cantemus Dominoを除いてそれらのすべては、典礼的メロディを複雑に扱っている。それらは、厳密なcantus firmus流に音符を置くのではなく、ポリフォニーの衣装を単純に纏ってもいない。しかし、それを、個々の精神における色彩化によって解釈している。 それらは、メロディの客観的な声明または「プレゼンテーション」から、時代を減るにつれて、それ自体がますます増えるように感じられたより主観的な「解釈」への重要な転換を示している。 芸術家の「個人的な音符」は、借用したメロディの変換において、彼がそれをパート音楽に設定するように光が当てられる。 LoMでは、この個人的な傾向は、メロディがはっきり認識できるような、初期の段階でしか見られない。自由なtrebleのスタイルへの同化を通して、メロディーはその本来の質素さを失う。 melody loses its original austerity and acquires a new human , even inlimate qualily. p139 Pepys MSはおそらく、モノフォニックのこの変換の最も明確な例を示しているが、特別に作曲されたチャントのバージョンである。 ここでcantus planusは、旋律的な装飾と計量記譜法によって、canlus fractusになった。 例えば、賛歌Inventor rutiliは、最初にこの興味深い1声の形(fol. 62)でPepys MSに現れて、それから直後に、LoMに記録されているように、3声で現れる。 LoMにはcantus fractiはないが、その他のほぼすべての形のcantus firmusの扱いが見られる。これらは3つのグループに分類される。チャントが (1)テノールで (2)migrant cantus firmusとして1声で (3)trebleで 担われるのである。 最初の2つの選択肢は、このコレクションでは、非常に稀である。trebleがplainsongの精巧さのために好まれた声部であるという事実は、まさにfauxbourdonについて言われていたことを裏付ける。 一つの可能性、すなわち全体を通しての中間声部としてのチャントの提示が、このコレクションに完全に欠けていることは驚くべきことである。この状況は、他のどの要因よりも、一般的なスタイルと特に、cantus firmusの扱いに関してのMeaux AbbeyとOld Hall MSSとの違いを明らかにしている。 OHの古い層やLoF Add.40011 Bの同様の設定で最も頻繁に生じているのは、まさしく、中間声部の中のプレインソングなのである。重要なことは、これら(OHの古い層やLoF Add.40011 Bの中間声部でのcantus firmusの設定)はグレゴリオ聖歌のメロディーの控えめで古風なポリフォニー化以上のものを与えず(訳注;cantus fractus化しない)、自由なtrebleスタイルでのミサ曲とは明らかに異なっている、ということである。しかしながら、OHとLoMの内容は、他の点では同じであるかもしれないが、cantus firmusの異なる扱いは、15世紀のイギリスで、音楽的慣習がいかに急速に変化したかを示している。 応唱Audivi(No.18)は、チャントが最も低い声部に現れる唯一のケースである(例7)。  これは、主にEnglish discantの影響を示す唯一の例として興味深い(訳注;英国の'faburden'を意味する。大陸での’fauxbourdon’との違いに注意。faburden参照)。 (本来)即興のこの形式が、ここでは書き出して示されている。 English discantでは、(trebleに置かれた)チャントは、faburden(訳注;原文’fauxbourdon)として、自由に振る舞えない。なぜなら、チャントのその位置が、自由なtrebleのスタイルの使用を妨げるからである(訳注;faburdenでは、対旋律がcantusの上に来るため。faburden参照)。 この例では、色付けはほとんどない。 音符はしばしば1つか2つの小節で持続している。 それでも、旋律の精巧さへの要求を、動きのあるリズムによって始まる自由な挿入において、見つけることができる。 音楽の中心は、最も低い声部でのroundであるが、trebleは,それ自体ではっきりとしたかなり華やかなメロディーである。 作品のパート書法は、もちろん、即興のEnglish discantの限界を超えている。それでもなお、純粋な六度和音進行が見られる。 (see m. 4-12) 。 p140 migrant cantus firmus の作品群は、Gloria laus (Nos. 1-2 ,and 4)の最初の(そしておそらくは2番目の)設定からなる。migrant cantus firmusのパラフレーズ手法は、trebleのcantus firmusのパラフレーズよりも通常自由であるため、例えばNo.4の方の例のように、疑わしいままの例がいくつかある。 冒頭のチャントの間違いない引用の後に、ある声部そして別の声部というような、不規則に現れるつかの間の言及がある。migrant cantus firmusにとっては、チャントがどこにでも現れるので、故意または「無意識」の言及として、音楽に対してチャントを読み込む危険性は、声部の数とともに増加する。 verseのカデンツのいくつかは、プレインソングの言葉と一致するが、その他の多くはそうではない。もしこれがmigrant cantus firmusであるなら、それはその種の最も自由な例のひとつとなろう。 Gloria lausの最初の設定(Nos. 1-2〉は、その一方で、疑いもなくチャントを複雑にしている。チャントは非常に自由に扱われるが、カデンツは常に遵守される。第3節’Plebs Hebrea’の冒頭から見られるように (Ex. 8)。 p141 gymelとして設定されて、多くの三度と六度は自由に交替するので、それはfauxbourdonのやり方で第3声部を即興でつけることは不可能である。 cantus firmusは終始、migrantではない。例2が示すように、断片のrepetendaは、trebleにそれを持っている。最初のverseの最初のセクションは、下の声部だけが保存されているgymelが、同様の方法で復元できている。同じverseの2番目のセクションでは、ほとんど何の装飾もされていない。写本に完全に保存されているその後のverseでは、cantus firmusは、2つの上声部の間で主に前後にさまよっている。 trebleの精巧さ、このコレクションにおける、一般的かつ傑出したcantus firmus技法は、前に述べられなかったすべての作品に適用される。 このグループの特定の作品(例えば、No.5および11)では、チャントは、一時的に中間声部に現れることがある。 これらのデュエットセクションは、設定内の相対位置が変更されないままであるため、cantus firmusをmigrantさせない。 精巧さは、典礼用メロディのほぼ正確な声明から、かなり華やかなバージョンまで多岐にわたるが、後者においても、チャントはそのアイデンティティを失うことはない。 p142 Salve festa dies (Nos. 13 and 13a)の2つの設定は、両者が同じcantus firmusに言及しているかのように、2つの選択肢を提供している(Ex.9)。  この初歩的な2拍子のFauxbourdon進行は、特に注目すべきことである。 Missa brevisの楽章は、精巧なグループに属している。 そのシラビックな簡潔さのために、グレゴリオチャントのメロディーは、楽章に適切な長さを与えるためのかなりの装飾がなされる。 様式的にMissa brevisは、ブルゴーニュ楽派の後塵を拝している。それを同じチャントで構成されたBinchoisによる2声の Sanctus と3声のAgnus Dei とで比較することが重要である。Binchoisの使ったものはは英語版とバチカン版(LU、No. XVIII)のどちらにもまったく合致してはいないが。 様式的類似性は、フェルマータの頻繁な使用だけでなく、時には文字通り同じになる和声進行で顕著である。 p143 メロディへのチャントの投影は、通常、cantus firmusのひとつの音符が,計量記譜の版のひとつのperfectionに対して有効であるやり方において、効果を持つ。こうした音符はしばしば、それぞれのmeasureの第1拍と一致し、それゆえに、O redemptor (Ex.10)の冒頭に見られるようなことが、必須なものとなるして、際立つ。  こうしたパラフレーズのタイプは、Guilielmus Monachusの書法に見られるような、cantus firmusの扱いの非常に機械的なやり方である。 我々は、LoMにおいて、借用されたメロディが計量リズムにおいて現れる(しかし装飾音符は少ない。なぜならチャント自体がメリスマ的だから)別の設定を見てみたい。そうしたタイプの設定は、Unus autem (Ex. 11) の冒頭に見られる。これは、それぞれの単一音符のほとんどtrebleがほとんど借用である。 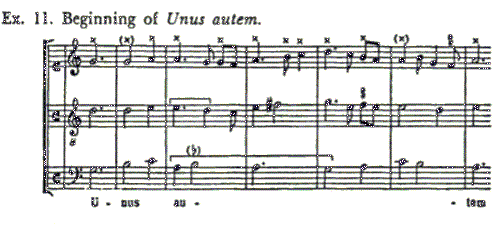  楽譜 引用された例から見ると、チャントを自由にかつ文字通りに採用したかどうかは、いずれの場合でも、コレクションがその様式的統一性に大部分を負うているメロディの流れに移されたかどうか、ということになる。 同様の手順は、あまり芸術的ではないが、Pepys MSに見出すことができる。 lnventor rutili(Nos. 10)の設定に加えて、これは、いくつかのテキスト設定に異なった音楽を含んでいる。LoMにおけるように。 p144 Rex sanclorum (Nos. 11)from LoM (Ex . 12a) と Pepys MS (Ex. 12b )の設定を比較することは、示唆的である。 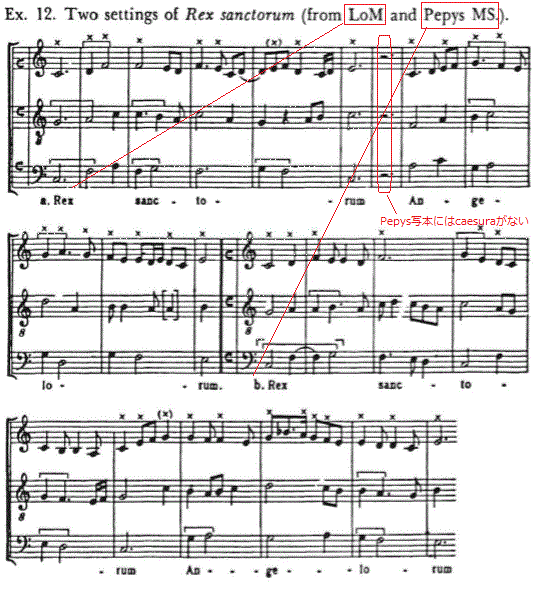 (前者はスコア形式)、後者は離れたパート書法において記譜されており、すべてフルテキストであるが、conductus様式の特徴を示している。それは、LoMのものと平行する同様の設定である。 チャントは同様に扱われるが、Pepys版では、 sanctorumのあとのcaesura(詩行の中間にある、耳で聞き取れる休止)が欠けており、カデンツは、チャントの知られた版に該当していない。 Pepys MSが後のソースであるにもかかわらず、そのバージョンはMeaux Abbey MS(LoM)のそれよりも、様式的に決して高度ではない。これは、Pepys MSのレトロスペクティブで地方的な性質の観点からは、驚くべきことではない。 p145 その後のRex sanctorum (Nos. 11)の6つのverseは、私たちのコレクションの中で最も長い「変奏曲」のセットである。各スタンザにおいて、プレインソングの色は、必須の音符を示すが、同時に反復性と単調性を避けるために十分自由になり、様式の制限内での変化変なを獲得する。 The A lleluia V. Confirtemini やAll . V. Salve virgoは、 cantus firmusを含む唯一の2つの2声作品であるが、3声設定のチャントの取り扱いとは特に異なることはない。パート書法は、おそらくよりスムーズであり、声部の小さな番号に負うているが。 最後に、Cantemus Domino(Nos. 52-53)は、コレクション中の唯一のモテットであるが、あらゆる点で他の典礼作品とは一線を画している(例13)。   テノールは、かなり長めの音価にふさわしいcantus firmusとして、真のモテット的な方法でチャントを提示している。ゆっくりしたペースは、テキストのついた上声部の流麗なデュエットと、テキストのつかないコントラテノールから、構造的な声部を区別している。テキストのつかないコントラテノールは、テノールが休止したときに、時々最低声部として機能する。しかし、大部分は、真のコントラテノールとして、または放浪者(vagans)として、テノールの上下を動く。 作品の2つの主要部分は、拡張されたデュエットでも非常によく似ている。これらのギメルは非常に独特の様式で記譜されている。初めは、同じフォリオに直接並置された2つのtrebleのためにスコア形式で記譜されている。最初の19小節では、trebleパートが2声に分割され、他のパートは休止している。デュエットの次のセクションは、1つのtrebleとアルトに続き、通常の方法で設定される。補足のtrebleパートは削除される。このセクションは、音楽的には最初のセクションと似ている(第13小節と第22小節を比較せよ)。下の2つの声部の入りは、ジメルの終わりを表している。そしてここから、モテットは本質的に4声で進む。テクスチャーは時折、短いデュエットやトリオに間引かれる。モテットの第2部はさらに、継続されているcantus firmus上に、同じ一般的なプランを繰り返す。 2つのパートの間の顕著な対称性が認識されなければならない。 p147 3拍子から2拍子への変更は、もちろん、イソリズムの原則が放棄された後も、長い間、後期モテットが保持していたイソリズムの原則での、標準的な過程であった。 さらに示唆に富むのは、休符が、テノールを、おおよそ対応するセクションに分割する方法である。最初のものは7小節から成る。それからそれらは長さは異なる。その対称性は、テクスチャーの特徴によって、さらに強調されている。第2部の4声部の始まりは、第1部の類似の場所に非常によく対応している。導入ギメルがド音のカデンツに達した後、アルトは両方の時価をリードします。高音部に続くスーツで。 After the introductory gymel has reached the cadence on c the alto leads off both times,with the treble following suit. 作品技法的な面として、モテットは間違いなくコレクションの中で最も先進的で完成した作品である。これは特に4つの声部の制約のない流れで明らかにされている。conductus様式の面白くない4声作品とは異なり、モテットは、一般的なデザインのスキルと計画を示し、4つの声部の管理が容易である。 休符は、パート書法の困難な状況に対する言い訳ではなくなった。そしてそれらの活気のある交替は、文字通りスペースと風通しの良い風合いを呼吸させる声を与える。それは、もはや声部が混雑していない優位性の証である。トータルの音域は、conductus設定よりもはるかに広く、2オクターブを超えている。ゆっくりと動くテノールは、和音進行の不規則な交替を終わらせるゆっくりとした和声リズムを産生する。 フルトライアドが頻繁に発生することに注意する必要がある。そしてそれらの響きある効果は、trebleにおける三度の賢明な配置によって強化される。これらすべての要素は、作品の進歩的な様式を示しているが、全作品の中に単一の近代的なカデンツがひとつもないという事実は一方、比較的早い日付であることも示している。上声部間のかなり多くの平行と不協和音程の摩擦は、4声書法の初期段階を示している。 模倣は、conductus様式には存在しないが、モテットでもごくわずかな役割しか果たしていない。それは上声部にのみ適用され、短いヒントでそれ自身を明示している。主にリズム的模倣である。 過程と様式に関するconductusとモテットの間の対比は、コレクションの第1部の音楽に戻って投射をする。明らかに、conductus設定は、このサービスのために意図的に控えめな機能的な音楽として作曲された。それらの単純さは、音楽テクニックの客観的な限界ではなく、その逆の制限の結果であるように思われる。 p148 モテットは、イギリスの作曲家が何を、順序だって高まった様式をいつできるかを示した。しかし、全体として、Meaux Abbey MSの音楽は、Bodleian MS Addはもちろんのこと、TrentやAosta MSSなどの後のソースへの英国の貢献に特徴的な書法を示していない。Bodleian MS Add. C 87についても、述べていない。それはOHやLoFのレパートリーと後の写本のレパートリーとの間の中間的な立場を保持し、そしてそれ故に偉大な音楽的、歴史的、そして典礼的な宣伝のリンクを形成している。 |