| Walter Frye and the Contenance Angloise7 |
| CHAPTER 9 The Inf1uence of English Musical Style upon the Netherlands Composers p176 A. Dufay and Binchois Dufayの作品は、非常に多様な手段を示している。似たようなシャンソンはほとんどなく、そして彼の初期の作品と後年の作品との間の様式の変化を見るのは簡単であるが、両者の論理的で系統的な発展の線をたどるのはそれほど簡単ではない。
Dufayは、(当時)考えられたほとんどすべての技法を利用した。場合によっては、13世紀のモテットに似た形に戻すことさえあった。 例えば、彼のJe ne puis-Unde venietは、テノールにラテン語の神聖なテキストがあり、discantとコントラテノ―ルにフランス語の世俗詩を持っている。こうしたPolytextualityは、別の彼のシャンソンResvelons nousにも見られる。その中でこのテキストがdiscantに現れている間、テノールとコントラテノールはostinato音型上のカノンを持っている。「Alons ent bien tos avec moy」という言葉で。 Ma belle dame souveraigneのような彼の作品のいくつかでは、間違いなくイタリアの caccia様式の影響を受けている。彼のrondeau、Par droit je puis は、コントラテノールで支えられた2声のカノン声部を伴って、カッツィア様に作られている。 同様に、彼のHe!Compaignons は、2声の伴奏するコントラテノールを伴う2つの対の声部として書かれている。そのうちの1つはオプションとなっている。 Dufay: He compaignons resvelons nous 楽譜(p127) Van den Borrenは、イタリアの形式で直接モデル化されているこれらの作品において、デュファイがテノールのcantus firmusの伝統を放棄した、と主張している。しかし、デュファイの成熟した作品においても、テノールは、重要な役割を再度演じている。 p177 Dufayのこれらの初期のイタリア作品は、彼自身の伝統とは全く異なるスタイルで自由に書くことができるという彼の天才を証明している。 それらが彼のスタイル全体に決定的な影響を及ぼしたと言えるのか、それとも一般的に、フランドル様式に影響を及ぼしたのかは問題である。 モーツァルトのように、デュフェイは折衷的で、フランス以外のスタイルでの彼の実験は非常に多い。 この折衷主義、広い範囲の活動、そしてDufayのシャンソンによって示された技法能力は、孤立した冒険の重要性を、ある特定の様式に限定する危険をはらんでいる。 15世紀の第2四半期は、新しいスタイルを実験し探索する時代であった。 デュフェイの作品はこの実験的な態度を反映したものであり、彼の青春時代のイタリア音楽への傾倒は一時的な関心以上のものであった証拠はない。 Dufayの多様性は、Gilles Binchoisの作品にはそれほど見られない。 Binchoisはかなり多様な表現を達成したが、彼が採用した技法は、一般的により統一されていた。そして彼は、彼の作品を通してずっと、Dufayよりもむしろより一貫したアプローチを示している。 彼の作品に対するイタリアの影響を示すものない。彼の外国人とのつながりはすべて英国人であった。 Binchoisは、20代の間何年もの間、Suffolk 公爵の一行として仕えていたが、この点では間違いなく、イギリスの音楽家と密接な関係を持っていた。 彼が実際にイギリスに行ったかどうかは知られていないが、1430年にブルゴーニュの宮廷に行く前に、彼がそこに短い訪問をしたといういくつかの証拠があり、彼は1460年の彼の死までそこに残った。 様式的に、Binchoisの作品は彼の英国の同時代人のものに強い類似点を示している。 彼のモテットへの相反する帰属は、すべて英国作曲家(Sandley、Dunstable、およびPower)に対してであり、メロンシャンソニエにおいてFryeに帰されているrondeau Tout a par moyが、別のソースではBinchoisに帰されていることは、重要である。 p�178 彼が7つものバラードを作曲したことも、イギリスの影響力の表れかもしれない。 これらのうちの1つ、Dcuil angoisseuxは、トレント90で保存された英語ミサ曲のためのcantus firmusを提供した。(BedinghamとLangensteissに帰せられている)。 Binchoisのシャンソンは、Fryeのバラードと全く同じ構造を持ち、9小節の終わり 、第1,2部の間には押韻を伴っている。 "clos"は、"ouvert。"の終わりを含んでいる。 そして、Fryeのバラードのように、BinchoisのDeuil angoissellxもモテットになった。(Rerum conditor,inTrent 88 No.345。) バンショワの作品をDunstableやFryeのそれらとキャロルレパートリーに関連づける彼の様式の観点については、少なくとも5つある。 ①メロディ様式 ②一般音域 ③テノールとdiscantの口調のよい関係 ④テノールラインの特徴 ⑤コントラテノール声部の特徴 少なくとも6つのDunstableのモテットに現れる1つのメロディ形象は、英語の特徴があり、多くのキャロルの中に見られる。それはまた、バンショワのシャンソンでも、明らかである。最初の1音を除いて、BinchoisのDe plus en plusの第2フレーズ、Fryeの Tout a par moy、DunstableのSancta Maria non estおよびcarol llluxit leticiaの2番目のフレーズは同一である。 (例24参照)  この同じフレーズの変形は、バンショワの Se j' eusse un seul peu d'esperance、 Dunstableの Sancla Maria succurre ,carol St. Thomas honor we でも見られる(例25)。 ) 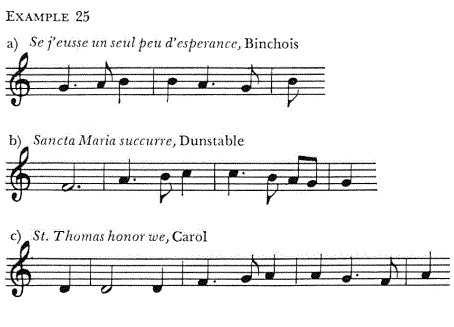 BinchoisのAdieu adieu、mon joyeuxの同様のメロディラインとAshmole Ms. 191のO kendly creature のうちの1曲の冒頭と、そしてキャロルのPrinceps serenissimeとを比較するのは有益である。(例26) キャロルとAshomoleの最初の2つの小節は、正確に同じであり、Ashomoleの歌の第2,3番目の小節は、バンショワのシャンソンの第3,4小節と同一である。 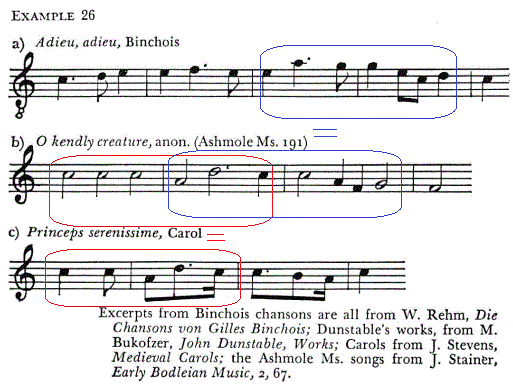 �p180 Adieu adieu、mon joyeuxとO kendly creature の最後の小節はモットーのようなもので、これは最初の出現では非常に遍在していて、特に重要ではないようである。 Jeppesenはそれをシャンソン文学の典型であると述べている。 彼はBinchoisによる2例、Dunstable(Puisqu'amour)による1例、そしてCaronによる1例を挙げている。そして彼は、Bedinghamの(?)Grant tempsからのものに言及している。 フレーズはブルゴーニュ楽派のシャンソンでは非常に一般的なものであるが、その最も初期の例は、英語の作曲家による作品、またはそれらに関連する作品に見られること、そしてそれはキャロルによる慣用句であること注意することが重要である。 Binchoisによる他の例は、De plus en plusとVostre alee me desplaistにある。以下の図は、FryeのAve Reginaのテノール部分の冒頭等であるが、Myn hertis lust(Grant temps)のdiscantパートではかなり目立ち、So ys emprentid では、マイナーな形で現れている(例27)。 こうした独自のモティーフは、第7章で指摘されているように、英国音楽によく関連している三和音形式の1つであり、discantの実践に関連している。頻繁に現れる。 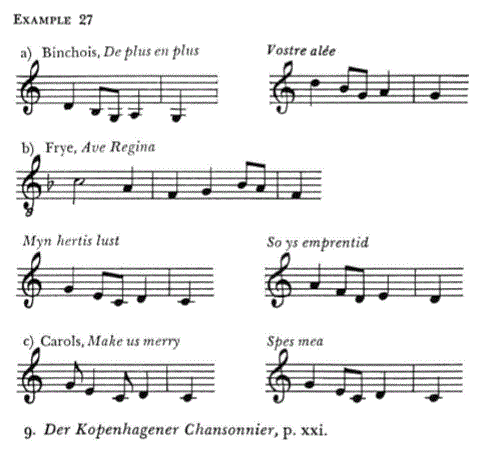 p�181 バンショワのシャンソンでの三和音のたびたびの出現は、ここで引用した特殊な形とは別に、discant様式の一般的な影響を示している。たとえば、Deuil angoisseuxの冒頭は、ヘ長調の三和音からなっている。 Binchoisの作品は、他の多くのメロディ的な特徴を含み、それらには、彼の英国の同時代人の作品と同一のものがあることがわかる。 彼のMon seul et souverain desirは、FryeのAve Reginaのdiscantの最初のフレーズと全く同じような形象から始まる(例28)。 これは、フライとダンスタブルの両者に特徴的なフレーズであり、キャロルにも広く現れている。  最後の例は、バンショワのPlains de plours et gemissemensの最後の部分で、初期の2声のキャロル Alma redemptoris materと比較されて、バンショワのメロディ様式とキャロルのそれとの類似性が示されている。(例29)  �p182 バンショワのシャンソンはまた、声部の音域に関して、キャロルと関係している。キャロルの多くは、すべて男声での演奏を示唆する音域で書かれている。そのために、バンショワのシャンソンの中で、Ay douloureux、disant helas、Adieu ma doulce、Amours et qu'as tu enpenseなどのような3つのバス音部記号で現代の記譜法に最もよく変換される例を見つけることは、かなり一般的である。 英国の影響の証拠を示すBinchoisの様式のもう1つの側面は、discantに対するテノールの関係、特にこれら2つの声部の間の不完全音程のほぼ一定の使用である。 それらの間にいくつかのオクターブがあるが、五度は比較的まれである。 キャロルのParit virgoと比較した場合、バンショワのMon seol et souverain desirまたはAdieu、adieu のテノールおよびdiscantは、キャロルの技法とバンショワのそれがどれほどこの点で似ているかを示している。 これらを、DufayのBon jour、bon mois、と比較するのは興味深いことである。両者の声部間では三度や六度の関係はほとんどない。 Je ne vis oncques やMalheureux cueurなどのDufayの後期のシャンソンにおいては、多くの汎協和音の扱いがあるが、バンショワのシャンソンの中では、discantとテノールでの非常に協和音的関係は出現していない。 Binchoisのシャンソンは、一般的に、「バラード」スタイルまたは「treble優勢」スタイルとして記述されている。discantは最も効果的な声部であり、テノールはほとんど同等ではない。 Binchoisの作品、およびキャロルの慣用的な形象の多くは、テノールラインのやや静的な性格に関連している。メロディでトライアド形式を頻繁に使用することは、同じテノールの音符にわたって、完全と不完全音程を交互に生成する工夫としてすでに言及されている。 もう1つの形象は、FryeとBinchoisの作品のほとんどの作品でのほとんど決まり文句であるが、不完全音程のみを交互にする、より高度なスタイルに採用されている同様の手法を示している。これは、discantの四度の上昇音程である。 四度のこの旋律的な跳躍の無数の例がある。そしてほとんどすべての場合、テノールは静止している(例30)。 p183 テノールは、ディスカントの最初の音符の三度下にあり、続いて、2番目のdiscantの音符の六度下になる。このように、三度と六度の交替は、すべて、テノールの音符を変える必要なしに達成される。 Tinctorisはこの技法を、彼のLiber de arte contrapunctiのBook IIIで提案しており、そこでは彼は8つの一般的な規則を定めている。第三章は、「テノールを同じ音程にしたままで、不完全であるだけでなく完全でもある多くの一致を、次々に連続して従うことを可能にする三度の一般規則について」と題されている。 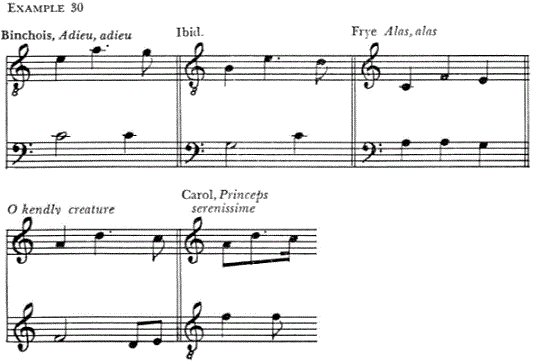 英国の音楽の、豊かで協和音的な音を模倣しようとした大陸の試みは、主にfauxbourdonにおいて見られると、しばしば言われてきた。 しかし、フォーブルドンの使用は、作曲家とレパートリーの両方に関して非常に限られていた。 一方、このタイプのメロディ的な工夫は、厳密なfauxbourdonではなく、treble領域が支配的な様式である大陸の伝統に、簡単に与したものであった。 声部が分離され、上声部がはっきりとリズム的に活発であるかなりの数のBinchoisのシャンソンがある。 メロディの四度の上昇は、これらすべての作品で際立っている。 p184 バンショワの音楽とキャロルのむしろ著名な特徴の1つは、テノール(あるいはキャロルの最下声部)が、しばしば、繰り返しのリズムスキームを伴い、オルガヌムの規則的なordinesの名残のやり方で書かれていることである。 これは特に、低い声部が、それが多かれ少なかれ密着している第2または第3モードのリズムパターンのように見えるものを持っているキャロルで見ることができる。 (例えば、Verbum patrisの低声部、またはAlmyghty Jhesuのburdenと合唱を参照)。 基本的にモーダルリズムでキャストされたメロディックラインもまた、L 'homme arme melodyによって示され、その原型は、キャロルPrinceps serenissimeに見られる。 イギリスでのdiscantが、このより古い実践との関係を保っていることは全く論理的である。これらのリズムパターンは、実際には、最も初期のディスカントスタイルの遺産であり、そこではディスカントセクションにおける両方の声部がモーダルリズムの原理に従って編成されていた。 Kenneth Levyは、英語の計量記譜法がフランスとは独立して発展し、ますます古いモーダルシステムに密着していったことを指摘した。それでも、この特徴は、15世紀には登場し、イギリスからのdiscant様式の影響を受けていた大陸の作曲家によっても引き継がれていったことは、特徴的である。 この技法はバンショワの作品、特にSe la belle n'a le voloir、Vostre tres doulx regárd、Amours et souvenir de celle、Bien puis、Esclave puist yl、Helas que poray jeのようなシャンソンで顕著に見られる。 バンショワがイギリスの作曲家の弟子であったことを示しているそのスタイルのさらにもう一つの特徴は、彼のコントラテノール声部の活発な性質である。これは、例えば、彼のKyrie Ferialeで見ることができる。 英国風の 同様にBinchoisの作品で、進歩した様式を示すのは、Adieu、adieu(m。6)、De plus en plus(m。8)、Margarite、fleur de valeur(mm 4と8)、Plains de plours(m 17)、その他のように動きをカデンツの後に動き続けるためのコントラテノールの使用である。こうした工夫は、コントラテノールが他のパートによって模倣される形を開始する、Vostre allee me desplaitにおいて、著名である。 Frye のcontratenorのように、Binchoisのそれは、通常、tenorやdiscantよりもメロディック的な特徴が少ない。 Adieu、adieu(m。15)においては、コントラテノールは、三度と五度でオクターブを超える連続で下降し、その後四度と五度の跳躍を続ける。 Adieu jusque je vous revoyeにおいては、この声部は、Frye のcontratenorとほぼ同じような角ばった様式で、はっきりと和声的な声部として、そして時には、三度や四度の下降跳躍のような、純粋に装飾的な形で、リズム的流れを続ける機能を果たす。(例31)。  ハーモニックなコントラテノールを使ったデュエットスタイルは、第7章で詳細に議論されている。それがBinchoisの作品に登場しているということは、英国音楽との密接な関係の1つの兆候である。 Binchoisのシャンソンのtreble優位の側面は、それが表面的には初期の大陸のシャンソンに似ているため、少し誤解を招く。これらの作品で簡単に見過ごされているのは、テノールとディスカントの間の協和音程関係、およびコントラテノールの役割である。 Binchoisのシャンソンの多くの discant -tenor デュエットは、Fryeのそれ、またはキャロルの2声のburdenのように、孤立している。 彼のAdieu、meslesres belles amoursは、2声でバンショワの最大の写本に保存されている。 ハーモニックなコントラテノールは、全く不要である。 p186 Binchoisのシャンソンのdiscant -tenor関係は、付随したソロソングのフレームワーク内の英語のdiscantスタイルの要素の最初の浸透を表している。 バンショワは、デュファイと共に、理論家や詩人によって、新しい様式の創造における重要な人物の一人として常に言及されてきた。しかし彼は、現代の歴史家からは、魅力的なシャンソンを書いた才能に栄誉を与えられることはめったにない。 Binchoisと英国との関係、そして英国の影響が彼の様式に与えた影響はあまり強調されていないが、Dufayのfauxbourdonによる実験にはあまりにも強調され過ぎている。 この不均衡は、英国のdiscantの実践と fauxbourdonとが混同されることによって引き起こされる。 デュファイのfauxbourdonは英国人によって鼓舞され、そして入れ替わって、英国がブルゴーニュのシャンソンの影響を受けていると主張する歴史家たちは、まったく余分な一連の両国の交流を仮定している。 たとえFauxbourdonがもっぱら大陸的現象として認識されていても、英国の音楽が英国の理論に照らして理解されない限り、問題は不必要に混同されてしまう。 BukofzerもBesselerも、厳格なfauxbourdonの中で、Dufayが英国の三度や六度のの完全な音響を追求していた、そして彼が後にはもっと柔軟なスタイルで、同じ原理を利用することができたと信じていた。 22 22 Bukofzer , Studies , p131 しかし、Bukofzerは、英国の音楽に影響を与えるようになったのは、Dufayのこの柔軟な様式であることをさらに示唆した。彼は、例えば、Egerton Ms. 3307の作品を、最初の「fauxbourdon様式の影響を反映するもの、しかしそれは、特徴的に定型化されたパート書法に変換された」と記述している。23 23 Bukofzer , Studies , p130-1 それでも、デュファイがこれらの自由な設定においてたどり着いた様式は、英国においても大陸でも、英国の作曲家によって知られ、実践された。それは、英国の理論家によって教えられた。DunstableのQuam pulchra esは大陸でよく知られていたその様式の例である。それはまた、かつてBedford公爵と共にフランスにいて、早くも1431年に亡くなったJohn Pyamourによる同じテキスト設定であった。24
24 Bukofzer , Studies , p130p187 ダンスタブルの作品の中でも、Sancta Maria non est やAlbanus roseoのような、よりメリスマ的なスタイルのものでさえ、discantは、tenorと常に良い関係を保っている。 これはDunstableやPyamourの作品だけでなく、若いイギリス人作曲家の作品でもあるFrye、Bedingham、Morton、Cockx、そして大陸の同僚、Binchoisをも特徴づける汎協和音的様式である。 おそらく、大陸の作曲家は、自由な協和音程様式に到達する前に、fallxbourdonを試してみることが必要であった。しかし、イギリスの作曲家たちは、14世紀に、以前とは異なる方法で実験をしてきた。そして、三度と六度書法の特定のフレーズを通り抜けることはなかった。彼らは、discantingの伝統から、不完全協和音程扱う技法を直接受け継いでいた。したがって、Egerton写本のいわゆる「定型化されたパート書法」は、英国の理論と実践の枠組みの中で、大陸の発展とはまったく別のものとして理解し得る。 その後、Fauxbourdonは、大陸の作曲家たちの一部における、リズム的に等しい声部のスタイルで三度と六度を扱うという特定の能力に到着しようとした試みとして、理解されたかもしれない。それはDufayにとって重要な一歩であった。しかし、硬直した形のfauxbourdonが、Binchoisの作品の中ではより小さな役割しか果たさなかったことは重要であった。彼の英国の作曲家との接触は、Dufayのそれより直接的で持続的であった。英国音楽の協和音程的で対位法的な様式は、デュファイよりもむしろ、Binchoisの初期の作品でより完全に同化された。フランドル様式の定式化におけるイギリスの要素の重要性は、むしろバンショワによって、理解され、評価された。 B. Busnois、 Obrecht、and Josquin 15世紀の終わり頃のフランドルの作曲家たちのうちでは、そのdiscant様式の影響が最も明らかであるのは、ジョスカン、Isaac、Agricola、そして特にBusnoisとObrechtである。 彼らは、Busnoisを除いて、イタリアへ旅行し、そしてその様式はこれまでイタリアのfrottolaに言及して説明されてきた作曲家である。 今では、イタリア人に影響した様式の要素の多くは、フライの世代の英国人作曲家たちの作品を通して説明できることがわかっている。 Obrechtがイタリアに初めて行ったのが1474年であった事実は、常に、問題となった。 p188 しかし、Fryeの音楽と彼との接触は疑いもなくより早く、そしてそれ故、オブレヒトの様式の基礎のためのより論理的な説明を提供している。 これらのフランドルの作曲家のうち3人が、Fryeの作品からの借用をしたという事実には、ある種の重要性が付けられよう。 ObrechtはFryeのAve Reginaを、モテットとミサ曲のモデルとした。 アグリコラは、ロンドーTout a par moy を、フライのテノールを使って作曲した。そしてJosquinは,Tout a par moyに基づいてミサを書いた。 ObrechtはFryeのテノールを彼のモテットのために、cantus firmus としてフライのテノールを借用したが、そのまま三度下げて移調して、ドリアン旋法とした。 彼は借用したテノールだけでなく、新しく作曲した声部でも同様に、FryeのAve Reginaのバラード形式を用いた。 したがって、Obrechtのモテットもまた、a b c bの形式的デザインをしている。 Ave Reginaに基づいたオブレヒトのミサ曲においては、テノールはそのままで、元の旋法に戻っている。cantus firmus素材の配置は、Kyrieにおいて特に興味深い。なぜならオブレヒトは、「Kyrie 1」のために、フライのテノールの最初のフレーズのみを使用し、それを繰り返しているからである。“Christe"では、フライのテノールの次のフレーズを取り上げ、そのprima pars の終わりまで、フライのテノールを続ける。「Kyrie II」は、Fryeのテノールの全 secunda pars を使っている。したがって、Fryeのテノールの2つの同一セクション、prima とsecunda pαrtes の終わりは、Obrechtのミサの「Christe」と「Kyrie II」の終わりに存在している。 最初のフレーズの繰り返しを伴う、こうしたcantus firmus素材の扱いは、GLORIAおよびCREDOにも保持されている。cantus firmusは、テノールにおいて最初の4つの楽章(Kyrie,Gloria ,Credo,Sanctus)に存在するが、AGNUS DEIにおいては、バスで出現する。3つの真ん中の楽章(Gloria ,Credo,Sanctus)では、cantus firmus素材は、他の声部でも見られる。例えば、GLORIAとCREDOの導入デュオは、テノールのテーマに基づいた計量カノンである。そしてSANCTUSでは、コントラテノールはテノールとのカノンのテーマを持っている。メロディは装飾されていないが、リズム的な長短での変化がある。オブレヒトは比例的な変更を加えなかったが、フライもミサ曲のためにそのままのcantus firmusを好んだ。 p189 フライの作品から借用した素材のジョスカンでの使用は、彼のMissa Faysant regretzで見られる。このタイトルは、ロンド―Tout a par moyに由来する。 Josquinは明らかに、このテキストのAgricolaの設定とFryeの設定を知っていた。 Agricolaは、Fryeのテノールのみを同じテキストの設定に使用していたが、彼はそれに対して、、コントラテノ―ルのオスティナート音型を付けた。 Josquinは同じ断片に基づいてostinatoを書いたが、それをtenorに入れた。 さらに、彼はそれをあらゆる規模の音階に移調したが、Agricolaのostinatoは1ピッチに限られていた。 ジョスカンは、自作をTout a par moyではなくMissa Faysant regretzと名付けて、アグリコラの設定に言及したが、フライのロンドーTout a par moyの全体のdiscantは、ジョスカンの “Agnus III." のsuperiusに引用されている。このメロディは、フライのdiscantを使用しなかったアグリコラからの由来ではない。 ジョスカンは、アグリコラを通すのではなく、フライの作品を自分自身で知っていたに違いない。 このような素材を借りること自体が、作曲家から別の作曲家への真の様式的な影響を意味するわけではない。 しかし、Josquinのスタイル、そして確かにObrechtのスタイルには多くの特徴がある。これらはFryeのスタイルに直接関係している。 ObrechtがFryeと直接の交流があったかどうかは疑わしいが、これら2人の作曲家間の明確な関連はAntoine Busnoisによって提供されている。 ObrechtとBusnoisの間には密接な様式的な関係があることはよく知られている。 さらに、Obrechtは、彼のL 'homme arme Massのために、Busnoisのテノールの定式化に従った。それらは両方ともブルージュの教会と関連していて、お互いに個人的によく知られていたかもしれない。 FryeとBusnois間の密接な関係も想定される。 Flyeが、Busnoisのように、Charles礼拝堂、Count of Charolaisで奉仕したという文書の証拠はないが、彼の音楽は確かにそこで知られていた。ブルゴーニュの作曲家による作品を中心としたメロン写本には、ビュノワのシャンソンの多くが、フライのそれとと一緒に保存されている。 Fryeのミサ曲3曲すべてを含むブリュッセル写本5557は、また、Magnificatを含め、2つを除くすべてのBusnoisのモテットを含んでいる。 我々は、フライの作品が、ブリュッセル写本5557の中核を形成し、そしてビュノワの作品に先行していたことを見てきた。tephanとSparksは、音楽構造を明確にするために細心の注意を払い、Busnoisのモテットは、作曲家自身によって写譜されたことを示唆している。 p190 Busnoisが実際にこの写本に自分の作品を写譜したのであれば、彼は写本の前半部分のミサ曲のことをよく知っていたはずである。なぜなら、すでに見たように、彼のモテットはすべて、gatheringの間を「満たす」位置を占めているからである。 彼のAnthoni usque liminaは、FryeのMissa Nobilis et pulchraが含まれているgatheringの最後の裏表紙から始まっている。 StephanとSparksによって進められた理論が受け入れられるかどうかにかかわらず、Fryeの作品がBusnoisが知られていた界隈に知られていたことはほとんど疑いなく、そしてFryeのスタイルの影響は、Busnoisの世俗的かつ神聖な作品の両方で明らかである。 Busnoisは彼のシャンソンで最もよく知られている。 実際、彼とともに、ブルゴーニュのシャンソンが、自由で和声的なコントラテノールと相まって、discantとtenorの模倣デュエットの形でその古典的なタイプを達成したことが仮定されている。 このスタイルは、すでに見たように、1450年代のFryeのシャンソンにもあった。 模倣だけが、前の2曲からは、欠けている。 しかし、それらのすべてはdiscant-tenor作品であり、それらは1455年には早くも書かれていたので、それらはdiscno-tenor chansonについてのBusnoisの定式化に先行していたにちがいない。 さらに、これらのイギリスのモデルから、またはおそらくBinchoisを通して間接的に、Busnoisは、不朽の名声を得たこれらの作品の形式を導き出した。 ブリュッセル写本5557には、フライとビュノワの宗教作品の間における強い様式的な類似性が存在する。 Busnoisのモテットには、古いtreble優位な様式の証拠はない。 すべての声部は基本的にnote-against-note の関係で、ほぼ同じリズム音価で動いている。 Edgar Sparksは、これらの作品の研究において、次のように書いている。 モテットは、全体的には時代の特徴とは言えないような多くの特性を示している。 例えば、Noel、NoelとVerbum caro factum estという2つの作品は、概念上は際立って和声的である。 直線的で水平的な観点は、通常よりもはるかに大きく、垂直的観点(訳注;和声的観点)に従属している。・・・ 完全な三和音の優位性がある。そして、和音から和音への動きは一般的にはっきりと定義される・・・Busnoisの和声は、彼より前の作家よりも優れたサウンドを持っている。 p191 Sparksが特徴的ではないと考えるこれらの側面は、Fryeのミサ曲に見られるように、discantの実践に密接に関係している。 確かに、完全な三和音における和声構造と三度、六度の優位性は、英国の影響を強く示唆している。 メロディ様式もまた、フライのスタイルに関連する特徴を明らかにしている。Sparksはある特殊性に注意を向け、ビュノワがしばしば、メロディの繰り返しパターン、時にはメロディとリズムの繰り返しパターン、時には単なるリズム(の繰り返し)、そして音部の組み合わせのために、自由に流れるメロディラインを捨てていることを指摘している。彼のRegina celi laetare 1の例は、この種の繰り返しを示している(例32)。 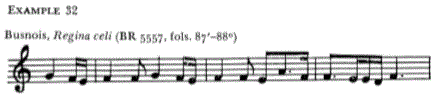 2声部からなる2番目の例(例33)は、模倣の連続を説明するために、例9(第6章p132)で引用したFryeのMissa Flos regalisからの抜粋に、明らかに関連している。  p192 Busnoisにはまた、Fryeと同じように、常に1つの高い音を強調しながら、狭い枠内で、曲がったり戻ったりするメロディラインを書く傾向がある(例8を参照p131)。 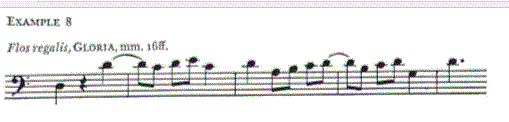 ビュノワのAnthoni usque liminaからの抜粋(例34)は、B♭に上昇するとまた下へ戻っていく、FryeのAlas alasからの箇所との非常に正確な関係を示している。  Fryeの作品の典型的な1オクターブの跳躍は、オフビートで、まったく同じ方法で使用されているBusnoisモテットにも現れている(例35)。  FlyeのMissa Summe Trinitatiですでに見られたostinato音型はまた、Bunoisによって高く評価されていた。 彼のモテットln hydraulis は、その顕著な例を含んでいる。 いくつかの点では、Busnoisのostinatoテクニックは、FryeのものよりObrechtのものにより密接に関連している。 4回のostinato音型の一例(例36)では、Busnoisは毎回いくつかの音符を追加する。 これはObrechtが彼のMissa Fortuna desperataのBenedictus で使った技法で、音型は降順で7回繰り返され、毎回少しずつ長くなる。  p193 ビュノワのcantus firmus の取り扱いは、一方でフライと、そしてもう一方でオブレクトと関連している。 それはモテットSostilali deditでは自由に扱われるが、Frye のcanlus firmusは、ミサ曲においては、完全に手つかずである。 同様に、メロディは、Regina celi IIのようなBusnoisのモテットのいくつかで色付けされている。 しかし、彼のミサ曲 L' homme arme やO crux lignumの中では、そのままで、未装飾のままとなっている。 Obrechtのように、Busnoisは、proportional diminution と augmentationを伴う繰り返しにcantus firmus をさらすことでFryeを超えた。Sparksが指摘するように、この技法は、 Dufay , Regis , and Caronにおいてはそれほど特徴的ではなかった。 SparksのBusnoisモテットに関する記事の中心的テーマは、Ockeghemの作品には先例がないが、より若い世代、特にObrechtの業績を明確に指摘しているこうした作品の多くの特徴である。 Ockeghemの作品に見られない先例は、一般的にイギリスの作曲家によって、そして特にWalter Fryeの作品によって提供されている。 BusnoisはFryeの多くの様式的工夫をかなり優雅にそしてもっと多様に扱った。 しかし、Fryeの作品は、驚くほど早い時期に、最初にBusnoisによって、次にObrechtとJosquinによって芸術的によく利用された要素の多くを明らかにしている。 p194 Obrechtの様式はあまりにもよく知られているため、多くの議論が必要である。しかし、Fryeに関連しては、ある種の特徴が指摘される可能性がある。 cantus firmus 技法に関しては、Obrechtはより古い英国作曲家に近い。 ObrechtもFryeも、cantus firmus をいじることなく、その素材を配置する独創的で非常に合理的な方法を示した。例えば、あるミサ曲のグループでは、オブレヒトは、各楽章がその一部しか持たないようなcantus firmus を割り当てた。例えば、Missa Maria zart では、それぞれの楽章に異なる断片が現れている。しかしながら、5つの楽章のそれぞれの中で、Obrechtは割り当てられた断片を数回繰り返しながらも、常に新しい断片で終止した。そして、それは順に、次の楽章の基礎となった。 Missa Je ne demandeでは、 "Benedictus"とACNUS DEIに割り当てられた断片に加えて、テノール全体が繰り返されている。 cantus firmusの分割の実践や、 このような工夫によるミサの統一を求めることは、SANCTUSもACNUS DEIも、Missa Summe TrinitatiにおけるFryeのcanlus firmusの取り扱いとの関係を示している。そこでは全体のメロディにおいて、それらは完全なcantus firmus を持っているわけではない。 Obrechtはより系統的であるが、Fryeのミサ曲は、生のcantus firmus素材の高度に計画的な配置を示している。 Bukofzerは、Obrechtの様式について、オクターブの飛躍の使用法、没頭された連続的使用、四度と五度の枠内でのスピニングについて言及し、包括的に説明している32。フライやオブレヒトの作品のパッセージでの比較は、オブレヒトがいかに英国の作曲家に負うていたかを示している。 32 Bukofzer , Studies , p292-96 Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC9 Fryeの世俗的な作品のほとんどすべてとBusnoisのモテットにおける同じリズム的な文脈で現れたオクターブ跳躍はまた、特にObrechtによって、彼の世俗的な歌で、広く使われた。 (たとえば、Odhecaton No. 67、mm 42-43、48-49、および77-78における彼のTandernaakenを参照。) ObrechtとFryeの両方によく見られるのは、単一の声部が、数小節にかけて上下する非常に狭いフレームワークである(例37)。  第6章の例13と例14に示されている純粋なリズムの連続(p133)は、Obrechtの作品でも常に使用されている(例38)。  ostinatoはObrechtのミサ曲やモテットのいたるところに現れ、場合によってはかなりの長さになる。 Missa Malheur me batではそれは、SANCTUSのEとF、そしてAGNUS DEIのEとAで構成されているような、2つの音符からなっている。これは、BusnoisのIn hydraulisのostinatoテクニックと非常によく似ている。 ostinatoは、フライのミサ曲においても、はっきりとした先例がある。 驚くべきことに、Fryeのテノールをcantus firmusとして使っているMissa Ave Reginaでは、Obrechtは、12回の、Missa Summe Trinitati(例16参照p134)においてフライのオスティナートとほぼ同一であるostinato音型(「Et resurx」のバスで)を書いている。 あらゆるタイプの連続性への好みは、フライやオブレヒトの作品の、いたるところに現れる。しかし、連続性やオスティナートとしてのそうした形式の非常に重要な特徴は、それらが文字通りそのままなのではなく、変化する、ということである。 p196 フランドルの作曲家が、メロディラインを刺繍することによって望ましいバリエーションを達成したことはめったになかった。 例えば、ObrechtのMissa Salve diva parensの最初のOsannaでは、低音の音型は単に反転され、同じ区間を部分的に逆行させることによって変化している(例39)。  フライのスタイルでも、文字通りの連続やostinatoは比較的まれである。 メロディまたはリズムのいずれかが変化しているか、そうでなければ、Tinctorisが言うように、nunc cum syncopls、nunc sme syncoplsとなる。 連続性は、その性質上、よりわかりやすくするために、そしてよりはっきりと定義するために、フレーズの構造を明確にする傾向がある。しかし、フランドルの作曲家たちは、その多様な使い方によって、2拍子の中に3拍子を挿入することによって、あるいは他の関連する技術によって、単純に模倣における異なった声部間の連続する音型をずらすことによって、フレーズ構造を曖昧にすることに成功した。 p197 それは、15世紀の初期の音楽にとても特徴的だった対称性と規則性の排除のための努力に対する新しいフランドル楽派の全体的な美学と完全に一致している。あらゆる種類のフレーズの分割を曖昧にするこの傾向は、Fryeの Missa Nobilis et pulchraにおけるKyrieの構造における彼の意図的な曖昧さにあいて類似性を見いだす。 彼はその時、形式と様式に関して、フランドル楽派の本当の先駆者であった。 確かにジョスカンの作品において、このような工夫は、最も高い芸術的な目的を果たすようになっている。 例8(第6章p131)に見られるような、メロディフレーズの中で何度も何度も繰り返されて生じている高い音符の強調は、Josquinによってさらに使われている(例40)。 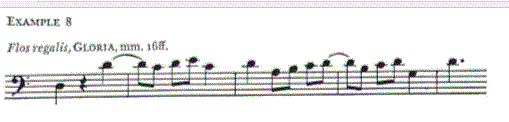 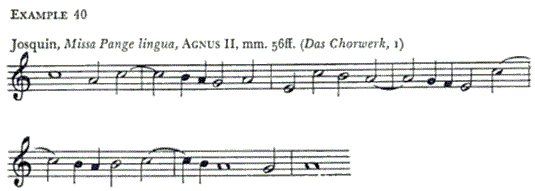 Josquinのメロディ書法で特に際立っているのは、単調になる可能性があるメロディの中でさえも、並外れた多様性が達成されることである。 一例(例41)は、Fryeの作品の多くのものと同様に、比較的小さな一群の音符を中心に展開している。 テノールとバスが全く異なる素材で連続して入るときに、同じ音型が、altusにおいて、模倣で入ってきている。  Josquin,De profundis, mm71 Josquin,De profundis, mm71例42のように、旋律的には正確だがリズム的にずれた配列でさえ、Fryeの作品の中で先例を見出す(例10)。   p198 ジョスカンにおいては、bicinium(二重唱)の技法は、全体構造の基本として見られる。4,5声作品は、(そのTuttiが)さまざまな声部の組み合わせにおけるデュオの連続で途切れる。これはFryeの唯一の4声のミサ曲Flos regalisで、彼が採用した方法であった。 このJosquinスタイルの発展は、フランドル様式がdiscantの実践にどれほど密接に関連しているかを示すのに役立つ。 その基本的関心は、テノール上でdiscant化している声部の書法とともにある。 15世紀後半の世俗的文献では、discant化の技法が、discant-tenor構造の進化を担ってきたことが示されている。ミサ曲とモテットの作曲では、最終的に、基本構造要素としての、デュエット形式の利用につながった。 それで、3、4声、さらには5、6声の作品では、デュエット形式の出現は、15世紀のイギリスの作曲家たちの作品に明白に示されている。 これまでの章では、フランドル様式の形成に対するイギリスの作曲家の貢献が、テノールとほぼ連続した協和音程関係を維持したメロディ・ラインの創作であることを示した。 このタイプのメロディーは、イギリスでは論じられていない理論と、イングランドにおけるdiscantの実践から非常に自然に進化したと見られてきた。 イギリスとフランドルの作曲家の手に渡って、それは一般的に、旋律の装飾的な音符、あるいは非和声的な音調を基本的に欠いていた様式をもたらした。 しかし、フランドルの作曲家の間では、メロディ書法が、対位法芸術をほとんど排除するまで発展していた2世紀の間の伝統があった。 したがって彼らは、 ndiscantのnote-against-note スタイルに、英国の15世紀の音楽以外では欠けていた抒情的な質を吹き込むことができた。 p199 オブレヒトの作品の最も素晴らしいパッセージの1つは、4声の Salve Regina (Example 43)の終止セクションである。 楽譜  こうしたパッセージは、discantの理論だけでは、説明できない。メロディラインの美しさ、優雅な性質、そしてそのようなメロディの純粋に叙情的な滲み出しは、厳密に対位法的なスタイルの理論的範囲内では考えられない。それは15世紀初頭の大陸の伝統、メロディが優勢であったバラードスタイルのそれともっと密接に関連しているように思われる。 しかしDufayの初期のメロディーとは異なり、Obrechtの場合は、六度、三度、または完全音程といった、その他の声部との協和音程である音調において作曲されている。そして、この新しいタイプのメロディラインは、間違いなく、15世紀初頭から半ばに、イギリスの作曲家たちによって大陸にもたらされた芸術的信条の結果である。 Dufay Salve regina 楽譜 このオブレヒトのパッセージはおそらく、フランドル風の最も典型的なものではない。それにもかかわらず、それは最初から存在していて、特にPalestrinaの作品においては、16世紀を通して続いたその様式の一面である。たとえメリスマ的であっても、それは紛れもなく新しい音楽時代の協和音程の慣用句に属しているので、それは15世紀初頭の様式と同一ではない。それは、何よりも、英国から来た協和音程の理想との結びつきを通して、フランドルの作曲家によって達成された芸術的な高さの説明である。 |