| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC9 |
|
OBRECHT p292 Obrecht Missa Caput: Kyrie 様式に関して、オブレヒトは、デュファイとオケゲムの肩に乗っかっている、と言えよう。多くの乱用したフレーズを使うことにおいて。 彼はたしかに、両者の特徴を結び付けているが、全体的に個性的になるような流行の新しさもある。彼が(デュファイ)からとりわけ受け継いだものは、カデンツの強調である。彼はそれを、ハーモニーやメロディ、公式な表現としての真っ先の意味合いのひとつとして、発展させた。彼がオケゲムから借用したものは、自由に展開するポリフォニーである。彼はまったく異なったやり方で、声部の横の相互作用を作り上げたが。 (デュファイ)やオケゲムから彼が最終的に離れたものは、連続ならびにそれがすべて意味するものへの没頭である。彼の音楽においては、実際の構造的機能は、彼のメロディの想像やリズムパターンに広まり、それゆえ、彼の地位は、彼の偉大な同時代人かつライバルであった。ジョスカンデプレと並ぶこととなった。 p293 オブレヒトのミサ曲は、Gombosiによって、詳細に分析されているが、ここでは、その本質の概要を述べ、彼の様式についての観点に注意を向けることで十分であろう。 オケゲムからオブレヒトへと目を向けると、最初の印象は、無限の潤沢さと尽きない活力であろう。オケゲムの不合理かつ具体性のない動きや憂いを帯びた音への偏愛と対称的に、オブレヒトの曲はがっしりとしていて粗野である。そして、フランドル楽派のカンバスを特徴づけるのと同じ男性的な空気を吸っている。 大陸のハイピッチなメロディのヴァイタリティは、メロディの連続に本質的に頼るしくみとなり、同一あるいは若干異なった楽想の直接の反復にさえなる。オブレヒトは、profiled themesの明らかな巨匠であり、そのリズムや音程において等しく覚えやすい。四度あるいは五度のフレームの枠組み内で動き、conjunct motionによって満たされ、テーマは、模倣において接置された非対称的な連続の手段によって、いつ果てることもなく連続的に拡大されている。 音楽的テキスチャーにおける連続の完全な相互貫入と模倣がここで再度出現し、、2つの工夫が異なった繰り返しの同じ原理の異なった観点のみとなる。モティーフは長いフレーズを遂行するの十分な特質を持つ。それらは、15世紀後半では一般的となり、ジョスカンの音楽において現れるような若干の基本的音型に煮詰められる。彼の作品のスピンアウトの過程において、オブレヒトは、特に機知に富んだやり方において、オクターブのスキップを活用する。そして、驚くべき変化を成し遂げる。 p�294 リズムドライブのダイナミックな活用は、強拍での絶え間ないパルスを飛ばし、小単位への拍の分割により、高められる。彼の音楽をすべて裏打ちする着実かつ不屈のパルスは、3拍子におけるヘミオラのリズムのあらゆる洗練さをもたらし、2拍子においては、細やかなシンコペーションや、オンとオフとで連続するアクセント、そしてリズムパターンの無限の可能性を示す。そうしたリズムパターンは、弱拍で始まり、それらが強白へと動くような弾みをつける。 彼の音楽のペースは、デュファイやオケゲムより素早く、勢いが強い。cantus firmusとその他の声部の関係に、それの典型が見られる。オブレヒトは、cantus firmusを、implied augmentation(潜在的増大)と呼ばれるやり方で作っている。その音価はデュファイやオケゲムのミサ曲と同じであるが、それに対してオブレヒトは、より短い多くの音符を2倍ほどに詰め込んでいる。そのために、実際、cantus firmusは、増大しているように見える。たとえ小節の数がオケゲムのミサ曲のそれと等しくても(Gloriaにおいてはむしろより少なく)、音楽を演奏するためにはほとんど2倍くらいかかってしまう。 フレーズ構造はさらに複雑である。オケゲムのそれのように、しかし全体的には異なった理由で。 オブレヒトにおいて、自由な声部のそれぞれは、自身のフレーズ分割を持っている。それらは主としてオーバーラップはしているが、それは連続的ないしは模倣的構造のためである。しかし、非常にしばしば、2声部は互いにペアとなり、平行あるいは反行に同じリズムで動き、同時にカデンツに到達する。 オブレヒトは、ひとつのフレーズから次のフレーズに、非常にスムーズかつ流動的に移ることを好んだ。彼はしばしば、最初のフレーズの最後の音が、次の音の最初の音となるように、フレーズの一部を省略した。テキスチャーは常に深く、巧みに作られ、最後のカデンツへのドライブにおいて、非常に張り詰めたようになった。 こうしたドライブにおいて、オブレヒトは、クライマックス的な緊張を高めた。それは、ジョスカンのみが比肩し得るものである。Kyrieの終わりは、カデンツへのドライブのもっとも最後の例の一つとして引用されている(Ex.11 )。ここではすべてのフリーのパートは、cantus firmusの持続的なソ音のあたりを動き回っている。非常に空間的に接近した模倣でもって。 オブレヒトが導入する広く動く連続的なモティーフは、その特殊な魅力を、分析の目的でもってしても分離することが不可能な、メロディのデザインや連続的取り扱いが完全に互いに融合しているという事実に負っている。 Caputミサ曲においては、模倣は自由な声部に制限されている。cantus firmusは、そこには参加しておらず、その他の声部に対してのモティーフも供給していない。オブレヒトは、 絶えずメロディの本質としては離れてそれらを保つことによって、借用し作曲した声部の間のテキスト的なコントラストを強調している。 p295 こうした精妙な声部の分化は、必ずしも彼の他のミサ曲に見られるわけではないことに注意すべきである。たとえ模倣が非常に簡潔であり、かつ果てしないストレットの効果に接近しても、それははっきりと聞き取り得て、この点に関するオケゲムのあいまいさと比較して正確に、合理的に構成されている。 模倣的なエントリーの狭い空間は、興味深いリズムのアンビバレンスを作りだす。なぜなら、モティーフは連続的に始まり、そのために、強拍と弱い拍の区別的かつ相対的ウェイトは、意識的にある時をおいて繋留される。カデンツでより強くすべてが再度主張されるが(Ex.14参照)。 連続や模倣における異なった反復は別として、オブレヒトは、メロディの進行やオスティナートパターンにおいて、広い範囲で、純粋なリズム的模倣をおこなう。それはすなわち、同じモティーフ音型についての直接的かつ非移行的な反復である。彼はパーセル風の流暢さと魅力でもって、オスティナートを管理し、他のどこの彼のオリジナルよりもはっきりと、この手のパッセージにおいて魅了し、裏切る。 オスティナートは、しばしば、カデンツへのドライブに追従する p296 モティーフの繰り返しもまた、オブレヒトの音楽で非常に典型的であり、シンコペーションにおける拡大したパッセージにおいて、重要な役割を演じている。 彼のこうした工夫への性向において、彼は、幾分、ルネッサンス音楽の異端者である。シンコペーションは、2つの形式を取っている。それは共に、非常に複雑で”四分音符的な”リズム型として、単一声部に現れる。あるいは、常にその他の声部の通常の拍をひっくり返しているような単純なオフビートパターンとしての声部のグループにおいて、現れる。 1つのタイプは、複雑な計量的記譜法の無限の置換やあらゆるルネッサンス期の作曲家たちが好んだ汲めどないソースとともに作用する。オブレヒトは、Ex.12のGloriaやCredoにおけるアルトパートのいくつかの注目すべきパッセージに見られるような洗練さには特にこだわらなかった。 引用した抜粋においては、3つのsemibreve(全音符)分にあたる1小節に対して、3つの拍がある。オブレヒトはメインの単位をオフビートへ移しただけでなく、ほとんど邪悪的な巧妙さで、そのサブ分割がオフビート同様、メインビートにまたがるようなパターンを案出している。こうしたパッセージは、tactus(拍)への厳密な固執を予想し、もっとも大きなリズムを刻むような正確さとともに使われるだけで、崩れ落ちる。計量的な複雑さは、ほとんどすべてが、このミサ曲のアルトに集中していることに注目すべきである。アルトはおそらく、少なくとも、楽器によって声楽に重ねられるべきであろう。 シンコペーションであるもうひとつのタイプは、困難な計量パターンの上ではさほどウェイトはないが、その他のグループについての規則的に進行するtactusに対する声部のひとつのグループにおいて置換された拍を対抗させる。 Credoは、cantus firmusに対抗するシンコペーションですべての自由な声部が9拍で動く(m. 51-54)パッセージを含んでいる。その効果において、拍は弱拍から強拍へと劇的に変化するように思える。まるでcantus firmusが突然置き換わったかのように。こうしたたくさんのシンコペーションは、しばしばオブレヒトの音楽に生じており、事実、彼の様式の特質である。その直接性、同時性において、それらはデュファイの公式化された優美さ、オケゲムの地味な強さ、そしてジョスカンの目もくらむような終止からは等しく無縁である。たとえ元気でヴァイタリティがあったとしても。 p297 こうした工夫に関係して、motivic syncopationと呼ばれるものがある。それは、tactusとモティーフの音律単位の間の摩擦によって特徴づけられる。Et incarnatusからの部分がこの手順を非常によく説明している。(Ex.13)。 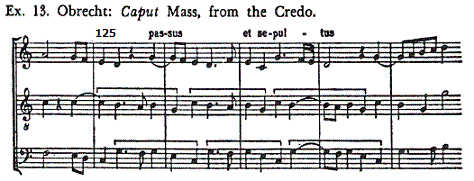 tactusは、ここでは、semibreve(四分音符)の偶数拍である。しかし、テノール(原文アルト)とバスのモティーフは、tactusに対抗するひとつの単位として5つのsemibrevesを構成している。オスティナート風に休符なしで数回繰り返され、モティーフ単位は、強拍と弱拍の間で前後に移り、パターンの興奮的なオーバーラップを産生している(モティーフ単位はかぎ括弧で示されている)。 興奮の印象は、2つのモティーフ単位が1つのsemibreve分離れており、そのために、シフトが異なったところで生じるという事実で強められている。Ex12のGloriaから引用された抜粋において、motivic syncopationは、計量的な洗練性と連帯して現れる。motivic syncopationは、近代音楽のある種の”動的”作品で再発見され、活発に使われているが、干渉する部分では、控えめに使われている。 オケゲムの横のアプローチはオブレヒトの音楽に強く生きているが、新たな重要性を受け取っている。そのハーモニーの本質的役割のために。音楽の流れは強い和声的なカデンツによってarticulateされている。そして、そこから、連続的なspun linesが、その方向性や力を受け取っている。 カデンツは、もはやデュファイにおいてのように厳密に限局化されてはいないので、オブレヒトは、より拡大したフレーズを打ち立てることができ、より長く保っている。中間のカデンツによって手短に上品に棒引きされたデュファイの公式的なフレーズと、一方でのオケゲムの終わりのないメロディのモザイクと、オブレヒトのさらうような幅広い作風との比較が現れている。 p298 カデンツの数に関する限り、オブレヒトは、両者の中間に立っている。しかし彼は、そのフレーズの幅において、両者を凌駕している。オケゲムのように、オブレヒトはポリフォニーの原理を打ち立てているが、違いもある。オケゲムの作風は受動的かつ浮動的であり、オブレヒトのそれは能動的かつ動的である。 カデンツの強い機能は、Ex.14のAgnusIIIからの抜粋から容易に見ることができる。このcantus firmusは、statementBの最初を示している。その活力とステップアップされたペースは、cantus firmusの不変の音価に対抗する短い音符の増大する使用において明らかになる。 オブレヒトが第27小節において、下降五度のモティーフを導入していることを見落としてはならない。それは、 (デュファイ)のミサ曲においてと同じリズム形式でありかつ同じ場所にある。しかしこの類似性は、おそらく偶然である。しかし、この抜粋がAgnusから取られていることについては、偶然ではない。この楽章は、選択されたものなのである。なぜなら、それはcantus firmusの場所(バス)において、オケゲムを真似しているからである。そしてそれゆえに、興味深い比較となっている。 p299 オブレヒトのバス声部は、本質的にオケゲムと同じ和声進行をとなっているけれども、それらは、トータルでは異なった作風となっている。それらの遅れたペースや、cantus firmusのimplied augmentationは、articulationにおける変化の部分的説明のみ供給している。さらに重要なことは、和声進行は、横のパート書法のまったくの副産物というわけではなく、それ自身の権利のハーモニーへのターンとして取り扱われているという事実である。それらは、注意深く半終止(m. 30),へと準備される方向にあり、偽終止のように解決されることもあるが、明らかに、periodの最後をマークしている。こうした戦略的なカデンツは、音楽にその合理的なデザインの透明性を与えている。 一般的に、オブレヒトの音楽は、異なった長さのよく洗練されたハーモニーのperiodではあるが、しばしば対称的なproportionを取っている、ということが主張されている。メロディ的意味合いや模倣によって統一されたことでで互いにリンクし、それらは、互いに、秩序だって、processionに従っていく。Et incarnatusは、こうしたperiod structureを特に、確信を持って、説明する。 最初のperiod(m. 1-9)は、note against noteで書かれ、同様のテキスチャーにて書かれた次のperiod(m10ー17)に相当する。m17とともに、バスのド音ではじまり、それからレ、ファ、ソ音からラ音へと厳密に類似するセクションにおいて上昇する3+半measuresの連続が始まる。 それぞれのセクションは、連続のドライブを支障することなく、カデンツによっていったん閉められる。続くperiod(m. 34-42)はそれから、Ex.13 で引用されたオスティナート音型によって、スピンアウトされる。連続性をそこなうことなく、新たなperiodが、cantus firmusの入りとともに始まる(m. 43-49)。この場所では、バスはドロップアウトし、テノールがそれを引き継ぐ。続くperiod(m. 49-59)は、バスが再度入るが、それ以前のperiodとともに排除され、m. 57-59において最初に現れるバスのモティーフによって、次の長いperiod(m. 59-70)といつのまにかリンクする。それからは全体に波及するオスティナートのモティーフとなる。 楽章の残りは完全に分析するには長すぎるが、同様に進んでいく。オブレヒトは、cantus firmus上に彼の音楽のperiod structureを置いている。cantus firmusは、動じることなく、そして、その他の声部の芸術的organizationに影響されることなく、そのコースをひた走る。オブレヒトはそれゆえに、sweepingの印象を作り上げ、連続性を徐々にぼやかし、反復の提案を避けている。 p300 実際、オスティナート音型は、音楽の流れに沈められるようになり、波及したドライブを調整しようと躍起になる。periodic structureと連続的拡大という2つの対立する原理の間の注目すべきバランスは、オブレヒトはジョスカンとシェアするが、彼の音楽において、もっとも重要な要素を示している。 それは、真実の、ニコラウス・クザーヌスの重要な概念であるcoincidentia oppositorum(反対の一致)であり、後期ルネッサンスの究極の音楽的達成である。 後期のデュファイの期間からハーモニーの世紀末へのハーモニーの素早い発展は、オブレヒトが彼のミサ曲の主要部分で使ったカデンツのタイプに光を当てることで明らかになる。 明らかに、彼のカデンツはより発展しており、 (デュファイ)やオケゲムのカデンツより変化している。オブレヒトのすべての最後のカデンツは、導音進行のカデンツと結びついて、近代的なドミナント-トニック進行となっている。それらは、メロディ構造と同様に、ハーモニーにおいても近代的である。 もうひとつの進行の特徴は、注目に値する。オブレヒトは、それぞれの楽章の第1部分を、フルの三和音で終わらせている。それは明らかに、彼が半終止と考えていたものである。オブレヒトはその他のところにもこれを使っていた(注138)が、それらは、 (デュファイ)において一度だけ現れただけで、オケゲムにいたっては、まったくそうしたところは見られない。 (注138)Christeの最後とSanctusの最初の長調カデンツを見よ オブレヒトのミサ曲で頻繁に使われる旋法はハ長調であり、すべての楽章は、一貫して、イオニア旋法の正格終止で一貫して終わっている(注139)。 (注139)オブレヒトのミサ曲は、イオニア旋法がグラレアヌスによって1547年に理論的に認められるはるか前より使われていたことを示している。 特徴として、cantus firmusのミキソリディア旋法は、最後のカデンツには、影響しない。オブレヒトは単に、必要に応じて、終止にド音を加えただけである。第1部分の最後のみで、プレインソングのオリジナルな旋法はそのままであるか転調において、これに直面している。 p301 オブレヒトの (デュファイ)を超えた発展、彼のハーモニーの価値への偉大な気づきは、cantus firmusを導入する彼の機知に富んだやり方の裏返しである。♭記号の音としての曖昧さは、オケゲムのハーモニー的曖昧さに通じるが、オケゲムや (デュファイ)の初歩的なハーモニースタイルにはあまり関係ない。すでに見てきたように、 (デュファイ)は常に、三和音の一種として、cantus firmusの最初の音を導入している。しかしこの和音はそれ以前の和音進行と直接の関係は持っていない。 オブレヒトは、より大きなハーモニーの持続にひざまずき、繋留音(Credo)あるいは単純な正格終止(Sanctus)とともにエントリーを用意する。KyrieとSanctusは、両楽章とも、オケゲムに似ているが、両ケースにおいて、イ長調からロ短調へと動く偽終止とともにcantus firmusを導入することによって、この点をより強調している。それを通して、メロディは、ミキソリディア旋法とはほとんど一致し得ない新たなハーモニーの微妙なあやを要求する。 (デュファイ)やオケゲムの循環の楽章が、多かれ少なかれ、別個のグループとなる間、そのようなアレンジメントはオブレヒトのミサ曲には見出されない。それはハーモニーとして統一される。ハーモニー自身はその他の作品よりも豊富で変化に富んでいるが。オブレヒトのミサ曲の楽章は、連続や模倣的deviceへの固執を負っている。”内部”統一の高い程度具合は、なぜオブレヒトがモットー冒頭なしですませたのかを説明する。それは、cantus firmusに並んで、”外部”の統一の基本的意味合いである。 高く統一されても、cantus firmusの連続したシフトによるだけでなく、それぞれのモデルへの親密性においてもまた、個々の楽章はお互い異なっている。すでにミサ曲におけるテノールを比較して見たように、3つの中間の楽章、G loria,Credo,Sanctusは、デュファイの後に流行した。その間、Agnusは、両者のモデルからの特徴を組み合わせている。Kyrieはそれ自身、cantus firmusを単回のstatementに縮小させ、自由な導入のセクションを欠いている。こうしたすべての傾向は、オケゲムのKyrieとも共通項がある。 オブレヒトの借用の一面は、今や完全に見逃されている。彼はGloriaの冒頭で、 (デュファイ)のGloriaのtrebleからの最初の8小節を引用しているが、それに低声部の新しいセットを与えている。引用は正確ではあるが、いくつかの装飾音がつき、モットー冒頭以上をかなり取り入れている。それは、疑いなく、オブレヒトが (デュファイ)のミサ曲を知っていたことを証明する。 p302 オブレヒトの作品は、特に作曲日時ははっきりしていないが、ハーモニーの傑出した役割やその合理的扱いからして、それは、イタリアにおける最初の滞在後の1474年以降に書かれたであろうことは確かに見える。この当時、彼の様式は、彼の後期作品に消しがたい印象を残した形式やテキストの明瞭さの段階をすでに通り抜けていたに違いない彼の清澄なテキスチャーやイタリア音楽の合理的明瞭さとの接触は、彼に、確固たるフランドル楽はの対位法を改変し、彼の後期の音楽を見分けるようなある程度の透明度や風通しをもたらした。 ミサ曲のもっともあり得そうな日付は、Gombosiが提案しているように、1483年-1485年の間であり、オブレヒトがカンブレー大聖堂のチャペルのmagister puerorumになっていた時期である。そこで彼は、(デュファイ)のミサ曲に接するちょうどよい機会を得た。当時オブレヒトは20代であり、こうした流行を吸収していった。 オブレヒトのミサ曲で、Caputをテノールとして用いる別のAgnusが存在する。この楽章は、現存の写本において、直接、オブレヒトの作品に続いている。そして、著作者の名はあら得られていないために、それがオブレヒトの代替楽章であるか、その他の作曲家の作品であるか否かは不明である。 ハーモニーと不協和音の取り扱いは、オブレヒトがその作品を非常に早い時期、彼のイタリア旅行の前に書いたことを意味している。しかしこうした結論は、その他の研究所見からは合わない。オブレヒトのオーサーシップは、不可避的に、模倣やcantus firmusの取り扱いの発展した段階と、ハーモニーや不協和音の取り扱いの初期段階との間の様式的矛盾を含んでいる。 完全版は、Obrechtのミサの補足としてCaput tenorに関するもう1つのAgnusを提示している。この楽章は、現存する唯一の写本の中でObrechtの作品に直接続いている。そして作者の名前が与えられていないので、それがObrechtによる代替の楽章なのか別の作曲家の作品なのかは明らかではない。 この点についての意見は分かれている。Wolfは、彼の前置きのコメントで、失敗ではないにしても、いくつかのあまりうまくない進行があるので、これをObrechtに帰すことを疑っている。Gombosiは、それが「疑いなく本物である」という一般的な様式の根拠に基づき、それをObrechtの本物の作品とともに、グループ化している。彼はミステイクの存在を認め、彼自身の「強い」修正によってそれらが訂正されることができると主張する。どちらの著者とも、この研究において、様式比較の貴重な道具であると証明してきたcantus firmus に光を当てた論議を考慮していないので、疑問は新たに研究されるに値するものである。 何よりもまず、cantus firmus が触れられていないことを述べなければならない。 それはメロディーとリズムのすべての詳細において例4(p260)に対応する。 セクションの一般的なレイアウトでは、作品は概して、オブレヒトのAgnusと一致する。 これは楽章が共通しているCモードによっても確認される。 表3(p263)と比較されるべき匿名Agnusのテノール構造は、以下のスキームとなる。 p303 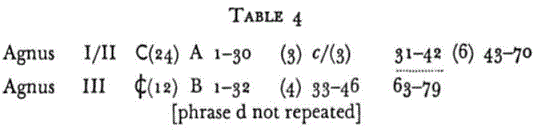 導入と中間の休符はObrechtのものと一致しない。それは、Dufayの後にパターン化されたものである。さらに、他のミサ曲からのいくつかの目立った逸脱がある。ステートメントAの拍子記号はCであり、予想されるとおりの〇ではありません。この2拍子は、cantus firmusのリズムが変更なしに採用されたという我々の主張と矛盾している。 それにもかかわらず、両方の記述は正しい。作品は、概して、2拍子で進行していくが、cantus firmusのもともとの3拍子は、その上に重ね合わされる。テノールの2つの小節は構成の3つの小節分となる。2つの付点付きbrevesは、3つの付点のないbrevesとなる。その結果、相対的なリズムの変化はなく、書法の変化だけが存在する。 Agnus II の冒頭には、テノールのフレーズc(m。31-42)が突然、augmentationに表示されている。上図では、点線の下線で示されているが、他のミサ曲には前例がないん。オリジナルの3拍子のaugmentationにもかかわらず、他の声部は2拍子のままである。ステートメントAの最後のセクションでは、augmentationは現れたと同時に突然放棄される。そしてさらに、スイッチバックが正式な細分割なしに楽章の途中で起こる。 'cantus firmus はテノールが担っていたが、Agnus III ではソプラノにシフトし、オブレヒトのグロリアと同様になる。 7. SUMMARY AND POSTSCRIPT ON OTHER CANTUS FIRMI (前略) アンティフォンVenit ad Pelrumの典礼的、音楽的歴史についての疑問にはまだ十分に答えられていないが、循環ミサ曲の歴史に関しての成果については疑いはない。 我々は、Caputミサ曲がセイラム典礼からの通常ではないプレインソングを基本としていることを確認した。 (デュファイ)(あるいは未知の英国の作曲家の可能性もある)はそれに、任意のリズムをつけ、続く作品にも厳密にそれを適用した。オケゲムはそれを引き継ぎ、この点を明確にするために、特に、”カノン”を案出した。そしてオブレヒトは、より高い統合での2つのモデルをもたらした。 3曲のCaputミサ曲は、非常に短期間に作曲された。それはわずか20年ほどの間であり、1463-1483(1485)年の間である。それらはデュファイにおけるルネッサンス音楽の勃興、オケゲムにおける後期ゴシックの神秘主義の最後の花、そしてオブレヒトにおける盛期ルネッサンスの音楽傾向の証言者である。それらは私たちに、非常な集中でもって、15世紀の後半の音楽様式の驚くべき成長の概観を見せ付ける。 その概観をしめくくるべきジョスカンのCaputミサ曲がないのが唯一、残念なことである。作品の重要性は、その固有の芸術的価値だけでなく、確固たる伝統の存在の開示にもまたあり、現在の作品に権威を与える過去からの声部の借用において提示されている。正確には、作曲家が伝統に固着するために、彼はあえて、同じ構造の声部を基礎にして、可能なかぎり対照的な古い作品と区別されるような新しい作品を書き始める。 3曲のCaputミサ曲は、それぞれ、ミキソリディア旋法、ドーリア旋法、イオニア旋法と明らかにその旋法が異なっており、それぞれの場合において、同じプレインソングのハーモニゼーションを備えている。 旋法の違いは象徴的である。それは唯一の、より重要な内部の様式の多様性についての外部の兆候である。実際の演奏においては、そこにある声部や構造はほとんど聴き取れないし、様式やイディオムの要素で押し流されてしまう。それらは、音楽素材のメカニックを超えて、音楽のイマジネーションの勝利を証言する。 (中略) デュファイのMissa Ecce ancilla Domini は、受胎告知の祝日で歌われる同名のアンティフォンを基礎としている。Van den Borrenは、テノールのフルテキストを出版しているが、2番目のセンテンスBeata es Mariaを誤ってGratare Mariaと読んでいる。引き続いて彼は、これが最初のチャントの続きではないことを見逃している。それは独立のアンティフォンであり、別の祝日、7月2日の聖母マリアのエリザベト訪問に関係している(Anl.Rom.,64)。 cantus firmusは、実際にそれゆえ、 常に同じ順序で現れる2つのアンティフォンから構成されている(KyrieI /Christe= Ecce ancilla KyrieII=Beata es Gloria前半=Ecce ancilla Gloria後半=Beata es だから、本当ならMissa Ecce ancilla Domini / Beata es Maria となるとこころですが、一般にはEcce ancilla Dominiと呼ばれています。Ecce ancilla Domini も Beata es Maria も、ともに聖務日課の晩課で歌われる聖母マリアのカンティクムMagnificatとともに歌うAntiphona。フォンス・フローリス古学院ブログより)。デュファイの循環ミサ曲は、当時、デュファイの秘書であったRegisによる同名のミサ曲と関係している。Regisの作品の冒頭は、第2のアンティフォン、この場合は受胎告知に属するNe timeas Mariaが、Ecce ancillaと同様につけられている。Regisは明らかに、デュファイを真似ていた。なぜなら彼は、異なったチャントを用いなかっただけでなく、Ecce ancillaの冒頭を正確に、デュファイがしたようなやり方で、変化させたからである。さらに、アンティフォンBeata es MariaとNe timeas Mariaは、同じメロディタイプに属しており、さらにそれゆえ、メロディとしてほぼ同じなのである。 Regisがデュファイと異なっているのは、きわめて重要なある点においてである。彼は、2つのアンティフォンEcce ancillaとNe timeas Mariaを、2声として同時に、二重のcantus firmusとして使っている。借用された声部に対する彼の独立した態度において、、彼は後の作曲家の特権(オブレヒトですでに私たちが紹介した)を利用した。 次が、デュファイやRegisと同じタイトルがつけられている、オブレヒトのMissa Ecce ancilla Dominiについてである。だがタイトルの同一性は、偽りである。なぜならば、オケゲムのcantus firmusは、これまで論じられてきたアンティフォンとは無関係だから。 Plamenacは、オブレヒトについて、プレインソングの原典に関して、誤った出版をしている。オケゲムは実際には、アドヴェントの期間に聖母マリアを記念して歌われるアンティフォンMissus est [Angelus] Gabrielを引用しているのだ。 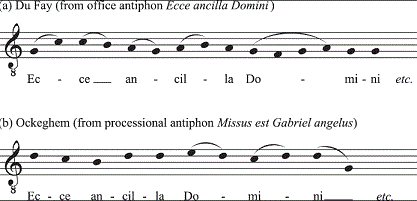 この作品が収められているキージ写本の光彩は、我々に、テキストに関する糸口を提供している。それは、大天使ガブリエルに訪問された聖マリアを描き、それゆえ、光彩として、直接に音楽に言及している。 オケゲムはプレインソングのメロディを忠実に用いているが、借用したパッセージは見出すことが困難である。なぜなら、それは、チャントの後半部分にあるからである。Caputのメリスマ場合のように、cantus firmusが冒頭を省略しているという事実は、正しい同定のための主たる阻害要因であり、こうした特殊ケースでは、混乱の理由は、言葉が別のチャントの始まりを示唆しているためである。 オケゲムの有名な、バンショワの死に際してのDeploration sur la Mort de Binchois "Mort, tu as navre"は、少なくとも、cantus firmusをベースとしている。Pie Jesuで始まるテノールの最後のセクションは、セクエンツィアDiesiraeの最後からの借用である。オケゲムは、そのメロディを強調し、忠実に引用している。 次に、オブレヒトのミサ曲Sicut sPina rosam genuitに目を向けたい。この曲は、彼のSalve diva parens Massとともに、もっとも重要な作品に属している。Wolfは、典礼的な原典やChevalierのRepertorium Hymnologicumには、プレインソングの跡はたどれなかった。それができなかった理由は、cantus firmusがここでもやはり、フラグメントだからである。 それは、ノートルダム学派の初期にポリフォニーで処理されたrespond Ad nutum Dominiの半ばに根ざしている。中世の演奏形態によれば、チャントのソロセクションのみが、ポリフォニー作曲のためのテノールとして供給された。こうした制限を無視して、オブレヒトは、合唱セクションから彼のcantus firmusを選んだ。合唱パッセージの選択は、ソロと合唱ポリフォニーの間の区別が、オブレヒトの時代にはあまりなくなっていたことを意味している。 オブレヒトによるMass Ave regina celorumを最後に語ろう。その示唆的なタイトルにも関わらず、作品には、グレゴリア聖歌のメロディが見つかっていない。そのテノールは、同名のオブレヒトのモテットからの借用であるというWolfの声明は正しいが、不完全である。ミサ曲とモテットの両者は、自由に作曲されたWalter Fryeのシャンソンモテットにまで行き着く。この英国の作曲家(彼は、その生涯の大部分をブルゴーニュ地方ですごした)による作品は、この種類の作品ではもっとも有名なもののひとつであった。オブレヒトはそのテノールを借用し、時には、trebleの部門も借用した。Ave regina celorumやCaputにもとづく彼のミサ曲のcantus firmusは、彼の音楽であるフランドル楽派よりも、ブルゴーニュ楽派にむしろ強く負っているのである。 Missa Ecce ancilla Domini (デュファイ) 循環ミサ曲 cantus firmus Caputミサ曲 cantus figuratus canlus mensuratus cantus planus |