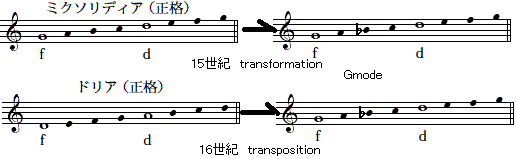| B-Flat: Transposition or
transformation? Dolores Pesce |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| p330 b♭は、西洋音楽理論の歴史において、決定的なポジションを占めている。厳密な全音階的音調システムを維持することを強調するために、11世紀から14世紀に活躍した理論家たちの多数は、旋法を特定するメロディの動きの核心にb♭を受け入れることに躊躇していた。 この純粋な態度の結果は、音調システムでのさまざまな位置で旋法を確立するために変化した音調に依存した移調の概念の認識における理論家たちの関心を遅らせることとなった。 多くの中世の著作家たちにとって、移調とは、音階の全音階的セグメント間でのメロディ素材の移動を意味していた。新しい位置でのb♭を含んだ移動は、transformation(変形)とラベルづけされることになった。 transformation(変形)という用語のこうした適用は、Guido of Arezzoによって提案されたような意味合いの延長であったようだ。彼は、どの音程も、単一の旋法的関連や、所与の音程のメロディセグメント内にb♭が追加されたならばtransformation(変形)されたであろう旋法的性質を持つ、と論じた。 理論的には、こうした音調システムの厳格な見方はもっともであったが、継承されたチャントのレパートリーを表記するために使用されていた慣習とは合わないことがあった。 特定のチャントに、旋法的には一般的でないinflectionが含まれている場合、スクライブたちは、b-flatが旋法の定義に不可欠な音調の位置にそれらを記すことにより、メロディの輪郭を維持させた。 このような表記の移動は、必要に応じてではあったが、音程の「transformation(変形)」をもたらした。こうした慣習をグイドの影響力のある優先順位に関する影響力のある記述とどのように調和させるかという問題が、多くの理論家をひき付けていた。 本研究は、ジャック・ド・リエージュの時代を通して、bフラットの理論的議論とその音調システムにおける役割をたどっていく。まずは、グイド以前の著作家たちが、どのように転調を考えていたかを示し、Musica Enchiriadisの著者の著作が、グイドと彼の同時代人にとって特に重要であったことを示唆したい。 <Hucbald、Musica EnchiriadisとScolica enchiriadisの時代> 中世の理論家たちが転調に言及したとき、彼らは常に中世の音階の音程間の関係の議論の中でそうしていた。 コンサルティングする理論家に応じて、socialitas、similitudo、またはaffinitasと呼ばれる音程関係が見いだされる。 (アフィニタスとアッフィナリス参照) 9世紀の終わりには早くも、五度間隔で区切られた音程と四度で区切られた音程は区別されていた。 Scolica enchiriadisにあるこれに関連するパッセージを次に示す。 実際、主に、どのtropeの性格も、それが終止音によってのみ存在していたという理由で、最後の響きに依存している。 ただし、これは、同じ最終的なサウンドとそのより一般的に関連する響き(sociales)がcommataや colaの最後にあるということが追加されている。 各響きは、五度での位置だけでなく、それに関連する響き(sociales)を持っているが、(オクターブ、五度に続く)第3の協和音程の位置である四度の位置(つまりdiatessaron)で、それに関連する他のサウンド(compares)を求めている。 p331 引用では、著者は明らかに、所与の旋法的終止音との関係で音程の階層を確立している。 彼は、socialisとcomparという言葉をそれぞれ五度と四度のサウンドに適用し、それらが言及されている順序によって、socialisはcomparよりも、終止音への密接な関係を持っている。 単独で考えると、この抽出は、著者が所与の終止音から動いた五度や四度で終わるフレーズを考察することのみを決定している。 彼がこれらの関連するポジションの1つにメロディーを移調したことを知っていた、その移調を裁可したりしていた暗示はあるのか? 私たちの答えは、musica enchiriadisにあるあまり知られていない一節にある。 ただし、最初の合意は、前述の方法[ユニゾン]でメロディーを指示するために使用されるものであることを知っておく必要があります。 重要度の低い別の一致があります。高すぎることの難しさを軽減したり、低すぎるのを上げたりしたい場合は、我々は、五度の移調によって、より高い位置またはより低い位置にもっていく。 また、音の八度の位置、つまり、若い声や高い声のメロディにシフトするときの第3の一致もあります。 そして、これらの関連付けを通じて、歌の特定の和声を維持することができます。 それ以外の場合は、移調によってメロディーが別の旋法に完全に変更されない限り、できません。 同じ一連の音のメロディーを1つ、2つ、または3つ上または下に移調すると、tropeの旋法が同時に別の種に移動します。 2番目の文章は、明らかに、音程の理由によって五度上下する移調を記述している。中世の音程の基準に関する明確な知識はないが、相対的な音程の概念は有効であったと考える合意がある。したがって、著者による「高すぎること」および「低すぎること」への言及は、音程自体には関係していないだろう。すなわち、一定の歌手に対してより低すぎて記譜されたメロディは、表記を変更せずに、単に高いピッチで歌うことができる。 p332 しかし、トータルの旋律の音域が歌手の声の通常の範囲を超えた場合、移調が目的を果たす可能性がある。 歌手の音域外のメロディー部分は、その部分だけを移調することで、その中に入れることができよう。 もしもこの意味合いがMusica Enchiriadisの一節に帰せられるとすれば、学者たちがどんなチャントを「部分的な移調」と呼ぶかについての最初の理論的言及が見られることだろう。 Guido of Arezzoは、1世紀以上後に、この慣習を説明している。 メロディセグメントが始まる場や旋法は、歌手の体験に任せられている。そのために、もしも移調が必要ならば、歌手は関連する音程を探すことだろう。 すでに簡単に論じたように、グィドの移調に対する合理性は、Musica Enchiriadisの作者によって提案された合理性と一致している。 Scolica のパッセージに戻ると、おそらく最初に、それが、より高い位置またはより低い位置に、五度移調することをほのめかすことに驚かされることであろう。 中世の音階では、メロディーが下五度に移調された場合、メロディーがその音程の内容を保持することはできない。 ただし、上五度では、六度の範囲内でメロディックなアイデンティティが可能であった(図1)。 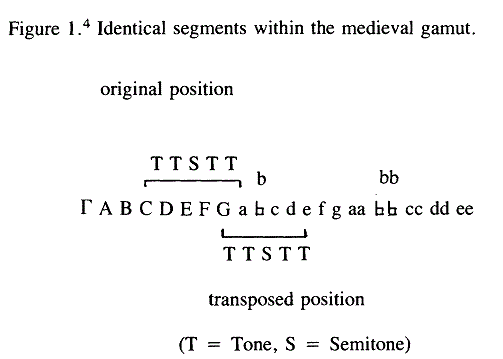 上方の五度でのような関係は、 Hucbald のDe harmonica institutioneによって初めて指摘された。 ただし、彼は、音域の制限については言及していなかったが。 彼の発言内容は、音階内の5つのテトラコードについてであり、すべてが4つの旋法終止音D E F GまたはTSTの音程配置に従って構築されている(図2)。 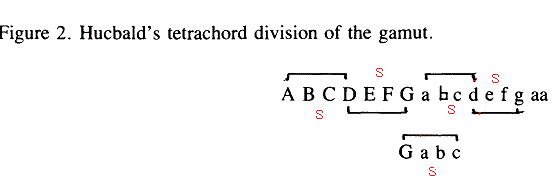 ちなみに、Hucbaldには、ある種チャントで必要なb-flatを説明するために、synemmenon(現代のG,a,b♭、cに相当する)テトラコードが含まれている。5 5 Hucbaldはもちろんb-flatという用語を使用しておらず、テトラコードsynemmenonとしてラベルを付けており、それは、特定のチャントでaとbの間に必要になる半音を指している。 b-flatを含むテトラコードに対する彼の理論的正当性は、ギリシャ理論のsynemmenonテトラコードにある。 古代の理論家たちはそれを、現代のa b-flat c d,に相当するピッチとしていたので、それは、上からTTSのテトラコード配置であった。 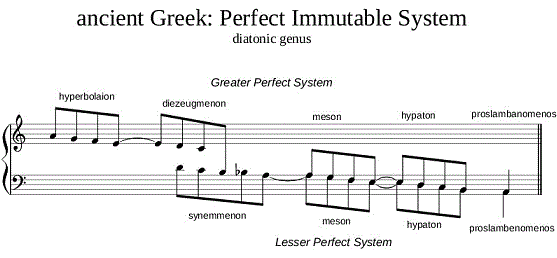 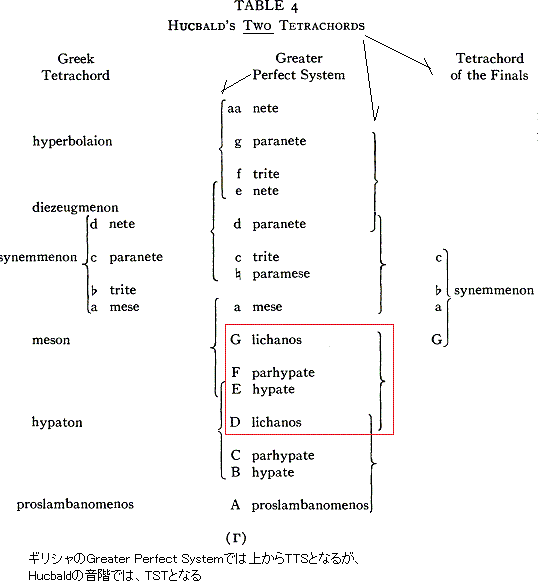 p333 終止音のテトラコードに特に言及し、Hucbaldは、そのトーンのそれぞれと五度上のそれぞれのピッチとの間に旋法関係があると単に述べている。これにより、彼は、暗黙的に上部のテトラコードに配置された類似のトーンを意味している。 Enchiriadis の作者は、TSTピッチと同じ一連のTSTを保ったまま。それぞれの五度上下の間で無制限の関係が発生するという特徴的な音階を構築した。(図3)。 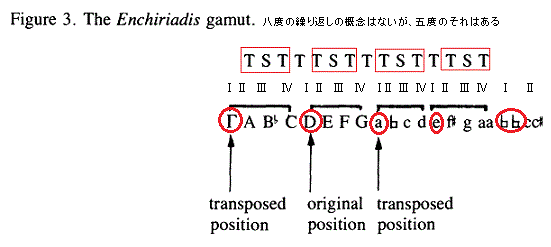 シュピッタをはじめとする多くの学者は、1889年に、この音階を、一連のdisjunctテトラコードとして記述し、それぞれは旋法終止音、TSTの内部配置を持っている、とした。6 任意の2つの隣接するテトラコード内に同様に位置していたピッチは、五度の間隔で分離されている。このような音階scaleを使用することにより、著者は、図1に示されるような中世の音階に固有な、五度の制限された関係を拡張させた。 Enchiriadisのスケールの広く保持されている解釈は、その構造が、完全五度以外のすべての発生を排除するので、それは、五度の平行オルガヌムの慣行を説明する。疑いなく、著者は心に留めておいたが、彼は明らかに、旋法関係に言及することによって、(四度のそれとは反対に)五度のオルガヌムへの彼の好みを支持することを求めた。 p334 Musica enchiriadisでは、作者はDで始まる限られた範囲のメロディーを取り、それがaに到達するまで、音階のより高い開始点に連続的に移動する。 Dから四度動いたメロディーについて、彼は次のように述べている。 3スペース分高くすると、4番目の旋法に上昇します。 それよりさらに1スペース高い位置となると、5番目の位置でふたたび、最初の旋法になります。7 7 Gustav Reese はこの一節を、一部のチャントがどの旋法でも歌われる可能性があることを意味すると解釈していたが、この解釈は誤っている。see Music in the Middle Ages (New York, 1940, p159). Enchiriadisでは、賛美歌「Te Deum」、特に15節「Tu patris sempiternus es filius」を引用している。この聖歌は作者の読者に知られていて、明確な旋法的関連性があった可能性がある。 したがって彼らは、音階での新しい位置で旋法がどのように変化したかを、簡単に認識できたことであろう。 旋法の識別は、その特定の全音と半音の配置に依存している。 したがって、メロディーが四度上に新たに配置されると、旋法の変化が発生してしまい、五度上の識別された配置では、その旋法をメロディが保持することを許容する。 著者はさらに、五度で分離した2つの声がどのように同じ旋法を担っているかを、読者に思い起こさせる。 既存の旋法的識別をさらに強調するために、著者は、スケール内の各テトラコードの4つのそれぞれのメンバーである4つの旋法の名前、 protus, deuterus, tritus, tetrardusを使用している。 この識別手段に基づいて、完全五度は、2つのテトラコードのdeuterus(第3,4旋法)メンバー間で発生すると説明できよう。 Based on this means of identification, a perfect fifth can be described as occurring between the deuterus members of two tetrachords. したがって、旋法的コンセプトの統合を持つ彼の特殊なスケールを通して、著者は五度オルガヌムの信頼性を供与している。 さらに,、同じファクターが、完全四度オルガヌムの完全な是認を妨げている。 四度をまとめているピッチは、2つの異なる名前が付けられている。 すなわち、Dはprotus、Gはtetrardusである。 言われたように、四度の位置で同じトロープが見つからず、異なるトロープの旋法を同時に維持することはできないため、このために、diatessaron(完全四度)の協和音程において、vox principalis とvox organalisは、四度の位置ではことどごく同意がない。 <BernoとGuido;Berno> 興味深いことに、2人の主要な理論家が、11世紀に Enchiriadisのピッチ関係に関する見解を、移調についての彼らの理論の出発点として、取り上げており、それぞれが何が許容できるかについては、異なる結論に達した。 2人のうちより自由なのは、 Berno of Reichenauであるが、彼の好敵手で、イタリア人であるGuido of Arezzoは、より制限されたアプローチを選択している。そのアプローチは、次の世代の筆記者やほとんどの理論家の間で支持されている。 p335 Bernoは彼のPrologus in tonarium で、旋法に応じて記譜し分類するという仕事において助力が必要な「学識あるカントル」に向けて、彼が受け継いだチャントの形を指示している。 Bernoは、特定のチャントが、通常の終止音、D E F G以外でのピッチで終わるのはなぜか、の理由を示している。 そうすることで、彼は上記の、五度や四度への移調を同等の条件で受け入れている。 最初に、socialesとcomparesの存在に関するScolica enchiriadisからのパラフレーズされたパッセージを得ながら、Bernoは続ける。 ・・・メロディの多くは、もしもそれらの固有の終止音にて始まったならば、半音がないために、よくない結果となる。しかし、もしもそれらが(移調されて)より高いレベルで始まったならば、それらは、その他のピッチに影響することなく、スムーズに続き、関連する終止音にて適度に終止する。 Bernoは、「いかなるピッチにも悪影響を与えることなく」チャントを保護することを可能にするため、移調を裁可しているが、それからの修正が移調の代わりの選択肢として、頭をもたげる。 これらの解決策のいずれかを要求する基本的な状況は、チャント内の、音階には当てはめられない音の存在にある。10 <四度上への移調> 第3旋法の聖体拝領 "Beatus servus" は、Bernoの良い例となっている。 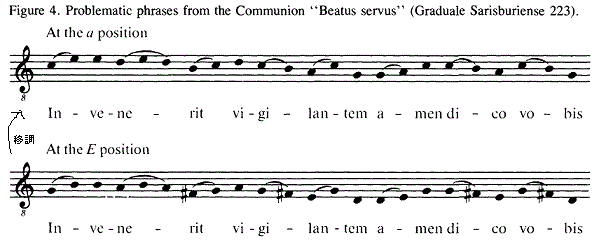 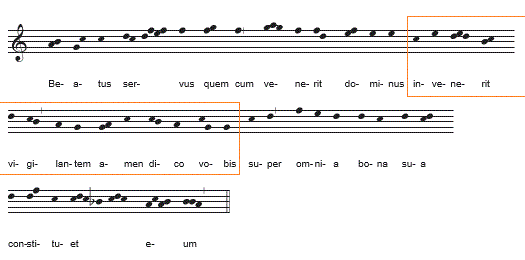 g01354参照 明らかに、移調されていないピッチレベルでは、「invenerit vigilantem amen dico vobis」というフレーズには、Fシャープを付けて表記する必要がでてくる。 Bernoたちは、コミュニオが四度上に移調されると、Fシャープを表記する問題が軽減されることを示唆している。Fシャープはb p336 Enchiriadisの音階は全音階的(図3を参照)であることを思い起こされたい。 一方、オーソドックスな中世の音階は、小オクターブでのピッチの2つの形式、b♭とb bフラットを採用することにより、終止音レベルで見出された内部進行の四度上に重ねることができる。たとえば、E F G aはa b♭ c dで、同等となる。 "Beatus servus"においては、EからFへの通常の旋法的なinflectionはaからb♭になる(そしてaはdeuterus終止音になる)。 この移調された場所の旋法にb♭を統合ピッチとして含めることにより、Bernoは、四度での旋法的アイデンティティを損なうことに対するEnchiriadisの反対を克服している。 <五度上への移調> 反対の役割が、五度上への移調でb♭とb 一部のチャントでは、明らかに、移調されていない段階でE♭を必要とし、2つがBernoによって言及されている。antiphon 「Domine qui operati sunt」と「Alias oves」である。 13世紀のWorcester antiphoner に保存されていた「Domine qui operati sunt」の版は、五度上へのチャントの移調によってなされるとb♭になる、E♭のinflectionを保持している。(Figure 5). 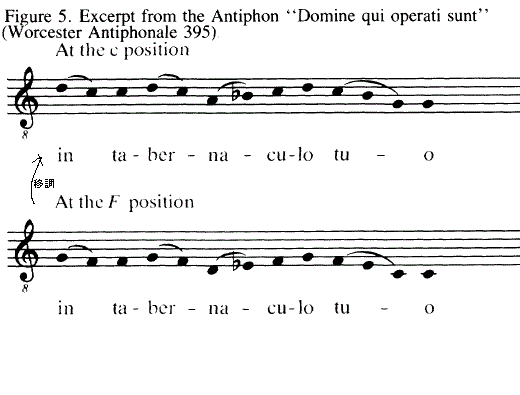 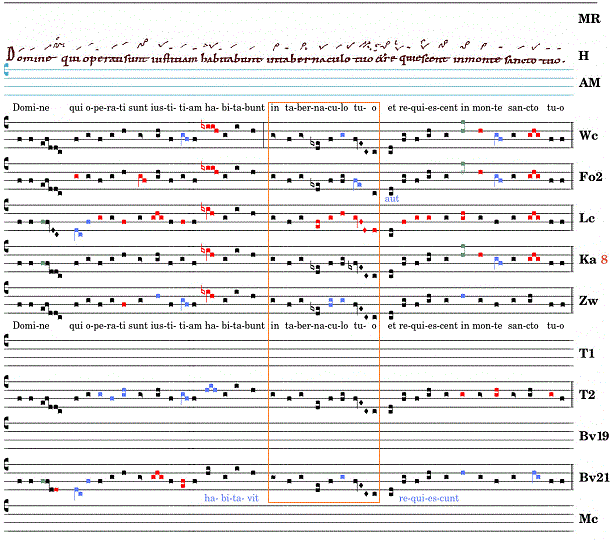 参照;1572 AN Domine qui operati suntModus 6 この解決は、終止音と五度上のピッチの間に、旋法的アイデンティティが存在するという、1世紀以上前のHucbaldの認識に従っている。11 11「Dialogus de musicaの作者もまた、「Domine qui operati sunt」を論じているが、彼は、Fのinflection(としてのEを)を考え、そのために、E♭を残すような(旋法的アイデンティティを保持するような形での)、五度上への移調は提案していない。 彼は、inflectionは、tritusの終止音(ファ、ド)の下での通常の半音進行(ミやシを使う)から始まる、としている。修正の可能性を無視して、FではなくGから聖歌を始め、tetrardus(ソ、レ)としてそれを再分類することを勧めている。なぜなら、終止音の下の全音でのinflection(ソファソ、レドレ)が、この旋法を特徴づけているからである。 彼の解決では、チャントの始まりの重要性も明らかにされている。彼は(♭を使わないことによって)メロディーのGへの移行を推奨したため、「このため、"Amen dico vobis."でのように「Domine」を(第8旋法で)始める。」 Amen dico vobisは第8旋法であり、それゆえに著者は、音楽家たちの何人かが、”Domine"の始まりを第8旋法の始まりと同様にすることを報告している。Ruth Steinerは、この手順のチャントのレパートリーの例を参考にして、それが旋法的に分析され、移調されたか、または修正された後に、メロディに新たな始まりを与えている。 p337 <Guido> グイドのMicrologusは、カントルではなく、チャントを学んでいる少年向けという点においてBernoのPrologusと区別できる。 Micrologusが、Bernoの直接的なやり方での記譜された「不規則な」チャントを分類する問題に取り組んでいないことは、驚くことではない。 しかし、彼の教科書では、表記法の問題に関する基本的な彼の好みが公開されている。 グイドがMicrologusを書いている時点でMusica enchiriadisを知っていたことの証明は、主に彼らのオルガヌムについての議論の類似性に基づいている。別の示唆に富む証拠は、グイドがモデルとしてMusica enchiriadisを利用したであろうEpistola de ignoto cantu の一節である。すなわち、グイドは、異なる音程でメロディーを開始したときに生じる旋法の変化を説明する。彼は、関連する議論でMusica enchiriadisの著者と同様、同じメロディー「Tu patris sempiterus es filius」を使用している。12 グイドの音程関係についての議論は、Musica enchiriadisの論文のそれに従っていないが、それは階層的スキームを設定するのと同じ傾向を明らかにしている。第7章では、「4つの旋法によるピッチの「アフィニタス」(四度下または五度上の音との同種性)について」で、Guidoはまず、旋法終止音とその五度上(あるいは四度下)との間の関係を解明している。 オクターブ関係は、旋法階層におけるその支配的立場が確認されている第9章で初めて言及されている。 Dとaにおいてはしかし、同じ旋法であり、我々は、非常にしばしば、同じ歌を歌い始め、終わる。私は”非常にしばしば”と言うが、”必ずしも常に”ではない。なぜなら、octaveにまで拡大すると、例外が出てくるから。 なぜグイドは、例外の方を重視するのか。どうやら、関連する2つの考慮事項が関係している。 1つは実用的なこと。通常の終止音の五度上に位置する音程は、代替の旋法siteを提供する。グイドは彼の理論に特有の使用法を見つけている。 もう1つは、音調システムの構成の解釈を提供するというより広い意図である。 Hucbaldは、音階が旋法を具現化する方法を示すことによって、後者のタスクの最初のステップを実行した。それは、終止音のテトラコードに従って分割可能であった。 グイドはこの発見を拡張したが、テトラコードで音階を分析したことはない。むしろ彼は、終止音と五度のピッチの間の類似性を認識した。両方とも六度の範囲内の同じ全音-半音の動きに囲まれているからである。グイドの理論ではオクターブの関係性が際立っているため、終止音の四度下にあるピッチにも注意を向けたのは当然のことである。 p338 したがって、関連するピッチは、protusの場合はA Dとa、deuterus場合はB E 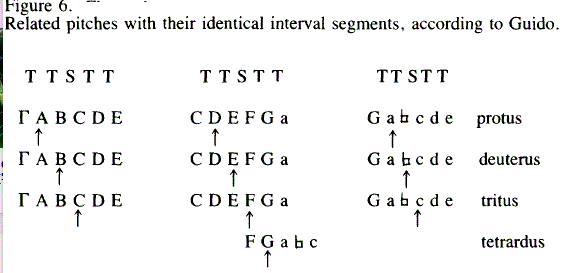 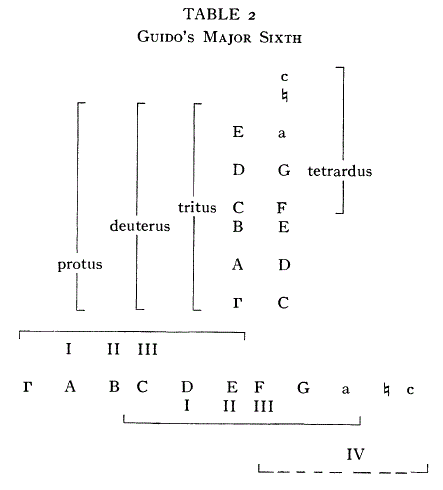 グイドは、音階が、六度の範囲にわたるこれらの同一のセグメントを見つけることができるように構築されていることを認識していた。 Richard Crocker が指摘したように、グイドの直後に書かれたBerno of Reichenau派のメンバーであるHermannus Contractusも、6音符のセグメントについて議論をした。 しかしながら、Hermannusは彼の結論を、テトラコードに関して表現した。すなわち、すべてのテトラコードの両端に音を加えて、音程についてはヘクサコードのように扱われた(Richard Crocker Hermann's Major Sixth p19)。there is still agreement of interval. したがって、それぞれのテトラコード内に同様に配置されたトーンは、六度の範囲内で互いにアフィニティがある。 グイドはA Dとaを、終止音の五度上と四度下のピッチ関係に言及して結び付けていたが、Hermannusは単にテトラコードの用語を要求した。 Guido と Hermannus の両者はその表現は異なったが、同じ目標を達成し、音階がどのように構築されるかをさらに理解した。 グイドは、五度で区切られたピッチのアフィニティを強調することで、彼の発見に注意を向けることができた。 彼のこのいくらか投機的な探求と実践の統合は、図6の同様に構成されたセグメントに旋法的な重要性を帰していることに反映されている。 彼は、tetrardusを除く各旋法(第1~6旋法)には、六度によって定義される旋律的な動きの特徴的なパターンがあると述べている。 第1旋法パターン(modus vocum は、ピッチがT下降し、TSTT上昇するときに発生します。AやDがそうであるように。15 このように彼は、他のメロディーから区別できるようにするために、 protus のメロディーは、その終止音のあたり(modus vocum)のこの特定の動きのパターンを必要とすると示唆している。 グイドの熱心な追随者であるリエージュの匿名の解説者は、彼の第7章の傍注で、そのような解釈を強調した。 p339 下降または上昇のこれらの特性は、最初に第2旋法と他旋法を相互に区別するため、特にフレーズの終わりまたは曲自体の終わりに観察される必要があることを知っておく必要があります。 そのためにそれは、自然の特性に応じて、旋法終止音に対して上昇または下降します。 この進行パターンをその終止音とする旋法についてのグイドの定義は、彼の先行者または同時代人のそれと一致していない。 Dialogus de musicaの作者は、メロディーの旋法がその終止音によって判断されることを最初に明確に述べているが、グィドは、それが決定的な役割をする終止音の周りの特徴的な動きのパターンであることを示唆しているだけである。11世紀の終わり近くに、修道士Johannes Affligemensisは、より明確に書いている。 <修道士Johannes Affligemensis> ・・・たとえば、Dはprotusの終止音であり、a acutaと一致している。実際両者は、Tで下がり、TSと上がっていく。17 修道士Johannes AffligemensisのDやaへの一般的なパターンは、グイドのそれのような、六度ではない。修道士Johannes Affligemensisがグイドのmodus vocumの概念を理解していなかったと示唆するのはtemptingであるが、修道士Johannes Affligemensisは理解したがそれを示さなかった可能性が高いことを認めなければならない。 その代わりに、修道士Johannes Affligemensisは、旋法を区別するために必要な最も基本的な旋律の動きを概説した。後で中世の作家が各旋法の特徴的な旋律の動きを詳しく説明するのに悩むとき、彼らは最小限の量を引用する修道士Johannes Affligemensisのアプローチを採用している。(図7) 18 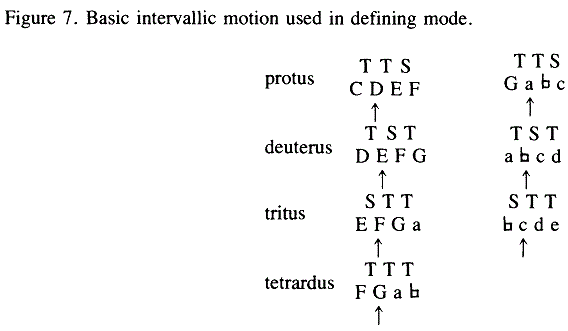 <♭記号を忌避したグィド:移調の萌芽> 実際、グィドにおける六度と旋法的アイデンティティとの結合は、全音階的調性システム(五度離れたある種の6音符セグメントのアフィニタス)の特徴を反映して作られた企てなのである。 ここで、これらの旋法セグメントのグイドの特異な使用(図6)について考えてみたい。彼は、所与のチャントからb♭を消去するための記譜のデヴァイスとしてそれらを高く評価した! Micrologusの第8章からの一節は、この点について啓蒙的である。 私たちは、Fまたはfが、高くても低くても、どちらかというとかなり広範に生じるような曲で主にb♭を使用する。 b♭は特定の混乱とtransformation(変形)を生み出すように思われる。b♭を使用することによって、Gはprotusとして、aはdeuterusとして響くが、b♭自体はtritusとして響く。 その結果、多くの人は言及していないが、二次的な もしもそれがD E Fの次に上がって、TTSを必要とし、あるいはD E Fの次に下がってTTを必要とするような種類のメロディセグメントである場合には、D E Fの代わりにa D E Fとa Epistola de ignoto cantuで、彼は、aの次のb♭とb ・・・すなわち、最初のaは、それに半音が続けば、それはprotusからdeuterusとなる。しかしもしも、2つ以上の旋法に属する1つの音程が許容され得るならば、これは、明確な境界線によって制限されず、制限なしでマークされているように見えます。 理論的には存在しない低B♭をも含め、あらゆるb♭を拒否して、Guidoは明らかに、すべての音程が単一の旋法的アイデンティティ、すなわちD protus、E deuterus、F tritus、G tetrardus、a protus、 したがって、dにはすでにprotusのアイデンティティがあるため、Gに関連した音符としてdを省略した彼の理由は明らかである。 Micrologusからの引用では、Guidoはb♭を否定するための2つの解決を提供している。 p341 最初の解決法は、b♭を含むフレーズを一全音高く移調することである。すなわち、F G a b♭→G a 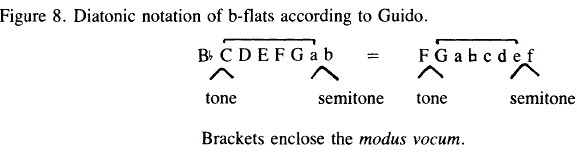 Bernoは、旋法核内でのさまざまな旋律の動きを可能にするための二者択一的なポジションを重視し、b♭とb しかし、Guidoは、旋法核外の柔軟性を容認するために、明らかに、b こうした特殊環境において、グィドはb♭の記譜法への嫌悪のみを考えたのであり、その耳の効果においてではなかった。 一方彼は、これらの音程が終止音として機能する時において考えるならば、b♭がGをprotusとすること、aをdeuterusとすることに注意している。すでに見たように、グィドは、それぞれの音程が、その周囲の全音階的動きで定義づけられた単独の旋法連関を持つことを要求したと思われる。音程aは、Gからeへの6音符の全音階セグメントに位置しているが、protusの性格を保持している。b♭と音程aとを旋法核内部で結びつけることは、グィドによれば望ましくないことだが、それをdeuterus(第3,4旋法)にtransform(変形)することである。 グイドが、こうした四度上への移調に積極的ではなかったことは、ほとんど疑いない。b♭が原因となったtransformation(変形)に関する彼の声明は、十分証明されているが、彼はまた、音程関係を、彼の階層的スキームの最終列上の四度に配置している。 Micrologusの第8章で、グィドは、両者共にTTSで下降する、同じようなメロディ進行を持ちながら、Eとaとは、”別ものである”としている。グィドは、aからの上昇でb♭を許容することによる類似性を主張せず、b♭の統合的な使用なしでは、四度への移調は実行不可能だっただろう。 <Guido、Berno後の世代> ゆえに、11世紀初期において、二人の影響力ある著者たちは、音楽について、移調における多様な見方を表現した。グィドは、音階の全音階的セグメント間の移調のみ裁可したのに対して、Bernoは、b♭を使用する移調を同等に扱った。次に、理論と実践の両方で表現されているように、移調に関する次の世代の見解に目を向けたい。 一般に、スクライブたちはb-flatを扱う際に、Guidoが推奨するアプローチほど厳格なアプローチは取らない。 多くの11世紀と12世紀の写本では、チャントが最終レベルで表記されている場合、通常は三全音が発生する場所にbフラットが存在している。 しかし、12世紀の写本であるLucca, Bibl. Cap. Codex 601は、そのようなbフラットを消去するようなGuidoの指示に従っている。 p342 ルッカの560ページでは、わずか32のフラットしか現れないことに注意されたい。 bフラットの表記を回避するために、チャントの一部またはすべてを移調した例を見つけることができる(例9参照)。ただ、メロディーをbフラットに変更した例はさらに多くあるが。 Guidoのb-flatsに対する嫌悪は、 1140〜1147年頃のチャントの改革と関連して、シトー派修道会によっても引き継がれた。おそらくGuy d'Euの作品である、Prefatioseu tractatus de cantuにおいては、改革の主な教義のひとつが述べられている。 チャントは、b♭なしで記譜ができるのであれば、それを伴うべきではない。 シトー派のアンティフォン集の研究は、b♭を消去するために使われた五度上への移調を明らかにしている。 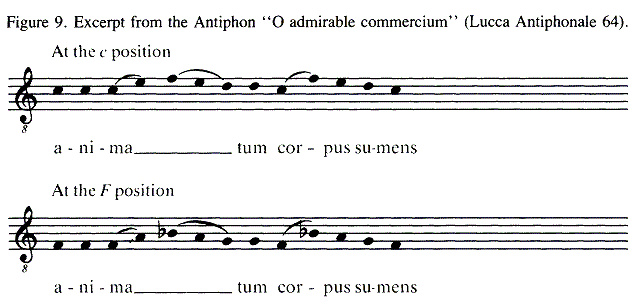 上記の四度上への移調に関しては、グイドの直接の後継者のほとんどが、それがチャンドブックで使用されていることを認めたとしても、あまり承認はしなかった。 明らかにリエージュ派と関係がある作家の1つのグループは、b-flatの「transformation(変形)」効果への言及の影響を非常に強く受け、「移調」と「transformation(変形)」の相対的なメリットについて理論的な論争を巻き起こした。 23 これらの作家たちの最初は、前に言及された(p338終わり)匿名の解説者である。旋法的アイデンティティとb-flatについての議論をするとき、彼はGuidoの言葉遣いに厳密に従うが、彼自身のチャントの例を提供している。 アンティフォン "'Urbs fortitudinis nostrae(L.U.p332)”は、その終止音のGのtetrardusとの関連を、(b♭を使って)一時的にprotusに変更している(下譜赤の部分)。 グイドのように、彼はtetrardus のmodus vocum をF G a 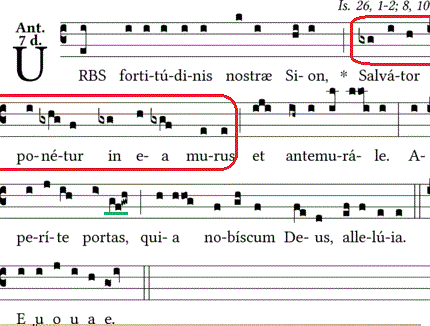 p343 もしもb♭が(チャント全体に)存在していたならば、それは、旋法と関連した全音階核内にあり、Gの特性がtransformation(変形)されていたことだろう。 "Urbs fortitudinis”の場合では、その多くのソースの調査においては、チャントがDからGへと移調されたのか、それともb♭が単にGレベルに加えられただけなのかという問題は、未解決のままである。http://cantus.uwaterloo.ca/chant/372367参照 24 24 "Urbs fortitudinis"は、旋法分類に厄介な問題を提示している。その最初に言及した理論家が、困難を明らかにしている。すなわち、Reginoはそれをモード1に割り当てる。Alia Musica は、モード1で始まりモード8で終了すると述べている。Odo of Arezzo のtonaryはそれをモード7に割り当てている。リエージュの匿名者のコメンタリーの最初では、チャントはGで始まり、bフラットを使用することにより、Gはprotusにtransform(変形)されると記述されている。 多くの作家が、このチャントの旋法的発展を追跡した。最も広範囲にわたる調査は、Jacobsthal のDie chromatische Alteration, pp. 198-205によって行われた。Steglich は、Quaestiones in musica, pp. 148-50,の彼の版について、さらにコメントを追加した。 Walther Lipphardt は、彼の版Der karolingische Tonar von Metz (Miinster, 1965), pp. 264-66で、さらに分析を加えた。 Lipphardtは、チャントがtetrardusのカデンツを持ち、この終止の旋法的優位性への関心がGまたはtetrardusレベルへの変化を促したとのJacobsthalの考えに同意しない。むしろ、彼はチャントがDで始まり、Dで終わるprotusを持っていたと信じている。そして、真ん中においてだけ、旋法は不調和となった。すなわち"portas"という歌詞部分に、メロディ形F♯EF♯Gがあった。これを表記上許容できるようにするために、聖歌はGに移動した。そこでは、F♯とF どちらの理論も証明することはできないが、どちらも終止音の動きに基づく線ぽぅてきアイデンティティが中世の音楽家たちの究極の関心事であったと主張しているようである。 ただし、この議論の観点から見ると、「Urbs fortitudinis」の重要性は、チャントの早い段階で、G上でのbフラットへのニーズがあったということである。 Dialogue論文以降、b-flatは(G終止音が)protusの性格を帯びないようにするために、G tetrardusから除外された。 むしろ、各旋法の終止音は、基本的な全音階的アイデンティティを維持していった。これは、Bemoなどのより広義の理論家でさえ、Dの代わりにbフラットのGを提案しない理由を説明するかもしれない。 いずれにせよ、匿名の解説者は、通常のtetrardusの終止音以外のGの役割を受け入れることを頑なに拒否した多くの理論家のうちの最初の一人である。 この作者は、ちなみに、b♭を記譜することを拒否して移調された2つのチャントの名前を提供している。すなわち、ひとつは"O admirabile commercium"であり、それはb♭を小さく書き、もうひとつは "Haec dies"であり、これは低い位置のB♭である。 Lucca 写本は、"O admirabile" (LA 64)の移調された版を含み、 Beneventan gradual, Bibl.Cap. Codex VI. 34 (GB 125)は"Haec dies." に対して同様である。 理論と実践を調和させるためのより大きな試みは、ライプツィヒ大学 Bibl. Codex 1492で発見された別の匿名の論文によってなされている。 Bibl。 分類整理のコンセプトに対する中世の趣味に従って、著者は移調とtransformation(変形)を区別しているが、さらなる細分化を通じて、可能性の連続性があり、いくつかは他のものより避けられることを示唆している。 最初に、彼はグィドからの引用によってtransformation(変形)を定義している。 ・・・transformation(変形)とは、Gがprotusとして響く時に、aがdeuterusとして響くことである。しかし、b♭はそれ自身、tritusとして響く。25 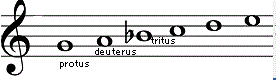 p344 それから彼は、それぞれのtransformation(変形)の例を挙げている。 protus chant on G, "Angelus domini nuntiavit"; deuterus chant on a, "Dum complerentur"; (L.U.p884)  tritus chant on b-flat, "Vox clamantis in deserto." (L.U.p1082) 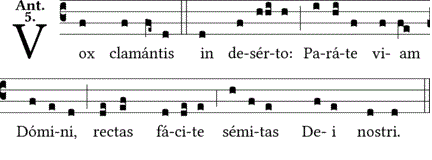 これらのアンティフォンの多くのソースは、D、E、Fで終わるprotus, deuterus, tritus としてそれぞれ分類している。26 3つはいずれも、表記された位置から移動する理由となる半音進行を含んでいない。 作者は、それらに単に四度高い記譜を認めているに過ぎない。それは、「まったく必要のない」transformation(変形)の形式である。 結果としてのb♭は、、著者の意見では、混乱を引き起こすだけである。 しかし、彼は別のタイプのtransformation(変形)を”必要に応じてもの”として、特徴づけている。 したがって、transoformationは、歌が規則的やり方での通常の終止音で終止しなかったり、そのequivocaに移調されなかった場合には、必要に応じては行われる。たとえば第4旋法のアンティフォン "Apud dominum"に見られるように。このタイプのtransformation(変形)では、言うまでもなく、b-flatは混乱を引き起こさない。 第4旋法のアンティフォン「Apud dominum misericordia」(L.U.p412)のいくつかの利用可能なソースは、末尾がaで、deuterusチャントとして分類されたバージョンでそれを保持している。これは、通常のprotusとの関連付けを失ったことを意味する。28 28 このバージョンを含むソースはAR 271、LU 412、AM 246、およびWA 33である。LA39はDファイナルで「Apud」を提示している。 そこは、移調されたバージョンはb 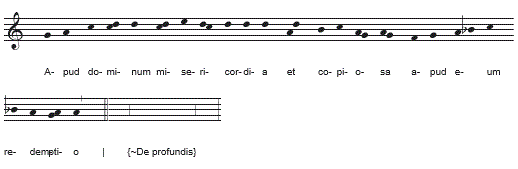 http://cantus.uwaterloo.ca/chant/228713 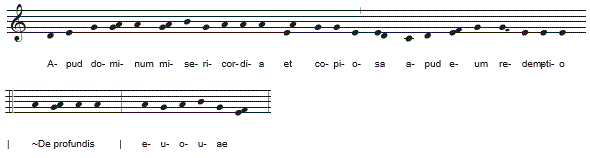 http://cantus.uwaterloo.ca/chant/253689 「Apud dominum」がEに移調された場合、 「Beatus servus」の場合と同様に、F 実際、彼はこれらの状況下では、四度上への移調を是認する。 ただし、こうしたtransformation(変形)の手順のラベル付けは、そのあたりの全音階的進行によって定義された単一の旋法的アイデンティティしか持たないことがあるグィドへの彼の究極の敬意を示している。 移調は、五度上へのメロディ素材のシフトに適用される用語を残している。 p345 第3の論文、Quaestiones in musicaは、ライプツィッヒの論文と同様のやり方で、移調とtransformation(変形)を併置している。しかし、Quaestiones in musicaの著者は、transformation(変形)に対する別の選択肢、すなわちemendation(修正)があることを、示唆している。 彼が言うには、2つのtetrardusチャント、"Si cognovissetis(L.U.p1465)" と”Salvator mundi,(L.U.p747)"は、終止レベルで記譜されたのであれば、Gに対して、F♯のinflectionを要求したはずである。 ひとつの解決法は、c(からの音列の)のtransformation(変形)をもたらす結果となる。すなわち、チャント全体が四度上に引き上げられ、FからGへの通常のinflectionは、b♭からcとなる。それゆえ(b♭が入ってくるために)、tritus(第6旋法)とcとの全音階的関連は失われる(結局、tetrardusになる)ことになる。 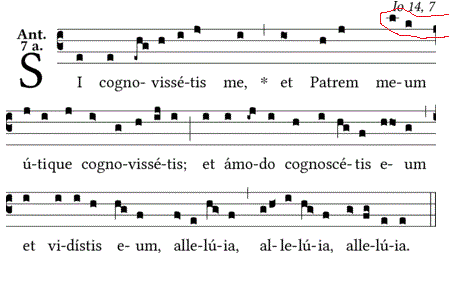 もうひとつの解決法はemendationで、単に、終止レベルにおいて、F♯がF 30 According to the author, "Si cognovissetis me" requires F-sharp at the words "et patrem meum" and "Salvator mundi" does likewise at "per crucem." In the named sources, all of which end on G, those positions use F-natural or another pitch. 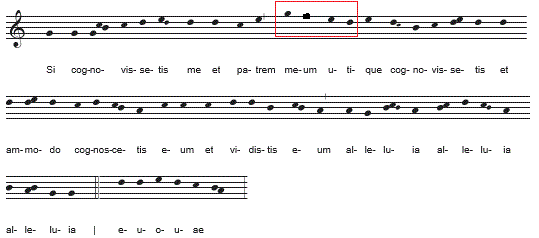 http://cantus.uwaterloo.ca/chant/256118 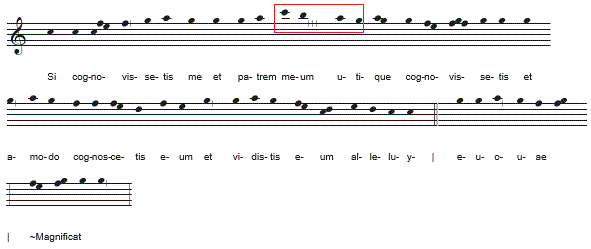 http://cantusindex.org/id/004879 別の11世紀後半の作者である修道士Johannes Affligemensisもまた、transformation(変形)に対して、emendationを好んでいる。特に"Beatus servus,"におけるGのinflectionとしてのF♯に言及し、(躊躇なくF♯はF Quaestionesから離れる前に、プレゼンテーションのもう1つのポイントは注目に値する。 ここで、移調は、「意志による」、「必要性による」、およびその2つを組み合わせた3つの理由で発生すると言われている。 「意志」とはbフラットを消去しようとすることを意味し、「必要性」は主に他の半音階音の回避を意味する。 「意志と必要性」は、メロディーがしばらくの間その領域で動き回った後、チャントの終わりをより高音域に移調するという、ややあいまいな用語である。32 32 Quaestionesのリファレンス(Steglich、p。53)は、関連する終止音で終了する3つのprotusのチャントについての数世代前のBernoの説明に一致するようである。その3つのprotusのチャントは、 responsories "Factum est dum tolleret"と、"Terribilis est" と communion "Cantabo Domino." の3つである。 "Factum est dum tolleret" はLA 272 と WA 167にあり、両写本は、メロディの最後はDとなっている。どちらの版も、終止音の十度上に上昇するメロディについてのBernoの記述とは一致しない。なぜなら、両写本の音域は、C から cまでだからである。 Cambrai, Bibliotheque municipale C 38 (40), fols. 189-189vでは、 "Terribilis est"は、"porta coeli"という言葉から、aでの終止へとより高い音域でずっと動く版で見出される。LR 235とWA 317での版は、「porta coeli」という単語でaへと移動するが、「vere」のシラブル「ve-」でのメリスマの間にDに戻り、その音程で終止する。 Bamberg, Staatsbibliothek lit. 25, fol. 122v は、 "porta coeli"という言葉においても、aroundDで動くが、それゆえ、他のソースよりも五度低くなる。 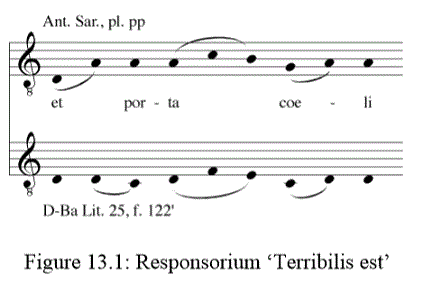 Machaut‘s Balade Ploures dames (B32) in the Light of Real Modality p193 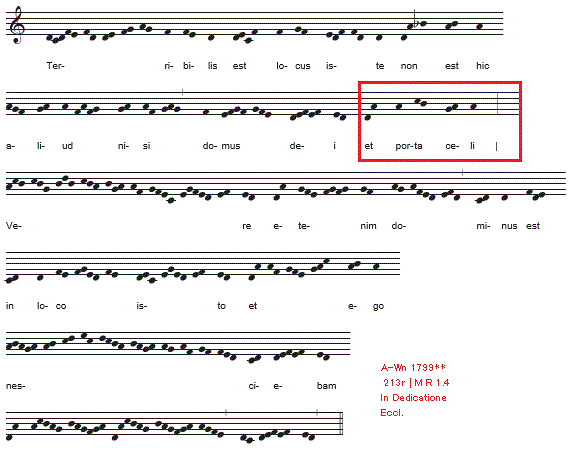 http://cantusindex.org/id/007763 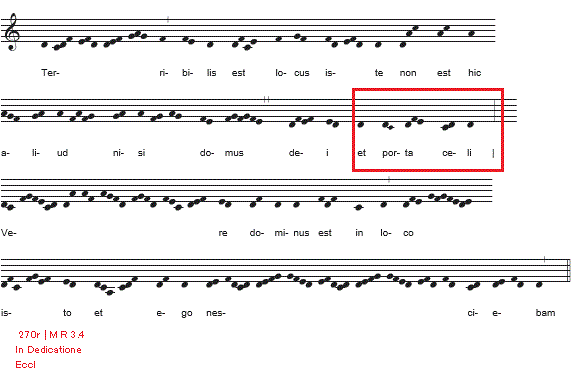 http://cantusindex.org/id/007763 私たちの目的では、「意志」のカテゴリが重要である。なぜなら、この著者が、b-flatが自動的に適用されるのを回避するためのGuidoのやり方を考慮しなかったことを明らかにしているからである。 <ヘクサコードとの関係> ここで、旋法的アイデンティティに関する13世紀の議論に移りたい。 ほとんどすべての理論家は、旋法終止音をD E F Gとしており、終止音でのメロディの動きを特定することは容易である。(それがグィドの六度であろうが、修道士Johannes Affligemensisの最小の四度音程であろうが)。こうした説明は、13世紀の根本的に重要な構造であるhexachordへの言及に置き換えられた。 p346 Magister Lambertusは、13世紀の第3四半世紀に、以下のように主張している。 旋法の最終シラブルはre、mi、fa、solである。 最終音はD,E、F、Gとなる。 グイドはmodi vocumを六度の範囲内の一連の上昇と下降として説明していた。ヘクサコードシラブルへの言及は同じ結論に達していた。すなわち、protusとreを結合することで十分であった。なぜなら、そのすべての設定utからlaに対して、reの位置は、Guidoが説明した上昇と下降の正確なパターンを可能にしたからである。それは、T(re→ut)下降とTSTT上昇(re mi fa sol la)である。グイド自身はヘクサコードシラブルをこのように適用したことはなく、聖歌隊の少年たちに新しい聖歌を教えるための教育的ツールとしてのみ考えていたようである。 ただし、modus vocum についての彼の理論には、後のヘキサコード理論の根底にあるのと同じ前提が本質となっている。すなわち、TとSの特定の配置は、音階の複数の場所にある。34 全体的なヘキサコードシステムでは、この「移調可能"ユニットは7回発生する(図10)。 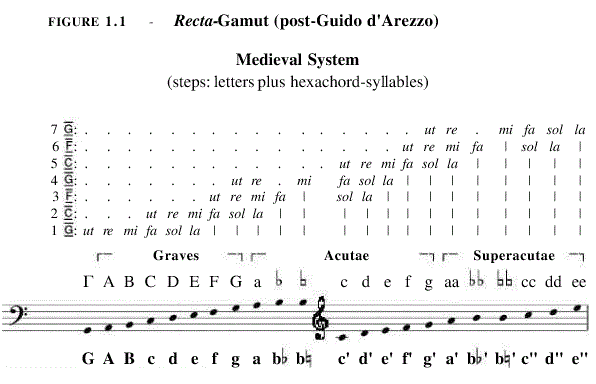 ただし、Guidoの場合、旋法核(アフィニタスで共通する6度の音程関係)の2つの主要サイト、全音セグメントCからaと全音セグメントΓからE(Gからe)のみが存在する。それぞれが後の「自然」および「硬い」ヘキサコードとなる。グイドのbフラットへの嫌悪は、彼が3番目のサイト、セグメントFからd(その後の「やわらかい」ヘキサコード)を認識することを明らかに妨げた。 グィドの次世代では、Wilhelm of Hirsau が、理論的に、Fからdへのセグメントを認めていた。Berno of Reichenau派のメンバーであるHermannusのテトラコード分割にしたがって、Wilhelm of Hirsau は、両端に一全音が加わったsynemmenon テトラコードF G a ♭ c d.としてのセグメントを記述した。 しかし、それを実行可能な旋法的配置としては拒否した。「その内部にあまり規則的ではないsynemenon(b♭)があるために」。Wilhelm of Hirsauが、この議論に進む前に、グイドのmodi vocumに関する章をパラフレーズしたことは重要である。35 先に示唆したように、13世紀は、ソルミゼーションに伴うプロセスを持った完全なヘキサコードシステムの確立をしていた。 音楽理論と実践の事実上のすべての側面は、ヘキサコードの用語で表現されている。 旋法終止音がシラブルにリンクされている(特に自然hexachord内で)というMagister Lambertusのステートメントから判断すると、旋法も例外ではない。そうすると、以下のように尋ねざるを得ない。理論家たちは、旋法とシラブルのこの関連付けを、音階内のすべての7つのヘクサコードに拡張したのだろうか?と。 もしそうなら、Bernoが以前に裁可した旋法配置は、通常の終止音より四度上に位置しており、理論的には正当化される。 aは旋法的な意味合いで、やわらかいヘクサコードでのmiを意味するために、deuterus メロディーはa上のもので終止することになろう。 p347 Magister Lambertus とJerome of Moraviaの著作にはそのような実践のヒントが含まれているが、そのような音階の理解を明確に表現しているのは、14世紀の有名な保守派Jacques de Liegeである。 「不規則なチャントのモードについて」というタイトルの彼のSpeculum musicaeの章で、彼は、どのチャントにも、その旋法に割り当てられたシラブルの1つで「最後に適切に終了する場合」、旋法を割り当てることができると述べている。For protus, the syllable is re, for deuterus, mi ,for tritus, fa or ut, and for tetrardus, sol or ut. p348 Jacques de Liegeは言う。 したがって、旋法の命名は、4つの最終音符[D E F G]からではなく、上記の言及されたシラブルからより一般的に行われているようです。なぜなら、これらのシラブルは、終止音のテトラコードに対してだけではなく、他にも見られるからです。 実際、それら(のシラブル)は音階に7回含まれているため、曲は、これらの4つの適切な最終音符に限定される以外の場所で終止できます。 (斜体は引用者) ここで我々は、旋法的終止音が7つのヘキサコードのいずれかにあるという最初の明示的なステートメントを目にする。 reとの関連付けを介して、protusは、自然のヘクサコードにおいてはDでの最終音、硬いヘクサコードにおいてはaでの最終音、およびやわらかいヘクサコードにおいてはGでの最終音となる。 Jacques de Liegeは、旋法配置が通常の配置の四度上になるための手段として、やわらかいヘキサコードを使用した。 Jacquesがどのように、彼がこの配置を、自動的に「transformation(変形)」の1つとなるような統合されたb-flatとともには考えていない、ということを間接的に彼の読者に知らしめているかに、注目されたい。 ただし、「適切な場合」と言ったのは、bフラットを通してG gravisで終了するが、それが適切ではないような特定の曲があるためです。・・・そしてそれは、bフラットを使った最終音程で歪められた他の特定のアンティフォンや応唱でも同様です。 この流れにおいて、彼はまた、Quaestionesの著者Johannes Affligemensisがb-flatを使用することでprotusにtransformation(変形)されたG上のtetrardus(第7,8旋法)チャントとしての、アンティフォン「Magnus sanctus Paulus」を引用している。 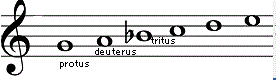 ソースでは、一部のスクライブが、三全音を修正するために2カ所にbフラットを追加している(図11)http://cantusindex.org/id/003683参照。 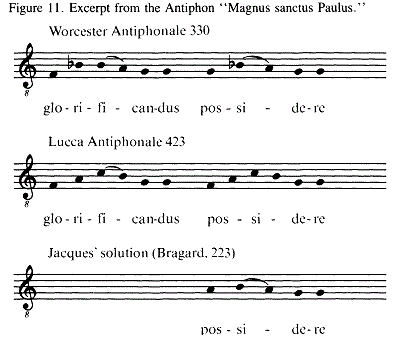 このアンティフォンがD上でのprotusとされ、その後Gに移調されたことを示唆する証拠はない。したがって、 "Magnus sanctus"でのtransformation(変形)へのJohannes AffligemensisとJacques de Liegeの両著者の言及は、チャントのそのままのG上の位置でのbフラットの追加はそのtetrardusの旋法的性格を歪めることを意味する、と解釈する必要がある。 このチャントの例に加えて、旋法の7回の位置に関する声明は、Jacques de Liegeがb♭のtransformation(変形)効果に関するグイドの声明を新たに理解したことを示唆している。 p349 チャントに追加されたb♭は、全音と半音の通常の配置を歪めることによって、旋法をtransformation(変形)する。しかし、移調の産物としてのb♭は、全音階的な音調システムをtransformation(変形)するのではなく、むしろそれを(半音を含めた領域へと)拡大するのである。 Jacques de Liegeの理論には、グイドの影響力のある著作によって促されたb-flatをめぐるこの論争の頂点が見える。 Jacques de Liegeは、メロディーをb-flatを伴って表記するための理論的な正当性を提供した。この説明は、皮肉なことではあるが、グイド自身が解明した6音符のセグメントに関連する概念に基づいたものである。 しかし、Jacques de Liegeの声明は、理論家による移調のより広範な定義の普遍的な採用を意味しない。やわらかいhexachordは、この発展における単なる仲介手段であった。 16世紀に入ってからのオクターブ理論への執心を通してやっと、変化した音調に依存した移調の概念が完全に受け入れられたのである。 しかし、それは音楽理論の歴史における別の章となる。 |