| p42 (まとめ) 私はmusica fictaの外側の限界、臨時記号という手段によって音程ステップをinflectionすることができない限界を確立しようと試みてきた。そして私は、そのような限界は、我々の時代の音楽家たちが音階について考えた用語によって制御されることを示唆した。 音階が、グイドの手のそれ(音階)であると考えられること、つまり、音楽家が主にシラブル( Boenの14世紀半ばのこの問題に関する独立した議論は、彼の前任者と同時代の人々が実際にそのような仮定を立てたことを確認した。たとえ、staff notationについての彼自身の考えは、2つではなく1つの臨時記号がつけられたどのような音符をも許容したとしても。 この伝統的なシラブル指向の見方は、音階を1オクターブ内で16を超えないピッチに制限し、この論文で議論される時代の終わりまで、グイドの手自身同様に、その活力を保持したという多くの兆候を見てきた。 そうでなければ、例えば、 ProsdocimusやUgolino の、彼らが提示したa♯の音程ステップの明確な不快感のような現象、。あるいは、Spataroの、del Lagoの、そしてAaronの、cとfを本当に♭化にし、a、 16ステップの音階が基本的な音楽導入の定番であったことは、たとえば、Martin Agricolaの1539年のRudimenta musiicesで見ることができる。 そこでは、C,F,G、d上のmi 少なくとも15世紀の初め以来、16ステップの音程の限界は、最低音だけでなく、すべてのオクターブに積極的にA♯(上の方のオクターブではa♯).を導入することによって挑戦されてきた。結果として生じた17ステップの音程は、ProsdocimusからAaronまでの理論家によって提唱された。 a♯の導入は、それまで音階を制限してきたバリアを破った。なぜならそれは、臨時記号の主な機能はinflectionすることであり、シラブルを示す機能は派生または副次的であることを暗示していたためである。 本当にaを♯化できるならば、他のステップもまた実際に♯化したり♭化したり、あるいは臨時記号を2つ並べることができない理由はもはやなかった。厳密にいえば、臨時記号が考えられないような制限はなくなった。今後、musica fictaの潜在的な無制限の世界は、実践的考慮のみによって制限されることになったのである。 15世紀の間、17ステップの音階を超える提案はなされなかったことは明らかである。A♯のある17ステップは、最低オクターブにおけるその合理的外観との類似のおかげで、(a♯を伴って)2つのより高いオクターブ内に登場した。 新しい音程ステップは、”黒鍵”の音程ステップと同等性あるものとしての♭やダブル♭の考えを、そして、グイド手とそのシラブルに関して、さらにはモノコードまたはキーボードに関して、より全音階的要素が少なくする考えを促進させた。 p43 キーボードを考慮したこのコントロールイメージは、順に、音階の制限を17ステップのみとし、その制限は、明らかに、すべての”白鍵”ステップに、上下の全音階的半音を置きたいという欲求から明らかに生じたものである。 すなわち、それらをmi 音階についてのイメージングや思考において、グイドの手についてのコントロールイメージや用語法からキーボードのそれへの変化は、15世紀の多くの理論的テキストでは、あきらかである。しかしそれは、Hothbyの著作で最も明確で影響力のある表現に達している。 彼の音階についての考え方は、次の世紀の初めにスパタロを導き、スパタロの調停を通じて、アーロンも導くこととなった。 実用的な音楽の音階が我々の時代に考えられる最大限の状態に到達するためには、2つの課題が残っていた。すなわち、二重臨時記号の需要と同様に、①cとf上の積極的な♭の受容と、②mi これらの課題は、臨時記号の主な機能が、ステップのシラブルを示すことではなくinflectionすることであると仮定することに加えて、キーボードではなく譜表記譜の観点から音階について考え始めることを前提としていた。 これらの課題は、両方ともウィラートの「デュオ」で提案され、1520年代と1530年代に、del La go と AaronとのSpataroの共同において、理論的に詳述された。1540年代のAaronの出版も同様であった。 3人の理論家全員が、21ステップの音階(すべての音符を♭化および♯化できる)が可能であることを理解していたが、Spataroのみが(おそらく、本当の確信からではなく議論のために)それが実践できると主張した。 他の2人は、ピタゴラスの音律システムの前提条件内で使用する場合、そこで生じた問題のために実際にそれを拒否した。 そして、ウィラールトの暗黙のダブルフラットは、スパタロ(それらを議論する3人のうちの唯一の1人)にとっては(可能であると)考えられ得るものとなった。彼は、ピタゴラス音律システムではそれらも実行不可能だと考えていたが。 このように、最初はグイドの手による、それからキーボードによる(訳注;原文の”than”は”then”の誤りと思われる)音階の拡大の上で課せられたバリアの破壊とともに、潜在的な臨時記号の無制限な増殖に対する新しい実践的なチェックが確立された。 こうした実践的なチェックによって、16世紀半ばには、17ステップの音階が、音楽的実践の最大限可能な音階となった。たとえ追加的ステップが時代を先んじる理論家において考えられたものであっても。そして、ヴィラールトの”duo"のような、別の意味合いによる音楽理論の継続として理解されるべきであるような作品における実験的なものであっても。 p44 musica fictaの内容に関する別の見方は、最近、マーガレット・ベントの「Diatonic Ficta」に関する想像力豊かで重要な論文で発表された176。 ベントは、「声楽的に考えられ、対位法に基づいたポリフォニーに」関連した音楽家によって「14世紀から16世紀にかけて、ピッチと呼ばれたものが、どのように構想されたのか」を説明する仮説を提示した。そして、彼らのピッチについての概念は、根本的に相対的である、つまり、与えられたピッチの定義は固定ピッチ標準から完全に独立しており、ピッチの間隔のみに依存している、と主張した。 (不必要な誤解を避けるために、読者はこの議論を通して、本書で次の用語が使用される特定の感覚に留意する必要がある。「ステップ」は絶対ではなく相対的な用語で定義されるピッチである。それは、音階の他のステップへの相対である。;「frequency」は、ピッチ標準に関連して定義されたピッチである。「ピッチ」はステップまたはfrequencyのいずれかをカバーする一般的な用語である) さて、ピッチの相対的な概念の考え方には、弱いバージョンと強いバージョンの2つのバージョンがある。弱いバージョンでは、音楽家が使用するステップのシステムが絶対的ピッチ標準から独立している、つまり、そのような標準に関連してより高くまたはより低く調整しても影響を受けないということだけが主張される。我々の時代の(そしてその後ずっと)音楽家たちは、この意味で相対的なものとして使用した音階のステップを疑うことはほとんどないであろう。 私が知っている限りでは、これは長い間、音楽学者の間で一般に受け入れられている見解であった。Bentはしかし、ピッチの相対的な概念のこの弱いバージョンに満足しておらず、さらに、音楽家たちのステップへの理解が、絶対的なピッチ標準だけでなく、歌手らによる作曲の始めに確立された相対的な標準にも依存していなかったと主張する。 ステップのアイデンティティ、定義、理解は、彼女の見解では、そのすぐ近くのステップとの関係にのみ依存し、実際のfrequencyが、作品の演奏にしたがって変化しても(たとえば、半音または2つ下に移動しても)影響を受けなかったことだろう。 または、同じ主張を異なって言うために、単一の作品の単一の演奏内で、同じステップが、異なったfrequenciesで表現された。 (ここでの意味合い、および以下の説明全体では、少なくとも半音の周波数差であり、累積的なcommaの適合による純粋なボーカルパフォーマンスのピッチの小さなスライドではない)。 それは、論文の真にオリジナルな貢献を構成し、ベントの仮説のエッセンスとして特定されねばならないピッチの相対主義の強いヴァージョンである。 論文にあったその他の重要な新しい考えのすべては(特に、ヴィラールトの"duo"への、そして、いわゆる「秘密の半音階的」レパートリーの主張する全音階的状態につながったその半音階についての理解は。器楽的なintabulationやそれらの声楽モデルの間の関係の見方。そして、音調の一貫性の概念)、この仮説に依存し、それとともにあった。 p45 Bentがその問題や彼女の議論の輝きを公式化したその大胆さや創造性を、賞賛せずにはいられない。それはちょうど、エドワード・E・ローウィンスキーの古典的なSecret Chromatic Art in the Netherlands Motet のように、間違いなく、私たちのトピックの歴史における本当に不可欠な介入の一つである。 彼女の仮説は、最も価値がある。なぜなら、中世後期のピッチの概念化を最大限の精度で考えることを私たちに強いるからである。しかし、私はそれが受け入れられないことを恐れていますstiiが受け入れられないことを恐れている。 声楽的なポリフォニーに関心を持っている我々の時代の音楽家たちが、ピッチについてどのように考えていたかについて私たちが知っているすべてのことは、彼らにとって、作曲の過程で遭遇するステップのアイデンティティが、すぐ周囲のステップとの関係だけでなく、作品の歌唱が始まってから聞いたステップとの関係にも依存していた。 元の記譜ではGで始まり、Gで終わるポリフォニー作品の声部の架空の例を見てみたい。しかし、我々のtranscriptionでは、Gで始まりG♭で終わる必要がある。なぜなら、従来の対位法規則のオペレーションにより、作品の途中のある時点で、半音だけピッチが低下するためである。 Bentによれば、我々現代人はそれに気づいており、おそらく作品の始まりと終わりの間のfrequencyの変化に悩まされている。なぜなら、ピッチの概念(ちょうど記譜法と同じ)は、作品の始まりで確立したピッチ標準に拠るからである。 初期の音楽家たちに対し、彼女は、ピッチの概念はそのような標準に依存していなかったため、frequencyの変化はまったく重要ではないと主張した。 我々が、曲の最初でのGのfrequencyが何であるかを知っていると仮定しても、絶対的ピッチGまたはG faは存在しない。 新しいGが、作曲家と歌手に共通する特性である対位法の規則の正しい一瞬一瞬によって確立された場合、もはや歌手は、Gの元のfrequencyとの関係で、彼が、一連の proportion関係を適用することを必要とした曲の始めに、semibreveの拍の元の音価が何であったかを覚えている必要がある以上に、自分がどこにいたかを追跡する必要がなくなる。 同様に、Obrechtの例の議論では、Bentは、1つの作品内の ‘ frequency stability” の仮定のみが、Fで作品を開始し、F♭で終了しないでいいようにするということを正しく指摘している。 ただし、単一の作品内の ‘ frequency stability”の仮定が我々だけのものであるかどうかは疑問である。 有能な初期の音楽家は、我々の架空の例の最後にあるGのfrequencyが最初のものとは異なっていたという事実を完全に認識していただけでなく、さらに重要なことに、彼はまた、2つのGについて、2つの異なるステップとして考えていたことだろう。 Bentの説明は、2つの誤解に依存している。 混乱の原因の1つは、上記の第1章で説明したように、初期の音楽家にとって、 '' G(またはその他の文字名)はステップのフルネームではなく、単に ”ステップに対する位置(lucus)の名前であるということを常に念頭に置いていないことにある。 p46 架空の例の最初のステップはGだけではなく、G-sol(または内容に応じてG-reまたはG・ut)であると考えられるが、最後のステップはG- fa(または、いずれにせよ、最初のものとは異なるヘキサコードに属するステップとして)となることが考えられる。 ベントの仮説がそうであったように、最後のステップのアイデンティティが、その直前の先行音(半音階的半音によるfrequencyの低下後に発生するステップのみ)のみに依存する場合、初期の音楽家らは、このステップをG- faとして、最初のGとは異なるヘキサコードに属するものとして認識する理由は、特になかっただろう。 しかし、初期の音楽家らがどのようにステップをソルミゼーションし、ステップについて考えたかについて我々が学んだことは、彼らが実際に、最後のステップがG-faであると考えていたことを疑う余地を残さない。(またはいずれの場合でも、最初のGのヘクサコードとは異なるヘクサコードからのシラブルが割り当てられたことだろう)。 確かに、歌手らは、元のステップに関連して、自分がどこにいたかを追跡する必要はないが、ソルミゼーションやmutatioの規則の正しい一瞬一瞬は、自動的に、最後のピッチが最初のピッチとは異なるfrequencyを持つだけでなく、異なるステップになることを確かめたことだろう。 つまり、歌手らにとって、最後のGの名前とアイデンティティは、その名前や、歌われたステップすべてのアイデンティティや、作品の初めから取られた、すべてのヘクサコードやmutatioに依存していたのである。そして、これは、彼らのピッチの理解が、絶対的なピッチ標準から独立しており、作品の演奏開始時に確立された標準に依存していたことを示している。 確かに、単一の作品の単一の演奏内で、同じfrequencyが異なるステップを表すことはできるが、逆は難しい。すなわち、同一のステップ(つまり、同じシラブル、同じヘキサコードと同じ場所を共有するステップ)を異なるfrequencyで表現することはできない。 混乱の2番目の原因は、Bentが、歌手のメロディーの演奏とそれについての彼の理解を混合させていることにある。in her deriving conclusions concerning the singer's understanding of the music from his way of reading it. 彼女は、もちろん、歌手のパートを解釈する際に、Gの元のfrequencyに関連して、歌手がどこにいるかを追跡する必要がないとの主張を、完全に正当化している。 彼がしなければならないことは、記譜法と作曲規則の要求に応じて、連続した音程を取得することだけなのである。 しかし、彼女の仮説は、声楽パートがどのように解釋されたのかについてだけではない。それはまた、我々がピッチと呼ぶものが、どのように概念化されたのか、についてでもある。すなわち、音楽家らは、ピッチについて、どのように考えていたのか、ということである。 さて、我々の想像上の例の歌手は、彼のパートをまったく機械的に解釋していることだろう。ひとつの正しいピッチから次に向かうことに注意して。 そして、我々が知るように、歌手はおそらく、彼のリハーサルにおいて、ソルミゼーションシラブルさえ使わなかったことだろう。しかしたとえば、彼が、自分が歌った最初と最後のステップが何なのか、と尋ねられれば、彼はそれぞれをG-solやG-faであると読んで、それらが異なった2つのシラブルであると考えたことだろう。 そしてこれは、すでに見てきたように、ステップについての彼の理解(解釈とは反対に)が、作品の歌唱が始まってからすでに聞かれていたステップとの関係とは独立であったことを示しているのである。 p47 ヴィラールトの「duo」(Bentの論文の重要な例)は同じ結論を示している。ここで、再び、ベントは、テノール声部を正しく読み取るために、歌手が記譜法と、不完全な四度と五度のメロディーの跳躍(訳注;三全音のこと)を禁止する基本的な規則に従うだけでよいことを、正しく観察している。 そして、再び、彼女は声部を解釋こととそれを理解することの違いを失念している。上記の想像上の例のように、ウィラートの「デュオ」では、テノール声部の歌手は、最初に使用された場合に、Eが持っていた元のfrequencyに関連して、最後のEを歌うときに自分がどこにいるかを追跡する必要はない。 しかし、もし彼が音楽を歌うだけでなく、それを理解したいなら、彼は最後のE-faが、最初のE-miまたはE-laからは非常に異なるピッチであることを理解しなければならない。そして彼は、それがどれほど違うかを正確に知っていなければならない。つまり、彼は自分がどこにいるかを追跡しなければならない。そうでなければ、テノール声部の最後のEが、ソプラノの終止音であるdよりも完全なオクターブ下に聞こえるように意図されたウィラールトの逆説的な構図のすべてのポイントを見逃してしまうだろう。 ベントの仮説が正しければ、ウィラートの歌手は彼の作品を読むことができるかもしれないが、彼自身はそれを書く理由がない。 さらに我々は、我々の時代の声楽的なポリフォニーがどのように歌われたかを知りたいとのことのために、それがどのように理解されたのかを気にする必要はないという幻想の下にあるべきではない。 実際、少なくとも一部のケースでは、理解は、演奏に直接影響する必要がある。上記のObrechtの「Kyrie」に対するBentの解決は、(我々の時代での)F♭、つまり、作品を通して歌われたFよりも半音階的半音分低いF-faで終わることを含むという歌手の理解は、、疑う余地なく、この解決、あるいは別の解決、(我々の時代での)F、すなわち、frequencyが変わらないF-faに従うかどうかの選択に影響することだろう。 彼らが(オブレヒトの時代の歌手たちがもっともよく信じていたように)、veraのF-fa-utの下の半音階的半音低いfictaのF♭が、実際に可能であったことの限界を超えていることを信じていれば、彼らはより過激ではない解決策を選んだことであろう。 さらに、ベントの仮説の下では、上記の多くの現象(特に、音階に限界があることを示す初期理論の特徴)が理解不能になることに注意されたい。 たとえば、そうしたことは、なぜSpataroらが、♭化されたcとf、そして♯化されたa, そして我々は、モノコードで示された考えとしてのあらゆる現象を無視することはできず、それゆえに、声楽的ポリフォニーのスケールについて、見当違いの存在となっている。逆に、前述した問題や音階はははっきりと、グイドの手や声楽的ポリフォニーの文字やシラブルで議論されている。 初期の声楽的ポリフォニーについて考える時、あらゆる考慮は、(ひとつの作品以上によって共有された絶対的なピッチ標準に対抗して))単一の作品内での”frequency stability”の考えの放棄は、我々にとっては、軽はずみなものになるという結論を導く。 (v) The common and the unusual steps of musica.ficta 前のセクションでは、ここで研究した時代内のさまざまな時点で、musica fictaの可能な限り最大の内容を確立しようとした。 musica fictaのすべての可能性のあるステップが平等かつ通常であると見なされたかどうか、またはいくつかのステップが他のステップよりも一般的であることが一般に認識されたかどうかを調べることが今、残されている。 (訳注;以下、THE COMMON AND THE UNUSUAL STEPS OF MUSICA FICTA p62~ を参照) 14世紀には、実際的な理由で音階を制限する方法について一般的に同意されたものはなかったようである。約1375年頃にパリで活躍したある音楽家(Goscalcus)は、「さまざまな音楽家たちがさまざまな数のconiunctaeを設定している[つまり、musica fictaの♭または♯のステップを含むヘキサコードを不規則に配置した]。たとえば、7つのconiunctaeがあると言う人もいれば、他の8つのconiunctaeがあると言う人もいる。 彼は続けて、a,d,e(ミラレソ)上の♭、そしてc、f上の♯であるmusica fictaを持つ音階を提唱した。すなわち、その音階は、16ステップを持っているが、2つの♯(ソレ)を欠いている。 彼のステップの選択は、彼自身のadmissionで、彼の時代のいくつかの流れの一つであった。しかし、興味深いことに、1490年のAdam von Fuldaによって同じ選択が行われた。Adamは、「faが置かれていないすべての場所に(または、現代の用語、およびオクターブの範囲内では、a、d、e、gに)b♭を置くことができる」と彼の選択を説明した。同様に、b 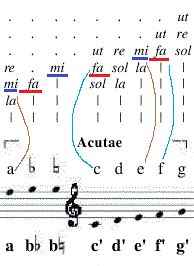 言い換えれば、Adam(およびおそらく14世紀後半の著作者)は、♭のフルセットを産生する原理(グィドの手においてfaがないところはどこでも、フラットによって表記されるfaを配置)と2つの♯のみに制限した別のセット(グィドの手にfaがある場合はどこでも♯の方法で表記できるmiを配置)を結びつけたのである。後者(2つの♯のみに制限した別のセット)の原則の正当化はすぐに明らかになるだろう。 最も有用であると考えられるステップの実際的な選択に関するコンセンサスは、15世紀の間にゆっくりと現れ始めた。それは、オクターブ内で理論的に可能な16のステップではなく、12(の音)を含む音階の形を取った。 12のステップは、音楽的に役に立たない面倒なcommaを実際の音階において回避したい場合、または、キーボード上の黒鍵の分割を避けたい場合、オクターブ内において可能な最大の数となる。 通常選ばれた5つの黒鍵は、B♭に加えて、C♯、E♭、F♯、A♭であった。すなわち、通常の12ステップの音階は、3つの♭と2つの♯を含んでいた。 この音階の初期の記述は、およそ1400年頃のイタリアの匿名の論文に現れているが、それは、音階が規則的に現れ始め、5つの黒鍵のこの特別な選択への説明が見出された15世紀からのテキストにおいてだけである。 p49 AnonymusXIの15世紀半ばのドイツ語のテキストには、musica veraのステップに加えて、B♭、E♭、F#、a♭、c#、e♭、f#、およびaa♭を含む音階が記述されている190。 みせかけステップの選択は、自然音階の半音と全音、またはその逆を生成したいという欲求によって説明される。a-gオクターブ内で、aとb♭の間の半音は、a♭や 結果として生じるみせかけのステップ、a♭、c ♯、e♭、f ♯(+musica veraの♭)は、すべてのトーンをすべて半音に分割するので、12ステップの音階で十分となる。 自然音階のすべての半音はmi-faにソルミゼーションされるため、Anomymus XIによって示唆された半音の拡張は、グィドの手にmiがあるすべての場所にfaがあり、faがあるすべての場所にmiが含まれることになる。 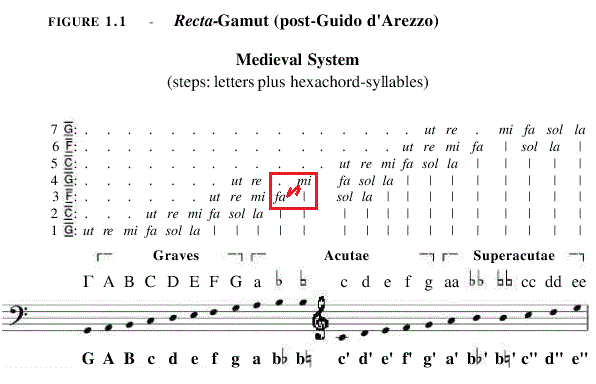 これは、通常の12ステップ音階の説明が通常取る形式であった。(Guidoの)手のどこにでもmiがある場合はfaを持ちたいという欲求(♭化への要求;そしてその逆も)によって、音階は正当化された。 この欲求の理由は、順番に、見つけるのは難しくはない。musica fictaステップの使用を管理する基本的なルールの1つは、垂直方向の完全な協和音でのmi contra faの禁止、つまり、垂直方向に増価または減価したオクターブ、五度、四度等を禁止することであった。増価または減価した場合、それらは mi contra faでソルミゼーションされねばならなかった。そうした音程は、mi contra mi(完全四度)あるいはfa contra fa(完全四度)でソルミゼーションされて、完全音程に戻った。 しかし、常にmi contra faを歌わないようにするには、音楽家は、faとその逆をすでに含むすべての場所に、miを含む音階を自由に使用する必要があっただろう。言い換えれば、mi contra faを回避する場合、faであるすべてのステップでmiを装い、miであるすべてのステップでfaを装うことができることは非常に有用であった。 要するに、黒鍵a♭、b♭、c ♯、e♭、f ♯を含む通常の12段階の音階は、mi-contra-faの禁止の要件に対する最も経済的な答えなのであった。 (上記のAdam von Fuldaの音階は、♭の完全なセットと2つの♯のみを組み合わせたものであり、後者は、(Guidoの)手にfaが存在した場合のどこにでもmiを要求した(♯化)原理に起因するものであり、その正当性は現在明らかであるはずである )(訳者注;Noblittは、「臨時記号の76%は三全音の回避に関連している。としているhttp://machikun.la.coocan.jp/zager1.htm ) 音階は、その説明された通常の理論的根拠としては、15世紀の最後の四半世紀から16世紀の半ばまで、音楽論文に定期的に登場した。例えば、Bartolomeus Ramis de Pareiaは、1482年(12)のMusica practicaで提唱していた。191 round ♭ and square p50 みせかけの a♭、c ♯、e♭、f ♯ とともに12ステップオクターブにおいて、すでに見てきたように、musica vera のすべてのステップがmi(またはfa)を歌うというこの原則は、musica fictaの結果では、fa(またはmi)でなければならない。(正確には、Ramisが、A♭が最低でee♭が最高のみせかけのステップをリスト化している。したがって、彼ら[つまり、歌手]によれば、♭は5か所、つまりB、E、 a、e、、 aa ...に配置され、その 我々は、Anonymus XIが、自然音階の半音と全音とその逆を生成したいという欲求によって、同じ音階を説明したことを、以前に観察した。 もちろん、アノニマスXIの説明とラミスの説明の間に矛盾はなく、むしろ補完的である。 Ramis自身は、見せかけのステップが全音から半音を、またその逆もしかりという、についての上記の議論に従っている。 ラミスは、Johannes de Londonis (whom we can perhaps identify as John Hothby)(16)や「そして、両方の記号(♭と 「それはほとんど拒否されることはない」とラミスは言う。、「そうすることはできるかもしれないが、そうすべきだと認めるつもりはない」、なぜなら「トーン全体がすでに名前の付いた[ステップ]によって2つの半音に分割されている場合、残りの余分なものは、これが許可されているため、無用に作られている。...そのため我々は、すべてのステップで全音と半音を持つことができる... 'からである。(9)。 言い換えれば、16ステップの音階は考えられるが、すべての実用的な目的のためには、12ステップの音階で十分である、ということである。 他の場所では、Ramisは、Gとaの間の黒鍵は、「実践者の少なめの識別力」198によって、a♭が存在する場合でさえも役に立たないステップ199であると彼が考えたG#に対して作られた、と書いている。 彼はまた、G♭を導入した友人のTristanus de Silvaを批判した。これらの発言は、彼の音階が最も一般的な12ステップの選択を表している場合でさえも、すべての音楽家たちが12ステップに自分自身を制限したいとは限らず、G#よりもa♭を好んだ人もいたことを示している。 Ramisは、F,Γ、A、B♭、C、D、Eb♭、F、G、a、b、c、d、e♭、f、g、aaのヘキサコードを持つ「composite hand' (」(manus composita)の形で音階を提示する。「composite」という形容詞は、通常の(Guidoの)手のヘキサコード(Γ、C、F、G、c、f、g上の)と、全音下げた移調(F、B♭、E♭、F、b、e♭、f)そして全音上げた移調の組み合わせ(A、D、G、a、d、g、aa)を意味している。 この解釈は、7つの通常のヘキサコードを「ナチュラルシリーズ」(ordo naturalis)として示す図で確認され、同じヘキサコードは「臨時記号のシリーズ」として全音下げて左に、全音上げて右に配置された。 p51 この3つの手の組み合わせを、Ramisは、'perfect hand' (manus perfecta):と呼んだ。「それゆえ、coniunctaeの追加後、[すなわち、不規則的にヘクサコードが配置され]、それはperfect handと呼ばれる。なぜなら、それはすべて、適当に半音に分けられるからである。」 ラミスは、これらの用語においては、通常の12ステップの音階について考えるだけではなかった。 Bonaventura of Bresciaは、彼のBrevis collectio artis musicae ... quae dicitur 'Venturina'(26) of 1489で、Guidoの手は、プレインチャントやポリフォニーを歌う目的としては、不完全で不十分であるとみなした。そして、'perfect hand'が、3つの手、すなわち、通常の手と全音を上下して移調した手2本の計3手であると記述した。 Bonaventuraは、それぞれの用語を、manus perfecta, manus composita, ordo naturalis, ordines accidentales と呼び、彼がラミスに直接依存する可能性が非常に高くなっている。 'perfect handの概念は、Franciscus de Brugisが1503年から4年にかけてヴェネツィアで印刷されたantiphonaryの前書きである「Opusculum」にも登場した(28)。Franciscus de Brugisは、Guidoの手の不十分さから始め、「歌手だけでなく、オルガニスト、リュートニスト、その他のためにも」彼の'perfect handを説明し続けた(29)。それは3つの「シリーズ」(ordines),) からなり、「自然な」もの(ordo naturalis)、これは一連の白鍵ステップを意味し、「柔らかい」もの(ordo mollis)はordo naturalisを全音下に移調し、「ハードな」もの(ordo durus)はordo naturalisを全音上に移調した。(30)。 この時点で、Franciscus de Brugisの'perfect handは、RamisやBonaventuraの手とは異なるように見えるかもしれない。なぜなら、そのordo naturalisにはbとb♭が欠けており、そのordo mollisにはa♭とaa♭が欠けていたが、3つのシリーズのFranciscuの図は、彼のordo mollisにa♭とaa♭も含めることを望んでいることは明らかであり(31)、Eb上のヘキサコードを追加し、そのために、全音G-aは適当に分割されたことを明示的に述べている(32)。 したがって、彼の'perfect handは、自然ではなく臨時記号のシリーズにbとb♭を割り当てるという点でのみ、ラミスとは異なる。ただし、その全音階は、ラミスとボナベンチュラの全音階と同じである。 また、Franciscusの音階の理論的根拠は、彼の前任者の理論的根拠と同じである。たとえばD♭などの追加のステップは、既存のステップとはコンマを生成し、コンマは歌うことができないため、望ましくない(33)。 そのまま、その手は、mi contra faの不協和音を避けるために音楽家に許容したfaやその逆があるGuidoの手のどこにでもmiを提供した。(34)。その結果、「完全楽器はどれもこのように分割されるべきなのである」(35)。 ラミスによって記述された12ステップの音階は、15世紀の最後の四半世紀と16世紀の最初の論文で出食わした黒鍵ステップの最も一般的な選択を表している。ボローニャのジョヴァンニ・スパタロは、私が他の場所で引用した箇所で、ラミスの音階が、彼の先生の時代の鍵盤楽器を示していたことを明確に確認した(36)。 彼はまた、ヴェネツィアの文通者の一人であったジョヴァンニ・デル・ラーゴを批判した。「彼が言う[デル・ラーゴ]の詩は、自然のA、 p52 実際、1520年2月の最終日付けの手紙で、デルラーゴはジョバンニダレッジに「よく知られているconiunctae,、つまりこれらは現在の5つの黒鍵ステップを含むポリフォニーにおいて使われた」と記述した。 同様に、Spataroは、1527年10月30日のデルラーゴ宛ての手紙で、使用していた楽器の黒鍵すべてが♭ではなく、c#やf♯を含んでいたことを確認した。なぜなら、「そこには2種類のconiunctaeがあるから。1つは丸い♭であり、普通にmiがある場所ではこの記号がつけられる。もうひとつは角ばった デルラーゴは、1533年8月15日(41)のSpataroへの手紙で、非常によく似た言葉で通常の12段階の音階に対してこの公式を繰り返した。 驚くことではないが、16世紀の前半に音階は、すべてのmiに対してfaを持ちたい、あるいはその逆の願望によって説明された。スペインでは、1492年から1518年までの間に3つのエディションがあったDomingo Marcos DuranのLux bellaで議論された(42)。イタリアでは、Sparatoとdel Lagoの手紙に頻繁に登場することに加えて、Stephano Vanneoが1533年(43)のRecanetum de musica aureaで説明した。(略) しかし、黒鍵a♭、b♭、c ♯、e♭、f ♯を持つ12段階の音階が15世紀後半の標準であり、1550年代まで多くの教科書で生き残った場合、Gとaの間の標準的な黒鍵ステップがa♭よりもG♯となっていたというエヴィデンスは、16世紀の第2四半期から増加する。 a♭とG♯との競合は、15世紀後半にすでに進行中であった。これは、Ramisが、a♭とは別に、あるいは同時にG#のキーを導入した演奏家たちの関心が薄い、と論じていたためである。 ラミスは、G♯を導入する理由を、テノールでのBからAへの反行として動くdiscantにおいて、オクターブへ進行する長六度をつくるため、つまりAへのカデンツに導音を供給するため、と説明した。 p53 明らかに、彼の同時代人の少なくとも一部にとって、Aカデンツへの導音を持ちたいという願望は、すべての可能なmi contra faの偶発を招くという危惧を上回っていた。 (a♭とG♯の)2つのステップのどちらがより有用かについての考察は、Arnolt SchlickのSpiegel der Orgelmacher und Organisten of 1511(51)から解釈することができる。 Schlickは、Gとaの間の黒鍵の名前の問題には特に関心がなかった。(彼は、それを特徴的に、”sol [つまり、a♭]またはG#の後のa-la-mi-reのfa”と呼んでいる。ちょうど、DとEの間の黒鍵を"re[つまり、E♭]またはD♯の後の"E-la-miのfaと呼んでいるように。しかしながら、あなたがそう呼んでも)、だが彼は、それがどのように調整されるべきかの説明を欲した231。Schlick is not particularly concerned with the question of how to name the black key between G and a( he refers to it. characteristically.as ‘fa in a-la-mi-re after sol [that is. a~l or G#'.229 just as he refers to the black key between D and Ea s‘fa in E-la-mi after re [that is. Eb 1or D#. however you call it’230 but he wants to explain howi t should be tuned_231 彼はG♯よりもa♭にアプローチするようにステップを調整しているが、A-cadencesの導音として、耳障りな場合でも、それを役に立てるように十分に調整している。しかし、彼は、そうでないと考える人がいることに注意し、cとe♭にステップを合わせる代わりに、彼が推奨するように、Aでのカデンツでさらに純粋な導音を得るために、Eと しかし、Schlickは付け加える。「私はそれについて多くのことを話し、最も経験豊富で最もよく知られている投機的で実用的な音楽家に指導を求めた。彼らは我々の時代でも賞賛されている。そして多くの人が同意したことがわかった。」(55)。 シュリックの発言は、彼の時代までに、シュリック自身のように、キーボードでa♭を要求した音楽家たちさえもが、使いやすいG♯を要求し、一部はG#を支持して、a♭を完全に犠牲にする準備をしていたことを示している。 。 そして実際、a♭の代わりにG#を使用した12ステップの音階の説明は、ますます一般的になっている。音階は、たとえば、人気のGonqalo Martinez de Biscarguiのスペイン語のテキストArte de canto llano et de contrapunto et canto de organo con proporciones et modos,に現れる(1508 and 1550(56))。 Gonqalo Martinez de Biscarguiは特に、a♭は、E♭からのアプローチがあるときに、mi-contra-faを避けるために、必要であろうとしているが、オルガンにはないので、歌われた可能性がある(57)。 その結果、a♭とG#の両方の有用性を彼が認識していても、彼は、彼が2つのうち必要なものとしてG♯を選択したスプリットキーを避けることを、楽器製作者に勧めたことだろう。 別のスペイン人、Juan Bermudoは、1550(58)の彼のEl arte Triphariaで、一般的に使われた一弦楽器のオクターブ以内の5つの黒鍵は、それぞれのmiにfaを供給する(あるいはその逆)規則から生じたことを説明している。Gとaの間の黒鍵はa♭の代わりにG♯が使われていることを例外として。しかし彼は、オルガンに当てはまることが声楽や別の楽器に当てはまる必要はない、と指摘した(6)。 イタリアでは、G♯を持った12ステップのモノコードは、たとえばPietro Aaron in Toscanello in musica (Book II, Ch. 40)で記述されている。それは、1523年と1562年の間でのいくつかの編纂に現れた。 アーロンは、コンマで分けられた2つのminor semitoneに分けられた(つまり、5つの黒鍵すべてが分割されている)すべての全音を備えたオルガンを持つのは有用である、としている。実際に存在するオルガンは、通常のG#を備えた5つの黒鍵を持つだけで、たとえばa♭やd ♯は欠けている。また彼は、a♭の欠如はG#で置き換えることができるため、その欠如はほとんど重要ではないと考えていた人は誤りである、とした。これは、cと同時にステップを使用する場合、コンマのそのような小さな違いでさえ不一致を引き起こすためである。 その他のG♯を標準とする12ステップキーボードを記述する時代のイタリアの作家には、 Giovanni Maria Lanfranco (Scintille di musica of 1533) (65) やGioseffo Zarlino (Le Istitutioni harmoniche of 1558が含まれる(66) 現存する実際的な証拠は、キーボード音楽ではG#がA♭よりも好まれたことを示唆していることをここに追加する必要がある。Robertsbridgeフラグメントに保存されている作品には多くのg#が要求されている。Faenza CodexにはG#sとg#sが要求されているが、どちらのレパートリーもA ♭は要求されていない。 前述の議論は、音楽家が、考え得るすべてのものから、通常使われたステップを選択した場合、彼は、彼の音階をオクターブ内の12ステップのみに制限する可能性が最も高いことを確かめた(コンマとスプリットキーを避けるため) 。 彼の選択は、すべてのmiとその逆にfaを提供したい(∵mi-contra-faの不協和音を避ける)欲求によって決定されたが、すでに15世紀後半には、G#を支持し(∵Aへのカデンツの導音を取得する)、a♭を犠牲にする準備ができていた人がいた。その数は次の世紀にかなり増加した。その第2四半世紀までに、a♭ではなく最新ではG#が標準を表していた。 これらの事実を念頭に置いて、音楽家が結局は、いくつかのコンマと分割キーを許可することを決定したときに何が起こったのかを推測することは難しくない。 a♭とG#の両方が明確な音楽的ニーズに答えたので、おそらく彼らは、分割キーを選択したであろう。 G#は導音として通常の12ステップ音階に追加されたため、同様に、他の欠落している黒鍵の導音、d#およびa#を追加することもできる。後者は、希少で後発のものである。ただし、前者が明らかに優先される。 16世紀のキーボード楽器について、または少なくとも当時のイタリアのチェンバロについての我々の知識は、この構図を完全に裏付けている。それらは、オクターブ内に最大で3つのスプリット黒鍵G♯ / a♭、a#/ b♭、d#/ e♭があり、これを超える実験楽器はほとんどない245。 この構図は、当時の理論家が鍵盤楽器について語っていることによっても裏付けられている。 1500年に書かれたDe harmonia musicorum instrumentorumで、Franchinus Gafuriusは、全音階をa♭、b♭、c ♯、d♯、e♭、f ♯、g♯でわけた'mixed genus' (permixtum genus) を記述した。すなわち、「通常の」12ステップの音階に、、d♯、とg♯を加えたのである。 Aaron はToscanelli in musicaにおいて、G#を伴った12ステップキーボードを記述したが、d#を使用するために、e♭の黒いキーを分割しなければならないことを観察した。そして、オルガニストが「より頻繁に、mi p55 私たちが見てきたように、Lucidario in musica Aaronでアーロンが、当時のオルガンに欠けているステップとしてa♭とd#を選んだのは偶然ではない(73)。 私たちの主題に関する最も具体的な情報は、彼の最後の論文である1545年以降に出版されたCompendiolo(74)で提供された。そこで彼は、Gとaの間の黒鍵は、G#であることを確認したが、a♭は別のキーを追加することで取得でき、同様にDとEの間の黒鍵はE♭であったが、 「イタリアのいくつかの楽器で見られるように」、E♭からコンマ離れた別のキーを追加する必要があった(75)。 豊かになった14ステップの音階が、通常の12ステップに、2つの導音を追加したことを示して、最後の導音a#の追加がそれほど緊急ではなかった理由、理論家たちによって既述されたキーボードが、2つの分割キーを越えなかった理由について説明した。 キーボードの楽器に適用した場合、3つ目の分割キーb ♭/ a#が必要だった音階の理論的な文書を1つだけ私は知っている。 1464年にコピーされた匿名のイタリア語のTertius liber musicae(77)は、通常の12ステップの音階とg#、d#、a#を示し、図式的にaa♭、♭、b♭(78)と同等であることを示した。 キーボード楽器に適用した場合、音階は3つの二重黒鍵(g#/ aa♭、d#/ e♭、およびa#/ b♭)を生成するが、ダイアグラムの形式はaa♭、e♭、およびb♭が標準を表すことを暗示している。g#、d#、およびa#は例外である。 繰り返すが、Tertius liber musicaeの音階は、私たちの時代には孤立した好奇心のままなのである。 <まとめ> この前のセクションでは、我々は、1オクターブ内に17ステップが含まれまるという(鍵盤用語では、7つの白鍵と10の黒鍵ステップ、または7つの白鍵と5つの分割黒鍵)理論とは対立する、15世紀初頭から16世紀半ばにかけて、可能な限り最大の実用的な音階を見てきた。 このセクションでは、15世紀から16世紀初頭にかけて、「黒鍵」ステップの領域を制限したい音楽家が、コンマや黒鍵の分割を避けたり、mi-against-faの禁則(A♭、B♭、C#、E ♭、.F♯)によって要求された5つの「黒鍵」ステップを選んだであろうことを学んだ。A♭は、15世紀後半から、カデンツでの導音の1つに(G♯)次第に取って代わられた。そのため、16世紀の第2四半期までに、前者(A♭)ではなく後者(G♯)が標準になった。 もしも分割された黒鍵の一部が許容されたとしたら、それらはなくなった他の2つの先行トーンを含んだことだろう。 |