| Music in the Middle
Age |
| Chapter6 Gregorian chant:Its modal System and Forms The Modes and elated Subjects p�P49�`176 p149 �v���C���\���O�̗��_�Ƃ������n�߂����K�́A���炩�ɁASynemmenon���܂Ñ�M���V���̂f������t��r �o����������t Syst���� �ł������B���ł�p136�Ō����悤�ɁA�����̒����̕������L���@�́A���e����̕����iA�|P�j���A2�I�N�^�[�u�̑S���K��15�̓x�����ɂ��ꂼ�ꊄ�蓖�āA���y�Ƃ����́A�����A-aa�Ƃ����BMusica Enchiriadis�̒��҂́A����A-P�̏�ɁAA-G�{a-g����ꍞ��ł���B �ނ͂������A���̗�������S�ɂ͎����Ȃ������݂̂Ȃ炸�A���m�ł͍\���I�ɐ���ƌ��Ȃ���Ă���̂Ƃ͈قȂ������K���̗p�����BOdo of Cluny�͏��߂āA�ʏ�̍\���̉��K�Ɋ��S�ɓ�d�̃V���[�Y��K�p���A�g�b�v��aa�������A���Ƀ����������B2�iMusica Enchiriadis�͂������_�Z�C�A�L���@�Ƀ��ɑ���������̂������Ă����j �@�\���~�[�[�V�����́A���łɌ����悤�ɁA�Ñ�M���V���Œm���Ă������A11���I�Ƀ��[���b�p�ōĔ������ꂽ�B�����Ă��̌��ʂƂ��āA���̃V���[�Y�̃g�[���͂��ׂāA�ŏI�I�ɂ͖��O�����t���I�ݒ����邱�ƂƂȂ����B8 ���̍Ĕ����̓O�B�h�ɋA�����Ă���B�����@�ɂ����č̗p���ꂽ�U�̃V���u���̗L�p���́A�O�C�h���������̗p����ȑO����F�߂��Ă������Ƃ���������Ă��邪�A�O�B�h�͖��炩�ɁA���������ۓI�Ȃ����œK�p�������B(���j p152 �@���m�̒����̗��_�Ƃ����́A�f������t��r �o����������t Syst�����i�{���j��ێ����Ă������A�M���V���ŗ�������Ă����悤�ȃI�N�^�[����́A�������E�ɂ����ẮA�������̈Ӗ������������Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă����B(���j �I�~���̌ܓx��i���Ȃ킿�A�t���M�A���@�������R�̐��i���@�̃e�m�[���j�́Aconfinalis,affinalis,socialis�ȂǂƌĂꂽ�B����͈ȉ����Ӗ�����B �@�����f�B����荂������œ����A�ܓx�͒ʏ�̏I�~���̑���ɁA�����f�B�[���I�����鉹���Ƃ��ċ@�\����B �A���@�̃s�b�`�̌ܓx��Ɉڒ������A�ܓx�́A�����f�B�̏I�~���ƂȂ�13�Bconfinalis,socialis�Ƃ������p��́A�l�x��ɂ��K�p����Ă���B����́A�ւ̈ڒ��Ƃ��āB14 p153 �@�I�~���ƕێ����ȊO�̉����́A���@�ɂ��̓���̋@�\�����^�������������B����䂦�A�����f�B������̐��@�Ŏn�܂�����́A��X�������̃I�N�^�[������O�ɁA���łɐ������n�܂��Ă����B �m���ɁA���i���@�ł̃����f�B�́A��ʂɁA�i��O�����邪�j�Asubfinal�ƌܓx��̊ԂŎn�܂�A�ϊi���@�̃����f�B�́A�I�~���̉��l�x�܂ʼn������Ďn�܂�B15 �@��������X��������@�̗��j�����ǂ�A�{�G�`�E�X�Ȍ�A10���I�܂ł́A�����ȃI�N�^�[�u�̊T�O���Ȃ����Ƃ��킩��B�{�G�`�E�X�̗p��ł́Adiaposon�Ƃ������t�͂��邪�A�I�N�^�[�u�͐��@�I�d�v�������o���Ă��Ȃ��B�ނ̗p���modi�͊܂ނ��A�ނ�������g�����ɂ́Atonoi�̘_�c�����鎞�ł������B�ނ͒P�ɃM���V�����tonos�����e�����modus�ɖ|�������ł������B �{�G�`�E�X�̎g��tonoi�́A�v�g���}�C�I�X�̂���ł���A�ނ͑�Wmodus�i��tonos) Hyper�~�L�\���f�B�A���@���v�g���}�C�I�X�ɋA���Ă���B p154 �v�g���}�C�I�X�͎��ہA��Wtonos�Ɍ��y�͂������A���F�͂��Ă��Ȃ������B����modus�E�́A�ia-aa�́j�g�b�v�Ɍ���A������_���iA�|a�ł���j�q�|�h���A���@�ɑ������Ă������낤�B�i�܂����ߓ�����̃y�[�W�Q�Ɓj �@�J�V�I�h�X��Isidore of Sevill�́A�I�N�^�[�u�X�P�[������f�B�莮�̂��Ƃ͘_�����Atonoi�̂��ƂɊւ��Ă̐��������Ȃ������B�ނ�̓{�G�`�E�X���l�Amodi�ł͂Ȃ��Atoni,���邢��partes musicae�ƌĂ�ł���B�����@�͒����ɂȂ�Ƃ܂��܂���������悤�ɂȂ�BAlcuin��Aurelian�́A�����f�B�莮�����������A������I�N�^�[�u�̗̈�ɂ܂ł͍L���Ȃ������B���������莮�̍l���́A�r�U���`����echoi������ꂽ�B ��Alia Musica�� �@�����̐��@���_�̗��j�ɂ�����]���_�́A10���I�̘_���AAlia Musica�ł���B����͕����I��i�ł���B�����炭��4�l�̕ʁX�̒��҂ɂ���āA���܂��܂Ȗ�肪�_�����Ă���B�\���̂����T�̒��҂́A�v�g���}�C�I�X��tonoi�ɂ��Ę_���Ă���B�ނ̎��݂́A�{�G�e�B�E�X�̉��߂��x�[�X�Ƃ��Ă��邪�A�{�G�`�E�X�𐳂��������͂��Ă��Ȃ������B �{�G�`�E�X�̐����ɂ��A�~�L�\���f�B�A���@�́|Hypermixolydians�������|�����Ƃ�����modus�ł���A�q�|�h���A���@�͂����Ƃ��Ⴂmodus�ł���A�Ƃ������Ƃ��������B�i�{��p26��Q�j�B 10���I��Alia Musica�̒��҂�1�l�́A���̐������I�N�^�[�u��ɓK�p���ĉ��߃~�X�������B����䂦�ɁA�ނ͌Â��M���V���̖��O���A�ނ̋�����@�ɓ��Ă͂߂����ɁA�~�L�\���f�B�A���@�������Ƃ������A�q�|�h���A���@�������Ƃ��Ⴂ�A�Ƃ����B���̏����̓v�g���}�C�I�X��tonoi���m�F�������̂ł������B �ނ炪Late Antiquity�i�Ñ㖖���j�̖��O���p�������A���̏����́A�M���V���̃I�N�^�[�u����t�ɂ���K�v���������B�Ȃ��Ȃ�A�����̃I�N�^�[�u�́Atonoi�̂���̋t�̏����Ŗ��t������K�v������������ł���B p155 ���������������_�Ƃ̌낿�́A�u�M���V����̉��K�ɂ����ẮA��ԉ����g�b�v�ɂȂ�A��ԏオ��ɂȂ邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ������v���邢�́u�M���V������A��ԉ��̉�����ł���ނ玩�g�̉��K�ɓK�p����ɂ������ẮA[�M���V���̃I�N�^�[�����]�����{�S�̂��t�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������Ƃł͂Ȃ������B�ԈႢ�͒P���ɁAmodes�ɑ���tonoi�̃~�X�ł������B �@�{�G�`�E�X�ɉ������āAAlia Musica�̒��҂�1�l��Hyper�~�L�\���f�B�A���@�ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A�I�N�^�[����������Ă��Ȃ��B�������Ȃ���A�ނ̍v���́A����Ȃ�ɂ��A�M���V���ꗝ�_�������悤�Ɠw�͂������Ƃł���A���łɓƗ����đ��݂��Ă������y�ɁA�X�P�[�����@�V�X�e�����d�悤�Ƃ������Ƃł���B �@����Ȑ��@�@�\�́A�{�G�`�E�X�ɂ����6���I�ɃM���V���ꂩ�璉���Ɏ��ꂽ�I�N�^�[�u���K�̒��x�ȏ�ɂ́AAlia Musica�̍�҂ɂ���Ă��炽�ȃI�N�^�[�u���K�̈قȂ����i�K���L�q����Ȃ������B Alia Musica�̑��̐��肳��钘�҂̂ЂƂ�́A�\�����ɂ̓v�g���}�C�I�X��modi�ւ̍v���ɂ��ăR�����g���Ȃ�����A�����≹�K�����A�����Ă���䂦�ɏ��߂āA�I�N�^�[�u�̊T�O�̒��ŁA���@�@�\���L�q�����B����́A������X���ʏ�ɍl���鋳����@���_�̎n�܂�ł���B24 �����ɂ�����A���y�̗��j�͉�X�ɕʂ̗��^���邱�ƂɂȂ�A�i15���I������́j�M���V�����̕����i����͕s�тȎ��s�ł��������j���Ӑ}�����t�B�����c�F�̂���ƌ��т����ƂƂȂ����B ��Hermannus�@Contractus�� �@�����������_�́AHermannus�@Contractus�̑����Ȏ�ɂ���Ċ������ꂽ�B�ނ́A���g�Ńq�|�~�L�\���f�B�A���@�ƌĂ��i��W�j���@�̑��݂�F�߁A����䂦��Hyper�~�L�\���f�B�A���@�ɑ����ւ����y���`����������������������B �q�|�~�L�\���f�B�A�i��W�j���@�́A��ւɂĊ��҂��ꂽ�悤��a-aa����ł͂Ȃ��A�h�[���A���@�Ɠ�����D-d�̉���ɂ������B�q�|�~�L�\���f�B�A���@�̓~�L�\���f�B�A���@�̎l�x���ł��邽�߂ɁA���̕ϊi���@�̗��_�I�n�ʂ̊m���́A�����V�X�e���̑Ώ̐��̎d�グ�ƂȂ����B p�P�T�U �@���̑Ώ̐��́A�~�L�\���f�B�A���@�̂S�x������n�܂���@�i����͋L�q�̃h���A���@�ł���j��P�ɋ�������ȏ�̍\��������B�I�N�^�[�u�̃V�X�e���́AAlia Musica�Ř_����ꂽ�悤�ɁA�����ɕ��͂��n�܂�Afinal(�I�~���j�₳�܂��܂ȃy���^�R�[�h�A�e�g���R�[�h���\��������@�j�ƌĂꂽ���̂ւ̍l�@�ɂ���āA�啔�����u������邱�ƂɂȂ����B ���e���꓾��y���^�R�[�h��TSTT,STTT,TTTS,TTST,�������e�g���R�[�h��TST,STT,TTS,�ł���B���T�x��l�x�͋��e����Ȃ��B�q�|�~�L�\���f�B�A���@��F�߂邱�Ƃɂ��AHermannus�́A�y���^�R�[�h�ƃe�g���R�[�h�̑g�ݍ��킹�̐��������Ă���B�q�|�~�L�\���f�B�A���@�ɑ���������̂������邱�Ƃ͋����[�����A�����炭�͐�����������p����A�r�U���`�����_�ŏo�����Ă���BHagiopolites�ɂ����Ď�����Ă���悤�ɁB ��Aribo Scholasticus�� �@Aribo���W�O�̃����f�B���o���A���̂����̂Q�W�͂������ے肵�A52���g���悤�ɂ������Ƃ́A�y���^�R�[�h�ƃe�g���R�[�h����̂��̂ł���BAribo�̋c�_�́A�������̓_�ɂ����Ă��Ȃ苻���[�����̂ł���B �@�ނ́A�����f�B���I�N�^�[�u�ł͂Ȃ��A�l�x�ƌܓx�̊ϓ_�ōl���� �A�ނ́ALombards���X�e�b�v�l�i�s���D�݁AGermans�������i�s���D�����f�B�\���ɂ����č������̈Ⴂ�Ɍ��y�����B �B�ނ̃����f�B�͐��@�̊T�O�ɂ����ďd�v�Ȍ����̒lj��I�؋�������Ă��� �����Ԋu�����@�̕s�\���Ȋ�ɂ����Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�h���A���@�ƃq�|�~�L�\���f�B�A���@�̍\���₱���̏I�~���A�ێ����̑��l�������瓱���������B������psalm-tone�̗��j�́A�����̌����ȏd�v���������B�����f�B�p�^�[���̍\���I�ϓ_�͏d�v�ł��邽�߁A������tone�̌����́AMode��Form�̎����ׂ����̂ł���B �@�����ɂ����鋦�a���́A�l�x�A�ܓx�A�I�N�^�[�u�݂̂ł���B�����̒����̋��a���̂��ׂĂ̕⑫�����邽�߂ɁA���j�]���Ə\��x�������ɉ�������K�v������B���i���@�͈̔͂͂����Ή����Ɉ�x�g�傳���i���f�B�A���@�͗�O�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����������I�~���邱�Ƃɂ�������A�㐢�̑I�D�ւ̒��ڂ��ׂ��ΏƂɂ�����Ό��������ɂ��邩��j�B �����������̐��@�́A��x�ł͂Ȃ��I�N�^�[�u�Ƃ��ĕ��ނ��ꑱ���Ă���B�Y�����ꂽsub-final�́Aextensions�̈�ŁAemmeles�Ƃ����p�ꂪ�K�p���ꂽ�B�Z�x�͂܂��A�����ł͕s���a���ł��邪�A���ނ��ꂽ���̂ɂ͌��т��Ȃ������ł���B�w�N�T�R�[�h�͎�̋�ʂɂ͓K�p����Ȃ������B�O�C�h�̌`���ɂ����ẮATTSTT�\���͕s�ςł������B p�P�T�V �������K�̐i�o�GB��Ƃ̊W�� �@11���I��Aribo�́A�e�g���R�[�hC-F���R�m�����_�ɂ����Ď�舵���AM��r������tt��s ���� �o���������̂悤��14���I�̍�҂́AC����ɑ����ꂽ���Ƃɑ���ŏ��̎�ɑR���āAD����̃e�g���R�[�h�A�y���^�R�[�h�A�I�N�^�[�u�̕ێ������K�v�������ĂƂ��Ă����B ����́A�P�U���I�ȑO�ɂ͌����ɂ͔F�߂��Ă��Ȃ����������K�T�O�̊ɏ��Ȑi�s�������Ă���B���̉��K�͂������Ȃ���ANotker�@Labeo�i�I���K���L���@�Ƃ��Ēm���Ă���Bp�P�R�U�Q�Ɓj�̒���ɂ����Ė��炩�ɂȂ��Ă���B�����K�́Atritus tonality�ɂ����āA��natural�̑���Ɏg��ꂽ���ɁA���̗L�p�������炩�ɂȂ�B �@natural�L���ɉ����ā�L���̕p�ɂȏo���͂������A���ҋ��ɁA�v���C���\���O�ɂ����āA���ژA�����Ă͌���Ȃ����A�����̒������_�Ƃ��������̐��@�V�X�e�����\�z�������Ă����o�����X����萫�������Ƃ��h������v�f�ƂȂ��Ă���B �O�S���̊����͂����A��̗��_�Ƃ����ɂ���āA��L�������̗��R�̂悤�Ɍ����Ă��邪�A�������_�ɂ����ċL�����ꂽ���R���K�̑�ւƂ��Ă̗��K�ɐ�������ł��낤���̂Q�̗v�f������B���Ȃ킿�A�@�ڒ��ƇA��{�I�ȂT�����K�\���ł���B ���łɌ����悤�ɁA�M���V���̈ڒ����K�͗��_�Ƃ����ɂ�錾�y���Ă���A����������ڒ��ɂ��ẴM���V���̊T�O�́A�����̊��s�ɂ����ẮA����\�������o���Ă��Ȃ��B�ڒ���������x�N�����Ă��Ă��A�����̒���ɂ����ẮA���܂�d�v�ɂ͈����Ă��Ȃ��B����́A�����̘_���ł́A�X�P�b�`�I�ɂ��������Ă��Ȃ��B p�P�T�W �ɂ�������炸�A���������q���g���������A�قȂ����i�K�ɂ���X�̃O���S���I���̂̃����f�B���r���āAGustav�@Jacobsthal�́A�����̉��y�Ƃ������A�L���@�ɂ����āA���H�Ŏ��ۂɁAF���E����g�������̂��B�����߂Ɉڒ��������Ă����Ƃ����������������B �ڒ��͕ʂ̖ړI�ł��K�p���ꂽ�B�������A������@����ʂ̐��@�ւ��]�����ʂ��āA��葽���̋ǖʂ��A��i���Ӑ}���Ă������@�̏I�~���ȊO�̉��ŏI������A�����f�B�̂��̕����̈ڒ��́A�Z�ʂ��������ɂЂƂ̐��@�����炵�Ă���悤�Ɍ�����B �O���S���I���̂̑啔���̉����͈͂́A�����ω����N�������ƂȂ��A�ڒ���e�Ղɂ��邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��Ȃ�A�����ʂ�̈ڒ��ɂ����ĕς�����悤�Ȓ��x�̂��̂͋N����Ȃ�����ł���B�ڒ��͂����Ε����ʂ�ł͂Ȃ��A�����f�B�\���̏C���ł���B�����͕p�ɂɁA�A����Œ�������Ă���B �@�����K���L���F�߂��Ă������Ƃ́AAurelian,Regino,����ɂ�Musica Enchiriadis�̍�҂Ȃǂ�������炩�ł����iMusica Enchiriadis�Ŏg��ꂽ���K�̌`�]p254�Q�Ɓ|���邢��daseian�L���ɂ���ď����ꂽ���̂́A���炩��f��cc���܂�ł���B����͔����ω�absonia�ƌĂ�Ă���j�B ��̒i�K�ł́A�����ω��͏C�������ׂ����̂Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ�B���炩�ɂ��������C���́AOdo of Cluny�̎���ɂ͈�ʓI�ł͂Ȃ������B�ނ̓X�L���̂Ȃ����y�Ƃɂ�邱�����������ɕs��������������ł���B �������K�̉���Ƃ��Ă̈ڒ��� ���オ����ɂ�A�����ω��́A�l�x���邢�͌ܓx��ւ̈ڒ��ɂ���Ĕ�������悤�ɂȂ����BBerno�͎l�x���邢�͌ܓx���҂�_���Ă���B�uJohn Cotton�v�͌ܓx�̈ڒ��݂̂�_�����B�ȉ���diagram�́Ab���b�i�`�������̏����ɂ��ڒ���ʂ���F���E��̔r���������Ă���B 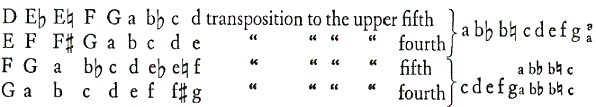 �@�e�F��������ω�������邽�߂̈ڒ��́A�l�x��ܓx��ւƓ��l�A�אڂ��鉹�K�ɑ��Ă����ꂽ�B���ꂤ���AE���F����܂ރp�b�Z�[�W�͂��ꂼ��A��S���㉺�ɓ]���������邱�ƂƂȂ����B�אڂ��鉹�K�͓]���ɂ����Ă��d�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�O���S���I���̂ɂ�����ЂƂ̐��@���瑼�̐��@�ւ̕p�ɂȃV�t�g�̑����́A���@�̏I�~������S��������Ă��邩��ł���B p�P�T�X �@�����f�B�͎��ɁA�قȂ����ʖ{���ɈقȂ������@�ŏo������B�����炭�͕s���m�Ȉڒ��̌��ʂł��낤�B���邢�́A���̐��@�͈قȂ�������Ŗ������ď�����Ă���B ���m�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�ڒ��͍s���Ă���B���Ƃ��A�h���A���@�̃����f�B�́A�����Ƃɂ��AG�Ɉڒ�����A�Atetrardus�ɋA�����邱�Ƃ��\�ł���B�P���ɏI�~����G�ƂȂ邱�ƂŁB �������ꂼ��̃����f�B���K�������ЂƂ̐��@�ɐ��������킯�ł͂Ȃ��B�����AMusica Enchiriadis�ɂ����ẮA�����Ă��̑��̏����̒���ɂ��A���郁���f�B�́A�������̐��@�Ō����icf�DExample�Q�W�@��T�́j�B�I�P�Q����15���I��Catholica�̋����[���\���Ɍ�����B �@�����̗��_�Ƃ����́Aethos��ނ�̐��@�ւƒu�������邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�悤�Ɋ����Ă���Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�M���V�����ethos�𒆐����_�Ƃ���������ɑ�������ƐM���Ă�����̂ƒm�o���Ă��邩��ł���B�O�C�h��Hemannus Contractus�AJohn�@Cotton�́A���@�ɗϗ��I���i���L�q���Ă������Ƃ��������Ă���B �@10���I�ɃI�h��ǐՂ���L�W�̒��_�iBerno�ƃR�b�g���ɂ��11���I�̂���Ȃ�i�K�����邪�j�́A12���I�O���̃V�g�[�h���v�ł���Ǝv����B���̑��̕ϊv�͂��Ă����āA���̉��v�͂��ꂼ��̐��@�̉����͈̔͂��P�O���ɐ��������BAmbitus�irange)�́A�I�h��ɂ���čl����ꂽ�����̂ЂƂł��邪�A�������������ɂ��ẮA�S�̓I�ȓ��ӂ͓����Ă͂��Ȃ������B �V�g�[�h���v�́A���e��������ω��₠�邢�̓t���[�Y�̏I�~�̉ߏ������邽�߂ɁA���邢�̓t���[�Y�̏I�~�̉ߏ������邽�߂ɁA���邢�͗\�z���ꂽ�͈͊O�ł̐��@�̏I�~��A���������Ɉړ����������p�b�Z�[�W�����e�͈͓��ɖ߂����߂ɁA�����̈ڒ��������炵���B �@�����K�̒m���́A���ʓI�ɏk�����A���m���y�ɂ����Č����I�Ȗ������ēx�ʂ������߂ɂ́A�|���t�H�j�[�̔��W��҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �@emendation�̐�����account�́A�Â����̂̓`���������I�ɂ킽���đ��������Ƃ̋����ɂ͉e����^���Ȃ������Bemendation�͎�ɁA���ʓI�ɖ����ň₳�ꂽ�����f�B�ɓK�p�����Z���̗�Ƃ��ċL�q����邩������Ȃ��B ���܉��K�\���̖����� �@���i�`�������̎g�p�́A�ڒ��ɂ���Ă����łȂ��A�������̃O���S���I���̂ɂ�����܉����K�I�\���ɂ���Ă��܂����������B������A�S�̂̌Â����p�[�g���[���܉����K��w�i�ɂ����Ă��邩�ǂ����͂��낢��c�_�����邪�A�����̃O���S���I���̂̃����f�B�͖��炩�Ɍ܉����K�ł��邱�Ƃ͎����ł���B�ȉ��̕��̃����f�B�͏����ɁAE��B�ȗ�����Ă���B p�P�U�O  E����b����������Ă��� �Â������f�B�ł́A���ۂɖ����܉����K�ł���A�Z�O�x����鉹�͑����I�ŁApien tone�ƂȂ��Ă���B�����A����͒����̉��y�Ŏg���Ă���Bpien tone�̗��_�́A�`���I�ȂW�̐��@�̕��ނ�ے肵�Ȃ����A���ꂼ��̐��@�ɂ����āA�ӂ��̉��K�itones�j�����R�ɁA���̂T�ɏ]�����ƂɂȂ�B���̗��_�ɑ��邩�Ȃ�̏؋��́Aquilisma�̏o���̓��v�f�[�^�ɂ��B1600�̃O���S���I���̂̃����f�B�̂����A���悻900��quilisma���܂݁A���̂����̂W�P�D�T���͒Z�O�x���ɂ���B330�قǂ�B���ɁA170�قǂ�E���ɂ݂̂���Bquilisma��pien-tone�̑�\�ł���ƌ�����BAribo�͎����A�L�����quilisma�͉��t��̑����̂��߂ł��邱�Ƃ������Ă���B �@���炩�ɁA�Z�O�xa-c�����ɂ͂Q�̂���������B�ЂƂ̗�́AB��B����p���邱�ƁB����䂦�AB��B�����l�ɁApien-tone�ƂȂ�BE�̏ꍇ�́AE���ɒu������邱�Ƃɂ���āAD����F���̊Ԃ�pien-tone�ƂȂ邪�A�ڒ��ɂ���Ă���E��͔r������邱�ƂɂȂ�B B���͕K���������pien-tone�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ����郁���f�B�́AE����B���ł͂Ȃ��AF����c�������܉����K�ɂ��邩������Ȃ��B�������Apien-tone�Ƃ��Ă�service�́AB���������Ԃɂ����ăe�m�[���Ƃ��Ė]�܂����Ȃ���Ԃɒu����������Ȃ��B�����āA10�`11���I�ɂ�����A�t���M�A���@�ɂ�����B������c���ւ̃e�m�[���i�ێ����j�̃V�t�g�ւ̐ӔC�ƂȂ邩������Ȃ��B�t���M�A���@�ɂ�����e�m�[��(�ێ����j�Ɋւ���s���肳�́A���̐��@�����[�}���̂Ŏg���Ă���������������邩������Ȃ��B p�P�U�P �@pien-tone���_�́A���̊܈ӂ��\���ɓ����AB�P��B�ɑ���]�܂����Ȃ���ւł͂Ȃ��A���̒��Ԃł���A�Ƃ������Ƃ������B�����ă����f�B���g�́AB��̕p�ɂȎg�p�ƂƂ��ɁA���̗��_��S���Ă���B �@�����̒��q�Ƃ́A�M���V����̔����K��[�n�[���j�b�N�̑��igenera)�Ɋւ��Č��y���邪�A�����������igenera)�́A�O���S���I���̂Ŏg���Ă����悤�Ȃ��̂��������Ƃ͂Ȃ��B�����y���G�ʖ{H159�ɕ\���A�قƂ�ǎl���̈ꉹ�ɋ߂����̂̐��@��̏d�v���́A�_���ł����y�͂���Ă��邪�A�܂��͂����肵�Ă��Ȃ��B ���̎ʖ{�ł́Ab����c���Ae����f���̊ԂŎl���̈ꉹ�͂����Ώo�����A�S�����K�ɂ����郁���f�B�ɂ������Ώo�Ă���B �������Ñ�̗��_�ł́Aintonation�Ɋւ��ẮA���炩�ɐ��������Ƃ��Ă����B�����́A�s�^�S���X�A�A���X�g�e���X�A�v�g���}�C�I�X�̉����̌n�̈Ⴂ��������A�ŏ��̃s�^�S���X���D�B�ނ̌��Ђ́A�s�^�S���X�̑̌n�𒆐��̒��q�Ƃ����ɑI����ɏ\���ł������B52 �@B�ɑ���B��̑�ւ����@�̐�����ς���Ƃ������Ƃ͂P�U���I�ɂȂ��Ďn�߂čL���F�߂�ꂽ���Ƃł���B�䂦���A�����ɂ����āAB�����T���@�́A�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��Atritus tonality�̌`���ƊŘꂽ�B������B�����P���@�́Aprotus tonality�ƊŘ�A���R�Z���K�ł͂Ȃ������B ����������́AB���B�̊Ԃ̓�����A�����̗��_�Ƃ����̔Y�݂̎��O�S���́A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA��{�I�ȉ��K�\���ɂ�����B�y�ڂ���transformation(�ό`�j�ւ̒��ڂ̒��ڂɌ����Ă������B����䂦�ɁA���@�����P�ʂ̂��̂𖾂炩�ɏ���Ɣ��f���ꂽ�P�ʂł���I�N�^�[�u�̔z�u�������N�����悤�ɂ���B p�P�U�Q �@���ׂĂ����蓖�Ă�ꂽ���@�����肷��ƌ����Ă��������f�B�̕����́A���������ł͂Ȃ������BAurelian��Regino�́A�i���K�I���@�jscalar modes�ɂ͊S���Ȃ��A���@�̕��ނ����߂鉞���ɂ��āA���̏I�������n�܂�ɊS�������Ă����B���K�I���@�ɂ����āA����́A���@�̊�Ƃ��ĕ��y�����I�~���ł������B���̑I���́A���H�I���R�ɂ��Bp�P�T�U�Ō��y����psalm-tone�́Arecitation�����ł���B�����͎��т̃e�L�X�g���̂����߂ɗp����ꂽ�i����䂦�A�����́A�V���A���enyana,�r�U���`����troparion�ɑ�������j�Breciting�̑啔�����s��ꂽ���̓e�m�[���ł������B ���@��psalm-tones�Ƃ̊Ԃ̊W���������ꂽ���A�����̏I�~���́A���炩�ɁA��Ԃ̏d�v���������Ă����B�Ȃ��Ȃ炻��́A���т��K������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̌���ł���������ł���B�����āA���̌��肳�ꂽ���@�͂���䂦�A�̎�ɂƂ��Ă̓����f�B�̑O�̕����̐��@�����d�v�Ȃ̂ł������B �@�����f�B�S�̂��A���ɂ͂��̎n�܂���ɂ���āA����ɂ͂��̏I�����ɂ���āA�P�̐��@�Ɍ��肳�ꂽ�Ƃ��������́A�����̉��y�Ƃ��������S�Ƀ����f�B�̍\�������Ă����Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ȃ��BRegino�́A��������antihons��Intorits���قȂ������@�Ŏn�܂�I��������Ƃ��L�������ɁA���������\���ɒ��ӂ��x�������B���łɂ݂��悤�ɁA�V�g�[�h���v�̗��z�̂ЂƂ́A�ψ�Ȑ��@�ł������B���������̗��z�́A�L���͈͂ł͐����������Ȃ������B�O���S���I���̂̓����f�B���L�x�ł���A���̗D��������͐Â��ɁA�����������z���ۂ������E���z���Ă������B�V�g�[�h���v�O�̃O���S���I���̂̏�Ԃ́A�������̎ʖ{�i�I�~�����قȂ��Ă���悤�Ɍ�����d�v�ȑ���͏����āj�ɂ����Ė{���I�ɓ���Ɍ����鐹�̂�����Ƃ���ł́A�A���u���V�I���̂ɂ���������������Ȃ��B�����I���o�āA���@�̃V�X�e�������ꂽ���_�ƂƂ��Ɋm�M���ďo�����ꂽ�O���S���I���̂̐��́A�^���Ȃ��A���Ȃ�̐��ƂȂ�B ���̔��W�̏����ɂ����đ��݂������K�V�X�e���̔F�����ǂ̂悤�Ɍ�����Ă��邩���������Ƃ́A�w�u���C��A�M���V����A�V���A��A�r�U���`����A�O���S���A�����y�ƂƂ��Ɍ��т��āA���@�Ɋւ��ẮA�\�������Ă����B��X�̓O���S���I���̂�ʂ��āA���@�����K�̃X�g���[�g�W���P�b�g�ɐ�������Ă��邱�Ƃɂǂꂾ���s���������Ă��邩�����Ă����B����䂦�ɁA�h���A���@�ɑ��郁���f�B�̊��蓖�ẮAb�i�`�������܂���B��̗L���ɂ�����炸�A�����f�B�̃C�f�B�I����������A���ꎩ�̂ʼn��K�\���ł�������A���@�̐������Œ肷�邤���ł�茈��I�ł��邱�Ƃ������X���ɂ���B �m���ɁA�����f�B�����́A���̐����ɂ����Ă��݂��ɋ�ʂ������̂ł���A�A�����Ă��܂��܂ȉ����̑��l���𗘗p�ł��Ȃ���A�����̍���ɂ���قȂ������K�����\���������B�������A�����̉��K�����ł��邩�𐄑����邽�߂ɂ́A���@�̔��W�̂�荂����Ԃɑ�����K�v������B �قȂ���@���������̕����̂̍���ɂ��鉹�K�̈Ⴂ����ʓI�ɑ��݂��Ă���悤�Ɏ�����Ă���ԁA���̍\�������K�̊ϓ_���画�f����āA�P�̐��@�ȏ�Ɋ��蓖�Ă��鎑�i�邱�Ƃ��낤���A������́A�ЂƂ̐��@�Ɋ��蓖�Ă���Ƃ������Ƃ́A��O�Ȃ��A�ŏ��̌`���玦�����悤�ɁA���݂Ƃ��Ď咣����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ip�P�T�R�j�B �@�����炭�͈ȉ��̂悤�Ȍ`�ŁA�V�X�e�������ꂽ���@�̔��W��`�����Ƃ͉\�ł���B����́A�������y���������A�@�����y�ɂ����ċK�������炳�ꂽ�\���������B ��P�i�K�G�����f�B�^�C�v�͕��ނ���邪�A�V���{���I�ɂ��邢�͂��������ȖړI�ɓK���Ă���Ǝv���鉹�y�Ƃ͊W�Ȃ����R�ŏ������B ��Q�i�K�G�����f�B�͖{���Ƃ��ĔF�߂���B�V���{���I�d�v������͗���A����ȉ��y�I�n�ʂƂ��Ċ��蓖�Ă���B���Ȃ킿�A�����́A����҂炪�V���{���ł͂Ȃ����y�ɂ���ĕ��ނ��ꂽ���p�[�g���[���\������悤�ɂȂ�B ��R�i�K�G�����f�B�͂��悤�Ƃ��鎎�݂�B�����f�B���n�܂鉹���͉̎�ɂƂ��ďd�v�ł���B�i�����f�B�̏I���̉������܂��A���ۏ�̗��R����d�v�ł���Ǝv����j�B ���������̍ŏ��̉����́A���̉����Ƃ̊Ԋu��ʂ��Ă̊W�������A�ǂ̂悤�ɂ��Č��߂���̂��H��������߂邽�߂ɂ́A���K�\���̍���ɂ��鑊��Ɍ���������K�v������B���̐����ɂ����ĈقȂ��č��ꂽ�����ȃ����f�B�����̍����I�ɑ傫�ȃ��p�[�g���[���A���鉹�K�ɂ��ׂĈ�v���邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B ��S�i�K�G�قȂ������K���Y���ł��邳�܂��܂ȊԊu�̑g�ݍ��킹�́A��������A�̌n�����ꂽ�B�����Ȃ��Ƃ����̗��_�ɂ����āB�ނ��auctoritas(���Ёj�Ɏ䂫����ꂽ�����ɂ����邱�������g�ݍ��킹�̒������A���_�Ƃ������Ñ�֗U�����邱�Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�����đ̌n������悤�Ȍ����́AAlia Musica�Ɏn�܂����B �̌n���̔��ɏ����ɁA�ʂ̉��K�i�Q�Ȃ�������ȏ�̉��K�������炭�A�P�ɁA�ʂ́A�d�����Ă�����f�Ђ������Ă��邪�A����͂�蒷�����K�̈ꕔ���ł���j�ł͎�����Ȃ����������̐��@�������Ɏ������ꂼ��̉��K�́A�̌n���O�Ɏ��ۂɎg���Ă������@�ɗ������A�����ɋ��R�̖��ł��낤�B�i�䂦�ɁA�M���V����̃I�N�^�[�u���K�́|���͎҂̖����̌��҂̂悤�Ɍ������l�����́A�ނ�̗��_�I���ʂ̗��s��ɒ����̍�Ƃɓ��B���邱�ƂɂȂ�A�����̌��ʂƋ���y�̊Ԃɂ͉��̊֘A���m���ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ𗝉����Ȃ��܂܂Ɏ��s�����Ă����|�Ɠ��̐��@�̏d�v�������K�v�͂Ȃ������j�B ���Ԃ��o�ɂ�A���������y�������̃����f�B���c���A��ʓI�ȕ������������x���ɂ���̂ł���A�L���Ȑ��@�V�X�e���́A�����̂��鉹�K�\���ɂ�����ω����Ȃ���A�i�����Ă��邱�Ƃ��낤�B ��T�i�K�G�����I�Ɍ��߂�ꂽ���@�̐����Ɖ��K�\���̊Ԃ̊W�ƂƂ��ɁA���y�Ƃ����́A�z��I�Ɍ����ɌŎ����邱�ƂȂ��A���@��ۑ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B�ނ�͊m������A�e���������g�����A�Â����̂�ێ����邱�Ƃ͎��R�Ǝ���g���āA���@�̐F�t������Ȃ��m����ʂ��ē���ꂽ�V�������̂�n������B���K�\�����A�I�~���A�ێ����A���̑��A���̗e�ʂɉ����������̏d�傳�ƂƂ��ɁA�ۑ������̂ł���B The Forms of Gregorian Chant and of Some Outgrowuth THE FORMS OF THE CLASSIC CHANT |