| Hermann's Major Sixth BY RICHARD L. CROCKER |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| まうかめ堂;アフィニタスからオクターヴ種へ参照。非常にわかりやすい解説です。 p19 まず、以前の作家によっていわば大まかな塊としてこれまで掘り出されてきた旋法を認識するための1つのルールを見てみましょう。ただし、不純物を完全には解消していません。 そして、それを真面目な学生にとって明確かつ純粋に際立つように述べましょう。 この認識の問題は、簡単な説明に減じられるかもしれませんが、それでもなお、非常にエレガントに示されていることは、旋法の適切で正当な基礎の中の場所を見つけるため、広範で特徴的なものです。 これら↑は、Hermannus Contractusの言葉であり、11世紀の中頃に書かれている。1 この論文では、Hermannが何を意味するのかを説明し、Jacques Handschinらがおおざっぱにおこなったものを磨磨き上げようとする2。 私にとってHermannは、彼と同じように話すことにはある程度の正当性があり、 彼がMusicaの終わりに発表した貴重なものは、実際には、9世紀のHucbald以来の、中世初期の理論家たちのゴールであった。 ヘルマンはさらに彼が考えていることを説明している(表1aも参照)。 お望みのテトラコードを取ってください。gravesのそれを。さらに、両端にトーンを追加します。さらに、旋法の基礎を形成する音調パターンの限界がある。 4つの旋法と同じ数のトーンパターンがあります。 最初のトーンパターンは、T下げて、第1種(TSTT)五度上げるものである。これは、Antiphon Prophetae praedicaverunt、In tuo adventuにおいて認められ、音域が6ピッチを超えない同様のパターンで認識されます。このパターンは、protusの主要ピッチA、D、a、dで認識できます。 p20 2番目のパターンは、2つの全音を下げて、第2種(STT)四度上げるものである。これは、deuterusの主ピッチB、E 、 3番目のパターンは、第3種(TTS)四度下げて、二度分上げるもので、これはtritusの主ピッチC、F、c、fを確立する。この例は、Antiphon Modicum et al videbitis(L.U.p820) 等において生じる。 4番目のトーンパターンは、一全音を上昇させ、第4種(TTST)五度下降させる。tetrardusがこれに当てはまり、この旋法の主要ピッチD、G、d、gを確立する。この例は、Antiphons Si vere fratresやMulti venientなどで認識できる。これらは、6つのピッチで構成されていると説明されており、6番とそのピッチ数で構成される最大音程の両方の完全性を示す。3 3 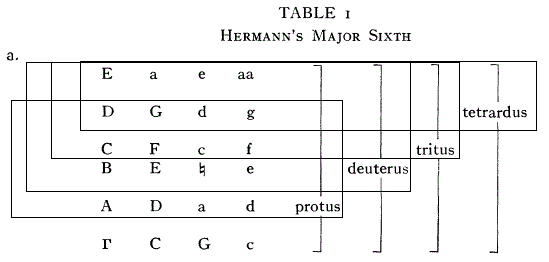 Hermannが「旋法の認識」について語っているという事実にもかかわらず、彼がここに提示したことは、我々が通常それらとして考える8つの旋法、または多くの作品で見られる4つの終止音についてさえ、特に有用な説明ではない。 Hermannは長六度の範囲内にある作品を選択するために、いくつかの問題に取り掛かる必要があった。そして、4番目のトーンパターンの場合、彼のスキームでは、終止音(G)から1全音のみを上昇させている。これにより、ほとんどのGで終止する作品での作業には問題ない。which will not take us far in working with most G-final pieces. アンティフォンSi vere fratres(Gからeまでの音域)の選択から、この場合、d上のtetrardusの終止音を想像しながら、ピッチGからeにチャントを配置し、ピッチセットの説明( 「一全音上げて、五度下げる」)は、チャントの音域と正確に一致する。そのとき、我々が位置づけた終止音は(dなので)、チャントの終止音Gとしての同じ位置にはない。 この混乱は、 Hermannの最終的な目的が個々の終止音の単なる識別ではないことを示している。この点については、p33で説明したい。  L.U.p509 p21 なぜ、六度への、このような特殊な六度への制限があるのか? Hermannは言う。「お望みのテトラコードを取ってください。gravesのそれを。」そして言い続ける。所与のトーナルパターンは、それぞれの旋法内で、たとえばprotusにおけるA, D, a,dのように、4つの”主要なピッチ”のそれぞれで見出される、と。 Hermannにとっては、テトラコードとは、TSTの第1種四度であり、そしてgravesのテトラコードはそれぞれ、A, B, C, Dとなる。その他のテトラコードは、下図のようになる。 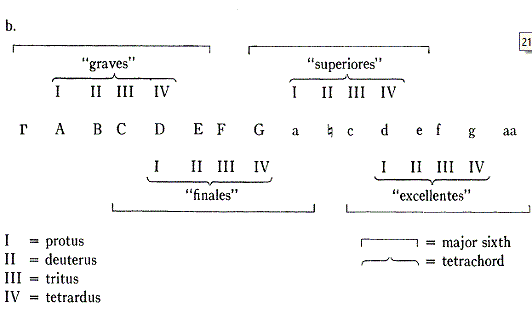 これらの配置において、4つの終止音のそれぞれの上行、下降は、長六度の音域を超えない限りにおいて、同一となる。たとえば、Aで始まり、五度上昇してEに達する場合、その上行は、長六度の音域のトップに到達する。 さらに上昇すると、ある場合では、Fへの半音が出てくる。しかし他の場合、b p22 長六度内においてのみ、4つの終止音の周りの上行と下降は、これらの終止音のすべての配置において同一となる。そして、終止音の多数の配置は、全体の構築の本質的な役割を果たしているように見える。 これまでのところでは、これはHermannの長六度の意味合いのように見える。これは明らかに複雑な2次的概念である。 どのようにそして特になぜそれが発展されるべきであったかは、簡単に答えられない質問である。 Hermannがそれを複数の理論家の研究であると語ったとき、我々はHermannを信じることができる。 彼が音楽理論に対するその価値を信じているとき、我々は彼を信じるべきだと思う。 <GuidoのMicrologus;Contractusとの違い> Hermannが考えている他の理論家を特定することは可能であろうか? Hermannの六度の最も直接的なソースは、GuidoのMicrologusであろう。 Hans Oeschは、Berno und Hermannにおいて、 Hermann がグイドの働きを知っていたという直接の証拠は見出していない。 それでもOeschは、可能な関係のいくつかの兆候を指摘している。4 Hermann から引用されたパッセージに照らしてMicrologusの第7章を検討すると、関連が明らかになる(表2を参照)。 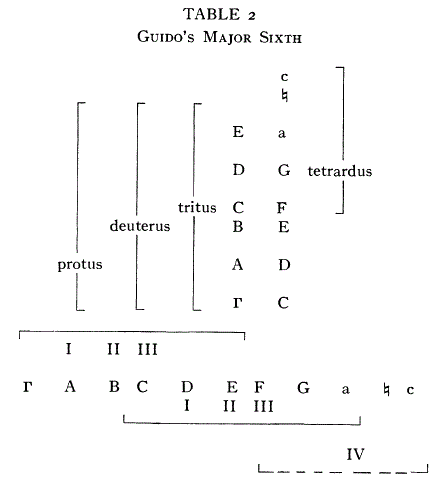 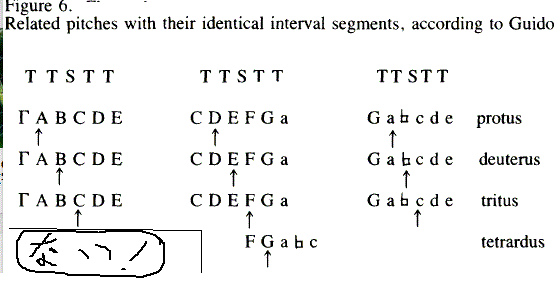 さらに、ピッチは7つあるので(他は、前にも言ったように同じです)、7つの方法でどのようなモードと品質があるかを説明するだけで十分です。 第1トーナルパターンは、ピッチがT下降し、TSTT上昇するときに発生します。AやDがそうであるように。 p23 第2トーナルパターンは、ピッチがTT下降し、STT上昇するときに発生します。BやEがそうであるように。 第3トーナルパターンは、ピッチがSTT下降し、TT上昇するときに発生します。CやFがそうであるように。 第4トーナルパターンは、ピッチがT下降し、TTS上昇するときに発生します。Gがそうであるように。 そして、これらが順番に続くことに注意してください。1つ目はA上で、2つ目はB上、3つ目はC上です。 次に、1つ目はD上に、2つ目はE上に、3つ目はF上に、4つ目はG上に配置されます。 また、ピッチが四度と五度で配置されていることにも注意してください。AはDに結合され、BはEに結合され、CはFに結合されます。 ここに示すように、四度下あるいは五度上で。 4つの終止音D,E,F,G周囲の上行と下降についての議論では、グィドは長六度内の3つの設定を含めている.。これはHermannの六度と同じであるが、この六度は、四番目の終止音周囲では、五度(F-c)範囲内でセパレートされた音域内で上行、下降をしている。(表2参照) グイドの配置Hermannのそれとの類似点は明らかであり、両者の違いは、「不純物を完全には解消していません」というHermannus Contractusの言葉そのものである。そして、Hermannus Contractusは、彼の先任者を批判し続け、両者の関係が明らかになる。 さて、グィドらは、私たちが話してきたパターンが最も完全に6つのピッチを構成している事実を無視して、7つのピッチを採用した。これらは規則的にA、B、Cの3つの旋法をレイアウトしているが、4番目の旋法tetrardusの存在は否定している。さらに、D、E、F上の同様の規則で上記の旋法の連続を求め、彼らは、4番目の旋法tetrardusを、最終的に、G上のみにおいて固定した。それは、ピッチがT下降し、TTS上昇するようになっている。 すでに述べたように、エラーは3回にわたって生じていた。最初に、彼らがこの同じ旋法を、その反対すなわちprotusの方向に向けなかったこと、次に、彼らがそれをパターンを超えて拡張し、C上で始まり、aに伸びる6ピッチの正当な制限を超えたこと、最後に、彼らが確立された分類をせずのこうした拡張を行っていること、等のためである。 p24 Hermannusは、 A, B, C, とD,E,Fの平行関係と、Gについての音域に関する特別な構成について、グイドのMicrologusの第7章をそのまま批判しているように見える。 Micrologusのコンテキストから、Guidoの目的はHermannの目的と同じであると判断できる。Hermannus Contractusは、終止音での上行と下降がどの配置でも同一であるとしたが、グィドは、は明らかに4番目の終止音Gでの上行と下降が長六度C-aの音域内では望ましくないと感じた。それは、G終止音上のためには無意味であったため、あるいは、彼が、Gについての上行と下降は、その他のピッチの終止音からはかなり異なっている、と感じたためであった。 いずれにせよグィドは、(protus, deuterus, tritus でのA, B, Cに対するD,E,Fに相当するものとしての)Gの四度下あるいは五度上でのtetrardusの終止音は見出していない。さらに彼は、F♯を要求するようなGから上行するための音程設定を示している。 グイドは終止音の別の配置を「アフィニタス」(四度下または五度上の音との同種性)と呼び、Micrologusの比較的大きな部分(第7章と第8章、特定の意味では第9、10章)を費やして、これらの類似性の意味を追求している。 1つの結果は非常に興味深いものであるが、第8章のダイアグラムに具体化された構造に気づくことはあまりない。7 ダイアグラムには困難がないわけではない。その中でグイドは、「ダイアグラムの中で誰かが私たちが話し合ったものの表現を求めれば、そこにそれを見つけることができる」と述べ、複数の解釈の余地を残している。しかし、最も顕著な特徴は、3つの基本的なピッチへのこだわりである。これらはダイアグラム自体ではC、D、Eとして指定されているが、ダイアグラムの直前の説明からはD、E、Fであるように見えるかもしれない。 グイドは、終止音の前後の上行と下降が、ダイアトニックシステムの構築のために、さまざまな文字で表現する必要がある、またはされ得る3つの基本カテゴリに含まれるかもしれないと言っている。彼は、これらの3つのカテゴリーは、全体としてのスケールや4つの終止音の通常の教義よりも基本的であることを強調しているようである。 第7章では、4番目の終止音を長六度の彼の規則の例外として扱い、第8章では、彼は、主要な終止音C、D、Eとの比較における補助グループとして、F、G、a、b 終止音に関して、グィドの考えを具体的に表現すると、(グィドが論じていたように)、終止音からの直接の上昇のみを考慮する場合、3つの終止音はすべて実際に存在する終止音である。 つまり、ある種の終止音(tritus)は、その上がTTとなる。2番目の種類(protus)は、その上がTSであり、3番目の種類(deuterus)はSTである。 p25 少なくとも全音階システムには他の種類はないが、考慮すべき音域の目的は何か? おそらく我々が、彼の最初の終止音を”長”、彼の2番目を”短”、彼の3番目を”フリギア”と呼べば、これらは、ポリフォニーにおける3つの主要なカデンツであることが思い起こされ、おそらく我々はグイドをもう少しよく理解するかもしれない。 むろん、そのようなことは、11世紀初期のグィドの心にはいっさい思い浮かぶべくもなかった。しかし彼は、終止関係と全音階システム全体とを、できる限り簡潔に、表現したかったのかもしれない。。 しかしさしあたっては、グイドの3つの終止音の提案は、追従者がいなかった。そして、少なくともHermannus Contractusは、3つの終止音を強調する代わりに、長六度以内で4つを均等に扱うことが良いと感じた。 グイドからHermannus Contractusまで、そのロジックを簡単にたどることができる。 しかしグイドの背後には何があったのか? <Dialogus;オクターブの概念の確立> Hans Oesch は、Micrologusにおけるグイドの一般的なアプローチが、Odo( Odo of Clunyではない1000年頃のAbbot Odo)に帰せられたDialogusから直接進んでいることを説得力のある方法で示している。8 モノコードへの独占的依存により、Dialogusは初期の論文の中で最も実用的であろう。 Dialogusの最後には、Guidoの第7章には、ほぼ類似した箇所があるが、大きな違いがある。すなわち、上行、下降についてのそしてまた、終止音の配置におけるDialogusの説明では、確かに、長六度についてのシステムがほとんどない。(たとえば、Dialogusは、b♭を伴うa上のdeuterusを置いている。その配置は、11世紀と12世紀の間に譜線譜記法で固定され、特定のAntiphonsで実際に使用されていた。) したがって、Dialogusは 他のいくつかの点では、システマティックであるかもしれないが、終止音についての上行・下降に関してはそうでもない。 グイドのアレンジメントがHermannus Contractusのアレンジメントよりも体系的でないとすれば、グイドのアレンジはDialogusのそれよりもはるかに多く、Dialogusは、長六度の共通の範囲については何も述べていない。 <Musica enchiriadis;非オクターブ的> グイド(そしてHermannも)が、Musica enchiriadisとその突飛なスケールに言及しているその侮りにもかかわらず、両者には、接点があるようである。 Handschinは、それらを認識していた。9 MSが示していることからは、Musica enchiriadisが、10~11世紀において、孤立していた書物ではなかったことが明らかとなっている。10 とにかく、グイドと Hermann は、重要ではない何かを批判しているようには感じない。 p26 Musica enchiriadisの用語で明白なのは、そのスケールが終止音のテトラコードprotus, deuterus, tritus、tetrardusに基づいているということである。(表3)。 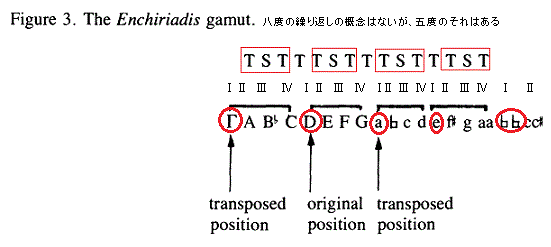 表3 スケールの独自性は、その成分たるテトラコードはdisjunctであり、conjunctではない、という事実に拠っている。すなわち、あるテトラコードのtetrardusと次の上のテトラコードのprotusの間には、disjunctionの全音がある、ということである。 その結果、スケールは一定のオクターブの重複をしていない。一方において、同じ機能(protusのような)は、オクターブの距離では、繰り返されない。(Dはprotusであり、dはtetrardusであり、eはprotusとなる)。他方、すべてのピッチは、スケール度合いがオクターブ上下に相当するわけではない(BはB♭でありbはb オクターブ重複の代わりに、スケールは、五度での一定の重複を具現化している。それは、五度に対するグイドのアフィニタスに相当する。 Handschin が考察したように、Hermannの「お望みのテトラコードを取ってください。さらに、両端にトーンを追加しなさい。」の指示は、 Musica enchiriadisのスケールのその成分たるテトラコードに、正確に、適用されている。トーンは、連続するテトラコードの間のdisjunctionに相当する両端に加えられた。したがって、Hermannの長六度は、 Musica enchiriadisのスケールのそれぞれのテトラコードの周囲に見出される。 Musica enchiriadisにおいては、その作者は、終止音のさまざまな配置の間にアイデンティティを確立することにおいて、Hermannの関心を共有していることが示唆される。 1種類のテトラコードから音階を作成するという考えは、ギリシャ人と同じくらい古いものであった。 しかし、終止音のテトラコードの使用は、明らかにそれほど古いものではなかった。 <HucbaldのDe harmonica institutione> 私は、それを最初に、Hucbald'のDe harmonica institutione見つけたが、その存在はHandschin やOeschによって指摘されておらず、 Weaklandによっても特定されていなかった。 Hucbaldの重要性は、一般に認識されていない。12 12 Oesch、Berno und Hermann、pp。104-6は、Musica Enchiriadisが、終止音のテトラコードを最初に使用したと考えている。 Handschin は、Der Toncharakter、p。 323において、このことに触れているが、終止音のテトラコードを特定していない。 Rembert Weaklandは、「Hucbald as Musician and Theorist" The Musical Quarterly、XLII(1956)、66-84」で、終止音のテトラコードの特定をせずじまいで、その重要性も見通していない。 Weaklandの論文は、Hucbaldに正しくアプローチをしている。「Hucbaldは、ボエチウスから、彼の目的に適するもののみを選び出し、彼の時代の慣行を確認する、あらたな理論を打ち立てた」。 しかし、Hucbaldが使用した、あるいは使用しなかった音調の構成については、さらに多くのことを述べる必要があり、彼の方法は、より具体的な歴史的文脈で設定する必要がある。 p27 Hucbaldは、最初に、ギリシャ語のテトラコードを使用して、Greater Perfect Systemを扱っている。(表4参照)。13 13 私は、現代の読者の便宜のために、文字表記(Γ、A,など)を使用している。多くの学者たちがこの文字表記を”中世の文字表記”と呼んでいるが、実はこの文字表記法は、Dialogus以前、およそ1000年前には存在しなかったことを銘記すべきである。 紀元1000年より前には、標準的な文字表記法はなく、ギリシャ語の名前以外のピッチに名前を付ける標準的な方法もなかった。Hucbaldが、文字のないギリシャ語の名前と格闘していたことにおいて、我々は、おそらくHucbaldと彼の業績をさらに讃えることになろう。 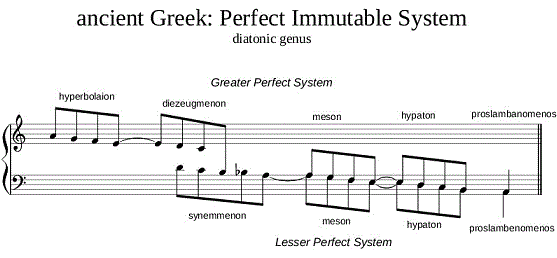 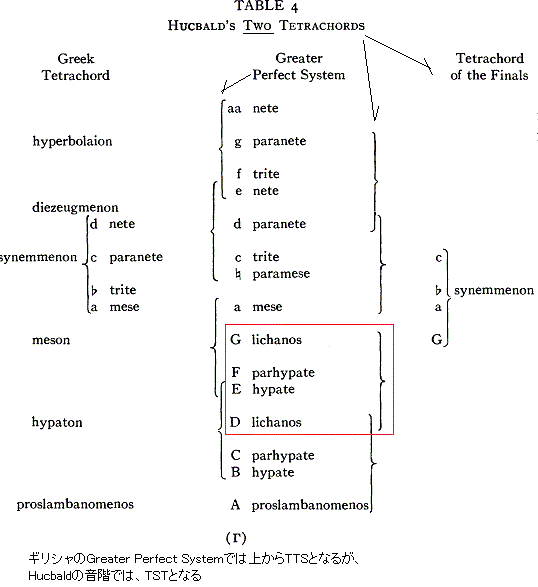 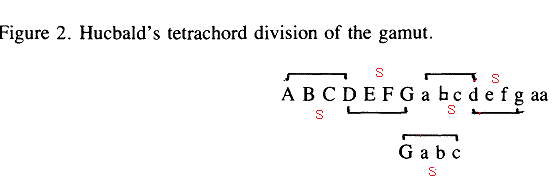 p28 それから、Hucbaldは、今度は異なったテトラコードを使って、Greater Perfect Systemを扱う。このテトラコードは、TST(Greater Perfect SystemではTTS)である。特にその中には(lichanos hypaton、hypate、parhypate、lichainos、D、E、F、G)の、(8つの教会旋法を支配する)4つの終止音のテトラコードがある。 こうしたテトラコードは、ギリシャの理論では機能がなく、ここで明らかに、初めてHucbaldによってGreater Perfect Systemに適用された。 スケールをテトラコードのような小さな単位に表現する目的は何か? なぜ、初期の理論家たちは、完全なスケール-Greater Perfect System-を持っていたのに、スケールのセグメント化を行ったのか? 我々は、別の議論のためにHucbaldが彼のdisposal pitch names (the Greek ones),Boethiusにおいて提案されたさまざまなローマ字表記、および、”声楽”、”器楽”と呼ばれた伝統的なギリシャ文字表記も持っていたというを持っていたという事実に注意する必要がある。 Hucbaldは実際にギリシャ語の名前を使用し、ギリシャ文字表記の1つの改作を推奨した。それにもかかわらず、彼自身が述べた理由により、ネウマ記譜法が普及し、西洋は、Dialogusで初めて、文字式記譜法を使った。14 これから読み取れる一般的な教訓は、教師の個人的教えによる言い伝えは、チャント作品の全体性を維持するためのグラフィックな代替手段よりも信頼性が高かったということである。 代替案がないわけではなかったが、その代替案だけでは不十分であり、つまり、個人的な指導ほど優れていなかった15。 しかし、そうであっても、なぜフランク人のチャントの教師は、わざわざ理論を作成し、概念化し、体系化ようとしたのか? 歌手に関する限り、理論的な問題はない。歌手は、グレゴリオ暦のレパートリーを、暗記することで覚えられるいくつかのメロディーとして学べたであろう。しかし、中世初期の理論家は熱心に、体系的な概念の構築に熱心に取り組んだ。 結局のところ、具体的な答えではなく、一般的な答えで満足する必要があっただろう。これらの理論家はフランク人であった。そのため、物事に秩序を求めたり、課したりするという特徴的なフランク人の反応をする傾向があった。教師として、彼らは日常的な概念を可能な限り迅速かつ確実に伝達する方法を毎日必要としていた。後に、グイドはその速度と効率性のために、彼の方法を推奨しました、他の人たちは同様の主張をした。そこには、歌われるべき多くのチャントがあった。そして、ローマのschola cantorumは暗記に満足していても、フランクの修道院は明らかにそうではなかった。 p29 要点は、フランク人音楽家がチャントを歌い始め、彼のやり方を、その他のことよりもスケールとして、理論的な構成に向かって働きかけたことである。 音楽家とは、歌手であり、教師であり、理論家であった。musica disciplinaではなく、Cantusこそが、彼の出発点だった。彼のカリキュラムは、7,8世紀の修道院学校のそれだった。それより初期には、自由科カリキュラムであったのに対して。17 Greater Perfect System自体は、基本的な仮定というよりは、むしろ理論的な抽象化であり、比較的慣行的経験とはかけ離れた存在だった。 その経験の点では、四度や五度など、扱いやすいサイズが明らかに必要であった。Greater Perfect Systemは、ほとんど理解できない名前を持った2オクターブの文字列として表現されていた。さらに、Greater Perfect Systemには、オクターブモジュールさえ明示されていなかった。なぜなら、上方のオクターブの名前は、下方のそれにはその名前の言及さえないからである。 オクターブモジュール自体もはっきりしていなかった。我々は、オクターブを基本的なスカラーモジュールと考えるのに慣れているため、こうした状況をすぐには認識できないが、フランク人の観点からは、オクターブはモジュールとしては、大きすぎるように見えたのだろう。 初期の理論家たちがオクターブについて語った時、それはしばしば共鳴のアイデンティティーの観点からであった-「男性と少年(女性)が同じ音符を歌うときのように」。また、拡張されたスカラー構成を検討する際には、標準的なリファレンスとして、便利な機械的なモノ、キーボードがないことを念頭におく必要がある。(この観点から、Dialogusにおけるモノコードの熱心な推奨を理解する必要がある。そこでは、そモノコードが、実践的指導のために、真っ先に採用されている。) 言及されているすべての音の構造は、歌われ、耳に保持されなければならない。Hence the obvious advantage of using repertory pieces of chant to illustrate, or rather to embody, tonal constrtions. 我々は、Hermannが、長六度内の終止音の各例について注意深く選んだ例を出したことを理解した。Hucbaldは、ユニゾンからそのオクターブ上までのチャントの説明をした。これは、中世理論の発展におけるチャントのレパートリーの中心的な重要性を具体的に示している。 スカラーモジュールの構造は、その大きさの問題を示している。 p30 最終的に選択されたモジュールの重要性を理解するには、少なくとも800年前に起きた理論的な構造に何が含まれていたかを暫定的に理解することが不可欠である(と私は信じる)。 我々は、彼らが生産した最終産物であるtonary(トーンや旋法にしたがってチャントを分類したもの)のみを知っているに過ぎず、これらの構造がどのように至ったかはわからない。 フランク人によって最初に保存されたtonaryは、795年のMSで発生している。ここに続くものは、tonaryとスケールにつながった発展の重要な瞬間を再構築する試みである。 最初のステップは分類自体であったした。 これは、終止音を基礎に、作品の音符に基づいて実行された。20 チャントは、最後あたりの音符の音程パターンに従ってグループ化された。これと比較すると、残りのチャント部分は、Tを下げ、TSTと拡張する領域(protus+その前後音)を介して動くように認識されたことだろう。 このやり方(グイドとHermannまで続く)は、分類の実用的な性質を明らかにしている。 アカウントが少数のピッチしか取り入れていないという事実は、音楽家がチャント作品の終止音の直前のピッチに集中していたことを示唆している。チャントが終了しても、ピッチはまだ耳に新鮮である。 いくつかの重要な瞬間が、実際にこの分類に続く。中世の理論などの長い発展における最初の決定は、影響の密度によって完全なワークアウトのために世代を必要とするように見える。ただし、最初にいくつかの終止音を共通のスケールで配置すること(基本的には当然のことと考えているステップ)は、実際には分類自体とは異なることに注意する必要がある21。 ピアニストが、メジャーとマイナーが配置された共通の調性システムに気づくことなく、メジャーの楽章が互いに似ており、他の楽章と異なることを観察しながら、ベートーヴェンのすべてのソナタを学ぶことは(類推によって)可能であっただろう。 p31 そのような類推が意味があるとしても、それはチャント歌手に状況自体を想像するための努力を必要とするかもしれない。すなわち彼はチャントのグループを認識し、各グループは独自の固有のセットトーンを持っているが、必ずしもスカラーに気づいていなかったであろうグループをそこに関連付ける共通点に気づく必要は必ずしもなかったことだろう。実際にも、そのような共通点はなかったかもしれない。 ある点においては、終止音は全音階システムに投影されていた。その全音階システムは、その最も単純な感覚においては、任意の2つの半音の間に少なくとも2つの全音が入っている(STTS)ものである。 オクターブのダブりが必要な場合は、さらに条件を満たさなければならないが、伝統的に、全音のペアに第3の全音が加わっている。...STTSTTTS...のように。 ただし、チャントのメロディーは、このようなシステムで要求されるよりかなりの柔軟性を要求する。したがって、Hucbaldが使用したGreater Perfect Systemの全音階システムでは、Lesser Perfect Systemのsynemmenonテトラコード(d,c,b♭、a)が、常に、メロディーによって実際に要求されたピッチを供給するために、呼び出されねばならなかった。 非互換性がさらに微妙に深まり、チャントのレパートリーをGreater Perfect Systemに重ね合わせるプロセスを継続する試みが継続的に発生していた。困難が非常に大きいので、プロセスが知られていない場合、それが発生する可能性があるかどうか疑う可能性があった。しかし、しかし、それは実際に行われ、フランク人が行った必要な修正は、彼らが伝統をある基本的な方法で「理解した」ことを証明するどころか、実際、伝統のために彼らの特徴的な無関心、明確な機知と独創性を示している。 自分の実際的な目的に合わせてそれを適応させて。 Greater Perfect Systemでの終止音の問題の配置について洞察を得るための最良の方法の1つは、従来とは異なる方法で達成されている。 たとえば、lichanos hypaton(D)はmese(a)に配置され、tetrardusとなり、他の3つは番号が付け直された場所にとどまっていた。 tetrardus mese (a) tritus lichanos (G) deuterus parhypate (F) protus hypate (E) この場合、trite hyperbolaion (f)は、しばしば、D-protusにおいて paramese diezeugmenon (b tetrardus は、parhypate hypaton(C)に位置し、そしてprotusと番号づけされる。 tetrardus parhypate meson (F) tritus hypate meson (E) deuterus lichanos hypaton (D) protus parhypate hypaton (C) p32 この場合、”protus”は、通常、G-tetrardusにおいて生じるtrite hyperbolaion (f)のために、常にsynemmenonテトラコードを使ったことだろう。 終止音が最後に実際に配置された方法については、protus と tritus の正格形(tones 1 and 5)は、それぞれ lichanos hypaton (D) と parhypate meson (F)に配置されると、非常に頻繁に b♭に対してのsynemmenonテトラコードの使用を要求するようになる。そして、protusとtritus(トーン2と6)の変格形は常にそれを必要とするので、こうした位置に関する限り、それらはGreater Perfect SystemではなくLesser Perfect Systemにある。 加えて、チャントの現実と全音階システムの理論的抽象化の間のギャップの程度を示すのに十分なその他の臨時記号が、Liber Usualis内にある。(最も明白なのはEaster Gradual Haec diesの開始時である)。 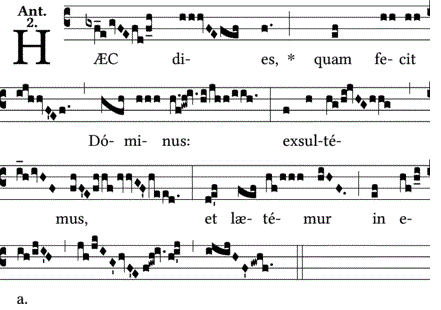 終止音で選択的にポジションを利用できるようになった理由は、Greater Perfect System が、四度と五度で限定された量の重複を組み込んでいたという事実からであった。 四度での重複は、主にconjunctテトラコード間およびその内部で見い出された。(parhypate hypaton、Cは、その隣人のparhypate meson、Fと同様の関係に位置している)。 五度での重複は、主にdisjunctテトラコード間および内部で主として見出された。(mese、aは、 lichanos hypaton,Dと同じように、disjunctionのトーンへのピッチに対するdisjunction a-b 結果として、終止音がlichanos hypaton(D)に配置されるとすぐに、終止音より下の音符Cとその上の4つの音符EFGを考慮すると、同じ終止音、つまり終止音あたりの音程関係の同じ設定が、自動的にmese(a)に現れた。(D-a→a-e) そしてまた、synemmenonテトラコードが使用された場合は、lichanos meson,Gにも現れた。(D-G→G-c(synemenon)) このような代替の配置を「移調」と考えるのは誤解である。つまり、protusが最初に、ある主な位置に置かれ、その後別の副次的配置に移されたということはあり得なかっただろう。 初期の理論家は、最初に、いくつかの選択的配置を知っていたであろう。問題は、正確には、これらのうちどれが主要なものと見なされたか、ということである。 この目的のために適応または考案された一般的なスケールでの終止音の投影は、困難なプロセスであったに違いない。 それは、800年前の時代には、フランク人の理論家が傾注していたことだろう。これを達成すると(少なくとも大まかに)、次の問題は、この一般的なスケールをどのように理解するかということである。モジュールの選択が重要になるのはこの時点である。 p33 そして今、我々は、Hucbaldの解決策-終止音のテトラコード選択-が、それまでの経験の中で最も具体的だったものを使うことの価値を持っていたことを見い出している。純粋に伝統的な構造として、ギリシャのテトラコードを事実上拒否し、Hucbaldは、Greater Perfect Systemの基本的なモジュールとして、それを終止音のテトラコードに代替させた。 彼が伝統的なシステムを再構築することをいとわない程度は、synemmenonテトラコードの彼の取り扱いによって示されている。すなわち、これまた彼は、終止音のテトラコードを lichavos meson (G) からmese (a) 、trite(b♭) paranete (c)までとしている。これは、ギリシャの観点からは、完全に異常な手順である。 一方、Hucbaldは、終止音のテトラコードを基本モジュールとして使用したいと考えていた。 他方では、彼は、伝統的なsynemmenonテトラコードにおいてのように、b♭を要求した。彼のやり方において立っていたその他のあらゆる伝統的観点を無視して、彼は可能な限り迅速に、b♭を供給し始めた。 このプロセスの根本的な瞬間は、 終止音間の関係、つまりある終止音と上下のピッチの関係でのスケールのピッチ領域の拡張を理解することであった。それから、それらが互いに上下するピッチを取った時の終止音間の関係を。 このステップは、いずれかの終止音の外側で、そしてそれを超えて進んだ。言い換えると、終止音のテトラコードの最終的な目的は、終止音のネットワークでスカラー構造を理解するように、特殊な終止音をスカラー構造で理解することではなかった。なぜなら、理解が必要だったのは終止音ではなくスケールだったからである。この違いが、後の発展を前向きに評価することを可能にしている。(まうかめ堂●アフィニタスからオクターヴ種へも参照) Musica enchiriadisは、この観点の最も極端な提唱者であった。 Musica enchiriadisのスケールは、これまでまたはそれ以降のどの西洋スケールとも異なっていた。なぜなら、終止音のテトラコードを、唯一の知り得る要素とし、不変のdisjunctionでそれを繰り返したからである。 その効果は、このテトラコードをスケールのモジュールとして最大化し、普遍化することであり、そのために、終止間の関係が、スケールの内容を完全に理解できるようにしている。終止音の前後の上りと下りは同一であるが、終止音のすべての可能な配置で同じである。 もしあなたが、Musica enchiriadisはなぜグイドとヘルマンに見られる長六度を使用しないのか?と質問するのであれば、その答えは、この六度は、Greater Perfect Systemにおけるその上行と下降が同一となるには限界があることを表しているから、ということになる。 Musica enchiriadisのスケールでは、そのような制限はない。上行と下降は、行きたい限り同一となる。 Musica enchiriadisのこの考えの論理的な結論は、スケールから音域の概念を排除することにある。そして、確かに、Musica enchiriadisはまさにそれを実行することに非常に近づいた。 p34 いずれにせよ、課された音域は非常に恣意的で奇抜なものであり、他の堅実な理論家の推論に容易に同化することはできない。彼は18ピッチで制限を設定している.。23 これは、2オクターブ+増四度の音域にまたがる(文字表記ではΓからcc♯まで)が、理論的根拠はあまりない。18はGreater Perfect SystemsとLesser Perfect Systemsを組み合わせたピッチの数だという説明は、あまり説得力がない。彼はスカラーの構築がどちらの方向にも無期限に進むことにもっと興味があるようで, したがって、すべてのテトラコードが互いに同一の関係にあるので、どこにそれが位置するのか(つまり、”どのテトラコードか”"-grave, finale,...) を知る必要はなかった。 すべての理論家たちがこれらの用語で考えているわけではない。実際には、ほとんどの理論家は、指示対象としての範囲の範囲、重複、および一般的な固定性がより大きな役割を果たすスカラー指向にある程度傾いた。 もっとも極端なのは、Dialogusである。さらにまた、DialogusとMusica enchiriadisを比較することで、初期の理論家が互いに独立していたことが把握することができる。 我々は通常、Dialogusをオクターブ重ねの提唱者と考えているが、これはより広い意味でのみ当てはまる。Dialogusには、文字通りでの完全なオクターブ重複がない(b♭とb 究極的に、Dialogusはスカラー構造の理論的根拠に依存せずに、メカニカルな音響的な楽器であるモノコードに依存していた。それは、Greater Perfect Systemよりもしっかりとピッチが固定されていた。 Dialogusは、他の理論家らによく見られる体系的なスカラー構造(四度種、五度種のように)からはたいへん自由である。Musica enchiriadisとDialogusとは、片やその終止音の関係の使用において極端な機能主義であり、片や、弦における計量ステップに頼った極端な操作主義であるという、二枚開きのようなものと言える。 Hucbald、Musica enchiriadis、Dialogusを背景に(表5を参照)して、GuidoとHermannは、先任者によって提供されたさまざまな抜本的な解決策を互いに、また音楽の実践の現実と調和させることに関心があった穏健派と見なすのは容易である。(11世紀までにでも、グレゴリオ聖歌以外の多数のレパートリーがあった) グイドは、Dialogusのモノコードスケールから始まり、7音や、オクターブ指向、octaveを重ねる厳密な全音階スケールを強調していった。同時に、彼はアフィニタス、つまりさまざまな場所での終止音の関係を根本的に探求し、最終的に、これらのアフィニタスを、終止音のテトラコードを囲む長六度の観点から表現した。 p35 Hermannは、四度種と五度種について,彼の師であるBerno of Reichenauによって強調された点から始まり、最初は、終止音の繰り返されるテトラコードとDialogusのスケールの間の不具合を調整するためにそれらに依存し、最終的には、同じ長六度に至った。そして、ヘルマンの.discussionでは、この長六度は、ためらうことなく同一であるべきだと思われていたヘクサコードに非常によく似ていた。24 <以下、HandschinのDer Toncharakterへの批判> しかし、Handschinはためらった。そして、この点についての彼の考えは従うのが難しいが、彼の言ったことに同意するための試みが行われなければならない25。 Der Toncharakter(p。335)の特にHandschinらしいパッセージで、彼は、長六度が、全音階システムの2つのストレッチ( "Ahnlichkeitsdoppelreihe")間の類似の遵守以上のものであることをおそらく否定し、グイドに関する限り、「移調が可能な」ヘキサコードによるこの「列」の同定を否定している。 これらの拒否の背後には、「移調可能な」エンティティとして使用された時(たとえば、Fまたは中世の理論家が最終的にそれを置いた他の音符のいずれかに置かれた時)の、ヘキサコードに基本的な不信がある。 p36 そして、長六度に対しての終止音とそれらのアフィニタスとの結びつきを指摘して、Handschinは、ヘクサコードとは単なる「移調可能な」実体であるに過ぎない、そして the seven-tone, octave-duplicating scaleの基本事項を歪める不毛な慣行だ、と感じていた。 この一連の信念は、初期の理論と後期のヘクサコードの間の重要な関係、またはヘクサコード自体における本当の重要性を彼が拒否したことに関係しているようである。 だがそれは反対であり、長六度とは、実際にはHandsschinが、「本質的な音質の列」( Qualitdtsreibe)ではなかったと言っていたもの(そして彼は、インテリジェントな人物、特にグイドがこの結論に達することができないことを暗示した)である、と私は提言する。 これらの用語を説明すると、Der Toncharakterの理論に深入りすることになるが、「音質」の本質的な特徴は、初期の中世に由来するか、少なくともそれによって表現できると主張しているために、私の立場を十分に定義している。 グイド(ヘクサコード)とHermann(長六度)の長六度は、本質的に、終止音のテトラコードであり、それぞれの「性質」のサマリーである。そして、後のヘクサコード理論は、長六度と終止音との初期の関係のシステム的適用にすぎないのである。 私が提案した方法で問題を検討することは、全音階システムよりも終止音の関係に、より大きな音の現実感をもたらすことに拠っている。 明らかに、これは中世の理論家を含む誰もが異なる意見を持つことになるポイントである。 私が言おうとしているのは、終止音の関係は、少なくとも一部の中世の理論家がそのように考えていたためと、これらの関係が中世理論の発展を理解するための実り多い基礎を提供していることから、私たちが与えたよりもはるかに深刻な考慮を払う必要がある、ということである。 Der ToncharakterでのHandschinのオクターブ全音階についての強調は、五度圏からこのスケールを産生することへの彼の好みに基づいている。26 この見方と、中世初期のカンター教師の特徴に対する私の見方との対立は、 2つの声明で要約することができる。すなわち、「使用されるピッチは、所与のピッチから一方向へと進む五度から得られる」というものと、それと対照的な「使用されるピッチは、チャントの断片に見られるとおりである。」 ということである。 彼自身の理論的な立場から、私は、Handschinが、少なくともGuidoの理論がHandschinの理論に適合する点で、Guidoを支持したと思う。 なぜなら、Guidoにおける一貫性は、Handschinが主張するよりもはるかに低いからである。 しかし、いずれにしても、グイドは中世の唯一の理論家ではなく、唯一の良い理論家でさえないのだ。 p37 Handschinは、グイドの七音全音階という重要性を強く主張した。 したがって、彼はテトラコードの無制限の「移調」によって展開された半音階システムを恐れた。 ここでも反対の態度は対照的なステートメントで表すことができる。「移動可能なhexachordは、全音階的要素のカウンターである」に対して「移動可能なhexachordは、終止音間の関係の再確認であり、それがどこにあるかは関係ない。」 残念なことに、Handschinは、基本的に理論、より具体的には「ToncharakterではなくTonpsychologie」に焦点を当てた本の中で、この重要な問題の議論を引き受けたと思われる。 終止音の間など、音の関係を1つでも確認する場合は、音の場全体を説明するために力強く体系的に拡張すると、最終的には解決できない問題が発生することを認めなければならない。しかし、これらの問題は必ずしも関連する概念の歴史的状況に反するものではない。 Handschinによって提起された異議は十分に現実的であり、やがて中世の理論家に起こったことである。違いは、Handschinがそうであるように、理論の観点からそれらを提起し、sub specie aeternitatis※(永遠の相の下に)の結果を判断して進むのか、それとも歴史の観点からだけであるのかである。後者の場合の判断は非常に異なり、それ自身の時代においては、ヘクサコードの重要性と有用性に影響を与えない。これは、16世紀までは、チャントとポリフォニーの両方の中心的な概念であった。27 人は、誤解の膨大な蓄積、不正確または無関係なものとしての中世理論の歴史について考え続けることができる。すべては、ラモー、ヘルムホルツ、リーマン、またはシェンカーによって排除され修正されたが、それは実りのないプログラムであり、特に中世の問題への対応として、中世の概念を独自の用語で理解する。 ※ オランダの哲学者スピノザの言葉。永遠の相のもとに万物を認識するの意で,神のもとにおいて認識することを意味し,真の認識であるとされた。 |