| Mozart's
Requiem3 |
音楽エッセイのページへ戻る
| Mozart's Requiem1(p107~) |
| Mozart's Requiem2(p117~) |
| Mozart's Requiem3(p129~) |
| Mozart's Requiem4 |
| Mozart's Requiem5 |
| Mozart's Requiem6 |
| Mozart's Requiem7 |
| Mozart's Requiem8(p234~) |
|
Sounds and
strategies in the Requiem Dies irae Dies irae,dies illa, 怒りの日!その日こそ、 Solvet saeclum infavilla 世界が灰燼に帰す預言が満たされる。 Teste David cum Sibylla. それはダヴィデとシビラが警告した通りである。 Quantus tremor est futurus, その恐ろしさはどれほどか Quando judex ext venturus, 裁き主があらわれ、 Cuncta stricte discussurus! すべてが裁かれる。 Thomas of Celano'の13世紀のラテンの賛美歌「Dies irae」は19節あり、、レクイエム・ミサのセクエンツィアを構成し、モーツァルトは6つの楽章に分けている。モーツァルトはその最初の2つの節をDies irae'の楽章とし、怒りの日とすべての永遠のための裁きの恐れに関心を持ち、(イントロイトのように)詩の形式が音楽形式を規定している。 曲は、3つのセクションに分けられる。全テキストを含む第1セクション(第1−19小節)。全テキストを含む第2セクション(第22−40小節。器楽の間奏あり)。Quantus tremor est futurusと Dies irae,dies illaの2回の交換(主にドミナント上にあり、、カデンツは第53小節(正確には第52小節のアウフタクトから)以降の第3セクション。となる。 モーツァルトは、声楽部位と器楽のチェロバスの他に、第1ヴァイオリンのために、68小節中43小節を作曲した。一見して、この初期の記譜の局面で、オーケストラのパートをこれほど書いていることや、その割には手がかりが少なすぎて、まだ記譜していない部分のための十分な助言メモが提供されていなかったことには驚くかもしれない。。しかし、詳細な検討では、ヴァイオリ素材の状態は、モーツァルトの細心の注意によって、響きのニュアンスは説明されていた可能性があり、この素早く、熱狂的な楽章の伴奏はほとんど変更を要しない。 第1、第2セクションの始まりのテキストへのヴァイオリン伴奏の比較は、ポイントとなる。第2の設定は、より頻繁かつ大規模な跳躍(第22-5小節、特に28小節)を含み、3つの音符による和音は、第26、31小節の下降音型へのウェイトを強めた10度や11度を横切る。そして、ヴァイオリンの増加した運動能力を例証している。 2番目の設定のバイオリンパートもボーカルラインから独立している。最初の4つの小節(第1-4小節と比較した第22-5小節)は、短三度で上がっているが、ソプラノを追跡していない。 そして、第26-7小節は、第5-6小節よりも、若干、技巧的で華やかであり、2オクターブ以上にも広がっていく。2番目の設定のこれらの新しい特徴は、先立つ楽器の推移(第19-21小節)で示されている。冒頭の第10回の跳躍は、これまでの最大の楽器の飛躍であり、もともとの楽器の推移(第8-10小節)は保たれているが、バイオリンやバスのためのギザギザのラインがさらに残る。モーツァルトの新しい、楽器の響きは、Dies iraeテキストの2番目の設定に参加する楽器の参加の強化に寄与している。。 伴奏スタイルの発展は、楽章の第3セクション('Quantus tremor est futures 'と' Dies lies illa '間の対話部分が、ユニゾンでヴァイオリンと並置されている。ヴァイオリンは奔逸しており、角張っている)でさらに重要性を増している。(see bars 40-8、Example 4.10)。  Example 4.10 p133 セグメントの間のコントラストはまた、セグメント間のスイッチ(12度 in bar 44、beats 2-3)でのヴァイオリンの12度凋落によって、そして第48小節の第2−3拍間の2オクターブ、そして、第44−6小節の'Quantus tremor est futurus' (先立った 'Dies irae'への頑固な無反応として来る)の逐語的繰り返しによって、前面に出される。 ('Quantus tremor est futurus' と 'Dies irae'の)対話は明らかに対立していない。コントラストのあるセグメントは、テーマとしては似ており、オーケストラ部分(少なくともバイオリンの注釈で表される部分)は、1つのセグメントまたは他のセグメントと明示的に配列されていない。音楽は「恐怖」(「Quantus tremor est futurus」)と「怒りの日」(「Dies irae、die illa」)の間のテキストの衝突を強調している。第50-2小節では不安定な寛解が続き、「Quantus tremor」はテーマ的に、この小節より、多くの声部において波及しており、Dies iraeのためにリザーブされた、前の表現(ra-ra sol-ra-sol-ra-sol-ra-sol-ra si-la)を和声化する。 「Cuncta stricte discussionurus」(第57-66小節)での楽章の終わりにはっきりとした協調的対話が続いており、ヴァイオリンはセクション2の最初の部分や最後のセクションの早い段階でのDies iraeのセグメントから独立した16分音符に再び戻ってくる。 私たちが、Dies iraeにおいて、モーツァルトの進化的な器楽の役割を理解する方法は不明である。第1セクション(bars 1-19)のテキストの最初の完全なstatement の冒頭で、バイオリンと声楽の間の密接な配列は、第2セクション(bars 22-40)の第2のstatementにおける大きな器楽的独立に、第3セクション(40〜)の最初での並置した配列と独立性に、そして最後は、楽章の最後の12小節(第57−68小節)における扇動された独立への回帰に向かうことになる。私たちはモーツァルトから、強力な楽器音 - 盛り上がる飛躍、シンコペーション、和声、低い盛り上がりと活気あふれる角々しさとのコントラスト‐を打ち破り、一括して処理する方法について明確なリードをされていない。 しかし、イントロイトのように、不安定さは確かに鍵である。モーツァルトは、すべての永遠のための判断の恐怖を伝えるテキストを設定することで、音楽的な不安を育てている。そして、熱狂的で熱狂的な(おそらく恐ろしい)16分音符の後、私たちは楽章の最も急峻な器楽の跳躍の二重化で終わる(最終小節のレ音の2オクターブの跳躍)。怒り狂った、騒がしい、絶え間ないエネルギーは、音楽の空白に不安定に共鳴する単一の音符において、最高潮に達する。 Tuba mirum
Tuba mirumは、「すべての王座」を呼び出すトランペットによって開始された判断の過程を記述している。トロンボーンとバスソリストの間の対話、テノール、アルトとソプラノの連続ソロ、そして4人のソリストの最終セクションである。 単一の音符がDies iraeで記述されていた怒りと恐怖を終わらせるように、非常に異なる単一音符(トロンボーンのb♭)がTuba mirumで説明された判断過程を開始する。トロンボーンの音は、第1,2小節でうつむく感じで、すばやく声楽と相互連携する。冒頭のトロンボーンの声楽の模倣は、メロディが両者の間で有機的に成長するような甘美な交換をもたらす。下降する分散音は、その後はトロンボーンの上向きのアルペジエートの連続になる(第4-6小節)。第6−7小節のファミレのトロンボーンの音は、バスソロのレ度ドシ(第7小節)によって継続される。 第11−13小節のトロンボーンと第10−13小節の声楽は、自発的かつ相互に依存しているように見える(下譜)。第15小節のトロンボーンの上昇音型は、前のフレーズが終了する声楽の続きからはじまる。声楽とトロンボーンは切れ目なく織られて連結する同じ職布から作り出される。掛け合いとしては、それは、「フィガロの結婚」における「手紙の二重唱」における声楽と楽器の永続的な交換と同様である。モーツァルトの教会作品においてこれに相当するのは、未完のハ短調ミサK427における 'Et incarnatus est'における管楽器とソプラノの掛け合いである。  ↑フィガロの結婚「手紙の二重唱」 Tuba mirum(第18‐44小節)の中間部分には演奏上の注釈は見られないが、声楽フレーズの間の連結は、先立つ声楽素材から直接由来するモーツァルトの器楽バスライン(第23,28,36小節)に現われる。楽章の冒頭からの楽器と声楽の間の断続的な交換はなくなった(またはまだ作曲されていない)が、イントロイトにおけるような声楽ステートメント間のスムーズな推移の促進剤として残っている。バイオリンの 'Cum vix Justus' (小節44-5の例4.13)へのリードインは同じ機能を果たすだけでなく、明らかに弦の新しい役割、すなわち単にメロディーを受け取るのではなく、先導を開始する。 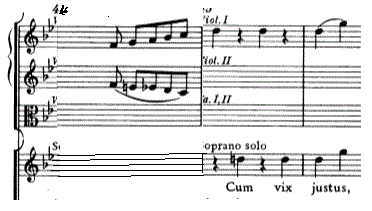 (例4.13) 「Cum vix justus」の3つのステートメントのそれぞれは、異なる、独特の強調をしている。最初(第45小節)は、2つのバイオリンパートに先行して、バイオリンとソプラノの1音符づつの繰り返しを特徴としている(第45小節)。次(第51小節〜)は、最初の4人のソリストの同時のエントリーで、sotto voceの指示とそして数小節後のより精巧なバイオリン(第52-4小節)の同時エントリーを含んでいる。3番目(第57小節〜)は、最初に三重音であるフォルテ・ヴァイオリンを特徴とし、フォルテとピアノの間で振れが続く(小節57-8)。楽章の控えめなクライマックス(bars 59-60)は、モーツァルトが。レクイエムスコアに入記入した唯一の2つのクレッシェンドのうちの1つを含んでいる。 Dies iraeとIntroitのように、Tuba mirumにおけるモーツァルトの楽器の響きと効果すべてにどのように対処するかは不明である。これらは、3つのステートメントのそれぞれが新しい響きと効果を提供するCum vix Justusの弦のために適度に花開く。Tuba mirumの最後のverse(Quid sum miser)は、テキストが抽象的な記述から個人的な反応に変わる唯一のものである。弦楽器の終止における声楽の取り扱いは、慈悲が必要とされていることを示している( Cum vix Justus sit securus?)時に、恐れと疑いに直面して、オーケストラ的慰めとして解釈されることができた。しかし、テキストがトランペットの音を直接記述しているところでは、楽章の冒頭でのトロンボーンと声楽の織り交ぜがはっきりとできていることと同じようなことは言えない。 実際、モーツァルトがここで慰めと同情を意図しているのであれば、それらはテキストの意味を強調しない。もう一つの不自然な音と効果の配列で、私たちは、軽い音の混乱がテキストの神経質な不確かさをサポートすることを意図しているのか疑問に思う。 The Sequence:Rex tremendae Rex tremendae majestatis, 恐るべき御稜威の王よ、 qui salvandos salvas gratis, 救われるべき者を無償で救われる salva me, fons pietatis. 慈悲の泉よ、私をお救いください Rex tremendaeはセクエンツィアの8番目のverse を設定し、Dies iraeやTuba mirumのように、3つの明確に区切られたセクションに分かれている。2小節のオーケストラ導入部分を伴うホモフォニックな第一の部分「Rex tremendae majestatis」(g-Vg、bars 1-7); 声楽と器楽の2本の流れにおける、中間のホモフォニー的部分を伴う対位法的設定(gF:dV / d、バー7-17))、そしてホモフォニーの 'Salva me、fons pietatis'(V / dd、bars 17-22)である。 モーツァルトは、楽章全体にわたって、第1ヴァイオリンを書いている。ヴァイオリンと器楽バスとの進化した関係は、モーツアルトがなぜバイオリンを全体的に記譜したのかを説明している。第1-4小節のオクターブでのヴァイオリンと器楽バスは、最初のセクションで配列されている。そして、最後のセクションで再度(オクターブで)一緒になる。中間セクションの中間では、その擬似的な対位法は、声楽のホモフォニーと一致して、第11小節の3つの拍で解消される。。 38 第6小節第2−4拍と、第20小節第2拍〜第21小節第4拍には、休符なしの第1ヴァイオリンの2箇所のギャップがある(下譜)。アイブラーとジュスマイヤーは共に、2番目の方には弦楽器をつけているが、最初の方はそうしていない。(訳注;ジュスマイヤーは、管楽器で対応している。なお、この問題に関しては、Rex tremendaeも参照のこと)。  第6小節  最終部分 冒頭と終止のセクションの器楽的関与の間の平行関係は、和声学的、音響学的に一致している。救いの嘆願(Salva me)は、受け手に対する別名を呼び起こし、Salva me、fons pietatisが冒頭の反転を示した時に、強力な、分離された「Rex」の声明を反映するよりもやや崩れた形で冒頭を再演するとき、王の権威は憐れみの泉となる。 ヴァイオリンとバスパートは第17小節第2拍で(ユニゾン)で再配列され、モーツァルトはそこに、piano と tasto solo(オルガンによる和声付けなしで)のマーキングをしている。彼はバスの下降リズムを残している。 (バスには付点リズムがない)。そして、最後の小節まで、フェードアウトしていく。4声はすべて、 ホモフォニー的に、第 3-5 小節、第6-7小節にそれぞれ集約されるが、そのインパクトは、pianoのディナミックを通して最小限に抑えられている。 第 1-3 小節および第18-22小節における和声進行は、第 1-3 小節がi―iv―ii6―i6-4―V―i、第18-22小節がi―vi―♭ll6(ナポリの六)―Dim.7―i6-V―iとなる。第20小節のナポリの六は、機能的なハーモニーとして楽章に対しては新しいが、第4小節のト短調の副和音としてのE♭を、強調というよりは従属的なものとして、再度使われている。  内部的対応と相補性とは無関係に、Rex tremendaeの終わりは、Dies iraeの終わりとの親和性を持っている。Dies iraeのテキストの不安とRex tremendaeのテキストの嘆願とは、部分的には、前者の音楽的なエーテルと後者の最終小節での死にかけにおいて、爆発的な第1ヴァイオリンのレ音の響きを説明するかもしれない。しかし、つながりは深くなる。短い楽章である両者は、Rex tremendaeの驚異的な感動と激しい統一的な発言で、オーケストラだけで伝えられた最終小節での不安定な暴力(Dies irae)と征服(Rex tremendae)を終わらせるだけのための記念すべき強制的効果の鎧を差し出す。 Rex tremendaeの第1ヴァイオリンのための最後の3つの音符についてのモーツァルトの注釈は、何ら素材提供されない2小節分の長い空白のあとで、この瞬間に正確な効果を生み出したい彼の願望を示している。外見上無害なニ短調の分散音は、第3拍までをオフビートになっていて、初期の記譜段階で注釈を付けるのに十分重要である。 控えめな結論をマークすることに加えて、Introitの冒頭に対する音調のリズム的で身振りの言及は、NiemetschekとArnoldが賞賛する手段の節約性を示しながら、Recordareへのそして/または静かな楽器の冒頭の場面の設定となるのだろうか?そのような解釈はもちろん、見る人の目と耳にある。モーツァルトの不完全なスコアは、構成戦略と優先順位の半分を明らかにし、彼の響きの環境とその意図を特に想像力豊かな解釈で表現している。 |