| Mozart's
Requiem5 |
音楽エッセイのページへ戻る
| Mozart's Requiem1(p107~) |
| Mozart's Requiem2(p117~) |
| Mozart's Requiem3(p129~) |
| Mozart's Requiem4 |
| Mozart's Requiem5 |
| Mozart's Requiem6 |
| Mozart's Requiem7 |
| Mozart's Requiem8(p234~) |
|
Requiem sounds and strategies in
context モーツァルトの手になる未完成な状態において、レクイエムの自筆譜は、音と効果に関連する戦略について特に鋭い視点を提供する。しかしモーツァルトの教会音楽のこの領域への関心は、レクイエムに限られていない。長期にわたる音と効果の進化は、レクイエムにおけるリンクとコントラストを含んでいるが、K427 とK618を特徴づけている。モーツァルトは彼の友人Anton Stollに、K317 とK275 を送ることをたずねている。聖シュテファン大聖堂での演奏の可能性を取り上げて。そこはモーツァルトが後に、補助カペルマイスターとなるところであった。 モーツァルトは、大聖堂で聴いたK337のための最初の所有の演奏資料(もはや現存していない)。これら3つの作品、その後、K. 427(ウィーン時代の彼の唯一のミサ曲)とともに、新しく作曲された「Ave verum corpus」は、レクイエムに向かう際のモーツアルトの音楽意識に大きな影響を与えたことであろう。 <K317> モーツァルトは、レクイエムと同様、K 317(1779)の音と効果の魅力を示している。たとえば、Kyrieにおけるリンクとコントラストは、開発され、変更され、変換される。コントラストのある音は、fとpの間の振動と、とりわけ、声楽にリンクして機能するさまざまな楽器の素材(木管楽器の持続音符と弦の厳密な付点八分音符)の両方で、最初の5小節で直ちにプロモートされる。 付点リズムが取り除かれ、弦と管の両方八分音符は、ホルンの持続音と一緒に、第5小節の第4拍から第7小節の楽章のpiu andanteソロ部分へのスムーズな器楽の移行を担う。mf と pの間の揺れにおける冒頭のコントラストを言及して。四分音符2つ分遅れてソプラノソロのpiu andanteのテーマを模倣し、オーボエが一緒に参加し(第9小節。トランペットを伴って)、声楽フレーズの間(bars 11. 13, 15)を16分音符で従っている。第21小節でMaestosoで再現され、弦楽器の付点リズムは、先行してpianoで聴かれる。続いて、第26-30小節で声楽とトロンボーンの対話となり、同時に、pianoのオーボエ(第28、29小節)とともに、楽章において、最初に現れたものとは対照的に、今や普遍的な楽器のテクスチャに完全に同化されている。 最後の2つの小節では、戻ってきたpiu andanteのテーマと(弦楽器の)16分音符の付点リズムが、声楽の出口を楽章の終わりまでエレガントに結合している。 レクイエムにおけるDies irae, Tuba mirum. Rex tremendae, Confutatis ,Domine lesuのように、K.317のKyrieのサウンドと効果は、この場合はコントラストのある音を徐々に調和させて、楽章を超えて発生し、発達する。 K.317のKyrieにおけるフォルテとピアノのコントラストの継承は、クレド(例4.25)の「Et incarnatus est」でさらに取り上げられている。ここでの音楽的な大転換は、明確で妥協のないものである。合唱からソロに至るまでの積極的なフォルテの弦からミュート、ピアノの半音の第1ヴァイオリン、アレグロ・モルトからアダージョへ、大音量のbassiから和音のないオルガンまで、そして、全音階の力強さから半音の、調整的な不確かさまで(f- A flat -E flat, bars 60-4)。Ignaz Arnoldによれば、これは簡潔で節約的な効果(レクイエムにおいて多くあったように)であり、この事例ではKyrieに戻って、引渡しの瞬間の衝撃でのパンチだけでなく、直接の範囲を超えた響きをも包含している。そして、モーツァルトのレクイエムのすべての楽章と同様に、単一の効果が「Crucifixus」(第65−71小節)の関連する効果を生み出す。 モーツァルトはトロンボーンと第2バイオリンを導入し、傑出したオーボエとともに、ソニックアンテを上げ、pからfへさらにppへと動き、再びKyrieのダイナミックなオーケストラ効果を呼び出す。 「ne perenni」や「Oro supplex」(Confutatis)のように、「Et incarnatus est」と「Crucifixus」は、作品の中の他の材料や出来事から取り除かれて、関連しているように見える、独自の表現豊かなバブルにおいて存在している。 <K337> モーツァルトの次のミサ曲であるであるK337のAgnus Dei もまた、新旧の効果を統合している。全体として、クレドはグロリアの大胆な壮大さを、Kyrie の精緻な器楽的な関与と結びつけている。後者は特に「Crucifixus」において明らかである。 'ex Maria'と 'Passus et sepultus est'でのオボーとファゴットの持続音とターンのような音の間では、木管楽器は「Crucifixus」で、声部と小節ごとの揺れの音型を交換する。その間、持続音もまた、周りを巡っている。ミサの結末では、'Dona nobis pacem'の最後の4小節において、モーツァルトは、Kyrie の最後と「Et incarnatus est and Crucifixus」の繊細な器楽効果を呼び起こす。モーツァルトは初期の「Agnus Dei見られた、ソロ・ボイス、オーボエ、ファゴット、オルガンの織り交ぜた対話に戻る。モーツァルトはミサ曲を、最後から5小節の大きなハ長調のカデンツで終了させることができたが、和音的に静謐で、巧みにスコアリングされた終わりの句を追加することを選択し、作品全体にわたる音と効果の進展、祈祷、および関係に注意を払うことを示した。 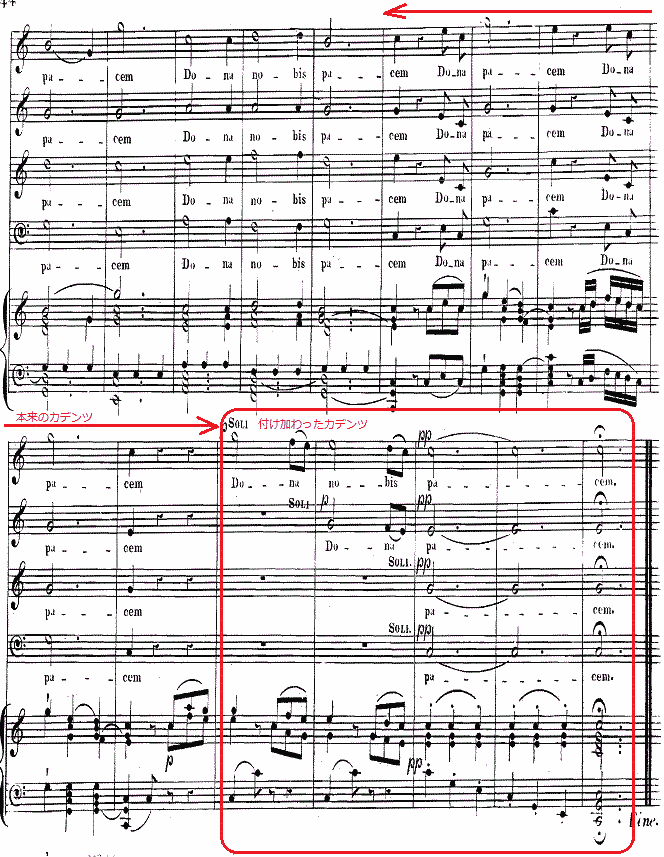 K337 最後の部分 <K275> モーツァルトは、小規模の変ロ長調のミサ曲K. 275(恐らく1777年、2つのヴァイオリン、バスと3つのコラ・パート・トロンボーン)と「Ave verum corpus」において、器楽の音と効果のニュアンスに鋭敏である。K.275のKyrieへの弦楽伴奏は、第4小節の終わりに明示的なリンクに進化する第2、3小節の声楽における寄与の間で事実上のリンクを提供する反復する八分音符から始まる。最初の「Christe eleison」では、第1ヴァイオリンは、ソロ・ボーカル・エントリー(第8,10,12小節)のそれぞれに、八分音符のアップビートを提供し、第2バイオリンはもともとの「Kyrie eleison」の伴奏を16分音符とともに装飾する(第15-17小節 )。 'Christe'(第19-20小節)の八分音符を基本とした伴奏様式には、声楽によるメロディのサポートが含まれている。小節の終わりの反響は、本質的にリンクとメロディサポートの役割を結集して、次の「Christe」(第27,28小節)を迎える。最終的な「とどめの一撃」(第30-3小節)では、モーツァルトは、第1-6小節以来使っていない元の3回繰り返し音符の伴奏に戻って、初めてキリエ・エリソンの素材にヴァイオリンの反響効果を適用する。先行する伴奏素材と密接に関連しているにもかかわらず、突然のpianoダイナミック(第30-1小節)、および新しい素材との関連(第32-3小節)によって、その効果は強調される。したがって、K. 275 のKyrieは、(比較的初期のモーツァルトの教会作品における)Arnoldの言う、目立たずに進化する伴奏を例示しており、それぞれ新しい音型は、先行するものの自然な結果として現れる。 <Ave verum corpus> "Ave verum corpus"はレクイエムのようではあるが、内容は小規模であり、メロディの内容の発信源であり、スムーズな移行の代理であり、個々の響きを”真正な”効果として、器楽のリンクを促進している。第6,7小節の第1ヴァイオリン  第29小節において、3つの四分音符に対して段階的に上昇する2つのヴァイオリンを含むつながりは、引き続く連続における3つの下降する四分音符を生じる。声楽は、器楽とのつながりを持っている。  個々の不協和音も独特の効果を作り出す。第1ヴァイオリンとソプラノ(第15,37-8小節)のd ''とg ' - d "は、唯一の不協和音である。altos, tenors and bassesからの声楽の寄与を中心に、協和音化されたリンクとは対照的である。レクイエムのように、モーツァルトは進化するプロセス(リンク)と独特の産生物(調和していない音程)の両方に目と耳で、音と効果について同時に広範かつ正確な視点を維持している。 <K427> モーツァルトの最も重要で重要な教会作品の一つとしての地位を考えると、K. 427は必然的に、採用された音と戦略に関してレクイエムと比較されることになる。 そうすると多くの相違点がある。(K. 427の)より大規模な木管楽器の集団は、モーツァルトによって完成されたレクイエムの木管楽器の集団よりも、明らかに多弁である。しかし時間を越えて、オーケストラの効果を強調したり発展させることに関しては、同様である。(K. 427の) Kyrieでは、楽器の移り変わりは、レクイエム全体と同様に、広範囲にわたる音の影響をもたらしている。 最初のKyrieのセクションでは、金管楽器の反復音符は、合唱のための積極的なサポートを含んでいるが、その後は異なった機能を果たしている _K427_Great_Mass_in_C,_FS.pdf 例えば、「Christe」への移行は、オーボエ、ファゴット、ホルンで軽く繰り返されるpianoの八分音符から成っている。ト短調を維持しながら、第33小節における変ホ長調のドミナントと同様の扱いで。Andante moderatoの反復する八分音符の慰めのような性質は、「Christe」自体の反復的な木管楽器の部分(オボーとファゴット、小節62−5)の中に適度に浮かび上がっている。 「Kyrie」の「Christe」への移行は、終わりの時点で事実上、再解釈されている。そこでは、完全な木管楽器と金管楽器の響き(第93-4小節)は、楽章の終わりへの声楽貢献の最後に引き続いている。それは、ppで、6拍にわたる楽章中で2番目に長い完全な響きである。 それは、レクイエムのIntroitの終わりに似ている。強力なサポート(イントロイトのトランペットやティンパニ)として以前に使用された楽器を微妙に取立て、それによってその楽章の最終小節に表面上新しいインストゥルメンタル・エフェクトを作り出す。それはまた、 microcosm中のKyrieからの木管楽器の参加をさせ、完全な木管楽器の音を提供し、移行への代理行動をする(楽章の終わりまで満ち足りていて、グロリアの大胆な木管楽器サポートにつながる)。レクイエムにおけるセクエンツィアの楽章がイントロイトの不安定さを作っているように、K427のグロリア終わりもまた、キリエの終わりを作り、フルの管楽器は、piano または pianissimoにて、声部の強力なサポートをしている。それは、声楽の出口から楽章の終わりへの架け橋となっている。(グロリア第56-60小節、そのオリジナルは第27小節から)。 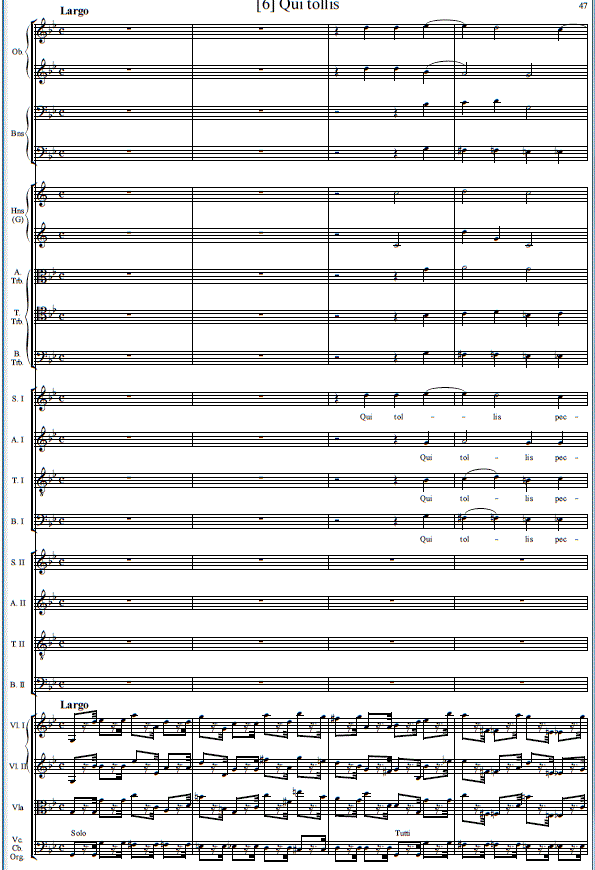 K 427 'のQui tollis'の初めと終わりの移行期の内容における特別なインストゥルメンタル・エフェクト - 弦の緊張した付点リズムの最初の(そして唯一の)無伴奏の提示と、木管楽器のリズムの唯一の長い反復 - は、楽章全体にわたる器楽の響きと役割を進ませることを再度強調する。 この機会に、モーツアルトは、弦と木管楽器と声楽によって提示された対照的な素材を段階的に調整する。 弦楽器の伴奏と木管楽器とが隣接した冒頭の独自の弦楽器の伴奏形(第3小節)は、相互に補強し、厳格で、離接し、ぎざぎざとなった伴奏が流れるようにほとんどくっついた声楽と結びつけば、別の興味を引く。素材は部分的には、第13-18小節と第26-32小節において調整され、あらたに結合した伴奏はシンコペートされた声楽を追跡するが、元の 'Qui tollis' の声楽素材の再現と関連して、(両者の)一致は、もとのコントラストの突然の再開に伴われている。 第43小節からの対応するパッセージは、素材の長引いた統合を目撃している。第43−7小節において、弦楽器は声楽の輪郭に従う(その前の「第15−18小節の"miserere'のように)。第48-50小節では、木管楽器と声楽が、小節ごとに1つの伴奏に関連した付点リズムを採用して、和声の強調(減七度)が、声楽とオーケストラのグループによって、統合される。そして、第52-5小節では、弦楽器での反復する音符がソプラノをフォローし、木管楽器が適度に光るようにし、最後はppで木管楽器に(そのパターンを)譲り渡す。多くのレクイエムの楽章のように、モーツァルトは"Qui tollis' の冒頭で特殊なオーケストラ効果を強調し、最後には、Ignaz Arnoldによって賞賛された、複雑に発展した伴奏書法の間で、別のものを取り入れている。 K427は、レクイエムのように、長時間にわたる個々の響きと効果の共鳴に対する感受性を最終的に実証している。 レクイエムやウィーンにおけるピアノコンチェルトの自筆譜のように、モーツァルトは、K. 427の自筆譜における器楽の細部に、細心の注意を払っている。明らかに無害な内容に対してでさえも。キリエにおける第24小節の第1拍のファゴットの四分音符は、第25小節へ合わせて全音符に改訂され、ファゴットはオーボエと結びつき、木管楽器のフォルテの持続音を若干強調している。tutti context と the bassi partは、低い音程に変わった、ヴァイオリンパートにおける反復する八分音符のラ音とともに、Laudamus teの最終的なトリルに直接走り、明るくなる。その間、ソプラノソロの段階的な上昇は、低いド音からはじまり、もともとの版よりも輝くようになっている。 自筆譜では声楽譜表上に書かれたトロンボーンは、キリエの最初の「Kyrie eleison」セクションの終わりに(第30-2小節 )二重になったpianoのトランペットや、'Cum sancto' fugue (bars 53-5, 73-5, 156-63, 167-75)でのpiano での無音部門のような、colla parteから離れるときに特に顕著な役割を果たす。前者では、金管楽器の響きを補充している。後者では、オーボエとファゴットでの装飾された音符のための付加的強調を可能にし、pとfの間の動的コントラストを強化する。 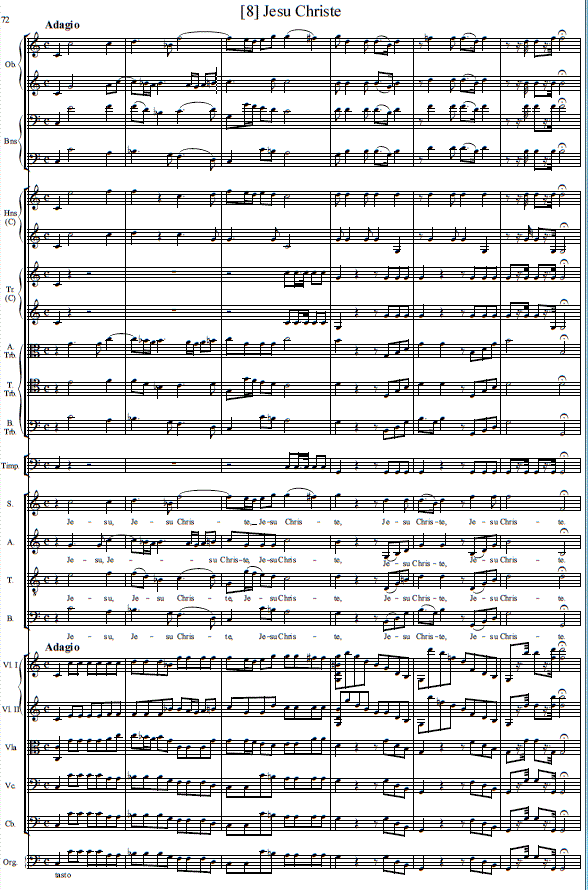 グロリアの短い'Jesu Christe'は、結びついた効果が関係するモーツァルトの世界への窓口を提供している。生の響きにおけるK. 427でのクライマックスの楽章は、 単一の音符で、フォルテで、フルオーケストラで、もっとも短い可能な方法において始まる。それゆえ、' Quam olim Abrahae'においてのように、K. 427での楽器の長いつながりは、、簡潔で力強いつながりで頂点に達している。すなわち、楽章の始まりから声楽の入りへの1小節の移行である(第1小節、第2拍)。そして、 Dies iraeの最後のヴァイオリンの音符のように、それは、多くの場合、楽器のひとつの音符によって、モーツァルトが最少の努力で最大の効果を生み出しているという、Niemetschek'と Arnoldの主張にさらに共鳴することになる。 Conclusion モーツァルトのレクイエムのスコアの音と効果の配列を考えることは、自筆譜の栄光と謎を大事にすることである。我々は、レクイエムでのモーツァルトの記譜と記譜されずにいたその意向を考える上での重要な限界に積極的に取り組んでいるが、(映画「アマデウス」のサリエリのように)、モーツァルトの創造的な才能開花の途中からはっきりと出会うような稀な機会を得ることによる我々の限界を楽しむことができる。不完全なスコアによる未解決の謎は、モーツァルトのPraterでの死の予感と最終日のリハーサルの記述の真実の程度など、レクイエムの伝説の不可解な謎を補足する。 人気もなく、学術的な想像力もなく、我々は、レクイエムの音楽を、伝記的な問題から、説得力をもって分離した。なぜなら、我々は、それらを正確に分離できない、ないしは、する意思がないからである。伝説と作品は、相互補強されている。暗黙的かつ明示的な伝説的なフィクションとモーツァルトの自筆譜による音楽の解釈は、未知のものと既知のものによって半分づつ刺激された同類の精神である。不確実性や疑いは、重大な不十分さや恐怖の源泉ではなく、重要なインスピレーションの源泉になるはずである。 しかし、こうした学問的な弁明には限界がある。レクイエムの伝説は、レクイエムの音楽によって強化され、モーツァルト自身というより、作品との出会いを通して、少なくとも部分的には、インスピレーションのありかを示している。作品を完成させるための実際的な目標のために、 Eybler(モーツァルトが残したSequenceの自筆譜を熟考する機会があった非常に少数の音楽家の1人)とSussmayrは、聞き、理解し、解釈する必要があった。眼前のページにある音と効果を聞き、理解し、解釈する必要があった。 モーツァルトが繰り広げてきた楽器のつながりは、時には表現的な共鳴では不確かであるが、補筆者に永続的な印象を与えている。表現的にどのように、個々に集団的に、解釈されるかに関わらず、特に不完全なスコアにおいて、つながりの頻度、視覚的および聴覚的重要性は、補筆者の音への優先順位および戦略の評価に影響を及ぼす。リンクは、簡単な機能を果たし、1つのvocal statementを次のstatementに結びつけるだけでなく、審美的共鳴とインパクトのある響きと効果を作成する。 モーツァルトの楽器の注釈は、個々の楽章を形作ることにおける暗黙の戦略にも注意を引く。音と効果は、移動の情勢や特定の方向性を獲得する。 Kyrieのあとに来る、'Christe'の目立つ主題は、'Kyrie' と 'Christe'のエントリーの連続した配分を示している自筆譜への初期の変更に関係している。器楽的な興奮はDies iraeの過程で増大し、Rex tremendaeの冒頭は、楽章の終わりに、根本的に異なる効果に再加工され、関連する前後のセクションの間で、緩やかなシンメトリカルな中間部分が現れる。フレーズ間の器楽的なつながりは、Confutatisで発達している。そして、Domine Jesuにおける最初の強力な器楽部分は、'Quam olim Abrahae' のフーガへの爆発的なヴァイオリンのつながりへと進化している。 彼の死の時、モーツァルトは10年以上にわたり、おそらくレクイエム・ミサの最初のウィーン音楽の設定を完成させていた(半分)。第1章と第2章で説明したように、多くの学者、評論家、ミュージシャンがレクイエムをモーツァルトの排他的業績として理解し、評価することを望んでいる。結局のところ、それが目的を持っていると見れば、彼の早すぎる死の感覚を理解することができる。つまり、彼の人生が終わりに近づくにつれて、死についての究極の音楽的表明をすることができる。我々は、伝記と音楽―レクイエムでモーツァルトの作品を理解しているような二重解釈的動機が関与している―が、音楽の偉大な天才の一人に合った、この特別な瞬間に調和していると信じることができる。しかし、最終的には、このように考えるのは間違っていることだろう。なぜなら、レクイエムは、1791年12月5日以降、モーツァルトの断片が完成した演奏可能な作品として日の目をみるようにしてくれた人たち(特にSussmayr、しかしEybler、Constanzeなども)についての生と死に関するものだからである。モーツァルトの死後、レクイエムの仕事の継続と完成に向けて、私たちは今も注目しなければならない。 |