| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A
Case Study in Performance Practice9 by William Geoffrey Kempster |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p152 CHAPTER 10 Other ficta alterations Kyrieの冒頭では、私が行った唯一のfictaは、導音やピカルディ終止の機能としてのC♯の組み込みとしている。 これらの導音の適用のうち、1つはすでに説明されており(第4章のp62 例28. mm。8-9を参照http://machikun.la.coocan.jp/larue4.htm)、他の2つ(m、5およびmm、6-7)はcausa pulchritudinis の六度→八度の進行でも支持されるわかりやすい例である。 残りのひとつはより注目に値する。これは非常に長いスパンにわたって伸びる装飾された導音進行の例であるためである。第2-3小節は以下例85である。 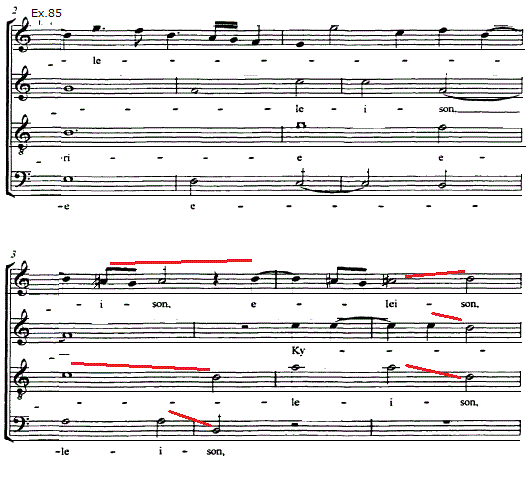 p153 変更を加える以外に選択肢がありません第3小節で始まる、よくある4/3繋留の和声進行は、すぐに2回繰り返され、ソプラノラインの休符部分によって作られたややalse sense of arrival は、即座の反復によってさらに強力になる。with the effect that the somewhat false sense of arrival created by the rest in the soprano line is made all the more powerful by the immediate reiteration. 休符が第3小節の3番目の音である二分音符の”拍”から次のところで3パートが同時にDとなることを妨げている事実は、 第4章(iii)で説明したとおり、ソプラノが下からの半音の装飾的なカデンツ進行の感覚等を持つパッセージを認識することを妨げない。 このパッセージでの両方のC♯が、それぞれtenor, bass, altoと tenorとともに1、causa pulehriludinisの進行の連続した例として二重にサポートされているという事実は、変更を加える以外に選択肢がない。 1 Major 6th⇒octave with the tenor; major 10th⇒double octave with the bass. Minor 3rd⇒ unison with the alto; major 3rd⇒octave with the tenor テノールのAの保持音と、Kyrie冒頭の終わりでの第8小節の下からの半音との関係については、すでに簡単に議論した(第4章のp62 例28. mm。8-9を参照http://machikun.la.coocan.jp/larue4.htm)。 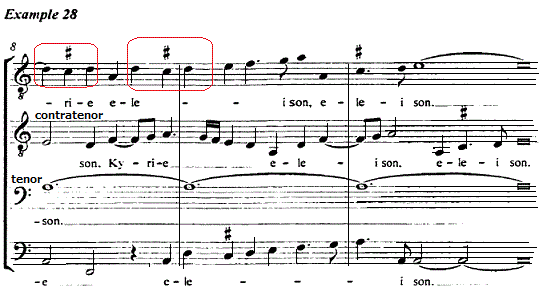 すぐ後に続くこのセクションの終わりも、この点で特に重要である。 以下のパッセージを検討せよ。 p154 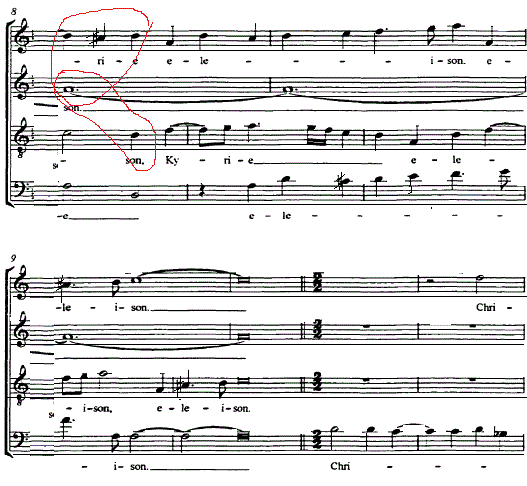 すでに述べたように、可能な限り四度への接近しようとするAとC♯(ソプラノとバス)と、続くDとでできた五度との間の第8小節での経過音的な三度と六度への強い傾向は、このC♯を導く私の傾向の背後の理由となっている。 私は、同様に、ピカルディ終止を供する効果を持つ、最後の小節のC♯を支持をする。第8小節のC♯は、聴覚的にこの変更を予見し、そしてこのパッセージはこの解釈に、より効果的である、と私は信じる。 これを禁じているパート書法はなく、そのために、ラ・リューの音楽におけるこうしたカデンツのこれまでの議論において、わたしは変更を決めている。 p155 次のパッセージは、Gloriaからのものであり、装飾された導音進行の別の例である。ここでは、カデンツ音調は、以下のようにアプローチされる。 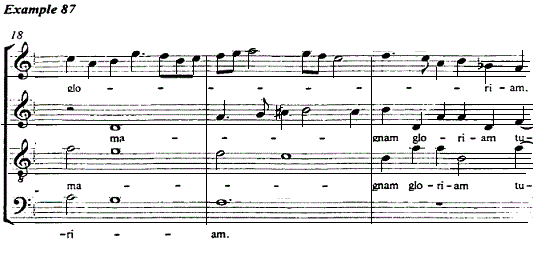 第19小節のアルトは、下からDの繋留にアプローチする。 ただし、これは、繋留D自体を強調するために使用された、導音カデンツのその他のバリエーションの1つである。 基礎となる和音は「小節」全体で同じままなので、両方のCをC♯に上げる必要がある。 このタイプのカデンツがミサ曲で非常に一般的である場合、第4章(i)の例14-16で説明されている多様なカデンツも同様となる。和声的三全音をがまんしても。ただし、このカテゴリ内でも、通常は繋留音の取り扱いに関係するいくつかのバリエーションがある。 このような2つの例を検討したい。最初の例は、グロリアの中央部分である。(例88) p156 次は、同じ楽章の最後の部分。(例89) 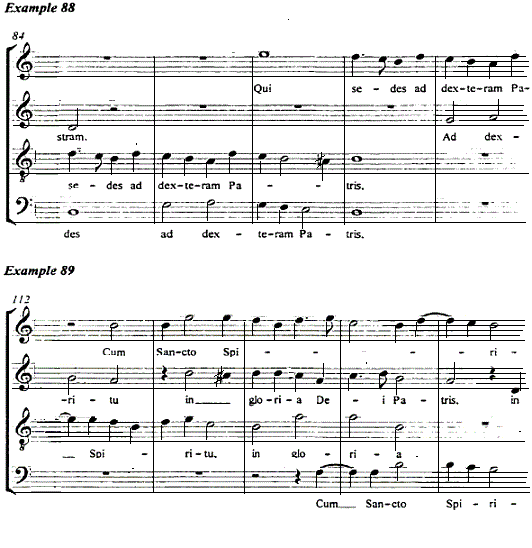 これらの例は両方とも繋留音を含み、どちらの例も3声のみでそれが形成され、どちらの例も和声的三全音が取り入れられている。最初の例では、2つの機能的声部が第87小節の強度なtactusに向かっての強いカデンツ的進行を形成している。しかし、2番目の例では、2つの機能的声部は、カデンツ的ではない。 p157 この問題の以前の議論のように、私は歌手が最初の進行と同じタイプのものとして2番目の進行を認識し、その独特の聴覚兆候に非常に同調している可能性が高いと主張した。その変更は当然のこととして実行されたであろう。 確かに、この音楽の歌手と指揮者の両方としての私の経験がこれをサポートしている。このようなパッセージの独特の悲しみに非常に敏感になり、この非常に当惑させるようなつかの間の「修正されていない」例を見い出す。 fictaの適用に関してより困難な課題を提示する一節がクレドで生じている。 生の部分は次のとおりである。 例90 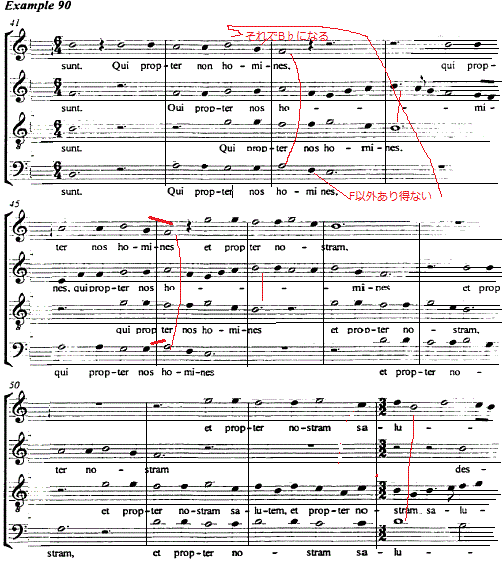 p158 全体のパッセージは、例54/3の第5-8小節の相当するL 'honmre armeメロディから引き出されている。多くの機会で見られたように、この動機には2つの版がある。1つは例54/3aで、第7小節がEになっている。もうひとつは例54/3bで、第7小節がE♭になっている。 動機が五度上下の音程で模倣されるために、全体のパッセージを同じソルミゼーションで統一することは、不可能である。ここでの問題は、これらのうち、どちらのバージョンが優先されるべきかということである。これは、一見非全音階なバージョン(やわらかいヘキサコードBbを含む)を含め、両方がrectaの選択肢として利用できるためである。 次の理由により、この節全体では、例54/3(b)に示されているバージョン(BがB♭になる)を使用することとした。 1 第41-43小節の最初の模倣は、ソプラノとバスの間で四度の音程(オクターブ離れて)で始まっており、同じソルミゼーションとなる音程となる可能性が高い。バスでのFを変えることは不可能である。そのために、ソプラノにおいては、これにあたるところは、B♭とした。 2 バスとソプラノは、第43、46小節、そして第53小節で5、オクターブ離れた音程となるが、これらの最初の2つの例では、B♭経由でそうなるのが可能なやり方となる。 最後の例では、E♭となる。6 5 第53小節では、Dのオクターブは、ソプラノでのFによる装飾があるが、causa pulchritudinisの有効性を変えることはない。 6 これらのそれぞれのケースでのGとCは、♯化はされ得ない。なぜならそうすると、L 'honmre armeメロディの動機の同一性が壊れるからである。 これらの点は互いに一定であり、それぞれのケースで、同じ変更を要する。これらの変更が受け入れられれば、全体のパッセージが同様の手順で扱われることは、問題ないことだろう。ゆえに、以下のようになる。 1 第46小節で模倣のポイントが変化すると、アルトはソプラノに続く。すなわち、B♭が再度生じてくる。 p159 2 第49小節のテノールとバスの間の三度⇒ユニゾンは”短”でなければならず、テノールはE♭となる。 全体を通して、これらの変更により、パッセージ全体が、例26に詳述されている進行に従うようになる。個々の流れもまた、このやり方でより容易に理解され、私はこの解釈は、生のままで変更されていない状態よりも優れていると信じている。第45小節のアルトではメロディ上の三全音が生じてはいるが。 したがって、パッセージ全体が、変更された旋法的なフレームワーク内で機能することがわかる。たとえば、第41-47小節では、ヒポドリア旋法になり、第47-54小節ではフリギア旋法になっている。したがって、recta B♭は常に存在する。 そしてやがてやってくるficta E♭は、フリギア旋法に変化する効果のために使われる。 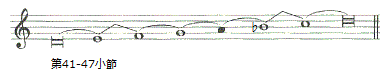 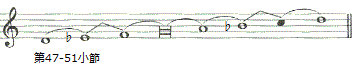 これはラ・リューのアプローチと一貫していると思われる。この特定のセクションが難しさを示すのは、このような音程配置での、近接した、迅速な模倣で例54/3を使用することが、全体の作品の唯一のパッセージであるためである。 このセクションの旋法的同一の議論は、コメントを必要とするパッセージの最後のfictaに関連する側面に行く。すなわち、第44,47小節でのDオクターブへのアプローチである。どちらの場合も、テノールのE♭は、バスとの減八度を避けるために不可能となる。それゆえ、私は、導音進行前に、段階的な上昇をするアルトパートを変更した。すなわち、B 7 ずっとB♭が続いているこの音楽のこの点でのヒポドリア/フリギア旋法的な性質は、元来はrectaであるB 以下がその全体像である。 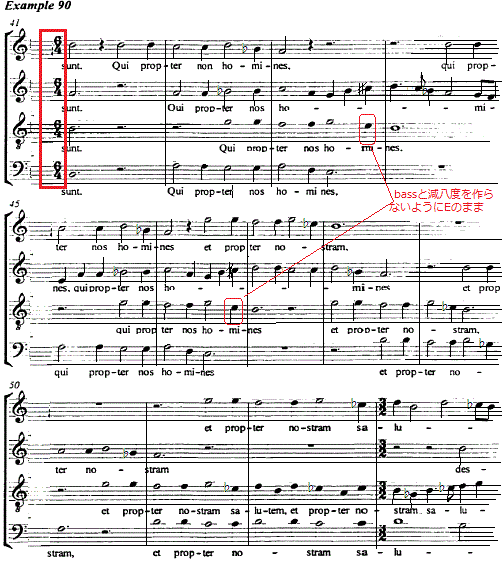 p160 私にとっては、上記のパッセージの解釈を支持する最後の決定的な議論は、このパッセージが次へと移動するときにやってくる。 第53小節でのdescendit de caelis のテキストとともに出現する時である。 この時点まで私が提案してきた旋法的同一性を考えると、この新しいアイデアは今や並外れた力や影響で作られている。 p161 少なくとも、16世紀の後半に見られるように、この時代の音楽は特定の音画法にふけることはなかったと、一部の学界では長い間考えられてきたが、それは誤解である。 la Rueがこの拡張セクションを完成させるパッセージを見てみよう。 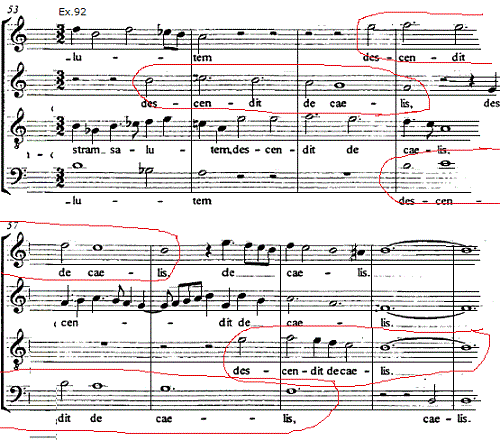 ここでのラ・リューの目的が、L'homme armeの例54/3(ii)から引き出された動機を用いて、直接の音画の観点から 'descendit de cadis'の概念を明確かつ明確に描写することであることを否定することはできない。 まるで天から降りてきたかのように、これらのエントリが次々に層化されるやり方は、最初にアルト(m。53)。ソプラノ(m。55)、次にバス(m。56)8、そして最後にテノール(m。58f)となっていて、最も硬直した(音画法への)懐疑論者は、反論を抑えられることになる。 8 第54-5小節のテノールパートも無論、密接に関連はしている。第58-9小節のソプラノのように。 p162 このテキストの動きの概念を考えると、ラ・リューによる他の2つの要因の操作は、彼のイメージを支えることになる。第53小節での(salutemの)パート書法によった遷移が、すぐに上向きになり、元の旋法が新しい言葉の出現時に正確に再確立されることは、決して偶然ではない。 これは、私がこれ以前に先行したパッセージ(第41-52小節)において提唱した解釈を、強くサポートするが、ここでのテキストの概念における変化と一致することだけが、重要な変更なのではない。 オリジナルのL 'honmre armeメロディについて我々が知っていることを考えると、Qui propterのセクション全体は、このリズムの特徴を反映しており、一般的な拍子記号で示された単純な3拍子に反している。9 9 この理由で、この編纂では、第41小節から第53小節に至るまで、2拍子的感覚であることに適合させるために、tactusの構造を(6/4に)変えている。すなわち、もともとは6/4ではなく、3/2である。 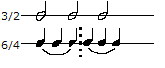 このリズム的アイデンティティは、拍子記号によって示唆されたものに明確に戻ること-再び第53小節で戻ること、で間違いない。 これらすべての要因は、ラ・リューがここでテキスト光彩の方法で、特別な何かを試みているという私の信念を裏付けている。そして私は、それらが、このように、特にパワフルで、先見の明のある設定として明らかにされたこのパッセージ全体を解釈することに対して十分な正当性を示していると信じる。 第7章では、クレドの第93小節から191小節への拡大セクションB♭の優位性を示した(http://machikun.la.coocan.jp/larue6.htm)。 このセクションではB♭が広く使われているにも関わらず、私は、第129小節と134小節における、EとE♭の可能性を示している(Ex.64 )。 このような箇所で疑問がある場合、介入するのは賢明ではないように思えるかもしれないが、私にはE この例では、同じ小節でのB♭とEの不安定な共存となることが、それらが直接衝突しないという事実にもかかわらず、Eが確信できない理由だと確信する。それゆえ私は、fictaであるE♭を用いた。 p163 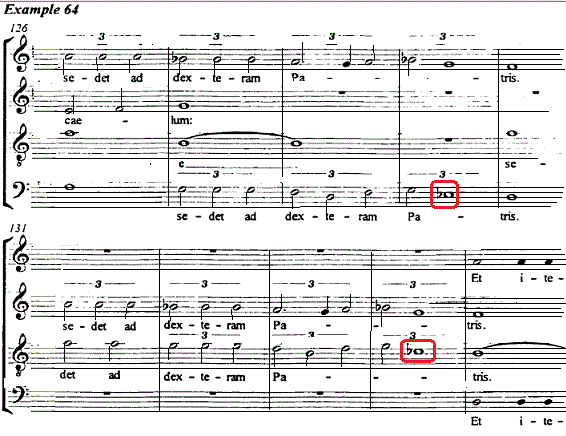 これと同じ議論は、この同じセクションの他のパッセージにもある程度は当てはまりる。 ただしこのパッセージでは、E♭が必要と思われる2つの類似したフレーズの後に、Eが確実に必須であるフレーズが続くために、問題はやや複雑である。 以下のように。 p164 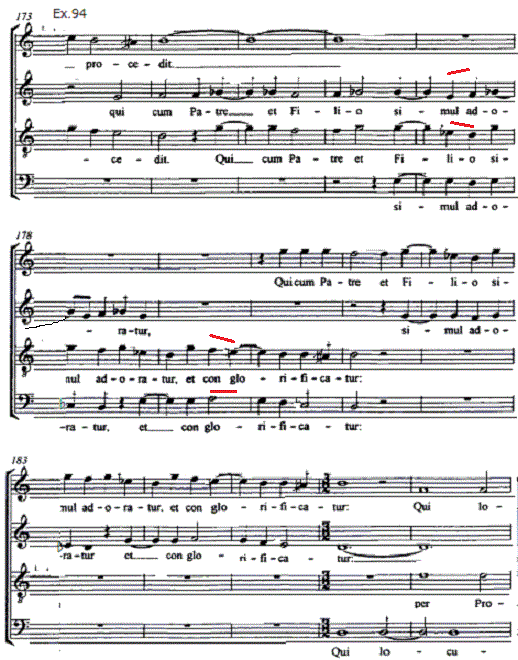 この例では、これまでたびたびあったように、第174-6小節のソプラノにおけるDの保持音は、アルトに対して、B♭とAの間のアルトの振れの結果として生じる一貫して繰り返される和声が長三度⇒完全四度の併置を作ることを要求している。 p165 この文脈において、第177小節でのテノールのE♭は、第178小節におけるバスと同様、以下の理由から、Eとはならない。 ① 三全音関係B♭⇒Eを避けられる ②第177小節におけるアルトとテノール、そして第179小節におけるテノールとバスの間の完全五度へのアプローチは、それぞれ、長三度、短六度から行われる。(後者はそれゆえ、Eとなる)11 11 第178小節でのアルトとバスの間で、同じ進行が、技法的に行われる。だがこれは一過性のもので、あまり重要ではない。同様に、ここでは、アルトとの和声的三全音を禁じている。 ③テノールで使われた例54/3(i)の版は、このセクション内以前で見られたものと一致している。 ただし、例54/3(ii)に反映されているシャンソンメロディのバージョンにバスが移動する場合、連続するE♭もA♭を必要とし、このセクションはDの旋法的「トニック」内で機能するため、これは正当化することが困難であったろう。したがって、第180- 181小節のカデンツ構成は、D上での導音の変異であらねばならない。 すぐに続く小節(181-186)では、la Rueは、この同じ素材を変更されたスコアリングで単純に扱っている-彼のスタイルの典型的なテクニックである。したがって、これらの小節に同じ変更を適用した。 L'homme armeメロディーから収集した動機の旋法的アイデンティティは、Sanctusにおいても重要である。第7章では、この楽章の冒頭で、ソプラノでのrectaB♭を使用するという私の決定について議論した。 p166 この楽章の後半には、いくつかのfictaの問題も対処する必要があるが、これを行う前に、いくつかの全体としての楽章についての観察は有用であろう。 この楽章の冒頭(例77を参照)では、ソプラノラインを除いて、すべての声部は、L'homme armeメロディーからの例54/1および54/2(組み合わせ)から明確に由来している。ただし、これらのD,A,Eの開始ピッチは等しく明確にはならないが、第8章で詳細に説明されているように、3つすべてを同じようにソルミゼーションできる。 この旋律の操作様式は、la Rueの、この楽章での例54/3のさまざまな動機の使用に特に典型的である。個々のパートは、純粋に旋律的なまとまり、いくつかの異なる旋法的「拍子記号」が同時に働いていることを示している。13 テノールが第13小節で例54 / 3b(ii)を取り上げてから初めて、これは問題になる。このパッセージがどのように機能するかを議論するには、全体を検討する必要がある。ここで最終バージョンを示す。 例95 p168 ここで検討が必要な最初の側面は、全体を通してのテノールの旋法的アイデンティティである。 楽章の冒頭から、テノールはcantus firmusをそのまま保持しているが、L'horne ameメロディーの性質のため、この特定のパッセージまでの旋法を最終的に決定することはできない。14 14 メロディがExample 54/3aに相当するに至っても、旋法の根音D 第13小節から最後までのテノールの構築には、例54 / 3aまたは例54 / 3bに対応するという、2つの選択肢がある。 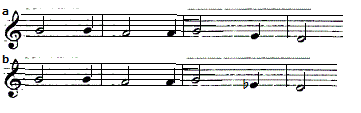 これが正しい解釈である場合、テノール部分のBの変更は、有効性のさらなる証拠を明らかにする必要がある。あるいは、この決定の不一致、または仮定を覆す不整合を明らかにする必要がある。 第15,20、24小節のテノールのB♭の影響は何か? ①第15-18小節、そして、20-23小節のバスにおける模倣と、第22-24小節におけるソプラノの模倣は同じようにソルミゼーションされるべきであり、第17,22,24小節においては、E♭となるべきである。 ②すべてのBは、B♭になり、その結果、第17、22小節のソプラノ、第24小節のアルトはB♭となる。 p169 ③第17,22小節のおけるアルトの装飾的な経過音は、(E♭である)バスとの対位法関係で、E♭となる。両者において、第18,23小節において、導音でのカデンツよりも、suprasemitoneカデンツ(訳注;フリギア旋法的)が発生する。 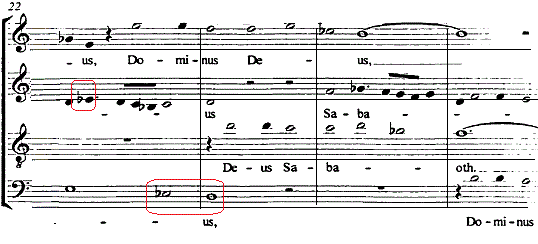 ①については、EからE♭への変更は、短三度経由でアプローチされるテノールとソプラノの間のユニゾンDを許容するいう事実で、第24小節で見られる。 テノールとソプラノが非常に近接しているという事実は、歌手がこれらのパートの相互関係について強い聴覚認識を持っていたであろう、さらにこの非常に馴染みのある形式を反映するために、進行を屈折させる(Eを♭化する)必要性をさらに強化するという私の主張を強める。 また。 第9章のp149の例84cでは、Sanctusの第18小節でのカデンツ形成の構成を詳細に調査し、suprasemitoneカデンツが適用可能であると結論付けた。 この構造は、上記の①を支持するだけでなく、③で引用された他の例の最終的な検証も提供している。、 ラ・リューが提供する旋法的色彩は、完全に意図的であり、それが作成された内省的な雰囲気は、まさにその終わりで、作曲家が、Chapter 4 (iv)で議論された、拡張されたカデンツで終止するピカルディ終止の可能な適応をやめるようにした時に、強められている。 この終止は、ラ・リューがこの最後のカデンツで使用する非常に珍しい二重化によって、より色彩的になっている。それはアルトパートだけでなく、ソプラノとのオクターブ短三度自体にも見られる。 この終止は、パッセージの私の解釈とまったく一致し、非常に説得力がある。 |