| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A
Case Study in Performance Practice6 by William Geoffrey Kempster |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p94 PART B APPLICATIONS TO THE MISSA L'HOMME ARME OF PIERRE DE LA RUE CHAPTER 6 La Rue's use of the l'homme arme melody (略) L'Hormme armeのメロディ自体は未知の起源であり、おそらく15世紀の最初からのものである。 Cohenが観察したように、「作曲家は多くの異なるバリエーションと旋法でメロディーを使用したため、L'Hormme arme曲のオリジナルバージョンを決定するのは困難である」。 旋法へのアイデンティティの柔軟性のこの側面が、私が特に探求したいと思うものである。 特に興味深いのは、Compere(c。1450-1518)とObrecht(1450/1-1509)の例である。どちらも、フリギア旋法のメロディーをcantus firmusとして利用しているためである。 さらに、メロディーのフリギア旋法的解釈によって暗示される半音の独特な配置は、より広い影響を許容する場合があり、その結果、個々の行が旋法的に屈折して興味深い効果が得られる。 CompereのMissa L'Hormme armeのOsannaの以下の例では、旋律の最後のフレーズは、bassus と tenorで、九度の全音階的カノンが出現する。作曲家がこのカノンを操作すると、両方のパートに強い旋律の三全音が生じてしまう。 これらはさまざまであるが、テノールの三全音は、硬いヘキサコードの上のfa super laのパラメーターの範囲内におさまっている。(F fa (m. 67) to B mi (m. 71)。この間、第69小節におけるbassusでのB♭記号は、その前の第66小節でのEとともに、増四度を形成している)。 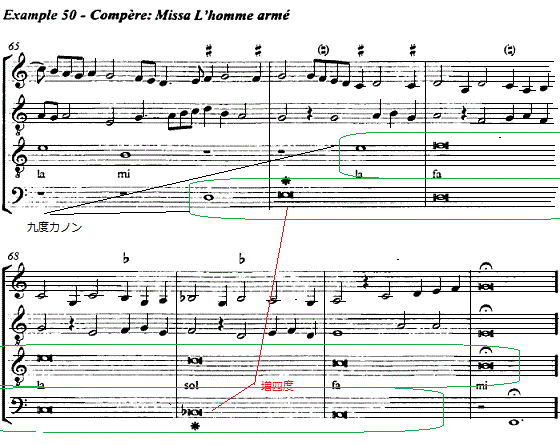 ラ・リュー以前のObrecht's MassのKyrie and Gloriaでは、cantus firmus のテノールでも、E上のフリギア旋法でメロディーを保持し、メロディーでの三全音を頻繁に使用しているが、クレドでは、cantus firmusは、Aに基づいたものにシフトしている。ただし旋法は、以下のように、rectaB♭が指示されているように、一貫して、フリギア旋法となっている。9 9 B♭は、明らかに、discantusとのmi contra faを避けることを意図している。 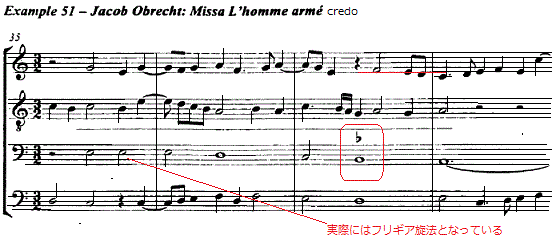 p98 この楽章の後の方↓では、メロディのフレーズは、Example 54/3b(iii)に相当し、B♭は、自然のヘクサコード上のfa super laとして示されている。それゆえ、フレーズ内で産生されたメロディでの三全音が著明になっている。 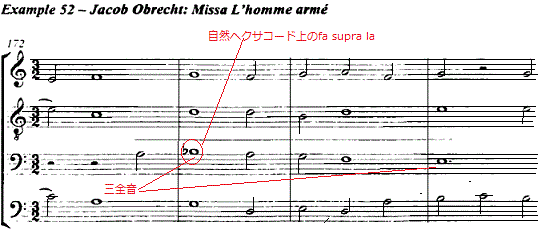 p99 これは、前述のコンペールのテノールと同じである。 ただし、このコンペールの例のバスがこのコンテキスト内に配置された場合には、fa super laのところは、 10 特に前者は、ミサ曲で何度かラ・リューが使用しているバージョンであると実証できる。CompereまたはObrechtのどちらからも、ラ・リューに直接的な影響があったかどうかはともかく、両者ともに、ラ・リューが精通していた可能性が非常に高い作曲家であり、これらの特定の作品をよく知っていたかもしれない。 これは、作曲家の創意工夫によってメロディの「聴覚的特徴」をどのように変更できるかの一例である。 Davisonは、Agnus Iのメロディーは「ドーリア旋法、フリギア旋法、リディア旋法のrnodeで同時にパラフレーズされている」と述べている。 この種の混合旋法の使用は、このセクションだけでなく、曲の多くがそうであると信じられている。 以下に例を示す。14 14 これらはla Rue固有のものではない。Gustave Reeseは、コンペールのMissa L'Hormme armeにおいて、フリギア旋法のcantus firmusは、ペアの声部でフリギア旋法以外の旋法として、カノンとして使われている、と述べている。Gustave Reese, Music in the Renaissance, (New York: W.W. Nonon, 1954), p228 p100 ただし、この段階では、la Rueが全体としてミサの動機として使用しているキーとなる旋律単位を特定する必要がある。 前言したように、これらは実際、段階的パッセージの操作を含み、そして、私たちが扱ってきたある種のメロディーまたは和声慣習から派生した半音変化、または全音階的性質の模倣的使用によって、ほとんど常にもたらされている。 各バリアント設定の音程の相違を強調するために、次の例では同じ開始ピッチでそれらを指定している。これは必ずしもミサ曲そのものでの使用を反映しているわけではないが、ほとんどの場合、それらから派生したように、異なる調性で現れる。 これらのヴァリアントは以下の通りである。 例54 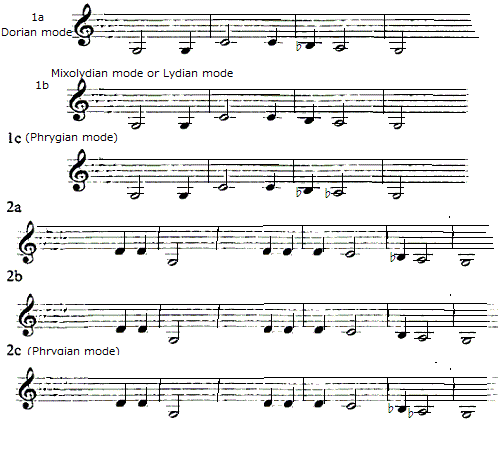 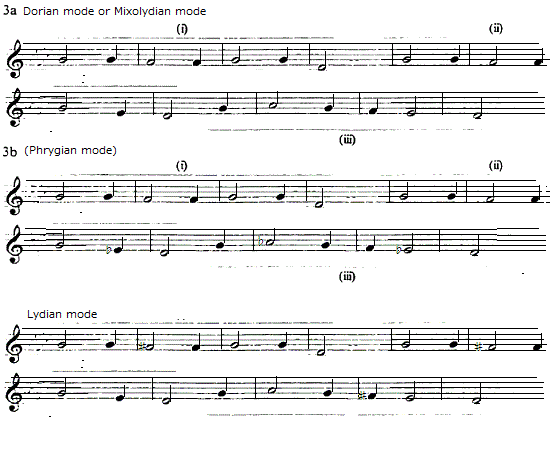 p102 CHAPTER 7 Recta alterations Christeのオープニングデュオは、両方のパートがソフトBまたはハードBのいずれかを使用して機能する可能性のあるパッセージの代表的な例である。ただし、この場合、B 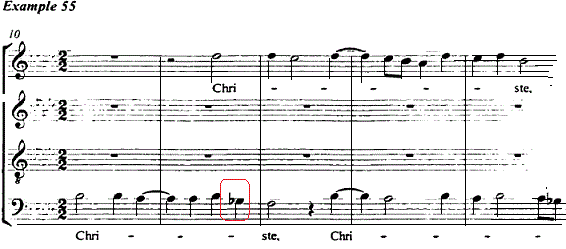 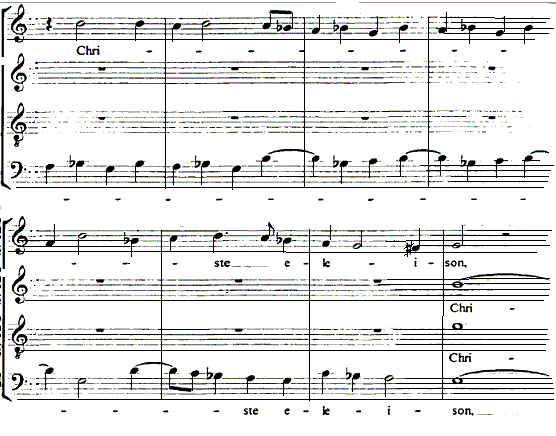 Davisonのエディションでは、第11小節のバスに対して助言的なB♭が提案されている。これは、明らかに、ソプラノとの三全音を避けるための処置である。1 1 またこれは、私が例54 の3b(ii)としてマークしたL 'hornme arme メロディのこのパートのバージョンとして、純粋に旋律的に、そして単独で見たとき、かなり妥当である。 実質的に同じ進行のパート書法が再び33小節で行われ、ここでもDavisonは同じ変更を提案している。 この不協和音のパッセージにもかかわらず、ここでB♭が正しいと思われる。 p103 しかし、このパッセージ全体を非常に興味深いものにしているのは、最初のB♭である。 バスは歌われたばかりのパッセージのわずかに変化した形で続く。そのパッセージは、シャンソンメロディのExample 54の3((a)または(b))iiの四度降下を写している。 疑問は以下である。 ①(a)または(b)のうち、ここで使用が意図されているバージョンはどちらだろうか? ②(b)で始まっているのに、なぜDavisonは、屈折したB♭をそのまま推奨しないのか? 確かに(バスの)歌手はほぼ必然的に(b)をそのまま使っていただろう。特にこの解決は、musica rectaの領域を決して越えない。 そして、第35小節まで、(バス)全体のパッセージは実際、柔らかいヘキサコードの範囲にきちんと収まっている。2 2 さらに、第27小節でこれを支持する根拠が生じている。そこでは、2声部が六度からオクターブへと拡大するにおいて、caura pulchritudinisに則って、長六度で表現されている。 p104 この場合、ソプラノは、第15小節以降は、22小節にいたるまで、柔らかいヘクサコードにおいて、その行を理解すべきどころか、しなければならない。3 3 他の声部によるヘクサコードの選択は、耳で聴いた歌手に影響を与えることになるに違いない。しかしここでは、B♭は、本質的には、mi contra faを避けることにある。 純粋にメロディーの観点から見た場合、これも非常に自然な手順であると思われ、特に、ficta alterationは要求されない。 Chisteセクション全体の音がこの解釈によって根本的に変化することは疑いないが、それはパッセージの正しい表現を表していると確信する。 私の信念は、それがフランクなKyrie設定とより大きなコントラストを提供するのに役立つという事実によってのみ強化される。 旋法的屈折でこのコントラストを導入することがla Rueの意図ではなかった場合、それは、パート書法によってはそれほど明確に促進されなかっただろうと思う。 fictaの変更なしでそれが非常に簡単に達成されるという事実は、私には、その真実性の決定的な証拠と思われる。以下例56は、妥当と思われるパッセージを示す。 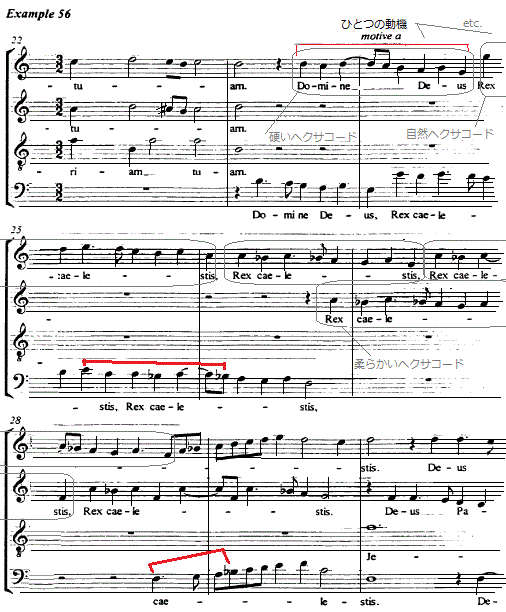 motive aは非常に独自的であり、L 'homme anneメロディのExample 54の2b の 後半をパラフレーズしている。 この動機の最初の3つの音符に含まれる全音の下降→上昇は、3つのヘキサコード配列で容易に示された五度の循環を通した進行として、これが同じソルミゼーションを要求する1つの動機であることを示唆している。The identifying falIing/rising whole tone encompassed by the opening three notes of the motive, as well as its progression through a cycle of fifths so easily represented by the three hexachord arrays suggests that this is a motive which may require same solmisation. p106 パッセージがより詳細に検討されるにつれて、この解釈を究極的に支持する他の要因が明らかになる。 1 mm. 25-6, 28-9 (bass)と27-29 (alto/soprano)における三全音を避けるあらまほしさ 2 第30小節での、パッセージがF(柔らかいヘクサコードの根音)でのカデンツに向かって働く強い”調性の”意味合い パッセージの変更は、三全音が、F上の柔らかいヘキサコードの動機付けによって容易に回避されるように、これらの両方に、補完的な解決策をきちんと提供している。同じことは、硬いヘクサコード、自然なヘクサコードにおいても(それぞれGおよびC上)はっきりとソルミゼーションされている。 第28小節におけるバスは、この拡張したパッセージの最低音としてFを含んでいる。このB 第30小節でのFにおけるカデンツは、この特定の模倣的な議論を完了させ、そして、次のテキストの概念を案内する。したがって、単に「調性」の方向を確認する。 B♭の選択が強く示唆される別の例は、ミサ曲でしばしば生じる。 以下の例57a、bでは、多くの重要な要素が正当化されている。 p107 変更されなければ(いかなる臨時記号を持たない)、第8小節のあるとにおいて、厄介な問題がでてくる。それは、B→Fの三全音である。 よく調べてみると、第8-9小節のアルトとバスの動きも、2つのパートがオクターブユニゾンに近づくにつれて変更する必要がある。 ここにある2つの解決のうち、1つはfictaの使用(例57a)であり、もう1つは単純なrectaの変更(例57b)である。 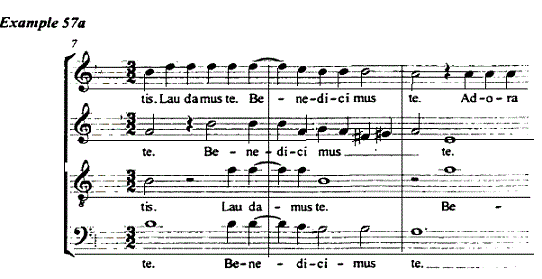 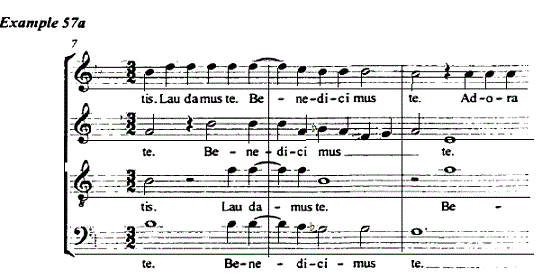 p108 それぞれ独立してみれば、これらのヴァージョンはリーズナブルに見えるが、Example 57aの第9小節では、C♯が妥当と思われる。この解決は、以下のページで見るように、かなりラディカルな意味合いを持っている。 この例では、たとえrectaの選択肢(Example 57b)が優先されなかったとしても、アルトとバスの両方でのB♭の追加が、より滑らかで簡単に歌えるアルトパートだけでなく、、私が上記で説明した理論的実践と一致する対位法における結果となっているので、2つのヴァージョンともあり得ることと思われる。 次の例58はGloriaからのものであるが、B♭は数多くの理由のために導入されている。 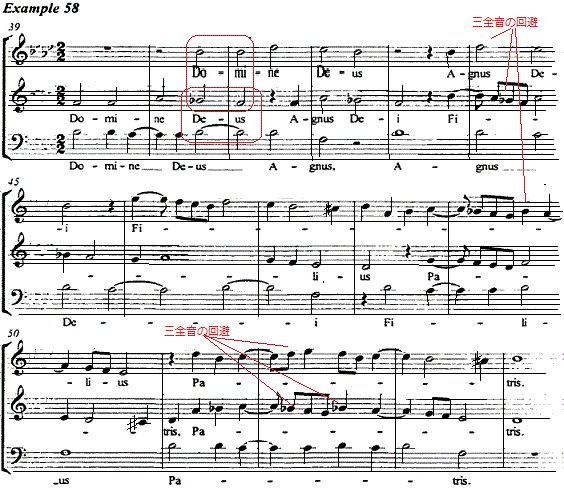 Gloria p109 causa pulchritudinisの概念と一致するように、第40小節から41小節のようなパッセージを変更する必要がある。完全五度 /オクターブ(第41小節)へのアプローチは、理想的には可能な限り最も近い不完全協和音程を介して行われる。 この場合では、これは、アルトとバスの間での長六度→完全五度と、アルトとソプラノの間での長三度→完全四度を意味する。 パッセージ全体の精査は、さらにB♭がいたるところで適用されねばならないことを示唆している。 まず、 B♭がほぼ同一である冒頭パッセージで歌われたとしたら、第42小節でB♭を仮定することは非論理的であっただろう。そして、第45小節でソプラノとアルト間のcausa pulchritudinisがさらに正当化される。 第44小節においては、B♭は、ソプラノとの三全音不協和音を回避できるため、示されている。 同じことがメジャー52にも当てはまる。ここでは、上部2つの声部のFとBは両方で正確に同期し、Bを♭化する必要があることを強く示唆している。7 7 第51小節もまた、Bはフラット化されるべきである。 これらの要因の組み合わせは、第49小節にもその証拠がある。この場合、上位2つのパートの動きは、アルトとの三全音を避けるためにB♭を必要とし、ここで要求される厳密な平行三度を保持している。 この小節の第3,4拍から、第40〜41および45小節での動きがすでに観察されているのと同じ要因が繰り返されている。ここでもB♭が必要となる。 何らかの理由かで、このセクションのアルトに示されているBのすべての例が♭化しているのは偶然ではないと思われる。 したがって、私が考える結論は、rectaB♭が全体に適用されるということである。 おそらく、この分析の最終的な正当性は、この3声セクションの終末(Qui tollis)に生じている(例59)。そこでは、ソプラノとのmi contra faを回避するために、バスでBを♭化する必要がある。 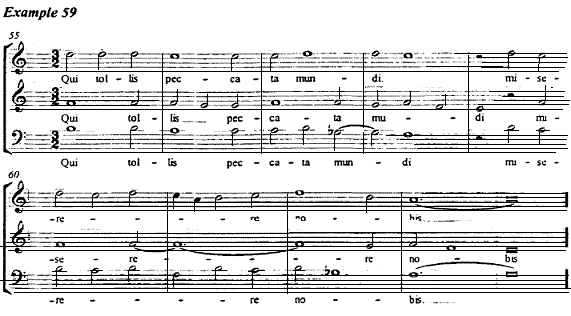 p110 したがって、全体のセクション(例58、59)は、その対照的な(ヒポドリア旋法)旋法の作成で一貫していることが明らかになり、L 'homme anne メロディのla Rueの旋法的屈折の別の例を示している。 やわらかい、そして硬いBの間の選択で思慮分別が要求される例60は、グロリアの第73-81小節のパッセージで生じている。 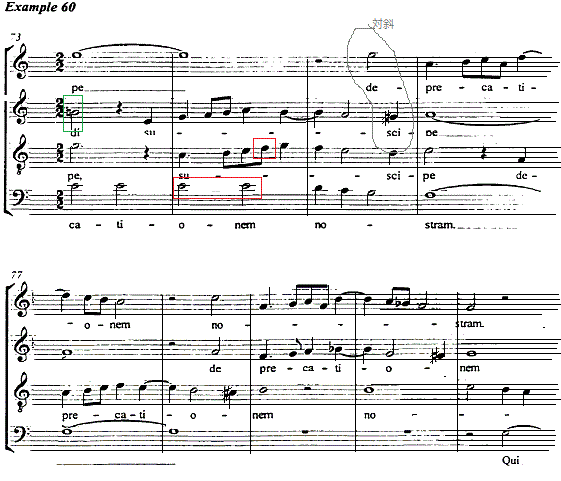 Gloria p111 この抜粋の冒頭では、アルトのB 8 第75小節でのGとG♯の同時の対斜は排除されることだろう。この不協和音は、仮に、(アルトの)BがB♭となったとしたら、直線的な半音階とは異なって表現されたことだろう。 しかし、これに続く例60のセクションでは、B♭とすることは、完全に説得力があるように思える。 第76小節(ソプラノ)、77小節(テノール)、および79小節(ソプラノ/アルト)を構成する動機づけ素材を検討してみよ。 これらの各バリエーションは、L 'homme anneメロディの例54/2のバージョンに大まかに基づいており、それぞれは、調性上の構造的和声トーンの三全音を回避するために完全となる必要のある四度上昇も含んでいる。 したがってこの場合では、第78〜82小節のアルトパッセージに対して、やわらかいヘキサコード(B♭ fa)が強く示唆されている。 この場合、次の小節でソプラノがB♭を歌わないことは、ひねくれた感じのものとなる。 p112 次の例61は、Gloriaからのもので、特に、rectaB♭を組み込むために提供する正当な理由の多様性にとって特に興味深いものである。以下の例61は、正しい形であると私が信じているものである。 ここでマークした変更をしばらく無視すると、一見すると2つの機能が目立つように見え、ここにもやわらかいBが意図されている別の例があるかもしれないという疑念を引き起こす。 ①第12小節のアルトのメロディ上の三全音は変更が必要である。 ②(第12小節での)テノールでのcantus firmus Fは、同じ小節内の書かれたB 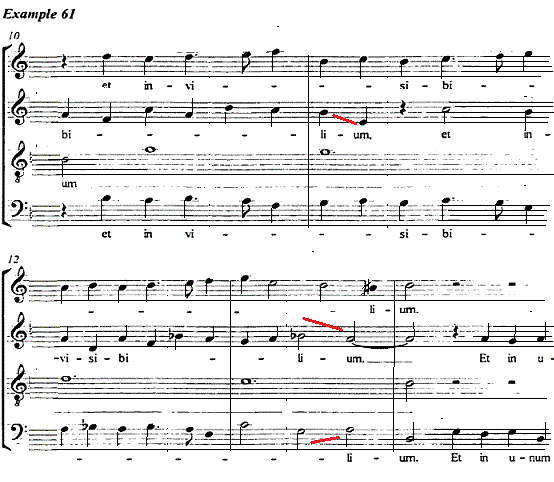 Gloria ただし、パッセージの詳細な調査には、さらに多くの関与が必要である。 第1に、ソプラノとバスラインのつながった構成は、第12小節ではB♭が必要であることを示唆している。 第2に、第13小節では、アルトのAへの進行は、バスの1オクターブ下でのAへの反行と一致しており、causa pulchritudinisがここで求められたことを示唆している。 p113 これらの要因の同時発生は、ここで変更が必要であることを強く示唆している。 上記のポイント1と2は両方とも、少なくとも、この(第12)小節では、BはB♭となることを示唆している。しかし、この変更をどの程度適用する必要があるのか? 明らかに第11小節(のアルト)では、B 第10(~11)小節では、バスはG上の硬いヘクサコードにてのソルミゼーションが求められる。しかし、第12小節ではGよりも下に下降し、自然またはやわらかいヘクサコードへのmutatioを必要とすることになるのではないか? 隣接していないC上の自然なヘキサコードを想定すると、第12小節の最後の3つの音は不自然な三全音を示すことになり、そしてまた、第13小節のCに対応するために硬いヘキサコードへのmutatioに戻す必要がある(例62a)。  はるかにより論理的な解決策は、歌手がこのセクションを視唱しやすいようにするものであり、第12小節の最初に、隣接するやわらかいヘキサコードをmutatioし、次に、フレーズの最後の音符に、自然なヘキサコードをmutatioすることである(例62b)  p114 ここで重要な最後の注意点は、第12小節のバスのやわらかいヘクサコードへのmutatioの実際のタイミングである。あるいは実際に、この小節の最初または2番目のBがmutatioを反映すべきかどうかである。 これを決定するには、第10小節から12小節の外側声部のdouble sequence が最も示唆的である。 La Rueはsequence を控えめに使用しているが、多くの場合、telling効果がある。 ここでは、両パートはsequenceの特徴があり、バスの音域では、 sequence は、第12小節の冒頭でB♭が最初に使われた場合、論理的に継続されることになる。これは、このパッセージの解釈をサポートする証拠のもう1つの補完的な部分を提供する。 これまで取り上げなかった問題は、recraB♭が当時普及した時に、Bが戻るべき場である。複数の可能性が示されることになるだろう。 たとえば、次のCredoの例63を見てみたい。 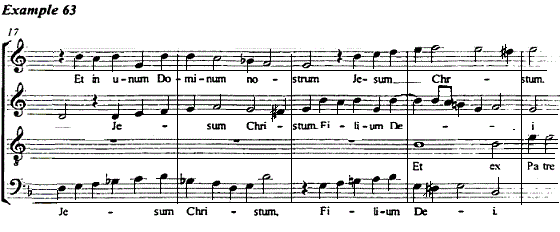 credo p115 この例では、バスパートの第17-8小節の最低音としてのF、そして両小節のBが、メロディ的な三全音を避けるために、rectaB♭を要求している。 しかし第20小節においては、バスはFより下のDへと下降する。そのために、明らかに、mutatioを要求する。それはどこで行われるべきか? 私は、第19小節では、B これは、(第19)小節の始めが休符であることで促進され、離れた音程を経由する場合のYssandonのficta mutationに対する規則にしたがってla→laとソルミゼーションされる-低いDを含めるために必要なmutatioがもたらされる-第19小節から20小節への五度下降を許容することになる。11 11 第20小節のこのフレーズの終わりは、第20小節の始めがla-sol-laの進行となるように、実際には、ficta B♭上のヘクサコードと理解されることになる。 クレドの最後の拡張セクション(例64)で、作品全体で音楽の途切れない最長のパッセージでは、ほとんどの場所でソフトB♭優先することとした。この決定は強力な裏付け証拠によって正当化されると信じている。 第118小節でB♭が導入された後は、音楽はBやB♭のいずれも使用せずに127小節まで進行する。 この小節では、ソプラノとバスが、平行十度で同一の動機を扱っている。このデュオは第131小節ですぐに、内声(アルトとテノール)に移る。ここではじめて、rectaの選択を決定しなければならなくなる。 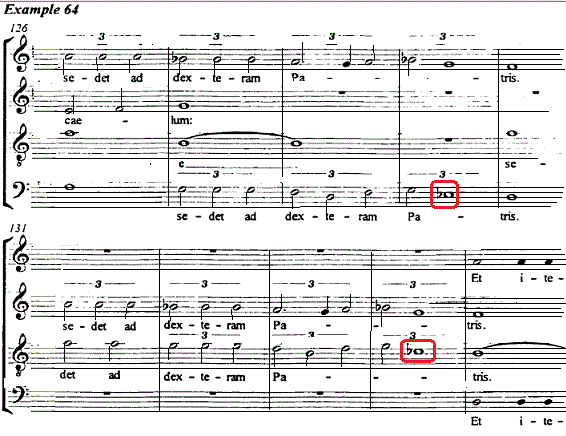 p116 第127-128小節からの進行では、テノールの保持音Dは、ソプラノの下で完全五度を作成する。したがって、完全音程へと進むこれら2つの声部間の六度は、causa pulchritudinisに従い、短六度となるべきである。13 13 第129-130小節のソプラノ部分もB♭を強く示唆している。さもないと、三全音B→Fが(メロディ上で)生じ、非常に厄介になる。B♭の側面も重要である。このパッセージが変わってくれば、その実質的な繰り返すも同様でなければならない。 |