| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A
Case Study in Performance Practice4 by William Geoffrey Kempster |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p57 (iii) Sub-seni itone, or leading tone progressions 例26の多くの進行とsubsemitoneの慣習の間に存在する補完的な関係についてはすでに言及した。 繰り返し音型で上げられた導音、すなわちre-ut-re、sol- fa-sol,あるいはla-sol-laが”一般的に非カデンツ的パッセージに適用された”ことは、最も保守的な編集者の間でさえ、一般的に知られていた。 この音楽ではほとんど常に、そのような音型は別の声部との対位法において生じ、最終的なアプローチを、特に例26 [a]と26h]の一貫したやり方において、オクターブまたはユニゾンに進める。 sub-semitoneを適用するための主に水平方向の推進力がこれらの和声秩序にきちんと一致することは、確かに偶然ではない。 おそらく、この規則をどのように適用すべきかに関する態度に伴う混乱と異議の程度は、「カデンツ」という用語が、この音楽では実際に意味があるという異なった概念からきている。 p58 カデンツを構成するこれまでで最も有用な研究はベルガーにあり、彼自身は「カデンツの完全な歴史はまだ書かれていない」と示唆している。46 46 Berger, Musica Ficta, 138. See also the greater discussion: pp. 127- 138 しかし、そのようなカデンツを認めることに我々が熱心であることに貢献する機能の彼の6点の要約を受け入れることは理にかなっている。 これらのポイントは、しばしば互いに絡み合っており、次のように簡単に言い換えた。47 47 Berger, Musica Ficta, 122- 154 1 A cadence signifies a certain measure of closure. 2 It is a musical punctuation of sorts. 3 Rests may often follow. 4 The octave (or unisoddouble octave) is an essentia1 component (along with the sorts of preparatory progressions with which we are currently dealing). 5 The final harmony should fall at the start of a mensural unit." 6 Cadences may be evaded in various ways" 実際には、2つ以上のパートのポリフォニック音楽がしばしば機能するが,これらの要件のすべてまたは多くを単独で快適に満たす進行では、他の部分はしばしば、2つの機能的な部分の独立性により、終止の主観的な印象またはテキストの句読点の感覚を損なう傾向がある。 したがって、多くの場合、声部は、この理由により「同期していない」ように見える。 私の主張では、そのようなパッセージでは、その機能がカデンツ的であると思われる2つのパートは、常にその役割が明らかにそうであるかのように扱われるべきである。 多くの理論家がこの立場を支持する証拠を提供している。 たとえば、サンタマリアは、音符の繰り返し音型について話すとき、そのようなすべてのパッセージの変更を主張ししている。「なぜなら、それらは、カデンツのように見え、その音は常に♯化されるから」 p59 Ornithoparchus(1517)は、作品に含まれた多数の「'clausulis'」が含まれているということについて言えば、同じことを暗示している。 すべての歌は、どれだけフォーマルな終止があるかによって、であるかによって、より甘くなる。そのような力は、終止にある。 それは、不協和音を完全化して、協和音にする。 Ornithoparchusがここで提供する非常に広範な例の冒頭部分だけで、ポイントを例示するのに十分であろう。そのようなすべてのカデンツパターンは、最終または重要な中間カデンツに現れるものだけでなく、変更が必要である。 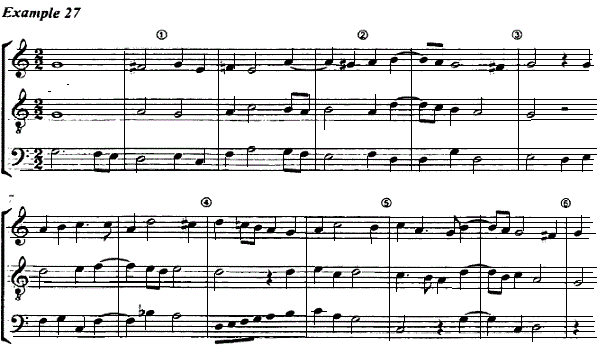 前述の例の「'clausula」のそれぞれのどのような例が、繰り返し音型を含むだけでなく、causa pulchriludinisもまた、六度→オクターブ進行は、六度が長六度になっているかは、興味深い。 上記のサンタマリアのコメントに照らして、上記の番号のついた「クラウスラ」内には、構造としての非常に重要な役割を担っているのは、終止感覚の強さの明確な階層があることにさらに注意する必要がある。 p60 主要なトーンとその使用法に関するこの議論では、まだ言及していない特定のクラスの進行が残っているが、時々変更が必要になる。 これには、re fa solの進行が含まれる。これは、特定のコンテキストでは、ut mi faに変更する必要がある。これは、Jacob of Liegeが1330年に文書化した慣行である。 慣行では、reからsolに昇って、faで歌う。re fa sol fa自体をさらに上げる必要がある。なぜなら、reとfaの間は、全音‐半音ではなくなり、2つの全音が生成され、faとsolの間はもはや全音は残されていないからである。 1世紀半後、ラミス(1182)は当時の書法を描いている。John of Villanovaも同様である。 メロディがa c dとなり、cに戻らなければ、re fa solとされるが、しかし、ut mi faとなるべきである。二全音(長三度)は許容される。 このタイプの進行がcausa pulchriludinissの一般的な原則に一致する方法を見るのは、たとえば、次のように、カデンツオクターブへのアプローチが長六度を介してなされることで、非常に簡単である。 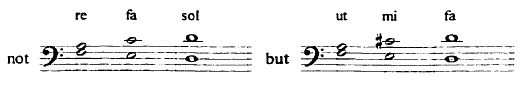 p61 したがって、一般に、私がとる立場は、すべての完全協和音程に対してそれらに最も近い経由で不完全協和音程を介してアプローチされることは不可能であるというBergerの主張を受け入れながら、合理的に可能な限り、オクターブに至ることである。 それによって、この音楽で作成された導音進行の多様性は、私にとっては、一種の陶酔感の一つとなり、この問題に関するCarvellの結論がよく見出されていることが、証拠によって示唆されている。すなわち、「解明された半音は・・・150年以上の期間、パフォーマンスの慣行の期待される部分であった。」それらの共同は、musica fictaの謎の多くを取り除いた」 この時代の音楽の各ページには、導音進行の簡単な例がたくさんある。 この論文に含まれる例には、このような進行がいくつもある。これらの多くについては、さまざまな文脈で紹介したい。59 59 このような場合、可能な限り上声部は♯化される。メロディーや和声の内容が、このように機能しないことを示唆している場合、下声部においては、suprasemitoneが適用される(例26a iiを参照)。 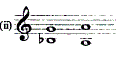 したがって、このスタイルの進行がまだ示されていると信じる、より曖昧なまたは暗示された例に続く分析に限定し、一般に、この論文の後半の段階まで、 Missa l'homme arme Iの分析例を保ち、これらに対処する機会はパートBで直接提示されないため、このような例の一部は以下のとおりである。 最初のそのような例はKyrie冒頭であり、カデンツの帰属の多くを持っているが、Bergerの上記のパラメーターによって判断される真のカデンツとは見なされなかったセクションを含んでいる。 p62 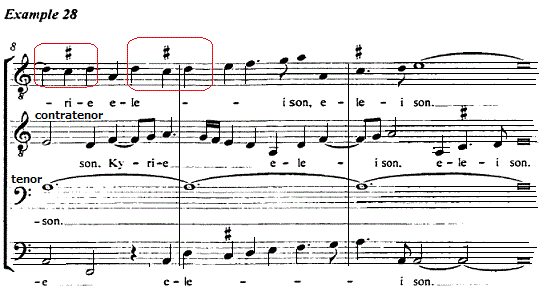 この例では、G上の硬いヘキサコードにおいて、discantusに2つのsol-fa-solがある。(抜粋の先頭)。これらはおそらく、和声を考慮することなく、♯化されるべきと思う。 しかし、それは、例26で示された内部進行を考えると、顕著である。C#は、バスと長十度→2倍オクターブを形成し、contratenorと長六度→オクターブ/長三度→完全四度を形成し、テノールとは長三度→保持音Aとして完全四度を形成する60。 導音カデンツの別の興味深い形式は、装飾的な期待の形式を特徴としており、 sub-semitone は通常予想される前に現れるべきであることを示唆している61。 そのような場合には、他の変更と組み合わせて検討した場合のこの装飾的な屈折の適用、 興味深い結果を生み出すことができる。 p63 たとえば、次のKyrieの最後で、以下のカデンツ構成の私の解釈では、正当と思われる増二度、減四度を経過して、直接的な和声的な三全音を産生している。 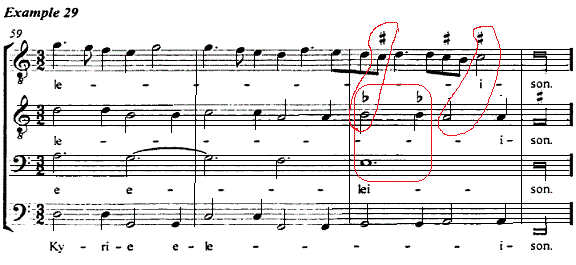 (略) p66 (iv) Tierce tie Picardie Routleyは、「15世紀半ばに、セクションまたは作品全体を終了するにおいて、慣習的に、作曲家たちが五度やオクターブに三度を追加し始めた。ピカルディ終止はどこでもいつも使われていた」と指摘している。 p67 こうした立場は、さまざまな異なる論文で実質的に支持されている。1529年のToscarrello in musicaでのAaronのコメントは、作曲家に彼の意図を明確に示すよう奨励しているが、実践があまりにも広範囲であり、演奏者によって変更が行われることを前提として、多くの場合、記名されていないままであった。 したがって、diesisのサインを示す必要がある。 。 。 そのため、 contrabassとの短十度はやや不協和音となる。もしもそこで半音上げられると、響きはよりスムーズに聞こえる。 この記号は、経験豊かで経験のある歌手にはほとんど使用されず、おそらく経験の浅い、知能のない歌手にのみ与えられるが、適切な演奏は、こうした記号なしでは、むずかしいだろう。68 68 アーロンがここで例(a)に言及している。彼はまた、最後の三度が半音上がるべき同様の進行(b)を示し、「以下の降下でもdiesisが必要である。」と言っている。 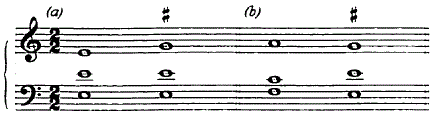 サンタマリア(1 565)も同様に明確である。 時々、作品は十度またはその複合体、すなわち17度で終止する。すなわち、これら2つの協和音程がD、E、またはA、またはそれらのオクターブのいずれかの上で響く場合、trebleは、♯上で終止する必要がある。 (略) p68 多くのの現代の注釈者は、少なくとも部分的に、この分野においては、矛盾する傾向のある根拠に頼ってきた。 たとえばToftは、「ジョスカンのモテットの作表は、ピカルディ終止は終止カデンツには日常的には適用されていなかった」という主張は実証されていない、とした。しかし一方、Routleyはこれに矛盾し、16世紀のジョスカンのParer Nosterの2つの作表からの証拠に基づいて、「中間部のピカルディ終止はオプションであるが、終止カデンツでは、パート書法によって不可能にされない限り、義務的である」と結論づけている。 (略) p69 (ここではこの問題には深入りはしないが)むしろ、ここで最も有益であると私が信じるのは、Routieyの指摘の最後の部分である。すなわち、作曲家が、歌手の側でピカルディ終止となるような変更を防ぐために、パート書法を操作したかもしれないやり方に関するものである。 la Rueの他の作品で、そのようなカデンツをいくつか調べてみたい。 Missa sine nomineからのKyrieのこの例34では、ピカルディ終止は、2番目の小節におけるdiscantusでF♯を導入することは、パート書法によって明らかに不可能になっている。もしもそうなるのであれば、テノールにおいて連続するC♯とB  以下の例35のKyrie of the Missa tous les regretsにおいて、discantusにおける同様のカデンツの装飾では、C♯の可能性はなくなっている。74 74 C#が機能する唯一の方法は、最後から2番目の小節で、contratenorをF#とすることである。しかし、すでに述べたように、これにより、バスとテノールの両方に対して、長六度から五度への進行が発生することになる。ここでは、causa pulchritudinisのために(スムーズな導音導入のために)は、短六度が必要になる。 p70 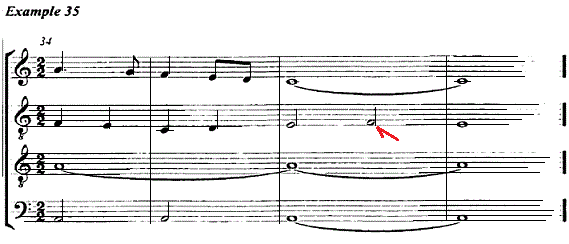 対照的に、同じ作品のChristeの最後のカデンツは、最後の和音において長三度になることを妨げる存在はない。 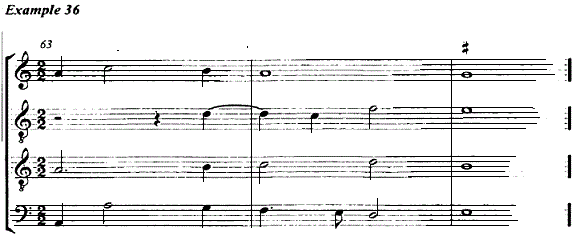 終止での解決への長和音の追加をサポートするカデンツのより複雑な例は、Missa Ave Mariaのクレドの壮大な終止にある。そこでは、causa pulciiritudinis(contratenor、 tenor I bassとともに)と同じ様に、追加されたfictaが、導音カデンツの補完的な適用に関連している。 p71 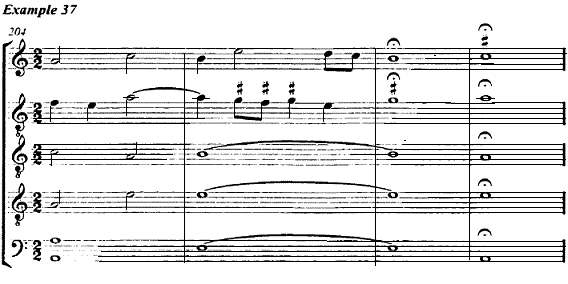 上記の最後のカデンツは、la Rueが彼のミサ曲設定で採用しているカデンツのスタイルのかなり代表的なサンプリングを表している。 私は、新版のla Rueのミサ曲の6巻で発生するすべての最終的なリズムの簡単な統計的サンプリングを行なった。この調査の結果は下記である。75 75 「 la Rueの作品のカデンツは、実際には、いつの時代においても、ピカルディ終止のfictaの追加は示されていない。この調査は、la Rueが実際に、最終カデンツで半音階変化を行うような歌手の慣行を鋭く認識していることを前提としている。 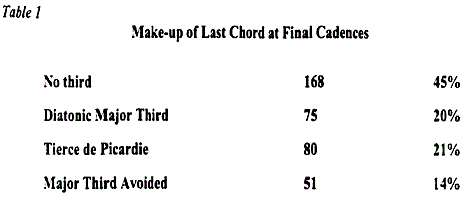 上記において、カテゴリー「全音階的長三度」は、作品の旋法的なアイデンティティが最終的な和音につながるパッセージを指しており、長三度がそのアイデンティティと一致していて、それゆえに、カデンツは半音階的変化を要しない長三度を含んでいる。 p72 カテゴリー「忌避された長三度」は、作曲家がパート書法を操作して、最後の和声で短三度を必須にするようにしたパッセージを指す。 実際に状況において、歌手が可能な限り最終カデンツで和声を自動的に変化させた場合、la Rueが最後の和声への到達を管理した例を見るのは非常に興味深いことである。 何がそうするための動機であったかもしれないかを決定するために、 この論文の目的は、これらの進行に使用される特定の対位法を使用することではなく、ここでの目的は、少なくともこの点に関して、これらすべての最終カデンツが、以下の基本的に2つのタイプとなることに注意することである。 1.最後の和声にに直接進んでいく進行:直接型のカデンツ。 2.最終的な和声が確立された後、1つまたは場合によっては2つの部分が何らかの形の装飾的な動きを受ける進行。延長型のカデンツ。 場合によっては、すべてのパートで最終和声が同時に到達しないことがある。 上記の2つの分類は、ある程度、判断の問題である。 一般的に、すでに響いている音が単純に繰り返される、またはパートが単に和音の別の音に移動するカデンツへの一種の「拡張」を、カテゴリー1に属するものとして検討した。 多くの場合、少なくとも2つのパート(ほとんどの場合バスを含む)は、他のパートの動きが「拡張」と見なされるリズムで動いている間に最終ピッチに達する。 この観点から、上記で要約した373個のリズムのうち、約70は「拡張」として分類でき、これらの約72%(約50)は、長三度と解釈できない構造である。 この分析の完全な結果を以下に示す。 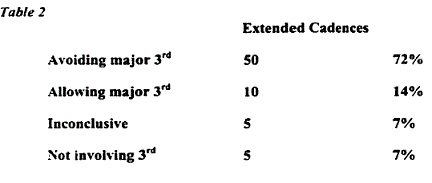 p73 la Rue が歌手たちに最終カデンツで三度の屈曲を期待しただけでなく、(慣行を除外したいときにパート書法を操作することをより好んだような)こうした変更を注釈する必要もないと感じたという主張を支持する根拠の重み は、説得力がある。 この目的を達成するために、無数のやり方を考案することでの作曲家の楽しみは、容易に想像できる。そのようなものが、ここに示された考案の多様性と範囲である。例38と39は、これらのメソッドの2つの例にすぎない。 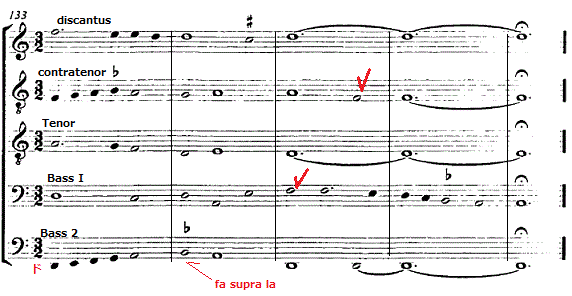 p74 上譜の例、Gloria of the Missa conceprio tuaは78、カデンツが拡張型ではなく、直接型であった場合で、つまり、最終和音がdiscantus,tenor,bassus2の終止音符とともにconjunctionに到達した場合で、bassus Iは、F♯となるよう試みられるだろう。 78 Bassus 2でのficta B♭は、多くのカウントで明確に示されている。causa pulchritudinisと同様に、最初の2つのカウントの両方での自然なヘキサコードでのfa super laとなる。これはあらゆるケースに適用される。C♯の導音もまた、causa pulchritudinisによってサポートされている。 だがこれは実際、特にbassus Iが、カデンツ構造を大幅に拡張し、この時点でF#とすることを不可能にするように、低いAに下がった(つまり、D上のfictaヘキサコードへのmutatio)という事実によって、事実上不可能になっている。 同様に、contratenorは、単独で純粋に旋律的な存在であると考えられていたため、3番目の小節でF#となるよう試みられたが、これは、特にbassus Iとの復唱ですぐに除外されるオプションであった。 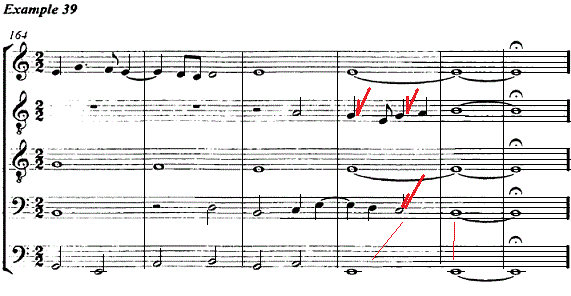 この例は、Gloria of the Missa ista est speciosaからのもので、最後の低いEの最初へのbassus2の到達でカデンツが終りに入った場合、contratenorは同じ時点でG#を取っていたことだろう。 bassusIがなければ、この可能性は受け入れられ、両方のGをシャープ化することができる。 しかし、bassusIを検討すると、それは明らかに不可能になり、bassusIの終止音Bへのアプローチで完全に間違って響くC#が必要となる79。明らかにla Rueは、ここで終止音としての短三度を欲していた。 79 C♯になると、 Example 26[d]にあるようなより好ましい短六度→五度ではなく、長六度→五度への進行を示すことになる。 p75 la Rueがこのタイプの延長型のカデンツを使用するケースの70%以上で長調和声を避けようとしている可能性があることを受け入れた場合、そのような使用法自体を調査する基盤は、特殊事例での可能な半音階的変化の指標として、非常に魅力的になる。 多くのそのようなパッセージを検討した結果、この技法は半音階的変化、特にrecra B♭の使用が特定の状況に適用されるべきかどうかを決定する強力なツールになる可能性があると思われる。 次の例は、Missa O gloriosa Margarerhaの第3Agnusからのものであるが、記名済みのrecra B♭の変更は含まれているが80、その他の(musica factaの)署名はない、過渡期のものである。 80 la Rue's Massesにおいて実際に記名された臨時記号の大部分がそうであるように、これは、当然のことながら訂正されるべき、かなり明らかなrecra B♭である。 p76 第111小節のbassusでの記名されたB♭は、歌手に、contratenorとのmi contra fa の危険性を呼び起こすためのスクライブによるの追加であるかもしれない。 したがって、そのFは、(♯化へと)変更されるべきではない。81 81 それはまた、メロディでの三全音の警告でもある。しかし、la Rueの同様のパッセージでは、このような注意喚起の記号は非常にまれであるので、B♭に対して与えられた和声上の理由はおそらく、もっとあるのかもしれない。 すべてのB♭は、明らかに、ヘクサコード的選択から要求されている。パート書法は、カデンツがもともと予想されていた場、すなわち第111小節に到達したら、F♯が取られるであろうことを示している。82 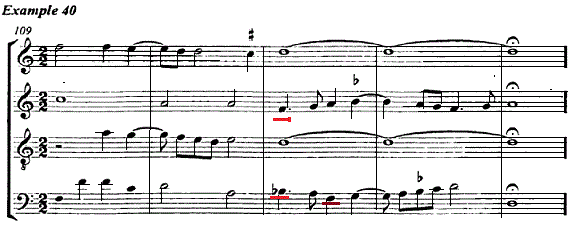 以下の例は、Credo of the Misse de feriaからのものであるが、これらの拡張型のカデンツでの可能な限りのfictaのついた状況を示している。 p77 まず、独立した最後の3小節のみを取り上げたい。ここのcontratenorは、最後から2番目の音符をDの半音上の隣接音とする、やわらかいヘクサコードのfa super laのように見える。 この場合、長調での終止(ピカルディ終止)を回避するために、B♭とE♭の両方が必要になり、最後から2番目の小節のcontratenorの両方のB♭が必要になる。 この例のE♭でさえ、実際のfictaの変化を表していないことを覚えておく必要がある。この音符は、mutatioなしで、柔らかいヘキサコードのこの位置で許容される。 この変化が”出し抜け”であったであろうと仮定するのは、現実的ではない。ただし、柔らかいヘキサコードの使用に一貫性があるかどうかを確認するために、以前の非常に重要なパッセージも考慮する必要がある。これを行うために、例に最終セクション全体を含めた。 多くの側面がすぐに明らかになることだろう。 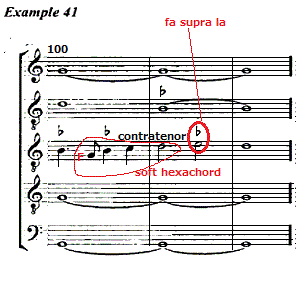 p78 1 第86→89小節のテノール2は、露骨なメロディ上の三全音を避けるために、明らかに、柔らかいヘクサコードを要求している。83 83 これにより、カノン的流れを予見して、テノール1における第88、9小節の半音上昇も可能となった。 2 第89小節のcontratenorのB 3 第89-93小節において、discantusでの柔らかいヘクサコードの使用は、上記2とともに一貫しており、第92小節において、1オクターブ低いcontratenorと合致する。 4 第92小節のテノール1におけるE♭は、上2声部においてB♭が要求されているがゆえに、この点において、fa super laとなっている。mutatioは、第91小節において、行われる。84 84 このE♭は、異なったソルミゼーションでの2つのカノン的声部を表現している。この例におけるその他の要素は、正確なカノンの利得を無効にしていると私は思っている。 5 第95小節から最後までのdiscantusにおける柔らかいヘクサコードの使用は論理的であるように見える。contratenorとのmi contra faを避けるために、B♭が、第97小節において要求され、このヘクサコードの音域は、どこにおいても超えられることはない。特にmutatioがなされる理由はない。85 85 最後の導音カデンツに適合したficta(ファ♯)は、やわらかいヘクサコードを変化させない。 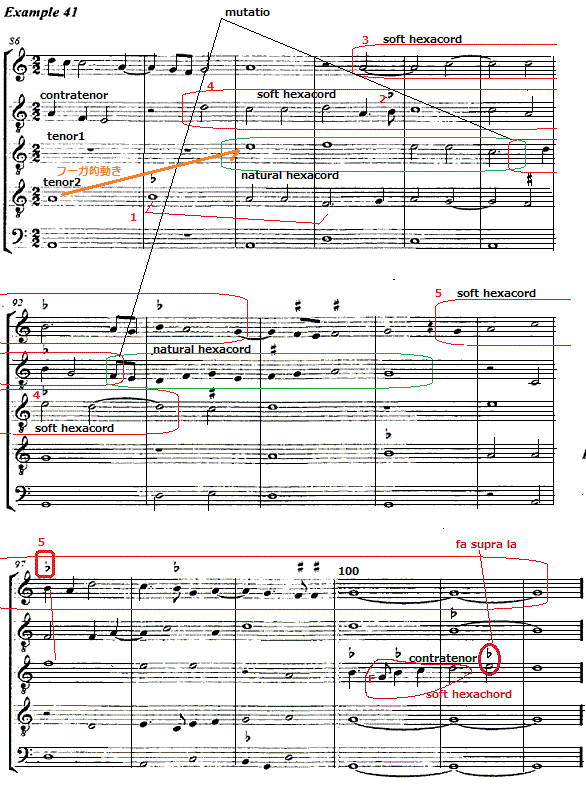 この解釈の難しさは、第92-4小節のテノールに関係している。そこでは、私の解釈はまっすぐな半音階主義のやり方によってパートを進行させている。 このようなパッセージのソルミゼーションの難しさのために、この種の進行は、この音楽では珍しいことは間違いない。 しかし、Routleyは、場合によっては(おそらくここなど)、この種の半音階の使用が許可されている可能性があることを示唆している。 したがって、このパッセージ全体を解釈することは、最後のカデンツ構造から導き出された最初の印象に沿ったものになるであろう。 私は必ずしもこれをどのように実現するべきであると主張しているわけではないが、単に可能性の探求におけるla Rueの様式的特徴の1つであると思われるものの利用を検討する価値があるかもしれない。そのような箇所は、他の観点から問題があると証明されるはずである。 |