| On the Theory and Practice of Chromaticism in Renaissance Music2 Zhuqing Hu |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p60 A Puzzling Proof Quid non Ebrietas (reconstruction) - Adrian Willaert 1533年10月30日に Aron に宛てた手紙の中で、誇り高い理論家であるSpataroは,彼の理論上の主張を裏付ける作曲家Adriano Willaert(1490-1562)を喚起した半音階主義を含む。16世紀の音楽におけるWillaertの影響は計り知れない。 もしもこのような微妙な考慮事項[C♭、B♯など]が無知な演奏家の理解の範囲外であるならば、彼らは、偉大な‘Quid non ebrietas.’を作曲した、サンマルコの傑出した音楽家Messer Adriano [Willaert]のような思索的な理論家や音楽家に大きな関心を寄せていたことだろう。この曲のテノールにおいて、彼は優れた論理とスキルと、思索的な音楽家らによって承認された理論的考察を持つC♭を配置した。 Spataroにとっては、Willaertの「Quid non ebrietas」は、del Lagoの批判に反対して、C♭などのステップの関連性を証明していることになる。そして、musica fictaの思索的的理論を実践する(図1-15)。86 実際、Spataroはほぼ10年前からこの作品を知っていて、彼は1524年5月23日にAron に宛てた手紙でそのことを言及していた。そして、彼のサークルでそれに関するいくつかの交換を促進した。87 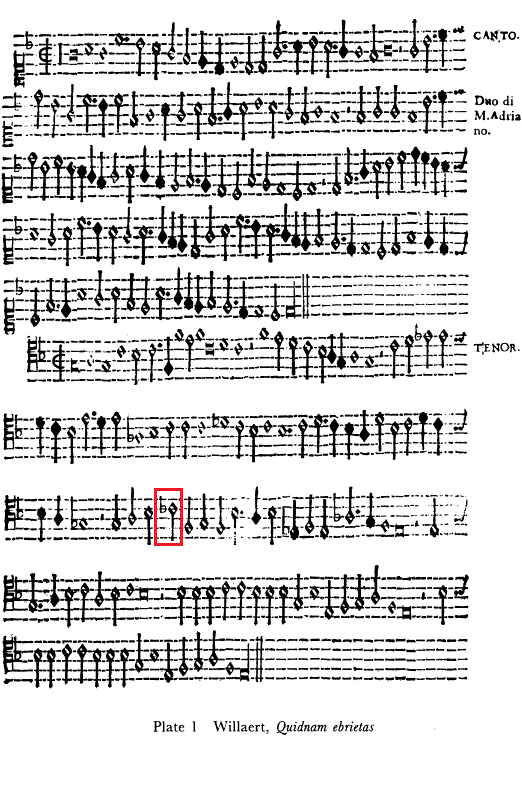 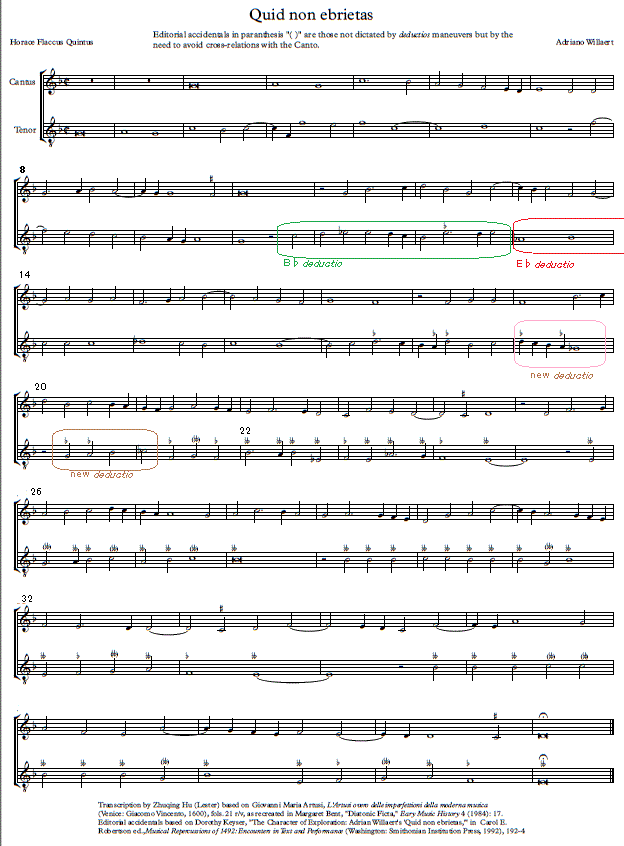 ↓ 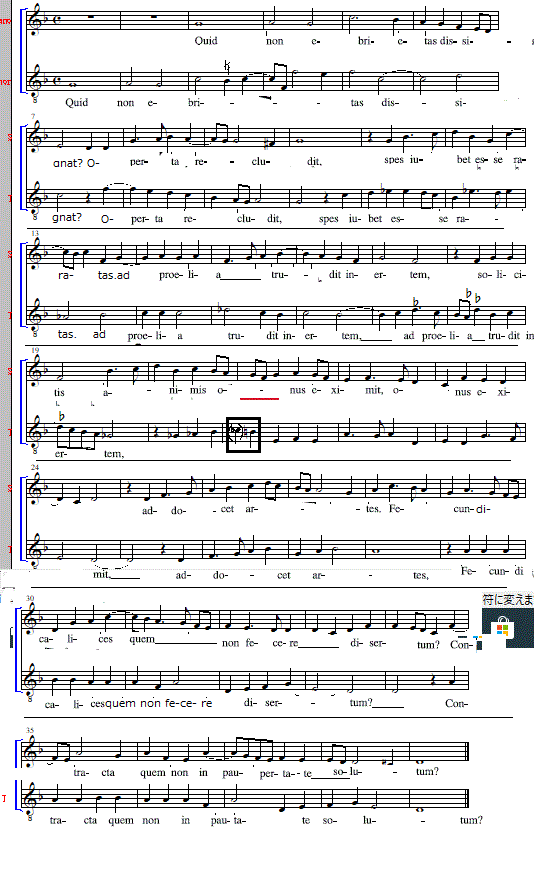 p61 「Quid non ebrietas」について最初に詳細に議論した最初の現代音楽学者の一人であるJoseph Levitanを含む後の音楽家らは、1600年にヴェニスで出版された、Giovanni Maria Artusiの論文L’Atusi, overo della imperfettioni della moderna musicaを通して、この作品を詳細に知っていた。 p62 Artusiは、そのテキストがホラチウスホレスの書簡からの引用である「“Quidnam ebrietas”」(原文のまま)と題したテノールデュオを出版した。 “Quid non ebrietas dissignat? Operta recludit, Spes iubet esse ratas, ad proelia trudit inertem, Sollicitis animis onus eximit, addocet artes, Fecundi calices quem non fecere disertum?” (Horace, Epistles I, V, 16–19) [飲酒によって達成できないことは何か?それは秘密を明らかにし、希望を実現し、非武装勢力の戦いを奨励し、 心配心から負担を取り除き、新しいスキルを教え、 誰にワインカップをより巧みに作っていないのか?] 1956年、Edward Lowinskyは、1529/30または1535に遡って印刷された音楽コレクションであるLibro Primo De la Fortunaのアルトのパートブックが「Quid non ebrietas」というタイトルの作品を含んでいることを発見した。そのテキストは、Artusiの論文内のデュオのテキストと一致し、そのメロディーは、後者の対位法に非常によく適合していた。90 1524年の交換で、AronはSpataroに「Quid non ebrietas」は当初4声で作曲されたと書き、Lowinskyは、Libro Primo De la FortunaのAltusパートが、行方不明のWillaertのアルトであると結論付けた。 彼の論文“Willaert’s ‘Chromatic Duo’ Reexamined,”において、Lowinskyは行方不明のバスを再構成した。 それ以来、「Quid non ebrietas」は大きな注目を集めている。 作品のあいまいさにもかかわらず、特にWillaertのアンソロジーMusica Novaと比較すると、「Quid non ebrietas」に関する文献はおそらく、Willaertの個々の作品の中で最大のものである91。 91 An exception is perhaps “Aspro Core” from Musica Nova (1549). Adrian Willaert - Madrigal "Aspro core et selvaggio" (1559) p64 “Quid non ebrietas”の非通常性は実際、 C♭.の存在以上に挑発的である。CantusがDで終わるにもかかわらず、テノールはEで終わる(第39小節)。そして、ルネサンス期の音楽家が終止にふさわしくない不協和音であると認識していた短七度を形成している。 Spataroによると、ローマでの最初の公演では多くの混乱が発生し、 教皇レオのmusica secretaの歌手であったモデナのLorenzo Bergomozzi が私に、Messer Adriano [Willaert]が教皇に七度で終わるデュオを送ったと言った時から3年以上経ちました。教皇の歌手たちはそれをうまく歌えなかった。それからヴィオールで演奏されたが、それもうまくいかなかった92。 教皇の歌手たちが歌うか、ヴィオールを使うかによって作品を演奏することに成功しなかった理由は、対位法的に不正確な終止によるものではなかった。Spataroは後に、「フェラーラにいる私の友人の良いオフィスを通じて、ウィラールトがデュオのコピーを送ってくれたので、ここボローニャでは、歌われ、演奏されて、高く評価されました」と自慢した。93 露骨な不協和音で終わるように見える作品に対するSpataroの満足度は、C♭(m。21)に注意を戻すが、これは第11小節のE♭で始まる一連のround bの間においてだけである。 対位法的文脈は、これらのすべての記号が、ステップをfaとしてマークするだけでなく、音程内容を変更して、増四度、減五度を避けようとしている。それらはまた、例えば、第12小節でのB♭-Eの三全音を避けるための第12小節のE♭での記譜されていない♭記号を示している。そして実際、Willaertはこれらの記号には節約的である。なぜなら、彼は各round bを1回だけしか記していないからである。 したがって、第21小節で表記されたC♭に到ると、歌手はそれをfaとして歌うことに加えて、Cをmajor semitoneだけinflectionさせたことだろう。もし彼がGuidonian deductioを、この作品への手助けとして考えていたのであれば。 p65 このC♭はC-faではなくC-flat faを意味し、del Lagoの♭とfaと同一視することは混乱を招く可能性があり、C♭はそれと同じくらい怪しく実際の作品で起こり得るという、Spataroのポイントを証明している。 それにもかかわらず、Spataroは、第21小節のC♭の後がどのようになるのかについては、コメントしていない。次のFには何の記号もない。しかし、この作品の文脈では、完全五度としての(下への)跳躍の必要性は、Fにround bがつけられることを要求としている。 「調号」の存在のため、変化しないように見える第22小節のB は実際にはB♭であり、F♭の存在は、追加のround bを要求してくる。 したがって、表記されていないB♭♭において、Bは2回faになり、2回下にinflectionされたことになる。 続いてテノールでは、第22小節の終わりに、round bとともに記譜されたEに遭遇する。 B♭♭とE♭は不完全五度を形成してしまうために、E♭♭が発生し、後に第23小節でのA♭♭が誕生する。round bが、第23小節後で生ずるのは驚くようなことではなく、このようにして、終止音Eは事実上は、E♭♭(=D)となる。その聴覚上の満足は、とにかく、完全四度および五度の跳躍を保つ必要性により生じている。 「Quid non ebrietas」に関する多くの議論は、もっぱらE-D、あるいは実際にはE♭♭-Dで終わっている部分にのみ、焦点が当てられてきた。 1524年9月9日のAronへのその後の手紙で、Spataroは、独創的に考案された作品が、最後にチューニングの問題に苦しんでいるとコメントしている。シラブルfaを割り当てることにより、ラウンドbは、major semitoneずつステップを下げて、その下のステップ上のminor semitoneとなる。 このように、テノールのE♭♭は、Eより下の2つのmajor semitonesなのである。major semitone と minor semitoneからなる全音であり、major semitoneはminorよりもcomma分だけ広いので、CantusとTenorの間の最終音程は、完全なオクターブではなく、オクターブ+commmaとなる。 p66 Spataroと後のLowinskyが指摘しているように、平均律を適用しさえすれば、major と minor semitonesを区別しないで、「Quid non ebrietas」の最後では、完全八度を得ることができる。94 当時の楽器が、平均律で調律されることはなく、Willaertのテノールの幅広いピッチに完全に適合することをデザインしていたために、Spataroは、Aronがキーボードで作品を首尾よく実演するのは不可能であった、と主張している。 一方、人間の声は作品をより上手く演奏できる。なぜなら人間の声は「自然の楽器であり、機械の道具のように、完全性を欠いていないから。」95 さらに、Spataroは、Willaertのパズルの解決は、思考を通じてのみ達成できるとAron警告している。すなわち、「この作品を実行することは分析することと同じではない。」なぜなら「不完全な耳は、これらの小さく、非寛容的な音程[comma]を判断できないから。」したがって、理性は、感覚が機能しない場を救わなければならない。」96 ルネッサンス音楽の進歩と予言の信者である、Lowinskyは、当然ながら、「Quid non ebrietas」が、ヴィラ―ルトの平均律へのマニフェストであり、Spataroのような保守的な理論家のさらなる悲劇への実践的な音楽哲学である、と論じた。 Lowinskyは、Spataroの追加の手紙からホラチウスの酒飲みのテキストまで、多くの素材を用いながら、ヴィラールトの平均律に関する知識と、それを作品でサポートしていることを証明した。97 Lowinskyの説明では、Willaertは、中世音楽の時代遅れの教義を捨て去ったルネッサンス期の改革者ということになる。 p67 より深い原因は、音楽でのアリストクセノスの哲学を復活させる意図に、数学に対する耳の優位性、ピタゴラスの数学的な教義によって争われた音楽的現実の認識に求められねばならない。すなわち、協和音程としての三度と六度の受容、2つの等しい半への全音の分割、オクターブを6つの全音・12の等しい半音に分割する可能性である。そして、これらとともに、音律は、新しく征服されたそして和声的な空間において1つの調性から別の調性へと、音楽を前後に自由に行き来させることになる。98 おなじみの響き? Karol Bergerは、「Quin non ebrietas」で記されていないinflectionの連鎖反応が重要な副証拠として役立つというLowinskyの“secret chromatic art,”には同意しないが、16世紀の音楽家たちが、あまり革新的ではなかった先代たちを乗り越えて新たに達成した「征服」と「プラグマティズム」には、に驚嘆する。 これに対し、Dorothy Keyserはロマンチックなタッチを与える。 彼女は、Willaertの完全な五度圏への探索が、1510年代の別の「圏」の探索と一致することに気づいた。すなわち、フェルディナンドマゼランの地球の周回である。 Willaertの「Quid non ebrietas」とマゼランの航海はどちらも、「中世とルネッサンスの空間の概念の衝突を反映」し、「「探検の性格」と呼ばれるものへの洞察を提供する」99 マゼランが地球が平らではないことを効果的に証明したように、ウィラールトはE♭♭-Dの終わりで「音階を元に戻し、線だったものから圏を作った」100。 さらに魅力的なのは、「ヴァスコダガマ、アルバカーキ、およびアルメイダが他の文化の開拓において畜殺者だったように」、Willaert自身は調整の冒険に攻撃性を欠くことがなかった、ということである。 p68 さらに、LowinskyとKeyserは、Willaertが不可解な「Quid non ebrietas」を書かなければならなかった理由を説明するための名誉、復讐、および陰謀の感動的な物語を作り上げている。 ウィラールトの最も親しい弟子の1人であったるGioseffo Zarlino (1517-1590),のLe Istitutioni harmonicheによると、1510年代半ばにウィラールトがローマにいたとき、教皇の歌手を訪ねて、彼のモテット「Verbum bonum」のリハーサルをした。Willaertが自分の作であることを主張したとき、教皇歌手たちは、それを彼らのレパートリーから落とすことにし、その作品がジョスカンによって作曲されたと思っていた、と述べた。101 Marsilio Ficino, Giovanni della Casa, そして Leo Battista Alberti,の人文主義的な著作を基に、Keyserは「名誉が高く評価され、暴力的に守られた社会」でウィラールトを描いている102。 教皇の歌手たちが解決できなかった音楽的なパズルで、Willaertは、彼の作品を捨てるのは彼らの力であるが、望んでもレパートリーに入れられない作品を書くのが彼の力であると彼らに示した。] 103 したがって、“Quid on ebrietas”では、Willaertは進歩的なルネサンス音楽家として平均律の課題を提唱し、尊厳あるルネサンス期の人間としての彼の名誉を回復させた。 私は、平均律がは「Quid non ebrietas」の避けられない問題であることに同意する。また、Willaertの物語が、我々の社会への優れた教育モデルとして役立つことに同意する。人々は、どのように巧妙に、彼らの意見を表明し、アートフルに自身を守るのかを、もはや、知らない。 p69 しかし、音楽のプロパガンダであろうと個人的な復讐であろうと、作品の背後にあるWillaertの意図の解釈は、押し付けがましい好奇心を満たすこと以外には何も報いない。 確かに、LowinskyとKeyserの話の多くはしっかりと仮説に基づいていた。 酔っ払って、むしろ平均律の不誠実で難解な冗談として意図していた間、Willaertが実際に「Quid non ebrietas」を作成した場合、違いが生じるであろうか? ウィラルトがそれを教皇の歌手に屈辱を与えるために使用することは言うまでもなく、自分のサークルを超えて自発的にそれを開示したことがない場合、それは、作品を魅力的にするだろうか? 私たちがほとんど知らないWillaertの伝記や音楽の政治との関係に関係なく、「Quid non ebrietas」は謎のままである。それはどのように歌われるのか?round bの記号を理解する方法は? Karol Bergerと Margaret Bentは、2つの矛盾した解釈を提供した。 Bergerにとっては、ダブルフラットの存在は、16世紀の音楽家らが、♯と♭をシラブルとしてではなく、 inflectionsとして解釈していたことの証明である。.104 104 Berger, Musica ficta, 39 グイドの手とそのシラブルの枠組みの中で、二重臨時記号は無意味であるため(すでにfaである音、それ自体の周りの特定の音程パターンをすでに暗示しているそのfaは、いかなる意味でも,"さらに”あるいは”二重に”faとなることはできない)、ウィラールトの本当のダブルフラットの含意、および作曲家の謎を解決できた同時代の人々によるこの含意の一般的な受け入れは、主にシラブルの観点から、16世紀初頭に、臨時記号についてどの程度考えられていたかを示している。少なくとも、一部の音楽家にとって、臨時記号は主にinflectionを示す方法であり、二次的にはfaまたはmiの兆候を示している。 反対に、Margaret Bentは、音楽家たちにとって、ピリオド、♯、♭は必ずしもユニバーサルな音程内容を意味しているわけではなく、常にシラブルmiとfa.を意味している 105 105 .Margaret Bent, “Diatonic ‘Ficta,’” 14-6 彼女は、「Quid non ebrietas」において、round bの記号を下向きのinflectionsとして解釈するのではなく、以下の2つの規則によって、テノールを理解している、と論じている。106 106 Margaret Bent, “Diatonic ‘Ficta,’” 16-8 (1) ♭は、その記号が置き換えられるまで、faを意味する。(そしてそれゆえ、下には半音を持ち、上には全音を持つ) (2) 四度と五度のすべてのメロディの跳躍は完全音程で歌われる。.106 p70 私は、BergerとBentのどちらもが、記号の聴覚的およびシラブル的解釈を相互に排他的なものとして扱うことに誤りがあることを提案する。 Spataroとdel Lagoの間の白熱した議論においても、双方は記号をシラブルとinflectionの両方として認識し、それらを両方の方法で使用した。さらに私は、第12小節のE♭から第21小節の想定上のF♭までをすでに実証した。♭をmajor semitone で音程を下げることと、あるいはそれをfaとして歌うことの間に違いはない。 実際の問題は、第22小節で生じる。(この小節では)テノールは記譜上のB音で始まり、ラウンドbで署名されたEで終わる。これらの2つの(B,E)ステップと、その後のすべてのBおよびEステップを2半音分下げる必要があることは否定できない。実際の大きさは、チューニングシステムに依存している。 それにも関わらず、記号の記譜についてのWillaertの特殊なやり方により、♭を下向きのinflection,またはfaとして解釈すると、異なるプロセスが導入される。 公平に見て、Cantus-Tenorデュオの唯一のソースは、Spataroによって最初に言及されてから80年もあとに出版されたArtusiの論文からのものなので、その記譜上の特徴の分析はかなり不安定になる可能性がある。 Artusiの転写は、Spataroの説明とは矛盾があるが、Artusiバージョンでは、少なくとも別の16世紀の音楽家の手によるものであり、特にWillaertの場合を除き、16世紀の記号の使用法を表すことができるので、記譜されたround bを使用する価値があると私は考える。 第22小節において、文字通りBとEを受け取ると、BとEのピッチを2音分ではなく1半音分だけ下げることになる。なぜなら、Willaertは1つ分だけしか記譜していないからである。 つまり、記譜された♭が下向きのinflectionのみを要求するのであれば、Willaertの記譜は不十分ということになる。これは、記譜された複数の♭が、特にすべての音程のinflectionで、前もっての連鎖反応的なやり方となっていて、テノールのメロディ的な内容よりも内在的な聴覚的な記号の意味合いとあまり関係がないことを意味する。 第21小節でのC♭とF♭を含んで展開するdeductiosは、記譜されたB♭とE♭でfaを歌うと、実際のピッチがB ♭♭とE♭♭に反映されることを示している。 p71 同じことが、第23小節でのA♭の記譜法にも当てはまる。それは、メロディの対位法により、想定された二重フラットA♭♭を導いた。したがって、第21小節以後の♭は、inflectionとシラブルfaの双方を含み、その記譜法は、より明示的、相対的、簡単に操作できることとして、後者の解釈を好むようである。 必ずしもWillaertのオリジナルである必要はないが、「Quid non ebrietas」の(4声への)拡大バージョンがその♭を記譜するやり方は、Willaertと彼の16世紀の同時代人とが、明らかに、音程のinflectionについてのこの謎を解決するために、グイド的なdeductiosに頼っていたことを示している。 Willaertの元の記譜法についての知識の不足に制限されることなく、確かに、musica fictaを想像する上でのdeductiosの役割は、第22小節から最後までのテノールの旋律的な輪郭を証明している。 作品のほぼ半分を占めるこれらの18小節分では、テノールは新しい「調性の冒険」を求めなくなり、E、F、G、A、B、Cの6つの表記されたステップの範囲にとどまる。すでに私が説明したように、E、A、およびBでの♭♭に加えて、LowinskyとKeyserの両方のエディションは、第21小節の仮定上のF♭以降、すべてのGおよびC音に♭♭を追加している。 21 .これらの説得力のある♭♭の設置は、テノール自体のdeductiosの直線的な連続とは何の関係もなく、代わりに、他のパートとの対斜を避けるのに役立っている。言い換えれば、彼らはdeductiosをずらしたのではなく、事後において、表面上でそれらを変更するだけである。実際、歌手らは、最初の通し稽古の後にいくつかの対斜が問題となって初めて、G♭や C♭からG、C音をさらに下げることを検討したのだろう。 本質的には、第23小節でのA♭の後に新しいfaになり、したがってA♭♭となる。テノールは、E♭♭―utのdeductioの制限内に留まっている。実際、E♭♭とC♭(♭)の間の六度を超えることはない。 p72 第21小節以前では、四度と五度の飛躍が、新しいdeductiosを要求する分離されたグィド的シラブルを介して、新しいmusica fictaを導入している。 たとえば第11-12小節では、歌手は、E♭での仮定のもとでfaを歌うだろう。このE♭faはB♭- ut deductioに属しているが、第13小節でのA♭fa以後は、E♭-ut deductioを要求する。 第19,21小節での五度の下降跳躍も同様に、新しいdeductiosを導入している。テノールが絶えず新しいficta stepsを導入しているとき(第23小節前)のアクティブなシラブルの分離とdeductioの移調と、テノールが「調性の冒険」をやめるとき(第23小節後)のdeductio操作の安定性との間の対比は、 Guidonian deductio がmusica ficta ステップを構想する活動的代理であることを裏付けている。 Lowinskyのチューニングと哲学革命への賛辞と、せいぜい接線方向に関連する2つの「周航」の偶然についてのKeyserの幻想の代わりに、「Quid non ebrietas」についての私の解釈は、音楽とその記譜法に対処する。 16世紀初頭の音楽家たちが音調空間と音程のinflectionsについて考えたやり方の証人として、ウィラールトの音楽パズルを扱うことは、実際に生産的である。 「Quid non ebrietas」の異常に投機的な性質も否定できないものの、このことは、グィド的な deductiosの移調が、理論的な議論においてだけでなく、また実際の作品においても、音階の例外的な調査範囲がどのように生じるかを例示している。 |