| Musica Ficta1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| p29 (iv) The expanding limits of musica ficta グイドの手の中に含まれていない音程ステップの領域としてのmusica fictaの定義は、グイドの手以外の音程ステップの増加に外部的制限があるかどうかの疑問を発する。 この疑問にアプローチする最も簡単な方法は、別の疑問を尋ねることである。2つの臨時記号、 p30 臨時記号は常に、シラブル( しかし、例外的なケースでは、臨時記号は、それがある場所で音符をinflectionするのではなく、むしろ、隣の音符(たとえば、Ugolino of Orvieto が♭記号記号を使用してGをF♯にしたような場合)、あるいはどの音もinflectionしないことも考えられる(たとえば、規定の音階の範囲以外の部分を示すために、単純にffに♭記号記号を置いてStephano Vanneoに嘲られた音楽家たちのように(http://machikun.la.coocan.jp/juvenis2.htm 参照)。 臨時記号の唯一の絶対に不可欠な機能は、シラブルを示すことであり、唯一の二次機能は、inflectionを示すことである。しかし、臨時記号の主な機能が、付随するステップがfaまたはmiであるかどうかを示すことである場合、既にfaである音程ステップに♭記号を適用することは無意味であり、すでにmiである音程ステップに 言い換えれば、faとmiの記号は、これらのシラブルをまだ含んでいないグイドの手の場所にのみ適用できる。これらは臨時記号の適用のための外側の限界であるべきではない。グイドの手の中では、 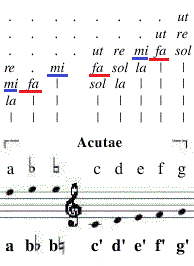 我々は、musica ficta の限界を発見したようである。 しかし、ある時点で音楽家がこれらの制限を超え始め、最終的にはオクターブ内で7つのinflectionした音をすべて♭化し、♯化することが可能になり、ダブルフラットまたはシャープを使用することさえできるようになった。 次に私は、音楽理論における半音階の拡大が進んだ段階を説明し、新しい征服に伴う音域についての考え方の変化を説明したいと思う。 round b( p31 1357年の彼のMusicaにおいて、Boenは 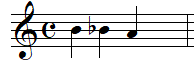 明らかにBoenは、ダブルフラットまたはシャープが可能であるとは考えなかった。引用されたパッセージの直前に、彼はしかし、 (彼が、たとえば、実際にaまたは したがって、Boenの場合、ダブルフラットまたはシャープは考えなかったが、実際にcやfをinflectionした♭(c→ これは、Boenがこれらの問題について、ソルミゼーションシラブルの観点(たとえば、♭記号化されたステップとcの両方がすでにfaであり、その結果、さらに♭化ができない場合)からではなく、譜表記譜の実際の視覚的な観点(音符bの前にはround b(♭記号)がついており、音符cはそうなっていない。そのため、後者はさらに♭記号化できるが、前者はできない)から考えていたことを示唆している。 その結果、彼がダブルフラットまたはシャープを考えていなかったとしても、 彼は明らかに、どんな音符にでも、消極的には単一の♭記号または♯記号をつけられるという可能性については考えていた。 Boenはこれにとどまらず、しかし、”昔の人”は事実上、下の方のminor semitone(つまり、fa)の音符は♭化できず、上の方のminor semitone(つまりmi)は♯化できなかった。すなわちこれは以下を意味する、と言っている。 言い換えれば、「昔の人」は譜表表記ではなく、ソルミゼーションシラブルの論理に従っていた。確かに、 「現代の使用法では、 「昔」と「現代」の唯一の違いは、前者は、cを♯化するとdを♭化はしなかった、ということである。(下のminor semitoneの音符は♭化しないため)。後者では、c♯とd♭はひとつの音階で共存する、ということである。 p32 <まとめ> Boenの議論は、ソルミゼーションシラブルの論理を示しているようであり、このソルミゼーションシラブルは、ラウンドb(またはスクエアb)が追加的に、すでにfa(またはmi)であった音程ステップをinflectionすることができなかったことを示している。それは、彼や彼以前の時代での一般的な力であり、譜表表記の観点からの彼自身の考え(任意の音符の前にフラットまたはシャープ付記ができる)は、彼の独立性と独創性の印であり、一般的意見を反映していなかったのである。 Johannes Boen とすでに言及されたもう1人の理論家以外は、14世紀の誰もが、16の音程ステップの制限に挑戦したものはいなかった。これらの制限が15世紀初頭にすでに揺らいでいたという指摘は、 Parvus tractatulus de modo dividendi monacordum にある。これは、パドヴァの理論家Prosdocimus de Beldemandisが1413年に書き、1425年から1428年に改訂された。126 Prosdocimus は彼のモノコードを紹介し、最初にmusica vera の手順を説明し、「見せかけの音楽は、同じ場所に半音があるように、全音に聞こえる2つの分離されていないletterの間に置かれなければならない」と説明している。127 彼はさらに続ける。全音を2つの等しい部分に分割することはできず、メジャーとマイナーの半音にしか分割できないため、みせかけのステップは、2つのそのようなletterの間に配置することはできず、minor semitoneは、一部の音楽家たちが提案するように、より低い方か、あるいは他の音楽家たちが提唱するようにより高く、のどちらかで配置されなければならない。 musica vera の音階内では、12の分割されていない全音があるために、それぞれの分割は、12の仮想の音程ステップを導入する。前者はa♭,d♭,e♭,g♭、それらのオクターブ相当物、およびB♭(これは(オクターブ上、およびさらにオクターブ上の) Prosdocimusはこれら両方のシステムに欠陥があると宣言し、実際には必要なステップが欠けていることを示し、前の2つを合わせた第三の音階を提案している。結果は、もちろん、16ステップの音階である。ただし、AとBの間にB♭記号とA#の両方があることに注意して、Prosdocimusは、a- 言い換えれば、Prosdocimusは、少なくとも15世紀初期以来の音楽家たちによっては、musica ficta の音程ステップの間で、a#とaa#を受け入れたがられていなかったことを証明している。そして、これらの音楽家たちがA♯の見せかけを禁じていない低いオクターブからの類推によって、こうした音程ステップの存在を合理化することを許容する手順を説明している。 しかし、こうした許容は、消極的ではあるが、主にシラブルの観点から臨時記号について考えることの優位性の最初の亀裂を表し、主にそれらが生み出すinflectionの観点から考えることへの移行の始まりを表す。こうした移行は、必ずしも困難ではない。なぜなら、臨時記号は、実際には通常、inflectionsを示していたからである。 p33 我々はすでに、Boenがこの音程ステップを作る能力があったことを見てきた。同時に、a♯の受容は、♭記号を、音階の全音を分割する別の音程ステップとして、その他のこのような”黒鍵”ステップと同じ状態であることとして、そしてグイドの手よりもむしろモノコードや鍵盤のための全音階について考える傾向を促進した。 Prosdocimusの推論が、 しかし 実際、そのようなモノコードが見つかった。それはNicolaus de Luduno に帰せられ、St BlasienのMartin Gerbert修道院での14世紀の写本の中にあった。 そのモノコードは、全部の音階のすべての音程ステップが、水平の譜線または譜間を持つダイアグラムで表されている。 適切な譜線や譜間は、左側にΓからeeまでのmusica vera の文字名でマークされている。そして右側には、musica fictaの音程ステップの文字名と、与えられた仮想のステップがminor semitoneなのか、あるいはその前のsemitoneよりも高いcommmaなのか、指示によってマークされている。 音階は、トーン全体がminor semitone、commma,および別のminor semitoneで分割されるという点でProsdocimusと同じであるが、Prosdocimusは、a- Nicolausは代わりに、全音 Nicolausの分割は厄介なa♯とaa♯を避けているが、代わりに同様に厄介なc♭記号とcc♭記号を導入している。 しかし、ニコラウスには続く者がいなかったようである。 一方、Prosdocimus のa♯とaa♯の正当化は、すでに正当なA♯からの類推によって、少なくとも1人の他の初期の15世紀の理論家 Ugolino of Orvietoによって受け入れられたような明白なステップであった。 Ugolino of Orvietoは明らかに、musica recta の音階から始まり、その分割されていない全音を半音に分割し(with the minor semitone either below or above the major one)、最後に、両方の部門を組み合わせて、Prosdocimusに従う。 しかしProsdocimus でさえ、a♯とaa♯、A♯に不安を持っていた。なぜなら彼は、それらを彼の”perfect division of the monochord"(monochordi perfecta divisioすなわち、2つのより前の分割を組み合わせること)に含めていたからである。 しかし、不可解にもProsdocimusは、(a♯とaa♯、A♯の)代わりにB♭、 要するに、17音程ステップの音階は、少なくとも15世紀初期の音楽家たちにとっては、可能となったのであるが、Prosdocimusが17番目の音程ステップ、A♯ は非常に稀である、としたことを信じる必要がある。 p34 <Giorgio Anselmi> そのステップが、天文学者であり、数学者であり、物理学者であり、音楽家であったParmesan の Giorgio Anselmi によって1434年の彼の論文に記述されたモノコードにも現れることを見逃してはいけない。 Anselmi は、4オクターブの全音階(♭記号なし、 私は以前に、17ステップの音階が、キーボードの観点で考えることを反映することを指摘したが、 Anselmiが、彼の議論を、オルガンのチューニングで記述したことで主張したことは重要である。 Anselmiの議論はやや混乱しており、彼の論文全体と同様に、その議論は、実用的な音楽家というよりも、思索的な興味を示していた。しかしそれは、論文がある写本を保持していた著名なミラノの理論家Franchinus Gaffurius によって、15世紀の後半に注釈を付けて修正することが十分に重要であると考えられたという理由だけで、ここで言及するに値した。 15世紀後半にも、a#を嫌がるという兆候が現れ続けている。 1464年にコピーされた、作者不詳のイタリア人によるTertius liber musicae は、6つの通常のヘキサコード(つまり、Γ上での1つ(硬いヘキサコード)を除くmusica veraのすべてのヘキサコード)と10の不規則なヘキサコード、そのうちの6つは「仮想の」(falsi)ステップ(D、a、♭、d、e♭、aa)のステップで、4つは”仮想のステップから抜き出されたもの(extracti de falsis、E、F#、 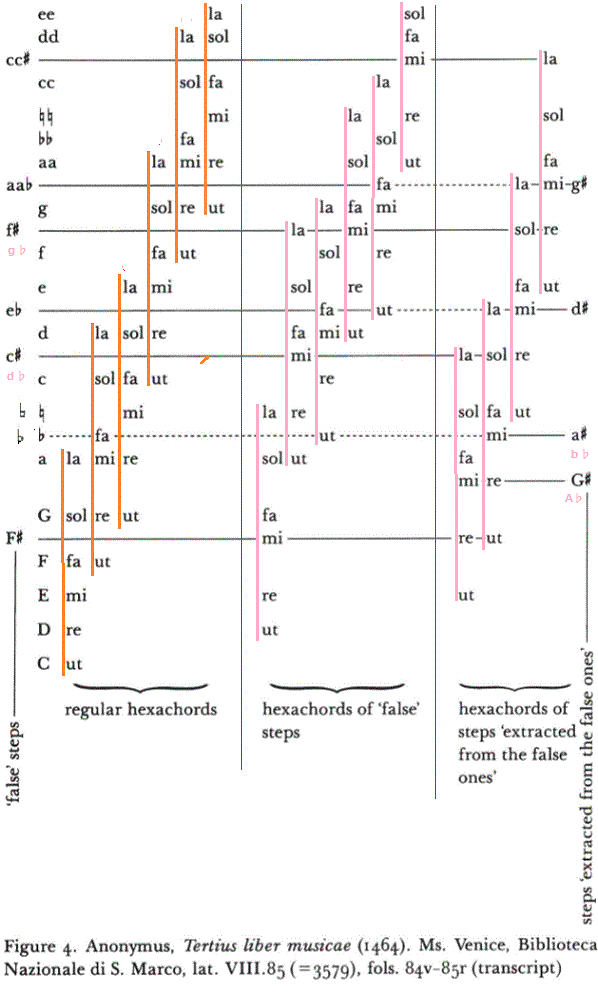 結果としての音階(「false」では、F#、、#C e♭、f#、aa♭、cc#を含み、および「extracted-from-the-false」ではG#、a#、d#、g#を含む)には、1オクターブにおいて#a が含まれるようになる。ダイアグラムは、その存在を不明瞭にしているが、d#とg#の存在を不明瞭にするのと同じように、これらが♭記号と同じレベルで示され、それぞれe♭とaa♭と同等に示されている。(平均律の萌芽) <Franchinus Gaffurius> また、Anselmiの論文に精通していたFranchinus Gaffuriusは、彼の最初のオリジナル論文Theorica musiice(1479年に書かれたと思われる)で、aと 我々は、a♯の想定が、ある程度、グイドの手が音楽家たちや他のイメージ、特にキーボードのイメージに対する想像力を失い、それに取って代わった程度に依存していたことを考察した。 この発展の追加的な徴候は、散発的に15世紀の論文に現れるmusica veraよりも、musica fictaの音程ステップとしての ブルゴーニュのフィリップ善良公の宮廷のドクトルであったHenri Arnaut de Zwolleは、1440年頃、クラヴィコードのチューニングについて記述し、彼は、白鍵ステップから始め、黒鍵である p36 現在の議論の内容において、もちろん、鍵盤楽器にかかわる人が他の黒鍵ステップとの類推によって しかし、音階のイメージが主にモノコードによって提供される作家たちでも同じ傾向が見られる。 Gaffuriusは、1496年に出版された彼のPractica musiceにおいて、「対位法の音程のfictaeおよびcolorataeは、弦の各全音を分割することによって、モノコードに見出される。」と説明した。 さらに、「グイドの全音階のIntroductoriumにおいて,musica fictaは、1つの音程、すなわち、柔らかいヘクサコードが、 A-la-mi -re [= a]と したがって、Gaffuriusにとっては―彼が「グイドの」手に存在する音程ステップとして明白に認識した― <Hothbyと17ステップ音階> 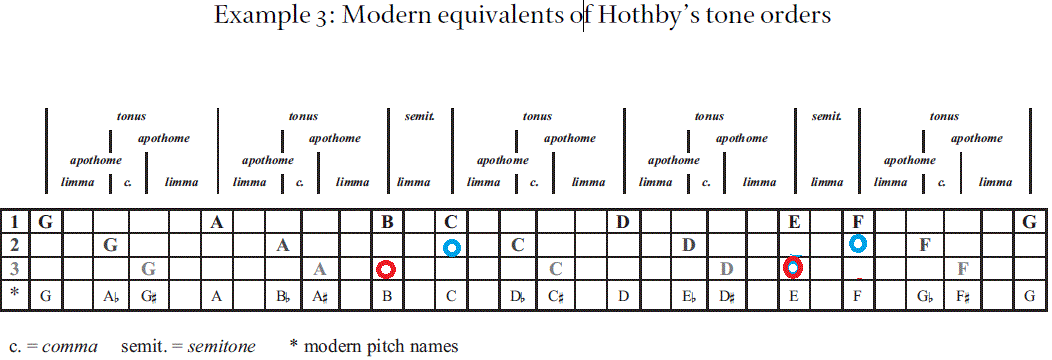 17ステップの音階[7つの「白鍵」ステップと「黒鍵」a♭、b♭、d♭、 e♭、g♭、a#、c #、d#、f#、g#の10」は、1450年代からイタリアに駐在していたJohn Hothby ーの作品で最も体系的で歴史的に最も重要なプレゼンテーションを受け取った。その著作は、1467年から1486年まで彼がルッカに住んでいた時期に暫定的に日付けられている。 La Caliopea legaleにおいてHothbyは、a-gオクターブの範囲内で、a, Hothbyは Hothbyは、上のdiatonic semitonとのステップをprincipe と呼び、これらのうちの2つは、ステップの first orderでは、 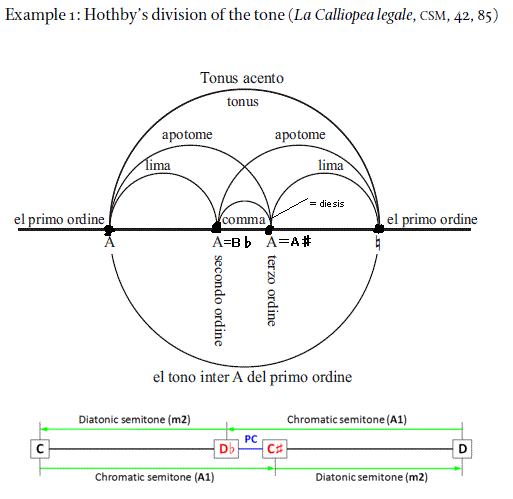 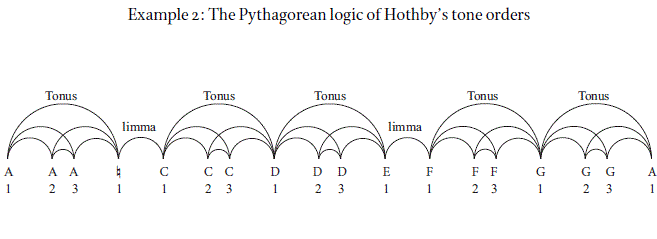 the mi syllable was the principe, and the fa syllable was the comite. Hothby calls mi the principe and fa the comite 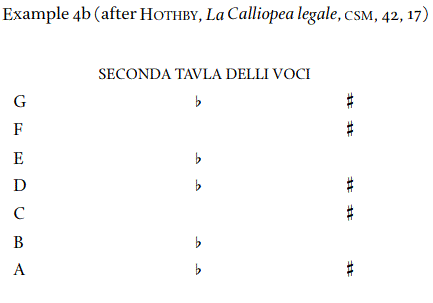 Hothbyは、なぜcとfが♭化できず、なぜ Hothbyが主にグイドの手とそのシラブルの観点から、臨時記号について、まず第一には考えなくなったたことは明らかである。なぜならそうでなければ、彼は、 彼がこれらの問題を、譜線記譜法の面において考えていなかったことはあきらかである。なぜなら、♭と♯をすべての音符の前につけることを許容していたからである。その代わりに彼は、鍵盤楽器の面において、基本的に考えた。白鍵は最初の"ordine"であり、黒鍵は第2、第3の”ordine"であった。そして、 p37 これは、グイドの手ではなく鍵盤楽器の用語で音階を考えたHothbyの傾向についての我々の以前の考察と一致している。 しかし、彼の考え方は、15世紀後半で普遍的に受け入れられた見方であったとは、とても言えない。 彼の若い同僚や仲間の外国人、スペイン人Bartolorneo Ra rnos de Pareiaは、イタリアにおいて、ソルミゼーションシラブルの側面での臨時記号について議論し、、 <Pietro Aaron とSpataro;半音階の拡大> 16世紀の前半に、考えられるすべての音階のシステマティックな供覧が、1525年のPietro Aaron のTrattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figuratoの最後の部分で、試みられた。 Aaron は、グイドの手のすべての場所に、6つのソルミゼーションシラブルを置くことができる、と宣言した。これは、事実上、私たちがすでに知っていること、言い換えれば、すべての場所にrniとfaを置くことができるということの、別の言い方であった。 さらに、原則は曖昧であり、音階の多様性となる結果となったが、 さまざまな音階をもたらす可能性があったが、仮想のfaからあらゆる場におけるすべてのシラブルから由来するとしたAaron の試みは、グイドの手が、彼が心に思い描いた音階は、すべての臨時記号ステップが♭(sなわち、オクターブ内での仮想のa♭,d♭,e♭,g♭)だったことを示したmiを持っていた場所であった。 アーロンの供覧は、ボローニャのGiovanni Spataro が彼とGiovanni del La gOと交わした手紙の中で議論された主題の1つとなった。Giovanni Spataro のAaronの論文についての理解は、ここで示したことと同様である。すなわち、彼は、すべての”黒鍵”ステップを持つ音階を♭とした。 1527年10月30日、Spataroは del Lagoに、♯を完全に無視して♭のみの音階を作ったAaronへの批判を訴えた手紙を書いた。彼は1529年1月4日の手紙でこの問題に戻り、同じ批判をdel Lagoにも繰り返した。1530年12月かおそらくそれ以前に、アーロンは自分の弁護でスパタロに手紙を書いた。彼が実際に持っていた音階は、真鍮においては、♭同様、♯のステップも含んでいたのである。(略) p38 同様に、1533年10月30日の手紙で、スパタロはアーロンに、モノコードを完全に分割するには、すべての全音は2つの”黒鍵”ステップに分けられなければならず、隣接する「白鍵」ステップから、片やminor semitoneで、片やmajor semitone離れていて、 兄弟ヨハネス・ホスビーが彼のLa Caliopeaで示したように、この真実は、私の名誉あるピエトロ兄弟よ、グイドの手のあらゆる位置で6つの公式名を見つける方法を教えるあなたのこの論文で、あなたの閣下によって忠実に承認されました。 表面的にはシラブルと場所の面で行われている17ステップの音階のこれらの議論が、モノコードとオルガンの呼びかけにどのようにスリップするかに注目する価値がある。これは避けられないように思える。なぜなら、すべてのシラブルをグイドの手のすべての場所に持っているというアーロンの原則(これは、グイドの手のすべての場所にmiとfaを置くことができる別の方法である)は、さまざまな音階に適合するからである。16ステップの音階はその最大のものである。 、非常によく知られているように、スパタロは尊敬する教師ラモス(ラモスには多くの批判者がいた。数少ないそうでない人がHothby だった)のさまざまな教義を守るために人生の多くを費やした。アーロンの追補はこのような熱意を持っており、フル音階の問題についてはRamosではなくHothbyに偏っている。(略) p39 <Willaert;Quid non ebrietas> 音階の制限の問題に対するSpataroの関心は、もともとAdrian Willaert(1490年―1562年 )の非常に議論された半音階の謎の '' duo 'Quid non ebrietas楽譜で、これは、1515年から1521年の間(おそらく1521年)に書かれたモテットであり、ここでは、テノールとカントゥスは7度(E-d)で終わるように見えるが、実際には、Eは♭♭が前にあるかのように読み取られるため、オクターブで終わる。 Quid non Ebrietas Adrian Willaert 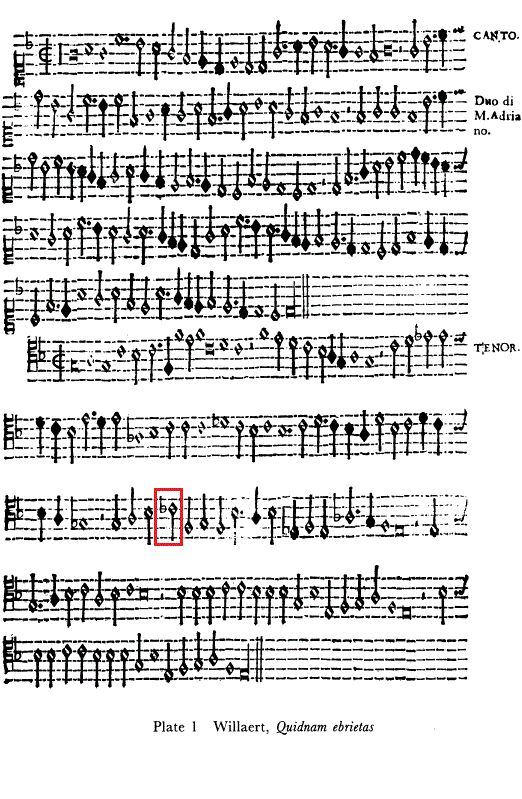 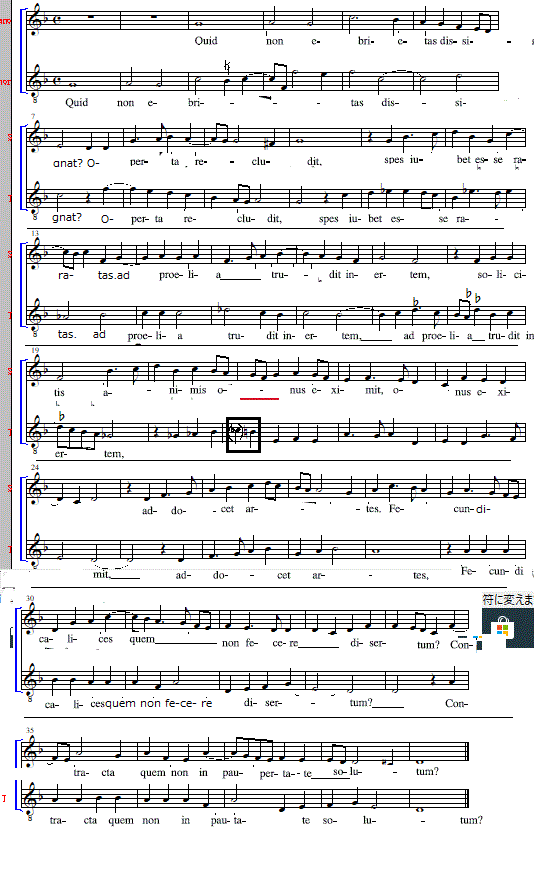 16世紀の作品をめぐる理論的論争、スパタロが積極的な役割を果たした論争は、その適切な演出に必要な音律の問題を中心に、テノールの最後の音符が、今日、我々が♭♭と考えることを暗示していたという事実は、疑うべきではなかった。 Willaertは、このような可能性を最初に考えた音楽家であると思われる。 また、彼の作品が音階の発展に与えた影響は、音律について考えることの影響よりもはるかに広範であった。グイドの手とそのシラブルの枠組みの中で、二重臨時記号は無意味であるため(すでにfaである音、それ自体の周りの特定の音程パターンをすでに暗示しているそのfaは、いかなる意味でも,"さらに”あるいは”二重に”faとなることはできない)、ウィラールトの本当のダブルフラットの含意、および作曲家の謎を解決できた同時代の人々によるこの含意の一般的な受け入れは、主にシラブルの観点から、16世紀初頭に、臨時記号についてどの程度考えられていたかを示している。 少なくとも、一部の音楽家にとって、臨時記号は主にinflectionを示す方法であり、二次的にはfaまたはmiの兆候を示している。 Spataroは、Aaronにむけて、1524年9月9日の手紙でこの件について議論した。手紙の中で、Spataroは、臨時記号について、シラブルの面からではなく、inflectionの面のみから、語っている。(参考;p30 臨時記号の唯一の絶対に不可欠な機能は、シラブルを示すことであり、唯一の二次機能は、inflectionを示すことである。) 音楽家らは、自然に考えられた音を適切な場所から取り除くことができる2つの記号のみを設置した。これらの記号とは♯と♭で、前者の♯は、major semitoneによって自然音を引き上げ、後者♭は、逆の効果を持つ、すなわち、音は、本来の場所からmajor semitone下げる。 臨時記号がこうした側面で議論されると、臨時記号は、音程ステップに2回適用されると、inflectionは2倍になる。実際、Spataroが、「その効果を2倍にする」ために♭記号を書いているのが見出される。 p40 スパタロはピタゴラス音律の一部としてこの作品を検討し、その結果、作曲家の実験を間違っていると批判したが、彼は、二重臨時記号は可能であるという、ウィラールトの基本的な考えを理解し、受け入れた。 ちなみに、ウィラールトもスパタロもそのような二重臨時記号を明示的には示していないことを指摘する必要がある。 グラフィック記号もダブルフラットの名前もない。 二重臨時記号の問題は、cまたはfを♭化できるか、あるいは 両方のケースで問題となっているのは、臨時記号の主な機能が、inflectionすることなのか(二重♭あるいはc♭を考えることも理にかなっている))、あるいはステップをfaあるいはmiに変えるのか(この場合、二重♭あるいはc♭は消極的となる)、ということである。 繰り返しとなるが、ウィラートの「デュオ」は、表記されたc♭と暗黙のF♭を含むため、問題への関心の重要な触媒であった可能性がある。これらの表記および暗示された♭記号は、半音単位でcおよびFを下げることを意図しており、作品に関するSpataroのコメントで難なく理解される。 さらに、Edward Lowinskyが、1521年5月14日の手紙を示し、「すなわち、これらのトーンはその前に♯化され、それらの通常の音に戻らねばならなかった時に、Spataro は、duo に関する彼の研究に3年先立ち、FとCの前に♭記号を置く可能性を1つだけ認めた。」ことを示している。「トーンCとFをフラット化できるというスパタロの確信は、確かに、ウィラートの「デュオ」を研究した結果である」ことが示唆されている。 <Del La go> 1533年に、このようなinflectionは、Spataro in Bologna やAaronやGiovanni del Lago in Veniceを巻き込んだ長引く論争の主題になった。議論された問題点は、F♭、c♭、 Del La go は、Spataro に、8月15日の手紙で答えを送った。 165 彼は、フラットはたとえば、FをEよりcomma分低くすることだろう、と論じた。(なぜならフラットはmajor semitoneだけステップを下げ、EとFの間のdiatonic semitoneはminor semitoneだからである。両者の差が1コンマとなる)。 そして、コンマは音楽慣行では使用されないため、F♭は避けるべきであり、同様の理由で、c♭、 この議論には いくつかのポイントがある。第1に、理論家にとって、臨時記号のシラブルが示す機能は、基本的なものではない。なぜなら、それらは、faあるいはmiであるステップではそれぞれ、♭化し、♯化さえするからである。 第2に、彼の禁則は、a♯には行かない。すなわち、彼の立場は、Hothbyに似ている。 第3に、二重♭に対するSpataroの議論のように、こうした記号が否定される可能性はないが、ピタゴラス音律システムの前提でのこうした慣行のみであり、すなわち、議論は、平均律を受け入れることに落ち着く。 p41 Del La goの見解は、Spataroの見解と本質的に同一であった。 両方の理論家は、臨時記号の主な機能は、すでにfaまたはmiであったステップに適用された場合でも、inflectionすることであると信じていた。 10月30日のアーロン宛ての手紙で、Del La goの立場に対する長い批判を説明できるのは、Spataroの飽くことのない欲求だけである。166 我々の目的では、Del La goと同じように、Spataroが、F♭やc♭はFやcよりもmajor semitone低くなるであろうこと信じていたこと、そして しかし、すべての音楽家たちが同意したわけではない。 1538年6月3日に書かれたヴェネツィアからの手紙の中で、 del Lago は、 Piero de Justinis を、彼のモテットの1つにおいて、 Pieroは昔ながらの意味で記号を使用したこと、つまり単にmiの記号として使用したことは明らかであり、eをシャープにすることを意図せず、むしろ、歌手によるフラット化を防止しようとしていたのである。(同時に、バスにはE しかし、デルラゴーにとっては、その記号は常に、半音を大きく上げるステップを移動する。しかし、彼はPieroの記号の使い方が間違っていると考えてはいたが、類似のケースでPieroの意図を認識するのに困難はなかった。これは、Pieroの従来の使用法が、1530年代後半にまだ流行しており、おそらく通常でさえあったことを示唆している。 アーロンは、1533年には、この問題に関するSpataroの手紙の受信者であったが、1545年の彼のLucidario in musica の出版物において、それについて議論した。171 CまたはFに♭記号を置くことができるかどうかと、 したがって、Cのbの符号を想像したい。 。 。それを信じた他の人に起こったことは、おそらくあなたに起こることだろう。音楽家または作曲家が、彼の音楽活動で しかし、このエラーから逃れるためには、♭記号を伴ってCに入力されたシラブルまたは音符faはそこから削除され、以前に見つかった場所ではなく、コンマの間隔で 驚くことではないが、アーロンの立場は本質的にスパタロやデルラゴの立場と同じなのである。しかし、1540年代の半ばには、たとえば、♭記号はCを下げないなどのより伝統的な見解から自分の見解を守らざるを得ないと感じていることは、注目に値する。 我々は、後者の(伝統的な)見解が、当時まだ非常に広範であったと推測するだろう。アーロンが、フラットがCまたはF、そして♯化した |