| 5 The Historical Context of St Martial and Calixtine Polyphony |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | |
| 次のページへ |
| St Martial and Calixtine polyphonyの再構築は、中世のポリフォニーの歴史にさまざまな影響を及ぼしている。これらは注意深い精査を必要とする。理論は、たとえ内部的に首尾一貫していても、仮説のスタイルのルーツと後の音楽への影響の可能性を合理的に説明できない限り、疑わしいかもしれない。 (もちろん、自然発生の過程を通じて、与えられたスタイルが孤立して生じたと仮定することもできますが、これは受け入れられないと思います。) この章では、St MartialおよびCalixtineのポリフォニーの和声指向が、すべての初期のポリフォニーに浸透した同様の和声指向の拡張であることを示す。実際、10世紀と11世紀のポリフォニーに特徴的な多くの特徴が、St MartialおよびCalixtineの2つのレパートリー内で現存している。 また、St MartialおよびCalixtineの2つのレパートリーの特定の要素が、後の音楽、特にノートルダムの要素でどのように生き延びているかを示し、12世紀後半の重要な様式の変化のいくつかを説明する。このプロセスの一環として、選択的仮説によって示される弱点についてコメントする。(略) p92lt. 現代の孤立した現存例がこれらの時代を代表していないとすれば、ポリフォニーの初期の発達で起こった変化のプロセスを理解する機会はほとんどない。現代の文書の不安定さを認識している間、私たちはこれらの資料が現代の慣行を歪めないことを期待する以外に選択肢はない。 これらの状況下では、必ずしも特定の例の間ではなく、同等の例のグループ間で得られたであろう一般的な一連の関係を想定することが可能である。 ヨーロッパのポリフォニーの最も初期の理論的記述に続く数世紀の間、作曲家がポリフォニック複合体のいくつかの声部を、同時にではなく(各パートづつ)連続して作成することが通常の慣習であった。 ほとんどのconductusのように、構造的基盤がcantus prius factusによって提供されなかった場合でも、作曲家は最初にテノールを書き、残りの声を一度に1つずつ追加するようにアドバイスされた。 この種の作曲技法の結果として、Ars Antiguaの間だけでなく、アルス・ノヴァでも、さまざまなソースでさまざまな数の声部で現存している個々の作品が見い出されることがよくある。 さらに、13世紀のモテットの中には、共通のポリフォニー核を使用する作品の族があり、多くの場合、個々の作品に固有の1つ以上の声部部分によって補完されている。 中世の作品の実践に関するこれらの非常に基本的な事実の認識と、中世のポリフォニーは本質的に概念的に線形である(訳注;垂直的和声の認識が乏しい)という結論のスタンスは、1つのステップに括り入れることができる。 そして、さまざまな中世のレパートリーで示される和声の性質の感覚は、ルネサンス後期に得られた感覚とは大きく異なり、さらに最近は、私たちはしばしばこの一歩を踏み出すようになりました。 そうすることで、重層的作曲(訳注;ポリフォニー)への2つのアプローチ(訳注;垂直的思考か、水平的思考か)の間に存在する重要な違いはなくなる傾向にある。一方では、新しい声部の形状は垂直方向の考慮事項によって厳密に管理されるが、他方では、連続して作成される部分は、形式の問題ではないにしても、少なくとも詳細の問題では、大部分が自明のこととなる。Luwigは言う。 これまでに述べられたオルガヌムは、本質的に note-against-note書法を超えるものではなかった。したがって、vox principalisは、元のメロディーの高低点(リズムの実行にとって非常に重要であることが多い)が2番目の声部の追加によってメロディー効果が弱められたように見えても、ポリフォニック作品で元のリズムを保持できたのだ。 実際、特定の状況下では、これらの影響は多かれ少なかれ正反対であった可能性がある。新しいメロディーに追加されたvox organlis は、まったく同じリズムで、音が少しだけ多くなったり少なくなったりすることはめったにない。 5 p92rt. ルートヴィヒの主張の本質は明確ではありません。彼は、vox Organalisのプロファイルを考慮して、vox prinicipalisのものと矛盾する一連のリズミカルなドライブを生成した可能性があります。しかし、そのような対立は、彼が選んだ高低のポイントに限定されません。 おそらく彼は、反行と声部交差から生じる対立を想定していた。しかし、通常の状況下では、cantus prius factusの個々の旋律のピークと低点はそのままである。下声部のピークが以前にそれをカバーしていた声部より上に上がる限り、それらは強調されることさえある。逆に、上声部の低点は、通常は下声部のレベルより下に下がる。 vox organalisがvox principalisとが平行に動き、確立された方向に進み、後者が(音程の)方向を逆にした場合にのみ、高低が変位する。検討中のスタイルの和声進行を管理する慣習は、そのような形式の運動をほとんど規定していない。十分な特異性が欠けているため、ルートヴィヒの主張は弱いようである。 ポリフォニーがリズミカルなディテールに及ぼす可能性のある影響について推測したい場合は、以前はメロディーによって一方的に支配されていた領域(ヨコのつながり)への和声的なパワーの入力に仮想的な変化を帰する方が簡単です。 p93 lt. 後の音楽に目を向けると、個々のクラウズラとモテットのいくつかの声部のフレーズの長さの違いについての過去の説明が検討されることになろう。一部の学者は、このよく知られた特徴を、いくつかの声部の構造的独立性と初期のモテットの概念の完全な線形性の主要な例と見なしている6。 6 " This view underlies Finn Mathiassen, The Style of the Larly Motet (Copenhagen, 1966): 'the composers were given a completely free hand with regard to the form of the motet upper voice' (p. 9 1); 'A medieval motet should not be read vertically like a modern score' (p. 77). 一方、 Finn Mathiassenは、問題の別の見方を促す。 1つは和声因子の強調である。この美的問題の鍵は、ディスカント的テクスチャ構造のより明確で一貫性を実現したいという作曲家の願望にあると思われる。 同じ時期に、Erwin Panofskyがモノグラフ「Gothic Architecture and Scholasticism」で指摘したように、同様の目的が視覚芸術と哲学の両方で機能していた。確かに、パノフスキーの中心的な議論を、13世紀初頭のモテットに焦点を当てた比較と非常に密接に並行させることは可能である。 I 200年前後の学識ある音楽家が持っていたリズムの概念を考えると、構造の明瞭さを達成するための主な手段は、休符によるテノールのリズムパターンの描写であったのは当然である。これらの休符は音楽の流れを中断し、テノールの動きを離散的で等しい時間セグメントに分割する。これは、一連の列が身廊の長さを進むにつれて、目が等しい空間間隔を認識するのに役立つのと同じである。 しかし、ある音楽の問題の解決には、別の問題の作成が伴った。このように構築された作品の構造的基盤は、連続性に欠けています。いくつかの接続要素が建築構造の柱をリンクしなければならなかったのと同じように、クラウスラやモテットが過度に呼吸困難にならないようにするには、音楽の動きの絶え間ないギャップを埋める方法を見つける必要もあった。so too was it necessary to find a way to bridge the constant gaps in musical motion if the clausula or motet was not to be excessively shortwinded. p93rt. これは、上声部の言い回しの違いの主な機能の1つであると私は主張する。継続性は、上声部に大きなフレーズを作成するか、フレーズを重ねることによってのみ実現できる。言い換えれば、フレージングの違いは、テノールの構造を無視するのではなく、その声部によって作成されたニーズと問題に対する前向きでよく考えられた反応を表している。 議論された2つの例は、聖マーシャルの作曲家が「依然として主にメロディストである」7という主張が、線形方向の伝統に良く適合していることを示している。しかし、私たちが初期のオルガヌムの声部の性質を再検討するならば、私たちはそのような視点を変える理由を見つけるであろう。 Musica EnchiriadisとScolica Enchiriadisで議論されている、ヨーロッパのポリフォニーの最も初期の現存例に目を向けると、厳密に並行したオルガヌムでは、追加された声部(vox organalis)に関連した創造的衝動が可能な限り低いレベルにあることがわかる。(平行オルガヌムは創造的ではない) メロディックな創造性について話すことはできません。和声的衝動は、単なるオクターブではなく、平行四度、または五度の追加による響きの豊かさで構成されている。 Musica Enchiriadisに記載されているモディファイされたオルガヌムには、わずかに異なる構造の原則がある。 8 それでも、vox organalisが全体を通してvox principalisと平行していないという事実にもかかわらず、ここではメロディックな創造性の増加について話すことはできない。 2つの声部の違いは、主に、vox principalisが移動している間、vox organalisを静的に保つことによって生じる(例I)。  例1 ユニゾンでのオープニングに続いて、和声的不安定性の要素がcantus自体に固有の進行生成要素に追加される短い瞬間がある。音楽は、最初の安定した協和音に達するまで進んでいく。 p94 lt. この時点で斜行は止まり、カデンツまで平行な動きが引き継がれる。Within the central section, the polyphony floats along, being shaped by the melodic and rhythmic elements responsible for the shape of the cantus. カデンツでは、ユニゾンに達する短い動的和声モーメントが再び出現する。 このダイナミックな和声要素を生み出すために、二度と三度が積極的に求められたとは思われず、それらは偶発的な副産物であった可能性がかなり高い。しかし、最終的には、和声の安定性の欠如と、フレーズを開始、終止させるユニゾンよりも中央の四度の安定性が低いことに気づくことだろう。 この初期形態のポリフォニーで機能する主な建設的原理-the alternation of brief periods of harmonic change with longer periods of static harmonie-は、グイド・ダレッツォによって記述された慣行やWinchester Troperにおいて、程度の差はあれ、修正されて存続している。 prosesのいくつかの設定で発生する一連の装飾された平行五度で、スタイルのその他のあまり明白でない念押しが観察される場合がある(第4章、例2を参照)。 なぜ五度または四度が、他の音程よりも、初期のポリフォニーの主な基礎を提供する必要があったのか、を説明する理由が考えられてきた。 ヨーロッパのポリフォニーの発達を倍音列の展開に関連付けようとする人もいる。人間の声の主要なクラスの自然な範囲を検討している人もいれば、初期のオルガンで演奏される音楽との関係の可能性などを検討している人もいる。 p94 rt. 実際の回答は、要因の組み合わせにある可能性が高いので、ここで追加の1つに言及したいと思う。 初期のポリフォニストは、意識的であろうと無意識的であろうと、過度にダイナミックな性格のために、同時にプレインソングから注意をそらさないであろうチャントの豊かさを求めていたように思われる。 言い換えれば、使用される音程は比較的安定していて、おそらく質が静的である必要があった。五度と四度は、これらすべての条件を満たす2つの音程なのである。オクターブだけでは、倍音の深さを十分に感じることはできない。二度、七度、 三度でさえ、倍音の観点からはより動的なのである。 明らかに、全音階的旋法内の三度の連続は、長調から短調に何度も変化(例;たとえばレーファーラード)している。しかし四度と五度は、オクターブの流れで1回だけ性質が変化(増、減音程ができる)し、五度に関しては、Musica Enchiriadisで説明されているdisjunctテトラコルド(Hermann's Major Sixth BY RICHARD L. CROCKER p26参照)で構成される音階では、この変化は排除された。 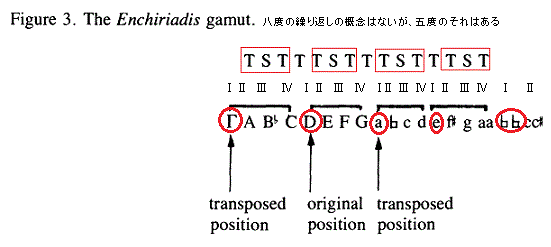 disjunctテトラコルド さらに、初期のチャントの根底にあるペンタトニックの基礎に関する提案が有効であると考えられる場合12、4度と5度の重要性がさらに強調される。特定のペンタトニック構造に応じて、四度、または五度のいずれかが、ペンタトニックcantusの各音符の設定に一貫して使用できる、オクターブ以外の唯一の音程なのである。 チャントが全音階のすべての音程を採用したとすると、作曲家がよりエッセンシャルな音(つまり、古いペンタトニックフレームワークに属する音階)と装飾的な付加詞を区別したと仮定した場合、この考察はそのまま有効である。 p95lt. <三和音の扱いの変化> 長期間の相対的な調和の安定性に対するこの欲求は、St Martial and Calixtine のポリフォニーで発生するムジカフィクタのある種の問題に光を当てる可能性がある。 音符b、e、およびfが垂直および線形の組み合わせで使用されている箇所があり、編集上の臨時記号の提案によって減五度を回避すると、三全音の存在のみが発生する。その逆も同様(三全音を回避すると、減五度の存在のみが発生する)。 おそらく、10世紀から12世紀初頭のポリフォニストは、五度から四度、または五度から他の音程に変更する方がより動的であり、したがって(五度から四度、または五度から他の音程に変更することは)、(五度から)減五度に変更するよりも望ましくないと感じていた。 減五度和音の使用は、vox organalisの旋律の進行とvox principalisの旋律の進行の生の平行進行を許容することとなった。  このようにして、減五度は、機能的協和音の外縁内で許容された可能性がある。実際、増四度と減五度を協和音として分類するいくつかの理論的研究があるのだ。協和音のこうした形式の使用につながった特定の状況(平行音程の長列の使用)は、(聖マーシャルとカリクストゥスの)2つのレパートリーの時代までにかなり少なくなったが、おそらく慣性のために、その伝統は残っている。 この慣性を克服し、増四度と減五度を和声的不協和音に変換するのに寄与した要因の中には、オルガンポイントの使用法の発達があったと思われる。中程度から長程度のメリスマの下で持続するf音は、上声部に書かれたb <第2期 自由オルガヌムの時代(11世紀後半)> 明らかに、ヨーロッパのポリフォニーの進化における決定的なターニングポイントは、新しく作成されたオルガヌム声部を形作る上で重要な要素としての反行の発達であった。 Winchester organaと同時期の初期段階で、反行は採用されたように思われ、その重要性はJohn [of Afflighem ?]の論文で明確に概説されている。 13 vox organalisの進行を制限していた命綱を壊したのが反行であった。最も初期のオルガヌムでの新しく作成された声部に存在する線形要素が、借用されたチャントの線形構成に起因することがわかっている。新しい響きを担った音楽家が制作したものではない。 p95 rt. St MartialとCalixtineのポリフォニーの上声部の形が主に線形(各声部のヨコの流れ)によって決定され、これらへの関心が、以前に確立された伝統を反映している場合、11世紀までに登場した新しいスタイルのポリフォニーに存在する線形指向の性質を確立することは可能であろう。 しかし、私は、この音楽の主に線形の理論的根拠を示すことができるとは思わない。それどころか、オルガヌムの声部スタイルは、既存のメロディーのスタイルからの大きな変化を表しているが、これらの声部のプロファイルと編成は、和声的要件への関心から生じている。 ・オルガヌムメロディーとチャントメロディとの違い 新しいオルガヌムメロディーとチャントとの顕著な違いの1つは、前者で考察できる活動の程度に関係している。 これは、音程の内容と音域の双方の問題である。チャントでは、ステップ進行(一音づつの進行)が一般的であり、繰り返し音と三度のスキップと自由に組み合わせて使用されている。大きなスキップは、メロディプロファイルを決定する上で重要な役割を果たす場合があるが、全体に占める割合は比較的小さい。 たとえば、イースターのミサ固有文を考えると、イントロイトのアンティフォンは、70 seconds, 46 unisons, and 22 thirdsとなっている。四度ないしそれ以上は2か所である。聖体拝領では、7I seconds, 25 unisons, 24 thirds and 3 intervals of a fourth or moreである。 よりアクティブなチャントでは、三度以上のスキップの割合がいくらか上昇するが、全体的なバランスは大きく変わらない。同じミサのOffertoryには、55 seconds, 26 unisons, 32 thirds, and 7 skips of a fourth or moreである。 The Respond and Verse of the Gradualは、それぞれ 67 and 73 seconds, 26 and 29 unisons, 40 and 3 5 thirds, and I and 4 intervals of a fourth or moreである。 Alleluiaの2つのセクションには、同様にそれぞれ、29 and 66 seconds, 7 and I 6 unisons, I3 and 24 thirds, and 4 and 10 larger skipsとなっている。 Omitting the second half of each of the paired versicles, the Sequence consists of 69 seconds, 9 unisons, I 7 thirds, and I2 larger skips. <Kyrie Cunctipotens genitorとBenedicamus Domino> ここで、論文Ad Organum faciendumのAmbrosiana写本の付録に記載されているKyrie Cunctipotens genitorの設定に目を向けてみたい。14 cantus prius factusでは、メロディー音程の半分以上(64のうち37)が二度であり、4分の3近く(46)が二度またはユニゾンである。三度より大きいスキップは4つだけである。 p96 lt. オルガヌムのパート(下譜上声部)を調べると、ほぼ逆の状況になる。メロディ音程の3/4は、スキップであり、1/4以上が三度より大きい。対照的に、メロディ音程の1/5以上は、一度づつの音程となっている。  訳注;例1と比較して、vox principalisとvox organalisが逆転していることに注意 同じ写本のBenedicamus Dominoの主設定では、定旋律がより活発である。したがって、声部の間のコントラストは減少しているが、それでもかなり残っている。(例3を参照)。 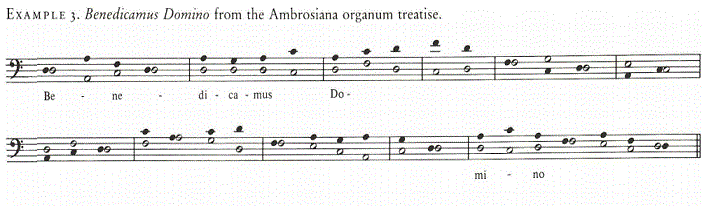 我々は、オルガヌムのメロディー構築では、単なる音程比の変更以上のものを扱っている。このレベルでの違いは全体を通して一貫して考察されることではないが、進行自体はしばしば異なる。 Cunctipotens genitorのvox organalisの冒頭の五度→三度の上昇は、チャントではかなり頻繁に見られ、最初のフレーズの残りの部分には、特に新しい要素は含まれていない。しかし、 'omni creator'という言葉に続く、第1,2Kyrieの「e-(leyson)」の一部としても見られる四度→三度の上昇は、チャントでは明らかに非常にまれである。 15 第3Kyrieの後半で発生する四度の降順の連続、「-e」-bについても同じことが言える。 16 上向きのスキップの連続('spiramen'の設定を参照)、または上向きのステップと連続音の組み合わせ(”sophia”の設定)のいずれかによって達成される終止は、通常のチャントでは見られない。 p96 rt.これらの各特徴には、簡単に説明できる和声機能がありますが、純粋に線形な方法で説明するのはより困難である。実際、四度の上方へのスキップと、それに続く同じ方向への三度のスキップは、標準的なCalixtineとStMartialのポリフォニー進行での五度やオクターブへのユニゾン冒頭の和声公式の一時なのである。(第4章、例10を参照)。 前に言及されたBendicamus Domino についての進歩は、以前に知られている様式からのさらに強い相違を示している。 たとえば、f 'からcへの11度の尋常ではない下向きのラッシュ(ファレファド)が、3つのメロディー間隔のスペース内で発生し、その後に短いジグザグの動きが続き、さらに三度下に下がることに注意されたい。 これは、当時のモノフォニックなレパートリーには相当するものがない状況なのである。 そして、最低レベルがA-c-Aとなってはっきりするや否や、メロディーは急激に上昇し、3つのメロディー間隔のスペース内で十度の間隔を上ることになる。 メロディーの全体の存在理由が和声的であり、完全協和音が支配的となっている(例3)。 確かに、パフォーマンスの過程で可能な装飾を考慮に入れる必要はある。我々がメロディックなgaucheryと見なすものは、中間音の導入によってよりスムーズに、より論理的になったかもしれない。しかし、こうした状況下でも、これらの作品の背後にある主要な生成したインパルスはハーモニックなままである。メロディ目標はすべて、和声的ニーズによって決定される。 p97 lt. これらのメロディ構成はまた、チャントのそれからは異なっている。さまざまな構造的アーティキュレーションは、写本内で縦のダッシュでマークされている。 これらのダッシュの直前のすべての音程はユニゾンまたはオクターブのいずれかであるため、音楽はこれらのポイントで最大の和声的安定性を達成している。 よく知られているように、Ambrosiana写本は、Benedicamus Dominoの合計3つの設定を提供している。これらは、垂直ダッシュの使用方法が異なる。 代替バージョンの1つで、vox organalis がvox principalisに対してオクターブ音程内の場合、vox organalisの最初のバージョンに存在しているダッシュは、(こちらの代替バージョンでは)省略される。 さらに、平行オクターブとユニゾンの唯一の例では、これらのダッシュは全体的に生じている。 これらが基本的に「死んだ」音程であるという提案は、これらの様式の特異性の合理的な説明をする。 言及された過度に膨張したオルガヌムの「線」は、主に、明らかに結合する機能がほとんどなかった大きなスキップのために生じる。 この構造の見方によれば、Cunctipotens genitorは次のように説明できよう。 最初の3つの言葉を設定する冒頭の部分は、4シラブルのouvertセクションで構成され、その後に5シラブル分のclosセクションとなる。 これに続いて、'omni creator'という言葉を設定する簡単な進行が続く。次のシラブルの短いメリスマは、2つの4音符セクションに分割される。これらのセクションは、双方が、ユニゾンに収束しオクターブに分かれる形になっている。 これらのメリスマの2番目は、五度→オクターブへとなるが、Christe eleisonの終わり近くで再度このパターンが生じる。 第1Kyrieもまた、五度→オクターブへとなる。 Christeは、多くの小進行の集合体として同様のやり方で構築されていることだろう。これらは、2-2(christe dei)、2(splendor)、2-3(virtus patrisque)、3(sophia)、4(e-)、2(-leison)にグループ化されている。 第3Kyrieを構成するグループは、全体として大きくなっている。前のセクションのものよりも、それぞれ5、3、5、6、2の間隔で分けられています。例3で与えられたBenedicamus Dominoの構造単位のどれも四度を超えない。 p97 rt. この(ここでは小節線で)小分けされた形の構造は、通常、個々の言葉の明瞭さをはっきりと浮き彫りにしている。この特性の残照は、St Martial and Calixtine polyphony. でも観察されることだろう。 この付加的な構造プロセスとの類似点は、中世音楽の他のセグメントだけでなく、中世美術にも見られる。 多くの場合、ミニチュアや絵画は、知覚的な統一としてではなく、個々のオブジェクトやシーンの集合体として構築される。そして、加法プロセスが視覚運動の知覚に影響を与えるのと同じように、聴覚リズムのパフォーマンスと知覚にも影響を与える可能性が高いように思われる。 提案された分析のタイプと正当化を支持して、プレインソングからポリフォニーへのリズムのわずかな変更を結論付けることは合理的である。 少なくとも、ポリフォニーは小さな枠組内を移動するように見える。プレインソングのメロディーの明らかな目標は、和声進行の目標でもあることがよくあるが、その逆は同じとは限らない。 一例を挙げると、第1キリエの最後から2番目の音符eが、モノフォニーでの文脈よりもポリフォニーでの方がリズム的に重要であったと考える理由がある。ポリフォニーの場合、それは予備的なリズムの目標として表示され、モノフォニーの場合、先に進むターンの一部として示される。 Ambrosiana写本の作品の構造のこうした見方は、論文自体に記載されているポリフォニーの作曲の途中でサポートを見つける。 これらの手順は、音程進行に焦点を当てているだけでなく、当面の目標に非常に強い関心があるため、旋律の力を最小限に抑えている。オルガヌムのメロディーは、チャントのようにバランス感覚と慎重に形作られたクライマックスで、長期間にわたって自然に発達することはないが、しかし、ほとんど偶然に、一連のポイントをつなぎ合わせることで発生する。各ポイントは通常、何らかの合理的な形式の和声論理によって前のポイントに関連付けられている。 当然のことながら、論文は、より想像力に富んだ作曲家の創造性を制限したりすることはない。しかし、現存している音楽の分析が理論家の説明によって裏付けられているという事実は、その適切さの指標となる。長い線で考える傾向を一時的に抑制し、これらの初期のオルガヌムのメロディーをチェーンリンクのグループから構成されていると見なすと、いくつかは強く連動し、他は弱く、さらに他は単に隣接しているだけとなり、作曲家の思考をかなり正確に捉えることができる。 <Chartres fragment, MS 109> 前述の発言を現在の関心にリンクする前に、破壊されたシャルトルフラグメント、MS109のポリフォニーの検討に進みます。 p98 lt. ここでは、オルガヌム声部でのconjunct進行の使用が著しく増加していることがわかり、それは、主に和声間隔のより多様な組み合わせを認めることによって可能になった。 三度は、Ad Organum faciendumの簡単な例とその論文で提供されているAlleluya Justus ut palmaの設定で認められているが、頻繁ではない。(Alleluya設定には、六度の一例がある。) 一方、Chartres fragment, MS 109作品のグループにおいては、五度の割合が大幅に減少しており、代償として、三度が多く、二度は適度で、六度は少なくなっている。 やや予想外のことは、断続的に交差する声部によって生成される連続した二度の出現である(例4を参照(略))。 しかし、よりスムーズな形の出現にもかかわらず、メロディー書法、オルガヌム声部は、主に和声的要素によって形成される。それは、チャントや他のほとんどのモノフォニックレパートリーで、通常よりも音域がさらに極端になっている。チャントは、Alleluia Surrexit Christusのオルガヌム声部のように、ターニング前に1オクターブにまたがる直接下降では始まらない。また、通常、この声部と最高音でのカデンツの引き続きの部分のように、着実に上昇することはない。 チャントのプロファイルはより曲がりくねっている傾向があり、チャントフレーズがカデンツに向かって上向きに移動すると、通常、終止前に高いピークに達し、その後わずかに下降する。 そのような一般化の例外が見つかるかもしれないが、これらでさえ明らかになっている。よく知られている賛歌旋律 Pange lingua gloriosi corporis mysteriumは、Alleluia SurrexitChristusで説明したのと同様の半カデンツに達する。 p98 rt. しかし賛歌では、動きがピークですぐに再開し、ターン(c'-d '-c'-c' -b-a-c ')に続いて、不安定なピークが最終的に下向きにbへと段階的に到達する。不安定なピークは、bで最終的に下向きの段階的な解決に向かう。これは、さらに下向きのconjunct motionの一部である(例5)。Alleluia SurrexitChristusのオルガヌムパート(上声部)ではしかし、このような形のメロディックな解決とリラクゼーションはない。c 'のピークはそれ自体が目標であり、その後、七度の急激な下方への跳躍がある。 この賛歌 Pange lingua gloriosi corporis mysteriumは、より後の日付のものであり、1263年に教皇ウルバヌス4世によって制定されたCorpus Christiの祝日のために聖トマス・アクィナスによって書かれたと言われている。(したがって)後から作られたチャントは、以前のポリフォニーで導入された旋律の形に影響された可能性は十分にある。 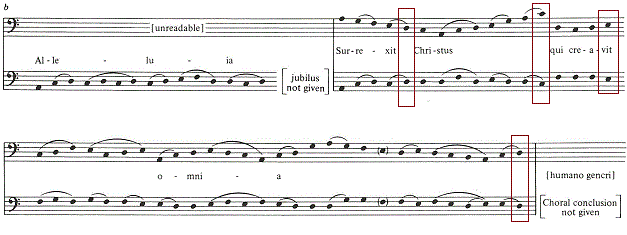 Alleluia SurrexitChristus シャルトル断片より 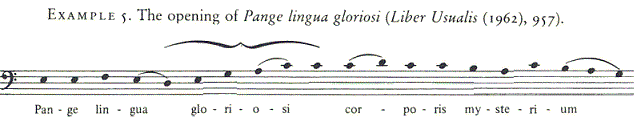 Ambrosiana organum treatiseのキリエCunctipotens genitorは、その狭い音域の目標がテキスト構造への関心によってある程度決定されていたことを示唆していることが先に示されていた。 19語のテキストのうち12の最終シラブルが、オクターブまたはユニゾンに設定されている。これらの場合のそれぞれにおいて、copulaは写本の中で縦線でマークされている。 Chartres fragmentでは、曲の音楽構造に対するテキストの同様の影響はさらに強くなる。以下に、解読可能な各ポリフォニック部分に付随するテキストを示す。ユニゾンまたはオクターブで終わる各単語はイタリック体で示されている。(略) p100lt. 1つの例外を除いて、すべての多シラブルの単語は、これら2つの安定した音程(ユニゾン、オクターブ)のいずれかで終了している。そうしないあらゆる種類の単語は、「qui」、「et」、「de」、「et」、「de」、および「Dicant」だけである。 ユニゾンとオクターブでの終止に関する同様の関心は、テキスト構造の問題とは別に(というよりは、それに加えて)、これらの作品のメリスマ的な部分の中で識別されるべきである。この点を説明するために、私は読者の注意を、Alleluia Christus resurgensからのフラグメントのシラブル「mors」を設定するメリスマに向けたい。次のスキーマでは、ハイフンがオルガヌム声部の連結符内の間隔の進行を結び付けている。セミコロンは連結符の終わりを示す。 p100 rt. 括弧は、リキッドネウマによって暗示される音程を示す。(略) 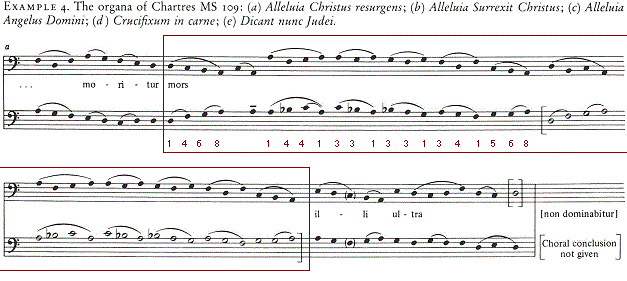 p101lt。 Chartres fragment 全体の和声の不安定な点と安定した点の間のより鋭いコントラストは、音楽に対してより鋭いリズムのプロファイルもあったことを示していることだろう。このプロファイルがより明確なアーティキュレーションによって、アクセントのある拍によって、より安定した音に応じて作成されたかどうかにかかわらず。19 19 一方、Dom Anselm Hughesは、「私たちはおそらく、和声の作曲家がグレゴリオチャントの古くて滑らかな流れに新しいリズムスキームを重ねることを望まずに、音符ごとに進んでいるのが正しいとするだろう」と示唆している。 この性質の研究では、聖マルシャルとカリクスティンのレパートリーに先行するポリフォニーの各例を扱うことはできません。すべてが同じ布から切り取られるわけではありません。しかし、ここで調べた部分で観察できる要素は他の部分にも見られ、提示された証拠は意味のある要約を可能にします。 反行の原理の発達は、それとともに、和声の原理に基づいた新しい旋律芸術をもたらした。上声部は、通常は、神聖なモノフォニーのオープニングには使用されないようなピッチで始まる場合がある。終止音は、多くの場合、チャントに対する通常の終止音ではない。多くの場合、音域はより極端である。新しい音程パターン、特にグレゴリオチャントに通常ではないスキップを採用しているパターンは明らかである。 さらに深く掘り下げ、同時に簡素化することができる。たとえば、上声部が、グレゴリオチャントで採用された最後の声よりも1オクターブ高く終わる可能性があるというだけではない。その音符で終わることによって、その音符を目標として持つことによって、全体の旋律のプロセスは根本的な変化を遂げた。 新しいスタイルは、基本的な違いの数にもかかわらず、St Martial and Calixtineのレパートリーのスタイルに関連付けることができる。 確かに、St Martial and Calixtineの2つのレパートリーのメロディーは、Ambrosiana論文に付随するものよりもconjunctな流れである。それらは、アンブロジアーナの作品にもシャルトルの断片の作品にも見られない標準的な装飾要素を備えている。対称的な構造、繰り返される音形、およびシーケンスの数が著しく増加している。 それにもかかわらず、これらすべてのレパートリーの間の根底にある親族関係は、メロディーがしばしば同様の和声の進行から生じるという事実を通して、小規模で示されることだろう。特にシャルトルの例に関連して私たちが指摘した音楽構造に対するテキスト構造の影響は、第7章で示されるように、聖マーシャルのレパートリーに明確に存在する。 p101 rt. より大規模な学者は、Calixtine写本中のCunctipotens genitorの基礎となる構造が、論文Ad organum faciendumの例の構造と密接に類似していることをすでに確立している。20 さらに、St Martial Benedicamus Domino、Humane prolis、および前述の論文Ad organum faciendumのBenedicamus Dominoの冒頭(例3 p96 lt.)の間にも、同様の類似点が示されている。 21 St MartialとCalixtineのポリフォニーのリズム様式は、最終的には、論文Ad Organum faciendumに関連して与えられているような初期のポリフォニーに固有のリズム原則に由来している。 さまざまな理論家の教えに従って、初期のポリフォニーは、ある意味ではmoderateと表現されるかもしれないが、実際には速い音価がないために、遅い印象を与えたテンポで実行された。ほとんどの場合、音価は基本的に同じである可能性があるが、そのパフォーマンスは強拍の感覚を生み出さなかった。それどころか、内部構造のアーティキュレーションの必要性は、規則的な厳格さからの逸脱をもたらした可能性がある。 さらに私は、主カデンツで音を長くするために、大まかに計量的な比を使用する可能性があったことを認めたい。 基本的に、これは、前述の例外を除いて、「equalist」様式のパフォーマンスになる。 この章の前半で与えられたこの音楽の解釈に従って、そのようなスタイルの演奏には内部的な正当性があり、この時点でチャントの古いリズムの伝統が消えていて、音価の均等化に向けてその後の変化が進んでいたという歴史的な正当化がある。 さらに、ある程度の初期のポリフォニーは、即興で演奏されたように見える。 本質的に安定した動きの仮説は、そのような即興のための実用的なリズムの基礎を想像することを可能にするであろう。 そして、そのようなスタイルは、St.MartialとCalixtineのポリフォニーの多くで想定されている本質的に等時的なベースを提供する。 Cuncti potens genitorの前の分析で示されたように、局所的な和声進行には、規則的には、音の均等な数含まれていなかった。the local harmonic progressions did not regularly include equal numbers of tones.(全体の和声の不安定な点と安定した点の間のより鋭いコントラストがあった) したがって、基本的に等しい音価を使用しても、音楽に韻律的階層は生じなかった。この意味で、リズムは「自由」と表現することができよう。 p102 lt. また、作曲家は既存のリズム的対称性の概念を出発点として採用していなかったため、ほとんどの音価で仮定された等価性は、ポリフォニー作曲の必須要素ではなかった。 上声部の精巧さとより大きな旋律の滑らかさの必要性が感じられたとき、ほぼリズム的に中立なこの立ち位置から、主声部のリズムの扱いのより大きな不規則性に向かって移動することが可能であった。 一方、作曲家は、規則的な旋律と和声進行を生み出すことによって、より対称的な、階層的な形のリズム組織を提案することも同様に可能であった。 両方の道が進んだ。前者はチャントと散文の設定で取り入れられた。後者はversusで採用された。両方の精査がほぼ同時に、同様の場で行われたように見える。 22 22 One may compare the contrasting styles of Catholicorum concio and Noster cetus, both of which are preserved in lat. I I 39. また、これらのプロセスには、Adsit johannis Baptisteで主流となっていた古いスタイルの完全な転覆は含まれていなかった。 新しいスタイルで発生する最も重要な出発点は、装飾のプロセスを含んでいる。そして、このプロセスは、 lat. I I39での聖マーシャルポリフォニーの最も初期の層の時にすでによく発展していた。 装飾の効果- note-against-note 進行の崩壊−は、ポリフォニーに新しいレベルのリズム活動を生み出し、その手段がこれを記譜法で表現することを要求することであった。 協和音の安定点の以前の原則(シャルトルのオルガヌムではっきりと観察できる)は、新しい装飾スタイルのサービスに明らかに適応された。 この時点で、リズム形と和声配置を示すわかりやすい手段の必要性は、テキストの歌詞付けの考慮事項を上回った。 p102 r 表記法の革新的な改訂を行うことは可能であったが、慣れ親しんだものを適応させ、固有の問題を徐々に解決する方がはるかに簡単であった。装飾自体の過程で、装飾的な音色は弱拍で自然に発生し、構造的な音符よりも占有する時間が少ない傾向があった。表記自体は音楽の動きをグラフィックで表現したものになり、特定の現代の時空間表記とあまり違わない方法で操作された。 (次の章でこの概念に戻ります。) 装飾と表記の相互関係の詳細な説明は、Ad honoremのパッセージとそのcontrafactum Gratulantes celebremusの対応するパッセージとの比較の形で入手できる。これは、2つの形式で表される。つまり、(I)各シラブルに等しい音価を割り当てて従来の整列方法に従って取得する形式と、(II)機能的協和音の仮説に従うことによって取得する形式である(例6)。 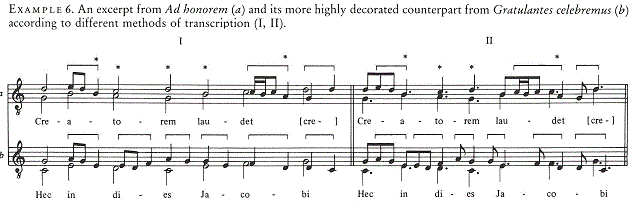 伝統的な解釈(I)によれば、構造音の一貫したリズム変位があるが、ここで推奨されているもの(II)では、それらは通常の場所にとどまる。2つのレパートリーの作品を担当する作曲プロセスは段階的に進行し、最初に構造的なフレームワークが構築され、後で装飾的な要素が適用されることはない。オルガヌムのメロディは、装飾的な要素にはある程度の柔軟性があるが、間違いなく、全体として発達した。 現存の証拠は、装飾されたバージョンと装飾されていないバージョンを集中的に対比する追加のパッセージを開示しない。ただし、同じ原理の孤立した状態を示す例が不足しているわけではないので、例7に一連のそのような抜粋を示す(プリカトーンの存在は、ここや他の場所で、メモを通る短い斜めのストロークで示される。)。 p103 lt. この例に示されている使用法の例外が見つかる可能性があることに注意することが重要だが、これらは一般的な慣行を否定するには少なすぎる。他の要因が等しい場合、構造的なトーンは、オプションの装飾要素によって置き換えられるよりも、通常、強拍位で慣れた場所を保持している可能性が高くなる。 機能的協和音の仮説に対する既知の代替案はすべて、the St Martial and Calixtine2つのレパートリーの出現前に、強拍位での不協和の採用が突然かつ急激に増加することを前提としている(だからそういう代替案は存在し得ない)。 p103rt. さらに、the St Martial and Calixtineの2つのレパートリーが使用されなくなると、そのような不協和音の慣行も同様に急激に減少したと考えられる。これらの仮説はどの学者によっても明確にされていませんが、採用された転写方法の必然的な結果である。以前のポリフォニーの簡単なレビューでは、the St Martial and Calixtineのレパートリーで伝統的に仮定されていた不協和治療の前例は示されなかった。連続する交差する二度の数ペアでさえ、私が争っている理論の原点と見なすことはできない。また、そのような不協和音の使用法の説得力のある続編もない。ノートルダムレパートリーの矛盾する記述がまだふるいにかけられ、計量されているという事実にもかかわらず、このレパートリーは主に強拍位に当たる協和音に基づいていると考えられています。 p104 lt. そのような方法で対立仮説の調和的な意味を述べることが可能であるというまさにその事実は、私たちを警戒させることだろう。 不協和音の実践における著明な変化は1600年頃に生じ、そして20世紀の変わり目に再び生じたが、どちらもここで検討されている範囲ではない。また、1世紀にも満たないうちに、これほど急激な二通りの不協和音の逆転はあり得なかった。 St Martial and Calixtine のポリフォニーの伝統的な解釈によって生み出されたスタイルの特徴に対して、レパートリーはもはや現存しない前兆は提供していないと仮定できよう。他の失われたレパートリーは、これらの特性を反映したことだろう。しかし、完全に消えた連続したレパートリーの存在を仮定することによってのみ、邪魔なスタイルの特徴を説明できる理論は、そのような必要性がない理論よりも弱い。 St MartialとCalixtineのポリフォニーの直線的なつながり的な見方は、他の点では不十分である。上声部に関して、2つのレパートリーのメロディースタイルが基本的に保守的なものであることを示すことができれば(古いスタイルのチャント、トロープス、または prosesに関連する)、中世のポリフォニーの発達では、作曲家が古いメロディーのスタイルをポリフォニーの新しいニーズに合わせるのが遅かったために、和声的な渋みが生じた時期があったことが示唆されるかもしれない。 作曲家が和声の感覚を身につけるには、3世紀近く(つまり、1170年頃に向けて)が必要であったことに気付くと、驚かれよう。しかし、反行の発達は、以前に存在したすべてのメロディーのレパートリーから多くの様式の本質で容易に区別できる新しいメロディーの芸術をもたらした。この新しいスタイルは、基本的に、和声的な要件に対応して形成されている。いくつかの線形要素は明らかにすべてのポリフォニーに存在する必要があるが、初期のポリフォニーの現存作では、線形要素(各声部間のヨコの関係)は要素の中で最も強力であるか、または作品の垂直方向(各声部間のタテの関係)に対する密接な関心との関連がないかは、実証されていない。 上記の段落のいくつかの点は、フラー教授とスノー教授の代替理論にも関係しており、どちらも聖マーシャルのリズムがチャントのリズムから派生していると仮定している。チャントのリズムの問題は、St Martial and Calixtine polyphonyのリズムの問題よりもさらに厄介で物議を醸している。これはある意味、2人の学者がチャントのリズムの性質に関して反対の立場を取っているという事実によって、反映されている。問題の複雑さのために、私は問題への現在の関与を最小限に保ちたい。 p104 rt. St Martialポリフォニーのリズムは、ある形式のチャントリズムから派生しているという仮説の2つの相互に関連する根拠を想像することができる。一方は様式的で、もう一方は記譜法的なことである。私は後者に対処することから始めたい。 視覚的な観点からして、2つのレパートリーの記譜法は、チャントでの記譜法である。2つのレパートリーを含む写本では、チャントの記録と、明らかに類似したリズム構造の原則を持つ他の神聖なモノフォニーの本体(つまり、versus and tropes)の記録の両方に対して、同じ表記法が採用されている。したがって、この種の表記法が発生するときはいつでも、この表記法の有効な解決法が適用できるはずであると主張する人もいるかもしれない。 さらに、単一のソースを扱う場合、意味の均一性が特に重要であることが示唆されるかもしれない。ポリフォニーの表記のために提案された解釈がversus and tropesの解釈に適用できる可能性は低いようであり、それは確かにチャントの演奏には適用されない。 したがって、チャント、versus、tropes、およびポリフォニーの記録の表記形式を区別しない写本の内容の一部についてのみ正しいとは考えられないかもしれない。 こうした議論は明らかに無効である。そもそも、各パートでさまざまな数の音色を持つより華やかなスタイルの出現は、記譜法のリズム内容の根本的な変換を必要とした。一方の声部の孤立した1音がもう一方の声部の4-I2音のグループと対位して設定されることが多い場合、チャントにおけるnotae simplicesがvirgae や punctaのリズムの重要性を持つことは不可能である。 さらに、一方の声部のbinariaがもう一方の2つのbinariaに対して設定されている場合と、1つのternariaが2つのternariaに対して設定されている場合を考慮する必要がある。どちらかの声部の連結符のリズムの重要性が同じ外観のチャントのネウマのそれと同等であると私たちが考えるならば、残りの声部の連結符は明らかに大きく異なる意味を持っているに違いない。 上記の議論の根底にあるのは、中世初期の音楽を扱うときに、コミュニケーションの実体とは無関係に、コミュニケーションの手段、つまり表記法を扱うことが可能であるという効果の前提である。個々の作品の健全な生地。これから見ていくように、この前提を適用する試みは他の分野でも行われています。 たとえば、トルバドゥールとトルヴェールの音楽の解釈に注意を向けると、上記の議論を2つの反対の方法で適用できることがわかります。 At the base of the argument stated above is a premise to the effect that when dealing with the music of the early Middle Ages it is possible to treat the means of communication- namely, notation-independently of the substance of communication-that is, the sound fabric of the individual work. p105lt. 表記上の外観の同等性が、記譜上の重要性の同一や統一を示すのであったら、次のことが当てはまるはずであろう。すなわち、多くのトルヴェールシャンソニエの表記は、多くの同時期のチャントソースの表記と形式が同じであったため、トルヴェールのメロディーは、13世紀から14世紀初頭に流行したリズミカルなチャントのスタイルで歌われることが意図されていた。(つまり、基本的に等しい音価の連続で構成されるスタイルで)。 中世学者がそのような議論を普遍的なルールとして受け入れることを真剣に提案するだろうとは思わない。よく知られているように、表記上の証拠は、トルヴェールのレパートリーの特定の部分がモーダルリズムで実践されたことを示しており、そして当時のconcordancesは、モーダルリズムの存在が必ずしも計量記譜法を使用してグラフィカルに表現される必要がないことを示しているようである。 同時にLa Rhythmique musicale des troubadours et des trouveresにおけるPierre Aubryによるこの議論の別の適用を思い出すかもしれません。 23 Pierre Aubryは、いくつかのchansonniers(i.e., Le Manuscrit du Roi, Le Chansonnier de Noailles, and Vatican, Reg. lat. I 490)では、モテットの上声部とトルバドゥールとトルヴェールのシャンソンにまったく同じ形式の記譜法が採用されていると述べた。 。彼は、モテットがすべてモーダルリズムであることが知られているので、シャンソンもすべてモーダルリズムであると推論した。 上記の写本のすべてのメロディーにモーダルリズムを均一に適用すると、深刻な様式の不一致が生じることが示される。Numerous items of stylistic evidence may be advanced to demonstrate that the uniform application of modal rhythm to all of the melodies in the above-mentioned manuscripts will result in severe stylistic incongruities. 世俗的なモノフォニーのリズムに関して存在している論争に参加することなく、我々は、ルートヴィヒが、Aubryが他の形式の推論によってモーダル解釈の妥当性を確立しようとしていたまさにその時代の彼の議論を拒否したことに気付くかもしれない。 24 音楽の目的とそのスタイルに基づいて記譜上の重要性を確認する必要性は、やや後のポリフォニーの写本で特に明白である。確かに、W 1のさまざまな内容の表記についての均一なリズムの重要性を推測しようとすると、その試みがモノフォニック作品、organa, clausulae, conductus、または第11冊子の内容の解釈に基づいているかどうかにかかわらず、悲惨な結果につながる。 p105 rt. 中世の音楽家は、同じ外観の表記記号が異なるスタイルを表現するために使用された場合、大幅に異なる意味を持つ可能性があることに注意する必要があった。そして、誤った様式的または文脈的関連が時々発生し、誤ったパフォーマンスが生じた可能性は低いとは言えない。 したがって我々は、ポリフォニーの2つのレパートリーの様式的期限に関する問題に戻る。 「スタイル」は多くの特性の複合体であるが、通常、その主要な構成要素の間にはかなり密接な相関関係がある。2つのレパートリーのメロディックなスタイルとチャントのそれとの鋭いコントラストを示す証拠が覆されない限り、問題の作品に関連するリズミカルなスタイルが同等であると仮定することは困難になります。 It would appear that we may have to deal with a twofold reversal in rhythmic style (as well as the previously mentioned twofold reversal in dissonance practice).チャントのために想定されるリズミカルなスタイルが流動的で計量的ではない場合、さらに困難が生じる。我々は、リズミカルなスタイルでの二通りの逆転(前述の不協和音の実践での二通りの逆転p104 lt.と同様)に対処しなければならないことが明らかになろう。 時系列スペクトルの一端では、グイード・ダレッツォとアリボの記述は、チャントのリズムが1025年頃までは、幾何学的な比によって支配されていたことを示しているようである。たとえこれらの比の知識が明らかにその頃までには急速に衰退していたとしても。 両理論家は歌手の無知を嘆いているが、どちらも、古いチャントのリズムが計測不可能なものによって置き換えられていたことは示していない。 もう一方の一端では、 I I 70年頃までに、モーダルリズムの幾何学的な比は、少なくともレオナンのcopula and discant clausulaですでに観察可能である。そのような基本的な内容の2つの正反対の様式変化が起こったために、その間の干渉期間は非常に短い。 Jammers26、Vollaerts27、Murray28などの学者の議論を拒否し、Cardine29と彼の信奉者の議論を受け入れたとしても、フラー教授によって提案された仮説に従って、和声要素とリズム要素を調和させようとすると、困難が見つかる。 p106lt. 演奏者が、harmonic values がポリフォニーのリズムに大きく影響することを許容すれば、彼または彼女はチャントに暗示されるものとは異なるリズミカルなスタイルを作り出すだろうと私は主張します。演奏者が「自由な」リズミカルなスタイルのチャントに固執しようとする限り、彼または彼女はポリフォニーの主要な形の原因となるvaluesを無視することを余儀なくされます。 さらに、チャントまたは準典礼的なソースから由来するcantus prius factusがある場合、ポリフォニーの演奏で元のチャントリズムを維持することは不可能です。ポリフォニーが実際にチャントリズムのシステムに基づいているとしたら、これは皮肉なことです。 チャントのリズムの計量的スタイルを仮定するRobert Snowの仮説を扱う際に、別の順序の困難が発生します。アメリカ音楽学会の第36回年次総会で読まれた論文の要約に提示された要約の中で30、彼は次のように述べています。 I.中世のモノフォニック典礼音楽では、12世紀に入るまで、特定の異なる音価が使用されていた。これらの音価は、9世紀以降に明示的に表記されていた。 2.初期のモノフォニック世俗音楽でも特定の音価が使用され、これらはモノフォニック典礼音楽の表記に使用される原則に従って表記された。 3・初期のポリフォニーでは、note-against-note書法やオリジナルチャントの音価が保持され、実際のソースでは、これらはモノフォニック典礼音楽で使用される原則に従って両声部で明示的に表記されていた。 4・11世紀の第3四半期までに、2つの別々のスタイル的に異なるポリフォニックの伝統が発展し始めた。1つはフランス北部、もう1つはフランス南部である。音価を記譜するためのやや異なるシステムは、各伝統で徐々に進化たが、両方の基本原則は、モノフォニック典礼音楽の音価の記譜に使用されるものから派生した。 2つの明確に異なる伝統の発展を主に促したのは、2つの地域でポリフォニー扱いを受けるために選択された典礼アイテムの種類の様式の違いであった。-北部地域の非常に精巧なレスポンソリウムのチャントと南部の詩的なテキストのある単純なシラビックチャントである。 p106 rt. 5.南部の伝統は、おそらくは上声部の即興的な丹精さの結果として、北部よりも早くnote-against-noteを超えて発展した。しかし、それは北部または「ノートルダム」の伝統の直接的な先回りではなかった。むしろそれは、イタリアのトレチェント音楽の表記上および様式上の究極の祖先であった。 6.完全のの概念と記譜法のリズム的モーダルシステムなどを備えたTriple metreは、北フランスの楽派の革新であった。 このテーマを扱う際に遭遇した最初の困難は、チャントのポリフォニック表記からの聖マーシャルポリフォニック表記の由来を支持するかもしれない証拠に関係している。聖マーシャルポリフォニック写本群は、Paris, Bib!. nat., lat. MS I II 8のように、ドットと水平ストロークを区別していない。 しかし、記譜法の意味の均一性を主張してスノーの転写システムを実現させると、計量的チャントで推定されたものとはかけ離れたリズミカルなスタイルが生成されることを見つけるのはさらに厄介なこととなる。 VollaertsとMurrayによって提供された説明によると、チャントは主に2:Iの比を持つ2つの音価に基づいている(つまり、longとbreveに相当)。このシステムは、時折duplex longsを受け入れることで拡張される。したがって、音価の最大範囲は4:Iの比に保たれる(4:Iの範囲は、Jammersの転写でより完全に利用される32が、これらはSnowの出発点を提供しない。) ちなみに対照的に、Snowは16:Iの範囲を提案している(つまり、duplex longs to minims)。また、Snowはduplex longsをシラブルの長さの通常の音価と同じにするため、多くのチャントの明らかな構成から削除されたように見える二重の韻律階層を作り上げている。 このような階層は、さまざまなアンティフォナ、特にオフィスのアンティフォナで提案されている33が、prosesなどの華やかな作品のスタイルは、ミサのより華やかなものよりも、それらのチャントからさらに削除されると思われる。 私は、南部の伝統の中での「上声部の即興の精緻化」に関するスノーの主張に同意する。そして私は、彼が聖マーシャルの音楽と初期のイタリアのマドリガルの音楽との間のリンクを想像することは、正しいと思う。 34 p107lt. それにもかかわらず、私は彼の南部と北部のスタイルの分離は受け入れがたいと思う。 「ポリフォニックな扱いを受けるために選ばれた典礼品の種類」に基づいて、これらのスタイル間の分裂を仮定することは困難である。 第1に、、そのような見方は、ノートルダム大聖堂のレパートリー内の conductus の重要性を無視している。これらのいくつかは、聖マーシャルのレパートリーの作品に匹敵する機能を持っているのである。 第2に、聖マーシャルとノートルダム以外のレパートリーを考慮する必要がある。議論のために、Calixtine repertoire が南部の伝統の一部であると宣言する場合、両方の伝統が精巧なレスポンソリウムのチャントの設定にある部分、関係していることを認めなければならない。一方、Calixtine repertoire が北部の伝統を代表するものであると宣言する場合、St Martial and Calixtine のレパートリーを統合するconcordances によって提供される2つの伝統の間のリンクを認める必要がある。 Snowの論文のこの部分では、2つのレパートリーとそれに続くレパートリーの間で観察できる連続性の形式に関する疑問を取り上げている。聖マーシャルの伝統とノートルダムの伝統との間の急激な断絶の理論には、いくつかの著名な支持者がいる。 私は第2章、脚注12で、ノートルダムのリズムシステムの新しさと過去の慣習との決別を強調するWilli Apel and William Waiteの文章を引用した(http://machikun.la.coocan.jp/karp0.htm p24)。さらに、レオ・トレイトラーは、「2つの楽派間の遺伝的関係についての文体的証拠も文書的証拠もない」と率直に宣言した35。 この章の冒頭で、私は直接のつながりには関心がないことを指摘した。私は一連の親子関係の観点から作品のグループを見たいとは思わない。ただし、特に区切られていない限り、「遺伝的つながり」という用語は、拡大族内に存在するさまざまな関係を包含するのに十分な広さである必要がある。 私は、聖マルシャルとカリクスティンのポリフォニーを、同時期のポリフォニーのより広い層の主な代表者と見なしている。現存の証拠は、様式の伝達の特定の道を特定するのには不十分であるが、ノートルダムの作曲家がこの層の一部を利用したと結論付ける以外に選択肢はない。 p107rt. 私は、これらの作曲家が、note-against-note style以外の先立つポリフォニーについての知識を持っていなかったと断言したくない。 確かに、聖マーシャル、カリクスティン、ノートルダムのレパートリーの間には多くの顕著な違いがある。私はこれらを註解したくありません。しかし同時に、そのような違いは、3つのレパートリー間の類似点を私たちに盲目にするべきではありません36。 後の音楽史のいくつかの時点で、1世代または2世代の期間内に、直近の過去を知らないことや、それとの完全な断絶を示すことなく、顕著な様式の変化が生まれた。(訳注;たとえば、1600年前後、1750年前後) こうした後の例では、はるかに多くの証拠にアクセスすることで、進行中の関係をより簡単に認識することができる。 p107 rt. 方向性を確立するために、この章の後半で浮かび上がる基本的な議論を要約したい。 12世紀後半の音楽の中心的な特徴の1つは、フレーズ、フレーズのグループ、または曲全体での完全に一貫したリズムパターンの出現である。また重要なことは、装飾的なパターン構成の実践である。そのために、構造的なトーンが、強拍に相当することになる。この慣行は、連結符の終わりにメイントーンを配置するという記譜上の特徴に関連している。 これらの音楽的特徴の2つ目には例外があるが、それは、厳密なリズムの一貫性よりも、スタイル全体の中心にあると思われる。 この慣行は、ノートルダムレパートリーにはっきりと表れている。私は、それがSt Martial and Calixtineレパートリー、そしてChartres fragmentのような作品にも存在することを示した。これらのレパートリーが、比較的に時系列的に連続しており、限られた地理的領域の産物であるという事実は、それらがすべて単一の継続的な伝統の一部であった可能性を示唆している。私の現在の目的は、そのような解釈を裏付けるさまざまな証拠を確立することである。 最も明白な証拠のいくつかは、それが非常に基本的であり、したがって特異性に欠けているために見逃された可能性がある。 それにもかかわらず、私は最も単純な形の証拠から始めてみたい。 可能な限り最も基本的なレベルでは、聖マーシャル、カリクスティン、ノートルダムのレパートリーの間には時間と場所の両方のゆるい関係がある。 p108 lt. 現在入手可能な証拠は、聖マーシャルのレパートリーの大部分が12世紀の第2四半期に作成されたことを示している。lat. I I 3 9はこの期間に先行し、世紀の変わり目に戻る可能性があるが、Add. 3688おそらく、より後日であろう。 全体として、学者らは、 Codex Calixtinusの内容について、12世紀の第2四半期のdatingを支持しているが、ギルバート・リーニーは、彼が編集した国際音楽ソース目録(RISM)の巻で反対意見を表明しています。 3 7 datingの一般的なコンセンサスが正しいと仮定すると、2つのレパートリーの大部分は、Leoninが活躍し始めてから25年以内、おそらく10年以内に知られ、流通していた、と結論付けることができよう。 場所の近さは、リモージュとパリの間の距離の計算と、これら2つの場所の間の交易路の性質だけに依存するわけではない。 当時、年間何人もの人々がサンティアゴデコンポステーラへの巡礼をしたと推定されている。聖マーシャルはこの有名な場所への主要な南方ルートの1つにあり、パリは長い旅の北の主要な場であった。 Limogesで演奏された1つの作品が、サンティアゴに届いていたことは知られている。lie de France の地域からの、または通過する巡礼者の数が過大評価されていたとしても、実際の数は依然として非常に多かったことであろう。 したがって、パリの聖職者界で音楽に興味を持っている人の中には、サンティアゴで演奏される音楽の性質に精通している人がいた可能性が非常に高いのである。 さらに、様式の伝達について、単一のルートを仮定する必要はない。 Codex Calixtinusのさまざまなポリフォニック作品は、特定の作曲家によるものである。これらの帰属は伝統的に大きな疑いを持って見なされてきたが、私はそのような態度の変更を促さない。 ただし、これらの作品の個々の作成者の検索に従事しておらず、サンティアゴ デ コンポステーラ以外でこれらの作品がどこで知られているのかを知りたいだけの場合は、帰属がより有用である可能性がある。 p108 rt. その観点から、この写本は、12世紀にポリフォニーが知られていたフランスの場所のネットワークを示しているようである。パリとシャルトルに加えて、パリの北東から南東に至るソワソン、トロイ、ベズレー、パリの南東にあるブルージュ、パルテネイ、シャトールノーなどの場所がある。 さらに、パリとリモージュの間の多かれ少なかれ仲介として。 38 実際、この種の音楽がさまざまな場所で知られていれば、様式の交換が行われた可能性のある方法の数は著しく増加する。 特に注目に値するのは、Congaudeant catholiciがAlbertus Parisiensisに帰属することである。 よく知られているように、Albertus Parisiensisは、パリのノートルダム大聖堂でカントールの地位を獲得し、c. I I 46 to c. I I 8 8まで、ノートルダム大聖堂の記録文書でさまざまな日付と日付のない行為を追跡できる歴史的な人物であった。 Albertus the Cantor の存在は、Jacques HandschinによってI932年に音楽学者の注目を集めました。 39 Calixtineの帰属を扱う際に必要な注意に注意しながら、Jacques Handschinはこの男がCongaudeant catholiciの作曲家と同一であったかもしれないと示唆した。このことは、Bruno Stablein40とHansTischlerによって再び提起された。 41 最近では、アルベルトゥスに関する追加情報を提供したクレイグ・ライトによって、身元の可能性が確認された。 42 Jacques Handschinは、この男がa Missal, a Lectionary, a Gradual, a Psalter with hymns, and two Tropersを、2冊の”versaries"と同様、 ノートルダム的にした、と指摘した。 後者の呼称は、モノフォニック、ポリフォニック、または混合のいずれであっても、conductusのコレクションを指すとJacques Handschinとライトは示唆している。 これらの2冊の”versaries"は、アルベルトゥスの人生の最後の年に書かれた可能性があり、最新のノートルダムconductusだけが含まれている可能性があるが、一方または両方がCongaudeant catholiciに代表される種類の音楽を保持している可能性がある。反駁できない証拠の欠如は、証拠の存在を否定するものではない。 それでも、ジャンル、テキスト、テキスト設定、および音楽に関して様式的な関係を示すことができなかった場合、前述のすべては無関係になる。 p109 lt。 中世盛期のダブルテキストの Benedicamus Dominoの設定のレパートリーは少ない。 それにもかかわらず、St Martial and Notre Dame レパートリーの両方にこのジャンルの例がある。 Beatis nos adhibe / Benedicamus Domino(F写本、fos。250r-252 rで保存)のcantus firmusの基本的な音域は、Stirps Jesse florigeraml /Benedicamus Dominoで見られるそれに匹敵する。 Beatis nos adhibe / Benedicamus Dominoは3声、Stirps Jesse florigeraml /Benedicamus Dominoは2声であり、Beatis nos adhibe / Benedicamus DominoはStirps Jesse florigeraml /Benedicamus Dominoよりもテキスト設定が華やかではないが、テクニックの根本的な類似性がある。F(fos。390v-392v)で保存されている tropic 'organal motet' Veni doctor/Veni sancte spiritusでも同様の設定が見られよう。 テキストの観点から、我々は、いくつかのSt Martial versus と the Notre Dame conductusの構成の類似点と、2つのレパートリーに共通の1つのテキスト、つまりDe monte lapisscinditurがあるという事実の双方を考慮する必要がある。 p109 rt. 各行の本体をシラビックに扱い、メリスマを行の最初と最後に配置するという慣習は、すべてに共通している。この関係は緩いものであり、15世紀半ばまで他のレパートリーに共通している。それにもかかわらず、私はその存在を風の中の藁と見なす。 3つのレパートリーの間に存在する音楽的関係は、さまざまな性質やさまざまな程度の特異性を持っている。たとえば、例8に示すような、類似したメロディープロファイルをいくつかできよう。 または、五度音程を占めるスカラー交差パターンなど、両方の声部に存在するパターンの類似した組み合わせを指す場合もある。 (例9)。 また、声部交換の使用によってもたらされる特定の形式的な対称性を備えたメロディおよび和声進行の組み合わせを指摘することもできる(例10)。 ただし、エヴィデンスの多くは―および最も重要な証拠)は―3つのレパートリーの和声構造の性質に関するものである。 非常に基本的なレベルでは、St Martial、Calixtine、およびNotre Dameのレパートリーが同じ和声的価値を持ち、ユニゾン、五度、およびオクターブを強調していることに注意する必要がある。 p110 lt. 四度と三度は明らかに安定性が低く、構造的に重要なポイントでの使用頻度ははるかに低くなっている。これらの事実が重要性を欠いているかもしれないということは、ハーモニックパレットはすべての人々とすべての時間で同じでした。 これらの事実は、和声的パレットがすべての人々とすべての時間で同じであった場合、重要性を欠いている可能性がある。 ただし、ヨーロッパには独特の和声傾向が見られる。3つのレパートリーの主な協和音は、Lombardyで報告された過ぎ去った「二度のハウリング」、およびブルガリア西部とユーゴスラビア東部の一部でまだ聞かれるさらなる二度の使用において等しい重要性を持たない。それらは、アイスランドやオークニー諸島のtvisongurの三度や、初期の英国音楽とは対照的である。 確かに、Notre Dame conductusの和声パレットは、St Martial versusの和声パレットよりも豊かで冒険的であり、三度を多く使用しているが、基本的なフレームワークはほとんど同じである。一方、オルガヌムとクラウズラの和声的語彙は、保守的であり、St Martial and Calixtineのレパートリーのそれと非常に似ている。 3つのレパートリーが同じ協和音と不協和音の枠組みを共有しているという事実は、これらが個別の方法で具体化されている場合でも、同じまたは類似の進行を共有する傾向を生み出している。 基本的な進行はすべての人に共通である。ユニゾン→五度5、ユニゾン→四度、オクターブ→五度、オクターブ→五度の進行が非常に遍在しているため、これらが3つのレパートリーすべてのバックボーンを構成するという事実に多くの重要性を与えることには、多くの人は気が進まないかもしれない。 ただし、これらの一般的な場を超えて、3つのレパートリーで共有される非常に珍しい音程の進行があることを示すことは可能である。 たとえば、2つの声部が五度の間隔であり、vox principalisが二度上行する状況(たとえばファ→ソ)を考えてみたい。通常、vox organalisは四度4分の1に下降(ド→ソ)し、2つの声部はユニゾンとなる。 この進行は、可能ないくつかの1つにすぎない。vox organalisは、オクターブ全体をカバーするはるかに拡張された降下に入る可能性があり、そうなると、2つの声部は相対的な位置を逆転し、そして、vox organalisはvox principalisの五度下になる。 例11a-dでは、この進行が St Martial のレパートリー内に現れる4つの異なる方法を示している。例11e-hは、4つのノートルダム conductusの進行での使用を示しているが、 例11 i-nは、6つのノートルダムオルガヌムでの使用を示している。 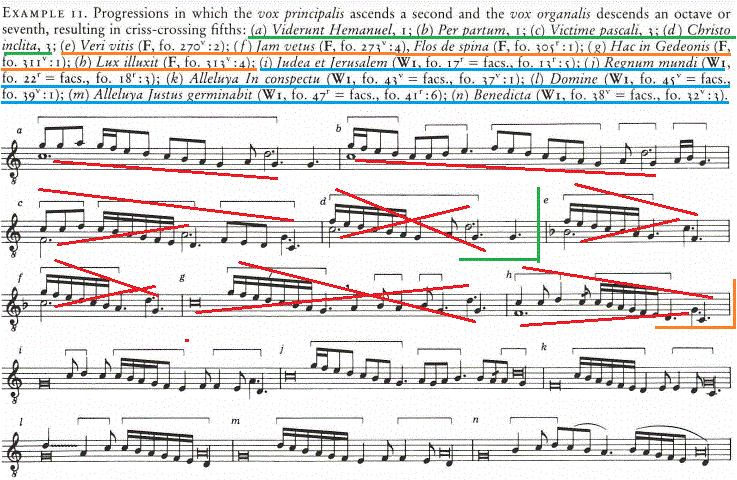 p110 rt. Viderunt Hemanuel(例11a)で採用されている最初の上昇形は、Lux illuxit(11h)に対応するものがあり、St Martialバージョンが最終的なゴール音に落ち着く前に上向きに跳ね返る傾向が、ノートルダムの例のいくつかで、さまざまな形式で存在することがわかる。私は、例11の個々の抜粋に対する可能なリズム表現を提案したい。ただし、これらは例の内容の中心ではないため、他の代替案を検討したいと思う。 問題は、私が例のありそうな調和の文脈を適切に表現したかどうかの問題であり、この問題は、ここで提供できるよりも広い文脈から最もよく決定される。 例11に示されているような進行は、Winchester organa, the Ambrosiana examples,あるいはthe Chartres fragmentなどのような、より昔のレパートリーには見られない。また、13世紀のモテット、その14世紀のdescendents、または14世紀のフランスやイタリアの世俗音楽の特徴でもない。それらはまた、中世の英国音楽に対しても異質であるように思われる。したがって、私は the St Martial and Notre Dame の双方でそれらの外観が保持され、何らかの形の共通の絆がある、と考える。 これら(the St Martial and Notre Dame)が12世紀のフランスのポリフォニーの最も重要なレパートリーの2種を表しているという事実を考えると、私は、直接的なスタイルの影響の可能性を想像したいが、直接的な影響は少なくとも間接的な影響と同じくらい可能性が高いというくらいしか、言えない。 第4章では、オクターブからユニゾンに進み、vox principalisが二度上昇し、vox organalisは七度急降下する、 Calixtine cadences の重要性に注目した。一連の26の抜粋が例9(第4章p72)に集められ、この基本的な進行を表現できるさまざまな方法を示している。 例I2では、 St Martial and Notre Dameレパートリー内で同じ進行を使用することを示す一連の抜粋が示されている。Notre Dame conductusの中で、進行は一般的に2つの基本的な形式のいずれかに標準化される。私はそれぞれの例を提供し、それらの外観の多数の例のいくつかを単に引用している。 43 EXAMPLE I 2.Progressions of an octave closing to a unison, the vox principal is ascending a second : (a-d) Sancti Spiritus, I, 1 & 2, 3, 3; (e , f) Rex omnipotens, 1, 4; ( g-i) Christo inclita, 1, 2, 3; (j-1) Aile- celeste, 3, 5, 5; (m) Per partum, 2; (n) Res jocosa, I; (o) Descendit de celis (WI, fo. I 7v = facs., fo. I 3 v: 3); (p) Dum complerentur (WI, fo. I9r = facs., fo . I 5'. : 6); (q, r) Inter natos (WI, fo. 20r = facs., fo. I 6r: 2, 3); (s) Regnum mundi (WI, fo. 22 v = facs., fo. I 8v: I); (t) A lleluya Hodie Maria (WI, fo. 4o' = facs., fo., fo. 34'" :4); (u) Aileluya Letabitur justus, (WI, fo. 46r = facs., fo . 40'" : 2), Aileluya Nativitas (WI, fo. 42v = facs., fo . 36v: 3); (v) Gaude virgo (F, fo . 283":6); (w ) Beata virginis (F, fo. 284r :6). ExAMPLE I 3. An unusual preparation for an octave-unison close: (a) Aile- celeste, 3; (b) Dulci dignum, 6; (c) Novum sibi texuit (F, fo. 306r: I).  p111 lt. これらの単純な進行は、3つのレパートリー(St Martial のレパートリー、ノートルダム conductus、ノートルダムオルガヌム)に固有であるため、単純であろうと複雑であろうと、何らかの形の相互関係の証拠を示す。 例I2に示されているオクターブ→ユニゾン終止は、3つのレパートリー(St Martial のレパートリー、ノートルダム conductus、ノートルダムオルガヌム)に非常に特徴的であるため、この終止へのさまざまな同様のアプローチを見つけるのは容易である。 Dulci dignum(例13b Add。3688I)では、 principal voiceに三和音的下降が見られ、その後に三度と二度の上昇が続く。進行は、ユニゾンから五度、そしてオクターブへと開始される。このオクターブが三度高くスキップし、標準的な終止を導入するのは珍しい。 こうした個性的要素があるにもかかわらず、同じ進行がNotre Dame conductus Novum sibi texuit(例13c)にも見られる。 (例I3aに示すように、Alle celesteでは lat. 3549から同等の進行が採用されている。ただし、この場合、 principal voiceの降下はスケール単位であり、四度音程となっている。) p111 rt. ユニゾンから五度、オクターブまでの関連する冒頭は(終止がすぐに続く)、前の五度からユニゾンへの内側への進行が先行することがあり、cantus はステップまたは三度のいずれかを上昇する(例I4)。または、例I 5に示すように、オクターブーユニゾン終止の前に、2つ以上の装飾された平行五度が先行する。 St Martial, Calixtine, and Notre Dame レパートリーで四〜六度音程の同等の進行を示す他の例他にもいろいろある。 これらのそれぞれを主張することは現在の議論を前進させないので、私は付録Eでさらなるサンプリングを提示するだけです。和声進行の徹底的な研究によって発掘される他の数を推定することはできません。 より大きな重要性は、主要なセクションまたは全体の部分をリンクする可能性のある構造の類似性に付随します。 しかしながら、上で引用された類似点は、それぞれの声部のvoces principales と tenorsの短い音程の動きの類似性から生じていると考えられる。 これらはnatural similar harmonic responsesを作ります。 St Martialの voces principalesを完全なメロディーと見なし、それらをノートルダムの作品群の基礎となるテノールと比較すると、外観に多数の違いがある。したがって、多くの大規模な対応が見つかる可能性は低い。 もちろん、St Martialの Benedicamus Domino trope Humane prolisの定旋律が、応唱Stirps jesse内のメリスマとして、そしてconductusレパートリー内のメリスマ的なcaudaとして、トロープス化されていないBenedicamus Dominoのオルガヌム設定のレパートリー内で何度か使用されていることを認める必要がある。 p113 rt. この場合には、大規模な構造的対応の可能性が存在した、とは言える。しかし、このBenedicamus Dominoの定旋律のSt Martial の設定はユニゾンで始まり、ノートルダムのレパートリーの後の作品での常態よりもかなりの程度、垂直方向の音程に大きく関わっています。したがって、より大きな構造的類似性のための適切な出発点を提供することはない。 同じ定旋律が、ダブルテキストのStirps jesse/Benedicamus Dominoで採用されている。この作品の最初の主要なセクションの全体的な構造の概要は、F写本に示される2つまたは3つのBenedicamus Domino設定の概要と類似しており、fo.87の2番目のシステムで始まる設定に最も類似している。 p114 lt. 例I6に示されているように、2つの作品のオープニングセクションはかなり異なるスコープであり、ノートルダムの設定には、聖マーシャルのものの約2倍のトーンが上声に含まれている。どちらの作品も、さまざまな繰り返しや順序など、さまざまな形の並列構造を利用している。 これらは、2つの作品内で異なって分布している。それにもかかわらず、上声部の全体的なゴールは類似しており、一般的な概要には多くの対応性がある。 (それぞれに適した異なるリズムの実現は、これらの対応がリスナーに与える影響を減らす。)平行のない大きな領域は、それぞれ小さな動機を作り上げることによって構築されることを考えると、これらの対応の数と頻度は注目に値する(例I6)。 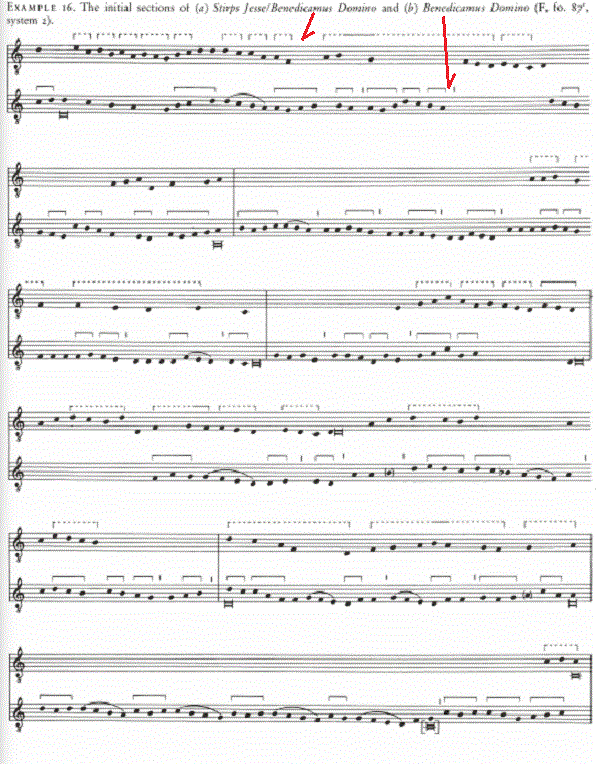 ここで紹介したセクションに続いて、ノートルダムの作品は、オルガヌム的流麗さで終止する前に、拡張されたディスカントセクションに進む。聖マーシャルの作品には、 principal voiceよりもorganal voiceにさらに多くの音符がついている。 2つの作品の中央セクション間の和声リズムの大きな違いと、聖マルシャルの次の12の同様のもののうちの8つがユニゾンであるという事実のために、両者の間に、これ以上の強い類似性はない。 しかし、強い類似性は他の手段によって示される。たとえば、かなりのノートルダムクラウズラを取り上げて、その構成セグメントのほとんどまたはすべてに聖マルシャルレパートリー内の類似点が存在することを示すことができよう。 これは、Viderunt omnesのverseからのクラウズラDominoの調査を通して示される。例I7では、3つの譜表の各グループの最上部がW 1のバージョンを転写で示している。2つの下部の譜表は、聖マーシャルのレパートリーからのそれに相当するセグメントを示している。いくつかの例では、3つ以上の類似点が生じる可能性がある。この比較を一定に保つために、追加の参照は省略した。  特徴的とは言えない和声進行を共有する一対の短い抜粋の類似性は、おそらく偶然によって発生する可能性もあり、基礎となる様式の相互関係を示すものではない。しかし、クラウズラDominoに代表されるような拡張された音楽空間をカバーする一連の関係の責任を認めることは、偶然で片づけることはできない。 p114 rt. これらの類似性の程度は、3つのレパートリーに固有の進行の存在と相まって、共通の継続的な伝統の強力な証拠である。 私は、現在検討している3つのレパートリーの間に別の形の相互関係が存在することを上でほのめかした。これには、通常、構造的な和声音程の配置を示すために記譜法を使用する方法が含まれ、したがってリズムの問??題が含まれる。 この章のさらに前半で、私はSt Martial and Calixtineの記譜法が基本的に装飾プロセスの表現として生じたと主張した。初期の段階で、作曲家らはこの要素に関してさまざまな可能性を模索していた。 いくつかの作品では、装飾は非常に控えめに使用されるか、まったく使用されない。他の作品では、それは頻繁に見つかるか、またはすべてに行き渡っている。いくつかの作品ではそれは単純であり、他の作品では精巧である。 おおざっぱには、以下が成り立つ。すなわち、装飾は、cantus prius factus を使用する作品の方が、それを使用しない作品よりも豊かになる傾向がある、ということ。 現在入手可能な証拠は、時系列に基づく装飾プロセスの違いを示唆していないようである。単純な装飾がより精巧な後の段階に先行したこと、または大げさな装飾が後でより抑制されたという明白なヒントはない。 しかし、12世紀の間に、装飾模様の多様性は徐々に減少し、プロセスは体系化された。リズム構造はますますシンメトリックで一貫性のあるものになり、最終的にはモーダルリズムの名の下で、私たちが知っているコード化が可能な一連の手順になった。この一貫性のピークは、モーダルリズムの理論が定式化された期間1190-1240年頃に到達し、保持された。 13世紀半ば以降、厳格なモーダルリズムの例外がゆっくりと増加し始め、世紀を経るにつれて力を集めていった。最終的には、残されたモーダル構成のscattered reminiscencesのみとなった。 私は、聖マーシャルのレパートリーの体系的なリズムにおけるパッセージと作品全体の存在さえもが、より大きなプロセスの兆候であることに気づいた。 さらに、作品全体の存在は、当時の哲学的および芸術的思考の多くの根底にある構成との同等の関心を反映している。 44 体系的な記譜法のパッセージに関連して使用される場合、和声配置と直接的な進行に関して第2章で進められた推論は、後のモーダルリズムに類似したリズム解釈をもたらした。この結果は意図的な結果というよりは偶然の結果であるが、それが理論全体の1つの強みを構成していると私は主張したい。 p117 lt. 私の議論は3つの部分で構成される。(I)私が想定している変革のプロセスの詳細な説明。 (2)聖マーシャルレパートリー内のさまざまな形の対称リズムのサンプリング。 (3)モーダルシステムの最終的な起源の問題に関係する最近の証拠の検討。 私は、聖マーシャルの記譜法が、破壊されたChartres fragmentを通して私たちに知られているnote-against-note作品での連結符の終わりでの安定性を求めた以前の慣習に由来することを示唆した。 当時、新たなレベルのリズム活動を表現する必要があったため、記譜法の観点から新たな出発をする必要があった。そのような過程で、音楽的コミュニケーションの明快さの必要性が、記譜法とテキストのデクラマシオンの関係の明快さの必要性よりも優先されるべきであったことは不自然ではない。 このとき、作曲家らは、テキスト設定とデクラマシオンについて、さまざまなアプローチを取った。極端な例として、一方では、ほぼまたは完全にシラビックであるパッセージがある。もう一方では、散文設定、チャントのCalixtine設定、Add36881のOra pro nobisの設定での華やかさや柔軟性を見い出す。また、作曲家らは、各作品を通して常に単一のテキスト設定方法を保持する必要があるとは考えていなかった。 |