| DUFAY D.Fallows1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| p90 Adieu ces bons vins の上声部は、当時のデュファイの多くの特徴を持っている。その低声部sは、いくつかの点において、その性格は似通ったパターンを示している。 このレパートリーに常に現れているように、低声部は”テノール”と”コントラテノール”とラベル付けされている。中世の音楽において、これらの名前は声部の声域を意味することはなく、むしろ、それらの機能を定義している。テノールはレパートリーのメインの構造声部である。 モテットにおいては、通常、テノールは借用されたチャントメロディを使っている。すなわちこれは、13世紀のその語のオリジンがあったように見え、デュファイのモテットの多くで、その機能は残されている。しかし、シャンソンにおいては、”テノール”という言葉は単に、和声進行をコントロールする主要声部を示しているにすぎない。 Almost invariably the teor and the upper voice make perfect two part counterpoint between them , a counterpoint that corresponds precisely to the fundamental principles of more modern counterpoint: the main vertical intervals are thirds ,fifths , sixths and ocves; fourths are treated as dissonances , as are seconds and sevenths; and the voice-writing is in contrary motion whenever possible. 多くは不変的に、テノールと上声部は、両者の間で、2声の対位法を形成し、そのcontrapunctusは、近代の対位法の基本原則に正確に相当している。主たる音程は三度、五度、六度、八度で、四度は二度や七度と同様、不協和音として扱われる。そして声部書法は、可能ならば、反行を示している。(例5) Equally characteristically , each cadential figure in the upper voice is matched by a stepwise falling line in the tenor: between them the two voices provide the entire contrapuntal structure of the work. 同様に特徴的に、上声部の各カデンツの形は、テノールの一音づつの段階的な下降線と一致している。それらの間で、2つの声部が作品の対位法構造全体を提供する。 contrapunctusの原理は、"discant"のheadingのもとで、中世の多くの理論家の論文において、十分に記述されている。7 そしてこれらの2声部の間の関係の重要性は、上声部が"discantus"と呼ばれるレパートリーを通して基礎的なものである。(それは、より一般的には”superius"と呼ばれ、その用語は、少し後の世代の書法でよく現れているが、テノールとの関係の重要性の強調はあまりなく、この声部が最上声部であることが強く示されている。 p91 Alongside the clear contrapuntal structure of the discantus and tenor comes the contratenor. Again , this name is a description not of range or of voice quality but of contrapuntal function -that of a part which in some respects matches the tenor. discantus とtenor の明確な対位法的構造に沿って、contratenor.がつけられる。 繰り返しとなるが、この名前は音域やその性質ではなく、対位法的機能を示しているのである。ある意味でテノールと(音域的に)一致する声部となる。 Adieu ces bons vins において、コントラテノールは、テノールと同じ音域を持ち、しばしばそれとホモフォニー的に動いている。当時の多くの作品におけるように、その基本的な機能は、2通りある。すなわち、上記の理由により、テノールとdiscantus が長い音符を持っているか、休符となっている可能性が高い場合、①テクスチャーを色付けすることと、②カデンツ点において特に、リズム的勢いを加えることである。 15世紀の3声作品のいくつかでは、contratenor が省略されることは可能であり、、その結果、作品は完全的感覚がつくようになる。 テノールが省略されると、15世紀のこの段階では、結果には四度の多くの不協和音が生じることだろう。15世紀の後半には、(露骨な)四度は現れないようだが、そうした作品には、結びつける声部の欠如が感じられる。 Discantusが省略されると、ほとんどの場合、協和音程となるが、discantus-tenorのデュエットによって提供される必須な形状が欠ける。 p92 Adieu ces bons vins の冒頭小節で、コントラテノールは、テノールとホモフォニー的に動く。(例6) 第5小節からは、他の機能が見られる。すなわち、オクターブの跳躍が、コントラテノールの動きの特徴となる。第6-7小節の模倣の hintは、等しく、様式の一般的特徴である。ちょうど、テクスチャーを生き生きとさせるhintとして。しかし、決して生き生きとしたものではない。第11小節の6/8拍子的な音形は、リズム的な動きを活性化するが、しかし、その2番目のテキスト行の不均衡の全体的な形状も要約している。また、discantus上を少しだけ先に目を向けるすることにより、その形がさらにはっきりと示される。  楽譜 中間のカデンツでは、コントラテノールは、次のセクションの準備での持続的な動きとなっている。その間、discantusとtenorのペアは そのままであるが。 テノールは、主に和声声部としての機能を強調するかのように、discantus よりもゆっくり動いている。これはデュファイでは特に一般的なことではない。なぜなら、一般的に彼の目的は、3声部のスタイルを統合しながら、それらの対位法的な機能を維持することであるからである。 好例が、バラードCe jour le doibtである。8 そのメロディ的和声的様式は、Adieu ces bons vinsを思い起こさせる。そして、そのテキストが Laon 時代の作曲を示唆していることをすでに見た(p。27)。 この場合も、tenorと contratenor はホモフォニー的に始まっているが、比較的すぐにコントラテノールがより独立して動き始め、その後、リズミカルな動きの小さな詳細と模倣のヒントが導入される(例7)。  Dufay - Ce jour le doibt, aussi fait la saison この曲は、Adieu ces bons vinsよりも洗練されていない曲かもしれないが、彼の発展の同じ段階に属しているわけである。すなわち、音楽様式は、テキストがすでに示唆しているものを裏書している。 そして、ある程度、これらの2つの曲は、彼の音楽の中で古い北部の様式を表していると見なすことができる。それはバンショワの多くの曲のスタイルであり、main interest-bearing part であるdiscantusと主に和声のバックグラウンドを提供する機能とを持つ2つの下部のパートを伴っている。 Oxford写本のデュファイの別の日付の作品は、彼の作品において、まったく異なった伝統を示している。それは1425年の7月12日付けのJe me complains piteusementで、それゆえ、Adieu ces bons vinsより数ヶ月早いだけである。 p93 彼はこの作品で、discantus、テノール、コントラテノールのヒエラルキーを打ち捨て、同じ音域で、3つの等しい声部を書いている。声部は一貫して、オーバーラップする。そしてそれらの音楽的等しさは、”Je me complains"という冒頭語句の3つの異なった設定によって強調されている(例8)。 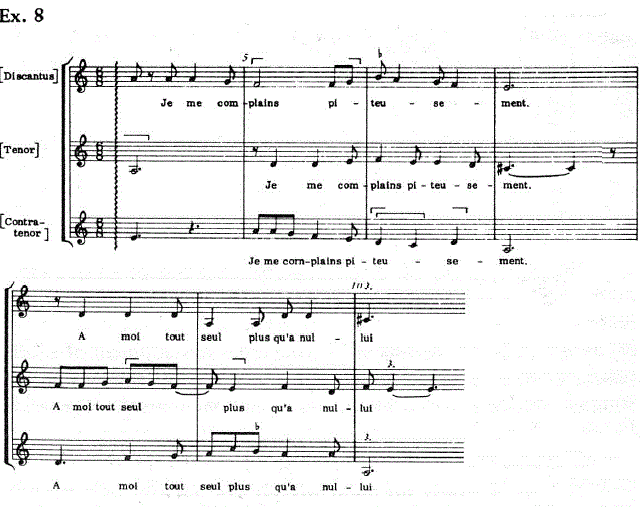 しかし、ここでの変化は、明らかである。上の2声は、完全な対位法となっている。一方、一番下の声部は、トップ声部と四度の不協和音程を形成しており(第4小節)、その後は、Tenorと四度を形成している。これは、15世紀の音楽のコントラテノールの特徴で、もうひとつの特徴が、第9-10小節でのオクターブ跳躍である。(略) このバラードで、デュファイは、特殊な作曲上の問題にアプローチしているように見える。すなわち、等しい音域での3声の使用と、等しさの重要性について、である。 p94 もしそうなら、彼は、おそらくは非常に良く似た様式である別の曲Mabelle dame souveraineで、よりうまく彼の目的を達成したことになる。 この曲では、3声はやはり同じ音域であるが、唯一のソースにおいて"triplum","tenor","cautus"とラベル化されており、それらの間の一貫性のある構造的関係の痕跡ははるかに少ない。9 こうした構造を維持するために、より下に4番目の声部が作られている。その長い音価や不規則なリズム、ligaturesの長さから判断して、この声部はおそらく、歌詞がつけられる意図はなかった。この声部は”コントラテノール”と写本では書かれ、その動きはオクターブや五度の多くの跳躍を含んでいる。 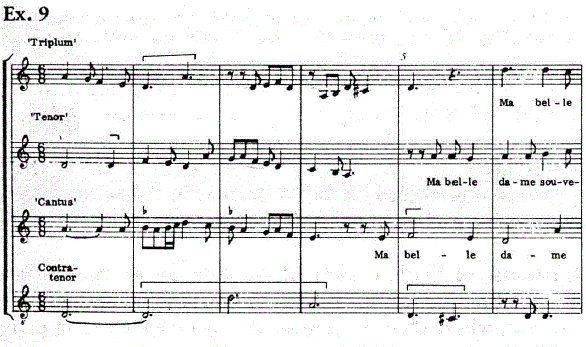 Dufay, Ma belle dame souveraine これは、BesselerがHarmonietragerと名づけた類いのものであり、デュファイが強く、調整的な和声スキームの発展においてチコニアのモテットと同様、イタリアのトレチェント作曲家らのcacciaの影響を受けた証拠とみなされている。すなわち、慣行的に、曲のすべての垂直的音響は、Dminorのtonic,dominant,subdominantの三和音として解釈され得るのである。 Ma belle dame souveraine は、Adieu ces bons vinsと並んで、デュファイの初期のもっとも完全な作品のひとつである。3曲の上声部のそれぞれは、そのピークの音符はDであり、最下部はAである。 p95 Je me complains piteusementにおけるように、Ma belle dame souveraine は、詩の冒頭の語句は、3つの異なったリズム形態で現れる。一方、 Je me complains piteusementに後から現れるような、ユニゾンのカノンは打ち捨てられている。 デュファイのリズムの使用は、彼の作品でのもっとも一貫した魅力的な特徴である。この始めるのに最もふさわしい曲はやはりAdieu ce bons vinsである。ほとんどの場合、各小節は2つの「コード」がある。つまり、テノールは通常第3拍でピッチを変更し、曲は定期的に波打つハーモニーの連続的なトロカイック(タータ)フローとして機能している。こうした規則性は、デュファイの作品においては、彼の同時代人のそれと同様、比較的希である。(これは、Adieu ces bons vinsの構成が、その規則性が明らかに、借用されたテノールの構造によって事前に決定されているGloria ‘de Quaremiaux' 上の作品から生まれたという提案を裏付けるもう1つの機能である。) こうした観点において、より特徴的なのが、ロンドー 歌での実質的なすべてのビートには、何らかのアクションが含まれているが、基本的なアクティビティは、各小節の1ビートと3ビート(トロカイック)または1ビートと2ビート(ヤンンビック)である。 そして、成功したパフォーマンスは、小節ごとにたった2つのstressesを中心とした穏やかなうねりを可能にするパフォーマンスのようである。 少なくとも、iambicパターンで最初のビートから「bounce」しようとすると、音楽の流れが破壊されることが経験からわかる(例10)。  p96 しばしば、フレーズの長さはバランスされているが、基本的には不規則である。詩の4行は4 + 5 + 5 小節分のフレーズに一致している。 グレゴリオ聖歌のコンテキスト内で最も簡単に理解されるのは様式である。この場合、通常のフレーズバランシングは厳密に回避されるが、音楽的行は、文字通りの意味で、はるかにバランスが取れていない。 フレーズの長さの一定の不規則性は、当時の理想であったと思われるフレーズの全体的なバランスにもかかわらず、音楽の流れに気まぐれな予測不可能性を与える。 そして、Adieu ces bons vinsの計り知れない記念性は、少なくとも部分的には、より後のリスニング習慣の影響である可能性がある。最初、2番目、5番目のテキスト行には、コーダと同様に4小節のフレーズがある。 他の場所にある5小節と7小節のフレーズは、基本的な4小節パターン内の落ち着きのある不規則性として聞こえる。 同様のことが、別の初期の作品、デュファイのAve regina celorumの最初の方でも生じている。この作品は、メロディ的にも和声的にも、Adieu ces bons vinsと同時代の作品であることを示している。 Ave Regina Coelorum 楽譜 15世紀の単純なリズムパターンへの心構えに多くの信頼を置くのは困難である。なぜなら、舞踏音楽や即興音楽は失われているからである。それらは、16世紀の最初期のはっきりとした記録以来の、舞踏音楽に特徴的な4小節フレーズの規則的パターンを含んでいたことであろう。しかし、規則的な4小節バランシングは、15世紀の記録されたポリフォニー音楽ではきわめて希であった。 現存するポリフォニーのほとんどはお上品なのである。理想的には、こうした(上品な)様式では、このような(舞踏音楽にあるような)一定の規則性は慎重に避けられ、よりエレガントなバランスが取られていたようである。 p97 だが、デュファイが、彼の音楽において、まったく舞踏様のリズムを避けていたとは、決して言えない。完全に対照的なことが、彼のロンドー Ce jour de l'anにおいて見られる。 すべての3声において繰り返された三和音的形態での冒頭を見ると、これまで記述されてきたような声部の標準的ヒエラルキーはまだその力を持っているということを、覚えておかれたい。すなわち、discantusとtenorは、対位法的構造の基礎を保持し、コントラテノールは、構文上で言えば、テノールと同じ音域において動く、従属的な声部となっている。 多くのデュファイの作品におけるように、その連続している声部は、これら3つの機能的に異なる声部の旋律スタイルが統一される方法を持っている。当時の構造体系の中のことにおいてではあるが。 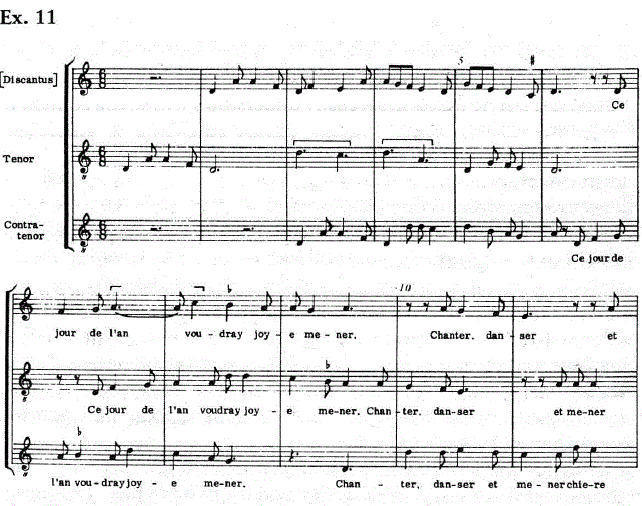 楽譜 この作品では、(近代譜作成における)その他の場においてと同様、もともとの音価は(近代譜では)1/4になっている。ゆえに、Adieu ces bons vins の3/4拍子は、同じリズムの作品とともに、基本的にbrevisとsemibrevisで動くことがオリジナルである記譜法を反映している。これは○で表記される。これに対して、Je me complainsのような6/8拍子の作品は、基本的に、semibrevisとminimaの記譜法を反映している。これは、 ○と p99 その理由は十分にはまだ解明されていないが、ヨーロッパ中の作曲家らは、1430年頃以後は、6/8拍子 それはCe moys de mayであり、この作品は、1小節分内における6/8 と3/4の間での極端なヘミオラの使用例となっている。(記譜法的には、colorの手段でこれは達成されている。多くは、白色記譜法内に黒色記譜の音符が書かれている)。(まうかめ堂参照) ここでの効果は、さまざまなリズミカルな要素-ヘミオラ、トロカイック6/8、およびiambic 6/8の並置で、非常にリズム的である。しかし、デュファイの時代までには、こうしたスタイルは決まり文句のようなものになっていた。 このスタイルは、14世紀後半の音楽の並外れた複雑さ(訳注;いわゆるars subtilior)に対する反応として最初に現れたようである。前世代のよりpreciousでリズミカルに贅沢な音楽の後には、堅牢で明確なものが必要だったのだ。 Ce moys de mayはしばしばデュファイの特徴的な曲としてプロデュースされている。実際、彼の曲の魅力は、彼が自分自身を膨らますことはめったになく、実際にはすべての曲、が異なる作曲上の問題を解決する試みであるということである。しかし、そうしたことを念頭においても、Ce moys de mayは、彼の作品においても、リズム的にはるかにアグレッシブな曲であることは間違いない。  p100 デュファイの初期のSongsの間では、いくつかの一般的特徴がある。 最初に、ロンドー形式がもっとも一般的である(通常、4行5連)が、彼は時折、特殊なイヴェントを記念するために、Songsのためにバラード形式を使っている。すなわち、彼の伝記の章はこれらのいくつかに言及したが、彼は、1430年代半ばで、バラードの使用をやめている。 第2に、デュファイのキャリアを通じて、彼は、同時代人の誰よりも、コントラストのあるテクスチャのパッセージのための特殊な選好を持っていた。それは、同音域で3声部がオーバーラップしている。この例はロンドーNavre je sui(例13)である。 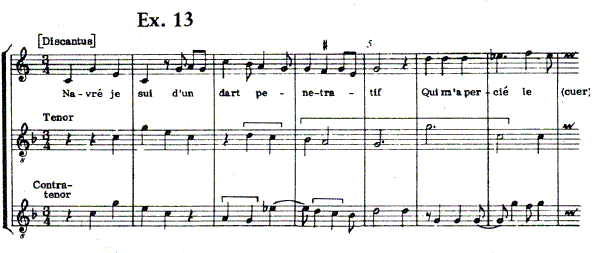 Navre je sui d'un dart penetratif このsongsは、1430年頃に特殊化したデュファイの魅力を特徴化している。それは、特に、Cを基礎とした、長調と短調の三和音交替である。 この問題はすでに、 Besselerによって、Terzfreieitと呼ばれていた、三度の動きである。13 Navre je suiにおいて、最初の声部のインターロックは、Cmajorの三和音を主張し、第3小節や第7小節のE♭の出現が、明らかになるようになっている。C上の三和音におけるこうした三度の動きは、デュファイの作品で現れ続け、彼の最後のミサ曲、Ave regina celorumでその頂点に達する。 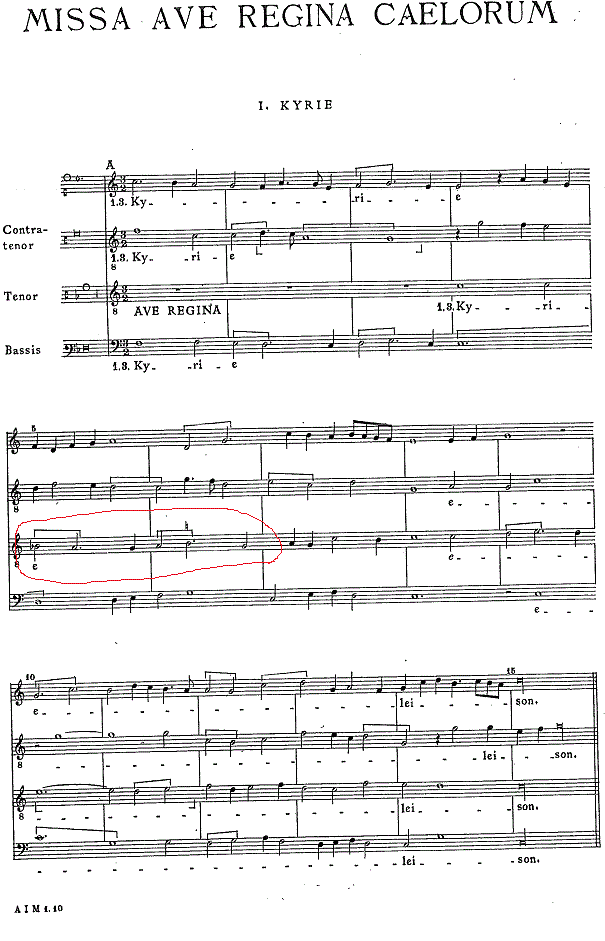 次の章では、1430年代にデュファイが、初期のモテットのいくつかの激しい複雑さに興味を失い、可能な限り最も経済的な手段を使用して、単純な種類の音楽表現として努力していたことを示します。1例がSe la face ay paleであり、もう1例が、Bon jour,bon moisである。14 As a final example of Dufay's early song style becoming more focussed in its aims,ロンドーHe,compaignons,resvelons nousは、ある種の複雑さを示す。それは4声であるが、しかし、3声の構造が、ほぼ常に適用される一貫した規則となっているように見える。デュファイの4声構造は、はるかに不規則である。歌詞がついた上2声は、互いに、discantus-tenorの関係にあるように見える。確かにそれらはオーバーラップしているが、それは当時の最もステレオタイプの曲でさえ頻繁に起こっている。そしてある程度、声部交換しているように見えますが、それも珍しいことではない。 例14では、歌詞のない下の2声部は、写本では、'contratenor'そして'concordans cum omnibus'と書かれているが、それらの動きは主に、G上のマイナーな共通和音の音符に限定されている。これは、曲の大部分で低音部分がGまたはDのいずれかであることを意味している。 これは、2つのテキストメッセージの流麗さによってある程度緩和され、第5〜6小節(例14)のように、行間のメリスマ的な書法の量によって緩和されている。 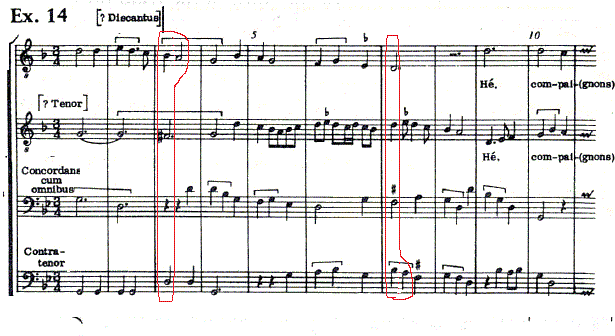 p102 しかし、作品の自主的な制限 は、それ以上に進んでいる。すなわち、第3,7小節では、Aに解決する前に、Bフラットとなる声部の1つによって形成される一時的な増三和音がある。この進行は、歌の重要なポイントでさらに3回発生している。15 それは、この曲が、これら2つのデバイスを使用するためのある程度の実例であるかのようである。 繰り返しになるが、これらは別の作品、彼の拡張されたシーケンス設定であるGaude virgo、 'mater Christi(v / 1)から派生しているように見える発想である。 ここでは、4声の音域が広くなっているが、対位法とリズミカルな動きは非常に似ている。最も低い声部は、He、compaignonsのように、G上の和音のマイナーバージョンに基づいた奇妙な広い飛躍を持っている(当時のトランペットではおそらく実行できないが、トランペットのような方法である)。そして、He、compaignonsほどではないが、増三和音の同様のカデンツパターンが現れる。 楽譜p127 Guillaume Dufay: Hé, compaignons デュファイの作品の膨大な種類の中で、これら2つの作品の類似性は特に印象的である。そして、どちらも彼の作品の他のものとはまったく異なっている。 デュファイの前後の時期の多くの作曲家は、創造的なエネルギーを集中させ、他の方法では起こらなかったかもしれない方向にそれを向けるために、アーティフィシャルな作曲上の問題を作成する必要があることに気づいた。 それは、ストラヴィンスキーによってもっとも納得できるように表現された発想である新ウィーン楽派の作曲家らに最もよく例示されている。 Hé, compaignonsにおいて、デュファイはおそらく、自主的な制限によって、彼や彼の同時代の人々による他のものとはまったく異なる曲を制作することを鼓舞された。そして、たとえ彼がそれらの制限を完全に超越することに成功しなかったとしても、作品は、彼の最高の作品のギャラリーにおいて、独自の特別な位置を占めている。そして、それはモテットへの移行としても役立つ。おそらく、シリアリズムの台頭前の音楽に外部から課せられた、作曲上の問題を伴う形式の最も重要な例である。 |