| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE
MUSIC8 |
| 6. STYLISTIC ANALYSIS OF THE CAPUT MASSES DUFAY(訳注;現在ではDufay作は否定され、anonimousとされている) 楽譜へ p272
デュファイのCaput Massは、Masses on Ecce ancilla and Ave regina celorumのように、彼のより後期の様式を代表している。耳を打つものは、メロディの透明な構成である。彼は、自身のパターンを直接作り上げ、カデンツに向かっての優雅なカーブや膨らんだ線がある。しばしば生じる短い休符は、彼の慣れた合理的なデザインの明瞭さを伴うフレーズ構造を築いている。それは、初期の頃のメロディとは一線を画している。 作品のメロディ的な興味は、その最高声部にあり、曲全体を導くものである。それは表面上に公然と存在する長い二重唱だけでなく、メロディが自由にcantus firmus(これは単に高音域の妨げられない流れのための引き立て役として役立つ)からあがってくるような4パート部位においても同様である。 メロディは基本的に、三度、四度で動く。それらは、ステレオタイプの装飾されたメロディ公式によって満たされている。こうした装飾は、メロディにその典型的なリズム的柔軟性を与え、同時に、公的な透明性や優雅性を与える。 メロディは、本質的に、和声的方法によって生まれたカデンツで支持されている。フルセクションにおける第2コントラテノールは、もはや伝統的なコントラテノールとは異なり、和音設定における事実上のバスとして機能する。その典型例が、 Qui tollis (Ex. 5)に見られる。 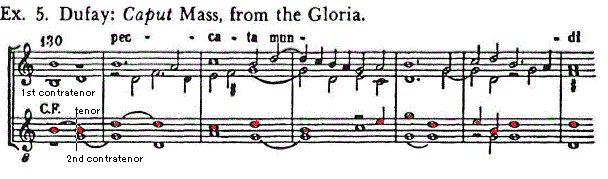 p273 この引用された部分は、statementBの最初を示している。和音は、純粋にバス進行と呼ばれるものである。こうした和声進行的なバスの出現は、デュファイの後期のもっとも様式的な進化を示す4声書法の新しいタイプの必然の結論である。 cantus firmusがドロップアウトするセクションでは、第2コントラテノールは、あまりバスのようではなく、よりメロディ的に出現し、上声部の対位声部として働く。第1コントラテノールは、二重唱においてのみ、必須である。そこではソプラノへのメロディの対位として機能している。4パート部分では、それは多かれ少なかれ、しばしば生じるスキップや休符の隙間を埋める存在として機能している。第1コントラテノールが、進行に侵襲を加えることなく、フルセクションでは省略される可能性があるという事実は、4パート書法の初期段階を示すものである。彼の後期様式においてさえ、デュファイは、そのメロディの重要性において、4声を等しく、バランスさせることは、まだできなかった。 高音域の優位性は、透明なフレーズ構造を説明する。それは、耳にも快く感じる。デュファイは、その早期から後期の様式を発展させ、彼は、自分自身、均整の取れたフレーズの巨匠であることを、ますます示した。音楽の横糸の透明さは、作曲家の豊かなテクスチャコントラストの使用によって大幅に強化されている。彼はこの点において、彼の後継者よりも尊敬されている。オケゲムもオブレヒトも、Caputミサ曲において、このような長い二重唱は書いていない。Dufayは、ほぼすべての可能な用例で音声のペア化を利用し、したがって、連続して直接に、または交互に完全な4声パッセージでお互いに続く様々なテクスチャのセクションを生成する。 Caputミサ曲のカデンツは、デュファイの初期の作品のそれとは、決定的に異なっている。ほとんどすべてはそのメロディの形においては、ステレオタイプの様式を残している。いわゆる「ランディーニ六度」である。デュファイは、その後期の作品において、このあまねく存在するメロディ音型を、ars novaの時代から普及していた古いVII6-Iあるいは六度カデンツ(ランディーニ終止)によってではなく、近代的なV-Iカデンツで和声化した。
p274 このカデンツは、15世紀の前半に次第に現れ、最初は、Ex6aにあるように、コントラテノールがオクターブ跳躍する形式を取っていた。4声における十分発展した形式を取るようになると、バスは、四度上がるか、五度下がることとなった(Ex.6b)。 重要なことは、デュファイのCaputミサ曲で広く見られるのは、後者である、ということである。以下において、もっとも重要なカデンツがリスト化されており、すなわち、これらはcantus firmusの第1,2statementからのものである。すべては、ト長調(Gmode)で、あらわされている。 すべての楽章の最後のカデンツは、近代的なV-I進行を使っており、最初のパートのカデンツにおいてもそうである。SanctusとAgnusは、最初の部分は、古臭い六度和音カデンツとなっている。正確には、後者の2つのカデンツは、三度を導き、しかし、Agnusでは繋留されている。最後の和音でのフルの三和音の使用は、言わば、古いタイプのカデンツを新しいものとした大陸の音楽の近代主義に触れているものである。一方、すべてのV-Iカデンツは、三度のない五度で終わる。SanctusとAgnusの同様のカデンツは、ミサの楽章のペアとなっていた配列の名残を示す唯一兆候である。 デュファイがカデンツをはっきり主張した和声は、ほとんどすべての状態からアプローチできる単純なドミナント・トニック進行から成り立っている。カデンツ間の和音進行は、機能的論理ではなく、メロディ、すなわち、横の線の原理によっている。Gombosは正しく強調している。カデンツの空間は、本質的にメロディに依存している、と。それぞれの楽章の流れは、事実、十分に発達した後期ルネサンス音楽の和音様式のようにカデンツによって分けられているわけではない。和音機能よりもメロディ機能が、和音書法がその初期段階にあったことをはっきりさせている。カデンツは自身、はっきり定義づけられ、確立していたが、その幅広い内容にはまだ影響はない。その組織的な力はその直接の周りを超えてはまだ発散されていなかった。 p275 デュファイの音楽において、カデンツの和音形式は近代的ではあるが、そのむき出しの本質にまだ制限されており、狭いスペースに限定されていた。他方、そのメロディ形式は、古い装飾的なカデンツ音型に戻っている。その行きつ戻りつの組み合わせにおいて、デュファイのカデンツは彼の後期のヤヌスの顔のシンボルとして、受け取られることができよう。作曲家の正確な歴史的な位置づけはEx6bの単純なフォーミュラにおいてまとめ上げることができる。 ミサ曲の和声様式は、全般的に、不協和音の取り扱いの標準化をはっきりさせている。それは、ルネサンス音楽の顕著な業績のひとつである。この標準化へのデュファイの貢献は、過大評価されがちであり、偶然にも、Tinctorisは、その作曲家の作品から対位法の "規則"を証明するのが好きなのである。 デュファイの不協和音の取り扱いは、三和音を主要な和音的な組み合わせと認めている。和音は最初の拍で、協和音程へと解決するような協和音あるいは繋留音であらねばならない。不協和音は、第2拍や拍の分割へ追いやられ、ほとんどは経過的に生じる。 ミサ曲には例外的に荒い不協和音もまた存在することは確かである。こうした摩擦は、4パート書法がまだまだ新しかったことを示している。まだまだ不慣れな4パート書法の多くが強制的に解決すらできない状況を作り出していた。 しばしば発生する上声部間の平行五度は、同じような困難を生じさせている。4パートがトラブルメーカーで、その他のパートの妨げになっていることは普通である。声部が省略されれば、基礎となる協和音程は通常、もとに戻る。 無数の不協和音がミスプリントによるものであることが判明し、誤った校訂によることも付け加えられねばなるまい。たとえば、Agnus(第178-179小節)の最初のコントラテノールは崩れ、校訂者によって誤って校訂されている。 模倣は、デュファイのミサ曲においては、ほとんど重要な役割は果たしてはいない。全体的に、テクスチャーは模倣的ではなく、模倣が生じる時にはいつでも、それは偶然であり、特に構造的な機能は持っていない。Christe(m. 190 ff.)やAgnus(m. 9-12 、 100-104)において見られるように。模倣は、cantus firmusへの影響はなく、自由に作曲された声部の間に起こる。 p276 時には、それはほとんど聞き取れないような、不明瞭な具合になっている。このようなパッセージは、ChrIste (m. 138-140)やGloria(m. 112-115)において見られる。こうした模倣は、そのモティーフにおいて、cantus firmusから完全に独立している。。こうした見方は、Schegarの視点からは異なっている。彼は、Austrian Denkmaler において、ソプラノは(ある程度は他の声部にもあるが)、cantus firmusの持続的なパラフレーズやメロディの丹精さに過ぎないと、分析している。 彼の主張は、すでに信頼のなくなっている古いSchegarの理論に陥っている。Schegarの分析は、その方法論や結果において、もはや、通用しない。cantus firmus自身の中の「バリエーション」が証明されたとされている同じような欠点のある方法はその他の声部にも適用される。 これまで主張されてきたcantus firmusとtrebleの間の類似性は、manipulationとははるかにかけ離れた結果である。Schegarは最初にcantus firmusを彼の仮説である"Grundformen"に分け、その他の声部を、基本的な間隔の動機的素材に縮小している。さらに彼は、彼の”動機”の部分的移調をさせるだけでなく、彼が基本的に、内容からはずれ、ステレオタイプ化し、偏在するメロディ音型と考えるintervalを持ち上げる。 こうした工夫された類似性は、この当時のほとんどの声部から見つかることは、言うまでもない。Schegarの分析方法は歴史的ではない。なぜならそれは、ルネサンス音楽の手順には合致しないからである。それは、擬似学者の徹底と誤った巧妙さの古典的な例として書き留めなければならない。 デュファイのミサ曲において、cantus firmusは、作品の一般的なフレームワークとして存在している。それは、その構成部分において、楽章に分けられ、バスに、さまざまな和声化を与える。しかし、メロディデザインは与えない。 オケゲムの作品でときどき見られる、cantus firmusのメロディの本質をもって自由に作曲された声部の一貫性は、例外はあるが、デュファイでは典型的ではない。作曲された声部のcantus firmusへの同化は、循環ミサ曲の後期局面においてのみ、出現してくる。cantus firmusは、もともと存在していた声部ではあるが、そのメロディは、trebleへの対位法的支えとしては、あいまいである。正確に言えば、こうしたサポートは素材を借用するために、trebleが、作品の焦点となる。 p277 最後に、全体的にミサ曲を考えてみよう。全5楽章に行き渡る循環的統一性は、本質的には、2つの要素によって保証される。1つは、作品の内部構造を統一している二重のcursusを持つcantus firmusで、もう一つは、すべての楽章で生じる導入二重唱のモットー冒頭である。110 110 モットー動機が、cantus firmusとは何の関係もないという事実は、ソプラノがテノールに依存しているという主張に対してありがちな議論としてとらえられるかもしれない。 モットーは厳密な構造機能は持たないので、聴取者には単に、構造としての4声部が入ってくる前に、各楽章が互いに関連していることを認めさせるだけである。 導入二重唱は、常にド音で入り、楽章は常にソ音で終わる。デュファイは、その和声において、ミキソリディア旋法を取り、それはcantus firmusに適当な旋法であり、それが入るときには、いつでもソ音上の三和音が響き渡る。 Kyrieのみが例外で、テノールが一度ホ短調となり、それゆえKyrieはいくぶん、和音の点で、その他の楽章とは異なっている。我々は、Sanctus and Agnusもまた、その古風な六度カデンツ(ランディーニ終止)で区別されることを見た。 さらなる区別は、cantus firmusの2つの先立つstatementを比べると、明らかになる。GloriaとCredoにおいて、それらは、Sanctus and Agnusの2倍の長さとなっている。テキストの長さのゆえに。音楽的には、5つの楽章は、巧妙に、区別され、Kyrie,GloriaとCredo,SanctusとAgnusというようにグループ化される。ゆえに、最初期の完全な循環ミサにおいて見られる楽章のもともとのペアは、デュファイの作品ですでに示されている。 ペアとしての配列は、しかしながら、楽章間のメロディの反復においては影響されない。その豊かなメロディの想像性に対し、デュファイは、モットーで開始した後、新しいメロディの服を、5つの楽章の不変のスキームに着せた。その間、フレーズ、カデンツは変化した。メロディは、リズムパターンや対位法的組み合わせの中でデザインされた。 たとえこれらすべてが、いくぶん公式化されても、それらは、新しい順列において開かれ、メロディにおいて、同時的な流れへとへつらっていく。ある種のパターンはこうした文脈から取り出され、メロディ反復の”証明”として引用されるが、こうした方法では、特徴的なモティーフのランクへ上昇する公式によるポイントを失うことであろう。 p278 例外的に、同じメロディ的ターンは、さまざまな楽章において、同様の場所で明らかになる。反復は、容易に注目を逃れる。そのメロディの持続的開放性ゆえに。 もっとも華美な、また拡張した反復は、GloriaとAgnusに見られる。statement Bのまったく同じところで、デュファイは、すべての声部において、事実上、同じ12小節を書いている(Gloria m. 130ー142= Agnus m. 115-127)。ソプラノとバスにおける相応部位は、期待通り、密接に関係している。Altoにおいてもほぼ同様に。この”double take”においてさえも、変化したカデンツによって、最後においては、メロディは異なって発せられ、それゆえ、2回目には、異なった観点となる。ミサ曲は全体として、デュファイの適切な発明と注目すべきメロディの発想の多彩さを証明している。 OKEGHEM 楽譜 オケゲムのCaputミサ曲の議論において、我々は、デュファイへ適用された手順の逆を行き、より大きな公式的観点から始め、内部の様式的相違へと移るべきであろう。 オケゲムのミサ曲は、デュファイのそれと比較すると短い。それは主として、導入二重唱ががより簡潔だからである。すべての5つの楽章が同じcantus firmusで結びついているが、循環的統一性の密接さは、あとの4つの楽章においてのみ、現れる。Kyrieは、少し区別される。それは極端に短く、cantus firmusは、切り詰められて、一度のみしか現れず、導入二重唱は省略され、他のすべての楽章で見られるモットー的冒頭も、この楽章では見られない。 モットー自身は、ほとんどデュファイからの借用であるが、三度低く移調されている(Ex. 7.)。その類似性は、すべての楽章に等しくはないが。その他の借用の特徴の観点においては、ほとんど偶発的要素はあり得ない。相応性は、ほとんど、Sanctus-Agnusのグループでもっとも明らかであり、その他のペアではさほどではない。 p279 楽章のペアは、導入二重唱の特殊な特徴において、明らかになる。Gloria and Credoのそれらは、全休符によって分けられる2つのセクションからなっている。こうした二重唱セクションの奇妙な状態は、Leonel-Dunstable世代の典型的な英国作品では適正である。オケゲムもまた、こうした英国の影響に従った可能性がある。Van den Borrenは、すでに、 Caputミサ曲のメロディが英国形式を踏襲している、と主張している。 英国の影響は、Kyrieの別扱いからも推論され得る。それは、英国が、ポリフォニーの対象とは認めていなかった楽章である。オケゲムは、彼のミサ曲をもともとは、英国的やり方で書いた。すなわち、4つの楽章に、その中に大陸的実践を持つ作品をもたらすための再考としてのみのKyrieを加える、と言う形である。あるいは彼は、その糸口を、仮想的な英国のCaputミサ曲から取ったのかもしれない。それは、Kyrieやモットーなしで作曲されていた。 4つの引き続く楽章のペアとなる配列は、和声的意味によって、目立たせられる。ミサ曲は概して、ドーリア旋法であり、しかしそれは、和声の揺れの広い音域をカバーするように、散発的のにみである。和声的なあいまいさは、特に移調などをせずに、作曲家に、ドーリア旋法の作曲とミキソリディア旋法のプレインソングとを合体させることを可能としている。 彼は、旋法の齟齬を、cantus firmusにレ音を加えることによって、単純に解決している。それは、デュファイが必要としなかった工夫であった。なぜなら、その時には、何ら旋法的問題は存在していなかったからである。2つのテノールのstatementの最後の主たるカデンツの調査では、以下のようなものである。 デュファイとの決定的な違いは、オケゲムのカデンツが、彼の時代にはすでに幾分時代遅れになっていた六度和音の手段を取っていることである。Trent写本とChigi写本の2つの写本のみがこの作品を保存しているが、Kyrieの最初の方のカデンツに関しては、異なっている。Trent写本では、cantus firmusの最後の音符が保持され、Chigi写本では、semibreveの休符が、付け加えられたレ音の前に挿入されている。 結果として、Chigi写本のVII6-Iカデンツは、Trent写本ではV-Iカデンツということになる。Trent写本のカデンツは、より正確なvariantである。なぜなら、持続音のリズム価は、デュファイのテノールとは一致しないからである。 p280 Kyrieは、和声的には、別の楽章とは離れており、この場所においては、カデンツの近代的形式を含んでいる唯一のものである。Kyrieがその他より後に作曲されたということに関する我々の疑惑の確信として、これを受け取ることは、ありそうもない。なぜなら、六度和声カデンツは、熟考された古風として採用されたものであり、それゆえ、日時に関しては、何ら有効な評価基準がないからである。私が”熟考”というのは、オケゲムが、彼の楽章をいつも自由に作曲し、どんな進行も彼を拘束しなかったcodaで終止しているためである。彼はさらに、いまだに近代的なカデンツを避けようとしていたのである。 メロディ形式に関して、カデンツはデュファイのそれとは非常に対称的な状態にある。例外なく、それらはもはや、装飾的な六度の保守的公式は採用せず、終止への導音を用いる近代的カデンツ(7−8)で代替している。オケゲムのカデンツはそれゆえ、ヤヌスの顔(の二面性)を示している。それらは和声的には過去に遡り、メロディ的には先に進んでいる。言い換えると、それらはデュファイのカデンツの正確な補完であるが、2つの構成要素は、場所を交換しているのである。より古い作曲家が発展のより初期段階から先へ進み、より若い作曲家がよりあとの段階から戻ってきているように見える。 デュファイのミサ曲のように、カデンツは、あとの4つの楽章を2つのグループに分けている。Gloria and the Credoはすべてレ音で終わり、Sanctus and the Agnusは、最初の半分のカデンツにおいてはソ音で終わる。 和声、導入的二重唱、モットーによって楽章を分けようとすれば、ミサは全体として、3つのグループになる。すなわち、Kyrie; Gloria and Credo; Sanctus and Agnus、である。ペア化はデュファイの作品よりもオケゲムのそれで、より顕著であり、より古風な特徴とみなされる。 音楽様式については、2つのミサ曲は隔たりを見せている。足がかりの声部の同一性にも関わらず、オケゲムの個性は、最小の詳細だけでなく、一般的アプローチにも急に入り込む。作品から出ている特殊な味わいを言葉で捕らえるのは困難である。Van den Borreは、オケゲムについて、「そこにシステムはない」と言ったが、そこにシステムがない間、そこには非常にはっきりと異なるガイド的原理がある。それは、彼のテクニックのあらゆるその他の要素を修正し、深遠な影響を与えるパート書法の横のつながりの概念である。 p281 この原理は、オケゲムの自己矛盾的観点と思えることを仮定する。なぜなら、それは、逆説的なやり方において、逆行的、順行的な特徴を融合させるからである。一方、それぞれの声部の横のつながりの概念から起こる独立性は、連続的に作曲された声部の積み重ねであるゴシック期のポリフォニーの遺物であるように思える。他方、声部はもはや、層として重ね合わされず、もし声部が同時に(縦に)産まれるならば、可能な豊かな対位法的な布地においてからみ合わせられる。 こうした音楽の顕著な特質のひとつは、4つの相当する声部の取り扱いにおける、デュファイを超えた進歩である。どんな声部も、全体を妨げずに省略されることはできない。デュファイが音楽的関心をtrebleに集中させ、それはフレーズ構造や和声化双方を決定づけているが、このような単一の決定はオケゲムにとっては存在しない。これは、彼の音楽を理解するための主な障害のひとつを構成している。 オケゲムの横のつながりの対位法は、本質的に模倣的ではなく、対位法の歴史的実践的著作において最小化された対位法書法のタイプに属している。模倣的ではない対位法は、対位法芸術の発展におけるちょっとしたわき道であり、想像への把握と挑戦を困難にする。今日の対位法の教示においては、ここで議論をする余地もないほどに、それはほとんど自明なことである。対位法は、実際には、模倣と同義であり、これと分けがたいものなのである。 オケゲムの対位法は、おそらく、反対の概念のもっともよい例である。Riemannが私たちに、不十分な音楽の知識と早熟な一般化を基礎に信じようとさせたように、オケゲムは、連続的構造的模倣の”父”である存在とはかけ離れている。 それどころか、オケゲムの神聖な音楽作品は、模倣的エントリーの不足によって特徴付けられる。そして、見出されるわずかなそれは、モットー的冒頭に対して抑制的であり、オケゲム自身、あるいは構造的機能のない単なる流行的模倣でさえないかもしれない。 彼の世俗作品において、少なくとも時折、よりシステマティックで首尾一貫した模倣の使用は、彼の著明な模倣的シャンソンPetite Camusetteにおいて見られる。模倣の発展へのオケゲムの貢献に対する主張があるのなら、彼のシャンソンがそれを支持し得ることだろう。しかしこの形式においては、模倣の工夫は、フランドル楽派の初期以来、使われていた。 p282 オケゲムのMissa Fors seulementのような後期の作品においてさえ、模倣はほとんどなく、主たる地位を確立しているとは言えない。 ヨハンネス・オケゲムによるMissa Fors seulementという5声のミサ曲は、しばしば最初のパロディ(模倣)ミサ曲と呼ばれる。音楽学者Fabrice Fitch は、いくぶんの誤り導いている:通常、パロディ(または模倣)ミサ曲という用語は、ミサ曲の設定のモデルとなる作品のポリフォニー的布地の全体的パッチを借用する、より後のテクニックに言及している。Missa "Fors seulement" は、同時には使われない、異なったいくつかのモデルを借用している。 テクニカルなことはさておき、このミサ曲は、彼自身の Missa "Ma maistresse,"からの cantus firmus の取り扱いに対するある種の実験を打ち立てた作曲家を示している。そして、彼のモデルから借用したメロディ(Ockeghem's own Rondeau cinquain Fors seulement l'attente)を取り扱っている。より大きな自由、器用さ、ミサ曲における満足度を伴って。 ミサ曲のひとつの写譜のみが現存している。彼の死後の写本において。しかし、作曲技術におけるその進歩(cantus firmus の取り扱い、模倣の使用において)は、後でオケゲムの人生において、それに日付を書くために、ほとんどの注釈者を促した。おそらくは、最初はチャプレンとして、後にはフランス王室チャペルのマスターとしての彼のもっとも重要なキャリアの期間である。 5声のための3作品(the motet Intemerata Dei mater, the Missa sine nomine, and the Missa "Fors seulement." )は、いわゆるChigi Codexと呼ばれる写本中に所蔵されており、それは、15世紀後半に写譜されたレトロスペクティブな名誉的なアンソロジーである。 これらの3作品は、声部において、非常に低い音域にあり、王室礼拝堂がbasso profundo の礼拝をしていた時代に同時に作曲されたと考えられる。 Missa "Fors seulement."については、Kyrie, Gloria, and Credoの3声部のみが現存している。この写本の初期がCredoの後に空白のページを残したことは、ミサ曲がChigi写本中に残されているように、不完全であることを示している。Credoは、前の2楽章と比べて、声部がいくぶん高い音域であり、学者らは、楽章の移調、アンサンブルの変化、あるいはCredoが異なったミサ曲の設定に属している可能性を示唆している。 オケゲムは、Kyrie and Credo を、"Fors seullement"上に作り上げ、cantus firmus の構造の明らかな原則を保っている。Kyrieは、中声部からの引用とともに、シャンソンモデルからの最上声部を借用している。 Credoの前半は、この同じ上声部のテノールstatementにて作られている。後半は、シャンソンの中間声部からの連続的な引用で終止している。cantus firmus の素材を含むフレーズは、シャンソンの異なったパートを示唆するパッセージとともにちりばめられている。声部のテキスチャーのコントラストは、しばしば、フレーズのアーティキュレーションを達成させる。Gloriaにおける cantus firmus は、しばしば声部から声部へと移り行くが、引用されたメロディはほとんど変っていない。Gloria and Credoの双方において、楽章は、3拍子である。モデルの引用は2拍子であるが。 全体的に、対位法は深く、特に、ミ音とファ音を基礎とした和声の間において、和声の変動の豊かさと関連している。Gloriaの終止は、潜在的例を供給する。あるパッセージにおいて、2つのテノール声部は、二度のメロディの音程差でフレーズを交代する。 Parts/Movements
Missa Prolationumは、計量的カノンを使用し、唯一の例となっている。なぜなら、カノン声部は一斉に始まり、そのために、模倣構造は特に、聞き取れないからである。 Caputミサ曲においては、模倣は事実上、存在せず、それが発見される珍しい例は、規則に従う。もっとも明瞭なケースはおそらく、Sanctus (m. 10-12)の導入二重唱である。それは、五度の模倣をもたらす。 通作模倣形式を思わせる五度の模倣 作曲家による模倣の曖昧な使用典型的な例は、 Credo (m. 68-73)に生じている。そこでは、自由な3声がゆるやかに互いに模倣をしている。 にもかかわらず、模倣の関係が明らかに故意のものである。それは、声部がしばらくの休符の後に、連続的に入ってくるためである。もうひとつの模倣の例は、Ex.9の下に見られる。 だが一般的に、容易に聴き分けられる素描されたモティーフを出すことなしに、声部は互いに独立に動く。オケゲムが模倣に際して、正確なモティーフを算出することができることは、彼のシャンソンで証明されているが、彼の神聖なる音楽においては、異なった道を取っている。彼の非模倣的なポリフォニーを維持しながら。 こうした観察は、我々に、決定的なことをもたらす。すなわち、きちんと明示され素描されたモティーフを予想するような、成功裡に操作し得ないことはない模倣である。 模倣の欠如はそれゆえ、唯一、こうしたモティーフの存在の論理的帰結となる。付き添った様式的要素は、オケゲムの明らかな、メロディの連続への明らかな嫌悪である。こうした工夫はひとつの声部への模倣の企図に過ぎないが、反復において聞き取り得る、認識し得るような一定のパターンを必要とする。全体の模倣と連続の複合体は、こうしたパターンに依存し、特にこれらはオケゲムに顕著な一貫性を控えさせる。 読者は、オケゲムの対位法が、否定的に書かれていることに気づかないわけではないだろう。こうした否定的なアプローチは、正確な文学上のデヴァイスではなく、我々現在の専門用語が、オケゲムの音楽を適当に記述するだけの積極的な用語を欠いているという事実の、論理的な結果である。 p283 こうした欠如は、様式分析の深刻な妨げとなる。それゆえ、オケゲムの対位法が何であるかを積極的に述べることは簡単ではない。我々は、その主たる原理が横のつながりのパート書法であることをすでに見ており、そして、それだけを通して、彼の対位法が妥当に理解されているのである。 制限されたパターンやアーティキュレーションの慣習的意味合いの欠如において、それぞれの声部はスムーズに流れ、自身の横方向へのみ、従っていく。こうした効果は、片やある声部、片や別の声部、そして必ずしも主たる声部としてのcantus firmusに対する必要はない対位法としての、それぞれの声部の書法からの結果である。 こうしたテクニックは、Credo (Ex. 8)の短いパッセージによって説明されることだろう。それは、Dufay (Ex. 5)から引用された抜粋との類似性を持つcantus firmusのstatement Bとともに始まる。 各声部が比較的均等に動いている 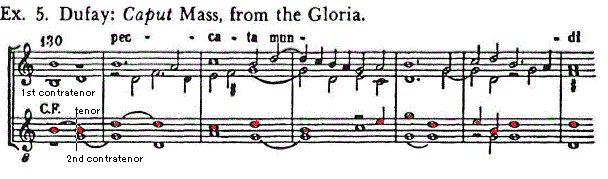 trebleの動きに優位性がある 声部は、対位法的テキスチャーやリズムペースに関してほとんど等しいことに注意されたい。デュファイが主たる声部を流動的にし、それをcantus firmus and bassに対抗させたのに対し、オケゲムは流動するパッセージをより均等に、あらゆる自由な声部に分配し、 リズムペースをcantus firmusのそれに適合させることによって、借用した声部とともにリズムのコントラストを最小化した。 こうしたリズムの均等化は、対位法的な関連性を育む。声部は、お互い相互的に、対位法に対するスプリングボードとしての役割をする。そのために、”メロディ”がどれか、を言い当てることが不可能になる。 p284 声部は主題はしばしばペア化され、互いに反行したり(see treble and tenor in m. 148-149)、平行したり (see bass and alto at the beginning of the example)することになる。後者の場合、声部は十度で動き、こうした目的のためのオケゲムの好みの音程のひとつとなる。 オケゲムの書法のまさにその性質によって、trebleはめったに主たる声部にはならなくなる。それは、primus inter pareにさえならなくなる。しかし、4声の自律性のひとつはまだ、声部を連関させている。重要さにおける交代、それぞれの声部は、交代に互いに、その主たる地位を放棄する。 リズムやメロディにおける独立性は、それ自身、モティーフの形成のためのその他の声部に対して目立つに十分な特徴ではない。単一声部のそれらの関連へのトータルの効果への従属性は、ある種の統一を創造する。それは、不活発を伴う混乱ではなく、声部の均等化による、自然の結果である。こうした様式の作曲の困難さは、それぞれの声部が、個々の声部であるに十分自律的であるに違いないことであり、他の声部に対して侵略するようなことはない。 自律的な声部の独立性は、明らかに、複雑なフレーズの構造に反映されている。こうしたパート書法において、声部は休止点においては一致しない。フレーズは、不均等な長さであり、それゆえ、一緒にカデンツになることができない。各声部の非対照的かつ独立したフレーズ構造は、強く、声部の独立を強化する。 フレーズをオーバーラップさせるような大陸的な流れは、我々に、オケゲムの音楽におけるそれは、もっとも重要なひとつの要素をもたらす。それは、カデンツの忌避、である。彼は、真の”空間恐怖症”であり、連続する絡み合いや声部のオーバーラッピングを妨げることや、同時の停止における声部の流れを中断することへの強い嫌悪を裏切る。 Ex.8に見られるセクションは、4声パッセージの始まりを再生し、46小節の間に対して1つの終止をも含まず、カデンツが最後に来ても、それを強調しようとしない。cantus firmusが最低声部として現れる事実は、カデンツ忌避を容易にし、明らかにこれが、なぜオケゲムがバスをそのように置いたかの主たる理由である。 そこには、声部の流れを支える2つのカデンツの工夫がある。ひとつは、ツァルリーノが妨害的カデンツと呼んだもので、 カデンツになじまない、あるいは簡潔に休止する音符上で、もうひとつの声部と互いに動く間、1つの声部があたかもそれがカデンツに来たかのように振舞う。 もうひとつは、”偽終止”で、我々はそれを、 Ex. 8,m . 155-156において見出すが、同様に、オケゲムがたえず使った偽終止進行は、時には、cantus firmusを導く意味合いさえある。 p285 カデンツの忌避(何とネガティブな用語だ!)は、オケゲムの音楽の特徴である休符のない持続性を説明する。主たる分割に対して、そこには、コントラストを柔和にし、二重唱とフルセクションの間のスムーズな移行をもたらす。彼がカデンツと共にデュエットを終わらしてさえ、彼はひとつの声部の動きを続け、そのままtuttiへと走りこんでいくdo (see the beginning of the Credo)。 オケゲムの二重唱→tutti 移行例;重なっている(Gloria) デュファイの二重唱→tutti移行例; 分離している(Gloria) Sanctusは、接合部における両者の可能性を説明している。カデンツを完全に無視し、2声から4声への設定を漸次拡大するこうした移行は、さらにより派手である。こうしたケースは、Qui tollisの最初に見られ、cantus firmusはほとんど気づかれずに入ってくる。 切れ目のない流れを作りたいという願望は、それ自身、メロディのデザインを強く主張する。デュファイのメロディが、上品に隣り合うフレーズ同士で進行し、代わる代わるゴールを設定して、カデンツへと導くのに対し、オケゲムのオーバーラップする声部は、中空で漂う。なぜならそれらは、カデンツが通常供給するであろう安全に固定したポイントへ投錨しないからである。 こうした理由のために、それらはデュファイのモティーフの直接的な力強さを欠いているのであり、それらは一見したところ輪郭がなく、不合理な方式で波打ち、それら自身の間隔的な進行だけのために縛られている。これらの特殊な反抗的なしかし温和な性質やそれらの終わりのない浮動は、おそらく、”終わりのないメロディ”という用語で記述されることがもっとも適しているだろう。それらは実際、ワーグナーの音楽以上に適当な用語なのである。 声部の浮動する性質は、鋭い角がない明澄なリズムと、連続性の欠如あるいは反復パターンの欠如の代わる代わるのパターンに依っている。こうしたことは、耳にはその予想は困難である。浮動がカデンツによって制御されていないために、主たるセクションは、自発的にあるいは散発的に、予め考えられたプランなしに、生じるように見える。 しかしそこには、この熱狂的な印象を普及させることに対するひとつの例外がある。オケゲムは、終止に向かって緊張を高めるための大きな注意を払っている。そして、最後のカデンツへ導く期待の感情を創造する。 彼は、メロディのペースや和声的リズムをステップアップし、対位法的な複雑さを増加させる。そして、これらのデヴァイスを結びつけることによって、クライマックス的なstretto効果を成し遂げる。こうした”カデンツへの駆動”は、現象として呼ばれるかもしれないが、ルネッサンス期(1480-1530)の中期局面のみの特徴であるように見える。そして、フランドル楽派の作曲家たちに限定して見られるように思える。それはオケゲムと共に始まり、オブレヒトやジョスカンによって完成させられ、その後すぐに衰えていった。 p286 オケゲムのミサ曲は、この駆動のいくつかの例を差し出す。それは、Caputミサ曲において、最後のAgnus(Ex. 9)の終止で顕著に見られる。ここでは、メロディのペースは、作品中のその他の場所よりも早くなっている。そして、声部は、模倣のモティーフ的フラグメントによって統一されている。しかしそれはあまりに狭いスペースにおいてであり、そのために、あまりに緩く、簡単に見逃されてしまう。 バスがこの駆動に参加していないことは奇妙に見える。彼は、バスにも許容しようとしたが、完全に、駆動の大部分において、ドロップアウトし、最後の和音で再度バスを入れている。明らかに、作曲家は、すべての声部において増大したペースがクライマックスをむしろ混乱させるであろうことを恐れていた。にもかかわらず、カデンツへの駆動は、5声の作品、すなわちMissa Fors seuLementにも、しばしば見出される。 p287 カデンツあるいはその不在は、メロディに関して、あるいはフレーズ構造に関して、とりあえず議論されてきたが、まだ和声に関しては、そうではない。メロディに関して、音楽を特徴づけるそわそわした浮動は、和声の一貫したシフトと、”和音”とは正確には呼べないような垂直の組み合わせの虹色の相互作用においてより多く発せられる。この用語は、利便性のために少し慎まれるべきであろうが。 オケゲムの全体的な横のアプローチの観点においては、彼が完全にポリフォニーにハーモニーを従属させ、ハーモニーそのものにはほとんど関心を示していないことは、驚くには当たらない。彼の和音進行は、音程についての彼の対位法的組み合わせを育み、そして、それらは、特殊なハーモニープランやそれらが常軌を逸した、気ままなように見えた論理によっては導かれることはなかった。 しかし、それらの表向きの非論理的な特徴は、単に、カデンツ、ハーモニーの論理の基本的な意味合いが失われているという事実のもうひとつの見方に過ぎない。(オケゲムの)ハーモニーは、デュファイの音楽のように、他とははっきりと区別されたバス進行によって方向付けられていないために、オケゲムは、最低声部にcantus firmusを持ってくる余裕があった。それは、van den Borrenが指摘するように、近代和声感覚において十分満足できるバスでは、決してなかったのではあるが。しかし、正確には、この非常なる特徴は、オケゲムの要求に応えたのである。なぜならそれは、典型的なハーモニー進行ではなかったから。 バスにcantus firmusを置いた付加的な理由は、オケゲムの、黒色譜や一般的に、低い音域への性向にある。合唱音楽におけるバス音域の発展への最初の重要なステップを受け取ったのは、オケゲムと彼の後継者であった。これは、Caputミサ曲の音部記号においても、明瞭に現れている。それらは、デュファイのミサ曲のソプラノ、アルト、テノールの音部記号よりもかなり低く書かれている。デュファイもまた、ときどき、バス音部記号を要求しているが、それは大部分、彼の後期の作品においてである。たとえば、Mass Ecce ancillaのように。彼は、和声的理由で、低い音域へ挑戦し、ハーモニーへの手堅いサポートを得ている。オケゲムは、それを色彩的理由で行い、まじめやミステリアスに混合された音響を得ている。 彼の垂直の音域の組み合わせにおいて、オケゲムは、根音上の三和音を好んだ。しばしば六度和音と交代しながら。平行六度のつながりは、 Caputミサ曲においては、短いセクションに限定されている。特に、最後のカデンツ前の最後の少ない進行において。 p288 英国の影響下で、六度和音様式のこうした名残を解釈するのは、あまりあてにならないであろう。なぜならそれは、デュファイの”後半期”にあたるフランドル楽派に共通する資産だったから。オケゲムの英国音楽への親和性は、彼のメロディ様式よりも、彼の六度和音において、より少ない。彼は、自分の声部を、平行十度で組み合わせることを好んでいる。特に、3声セクションにおいて。こうした工夫は、”四度ではない和音”と呼ばれたものを示唆する。しかし Caputミサ曲にはこうした書法の証拠はない。 不協和音についての彼の取り扱いは、current practiceとは本質的に異なっている。強拍上の不協和音は、通常、装飾的六度、倚音、逸音、といったステレオタイプのメロディ公式で準備され、導入される。すべては協和音進行に風味を与えるものである。 彼は、繋留音をときどき、不規則なスキップによってあるいは、echappee公式による典型的な装飾的やり方によって、解決する。例としては、 Sanctus (Ex. 10) or m. 14-15 of the Gloriaがあげられる。 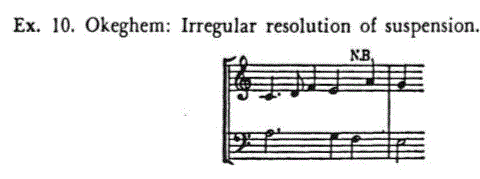 Caputミサ曲のもっとも驚くべき不協和音は、編纂者のミスである。最後のAgnusの全体セクションには、不正確な写譜やAustrian Denkmalerの版で任意に変えられている。しかし、Plamenacによる校訂では正されている。しかし後者は、キージ写本中の1つあるいは2つの書記の間違いを見逃していた。彼は、Agnus (m.72 -73)の筆写において、cantus firmusの間違った理解をそのままとし、トレント写本の正しい版を校訂のapparatusへ追いやっている。トレント写本の理解が正しいことは、cantus firmusのstatementから容易に確信できる。Credo (m. 24)のコントラテノールにおいてもまた、トレント写本の変異は好ましい。 p289 オケゲムのミサ曲にあまねくある旋法は明らかに、ドーリア旋法、あるいはヒポドリア旋法が中心であるが、声部の組み合わせは、確立した旋法には該当しないような三和音の進行という結果となる。 歌手がシ音を(cantus firmusの前半部分に奇妙な外観を与える)フラットさせないようにするために、ムジカフィクタはしばしば記述され、重要な場所では、しばしば出てくる。バスにおけるこうしたシ音は、Agnus (m. 93)におけるシ音の注目すべきカデンツをもたらす。そこでは当時の作曲家は、可能な限り避けるべき苦痛を受け取っている。 シ音はさらに、メロディ的三全音同様、ハーモニーにおいても三全音を発生させる。こうした頻度の多さは、それらが意図されていたことを示している。三和音が完全であってさえ、それらはV-I進行を捨て去ろうとして、もっとも特有なものに変えられる。cantus firmusの入りで、それらはD minor and B minorの間を行きつ戻りつしている。こうした特徴的な進行は、非常に接近したスペースに、対斜(f-f♯)を含んでいる。 旋法に関して、オケゲムの作品に持ち上がるいくつかの複雑な疑問は、Seayによってすでに論議されている。困難さは、以下のような事実からあがっている。オケゲムが、ドーリア旋法の作品にミキソリディア旋法のcantus firmusを導入していると言う事実。 Seayによれば、彼女はこうした組み合わせを、 2つの旋法の間で、自身の特殊な味わいを持つ”over-all mode"として認めることを提案している。オケゲムの音楽が、旋法への強い味わいを持っていることは確かであるが、旋法の組み合わせのトータルの効果が純粋の旋法で理解され得るかどうかは疑問である。彼女は、ティンクトーリスのポリフォニー音楽における旋法の問題の不十分な取り扱いを批判し、一方で、”旋法的和声”の概念を拒絶している。なぜならそれは、オケゲムの音楽への19世紀的発明を適用するようなアナクロニズムだからであろう。 p290 De Natura et Protrietate Tonorumにおいて、ティンクトーリスは、旋法を、ポリフォニー作品の単一声部にのみ適用される排他的メロディの本質と定義している。彼は、彼の定義を、彼がmixtio そして commixtio modiと呼ぶものも含めている。mixtioは、正格、変格旋法の混合に言及し、commixtio modiは、それぞれの旋法の第4,5の性質のさまざまな種類の混合である。 彼の厳格なメロディの概念に一致して、彼は、テノールからポリフォニー作品の旋法を決定している。それらは分離された異なった旋法である。これらの”over-all effect"は、単に同時的使用に対する別の言葉であり、ティンクトーリスにとっては、メロディの本質の組み合わせを残している。それを彼は、compositio ex diversis partibus diversorum tonorum efJectaとして認めている。このcompositioの音楽的結果は、しかし、旋法の概念を超えて、ハーモニーの領域を導いたintervallic combinationsを産生する。 ティンクトーリスはそれゆえ、無定見や問題を避けることを非難されるはずであった。彼は、彼自身の前提を壊すことなしに、旋法の分析を進めることはできなかった。ハーモニーの理論は、存在せず、必要ともされなかった。なぜなら、組み合わせは、音域の用語内では説明され得なかったからである。 こういった理由で、作曲家や当時の理論家たちは、和声進行やカデンツに対しては、まったく経験的な態度を取った。当時の論文は、音程の考慮よりも、いくつかの規則的原理なしで、すべての創造可能なケースのための多数例のやり方によって、決疑的にそれらをリスト化している。 今日の音楽的思考がハーモニーの利害で支配されており、ルネッサンス音楽の初期のハーモニーの手順は、後に魅力的と考えられた注目を浴びた。”over-all mode"と言う用語においてこれらと議論しようとする試みは、それ自身、ハーモニーを伴う偏見の兆候なのである。 ”旋法”という用語を、ハーモニーの注釈からは離れて、保とうとすることを薦めるべきであるように思われる。そして、実際のものとして、”over-all mode"という用語を認めてもよいと思われる。それは、旋法的和声の特殊なタイプなのである。 この旋法的和声は、むろん、19世紀のそれとは区別されなければならない。19世紀のそれは、自律的和声で動き、音階の長短調の調性に類似していた。旋法パターンを、調性の拡大として明らかに証明するものとして。ルネッサンスの旋法的和声は、パート書法そしてそれゆに横のアプローチを反映する音程的組み合わせとともに働く。 p291 オケゲムの音楽における三和音の進行は、調性の方向の欠如において、こうした旋法的和声の完全な例である。デュファイとオケゲム両者は、彼らの音楽の中で、ティンクトーリスによって記述されたやり方において旋法を結びつけている。 しかし両者は、ハーモニーに関しては、非常に異なっている。なぜなら、デュファイは、彼の後期作品において、彼の近代的カデンツのやり方で、初期の調性をかすかに示しているのに対して、オケゲムはそうしたことを避け、パート書法に対して和音を従属させ、あらゆる方面の”旋法”の印象を創造しているからである※。オケゲムの旋法的和声は、彼の旋律的なデザイン、彼のカデンツの忌避、そして彼の対位法の概念と直接、密接な関係がある。それゆえに、それは、彼の一般様式の一部なのである。 ※現在では、デュファイ作といわれたMissa Caputは、作者不明となっているので、オケゲムよりも後期の作曲家の作品である可能性もあり、そうであるとすれば、この曲がオケゲム作のものよりも斬新である理由がつく オケゲムの神聖な音楽は、devotio moderna、”漠然とした、神秘主義的なNeo-Gothic"そして、ゴシック芸術のあらゆる魅力的な豊富さが復活した北部の後期Gothicの開花の恍惚的味わいと、ちょうどよく連関している。 こうした特徴は何か?あるいは、オケゲムは音楽における”神秘”をどのようにマネージメントしたのか? 彼の様式の目だった特徴に戻ってみると、我々は、彼が驚くべき一貫性でもって、作品表現のあらゆる慣習的手段を非難していることを見出す。カデンツ、profiled motives,対称的なフレーズ構造、清澄なパートの関連性、模倣、連続、1つの声部のその他の声部に対する優越性、などなど。 作品のより大きな構造的観点でさえ、こうした結末に貢献している。cantus firmusは、それは構造的な声部ではあるが、Caputミサ曲においては、バスに隠れており、直接的認識を超えて、装飾されている。カノンもまた、もっとも合理的音楽の組織の手段であるのだが、オケゲムによって、特に非合理的なものとして利用されている。彼が、計量的カノンとしてのMissa Prolationumにおいて、それを導入したことは象徴的であり、言わば、最低限の覚知し得る形式である。 p292 彼の音楽は、リスナーがその大きな構造単位を掴み、それらを内心で統合することが可能であろう特徴を遠ざけている。私たちは音楽において、合理的なorganizationの拒否をずっとしていた。そして、それが、我々が音楽の神秘主義について話すことを正当化されていた理由である。 オケゲムの作曲作法は、合理的に分析され得るが、その効果はおそらく非合理的である。 後期ゴシック大聖堂のきらびやかな様式のように、構造的な柱や支持は、繊細でエンドレスの分枝において絡み合い、分岐する肋ろく材の無限のネットワークの下に隠されている。オケゲムのミサ曲において、cantus firmusは、終わりのない、不合理な流れによってカバーされている。 重要なことは、合理的な発言の欠如が、否定的な用語によって記述され得ることである。そうした用語は、神秘主義のdocta ignorantia(無知の知)において、時代の”否定的な哲学”においてもっとも重要に思える。そうした神秘主義は、Cusanus(そのdevotio moderna(新しい信仰)においてよく知られている)の最後の偉大な概念を見出した。 オケゲムの様式のあまり知られていない特徴は、これまでの世代を当惑させてきた。今日我々は、こうしたことの妥当性を認めるより良いところにいる。ある種の近代音楽における発展によって。特に、ハーモニーにおける革命や、いわゆる”無主題”様式のために。 これらは神秘主義とは無関係であるが、我々の理解や見透しを深くした。そして、オケゲムの作品の奇妙な特徴が、欠乏状態からはかけ離れていると言う事実に我々を向かわせた。 オケゲムがどのように彼の制限された素材を、永久的かつ深い音楽的織物に織り込むことができたかは、常に、驚愕と賞賛の的となっている。 循環ミサ曲 cantus firmus Caputミサ曲 cantus figuratus canlus mensuratus cantus planus |