| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE
MUSIC�V |
| 5. THE CAPUT
MELISMA AS MASS TENOR ��256 �@�v���C���`�����g�́A�~�T�Ȃ̃e�m�[���ւ̓]���́A ���Y���ƃ����f�B�̗����Ɋւ��Ďؗp���ꂽ�f�ނ̂����̏C�����܂�ł���B�Ƃ�킯�Acantus planus�́Acanlus mensuratus�ւƈڂ�B���Ȃ킿�A�͂�����Ƃ����v�ʃ��Y���������f�B�ƂȂ�B ��ȉƂ�2�̑I�����ɒ��ʂ���B�����ȈӖ��ɂ����āA�d������cantus firmus�Ɠ����������ɂ����Ďؗp�����`�����g�������A�����Č����ɂ͌v�ʉ�����Ă��Ȃ��v���C���`�����g�̃��Y���̌��ʂ����|���t�H�j�[�������A���邢�́A�v���C���`�����g�Ƃ͉���W�Ȃ��A�P�Ƀ|���t�H�j�[�ݒ�ɂ���Č��肳�ꂽ�A���g�őI���Y���p�^�[�������ɓ��ꍞ�ނ��ł��邪�A�R��Caput�~�T�Ȃ��K�p����Ă���̂́A��҂ł���B �����f�B�[�Ɋւ��ẮA2�̉\������ʂ��邱�Ƃ��ł���B��ȉƂ́A�ؗp���������f�B�d���Ă����ω��������ɂ������A������A�p���t���[�Y���ꂠ�邢�̓��f�B�t�@�C���ꂽ���ۂ�cantus figuratus�ւƕϊ����邩�A�ł���B����́A�J�f���c�ł̂������̑�������A���܁A���̃����f�B�[�̉ߒ������ł�����\��������g���}������у����f�B�̓ˏo���ɂ܂ŋy�ԁB��҂̏ꍇ�A���Y���̓����f�B�̈����Ɠ��l�A���R�łȂ���Ȃ�Ȃ��B������Caput�~�T�Ȃɂ����ẮA�ؗp���ꂽ�f�ނ́A���̂܂܃����f�B�Ƃ��Ďc��A���̂��߂ɁA���Y���ɂ����鎩�R�́A�����f�B�Ɋւ��錵���Ȉ����ɂ���āA�ނ荇�����ƂɂȂ�B P257 �@Caput�e�m�[���̋c�_�́A3�Ȃ̂����ł����Ƃ��Â�Dufay�ɂ��~�T�ȂŎn�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����Dufay�����āA�A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�̑I���𑣂������Ƃ��́A�킩��Ȃ��B����ɂ́A�ނ��ؗp�����T��f�ނ��킩��Ȃ��B �f���t�@�C���~�T�Ȃ���Ȃ����Ƃ��A�ނ́A�J���u���[�吹���̎Q������ŁA�������́A�J���u���[�����15���I��Gradual�̎����������邱�Ƃ����҂��Ă������낤�B�c�O�Ȃ���A���̂悤�ȓT��W�͏o�ł���Ă��Ȃ��B�B��̃J���u���[��missal�́A�A���e�B�t�H�����܂܂��A����ɁA�S�̂Ƃ��āA�p���̓T��ɏ]���Ă���B ���̑��̃J���u���[��Gradual�Ƃ̔�r�́A�����ɂ͂Ȃ肻���ɂȂ��B�Ȃ��Ȃ�A�f���t�@�C�̃~�T�Ȃ̃e�m�[���́A�A���e�B�t�H���̒��̒m��ꂽ�t�����X�łƂ͈قȂ��Ă��邩��ł���B �����ADufay������ځA�ԐړI�ɃZ�C�����T�炩��ؗp�����ɈႢ�Ȃ��Z�C�����łɂ��Ă̏ڍׂɂ́A���m�ȍ��ӂ�����B�Z�C�����łւ̈ˑ����́A�R�̉����ɂ���Đ��������B �@�J���u���[�ł̓T��́A�Z�C�����T��ɂ���ĉe�����Ă��� �A�f���t�@�C�́Acantus firmus�ځA�Z�C�����u�b�N����̗p�����B�����炭����́A��i���p���Ɉϑ����ꂽ����ł��� �B�f���t�@�C�́A�ނ̃e�m�[����������A���łɑ��݂��Ă�����i�A�p���l��ȉƂɂ���č�Ȃ��ꂽ��菉����Caput�~�T�Ȃ���̗p�����B����䂦�A�I�P�Q����I�u���q�g�Ɠ��������ŁA�p�����f�����ؗp�����B�Ō�̉����́A��Ղ̂悤�ɁA�n�l�ɂ����Ă̂��ꂽ�p����Caput�~�T�Ȃ̑��݂����肵�Ă��邪�A���݂ł͎����Ă�����̂ł���B�v���g�^�C�v�����ۂɑ��݂��Ă��邩�ۂ��͏ؖ����꓾�Ȃ����A����͔��Ɏ��R�Ƀe�m�[���̃Z�C�����ł�������ADufay�̎d���ɂ�����p���̉e���̓���̒�����������ł��낤�B �����ԂɁA�f���t�@�C�̗l���I���W�́A��ʓI�ɂ́A�p���̘Z�x�a���l�����猈��I�Ȏh�������B���ɁA�_���X�^�u���iDunstable�j�̔ċ��a�ipanconsonant�j�X�^�C���ł���B���̉p���̉e���͂́A�ނ̏����̍�i��Martin le Franc�̏،��ŁA�͂�����Ɨ��t�����Ă���B�ނ́AChampion des Dames�ɂ����āA���炩�ɁA�p���ւ̍�ȉƂ̈ˑ����ɂ��āA���y���Ă���B ��258 �������������́A�f���t�@�C�̏����̍��ɑ����Ă��邪�ACaput�~�T�Ȃ́A�p���̉e���̕ʂ̌`���ɂ����āA��X�ɋ߂����B���̉e���́A�ނ̌���Ɋ֘A���Ă���̂ŁA�C���O�����h�ւ̔ނ́i�O���́j�|�p�I�ˑ����]�������Ƃ��ɂ́A�ʏ�l������Ă��Ȃ��B ��X�͂Ƃ�킯�A�z�~�T�Ȃ��̂��̂Ɍ��y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�e�m�[���~�T�Ȃ��̗p����ɂ�����A�f���t�@�C�́A�p����ȉƂ��c�������ɏ]�����Bcantus firmus�����Ƃ��p���N���ł͂Ȃ������Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ͎����ł��낤�B �p���̉e���̕ʂ̑��ʂ́ACredo�̃e�L�X�g�̂��镔���̏ȗ��Ɍ��Ă邱�Ƃ������Ă���B����́A�p���̃~�T�ȍ�Ȃ̓����ł���悤�Ɍ����邵�A���܂��T��I���ʂ���͐�������Ȃ��B �f���t�@�C�́AEt in sPiritum sanctum to Confiteor�C���邢�� Tertia die ����Et ascendit�A�ɂ����Ẵp�b�Z�[�W���ȗ������B��X�́A���������Z�N�V�����͂Ƃɂ����A�g�����g�ʖ{�ɂ͂߂����Ɍ���Ȃ��Ƃ������Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B �Ҏ[�҂͌����������t��₤���A�M���b�v�͎c��B�������AEt resurrexIt (m. 151�j�̎n�܂�ŁA���t�͐����Ԃŕ��������ׂ��ł���A���̂��߂ɁA�A���g�ƃo�X�����������p�b�Z�[�W�����ׂ��ł���B���m�ɂ́A���������A�����W�́A�I�P�Q���̃~�T�Ȃɂ����Ă������悤�ȂƂ���Ō��o�����B����́A��ʓI�ɁA���t�̕��z�ɂ����āA�f���t�@�C�̍�i�𒉎��ɖ͕킵�Ă���B �����������Ƃ���������A�f���t�@�C�ƃI�P�Q���́A�ȗ��ł͂Ȃ��A�P�Ƀe�L�X�g��telescope�ň�v���Ă���̂ł��낤�B����́A�嗤�̃~�T�Ȃ̐ݒ�ɂ����Ă����p���ɂ����Ĕ��ɂ����Ώo������B �@�p���̉e���͂܂��AStrunk�����ɂ���Ă��������ꂽ�B�����A�f���t�@�C��Kyrie�̃g���[�v�X�ł���Deus creator omnium���g�p���Ă���B����́A�g���[�v�X�����ꂽSarum Gradual�ɂ����āA�s�ϓI�ɏo�������p���l�D�݂̂��̂ł���B90 90�@����A�z�~�T�ɂ�����|���t�H�j�[��Kyrie�̑}���́A�p�����y�̓T�^�ł͂Ȃ� ����܂ŋc�_���ꂽ�p���̓����́A����I�ȉp����Caput�~�T�ȂɗR������ł��낤�B�����āAcantus firmus�Ɋ�Â��A�ނ̍ŏ��̏z�~�T�Ȃł��邩������Ȃ����̂̂��߂����̃e�m�[���̎ؗp�ɂ����āADufay�͋��炭�A���̗l�����p��̋N���ł��邱�Ƃ�F�߂Ă���B �m���ɁA����͉����ł���B�Ȃ��Ȃ�A�p����Caput�~�T���̒��ڂ̍��Ղ͂Ȃ�����ł���B�����I�ȖړI�̂��߂ɁA��X�͂��ꂩ��Dufay�̍�i�����̂��̂Ƃ��čl���邪�Acantus firmus�̑I���Ƒ���͂����炭�A�p���̍�ȉƂ̍�i�f���Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B p259 �@�~�T�Ȃ��A�p���N���́A�ʏ�Ƃ͈قȂ�cantus firmus�Ɋ�Â��Ă���Ƃ��������́A���ꂪcantus figuratus�ɕς������قǂɂ́A���܂�d�v�ł͂Ȃ��B�S�̂�cantus firmus�́A�e�m�[�������Ƃ��āA���炩�ɂȂ�BEx.4�ł݂���悤�ɁB ���ꂼ��̊y�͂ŁA�����f�B�́gdouble cursus�h�ƌĂ��悤�ɁAstate��2��J��Ԃ��B�ŏ���perfect time(statement A)�ŁA���ꂩ��A���Y����ς��āAimperfect time (statement B)�ŁB�Q��statement�́A�����f�B����ӏ��قȂ�B�t���[�Y���̌J��Ԃ��́AcursusB�ɂ����Ă̂݁A�o������B2��statement�̉����́AEx.4�Ɏ�����邪�A�����͍��킹�Ă���B�e�m�[���̓Z�C�����ł̃����f�B�Ɉ�v���Ă���i��P�j�B�Q�������lj�����Ă���iAsterisk�ɂ���Ď�����Ă���j�B�h ���̓t���[�Y���̍ŏ������ŁAA40��B44�ɕt����A�������Ō㕔����A69 ��B78�ɂ����Ă���B �h���͂Ȃ��ŁA�����̃J�f���c�ɓ��B���邽�߂ɕK�v�ł���B�����̕��́A�f���t�@�C���P��cantus firmus�̌��@�𐳂������Ƃ͖��炩�ł���B�v���C���`�����g�̍Ō�̃V�\�\�́A�X�e���I�^�C�v�̃e�m�[���̃J�f���c�̎g�p�|�Ō�̉��~�X�e�b�v�A����͓����̗玮�ɐ�ΓI�ɂ������������́|�ƂȂ�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���B ��ȉƂ��m���Ă��Ȃ��`�����g�̃��@���A���g����ؗp�������Ƃ��_�����邱�Ƃ��낤�B�������������́A���蓾�Ȃ����ƂƂ��āA�r�������B�Ȃ��Ȃ�A�}�����ꂽ���͈�x�����������ꂸ�A�����ł̓J�f���c���K�v�ł���A�\����̃J�f���c�������A�v���C���`�����g���K�v�ȃX�e�b�v�I�i�s����������悤�������t���[�Y�̌J��Ԃ����Ȃ�����ł���B 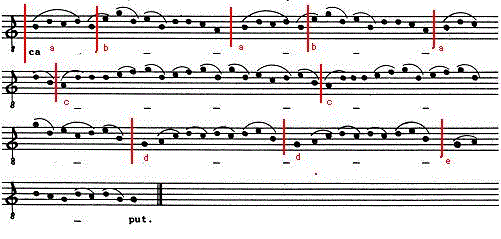 �f���t�@�C�~�T�J�v�g�� 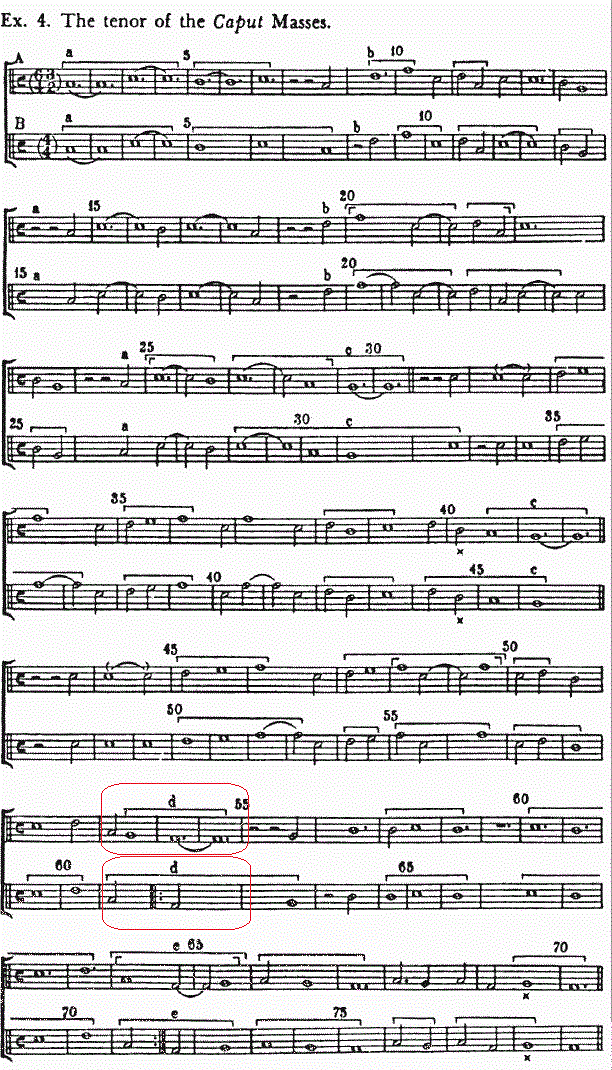 p261 ���Ƃ̃v���C���`�����g���h�����܂�ł����Ƃ�����A�t���[�Y���̂��̑��̉������ׂĂ�2��J��Ԃ��ꂽ���Ƃł��낤�B����䂦�A�Q�̊J�����J�f���c�̂��߂ɂ������ꂽ�Ƃ������_������Ȃ̂ł���B����ȊO���v���C���\���O�́A���ꂪ�T��̃\�[�X�Ō�����悤�ɁA�����ȃ����f�B�ω����k�����킸�Ɍ����B �@���������ώ@�́Acantus firmus�ɂ��Ă�Schegar'�̕��͂��ɂ��Ă��܂��B�ނ́Acantus firmus���A�������̃����f�B�́h�ω��h�Ɓh�����h����\������Ă���A�Ƃ��Ă���B����͔ނ̌����h��b�I�`���h�ł���B �ނ̃A�i���[�[�́A�\�ߗ\�z���ꂽ�ψق̍l���Ɋ�b��u���Ă���B�����́A�x�[�g�[�x���̌�����y�l�d�t�Ȃɂ͓��Ă͂܂邪�A15���I�̉��y�ɂ͓K�p�ł��Ȃ��B���̂悤�Ȕ���j�I�Ȃ����Ŏ咣���ꂽ�h���ʁh�́A�T���āA�_���ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�{���I�Ȃ����܂�����������̂́Acantus firmus�̓�������������ꍇ�A����I�ȕ��@�ł�������x������悤�ɂ��邩��ł���B �@A��B�̓����f�B�͌����ɓ����ł͂��邪�A���Y���z���{�I�ɈقȂ��Ă���B����͒P�ɁAperfect����imperfect time�ւ̕ω��̎��R�ȘA���ł͂Ȃ��A��ȉƂɂ���ďn�l���ꂽ�f�U�C���ł���ׂ��ł���B �v���C���\���O��canlus mensuratus�ɕς��邱�Ƃɂ����āA�f���t�@�C�͊��S�ɁA���Ƃ��Ƃ̘A�����̔z��������B���Ƃ��Ƃ̃t���[�Y�̕��������l�ɁB���Ƃ���X���A�Z�C�����̃��@���G�[�V�����̂��Ƃ��Ƃ̘A����������Ȃ��Ă��A��ȉƂ��������������Ƃ͏ؖ�������B�Ȃ��Ȃ�A�����͂Q��statements�ɂ����ē���ł͂Ȃ�����ł���B �������A�������ނɏd�v�ł���A���ӂ����������Ƃ��낤�B�v���C���\���O�̃I���W�i���ȃt���[�Y�I�����̖����́A����ɖڗ��BEx.1�̃v���C���\���O�̃t���[�Y��������́AEx.4�ł̌v�ʔł։�����ꂽ���A���ꂪ���͂�K�����Ȃ����Ƃ͖��炩�ŁA�Q��statements�̓����ꏊ�̃J�f���c�́A��v���Ȃ��B�������������ł́A�J�f���c�̉������C�ӂɑI��邱�Ƃ��厖�ł���B���Ƃ��A�t���[�Ya�́A���ꂼ��A���Ƃ��̏I���ɍ����B ����Ȃ鑽�l���́A�t���[�Y���̈����ɂ���B����́AA29�|30��B�R�P�|�R�Q���ׂ�Č���A�킩�邾�낤�B���̓����p�b�Z�[�W�́A�ŏ��̓t���J�f���c�ւƂȂ��Ă���A�����āA���̎��ɂ́A���̂܂ܑ����Z�N�V�����Ƃ��Ď�舵���Ă���B������statements�́A���ځA�v���C���\���O�̃t���[�Y�����ɏo��B�ǂ���̏ꍇ���A�t���[�Y���̍ŏ��́h�O�Ɂh�J�f���c���Ăэ��ށB�t���[�Y�́A�A����a-d'�Ŏn�܂�A��ȉƂ́A�ŏ��̉������A���̑O�̃t���[�Y�̍Ō�ɂ����āA�Q�ɂ킯�邱�Ƃ����߂���Ă��Ȃ��B p262 �@cantus firmus�̎��R�Ń��Y���I��cursus�̔�r�́ACaput�̃e�m�[�����A�����Ɋւ��ĂƂƂ��ɁA�v���C���\���O�Ɉˑ����Ă��邪�A���̘A������t���[�Y�A���Y���p�^�[���ɂ͓��ɒ��ӂ��Ă��Ȃ������𖾂炩�ɂ����B ���̓_�́Acantus firmus�ƃv���C���`�����g�̃��Y���̊Ԃ�������ꂽ�U��̗ގ����̊ϓ_���狭������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �v���C���\���O��cantus firmus�Ƃ��ē����悤�ɂ��邽�߂ɍ�蒼���ꂽ���Ƃ́A15���I�̉��y�ɂ����Ă͗�O�Ƃ������͂ނ���A�K���Ȃ̂ł����B���̂��Ƃ́ADufay��Caput�~�T�Ȃ����łȂ��A�ނ�Masses on Ave regina celoTum and Ecce ancill�ɂ���Ă��m�F�ł���B���l�Ȃ��Ƃ́ABusnois�C Regis�C Okeghem�C Obrecht�C Josquin,�Cand other�ɂ������i�ł��A�^���ł���B ��r�I�����̍�i�ɂ����ẮA�v���C���\���O�́A�����ʂ�A���ꂼ��̉������������_�ɂ����āAcantus planus�Ƃ��ĂƂǂ܂�B����ɂ����A����̓��Y���p�^�[����A�����ɍ��x�Ɍʉ����������f�B�̒O���i���ꂼ��̊y�͂��z����ɂ͎����Ă��Ȃ��A�����j���ɂ���ďC������Ă���B cantus firmus�́A�P���A��ȉƂ����R�ɔގ��g�̑z����y�͂̋}���ɂ��������Ď��R�Ɏn�߂�ꂽ��Ȃ�����Ƃ��Ďg��ꂽ�B�p�ނƍ������Ƃ̑�����`���������A�A�ނ炪�x���������̌`�ɃJ�b�g���ꂽ�悤�ɁA cantus firmus�́A���y�\���̃t���[�����[�N���m�����Ă��邪�������A�ɂ�������炸�A���̌`���́A���ꂪ����ɂ����i����`������Ă���B ��ȉƂ�cantus firmus�ɉۂ����Ɠ��̃��Y���́A��Ȃ̉ߒ��ɂ��Ă̐��������Ƃ����������`�������B�����Ď��ہA�ؗp�����f�ނ��{���̍\�������d�v�Ȃ��̂ł������B�������A��҂ւ̊S�̌��@�́A��Ƃ��āA�v���C���\���O�ɑ��ē��Ă͂܂�B�������|���t�H�j�[�Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă����ꍇ�A���Ƃ��Ƃ̃��Y���͈�ʓI�ɂ��̂܂܂Ŏc���ꂽ�B�������A��҂̏ꍇ�ł����A�V�����\���̃e�m�[�����C�ӂɏ\���ɁA��舵���Ă����B p263 �@Caput�̃e�m�[���̃��Y���`���́A�����炭��Ȏ҂����ʂ����a����Έʖ@�̌`�Ō��肳�ꂽ�B��x�m�������ƁAcantus firmus�̃��Y���͕ς��Ȃ��B���鎞�ɂ͕ێ�����A����Ƃ��ɂ͕�������Č�����A�����≹���̋L���@�̑����̑��l���������āA�e�m�[���͂��ꂼ��̊y�͂ɁA�������Y�����^�ŏo������B ����������ƁA�C�\���Y���I�e�m�[���@�^���A�́A�傫�ȕ������߂�悤�ɂȂ�B���Ȃ킿�A�y�͑S�̂ɁB�f���t�@�C���S���������B��̎��R�x�́A�s�ς̃e�m�[���̎�Z�N�V�����������x����t���[�Y�A�����x���̍폜�̋c�_�ł���B �������C�\���Y���~�T�ɂ����āA��������interruption�ł����A�ނ��A���Y���p�^�[���ɂ����Č��߂���B�^���A�ɂ�����C�ӂȃ��Y���p�^�[����mapping out����Â��`���́A�~�T�̃e�m�[���̃��Y���z��ɂ����āA�����Ƃ������c���Ă����B�ŗL�̃C�\���Y�����e�b�g�������ȗ����������āA�C�\���Y���̎菇�̎��Ղ�15���I�I���ɐ����c���Ă������Ƃ́A�����A�z�~�T�Ȃ̃e�m�[���ɂ����Ăł���B �@�e�m�[���Z�N�V������Caput�~�T�Ȃɖ߂鐔�w�I���m���́A���ꎩ�g�݂̂ł͂Ȃ��A���ɁA�R�̃~�T�Ȃ̓Ɨ��Ɋւ��āA�d�v�ł���B����́A���_�Ƃ��āA�P���ȃp�^�[���̑��݂��ؖ����Ă���B �I�P�Q���́A�ނ̐�s�҂̃f���t�@�C��I�u���q�g�̍�i�ɋ߂��������B2�l�̂��Ⴂ��ȉƂ����́Acantus firmus�̃����f�B�����łȂ��A���̐��m�ȃ��Y���`����t���[�Y�\���܂ň����p�����B�ނ�́A�e�L�X�g�ɁA�f���t�@�C�Ɠ��������ŁA�荞�B�����āA���ꂼ��̊y�͂̎�v�ȕ����ɌŎ������B�ꌾ�Ō����A�f���t�@�C�̃~�T�Ȃ́A��̍�i�̂��߂̃��f���ƒ���������B ���������_�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�f���t�@�C��cantus firmus���A���̑��̂Q�̃~�T�ȂƁA���߂��ƂɁA���邢�͉������Ƃɔ�ׂĂ݂�K�v���|�C���g�ƂȂ�B�e�[�u���R�ɂ́A�R�̃e�m�[���̏ڍׂȃA�i���[�[������B�����́A�ȉ��̓_���킩��悤�ɂȂ��Ă���B �@���q�L�� �AstatementsA��B�̏��ߐ� �B�e�m�[���Z�N�V�����̑O�A���Ԃ̑}�����ꂽ�x���̐��i�J�b�R�Ŏ����ꂽbreves�̐��j �C�����ނ�I�u���q�g���Z�N�V�����̏I���ɕt������������ �e�[�u���ɂ����āA���Y���ƃ����f�B�̓��ꐫ�́A�d���D�S�ɂ��鏬�ߔԍ��Ɠ���ł���B���Ƃ��A�R�̃~�T�Ȃ̃N���h�ɂ�����`1�|30�́A���ꂼ��̊y�͂��Acantus firmus�̓���̃Z�N�V�����Ɋ�b��u�����Ƃ��Ӗ����Ă���B���Ȃ킿�AA 1-30 of Ex. 4�Z�N�V�����ł���B ��i�̂������̓_�ŁA���ۂ̏��ߔԍ��͈قȂ��Ă��邩������Ȃ��B����́A�x�������ꂼ��̍�i�̍ŏ��ŕω����邽�߂ł���B�e�m�[���̓��ꐫ�́A��b�I�ł��W���Ƃ��Ĉ�����A������邱�Ƃ��ł���B�����t��������dminnuition�������Ă���B Table3 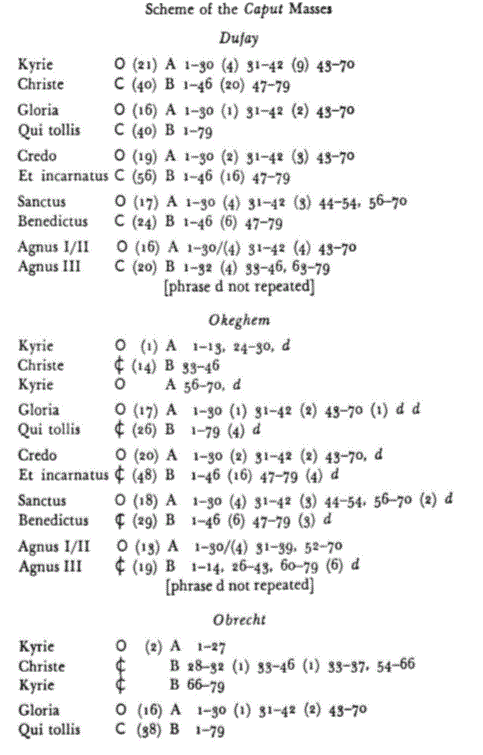 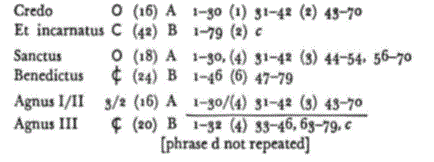 ��265 �e�[�u���ɂ����āA���Y���ƃ����f�B�̓��ꐫ�́A���ߐ��̓��ꐫ�ɂ���āA��S���Q�Ƃ��āA���ڎ������B���Ƃ��R�̃~�T�Ȃ�Credo��A1�|30�́A���ꂼ��̊y�͂��A��S�ł�A1�|30��cantus firmus ����b�ɂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B��i�̂��ꂼ��ɂ����āA���ۂ̏��ߐ��͈قȂ��Ă���B����́A���ꂼ��̍�i�̖`���ł̋x�����ς�邩��ł���B�e�m�[���̓��ꐫ�́A��{�̔ł��Q�Ƃ̕W���Ƃ��Ă̂ݎ���邱�ƂŎ������B �@�����ŁA�X�̃~�T�Ȃ̃e�m�[���ɖ߂��Ă݂悤�B�ǂ�قǂ��ꂼ�ꂪ�قȂ��Ă��邩�����邽�߂ɁB���ꂼ��́A�����f�B�ƃ��Y���ɂ����ē���ł���̂ŁA����́A�����A�Z�N�V�����̃O���[�v������A�}�����ꂽ�x���ł̂����B �e�[�u���R�ł́A�����́A�R�̃~�T�Ȃ��ׂĂɂ����ē����ł��邱�Ƃ��킩��B�f���t�@�C�́Astatement�`���R�̃Z�N�V�����ɂ킯�A���ꂼ��͋x���ɂ���Ė��ĉ�����Ă���Bstatement�a�͂Q�ɕ�������B �����́A������肩���ŁA�قƂ�ǂ��ׂĂ̊y�͂ɂ����Đ�����B�x���͕ω����A���ɂ͍폜���������BQui tollis�ɂ�����悤�ɁB. Agnus III�́A�e�m�[���̃C�\���Y���p�^�[����ʂ���break�����B��̊y�͂ł���B����́A�a47�|62���ȗ����A����ɁA�t���[�Y�����J��Ԃ��B�d���D�S�ɂ����Ă�����g���[�X���邱�ƂŁA��X�́A����炪�A�t���[�Y�̌J��Ԃ��݂̂ō\������Ă��邱�Ƃ����o���B �f���t�@�C��ނ̉p���̐��҂́A�Z���e�L�X�g�ɍ��킹�邽�߂ɁAcantus firmus���k�������B�����Ă܂��A�ނ́A�C�ӂɂ��̍폜���s���������łȂ��A�P���Ƀ��s�[�g�����炵���B���̂��߂ɁA�����f�B�͂���ɁA�S�̓I�ɑ��݂��邱�ƂƂȂ����B �����������Ƃ́A��ȉƂ������X�}�̓����\���ɋC�Â��Ă������Ƃ��ؖ����Ă���B�����āA�ނ̃t���[�Y�����́A���m�ɂ́A�`�����g�̃t���[�Y�Ƃ͈�v���Ă��Ȃ��B�ނ́A���ׂĂ̖{���I�ȊԊu�����̂܂c���A�����N�Q���邱�ƂȂ��A�����f�B�[��Z������悤�ɂ��Ă���B �r�������������̂��s�K���ȓ����͂��łɋL�q���ꂽ���A�`�R�T�Ƃ`�T�T�������Ă���B���������M���b�v�́A���ꎩ�g�͂��܂�d�v�ł͂Ȃ����A���̑��̂Q�̃~�T�ȂƂ̊W�ɂ����ẮA�d�v�Ȃ̂ł���B ��266 �@Caput�����X�}�̌��T�Ɋւ������A���Y���\���ɐӔC�����ȉƂ����܂��Ă��Ȃ����Ƃ͒m���Ă��Ȃ������B���܂�Acantus firmus�́A�C�ӂ̃��Y���̃v���C���\���O�Ƃ��ĔF�߂���悤�j�A�Ȃ��Ă���B��̃~�T�Ȃɂ����铯�����Y���̏o�����A�e�m�[���̖{���̓����ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�ނ���A�I�P�Q���ƃI�u���q�g���A���̃��Y���𒉎��ɕۑ����A���̑I���ɂ����Ă̂ݕω������A�Ԃ̋x���̐���ς��Ȃ���A�f���t�@�C����\���I�������ؗp�������Ƃ��A�ؖ�����Ă���B ���_�I�ɁA�I�P�Q���ƃI�u���q�g�́A�f���t�@�C�̃��f���ɏ]���`���͂Ȃ��A�قȂ������Y���^�ɂ����āA�v���C���\���O�𓊎˂��邱�Ƃ��ł����B�������A���l�T���X���y�̃��f����̍�i�̓`�����Ȃ̌���I�����ƂƂ��ɁA�f���t�@�C�̃~�T�Ȃ̂܂��ɂ��̑��݂��A�Ⴂ��ȉƂ����ɁA����cantus firmus�Ń~�T�Ȃ��������Ƃ𑣐i�������Ƃ́A�������Ƃł͂Ȃ��B�����āAcantus firmus�̂悤���h���Ђ̂��鐺���h�ɗ��邱�Ƃ́A���̎����������F�߂邱�ƂɂȂ�B �I�P�Q���ƃI�u���q�g�́ACaput�����f�B�[���A���łɑ��݂����i����S�̓I�Ɏ�����A�T��I�\�[�X����̃v���C���\���O�Ƃ��ẮA�����͂��Ȃ������B����̓f���t�@�C�ɂ����l�ł͂������A2�l�̎Ⴂ��ȉƂ����̏ꍇ�ɂ��m���Ȃ��ƂȂ̂ł���B �@��̍�i�̃e�m�[�����f���t�@�C�̂���Ɣ�r�����Ȃ���A�����悤�ȃ��Y���ɂ�������炸�A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA�`���̔��肪�ɂݎn�߂��m���Ȉ��邱�Ƃ����o��������Ƃł��낤�B �I�P�Q���́A�I�u���q�g�����A���Ђ��鐺���icantus firmus�j�ɋ߂Â����Ƃ��Ă���B���̈ӌ��ɑ��ẮA���O�̑����̏؋�������B�I�P�Q���̓I�u���q�g�Ƃ͈قȂ�A�e�m�[���̋L���ɂ����āA�{���I�ɕs�ςł���ؗp���������̉����L���Ɠ��l���A�������c���Ă���B�I�P�Q�����A�f���t�@�C�̃e�m�[�����o�X�ɒu���Ă���B�����[���h�J�m���h�̎�i�����Ȃ���B����́A�I�N�^�[�u�Ⴂcantus firmus���I���W�i���ȃA���g�L���ɉ̎�����̂ł���B���Ȃ��Ƃ��A�o�X�L���̉����Ő�������������A�����ꂽ�w����S���g��Ȃ��悤�ɂ���̂́A�ȒP�Ȃ��Ƃł��������낤�B �I�P�P�����A���̍�i�ł͂��Ȃ�d�v�Ȗ������ʂ����Ă����f�o�C�X�ɗ������̂͂Ȃ��ł��낤���H�@���̋^��ɑ���B��̓����́A�ȉ��ł���B�ނ́A���Ƃ��Ƃ̓����I�ȃA���g�L����ۂ��A�����f�B�[�͎��ۂɂ̓o�X�̉���Ɉڒ�����Ă��邪�A���́h�O�ςɁh�ω��͂Ȃ��B���������āA�J�m���͌��O�Ƃ��Ă͂悯���Ȃ��̂ŁA�e�m�[������i�S�̂Ƃ����ؗp���ꂽ���Ƃ����������Ȏ�i�ł����Ȃ��B �o�Q�U�V�@�@ �@�h�J�m���I�ȁh�ڒ��͂Ƃ������A�e�m�[���͓����⒇��̋x���A�J�f���c�ɉ�����ꂽ������statement B�̋L�� Gloria�CCredo�C Sanctu���ɂ������e�m�[���Z�N�V�����̈�ʓI�z��́A���ꂼ��̒P��ȓ��L���ɂ����āA�I���W�i���Ȃ��̂��d�ɂ��邱�Ƃł���BQui tollis�́A���ɃT�u��������邱�ƂȂ��A��������B�����āAEt Incarnatus�CPleni sunt�COsanna�̃Z�N�V�����́A���m�ɓ����ꏊ��fall����BSanctus���f���t�@�C��Sanctus�̂������ȕs�K�����iA43,55�̍폜�j��ۂ��Ă���̂́A���ɋ����[���B�����������ׂȌX���ɑ���������̂́A���y�I�d�v���͓��ɂȂ����A���R�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B�I�P�Q�����A�����������ꂪ�Œ肳�ꂽ���̂̂悤�ɁAcantus firmus��1���M�ʂ��Ȃ������̂͌���I�ɏؖ�����Ă��邪�A����͊y�͂���y�͂ւƈ����p����A�P���ɁA�ނ�����i����悤�ɁA�e�m�[����M�ʂ��Ă���B����́A��X�ɁA���l�b�T���X���y�ɂ����čs���Ă����ؗp�̌o���I�����ւ̓��@�𖾂炩�ɂ���B �@Kyrie��Agnus�́A���̂܂܂̌`�ɂ����Ă̓e�m�[�����Y�����Ȃ��B�����ŃI�P�Q���́A�f���t�@�C�̂悤�ɁA�Z�N�V������I�����A�v���[�������ŁAcantus firmus��Z�����Ă���BKyrie�ɂ����ẮAcantus firmus�́A��x�����̑��݂ł���A�����X�}�̓����̌J��Ԃ��͏ȗ�����Ă���B����́ATable�R�̏��ߐ��ɂ����Č�����B����Ȃ镡�G�����A�ނ�statementA��B��g�ݍ��킹���Ƃ����ƌ����������猻���B�t���[�Yabacde�́A���������ԂŌ����̂����A�t���[�Y����statementB�ɑ����A���̑����ׂĂ�statementA�ɑ����Ă���B�t���[�Y�����̑I���ɂ����āA�I�P�Q���̓f���t�@�C�ɍēx�\�Ȍ���A�]���Ă���B���Ƃ��AChriste�̃t���[�Y��B33-46��������\������A�f���t�@�C���ނ�AgnusIII�ŊȌ��������̂����m�ɓ������ߐ��ł���B p268 cantus firmus�̓I�P�Q����Agnus�ɂ����Ă��Z���Ȃ��Ă��邪�AKyrie�ɂ�������͏d��ł͂Ȃ��B�����f�B�͎��ۂɂ͓�x�ł��邪�A���x�́A�ʏ�͌J��Ԃ����t���[�Y�̏ȗ����B���������Z�����́A�I�P�Q�����A�ނ�Caput�̃����X�}�ڃv���C���`�����g������p���Ȃ������ɂ�������炸�A���̓����\�����\���ӎ����A�����Ĕނ��̗p���������f�B�̃G�b�Z���X���A�j�Ȃ��悤���Ӑ[���������Ƃɋ^�����c���Ȃ��B �@��X����L�̔�r����ސ����������Ƃ��d�v�Ȍ��_���A�I�P�Q����cantus firmus�ɂ́A�f���t�@�C�֖߂�Ȃ��悤�Ȃ����ꏬ�߂��Ȃ��A�Ƃ��������ł���B�����f�B�̃��@���A���g�Ƃ��ĕ\�ʓI�Ȋώ@�҂����炩�ɂȂ���̂́A�I���Ƒg�ݍ��킹�̌��ʂł���Ɣ������邱�Ƃł���B ���������ώ@�́A�e�m�[���̌��T�����肳��邩����Ȃ����Ɋւ�炸�A�Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A����́A�e�m�[���̉�����Y���݂̂ɊS�����邩��ł���BDenkmale���ɂ�����ނ̃e�m�[���̕��͂ɂ����āASchegar�́A���̌���I�ȓ_��������B�����āA���������āA�ނ́A�t���[�YC6���A�I�P�Q���Ɠ��́h�ψفh�ł���Ƃ������̂Ƃ��āA���X�g�������B����͎��ےP�ɁA�f���t�@�C��B33-43��60-62�̑g�ݍ��킹�ɉ߂��Ȃ������B �����������͂̃~�X�ɂ��A���̑��̊w�҂�́A���l�ɁA�f���t�@�C�ɑ���I�P�Q���̓z��I�ˑ��ɒ��ڂ��邱�ƂɎ��s�����B�����āA���������Z�]�́A�����ƂƂ��ɁA�ψق���BGombosi�́A�e�m�[�������ꂼ��̊y�͂ň�x��������Ȃ��A�ƌ����ă~�X�����Ă���B����́AKyrie�ɂ����Ă̂݁A�������BVan den Borren�͌���āA�e�m�[���̃��Y���́h���R�h�ł���ƍl���Ă����B�����āAPirro�͌���āA�Ō��Agnus�̓e�m�[�����htout entier�i�S�̓I�Ɂj"�܂�ł���A�Ǝ咣���Ă���B �@�e�m�[���̔�r�́A�~�T�Ȃ̎��n��I�A���ɂ��Ă��ʂ̏d�v�Ȍ��_��ۏ���B��X�́A�f���t�@�C��Caput�~�T�Ȃ�1463�N�̃J���u���[�̃N���C���[�u�b�N�ɓ����Ă���Ƃ������Ƃ��A�Õ����L�^����m���Ă���B����́A���̍�i�����̓�������O�������N�ɍ�Ȃ���A��i�̌���l�����m�M�����Ƃ������_���ؖ����Ă���B Gonbosi�͓����l���I�y��ɂ����āA�I�P�Q���̃~�T�Ȃ��A��葁���̎����ɂ����A1470�N���O�ł���Ǝ咣���Ă���BVan den Borren�́A�����̍H�v�ȓ����ɂ����āA���ꂪ�f���t�@�C�̃~�T�Ȃɐ旧�Ƃ����A�咣���Ă���B���݁A�ނ̉����́A���蓾�Ȃ����̂Ƃ��Ė�������Ă��邪�A�����ĕs�\�Ȃ킯�ł͂Ȃ��B p269 ����A�I�P�Q���̃e�m�[���̃f���t�@�C�̂���ւ̈ˑ����́A�^���̂Ȃ������ł���B�I�P�Q���͊��S��cantus firmus����̑I�������邽�߂ɁA���邢�́A�����Ipresentation���S�̂�presentation�ɐ旧���Ƃ͂قƂ�ǂ��蓾�Ȃ����߂ɁA�I�P�Q���̃~�T�Ȃ́A��肠�Ƃ̍�i�ł���Ƃ���ׂ��ł���Bcantus firmus�̓���͂���䂦�ɁA��X�ɁA���n��̃|�C���g�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��\�ɂ���̂ł���B �@����ɁA���`�I�^��ɂ����炽�Ȍ��������������Ă���B�����̎Q�ƍ�i�ɂ����āA�I�P�Q���́A�f���t�@�C�̒�q�ł���ƌ����Ă��Ă���B���������咣���x������悤�Ȏ����I�ؖ��͂Ȃ��ɂ��ւ�炸�B �I�P�Q���̍�i�́A�o���V�����̉��y�ɑ��Ă̂݁A���ڂ̊W�����邱�Ƃ������Ă���B�����Ă��ꂪ�����炭�A�Ȃ�Plamenac���A�o���V�������I�P�Q���̋��t�ł������ł��낤�ƍl���Ă��邩�A�̗��R�Ȃ̂ł���B Caput�~�T�Ȃ̃e�m�[�����A�^���Ȃ��A�f���t�@�C�ƃI�P�Q���̊Ԃ̒��ڂ̃R���^�N�g�̑��݂����������Ƃ͋^���Ȃ��B�^��ɓ�����ɂ͏\���ȏ؋�������킯�ł͂Ȃ����A������ɂ���A�����������Ƃ́A���҂̊Ԃ̊W�ɐV���ȑ��ʂ������Ă���B �@�I�u���q�g��Caput�~�T�Ȃ��A3�Ȃ̂����ł����Ƃ��V�����Ƃ������Ƃɂ͌����ċ^��͂Ȃ����A����́A���ꂪ����̗l���������Ă��邩��ł���B�I�u���q�g�̃e�m�[���̒��Ӑ[�������́A�I�u���q�g������i�ɐe����ł������Ƃ��Ӗ�����悤�ȁA�Q�̐�s�����i�ւ��������̒��ڂ��ׂ��W�𖾂炩�ɂ��Ă���B �S�̓I�ɁA�I�u���q�g�́A�f���t�@�C�̃e�m�[������葸�d���Ă���A������ʂ�Ɏؗp���Ă���B�������ނ́A�L����A�����ɂ����ẮA�ꑮ���Ă͂��Ȃ��BTable�R�������悤�ɁA�R�̊y��(Gloria�CCredo�CSanctus)�́A���m�Ƀf���t�@�C�i�ƃI�P�Q���j�̃t���[�Y���������̂܂܂�������g���Ă���BSanctus�ɂ����ẮA�����Ԃ�s�K���ł͂��邪�B���ɁA�}�����ꂽ�x���́A�f���t�@�C�̂���ƍ������Ă����A���ɂ���́Athe Gloria�CSanctus�C Agnu���ɂ����Č����ł���B�I�P�Q���́A���̓_�Ɋւ��āA�f���t�@�C����̂��Ɨ��������Ă���B�i�G���������_�ɂ����Ă��A���݂ł̓f���t�@�C���Caput�~�T�Ȃ͂Ȃ��̂ŁA�K���������̂悤�ɂ͌����Ȃ��ł��낤�j p270 �@����A�I�u���q�g�́A�I�P�Q����肩�Ȃ莩�R�ł���B�I�u���q�g��statementB�̔��q�L���́AC�� ����ɁAAgnusI��II�̃e�m�[�����A�����ɏk��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�������������̓I�u���q�g�ɏے��I�Ȃ��Ƃł���B�ނ́A�V�����\�����������A�ؗp�����������A����̍�ȉƂ�����ł��낤�悤�ɂ����B����ɁA �����ԂЂ��鐺���icantus firmus�j�ɑ��Ēo�ɂ����ԓx�������悤�����Y���ƃ����f�B�ɂ��Ă̎���ꗂ�����B(�㗪�j ���������ύX�̓~�X�ł͂Ȃ����Ƃ͂����炩�ŁA����ǂ��납�A��ȉƂ����S�l��������ȉ��y�I�i���ɓK�������邽�߂́A�n�l���ꂽ�ω��Ȃ̂ł���B �����ʼn�X�́A�I�u���q�g�́A���ւ̂��߂́h���܂��h�����Ă݂悤�B�Ō�ɁAcantus firmus����̃t���[�Y�̑I���Ɗȗ����Ɋւ��āA�I�u���q�g�́A�I�P�Q���������Ɨ��������_�����炯�o���Ă���B�I�u���q�g�́AKyrie�Z�����A�����A�t���[�Y�̑I���͔C�ӂł���BB35-37���߂́A��x�o������B���s�[�g�͗���Ă���AEx4�͉�X�ɁA����炪��x�A���������Ƃ������قȂ������Y���Ƃ�����B47-53�ɒu������邱�Ƃ������Ă���B���̕s�K�����ɂ��ւ�炸�Acantus firmus�͂��̑S�̂���x�͂����Ɖ����ʂ��Ă���B �@Kyrie and the Agnus�́A�I�u���q�g�̐�̂Q�̃~�T�ȂƂ̐e�a���̖����Ȏ�����^���邱�ƂɂȂ�Q�̊y�͂ł���B�I�u���q�g��cantus firmus���f���t�@�C�̂���Ɠ���ł��邱���́A�f���t�@�C�̍�i�Ƃ̐e�a�����ؖ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炨���炭�A�ނ͂�����I�P�Q������ؗp���邱�Ƃ��ł��A����䂦�ɊԐړI�Ƀf���t�@�C����ؗp�������ƂɂȂ邩��ł���B�t�ɁA�ނ͂�����A�I�P�Q���̍�i�̒m���Ȃ��ɁA���ڃf���t�@�C������������Ă��邱�Ƃ��ł����̂ł���B p271 �����ǂ�����Ȃ������B���łɎw�E�����悤�ɁA�x���̐��͑啔���̊y�͂ɂ����āA�f���t�@�C�̂����i�����Ē��ڂ̈ˑ����������������ł͐������꓾�Ȃ��j�ɋ߂��B���Kyrie�́A�I�P�Q���̃p�^�[���ɕ���Ă���B����́A��������̃e�m�[����statement�ł���i�f���t�@�C��2��j�A�����āAstatementA��B����̑g�ݍ��킹�ŁA�ЂƂ�cursus�ƂȂ�B����̓I�P�Q����Kyrie�̓Ǝ��̓����ł���A�I�u���q�g�́A�ڍׂ͂Ƃ������A�����I�Ȗʂł���ɏ]�����̂ł���B �Ō�ɁAAgnus�́A�f���t�@�C�ƃI�P�Q����Agnus�̌����ȓ��F�̃��j�[�N�ȑg�ݍ��킹�ȏ�̂��̂ł���B�e�m�[���̈�ʓI�p�^�[���Ɋւ��āA���Ԃ̋x���̃Z�b�g���܂߂āA����̓f���t�@�C�̂���Ɠ����ł���B�t�ɁA Agnus�́A�ؗp�̓����ɑ��Ă����łȂ��A�I���W�i���Ȃ��́A�I�P�Q�����f���t�@�C������Ă��Ȃ�statementA�̏k��ɑ��Ă��A���̑����ׂĂ̊y�͂���ʂƂȂ��Ă���B�I�u���q�g�́A���̍Ō�̊y�͂ɂ����āA�S�̍�i�̓K�������N���C�}�b�N�X�������Ă���A�ނ������ɂQ�̐�s�����i�̓�����ێ����Ă��邩���킩��B���ہA�I�u���q�g��Agnus�́A���l�b�T���X���y�Ō����u�ؗp���ꂽ��i�̌|�p�v�̊��S�Ȍ��{�Ȃ̂ł���B �ؗp���ꂽ�����̎�舵���ɂ����āA�ނ͓`���ƃI���W�i���e�B�̊Ԃ̃o�����X�����܂�����Ă���B�܂��ɂ��̓����A�ނ̃~�T�Ȃ��A��葁���̍�i�ɋ��ʂ��āA�͂�����ƁA�u�I�u���q�g�͂Q�̂��̑��� Caput�~�T�Ȃ�m���Ă����v���Ƃ��Ӗ����Ă���B �@�e�m�[���̍\���̕��͂́A���܂łɋ^��Ƃ���Ă����~�T�Ȃ̊Ԃ̂��ٖ��ȊW�𖾂炩�ɂ����B����͐V���Ȍ��������J���A�����f�ނ���舵��unbroken line�𖾂炩�ɂ����B���Ȃ킿�A�����Ȍ��t�ł���traditio�ɂ��āA�f���t�@�C�̌������I�P�Q�����āA15���I���̃I�u���q�g�̎���ɂ܂ōs���n����̂ł���B���̂��ׂẮA�e�m�[���̒P���ȃ��J�j�b�N����W�����꓾��̂ł���B �\���I�Ȑ����́A�����̈قȂ��������ɂ����āA��i���ɑł����Ă��邱�Ƃ��ł��A��i�̉��y�l���ɂ͂قƂ�Lj����Ȃ��B�����������R�̂��߂ɁA����́A���ړI���݈ˑ��̌���I�ȓ����I�؋�������鏃���ȍ\���I���ۓI�W���m������̂ł���B �z�~�T�� cantus firmus Caput�~�T�� cantus figuratus canlus mensuratus cantus planus |