| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE
MUSIC�U |
| Caput: A
Liturgico--Musical Study S. LITURGICAL ASPECTS OF THE ANTIPHON VENIT AD PETRUM p230 �@antiphon�̉��y�Ɉڂ�O�ɁA���̓T��I���ʂ���舵�������B���łɌ����悤�ɁA�����͎��ۂɁA�A�����̒ʏ�ł͂Ȃ����y�I�����������Ă���Banthiphon�́A�C�G�X���Ō�̔ӎ`�Ŏg�r�����̑��������������L�O���鐹�T�̐������̋V���ɑ����Ă���B p231 ����pedilavium(�����j�́A�ʏ�A�D�́i���邢��"Shere")�ؗj���̔Ӊۂ̂��Ƃɍs��ꂽ�B�Z�����j�[�̊Ԃɂ�antiphons���̂��A�ŏ���Mandatum novum�i�V�����|�j���V���S�̖̂��ƂȂ��Ă���AMissals or Processional�ɂ����āAMandatum�Ƃ��ċK�肳��Ă���B���̖��O�́AMaundy Thursday����R�����Ă���AMaundy�́AMandatum�̉p�ꉻ�ł���Bantiphon�̖��O�́A�����n�l�ɂ�镟�����iSt. John�C13�C6 -9�j���痈�Ă���B Venit ad Petrum; dixit ei Petrus�CNon lavabis mihi pedes in aeternum; respondens Jesus dixit�CSi no lavero te�Cnon habebis partem mecum; Domine�Cnon tantum pedes meos�Csed et manus et catut 6�@�������āA�V�����E�y�e���̔ԂɂȂ����B����Ɣނ̓C�G�X�ɁA�u���A���Ȃ����킽���̑������ɂȂ�̂ł����v�ƌ������B �V�@�C�G�X�͔ނɓ����Č���ꂽ�A�u�킽���̂��Ă��邱�Ƃ͍����Ȃ��ɂ͂킩��Ȃ����A���Ƃł킩��悤�ɂȂ邾�낤�v�B 8�@�y�e���̓C�G�X�Ɍ������A�u�킽���̑��������Đ��Ȃ��ʼn������v�B�C�G�X�͔ނɓ�����ꂽ�A�u�����킽�������Ȃ��̑�����Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��͂킽���ƂȂ�̌W�����Ȃ��Ȃ�v�B 9�@�V�����E�y�e���̓C�G�X�Ɍ������A�u���A�ł́A�������ł͂Ȃ��A�ǂ����A��������v�B �e�L�X�g�́A�y�e���ƃC�G�X�̉�b�ƂȂ��Ă���B�����Ē��ځA����̕����̂����̂������̏ȗ��ɂ���Ă����̔�������Ă���B�����ɂ͂Q�̏d�v�Ȍ��t�����܂�Ă���B�u�����킽�������Ȃ��̑�����Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��͂킽���ƂȂ�̌W�����Ȃ��Ȃ�v�ƁA�u���A�ł́A�������ł͂Ȃ��A�ǂ����A��������v�̂Q�ł���B�Ō�̌��t catut���A���R�͖��炩�ł͂Ȃ����A�����X�}��ʂ��āA�����Ƃ����y�I�������Ȃ���A���ʂ̃l�E�}�I�l���Ƃ͈�����`�Őݒ肳���anthiphon�S�̗̂B��̕����ƂȂ��Ă���B �@��andatum�̊��Ԃɉ̂�ꂽantiphon�̘A���́A�����ɂ͏�����Ă��Ȃ����A�قȂ������A�n��ŕω����Ă���B�i�ȉ����j p232 �@��L�̃\�[�X�͂��ׂāA�t�����X�A�p���N���ł���B�ŏ��̃t�����X�N���̂��̂́A���}�[�V�����C���@�ɑ�����Saint-Yrieix�ł���A��Ԗڂ́ANorman use of Rouen�ł���B�O�Ԗڂ�use of Paris�ł���A�p���̃\�[�X��Sarum use�ɑ����Ă���BNorman ��English�T�炪�����̒ʏ�ł͂Ȃ��A���e�B�t�H�������L���Ă��鎖���́ANorman ��Sarum rites�̊Ԃ̋߂������j�I�W�̊ϓ_���炵�āA�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B �����ɍL���A���e�B�t�H�����t�����X���ɓ`�d�����������肷���Ƃ͍���ł��邪�A3�ӏ��̏d�v�n�_(Saint-Mart �Cila Paris�C Rouen�j�ɂ����Ă��ꂪ�N���������Ƃ́A�L���g��������Ă���B p233 �@antiphon Venit ad Petrum�ւ̌������t�����X�Ɖp���̃\�[�X�Ő������Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ��A���[�}�T��ɂ�����\�[�X�ł͔ے�I�Ȍ��ʂƂȂ��Ă���Bmandatum�̏j�Ղ��̂��̂́A���[�}�T��ɂ����Ă��K���I�ɏo������B�����A�����̃A���e�B�t�H�������邪�AVenit ad Petrum�͒�����Graduals �� Processional�A���邢�͍����̃��[�}�̋V���ɂ����Ă��܂܂�Ă��Ȃ��B ���炩�ɁA�A���e�B�t�H���̓O���S���I���̌ŗL�̂��̂ł͂Ȃ��A���邢�́A���[�}�̓T��̖@�T�ɂ͌����Ȃ��B���̋����悤�Ȃ��邢�͈ӊO�Ȍ��_�́A�����f�B�̔�O���S���I���̓G�ȓ���������m�F�����B �@���[�}�AFrench. English�ɂ�����mandatum�̔�r�����́A�ŋ߂͎��s����Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͂��L�������������K�v������ł���B�A���e�B�t�H���̃Z�b�g�̃��X�g���́A���܂��܂ȃ\�[�X�ɂ���Ă���A�[�}�ƃ��[�}�T��̊Ԃ̈Ⴂ�������Ă���B���܂��܂ȃZ�C�����\�[�X�����Ƀ��X�g������K�v�͂Ȃ��A�����͂��ׂāA�{���I�ɁA������A���e�B�t�H���̐��ɂ���Ă���B �ȉ��ɁA5�����Ɍ��肵�āA���������A���e�B�t�H���������B �e�[�u���P
p234 ��L�̃��X�g�́A�R�̃A���e�B�t�H���̃��[�}�Z�b�g�Ɣ�r�����B�ŏ���Missale Romanum(1474)�̈���łł���B�Q�Ԗڂ͑嗤�A�����炭�̓C�^���A�����15���I�����̎ʖ{�W(Cambridge. Univ. Lib. Add. MS. 6668)����̂��̂ł���B���̓��e�͂��܂��L�q����Ă��Ȃ��B����́A��ʓI�ɁA���[�}�V���ɏ]���Ă���A�����őI�����ꂽ�B�Ȃ��Ȃ炻��́A�����̂��̑��̑嗤�̃\�[�X�����͂邩�ɑ����̃A���e�B�t�H�����܂�ł��邩��ł���B�R�Ԗڂ́ALiber Usuali���ɂ����Ċ܂܂�Ă���A�������i�G��@�`�J������c�ȑO�́j�A���e�B�t�H���ł���B �e�[�u���Q
p235�` �@���܂��܂ȃV���[�Y���r����ƁA�قƂ�ǂ̃\�[�X�ɂ����ẮA�ŏ���Mandatum novum���u����Ă��邱�Ƃ��킩��B�C�^���A�̃R���N�V�����ł͗�O�ŁA�ŏ���Dominus Jesus postquam cenavit���u����Ă���B p236 ���̃e�L�X�g�ł́A�ŏ��̃t���[�Y���Ō�̔ӎ`�ł̐����ł���A�d�v�Ȍ�gExemplum dedi vobis."���܂�ł���B����䂦�ɁA�����mandatum�̋V���ɐ旧���ċ�������Amandatum�����̖��O���ؗp����antiphon��u��������̂ɓK���Ă���B Sarum use�ł́ADominus Jesus postquam �Ƃ����e�L�X�g�����l�Ɍ���邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B����́A��s����~�T����ommunio�Ƃ���mandatum�ɐ旧���Ă���B�����Ă���䂦�ɁA���ځAmandatum�����[�h����B�ŏ���antiphon�͕ʂƂ��āA������anthiphon�̑I���̊Ԃɂ́A�����ׂ����ꐫ�̌��@������B�����������l���́A�K���I�ȓT��ł͂܂�ł���A����ȋ@��ɂ����邻��ɂ����ēT�^�I�Ȃ��̂ł���B �p���ƃZ�C�����ł̊Ԃł́A�ψق����Ȃ��B���҂�antiphon�̐������łȂ��A�ЂƂ̗�O�������āA�`�����g���g�������ł���B���ꂪ�T��̋ߐe�����Ӗ����邩�̔��f�͍���ł��邪�A������ɂ���A���ɒ��ڂ��ׂ����Ƃł���B The Gradual of Saint-Yrieix�́A������antiphon�������A���̑��̃\�[�X�̂قƂ�ǂ��ׂẴ`�����g���܂�ł���B����́A�ʖ{�������ꂽ�C���@�ɂ����ċV���������ɔ��W���Ă��������������Ă���B �@antiphon�́A�K�������A�C�G�X�̐����̕���ƊW���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��AChester ��Accepit Maria�́A John 12:3�� Luke 7:38�̑g�ݍ��킹�ł���A�}�O�_���̃}���A�ɂ��C�G�X�̑��ւ̓h���������Ă���BIn diebus illis�iLuke 7:38�j��Maria ergo unxit�iJohn 12:3�j�͓����o�����ɂ��Č��y���Ă���B �����Ɍ����A�}�O�_���̃}���A�̘b�́Amandatum�Ƃ͖��W�ł���Amandatum�͐��m�ɂ́A�C�G�X�����l�̑����������Ƃ��ł��邪�A���̗ގ������l���ɓ�����Ă���̂ł���B �@���̑���antiphon�́A�����Ɋւ��ẮA�܂����������Ă��Ȃ��BSaint-Yrieix�ɂ����ẮABenedicat Dominus�����o����A�C�^���A�̂��̂ł́ABenedicat nos Deus��������B���҂Ƃ��ɁA�j���̂��߂̋F��ł��邪�A�e�L�X�g����f�B�͓��肳��Ă��Ȃ��B ���[�}�̃��X�g�ɂ����ẮAantiphon Benedicta sit sancta Trinitas�́A���̑��̂��̂Ƃ͂܂������قȂ��Ă���B����͎O�ʈ�̂̏j���ɑ����Ă���A�����i�G��@�`�J������c�ȑO�j�ł́A�قȂ��������f�B�œ������t�ŃC���g���C�g�Ƃ��ĉ̂��Ă���Bmandatum�̃V���[�Y�ɂ����邻�̑}���́A���[�}�T��ɓƓ��̂��̂ł���B�����Beneventa���ʖ{�ɂ����o����A���Ȃ��Ƃ��A11���I��葁���������炠��B p237 ����antiphon��������mandatum�ƌ��т��悤�ɂȂ����̂��͕s���ł���B������ɂ���A���̃`�����g�͊�ȗ����ʒu�ɂ���B �t�����X�Ɖp���̃\�[�X�ł́A����͒P���ɏȗ�����Ă���BChester Processiona���ɂ����ẮAantiphon�́A�Q�̃O���[�v�ɕ������A��Ԗڂ́ATellus et aethera����n�܂�B���̃`�����g�́AChester �ł͓��Ɏw��͂Ȃ��A���̑��̂��̂Ƃ͈قȂ��Ă���B�����antiphon�ł͂Ȃ��Aprocessional hymn ���邢�� versus�ł���A���������^�C�v�͑����̒����̃\�[�X�Ō�����B Saint-Yrieix�� Cheste���ł͂܂��A���ʂ̍Ō��antiphon�@Domum istam������B����́A�h���@�h�ւ̖h��̂��߂̋F��ł���B���̃A���e�B�t�H���́A�C���@�ŕҎ[���ꂽ�Q�̎ʖ{�Ɍ����B�`�����g�̋V����mandatum�Ƃ̓��I�Ȃ���͂Ȃ��B �@�e�[�u���P�ŏЉ���A���e�B�t�H����5�����ł̃Z�b�g�̏ڍׂȒ����ɂ��A�����͂Q�̃^�C�v�̃\�[�X�����邱�Ƃ��킩���Ă����B�ȒP�Ɍ����A�C���@�I�����邢�͑吹���I���A�Ƃ������Ƃł���B �C���@�I�Ȃ��̂��ASaint-Yrieix���邢�� Chester�ł���A���Ԃ�Venit ad Petrum��u���Ă���A�Ō��Domum istam�ŏI���B �吹���I�Ȃ��̂́ARouen�CParis�C Sarum�̂���ŁA����Venit ad Petrum�ŏI���B �����̃^�C�v�̓A���e�B�t�H���̑I���Ɛ��ɂ����鑽�l���������Ă��邪�A�ЂƂ̏d�v�ȓ_�ŋ��ʓ_������B�����͕s�ϓI���AAnte diem festum�iJohn13:1-5�j�ɏ]��Venit ad Petrum�iJohn13:6-9�j���������Ƃł���B�Q�̃`�����g����ɂ��̏����Ō���邱�Ƃ́A���t�ɂ���āA�e�Ղɐ��������BAnte diem festum��John13:1-5����̂��̂ł���A�����āA�v���N�������悤�ɁA�����͂̑�6�߂���n�܂�Venit ad Petrum�̐��m�ȕ⑫���`�����Ă���B ���t�Ɋւ������A�A���e�B�t�H���͌p�����Ă���̂ł���BAntiphonary of Worcester�ɂ����ẮA�Q�̃`�����g�͎��ۂɁA�ЂƂ̃A���e�B�t�H���Ƃ��ďk��Ă���A���̂��߂ɁAVenit ad Petrum�̓A���t�@�x�b�g���̍����ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��̂ł���B p238 Venit ad Petrum�̂��̓����version�́ASarum use�Ƃ͂����Ԃ̉��y���قȂ��Ă���B�����āA��X�̎��ɂ͉���̍v�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�Acaput�Ȃ��́A�Ō�̃����X�}�ɐݒ肳��Ă��Ȃ�����ł���B�k�ꂽ�ʂ�version�́Acantatorium(Add. MS 23922�Cfo .l 3JV-32)�ɂ����Č�����B�����ł�caput�Ȃ��́A�P�ɒ��������X�}�ƂȂ��Ă��邪�A�Z������Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̉��y��staffless neums�ʼn�ǂł��Ȃ�����ł���B �@Ante diem festum��Venit ad Petrum�̑����̃\�[�X�ɂ����ẮA�قȂ��������f�B�����Q�̓Ɨ������`�����g���o������B�������A����_�ɂ����ċ��ʓ_������B�����Ƃ����������X�}�ŏI��邱�Ƃł���B���ꂼ��Adiscipulorum�� caput�ł���B�v���C���`�����g�ɂ����āA�����X�}�͋��R�ł͂Ȃ��A�ʏ�I�ɋ�������Ă���̂ŁA2�̌��t�͓��ʂȏd�v���������Ă��邱�ƂȂ̂��낤�B�����X�}�̓����f�B�͈قȂ��Ă��邪�A�ȉ��̂悤�ȁA���ʂ����O�I�ȓ����������Ă���B �@�����f�B�̉����̍L���ƒ����I���� �A����炪�A���e�B�t�H���̍Ō�Ɍ���邱�ƁB���������X�}����ʓI�ł͂Ȃ��T��I�`���B ����ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A�����Q�̃A���e�B�t�H�����A�t�����X��p���ł̓T��Ƃ͈قȂ�A���[�}�T��̓T��\�[�X���ɂ����āA�K���I�ɁA�폜����Ă��邱�Ƃł���B�����͖��炩�ɁA�O���S���I���̈ȑO�̂��̂ł���A �^��Laudes Regiae��Christus vincit�Ƃ���悤�ȃ`�����g�̔[�}�I�ȑw�ɑ����Ă���A�Ƃ������Ƃł���B ���[�}�T�炩��̂����Q�̌���I�ȃA���e�B�t�H���̌��@�́A���y�I�w�i�ł͐������꓾���A�܂����y�I�ȃA�N�Z���g��caput�Ƃ������t�ɓ�����悤�Ȋ�ȏ������������Ȃ��B �����́A�ɒ[�ȍ����ł���悤�Ɍ�����B�Ȃ��Ȃ�A�����̋V���ɂ����ĂȂ�Apedes�i���j�Ƃ��������������������K��������ł���B���̓_�ɂ��ẮA�T�畨��ɂ�������Ƃ̏������K�v�ƂȂ�B p239 �@�����́A�����̍s�ׂ����łȂ��A��ւ̕���ɂ����āA�[�}�T��̑����ƊW���Ă����B���ɁA����̔�ւɂ����āB�����́AMozarabic�CGallican�CAmbrosian�C Irish rites�Cthe African Church�Cand some Eastern churches�ɂ����āA����̔�ւɑ����Ă����B�����Ɛ���̊W�́A���Ɏ����̂��Ƃł��邪�A�g�k�̐�����ے�����D�̖ؗj���ɂ���������̉��߂ɑk��B ���̊T�O�Ɋւ���悭�m��ꂽ�؋��́A��ւ̗̈�ւ̐��������グ��X���ɂ��邪�A�����o���̃\�[�X�Ō������Ă���B���A���u���V�E�X�́A��ւƂ��Ă�pedilavium�̐����ɂ��Ă̎傽�錠�Ђ̈�l�ł���B�ނ́A������܂�"���߂̓����h�A�h�ЂƂ̔�ցh�ƌĂ�ł���A���[�}�ɑR���āA�~���m���`�������B�~���m�ł͋V���́A�Z�툤caritas�̊����Ƃ��Ă̂ݔF�߂��Ă����B����Ɛ����̒��ڂ̊֘A�́AGallica�N����9���I�ɍ쐬���ꂽ�U�C�V�h���X�@�ߏW�ɂ����āA�����Ɏc����Ă���B���̒��҂́A��Z�ɁA�gLavatio pedum nostrorum significat battismum.�h�ƋL���Ă���B non-Roman and Roma���̊Ԃ̉��߂̈Ⴂ�́A�P�ɁA�A�E�g���C���݂̂ɂĖ��炩�ł���B���[�}�T��̑啔���ɂ����ẮA�Վ��͔ډ��̊����ł��������A�����ɁA����̔�֗̈�Ƃ��֘A���Ă����B���[�}�ȊO�̒n�ɂ����ẮA��ւ̊܈ӂ͓��ɂȂ��A�Ō�̔ӎ`�ɂ�����P�Ȃ�L���X�g�̍s���̌h�i�Ȗ͕�ɉ߂��Ȃ������B����͌Z�툤caritas�̎��H�ł������B �@�����������߂̑��l���́A�A���e�B�t�H���̑I���ɂ��W���Ă����Bmandatum�ɂ��Ẵ��[�}�`���ɂ����ẮAcaritas�����y���A�A���e�B�t�H��Ubi caritas et amor�ɂ����āA�^���Ȃ�����͎�����Ă���B�d�v�Ȃ��Ƃ́A���̃`�����g�́A���[�}�̈�A�ɂ����čŌ�ɁA�����Ɍ���邱�Ƃł���B�v����ɁA����́AVenit ad Petrum�Ɠ����ꏊ�ɂ���BUbi caritas et amor�̃e�L�X�g�́A�Z�툤��mandate�Ɍ��y���Ă���A����͐����ɂ�����mandatum�Ƃ��Ē�`����Ă���iJohn�C�P. Epist��e�C4:21)�B����䂦�A����́A������mandatum�ɂ����ĉ̂��邱�Ƃ��K���Ă����B�����́A���炩�ɁA�����ł�caritas�̐��_���������B �[�}�I�`���ɂ����ẮA���������l���́A�w�i�ɑނ�����BSaint-Yrieix�� Rouen�ł́A�A���e�B�t�H��Ubi caritas���܂܂�Ă������A�����͂��܂�d�v�ł͂Ȃ��Ƃ���ɂ������B�������A�p���̃\�[�X�͂���ɐi��ŁA�قƂ�ǂ��폜����Ă���B p240 �h�吹���h�O���[�v�̃\�[�X�ARouen�C Sarum�C Paris�ɂ����ẮAcaritas����pedilaviu���ւ̃A�N�Z���g�̃V�t�g���ؖ�����Ă���B�����́AAnte diem festum��Venit ad Petrum����A�ŏI����Ă���B����䂦�ɁA�[�}�I�`���ł���mandatum�́h��֓I�ȁh���߂������Ă���B �@��d�̉��߂́A�}���w�I�؋��ɂ���Ďx������Ă���B�����́A�����̌|�p�ƂɂƂ��ẮA�D�܂������ł������B�����āA�����̏�ʂ̂��ׂĂ̊G�̕\���̒��ł́A�ނ�͒ʏ퐹���̒����Ȑ�����^���悤�Ƃ����B ��ʂ��\����Q�̐}���w�I�l��������B�ЂƂ́A�y�e��������������āA�C�G�X���ނ̑�����Ƌ��Ƃ��ɁA�R�c�Ɣ������Ă��邱�Ƃ������Ă���B����́A�h'non lavabis mihi pedes in aeternum"�Ƃ������t�ɑ������A�ډ��Ɓ@caritas�̍l���f���Ă���B  �����ЂƂ̃^�C�v�́A�قȂ������_�̏�ʂ��\���Ă���B�����ł́A�y�e���͉E���ނ̓��ɓ��ĂĂ���B���̂������́A�gnon tantum pedes meos sed et manus et caput�h�Ƃ������t�ɑ������Ă���B�����āA����̍l���f���Ă���B  ��P�̃^�C�v�́A���[�}�̈�Ŏx�z�I�ł��������A��Q�̃^�C�v�́A�r�U���`���|�p�̈悩�琼���ɂ���Ă������̂ł���A10���I�ɂȂ��ď��߂Ď��ۓI�ɂȂ��Ă����悤�Ɍ�����B �@caput�Ƃ������t���������闝���́A�e�Ղɓ�����悤�ɂȂ����B����͓��ʂȓT��I���߂̃L�[���[�h�ł���A���������A�����X�}�ɂ�鉹�y�I�D�ʐ����^������B�G��I�w���Ɖ��y�Ƃ̊Ԃ̐��m�ȕ��s�W�́A���ɋ����[�����Ƃł���BCaput�ɒu���ꂽ�y�e���̎�́A���炩�ɃA���e�B�t�H���ɂ����郁���X�}�̔@���ł���A�ڂɑ��閾�������ɑ��閾���Ƃ���B p241 ��X�́A�����ŁA�T��̗��j�̗̈�A�}���w�A�����ĉ��y���݂��ɂǂ̂悤�Ɋ֘A���A�ЂƂ����̑���ʂ��Ă킩��₷���Ȃ��Ă���B��X�̃X�^�[�g�n�_�́A���y�I�Ȃ��Ƃł���B�ʏ�ł͂Ȃ������X�}�́A�T�炾�����痈�邱�Ƃ��ł���������v�������B���������������̈悪�����炳���A�����́A�������Ăł͐������꓾�Ȃ����������������邱�Ƃ��ł���B ����䂦�ɁA�����݂͌��ɗ��v�ƂȂ�B����܂ŁAmandatum�́h��֓I�h�ȉ��߂́ASarum rite�ɂ����Ă����݂��Ă������Ƃ͒m���Ă��Ȃ������B��X�́ACaput Masses�������ꂽ���ɁA�����������߂������15���I�̓T��ɉe����^�������ǂ����͒m��Ȃ��B���邢�́A���łɂ��ꂪ���ނ������ǂ������B ������ɂ���A���y�ɂ����Ă���͕ۂ���Ă����B���y�Ɣ��p�̗��j�̒́A�T��I�T�O�ɂ���Č`������邩������Ȃ����A�����͂���玩�g�̐��������A�����𑣐i�����T��V���ȏ�ɒ������݂����B�䂦�Ɍ|�p�ƓT��̌`���̊Ԃ̃^�C�����O�́A��X�ɁA�O�҂ɂ����Č�҂̍��Ղ��ł���悤�Ȍ��ʂ��`���̂ł���B �@�A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�̗��j�́A�[���ł���A�{���̌����̗̈���Ă���B�����āA�����̓T��\�[�X���A�N�Z�X���꓾��B�����̌����́A���A���e�B�t�H�����ŏ��ɂ��̓���ȉ��y�̈�Ɍ���āA�ǂ��œ�������A�����ɈقȂ����n��T��ɍL�܂����������肷�邱�ƂɂȂ�ł��낤�B ����ɁA�A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�����߂���mandatum�ƂƂ��ɊW���Ă����̂��A���邢�͑��̋@�\���������̂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��BCaput�̃����X�}�̋N����ψق͔��ɋ����[�����Ƃł���B���y�̃\�[�X��11���I�ȑO�ɋL���ソ�ǂ蓾��̂ŁAGradual ofSaint-Yriei�����A���m��trascribe���ꂽ�`���ɂ����郁���X�}���܂ނ����Ƃ������̃\�[�X�ł���\��������B �Z���҂́AGradual of Saint-Yriei����Gallican�`�����g�̃T�o�C�o�����܂�ł���A�Ǝ咣���Ă���B��X�̃A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�͂����炭�AGallican�O���[�v�ɑ����Ă��邩������Ȃ��B��X��Gallican�`�����g�ɑ���m���͌����Ă���̂ŁA������������ɑ��钼�ڂ̏ؖ�������킯�ł͂Ȃ����B p242 �A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�́A12���I��Ambrosian antiphonar���ɂ��~���m�T��� Antiphonale Mediolanense�ɂ����݂��Ȃ��B���U���x�T���Missale Mixtum�ɂ����݂��Ȃ��B�A���e�B�t�H���͂���䂦�ARoman�CAmbrosian�CMozarabic chant�ɂ����Ă͒ǐՂ����Ȃ��B��r�I�����Gallican and Sarum�T��ɂ����邻�̑��݂́A�t�����X�N�����������Ă��邪�A����ŁA���̑��̔[�}�T��̉��y�\�[�X�͕s���S�ȏ�Ԃɂ����Ă����A�m���Ă��Ȃ��B �@���B�� antiphon�ɂ��Ă̓T��I���ʂ̘_�c���I����O�ɁACaput Masses���̂�ꂽ�����Ƃ̊W���ǂ��ł��������ɂ��čl�@���Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����͊D�̖ؗj����antiphon�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����ƍl����̂����R�ł���B�������A���̉���ɂ͂܂��^�₪����B Caput Masses�́A�l�{�߂̋G�߂̊Ԃɂ͋K���I�ɊO���ꂽ�O�����A���܂ށA���S�Ȓʏ핶�̐ݒ�ł���B�������ASarum Gradual�́A�i�����~�T���j���Ƃ��ɂ́A�O�����A���̂��悤�ɂ��Ă���B����䂦�ɁACaput Masses�́A�D�̖ؗj���̑����ȋ@��ɉ̂�ꂽ�ƍl������B ����A�z�~�T��cantus firmi �́A�T��I���R�����K�v�͂Ȃ������B�_���ȉ�����cantus firmus�Ƃ��ĐU�镑�������AAve regina caelorum�̂悤��antiphons���g��ꂽ���Ƃ͖��炩�ł���B���̉��t�ɂ��Ă̌��_�͈����o���Ȃ����B Ave Regina�̃~�T�́AFeast of the Holy Virgin�ɉ̂��A����ɁA���l�ɁACaput Masses�́A���y�e�����L�O���邽�߂ɍ��ꂽ�B��R�̉\���\�܂�A antiphon���~�T�̓T��I�^���ɉ���e����^���Ȃ������Ƃ����\���ے�͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����̓T��I��@�ւ̖��S�̓��l�T���X���y�̓����ł��邩��ł���B 4. MELODIC VARIANTS AND STRUCTURE OF THE CAPUT MELISMA  �@antiphon Venit ad Petrum�́A�~�L�\���f�B�A���@�ł��邪�A���i���ϊi���ɕ��ނ��邱�Ƃ́A�e�Ղɂ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炻��́A�����f�B�̈قȂ����Z�N�V�����ɂ����āA���҂̐��i�������Ă��邩��ł���B�h�~�i���g���邢��tone of recitatio���́A�ŏ��͋^���Ȃ������ł͂Ȃ��A�h���ł���B����͕ϊi�̃����f�B�ł���B�������A�Ō�Ɍ������ƁA���ƂɃ����X�}�ɂ����ẮA����̓\���ƂȂ�Arecitation tone�ցA�����ւƃV�t�g���A�����f�B�͐��i�ƂȂ�BGraduale�@Sarisburiens�ւ̍����ɂ����ẮAFrere�̓A���e�B�t�H�����V�C�W���@�ւƊ��蓖�ĂĂ���B �ߑ�̕��ނ͂��ꎩ�g�A���܂�d�v���͂Ȃ����A�`�����g�ނ���ۂ̏�Q�́A�����ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����͐��@�V�X�e�����m������ȑO�ɂ������`�����g�̑w�������Ă��邩��ł���B�����f�B�́A�ϊi�Ɛ��i�͈̔͂��ۂ��Ă��邪�A��O�I�ɁA�I�N�^�[�u�{�l�x�̗̈�ɋy��ł���BRoue���ł́A��v�������A���e�B�t�H�����l�x��Ɉڒ�����Ă���_�ɂ����āA���̑��Ƃ͈قȂ��Ă���B���̂��߂ɁA���K�v�Ƃ��A�h�~�i���g�̓t�@���ƂȂ�A�Ƃ��Ƀ~���ɂȂ邱�Ƃ�����i����̓~�L�\���f�B�A���@�̃I���W�i�����ł���V���ƂȂ�j�B �gnon tantum pedes�C�ɂ����ẮASarum version�̓��j�]���Ői�݁ARoue���ł́A���Ƃ��Ƃ̈ڒ��̂Ȃ��ʒu�ւƁA�ˑR�l�x���ɗ�����B���̂��߂ɁA�����X�}���g�͂����邻�̑��̃\�[�X���l�A���������Ō����B���̌��ʁA�A���e�B�t�H���̓I�N�^�[�u���Ȃ����ƂƂȂ�BRoue���łɂ����ĉ����͈͂��I�N�^�[�u�Ɏ��܂鎖���́A�����f�B�̕s�K���������炵�A�T�^�I�ȃO���S���I���̂̃����f�B�ɂ���ėv�����ꂽ����̒ʏ�͈̔͂ւ̈ڒ��ɂ���ăA���e�B�t�H�����̗p����X���Ɠ��l�ł���B�����������_����������ARoue���ł̓I���W�i�������f�B�̂�肠�Ƃ̉����ł��������ƂɂȂ�B �@�����ŁACapu���̃����X�}���g�̋c�_�Ɉڂ肽���BEx.1�ɂ����ẮA�T�̎�v�ȕψق����L����Ă���B�����X�}�̒ʏ�̕����I�ȓ����\���́ASarum version�ɂ����ėe�Ղɔc�����邱�Ƃ��ł���B����́A���̑��̕ψق����A�K���I�ɍ\������Ă���B p244 ����́A�������Ȃ������̂T�̃t���[�Y����Ȃ��Ă���B�����́Aa b a b a c c d d e.�ƂȂ��Ă���B�����X�}�͂��̓����I�`�Ԃ��A�����̔����������Ă���B����͈ȉ��̃_�C�A�O�����ɂ����ċL�q�����B �����I�Ȃ͂�����Ƃ����\�������łȂ��A�����f�B�̓��ꐫ���ASarum version�����̑������ʂ���BSarum�ψق́A���̑��̕ψقɂ����ē����悤�ȏꏊ�ɏo���������̂����A�����L���D�܂�Ă����B�t���[�Y���ɂ����ẮA�����\���܂ł���i���̓_�Ɋւ��ẮARouen�� Paris�C�ł����l�ł��邪�A Chester �� Saint-Yriei���ł͈قȂ��Ă���j�B�����āA�Ō�̃t���[�Y�ł́A�~���܂ŏオ��A���̂��߂ɁA���S�l�x�~-�V��̉����ƂȂ�B���̑��̃\�[�X�ɂ����ẮA���̉����̓�-�V��̎O�x�����ƂȂ�B �L�������̎g�p��A��x���O�x�ɒu�������邱�ƁA�����ē��l�̃����f�B�ω��́A�O���S���A���̖̂k�������̓����ł���BChristus�@vinci���̊��ĂƂ̊W�ɂ����āA���́A�Z�C�����T��ɂ�����k�������ɂ��Ă̓��l�̒��������B��������Capu���̃����X�}�Č��́A���̏����̌������疾�炩�ł��邪�A�Z�C�����`�����g�͊Q���āA�k�������ɂ����ăO���[�v������APeter Wagner�Ƃ͈قȂ�A����́A���}�l�X�N�����ł���B  �@Ex.1�Ɏ������Z�C�����ł́A�T�̃\�[�X���琬�藧���Ă���B (1) the Sarum Missal (Manchester�CJohn Rylands Library�CMS lat. 24�Cfol. 90); (2) the Graduale Sarisburiense (fol. 98); (3) a manuscript Processional of the fourteenth century (Brit. Mus.�CHarley 2942�Cfol 48-48v); (4)the printed Sarum Gradual of 1507; (5) the printed Sarum Processional of 1555 (Pollard 16248) �\�[�X�͂��̓ǂ݂ɂ����Ă͖{���I�ɂ͈�v���Ă���B�����̕ψق́A�����̃G���[��~�X�v�����g�ł���A��҂́A���y����̐V�K���䂦�ɓ��ɑ����B �@Sarum Missal (Plate 6)�ɂ����āA�t���[�Y���̂R�Ԗڂ̕��i�������ꂽ�����j�͏ȗ������liquescent neum�Œu���������Ă���B����ɁA�t���[�Y���́A�P���ƂȂ��Ă���B�Ō�ɁA�t���[�Y���i�������ꂽ�����j��4�Ԗڂ̕����ȗ�����A����Ȍ�̎ʖ{���l�Aliquescent neum�ɂ���Ēu���������Ă���B p245 �@Graduale Sarisburiens�́A�t���[�Y���ɂ����āA�ŏ��̘A�����̌�ɂ���ɌJ��Ԃ�������}�����A�t���[�Y���̌J��Ԃ��ɂ������čŏ��̃~-�t�@�A�\-�������폜���Ă���B����́A�t���[�Y���ɂ����Ďl�Ԗڂ̕����������A��������h����liquescent neum�Œu���������Ă���B �@14���I��Sarum Processiona���́A�f���t�@�C���g�����łƍ������Ă���B�Ⴂ�͂ق�̂킸���ł���B�i�ȉ����j �@�Z�C�����łł̍��ׂȑ���Ƃ��ƂȂ�A�嗤�̔łł́A�قȂ�����肩���ŁA���܂��܂Ȓn��T��ō̗p���ꂽ�����f�B�̐^�̕ψق�����B���������ψق̂������́A�݂��Ɋ֘A�����邪�A�����̃I���W���ɏ]���āA�ʁX�̃O���[�v�ɋ�ʂ���ɂ͕s�\���ł���B ��P�ɂ����āA���ׂĂ̔ł́A�Z�C���������X�}�Ƃ̗ގ��������������ɏ]���āA�T�̍\���v�f�ɂ���ĕ��͂����B�t���[�Y�̓����f�B�I�����ł͂Ȃ��A�`���I�ɂ��قȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�����͂����ΐ��m�ł͂Ȃ��A�݂��Ɍ������Ă��邩��ł���B �i�ȉ����j p249 �@Caput�̃����X�}�́A�A���e�B�t�H���̃����X�}�I�L�W�O���[�v�ɑ����Ă���A��ʓI�ɂ�neuma ���邢�� cauda�ƌĂ��B�����͑����ȋ@��̃A���e�B�t�H���̔����ɒ����Ă���A�A���e�B�t�H���̃`�����g�̒ʏ�̃l�E�}�l���������X�}�I�������璘���ɋ�ʂ����B ���̂悤�Ȋ��K��������n�܂������͂킩��Ȃ����APeter Wagner�ɂ��A�Â����m�I��Y�ł���B���_�Ƃ����́A������@�ɏ]���āA�������������X�}�S�̂̈�A���L�^���Ă��邪�A����������́ACaput�̃����X�}��Aantiphon Ante diem�ɂ�����discipulorum�����}���I�ł���B �������������≹�y�l���ɂ����āA��҂͉����`�����g�̃����X�}�Ɏ��Ă���B��X�̃A���e�B�t�H���������Ƃ��̐��������L���Ă���Ƃ��������́A�A���e�B�t�H���≞���̗l���̍����������Ă���B���������l���̍����́A��O���S���I���̂�[�}�`�����g�ł̓T�^�ł���B �@�O���S���I���̌ŗL�̂͂����肵���l���I��ʂ́A�ŏ���Peter Wagner�ɂ���Đ������ꂽ���A���ɂ킸���Ȃ��̂ł����Ȃ��BCaput�̃����X�}�́A�����`�����g�ł���allleluia�̖��c��ł��邱�Ƃ���������Ă���APeter Wagner���g�A���̓_�ɂ����ẮA�m�炸�m�炸�ɂ����Ċm�F�������B���Ȃ킿�A�ނ̓����X�}�����ۂɃA���e�B�t�H���ɑ��������̂ł��邱�Ƃ�m��Ȃ���������ł���B ���l�̐����̃����X�}�͊T���āA�A���e�B�t�H���ł͂Ȃ��A�����ɂ����Č�������BJacobus of Liege �́A���ꂼ��قȂ���@�ł���W�̒������������X�}�����p���A�����̗�́A�܂������ACaput�̃����f�B�̂悤�ɐL������Aflorid�ȗl���ł���B 9���I�ɁA�J�������O���̗��_��Amalarius�́A�ނ�De Ordine A ntiphonarii�ɂ����āA���� Descendit de celo�ւ̍ŏI�����X�}�ł���Fabrice mundi�Ƃ�����ɂ�����L���� triplex neuma�ɂ��Ę_���Ă���BPeter Wagner�ɂ��A�����A�����X�}�������������߂�X�������債�Ă����Ƃ̂��Ƃł���B p250 10���I��Hartker's Antiphonary of Saint-Gall �ɂ����ẮAAdvent�CChristmas�CTrinity�Ƃ���������G�߂�j�Ղ̂��߂̌���ꂽ�������������ꂽ���A�����͂��łɁA12���I�̃��b�J�ʖ{�ɂ����Ă͋���ȗʂɒB���Ă����B�������A���̎ʖ{�ɂ����ẮA�����́A��P�C�W���@�̃`�����g�Ɍ����Ă���A��W���@�͂܂��Aantiphon Venit ad Petrum�Ƃ���v����B���W�̐����ɂ����ẮA]acobus of Liege���ڌ������悤�ɁA�����I��caudae�́A��������@�ɑ��ċ�ʂȂ��A�t�����ꂽ�̂ł���B �@�Ȃ�Caput�̃����f�B�������̃����X�}�ƘA�ւ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��Ƃ����A����I�ȗ��R�̂ЂƂ́A���̓����\���ɂ���BPeter Wagne���́A�O���S���I���̂̌`���Ɋւ�����I����ɂ����āA�����̃����X�}�����̕��͂����A�T���āA�����́A��x�o�������ЂƂ܂��͂Q�̘A������t���[�Y�̌��݂̓����̔�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������B ���̍\���́A�X�L�[���Ƃ��āAa a b b [ c c] d [ e]�Ƃ��Ď������B����͌����Ƃ��āACaput�̃����f�B�ɂ����Ă���v���Ă���B���������́A�����ɂ����ē��ޏo������Balleluias�ɂ�������̂ƁA�p�x�͉����邪�Aoffertory�ɂ�������̂ł���B Peter Wagne���������ɑR���Ď������O���[�v�́Atract��gradual�ł���B�����́A�hmiglant melismas"�ƌĂ��X���ɂ���florid�ȃZ�N�V�����ɂ����Ďg���Ă���Bgradual�́A�قƂ�Ǔ��������������Ȃ����A�����܂��������I�ȕ��@�ɂ����āAflorid�ɍ\������Ă����B�����͂����̒�^�I�����ɗ����Ă���Atract��gradual�̑����ɂ����ĕs�ϓI�ɍēx�o������BPeter Wagne���́A��������miglant melismas���A���̃`�����g�̌Â��w�̓����A���m�N���A���[�}�i�K�ł̔��W�ɔ����g�D�����ꂽ�����X�}�̌`���I������`�ƘA�ւ����Ă���BSaint-Yriei���̂����܂��ɍ\�����ꂽ�ψق́A�����X�}�̏����i�K�������Ɨސ�������B�����āA�Ȍ������ĂȃZ�C�����ł́A�����Ƃ�����̒i�K�ł��낤�B p251 �@�����A�Z�C�����ł����̍\�����h���[�}�h�̉e���ɕ������Ƃ͂��܂肠�蓾�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̃A���e�B�t�H���́A���[�}�̃��p�[�g���[�ɂ͑����Ă��Ȃ�����ł���BPeter Wagne���́h���m�h�Ɓh���[�}�h�̊Ԃ̋�ʂ́A�����ł͂Ȃ����A�ނ���A�`���I�Ȗ��m���ɑ��邢�����̌X���ɂ����ČŗL�́A���傫�ȍ������ɑ���X���ɂ���B ��ʂ͐�ΓI�ȗL�����ł͂Ȃ��A�Q�̑Η�����e�N�j�b�N�Amigrant melisma�̃��U�C�N�ƕω����������ʂ�̔����ɂ��\���̂悤�ɁA�܂���ɂ͂������ʂ����킯�ł͂Ȃ��BPeter Wagne���́A���̓_����ɖ��m�ɁA�������y�����������ɏo���āA�ؖ������B�Q�̑I�����������āB �ނ́Amigrant melisma (No. 21)�Ƃ��āA���������f�B�����X�g�����A���̗�Ƃ��āA�����I�ȃ��[�}�̃e�N�j�b�N�����グ���B�ނ͂��ꂼ��Agradual Domine praevenisti �� the alleluia Surrexit Dominus�����グ�����A�قȂ����e�L�X�g�ɂ�������炸�A�Q��versus�̃����X�}������ł��邱�Ƃ����������B����́Agradua�� alleluia�����ʂ̃p�b�Z�[�W�����B��̃P�[�X�ł͂Ȃ������ł͂Ȃ��A���̓���ȃ����X�}���g��ꂽ�B��̃P�[�X�ł��Ȃ��B ����䂦��X�́A�����I�`�����g�̂Q�̃O���[�v�Atract��gradual�́A���ۂ����߂����������̂ł���ƌ��_�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���҂́A�����̃L���X�g���k�̃`�����g�ɑk��A����䂦�A�ԐړI�ɓ��m�I���H�Ȃ̂ł���B�ЂƂ̃^�C�v�ɂ����Ă͓��m�I�����c��ł���A�ʂ̕��͂����̋��e�ł���Ƃ̎咣�͐������͂Ȃ��ł��낤�B���҂́A���܂��܂Ȓ��x�ɂ����ĕۑ�����Ă���B ��X�́A���ɍ��ݓ������W�ƁAthe melismas of graduals�� those of alleluias�̊Ԃ̐e�a���ɂ��Ă̘_�c�ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������������́A�`�����g�̗��j�I���W�Ɋւ��āA�V���Ȍ����Ƃ炵�A�����炭�́APeter Wagner�̗������n�ɂ��ẮA�����̏C�������Ƃ��낤�B�������A�������������̌����͂����炭�A�ނ̊�b�I������ʂ��Ė��炩�ɂȂ������Ƃ�Y���ׂ��ł͂Ȃ��B p252 �@�v���C���`�����g�̗l�������̌��@�ɂ����ẮACaput�̃����f�B���ǂ̒��x�Â��̂����A���y�I���n���猈�肷�邱�Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\�ł���B����́A12���I��������A���e�B�t�H���ɕt�����Ă���neumata�̂ЂƂƂ��Ă̋N���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炻��́A���Ȃ��Ƃ��A�l���ɂ����ĈقȂ��Ă���A���̓������1���I�͌Â�����ł���B����͉����̃����X�}�ɔ��Ɏ��Ă���A���̃����f�B�̓����́A��O���S���I���̂��邢�͏��Ȃ��Ƃ��`�����g�̔[�}�w�Ƃ̊֘A���������Ă���B����ȃ����f�B�l���ɂ��Ă̖L�x�ȃ����X�}�́A�A���u���V�I���ʓ��l�A���U���x���̂ɂ������Ό�����B����́A���[�}�̍��������o�Ă��炸�A����䂦�A�O���S���I���v�̑�����ɏ����ꂽ��i�ɂ����Ă����A��O���S���I���̓I������ێ����Ă���B �������������X�}�́A�T���āA�Z�C�����ψق̂悤�ȑΏ̓I�����̎�i�ō����I�ɍ���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ނ���ASaint-Yriei���̎��R�ɍ\�����ꂽ�łɎ��Ă���BThe melisma vellus from the cantus(the Ambrosian term for tract) Suscipiant Domine�́A�A���u���V�I�����X�}�̓T�^��ł���B�iEx.2)�@����́A���ꂽ����̎g�p��������������łȂ��A���Ɏl�x�̋����ɂ����āACaput�����X�}�Ɏ��Ă���B���������l�x�̋����́A���[�}���̂����A���u���V�I���̂ɓ����I�Ȃ̂ł���B 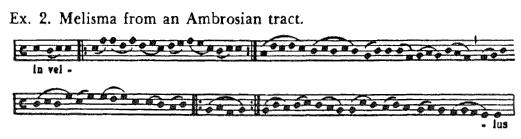 ���������^�C�v�̃����X�}�́A�A���u���V�I���p�[�g���[�ł͔��Ɉ�ʓI�ł���A����ȏ��@�ɂ�����Caput�����X�}���͂邩�ɗ��킵�Ă���B Caput melisma ��Ambrosian style�̊Ԃ̈�ʓI�ȗގ����͔ے�ł��Ȃ����A���܂肻���l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��X�����_�ł��邷�ׂẮA�[�}�I�������A���[�}���̂��݂��ɐڋ߂����W�����ꂪ����A�Ƃ������Ƃł���B p253 �@���̃A���e�B�t�H���̐��@�́A��ȔN��ւ́A���Ȃ��Ƃ��������̃q���g��^����B�����X�}���ŏ��ɑ}�����ꂽ�Ƃ��A��P�A��W���@�̉������܂��I������A�����������@�����̑��������Â��ƐM���闝�R�ƂȂ��Ă���B �� Caput melisma��tracts�� ���̓_�́Atracts�ɂ���Ċm�F�����B����́A�����Ƃ������̃~�T�ł̓��m�I�ȃ`�����g�ł���B�����ł́A�����͑�Q�A�W���@�ɓ��ٓI�ɑ����Ă���BPeter Wagner�̈ӌ��ł́A�����̐��@�͌Â�����̂��̂ł��邪�AFerretti�́A����I�ł͂Ȃ��ɂ���A��W���@���Q�̂����ł��Â��A�����T��̊�{�ɂ�����؋��������咣�����B�������Ȃ���A���ꂪ�ǂ��ł����Ă��A��W���@���`�����g�̌Â��w�ɑ����Ă��邱�Ƃ͋^���͂Ȃ��B Venit ad Petrum����W���@�ɑ����Ă��������́A���_�A���̃A���e�B�t�H���̎����ϋɓI�ɂ͏ؖ����Ă͂��Ȃ����A�Â�����̋N���ł��邱�ƂŖ����͂��Ȃ��B������ɂ���A���̐��@�́A�v���C���\���O�̂����Ƃ��Â��`�����ێ����Ă���B �@��Q���@��tractus�Ƒ�W���@�̂���Ƃ̊Ԃɂ́A�����f�B�̃^�C�v�ɂ����āA�����ȗl���I���Ⴊ����BPeter Wagner�́A��W���@��tractus�͑S�̓I�ɒZ���A��W���@��tractus�͑�Q���@�̂������verse�����Ȃ��A�V�N�ŗ͋����s�ɂ���ċ�ʂ����ƁA���������ĂƂ��Ă���B Wagner ��Ferretti���A�����f�B�l���̊�{�I�ΏƐ��ɂ��Ă͏q�ׂĂ��炸�A�����l���I��Œ�`���Ă���B��Q���@��tract�́A��r�I���������͈͂ŁA���Ƀ����X�}�I�ȃZ�N�V�������Ă���B�����A�O�x�ȓ��ŋߐڂ��A�~��`���悤�ɓ����Ă���B�������A��W���@�ɂ�����tract�́A����ʓI�ɁA�Q�̎l�x���d�ˁA���x������B����͂����A�I�N�^�[�u���x�ɂ܂Ŋg�債�Ă���B Ferretti�́A��W���@�ɂ�����tract���́A��Q���@�ɂ����邻������h���P���ɍ���Ă���h�Ƃ�������I�Ȏ咣�����Ă���B�ނ̎咣�ɂ͓������A��W���@��tract�ɂ����郁���X�}�́A��菭�Ȃ��莮�Ɍ������Ă���A�Ƃ������Ƃ�����B p254 ���ۂɂ́A�����́A�܂��������������B����ɁA�����͍\���ɂ����ĕ��G�ł���A��Q���@��tract��艹���i�s�ɂ����Ă�藣��Ă���B�����́A�\���I�ȉ����Ƃ��Ďl�x���D�݁A���ɉ��y�I�S�ł����āA�����f�B�̃f�U�C������|���Ă���B Caput melisma �́A��W���@�̃����f�B�l���ւ̍L���g����Ƙ������������ɂ����āA���ꂪ�m�F�����B����䂦�ɁA�A���e�B�t�H���I�̏����������I�Ȑ����������Ă���B��W���@��tracts��Caput melisma �̊Ԃ̉����i�s�̈�ʓI�ގ����́Atract Commovisti.�����"�����X�}est�ɂ����Č�����ł��낤�B�iEx.3)  ��W���@��tracts��Caput melisma �̊Ԃ̉����i�s�̈�ʓI�ގ��� ����A�����ɂ͒��ڂ��ׂ��`�d������Btracts�̃����f�B�l���́A�A���u���V�E�X�̃����X�}�l�����O���S���I�i�K�̂悤�ɁA�����������قƂ�ǂȂ��A�`���I�Ȏ��R��s�����ȗ���œ����Â�����B���p���ꂽ�����́A�l�x��-�\�A�\-�h���d�˂��A���@�̍Ō�̃\���ƂȂ����Ă���B�������l�x�́A�A���e�B�t�H��Venit ad Petru���ɂ����Č���I�Ȗ������ʂ����Ă���B�����ł́A�\�[�h�A��-�\�Ƃ��������L���Η��I����ɂ�������L����Ԃ�����Ƃ���������Ă���B �@tract�Ǝ������������Ă���A���e�B�t�H���̑��݊֘A�����݂��A�Ō�ɂ́Atuba���邢�͔����I�����Ɗ֘A���đ��݂���B�O���S���I���̂̂��̑��̂������̗l���̂悤�ɁAtract�́A�����̕ێ����������Ă���B��8���@�̓�d�̕ێ����́A�h�����邢�̓V���i������͌Â���i�݂̂ɂ�������Ȃ��j�A�����ă\����ɂ���A�\���́A�ێ����ƏI�~���̓�d�̋@�\��S���Ă���B���łɁA��243�ɂāA�������������Ă���A���e�B�t�H���������̕ێ����������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B����́A��P�Z�N�V�����ł�tuba�́A�h���ƃ\���ɗ��������B�Ō�ɂ́A�����ւƃV�t�g����B 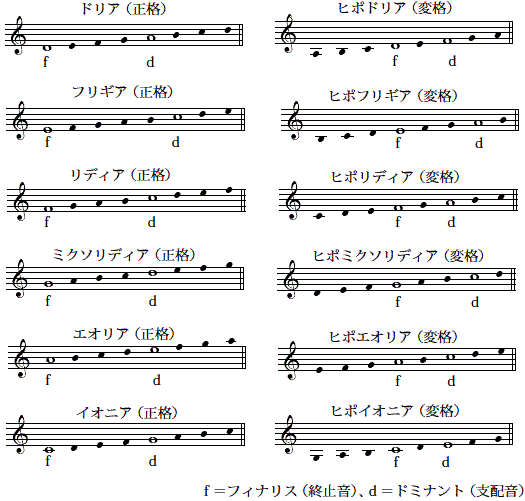 p255 ���̂悤�ȓ�d�́i���邢�͎O�d�����j�ێ����́A�v���C���`�����g�̂��܂��܂ȌÂ��^�C�v�ɂ����Č���邪�A����́Atonus peregrinus��A�������ۂɂ����鉞���I���я��ɂ�������B�����������������A���e�B�t�H���͌Â��ɈႢ�Ȃ��A�ƌ����悤�B�Ȃ��Ȃ瑽���̕ێ��������`�����g�́A�ʏ�̐��@�ɂ͎��܂炸�A�����͂����炭�́A�X�e���I�^�C�v�I�ȕێ����≹��������@�V�X�e���̕Ґ��ւ̂��������Ȃ̂ł���B����́A9�`10���I�ɋN�������B�A���e�B�t�H���͂قƂ��9���I�ȍ~�ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�B �@���y�ƓT��ɂ��Ă̘_�c�ɖ߂�ƁA��X�́A��X���������n���A�����ɕs�m���ł�����������������Ȃ��B�c�_�̓]���ɂ����ẮA��X�̌��݂̒m���̕s���S�ȏ�Ԃ��A���H�ɓ��B�����B���ɁA���n��ɂ����āB�ɂ�������炸�A�ȉ��̂悤�Ȍ��_�ɖ��m�ɒB���邱�Ƃ͉\�ł͂���B �@antiphon Venit ad Petrum�́A�T��ɂ����āA��O�I�n�ʂ��߂Ă���B����́A�~�T�ł��������ۂł��Ȃ��A����ȗ�q�A�D�̖ؗj���ł�pedilavium ���邢��mandatum�ɂ����Ďg��ꂽ�Bcaput��̂���т₩�ȃ����X�}�́A�������g�k�����̐�����ے�����Z�����j�[�̔�֓I�ȊT�O��\�����Ă���B�G��I�����́A���y�e���̓��̃|�C���e�B���O��`���Ă��邪�A���̂������́A�����X�}�Ɠ��l�ł���B��֓I���߂́A�n���̓T��ł����ʂł��邪�A���[�}����ɂ͂��܂�Ȃ��݂��Ȃ������B �A���e�B�t�H��Venit ad Petrum�̉��y�́A���[�}�̃��p�[�g���[�ɂ͑����Ă��炸�A���̔[�}�I�N���́A�ʏ�ł͂Ȃ����y�l���ɂ���Ċm�F�������Ă���B�`�����g�̓A���e�B�t�H���Ƃ��ĕ��ނ����ɈႢ�Ȃ����A����́A���̃����X�}�ɂ����āA�����I�`�����g�̖ڈ��S���Ă���B����ɁA���̉��y�ɂ����āA���̗�O�I�ȓT��I�n�ʂƕ��s���Ă���B ����́A���@�V�X�e���̓`���ɂ͌����Ȃ��B�l�x�̋����ƒ����̓����́A�A���u���V�I���́i�~���m���́j�̓����ł���A���[�}�T��̉����́A���m�N���̓�����S���Ă���Btract�̂悤�ɁA���[�}�̕W������v���C���\���O�̒ʏ퉻�⍇�����ɂ���Ă͐G����Ă��Ȃ����̂ł���B p256 �����̕ێ����́A�Õ��ȗl���������Ă���B�����X�}�̃����f�B�^�C�v�́A��8���@�Ƃ��ċL�q�����s���m�ȗB��Ȃ��̂ł���B�����X�}�́A���̂��̃����f�B�^�C�v�����L���邪�A��W���@��tract�ƂƂ��ɁA���̍\���͋��L���Ȃ��B����́Atractus��Ȃ̓`�������������܂������Ă͂��Ȃ����ɁA�����ɍ�Ȃ��ꂽ�悤�Ɍ�����B����́A�A���e�B�t�H���I�`�����g�ɑ���Õ��ȉ��t�̊g��������Ă���B �@�����������_�́A�����ώ@�����ɂ��Ă���B���������A���e�B�t�H���̎���Ƃ��Ă̌��i�Ȗ��A���̋N���̏ꏊ�A�`�d�������̐��@�̉𖾁A�͐��Ƃ̎�ɂ䂾�˂��Ă���Bmigrant melisma�̌����́A�^���Ȃ��A�����̃����X�}�Ɗ֘A������̍L���͈͂̉��ŋ����Ȃ�A�����q�K�R�I�ȁr�ɒf�ГI�ŁA�����I�ȕ����Œ�Ă��ꂽ���̂������邩�A�܂��͏C������B |