| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE
MUSIC�T |
| Caput: A
Liturgico--Musical Study 1. THE ORIGINS OF THE CYCLlC MASS p217 ���y�����̏����̎��ォ��A15���I��Mass cycles�́A�������L���ł��邳�܂��܂ȗ��R�ɂ���āA�w�҂≹�y�Ƃ̓��ʂȒ��ڂ��W�߂Ă���Bcyclic Mass�́A���l�b�T���X���y�̑�\�ŁA�i�W�����`�Ԃ�̌����Ă��邽�߁A���̊��Ԃ̉��y�̒��S�I���݂ƂȂ��Ă���B Ambro���̂悤�ȏ����̗��j�Ƃ́A���̌`���̌�̊��Ԃ̊T�O���`�����Ă��Ȃ��B�ނ�Geschichte der Musik �ɂ�����15�`16���I�̂��Ă̏͂ł́A�~�T�̃Z�N�V��������������A�قƂ�lj����c��Ȃ��ł��낤�B�~�T�Ȃ̒ʏ핶�̏z���A��ȉƂ̂��ׂĂ̌|�p�I��]�ƋZ�p�I���ʂ���������œ_�ł������Ǝ咣����̂͌֒��ł͂Ȃ��B ����́A18���I��19���I�̌����Ȃ̂悤�ɁA���y�I���l�̃q�G�����L�[�ɂ����āA�x�z�I�������Ȓn�ʂ��߂Ă���B �@�~�T�ʏ핶��5�̕�����1�̃T�C�N���ɑg�ݍ��킹��Ƃ����l���́A��ʂɐM�����Ă���قnjÂ��Ȃ��B�T��V���̊ϓ_����́AKyrie��Gloria�������āA�����̓~�T���j���Ԃɒ��ڑ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����Ēʏ핶�ł���s�ϕ����ꂷ��K�v���Ȃ������B���Ƃ����ꂪ�������Ƃ��Ă��A�������F��ƃ`�����g�ɂ���Ă���͏d�v�ł͂Ȃ��ł��낤�B�����̉��y�ł́A�X�̊y�͂������T��Ŏg��ꂽ�̂Ɠ����悤�ɉ��y�ɐݒ肳��Ă��邽�߂ł���B cyclic Mass�̍ŏ��̂��̂�14���I�Ɍ�����B������Mass of Toumai�ƌĂ�Ă�����̂ł���A�ŏ���cyclic Mass�ƒ����ԊŘ�Ă������A�����ɂ�Mass cycles�Ƃ͌����Ȃ��B���̍\�������͕ʁX�ɍ�Ȃ���A��ɔC�ӂɑg�ݍ��킳��A�P��̊y�͓��m�ɂ́A���y�I�ȊW�͑��݂��Ȃ��B�����́A���܂��܂ȗl���ō�Ȃ���Ă���B p218 �P�̒P�ʂƂ��č�Ȃ���Ă��邱�Ƃ��m���Ă���ŏ���cycle�́A�t�����X�̍�ȉ� - ���lGuillaume de Machaut�ɂ���ł���B���̍�i�ł́A�ʏ핶���U�̏z����ł���ƍl���āA���ɖ��͂Ȃ��B6�ڂ�lte missa est�ł���A�}�V���[�͉��y�ݒ�ɂ�����܂߂Ă���B�}�V���[�̃~�T�Ȃ́A�������铮�@�œ��ꂳ��Ă���Ǝ咣����Ă͂��邪�A���������咣�ɂ͋^�₪�悳��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���@���\���ɓ����I�ł͂Ȃ��A�{���ɓ���I�ȋ@�\�����邽�߂ɏ\���ɂ͔z�u����Ă��Ȃ��`���ł���悤�Ɍ����邩��ł���B���ۂɂ́A�y�͂̂������́A�v���C���`�����g���g�p���Ȃ�conductus�l���Ŏ��R�ɍ�Ȃ���Ă��邪�A���̂��̂́A�e�m�[���ɓK�ȃv���C���`�����g�����C�\���Y���E���e�b�g�̂悤�ɏ�����Ă���B���̃~�T�ɂ���Ď�����铝��́A��ɓT��I�Ȃ��̂ł���A���y�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �@ ���y�Ɨ�q�̌��т��̋�ʂ͏d�v�ȃ|�C���g�ł���A���̏d�v���͂���܂ł̋c�_�ł͏\���ɋ�������Ă��Ȃ������B����Ȃ��ł́AMass cycle�̈Ӌ`�Ɛ��_�I�w�i�͗����ł��Ȃ��B�~�T�Ȃ̕s�ϕ����́A�ʂ̓T��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A5�̉��y�I�Ɉ�ѐ��̂����i�̃Z�b�g�Ƃ��č�Ȃ����ׂ��ł���Ƃ����l����z������ɂ́A���ɑ�_�œƗ������l�������K�v�ł���B��҂̏ꍇ�A����̎�i�͍�ȉƂɂ���Ē���A�T��ɂ���Ă͒���Ȃ��B ���̍l�����́A�z����ʏ핶�̗��j�I�O��ł���A�����ɗ�q��̔z������܂�A�{���I�ɐR���I�ȊT�O����������Ă��邱�Ƃ𗠕t���Ă���B �|�p�� "��ΓI��"��i�́A�T��I�ȋ@�\��N�Q���n�߂Ă���B��X�́A�T�^�I�ȃ��l�b�T���X�̑ԓx�����A�����Ă���͂܂������Acyclic Mass�̐��_�I�w�i�������郋�l�b�T���X�̌|�p�N�w�Ȃ̂ł���BMass cycle�̎n�܂�́A���y���l�b�T���X�̎n�܂�ƈ�v����B p219 �@����䂦�Acyclic Mass�̔��W�ɂ����錈��I�^�[�����A15���I�����ɋN�������Ƃ́A�قƂ�Nj����ɂ͓�����Ȃ��B�����A�������y�f�ނ��g���Ēʏ핶�̊y�͂ꂵ�悤�Ƃ����ŏ��̎������s��ꂽ�B �����ł�2�̕��@����ʂ���K�v������B ��1�ɁA��Ȏ҂́A1�܂��͕����̐����ɂ����āA�e�y�͂̊J�n���ɓ����܂��͋͂��ɕω������`�ԂŌJ��Ԃ����Z�������I�ȓ��@���g�p���āA�S�̂̏z�̃��b�g�[����������B �������A�����̃��b�g�[�̎n�܂�́A�ŏ��̐����߂ɂ����߂����A��i�̂��̌�i���\���ɂ͉e�����y�ڂ��Ȃ��B ��2�ɁA��ȉƂ́A�\���I�Ȑ����Ƃ��Ă��ׂĂ̊y�͂̊�b�ƂȂ�A����䂦�`�����@�����͂邩�ɋ��͂ň�т�������v���Ƃ��ċ���������̂Ƃ��Ă��e�m�[���ɂ�����cantus firmus���ؗp�����S�B�`�����@��cantus firmus�́A�����ׂ肠�킹�Ŏg���Ă���B 4 ��R�̉\���́A���̂Q�Ƃ͖��W�ł��邪�A�|���t�H�j�[�̃v���C���\���O�~�T�Ȃł���B����́A�ʏ핶�̃`�����g�̃p���t���[�Y�ł���B���y�I�f�ނ́A���ꂼ��̊y�͂ňقȂ��Ă���̂ŁA�����ȈӖ��ł̉��y�I������������Ƃ͂ł��Ȃ��B����͒����̉��y�ɂ����Ēm���Ă����T��I�ȓ���̊g��ł��邩��B�������A���l�b�T���X���̃v���C���\���O�~�T�Ȃ́A���ꂳ�ꂽ�e�m�[���~�T�Ȃ̃��f���Ƃ���A���̉��y�l����ʂ��āA�|�p�I���ꐫ�𐬂������Ă���B �@2�̓�����@(�`�����@��cantus firmus)�́A�Ɨ����Ĕ����������A�����[�����ƂɁA���m�ɕ��s���Ĕ��W�����B �ŏ��̒i�K�ł��鏉����cycle�́A�O�����A�ƃN���h�A�܂��̓T���N�g�D�X�ƃA�O�k�X��2��g�ɂ����y�݂͂̂��琬���Ă���B �����炭�����̊y�͂̃J�b�v�����O�́A�e�L�X�g�ɂ���đ����ꂽ�̂ł���A�e�O���[�v�͋��ʂ̃e�L�X�g�\���������Ă���B Gloria��Credo�́Apsalmody�̂悤�Ɍ��݂ɍ\�z����ASanctus��Agnus�͂R��J��Ԃ��\�����Ƃ��Ă���B ��҂�Kyrie�̏ꍇ�ɂ����Ă͂܂�A���鏉����cycles�ł́AKyrie�����̂��̂���Sanctus.Agnu�̃O���[�v�ɖ��ڂɊ֘A���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���B ���`�����@�~�T�ȁ� �@�����_�œ���\�Ȃ��ׂĂ̏؋��ɂ��A�`�����@�Ŏn�܂������I��cycles�́Acantus firmus�̂��̂��������������������ƌ����邩������Ȃ��B���������āA�O�҂��ŏ��ɋc�_�����ł��낤�B�`�����@�Ŏn�܂��y�͂̑g���́A�������̃\�[�X�ɂ���ď\���ɗ�����Ă���B �ŏ��̎����́A���悻1410-20�N����Turin MS( TuB)�Ɍ��o�����B���炩�Ɉꏏ�̗l���ɑ����Ă���5��Gloria-Credo�̑g���L�^���Ă���5�B�����̂����̂������́A�`�����@�������Ă��邪�A�킸���ł���B p220 ��K�͂ȑg�������ł������̃\�[�X�́A���XPiacenza�̂��߂ɏ����ꂽ�{���[�j��MS�iBL�j�ł���A���̂��Ȃ�̕�����Gloria-Credo�̑g�Ő�߂��Ă���B�����̑����́A������ȉƂɂ����̂ł���AHugo de Lantins (fol. 84V-86) �� Dufay (fol.33v-38�j�ɂ���i�ŁA���ɂ͂�����Ƃ������b�g�[�W��������B������Hugo de Lantins �ɂ�鑼�̍�i�́A���m�ȃ��b�g�[�������Ȃ��B���Ƃ��AAntonius de Civitat�ifoll�B81V-84�j�B�@����ɂ��̑��́A�ʂ̍�ȉƂɂ���ď����ꂽ��i����\������A�{�����g�ɗގ����āA�M�L�҂ɂ���đ����ꏭ�Ȃ��꜓�ӓI�ɑg�ݍ��킹���Ă���B �Ō�̃P�[�X�ł́A���炩�ɁA���b�g�[�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �{���[�j��MS�iBL�j�ɂ�Gloria-Credo�̑g�݂̂��܂܂�Ă���B�I�[���h�z�[��MS��Leonel�ɂ�邠���̍�i�ł́A�~�T�̒f�ЁiGloria-Credo�����Sanctus-Agnus�j�̑g�����B���Ɏ�������Ă���B�M�L�҂͂܂����ۂɂ������O���[�v�����Ă��Ȃ������BAosta and Trent MSS��MSS�ł́AGloria-Credo��Sanctus-Agnus�̑g�����F�߂��Ă���B Tr�̕M�L�҂͎��X�A�����ꂽ�����ɂ���āA�g�̊Ԃ̂Ȃ�����w�E���Ă���B�ʖ{����AGloria-Credo�g���ŏ��ɑg�ݍ��킳�ꂽ���̂ł���A���̂��ƂɁA�Ή�����Sanctus-Agnus�g�ɂ���ĕ⊮���ꂽ�Ɛ������邱�Ƃ��ł���B �@�`�����@�~�T�Ȃ̎��̃X�e�b�v�́A1�̍�ȃT�C�N����2�̕ʁX�̑g��g�ݍ��킹�������ŁA2�̖��W�ȒP��̍�i�̑g�����������x���ŌJ��Ԃ��B�{���[�j��MS�iBL�j�ɂ�Zacharia-Dufay�ACiconia-Arnold de Lantins�Ȃǂ̂��������i�����́jcycles���܂܂�Ă���B Ciconia�ALantins��cycle�́A���Ɍ��y���ׂ����l������A�ȉ��̂悤��3�̑g����Ȃ��Ă���B �i1�j�C���g���C�gSalve sancta paren��Lantins�ɂ��Kyrie �i2�jCiconia�ɂ��Gloria and Credo �i3�jLantins�ɂ��Sanctus��Agnus Lantins�ɂ��ݒ�́AMissa de BMV�iGrad.Rom.IX�j�̃v���C���\���O���g�p���Ă��邽�߁A�����I�ȃv���C���\���O�~�T�Ȃ��\���Ă����i�C���g���C�g���܂��A�e�m�[���ɂ����ẮA���l�Ɉ����Ă���j�B������Ciconia�̑g�͖`�����@�œ��ꂳ��Ă��炸�A���R�ɍ�Ȃ���Ă���B����ɂ�������炸�A�َ�̑g�͕����I��cycle�ɃO���[�v������Ă���B�����ʖ{�ɂ́A����ł́A��l�̓�����ȉƁiLymburgia�AArnold de Lantins�ADufay�j�������������Ȃ����S��cycles���܂܂�Ă���B�����́A�����ꏭ�Ȃ���A���b�g�[�I�`���œ��ꂳ��Ă���B p221 Dufay��Missa Sancti Jacobi�ɂ́A�ʏ핶�S�̂����łȂ��A�ŗL��Plainsongs�Ɋ�Â��ŗL���̕������܂܂�Ă���B����͓��ʂȐ������ۂł���ABL�̏�����cycle�̊Ԃœ��ʂȒn�ʂ��߂Ă���BLymburgia�� Lantins�ɂ��Mass cycles�́A���炩�ɓ����`�����@�ō���Ă���B����ł�Gloria-Credo�̑g�A��������ł�Sanctus-Agnus�̑g���قړ����悤�Ɏn�܂�A���傫�ȃT�C�N����2�̖��ڂɊ֘A����g���`�����邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�ǂ���̃P�[�X�ł�Kyrie�͂����Ԃ�قȂ��Ă���B�䂦�ɁA���Ƃ��Ƃ̑g���͂���ɁA���b�g�[�`���ł̓��ꂳ�ꂽMass cycles�̍ŏ��̂悭�m��ꂽ��ƂȂ��Ă���B���̂悤�ȃ^�C�v��cycle�͎��Lymburgia�ALantins�ADufay�Ɋ֘A���Ă���̂ŁA��X�͂��ꂪ�A1425�N���̃u���S�[�j���y�h�̍�ȉƂ����ɂ���Ĕ��W������ꂽ�Ɖ��肷�邩������Ȃ��B ��cantus-firmus�ɂ��Ƃ���Mass cycles�� �@tenor Mass���邢��cantus-firmus cycle�̍ŏ��̏o���́A�i�`�����@�~�T�Ȃ��j���x���A15���I�̑�Q�l�����I�ł���A��ɁA�p���y�h�̍�ȉƂ����A����Leonel Power��Dunstable�Ɗ֘A���Ă����B�����Ɋւ��ẮATuB�AOH�ABL�́Acantus-firmus��cycle�̑��Ղ͎����Ă��Ȃ��Bcantus-firmus������Mass cycles�́AAosta �� Trent MSS��Bodleian Library�ŐV���ɔ������ꂽ�t���O�����g�̂悤�Ȍ�̃\�[�X�ł͌����Ȃ��B �@�ʏ핶�̃v���C���\���O����ؗp���Ă��Ȃ��e�m�[�������~�T�Ȃ��������Ƃ́A�����̌`���ł���C�\���Y�����e�b�g�ɂ���đ����ꂽ�B���̔��W�̌��_�́A�C�\���Y���Z�p���~�T�Ɉڂ����Ƃł���A������OH��LoF�̑����̒P��̃C�\���Y���~�T�Ȃ�������Ă���B�z�I�ȍl�����Ɋւ��ẮA�ʏ핶�S�̂̐ݒ�́A�T��̋@�\���ʏ핶�ɊW���Ȃ��Ɨ������e�m�[���ɂ���ē��ꂳ������Ƃ��A���L���Ă������Ƃ��d�v�ł���B�}�V���[�����̃X�e�b�v��ł��Ȃ����Ƃ́A��L�Ŏw�E����Ă���B�ނ̃C�\���Y���e�m�[���́A�ʏ핶����̃`�����g�ł���ALeonel�iAo 16g-170�j�̃O�����A�ƃN���h�iAo 16g-170�j�̂悤�ɁA�y�͂���y�͂ƕω����Ă���B p222 ���̑g�ݍ��킹�́A���j�I�ɏd�v�ł���BLeonel���g���L�����A�̏I���ɍ̗p�����V���������Ɠ`���I�Ȃ��̂��̒��ԓI�Ȃ��̂ł���B�l�����̃~�T�Ȃɂ����āA�e�m�[���͂�͂�T��I�ł͂��邪�A�T���āA�~�T�ȂƂ͖��W�ł���B�㐺�������X�ɂ��̍H�v��������Ă��A�e�m�[���͈��������C�\���Y���ł��葱���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������B����ɉ����āA�C�\���Y���łȂ��e�m�[���̐ݒ�́A�ʏ핶�ɂ͂Ȃ��݂̂Ȃ��\�[�X���痈�Ă���B�����̐ݒ���A�قƂ�ǂ��p���N���łȂ̂ł���B �@cycle�Ɍ���������I�ȃX�e�b�v�́A�`�����@�Ƃ͈قȂ����A����I�Ȋm�ł���v�f���m�����������e�m�[���̊�b�ɂ����āA2�̊y�͂�g�����A�S�̂̉��y�\���𐮂��邷�邱�Ƃł���B Dunstable�� Jesu Christe fili���Gloria��Credo �́Acantus firmus����������Mass cycles�������Ă���B 2�̊y�͓͂����C�\���Y���e�m�[���Ɋ�Â��Ă���A�ǂ�����`�����@�͎����Ă��Ȃ��B�p���̍�ȉƂ͑嗤�̍�ȉƂقǔ��W���Ă͂��Ȃ��悤�����A����́A���ʂ̃e�m�[�����K�v�Ƃ���Ȃ��������߂ł���Bcantus firmus�ɂ����2�̊y�͂�g�ݍ��킹��Ƃ����l�����m�������A�ʏ핶�̂��ׂĂ̊y�͂ւ̂��̊g��́A�������������ł���B �ŏ��̂悭�m��ꂽ���S��cycle�́ATrent codices �̌Â������� Aosta MS�Ɏʕ�����Ă���ALeonel Power��Missa Alma redemtoris��Missa Rex seculoru�����܂�ł���APower�ɂ��Ă�Tr�ɁADunstable�ɂ��Ă� Ao �ɋL����Ă���B�O�҂̍�i�́A�C�\���Y���I���J��Ԃ����e�m�[���Ɋ�Â��Ă���A��҂͎��R�ȃ��Y���Ń����f�B���ω����Ă���B���������āA�e�m�[����2�̃^�C�v�A�ω��̂Ȃ����̂Ə_��Ȃ��̂�����BBodleian�̒f�Ђɂ́AMissa Requiem eterna�̃O�����A�A�N���h�A�T���N�g�D�X�̈ꕔ���܂܂�Ă���A���l�ɃC�\���Y���̃e�m�[����ɍ���Ă���B����̓��N�C�G���i�O�����A���܂܂Ȃ��j�ł͂Ȃ��A���҂̂��߂̃~�T�Ȃ���̃C���g���C�g���Mass cycle�ł���B p223 �p���̍�ȉƂɂ�鑼��cycle�́A�s���S�Ȍ`���œ`����Ă���B���́ADunstable��Da gaudiorum premia���Credo��Sanctus �ł���B�����ł���͂�A�e�m�[���̓C�\���Y���ł���B�B Ao�Ɍ�����2�̊y�͂͂����炭�A���S��cycle�ɑ����Ă��邪�A���݂ł͎���ꂽ���̂ł���B�Ȃ��Ȃ�ACredo��Sanctus�̑g�ݍ��킹�́A���܂�Ȃ�����ł���B�ł������̉p����Mass cycle�́A���ׂēT��I�Ȃ����Ɋ�Â��Ă���A���ɖ`�����@�̎n�܂���������Ȃ��BLeonel Power��Missa Alma redemtoris�́A���������A�`�����@�������������Ȃ��B���̍�i�ł͂܂������Ȃ��B ���I�̂���ɂȂ��āA�`�����@�~�T�Ȃ́A�p����Mass cycle�̕W���I�ȓ����ƂȂ邪�A�^���Ȃ��A�����Franco-Flemish�̖͕�ɂ����Ăł���B�g�������y�͂̔z���S��Mass cycle�Ɉ����p���ꂽ���Ƃ́AMissa Rex seculoru���ɂ����Č��邱�Ƃ��ł���B �@ �@��L�̍�i�́A���ۂɂ��̃^�C�v�̏����̗�ł���Ǝ������͂ǂ̂悤�ȏ؋��������Ă��邩�H�����̗��_�Ƃ�cyclic Mass�̔��B�ɂ��Ă͉��������Ă��Ȃ��B��i�̂ǂ�������m�ɓ��t��t����Ă��Ȃ��B���������ߋ��̃f�[�^�Ƃ��Ď����Ă���̂́APower �� Dunstable�Ɋւ��鍱�ׂȓ`�L�ł���B���I�l���E�p���[��1445�N�Ɏ��S�������Ƃ��������Ȃ�A�ނ́AMass cycles��15���I�̑�2�l�����ɂ̂݁A�����炭�͔ނ̐l���̍Ō��10�N�ŁA��Ȃ������ƂɂȂ�B����͕ʂƂ��āA�\�[�X���g�̃��p�[�g���[����͂ނ��댈��I�Ȑ��_������B Ao�̑啔���́A�~�T�̊y�͂��i���ׂẴL���G�Ȃǁj�����̂����ŁA�N���X�ɂ���ăO���[�v�����Ă���̂ɑ��A�����͎��X�Ԉ���đg�ŃO���[�v������Ă���B Leonel��Missa Alma redemptoris�́A�ʖ{�S�̂ł̗B��̊��S��cantusfirmus��cycle�ł���A����cycle���ATr�iCodex 87�j�̍ŌÂ̕����ɂ������B�ؗp���ꂽ�e�m�[���̕����I�܂��͊��S��cycle�́A �����Ƃ������̃\�[�X�iAo�ATr 87��92�j�ɋA�����邪�A�قƂ�ǂ��C�M���X�̍�ȉƂɌ����Ă���A���̌`���̍쐬�ɕs���ȍv���ɂ��Ă͋^���̗]�n�͂Ȃ��B�z�I�ȃe�m�[���̃~�T�Ȃ͑啔���A���l�T���X���y�̉p���y�h�̉e���ō���Ă���B p224 �@��������m�������ƁA���̌`���͂����Ƀ��[���b�p�̉��y�ɕ��ՓI�ɍ̗p���ꂽ�B Dufay�̃��[�_�[�V�b�v�����̓_�ł�����I���������Ƃ͋^�����Ƃ��ł��Ȃ��B �Ȃ��Ȃ�ADufay�̌㔼��Masses�͏��cantusfirmus���̗p���Ă����̂ŁA�ނ̔��W�̂��̒i�K�ŁA�e�m�[����cantus firmus���z�I�ȓ���̍ł����S�Ȏ�i�ł���ƔF������Ă����ɈႢ�Ȃ��B �ނ�cycles�́A�_���ȃ����f�B�[�iCaput�AEcce ancilla�AAve regina�j�����łȂ��A�����I�Ȃ��́iL'homme arme�ASe la face�j�ɂ�������B Dufay��cantus firmus�̌��𐢑��I�ȕ���Ɋg���������łȂ��A�e�m�[�����n�܂�O�ł̃��b�g�[�I�`�������s�ϓI�ȊJ�n���s�����B�䂦��Dufay���A����̂��߂̂Q�̎�i��g�ݍ��킹�������łȂ��A���I�̌㔼���x�z���A�T�^�I��cyclic Mass�̍l�������`�������`���ɂ����āAcyclic Mass�ւƓ����Q�̗�����������̂ł���B �@�`�����@��������cantus firmus �������Ȃ�Mass cycles�́A���S�ɂȂ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ������B����̓I�P�Q���̍�i�A���Ȃ킿�AMissa Quinti toni�ɂ݂�ꂽ���A�]���I�ȗ���ł͂������B �@�ȏ�́A��܂��ȊT�v�Ƃ��āA���ɒZ�����ԓ��ɋ��ٓI�Ȑi���𐋂������y�̌`�Ԃł���AMass cycles�̋N���ł���B ���̌`���Ɋւ���2�̓_���A�܂��G����Ă��Ȃ��B���Ȃ킿�A �@�O���S���I���̂̒ʏ핶�ɂ����āA�z�I�ȍl�����ǂ̂悤�ɒ��ꂽ�̂��A�Ƃ��������A �Acantus firmus �̑I���ɂ������ǂ̂悤�Ȋ���������̂��A �Ƃ������Ƃł���B �ŏ��̓_�́A�s�[�^�[�E���O�i�[�ɂ���āA�Ȍ��ɘ_����ꂽ���A����͂��O��I�Ɍ������鉿�l������B�v���C���`�����g�̒����I�ȃR���N�V�������A�N���X���ɂ��ʏ핶�̃����f�B���O���[�v�������Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���A���̎�茈�߂�16���I�ɂ���������Ƒ����Ă����B OH��Ao�̌㔼�Ɍ�����悤�ɁA�����̒����̑����̉��y�\�[�X�ł́A�������ނ��D�悳���B�����̏j�Ղ�T��I�@��̂��߂̒P��̒ʏ핶�ɂ�����v���C���\���O�̔z��́A���j�I�Ȕ��W�ɉ߂����A���ۂɂ́AOrdinarium Missae�Ƃ����p����A�����̊��K�ɂَ͈��ł���B �s�[�^�[�E���O�i�[�̈ӌ��ł́A���ꂳ�ꂽ�N���X�����́A�|���t�H�j�b�N��Mass cycle�ɂ���đ����ꂽ�B15���I�̌㔼�ɂ́A�|���t�H�j�[�̎ʖ{�́A��ʂɁAMass cycles�ɂ���āA�O���[�v�����ꂽ�BModena�AEst�B lat 456�A�Ɍ�����悤�ɁB�����Ă��̏����̓��l�T���X�̎ʖ{�̓T�^�I�Ȕz��ƂƂȂ�B�������A�|���t�H�j�b�N�Ȑ_���ȉ��y���v���C���\���O�̃R���N�V�����̂��߂̃��f����ݒ肵�Ă��邩������Ȃ��Ƃ������[�O�i�[�̍l���́A���̋t�������̉��y�ɂ͈�ʓI�ɓ��Ă͂܂�Ƃ����������l����Ƃނ�������ł���B p225 15���I�̑啔���̃O���S���I���̂̃R���N�V�����́A1�̃N���X�̃`�����g���ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��A�����̃\�[�X�̂͂�����ʏ핶�ɃO���[�v�����A����ȋ@��̂��߂ɍ�Ȃ��ꂽ�B�|���t�H�j�[���y�̏�����cycle�̍ŏ��̒��������TuB�́A�T�̃O���S���I���̂�Mass cycles�A�Q��Missae breves�A3�̊��S�Ȓʏ핶�������Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���Bplainsong�̒ʏ핶�́AMachaut�̃~�T�Ȃɐ�s������̂ł͂Ȃ����A���l�T���X�̉��y�I�ȓ��ꂳ�ꂽMass cycles���͑��������B �@�Ō�ɁAcantus firmus�̃X�^���_�[�h�̑I���̊�b�ƂȂ錴�����������Ă݂悤�B���b�g�[�I�`�����y�́A�����Ƃ��Ď��R�ɍ�Ȃ���Ă����̂ɑ��A���̐�����cantus firmus�ł����A ����̓v���C���`�����g����ؗp���ꂽ���̂ł�������A���邢�͐��Ȃ�܂��͐����I���̂����ꂩ�ł���B����ꍇ�ɂ́Acantus firmus�́A��ȉƂɂ���đn�삳��邱�Ƃ����蓾��isoggetto cavato dalle vocali�\���~�[�[�V�����̃V���u���Ȃǁj�B���l�b�T���X�̍�ȉƂ��\���I�Ȑ�����I�Ԃ��Ƃɂ����Ė��炩�ɖ����ʂɂȂ��Ă������Ƃ́A�p�ɂɌ����Ă���B �����̌h�i�ȍ��ɂƂ��ăV���b�N�Ȃ̂́A���u�\���O��Mass cycles��cantus firumi�Ƃ��Č���Ă��邱�Ƃł���B����͊m���ɓT��̏������߂邱�Ƃ������Ă��邪�A����Ɠ����ɁA���l�b�T���X�������ނ��뒆���ɑ傫���L�����Ă��������Ɛ_���̑��ݓI������������Ă���B�_���ȍ�i�̐����I�ȃe�m�[���́A���ۂɂ́A�����̃��e�b�g�̈�Y�ł���B����ɁA�}���A�̌���Ave regina�̂悤�Ȑ_����cantus firmus�̑I���́A���炭�T��̊ϓ_����́A����ɋ����ׂ����̂ł������ƍl������ׂ��ł���B���̂悤�������́A�~�T�ł͂Ȃ��A�������ۂʼn̂��Ă����B�����āA���ɂ́Acantus firmus�Ƃ��Ă̖������ʂ����Ă����B����́A��q�̋@�\�������Ȃ������𑫏�ɂ��邽�߂ɍ~�i���ꂽ�B �ʏ핶�Ɛ������ۂƓT��I�����f�B�ƁA�V���I�ȃ����f�B�[�̔�T��I�Ȏg�p�̍����́A�����炭�A�����I��cantus firmus�̑I�������A�T��I�ȑÓ����̐[���Ȍ��@�������Ă���B������ɂ��悻��́A�T��I�ȍ����������N�������Ƃ͂Ȃ��B���l�b�T���X���̉��y�Ƃ́Acyclic Mass���ł����Ђ̂����Ȍ`�ԂƔF�����A�@����̑������A�ԐړI�����łȂ��A�Ƃ�킯���y�I������ł��d�������{���I�Ȍ|�p�I�A�v���[�`�Ƃ��ĔF�߂��B�ނ�͂��͂⒆���̉��y�Ƃ̌��i�ȓT��I�ȑԓx�ɂ���ē�����Ȃ��Ȃ����B Mass cycles���A�I�y���ƃV���t�H�j�[�̖��J���ȑO�̂����Ƃ��g�債����Ȍ`�Ԃł���A�����A�T�特�y�́h�D�G���h�Ƃ݂Ȃ���Ă����̂��A���ۂɂ́A���l�T���X����̗�q���J����߂錋�ʂƂȂ������Ƃ͋t���I�ł��邩������Ȃ��B ��226 2. THE SOURCE OF THE CAPUT MELODY �@Mass cycles��,���̐R���I�Ō|�p�I�ȏd�v���ł��̂ӂ��킵����F�߂��Ă��邪�A�܂��������������Ă��Ȃ������̖������̋^�₪�c���Ă���B�T���āAcantus firm�́A��i�̈�ʓI�ȃ^�C�g��������Ă���B���������ؗp�����f�ނ����̌`�Œm���Ă���A��Ȏ҂�������ǂ̂悤�ɗ��p�������A�܂�����ɓK�����邩�ǂ����𐳂����]�����邱�Ƃ��ł���B Dufay�ɂ��Ave regina celorum��I�P�Q����De plus en plus�̂悤�ȃ~�T�Ȃɂ����āA�Ȗ��͎������ɒ��ړI�Ƀv���C���`�����g���A���邢�͎�����A��ȉƂ������p���A�����̍�i�ɂ����āAcantus firmus�́A�w���������A����ł��Ȃ��Ȗ��������Ȃ��B��҂̏ꍇ�A�Ȗ��́A�ǂ��ɂ����蓾�Ȃ������̓��H�W���̂悤�Ȃ��̂ł������B�Ȃ��Ȃ�A����͌����āA�I���W�i���ȍ�i�ɂ͓����Ȃ���������ł���B �ʖ{�̎n�܂�Ō��y���ꂽ�����f�B�́A�����̎ʖ{�ł͂悭�m���Ă������A�����́A���͂�15���I�̃��p�[�g���[�ɑa���Ȃ�A���邢�́A��5���I�̕ϑJ�ɑς�������ꂽ���̍�i�����m��Ȃ��������ɂ́A�Ȃ��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ����B�����̉��y�w�̃V���[���b�N�z�[���Y�����́A�L�͈͂ɎU����Ă���\�[�X����̏؋��Ə����Ȃ����킹�āA�~�T�ȃ^�C�g���̓���������悤�Ƃ����B �n�܂�����S�Ɍ����Ă���~�T�Ȃł́Acantus firmus�̓��肪���݂��A���������R�F�߂���@��������B��ȉƂ������I�ȍʐF���̗p���Ă���ꍇ�́Acantus firmus���S�����݂��邩�ǂ��������߂邱�Ƃ͕K�������\�Ƃ͌����Ȃ��B2�̋ꋫ�̂ǂ��炪���܂�]�܂����Ȃ��������߂�̂͊m���ɍ���ł���A���ɉ��̎w�����Ȃ�������i�ǂ���̏ꍇ�ł��A���Ȃ��Ƃ��A�\���I�Ȑ������ؗp�ł͂Ȃ��A��ȎҎ��g�ɂ���ď����ꂽ���̂Ɖ��肷�邱�Ƃ͂ł���j���邢�́A�P�ɒm���Ă��Ȃ��\�[�X�̋Ȗ��ł�������ɂ����ẮB p227 �@ ���̌���������~�T�Ȃ́A���̃J�e�S���[�ɑ����Ă���B 3�̗L����Caput�ɂ��~�T�Ȃ́A15���I��3�l�̎�v��ȉ�Dufay�AOkeghem�AObrecht�̍�ł���B�ނ�͂��ׂāA����cantus firmus���g�p���Ă���A��߂����P�P��Caput�i���j�ɂ���ď�������Ă���B 3�̍�i�͒����ԁA��ʂɓ���\�ł��������Acantus firmus�̎��ʂɂ͎��s���Ă����B ��̂���I�[�����ACaput Masses�ɂ͂���B���������m���Ă������A������3�l�̍�ȉƂ́A���̓���̃����f�B�[���g���āA�S�ʓI�ȃ~�T�Ȃ��������Bcantus firmi ���ؗp���āA���x���J��Ԃ��ݒ肷��̂���ʓI�ł������B����͂܂��A���ړI�Ɉˑ����Ă��Ȃ��Ă��A����܂ŋC�Â���Ă��Ȃ����������̓_�ɂ����āA�e�m�[���̃����f�B�[�̈����ɂ������A�ԈႢ�Ȃ��ގ��_���J������悤�ȕ��@�ŁA�t�����h���y�h�̂���3�l�������g�p���Ă������Ƃ͒��ڂ��ׂ��ł���BCaput�̃����f�B�[���̂��͓̂�߂��Ă���A���̕s���ȋN���̂��߂ɂ����ł͂Ȃ��A���̐_���Ȃ�N���ɂ��ċ^�O������������ٓI�Ȑ����I�����̂��߂ɂ��A���f���Ă���B �@�l�X�Ȏ咣�Ɨ��_���A�_��I�ȃ����f�B�[�ɂ��Ĕ��W������ꂽ�B�������A �����͖����قƂ�lj����͂��Ȃ������B�I�[�X�g���A�l��Denkmaler �̔łւ̒ɂ����āAFranz Schegar�́A���Ȃ��Ƃ�caput�Ȃ��������R�̓T��e�L�X�g�ɒ��ڂ����B���̂悤�ȃe�L�X�g�̃��X�g�́A�������Ɋg���ł������A�����̂�����1�ł����Acantus firmus�Ƃ̂ǂ̂悤�ȊW�ł��������Ƃ͂Ȃ������BSchegar�́A�ނɂ���Ĉ��p���ꂽ�R�̃e�L�X�g���Acaput�̃����f�B�������Ă��邩�ǂ����ɂ��ẮA���Ƃ��Ďc�����B �ގ��g�̌��y�Ƃ��Ă͖��炩�ɕs�����ł���A�ނ͂ނ���ˑR�A�����f�B�[�̐������������N���ł���A�ƒf�������B p228 cantus firmus�̃��e����̓����́A���̈ӌ��ɐ��m�ɂ͓��������A���ɁA���鉹���̕p�ɂȎg�p�́A�O���S���I���̂̐����Ƃ͂�������Ă����B���̂��߂ɁA�����́A���Ȃ��Ƃ��O���S���I���̓I�ł͂Ȃ��v�f�́A���̖������悭�ʂ����Ă����B �c�O�Ȃ���A�_���ȗl���Ƃ������ꂽ�h�����l���h��15���I�̉��y�łǂ̂悤�ɍ\�����ꂽ���ɂ��Ẳ�X�̒m���́A�����Ă���A�J�e�S���[�Ƃ��Ă̎咣������ɂ͕s����ł��낤���ӎ��̕Ό��ŋ����ʂ��Ă���B �@�����c�_�������ׂĂ̑��̊w�҂́A�����f�B�[ �̂���܂ق����_���ȋN����K�v�Ƃ������A����́A����炪�ޓ������ӂ��Ă���B��̃|�C���g�ł���B�s�[�^�[���O�i�[�́A�v���C���`�����g�̐��Ƃ̌P�����ꂽ�ڂŁA cantus firmus�̃����X�}�I������F�߂āA���ꂪ�~�N�\���f�B�A���@��alleluia�� jubilus �ɈႢ�Ȃ��A�ƒ�Ă��Ă���B�������A ���̃����f�B�[�ɂ́Aalleluia�͑��݂��Ȃ��B ����AObrecht's Mass�Ɋւ���ނ̕Ҏ[�ɂ����āAJohannes Wolf �́A cantus firmus�͂����炭�A�����j���ɉ̂�ꂽ tract Eripe me�̂���Z�N�V��������R�������A�Ǝ咣���Ă���B���ɁA����verse Caput circuitus �́A�d�v�Ȍ��t�ɂ����ă����X�}�Ŏn�܂邯��ǂ��A�Q�̃����X�}�́A�ǂ������Ă������Ƃ͌����Ȃ��B �@����ɕʂ̒�Ă�����B�����āA���ɍI���Ȃ��̂ł��邪�A�����Andre Pirro������ꂽ�B�����f�B�͓����悭�m���Ă����ɈႢ�Ȃ��A�ƌJ��Ԃ��A �ނ́A"���h�Ƃ������ɒ��ڂ��A����͓���Ȑ������ۂɑ����Ă���A�ł���ɂ��ꂽ�}���҂̂��߂ɍ�Ȃ��ꂽ�A���邢�̓J���u���[�̋���œ��ʂɑ��h���ꂽSt. Andrew�̂��߂̝R��̖|��ł���A�Ƃ����^����������BPirro�̌����Ȑ��_�́A��q���̏��l�����i�ނ̑O�C�҂͎��s�����j�A����ɂ�������炸�A�����Ȍ��ʂ������炳�Ȃ������BPlamenac�́AWagner��WoIf�̑��l�Ȉӌ�����Ă���B �����g�̃����f�B�ɑ��錤���ł́A����͂����炭�Z�N�G���c�B�A�ł��낤�Ƃ����^�₩�瓱���o���ꂽ�B���̉����́A�����f�B�[�̕ϑ��I�ȓ����ƃ����X�}�����̌J��Ԃ��\���ɂ���Ď������ꂽ�B���������̓Z�N�G���c�B�A�ɋ��ʂł���B����͒ʏ�ACaput�̃����X�}�����K���I�ɍ���Ă͂��邪�B�������A�������̒�����sequentiaries�ł̌����ł́A����͕s�тł������BCaput �̃����f�B�[�̋N�������肷�邷�ׂĂ̎��݂́A�l�K�e�B�u�Ȍ��ʂƂȂ����B p229 ��Bukofzer�����̔����� �@���ǁA�{���̃\�[�X�̔����������炵���ŏ��̎�|����́A "Processional of the Nuns of Chester."�ƌĂꂽ15���I�̗�q���̎ʖ{���痈���B ���̃R���N�V�����̃e�L�X�g�́AHenry Bradshaw�ɂ���ĕҎ[���ꂽ���A���n�����Љ�ɂ����Ă͒ʗ�̂悤�ɁA��q���̏o�ŕ��ɂ����ẮA���y�͖��ȃA�N�Z�T���Ƃ݂Ȃ���āA�o�ł���r������邱�ƂƂȂ����B���y�̒ʗ�I�Ȕr���́A�قƂ�ǂɂ����ĕs�K�ł���A����̓I���W�i���ɖ߂邱�Ƃ��������鉹�y�w�҂����̂��߂łȂ��A�e�L�X�g�ɂ͌���Ȃ����[�}�T���[�}�T��̊Ԃ̒n�捷�ɂ��āA���̉��l�̔��f��D���邱�ƂɂȂ����T��w�҂ɂ����Ă����l�ł���B �@���̒��ӂ�������Chester Processional�̓���̃Z�N�V�����́Aantiphon Venit ad Petrum�ł������B����́A�Ō�̌��tcaput �ɂ����āA���������X�}����������т₩�Ȃ��̂ł���B�u���v�ɂ��Ē��N�����Ă������̊��o�ɂ���āA�����Ɏ��̋����������N�����ꂽ�B�����L�����画�f���邱�Ƃ��ł�������|Denkmaler�́A�����̓A�N�Z�X�\�ł͂Ȃ���������ǂ��\���̃����X�}�͂����܂��ł��������A�~�T�̃����f�B�Ɠ���ɂ͎v���Ȃ������B�������A����antiphon�̃o���G�[�V���������݂������ǂ����ׂāA���̍D��S���\���Ɏh�����ꂽ�B p230 15���I�̂������̃C�^���A��Prosessionals and Gradual�̐����͉��������o���Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�R���N�V�����́A�f�Ђ��܂�ł������Ȃ���������ł���B�������ASarum Processionals ��Sarum Graduals�ł̌����́A���ɏ\���ɕ�ꂽ�B�����ɂ�antiphon���܂܂ꂢ�邾���ł͂Ȃ��A������ cantus firmus �ƒ���I�Ɉ�v����Caput�̃����X�}�̔ł����݂��Ă���BCaput Masses�́A����䂦�ASarum use��antiphon Venit ad Petrum����̃Z�N�V�����Ɋ�b��u���Ă���A����ɂ��̍Ō�̌��t�ɂ����āA����ȃ����X�}�ő�������Ă���B�i(see Plates 6 and 7�j�B 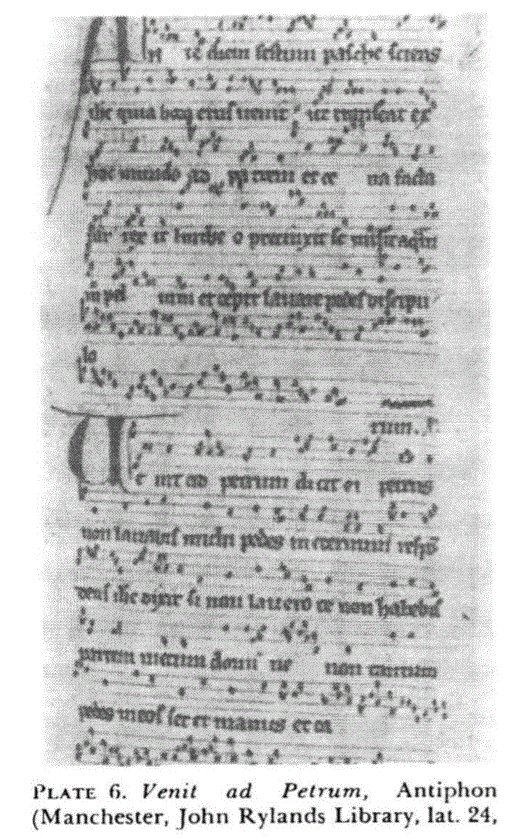 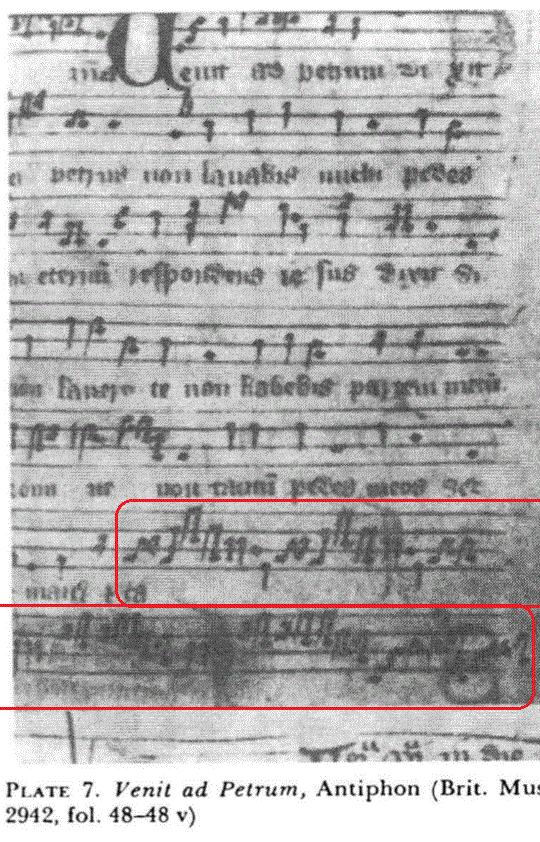 �@�����������Ă݂�A����тȂ�����Ȃɒ�����cantus firmus�����肳��Ȃ������̂����l����̂͗e�Ղł���B�B��́A�����Ƃ��d�v�Ȍ��t�́Aantiphon����̎ؗp�ł������̂��B�Ȃ��Ȃ炱����Ō�̂��̂ł���Aantiphon�̍�i�ɂ����Ă͌�����Ȃ���������ł���B����ɁASarum Processionals�͂����̉��y�ƂƂ��ɍĔł���Ȃ������B�ߑ�̃e�L�X�g�̕ҏW�ł͓���\�ł��������B���������y���A�N�Z�X�\�ł������Ȃ�A �e�m�[���̃\�[�X�͂��Ԃ�A�����Ƒ�����������Ă������Ƃł��낤�B�������Aantiphon���A1894�N�ȗ������Ȃ��Ȃ��Ă���Graduale Sarisburiense�̃t�@�N�V�~���łɂ����Č����邱�Ƃ́A�F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Ȃ��ЂƂ̌��t�ɂ��������f�B���S���Ă����̂��Ƃ����~�X�e���[�́A���݁A�����Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���̌��t�́A���ɁA���̃����f�B�Ɛ��Ɋ֘A����B��̂��̂ł��邩��Bcantus firmus�̃\�[�X�̔����́A15���I�̓���������A����ŁA����܂łɂ͌����Ȃ������������̐V���ȋ^����܂������オ���Ă����̂ł���B |