| TUDAR MUSIC5 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
p69
Fayrfax MSでソングは、王を扱っている。"Enforce youseelf as Goddis knyght /To
strenkyth your comyns in ther ryght'.
ヘンリーVII世が、コモンズの権利を強化し、音楽と詩は、ライバル関係であるランカスター家とヨーク家の連合によってもたらされた安定性の恩恵を受けていた。実際、 Fayrfax MSはルフラン「‘O rote of trouth , 0 princess to my pay' . (cf. MB XXXVI no. 46)」を有するIyricで、バラ戦争の終結を祝っている。 写本と作曲家Fayfaxとの関係は明らかであるが、彼が実際それを筆写したかどうかは、明らかではない。彼は1504年に博士号を取得したが、このタイトルは彼の名前を担う項目と関連して生じてはいないので、おそらくその日付は、世紀の変わり目(1500年頃)より早いであろう。 このソースのソングやキャロルは、複雑な音楽スタイルを示し、隠喩的抒情詩とは、熟慮された状態で、組となっている。中世の言葉遣い、John Lydgate (c1370--1449)の精巧な言葉遊びが普及し、長い情熱的キャロルの非常に装飾的な旋律スタイルは、Guillaume de Machaut の作品に勝るとも劣らなかった。 それゆえ、言葉と音楽との統一は偽りであり、それぞれは独自の道を歩んだ。こうした多様性は、マショーの死を悼んだ詩を書いたDeshampsが musique naturelleとして、Miltonの音楽を持つ詩を賞賛し、それが十分であった14世紀に起こった。 Deschampsは、musique artificieleを、言葉が音楽とが、多かれ少なかれ平等なパートナーシップで結婚するとしていたが、それは衰えていった。 p70 両者のこの統一は15世紀の宮廷抒情詩においては消滅し、人気のある曲においてだけで生き残った。16世紀には、Skeltonによって、単純な語法への回帰が推進された。これは、最終的には16世紀半ばまでに勃発した。 Richard Pygottの‘ Quid petis , 0 fili' ( (112v-116r) the only piece in King Henry VIII' s MS with sacred words) は、その音楽様式がさらに1ステップ上であることで注目すべきものである。それは、特徴的な言葉の繰り返しの使用によって適合された、高度に組織化した模倣の技法である後の時代のマドリガルの技法を先取りしていた。 Richard Pygott ‘ Quid petis , 0 fili' Ritson MSは、2人のヘンリー王にまたがった時代のものである。その内容はおそらく、1480年から1530年におよび、Fayrfax MSの情熱的なキャロルよりも古風で、合唱的様式における聖なる言葉を伴う典礼的なキャロルを含んでいる。 Ritson MS中のこうした作品は教会で使われたが、Fayrfax MSのそれは、純粋にdomestic devotionalな音楽に現れていた。Ritson MSにはまた、 King Henry VIII's MSに見られる、メリスマの少ない活発な動きのソングやキャロルを伴う、ブルゴーニュ楽派のバラード様式も含まれている。 Ritson MSとRitsonのソングやキャロルは、幾分不完全に、筆写されて現れる。それは、アマチュアの書記によって、プロのレパートリーが加えられたことを示唆している。 Fayrfax MS(BL Add . 5465)とKing Henry VIII's MS(BL Add. 31922) とは、双方ともに宮廷で生まれたが、Ritson MS(BL Add. 5665) は、宮廷地方コレクションや、Devon地方の州のレパートリーを示している。 Fayrfax MSには、ヘンリーVIIIの統治の出来事に言及する、いくつかの政治的、随時の作品が含まれているが、King Henry VIII's MSは、16世紀後半の音楽の好みを反映し、宮廷音楽作りのはるかに鮮明な像を提供している。ソングブックは、カノンや、「three men’s song」や器楽CONSORTSの雑多なものである。それらは、王の宮廷から直接に放射され、王の音楽趣味の記録となっている。 ヘンリー8世の作曲家としての能力は、しばしば誇張されている。彼がチャペルのために作曲したと考えられている”Service"は、Peacham(1622、p99)によって述べられているが、現存していない。こうした作品が現存していたとしても、その音楽的価値は、問題の写本中に現存しているものより偉大であるということは、ないだろう。これまでの作曲家の作品に加えられたわずかに優秀な部分を除いて、王の音楽的語彙は、決定的に限られているように見える。 p71 有名な ‘Pastime with good company'[ff. 14v-15r] は、彼のその他の作品の多くと同じフレーズで正確に始まっており、いずれの場合もフランスの劇シャンソン「Demon triste et desplaisir」からの借用であると思われる。 King Henry VIII Pastime with good company しかし、おそらくヘンリー王の音楽的関心は小さいが、彼や宮廷作曲家たちが設定した言葉は、当時の王廷の雰囲気のよき証言となっている。確かに、多くの卑猥な「森番」ソングがあり、実際には、少なくとも1つのページェントが、6人の森番の代表を含めていた。 しかし大半の曲調は、ちょっとした卑猥であった。それは、初期のFayrfax MSの同じ作曲家による艶のある曲は著しく異なっている。ヘンリーの宮廷と彼の新婚のキャサリンの宮廷においては、愛すべき神聖な感情の極端さがなくなり、アン・ブーリンの時代までは戻らなかった。 その代わり、King Henry VIII's MSは彼の統治の初期時代のバカ騒ぎを反映している。(略) Fayrfax MSのソングにおける風刺的な音調は、このような人工的な騎士道によって置き換わり、数年の間には、コーニッシュの"Hoyda,joly rutterkin' の武骨さが現れる。この作品は、コーニッシュ自身の痛恨の受難キャロルとは対照的である。 p72 コーニッシュは1509年にウィリアム・ニューアークを王室礼拝堂の子供部のマスターとして継承した。このポストでは、彼は、当時宮廷で占領されていた多くの舞台を担当していた。議論されているコレクションの歌のいくつかは、疑いなく、ここでの'工夫'の中で歌われていた。 詩人スケルトン、無慈悲な評論家Wolseyとの関係は、時から時への協力関係の結果であった。しかし、この時代の設定へのスケルトンの詩的な貢献は、しばしば誇張されている。 コーニッシュが反逆的な風刺に関わっていたと思われるのは、非常に疑わしいことである。 それにもかかわらず、コーニッシュをFleet監獄に入れるような1504年に疑獄事件が起こった。そこで彼は、音楽用語を使用することで驚くほど顕著な「A treatise betwene Trouth and Enformation 」を書いた。 この長い詩によれば、彼の投獄は2つの間違った目撃者のせいであった。 結局、彼はすぐに解放された。 1513年、コーニッシュは王室礼拝堂と共に、フランスへ旅した。その歌を通して、偉大な名声を勝ち取って。そして、1520年に、Field of the Cloth of Gold(金襴の陣)で、パf--マンス学校、華やかなフランスの地で行われた(Anglo、1969参照)。 St Alban修道院からのFayrfax、John Browne(明らかにOxfordの作曲家)、Richard Davy(Oxmagdalen College、Oxford)が、コーニッシュの著名な仲間であった。 教会のために彼らが書いたアンティフォン、マニフィカト、その他の音楽において、彼らの能力に対する十分な証言が得られている。それは、ソングブックにおいて、キャロルや同様の作品にも見出された。しかし、これらの作曲家の中で最も多彩なものは間違いなくCornish自身のものであった。 p73 FayfaxMSのキャロルは、ほとんどがスルーセットであり、それぞれのverseは異なる音楽を持っている。King Henry VIII's MSは有節形式である。さらに、場合によっては、同じ旋律の素材がverseとルフランの両方のために使われた。 前章で触れたように、ルフランを示す「burden」という言葉の近代的使用は、誤解を招くものと時代遅れのものである。その他のルフラン形式との関連は、15〜6世紀での別の感覚において使われた言葉の流れにおいて、あいまいになっている。 キャロルは、ロンドー、ヴィレライ、バラードとともに、舞曲として始まった。こうした舞曲は非常に人気が高まったので、しばしば卑猥な母国語テキストであったものから、ラテン語の高尚な感覚に代わり、フランシスコ修道会は、それ自身の目的のための曲調を引き継いだ。しかし、舞曲はまもなく静かな歌に変化し、現代では、きちんとしたラテン語文学となり、中世の冬至のような異教徒の祭りとの関連が残っている。 こうして、これらの歌は、教会が古い慣習の圧力に抵抗することが困難であった時、特にクリスマスに、典礼に組み込まれた。そして、Feast of Fools、Boy Bishopとしての祭日への道を作ったりした。 Harrison(1958)が示しているように、キャロルは頻繁にBenedicamusの代用品として使用され、したがってDeo gratiasというフレーズが頻繁に出現する。 しばしば形勢は逆転し、教会キャロルに不信心な「goliardic」な風刺が、世俗領域へのジャンルに復元された。しかし、バラードなどと同様、民謡の記憶を残し、初期のキャロルが完全になくなったわけではなかった。 典礼的キャロルは、Ritson MSで見られた遅い例でさえ、単純なブロックコード様式の影響を受け、民謡キャロルの単純さからさほど離れてはいなかった。 これは、他の「fixed forms 歌曲定型」とは違う発展を経ていったためである。 14世紀のロンドーとバラード(そしてより変化した、virelai)は、その素朴な起源から離れていった。チョーサーとマショーの時代の宮廷のロンドーとバラードは、音楽的にも言葉的にも、双方が非常に複雑で、両要素は最終的には、Deschampの時代に離れていった(p69参照)。 チョーサーのバラードの一つ、” Hide Absalom”in the Legende of Good Women ,は、 ‘as it were in carole-wyse”(キャロルの様式で)歌われることを意図されていた。 しかし、一般的に、バラードは語り的なバラードに堕落し、最終的にそのルフランは消え去った。 p74 歌詞定型間の相違は、時間が経つにつれ、ぼやけた。 もともとそれらのアイデンティティーはダンス・ステップとの音楽構造の問題であった。 しかし、最も初期に記録された音楽ソースで認識できる公式な性質は、ルフランとverseの音楽と詩との間の相互関係に関していた。 次のダイアグラムでは、テキストの行を示す数を使ってルフランをイタリック体で示し、テキストの性質に関する限り、典型的なヴィルレーとキャロルが同定されている。 12 3456 12 しかし、2つの種類の抒情詩の区別は、ルフランとverseの音楽との関係にある。 音楽の様々なセクションが、縦二重線で示され、数字は、歌われる音楽フレーズに従って、縦に配置されている。典型的なヴィルレーがこの形式となる(AbbaA)。 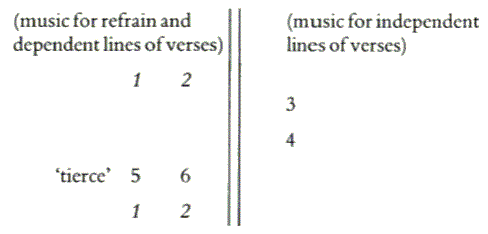 したがって、ルフランは、verseの終止部分によって、音楽的に予告される。 同じテクニックは、フランシスコ修道会のlaudeとその他の同種のコントラファクタの抒情詩で見られるような、最も初期のキャロルでも認められる。 しかしここでは、独立した行は2つの別々の楽節で歌われる。以下のように。 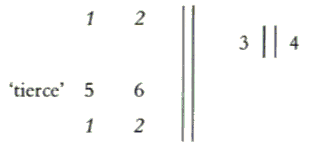 tierceのセクションは、ルフランが、最後の行だけなのか、あるいはそれより前も含めてなのか等で、しばしばモディファイされる。 一般的に、典型的なロンド―、ヴィルレー、キャロルの形式はルフランで始まる傾向がある。 しかし、この一貫性は幻想的であるが、ルフランの出現が、典型的なバラードのように、冒頭のverse後まで遅れることがよくある。 それゆえ、最初のルフランの有無が、こうした歌詞定型の必要な公式的質であることは、特にキャロルにおいては、ない。 最古の抒情詩の定型パターンは、すぐに修正された。英語のソースにおいて、上に示したパターンに正確に答えるヴィルレーとキャロル定式はほとんどない。 MB IV no.11a‘ As I lay upon a night'は、修正されていないヴィルレーの形式になっている。そして、no. 63、 'Ecce quod natura'は古いキャロル構造をしている。どちらもまれな例である。 フランシスコ会の托鉢修道士James Rymanは、15世紀のキャロルにおいて、‘ Ecce quod natura' の曲調とルフランを取り、英語のversesを加えている。しかし、ここではキャロルの形式が変更されている。なぜなら、tierceを持たないからである。 偶然にも、Oxford Bodleian Arch. Selden b 26(MB 1V No. 37参照)の 'Ecce quod nature'のバージョンもまた、このセクションを欠いている。Rymanの(キャロルの)構造が、こうしたソースからのものであることは、あり得ないことではない。そこでは、書記がその形式を誤解していたのである。 こうした誤解は、しばしば、無意識的なイノヴェーションをもたらし、とりわけ、Wyattの時代にあった流行を模倣し、Christine de Pisan(主にフランスのパリ宮廷で活動した、中世のヴェネツィア出身の詩人、文学者。フランス文学最初の女性職業文筆家とされる。反フェミニスト的な論調を取る『薔薇物語』続編に対抗し、『薔薇のことば』で女性擁護を訴えた) の修正されたロンド―・ルフラン(rentrement;訳注:ルフランが短縮されたもの)をもたらした。 Rymanの「Eccc quod natura」の英語版は、間違いなく、同じカテゴリの偶然のイノベーションに属している。 'Ecce quod natura'  他のキャロルでは、ルフランとverseの間には痕跡的な結びつきがある。 確立された正式なパターンの内訳は、しばしばその作品がどのように演奏されるべきかを見分けるのを困難にする。 ロンドーはまた、その複雑な構造の崩壊に苦しんでいた。 もともとは、その典型的な構造は、以下のようであった。 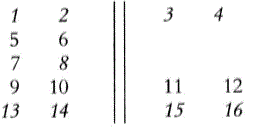 ABaAabAB ここで、7行目と8行目は、ルフランの前半と同じである。 5と6の音楽は同じであるが、異なる言葉で歌われている。 最後の4つの行は、冒頭のルフランとまったく同じ(言葉と音楽)であり、9-12行目であらかじめ設定されている。その行の音楽は、続くルフランの行と同じである。 この精巧な構造は、Henry VIIIのMS(No. 36)に見いだされるvan Ghizeghemのロンドー「De tous bien plane」[30 ff. 40v-41r]と、同様の匿名のロンドーIay pryse amours [31 ff. 41v-42r] (No. 37)で使用された。 しかし、言葉が欠けているので、最初のstrainがどこで終わるべきかの示唆がほとんどない(単に、孤立したsignum congruentiae van Ghizeghem ロンドー「De tous bien plane」 p76 初期のチューダーの歌集に見られるキャロルの形式も、公式的な退行の兆候を示しているが、修正の程度は必ずしも明確ではない。その結果、いくつかのパフォーマンス演奏上の問題が生じている。 Fayifax MSの長い情熱キャロルには、長いルフランが先行したスルーセットのスタンザがある。ルフランの言葉は各詩の終わりに取り上げられ、そこではルフランの音楽もあらかじめ設定されている。 コーニッシュの ‘Woefully arrayed' (MB XXXVI, no. 53) はこのテクニックの良い例である。全面的なルフランの繰り返しは、特に示されていないので、大きなルフランについては、演奏者が、大きなルフランに対して、小さい方が取って代わってもよいとされている。 コーニッシュ ‘Woefully arrayed' しかし、J.Browneの'Jesu mercy' (no. 51)は、長いルフランの繰り返しについての明確な指示を持っており、こうして‘ Woefully arrayed'の構造を明らかにする。同様に、、Henry VIIIのMSのキャロルスタイルの作品形式はおそらく、冗長に向かうこの傾向が念頭に置かれていると、おそらくよく理解される。 J.Browne 'Jesu mercy' この歌集中のいくつかの同様の作品と共通して、If I had wit for to endite' MB XVIII no. 29)は、 キャロルに変換された人気のある宮廷歌である。変容は、元の歌の最初のverseによって達成され、これを擬似的に偽装した形でルフランとして使用している。 他の例のように、元のバージョンの曲は、別の不完全な宮廷歌集で追跡することができる。ポリフォニック版では、それは、"threemen'sのテキスチャーのテノールパートの一部として、ルフランに隠されている。このリフレインに続き、後続のverse(原曲の第2スタンザ)は、3声部のルフランが従い、飾り気のない曲調に歌われた。 しばしば、元の曲のようなふるまいは、それをテノールに置くだけではなく、もっと長さが取られた。キャロル「‘This enders night' 」において、ルフランの音楽は、近代譜の4/4拍子に相当し、3拍子のメロディの真の性質を、効果的に隠している。 キャロル形式の人気は、よく知られた宮廷の曲が頻繁にキャロルに変換されたという事実によって証明されている。 皮肉にもこれらの曲は、しばしば、古いキャロルから派生したものである。そのルフランは、時間の経過と共に少なくなり、ソリストとコーラスによる演奏の流行の変化によって修正された。 キャロルの特徴であった音楽と詩的なつながりは、、Henry VIIIのMSに、しばしば示されている。(signum congruentiae p77 [Refrain a 3] Iff 1 had wytt for to endyght Of my lady , both fayre and frej ト ε Of her godnes than wold 1 wryght; Shall no man know her name for me [*Shall no man know her name for me] [Verse : Solo] 1 love her well with hart and mynd She ys right trew , 1 do it se My hart to have she doth me bynd Shall no mane know her name for me [*Shall no man know her name for me] [Refrain a 3 . etc .] 「A the syghes that cum fro my hart 」( King Henry VIII's MS第27号[22 ff. 32v-33r] )はCornishによるものであるが、これは、別のソースで見られる曲調の編曲である。しかし、signumは、それぞれの最後の行がソリストで歌われ、それから、verseと合唱の間をつないで、3声が繰り返しをすることを示している。Cornish の ‘Blow thy horn hunter' (see Ex. 34 p55)はそのsignumが欠けているが、同じ方法が当然採用されているようである。 ヘンリー王自身の'The time of youth' ([19 ff. 28v-29r] no. 23) もおそらく同様の方法で歌われた。一組の音調が、ルフランの最初の2行のテノールパートであると仮定することは、リーズナブルである。しかし、後の部分、signum以降は、明らかに、link-lineとして意図されている。 彼の'Whereto should I express' ([41 ff. 51v-52r] no . 47) は、signumを持たない。ここで最も適切なつながりは、 ‘No myrth can make me fayn/Tyl that we mete agayne.'の繰り返しであろう。書記が記号の書法に矛盾をしているのは、彼の失敗と、多くの作品のverseのために音楽や言葉の供給とを比較した帰結ではない。 Henry VIII Whereto should I express 疑いなく、コーニッシュは、‘You and I and Amyas' ([35 ff. 45v-46r] no . 41)を既存の曲調に基づいて作っている。おそらく、スタンザとルフランは、既述したやり方で結びついてはいるが、verseは、ルフランにはうまく結びつかない。したがって、これは異なる種類の曲であろう。ヘンリー王の‘ Green grow'th the holly' (no. 33)や同じフォーマットの他の作品と共通して、ルフランは完全にオリジナルであったか、または既存のものの編曲であったに違いない。その音楽は、スタンザのそれとは異なってはいたが。 良く知られたソングが含まれていた可能性は、 Cornishの‘ Adieu , courage , adieu' (no. 38) がなぜversesに対して言葉も音楽も持たなかったのかを説明している。しかし、signumは存在し、明らかに、スタンザとルフランのつながりを示している。 p78 当時の演奏者に対しては、こうしたあいまいさや省略は、ほとんど問題にはならなかった。なぜなら、口述は書写の欠点をすぐに補うことができるためである。しかし、今日、これらの不十分さは、演奏にとってかなりの困難を引き起こす可能性がある。 特に不明瞭なのは、15世紀の終わりまでの、準典礼的キャロルを含んでいるソースである。そこでは、しばしば、隣同士で存在する2つのルフランが現れる。しかし、これらの1つは、プレリュードにすぎない。それは、すべての声部が入ると、一度省かれる。 こうしたプレリュードの使用は、Cornishの「 ‘A Robin' (no. 49 - cf. Ex. 35)と ‘My love she mourneth for me' (no. 25). において明らかである。 Browneの「Jesu mercy how can be this」(MB XXXVI、No.51)にも同じものがある。その固有のルフランは、プレリュードが先行している。 彼の‘Woefully arrayed' (ibid. no . 55) が、同じ言葉の設定 (ibid. no. 53)と同様に、同様のやり方で演奏されることが意図されたかは疑問がある。編集の試みは、MBの‘burden' と ‘refrain との間を誤って区別し、問題が単純化されるのではなく複雑である「プレリュード」を同定することに失敗している。 上記で概説した構造的な難しさに加えて、ソースはまた、声や楽器の種類に関しては役に立たない。コーニッシュの ‘A sighs' は、あるソースではその他のそれよりも、五度高いピッチである。どちらかであれば、どちらのピッチが正しいのだろうか? “threemen's songs' のうちのいくつかは、非常に高いように見え、他の曲は低い。どのパートにも声部の名前が何も表示されていないので、歌手が必要とされたものについてのガイドはない。この問題は、教会音楽に関連して、後の章(8)で取り上げられる。 神聖な音楽と世俗的な音楽の作曲家や歌手はしばしば同じであったので、音楽のために合理的に確立することができる音域は明らかである。 したがって、p212に印刷された音域は、間違いなく、宮廷レパートリーに適用されるはずである。 結局のところ、王室礼拝堂の歌手と聖職者は、宮廷のペイジェントやその他のエンターテイメントに参加した。 <器楽と声楽> 声楽の問題はさておいて、楽器の問題は、一見しては声楽であるように見えても、避けることはできない。 多くの無言のパッセージが歌に現れ、それらをメリスマとしてとらえるとしても、楽器の参加を十分暗示するほどに、長いものだ。 以前の音楽にも同様の問題がある。長い言葉のないパッセージでは、現代の見方では、楽器の使用が示唆されるが、当時の視点が異なっていた可能性を軽視することはできない。 エリザベス朝のファンタジアは、「solfaing songs」と呼ばれ、楽器で演奏されるのではなく、ヴォーカライズされて演奏された。 p79 それにもかかわらず、ヘンリー王が使える多くの楽器があった。Henry VIIIのMSに見出される、全体的に歌詞がない作品が器楽用であったと仮定することは、理由がないことではない。たとえば、no.60のように(下譜)。  コーニッシュによるこの作品は、最初と最後において、一般的にはmusica fictaと呼ばれる実践である♭と♯の追加が難しいことを思い起こさせる。しかしここで、そうした情報の欠如は故意であるように見え、作品は、コレクション内の他の場所にある謎のカノンのようである。ルネサンス期の音楽家は、カノン自体を演奏するよりも、パートのピッチや順序を決めるのに苦労した。以前はバード作とされていた ‘ Non nobis domine' は、このジャンルのよく知られている例である。Henry VIIIのMSの謎のカノンは、特に難解なものではない。 コーニッシュの作品は、カノン様に書かれ、最下声部は、cancrizans(回文)カノンの2つのセクションを持っている。実際のパズルは、作品自体がジョークで、「 ‘ロクリア旋法' 」(訳注;シ音を終止音とする旋法。シベリウス作交響曲第4番第3楽章などで見られる:1547年のGlareanのDodecachordonですぐに議論される)の不合理性を示している。あるいは、OckeghemのMass 'Cuiusvis toni'では一般的だが、作品はcatholicon(万能薬)であり、そこでは、音部記号と臨時記号の異なる組み合わせを読み取って調性を変更することができる。 この独創的な作品は、コレクション全体の中で最も興味深いものの1つであり、その秘密はおそらく、多くの楽器リストに課せされたであろう。しかし、より基本的な謎は残っている。どのような種類の楽器がこの作品を演奏するか? ということである。(略) p80 多くの初期のポリフォニー器楽音楽は、言葉のない声楽であった。 rebecで演奏されたより粗い種類の「ミンストレル音楽」はダンス音楽であり、これまで譜に書かれたことはほとんどなく、前章で紹介した(シェイクスピアのPassy measuresのような)passamezzoのようなよく知られたハーモニーパターン上での即興がほとんどであった。 しかし16世紀半ばまでには、これら2つの極端なものがある程度一緒になっていて、器楽音楽はますます独立した性質を持っていた。 TavernerのMass「Gloria tibi Trinitas」は,ベネディクトゥスを通して、プレインチャントのメロディーを持っている。そこでは「In nomine domini」セクションが始まる。  これらの小節の特定の魅力を説明することは難しく、なぜIn Nomineのためにこのような流れを始めるべきだったのであろうか? TavernerのBenedictusのこのパッセージは、転写され、演奏され、加えられ、広く模倣された(Woodfield、1984、p.217参照)。 'Gloria tibi trinitasのcantusは非常に人気が高くなり、In Nomineは16世紀後半の最も特徴的な英語の器楽形式とみなされるだろう。 謎のカノンは作曲され続けており、「Salvator mundi」、「Christe qui lux」、「Miserere」(すべては晩祷に適していた。なぜならこれらは、終祷のためのhymnやアンティフォナだからである)は、広く使われた。 さらに人気があったのは、単純なスケールである定式 ‘ut re mi fa sol la' である。Christopher Tye らは、彼らのファンタジアに、街の叫び声を取り入れた。‘The leaves be green' (commonly known as ‘Browning' see p. 56)のような曲は、In Nomineのテーマの人気で、そのライバルとなり始めていた。 p81 Mulliner Book(MB 1)は、世紀の半ばの音楽の嗜好をよく示している。楽器のポリフォニー化の過程を、単なる声楽のアレンジからより真に器楽的なテクスチャへと進化させて、示している。 Thomas Mullinerのコレクションは、主にキーボード用のスクラップブックで.、Tavernerの「In Nomine」の初期のキーボード配列に加えて、パートソングアレンジ、ダンス、アンセム、典礼作品、いくつかのファンタジアが収録されている。 彼の編曲は、Tallis、Sheppardおよび他の人たちによるいくつかのパートソングの重要なソ―スである。そこには、アンセム(誤って John Redfordに帰せられた‘Rejoice in the Lord alway 'も含まれている)の編曲も含まれている。 そしてそこには、Mullinerと関係を持っていたように見えるWilliam Blithemanのオルガン作品がたくさんある。 コレクションの宝石の中には、器楽ファンタジアと、事実上知られていない新人による「A pavyon"がある。おそらくはRichard Edwardsのパートソング「‘In going to my naked bed' 」のような数多くの作品は、Mulliner's MSで独自に保存されている。 p82 Edwards' の名声は、特に、少年合唱団の演奏の演出家として、相当なものであった。シェイクスピアでさえ、聖歌隊の重大な批評家であったが、Romeo andJuliet (IV , v). で、彼の歌のひとつ( (‘ When griping griefs'))から引用するように心動かされた。 以前に論じられたヘンリー王朝のコレクションとマドリガルの隆盛との間の期間のかなりの部分のレパートリーは、現存するソースには、断片的にしか遺されていない。 Mulliner Bookの1/6は、これらのパートソングの鍵盤編曲からなり、チューダー朝初期とは異なり、一般的に、4声となっている。 これらの歌の言葉は、多くの場合、The Paradys e of Dainty Devises (1576)のようなコレクションからリカバーされることがある。これは、少年合唱団の演劇、Edwards , William Hunnis , Francis Kinwelmarsh などの詩人による大量のverseを含んでいる。 興味深いなことに、Jasper Heywoodの「The bitter sweet」はMullinerに含まれているが(テキストは1578年のA Gorgeous Gallery of Gallant Inventionにある)、彼のより有名な通称John Heywoodは含まれていない。 この有名なTudor王朝の紳士とMullinerの関係は明らかに親密で、Mulliner Bookの碑文には「Sum liber thomae mullineri、johanne heywood teste」と刻んである。 1549年、Whythorneは、彼がGyttern , Sittern を演奏することを学んだと指摘している(Osborn、1961、p.19)。 Mullinerのアンソロジーには、Stevens(1952)によって印刷された、これらの新しい流行な楽器のためのいくつかの作品が含まれる。citternは非常に限られた音域なので、フルコードを演奏する能力は厳しく制限されていたため、Mulliner'sからAntony Holborneのコレクション(1597)までの多くの楽曲は、第2転回和音(64)とその他の和声的独特さから構成されている。 何人かのプレイヤーは、このように演奏することに満足しているかもしれないが、バスヴィオールがハーモニーを完成させることはおそらく、困難であった。 Holborneのコレクションでは、ヴィオールパートでは、より複雑な作品が残されている。グラウンドバスで作られた作品に対しては、ヴィオール奏者明らかに、即興を期待されていたであろうが。同様に、Mullinerの作品はグラウンドバスに基づいており、これらは、大部分がアマチュア演奏のみでなされたと考えざるを得ない。  Mullinerで保存されたパートソングレパートリーの彼の議論(Stevens、1952)に加えて、Denis Stevens は、世紀中盤の他のより断片的な資料の貴重な調査を発表した(1950,1955)。 これらのソースの照合(Milsom、1981も参照)はSheppard's ‘o happy dames 'のような、これらの曲の極端な人気を示している。 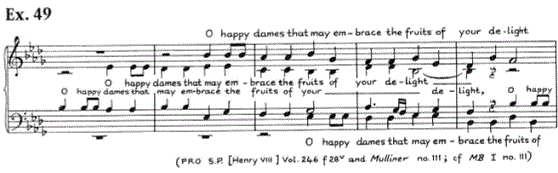 Sheppard's ‘o happy dames アマチュアの音楽制作への関心が高まったことで、パートソングの台頭、そして最終的にはマドリガルへと導かれ、ゆえに、Peachamは、以下のように記述している。 私は、あなたにもはや望んでいない。あなたが自分のパートを歌うこと、そして、初見で、ヴィオールやリュートを演奏することを。(Peacham 162) アマチュアの音楽制作の台頭は、Mulliner Bookよりもわずかに新しい別の著名なアンソロジー(BL Add。31390)でも証言されている。それは4つの異なる角度から読むことができる'table book 'である。本の底から、逆さまに、そして両側から。 p84 これらの作品の多くは教会の音楽の編曲だけであるが、大部分は、Tyeの名前さえが覗かれる真正の器楽音楽である。冊子はA booke of in nomines and other solfainge songes of v:vij: and viij parts for voyces or Instrumentesと銘打っている。 「‘solfaing'」の実践は、おそらく声楽の譜読み、そして楽器以外の人にとっても幅広いレパートリーを演奏する手段であった。モテットが情熱を奮い起こすことができないことが分からないモーリーによる貧しい代替のように見えた。モーリーは以下のように言っている。 多くのひとが歌うことでその歌い方は一般的になる。あたかも音楽がただ楽器だけのために作られているとしたら、歌詞を取り除いて、音符のみを歌うようになる (Morley , 1597 , p. 179)。 BL Add. 31390の音楽に含まれていた楽器は、それ以前の年代と同様に、絶対的な確信をもって特定することはできないが、ビオルを仮定することができる。 Peacham、Draytonなどが残した印象にもかかわらず、英国の紳士は、その歴史の比較的後まで、日常的な楽器としてヴィオールに取り組んでいなかった。 このような楽器で演奏できるアマチュア音楽家の数は少なかったであろう この音楽のほとんどは、少なくとも世紀末の終わりまでには、専門家によって演奏されるようになっていたことだろう。 Whythorneは、器楽音楽の歴史の中では、マイナーなものであろう。彼はまた、パートソングの発展において、ニッチを占めている。Fellowes(1948年、34頁)が指摘したように、彼とダウランドやウィルビーとの関係は、Wyattや Surrey とシェイクスピア、スペンサー、シドニーとの関係のようなものであった。(略) Whythorneは、1596年に死んだ。(略) p90 1589年と1611年のコレクションにおける楽器伴奏付きで出版されたバードのアンセムは、おそらく私的使用のための編成だった。 この種の作品は、一般的な家庭用音楽制作(Monson、1982を参照)であり、この目的のために、いくつかの例が明示的に作曲されていたことは間違いない。 しかし、ギボンズの唯一のアンセム(‘ See , see , the word is incarnate' , in Myriell's collection of 1616 )のみは、世俗的なパートソングのセットとして存在し、それゆえギボンズは、1612年のマドリガル集におけるこうした類のアンセム集を出版したようなバードとは異なっていた。それゆえ、ギボンズの器楽用アンセムは私的ではなく、教会のために設計されたものである、と結論づけなければならない。 ‘ See , see , the word is incarnate' 純粋な器楽音楽の領域におけるギボンズの貢献は、著名な同時代人と比較しても際立っている。 Byrdの器楽音楽は、一貫して高い水準ではないが、ギボンズのファンタジア、パヴァーヌなどのいくつか、あるいはその他は、彼のその他の音楽で見られる流暢さや音域の広さなどが見られる。特に、彼の2つの6声構成のファンタジアは、その技法において、君臨している。 Alfonso Ferrabosco II、Tomkins、Peerson、Lupo、Ward、Coprarioの器楽音楽でも賞賛すべき点がたくさんある(一部はMB IXで印刷されている)。しかしギボンズのFantazies of three parts (printed about 1620 )は、パーセルの3声のファンタジアが現れるまで、比べるものがなかった。 ギボンズのファンタジアの注意深い扱い、特に彼の狡猾に働く対位法に関しては、声楽と器楽の間を融通無碍にする。にもかかわらず、彼の意欲的な器楽的なスタイルはミスがない。本物であることが証明された(Hobbs、1982参照)、オルガンを伴う6パートのファンタジアは、レパートリーへの最も重要な貢献であるとされている。  彼のIn Nomineの作品で、Gibbonsは、cantus firmusが実践されるであろう制約について、無視をしている。 5声部のIn Nomineの5部構成は、この自由度を実証しているが、それに加えて、偶然にも、演奏実践の重要な側面を強調している。 最終的にギボンズは次のようなパッセージを書いていた(c f。MB I X no。52)。 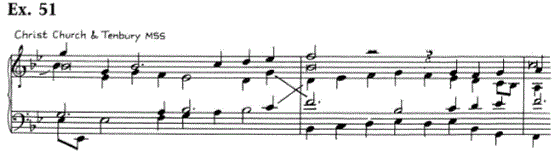 p92 特定のリズム的な活力に欠けているこのセクションは、シンコペーションされたエントリーから始まり、上向きの「分割」に出会った下向きスケールのパッセージの複雑な網を通って発達する作品に対して、クライマックスとして行動している。 私たちが普通にソースを信じるならば、ギボンズは、リズム判断の興味深い過ちを犯したことになるだろう。だが、別の ソースが確認すると、演奏者は自動的に「分割」を追加して、そのパッセージを下譜のように修飾する。  (略) |