| TUDAR MUSIC3 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
|
韻律論の通常の専門語が、全体的にverseを取り扱うのに不十分であることは、明らかである。そこでは、脚がmovementの単位となっている。抒情詩のverseを仮定の”脚”に当てはめると The cur/few tolls / the knell / of part/ing day となるが、これは、拍によって命じられたくぎりとは一致しない。 The/ curfew / tolls the/ knell of / parting / day ここで我々が持つのは、変化する(シラブルではない)リズムである。それは、アップ拍で始まり、ダウン拍で終わることは特に重要ではない。多くの共通の音律的区別、たとえばiambicとtrochaicの区別は、この点で的外れである。より重要なことは、アクセントと拍の関係の記述である。もしもGrayの”Elegy"がダウランドによって、galliardにセットされれば、以下のようになる。 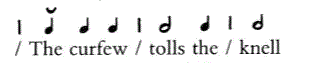 最初の言葉は、第1拍の上にあるが、強拍(ストレス)ではない。ダウランドのソング" Awake sweet love"(1597年)のように。 このような、拍とアクセントのずれは、 Vladimir Nabokov (1964)が「scud」と表現していることである(韻律論参照)。 反対に、reversed accentや屈折は、強調されたシラブルがオフ拍と一致する場合に発生し、 ‘level stress' は、「scud」とreversed accent の中間を記述し、そこでは、隣接する2つのシラブルは、 ストレスを受けたり、ストレスを受けなかったりしている。 こうしたくふうは、かなりの程度まで引用された詩で使用することができるが、音楽が関係している場合は、ここでは音楽の構造が許されているところのみで使われることは、明らかである。 Philip Rosseter の ‘Ay me that love' は、様々な可能な技法の例を提供している。ここでは、ほとんどの行は、reversed accentの冒頭とともに、10シラブル行の変化に近しい。チョーサーに戻り、彼を超えて、St Ambroseの8行シラブルはゆえにこうなる。 しかし、音楽はより変化した音律を作る。 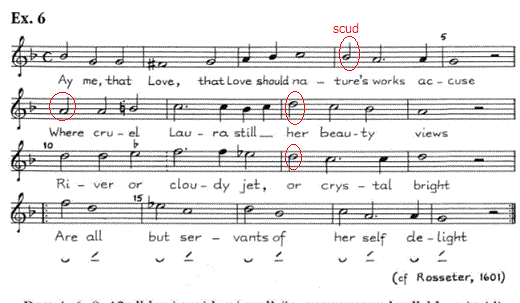 第4,6,8,12小節はすべて、scud(ストレスのないシラブルと強拍が一致する)である。これは、すでに述べた特徴であり、したがって、3拍子は容易に、第2拍に移ったストレスに適合している。 第3−4小節は(第11−12小節と比較して)特殊な場合である。なぜなら、nature'sは、第1シラブルとしてはより長く、高い音が当てられており、ゆえに、長さと抑揚アクセントのオフ拍を引きつけているからである。2つの3/4単位は、それゆえ、より大きな3/2単位と合体する。この工夫は、”hemiola"として知られており、galliardリズムの特徴である。 第14−17小節は、さらに興味深い。iambicリズムが、アップ拍となった口頭ストレスを許容している。これは再度、3拍子で工夫されたものだが、主拍はscudに適合しており、しかしオフ拍は、長さのアクセントの手段でもアクセント化されている。 この例は、明らかに、エリザベス王朝やジェームズ王朝人のマドリガリスト等の技法を示している。彼らは、音楽と言葉のアクセントの対位を可能な限り利用している。しかし、ビクトリア朝の人々は、 拍とアクセントを分離することができなかったために、こうした作曲家たちが、貧しい言葉遣いを犯している、と判定してしまった。 それは、彼らがルネサンス時代の詩人たちに対して、ギリシャ語やラテン語の定量システム(強弱ではなく長短)で、英語のストレス(長短ではなく強弱)を巻き起こしていると信じていたものに対して避けなければならないような、同様の誤解であった。 現実には、幻想的な危険性があった。避難地は想像されていたほどのものではないことが判明した。(語学的に無理があった)英語での定量的(強弱ではなく長短)な詩の効果のための考えは、 サッフォー音律でのCampionの曲から集められる。 サッフォーは、古典時代から世代を経て受け継がれてきたもので、 ホラチウスのInteger vitae scelerisqueは、中世時代の学生歌あった。そして、多くのhymnsは(最も有名な「Ut Utant laxis」)は、同じリズムで構成されていた。ダウランド自身がこの音律を採用した。 p21 Where Sinne sore wounding , daily doth oppresse me, There Grace abounding freely doth redresse mee: So that resounding still I shall confesse thee , Father of mercy (ダウランド;A Pilgrimes Solace , 1612) しかし、このサッフォー風の形式は、Roman caesuraと呼ばれ、第5,6シラブルの間で中断が入り、ここでは、行を分けるようになっていた。さらに、ホラチウスの行は、量的ではあったが、アクセント的に読まれることができ、ダウランド以上のものであった。  しかし、Roman caesuraやそのアクセントのパターンは、New Learningによって批判され、ギリシャ語のcaesuraを好むようになった。 ホラチウス自身は、後者の工夫をもてあそんだ。彼がダンサーに、Lesbian (Aeolic Greek)リズム 'Lesbium servate pedem meique pollicis ictum' (Odes IV , 6).に従うようにダンサーに指示した時に。 したがって、Campionは、彼の実験のために徹底的に進んだ「ギリシャ語」のサッフォー風を選んだ。 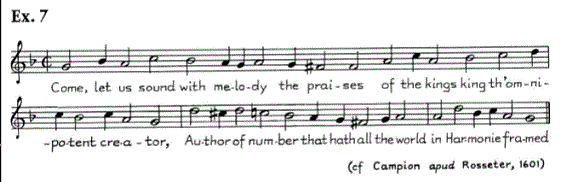 叙情詩の独特の堅苦しい歩みは、3つの主要なアクセントのタイプ(強弱、短調、高低)を自然に解くことがことができない3元連立方程式を強制されるためである。 Campionの古典的な理想の信奉は、彼の他の歌にほとんど影響を与えなかったが、 それは、Observations in the Art of English Poesie (1602). のパンフレットを書くよう、彼に促した。 彼が言ったことの多くは、十分に分かりやすいものであった。‘lambicks' の模倣はおそらく、ラテン語のiambic(おそらく、韻律家の「iambic」とは対照的に。彼は、Grayの‘Elegy' がこの音律にあることを信じていたことだろう)がそのように響いたのだろう。 Raving Warre , begot In the thirstye sands Of the Lybian Il es Wasts our emptye fields . しかし真実の間には、誤りがあった。あるいは、少なくとも、誤解させるようなことがあった。なぜなら、主に、この理論の多くは、すでに論じたような古典韻律に関する誤謬に基づいていたからである。そこでSamuel Daniel 氏はA Defence ofJ Ryme(1603)において、このケースは無視していた、と述べている。 古典的なリズムへの親和性に与しようとするCampionの不運な試みは、Edmund Spenserのものよりもやや遅れた。そして、この良き行為は注意力が不足していた。Sidneyのフランス語楽派への模倣や、Wyatt's と Surrey's のイタリア語の模倣よりも真面目であった。 しかし音楽的側面では、英語でのvers mesures へのかなりの極端な試みがいくつかある。そのうちの最も興味深いのは、16世紀中頃の抒情詩、,‘ This enders night' である。オリジナルでは Ex.8として示されている。  すでに存在しているメロディに歌詞をつけていくSidneysの習慣(現代の言い回しでは「小歌曲」と呼ばれる)は、詩人の中でさえ、音楽と詩を同じ手袋に合わせる能力があまりないこと証明した。 ゆえに、Sidneysのverseは、当時のバラード風抒情詩でよく見られた "chevy-chase"音律(8686)から逃れることによって、そしてより多様な音律モデル(例えば、無名のフランスの詩編など)に向かう傾向にあり、非常に歌いやすかった。彼はNew Poetry の原則が実践される道を開いているようだった。 しかし、もう一つの皮肉なことに、それは、英国に、最終的に"chevy-chase"音律(8686)の覇権を確立したカルバニズムの潮流をもたらした詩編唱であった。 p24 最初に、フランス語のユグノー詩篇は、その後Anglo-Genevan Psalterが続いたが、BaifとClaude le Jeuneによって奨励された様々なリズムを示した。Sarabandとガイヤルドが世俗的な曲に使われていたので、ダンスリズムが新しいフランスの詩篇のために使われた。長短短のパヴァーヌやストランボットリズムは、英語にもフランス語詩編にも相性があった。 これとダウンビートの短長短リズムは、英語の詩篇にも引き継がれた多くの曲の定番である。 しかし、Sternhold and Hopkins' Psalter のメロディは、メロディー的にも音律的にも、フランス語の相当するものよりも面白くなかった。様々なリズムが徐々に解決されてきたため、慣習的には問題ない。詩編は、宗教改革が重ねられるにつれて、より遅く、よりまっすぐになった。ルター派のコラールは、ほとんどの英語の詩編唱が単調に連続したものになってしまった時、バッハの時代までには、四分音符でさえ、ゆっくりと歌われるようになった。 さらに、最も確立された音律は、‘ common metre' (8686 - "chevy-chase"音律と同様)とその親戚関係の8つのシラブル行‘ long metre' (8888)のバラードであった。非常に軽蔑された ‘Poulter's measure' でさえ、‘ short metre'(6686)に祀られていた。 これは残念なことであった。なぜなら古い詩編唱のオリジナルのリズムは、多少の時代遅れの「common」と「long」音律の中でさえも、音律の変化をもたらしたからである。 長短短または短長短リズムは、すでに論じた三拍子リズムによって供給された可能性に類似した方法で、 reversed foot あるいは level stress openingを許容することによって、英語の行にあまねく存在するアップビートの問題の解決の手助けとなった。 William Ketheの有名な百詩篇のパラフレーズ(Ex.10、この曲は、最終的に「Old hundredth」と呼ばれている)は、この技法の良い例である。 基本的な行は、ドキソジーに見られた交互のパターンであるアップビートである。  この動きの退屈さは、各行冒頭の(時には別のところで)、reversed あるいは level stress によって緩和される。 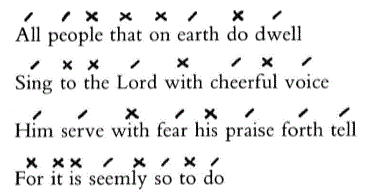 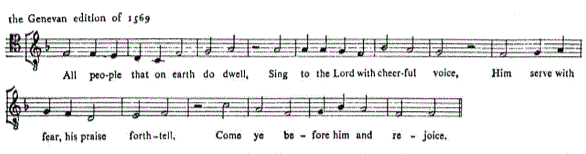 曲のリズムは、ストレスのアクセントを変化させて、音符の長さやピッチに合わせて変化させることができるようになった。これでビートが強調されるようになった。 すでに起きているように、曲がminimsの退屈な流れ解決していたら(そしてそこに魅惑的に歌われた)、verseと曲の微妙な相互作用は,鈍い音調に歌われたように中傷されたであろうことは、明白である。 詩編唱の衰退につながった、増大する冗長な演奏のアミューズメント的確信は、‘gathering note'という用語の使用において見いだされる。この添え名は、しばしばそれぞれの行の冒頭の長い音符に適用され、漠然とした間隔で勢ぞろいした会衆の奇妙なイメージを思い起こさせる。 しばしば教会ではなく家庭での「プライベート・ミュージック」としてのソロ・ヴォイスによって、曲が元のスピードで歌われたときに、歌手がこのように集まる時間はなかったであろう。実際「Genevan jigs」という名前は、これらのメロディーが憂鬱な投げ捨てのように聞こえた場合、ほとんど得られなかった。 したがって、Sidney ,Campion らが想定していた音楽と詩の理想的なパートナーシップは達成されなかった。しかし、これら両者は、その名がリュートソングまたはマドリガルの詩の作者としてしばしば見出されたので、ある程度の利得は得た。 しかし、狂詩は戻ってきた。パーセルのような作曲家が美しく繊細なメロディーを掛けることができる言葉の物干しスタンドを形成して。あるいは、ミルトンのような反対の極端な詩人は、大きなdeclamationで響き渡ることができ、控えめなrecitativeのレベルを上回っていると主張していない音楽の設定を承認することができる。こうして、ミルトンはHenry Lawes (ヘンリー・ローゼス)への賛美で、次のような行を書きました。 Harry , whose tunefull and well measur'd song First taught our English Music how to span Words with just note and accent , not to scan With Midas ears , committing short and long; (Sonnet XIII 1 p25 slver swanの時代とは何か? それは何を成し遂げ、どの程度続いたのか。 この時代は短い時代であり、意味的には熱狂的であることを示唆しているように見えるかもしれない。しかし、マドリガルとリュート・ソングの印刷されたコレクションは、比較的短期間に大量に登場したことを示している。 流行の始まりと終わりとして、それらの出現や消滅を受け取ることは賢明ではないが、それらは明らかに需要を差し出すことを意図していた。だから1588年、Musica Transalpinaの年には、英語のテキストを提供するイタリアのマドリガル、そしてバードのPsalmes Sonets&Songs(マドリガリアの装いで完成したコンソート・ソングやアンセムなどで急いで編纂された)が流行の始まりであり、10年間続けられ、20年後にはすべて終わった。 リュートソングにとっては、その支配はさらに短く、16世紀末から1612年にかけてであり、DowlandのA Pilgrimes Solace(Campionsの1617コレクション、1622年のAttey'sの誕生日)の期間である。 concerted song , madrigal and lute-song に戻ると、それらは、マドリガル、リュート・ソングなど、彼らはすべてエリザベス朝とジェームズ朝の音楽に密接に関連したメンバーであったように見える。 作曲家自身は、この概念で、愉快さ、恐怖さえ表現していただろう。彼らのうちのほんの少数は、複数のジャンルで書いたか、あるいは書きたいと思っていた。 例えば、バードは、concerted songの純粋な音楽的演奏を好んだ。 より身近な用語「コンソート・ソング」( ‘concerted song' )は、 Philip Brettによって、作られた。これらの‘concerted song' が見つかっているパートブックには、特定の楽器が指定されていないが、ヴィオールが意図されていたことは間違いない。なぜなら、聖歌隊の少年によるこうした使用が証明されているからである。 彼のマドリガルのコレクションで、ギボンズが主張していた高水準の印象的な文章で、バードの‘concerted song'のテキストは、しばしば純粋な狂詩に近い。 さらに、彼が音律的な詩篇を唱えるとき、彼はしばしば「共通の音」のリズムを模倣することに満足していた。 バードは彼らのテキストに無関心だったとは言えないが、彼は、ほとんどそれらが言葉が加わった器楽ファンタジアのように、彼の歌に接近した。 彼は、ほとんどmadorigarismには耽られなかった。あるいは、DowlandやCampionの理想であった言葉と音楽の親密な関係に向けて働いたりしなかった。 彼が崇拝した教師であるタリスの死に対する彼の哀歌は、彼が通常は使わなかったmadorigarismのやり方をしている。(Ex.11)  冒頭は、厳格な模倣書法であり、「‘sacred muses' 」の技法的専門知識にによる語呂合わせである(Gibbons 'O that the learned poets'、1612年と比較せよ)。‘ and Music dies“の長いメリスマが、ゆっくりと涙が落ちる悲しみの効果をもたらしている。 このテキストは、マドリガルのやりかたではなく、 Campion(apud Rosseter、1601)を批判する言葉を使って、「bated with fuge」、「manie rests],[a long Preludium"というように、むしろ行ごとに設定されている。 しかし、ほとんどの場合、バードのconcerted songs は、抒情詩のように扱わなくても、言葉をよく反映している。設定は、確かに、パーセルの自由な音楽的アプローチに向かっており、ミルトンの理想からは離れている。それでも、それらは、どの言語でも最高の歌の例である。 'Come pretty babe' や有名な ‘Lullaby ,my sweet Iittle baby'、‘Ye sacred muses' のようなエレジー、そして、 ‘Though Amaryllis dance in green' ともにキャロルである ‘o God that guides' ,‘ From Virgin's womb' そして ‘An earthly tree' は、その顕著な例である。 (printed in the Byrd Edition , Vols 13 ー16) ”Pandolpho”(attributed alternatively to Robert Parsons or Richard Farrant)、,‘ Come tread the paths' (Anon) ,そして生き生きとした ‘In a merry May morn' (Richard Nicolson) そして その他の作品が , Musica Britannica (MB) XXII.にて出版されこのジャンルの最高点として、並んでいる。 シェイクスピアは、われわれが見たように、これらのクワイヤーソングの一部を是認することはほとんどなかったが、ほとんどの場合、言葉における音楽の覇権は誇張されていない。 マドリガル固有では、バードはあまり確信していないようだ。彼の最初の努力は、特に成功しなかった。Kerman(1962)は、(TallisとByrdに収蔵されていたが)英国の音楽出版独占は、世俗音楽を是認せず、追放されたHuguenot、Vautrollierによって支配された。その結果、従って実質的に検閲者として働いた。 続いて、1588年のVautrollierの死においては、新しい形のマドリガルを出版するための争奪戦がありった。そこでバードは、伴奏の部分に加えられた言葉によるserviceを使って、concerted songs (「ララバイ」など)を出版した。 マドリガル版ではほとんど説得力がなかったが、なぜなら、伴奏の部分は、歌詞づけがしばしば稚拙であり、あまりに器楽的な性質であったために、歌うには適さなかったからである。 しかし、後のコレクション(アンセムと歌の中で、彼はまだ数を作るために奮闘していた)では、バードは軽い音色を採用し、説得力のあるマドリガルを書いた。その1つ、「‘ Come woeful Orpheus' 」で、彼は、イタリア語の文字通りの言葉を使って、言葉の”今日妙な半音階音調”と”もっとも酸っぱい♯とぎこちない♭”を説明している。しかし、バードのマドリガルへの努力は、彼の他のスタイルや、モーリー、トーマス・ウィルクス、ジョン・ウィルビーなどのマドリガルと競うことはできない。 英国のマドリガリスト、特にモーリーは、イタリアのモデルに忠実に従った。Triumphes of Orianaは、エリザベス女王に敬意を表して(1601年)に出版され、当時の大部分のマドリガリストによる項目(バードと若いギボンズは特に除外されているが)を持っていたが、それは、1592年に現れたII Trionfo di Dori の模倣であった。 しかし、英国のマドリガルの重要な要素は、イタリアのマドリガルが英国化した程度である。シャンソンのフランス人作曲家は、全体をフランス語で書いたのに対し、ドイツ人のマドリガリストは、裏切るように、イタリアのイディオムで書いた。いわば、ほとんどアクセントの痕跡を認めていない。 しかし、英国のマドリガルでは、大げさなジェスチャー(半音階、音画技法、文学的喜劇、音楽の方向性の急激な変化)は、デザイン全体としてはより控えめで統合されている。 Gastoldiのbalettiは、MorleyやWeelkesの模倣よりも粗く、その音楽的構造は、そのモデルよりも満足できるものである。 イタリアのマドリガルは文字通りの動きに基づいていたが、英国のマドリガリストは知識人であった。先に述べたように、「声楽とviolへの傾向」の見出しは、空想的なものではなく、英国マドリガルの多くの作品は、いくつかのパートで同時に「音符とアクセントだけで」という言葉から離れて、ファンタジーのように慎重に行われていた。関係する複雑さのいくつかのアイデアは、以下の例から集めることができる。 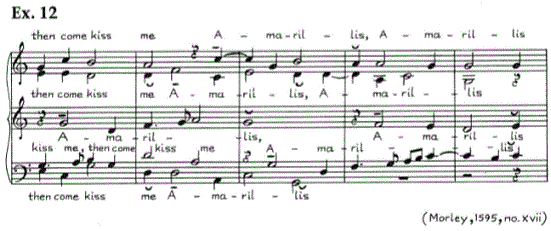 p30 「Amarillis」のアクセントは拍とは対応していない。この曲の技法は、すでに、リュートソングで記述されたが、5つのパートで同時に使用されている。 単語が文字通り音楽に描かれているマドリガルの形象(例:”Wilbyeの「Longは1つの音符が伸びているこれらの丘を作った」“は、最初の音符が長くのばされている。)は、英語の大半によってやや丁寧に使用されていたが、そのイタリア語の対位法とは対照的である。 おそらく、最も凡庸な言い回しは、翻訳された冗談であり、「sigh」という言葉の前には休符がある。イタリア語のsospiroは休息とa'sighの両方を意味がある。 しかし、最も特徴的な英語の形象は、Dowlandが彼の「Iachrymae」のパヴァーヌで採用した「 ‘weeping' 」動機であった。その後、彼は「Flow my tears」という言葉を付け加えた。 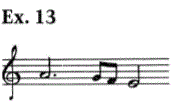 「 ‘weeping' 」動機 この形は、ダウランドの音楽の「weepmg」のトレードマークとして、無数の英国のマドリガルでしばしば巧みに使用された。他の有名な4音符「B-A-C-H」のように。偶然、彼のラテン語のpunである semper Dowland semper dolens が、その名が‘Doe-land'のように発音されたことを示唆している。 英国のマドリガリストが、自分たちのセッティングに惜しみなく与えたケアを実証するために描いた例の数は、代表的な選定さえも困難にするほど多い。ギボンズの1612年のコレクションは、イギリスのマドリガルにとって最も重要で、一貫して質の高い貢献である。そのボリュームの一部が、器楽を伴って元々はソロ・ソングであった―それゆえ、トップパートは、言葉の矛盾が会ってはならない―というKermanの主張(1962、pp。122-4)は、突然に始まったもので、何度も言われてきたことだが、声部のうちのどれが「最初の歌唱部」と見なされるのかを識別することの困難さは、特にByrdのソロ・ソングが密接に比較されているときに、Kermanの議論を満足に確信していない。 逆に、ギボンズが、器楽と声楽のアプローチを彼のマドリガルに融和させるスキルは、これらの作品で、文学的要素と音楽的要素が最も重要な要素となってきた点を、単に表現している。 ギボンズの後の最も重要なマドリガリストは、WeelkesとWilbyeであった彼らはTomkinsと共に、より小物であるGeorge KirbyeとWardのように、このジャンルに著しい貢献をした。 Wilbyeの音楽は、David Brown(1974年)によって絶賛されており、そしてWilbyeの彼のパトロンHengrave HallのKytson家族との関係における地位は、すでにPrice(1980)によって扱われている。 ウィルビーは、ひとつのパトロン家以外の指名をもたなかったことで、チューダー朝の音楽家としては異例であり、マドリガルしか作曲しなかった。 彼の2つの寄稿は、聖なる言葉の設定であるが、‘O God th e rock 'は、単なる有名な1609年の ‘ Draw on sweet night'の焼き直しである。 Wilbye'の音楽は、‘Flora gave me fairest flowers' のような軽いマドリガルから、芸術的ではない ‘ Adieu , sweet AmaryIlis ' 、より複雑でイタリア化した‘Of joys and pleasing pains 'まで、念入りに仕上げられている。 彼のテクスチャーは、‘ Weep, 0 weep mine eyes 'のように豊かであり、だがとりわけ、彼の音楽の考えの公式の順序は、注意深く考えられている。その結果、彼のマドリガルは、器楽だけで演奏されても、音楽的に成功している。 E. H. FeIlowesの献身的な努力により、このジャンルの著名な多くの例は、良く知られるようになった。Thomas Bateson, John Bennet , Michael East 、 Giles Farnabyaのようなよりマイナーな作曲家も知られるようになった。 一人の名前、ウィールクスを挙げねばならない。なぜなら、ウィールクスの大胆な大規模なテクスチャー(たとえば、 ‘Like two proud armies')を無視しえないからである。そして、 ‘ Thule ,the period of cosmography'に見られるような彼のマジック的な音画技法は、特にコメントを要する。 後者において、‘ sulphureous fire'の彼の肖像は、実際火山のようであり、‘ how strangcly Fogo burns'での半音階は、まったく奇妙で辛辣なものである。彼の音楽的描写の腕前はしかし、彼の大規模作品ではわからない。3声の ‘ Cease , sorrows now' は、非常に創意に富んだ作品であり、半音階に挑戦している。 しかしウィールクスとその仲間が注意深く言葉と音楽を接合させたその手段は、しばしば、拍子抜けするくらいに希薄である。こうした例のうちでは、1600年の‘ Take here my heart 'を挙げれば十分であろう。(Ex. 14). 全体の冒頭は、13小節にわたって広がっているが、単なるCとGの交代で、下降音型を伴っている。にも拘わらず、注意深い工夫が見られ、ほとんど鈍いようなことはなく、スタティックな効果が、I give it thee for ever' の確固たる約束を強調している。そのスケール音型は、ウェディングベルの音を模倣している。 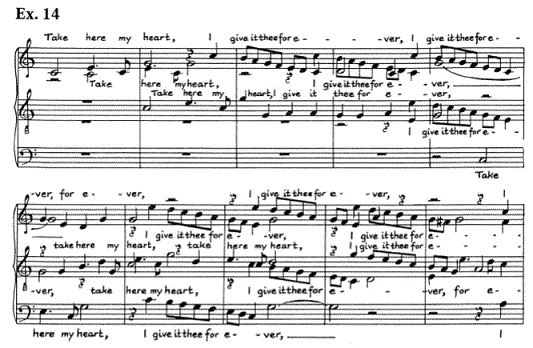 Campionの趣向であったconcerted songとマドリガルの”癒合”はない。彼のayresは、ダウランドらと共通であり、しばしば、4声公式が、リュートソングと代替できるようになっている。しばしばこれらの低声部は、awkwardで、こそくなやり方で作られた。それゆえに、バードの歌の出版された版との共通するものを持っていた。 p31 商業的な圧力は、ayres、concerted song、マドリガルの間をリンクさせるようにしたが、こうした意図は、非常に別のものとなり、、そのリュートソングの様式は、Giovanni de' Bardi伯爵の新音楽やフィレンツェのカメラータの原理にほとんど近づいていた。 新しい音楽へのこうした主唱者は、マドリガルの文字通りの音画法を避けるようになり、一般的なポリフォニーにも対立し、リュートソングを音楽的丹精さからははるかに遠ざけるようにしたが、彼らの趣向としてのdeclamationにはまだまだ不十分であった。 p34 モーリーのtablaturesは、リュート技法のうわべだけの知識を示している。さらに、彼のソングの多くは編曲ではないかという疑念が持たれている。たとえば、 ‘It was a lover and his lass' は、シェイクスピアがその As You Like Itで使っているが、‘Willow song'で行われたように、明らかに共通の流れを持っていた。 その他の無名の作曲者も、忘れられるべきではない。Miserere my maker' showsのこの設定が示すように。 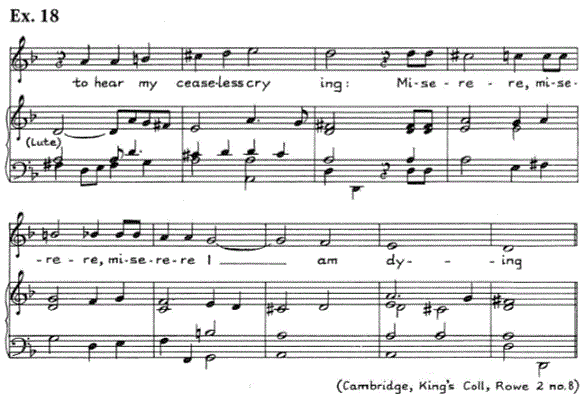 p35 ダウランドは、リュート奏者・ソング作者として比類のない位置にいた。 彼の Second Booke of Songes or Ayres ( 1600)の中の ‘ Sorrow stay' は、彼の不朽の名声を確立した。同じ本の中の”Fine knacks for ladies"は、彼がsemper dolensではないことを示している。 ”Fine knacks for ladies" ”‘ White as lilies was her face' 彼女の顔は百合のように白かった”は、Campionの設定の単純な優雅さを持っている。”Shall I sue"もまた同じ様な音調を例示している。 ”Shall I sue" A Musicall Banquet(1610)からの"In darkness let me dwell'は、これまで書かれたものの中ではおそらく、一番暗いものである。導入的冒頭のあと、'jarring, jarring sounds'は、感情的態度を打つ。さらにdeclamatoryな'O let me livin g, let me livin g, livin g, die, till death do come.'が続く。その”効果”は、クワイアボーイの死の歌よりも、イタリア語のモノディに近い。ダウランド以外、これを書いた者はいなかった。妙技は、冒頭の忍従である。これは、曲の最後にも繰り返される。聴く者は、音楽やverseが半信半疑のまま、ちゅうぶらりんで残される。 "In darkness let me dwell' イタリアのモノディに近い  イタリア風の影響は、 ' Lasso vit a mi a mi fa morire. ' において、もっとも明らかである。ミ音あるいはファ音上のシラブルが表れるどの場所においても、適度な音符が与えられている。これだけでなく、Deh あるいは Ahi me という言葉には、カッチーニの新音楽(1602年)の音型が設定されている。 1610年のMusicall Banquetに現れるうちでの後のコレクションからの2つのソングが明らかにしていることだが、A Pilgrimes Solace(1612年)に見出されたダウランドのエッセイが、彼がイタリア人に引けを取らなかったというマニフェストとして読まれたことは、明白である。 確かに彼は冊子の2つのコンパニオン作品(すべては、声楽とリュートを一緒にして、obbligatoの高音声域と低音楽器のために。)のためには、より明確に示されていない。 ‘ Go nightly cares' と ‘From silent night' は、威厳ある個性的な作曲家のもっとも個性ある作品のと言える。 A Pilgrimes Solace(1612年)への序文は、クリスチャン4世(Christian IV, 1577年4月12日 - 1648年2月28日)へのリュート奏者として彼のデンマークにおける滞在に言及している。そこで彼は、時代遅れであるという非難を受け、Tobias Hume からの無作法な言葉を受けている。リラヴィオールがリラと同じであるという主張に対して・・・ Humeのエキセントリックは、ついに、狂気にまで発展した。ダウランドが新しい様式では作曲できないという彼の根拠のない批判に対して、彼の,‘ Go nightly cares' や ‘From silent night' や ‘Lasso vita mia' は、強い反駁の証拠となるであろう。 ‘From silent night' は、"sighs”という言葉の前に、オブリガート的な休息がある。そして、押し寄せるような半音階のアクセントは、疑いなく、 Pier Francesco Tosi (1723) のJohn Galliardの翻訳として演奏され、 ‘ with a Messa di Voce《徐々に強く演奏していき、あるところから徐々に弱く演奏していく》。 the Voice always rising till he reaches it"と示されている。 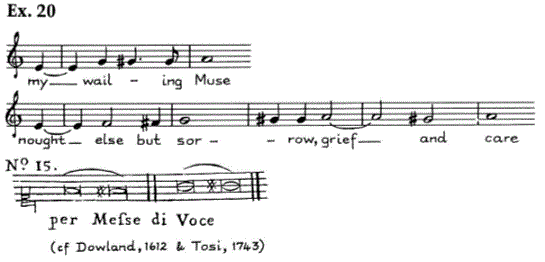 Humeのエキセントリックは、ついに、狂気にまで発展した。ダウランドが新しい様式では作曲できないという彼の根拠のない批判に対して、彼の,‘ Go nightly cares' や ‘From silent night' や ‘Lasso vita mia' は、強い反駁の証拠となるであろう。 ‘From silent night' は、"sighs”という言葉の前に、オブリガート的な休息がある。そして、押し寄せるような半音階のアクセントは、疑いなく、 Pier Francesco Tosi (1723) のJohn Galliardの翻訳として演奏され、 ‘ with a Messa di Voce , the Voice always rising till he reaches itを示している。 第2,3verseの言葉は、印刷された音楽に対して、歌手による若干の変更を要求する。ここでもやはり、詩と音楽が技法的な限界まで拡張されたやり方の適切な説明がある。 それぞれで繰り返された節の設定において、第1verseの孤立した言葉は、その他のverseにおいて適切なフレーズによって適合されなければならない。そして、次のverseが休符の部分により長い音符を要求する場合は、音楽は変化せねばならない。なぜなら、”主たるPauses"は、それらが最初のスタンザを持つ行の同じ場所で注意深くreduceされねばならない”からである。 このvirtuosityはultimum vale(最後の告別)であり、ダウランドのみならず、「抒情詩の姉妹”であり、後にミルトンやLawesもまた続いている。 同じような複雑さは、‘ Go nightly cares' にも見られる。 ' . At the words ‘o give me time to draw my weary breath' 「私の疲れた息を引き出す時間を与えてください」という言葉には、精巧な音楽的な語呂合わせがある。 声楽は、死の鐘を鳴らすことを示す単声部で歌う。ベル(伝統的に多くの曲においては3音符である)は、リュートとバスパートに登場する。‘O death rock me on sleep'のある設定(BL Add. 15117、f3)では、「死の鐘を鳴らす」の言葉のところで3つの音符による形象が作られる。別の版では、鐘を鳴らすようなクラッシュがある。 ダウランドは、‘ Go nightly cares'と‘From silent night' の両者において、‘lachrymae' のトレードマークを挿入する工夫をしている。「‘Lasso vita mia'」の冒頭で彼の「Sorrow、stay」の始まりを引用するのと同じように。 p38 ダウランドはシルバースワンの時代の典型である。 競争と批判の拍車をかけられ、ダウランドは最も思い出深く、思いやりのある歌を作った。 ギボンズや他の人と共通して、詩や音楽の限界を同時に探ることは、それ自体を燃やさなければならない輝きを得ることであった。 ダウランドは燃え尽きた。Pyacham(1612)が言ったように、「あなたの年齢は、あなたを真っ白にした。」 ダウランドの死の10年以上前に書かれたこの言葉は、独特の憂鬱な肖像の一部で、次のように始まる。 Heere , Philomel , in silence sits alone , In depth of winter , on the bared brier . ゆえに彼は歌い、そして、それ以上歌われなかった。 |