| TUDAR MUSIC13 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| CHAPTER 12 The Chauncels as in Tymes Past p314 エリザベスは、経済的、政治的、宗教的な問題の脅威に悩ませられながら、国の王位に就いた。これらの国難は、教皇との関係を続けるかどうか(その影響は疑いなく彼女の父親がそうしたように、少なくされていた)、あるいは、メアリーが彼を死に追いやる前にクランマーが手がけた道に従っているかどうかについての重要な決定を強調していたことに、ある程度は関連していた。 理想的には、彼女は父の宗教改革前に戻っていただろうが、すぐに、はっきりとした選択肢の間に置かれていることが明らかになった。教皇当局からのより過激な挑戦するか、あるいは、それににべもなく従うかである。 前者を選ぶ際に、彼女は議会、少なくとも下院を通した。領主らは気乗りしなかった。しかし、1559年4月までに Elizabethan Settlement が達成された。 実際にはかなりのコストがかかっていたが、新しい祈祷書は、新しい装いではあったが、1552年には挫折していた。それでも、1559年の祈祷書のルブリックは、1549年の慣行に耳を傾け、新しいピューリタン宗派になる人々にとっては「ローマカトリック的」と判断された。一方、エリザベスの崇高性への宣誓を拒否した者は、新たな国教忌避者となった。 このバランスは、Cateau-Cambresis条約(※)の署名により、ローマでの休戦に有利な方向に向けられ、メアリーが引き起こした、国を軍事的な混乱、政治的な弱体化、財政的破滅にさらした悲惨な戦争を終結させた。 エリザベスは、彼女の祖父母によって行われたのと同様のタスクに直面した。 彼女は信じられないほどの信用のために、 自身を中庸化した。彼女の財政が、教会音楽(チャペル・ロイヤルを除いて)のような贅沢を十分に提供することができないことを犠牲にして成り立っていたにもかかわらず、彼女は価値の低下した通貨の信用を回復させ、それにスターリング 'の言葉の意味を与えた。 Peace of Cateau-Cambresis ※《the 〜》カトー・カンブレジ条約◆1559年、イングランドのエリザベス1世とフランス王アンリ2世間、およびスペイン王フィリペ2世とアンリ2世間で結ばれた平和条約で、これによりイタリア戦争(the Italian Wars)が終結した。フランスは、ピエモンテとサボワをサボイ侯爵に、コルシカをジェノバ共和国に返還し、ハプスブルク家のスペインがイタリアの多くの地域を支配することになった。 p315 彼女の治世中の多くの問題において、反乱や戦争、放浪や失業などでは、彼女は自分自身にとって珍しい戦略を示した。 彼女自身が感情高かったかもしれないが、Hawkinsがスペインのアルマダを非常に巧妙に操る船を造るのに十分な資金にアクセスできるようにした。 法定の実習を行うことで、失業率が確認され、労働力の移動が安定した。 ギルドの勢力はすでに父親のもとで増加していた(例えば、アマチュアとプロの間の明確な区別をつくる)。 これは、「宮廷的な」マナーとスピーチに新たな重点を置いて、新しい階級の区別の線を描き始めた。 エリザベスは、新しい国教会がジェノバの最悪の余剰を避けたことを見た。 彼女の祈祷書への序文には、「内陣は残る。それらが過去にそうあったように」と述べている。 音楽的には、葛藤があった。週日の機会でのパート音楽の使用を控えるようにしたNorwich(Watkins Shaw、apud le Huray 1967、38)での命令にもかかわらず、Osbert Parslcyの記念碑は、参事会と聖歌隊の間の調和の証拠をそれぞれ示している。 しかし一般的に、ローチャーチの人たちは、Elizabethan Settlement の初期には、優位を占めていたようだ。 当時の教会音楽を過度に抑制する傾向にあったように見える。教会音楽の実践を抑えるような試みが何度もなされた。1571年にウィンチェスター大聖堂と関連した勅令は以下のように書かれている。 聖歌隊にあっては、言葉やシラブルを示す歌のみが使われるべきであり、長さにおいては言葉やシラブルは短くなければならない。・・・言葉や文への音符の繰り返しは、これを使うべきではない p316 この時期のTalisの音楽は明らかに、当時の作曲家によって感じられた、明らかな制約を示している。 彼の ‘O Lord , give thy holy spirit'は、技法において明らかに、エリザベス朝的である。しかし、エドワード朝の作品と同じくらいの長さの作品も存在する。5声のTe Deumである。 Thomas Tallis (1505-1585) - "O Lord, give thy Holy Spirit" これは、来るべきもののいくつかのヒントを与える。 Preces、Responses、およびPsalmsの彼のセッティングは、ラテン語音楽のTallisのしばしばの光を伴った、手際のよいものである。 しかし、タリスは英語の礼拝音楽に多大な貢献はしていないようで、彼自身、ラテン語の”聖なる”(典礼的なものとは対立する)音楽の中に身を置くことを好んでいた。 Thomas Tallis - Te Deum しかし、シェパードは第2サービスを設定した。それは、彼の最初のものよりもはるかに活発である。最初サービスは2つのM1A T B合の聖歌隊のためのものであるが、第2のものは5つの声部(M A A T B)の配置を有し、DecaniおよびCantorisセクションの4声に戻る。 シェパードは、同様のサービスを作曲したマンディやパーソンズと一緒に、この種の音楽において、スコアリング形式の慣習を確立することに影響を及ぼした。各Canticleや楽章はホモフォニック・フル・テクスチャーから始まり、その直後に、対位法が入ってきて、聖歌隊の交替サイドで歌われた。 以前のアンセムと詩編唱の慣習は、このようにしてサービス音楽に移された。冒頭動機による様々な楽章の始まりを結びつけることは、反面、随意アンティフォンをモデルとしたミサ曲の伝統に立ち返ることになった。また、プレインチャントTe Deumの独特の音調がシェパードの設定に引き継がれていることにも興味がそそられる。事実、後代の設定の多くのデザインは、こうした特徴に影響させられている。チューダー・ポリフォニーのルーツは、それゆえに、常に生きている。 高音域のtrebleのためのいくつかのアンセムは、Ludlow(Smith、1968)のような場所での使用に適応していた。 より顕著なのは、この時にこそ、trebleのためのアングリカン・サービス音楽が新しく作曲されたことである。 W.Mundy's Evening servlce 'In medio chori'は、朝の礼拝(明らかに無関係)と一緒に、このジャンルのエキサイティングなものであり、”trebleのための”シェパードのMagnificatとNunc Dimittis for treblesは、最も確かな作品の一つで、これを垣間見ることができる。作曲家の目は彼の応唱設定の豊富さを取り戻している。 オルガンスコアの形でしか現存していないが、シェパードのオリジナルのテクスチャーは、Nunc Dimittisの例のように(例149)作られているかもしれない。 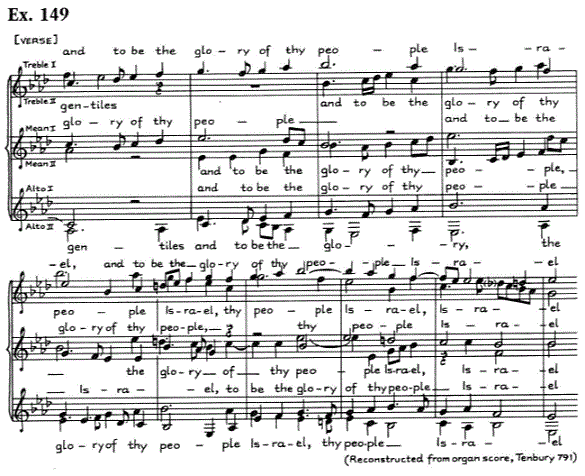 Nunc Dimittis - Sheppard (1515 - 1559) 4つのサービス (settings of canticles and other items for the new English Matins, Evensong and Communion services) は、すべての不完全な形で現存している。第2サービスは、それがバードのGreat Serviceに影響を与えたことで興味を持たれている。 (research by Richard Turbet).。https://en.wikipedia.org/wiki/John_Sheppard_(composer)#English_music シェパードよりも若い同時代人のうち、パーソンズは、1570年にNewarkのTrent川で悲劇的に溺死する前に、教会の音楽を比較的よく書いていた。.Mundy'sのMagnificatとNunc Dimittisは、「パーソンズの5声部のサービスのために」書かれた。 W.マンディは、多数のアンセムとともに、かなりの数のサービス(男声のための設定を含む)を作っている。アンセムの一部は、単に" Mundy"としか署名されておらず、彼によるものではないかもしれない。特に、多くの男声のためのいくつかの作品は、同じ圧力のためのサービスと同様、粗雑で魅力のないものである。 しかし、 ‘O Lord , the maker of all thing' は有名で、‘O Lord ,I bow the knees of my heart' はよく知られている。 O Lord the Maker of All Things - William Mundy 317 Mundy のverse anthemsは、そのジャンルの中で最も初期の企ての一部を表すという点で特に興味深いものである。しかし、それ以前でも、le Huray (1967、p。218)によって引用されたWanley partbooks では、韻律的な祈りが設定されている。現存していなくても、器楽伴奏がソロ・ラインを支持していたに違いない。後者は、コーラステクスチャの一部として使用している。 それほど基本的ではない技法が、ファラントの‘When as we sat in Babylon(詩編137)' の韻律的設定で採用されている。現存する形では伴奏はオルガンのものであるが、当初は、ビオールが含まれていたと考えられる(Reeve、1971参照)。合唱は、Verseの最後の小節の修飾版を繰り返している。前に説明したキャロル反復のやり方で。 Mundy's Verseのアンセム”Ah helpless wretch' や ‘ The secret sins' では、全く同じ技法が使われている。これらのアンセムは、オルガン伴奏で現存しているが、もともとコンサート用楽器のためにスコア化されていたようである。(略) p318 Parsons、Edwardes、Nathaniel Patrickはこれらの劇に関連するコンサートソングを書いたが、これらの作曲家によるVerse anthems は現存していない。ファラントとバード(特に後者)は両方のジャンルで多作であった。この種のおそらく最も初期のバードのアンセムの1つは ‘ Alack when I look back' である。これは、 Hunnis' 1583 collectionから、音調とテキストがとられている。 ここでは、初期のVerseアンセムのパターンが明白であり、キャロルのような、その最後の小節が繰り返されるような伴奏がついたソロverseから構成されている。 最後のverseでのみ、より広範な合唱がある。 このルフランパターンは、次に、バードのコンサートソングに引き渡される。 これらのいくつかは、ソロ・リピートがあるものもあれば、コーラス・パートが付いているものもある。 それゆえ、全体として、Verse anthemsの範疇にはいっている。 シェパードの ‘Of all strange news' は、英語のアンティフォン様式キャロルの後期の例であり、Verse anthemsの発展に影響を与えたようだ。同様に、ラテン語のレスポンソリウムとMagnificatsの間の生き生きとした特徴であった、チャント化したセクションとポリフォニーセクションの間のコントラストの喪失は、Verseと合唱の交替によって、果されることとなった。 Verse anthemsとサービスの初期の技法への詩編唱の影響は既に指摘されている。 この種の音楽における「繰り返し」の使用は、当時の型にはまったライター達によってしばしば攻撃された。そのひとり(ブラウン、1582)は、「彼らの詩編や文章の前後する振る舞いは、テニス選手のようだ」と観察していた。p Mathew ParkerのPsalter(c.1567)は、「The Rectors」、「Quiere」、「 'The Meane'」の指示を持ち、明らかに交互に歌っている。 同様のパターンが、バードによって「 ‘ Third psalm to the Second preces' 」(Teach me,O Lord 詩編119編)にて採用されている。 ‘Lift up your heads'を割り引いても、 バードの詩編は詩編唱の発展の移行期を示している。 タリスは、テノールの詩編音程をテノールに設定し、falso-bordone様式で、DecaniとCantrisを交互に演奏することで満足していた。しかし、Precesとレスポンソリウムにおいて、固有のチャントはテノールに保持されているが、特殊な詩編のひとつのみがプレインチャントを使っている。 p319 朝祷と晩祷の第1Precesとレスポンソリウムは、司祭によって歌われ始め、(「主よ、私たちの唇を開いてください」)と聖歌隊が(「私たちの口はあなたの賛美を示す」)と応答する。しかし、Sarum Rite の対応する部分とは異なり、合唱の反応はポリフォニーであった。そして合唱は、 ‘O Lord make haste to help us' に続いて、‘ Glory be . .. Praise ye the Lord' と歌う。続いて、特別な詩編が続き、それもまた、ポリフォニーに設定された。 PRECES and RESPONSES William Byrd <バードのサービス>
バードの「第1precesへの詩篇」は、「第2preces」よりも、明らかに後のものである。さらに、‘ Third psalm to the Second preces' の詩編(Teach me,O Lord 詩編119編)は、オルガンを伴なっている。オルガンの導入後、meanは第1verse ‘ Teach me, O Lord' を3拍子で歌い、その後、第2verseを合唱がfalso-bordoneで歌う。そこでは、tonus peregrinus の声が最上部で聞こえる。この過程は、同詩編全部に広げられる。 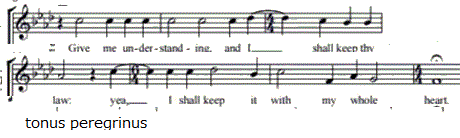 Teach Me O Lord p320 ‘When Israel came out of Egypt(詩編114編)' は、別のテクニックを採用している。ソロイントーン以外は、タリスの方法で合唱アンティフォンを行う。しかし、ここでは、バードは詩篇唱には言及していない。 「Hear my prayer」も同様だが、ソロのイントーンはない。同じパターンが、第1precesの‘O clap your hands(詩編47編)' に続いている。 詩編集はおそらく、バーナードによるものである。彼は、1641年の彼の刊行物に大きなセレクションを印刷した。バードの詩篇の連続は、明らかに異なった様式と日付の作品の間で方向が変わっている。その中で、 ‘ Save me, 0 God' (for the ‘First preces'詩編54編)は間違いなく、一番新しい。 ここでの設定は全体を通して3拍子で行われており、第3サービスのMagnificatとNunc Dimittisとは明らかにペアになっている。なぜなら、後者は、同じ拍子記号と同様の旋律的な素材を使用しているからである。’ Save me、0 God 'は、4声の上声部のための無伴奏のverseセクションと、4、5声の低声部とが交互に歌っている。ゆえに、初期の時代の随意アンティフォンが再燃し、Gloria(ドクソロジー)以降でのみ、フルコーラスが出現する。 バードのサービスは、エリザベス調とジェームス朝時代の形式の一般的な発展を反映している。 彼の最初のサービスはショートサービスである。サービスのこのタイプは、通常4声のアンティフォンで進行し、絶えずシラビックになっている。 バードのVenite(詩95編)の設定はこの種のものであるが、Te Deumはその後のBenedictus(ザカリアの頌)と同様に5声で始まって終了する。さまざまなスタイルが次々と表示される。 The Benedictus: Byrd Short Service 同様に、Kyrie(すなわち、 Commandmentsへのレスポンソリウム)はフル合唱であり、Creedは5声または6声のFULLセクションと、高声部と低声部が抜けた声部との繰り返しとなる。 いくつかのソースには、はっきりと4声版の繰り返しがある。確かに、聖体拝領の設定は、ほとんどKyrieとCreed以外のものを含んでいなかった。バードに帰されたサンクトゥスの設定もまた偽りである。 ShortサービスのEvening Canticlesは、スコアリングがより一貫しているため、より後のもののようである。サービスの初期の部分は、1563年からそこのオルガン奏者であったリンカーン時代のバードのものであった可能性があるが、後の部分は、1570年にパーソンズが死んだ後を引き継いだ、チャペル・ロイヤルに任命されてからのものであるかもしれない。成功した多くの音楽家に共通するように、彼は複数の任命を受けていた。少なくとも最初はしかし、1572年12月、彼は彼のリンカーンでのよい地位を捨てた。 Magnificat and Nunc Dimittis"Short Service" (William Byrd) 第2サービスは2つのバージョンに分かれている。最初のものはTenbury Orgarn Bookにあり、もうひとつは、Elyソースにある。改訂された形では、それは付属のVerseを具現化した成熟した作品である。それはVerse詩篇 ‘ Teach me 0 Lord' に関連しており、「as he promised彼が約束したとおりに」という節から明らかである。ここのところは tonus peregrinus を使っている。 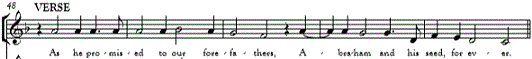 Full servicesと同様に、「冒頭動機」はMagnificatとNunc Dimittisを結びつけている。  p321 第3サービスは、3拍子で、5声の合唱が交替するフルサービスである。第2サービスのように、 Evening canticles だけ(MagnificatとNunc dimittis)が設定されている。 Nunc Dimittis (Third Service) - William Byrd しかし、Great service では、KyrieレスポンソリウムやCreed同様、Morning canticles (Veniteを含む)が含まれている。 Venite from the Great Service - William Byrd Te Deum from the Great Service - William Byrd Benedictus from the Great Service - William Byrd Byrd - Kyrie The Great Service Byrd - Creed The Great Service Byrd - Magnificat The Great Service 訳注;なお、この曲においては、バードにおいては数少ない(タリスではかなり多い)English Cadenceが1か所だけ見られる。 Byrd - Nunc dimittis The Great Service 大規模なテクスチャは、しばしば10声構成を含み、「ショートサービス」スタイルと完全な対照となっている。全体がシラビックなのではなく、設定の長さは、メリスマの使用からではなく、徹底した模倣的なテクスチャーに関わる繰り返しに拠っている。 バードのGreat service は、アングリカンの典礼に素晴らしい貢献をしており、ローマカトリックを堅実に守っていたにもかかわらず、彼はエリザベスの下のチャペルロイヤルの忠実なメンバーであった。女王がウスターの伯爵について言ったように、彼は「手堅い教皇(制度)礼賛者であり良き下僕」であった。 ‘O Lord , save thy Servant Elizabeth our Queen' は、心からの貢献であった。そしてその他の英語のフルアンセム (特に、 ‘Prevent us 0 Lord' ,‘ Sing joyfully' ,‘Arise 0 Lord ' , ‘ Unto the hills' and 'Turn our captivity' -これらは、彼がマドリガルコレクションとして出版したものだが)は、等しくすばらしい。"Exalt thyself"は、フルアンセムの歴史のランドマークである。なぜならそれは、ギボンズが彼に密接に関連した‘Hosanna to the Son of David'や Weelkesの ラテン語表現と自国口語の表現を混ぜ合わせてできた文体‘Gloria in excelsis'で取り上げられたternaryを利用しているからである。 第2サービスのように、 Evening canticles だけ(MagnificatとNunc dimittis)が設定されている。しかし、Great service では、KyrieレスポンソリウムやCreed同様、Morning canticles (Veniteを含む)が含まれている。 大規模なテクスチャは、しばしば10声構成を含み、「ショートサービス」スタイルと完全な対照となっている。全体がシラビックなのではなく、設定の長さは、メリスマの使用からではなく、徹底した模倣的なテクスチャーに関わる繰り返しに拠っている。 バードのGreat service は、アングリカンの典礼に素晴らしい貢献をしており、ローマカトリックを堅実に守っていたにもかかわらず、彼はエリザベスの下のチャペルロイヤルの忠実なメンバーであった。女王がウスターの伯爵について言ったように、彼は「手堅い教皇(制度)礼賛者であり良き下僕」であった。 ‘O Lord , save thy Servant Elizabeth our Queen' は、心からの貢献であった。そしてその他の英語のフルアンセム (特に、 ‘Prevent us 0 Lord' ,‘ Sing joyfully' ,‘Arise 0 Lord ' , ‘ Unto the hills' and 'Turn our captivity' -これらは、彼がマドリガルコレクションとして出版したものだが)は、等しくすばらしい。"Exalt thyself"は、フルアンセムの歴史のランドマークである。なぜならそれは、ギボンズが彼に密接に関連した‘Hosanna to the Son of David'や Weelkesの ラテン語表現と自国口語の表現を混ぜ合わせてできた文体‘Gloria in excelsis'で取り上げられたternaryを利用しているからである。 しかし、‘Gloria in excelsis'は、バードの作品の中で顕著な立場を保ち、国教忌避者サークルで特に人気があったであろうキャロルにも関連している。”This day Christ was born' (1611)のほかに、 ‘An earthly tree' や ‘From Virgin's womb' (ともに1589年)が印刷された。 後者は双方とも、交替で歌われており、あまり精巧でないMSのものである。明らかに教会の使用のためのものである。それらの元の版において、有節的に設定された、‘O God , that guides' (1611)と共通して、音楽的には無関係な合唱がコンソートソングに続いている。 O God, That Guides the Cheerful Sun - W. Byrd 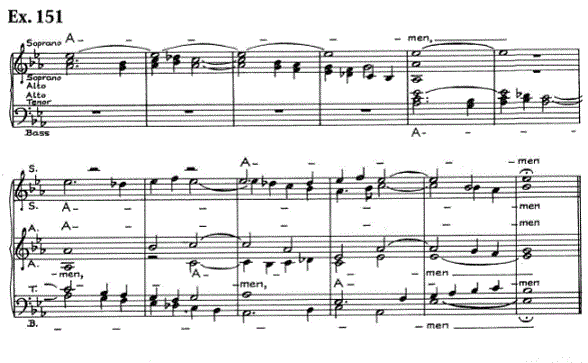 ‘From Virgin's womb' 4分?秒より ”This day Christ was born' 9分より An Earthly Tree (William Byrd) p322 これらのすばらしい作品は、1589年に出版された ‘Christ rising'の設定に合っており、 ‘Have mercy' (1611)と同様に、 Verse anthems とconcerted song との完全な結びつきを示している。‘Christ rising'では、Verseセクションが合唱と結びついている古い用例がより大きな自由で扱われている。この特徴は、アンセムの最初の部分全体では、見られない。‘Christ is risen again' では、Verseと合唱は、 バードをverseの技法のもっとも一貫した改革者のひとりとしてマークするのに役立つよう、巧みに統合されている。。 Verseサービスは、技法的には、伴奏された独奏的なパッセージがテクスチャに不可欠なサービスである。いくつかのフルサービスは、必要不可欠なVerseの適応やオルガン伴奏を有する。それゆえ1つジャンル内にとどまらない。 <Farrant> 最も早期の固有のVerseサービスはおそらく、ファラントによって行われた。彼のVerse anthemsの分野における先見性は、すでに論じられている。彼のVerseサービスは、バードの第2サービスのような音楽的関心はないが、そのパイオニア的なクオリティは、は必ず認識されねばならない。Verseは平均的に現れる。 ファラントの他の音楽、”Hide not thou thy face'や ‘Call to remembrance' は、長い間(Rim??bault 1872、pp。17 8-9、182)、チャペルロイヤルでの Maundy(洗足) servicesのために使われていた。 Hide Not Thou Thy Face Call to remembrance 'Lord ,for thy tender mercies' sake' はかつてはファラント作とされていたが、現在ではJohn Hilton作とされている。 FarrantのFullサービスにはいくつかメリットがありますが、全体的に彼の音楽はがっかりさせられる。彼の少年の演奏への関与とBlackfriars 劇場設立は、おそらく彼に、教会音楽として育っていく時間をほとんど与えなかった。彼はこうした義務に疲れ果て、チャペルロイヤルのジェントルマンとしての昔の地位に戻るために、St George's , Windsorでのポストを 辞した。彼は、1580年頃に死ぬまで、その地位にとどまった。。 Lord, for Thy Tender Mercy's Sake (Richard Farrant, ca 1525 - 1580) p323 St George's では、Magdalen College , OxfordのchoristerだったNathaniel Gilesがファラントを引き継いだ。GilesはHunnisに続き、Chapel Royalの少年部門のマスターとして、1597年に、ウィンザーで彼のポストを保持していた。ファラントと同様に、合唱団の少年の演奏への関与は、Gilesのサービスと賛歌に反映されている。彼のかなり多くの Verse anthemsは、meanのための多くのソロを含んでいる。彼の音楽は変わってきており、当時のトップランクにあったが、、偶然にも、半音階主義には何ら異様性を感じていない。  Verse anthemsについての彼の発展は、しばしば非常に個性的である。 いくつかの例では、Verseとフルパッセージは、繰り返すことなく交替するが、その他の例では、彼のスタイルの関心事に大きく貢献する発達と反復がある。 GilesはTallisの死の年である1585年にWindsorに到着した。 トマス・タリスの死は時代の終わりを刻んだ。感情は声高に、Byrd's Elegyを発した。そこでは、「タリスは死んだ、音楽は死ぬ」と結論付けている。彼は、グリニッジに埋葬された。そこでは、4人の君主につかえた彼の長い人生(service)の記念と彼の愛すべき気質との祝福が埋葬された。 (略) p326 <Weelkes> 作品 チャペル・ロイヤルの条件は耐えられるであろうが、教会音楽の実践は、世俗音楽への関与が音楽から十分な収入を得る唯一の方法であったように、退潮傾向にあった。 Chichesterのような地方の大聖堂では、規律は信じられないほどゆるく、士気は低かった。聖歌隊の管理会計は、大聖堂のサービスが、興行のよくないサーカスの予想よりもかなり尊厳が低かったという印象を与えたことだろう(cf ブラウン、1969)。 こうした人員不足のよろめき状態は、聖人を酔わせようとすることになる。そして、トーマス・ウィルクスは聖人ではなかったことが明らかになる。彼の無慈悲で酔っぱらった行動は、最終的に彼のポストに響き、チャペルロイヤルにおける世紀の地位を早くも失う結果となった。しかし、彼の性格におけるこのFalstaff (陽気な性格)は、彼の苦難の原因ではなく、大きな効果であった可能性がある。 若々しい野望の時代に、ウィルクスは一番最初のマドリガルのコレクションに見られるように、一貫して最高の音楽を作った。その後、より高いレベルに到達し、維持し続けたが、それほど頻繁ではなかった。同様のことはおそらく、他の形態の構成にも当てはまるが、彼は書いた。「これは、頂上としての霊感レベルの谷を示し」。むろん、彼のマドリガルは間違いなくウィルクスを代表しているが、主に注目を集めるのはアングリカン・サービスの音楽である。彼の最も個人的な貢献が見られるからである。 p327 <サービス>
ウィールクスのサービスは、以前の作曲家によって確立された変化を例示しているが、いくつかの興味深いバリエーションがある。彼のショートサービス(No.7はDavid Brownのナンバリング)は、この時代の他の例と区別されるようなものではない。 note-against-note homophonyに制限された時代に、彼の同僚の音楽的レトリックとは著しく異なることに多大な貢献をすることは困難であった。 しかし、 '第8'サービスは5声のものであり、より拡大したテクスチャと音域を提供している。オルガンスコアでしか現存していないが、Verseセクションは明らかにサービスであり、5声のアンティフォンが多くのテクスチャを通して意図されていることも明らかである。 2つの完全な5声の聖歌隊が効果的に要求されているので、この作品はチチェスターのために書かれたものではない。 Byrdの5声の第3サービスは規模がかなり小さく、均一なショートサービススタイルの厳しさから緩やかさへのブレイクは起こらない。まったくもって、ほとんどの比較できる設定は、Weelkesの「第8」サービス(そのテクスチャーは、Verseサービスのそれと同じように変化している)の独創性に近づくことはない。 第8'サービスはオルガンスコアでのみ現存するが、そのパート書法の指示は異様に多く、再構成を合理的な信頼で行うことができる。ウィールクスのサービスの規則的特徴は、アンセムからの引用をしていることである。サービスにおけるこれらのcontrafactセクションの出現は、アンセムとサービスが同時に使用されるように作曲されていることを示唆している。しかし、引用は、Weelkesの失われたオリジナルの結びつきを大きく助けるためには短すぎる。例えば、「第8」サービスでは、MagnicatのAmenだけが,彼のアンセム‘O how aimiable'から派生させられている。以下の例は、この作品の丹精な様式のいくつかを伝えている。 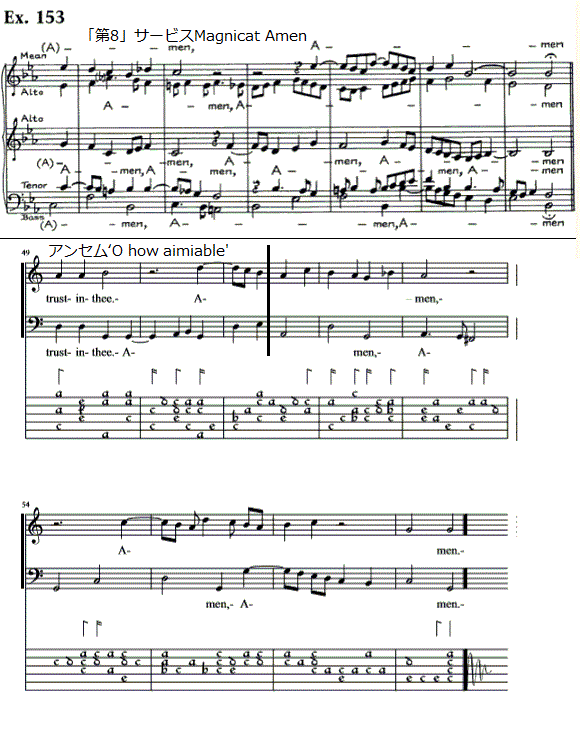 p328 「7声で」と表現されている第9サービスにおいては、テクスチャーはいっそう緻密であり、バスとmeanは二重になり、5パートの聖歌隊MAATBは、MMAATBBとなる。しかし、2声のアルトパートとテナーの倍増を考慮すると、同時に鳴り響く10声の可能性があり、そのために、この作品は、実際には、Great serviceとなる。テノールパートは、アルトパートの1つと同様、MSSでは欠失している。MagnificatのAmenだけが10声であるように見える。そのほかでは、スコアのパートは間引かれ、 2つの現存するパートは、明らかに3つの他のパート、ひとつのアルトと2つのテノールと結合している。 DecaniとCantorisの交代以外にも、Great serviceの特徴として、そこには、かなりの、減らされた声部やpart antiphonyがある。Verseはしばしば、ソリストによって歌われた。しかし、meanとバスは、それぞれずっと分割されている(必ずしも一緒に歌うわけではないが)。 再構築の問題は、Weelkesの音楽の一般的な特徴である緊密な編み込み模倣書法によって、単純化される。そして、 ‘ and the rich he hath sent empty away' やNunc DimittisのAmenには、 ‘O Lord ,grant the King a long life'からの引用がある。 Serviceにおける多くの良きパッセージのうちで、Magnificatの10声部のAmenを含め、Nunc Dimittisの ‘For mine eyes have seen' のセクションは特に注目すべきで、 確実にクライマックス感覚で、‘ and to be the glory'のセクションへと導く。 十分ではないとしても、Weelkesは最終的なburgeoning からテクスチャを抑制することができる。 . ‘ Glory be to the father' という言葉はアンティフォンスタイルで始まり、それに続くフルセクションが続く。Weelkesの技法的な優位性は明らかである。なぜなら、 ‘as it was in the beginning'は、 徐々に輝くように、サービス全体で初めて現れる強調されたトップのGに上がるからである。 Weelkesのアンセムには、文学への著名な貢献が含まれている。明らかに、 Morleyの名前で流布された設定の影響を受けて書かれた 'Laboravi'は、おそらく、オックスフォードの音楽博士号のための「作品」であった。 これは、Weelkesの唯一のラテン語の作品である。「Gloria in excelsis deo」はラテン語のルフランを持っているが、それ以外の部分は英語である。 refrain-verse-refrainパターンの使用は明らかにキャロルに回帰している。「Gloria in excelsis deo」はっ後期の例である。そのternary形式(良く知られたアンセム‘Alleluia I heard a voice' や ‘Hosanna'でも使われている)は別として、このキャロルはマドリガル風の調性変化に注目が集まる。特に、 'Crave thy God to tune thy heart'という単語において。 「Gloria in excelsis deo」  Weelkesのアンセム集はMB XXIIIで印刷されている。彼のサービスと同様、多くは不完全である。 ‘O Lord arise' , 'When Oavid heard' ,‘ O Jonathan' and ‘o Lord , grant the King' は、フルアンセムのすばらしい例であるが、そのレベルはいつも一様に高いわけではない。 Verseアンセムもまた、さまざまなレベルの達成度が示される。 ‘ Give the King thy judgements' ,‘ In thee 0 Lord' 、 ‘Plead thou my cause' は良い例である。 ‘Give ear ,O Lord' は、この分野でこの最高の試みの1つであり、おそらくこの時代の最も素晴らしい作品にランクされている。 (Ex. 156). 。 Weelkesのアンセムには、いくつかのマドリガル風の特色がある:しばしば、 ‘’Hosanna to the Son of David' のように、それらは、苦心のあとが見える。ギボンズの同じテキストによる設定はそれほどドラマチックではないが、よく抑制が効いている。彼の4つの出版されたマドリガル集は、この時代のテクニックの範囲を余すことなく示した。 Hosanna to the Son of David - Weelkes Hosanna to the Son of David - Gibbons 彼は、 ‘As Vesta was'や ‘Like two proud armics' のより伝統的なイメージを通して、 ‘O care thou wilt despatch me' や ‘ Thule、the period of cosmography' の表現から、ロンドンのcriesへの接触、 'The ape , the monkey and baboon'へ移り変わっている。 p329 Weelkesが最も一貫しているところにあるのは、これらのコレクションである。彼の教会音楽は(その質が)不均一ではあるが、彼は英国人のマドリガリストの中でも最も偉大な人のひとりであった。 それにもかかわらず、当時の音楽において特に重要な意味を持つServiceは、当時のService音楽の流れからそれらを排除するこのマドリガル風の自由の一部を持っている。 p332 宮廷では、Allison , Bennet , Hooper , Gibbons and Tomkinsらによる作品が増していった。たとえば、1605年の火薬陰謀事件(1605年にイングランドで発覚した政府転覆未遂事件である。イングランド国教会優遇政策の下で弾圧されていたカトリック教徒のうちの過激派によって計画されたものであるとされてきた。首謀者はロバート・ケイツビー、実行責任者はガイ・フォークス。上院議場の地下に仕掛けた大量の火薬 (gunpowder) を用いて、1605年11月5日の開院式に出席する国王ジェームズ1世らを爆殺する陰謀 (plot) を企てたが、実行直前に露見して失敗に終わった)は、感謝祭のアンセムを鼓舞した。地方では、ダーラムのウィリアム・スミスの音楽は名誉ある例外であるが、教会音楽は低調だった。 Byrd , Weelkes , Tomkins、 Gibbons は、以前に確立された標準状態を引き続き維持していた。トムキンスは別の時代なので、彼の特別な立場は次章で考察される。彼以外は、皆1,2年以内に死亡している( Byrd , Weelkes Gaude 1623年、ギボンズが1625年に死亡)が、ギボンズはJacobean教会音楽の主宰者である。 <Gibbons> 作品 Orlando Gibbons - The Best of Choral and Organ works 1. 00:00:00 - O clap your hands 2. 00:05:06 - Great Lord of Lords 3. 00:09:55 - Hosanna to the son of David 4. 00:12:49 - Prelude in G major 5. 00:14:40 - Out of the deep 6. 00:20:38 - See, see, the word is incarnate 7. 00:28:18 - Prelude in D minor 8. 00:29:33 - Lift up your heads 9. 00:32:46 - Almighty and everlasting God 10. 00:35:16 - Magnificat (2nd Service) 11. 00:41:49 - Nunc dimittis (2nd Service) 12. 00:45:45 - Fantazia of four parts 13. 00:51:05 - Magnificat (Short Service) 14. 00:54:25 - Nunc dimittis (Short Service) 15. 00:57:03 - O God, the king of glory 16. 01:01:30 - O Lord, in thy wrath オックスフォードとケンブリッジはともに、オーランド・ギボンズを育てたと主張している。彼は1583年にオックスフォードで生まれたが、約5年後に家族はケンブリッジに移ったからである。 そこでは、1596年からケンブリッジのキングズ・カレッジで聖歌隊の指揮者をしており、1606年、音楽博士の学位を取得した。まだ21才であった。 彼の演奏について、当時の報告は、彼が「英国の最上の手」と語っている。 別の作家は、彼の演奏を聞いて、「オルガンはその時代の最高の指に触れられた。」と言った。 1622年、ギボンズは Doctor of Music at Oxfordとなり、彼の友人のWilliam Heytherの仲間の一員になった。音楽の教授法が基礎づけられた。 翌年、ギボンズはウェストミンスター大修道院のオルガニストに任命された。しかし、すぐに、1625年に、チャペル・ロイヤルの紳士としてチャールズ王に出席している間に、彼は突然死亡した。王はカンタベリーに新しい妻Henrietta Mariaがフランスから到着するのを待っていた。6月5日に、ギボンズは脳卒中の運命的発作の襲われたのであった。 ギボンズは比較的早い年齢で(41歳)亡くなったが、この状況は、彼の作品の少なさとは関係ない。2つのサービス、2?3ダースのアンセム、マドリガルの本、適度な量の鍵盤と協奏曲、その他の雑多な作品。 p333 もっと若くして死んだパーセルと比べると、あるいはバードの数多くの作品と比べると、これらの少数の作品はまったく貧弱に見える。ギボンズは演奏家として多大な時間を費やし、作曲においても完璧主義者だったのかもしれないし、単に筆が遅かっただけだったのかもしれない。これらの理由のすべては、私たちに残された少ない遺産を説明するかもしれない。 しかし、このことから、特に貴重であり、部分的に失われた作品の一部を回復しようとすることは重要である。時の経過による(作品の)損壊は、かなりの自信を持って、Weelkesの作品のように、しばしばうまく再生されるかもしれない。これはGibbonsの作品のかなりの部分を占めているので、この作業は十分に価値がある。 しかし、明らかに私たちのために完全に保存されている作品でさえ、それらは見えるものではない。オルガン伴奏が存在する Verse anthems の多くは、もともとコンサート楽器のために設計されていたという証拠がある。Second service には、この種の伴奏があったかもしれない。なぜなら、そのソースの一つには、以前の器楽バージョンから来た可能性のある言葉がついていない部分があるためである。アンセム ‘Behold ,I bring you glad tidings .'の中にも同様の痕跡が見られる。他にもたとえば、 ‘Almighty God , who by thy Son' は、現在ではオルガンパートである部分を繰り返しているが、別の楽器の性格のように見える。複雑な対位法もなく、弦楽器の特徴もなく、 ‘O God the King of Glory'は、特にオルガンに合っている。さらに興味深いことは、”See , see , the word is incarnat”は別として、コンソートの伴奏が、唯一、1つの写本に残されていることである。 Oxford Ch Ch 21は、複数の点で並外れている。それは、スコア形式であり、当時としては非常に稀なことであった。加えてOrlando Gibbonsと謎の関係がある。写本は長い間、彼の自著であると考えられていたが、それは後で彼の息子、クリストファーのものであることが明らかになっている。これがどうあれ、このMSのバージョンは真実なのか疑わしいのかが、代わる代わる入れ替わる。”See , see , the word is incarnat”は、独立したソース(MyriellのTristitiae rem edium)に類似のバージョンが存在するが、他の場所には存在しない。 Oxford Ch Ch 21のアンセムの中には、作曲家による作曲の状況に関する見出しがある。 アンセム ‘Blessed are all they that fear the Lord'は、 ‘ wedding Anthem first made for my Lord of Summersett'として記載されている。しかし、この明らかに個人情報に対して、スコアで見つかったこのアンセムのバージョンは、他のMSSで見られるものとは驚くほど異なるやり方で終了する。 それは1613年の英語風嗜好を前にして、幾分、バロック的流れを持っている。クライストチャーチの資料を見れば、さらに他の興味深いことが明らかとなる。引き続きのペアである‘ This is the record of John'は、ギボンズがほとんど書いていないことが明かである。 'We praise thee , O father'は、オルガンソースに見られる導入が欠けている。そして、 ‘Glorious and powerful God' においては、 ‘points' のひとつが、上下逆に表示される(その効果は、バックで歌われる ‘cuckoo 'という言葉を聴くとむしろ現れる)。オルガンのスコアの源は明らかに正しい形式でこのパッセージを持っている(‘Sing unto the Lord' の特質 - EECM 3参照)。これらおよび他の多くの理由から、ギボンズは、そのままの状態として、これらの版の多くを書いたことはあり得ない。 一方、 ‘Glorious and powerful God' は5つの部分に分かれているが、この非常に人気のあるアンセムの他のすべての版は、明らかにオリジナルでは、4声構成である。そして、王のために作曲された2つの時折の作品を含む多くの独特なアンセムがあり、少なくとも1つの(悲惨で暴力的な‘O Lord , in thee is all my trust'))は初期の作品のようである。写本の証言はこのように矛盾している。 ギボンズのフルアンセムは、第1アルトとテノールパートが欠落している‘I am the resurrection' を除いて、現存している。 こうした欠落にもかかわらず、このアンセムはギボンズの最も洗練された作品の1つであることは明らかである。 p335 ギボンズがLeightonの1614年のコレクション「,‘OLord , how do my woes' と ‘OLord ,I lift my heart to thee 'に貢献した、非常に高価な光彩では、同じ高い基準が達成され、おそらく凌いでいる。 6声の ‘O Lord , in thy wrath'は、それ自身のクラスにある。 ‘Almighty and everlasting God' とともに、 Fellowes がこの音楽にもう一度光に当てて以来、半世紀にわたり大聖堂のレパートリーでその名誉を残していたことは間違いない。 Orlando Gibbons: O Lord, in thy wrath 同じことが’Hosanna to the son of davidにも当てはまる。 Byrdの「Exalt thyself」に形式的には、よく似ている(形式的に双方ともA B A構造であり、ある程度メロディも似ている)が、ギボンズは、はるかにエキサイティングなテクスチャーを作り出し、より強いデザインのセンスを示している。 最後に向かって、フルセクションが終了する前に、Verse冒頭が出現してくるところが見事である。 ‘ Hosanna' がこのように現れることは、耳をと想像力を巧みに捉え、作品の印象的な終わりを示す。 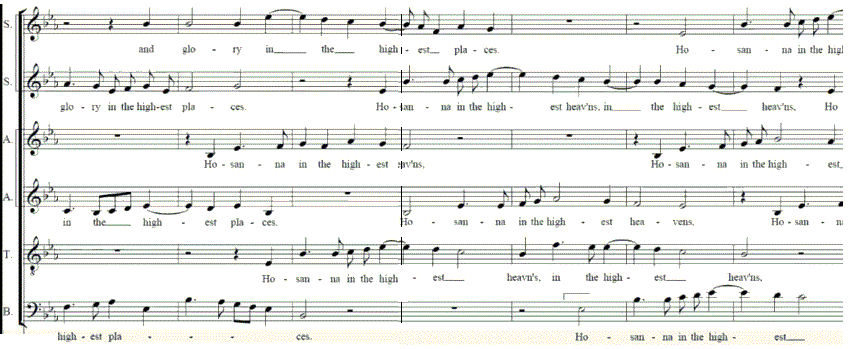 Heytherの音楽博士号の作品として書かれた大規模な ‘O clap your hands'はすべて8声であである。しかし、最初のセクションは、聖歌隊を8声部全体として取り扱い、第2セクション’God is gone up' はDecaniとCantoris の交替となっている。この活発なアンセムは、ギボンズの最も拡大した企ての一つであり、また、この時代の傑作の一つとも言わなければならない。 O Clap Your Hands Together - Gibbons 「Lift up your heads」, '0 Lord in thee is all my trust' や'Deliver us O Lord' や‘Out of the deep' らすべては、初期の作品であり、ギボンズが伝統への関心を惜しまなかったものである。 (18世紀初頭の)Tudwayの記述によれば、‘O Lord increase our (my) faith'は、ギボンズ作ではなく、 ‘Why art thou so heavy' とともに、 Henry Loosemore 作とされている。 Verse anthems に目を向けると、ギボンズがこの形式の巨匠であること、疑いない。’See , see , the word is incarnate' は、良いテキストの適切な設定である。 ‘ and heaven laid open to all sinners'の「バロック」的終止は、注目すべきである。いくつかの別のパッセージ、特に‘the powers of hell are shaken'での工夫されたクライマックスにおいてと同様に。 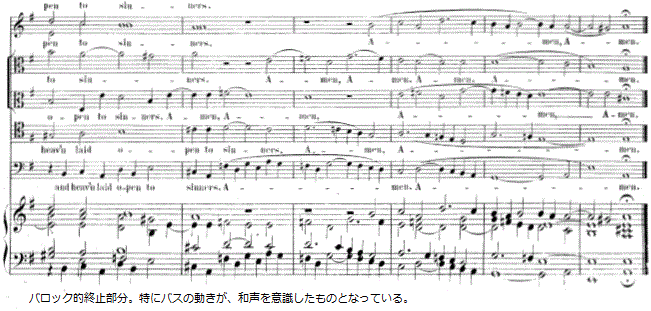 Gibbons: See, See the Word is Incarnate p336 このアンセムは、良く知られた ‘This is the record of John' とともに、完全に作られた対位法のテクスチャー中でdeclamatory な声部を包み込み、prima pratticaを seconda pratticaと結合するギボンズの奇妙な能力を示している。 ‘Sing unto the Lord' は、2つのバスのための珍しい冒頭二重唱と、 ‘when I go down into the pit'という言葉での効果的な音画法とを伴っている。この作品はまた、Verse anthems についてのギボンズが採用した様々な技法の良い例でもあり、VerseとFullセクションの間には時には繰り返しがなく、時にはセクションがありつぎになる。 Sing unto the Lord - Orlando Gibbons (1583 - 1625) ‘ We praise thee ,O Father'は別の素晴らしい例である。ここでの通常と異なる特徴は、‘for he is the very Paschal Lamb' におけるテノールの甘美なデュエットである。 ‘Blessed are all they' (1613) ,‘Glorious and powerful God' , 'If ye be risen' , 'Lord , grant grace' , そして‘O God the king of glory' はすべて、第一線として位置づけられる。 ‘Behold thou hast made my days' (1618) はそれほど成功していない。これらの付随的な見出しの唯一の源であるオックスフォードCh Ch 21によると、「このアンセムは、彼の死ぬ前の1週間前に、Doctor Maxcie , Deane of Winsor のentratieで作られた」。おそらくは、時間の圧力が、作曲家をして、奇妙な言葉の反復のためにコミカルなものに直面するセクション‘O spare me a little'のための義務を履行するために、 ‘lachrymae' パヴァーヌを使う原因となったのであろう。 機会のためのアンセムは、しばしば成功しています。特に、スコットランドの王のために1617年に書かれた‘Great King of Gods' がそうである。この作品は、1603年にイングランドの王になって以来、見たことがなかった母国のスコットランドへのジェームズ王の帰還によっても引き起こされたコンサートマドリガル‘Do not repine , fair Sun' の仲間である。その旅は、経費が掛かり、労力を要した。Holyroodのチャペルは改装され、新しいDallamオルガンがInigo Jonesによって設置され、エジンバラの学生が、ギリシャ語とラテン語のVerseで、賛美を表現した。‘Do not repine , fair Sun'は、スコットランドの息子の帰還を演じ、太陽が昇る場所(エジンバラでジェームズは生まれた)に言及して、堂々たる威厳によって、強く光った。 ‘Great King of Gods' Do not repine, fair sun (Orlando Gibbons) ジェームズ、「キリスト教世界の最も賢い愚か者」はまた、「‘O all true faithful hearts' 」(1619-「非常に危険な病気からの王の回復のための感謝」)において、評価された。後の ‘Thou God of wisdom' (fragmentary , but able to be completed) はあまり成功しなかったが、 ‘Grant , O holy Trinity' は、ギボンズの死んだ1625年の、6月12日の三位一体主日のチャールズ王のためのものであるが、ギボンズの過失が単に一時的であったことを示している。 p338 <ギボンズの Service 音楽>
 ギボンズの Service 音楽は重要で、比較的少量であるが。 4声の第1サービスの和らいだ性質は、この作品を、ギボンズの全期間の中で最も優れたFull Serviceの1つとして刻印する技法的保証を見えないようにしている。Precesの彼の設置は、率直に言って鈍いが、‘I will magnify thee' のような、第2precesに関連する詩篇は良く作られている。‘The eyes of all' は、Verseパッセージを持っているが、‘ Awake up my glory'は、より精巧な Verseの取り扱いをしている。 Gibbons - Magnificat (Short Service) 第2サービスがギボンズの最も優れた作品の一つであることはほとんど疑いがない。それはすべてのVerseサービスの中で最も完成度が高く、英語教会の歴史の主要なランドマークである。 Veniteは設定されていないが、通常のEvening Canticlesと一緒に、Te DeumとJubilate Deo(Gibbonsは、後の祈祷書で規定されたBenedictusに代わってJubilate Deoを設定した数少ない作曲家の1人であった)がある。 朝課のための現存するオルガンパートは、オリジナルを短く編曲したものと関連している。長い方の版がギボンズ自身のものであるということは、切り詰め版で明らかなバランスと幅の欠如とは別に、Gloria of the Jubilate (the same as that of the Magnificat and Nunc Dimittis)で明らかである。 このサービスでは、 'he hath shewed strength' あるいは 'he hath put down' での劇的なデュエットや二重デュエットから、穏やかな(フーガ様の) 'he remembering his mercy'へと典型的なギボンズが明らかである。  第2サービスは、比類のない最高のギボンズを表している。今日、彼のVerse anthems とサービスがなぜ彼のフルアンセムよりも劣っていると考えられてきたのかは分からない。 たとえば”チューダー教会音楽誌”の編集者たちは、「彼の功績は彼の同時代人によって幾分過大評価されていた」と結論づけている。そして‘O God the king of glory'のような「パイオニア的作品」において、その「未熟さ」を見いだしていた。 彼らは「(自らの主張の)大胆な確信をさせる」作品として、無感覚な ‘Lift up your heads' を取り上げいるので、我々は、これらその他のかなり不幸な判断に対して、18世紀の変わり目に、ギボンズの作品は、タリスやバードの時代以降に出現した教会音楽の中で最も完璧なものである、と書いたTudway以上に信頼をおくことはしないだろう。 特に、 Verse anthems がフルアンセムと比べて劣っていたという彼らの主張は、精査の必要はない。なぜなら、双方の種類の良い事例と悪い例とがあるが、多くの彼のVerse作品の質は非常に高いからである。 1つの特徴を取り上げるとすれば、それはルネサンス期の徹底した対位法的テクスチャーと、バロック的(モンテヴェルディ的)なdeclamatoryな様式との融和であろう。 ‘This is the record' , 'We praise thee 0 Father' ,‘ Sing unto the Lord' や、大部分の彼の他のVerse設定では、それらのソロパッセージにおいて、音楽的な制限なしに、recitativeのdeclamatory的な性質を持っている。 ギボンズは、彼の弟子のWalter PorterとChristopher Gibbons を通して、後の世代のための標準を設定した。それは、革命の頃のチャイルドのような取るに足りない努力にもかかわらず、BlowやPurcellに繰り越されていった。 BlowやPurcellは、GibbonsのFirstサービスにまでさかのぼって、彼らのサービスにカノン様のGloriaを取り入れた。BlowやPurcellの作品の多くに見られるdeclamation と expressive counterpoint の組み合わせでは、ギボンズの影響を見ることは困難ではない。パーセルの特別なファンタジアもまたギボンズの負うところは、疑いない。(略) ダウのパートブック(Oxford Ch Ch 98 98?88)の娯楽的な1つの意見は、キケロを引用して、英国人は、奴隷以外の略奪物を持っていない、誰も文学や音楽に熟達していない、と言っている。 Dowは、ラテン語の応答で言う。”バードは、こうした非難から英国人を開放した男だ”と。 ギボンズとバードは、ダウランドや他の多くと共に、意識的に大陸音楽の優越への挑戦をした。 そして、英国音楽は、最新の流行、特に(新しいバロック音楽の)朗唱の流行には乗り遅れたかもしれないが、その技法的達成は、決して大陸に遅れを取ったものではなく、純粋な表面上のレベルは保っていた。 しかし、時代は絶頂に達していた。 バードは1605年のGradualiaの序文で言った。「白鳥は、死が近づくと甘美に歌う」。 p340 シルバースワンの時代の終わりが近づいていた。1623年のバードの死に続いて、1625年のギボンズの突然の死があった。ジェームズ国王はその前年に亡くなっていた。チャールズ国王とヘンリエッタ王女は、代理人を通して結婚した。その後、新しい女王は、カンタベリーに来た。そこでは、結婚祭が始まる前に、ギボンズは、彼の碑文が言っているように、「嘆きのぼるような血の猛烈な駆け引きと運命の残酷な手によって人生を奪われた。1625年の聖霊降臨日に天に召された」 碑文は、彼の「指は球体の調和に匹敵する」と書き、彼のまっすぐで愉快な人格、音楽家気質、彼の妻の悲しみについて語っている。彼の気質はバードのそれと平行していた。彼らは(ギボンズの肖像が示唆しているように)「おのずから、威厳と篤信に満ちていた」。 不運なチャールズが王座に加わり、ギボンズが死亡したことで、英国の教会音楽の黄金時代は終わりを迎えた。しかし、この時代の残照はまだ残っていた。ウスターに。そこにはトムキンズが、なお古い様式で作曲を続けていた。チューダー時代の太陽が沈んだ後の夕暮れに、彼の音楽は、多くの業績の輝きに包まれた。 |