| TUDAR MUSIC12 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| CHAPTER 11 The Lighte of Candelles p292 1553年7月にメアリーが王位に就いたとき、英国は、プロテスタント派の偏見からローマカトリックへの再転換の狂信へ急転回した。 BucersとPeter Martyrsは大陸に逃げたたが、Cranmer、Latimer、および他の人たちは死を選び、関係者を軽蔑した。 Latimerによる初期プロテスタント説教は皮肉なことに預言的であった。 聖書よさようなら、ロザリオよこんにちは 福音書よさようなら、キャンドルの光よこんにちは 彼には、問題はこれほどに簡単であった。 しかしそれは、多くの英国人が外国の宗教と見なしたものに対して感じた嫌悪の原因となった、哀れなLatimerの嗜好であった。音楽家たちは疑いなく、Sarum Ritesへの復帰をうれしく思っていた。Samum Ritesは、エドワード朝のサービスの絶え間ない変化よりも、壮大さと安定を約束していた。 議会は統一令を撤回し、キャサリンとヘンリー王、メアリの父母の間の離婚を取り消し、彼女の合法性を確立した。 しかし、それは、ローマ法王の権威と隔離された教会の土地の復活に対する女王の要求に左右された。 議会はまた、ミサに出席しなかった人々に対して罰金を科すことも拒否した。メアリー統治の始まりは比較的平和であり、女王と彼女の主題の間には、ほとんど摩擦はなかった しかし、1年以内で、事態は変わった。女性独裁の考えはチューダーの嗜好ではなく、低い生まれの英国人と高位の外国人の婚姻による王位を描くことは、その継承の緊急性が何であれ、同じように厄介であった。 したがって、スペインのフェリペ2世との結婚は、事実上全会一致の閣僚の助言に対して、主要な動きではなかった。 議会は大変だった。 彼女の問題に火が付いた。 p293 一組の外国人を追い払って、別の人がその場所を取ると脅した。(メアリーとフェリペ2世の結婚に反対していた)Sir Thomas Wyattは、特にこの見通しを曖昧に見て、ばら戦争以来、他のどのような戦争よりもほぼ成功した反乱に、彼の疑いのない軍事的な洞察力を与えた。もしもメアリーが、Gardinerの忠告を受けて、ロンドンから去っていたら、ワイアットは勝利していたことだろう。 p294 しかし、そうはならなかった。勝利してロンドンの壁を壊す代わりに、彼はロンドン塔へと引き渡された。彼の行動は、無実だったLady Jane Grey をも同様の運命に導いた(連座させられた)。彼女は、エドワードの死後、9日間だけ女王の地位にあったが、メアリ派の主張によってすぐに退位させられた。 これらの死が政治的に必要だったならば、300人もの一般人の処刑者、ワイアットに続いたケント人は存在しなかったことだろう。結果として、民衆は今や公然と敵対的となった。同時に女王の心が頑なになった。 3月、ワイワットの不断のクーデターのあとの一か月後、メアリーはフェリペ2世と結婚した。 7月にはウィンチェスターで儀式が行われた。 11月24日、メアリーの計画の中で最も大切にされたものが成果を上げた。 エドワードの時代、枢機卿Reginald Poleは反逆のためにイギリスから追放されていた。 その後、彼はぎりぎりのところで、教皇になることを逃し、メアリーの元にいた。 彼女は議会にポールに対する告発を無効とさせ、教皇の覇権を受け入れるようにした。 しかし、教会の土地の問題は、依然として残っていた。 両者は29日に会い、その領域は、Reginald Poleによって、分裂から形式的に排除された。 メアリーの支配の最初の1年かそこらの間に、教会の音楽家たちは、無効とされたSarum Rite を復元するために膨大な仕事をしていたことだろう。メアリーの治世の時のものであったGyffardのパートブック(BL Add。17802-5)が、新しい君主の最初の年の王室礼拝堂の経過措置を反映していると見ることは、不可能ではないだろう。パート・ブックは、Masses、Magnificats、antiphons、Passion、Psalms、Hymns、resondsの写しであり、そしてその多くが、礼拝堂の2人に主要作曲家であるTallisとSheppardによるものであると思われる。 しかし、その音楽のほとんどが男声のためであることは、Sarum liturgyやその polyphonyにおいて、実質的に訓練されていない少年を指導することの困難さを反映している。 音楽の多くは、おそらく1554年の復活祭のためのものである。Tavernerの「Dum transisset」は4声で構成されているが、彼の「Audivi」はSarum Riteから要求された少年ためのオリジナルバージョンである。これは、音域が1オクターブ下に移調された少年のための設定を示すように見える、シェパードの「Audivi」には、当てはまらない。タリスの設定は、おそらく最初は、男声のための作品であった。それは、 Sheppardとは対照的に、ヘンリー王時代の作品ではないようである。 MSSの興味深いことは、それらが多かれ少なかれ典礼的順序で並んでいることであるが、それに加えて(Bray、1969によって指摘されているように)、さらに、作曲家はしばしば年功序列で組み立てられていることである。 それゆえ、Robert Cooper , Barber and Robert johnson (a Scotsman , born in about 1490)は、Taverner、van Wilder、Tye、Tallis、Sheppard、Blithemanより前に来ている。 Thomas Wrightの「Nesciens mater」は、Richard Bramstonの「Recordare domine」とともに、コレクションの宝石の一つである。Te Deum設定のあとには、 ポリフォニーのミサの固有文と通常文が置かれ、そのあとに、 All Saints から Easterまでの聖務日課のポリフォニーから成っている。さらに、Jesus Mass Propers , その他の Masses , Magnificats や antiphonsが続いている。Easterのための豊かな音楽の間には、シェパードによる行列詩編 ‘Laudate pueri'の男声のための設定と、「マンディとバード」の共同で作曲された、 ‘In exitu' がある。 この音楽の少なくともいくつかは、1553年の All Saints' Day (11月1日)から翌年のほぼ同じ時まで、チャペル・ロイヤルの聖歌隊は、高いtreble様式の以前の素晴らしさを復元する前にそのレパートリーを築いた。 1554年の11月に、Stow(1580)は、「Ne timeas Maria」が歌われた前に、、「Te Deum」と「Salve festa dies」(Bray、1981)後に、説教が行われたと記録している。 Sarah Cobboldは、「Ne timeas Maria」(レスポンソリウム「Dixit Angelus」からのもの)とSheppardのミサ曲‘ Be not afraid'のテーマのつながりを指摘している。ミサが同じ機会に作曲された可能性は、後者が明らかに男性の声のために急いで未完成の作品であるという事実によって強化される。 この機会に、GyffardパートブックのSheppardのEaster 'Salve festa dies'を使用することができた(Sheppardによって設定された部分はすべての季節で同じである)。また、Tavernerの名前で登場するTe Deumが実際にはSheppard作(彼のあまり壮大ではない6声設定よりも作曲家の特徴的があると思われる)である可能性がある場合、この作品は、男声のための三部作の完成かもしれない。この三部作は、おそらくミサが根拠とした、失われた作品‘Ne timeas' を含むこの機会のために、シェパードが作曲した。 もしそうであれば、、Gyffardパートブックに「Audivi」(11月1日)の男声のための2つの設定があるので、少年たちは、慣れ親しんだ特権を取る準備がまだできていない可能性がある。タリスの男声のための ‘ Hodie .. . Gloria in excelsis '(冒頭はポリフォニーで設定されている)は、同じ方向のものである。彼の「Audivi」とは違って、これは以前の作品の転調バージョンであるようだが、Tavernerによるこれらのレスポンソリウムの設定は、不調であり、SheppardとCooperの設定に取って代わられた可能性が高いようだ。 Sheppardの 'Frences'ミサも、もっと古い作品の編曲であったようだ。 Noble (apud Doe , 1968)が指摘しているように、枢機卿Reginald Poleによる国家の「赦免」は、タリスの「Suscipe quaeso」の機会となったかもしれない。それは、Tallisの 'Puer Natus' Massと同じ声部(M M A A T B B)に設定されている。女王メアリーは自身が王位継承者であると確信していたので、1554年のクリスマスに、Tallisの 'Puer Natus' Massは二重に充当させられた。 p295 Philip2世の華麗なCapilla flamencaには、7人の少年、4人のアルト、6人のテノールおよびPhilippe de Monte を含む4人のバスがいたが、兄弟であるCabezonその他の著名な音楽家も伴っていた。 彼らは、12月2日に、そしておそらくクリスマスにも、イギリスのチャペル・ロイヤル(セント・ポール)でミサに参加した。 ‘ Puer natus' ミサの奇妙な声の傾向は、Capillaのそれを反映している。cantus firmusの取り扱いや、模倣の深みは、外国人に彼の英語のpustureの気質を示すための、タリスによるマニフェストであった。 同様に、「Suscipe quaeso」の二重の模倣も同様の機能を持っている可能性がある。 1555年、宗教的状況は悪い方向に向かっていった。なぜなら、この年は、クランマーやその他のオクスフォードの殉教者たちが火刑にされた年だからである。迫害は、メアリーの師の1558年まで、その報復とともに続いた。しかし音楽家たちはおそらく、こうした問題を心の奥底にしまっていた。シェパードやタリスのヒムやレスポンソリウムの大部分は、メアリー―王朝時代に作られた。状況が改善するにつれ、meansやtrebleのための音楽は、より普及していった。そして、いくつかの”二重”設定が、Chapel Royal の聖務日課のポリフォニーのレパートリーの発展や改訂に帰せられた。Redford , Parsons 、 Mundy らが貢献した。特にTallisとSheppardは、ポリフォニーのレスポンソリウムやヒムのサイクルおいての貢献をした。 p297 レスポンソリウム様式の絶頂期は、”Gaude, gaude, gaude' by Sheppard ,や ”Videte miraculum ' by Tallis. といったキャンドルミサの作品において、見出される。タリスは、これまでシェパードの嗜好であった霊感のバランスを是正している。”Videte miraculum ' において、”Maria”という言葉の音楽上の強調は、より君主制にふさわしかった。 タリスの'‘ Gaude gloriosa' は、テキストに多くのマリアへの言及があり、メアリー女王を記念して特に書かれたものではあったが、この時期に復活した。なぜなら、ぞんざいなテキストが、”真の”境界の回復への言及と解釈されたからである。 縮約された音楽とフルセクションの間の、Tudor Church Musicにおいて印刷された休止は、誤りである。John Milsom が指摘したように、これらの休止はソースで示されたように、フルアンセムの終わりと定義されている。 ‘ Gaude gloriosa 'は、より有名であったSheppardの‘ Gaude virgo christiphera"に隠れがちではあるが、よい作品である。これらの随意アンティフォンは、Mundyの” Vox patris coelestis' への霊感となったと思われる。同じくMundyの‘ Maria virgo sanctissima' は、顕著な大規模作品であるが、より長い” Vox patris coelestis'は、おそらくはこの分野において、最良の作品としてそびえている。 Mundyの‘ Videte miraculum ' は、タリスの設定と比較すると、劣る。” Vox patris coelestis'は、その建築的センスやその無双のメロディにおいて、‘ Gaude gloriosa 'よりも優れている。‘ Gaude gloriosa 'において、タリスは、trebleとmeanに対して、"Gaude virgo"よりも早く、クライマックスを置いている。Mundyは、彼のgimelである ‘ Veni ad me' を、最後のフルセクションに先立って残している。 (略) p299 シェパードの6声のマニフィカトは、Tye , White , Parsons , Mundy等の設定と同様、、古いアンティフォン様式のレイアウトを保っている。彼らの設定における類似点も、Magnificatsで公式をコピーするという伝統を引き継いでいる。 残念ながら、これらの作品のほとんどと共通して、シェパードの6声の設定は不完全にしか保存されていない。 しかし、後に書かれたSheppardによる男声のためのMagnificatは、そのまま現存している。これは初期の大規模な作品を反映している。 シェパードの音楽の時系列の問題は、彼のキャリアの知識がほとんど完全に不足しているために、はっきりとしていない。タリスより年少ではあるが、彼は1515年に生まれた可能性が高い。なぜなら1554年の、オクスフォード大学の音楽博士への彼の嘆願が、通常の公式‘studiosus musices quatenus viginti annos'を持っていたためである。 通常の式「studiosus musiques quatenus viginti annos」を持っていました。 1543年から1548年にかけて、彼はMagdalen CollegeのJormator chorisfarumに、Appelbyに続いて、1年後に辞職した(リンカーンに戻り、Tavernerとの面白い並行を与えた)。 1553年、シェパードは紳士としてチャペル・ロイヤルに加わりました(ストウ571 f。36v、エクッチ・ロール434,5~10)。後者のMSには、1553年のクイーン・メアリーの戴冠式と関連していたかもしれないことへの言及がある。「クイーンズ・シェイプ」のメンバーであるMSSは、マグダレンとの関係を失った。この日付には、Sheppardと同じ名前の大学の他の一員と混同している可能性のある同僚のレコードに関連するいくつかの問題があります。確かにシェパードはフェローではなく、時には述べられています。チャペル・ロイヤル・シドロック(Exch。Rolls p300 <W.Mundy> ウィリアム・マンディの業績は相当なものである。実際、Robert Dow が彼のパートブック(オックスフォードCh Ch 98-8)に入れた行では、マンディを月に、バードを太陽にと、はっきりと比較していた。 p301 すでに述べたように、「Vox patris coelestis」は、その時代の最上の業績の1つとして説明されなければならない。初期の ‘square' ミサ曲と、彼のマニフィカト、そしてGyffard partbooks 中のその他の作品は、少なくとも彼の作品の中では、興味ぶかいものである。しかし、退屈なレベルを上回らないものもいくつかある。 しかし、強力な「Sive vigilem」と印象的な「Beatus et sanctus」は、彼がチャペル・ロイヤル・サイクルに貢献したと思われる賛歌の1つか2つとして、注目に値する作品で、'A solis ortus' は、最も印象的である。 マンディの詩篇は様々な形で定められています。 'Eoliavit cor meum'は古いantiphon 様式であるが、 'Noli aemulare'と 'Domine quis habitabit'はSheppardの詩篇と技術的に似ている。 優れた「Adolescentulus sum」は、そのスタイルがElizabethanなので、おそらく後の日付である。 大陸の影響は、マンディのテキストの選択において明白である。Henry Chadwickが示したように、彼のMiserereのテキストは、1556年にウルガタ聖書と並行して印刷されたヒューマニストの版に基づいている。 <Robert White> ロバート・ホワイトもかなりの数の詩編作曲を作った。 Mundyとは違って、実質的にすべてのWhiteの音楽が出版されている。 まだそれは、その価値を認識していない。 1926年、Tudor Church Music の編集者は次のように書いている。「時間と変化が、間違いない試金石によって評判を得ようという心地よい信念がある。 忘却の不義は、結局のところ、盲目的にそのポピーを散らしていない。この信念は、ロバートホワイトによって急激に挑戦されている。 たとえ英語のポリフォニー楽派の名声が最も低くなっていたとしても、バードとタリスは、名誉の小箱を得ている。 ホワイトの、その音楽は、スキル、発明、誠実さのために、彼らの立場に立つのにふさわしく、当時の評判は高いが、・・・名前は無視されている。」 今日、半世紀以上経過し、ホワイトの名前は間違いなく無視されてはいないが、彼の音楽のクオリティが適切に評価されているかどうかは、未解決の問題である。 それにもかかわらず、2人の Robert Whitesが存在することは認められなければならない。 ひとりは知的内容が感情をはるかに上回る複雑な対位法に陥っていた。 ここでは、作曲家の高い創意工夫が、私たちの頭をはるかに超えている。 他のロバート・ホワイトは、この技術的な腕前をより暖かく、より親しみやすい表現の方法と調和させる。 この後者の個性が込められた作品は、ホワイトがタリス、シェパード、マンディーが共演した輝かしい大空の中で最も明るい光の1つになることを目指すべきであるという独創性を示している。(略) 現存するホワイトの作品の中で、そのMagnificatは、おそらく彼の作曲の初期のエッセイの1つである。それは、対位法の流れの組織化において、cantus firmus の使い方において、そしてそれぞれの声部における声楽的特徴において、Tavernerの影響の切り株をになっている。 成熟したホワイトはまだこの作品では明らかではないが、私たちは若々しい新鮮さでこのpersonaの何かを見ることができる。treble声部は残念ながら欠けているが、さほどの影響はなく、treble gimelを必要とするように見える「Esurientes」では十分に重みがある。 ホワイトの対位法の創意工夫は、彼がcantus firmus を使っているほどには明らかではない。 'Regina coeli'では、男声のために、テノールがプレインチャントを長い音符で歌う。ポリフォニーの帆が付いている音楽のメイン・マストとしての役割を果たすが、随意アンティフォンでは珍しい過程である。「Tota pulchra es」は同じ独特の特徴を発揮する。 これらのCantus firmus antiphonsは、ケンブリッジのトリニティカレッジで1554年〜1562年の間に作曲された可能性がある。後年、ホワイトはクリストファー・タイにElyで引き継いだ後、タイの娘エレンと結婚した。 2人の男性が、音楽の個性によってつながっている。彼らの作品は、特定の特有の特質によって似通っている。 ホワイトの幾分技法的な作曲への態度は、夜課の賛歌「Christe、qui lux stee dies(歌詞)」を4回以上設定した場合などに、同じテキストを〜3回使用するという困難な課題に取り組んだときに、観察される。明らかに彼はそのテキストに多くの魅力を感じ、彼の様々な取り組みで、素晴らしい創造性を示している。 すべての設定はalternatimに行われており、すべてがcantus firmusとしてチャントを含んでいる。trebleでの第1設定は、note- against-note style で、後に、バードによって模倣される。 White Christe Qui Lux es et Dies I Byrd: Christe qui lux es et dies 第2設定は、trebleにおいて、長い音符でのチャントを持っている。第3設定はまた、一番素晴らしいものであるが、trebleにcantus firmusを持っている。ここでは、祝祭と感情の性質が等しい条件で出会っている。 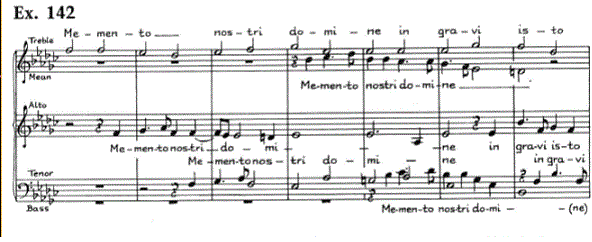 p303 この賛歌の4番目の設定では、インスピレーションのレベルはわずかに低い。それでも、それはまだ、特にその最後まで、驚くべき作品である。これらの5声の設定はすべてボーカル(さらに、純粋に4声の器楽的な設定が存在する)であるが、典礼的な使用のために作曲されたようには見えない。それらは、バードが模倣した形の楽器の作品としてかなりの流行をした。 Robert White - 'Christe qui lux es et dies' IV しかし、ホワイトの主な関心事は、彼の詩編の設定であった。 Mundyと同じく、このジャンルでの彼の初期のエッセイは、 "Portio mea"とJustus es "がおそらく最も印象的な古風なアンティフォンスタイルにある。 'Exaudiat te'と 'Domine quis habitabit'のバージョンの1つは、思い出に残るパッセージがある。 ホワイトは後者のテキストを3回変え、3組の声部の最終的な設定が最も素晴らしい。そこには‘ non movebitur 'で頂点に達する、言葉の音画法のよい扱いがある。そこでは、適切に執拗な姿が、共鳴しているアーメンにほとんど不本意に動いているように見える。ホワイトは、エリザベス朝の儀式のために作られた、特に鼓舞されることのない英語作品のひとつのために、英語の同じ詩編に立ち戻った。 Robert Whyte - Domine, quis habitabit (III) 'Christe qui lux es et dies' の写本のひとつに、Dowはラテン語のモットーを書いた。 Maxima musarum nostrarum gloria White Tu peris,aeternum sed tua musa manet ホワイトは、我々の芸術の輝かしいリーダー、あなたが死んでも、あなたのミューズは永遠に生きている 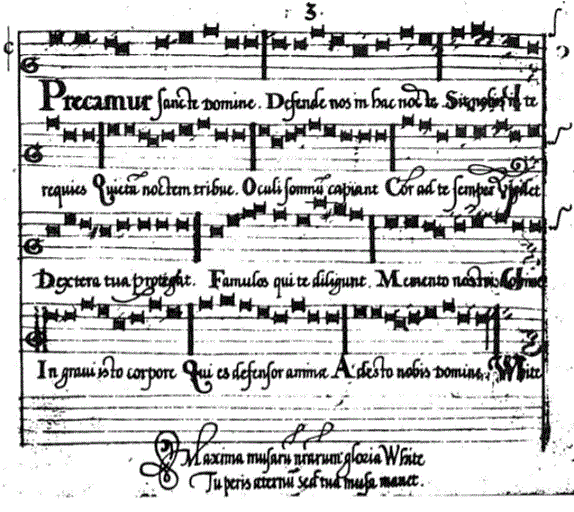 ホワイトの死は悲劇的だった。彼と家族全員が疫病に襲われた。彼のLamentationsは、彼の白鳥の歌と見なされるかもしれない。なぜなら、それらは、彼のもっとも成功した作品の間にあり、それらが彼の最新の作品の中にあることは不可能ではないからである。 最初期のLamentationsの設定は、6声であるが、非常に劣っている。 Robert White - Lamentation a 6 5声のバージョンでは、以前の素材の一部を手堅く再利用している。タリスの哀歌と同じく、この作品はSarum典礼から逸脱しているために非典礼的であるが、ホワイトのテキストの取り扱いはタリスのそれとは著しく異なる。 p304 ホワイトは、trebleを用いる(タリスはmeansを用いた)が、預言者の言葉における、諦められた、絶望的な音色を強調し、意図的にあまり劇的ではないテクスチャーを生み出している。 それにもかかわらず、同時代の大部分の音楽よりもやや大陸的な音を奏でるこの音楽では、徹底した誠実さがある。ホワイトとタリス5声のLamentationsは、現実にはペア設定であり、それぞれが 'Jerusalem , convertere ad dominum deum tuum' の嘆願で終わる。これらの作曲家は、バードと同様、テキストの同じ部分をめったに設定しないため、重複を避けているように見えることは注目に値する。特定の古典的な公式、特にカデンツの使用は、これら3人の作曲家を結びつける。 Whiteの5声のLamentations の写譜の最後に、Dowは以下のcoupletを書いた。: Non ita moesta sonant plangentis verba prophetae Quam sonant authoris musica maesta mei 予言のもの悲しく鳴り響く言葉は、この作曲家の音楽の陰鬱さが私に対するほどに悲しいものではない。 p305 その嗜好のいくつかは、以下の例で味わうことができる。これは、ヘブライ語のTethという1語の設定である。 元の各行最初[最後]の字を並べるとある単語になる遊戯詩では、各verseは,ヘブライ文字のアルファベットから異なった文字で始まっていた。ラテン語のプレインチャントは、それぞれのverseの前のメリスマに文字を設定することによって、この文字通りの奇抜な思いつきを保存した。 この実践はポリフォニー・セクションに伝わり、作曲家は抽象的な作曲の贅沢を可能にした。こうしたパッセージは、光彩を持つ最初の文字の音楽的同価である。 Robert White Lamentations a 5 Lectio Prima  Dublin Virginal Book(Ward、1983、no。21)のパヴァーヌの1つが、同じパッセージ(LAMEDの文字の部分)に基づいて作成されていることに注意したい。 WhiteのLamentationsは、そのtrebleの声部の使い方において、Parsleyに従っている。タリスは、mean声部においては、ラッススの様式を英国に引き渡す際の仲介者であったAlfonso Ferrabosco IIの Lamentations の影響を受けたと思われる。 <Tallis> メアリー王朝の支配が終わるまで、タリスの様式は、拡大したアンティフォンテクスチャーに最も適していたが、私たちが見たように、長いレスポンソリウムやヒムにおいて、それほど成功しているわけではない。 しかし、「Videte miraculum」は、Tallisが後に開発した表現力豊かな最新の技法を示している。それらは、後にタリス自身が発展させ、シェパードの死によって否定されたものである。 Tallis Videte miraculum エリザベス朝の時代になってからは、ラテン語のポリフォニーはもはや英語の儀式の一部分ではなく、タリスは新しいスタイルを容易に感じていたようである。彼がバードと共同で出版したマニフェスト、1575年のCantiones quae ab argumento sacrae vocanturでさえ、暫定的であるか時代遅れのものとして取り扱われた。しかし、「Absterge domine」、「Injejunio」、「Salvator mundi」、そしてhymn 'o nata lux 'は、タリスが、すべてが典礼起源である「Candidi facti sunt」、「Honor virtus」、「Te lucis」からどれだけ進展してきたかを示している。 Thomas Tallis: Te lucis ante terminum Salvator Mundi - Tallis エレミヤの哀歌において、タリスは彼の最も集中したポリフォニーを書いていいる。 ホワイトの設定と同様に、そこには、ヘブライ語の文字を導く設定における「純粋な」音楽の機会がある。 TallisはMAATBを使用し、その結果、音調は、誤って書かれたピッチのままで歌われると、よい結果がでない。 最初の長い嘆きの設定のそれぞれのページは思い出深いものであるが、「plor ans ploravit」で始まるセクションはおそらく特に注目に値するであろう。すばらしい憂い、Jerusalemへの喜ばしい呼び声に溶け込んでいく。 低い、オルガンの和音は、特に独特の質を持っている。 p306  Thomas Tallis - Lamentations of Jeremiah I 哀歌の第2設定の中の「Daleth」は同様のカデンツを持っており、、Morleyによってけなされているが、Tallisの多くの作品で共有されているのと同じようなリズムを持っている。文字Heは、偶然、いくつかのソースで間違ってHethと書かれた。 この設定の焦点は、カデンツ前の移行部分である。 タリスの好んだカデンツ(Doe、1968)は、Parvuli ejus ducti sunt captivi ante faciem tribulantis」とそれに続く「Jerusalem convertere」の効果に使用されており、第1設定のところとは異なったやり方になっている(2つの設定は、別の調性となっている)。ここでの Jerusalem へのアピールの上下は、別の手段で成し遂げられている。  Latin text p307 タリスの詩編設定( 'Domine quis habitabitと' Laudate dominum 'は、流行ジャンルでは特に区別されたエッセイではない。同じように不満足なのが、ラテン語のMagnificat と Nunc Dimittis の奇妙なペア設定である。 シラビックな歌詞付けに伴うtreblesの使用は、‘In manus tuas'の非典礼的設定にはないある種の臆病さを形成している。‘ O sacrum convlvium'はtrebleはないが、エリザベス朝時代には有名になった。双方ともラテン語と英語版がある。 O Sacrum Convivium (Thomas Tallis) - In Manus Tuas (Tallis)- タリスの最高傑作は、疑いなく、‘ Spem in alium' である。この40声のための驚くべき作品は、最高級のシリーズとして記述されることだろう。その概念は、Striggioのいくぶん陳腐な40声作品への挑戦としてその起源がある。作品は、数奇な運命にあったDuke of Norfolkのために書かれ、1571年の彼の短い自由な時代に演奏された。 タリスの技法的達成は、そこに光が当たって再び光り輝いて初めて、声は単に従来の手法で音符を埋めることによって時を刻むことを明らかにする、という事実に拠っている。 一方、それぞれの歌手にとっては、テクスチャーのもっとも重要なところを与えられているという想像をすることが可能である。 タリスは8つの聖歌隊(それぞれは当時としては稀であったTr M A T Bで配列されている)を、ある時は分離し、ある時は連続しある時にはポリコラールで、ある時には全体の40声のテクスチャーで、と取り扱っている。しかしそこにはどこにも、霊感の技法的抑制やつまずきの証拠は存在しない。 テキストの拡大した取り扱いは、声楽に、Magnificat と Nunc Dimittis のペアにおいて否定された拡がりを成し遂げさせる。 すべての40声が"respice”を歌う前にドラマティックな休符を伴ってセクションが始まるのは、このあとに4つの聖歌隊がペアで歌うが、おそらく、注目すべきであろう。 p308 作品は、別の”respice"の後に、同じやりかたで終止する。そして、40声の長い結語が続く。 小規模な ‘O nata lux' (scored for Tr M A T B) ,やエレミヤの哀歌、とともに、あるいは1575年の Cantionesとともに、‘Spem in alium'は、タリスの人生における、実りの秋の重要な証明である。春の開花のための種子は、彼の友人であり、後輩であるWilliam Byrdへとセットされた。 <W.バード> List of compositions by William Byrd タリスと異なり、バードは国教会忌避派であった。ラテン語のポリフォニーはエリザベス朝によって禁止されてはおらず、違法的儀式の象徴としても解釈されていなかったが、タリスとバードの1575年のコレクションは、Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur と呼ばれ、そのタイトルは暗に、神聖な言葉の選択であることを意味していた。 バードのラテン語作品の多くは、楽しむために歌われる音楽として、あるいはラテン語が理解されたラテン語のアンセムとして解釈されることができる。しかし、その大部分は、バードのローマ教会の忠誠についての情熱的信奉を例証している。それは、セーラム儀礼との結びつきが壊れたことで、二重に非合法となったが。そしてそれは見知らぬ、まったくの反逆的なものとなってしまった。 バードの最初期の作品、すなわち、 ‘Christe qui lux' ,エレミヤの哀歌 , あるいは ‘ Laudate pueri ”などは、賞賛に値する作品であるが、それは決して1つの流れだけではない。'Laudate pueri ”は、器楽ファンタジアからのadaptationにすぎない。 「Christe qui lux」は、cantus firmusを、連続声部や調性を通してシフトさせることによって、Whiteを超えることを試みている。しかし、スキームの興味は、ホワイトと比較してのハーモニーの威風堂々によって廃止されている。 バードはまた、このヒムの器楽バージョンの1つを、他のホワイトの設定で、密接にモデル化した。 エレミヤの哀歌は、古風なカデンツを含み、タリスのそれを参照としているが、タリスが持っている集中力は、Byrd'ではより散発的である。しかし、 'Emendemus' は、それが包括する表現豊かな音域の予感を与える。 パーソンズの作品はバードのそれに影響を与えているように見える。‘ Peccantem me' や‘Libera me' は、古い作曲家の同じタイトルの作品の前例を持っている。 しかし、Alfonso Ferrabosco IIの音楽は、バードが初期の音楽の大部分を流行させる最後の要素となった。 ラッソスや他の大陸の作曲家は、古典的なラテン語の韻律の復興に強く関心を持ち、しばしば、Roman Sapphic」などの韻律の設定に影響を与えた。 'Ecce jam noctis'と 'Siderum rector'はいずれも、長短の古典的パターンに従い、フェラボスコを通して翻訳された。 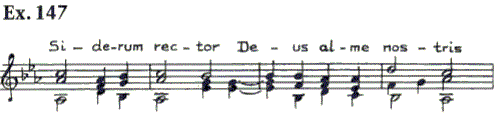 バードとフェラボスコは友好的であった。なぜなら、彼らは「Miserere」のプレインソングを使ったカノンを作るために互いに切磋琢磨していたからである。フェラボスコへのバードの依存は、スパイとしての彼の活動の疑いの結果として、イタリアに帰ったときにおそらく終わった。 バードはまたスペインのフィリップ2世の礼拝堂がイギリスに来たときに会ったデ・モンテとの「友情的競争」(Peachamの言葉)をした。 1583年に彼は、詩編「Super flumina」の一部を8声部構成としたものを送った。バードは「Quomodo cantabimus」を作って、それに応えた。 しかし、 Kerman が示したように(1981年)、その対応は、国教忌避のの隠れた主張であった。Edmund Campion は、彼の活動の結果、その信念への殉教や反逆のために処刑された。 バードの妻は1577年に国教忌避を出動されたとされ、1587年にバード自身もそうした。 Elizabeth女王がローマカトリック教の支持者に向かって示した寛容は、ピウス五世が信仰や女王に選択肢を与えた後に消え始めていた。 海外から来るイエズス会の伝道者が、国の政治的安定を損なうことを試みようとはしなかったこと、またその実際の征服をしようとするものではなかったことが明らかになった。したがって、国教忌避者にとっては、試練の時となった。彼らは、裏切り者として汚名を着せられ、逃れることができなくなった。そして、人々の記憶では、血まみれのメアリーの恐怖はまだまだ新鮮だったのだ(訳注;今度は国教会がカトリックを、と逆の状況だが)。 この時期のバードのラテン作品の多くは、‘Super flumina'含んで―”Quomodo'がそれに相当するが、double entendre(話し言葉の句が2通りに理解できる駄洒落に似た修辞技法)を持っていた。これはverseであり、Kermanが言うように、国教忌避者たちが自身を”バビロンの捕囚”と揶揄していた中で、「それとなく再整理を」 していた。 ますます、バードの音楽は政治宣言の道具となっていった。彼のキャラクターのこの面は、彼の2つのコレクションであるCantione s sacrae (1589年と1591年)で大きく見られるであろう。 国教忌避者たち、この写本、そしてバードとの関係は、Brett(1964)とHofman(1973)によって研究されてきた。 Byrdのラテン語音楽の徹底的な調査は、Kerman(1981)によってしばしば有益な方法で行われてきた。しかし、Kermanの「モテット」としての典礼的なアイテムの指定は、残念だが、バードの音楽の多くに関わる声の力を認識していない。 たとえば、1589年の ‘Defecit in dolore' は、彼の1589年のCantionesの最初の男声のための壮大で長い作品であるが、「O quam gloriosum」と同じ声部の組み合わせのように扱われている。これは特に誤解を招くものである。なぜなら、‘Defecit in dolore'の中で使用されている暗い調性と声部は、その声域が全く異なる「O quam gloriosum」とは非常に対照的だからである。(Fellowesの版による)。 Byrd: Defecit in dolore W Byrd, O quam gloriosum 声域がかなり違っていて、バードの作品の完全版でフェローズによって認められたように。しかし、フェローズは、「 infelix ego」(1591)は、高音、平均、2アルト、テナー、ベースの旧式の合唱用であることを理解していませんでした。この作品は、完全な力と弱い力との間で得点を変える古いアンチフォン様式を再現したものです。テクスチャi Byrd: Infelix ego しかし、Fellowesは、 ‘Infelix ego' 」(1591)は、 trebles , means , two altos , tenor and bassの古い湯式の聖歌隊用であることを理解していなかった。この作品は、フルと少ない声部との間の変化における古いアンティフォン様式を再現したものである。ある意味、テクスチャーは古風であるが、作品の感触は確かに現代的である。 このテキストはLassusから借用されている。3つの別々のセクションで長い品である。バードの出版された作品のこうした分割は、おそらく、その冗長さに異議を唱えるような長い作品を世に送り出すための作曲家の服従を反映している。 この当時、バードは、大規模な作品を好んでいた。そこでは、音楽的関心と感情的緊張の両方を維持することが困難であった。 '‘Infelix ego' 'は、この点を踏まえた事例である。 第3のセクションは、いくつかの最初の感情的なピークの後に、単語miserereの最初の出現の直後に散逸する絶妙な対位法的緊張の雰囲気を作り上げる。しかし、さらなる最後の危機が、同じ単語で現れる。この時にはホモフォニーになり、ハーモニーの芳香の突然の変化が、驚異的なタイミングで顕著である。 Tristitia et anxietas '(1589)はもう一つの長い傑作である。 ‘Defecit in dolore' と一緒に、聴衆を長く不安に陥らせ、演奏者も聴衆も、音楽によって感情の最後の一滴をも絞り出すバードの能力を証明している。 'Ad dominum cum tribularer' (テキストのない写本として現存)は、比類のない質を示している。 Tristitia et Anxietas - William Byrd したがって、これが、初期の作品であるとするKermanの見解を支持することは困難である。バードの9声部の「Domine quis habitabit」は、同じテキストを使ったTallisの設定と同様、平凡な作品であり、Whiteの第3版のような想像力豊かな扱いに欠けている。 フェラ・ボスコの‘Ad dominum' は独創的であり、短二度(の繋留音)を多用して魅力的な効果を生み出している。しかし、バードの 8声の‘Ad dominum' のテクスチャーは、フェラボスコが求めた力よりも要求が厳しく、真に目立つ技法的な優位性によって達成された持続的なしたを示している。 Tallisの「AliumのSpem」のように、「‘filling in'」のヒントはない。それぞれの声部は、持続的に、基本的な貢献をしているように見え、緊密な議論でそれらの点を比較的容易に指摘をすることができる。 p311 (略) 16世紀の”旋法”幻想に対するKermanの態度は、「作品のモードを決定すること」に頼ることを警告している1575年の Cantiones のうちのいくつかの「常軌を逸した調性記号」に注意を払って、相当な注意を払って扱われなければならない。 脱線は、バードについてではなく、誤ったモード理論のものである。この問題は、いわゆる Klang and Tonartsystemに関連した、音部記号と音域の議論によってさらに混乱してる。われわれが見てきたように、音部記号の重要性は、ゲルマン人の抽象的な構成ではなく、英国人の色彩的な好みの反映である。バードの音部記号と音域は、彼が心に留めている調性と、与えられた調性によっている。 「F major」を語ることは時代遅れですが、「イオニア旋法」の話も同様に正しくない。鍵盤楽器音楽のように、バードは前章で説明した、 Glareanus in the book (1547) ででっち上げられたモード様式ではなく、当時の調性システムを考えていた。 しかし、これらの問題とは別に、Kermanはしばしば光彩を放っている。特に、バードのテキストの重要性は精緻に研究されている。写本と、1589年と1591年の2つの Cantiones のコレクションの中に見出された「政治的」作品の後、バードは、秘密の国教忌避者のための儀式のための典礼的な作曲に転じた。彼がペナルティなしでポリフォニーの大規模なサイクルを公表することができたことには、多くの証言がある。しかし、ミサ曲(1592-5、Clulow、1966参照)とGradualia(160 5-7)は、バードのラテン語作品の最後の出版物であったことは注目に値する。全体で200以上のラテン作品が知られている。これらのかなりの部分は、彼のGradualiaに見出される。これは、ローマの儀式による教会歴のためのミサ曲固有文の大要であり、IsaakのChoralis Constantinus以外、こうした作品はこれまでなかった。 この巨大なコレクションの構成は、Jackman(1963年)によって研究された。彼は、このセクションが、典礼用に再編成される意図であったことを、功名なやり方で示した。グロリアは借用されており、 Alleluia は他からの引用であった。 残念ながら、バードの熱狂はしばしば彼の想像力を超えていた。特に、3声作品は、まるでさえない。ミサ曲、「Turbarum voces」(StJohn Passion)とPropersはしばしば陳腐である。より大きいMasses(BrettがTavernerの 'mean' Massで前例のあることを示している)は、Agnus Deiに至るまで、Byrdの熱狂が現れない。Agnus Deiは、4,5声のMassesの両方においては、突然強烈になるのに。 同様に、ミサ固有文の間には多くの関心があるが、祝祭のほとんどには一様に素晴らしい音楽はほとんどない。 しかし、 All Saints' Day のためのミサ固有文は、顕著な例外である。 Introit 'Gaudeamus'は活発な作品であり、GradualとAlleluiaのTimete dominumは静かなコントラストを持っている。 Offerory '' ustorum animae 'は、特に情緒的な集中作品であり、バードの一番のものである。聖体拝領「Beati mundo corde」は、「Justorum animae」の強烈に従うという不可能な仕事のように見えるものを実現している。信仰の肯定的な確信は、All Saints' Massの絶頂にふさわしい。 1605年のGradualiaには、盛り沢山の作品が含まれているが、ラテン語音楽におけるByrdの傾向は、その作品残りの部分でも内省的な音楽に向いていたことは明らかである。有名な「Ne irascaris」(その2番目のセクション 'Civitas sancti tui'は英語版「‘Bow thine ear'」で広く流布した)は、典型的なバード的な作品であるが、「Haec dies'(1591)や 'Laudibus in sanctis'はそれほど典型的ではない。後者は、1591年のコレクションであるが、歓喜のムードの、バードの最も持続的なエッセイである。テキストは、詩篇150の韻文版であり、それぞれの3つのセクションは素晴らしいものである。例えば、第2セクションの最後の ‘laude dei' など。 長い3番目のセクションは、 ‘agili laudet' における敏捷性、「laeta chorea pede」のdans様の三拍子、「cymbala dulcesona」の穏やかな鈴のようなリズム等、ハレルヤに至る一連の光彩の連続である。あまりにも大きく歌われた場合、「 ‘tempus in omne deo' 」に続くべきクライマックスを先制し、作品に、deo という言葉が外に吹奏されるクラリオンのような繁栄をもたらす。 William Byrd - Laudibus in sanctis. Psalm 150 バードは1543年または1544年に生まれた。(1622年に彼は「80年のわが年齢」と言及しているので)しかし、彼の Gradualiaは、状態が弱っているように見える。英語の礼拝はその後、 彼の出席を要求した。 彼の崇拝者Morley(1597年、115頁)は、canons on the 'Miserere'で、FerraboscoとByrdの「激しい論争」を指摘し、この「恨みなし」の論争とその他の「陰口」とのこの対立を対照している。 Morley自身のラテン語の作品は、Ferraboscoを含む大陸モデルに多く負うており、故意に他の人の作品に彼の名前を付けたという重大な疑惑があることは注目に値する。 'Gaude Maria virgo'は、Pike(1969)によって、ピーター・フィリップスの作品であるとされている。さらにLaboravi in gemituは、最近大陸での作品として同定されている。彼のソロ・ソングの派生要素と、彼のConsort Lessons のソースを認めなかったことを念頭に置いて、モーリーが指摘している「陰口」は十分に受け入れられているかもしれない。すべての出来事において、Morleyのラテン作品の判断は、カノンがしっかりと確立されるまで延期するのが賢明である。 「.‘Domine dominus noster' and ‘Domine , non est exaltatum' は、ソースが示唆しているように、バードが19歳の時に、おそらく書かれていた。それらは区別がつかず、、"De profundis"や1597年の論文で印刷された作品とははっきりと対照的であり、その業績は異なるオーダーである。 バードとアルフォンソ・フェラボスコ2世とは別に、ほとんどの作曲家はアルマダ後にはラテン語テキスト設定をしていないが、Philips や Deering は例外である。彼らは多くのラテン語作品を作曲した。それらのいくつかは、英国で国教忌避者たちのサークル内で歌われた。 英国人の作曲家、ことに Lupo , Kirbye , Weelkes、Nathaniel Giles はかなりの作品を残した。Nathaniel Giles の 'Tibi soli' (surviving in a wordless source)や ‘Vestigia mea' は、非常によい作品である。 Oxford musicianであるRichard Nicolsonは ,’Cantate domino ’にもとづく壮大で珍しい設定を作曲した。 国教忌避者である Martin Peersonと他のチャールズ王朝時代の作曲家もレパートリーに貢献した。 しかし、不思議なことに、ラテン語の音楽への関心は、そのテキストがもはや典礼とは離れてしか関連づけられなくなったコモンウェルス時代(英国でピューリタン革命期のチャールズ1世処刑から王政復古まで1649年―1660年の間の共和政体)に大きくなった。 それまでのSheppard、Tallis、White、Parsons、Mundyの業績は、メアリー王朝時代の苦しみのように、歴史的に後退していた。 バードの巨大なラテン語作品でさえ、彼の死後に大部分が忘れ去られた。 新たな聖公会の儀式のための音楽でのみ、これらの作曲家の名前は、大聖堂のレパートリーの中で一貫して記憶される他はなくなった。 |