| MEDIEVAL MUSIC
第19章−1 |
Known and unknown Models for Mozart's Requiem Wolff pointed out that Mozart, in writing the Requiem in a new and innovative style of church music, obviously also consulted historical masses for the dead and sometimes even quoted from them quite audibly― thus making a contemplative review of the genre while creating a funeral music on a par with the finest music of his own era. According to Wolff, the INTROITUS is “largely based on the initial chorus of Handel's Funeral Anthem for Queen Caroline HWV 264, written in 1737”. The final chorus from Handel's Dettingen Te Deum served as a model for the KYRIE. As established by Hartmut Krones, Leopold Nowak and other commentators, Mozart's Requiem further bears numerous reminiscences and quotes from masses for the dead by Gassmann, Gossec, and Michael Haydn, as well as from Bach's Mass in B minor, Christmas Oratorio and Magnificat, C.P.E. Bach's Auferstehung und Himmelfahrt Jesu and the Missa S. Caroli by Georg Reutter the younger. Wolffは,モーツァルトはレクイエムを書くにあたり、教会音楽の新しい革新的な様式であり、明らかに、歴史的な死者のためのミサ曲や手に入るさまざまな曲を参考とした、と指摘している。それらは彼自身の時代の最高の音楽と同程度の葬儀音楽を作りながら、ジャンルの熟考のレビューをしている。 Wolffによると、INTROITUSは「大部分が、1737年に書かれたヘンデルの「キャロライン王妃のための葬送アンセム」HWV 264の葬儀の賛歌の最初の合唱に主に基づいている」。 HandelのDettingen Te Deumの最終コーラスは、KYRIEのモデルとなった。 Hartmut Krones, Leopold Nowak、その他によって確立されたように、モーツァルトのレクイエムはさらに、Gassmann、Gossec、Michael Haydnの死者のためのミサ曲からの引用がある。また、大バッハのロ短調ミサ、クリスマスオラトリオ、マニフィカト、C.P.E. BachのAuferstehung und Himmelfahrt Jesu、そしてGeorg Reutter the youngerのMissa S. Caroliも引用している。 However, one of the most important models for Mozart has remained undiscovered and unmentioned to this day―the Stabat Mater in F minor, c. 1734, of Giovanni Battista Pergolesi (1710.1736), a work which was sensationally successful at the time, as witnessed by various print editions as well as a great number of copies in numerous libraries and music collections all over the world. Furthermore, various parodies and transcriptions of it exist, among them those of Giovanni Paisiello, Johann Sebastian Bach (Psalm 51 “Tilge, Hochster, meine Sunden”), Johann Adam Hiller (1776), Joseph Eybler (c. 1800) and Alexej Fyodorovich L'vov (c. 1830). A curious arrangement by an editorial team has even survived ― a four-part vocal setting by Salieri, with wind parts added by Susmayr, trombones by von Seyfried (1831), the whole revised and edited by Otto Nicolai (1843). The old Pergolesi Complete Edition (Florence, 1942) even published an anonymous arrangement of this work as a Dies irae, from a manuscript found in Bologna that includes arrangement for chorus, the addition of two corni da caccia and a Largo in C major as an introduction. (The editors assumed here that this represented an initial version of the Stabat Mater from c. 1730/31; however, most present-day researchers have rejected this theory, even if it has not been possible to establish any definitive authorship.) This renders Pergolesi's Stabat Mater all the more interesting as a model or precedent for the Requiem. しかし、モーツァルトの最も重要なモデルの1つは未知のままであり、今日まで言及されていない。 それは、ペルゴレージの1734年作のヘ短調のStabat Mater である。この作品は、当時非常な成功を収め、さまざまな版で出版され、多くの図書館に写譜され、世界的な音楽コレクションとなった。さらに、これによるさまざまなパロディが存在する。たとえば、Giovanni Paisiello, Johann Sebastian Bach (Psalm 51 “Tilge, Hochster, meine Sunden”), Johann Adam Hiller (1776), Joseph Eybler (c. 1800) and Alexej Fyodorovich L'vov (c. 1830)などである。校訂チームによる好奇心をそそる編曲も現存している。 Salieriによる4声部作品、Susmayrによって追加された木管楽器の部分、von Seyfried(1831)によるトロンボーン、全体がOtto Nicolai(1843)によって改訂され、編集されている。古いペルゴレージ・コンプリート・エディション(フィレンツェ、1942年)は、Dies iraeとしての匿名による編曲を出版している。それは、ボローニャで発見された合唱のための編曲からのもので、2本のcorni da cacciaを持ち、ハ長調のラルゴが導入曲となっている PergolesiのStabat Materは、レクイエムのモデルや先例として、さらに興味深いものである。 Mozart most likely knew the original version, which appeared in print for the first time as early as 1742, and would at the latest have been familiar with it from the arrangement by Hiller (1776), which was quite widely known. The beginning of the Stabat Mater already reminds the listener of the beginning of the Requiem (and also, as a major-mode variant of it, the beginning of the Recordare). Particularly remarkable, however, is the similarity of the final sections of the Dies irae arrangement from the old Pergolesi edition, the Lacrymosa and Amen, to the corresponding sections in Mozart's SEQUENTIA: the initial motif of the Lacrymosa is quite similar, and in particular, the fugato beginning of the Amen by Pergolesi, even more so in its arrangement for four vocal parts, almost identical with the Amen sketch for the Requiem discovered by Plath―apart from Mozart's change to 3/4 metre. モーツァルトは、1742年の初めに初めて登場したオリジナル版を知っていた可能性があり、遅くともHiller(1776)の編曲からそれをよく知っていたであろう。 Stabat Materの始まりは、レクイエムの冒頭を聴衆に思い出させる(また、長調に変形されて、Recordareの始まりにおいても)。しかし、特に顕著なのは、古いペルゴレージの版からの、Dies irae編曲の最終章における同一性である。そこではLacrymosa と Amenが、モーツァルトのSEQUENTIAに対応している。Lacrymosaの最初の動機がまったく同様であり、特に、ペルゴレージによるAmenのフガートの始まりは、Plathによって発見されたレクイエムのAmenスケッチとほぼ同一である。モーツァルトはこれを3/4拍子に変更しているが。 Susmayr's Arrangement As suggested by Wolff, anyone keen to see where in Susmayr's additions possible traces of Mozart might be found would do best to start with the bass line and the vocal parts, which Mozart used as his starting point for the compositional structure. The strongest argument in Mozart's favour here is the use of motifs from earlier parts in order to forge an inner unity―a technique that Susmayr himself had not mastered, as is apparent from his surviving compositions. Wolffの提案するように、Susmayr補筆でモーツァルトの痕跡を見つける可能性がある場所を知りたい人は、モーツァルトが作曲構造の出発点として使用したバスラインとボーカルパートから始めるのが一番良いであろう。ここでのモーツァルトの嗜好における最も強い論議は、全体の統一を築くための、初期のパートからのモチーフの使用である。そのテクニックは、Susmayrの残した作品から明らかなように、彼がマスターできずに終わったものである。 For example, scholars who set about analysing the work established early on that the choral bass at the beginning of the Agnus Dei quite audibly quotes the main Requiem theme that is developed by Mozart in numerous contrapuntal forms in many sections of the piece, ensuring its inner coherence. Further connections can be found in the Sanctus. The soprano part at the beginning is none other than a major-key variant of the beginning of the Dies irae in augmentation, while the subject of the Osanna fugue ― which the young Franz Schubert found so delightful that he quoted it in the Osanna of his own G major Mass― is a variant of the Quam olim fugal subject. The opening of the Benedictus has been identified as a theme that Mozart jotted down in the exercise book of his pupil Barbara Ployer. The final phrase of the theme is also reminiscent of the Incarnatus of the unfinished Missa Solemnis in C minor, K. 427, which was certainly unknown to Susmayr. Moreover, towards the end a solemn figure appears with which the composer might well have intended to form a bridge back to the Osanna fugue―a figure that appears earlier in similar form in the INTROITUS at the words “et lux perpetua”. Apart from these audible hints there are further small details which one can take as examples of planned connections . for instance, the continuous semiquaver figure at the beginning of the Benedictus as well as the Agnus Dei, which connect them with the Lux aeterna and the accompanying figure of the final fugue. Such elements support the impression that at the least the substance of the entire vocal setting of the Requiem was composed by Mozart himself. If that is the case, the corresponding sketches which Susmayr had at his disposal, must now be regarded as inaccessible or wholly lost. 例えば、Agnus Dei の最初の合唱バスパート上に確立された作品の分析をする学者は、レクイエムのテーマを引用する。それは、モーツァルトによって発展させられた、作品の多くの場所で出現する対位法の形式である。サンクトゥスではさらにつながりがある。初めのソプラノの部分は、Dies iraeの最初の長調としての変奏以外の何ものでもない。 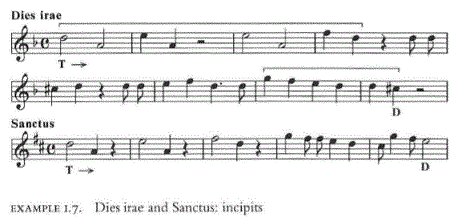 Osanna のフーガの主題は、Quam olimフーガの主題の変奏である。Benedictusの冒頭は、モーツァルトが彼の弟子のBarbara Ployerへの練習帳にメモしたテーマと同一である。 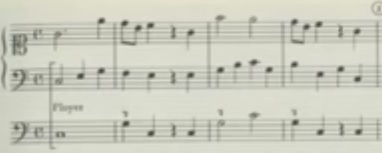 このテーマの最後の句は、未完のハ短調の荘厳ミサ曲K427のIncarnatusを思い起こさせる。確かに、Susmayrはこれを知らなかった。さらに、最終的には、作曲家がOsannaのフーガに戻ってブリッジを形成しようとしたかもしれない厳粛な形が現れる。それは、 INTROITUSの "et lux perpetua"という言葉に類似した形で先に現われた形である。こうした、耳で区別し得るなヒントとは別に、予定された接続の例として取り上げることができるさらに小さな詳細がある。例えば、Agnus Deiと同様、Benedictusの始まりにある連続的な16分音符の形は、Lux aeternaや最終フーガに付随する細かい音形と結びつく。このような要素は、レクイエムの全体のボーカル・セッティング内容が、モーツァルト自身によって予め作曲されていたという印象を支持している。そうであれば、Susmayrが持っていたこうしたことに対応するようなスケッチは、アクセス不可能または完全に失われたとみなされなければならない。 Earlier Editions and their Intentions Susmayr's voice leading, his pallid instrumentation and the lack of inspiration in the sections composed by him have often drawn criticism. However, the new editions available today ― and several more surely exist unpublished in desk drawers ―present differing strategies in approaching the problems of the work. The newer editions by Franz Beyer (1971) and H. C. Robbins Landon(1990) maintain the compositional fabric of the Susmayr completion with the intention merely of correcting or improving its instrumentation and voice leading. The new editions by Richard Maunder (1988), Duncan Druce (1993) and Robert Levin (1994) are more critical as regards Susmayr's compositional substance: Druce reproduced not only a corrected and edited Susmayr text, but also, as a supplement, his own, new arrangement of the sections that follow the unfinished Lacrymosa. Hans-Josef Irmen (1978) even replaced the Amen, SANCTUS and Agnus Dei with parodies: for the SANCTUS he choose the chorus “God mighty above all” from the opera Thamos of Egypt, K. 345; the Laudate pueri from the Vesperae Solennes, K. 339, served as an Amen, and as Agnus Dei that of the Missa Brevis in B flat, K. 275. Susmayrの声部補筆、彼の活気のない器楽作法と彼が作曲したセクションのインスピレーションの欠如は、しばしば批判を巻き起こした。しかし、今日入手可能な新しい版は―そして机の引き出しの中にあっていくつかの出版されなかった作品―作品の問題へのアプローチへの異なった戦略を提示する。Franz Beyer(1971)とH. C. Robbins Landon(1990)の新しい版では、Susmayrの補筆の意図を保っている。Richard Maunder (1988)、Duncan Druce(1993)、Robert Levin(1994)の新しい版は、Susmayrの補筆に関して、より批判的である。DruceはSusmayrのテキストの修正、編集だけでなく、Lacrymosa未完成部分の続きを、彼自身で新しいアレンジをしている。Hans-Josef Irmen (1978) は、Amen、SANCTUS、Agnus Deiをパロディーで置き換えた。SANCTUSのために、「エジプト王タモス」K. 345を、 AmenとしてVesperae Solennes(K. 339)のLaudate pueriを、Agnus DeiはB flatのMissa Brevis(K. 275)を当てた。 The last edition of Robbins Landon can be regarded as a ‘mixed version’. It includes all of Eybler's instrumentation as well as own additions, as far as the Lacrymosa. Eybler had already finished most of the instrumentation up to the Lacrymosa, breaking off at a point onwards of which more substantial composition would have been required. As an example for his intelligent competence may serve here the instrumentation of trumpets and timpani in the Dies irae: Eybler complemented the rests of the chorus with short notes in the wind instruments and kept the choral texture open, so that the entire fabric sounds more transparent, and the trumpet and timpani entries more dramatic. Susmayr, on the other hand, wanted to support the chorus with sustained notes in the wind instruments, but in doing so covered up the vocal parts. As Wolff has shown, Susmayr sometimes used some of Eybler's ideas, sometimes ‘correcting’ them for the worse, but often he ignored them completely, replacing them with his own routine instrumentation. However, following the Lacrymosa Robbins Landon simply reproduced the pure Susmayr text, so that his edition is marred by an internal dichotomy. In addition to this, Robbins Landon also maintained an often-criticised element of the Susmayr arrangement: the Sanctus and the following Osanna fugue are both in D major, the Benedictus is in B flat major. Following the model of the Quam olim fugue, one would have expected a repeat of the Osanna in D major. Susmayr, however, repeats it as a variant in B flat major. Robbins Landonの最後の版は「混合版」とみなすことができる。 それには、Lacrymosaまで、Eyblerのすべての補筆が含まれている。 EyblerはLacrymosaまでの補筆のほとんどを既に完成させていた。大事なところの前で筆を折った。彼の高い能力の例として、ここではDies iraeのトランペットとティンパニが挙げられる。Eyblerは金管楽器の補助とともに合唱の残りを完成し、合唱の肌理はより透明に聞こえるようでありティンパニのエントリはより劇的である。一方、Susmayrは金管楽器の持続的な音で合唱を支えようと考え、そうすることで声楽部分をカバーした。 Wolffが示しているように、Susmayrは時にはEyblerのアイデアのいくつかを使って、時にはそれを悪化させて修正することもあったが、彼はそれらを完全に無視して、自身の手馴れたオーケストレーションに置き換えた。しかし、Lacrymosaに続いて、Robbins Landonは、純粋なSusmayrのテキストを単純に再現したので、彼の版は内部の二分法によって傷つけられている。これに加えて、Robbins Landonは、しばしば批判されたSusmayr補筆の要素を温存した。SanctusとOsannaのはともにD majorであり、BenedictusはB flat majorである。 Quam olim fugueのモデルに従えば、D majorでのOsanna の繰り返しが期待されただろう。しかし、SusmayrはB flat majorとしてそれを繰り返している。 Robbins Landon allowed this lapsus to remain. Its correction, after all, would have required a newly composed transition from the end of the Benedictus into the Osanna, perhaps by making use of Mozart's afore-mentioned modulatory motive. Robbins Landonはこの状況を残した。結局のところ、その訂正は、おそらく、モーツァルトの前述の変化した動機を利用して、ベネディクトゥスの終わりからオサナに新たに作曲されることとなった。 Richard Maunder regarded both Sanctus and Benedictus as inauthentic and proposed dispensing with them entirely. However, he added Susmayr's completions of these sections as a supplement to his score, leaving the decision to perform the Requiem as a torso or not to the conductor. On the other hand, the new instrumentation Maunder provided for the work does not at all match with that of Susmayr's Sanctus, Benedictus and Osanna. Richard Maunderは、サンクトゥスとベネディクトゥスの両方を真実ではないとみなし、完全にそれをなくすことを提案した。しかし、彼は自身のスコアへの補足として、これらのセクションのSusmayrの補筆を追加し、レクイエムを未完成として、あるいは指揮者に、これを演奏するかどうかをまかせることとした。一方、Maunderが作品のために行った新しいオーケストレーションは、SusmayrのSanctus、Benedictus、Osannaとはまったく一致していない。 Duncan Druce found an even more radical solution. He composed an entirely new Benedictus with solo quartet on what is acknowledged to have been Mozart's theme, enabling him to compose his own transition to the D major of the Osanna. Unfortunately, apart from the theme, the results completely forsake any hint of Mozart's own work. Duncan Druceはもっと根本的な解決策を見出した。彼はモーツァルトのテーマであったと認められているものについて、ソロカルテットとともに全く新しいベネディクトゥスを作曲し、OsannaのDmajorへの移行を作曲することができたた。残念ながら、テーマとは別であり、結果は完全にモーツァルト自身の作品のヒントを捨てしまっている。 The harshest criticism of Susmayr, as Wolff proposes, is that he was apparently incapable of further elaborating Mozart's sketches. An eloquent example for this is the Sanctus, continued by Susmayr in a rather awkward manner (remarkably, he used the opening of this movement again some years later for the Sanctus of his own Missa Solemnis in D, SmWV 106). The break between Mozart and Susmayr is marked by a rather ugly cross-relation (C sharp/C) in the bass. Beyer and Druce tried to cover this up rather unsuccessfully with a clear concluding flourish in the trumpets; Robbins Landon tried to mitigate the effect. Only Levin in his realisation followed an insight of Wolff's, that this was a purely harmonic problem, a possible misreading by Susmayr of an original sketch, and convincingly replaced the C in the bass in b. 6 with an A in the alto. Wolffが提案しているように、シュトマイヤーへの最も痛烈な批判は、モーツァルトのスケッチをうまく利用できないと思われたことである。その例として挙げられるのが、Susmayrがやや不器用なやり方で書いたSanctusである(興味深いことに、彼は数年後に自身のニ長調のMissa Solemnis SmWV 106のSanctusのために再びこの楽章の冒頭を使用した)。モーツァルトとSusmayrの間の断裂は、バスパートにおけるCと(その他の声部の)C♯の醜い関係によって印される。BeyerとDruceはこれをカバーように試みたが、トランペットにおけるはっきりとしたファンファーレとともに、むしろ失敗に終わった。 Robbins Landonはこの影響を軽減しようとした。レヴィンだけが彼のリアリズムの中で、Wolffの洞察に従った。これは純粋に和声的な問題であり、元のスケッチへのSusmayrによる誤解の可能性があり、バスパートのC音が、アルトのA音で置き換えられている。 Also, the Osanna fugue is most likely based on an original sketch for its exposition which Susmayr was not capable of elaborating, or not prepared to. After presenting the theme in all four parts, he merely added a short, rather clumsy ending. In opposition to Beyer and Robbins Landon, both Druce and Levin were enterprising enough to elaborate this exposition into a full fugue. In doing so, Druce was less successful, because his version is longer than Mozart's own fugues in similar instances (for instance, the Kyrie fugue), and it also goes beyond the limitations of the Requiem's harmony and style. Levin's fugue has only 58 bars and remains shorter and simpler. However, one would expect a strictly vocal fugue here, whereas Levin introduces independent instrumental entries of the theme. Also, his decision to introduce clarinets for this section only is rather odd. He argues that Mozart himself would not have used basset-horns in F for a movement in D major, preferring basset-horns in G which, however, are no longer available. On the other hand, Susmayr used basset-horns in F with three sharps in the Sanctus, something which, pace Levin, certainly lay within the parameters of performance practice at the time. また、Osannaのフーガは、Susmayrが扱いきれなかった元のスケッチを基礎にしている。4つのパートすべてにおけるテーマの提示の後、彼は短い、むしろ不器用な終わりを追加しただけである。 BeyerとRobbins Landonに対抗して、DruceとLevinは両方とも、このスケッチを完全なフーガに盛り込むために十分な企画をした。だがそうすることに、Druceはあまり成功しなかった。なぜなら、彼の版は、同じようなモーツァルト自身のフーガよりも長く(例えばKyrieフーガ)、レクイエムの調和と様式の限界を超えているためである。Levinのフーガはわずか58小節しかなく、短くてシンプルである。しかし、ここでは厳密なフーガが期待されるが、Levinはテーマからは独立した楽器のエントリーを導入している。また、このセクションにクラリネットを導入するという彼の決定は、むしろ奇妙である。彼は、モーツァルト自身が、F管のバセット・ホーンをニ長調の楽章に使えなかったために、もはや使用されないG管を愛用していたと主張している。他方、SusmayrはF管のバセットホーンを、♯が3つつくSanctusで使用していた。 The Amen fugue concluding the Lacrymosa must be seen as indispensable in making clear the structure of the Requiem and its symmetrical axis in D minor (Kyrie fugue / Amen fugue / Cum sanctis fugue). Susmayr, however, “dispensed with an elaboration of the Amen fugue in favour of a plagal cadence of two bars. But certainly not because he knew nothing of Mozart's intentions, the less so since Mozart ‘had very often spoken with him about the working-out’ (Doc. 15), but merely because he could not do justice to the demands of strict polyphonic writing . and even less so with the planned structure of the fugue in mind, for which Mozart intended inversion, diminution and perhaps even cancrizans. As one can see from Mozart's sketch, the principal subject of the Amen fugue is an exact inversion of the main theme of the first movement of the Requiem” (Wolff). On the other hand, in defence of Susmayr it is possible that Eybler perhaps did not return all the sketches he obtained from Constanze. (Perhaps the Amen sketch remained in Eybler's possession?) The collocation of the sketch is, however, incontestable by virtue of its use of the Requiem theme in inversion. Lacrymosaを締結するAmen fugueは、D minor(Kyrie fugue / Amen fugue / Cum sanctis fugue)のレクイエムとその対称軸の構造を明確にする上で欠かせないものとみなされなければならない。しかし、Susmayrは、2小節のアーメン終止を好み、精緻化して使用すべきAmen fugueを省いた。彼は、モーツァルトの意図を何も知らなかったわけではなく、むしろ、モーツァルトが非常に頻繁に彼にワークアウトについて語っていたので、厳密なポリフォニー書法への要求に応えられなかったのである。そして、モーツァルトが意図していた反転、縮小、回文といったフーガのプランも作れなかった。モーツァルトのスケッチからも分かるように、アーメン・フーガの主題は、レクイエムの最初の動詞の主なテーマを正確に逆転させたものである(Wolff)。一方、Susmayrの弁護をすると、Eyblerは、彼がコンスタンツェからもらっていたスケッチをすべて返さなかった可能性がある。 (おそらく、Amenのスケッチは、アイブラーの所有にとどまっていたのだろうか?)しかし、スケッチの配置は、レクイエムのテーマを逆さにして使用したことによって、懐疑的である。 Despite this, Beyer and Robbins Landon chose not to use it, even though they must have been familiar with the sketch, which was discovered in 1960. In his new edition of 1991 Robbins Landon went so far as to ascribe the Amen sketch to the earlier Munchener Kyrie, K. 341, despite the fact that Alan Tyson, after comparing watermarks, had explained in 1987 that the Amen sketch was notated on the same paper type II that Mozart first began using at the end of September 1791. (Is it really possible that this was unknown to Robbins Landon?) それにもかかわらず、BeyerとRobbins Landonは、1960年に発見されたスケッチに精通していたが、これを使わないことにした.1991年の新版で、Robbins Landonは、Alan Tysonが透かしを比較して、1987年に、Mozartが1791年9月の終わりに最初に使用したのと同じ用紙タイプIIでAmenのスケッチが記されていると説明したにもかかわらず、より早い時期のMunchener Kyrie、K.341のためのものであるとした。(これはRobbins Landonには知られていなかった可能性があるだろうか?) Maunder was perhaps the first to attempt an elaboration of this fugue. His version is convincing for its strength and brevity, even if it contains modulations, as Levin observed, while “18th century fugues of this kind remain in the same key, thereby providing a stable conclusion not just to the movement (Lacrymosa), but to the entire section (the Sequence)”. In addition, the ending, at a mere six bars, is perhaps a bit too short. Maunderはおそらくこのフーガの精緻化を試みた最初の人であった。彼の版は、たとえそれがモジュレーションを含んでいても、その強さと簡潔さを確信している。Levinが観察したように、「この種の18世紀のフーガは同じ調性にとどまっているので、それゆえに楽章(Lacrymosa)だけでなく、全体のセクション(セクエンツィア) にいたるまで安定した状況となる」。さらに、エンディングはわずか6小節で、少し短すぎるかもしれない。 Druce's fugue contains bold breaks and some curious syncopations; stylistically it sounds more like Brahms (Deutsches Requiem), and with 127 bars is so long that it destroys the work's proportions. Levin took a middle path: His fugue, with 88 bars, is slightly more than Maunder's, uses denser counterpoint and contains a longer closing section, but following the Lacrymosa it seems too exuberant and virtuosic. Druceのフーガは、大胆なブレイクといくつかの好奇心をそそるシンコペーションを含んでいる。 様式的にそれはブラームスのように響き(Deutsches Requiem)、127小節もあって長すぎるため、作品のプロポーションが損なわれている。Levinは中道を取った:彼のフーガは、88小節で、Maunderよりわずかに多く、より密集した対位法を使用し、より長い終止過程を含むが、Lacrymosaに続いて、それはあまりにも豪華で芸術的に見える。 Moreover, it again contains independent subject entries in the accompanying instruments, as opposed to Mozart's fugues in the Requiem fragment, which are strictly vocal fugues where, with few exceptions (trumpets, timpani, bass), the instruments have only to support the vocal parts; in fugato passages they rarely appear in obligato roles. さらに、厳密な声楽のフーガであるレクイエム断片のモーツァルトのフーガとは対照的に、付随する楽器には独立した主題のエントリーが含まれているが、いくつかの例外(トランペット、ティンパニ、バス) を除き、楽器はフガート句(オブリガートの役割しかほとんどしていない)において、声楽を支持するだけである。 As Mozart's Lacrymosa breaks off after the eighth bar, Druce and Maunder composed their own transitions to the fugue. Levin, on the other hand, retained Susmayr's version, merely correcting details, making changes only at the end. Druce included the two further bars of melody that were sketched by Eybler, but his instrumentation, the lengthy composition of an interlude and transition again exceeds the stylistic parameters of the work. In all, his Lacrymosa occupies 36 bars. Maunder continued with his own composition as well, but with 24 bars it is six bars shorter than Susmayr's and stylistically more convincing. モーツァルトのLacrymosaが第8節の後でストップしたので、、Druce and Maunderは、自分たちのフーガへの移行部位を作った。 一方、LevinはSusmayrの版を保持していただけで、細かい部分を修正して、最後に変更を加えただけだった。 Druceは、Eyblerによってスケッチされた2つのメロディーの小節を含めたが、彼の補筆は、間奏部分と移行部分の長い作曲は、やはり作品の様式的限界を超えている。この部分の彼のLacrymosaは36小節に及んでいる。。 Maunderは自身の作曲部分も続けたが、24小節では、Susmayrのものよりも6小節よりも短く、様式的により説得力がある。 Hans Josef Irmen had the in itself attractive idea of completing Mozart with Mozart, but the models he chose for this parodic technique are taken from works composed between 1773 und 1780, and the result is as unconvincing as, for instance, the pasticcio arranged by Alois Schmitt in 1901 to complete the C minor Mass. Irmen's most interesting idea is perhaps the choice of the Laudate pueri from K.339 as a final fugue for the SEQUENTIA, since it bears similarities not only with the theme of the Kyrie fugue in the Requiem but also with the final chorus from Pergolesi's Stabat Mater. However, in the instrumentation of this fugue (as well as in that of the Agnus Dei, chosen from the Mass, K. 275) there is no independent viola part, and Irmen also made no use of basset-horns or bassoons. Overall, his scoring exceeds the limitations of Mozart's own instrumentation, because for his SANCTUS parody Irmen adopted the instrumentation of the original, adding two flutes and two horns which nowhere else occur in the Requiem. He argued that the C minor Mass, in its Incarnatus, adds a flute too, but overlooked the fact that in Mozart's time flute and oboe parts were often taken by the same players. In the C minor Mass, the Incarnatus has only one oboe; the flute part was certainly taken by the other oboist. Hans Josef Irmenは、モーツァルトでモーツァルトを完成させるという魅力的なアイデアを持っていたが、このパロディー技法のために選んだモデルは、1773年と1780年の作品から選んだもので、結果はたとえば、Alois Schmitt による1901年完成の、ハ短調大ミサ曲のパスティッチョのように、確信的なものではない。Irmenの最初のもっとも興味深いアイディアは、おそらくは、セクエンツィアの最終フーガとしてK339のLaudate pueriが選ばれたことである。なぜならそれは、レクイエムにおけるKyrieフーガのテーマだけでなく、ペルゴレージのstabat Materの最終合唱もまた担っているからである。しかし、このフーガのインストルメンテーション(Agnus Deiと同様、Mass、K. 275より選ばれた)では、独立したヴィオラの部分はなく、Irmenはバセット・ホーンやバスーンも使用しなかった。結局、彼のスコアは、モーツァルト自身のインストルメンテーションの限界を超えている。なぜなら、彼のSANCTUSのパロディのために、Irmenはオリジナルなインストルメンテーションを採用して、レクイエムにはどこにもない2管のフルートと2管のホルンを追加したからである。彼は、ハ短調ミサ曲は、Incarnatusにおいて、やはりフルートを加えたが、モーツァルトの時代にフルートとオーボエは同じ奏者によって演奏されていた事実をを見逃していた。ハ短調ミサ曲において、Incarnatusは1パートのオーボエだけであったが、フルートパートは確かに、その他のオーボエ奏者によって演奏された。 。 Irmen went so far as to criticise the generally dark colours in the Requiem with its basset-horns and bassoons as a “stereotypical, grey layer of sound”, but if we consider that Mozart in his Salzburg church compositions often dispensed with woodwinds completely, and that most of his orchestral compositions call for an orchestra of only strings, bass part, two oboes and two horns, we could similarly regard this as ‘stereotypical’. We should also not overlook the fact that neither Susmayr nor Eybler added further wind instruments, which would have destroyed the unique simplicity of the Requiem. On the other hand, the instrumentation, as it has been handed down to us, still allows for many nuances. Essentially the basset-horns merely replace the otherwise typical oboes; the only problem here is the limited range of the basset-horn, which, if the first basset-horn is being led colla parte with the sopranos, requires variation when the soprano goes beyond the upper limit of the basset- horn's range. Irmenは、バセットホルンやファゴットを持つレクイエムをステレオタイプの灰色の響きとしてそのくらい色を非難したが、ザルツブルグ教会でのモーツァルトの作曲が、しばしば木管楽器を完全に使い、彼のオーケストラ作曲のほとんどが弦楽器、バスパート、2管のオーボエ、2管のホルンのみしか使わないと考えれば、我々はこれを同様にステレオタイプとみなす事になろう。また、SusmayrもEyblerも、レクイエムの独特なシンプルさを否定するようなさらなる木管楽器を追加していない、ということを見逃してはならない。一方、インストルメンテーションは、私たちに伝えられているように、まだ多くのニュアンスを許している。基本的に、バセットホーンは単にそれ以外の典型的なオーボエを置き換える。ここでの唯一の問題は、最初のバセットホーンがソプラノとコラボレーションされている場合、ソプラノがバセットホーンの範囲の上限を超えたときに変化を必要とする、バセットホーンの限られた音域である。 Irmen's score, which appeared in self-publication, must ultimately also be considered unfinished. Despite a few performances during his lifetime, there are many mistakes, missing performance indications, no figured bass whatsoever, and Irmen left many of the shortcomings of the Susmayr arrangement unaltered. This edition is not even available anymore, since the editor's ‘Prisca Verlag’was already liquidated by the time of his sudden death (2007). As Irmen's widow explained to the present writer in 2009, no further impressions of his edition are planned. 自費出版で登場したIrmenのスコアは、最終的に未完成とみなされなければならない。彼の一生の間にいくつかの公演があったにもかかわらず、多くの間違い、パフォーマンスの欠如兆候、数字付き低音はまったくなかった。そして、Irmenは、変更されていないSusmayrの補筆の欠点の多くを残した。この肯定はもはや利用できない。校訂者の 'Prisca Verlag'は、彼の突然の死の時にすでに清算されていた(2007年)。Irmenの未亡人が2009年に現在の作家に説明したように、彼の版のそれ以上の案は計画されていない。 Looking at all the readily accessible arrangements of the Requiem, one can only come to the disappointing conclusion that one can raise a number of fundamental objections against each of them. The real devil is in the details― not only those of the compositional additions, but also of the instrumentation, since Mozart himself left the majority of the score unorchestrated. So one has not only to draw Susmayr into question, but also all the other editions that have been discussed here. Beyer and Robbins Landon corrected some of Susmayr's errors but left more standing. Maunder and Druce made reference to the later operas (Zauberflote, Titus) as models for their instrumentation, but rarely recognised the entirely different demands of the ‘pathetic style’ of church music, and ignored Alan Tyson's research on paper types, concluding that the Requiem was begun only after Mozart had finished his operatic works, namely, after his return from Prague (mid-September 1791). 手にし得るレクイエムのすべての補筆を見てみると、それぞれに対して根本的な苦情の数を増やすことができるという失望した結論に至るに過ぎない。 本当の悪魔は、 モーツァルト自身がスコアの大半をオーケストレーション化せずにしておいたために、(未完成部分への)作曲の付加のみならず、インストルメンテーションにもある。 だから、Susmayrに疑問を抱くだけでなく、その他のすべての校訂も取り上げている。 BeyerとRobbins Landonは、Susmayrの和声学的間違いのいくつかを修正したが、より多くの問題を先送りした。MaunderとDruceは後のオペラ(「魔笛」、「皇帝ティトスの慈悲」)をそのインストルメンテーションのモデルとして参考としたが、教会音楽の”悲愴的様式”についての全体的に異なった要求をほとんど認識していなかった。Alan Tysonの研究を無視し、レクイエムは、モーツァルトがオペラの仕事を終えて、すなわち、プラハから帰国した後(1791年9月中旬)に始まったと結論づけている。 Druce's imaginative additions go entirely beyond the work's stylistic domain; the passages composed by him show little knowledge of historic compositional techniques or of the stile antico, which occurs at points in the Requiem and would certainly have played a major role in the Amen fugue as well, as Mozart's sketch itself demonstrates. Levin is a similar case, making an even worse mistake by referring to Mozart's earlier Salzburg style, thereby ignoring the fact that the Requiem expressly followed Viennese models, as also with regard to instrumentation. Levin even used the stylistically wholly different, unfinished C minor Mass of 1783 as a model (Sanctus; Amen fugue). Such models cannot simply be transferred to the Requiem, for which Mozart developed an entirely new style that was unique to the work. Irmen even exceeded Mozart's own instrumentation; his completion also appears to be stylistically unconvincing with regard to the compositional parameters Mozart set himself ―paradoxically, given Irmen's method of using parodies of Mozart's own works, of which only the Laudate pueri is in any way stylistically appropriate. Druceの想像力豊かな補筆は、作品の様式的領域をはるかに超えている。彼が作曲した句は、歴史的な作曲技法についてや、レクイエムが作られた当時のstile anticoについての知識がほとんどない。そしてモーツァルトのスケッチ自体が示しているように、Amenフーガにおいて主要な役割を演じたであろう。Levinも同様のケースであり、モーツァルトの初期のザルツブルクスタイルを参照することでさらに悪いミスを犯し、インストルメンテーションに関しても、レクイエムが、ウィーンのモデルを明示的にたどったという事実は無視する。レヴィンは、様式的に完全に異なる、1783年の未完成のハ短調ミサをモデルとして(Sanctus; Amen fugue)使った。このようなモデルは、レクイエムに単純に移行していくことはできない。なぜなら、モーツァルトは、作品に固有のまったく新しいスタイルを開発していたからである。Irmenはモーツァルト自身の楽器を上回ってさえいた。彼の補筆、モーツァルトの作品をパロディとして使ったIrmenの方法(Laudate pueriのみは様式的に適当だとは思うが)は、モーツァルトが設定した作曲上の限界に関して、様式的に矛盾しているように見える。 Concerns of the New Edition In view of the above, anyone preparing to perform the Requiem finds himself on the horns of a dilemma: if one cannot decide wholly and solely in favour of one of the editions, one can only attempt to assemble elements of them. Indeed, entire generations of church musicians have created their own personal ‘versions’ of the Requiem by doing so. But this calls for far too many fundamental decisions, and some of the problems would remain since they were not resolved in any of the existing editions. For this reason, the present writer has attempted to arrive at his own edition, which was undertaken under the following premises: 上記を考慮して、レクイエムを演奏する準備をしている人は誰でも、ジレンマの角に陥る。校訂のどれを使用するかを決めることができなくても、それらの要素を集めることはできる。実際、教会の音楽家の全世代は、そのようにすることによって、レクイエムの独自の「バージョン」を作成している。しかし、これには根本的な決定が非常に多くなり、既存の校訂版では解決されていないために、問題のいくつかは残る。このため、現在の著作者は、自分の版に着手しようとする。これは、次の前提の下で行わた。 1.) Since Susmayr's supplementations lie closest to Mozart's own time and we can assume quite rightly that they are based at least partially on sketches by Mozart himself (as explained above), they represent an indispensable consideration for every new edition, particularly as regards the vocal parts and bass line in the second half of the Requiem. However, they have to be scrutinised and wherever necessary modified or replaced with other material. The Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna and Agnus Dei required entirely new versions (despite maintaining passages most likely sketched by Mozart himself). Inevitably, similarities with other editions appear where the text of Susmayr or Eybler has been used, and where either the corrections were obvious or very few alternatives were possible. 1)Susmayr'の補筆は、モーツァルト自身の時代にあり、モーツァルト自身のスケッチに少なくとも部分的に基づいていることを前提とすることができる。それらは、レクイエムの後半の声楽部分やバスラインに関するすべての新しい版のためには不可欠な考慮事項である。しかしそれらは精査されなければならず、必要に応じて他の素材と交換、変更されなければならない。モーツァルトがスケッチを残していたにもかかわらず、Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna、 Agnus Dei は、完全に新しい版を必要とした。必然的に、他の校訂との類似点は、SusmayrまたはEyblerのテキストが使用されている場所に現われ、そこでは修正が明白であるかまたは代替の可能性は非常に低かった。 2.) Since Eybler was certainly a much better and more experienced composer than Susmayr, his additions in the SEQUENTIA were preferable to those of Susmayr, where necessary modified, amended or corrected, sometimes even reduced, given their stylistically doubtful “tendency towards a more elaborate, independent orchestral accompaniment”, as Wolff rightly noted. 2)EyblerはSusmayrよりもはるかに優れた経験豊かな作曲家だったので、SEQUENTIAでの彼の追加はSusmayrのものよりも好まれていた。Wolffが正しく指摘したように、必要な修正あるいは減少さえもが、様式的に疑わしい「より精緻に、独立したオーケストラの伴奏に対する傾向」を与えられた。 The instrumentation must respect the peculiarities of the composition. Thus, as Mozart's existing instrumentation suggests, independent passages for the trombones were largely avoided, with only a few, carefully considered exceptions. In the tutti passages the woodwinds support the chorus, the bassoons from time to time the bass line, to which they contribute greater rhythmic profile as well as adding to the orchestral resonance. The compositional texture of the upper strings is orientated around the bass and vocal parts. インストルメンテーションは、作品の特性を尊重しなければならない。したがって、モーツァルトの現存時のインストルメンテーションが示すように、トロンボーンの独立した句は、慎重に考慮された例外を除いて、大規模には避けられ、わずかである。 tuttiの句では、木管楽器は合唱をサポートし、ファゴットは時にはバスラインを吹き、オーケストラ的響きに加えて、より大きなリズム的な輪郭に貢献する。上部の弦楽器の作曲的肌理は、バスパートとボーカルパートに対峙する。 3.) Since the autograph itself offers only few such indications, this new edition had to a large degree to supplement articulation, tempo markings, dynamics and figured bass in line with Mozart's usual procedures and the sparse directives to be found in the manuscript. 3.)モーツァルトの自筆譜自体はほとんどそのような指示を提供していないので、この新版は、アーティキュレーション、テンポ設定、モーツァルトの通常の指示に沿った大胆かつ数字付きバス、写本中に見られる粗い指示を補充しなければならない。 The main purpose of this new edition (= NE) is to complete the piece in a style corresponding more closely with that of Eybler (including freer part-writing in the winds, and greater independence in the violins and violas, occasionally resorting to divisi). The effort to eliminate the majority of Susmayr's technical shortcomings is intended to render the work more stylistically coherent, even if this means replacing Susmayr's second-hand additions with those of the present writer, who is all too aware of the problems involved. このニュー・エディション(= NE)の主な目的は、Eyblerの校訂とより密接に対応するスタイルで作品を完成させることである。(木管楽器のより自由な書法、時に分割されるバイオリン、ヴィオラの自立性を含む)。Susmayrの技術的な欠点の大部分を取り除く努力は、たとえSusmayrの補筆を現在の校訂者のものと置き換えても、様式的に一貫性のあるものにすることを意図している。 For this reason, the question as to whether it might be possible to find convincing earlier pieces by Mozart which could be used as a basis for parodies (Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna, Agnus Dei) was examined. But in opposition to his completion of the CREDO and AGNUS DEI of the C minor Mass, the present writer came to the conclusion that this would make little sense here. First of all, the style of the Requiem, as is apparent from the passages in Mozart's own hand, is so unique in its texture and its simplicity that it would be extremely difficult to find pieces to convincingly adapt and parody in such a way as to form a credible match with its style. このため、モーツァルトの初期の作品をパロディーの基礎とすることができたかどうかを調べることができるかどうかの問題を検討した(Amen, Sanctus, Benedictus, Osanna, Agnus Dei)。しかし、ハ短調ミサのCREDOとAGNUS DEIの完成に反して、現在の校訂者はこれがほとんど意味をなさないとの結論に達した。まず、レクイエムの様式は、モーツァルト自身の手によることが明らかであるように、肌理においてユニークであり、その単純さゆえに、納得のいくような作品を見つけて、そのスタイルと信頼できる適合を形成することが極点に困難であった。 Irmen's decision to use an extract from Thamos as a SANCTUS, which goes entirely beyond the stylistic parameters of the Requiem, bears witness to this dilemma. (Irmen's arrangement would have been better suited to a completion of the unfinished Mass in D following the Munchener Kyrie, K. 341 the other movements of which Mozart did not undertake.) Generally speaking, there were few convincing models to be found. There was no appropriate piece whatsoever to use for the SANCTUS. For some time the editor was tempted to follow Irmen's lead and provide an Amen fugue based on the Laudate pueri, with the instrumentation expanded to match that of the Requiem. But the piece seems overly long, and worse, the metre is wrong; as the sketch reveals, Mozart clearly intended a fugue in 3/4 time, not in alla breve. (He even changed the metre of Pergolesi's original, of which the Laudate pueri is even more reminiscent, for that of the Amen sketch.) Irmenが「エジプト王タモス」K. 345からの抜粋をSANCTUSとして使用するようにしたことは、レクイエムの様式的限界を完全に超えており、このジレンマを目の当たりにしている。 (Irmenの編曲は、「ミュンヘンのキリエ」K341を使った未完のハ短調ミサ曲の完成には向いていたことだろう)。一般に、確かなモデルはほとんど見つかっていない。 SANCTUSには適切なもの作品はなかった。校訂者は、しばらくの間、Irmenの指導に従い、レクイエムに適合するようにインストルメンテーションが拡大された Laudate pueriを基礎としたAmenフーガを供給するような試みを受けた。しかし、この作品は長すぎたようで、さらに悪いことに、拍子が間違っていた。スケッチが明らかにしているように、モーツァルトは明らかに、2/2拍子( Laudate pueriの拍子)ではなく、3/4拍子のフーガを意図していたのだ。 (彼はさらに、Pergolesiのオリジナルの拍子を変更した。Laudate pueri は、Amenスケッチの拍子を思い出させる。) Christoph Wolff underlined the importance of this decision for the structure of the work: “For formal reasons, ending the SEQUENTIA with a fugue is an almost compelling necessity: all five sections of the work would then include a fugal movement, and in a clearly symmetrical fashion: even―odd ―even― odd―even metre. The Osanna fugue (seen apart from the shortcomings of Susmayr's elaboration) fits perfectly within the continuum of intentionally original solutions, being based on a clearly profiled theme that further develops basic elements of the Quam olim Abrahae fugue subject, and in doing so fulfills the requirements of overall structural stability. On the other hand, the Osanna fugue highlights the novel and individualistic, not least of all due to its syncopated beginning in triple metre, but moreover due to the strong contrasts of its internal organisation: its asymmetrical structure (3+3 bars), with syncopated beginning and finally sequence of regular quavers. But in Mozart's treatment of the fugue more generally, i. e. as a compositional category, it becomes evident that two main concerns are in operation: Mozart observes tradition, but does so by transforming it qualitatively into something new. One is reminded here of Nissen, who spoke of a bond linking the ‘holy dignity of old music with the rich decoration of the new’. Hence, it is no coincidence that the entire Requiem is embedded in a stylistic frame of precisely this kind: the music of Introitus and Kyrie represents the point of setting out; their repeat, with altered text, the point of arrival.” Christoph Wolffは、作品の構造決定のためのこの決定の重要性を強調した。「正式な理由から、フーガとともにSEQUENTIAを終わらせることは、必然であった。作品の5つのすべてのセクションは、フーガを含み、シンメトリカルな流れで、(そのフーガ)は偶数―奇数―偶数―奇数―偶数という拍子で動く。Osannaのフーガは、(Susmayrの精緻化の欠点とは別に見られる)は、意図的にオリジナルな解決策の連続体に完全に適合し、Quam olim Abrahae fugueの主題の基本要素をさらに発展させる明確な輪郭を持つテーマに基づいて、全体の構造安定性の要求を満たす。一方、Osannaのフーガは、三拍子でのシンコペーションの始まりによるのではなく、その内部構造の強い対照性のために、その新規さと個性を強調する。それは、シンコペートされた始まりと最後には規則的な8分音符で終わるその非対称構造(3 + 3小節)である。しかし、より一般的には、モーツァルトのフーガの扱いでは、すなわち、作曲概念として、2つの主たる関心が明らかになっている。モーツァルトは伝統を守っているが、それを質的に新しいものに変えることでそのようにしている。ここでは、「古い音楽の聖なる尊厳と新しいものの豊かな飾り」を結びつける絆を語ったNissenが思い出される。したがって、レクイエム全体がこのような形式の枠組みに組み込まれていることは偶然ではない。Introitusと Kyrieの音楽は、出発点を示す。それは、反復、変化するテキスト、到達点でもある。 For all these reasons, it seemed to be better not to disturb the structural disposition of the piece and to favour a new ‘second-hand completion’ of the Amen fugue over a parody. For the same reason, no model was chosen for a parody of the Cum sanctis, despite some good arguments ―the insufficient text distribution of Susmayr's KYRIE parody, and particularly the ending of the work, which has nothing of the mildness appropriate to the text, “quia pius est”, nor lends comfort to those in mourning, as a requiem should. The latter problem was solved by the editor's decision to add an alternative ending in D major, one bar longer, and with a more comforting plagal cadence. There was, in fact, a very good model available for a parody Cum sanctis, namely, the motet Misericordias Domini, K. 222(1775), which is in D minor, contains in b. 3 the later, well-known Requiem theme, and has a main section anticipating elements of the Kyrie fugue. (It would certainly be interesting to perform this motet and the Requiem within the same programme.) これらすべての理由から、作品の構造上の配置を妨げずにパロディー以上のAmenフーガの新しい「補筆」をすることはできないように思えた。同様の理由から、いくつかの良い議論があるにもかかわらず、Cum sanctisのパロディのために選択されたモデルはなかった。 SusmayrのKYRIEのパロディーの不十分なテキストの配置、特に、テキスト"quia pius est"に適していない作品の終わり部分、またはレクイエムとして必然の悲しむ人に対する慰めのなさ、といった議論である。後者の問題は、ニ長調での終止において1小節長くし、より慰め的な半格終止によって解決された。実際には、Cum sanctisのパロディために利用可能な非常に良いモデルがあった。それはモテットMisericordias Domini K.222(1775)である。この作品はニ短調であり、後にレクイエムのテーマとして知られたテーマを含み、キリエのフーガを予言したセクションを持っている。(このモテットとレクイエムを同じプログラムとして演奏することは興味深いことだろう)。 Editorial Method and Layout The NE is expressly intended as a practical arrangement rather than a ‘critical edition’; it therefore seemed unnecessary to differentiate its other additions by means of small type, dotted slurs or squared brackets, which would only have looked cluttered. Mozart's autograph, after all, is available in facsimile, and anyone interested can consult it wherever questions arise. For the same reason this edition contains only a comprehensive Commentary and no ‘Critical Report’ on each and every tiny detail of the sources. Practical musicians nowadays rarely take the time to study such reports, or investigate detailed philological problems. Furthermore, even now scholars do not agree as to the extent of the various hands that can be found in the manuscript. In his edition Robbins Landon, for instance, marked with an “M” sections which were assuredly not written by Mozart himself. NEは、「批判的な版」ではなく、実際のアレンジとしてはっきりと意図されている。 それゆえ、小さなタイプの点線のスラーまたは四角いブラケットを使って他の追加を区別する必要はないであろう。 結局のところ、モーツァルトの自筆譜はファクシミリで入手できる。誰でも興味のあることがあればどこでもそれを調べることができる。 同様の理由から、この版には包括的な解説のみが含まれており、原典の細部ごとの「批判的な報告」はない。 実際の音楽家は、このようなレポートを研究したり、詳細な言語学的問題を調査することはめったにない。 さらに、現在でさえ、学者は写本に見いだされる様々な手のつき具合の程度について同意しない。 ロビンズ・ランドンは、モーツァルト自身が書いたことのない「M」のセクションを収録している。 Concerning the Trombones The autograph shows that Mozart was quite careful with the use of independent trombones, which he gives colla parte within the vocal parts. Due to the small number of participants, which do not exceed the scope of 12-stave music paper, this was a practical solution (secondary partial scores would otherwise have been required, as in the case of the C minor Mass, which is laid out for much larger forces). Only two independent cues of the trombones exist in Mozart's own hand―their first appearance in the Requiem and, as dictated by the character of the piece, the tenor trombone solo at the beginning of the Tuba mirum. この自筆譜は、モーツァルトが独立したトロンボーンの使用に非常に注意を払っていることを示している。彼はもともと、アルト以下の声楽部分の補強として当てていた。12段の用紙を超えないほどに、楽器の種類が少なかったために、これは実用的な解決策であった。(ハ短調ミサ曲の場合では、2段スコアが必要であった)。モーツァルト自身の手では、トロンボーンの独立した糸口は、2つしか存在していない。レクイエムでの最初の出現は、作品の性質に促され、Tuba mirumの最初に、テノールトロンボーンソロとしてである。 Susmayr, on the other hand, was tempted to write more independently for the trombones, which he notated separately on two staves wherever possible. However, the excessive independent trombone writing of other editions based on Susmayr―particularly irritating in the Benedictus―seems alien to the style of the work. One should also not overlook the fact that the original manuscript can be regarded an ‘emergent autograph score’; its indications of trombone cues in Mozart's own hand are rare and where added by Susmayr not without contradiction. Hence it seemed best to deal with the trombones as schematically as possible and use them independently only in rare, well-reasoned instances. The trombones have also to rest in vocal solo as well as in soft passages; these are indicated throughout the NE with ‘senza Trb.’. 一方、Susmayrはトロンボーンのために独立した書法をする誘惑に駆られた。彼は、トロンボーンパートを、可能な限り2つの譜表に分けて別々に表記した。しかし、Susmayrに基づいた他の校訂での過剰な独立したトロンボーン書法は―特にベネディクトゥスでは特徴的な―作品の様式とは異なっているように見える。オリジナルな写本は、「突然現われ出た自筆譜」であり、モーツァルト自身によるトロンボーンの指示はほとんどなく、Susmayrによって付け加えられた箇所は特に矛盾はない、という事実を見逃してはならない。したがって、トロンボーンをできるだけ計画的に扱い、正当な理由がある場合に限り、トロンボーンを独立して使用することが最善の方法であった。トロンボーンはまた、ボーカル・ソロやソフト・パッセージにも休止する必要がある。これらはNEの中で「senza Trb」と表示されている。 Nowak made a comprehensive examination of the practice of trombone writing and playing in the Requiem. (NMA, Vol. I/1/2/2, pp. XVIIIff; see also Vol. I/1/2/1, pp. XIIIff) In particular he noted the following: “It could sometimes occur that smaller rhythmic values given in the vocal parts were represented in the trombone parts by notes of longer value. However, this differed according to the customs of music making and place of performance.” Only rarely did Susmayr indicate such simplifications. (Nowak, p. XIX) However, the NE gives no such simplifications of rhythm, leaving them to the discretion of players; this corresponds to the practice of Mozart's time, as can be seen from surviving trombone parts (where the trombone players did not simply play from the vocal parts), although one may perhaps agree with Irmen, who noted that in rapid passages the trombones most likely played only the main notes: “The delightful virtuosity of present-day instrumentalists should not cause us to overlook the fact that Mozart himself nowhere expressly demanded such artistry as can often be heard today in Requiem performances.” On the other hand, in Mozart's time coloratura passages may already have been seen as a challenge for good trombone players, and he would surely not have objected if they were capable of playing every note as written… Nowakはレクイエムでのトロンボーンの書法と演奏を包括的に検討した。 (NMA、Vol。I / 1/2/2、pp。XVIIIff; Vol.I / 1/2/1、pp。XIIIffも参照) 特に、彼は次のように指摘した。「ボーカルパートの細かい音符は、トロンボーンパートにおいてはより長い音で表現されていた。しかし、これは音楽制作の慣習と演奏する地域によって異なる。」 Susmayrはこのような単純化を示すことはまれである。 (Nowak、p。XIX) しかし、NEではリズムを単純化していないので、演奏者の裁量に任せている。これはモーツァルトの時代の演奏に対応している。現在のトロンボーンのパート(トロンボーン奏者は単にボーカル・パートを演奏したわけではなかった)から見ると、すばやいパッセージにおいてトロンボーンは大体において、主旋律のみを演奏するだろうと指摘した Irmenに同意するであろうが。「今日の楽器演奏家の喜ばしい演奏は、モーツァルト自身が、レクイエム演奏で今日聞くことができるような芸術性を明示的に要求していない、という事実を見落とさないようにすべきである。」 一方、モーツァルトの時代コロラトゥーラのパッセージは、腕の良いトロンボーン奏者のためのチャレンジとみなされているかもしれない。そして彼は確かに反対しなかっただろう。もし彼らが書かれているようなすべての音符を演奏できるのであれば・・・ In order to underscore the uniqueness of the Requiem, the NE, just like the manuscript, notates the trombones colla parte with the vocal parts, giving tenor and alto in corresponding clefs. Reading them should not prove difficult for the conductor. The modern treble clef was maintained for the soprano, however, and of course the vocal score places all parts in modern clefs. レクイエムのユニークさを強調するために、NEでは写本のように、テノールとアルトに相当する音部記号で持って、トロンボーンをヴォーカルパートとcolla parteであるように記譜する。 これらを読むことは、指揮者にとっては難しいとは限らない。 しかし、現代のトレブル音部記号は、ソプラノのためのもので、無論、ヴォーカルスコアは現代音部記号で書かれている。 |