| MEDIEVAL MUSIC
��X�� |
| ��173(143) �b�g�`�o�s�d�q �\ �s�����@�r�����������@�����@�m����e Dome THE SIX RHYTHMIC MODES �����̗��_�Ƃ����́A�U�̃��Y�����[�h���邢�͌ÓT���̒�ʓI�����̒����ɑ�������p�^�[�������X�g�����Ă���B�������������̖��O��\����Table�W�ɂ����Ă��邪�A���̃��Y�����[�h�́A�ʏ�A�ԍ��݂̂œ��肳��Ă���B�����������W�́ASt..Augustine(354-430)�̘_���ADe musica���̒�ʓI�����̋L�q�ɂ���Čە����ꂽ�B���̋L�q�ɂ�����St..Augustine�́A�����ӂ��̉����̌v�ʒP�ʂ��g�����B���Ȃ킿�Along�ilonga�j��breve�ibrevis�j�ł���B�����āA�ނ́Along�͂Q��breves�ɓ������Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����B ���������P�ʂ��g���ɂ�����A�t�_�Ȃ�������������A�����́A��P�C�Q�A�U���Y�����[�h�ւƌ��������ꂽ�B���������̑��̂R�̃��[�h��St..Augustine�̌v�ʒP�ʂɂ͂Ȃ������A��蒷�������i�t�_�������j�������B���̂�蒷�������̓����̗��R�Ƃ��Ă킩�邱�Ƃɂ��āA���̃��Y�����[�h�̎��n��I���B�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@��P���[�h�́A�����������[�h�̂����ŁA��ʂɎg����悤�ɂȂ����ŏ��̂��̂ł��낤�B����́AMagnus liber�̂����Ƃ��Â����ڂɂ����Ĉ��|�I�ɗD���ł���B�����āA���̑��̃��[�h���������ꂽ���Ƃɂ����Ă��A���̗D����ۂ��Ă����B��P���[�h�̍l���������Ċm�����ꂽ�Ƃ��A���̉����̋t�ł���jambic�����ł����Q���[�h���A���R�I�ɔ��W���Ă����B��U���[�h�͂����炩�ɁA���ꂪ���g�̌����Ƃ��ă��[�h�Ƃ��ĕ��ނ����O����A��P�C�Q���[�h�̑������ꂽ�łƂ��Ďn�܂��Ă����B�����R�̃��[�h��longs��breves�̉����̋L�q�́Arecta�Ƃ����q����g�����B���̑��̂R�̃��[�h�̂�蒷��longs��ultra mensuram�ƋL�q�����B ����������蒷�������̋N���́A�����炭�A���Â�discant clausulae���Ɍ�����B�����ł́A�e�m�[���͓����������̘A���ł���A��P���Y�����[�h�̂��ꂼ��̂ЂƂ̑g�ɑ��ĂЂƂ̉������������B�����I�ȗ�́AAlleluia ;Nativitas�ɂ�����"glorio(se)"��"virginis"�̌��t�ɂ����ĂɌ�����i�`�l�l�A�m���D�R�R�j�B��̔��W�ɂ����ẮA���̂悤�ȕ��ނł��Ȃ������̘A���́A��T���Y�����[�h�̌J��Ԃ��p�^�[���ւƐi�����Ă���B�قȂ��������ɂ�����قȂ������[�h�̑g�ݍ��킹�ɂ��Ă̓��l�̃v���Z�X�́A�^���Ȃ��A��R�C�S���[�h�ɂ����鉹���̕s�����ɂ�������ω����Y�B ���_�Ƃɂ��A�����������[�h��long-short-long���邢�́Ashort-short-long���琬���Ă���B�������A�����̉����͂ӂ��̈قȂ��������ɕψق��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Blongs��ultra mensuram�ƂȂ��A���ꂼ��̃��[�h�ɂ�����2�Ԗڂ�breve�͉����ɂ�����2�{�ƂȂ�A�����atered breve(brevis altera)�ƂȂ����B �����������ʂƂ��āA��R�C�S���[�h�̈�g�\�����Ă܂���T���[�h���\�͑�P�C�Q�C�U���[�h�̈�g��2�{�ƂȂ����B�䂦�ɂR�̒P�ʂ́A���ׂẴ��[�h���Y���̊�{�ƂȂ����B�����āA�����̃��Y���̍��������p�^�[���͕ʂ̃��[�h�����I�g�p��}�������B�Ō�̂T�̃��[�h�͂ǂ̂悤�ȑg�ݍ��킹���\�ł͂��������A��P���[�h�͒ʏ�A��T�C�U���[�h�݂̂ƂƂ��ɂ�����悤�ɂȂ����B �@���Y�����[�h�̒P�ʂ��邢�͑g�́A���_�A��蒷�����y�I�]�ڂ̌��݂̂��߂̃r���f�B���O�̃u���b�N�ł���B��g�̘A���Ƃ��āA���̂P�s������A���Y�����[�h�̔����p�^�[�������y�̃t���[�Y�����o�����B���������t���[�Y�ɑ��钆���ɂ����閼�O��ordines�i�̂��Ƃ����Ӗ��Dordo)�ł������B���̌��t�́A���m�ȁA�R���g���[�����ꂽ�����̘A���������Ă���B �������́A�x�������[�h�p�^�[���̏I�~�̂ЂƂA���邢�͂���ȏ��statement�Ƃ��āAordo���`���悤�B���_�Ƃ����́A����炪�܂�ł������S�ȃp�^�[���̐���A�I�����̋x���̈ʒu�Ȃǂɂ���āAordines���k���ɕ��ނ��Ă����B���Ƃ��A�������̃��[�h�ɂ������Qordo�́A���̃��Y���p�^�[���̂Q�̊��S��statement���܂�ł���B���������ꂪ�R�Ԃ߂́A �x�����p�^�[�� THE NOT�`TION OF RHYTHMIC MODES ordines�̓��[�h�p�^�[���̘A�����锽����萬���Ă���̂ŁA���ꂼ��̃��[�h�́A�A������l�E�}�̓���Ȕz��ɂ���ē��肪�\�ł���B���̃V�X�e���́A����̋L���@�̒m�����͂邩�ɁA���R���_���I�ł������Borganum�̍�ȉƂ����́A�ނ炪�m���Ă����B��̋L���@�݂̂Ńv���C���`�����g��organum�L�����n�߂�K�v���������B�����X�}�I�ȃp�b�Z�[�W�ɂ����āA�v���C���`�����g�̋L���@�́A�X�y�[�X��ߖ��肷�邽�߂ɁA�l�E�}���邢�͘A�����ƂƂ��ɉ������h���������Ă���h�B����ɁA�v���C���`�����g�ɂ�����P��̉����́A�v�ʓI�d�v���͎����Ȃ��B���������g�p�ɂ���ʂł́Avirga ���������A�����́A���ꎩ�g�͂Ȃ��v�ʓI�Ӗ������������Ă���킯�ł͂Ȃ��������A���Y�����[�h�̋L���ɂ��Ă̖��̓Ƒn�I�A���P���ȉ����@�������Ă����B�Ȃ��Ȃ�A�����X�}�̉����́A�A�����̈قȂ����p�^�[���ɂ���ăO���[�v������邩��ł���B���������p�^�[���́A�قȂ������Y�����[�h����肷�邽�߂Ɏg��ꂽ���Ƃ��낤�B���Ƃ��A��ȉƂ���P���[�h�ł̉��t��]�߂A�ނ́A�Q���A�����̘A�������R���A�������������B���l�ɁA3���A�����ŏI������2���A�����̘A���́A��Q���[�h�ł̉��t�������Ă���B���܂��܂Ȓ����̐�������ordines�̍Ō�������Aappropriate�x���ƌĂꂽ�B���Y�����[�h����肷��A�����̓����I�ȃp�^�[����Table9�Ɏ�����Ă���B 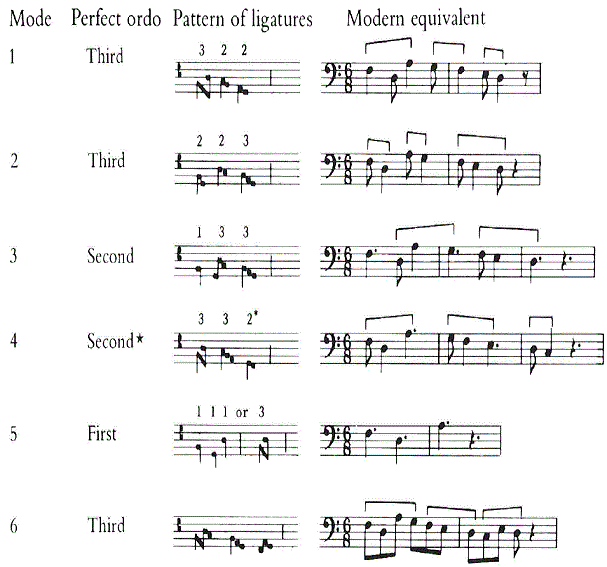 �@table9�̗�́A�A�����̌`���A���ꂪ���������Ƃ͖��W�ł��邱�Ƃ������Ă���B2���A���́A�ʏ�Abreve-long�ʼn̂�ꂽ�B�������A3���A�����́A���Ȃ��Ƃ��A�T�̉��߂��ł���B13���I�̗��_�Ƃ����́A�قȂ��������������A�����̌`��ω������悤�Ƃ������A����́A���ۂɌv�ʋL���@�̐i���Ȃ̂ł���B���[�h�L���@�̎ʖ{�����́A�v���C���`�����g�̒ʏ�̘A�����`�ɐ�ΓI�ɗ����Ă���A�����̉��߂́A����ꂽ���[�h�p�^�[���Ɉˑ����Ă���B�A�����̌`�������̈ʒu���x�[�X�Ƃ������̉����̌���́A���[�h�L���@�ƌv�ʋL���@�̊Ԃ̏����I�Ⴂ�̂ЂƂł���B �@���[�_���L���@�̊�{�p�^�[���́A���ɖ��Ăł͂��邪�A���̃V�X�e���́A�A�����̂��܂��܂ȉ��߂��������Əd��ȕs���v�ɋꂵ��ł����B���[�h�̃��Y���Ɍ����ɌŎ�����ƁA�����f�B���Ŕ������鉹���͒ʏ�̋L���@������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ炻��́A�A�����ł͏����\���Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����B�A�����̃p�^�[���ɂ�����ꎞ�I�Ȓ�~���N�����Ƃ��A���̗��R�͒ʏ햾���ł���B�������A�\���Ȑ��̔����̉������g�p����ƁA�ǂ̃��[�h���g�p���ׂ�����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B ��荢��Ȗ��́A���[�h���g�̃��Y���p�^�[���ɕω����o������Ƃ��ɋN���Ă���B�K�^�ɂ��A�m�[�g���_���|���t�H�j�[�̌|�p�I���l�≹�y�I���Q�ɂƂ��āA���̍�ȉƂ����͊�{�I�ȃ��[�h�p�^�[���̕s�ςȔ����ɂ͂��͂▞�����Ă��Ȃ������B�ނ�́A��Ȃ̂��镔�傩�瑼�̕���ւ̃��[�h�̌����ɂ��ω��𐬂��������B�������ނ�́A�ЂƂ̃��Y�����[�h�̘A�������p�^�[�����C�����Ƃɂ��P������������B13���I�̂��������v���Z�X�́Afractio modi�Ƃ��Ēm���Ă���A���[�h�p�^�[���̉��������Z�������ɂ킯�邱�Ƃ��Ӗ����Ă����Blongs��breves�ցAbreves��semibreves�ւƕ�����ꂽ�B �t�̉���́Aextensio modi�ƌĂ�A���[�h�p�^�[���̑g�A���킳�ꂽ�����͂�蒷�������Ɉ����L���ꂽ�B���Ƃ��A��P���[�h��long��vreves�́A�P���ɁA�ЂƂ�long���A�R��breves�ɂȂ����B���������C�����L������d���́A�ʏ�̘A�����p�^�[����N�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B���̑��͂قƂ�ǁA���������p�^�[���𗝉��ł��Ȃ����̂Ƃ����Bfractio modi��extensio modi�́Aorganum�ɂ��̓����I�ȃ����f�B�l����^����d�v�Ȗ��������������߂ɁA��X�́A��ȉƂ��������Y�����[�h�̃p�^�[����ω������邽�߂Ɏg�����������̍H�v�ɐڋ߂��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B THE PLICA plica�́A�v���C���`�����g�̓����̂Ȃ߂炩�ɂȂ����l�E�}����i�����������ł���B�����Ă���́A14���I�Ɏ���܂Ŏg���Ă����B���ꎩ�g�̕����́A�ЂƂ̉������邢�͘A�����̍Ō�̉����ɉ�����ꂽ��s�A���s�̐�(stem)�ł���B����́A���g�̎���̉����̏㉺�ɑ����I�����������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B������ꂽ�����̉��������Y���������A���e�ɂ��������Č��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ɋւ������A������ꂽ�����iplica)�͒ʏ�A�㉺�ւ̗אڂƂ��ċ@�\���A���邢�́A�O�x�̉��������o�߉��Ƃ��ċ@�\�����B �Q�̏����ꂽ�������O�x�ȏ㗣��Ă���ƁA������ꂽ�����iplica)�̉����́A�s�m���Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B���Y�������̌���͂����Ԃ��肪����B������������iplica)�͏�ɁA���̉������Aplica���ڂ��Ă��鉹���̉������猈�߂��Ă���B������triple�̉����ł���A������������ɑ��āA�P�^�R�ƂȂ�A������duple�ł���A���̉����̔����ƂȂ�B ��������plica�́A�m�[�g���_���|���t�H�j�[��fractio modi�̎Y���ɂ��Ă̕X�I��i�����������Bplica�̂����̎g�p�́A���Y�����[�h�̖{���I�Ȑ��������ƂȂ��ɁA���}���ׂ��ω����B�������A��т����p���I�Ȏg�p�́A���郂�[�h��ʂ̃��[�h�ւƕϊ�������B���Ƃ��A��U���[�h�́A���炩�ɁA��P���[�h����̔��W�ł������B��X�|�P�ł킩��悤�ɁA�A������̑�P���[�h��plicas�́Aordo�̍ŏ��̈�g�������āA��U���[�h���Y�����Ă���Bplica�́A�A�����̍ŏ����邢�͒��Ԃ̉����ƐڐG�ł��Ȃ��̂ŁA4���A�����́A�ŏ���long�̍ו������K�v�ƂȂ����B��́A��U���[�h��ordines�𑱂��邽�߂̂R���A�����̎g�p�́A���炩�ɁAplicas�����o�������͂�����Ƃ������������������Ƃ����~���̌��ʂł������B  �@�����̘_���́Aplica�ɂ���Ď����ꂽ���������́A����Ȑ��y�I��舵���������Ƃ������Ă��邪�A����������舵���̋L�q�́A���ɂ͂����肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B���t�̂��Ƃ��Ƃ̂�������ސ����邵���Ȃ����A��X�́A������ꂽ�������I�v�V�����ł͂Ȃ��A�͂�����Ƃ������Y���I�����ł��邱�Ƃ�m���Ă���B����䂦�ɁA����̍Z���ł́A�����ꂽ��A������Ȃ������肷�鉹���ƂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B��҂̏ꍇ�A�����ŗp����ꂽ�悤�ȁA�����ɉ�����ꂽstem�ɒu���ꂽ�ߑ����Ƃ�������ȕ����ƂȂ�B���t�ɂ����ẮA�ʏ�̉����Ɠ��l�̎�舵���́A�����炭�́A�����Ƃ��������ׂ����ʂ������炷���ƂɂȂ邾�낤�B SINGLE NOTES �P�Ɖ����ɂ̓R�����g���K�v�ƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�����́A�����̈قȂ��������������Ƃ��\������ł���B�M�L�҂����͂����炩�ɁA�P�ƕ��̌`�ɂ����āA�ނ�� �������A�����A�P�ƕ��́A�ʏ�̉�����2�{�ł���duplex longs�ƂȂ�Bduplex longs�́A�Ƃ��ǂ��A��蒷�������Ƃ��ď�����邪�A�����̏ꍇ�A�����́A�������݂��ɍ����悤�Ȃ����ł����F������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�㐺����organum�̐����̒P�ƕ��́A�����f�B�ɂ����锽���������邢��extensio modi�̌��ʂ�������B����䂦�ɁA������breve��Alonga recta,,longa ultra mensuram THE CONJUNCTURA OR CURRENTES �A�����̓���Ȍ`���Aconjunctura���邢��currentes�́A�P�Ɖ�����A�����̍Ō�̉����ɐڂ����Ђ��`�����̘A�����~���琬���Ă���B���̌`�́A�R�Ȃ����S�̉����̘A�����ւ̃v���C���\���O�̋L���@���ɔ������邪�A�m�[�g���_���̍�ȉƂ����́A�P�I�N�^�[�u���邢�͋�x�̉��~�ɂ����Ă������g�����B���������Ă��������p�b�Z�[�W�́A�m�[�g���_���l���̌����ȓ����ƂȂ��Ă���B�S�̉����ȏ�̌����͖��炩�ɁA���[�_���L���@�̘A�����p�^�[���ɂ͓���ׂ��]�n���Ȃ��B�����������Y����̂��Ƃ��Ƃ̌��ʂ́A��シ��currentes�������悤�ɁA���[�h�p�^�[�����Alongs��breves�ɂ�����肩breves��semibreves�ɂ���悤�Ȃ��₭������A�̉����ւƔj��悤�ɂȂ�i��X�|�Q�j�B 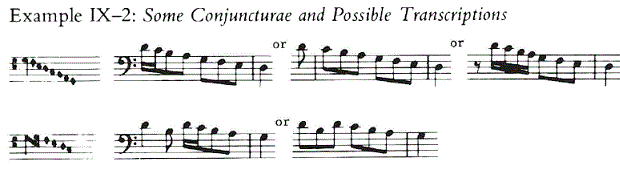 �Ђ��`���̌�̎g�p�́Asemibreves��cunjuncturae�ɂ���č����ł��낤���Ǝ������Ă���B�����͕K���������̈Ӗ������ʼn���������Ă���킯�ł͂Ȃ����B���ɁAcunjunctura�̍ŏI�����́A�ʏ�long�ł���A���̎�O�̉�����breve�ł���A��蓮���̑��������́A���~�̍ŏ��ɂ���Ă���B���������K���̈�ʓI�ȓK�p���ɂ��ւ�炸�Acunjuncturae�̐��������Y�����߂́A�����Εs�m�������c���Ă���B�����͂����Ƃ������́A�ێ����l�������ɂďo������B�����ł̓e�m�[���͂��̒��������߂邽�߂̏������Ȃ��B����ɁA��X�́A���[�h�p�^�[����cunjunctura���A�ŏ��̉�������n�܂�̂��A�r���̉�������n�܂�̂��A����Ɍ��߂���킯�ł͂Ȃ��B����䂦�ɁA�����cunjuncturae�̍Z��������^��Ȃ������K�v�͂Ȃ��B�����̘A�����́A���Ȃ莩�R���_��ɉ��t�����ׂ��i�����Ă���͌��݂ɂ����Ă��j���̉₩�����\���Ă���悤�Ɏv����B �@pllicas��P�ƕ��Acunjuncturae�ɂ���ē������ꂽ��������قǂłȂ��Ă��Afractio modi��extensio modi�̑o���̑��݂́A�����A�������̉��߂����e����A�����̕s�K���O���[�v���\������B����䂦�A����organum�̈قȂ����Z���ł��߂����ɂ��ׂẴ��Y���̏ڍׂ�����Ȃ�������A��������ordines�ɂ����ĈقȂ������Y�����[�h�������g�����Ƃ��Ă��A�ʂɋ����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B���[�h�L���@�ɍ�����s�m���������o���̂́A����̍Z���҂����ł͂Ȃ��B�V�X�e�����L�q���������炩�̗��_�Ƃ��܂��A�قȂ����̎肽�����قȂ�����肩���łς��Z�[�W�����߂��Ă��邱�Ƃɕs�����q�ׂĂ���B���[�h�L���@�����m�ł���A������i�̂Q�̍Z���͒ʏ��v����ł��낤�B�������A�A�����̕s�K���p�^�[�����h�������h�����@���^�킹��悤�ȏꍇ�́A�����͂��Ȃ�قȂ邱�ƂɂȂ邾�낤�B SUSTAINED-NOTE STYLE AND MODAL RHYTHM 2��organum���L�q����ɂ����āA13���I�̗��_�Ƃ�discant�l���A���������v�ʉ\�Ȃ��́A��organum purum�A�e�m�[���̕ێ������v�ʕs�\�Ȃ��́A�̊Ԃ���ʂ��čl���Ă���Borganum purum�̏㐺���̓��[�h�I�ł���A����炪�������đ�������statement�ł���A���[�h��non rectus���邢�͕s�K���ƂȂ�B�s�K�����̐����͑S�̓I�ɂ͂�����͂��Ȃ����A�����̓��Y�����[�h�̒ʏ�̉�������̈ӂɗ���悤�Ƃ��Ă���悤�Ɏv����B�X�̉̎�͔ނ�̌l�I�D�݂ɉ����ĉ����̒�����������Z�������肷�邩������Ȃ����A�L���͋K���I�ȃ��Y�����[�h�Ƃ��ē���̂܂܂ł���B����̊w�҂�́A�����̂��������C���́A�R�̃��j�b�g���̃��[�h�p�^�[���̂����݂͉Ȃ��ƍl���Ă���B���Ƃ��A�s�K���ȑ�P���[�h�� �@�Q����organum�ɂ����āA�ێ�����̖L���ȃ����X�}�͂��̗l���ɂ����āA���m�I�ł���悤�Ɍ����A������responsorial chants�������g�債�������X�}�I�g���[�v�X�Ƃ̊֘A�������Ă���B���܂�A�ێ����͂�����x�����f�B�̉₩�����R���g���[�������b�������Ă���B�ΐ����̃����X�}�́A�e�m�[���ƂƂ��ɍ�鋦�a�������n�߂���I���ɂ����肷��t���[�Y��break up�����B���������o�߂���̏o���́A�����f�B�̘A���̓�������̌��ʂł������B�m�[�g���_���̍�ȉƂ����̍ŏ��̍H�v�̂ЂƂ̓����f�B��g�D�������邱�Ƃł������B �ێ������ΐ����̃����f�B�b�N�ȕ����ʼn��t���Ă���悤�ȃR���g���[�����ǂ�����A�����͊m���ɁA���Y���\�������Ȃ������B�ʂ̐����̉������l������K�v���ɂ���ĖW�����邱�ƂȂ��A�ǂ�ȉ̎���Atriple�������ێ����邱�Ƃ͂��肦�����ɂ��Ȃ������B���Ƃ������̋L���@�����m�ŊԈႢ���Ȃ��Ă��B ����������́A���ۂ̎������̋L���@���A���_�I�L�q�ƌ���I�ɈقȂ��Ă���ꍇ�ł���B���[�h�L���@�̒ʏ�̘A�����p�^�[���Ƒ����āA�����A�A�����̔z�u������̃��Y�����[�h�������Ă��Ȃ����Ƃ��A���p�ɂɂ����B���������́A�����I�ɂ͑�����cunjuncturae����N���邪�A���̑��̘A�������܂��S�`�V���ł���B�Q�`�R���A�����݂̂�ordines��P�ƕ��ɂ����Ă����A�O���[�s���O�͂����Εs�K���ŁA�������̈قȂ������Y�����߂��\�ł���B���̂悤�ȋL���@�ɒ��ʂ��āA�̎肽���͂قƂ�ǃ��Y�����[�h��F�߂���A�g�����肷�邱�Ƃ����҂���邱�Ƃ͂Ȃ������B �ނ炪���[�h�̃p�^�[�����A���㕈�ł����U�^�W���q���Z�o����g�ɂ�O���[�v�����邱�Ƃ͂��܂�l�����Ȃ��B���y�͂��ꂪ��������A���t���ꂽ�悤�ɍZ������A�w�҂����͋^���Ȃ��A�����̃X�^�[�g�n�_�Ƃ��ă��Y�����[�h�̃p�^�[�����g��������ł��낤�B�̎肽�����A�����̃p�b�Z�[�W���قȂ������Y�����߂ɂ������Ċ���ł���A���炩�ȃ��[�h�L���@�ɂ�����K���I�ȃp�^�[���ł��������炭�A���R�ɉ��t���ꂽ���Ƃ��o���Ă���A�Q�͂Ȃ����Ƃ��낤�B�����̗��_�Ƃ����́A�h�m���Ă���h���y�ƂƁA�P�Ɂh���Ă���h�̂���̊Ԃ̈Ⴂ���������邱�Ƃ��D��ł���Borganum purum�̋ɒ[�Ȕ��������t����ɂ́A�̎肽���̖{�\���A���_�I���y�Ƃ̒m�������m���ȃK�C�h�ɂȂ邱�Ƃ��낤�B���Ȃ��Ƃ��ǂ�����l���ɒl����B DISCANT STYLE AND MODAL RHYTHMS �ێ����l���̏㐺������̃��[�h���Y���̓����́AMagnus liber�̂Q����organa�ɂ����Ă͌����Ȃ������Q�i�I�ߒ��ł������ł��낤�B�����Adiscant clausulae�́A���[�h���Y���������Ɏg�p�����Ǝv����B���[�h�L���@�́A�܂��\���ɔ��B���Ă��炸�A�S�̓I�Ȉ�ѐ����Ȃ��������A�����I�ȃp�^�[���͂����A�F�����āAfracture���ꂽ�B�ɂ�������炸�A���[�h�͒ʏ�A����\�ł���A�������Ōv��ꂽ�����̑��݂́A���Y�����̑啔�������������Bdiscant clausulae�ɂ����āA��ɁA��X�̓��Y�����[�h�̔��B�ƃm�[�g���_���|���t�H�j�[�̐��i��ς��������̗������ώ@���邱�Ƃ��ł���B �@Magnus liber�̍ŏ����̌`���ɂ����āA�����炭�̓��I�i���ɂ���āA�ێ����l���́A���|�I�ɗD���ł������Bdiscant clausulae�������ƁA�ێ����l���͒Z���A���܂蔭�W���Ȃ��Ȃ����B����قǕp�ɂł͂Ȃ��ɂ���A�㐺���̃��[�h�p�^�[���͂��Z�������ɂ���ĉꂽ�B�����ăe�m�[���͕��ޕs�\��longs�̘A���ƂȂ����B�����longs�͒ʏ�A��P���[�h�̂ЂƑg�ia foot)�ɓ�����3�{���ł���B�����������͂܂��A������2�{��duplex longs�Ƃ��Ȃ��Ă���B ��̑��clausulae�ɂ����ẮA�傽�锭�W�́A���Y�����[�h�̂�薾�炩�Ȓ�`�A���V�X�e�}�e�B�b�N�Ȏg�p�Ɉ˂��Ă���B�㐺���́A���̃��Y���̎��R�x�������]���ɂȂ��āA���[�h�̃p�^�[���ɂ��Ŏ������B�e�m�[���́A���̃��Y���\��������ɃV�X�e�}�e�B�b�N�ȋ@�\�Ƃ����B������longs�̘A���̑���ɁA�e�m�[�������f�B�̉����́A�����Aclausula�S�̂ł��肩������郊�Y���p�^�[�����Ŕz��Ă���B�����Ƃ���ʓI�ȃp�^�[���́A��T���[�h�̑�Pordo�ł���B�������Aclausulae�̃e�m�[���́A��P�A�Q���[�h�̒Z��ordines���܂��A�g���Ă���B���̑��̂�蒷���p�^�[���́A��T���[�h��duplex longs�A���邢��triple longs�Ƒ�P���[�h�Ƃ̌��̌��ʂƂ��Ăł���B��X�|�R�̓����I�p�^�[���ɂ���悤�ɁAclausulae�̃e�m�[���͒ʏ�A6/8�A�H�ɂ�9/8�Ƃ��čZ�������B���������p�^�[���́A��P�A�Q�A�U���[�h�P�ʂ��y�A�Ō���A�����̃��[�h���ʏ�A3/8����6/8�Ƃ��čZ������鍪���ƂȂ��Ă���B �ێ�����̃����X�}�ւ̂��������菇�̈�т����K�p�́A���^�₪����B6/8���q�łł����K���I�ȃt���[�Y�́A���Y�����[�h�V�X�e���ɉ����Ĕ��B���Aorganum purum�̂�菉�����邢�͎��R�ȃX�^�C����������discant�X�^�C������ʂ���悤�ɂȂ����B �@�e�m�[���ɂ����Ė��炩�Ȕ������Y���p�^�[�������Ƃɂ��Ă��鉹�y�\���ɂ����鐬���ւ̊S�́A��ȉƂ����ɑ��āAclausulae�̒������g����������������߂������B�e�m�[���͒ʏ�A�v���C���`�����g�̃����X�}�̂����鉹���g���Ă������߂ɁA���Ƃ��Ƃ̃`�����g�̂�葽���̉������܂߂邱�ƂŒ������g�����邱�Ƃ��ł��ɂ����B�B��̉����́A�P���clausula���̃����f�B�̂��ׂĂ��邢�͈ꕔ�����邱�Ƃɂ���āA�e�m�[�������邱�Ƃł������B��ȉƂ����́A�������������B�����̓����f�B�̍ŏ���statement�����Y���Ƃ��A���邢�́A�قȂ��������ł���͕ς���ꂽ��������Ȃ��B ����clausulae���ł́A�e�m�[���́A�ЂƂ̃��Y���p�^�[���������ƕۂ��Ă��邪�A�����f�B�̔����́A�p�^�[���̈قȂ��������Ŏn�܂��Ă���B����䂦�ɁA�������������́A�e�m�[���p�^�[���̐V���������f�B�`�ۂɂ����disguised�����B���̑���clausulae�͍\�����������A�����ɁA�e�m�[���ɂ�����V�������Y���p�^�[���̔��������������邱�Ƃɂ���ėv�f�̃R���g���X�g������Bclausulae�̃e�m�[���̃����f�B�̔����̕ω��̗����\�b�h�́A��X�|�S�Ɏ�����Ă���B �������������f�B��Y���p�^�[���̌������������́A13���I�ȍ~�́A���d�v�ȑz�������ł������B�����͂���䂦�A�m�[�g���_���y�h�i�����ăy���^���ɋA�����Ă����i�j�̂����Ƃ��d�v�Ȋv�V�̂ЂƂł���B DIFFERENT VERSIONS OF ALLELUIA NATIVITAS Anonimous�W�̃y���^���̒Z�k�`��Magnus liber�̉����ւ̊S�ɂ��Ă̒��ڂ́A���clausulae���A�ʂ�discant clausula���邢�͂��Ƃ��ƕێ����l���ō��ꂽ�p�b�Z�[�W�̗��҂̑I��I�u�����������̋N���ł���Ƃ����������B����������P�[�X�ł́A�K�v�ȏ�ɑ�����clausulae�������e�m�[���̃����X�}�ō�Ȃ���Ă���B�����Ă������́A�Ɨ�������i�Ƃ��Ďg����Ӑ}��������Ă����悤���B ��X�́Aclausulae���A������i�̈قȂ����ʖ{�Œ���interchange����Ă��邱�Ƃ����o���Ă���B������i�������f���������̉ߒ��́A2��organum Alleluia:Nativitas�Ƃ��̓Ɨ�����clausulae(AMM<No.33)�̑����_�c�ɂ����āA���炩�ɂȂ邾�낤�B �@�m�[�g���_���ʖ{�̂Q���A�Q����Alleluia:Nativitas�̂��̐ݒ���܂�ł���B�����āA�R�̎ʖ{�͂R���ݒ���܂�ł���BAnonimous�W�ɂ��A���̂�����1�̓y���^���ɋA������B�Q���ݒ�̂����̌Â����́AW1�ʖ{�ɂ���BF�ʖ{�����Â����̂ł���B �@�ێ����l���̖`����"Alleluia"�����́A�Q�̔łł́A�킸���ȈႢ�����邾���ł���B���̏́Averse�����ł͕ς���Ă��܂��B��Q�̃e�m�[�������̎n�܂�ł́A�ێ����l���̕����̃����X�}�͂قƂ�LjقȂ�����i�̂悤�Ɍ�����B���łɂ����Ă킸���ȒZ���p�b�Z�[�W����������ł���B�������A����͂����Ƃ��L�v��clausulae�̈����ł���B�hgloriose"�̐ݒ�́AF�ʖ{���ŐV�������A���Z���I�~���郁���X�}�������Ă���B�������A�����̔ł́hVirginis"�ɑ��Ă͓���clausula���g���Ă���B �����Ƃ��d��ȈႢ�̂ЂƂ́A���̌��t�hMarie"�ŋN����BF�ʖ{�ł́A�V���ߕ���clausula���AWaite�̍Z���ł�6/8���q��33���߈ȏォ�琬���Ă���ێ����l���̃p�b�Z�[�W��u�������Ă���B F�ʖ{���́hMarie" W1�ʖ{���́hMarie" "ex semine"��̈�A�̎���clausula�́A���l�ɋ����[���BW1�ʖ{�̐ݒ�́i�e�m�[���ЂƂ̉�����13���߁j�A��X�|�Sa�Ɏ�����Ă���悤�ȃ����f�B�����ɂ���Ċg�傳�ꂽ�e�m�[���̔������Y���p�^�[��������蒷��clausula�ɒu���������Ă���B ���Â��ݒ�͒P���ɔj������Ă��邪�AF�ʖ{���ł͑��clausulae�̊Ԃɕۑ�����Ă����B�V�����ݒ�́A�����[�����ƂɁA�y���^���ɋA�����Ă���3����Alleluia:Nativitas���̂Q�̒Ⴂ�����̐����ŏؖ�����Ă���B���ׂĂ̕ω��̌�A��Q�ł�verse�̎c��̂��߂ɁA�قƂ�NJ��S�ȓ��ꐫ�ɖ߂��Ă���B�Ō�̕��ŁA��X�͕ʂ̑�ւ����o���B �����̔ł́A"Juda,"��"Ju-"�ɂ����āA�������Z��clausula�������Ă���B�������AW1�ʖ{�̔ł͕ێ�����̃����X�}�ƌ��_�Â����Ă���B���̍Ō�̏ꏊ�ł́AF�ʖ{�̔ł́A�V�����R�����f�B��Ōォ��2�Ԗڂ̉����ɒZ�������X�}��t�����肵���e�m�[�����J��Ԃ����Ƃɂ���āAclausula���g�債�Ă���B verse�ɏ]���AF�ʖ{�́A�`����Alleluia�ɂ���Ȃ�ݒ���s���Ă���B���������ߒ��́AF�ʖ{����Alleluia�ɂ͈�ʓI�ł��邪�A���̑��̃m�[�g���_�������ɂ͂Ȃ��B����͖��炩�ɁA��̍�ȉƂ���������������AMagnusLiber�̌��^�ɉ������������肵�����ʂł��낤�B���̗�ɂ����āA"-lelu-"���discant clausula�́A�S�̓I�ɕێ����l���ł���ŏ���Alleluia�������Ȃ�Z���Ȃ��Ă���B �@Alleluia:Nativitas�̑�Q�łɂ�����g�債���ω��́AF�ʖ{���̎����Ɍ����鉹�������ł͂Ȃ��B"Ex semine"�̂Q��Clausulae�ɂ��āA�ЂƂ́A���łɌ��Ă����悤�ɁAW1�̂��Â��ł���ł���B�iPerotin Clausula�̎����Q�Ɓj ������iAMM,No.34b)�͐V����������B���̃e�m�[���́A���S��organum�ɂ�����y���^����clausula�̍ŏ��̂Q�Q���߂Ƃ��Ă̓������Y���ƃ����f�B�̔����ł��邪�B�������A���clausula�ɂ����ẮA���Ƃ���̃����X�}�̏I�n�����ɍs�������O�ɁA�e�m�[���͂���ɍ��v�łQ�Q��̔������s���Ă���B���̌��ʂ́A"Ex semine"�ɂ�����R��clausulae�̒����ɂ����錰���ȈႢ�ł���B�����Ƃ��Z�����̂�13���߂ł���B�y���^���̂��̂͂R�Q���߁A�����Ƃ��������̂͂T�S���߂ł���B���̂����Ƃ�����clausula�́A���ɁA���̑��̂Q���������ꂽ�̂Ɠ����悤�ɁA���S��organum�ő�ւ���邱�Ƃ��ł���B �@������ɂ����Ă܂��܂����x�ɍ\�����ꂽdiscant clausulae�̂����Ƃ����債�������́A�y���^�������I�i����organ��Z�k����statement�ł���ƐM�����Ă���B����炪Anonimous�W���������h���ǂ��hclausulae�ł���Ɖ�X�͉��肷�邪�A�����͗B��̐V�������̂ł͂Ȃ��B150�ȏ�̔��ɒZ��clausulae�́AF�ʖ{����discant�ݒ�̍Ō�̂Q�̃T�C�N���ifol.178-84v)���\�����Ă���B���̑��Ɠ��l�A�����̃T�C�N���͓T�珇���ɔz��A����ȃ`�����g�̂��߂�clausulae�́A���������тƂȂ��Ă���B���������Z��clausulae�́A�ێ����l���̃p�b�Z�[�W��u��������������̋@�\�������Ƃ��ł��Ȃ��B ��X�͂��łɁAAlleluia:Nativitas�̊��S�Ȑݒ�̑�Q�Œ��́hMarie"�Ƃ������t�ł̒u�������ɂ��ċL�q�����B����A��X��"-le-lu-"�A"-ti-vi-"�A�hMarie"�A"Abra-"�Ƃ��������t���邢�̓V���u����̂��̃`�����g�̂��߂̂S�ȏ��clausulae�����o���Ă���B�����̂�����3�Ԗڂ́A���łɋL�q�����B���������̑��͂��ꂼ��A���Z��discant clausula�ւ̑�։�����Ɋg�傳�ꂽ�����X�}�ւƃR���o�[�g�����B��X�̓I���W�i�����ǂ̂悤�ɒu��������ꂽ�̂��ɂ��ċ^�O������������Ȃ����A��������clausulae�̑}���̍���́A�����đς����Ȃ����̂ł͂Ȃ��B�����āA����炪�}������邱�Ƃ��Ӑ}����Ă��邱�Ƃ͋^��ł͂Ȃ��B �@Alleluia:Nativitas�ɂ����邱������clausulae�̂S���ׂĂ��g�������̌��ʂ́A2�{�ł���B����炪�e������Ïk�́A"Ex semine"��̂����Ƃ�����clausula�ł������₤�B�����āAdiscant�l���͍���A���Â�organum purum���x�z���Ă���B�����Anonimous�W�̏،��𗠕t����悤�Ȕ��W�i�m�[�g���_���|���t�H�j�[�̐��i�ł���j�ł���B�y���^���������炭�A���ׂĂ̑��clausulae����Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ́A�d�v�ł͂Ȃ��B�m�[�g���_���y�h�́A���}�[�V�����h�y�h�h�̂悤�ɁAdiscant�l���ւ̑��傷��I�D�������Ă���B��������discant�l���͋^���Ȃ��A���y�I�\����f�U�C���ւ̑��傷��S�f���Ă����Bdiscant clausulae�ɂ����organum���������悤�Ƃ��āA�m�[�g���_���̍�ȉƂ����́A13���I��ʂ����|���t�H�j�[��i������Â���\�������ƋZ�p�B�������B ORGANUM TRIPLUM AND QUADRUPLUM 3���A���邢�͂S����organum�́Aorganum triplum,organum quadruplum�ȂǂƌĂ�Ă���B�������P�Ƃł́Aduplum,triplum,quadruplum�Ƃ����p��͂���炪�e�m�[����ɂ���P�ꐺ���̌Ăі��Ƃ��Ďg���Ă���B���_�I�L�q����ۂ̎����̏؋��ɂ��A�����͂��̖��O�̏��ɍ�Ȃ���A���ꂼ��̉ߒ��͉��y�I�ɏ\���Ȍ��ʂł������B���ꂪ�A�y���^����"Ex semine"��̂R��clausula���AAlleluia:Nativitas�̂Q���ݒ�̎g�p�̂��߂ɓK�p���ꂽ���R�ł���B���邢�́A�y���^����clausula�̂Q���̔ł���Ȃ����̂́A�ނ��Â�organum duplum�������f�����O���đ�R�����������������Ȃ̂��A�ނ����S��organum triplum����Ȃ������Ȃ̂��H�@�ǂ���̉ߒ����A��������ł͉\�ł���A��ʓI�Ȃ̂ł������B �@��R�A�S�����̕t����,organum�̑S�̂̌`����ς��邱�Ƃ͂Ȃ��������A���y�l���́A�����̐��ɂ���ĕς�����B�e�m�[���͕ێ����ƌJ��Ԃ��̃��Y���p�^�[���̊ԂŌ��݂ɂȂ������A�㐺���͂قƂ�ǂQ�̃X�^�C���̊Ԃŋ�ʂ͂Ȃ������B�e�m�[����2���A�R�����I�[�K�i�C�Y����K�v���́A�^�������Aorgana tripla,organa quadrupla�̓������������Borganum duplum�͈̔͂̍L�������X�}�́A���Z���A�K���I�ȃt���[�Y�ɕ����Ă��܂��B�̎�͒j�ł��邽�߂ɁA�����鐺���͓��������ŁA�����N���X����B�X�̃����f�B�͋����͈͂ŁA�e�m�[���̏�����S���a�����œ����B���̌��ʁA�S�̓����f�B�̗��ꂩ�烊�Y����R�[�h�\���ւƈڂ�B��P���[�h�͈��������x�z�I�ł���A�����p�b�Z�[�W�́A�قƂ�lj�Ȃ��܂܁A���[�h�p�^�[����ۂB�K���I�ȃ��Y���Ƌ��a�����̑g�ݍ��킹����A�R���A�S����organum�́A��ȉƂ������]�����A�J����ȍÖ��͂�B HARMONIC STRUCTURE 3,4����organum�̘a���\���́A���������A���j�]���A�ܓx�A�l�x�A�I�N�^�[�u�Ƃ��������S���a�����Ɉˑ����Ă����B���_�I�ɁA�����������a�����̓��Y�����[�h�̂��ꂼ��̃p�^�[���̍ŏ��Ɍ����ׂ��ł��邪�A���Ԃ̉����ɂ���č��ꂽ�s���a���̑g�ݍ��킹�ɂ͓��ɐ����͂Ȃ������B ���������t��́A��X�͂��̋��a�����̎�舵���̋K������̑����̈�E�����o���B�ŏ��ɁA�l�x�͂܂��܂��A�ʼn�������ł́A��ʓI�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B����͏㐺���̊Ԃł͎c���Ă������B���̌��ʂ́A�ܓx�ƃI�N�^�[�u�̗D�ʐ��ł���B���������a���́A�t���[�Y�̍ŏ��ƍŌ�ł͂قƂ�Ǖs�ϓI�ɋN�����Ă���B �������A�K������̑�Q�̈�E�Ƃ��āA�O�x���t���[�Y���ɋ��a�����Ƃ��ďo�����Ă��邱�Ƃ���������B����䂦�ɉ�X�́A�ߑ�̎��ɂƂ��ẮA���S�O�a���͎O�x�̂Ȃ��O�a���������̌��ʂɂ����āA���s���肩�s�m��I�ƂȂ�Ƃ����A��ȏɒu�����B ����Ȃ�ʂ̋��a��������̈�E�́A�����̘A��������Ȃ���̋K�����痈��Btriplum��quadruplum�������ƁA���łɑ��݂��Ă��邠���鐺���ƕK��������v���Ȃ��Ȃ�B���̌��ʁA�s���s���a���̑g�ݍ��킹���A�����ɂ����ċN���邱�ƂɂȂ�B���̑��̃A�N�Z���g�̂��镔���̕s���a�����́A���������A���a��������������appogiaturas�̂悤�ɐU�������ƂɂȂ�B��������appogiaturas�́A�����A�t���[�Y�̍Ō�̉�����organum���s�ϓI�Ɏn�܂�ێ����ꂽ�Ԋu��a�����C������B���̈ʒu�̂��������g�������I��I�ł��邱�Ƃ́A�ʖ{�̂��܂��܂ȕψقɂ���Ď�����Ă���B ���Ƃ��AAlleluia:Nativitas�́AW1�ʖ{�ɂ����Ă͑����̂Ȃ��I�N�^�[�u�Ŏn�܂邪�AF�ʖ{�ł̓I�N�^�[�u�́A�i�ߑ�a���w�I�ȁj������v���钷���x�Ŏn�܂��Ă���B���_�Ƃ����͖��炩�ɁA�`����appogiaturas�͑S�����Ȃ����A�s���a���̓e�m�[���̓����x�点�邱�Ƃɂ���Ĕ�����ׂ��ł���A�Ƃ��Ă���B�ނ�͂܂��A�ێ�����ɏo�����鑽���̕s���a�����F���Ȃ��B���������s���a����������邽�߂ɁA�e�m�[���́i�ꎞ�I�Ɂj���ق�ۂ��A���a�����ֈڂ�ׂ����A�Ɣނ�͌����Ă���B �̎肪�ǂ̒��x�������������ɏ]���Ă����̂��́A�������͒m��R���Ȃ��BAlleluia:Nativitas��Sederunt�̗����ł́A�s���a���̏����́A�ێ����̕p�ɂ̒��f��ύX��v���Ă������Ƃ��낤�B�v���C���`�����g�̎��R�Ȏ�舵���́A���t�ɂ����āA����Ȃ��̂ł��������A�ߑ�̍Z���҂́A���ꂪ�ނ�̋L�q�ł��邱�Ƃ��������Ƃɂ͂��܂蓯�ӂ͂��Ă��Ȃ��B ��ȉƂ≉�t�Ƃ��A���y�ɋL�^����Ă���s���a�����̎��R�Ȏ�舵��������A�J�Ă����\���͂���B���̂悤�ȕs���a���̐����̌��@���^�����Ƃ́A���R�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B���_�Ƃ����́A���������s���a������菜�����Ƃ��Ă����B�������Ĕނ�́Aorganum���A�ނ����̘a���̍�@�̕W���ɂ��悤�Ƃ����̂ł��낤�B STRUCTURAL DEVICES IN ORGANA TRIPLA AND QUADRUPLA organa tripla��organa quadrupla�̗͋������ʂ́A���Y����a���̌J��Ԃ��̗B��̌��ʂł͂Ȃ��B�����f�B�̌J��Ԃ���\�����܂��A�d�v�Ȗ������ʂ����Ă���Borganum duplum�ł́A�Q�����Ԃ̑ΏƓI�ȃ��Y���\���́A��Ȏ҂�ɑ��āA�����̊Ԃ̃����f�B�W���m��������@����قƂ�Ǘ^���Ȃ��B�����A�e�m�[����̂Q�`�R�����́A�����̃����f�B�̊W��A���������鉹�y�\���ւ̃����f�B�f�ނ̌`���ւ̉ߒ��W������K�v�����\�ł���B����䂦�A�����discant clausulae�ɂ����ċL�q���ꂽ�n���I�H�v�̋�����3���A�S����organum�ɂ����Ă�苭�����Ƃ͎��R�Ȃ̂ł���B �@organum duplum�Ɍ��o���ꂽ����H�v�́A�P���ȃ����f�B���̃t���[�Y����ʂ��邽�߂̃����f�B�̘A���I�Ȏg�p�ł���B���ɂ��������A���̖L���Ȏ����́A��X�|�T�ɋ������A�N���X�}�X��Responsory Descendit de caelis�ł���B���̔��������́Averse�̂��̃V���u���h-quam"�̂��Ƃ̂��̂ł���B �ŏ��ɁA�R�̋ǖʂ̈قȂ������Y�����[�h�i��R����Q����P�j�ƁA�����̋L���̃e�L�X�g�̋K�����ɒ��ڂ������B ���ɂ����ẮAtriplum�ɂ����邷�ׂĂ̂R�̘A�����A�e�m�[���̕ێ����t�@�̏�ɁA�t�@����h�ւƉ��~�����{�I�����f�B�i�s�����邱�Ƃɒ��ڂ������B triplum�݂̂���т��ĘA���I�ł��邱�Ƃ́Aduplum���������[���d�v�ŁA�Q���̂����ǂ��炪�ŏ��ɍ�Ȃ��ꂽ�̂��Ƃ����^�����B������triplum�����ۂɍŌ�ɏ����ꂽ�̂ł���A����́Aduplum�������O�ɂ��łɁA��ȉƂ̐S�̒��ɑ��݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B �@�X�̐����̍�ȉے��́A�����̌������ӂ��܂�Ă���ƁA��Â��ꂽ���Ƃ��M�p�ł��Ȃ��Ȃ�B���������H�v�͂��łɁA�������̐��}�[�V������i����discant�l���ŏo�����Ă������A���̎g�p�͂Q��organum���ł͎��ۂɂ͕s�\�Ȃ��Ƃł������B�������A�e�m�[����łQ�`�R��������A���������͍\���I�H�v�̂����Ƃ���ʓI�Ȃ��Ƃ̂ЂƂƂȂ�B���ɁA�g�����ꂽorganum quadruplum�̃����X�}�ɂ����Ă���͒������B �y���^���̂S����iSederunt�̖`���͂��̓����I������B13���ߖڂɂ����āAduplum��triplum�́A�Q���ߓ��C���̐����������s���B����ɁA13���߂���23���߂�11���ߕ��ɂ����ẮA������������24�`34���߂Ɛ��m�ɓ����ł���B���̂P�W���߂ɂ����ẮA���������͂����Ԃ��邭�Ȃ��Ă���B�U���߃p�^�[���͍ŏ��Aquadruplum�ɂ����Ė��炩�ł���A���ꂩ��triplum�ƂȂ�A�ēxquadruplum�ƂȂ�B���̃p�^�[���̉��ł́A�I�X�e�B�i�[�g�̂悤�ɁA���̐����̓����f�B�̃A�E�g���C���̓t���[�Y�\���̑o����ς��Ă���B ����������ł́A�A�����������̍�Ȃ́A�s�ϓI�ے��������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ����炩�Ƃ���B���Ȃ��Ƃ��A�������̕���́A���ׂĂ̐������ǂ̂悤�ɂȂ�̂���\�����č�Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA3���̊Ԃ̃����f�B�̌����́A���y�I�f�U�C����j�邱�ƂȂ��ɁA�����͏ȗ����꓾�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B����䂦��X�́A�y���^����Sederunt���S����organum�Ƃ��čl�������ƁA�ނ��قȂ��������̕��G�ȊW�����炩���ߌv�悵�Ă������ƍl����̂ł���B �@�Ȍ����́Aorgana tripla,quadrupla�̍�Ȏ҂ɂƂ��Ă͉���S���Ȃ��������Ƃ́A���炩�ł���BMagnus liber�̒Z�k�ł����A�ێ�����̌Â�organum������ɍ�����discant�l���ɒu�������悤�Ƃ����]�ɂ�������ʂł������B3���A�S����organa�ɂ����āA�㐺���͏��discant�l���ł������B�����āA�\���I�H�v�ւ̒���́A��t��ǐM���������قǂ̒����̍�i�����ݏo�����B�`���̘a����ASederunt�̍ŏ��̃e�m�[���͂S�U���ߑ��������X�}�̉��ŕێ�����Ă���B�ЂƂ̌��t�ɂ��Ă̊��S�Ȑݒ�́AGradual�̃\����intonation�ŁA�����142���߈ȏ�ɂ��g�傳��Ă���B�����đS�̂̍�i�̉��t�́A�Q�O����������B���y�I�\�������̂悤�ȋ����悤�Ȏ����ɒB���邱�Ƃ͂���܂ł͂Ȃ������B�m�[�g���_���̖{�����������āA�����̑O��̂Ȃ��傫����s�傳�́A���̍L���ɂӂ��킵���悤�ȉ��y�������悤�y���^�����������Ă��B���̖ڕW�̂��߂̔ނ̐����������т̂��߂ɁA�ނ́u�����Ƃ��̑�Ȃ�y���^���v�ƌ����Ă���̂ł���B |