| MEDIEVAL MUSIC
第10章 |
| p272 C H A PT E R X T he School of Notre Dame,Ⅱ and Motet T H E C O N D U C T U S オルガヌムのレパートリーと同じくらいの規模であるが、それ(conductus)はノートルダム楽派の作曲家の全体の作曲数には決して及ばない。あらゆる写本資料は、教会の公式典礼に属しないラテン語詩の設定を含んでいる。そうしたコレクションでもっとも大規模なものが、F写本である。それは130の2声、56の3声作品を擁している。さらに加えて、F写本のふたつのセクションは、143のモノフォニックなラテン語詩を含んでいる。 こうした主題がどうあれ、これらの作品は一般的にconductusという名で知られている一つの作曲分野を構成している。ダニエル劇のような、conductusとして扱われる作品はprosession(典礼行事における行列)における歌であり、おそらくこの言葉はオリジナルな意味を表わしている。 12世紀半ば頃のSantia de Comostelaのレパートリーもまたconductusを含んでいる。それはおそらくポリフォニーでもモノフォニーでも同じ機能を果たしていると思われる。13世紀までにしかしながら、conductusはSt.Martialのversusとほとんど同じ意味の言葉となった。 いくつかのconductusは、特別な教会行事や聖人の祝福を記念するための半典礼的な歌詞を持っていた。そのいくつかは、Benedicamus Dominoである。より時事的性質を持つ多くの歌詞は、政治的事件に言及していた。司教や王の戴冠、彼らの死の追悼、十字軍への説教等である。さらには、道徳的lessonや社会悪を攻撃するものもある。たびたび風刺にもなっており、その相手は誰とも問わない。牧師さえもその対象となる。 こうした歌詞のヴァラエティのため、conductusを定義するのは難しく、そしてその機能もまた決めることが難しい。いくつかのconductusは、典礼に対して非公式な側面をも加えていた。より適当な使用は、聖職者や学者たちの楽しみや若者への音楽的・道徳的教えといったことであっただろう。 歌詞は明らかに、聖なる主題から離れていくにつれ、俗的なラテン語歌と重複し始めた。聖と俗との境界線を引くのが困難になっていった。これは、特にモノフォニックソングで著明であり、次の章で取り扱う予定である。ここでは、ノートルダム写本中に保存されているポリフォニックなconductusをまず見ていきたい。 音楽的な形式、様式において、conductusは、その歌詞内容の主題同様、ヴァラエティに富んでいる。にもかかわらず、音楽的性質の区別は比較的簡単である。最初に、我々は、13世紀の理論家、ケルンのフランコがconductusの作曲のために与えた方向性を取り上げよう。 フランコは「conductusを作ろうと思う者は、最初にできるだけ美しい旋律を作らなければならないetc.」と話している。こうした記述から、我々は再度、連続的に各声部を書くことがは正常な手順であることを理解する。そして我々は、 単声のテノールを書くことから始まるそれぞれの連続したconductusの版は、それ自身が完成品であると推論する。こうした推論は、多くの場合真実であり、現存するconductusのさまざまな版で証明されている。 conductus Veri florisは、非常に重要な例のひとつである。この歌詞の本質的設定は、それぞれ単声、2声、3声の版において9つ以上の写本に現れる。多くのconductusは一つの資料に2声のみか、付け加えられたtriplumとともにかで、現れる。この状況は13~4世紀の多くの音楽の特徴であり、したがって我々は、ある版がオリジナルであるとは常には言えないのである。いくつかの例では、第3または第4の声部が、おそらくは別の作曲家によって後からつけ加えられている。 conductusの作曲のためのフランコの処方箋からの別の類推は、これらの旋律の素材はまったく新しいものである、ということである。結果的に、我々はしばしば、conductusが最初の完全なオリジナルなポリフォニックな作品であると理解している。 (このフランコの)statementは概して正しいが、qualificationの必要性が出てくる。フランコよりやや後の理論家である、Odhingtonによれば、conductusのテノールはもともと知られていたか、新たに作曲されたか、両方の可能性があるという。実際、conductusのいくつかのテノールは、俗界で歌われているモノフォニックな世俗歌として表れている。一番よく知られている例は、3声conductus Veris ad imperiaである。そのテノールは、春の訪れを祝福した歌でもあるトロバドールダンスソング、A l'entrada del tens clarの翻訳されたものである。 その他の借用素材は、プレインチャントの断片からの引用、そしていくつかの長いconductusにおいては、完全なクラウズラでさえも含んでいる。こうした借用の完全な程度は、すでにいろいろ調べられているが、完全なオリジナリティはconductusの本質的な特徴とは言えない。さらに言えば、世俗歌、プレインチャント、オルガヌムとconductusとの確立された関係は、Bukofzerの言葉を借りれば「13世紀の音楽における驚くべき内部調和と様式的統一性の対する雄弁な元気のある証」ということになる。 THE TWO CLASSES OF CONDUCTI 音楽様式の基礎において、13世紀の理論家たちは、connductusの二つの分類をしている。最初の部門はconductus simlexあるいはsimle conductusとして知られている。テノールのメロディはシラビックであり、付け加えられた声部はnote-ageinst-note形式あるいはneume-against-neume形式であり、それはディスカント様式の対位法である。多くのこのようなconductusは有節歌詞を持っており、音楽はそれぞれのスタンザを繰り返す。それゆえ、音楽形式とテノールの旋律様式の両面において、simple conductiは同時代の世俗歌の賛歌と類似することになる。 次の部門は、conductiのより精巧な部門であり、embellished conductusと呼ばれる。conductus with caudaeと呼ばれることもある。caudaという言葉は、最後のあたりを意味するうイタリア語codaと似ているが、13世紀のcaudaはメリスマ的流れのことを意味する。それは時には驚くほど長くなることもあるが、conductusのどの場所においても見出すことができる。 いくつかの作品は短いメリスマ的拡張のみであるが、典型的な装飾されたconductusは、最初と中間にも最後と同じいようなcaudaeを持っている。概して、メリスマは、最初か、詩行の最後か最後から二番目のシラブルで発生する。もっとも極端な場合、caudaeは、単純なconductisの賛歌のような性質ときわめて対照的に、音楽の発展に対して歌詞が従属するようなメリスマ優位の形式を取る。単純か装飾的なconductusかどうかの歌詞の設定は、その主題や詩の形式とは独立して決められている。おそらくは、独立した機能は、現在は確かではないが、決定的な要素なのであった。機能が特殊な歌詞設定において単純か装飾的かの程度が糸口なのである。 PERFORMANCE PRACTICE AND RHYTHMIC INTERPRETATION 我々がconductiのふたつの分類の詳細な研究に入る前に、簡単に演奏やリズム解釈の問題を取り扱わねばならない。ポリフォニックconductusは通常な最下声部の下に歌詞が置かれたスコア形式で書かれた。この配置は、学者らにより、上声部はメリスマとして詠われ(訳注;歌詞がつかない)、あるいは楽器によって演奏された、と解釈されてきた。装飾的conductusのcaudaeの器楽的演奏は、たしかに考えられる。conductiはこのように演奏されたのであろうが、この仮定は、疑いの余地がない程に確固たるものではない。 スコアにおける2声、3声、そして4声でさえ、すべて歌われるという前提で、それぞれの声部の下に歌詞を書く必然性はない。さらに、書記は、異なった声部の音符が歌詞のそれぞれのシラブルと一緒に動くことがわかりやすいように気を付けたことだろう。caudaeについては、メリスマ的なオルガヌムの演奏が普通だった時代には歌われなかった理由がない。 しかしながら我々は、特殊なconductusの様式や機能がその演奏形態に影響を及ぼしたことを認めなければならない。caudaeを伴うより精巧なconductiは、ソリストのために作られたが、単純なconductiは多くのグループで歌われたであろう。典礼に対して作られた作品は、当然のことながら、器楽の参加は考慮外であっただろう。教会の儀式で、唯一聖なる楽器とされていたオルガンは除いて。 他の楽器は、無論、通常は世俗の楽しみために使われていた。そしてそれらは、典礼とは関係していないconductiの演奏において、人声と一緒に、あるいはむしろそれに置き換わっていった。中世やルネッサンス期演奏形態は、我々が後の音楽で慣れ親しんでいるような形態よりも柔軟であった。そして我々はそれゆえ、conductiを、当時のように歌い、演奏するであろう。 conductiのリズム解釈はより問題が多い。モード記譜法は、メリスマ的なパッセージにおいてのみ使われていた。conductusにおいてはそれゆえcaudaeのみが、 意図したリズムとしての合理的確からしさとして記譜法で書かれていた。単純なconductusとそのシラビックな部門は、単純なネウマ譜で、一つのシラブルにつき一つの音符、あるいは一つの連結符で書かれていた。 2種類の解決法が示された。一つは、それぞれのシラブルが同じ音価を持つということ、それは連結符が2ないしそれ以上の音符を持つ場合、より小さく分割されることを意味する。もう一つは、シラビックな部門をリズムモードのひとつとすることである。後者の解決法の場合、テキストは通常は、連結符がfractio modiを導入する時には、モーダルパターンを維持している。 p276 最近の意見では、後者の解決法が支持されているが、リズムモードが使われる場合には、そうした同意はしばしばストップする。装飾されたconductusにおいては、caudaにおいて普及しているモードは、しばしばシラビックな部門に最適であることが証明されている。そしていくつかのcaudaは、歌詞を伴て歌われる音楽のあらゆる部分を繰り返し始める。 こうした論議は ―異なったモード内のcaudaeの繰り返し―として知られる現象によって、いくぶん弱められる。それは、conductusにおいては、確立されて技術である。 第5モードのようなシラビックなパッセージが、第1あるいは第2モード内で直接繰り返されることができないと仮定する理由は特にはない。さらに言えば、caudaeはそれ自身、正しいリズムモードとして異なった意見を禁止するような十分な明瞭さでもって、常に記譜されるわけではない。 もちろん、単純なconductusであれば、どのリズムモードが使われるべきかを決めることは、より困難なことになる。記譜法の詳細が長い音価を示していても、結論は歌詞と音楽的性格を考慮して 常に保留にされる。詩行の長さとその支配的な韻律パターンは、1つのモードをより適度なものとする。ひとつの音符と連結符の交代、あるいは連結符の一貫した出現は、長短音価の繰り返しパターンを示唆しているのかもしれない。なぜなら、多くの連結符を持つ旋律は不規則に位置し、第5モードのみがそれに合っているからである。 第5モードによる写譜は、偶然に、全体的なモードの利用を拒絶したり、シラブルを同価と評価するようなシステムとほとんど同じ結果をもたらす。 最後に、詳細な組み合わせは、extensio modiの使用と比べられるような、不規則なリズムを示唆するかもしれない。普及した第1モードにおいてはたとえば、いくつかのシラブルは二分法よりも三分法のロングを要求するだろう。 conductusの歴史的発展においては、最初期の例はそれぞれのシラブルが同価であることが確かめられている。リズムモードの発展につれて、こうした同一長さの音価は、連結符によって導かれたより小さな音価からのより一貫したorganizationを供給するような第5モードにおける三分法となったのであろう。 後のconductusは、メリスマ的なcaudaeに対してと同様、自身の歌詞を設定するための他のモードのリズムパターンが適用されるようになった。残念なことに、こうしたステップは、たどることが困難になっている。正確作成日時がわかるconductusはほとんどないし、すべては、歌詞とともに、同じく非計量的な記譜法となってしまっている。計量的記譜法で書かれた後の資料におおけるconductusの偶然の出現でさえも、こうしたオリジナルなリズム機構を確かめることはなかなか困難である。 現代譜は、書記の記譜法でその長さが記されていない音符の長さを決めるためには同じ手順を踏んでいる。我々の確信として強く言えることは、こうした手順は必要であり、我々は作曲者の意図や中世の演奏者たちの実践を再度捉えることは、決して完全にはできない、ということである。 p277 FO R M S A N D S T Y L E O F SIM IP L E C O N D U C T I 単純、あるいは装飾的なconductusの対照的な形式を綿密に比較すると、両者は、異なった基礎を持っていることがわかる。研究に役立つほんの少数のconductusにおいてさえ、手順の多様性は、"危険なことである。しかし、conductusの2分類は十分に多様的であり、少なくとも極端な状況においては、議論を分ける必要がある。我々はそれゆえに、caudaeを持つ拡張例のようなより複雑な過程を持つconductusに進んでいく前に、単純なconductusにおける様式と形式の特徴的関係について考えてみたい。 我々は、単純なconductusは、その旋律形式と有節的詩のそれぞれのスタンザに対する同じ音楽の使用において、賛歌のようである、と認識している。現在、我々は、conductusとhymnが同じ音楽形式であることを理解している。これらはそれゆえ、hymn形式と呼ばれているが、異なった音楽の局面の連続はおそらくはもっとも一般的なことであろう。 多くのconductusはしかしながら、aabc,abab,aabbというパターンを繰り返す。conductusのスタンザは一般的なhymnの4行スタンザよりも通常は長いために、それぞれのこれらのセクションは 2ないしそれ以上のフレーズを含んでいる。しかし、それらは明らかにすでに見られたパターン(第4章参照)の拡大版である。同じ形式は、世俗歌においても起こる。ラテン語、世俗語両者そして、多くのconductusにおけるrerainの存在は、同時代の世俗歌との密接な関係を構築している。これらのあらゆる中世音楽の均一性のさらなる証明は魅力的であるが、それらは相互関係の解放や特殊な音楽ジャンルの特殊な形式、様式を示すことと関連することは不可能である。 単純なcondctusの多声設定をしているテノールは、通常、単声歌と同じ構造的パターンを持っている。加わった声部は他方、こうした形成期を反映したりしなかったりするかもしれない。それらは通常、連続するテノール上の正確なフレーズの繰り返しを示すことはできないが、フレーズのはっきりとしたテノールの繰り返しの上にそれらはそれら自身、連続的である。 sol sub nbe latuitの最初の8小節は、こうしたむしろ一般的な手順を説明する(Example10-1)。テノールの繰り返す4小節単位は、ふたつの同じようなフレーズから成っている。こうしたケースでは、作曲者は、彼のスキルを示す丹念な努力をしたことが見て取れる。 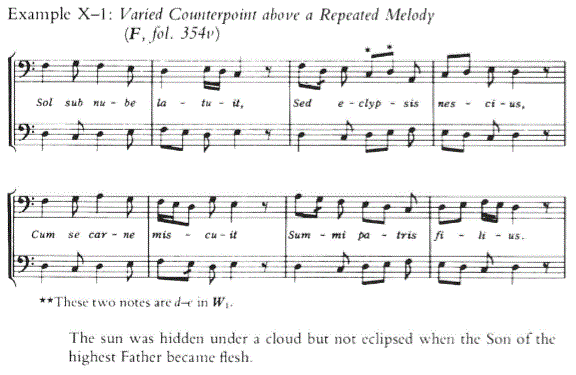 別々の声部の繰り返しと連続的形式の組み合わせの代わりに、作曲者は時々、他の声部においてそれを再生産することによって、テノールの構造を強調することを選択する。かれらはたびたび、セクションを正確に繰り返すが、duplumとtrilumの間の声部交換を導くテノールのフレーズの継続的状態を利用するかもしれない。 Veris ad impereaは、テノールのオープニング局面の4つの状況に関する、特徴的な例である。上声部はそれぞれの引き続く繰り返しで、声部交換を行う。もう一つの単純なconductus Procurans odium(Earning hatred)は、すべての3声部において尋常でない複雑な声部交換を含んでいる。(AMM No.36) FORMAL ORGANIZATION INEMBELLISHED CONDUCTI p279 Procurance odiumは、おそらくは、すでにst.Martial楽派の後期の作品とNotreDameオルガヌムにおいて示された傾向である構造主義的傾向の極端な例である。作曲の通常の過程は単純なconductusにおける力作の珍しさを説明することだろうが、装飾されたconductusuのcaudaeは、大規模な音楽形式の機構と声部のシステマティックな統一のためのより多い機会を供給する。メリスマ的な拡大を伴う作品(最後のみにそれがあるいわゆる真のコーダ)は、単純なconducutusからの他の観点と異なることmこなく、形式的な構築の単純な方法に従う。 特徴的な例は、すでに示したhac in anni janua とSol sub nube latuitである。後者はいくつかの理由から興味深い。8行のスタンザはaabb型である。4行のrefrainは、それぞれのスタンザの後を、連続的に繰り返している。そして、最後の唯一のcaudaは、refrainの最後のフレーズを繰り返し始める。 単声のconductus Beata visceraは、Anonymous4によって、ペロタン作とされているが、refrainを伴うcaudaeをやはり、使用している。ここで我々は再び、4行refrain8行スタンザを考えて見る。今回は、スタンザの音楽はaabc型である。refrainはメリスマとともに始まり、最後の行の最初の言葉においてそれは繰り返される。同じcaudaが2回出現し、refrainを単純なconductusの形式において、スタンザから区別する。 いくつかの装飾されたconductusは、単純な様式での完全な歌詞設定を伴って、終結部と同様、メリスマ的な導入部を持っている。より特徴的な形式は歌詞自身においてメリスマを導入する。 適度な長さの典型例は、単声のSo. oriturと2声のRoma gaudensである。これらの作品においては、caudaeは再び、導入部と終結部として機能する。しかし今や、歌詞全体に対してというよりも、部分的ではあるが。シラビックな、あるいは若干ネウマ的様式はさらに支配的特徴である。そして、caudaは装飾的な付加物を残す。この状況は、装飾的conductusのより大きな例においても、ほとんど残されている。今、caudaeは支配的であり、テキストを伴う短いフレーズは、いくぶん不自然な挿入であるような印象さえ受ける。 この機能的逆転を説明するために、F写本中の2声のAve Mariaを引用したい。conductusの全長は162小節であり、6/8拍子である。そして、最初と最後のcaudaeはそれぞれ、35、30小節から成っている。間の97小節(162-30-35)のうち、わずかに27小節のみに歌詞がつけられているに過ぎない。残りの70小節は、それぞれの長さが11~18小節の5つのcaudaeとして分割されている。メリスマはそれゆえに、全体の3/4以上にも及んでおり、尾の部分の多重度とともに、歌詞を圧倒しているのである。 p280 ある意味、少なくとも、我々はcaudaeを伴ういくつかのconductusの大きさを、得られた新たな自由への作曲者の悦楽の反映として見なければならない。こうした作品を形成するための既存のチャントはなく、彼らは、複雑な統合や構造的工夫を発展させる傾向に、いくぶん多めに、耽っていたのである。そして彼らは、そうした工夫を2、3、4声のconductusに用いたのであった。 こうしたいくつかのconductusの長さを見ていると、どのような作品さえも、異なった何百というcaudaeに示されている多様性や独創性の適度な描写をしているとはとても言えない。こうした特徴的過程について考慮してみて、我々はしかしながら、Soli nitorem・・・addoを見てみたい。これは装飾的なconductusで、F写本中の適度な長さのものである。(AMM、No.37) より後のスペイン語起源の写本もまた、Soli nitoremを所有しているがしかし、リズム価値をはっきりと示す計量記譜法においては、第1モードは歌詞を伴うあらゆるパッセージにとっては初期的なものである。 最初のcaudaはこの第1モードを導入し、G音が音の中心であることを示す。それはまた、1小節遅れてduplumを追っていくテノールを持つ、カノン書法の例でもある。声部交換のこのような書法の関係は、2声間のG-F-Gという動機の交代する出現で明らかである。 2番目のcaudaは、さらに最初と最後の2小節の繰り返しによる音の中心を強調する。歌詞を伴う第2セクションは、第1セクションのヴァリエーションであり、そして両者は、声部交換をしながら、同じ2小節単位で終了する(16-17小節=34-35小節)。 3番目のcaudaはこれらの2セクションと、間違いなく、互いに最後の4小節をもって、関連する。それは、36~43小節=14~17小節+32~35小節となる。 歌詞の最後の6行の設定は、中断するメリスマもなく進行するが、C音で終わるいくつかのカデンツが、最後の拡大されたcaudaよりも前で、音のコントラストをもたらす部分を作る。これは、我々が見る限りはしかし、3番目部分が若干変異した要約に過ぎない。第2cauda,第3caudaの両者は第5モードへと変身する。 (Measures65 -80 correspond to 36-45 , and measures 81-96 to 18-25.) 。新しくしかし、最後の10小節で関係したメロディは、第2caudaを完成させた同じような終止の繁栄を導く。作品を通して、繰り返すリズムやメロディ形は、異様なまでにシラビックとメリスマティックなセクションを統合する格式ばった組織化の効果をもたらす。 このように高度に組織化されたconductusは、我々に、成功すべき声部の作曲法についての見方を変えることを強いる。ちょうど我々が、オルガヌムのいくつかの例において、同様な構造的手順によってそうするように。まったく明らかなことに、どんな作曲者も、彼がduplumのいくつかの部分を創造する以前に、Soli nitoremのテノールを完成させることはできなかった。テノールは、メロディが作られる前に、先立つduplumの旋律を再生産することはできなかった。そして、完全な声部交換は両者のメロディが存在して初めて出現したのである。カノン書法についてはさらに、両声部は連続してというよりも、同時に生まれなければならなかった。 p281(251) 音楽自身のその他の証拠の断片から、作曲者は常にケルンのフランコのよって勧められたような手順を踏むわけではない、ということが明らかである。おそらくは彼は、単純なconductusを書く上での初心者のための企てをしたのであろう。それらはほとんど使い物いはならず、確かに、装飾されたconductusを彼らのもっとも高度なテクニック達成のための手段として使うような芸術家たちを終わらせたのである。 合理的な組織とテクニカルな達成は決して、装飾されたconductusへの我々の興味に対する唯一の理由ではない。特にcaudaeは、中世の最も魅力的な音楽のいくつかを繁栄させ、音楽はDom Anselm Hughesが言うように、「単に知られるために必要であり、広く認められるために解釈された」のである。こうした魅力の多くは、生き生きとしたリズムや、最初と最後の2~4小節にわたるフレーズの、後の時代の音楽が親密になり理解を示した組織化された手順、等に由来するのである。 おそらくは、それこそが、Hughesを、いくつかのcaudaeが古いダンスや歌を組み込んだかもしれないという提案をHughes氏にさせた特徴なのであろう。こうした引用は、確かに中世の音楽の演奏と無縁ではないが、しかし我々はまだこの種の既存の資料の証明は持っていない。多くのcaudaeの構造的な独創性は、同時代のダンスや人気歌曲の存在を否定しがちである。こうしたものの非芸術的形式は,caudaeのスタイルやフレーズの構造に影響を与えたかもしれないが、我々の判断が、人気歌曲やダンスは何をもって構成されていたかという後の概念に影響されたという可能性もある。 conductusは結局、高度に洗練された作曲者が、同じく洗練された聴衆のために作ったものだ、ということである。我々は、このような作曲者が堅苦しい保守主義において、彼らの興味を追求したことに、同時にそのアピールにおいてかくも新鮮に直接的に音楽を作り上げたことに、驚くばかりなのである。 13世紀半ばまでに、しかしながら、作曲上の工夫への関心やconductusそれ自身に対するそれも、衰え始めていった。典礼的オルガヌムの分派としての起源から、新しい形式、モテットが当初はconductuの陰に隠れて発展してきた。そして、それは非典礼的な多声音楽の主要なタイプとして、conductusに入れ替わっていった。conductusよりも長く生きながらえ、モテットは、後期中世のもっとも重要な音楽形式の1つとして生き残った。にもかかわらず、我々は、14世紀初期の反動的な理論家Jacqes de Liegeに同意するかもしれない。彼はcondutusに言及し、「なんと美しく、なんとチャーミングで、そして芸術性にあふれている、そんなものが見えなくなってしまった」と言って、残念がった。 p282(252) CREATION OF THE MOTET 音楽に対峙する中世の姿勢が、我々のそれとかなり異なっていたことは明らかであろう。どんな理論家も、どんな作曲家も、どんな演奏者も、固定した、変化のない、最初の創造者において与えられた形式を正確に保持している存在として音楽作品を見なすことはできない。 こうした姿勢に対して、我々は、同じ作品の異なった写本版間に生じる相違―minor variantからmajor changeへ―以上のものを負っている。大部分のmajor changeはそれゆえに、純粋な音楽とはかけ離れている。conductusにおける声部の追加や削除、substitute clausulaによるオルガヌムの短縮や改善など。 詩人は、他の歌詞に対して作られた作品のcontrafactaの少数の作品を書く程度でconductusの改変に協力した。彼らは、もっと重要な貢献をした。トロープス化の古い実践を続けながら、オルガヌムの声部や上声部に言葉をつけていった。我々は新しい音楽の分野の創造を請け負ったことは、こうした活動に対しては、むしろ音楽的よりも文学的であった。 motetというその名前はフランス語motから由来しているが、motetusという言葉は、概して、テノール上の声部を言い、duplumに相当した。さらにもう一声付け加わるとtriplum,さらにquadruplumと続く。 メリスマ的オルガヌムへの歌詞の付加は、何ら驚くには当たらない。歌詞と音楽による典礼の装飾は、すでに単声トロープスやポリフォニーそれ自身で行われていた。responsorial chantは特に、メリスマの大きさにおいて、音楽的トロープスをしばしば拡大していた。歌詞がついたtロープスの言葉は、後から加えられたものである。(第6章参照)。プレインチャントのテノールの歌詞をトロープス化した言葉を伴うオルガヌムのメリスマ的上声部に供給することはきわめて自然なことであった。 もっとも古いこうした過程の例としては、St.Martial 楽派のレパートリーに見られる。これらの作品は同じBenedicamus Domino旋律について持続音スタイルにおいて、異なった設定となっている。そのうちのひとつにおいては、トロープスがDominoという言葉上に出現する。他の例では、Stirps Jesseにおいては、上声部はすべて歌詞がつけられており、5つの4行スタンザの完全な詩となっている。持続音であるテノール上に、この上声部は歌詞を伴っていて、ディスカント様式のような作品となっている。同じ行の設定は完全にシラビックであり、他のところはネウマティックである。いくつかの行は、引き延ばされたメリスマとして終わる。音楽的観点から見れば、Benedicamus Dominoのトロープスは、後のモテットとは似ても似つかぬものである。それはしかしながら、二つの異なった歌詞が同時に歌われるという(後のモテットにつながる)形式を導入するのである。 p283(253) 持続音様式のオルガヌムの少数のトロープスは、ノートルダム楽派のレパートリーとしてまとまっていく。もっとも注目すべきはペロタンの4声のオルガヌムViderunt とSederuntに加えられた一連の歌詞である。Ma写本中のこうしたトロープスのうちの4声作品はことに興味深い。なぜなら、triplumとquadruplumの変更は、すべての3声が歌詞付きで歌われるようになるからである。結果的に、3声は単純なconductusと同じような動きをすることになる。 このタイプのモテットは実際、conductus motetとして知られている。それらは異なった歌詞を持ち、異なったリズム構成を持っている点において、真のcunductusとは区別される。motetusにおいては、すべての付加された歌詞はその先祖を間違いなく裏切ることになる。テノールのテキストはひとつかいくつかの言葉からなり、ほぼ変わることなく、トロープス中のどこかに出現する。同じようなことから、さらに、詩の韻はテノールによって同時に歌われたシラブルと類韻となる。VideruntとSederuntの言葉に付加された長い歌詞は、めったに韻を踏むようにはなっていない。 メリスマに加えられた歌詞に関してこうした特徴を持つモテット中の再出現は、よく知られた、あるいは長く確立されたトロープス化の原理が新しい音楽形式の創造の背後に横たえている十分な証明である。こうした創造過程において、保持音としてのテノールを持つモテットは、成功したものではない実験、と見なされる。あるいは、少なくとも、実りのない実験、とされる。独立した形式としての真のモテットの発展は、完成したオルガヌムのためではなく、ディスカントクラウズラに対してトロープスを付加する事とともに始まるのである。 こうした禁則は、極端に長い歌詞を書く必要性から詩人を解放した。そして同時に、特定の典礼的機会とは無関係な歌詞の創造への扉を開いた。それはまた、作曲家たちが代替クラウズラの様式において新しい歌詞を作るためにモテットの制作に新たに参加し始めたことを意味した。 このようにして、13世紀初期の典型的なモテットは、関連する歌詞や上声部中の歌詞のほとんどすべてがシラビックな設定であり、テノールの繰り返しのリズムパターンでアレンジされたプレインチャントのメリスマを基礎として作られた比較的短い作品となった。 いくつかの例では、我々は、モテットが完全にオリジナルなのか、あるいはあらかじめ存在していたクラウズラに対して言葉がつけられたのかということがわからない。多くのクラウズラは、しかしながら、完全なオルガヌムの一部分を形成したものを含んでおり、プレインチャントの歌詞をトロープス(歌詞)化したモテットとして再度現れる。 もともと存在していたクラウズラからモテットが創造されたことを説明するために、我々はペロタンのAlleluja Nativitasとその言葉Ex semineを用いたクラウズラに戻ってみたい。AMM No.38において、クラウズラに付け加えられた多様な歌詞は、3声オルガヌムのオリジナルな形式を再生産する音楽バージョンとともにもたらされた。メロディとリズムの細かな変化は、記録されていない。なぜなら、それらはめったに、言葉が音楽に合うやり方にかかわらないからである。 ふたつのラテン語のトロープスの内の古い方はチャントEx semine Abaheの全フレーズとともに始まり、最後に、semineの言葉に戻る。テキスト内で、‐ineという韻と、テノールのE(x)上のメリスマの母音との類韻は、トロープス(歌詞)作曲の古い伝統に続いている。 Ex semineというテキストを利用するモテットは、3つの異なった形が存在する。F写本中では、テノールとmotetusの設定は、同じ写本の2声のAlleluja Nativitasの”代替”であるクラウズラに相当する。 第2の形は、duplumとtriplumが歌詞を持つ3声のconductus-motetである。この版は興味深いことに、 英語起源として作られ、存在するAlleluja Nativitasの3声設定の”代替”クラウズラとして機能している。 第3の形は、13世紀後半のモテットコレクション中に見られる。歌詞はやはりEx semine Abaheであり、duplumにはしかし、新しいトロープス(歌詞)Ex semine rosa がついている。この新しい歌詞は、最後の”semine"の言葉と”-ine”という韻と、テノールの母音との類韻ともに、古い歌詞に従う。 プレインチャントのテキストをトロープス化しようとモテットが意図した機能は、確かではない。それらはディスカントクラウズラとして、ノートルダム写本のモテットは互いに別のコレクションでグループ化されている。 現在、しかしながら、その配列は、テノールの典礼順序ではなく、加えられた歌詞のアルファベット順になっている。こうした配列は、モテットが典礼とは独立した作品となっていたことを示している。 motet-tropesは、もともとは、すべてのオルガヌムの典礼遂行のために用いられたと思われる。英語資料のEx semineモテットは、そうした実践が知られていなかった証拠を差し出す。 もう一つの可能性は、クラウズラとして作られたということである。聖なる歌詞を持っているモテットやクラウズラは、トロープス化されていようとなかろうと、特別な祝日の礼拝に適当な独立した作品となっていたことだろう。これが主たる機能となったのであろうが、我々はしかし、両者のタイプが音楽的発展、あるいは、すでに存在していた典礼ポリフォニーのテキストの拡大としてそもそも出現してきたことを考えておかねばならない。 ラテン語のトロープスEx semineは、ペロタンのクラウズラに加えれた唯一の歌詞ではない。モテットの歴史の非常に初期において、明らかに、詩人は既存のクラウズラに適合するようなフランス語詩を書き始めていた。 W2写本は初期のフランス語モテットの大規模なコレクションであるが、そこには、Ex semineの音楽が2つの異なった歌詞で3回出現する。2声に減じられた版においては、上声部はHyper mein trespensis errieという歌詞になっている。第2のフランス語歌詞Se j'ai ameは2回出現する。一度は減じられた2声版のduplumとして、もうひとつは完全な3声クラウズラのduplumとtiplumのcondutus-motetとして。 p285 これらの歌詞はいずれも、クラウズラの典礼的機能、あるいはテノールにある"Ex semine"の言葉を持っていない。Hyper meinは、トロバドールやトロヴェールたちによって開拓されたpastourelle形式のミニチュア版である。Se j'ai ameは、こうした流行語において表現されたラブソングである。その性格として、地上の女性あるいは聖マリアへの献身を表現していた。 ふたつのフランス語歌詞が、既存のメリスマに適合するように書かれた事実を超えて、トロープスとは何ら関係がなかったことは明らかである。 我々は、トロープス化の過程よりも、contrafactaを作る中世の好みに対するフランス語歌詞を持つモテットの出現に関心を持っていくべきであろう。この例において、フランス語のcontrafactaは、モテットに、世俗的快楽のような新たな社会的機能を付与した。そして、そうした快楽と世俗歌の当時の形式の間の密接な関係を確立した。 我々は、それゆえ、ラテン語と世俗後双方におけるモノフォニーの歌の勃興について調べ直さなければならない。初期の文学や音楽活動への知識を備えることにより、我々は13世紀の世俗ポリフォニーの突然の勃興をよりよく理解し、独立した音楽形式へのモテットの発展をたどっていくことができる。 |