| MEDIEVAL MUSIC
��T�� |
| ��146(116) �b�g�`�o�s�d�q �X The Roman Mass �L���X�g���̗��j�ɂ����āA��̔ӎ`�̍Č��\Communion service-�͂����Ƃ��d�v�����l�ȋ���̋V���ł���BCommunion�̋V�����g�́AEucharist�Ƃ��Ēm���Ă��邪�A���܂��܂ɌĂꂽ�����̌`���ɂ����ēT�犈���̒��j���`�����Ă����B ��X�́A��������̈قȂ����}�̂��܂��܂ȈӖ��ɊS���K�v�͂Ȃ����A���e�����missa�Ƃ������t�̋N���ɂ́A������v����B ���ɏ����̎���AEucharist�̏j����offering���邢��sacrifice�ƌĂ�Ă����B�R�`�S���I�ɂ͂���͂����ΒP�Ɂh��h�Ƃ���悤�ɂȂ����Bmissa�Ƃ����F���Ȃ����t����菖�q�I�ȈӖ����������������Ƃ͋����[���B���̌�missa�͒P���Ɂhdismissal�i�o�Ă����j"���Ӗ����A�I����hIte,missa est�i�����A���o�ł䂩��j"�ɂ����Č����B�����ł͉�O�͗�q�̏I�����Ӗ����Ă����B �S���I�̏I���܂łɁA���炩�ɁA���̌��tmissa�͏W���̏I���A�V���̏I�����Ӗ����Ă����B�����ĂT���I�ɂ́A���̌��tmissa�́A�������ۂ��܂ޗ�q���Ӗ�����悤�ɂȂ����B����ɂ������Amissa��Eucharist�̏j���Ɍ��肳���悤�ɂȂ�A���[�}�ɒ����𐾂��Ă���L���X�g�҂̊Ԃł́A���̑��̖��O�Ɏ���đ���悤�ɂȂ����B �@�J�g���b�N�̗�q�̂����Ƃ����Ȃ镔���Ƃ��āA���[�}�~�T�͏j���V���B�������B����́A�L���X�g�������̒��S�ƂȂ�|�p�I���B�ł������B�����������B�ɂ����āA���y�͏�ɁA���ɏd�v�Ȗ�����S���Ă����B�~�T�͑��̓T���q���������̍�ȉƂɂ���āA��葽���̉��y�����@����B����͖��_�A���ɒ�����l�b�T���X����ɂ����Ė��炩�ł��邪�A�~�T�ɑ��鉹�y�̓v���C���`�����g�₱�̎���̃|���t�H�j�[�Ɍ���Ȃ��B�Â��e�L�X�g�̓o�b�n��x�[�g�[�x������X�g�����B���X�L�[�܂ŁA�̍�ȉƂ𖣗��������Ă���B �@���̌|�p�I�i���ւ̃v���C���`�����g��|���t�H�j�[�̏d�v�ȍv���𗝉����邽�߂ɁA�ڍׂɃ~�T�̊�b�\�������Ă��������B �@�~�T�̖{���I�ȃt���[�����[�N�͐����I�ɂ킽���Čł߂��Ă��������A��X�́AA.Jungmann�����ڂ����悤�ɁA�h�ӎ��I�Ɍ��肳�ꂽ���邢�͐���������ꂽ�v��h�̏I�������|�p��i�������̂ł͂Ȃ��A�h�����Ă����i���Ȃ킿�A�����I�ɂ킽��l�ԁA�����̌��t�̂�����ׂ肪��^������i�h�������Ƃ������Ƃł���B�~�T����ɔ��W���Ă�������Ƃ��ŋ߂̗�́A���o�`�J������c�Ō��Љ����ꂽ�ω��ł���B��X�́A�~�T������䂦�A�������ꂽ�`�ł̌|�p�I�B���A�Œ肳��ω��̂Ȃ��`���ƍl����ׂ��ł͂Ȃ��B �@����ꂽ���j����ɂ����Ăł��A�~�T�̋V���͂��Ȃ�ω�����̂ł���B���̊�b�I�\���͓����Ȃ̂ł��邪�A�i�����V�~�T�ł́A��l�̖q�t�ɂ���Đ��s�����~�T������萸�k�ł���͖̂��炩�ł��낤�B���̑��̑���_�́A����N�̋G�߂����ȓ��ɂ��̏d�v���A���邢�̓~�T�̋@�\���̂��̂f����B ���N�C�G���~�T�ł͂��Ƃ��A��т̏j�T�̍��ʃ~�T�Ƃ͋ɒ[�ɈقȂ�B����ɁA��O�̐��A���Ղ̐��A�P�����ꂽ���̑��̑��݁A��q�ꏊ�̑傫������A��O����q�ɂ����ĉʂ��������ɑ���n���̑ԓx�ɂ���Ă��Ⴂ���o�Ă���B �@�~�T�̏j���ɂ�����T��̓���������炷�����̎U���I�w�͂ɂ�������炸�A����͈ӎ��I�ɓ����ꂽ�قȂ����p�@�ւ̒��ڂ��ׂ��E�ς������Ă���B���O���S���E�X�́u�M�ɂ����ẮA���l�ȗp�@�͋���ɂ͌����ĊQ�ł͂Ȃ��v�Ə������B���̌��t�́A�������ɖ苿�����B1�U���I���̃g�����g����c�ɂ����ď��߂āA�����̒����������͊������A�P�����A���ꉻ���ꂽ�~�T�̓T��́A���[�}�J�g���b�N����ɂ����銮�S�Ȑ����������炵���̂ł���B THE EARLY FORM OF THE MASS ��X�́A�g�k�����⏉���̋���ǂ̂悤�ɂ��ăL���X�g�̖��߁A���Ȃ킿�u�䂪�L�O�Ƃ��āv�p���ƕ������̔�Ղ����s�����̂��͐��m�ɂ͒m��Ȃ��B���炩�Ȃ��Ƃ́A�ނ�͍ŏ��ɁA�����H�ɑ��郆�_�����̋V�����A�߂��z���̏j���̋V���v�f�ƌ��������H���ƊW���āA������j�������Ƃł���B ��ҁi�߂��z���̍Ղ�j�́A���K�I�ɁA��Ȃ��p���̏j���ƂƂ��Ɏn�܂����B�p��������A���ׂĂ̐l�ɕ����^�����B���l�ɁA�l�X�́A�����ɂ��邷�ׂĂ̐l�����݊����Ă��烏�C�����j�����Ȃ���A�H�����I�����B������̏d�v�ȉ߂��z���̋V���̈ꕔ�́A�n�����i�^���̎��сj���̂����Ƃł������B �@�L���X�g���҂̃O���[�v���傫���Ȃ�ɂ�A�H���Ƃ̊W�͂Ȃ��Ȃ��Ă������BCommunion�͂��ɂ́A�ЂƂ̓���ȏ@���V���Ƃ��Ă̂ݏj���邱�ƂɂȂ����B���̉ߒ��ł́A�Ⴂ�@���̃��[�_�[�́A�ނ炪�e����ł������_�����ւ̒����ȋV���W�J���������Ă����BCommunion�ƊW�������ʂ�F��́A���_�����̒莮���̗p���A�L���X�g���k�̃j�[�Y�ɉ������B�hAmen�h�����́A�|�ꂸ�ɂ��̂܂c�����B�V�i�S�[�O�̈���������A���@��a���̐����N�ǂ̎��H���n�܂����B���������N�ǂ́ACommunion�V���ɐ旧���āAfore-Mass(�~�T�O���j�̊j�S���`�������B����䂦�ɁA�̂��̃~�T�̃A�E�g���C�����`������n�߂��B �@fore-Mass(�~�T�O���j�͒ʏ�A�����̂R�̘N�ǂ��琬���Ă����B���������݂́A�V���A�Ȃ����A�g�k���╟�������d�������B���܂��܂ȓT��̓e�L�X�g�̑I���ɂ����Ĕ��ɈقȂ邪�A�Ō�̘N�ǂ͕���������̂��̂ŕs�ςł���A���̌�ɐ�����F�肪�����B���ꂼ��̍ŏ��̂Q�̘N�ǂ̌�ɂ́A���т�responsorial singing���]���B fore-Mass(�~�T�O���j�̋@�\�͓�d�ɂ������B�ЂƂ�Communion�ɑ���M�S��S�����邱�ƁA�����ЂƂ́A�L���X�g���̊�b���ł߂邱�ƁA�ł���B �������������catechumens�Ƃ��Ēm���Ă����B�����Ă��̌�Afore-Mass(�~�T�O���j�͎���Catechumens�̃~�T(����u��҂̃~�T)�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�F�肪�I�������Acatechumens�͏I���ƂȂ�A����Communion�ƂȂ�B �@Communion�̋V�����g�́A����ȋF����ďj��ꂽ�B���̋F��͎���ɁACanon�@of the Mass(�~�T�T���j�Ƃ��Ă�����s�ςȌ`�ƂȂ��Ĕ��B���Ă������B���̎n�߂͂������A�܂��ω��ɕx��ł���A����Preface�i����sursum corda�G����S���グ��)�ƌĂ����̂ƂȂ����B���ɏ�������AIsaiah���U�F�R����̂R�x��Sanctus�̏������������B��X�́A���_�����̈������̗�q�̂����ЂƂ̗v�f���l���Ă݂�B����́A�L���X�g�҂̃j�[�Y�ɏo�����č̗p����A�g�����ꂽ�e�L�X�g�ƂƂ��Ɉ����p����Ă��������̂ł���B ���̃`�����g��^���̋F��̔w��ɂ́ACommunion�ɂ�����p���ƂԂǂ�������̋]���ł���Ƃ����l�����������B����͐��`���̑O�ɋ]�����������邱�Ƃł������B�\���Ƃ��Ƃ͓�����ʕ��\ ��X�́A�M�ɂ��������̂��R���I�̍ŏ��������Ă����B�����Ă��̎��H�͏����̃~�T�̏d�v�ȗv�f�ɂȂ��Ă������Boffertory procession�ł���B�䂦�ɁA�~�T�̐�����k���̉ߒ��́A�����I�ɂ킽���đ����Ă������B�������������𗝉����邽�߂ɁA�����ɁA�ŏ��̂R�`�S���I�̊Ԃ̃~�T�̍\���̊O�ς�������B 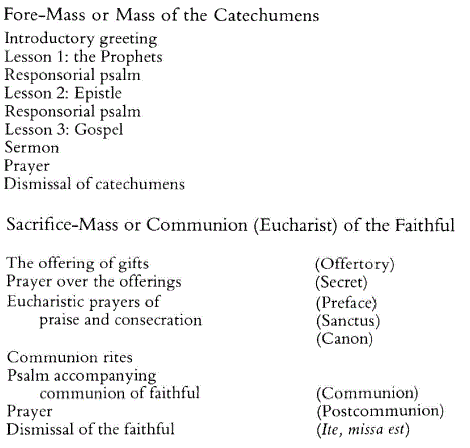 DEVELOPMENT OF THE MASS ITS COMPLETED FORM ABOUT A.D.1000 ����܂ŊT�ς����~�T�̍\���ɑ�������Ƃ��d�v�Ȓlj��́A��q�̍ŏ��̂Ƃ���ŋN�������B���[�}�ł́A�x���Ƃ�5���I�ɂ́A�~�T�͒��ڂ̘N�ǂ��n�܂����B����ɂ������A�����̖��W�ȍ��ڂ́A��X�����Ղ��邢�͖`���V���ƌ����镔���ɏW�߂�ꂽ�B���������V���́A���炩�ɁA���������I�ɔ��B���Ă������B�����炭�́A�V���́A�N�ǂ��������̓�����K�v�Ƃ����Ƃ����l���ɂ���ē��@�Â���ꂽ�B ���[�}�ł̓��ՋV���̌`���́A���ړI�ɂ́A�U�|�V���I�̂�����stational Mass�ƌĂ����̂ƒ��ڌ��т��Ă���B��j���̂��ꂼ��̓��ł́A���c�̓~�T���A���c�����v���Z�b�V�������s�����قȂ������[�}����ŏj�����B��O�͒ʏ�́A���[�}��7�̒n������A�V�̃v���Z�b�V�����ɂ���Ă����B�������A�����̉���̓��ɂ́A���ׂĂ͒����ɏW�܂�A��q���s��ꂽ����i�B���ɁA��҂̓��ł́A�j���������@eleison���̂���̂��ʏ�ł������B���c������ɓ�������ƁA����Ȃ�v���Z�b�V�������h��������������psalm��anthiphon�������Ȃ���������������Ă����B �@���[�}�T�炪�M���V����Ő��s���ꂽ������c����Ă���̂ł͂Ȃ����A�j����������5���I�̓�������A�����炭�̓~���m�o�R�ŁA�������ꂽ�B���݂̃A���u���V�E�X�T��ł́A�����g�̎����ł́A�A���́A�h���������������̂��Ƃ�3�x�̂j���������@eleison�ŏI������B�U���I�ł́A���[�}�T��̓~�T�̖`���V�����܂ށA���ӏ��Ŏg���Ă����A���������B�����͊��S�ł��������A���̑��̎����́Akyrie�̕W���`���ƂȂ���9��̌Ăт��������������Ă����B �@�j�����������l�A��h���̏��iGloria in excelsis Deo)�́A���Ƃ��Ƃ̓~�T�ɂ͊܂܂�Ă͂��Ȃ������B����́A������́A�����I�R��̖͕�Ƃ��ď����ꂽTe Deum�ƂƂ��ɁA�����Ȃ������c��̂ЂƂł������B �f�����������͎^���̉̂ł���A���ɏj���̋@��ɁA�i���ɂ���ďj��ꂽ�~�T�Ɋ܂܂�Ă����B��ɁA���̎g�p�͑��̏j�������ɂ��L����A���`�����q�t�ł��鎞�ɂ��s����悤�ɂȂ����B �@����́A�S�̂Ƃ��Ă̋F��ƁA�F��������čō����ɒB������subdivisions�̑o���ɂƂ��āA�T��I�V���ł͕��ʂ̂��Ƃł������B�䂦�ɂ����́A�`���̋V����Collect�h a gathering together,by the priest ,of the preceding petitions of the people�h�ŏI��邱�Ƃ��킩��̂ł���B �@���炽�ɔ��W�����`���̋V���ƑΏƓI�ɁA�N�ǂ͋I��1000�N�Ȍ�̐��I�ł́A�}���ȕω��͂قƂ�ǂȂ������B6���I�܂łɁA�N�ǂ̑����͂R����Q�ւƌ����Ă��邪�A�ӂ��̃`�����g�ɌÂ�����̍��Ղ��c����Ă���B�����̃`�����g�́A�Ԃɓ���`��Gradual�Ƃ`�������������� ���邢�͂s���������ŁA���݂ł́A�A�����Ď���s���Ă���B ���Ƃ��Ƃ̓C�[�X�^�[�̃`�����g�ł������A�������͎���Ɉ�N��ʂ��Ă�A���ʂȏj���Ɏg����悤�ɂȂ����B�����g�̂悤�ȉ���̋G�߂̂悤�ɁA�f�����������̂悤�ȉ����ȃe�L�X�g���s�K���Ȏ����ɂ����ẮA�s���������ɒu��������ꂽ�B9���I�̍ŏ��ɂ́A�A�������ɂ͂����Z�N�G���c�B�A�������悤�ɂȂ����B �@�N�ǂ̑��̕ω��́A�I���̋F���dismissal fourmulas�ł���B�O�~�T�������҂̃~�T�ƌĂꑱ�������A����dismissal formulas�́A��O����������ł��o���悤�ɂȂ��Ă���́A�����Ȃ��Ȃ����B���ɂ́A�b����������Fore-Mass�~�T�O���i���Ƃ̓T��j�̍Ō�̋F��Ɏ���đ������B �@���������F��̂����̎c��̂��ׂẮA�P��̌��tOremus�ł������B����́A�����ɂn�����������������������悤�ɂȂ����B�������A����˂ɂb�����������A�����d�v�ȏj���̂��߂ɂ̂ݓK���ł���Ƃ݂Ȃ��Ă������Ƃ́A���ڂ��ׂ��ł���B �@�F���V���I�s���i�n������������������Communion�ɔ����j�̌`������e�́A����ɕω����A�ЂƂ̍��ڂ������t������邱�ƂɂȂ����B���ꂪ�`���������@�c�����ł���B����́A���X�����ɂ���Ēǂ�ꂽ���E�҂����ɂ���āA������������炳�ꂽ�B�����āA�V���I�㔼�ɂ̓��[�}�~�T�̈�v�f�ƂȂ����B�`���������@�c�����́A���Ƃ��Ƃ̓p��������s�ׂ��Ă������A��Ȃ��p���̓������V����superfluous�ɂ���ƁA����͐��ʂ�Communion�̊Ԃ߂�悤�ɂȂ����B �@�Ō�Ɍ��ꂽ�ω��́A�~�T��Gloria�������Ȃ�����̂��Â�dismissal formula�@Ite,missa est�ɑ���Benedicamus Domino�ւ̑�ւł������B���炩�ɁA�I��1000�N�O�ɂ̓��[�}�ł͒m���Ă��Ȃ�����Benedicamus �莮�́A���Ƃ��Ƃ�Gallican�T��ɗR�����Ă����B�~�T�ɂ����邻�̎g�p�ɉ����āA����͐������ۂɂ����āA�W���I��dismissal formula�ƂȂ����B �P�P���I�̏����ɂ́A�~�T�̍\���́A�����܂Ŏc����Ă�����̂ƂȂ����B�ȉ��Ɏ������������\���̃A�E�g���C���ł́A�啶���͎��R�ȃ����f�B�ʼn̂��A�����recitation tones�ʼn̂�����̂ł���B���ׂĂłP�W���邱���������y���ڂ́A�������̃~�T�̊��S�ȃv���C���`�����g�Ɋ܂܂�Ă���B�iAMM No.5-22). 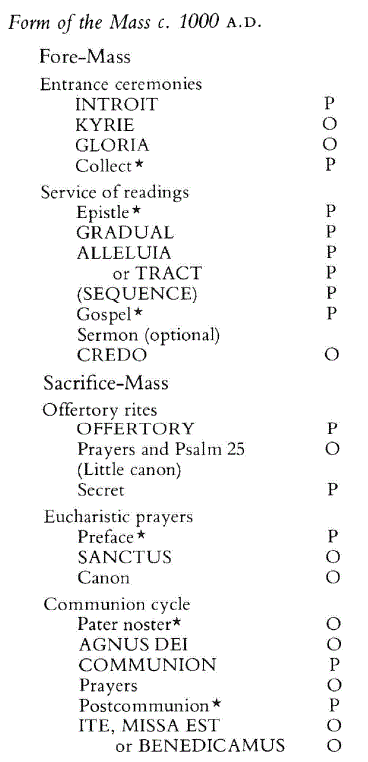 PROPER CHANTS OF THE MASS FORM AND FUCTION �~�T�̌ŗL���ɑ�����`�����g�́A���̃e�L�X�g������N�̎l�G�ɏ]���ē��X�ω�����B�啔���A�����̃`�����g�͂��邢�͏��Ȃ��Ƃ��e�L�X�g�́A�~�T�ɂ����Ă͂����Ƃ��Â������ł���B�����͂��ׂāApsalmody�̌Â����H����n�܂��Ă���B�������̃P�[�X�ł́A�����������H�͍��ł͔F���ł��Ȃ����B �~�T�����W����ɂ�A�ŗL���̃`�����g�̌`���́A�̕ω��ɑΉ����邽�߂ɁA�₦���ς���Ă������B���������i����������邽�߂ɁA��X�̓`�����g�������݂��Ă���`�ŗ������悤�Ƃ��邪�A��X�����Ƃ��ƊS�������Ă����̂́A�Ō�̌��ݓI�Ȍ`�Ȃ̂ł���B �@���Ƃ��Ƃ͌ŗL���̃`�����g��,salmody�̂Q�̊�b�I�^���ł���Aantiphonal��responsorial(�����^���́j���\���Ă����B���̌^���̑I���́A���L�ȃ`�����g�̋@�\�ɂ���Ă����BAntiphonal psalmody�́A�~�T�ɂ����Ă��܂��ȍs�������Bentrance��offertory��processions�ƐM��Communion�ł���BResponsorial psalmody(�������я�)�́A�������ۂɂ����ẮA���ۘN�ǂɏ]���B�^���ւ̕������ʁX�̉��y�̐����Y���Ă��邽�߂ɁA��X�͂��ꂼ��̌^���̃`�����g�������ɏ]���c�_�ł͂Ȃ��A���j�b�g�ƂƂ��čl�������B ANTHIPHONAL CHANTS OF THE PROPER �~�T�ɂ�����O��anthiphonal chants�ł���h�������������C�n�����������������CComunion�́A���y�̌ŗL���̐V�����������\������B�O�q�̂悤�ɁA���A���u���V�E�X�͓�������~���m��antiphonal singing�������炵�����A���cCelestine1���̓`���ɂȂ炢�A��������[�}�֓��������Bantiphonal channt���́A��ɐ��̑��ɂ���ĉ̂��邱�ƂɂȂ�A����䂦�A���̉��y�I�^�����A�~�T�̑��̃`�����g��������т��ĕۑ����Ă����B���̌`���͂������A�}���ɐ荏�܂ꂽ�B �@���Ƃ��ƁA�h�������������C�n�����������������CComunion�͂��ׂāA�ŏ�����Ō�܂ŁA�h�N�\���W�[��pre-verse���邢��antiphon���A���S�Ȃ鎍�т��琬�藧���Ă����Banthiphon��psalm verses�̌J��Ԃ�������Ă������ǂ����͋^��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���H���@�͏ꏊ����ꏊ�ւƕς�邩��ł���B �Ƃɂ����A���ׂĂ̂R��antiphonal chants�́A���ꂼ��قȂ��������̈قȂ��������̊����ɔ����悤�Ƀf�U�C������Ă����B�ł������̃��[�}�̗�q�K�菑�iordinals)�ł����A�������̍s�ׂ��I���ɋ߂Â��Ă���Ƃ��ɁA�i�������̑��ɑ��āA�h�N�\���W�[�ƍŌ�̃A���`�t�H�����X�L�b�v����悤�Ɏw�����Ă���̂ł���B �قȂ����V�����A���I��ǂ����Ƃ��ύX����A�Z���Ȃ�ɂ�A����ɔ����`�����g���܂��܂��܂��k������Ă������ƂɂȂ�B���ɂ́AOffertory��Communion�́Aantiphon�݂̂ƂȂ��Ă��܂��A�h�������������݂̂����̌��̌`���̎p���Ƃǂ߂�ɂ��������̂ł���B �h�m�s�q�n�h�s Introit�̎��т̒Z�k���́A�W�|�X���I�̊ԂɋN����A����ꏊ�ł͂�葁���N�����B�����̋���ɂƂ��āA���c�̓T��̉₩���ƂƂ��ɁAprocession�����Ƃ͕s�\�ł���A���߂���悤�Ȃ��Ƃł��Ȃ������B�����čŌ�ɁAIntroit�͍Ւd�̑����Ɏ������i�Ղ̂��Ƃɉ̂���悤�ɂȂ����B����䂦��Introit�́Aprocessional chant�ƌ������́A��q�ɑ���Ɨ��������y�I�v�������[�h�ƂȂ����B �����炭�͂����������R�̂��߂ɁAIntroit�́A���̂Q��antiphonal chants�����I���W�i���Ȍ`���ɋ߂��܂܂ł������B���т̍ŏ���verse�ƃh�N�\���W�[�͎c����A�I��蕔����antiphon�ɉ����Ă����B���ʂƂ��Ă̌`���́A�`�u�c�`�ƂȂ�B �n�e�e�d�q�s�n�q�x �n������������������procession�ɔ���antiphonal psalmody�́AIntroit�ɑ���̂Ƃقړ��������ɋN��������ƍl�����Ă���B�������A�nffertory�́A�����[���A���j�[�N�Ȕ��W�����Ă���BOffertory�́Aresponsorial psalmody(�������я�)�̌`�����̗p�����B���antiphonal chant�ł������B���������ω����Ȃ��N�����̂��͕s�������A�ŏ��̐��̏W�������O�ɂ��ꂪ����������ꂽ���Ƃ͖��炩�ł������B ����responsorial chants�̂悤�ɁAsolo verses�̉��y�I���k���͑����̌��������B���S�Ȏ��т̑���ɁAOffertories�́A�����̎ʖ{���ɂ����āA�P����S��verses�������A��҂�respond�i���X�|���T�j�̕����i�q���j�́A���ꂼ���verse�̂��ƂɌJ��Ԃ������Ă����B�R��verses�����S��Offertory�̌`���́A�qab V1 Rb V2 Rb V3 Rb�ƂȂ����B ���̂悤�Ɋg�����ꂽ���߂ɁA�`����Offertory procession�Ƃ��Ĉێ��ł��Ȃ��Ȃ�A�p�~�ɒǂ����܂ꂽ�B�������AOffertory verses�́A11���I�ɂȂ��ď��߂āA�����Ȃ��Ȃ����B�����͒�����ʂ��ė�O�I�P�[�X�ł���Ǝ咣�������Arespond�i���X�|���T�j�̂݁i���Ƃ��Ƃ�antiphon)�́A��̎���ɂ��c�����B �P�U���I�̓T����v�ɂ����ẮAOffertory�͎��҂̂��߂̃~�T�ɂ����ẮA�P��verse�͕ێ������B������Offertory��verse�̓A���u���V�E�X��q�X�p�j�b�N�̋V���̗����ɂ����đ��݂����B �c�O�Ȃ���AOffertory��veres�́A�����Ď��p�I�ɉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���̊��S�Ȍ`���ɂ����āAOffertories�́A�S�̂̃��p�[�g���[�̂����ŁA�����Ƃ������[���ʏ�ł͂Ȃ��`�����g�Ȃ̂ł���B�����炭�́A���̂����Ƃ������I�ȓ����i�O���S���A���`�����g�ɂ͌����ďo�Ă��Ȃ��j�́A���t�ƃt���[�Y�̕p�ɂȌJ��Ԃ��ł��낤�B�����ɂ͂P�|�V�̌J��Ԃ������邪�A���y�͓����ł�������قȂ����肵�Ă���B���������J��Ԃ��͓��ɍ����͎g���Ă��Ȃ�verses�̓����ł͂��邪�A�����͓��l�ɁAresponds�i���X�|���T�j�ɂ�������iLU p480,514)�B �@���l�̃����f�B�̌J��Ԃ��́AOffertory verses�̊g�債�������X�}�̑����ɂ������Baab�̌`���́A���ɍD�܂ꂽ���A���̂�蒷���`�����܂��A���т��яo�������B �@ �@���S��Offertoies�̂����Ƃ������I�Ȃ��Ƃ́AOffice Responsories,Graduals,Tracts�Ƃ������Â�responsorial chants�Ɍ���Ȃ����Ƃł���B�������������́AOffertoies�ɂ�����responsorial singing�̂�����̓��������łȂ��A�V�����n�����_�����ؖ����Ă���B�O���[�v�̓����������������ʂ��������f�B�̒莮����������ɁA��ȉƂ����͌X�̂��邢�͋��ʂ����|�p��i�ɑ���`�����g���\�����邽�߂̃e�L�X�g�A���y�̗����̌J��Ԃ����g���悤�ɂȂ��Ă���B�����炭����́AOffertory verses�����̈ʒu����藣�����Ƃ����l�I���邢�̓h���}�`�b�N�Ȑ����ł��낤�B �b�n�l�l�t�m�h�n�m Communion�͋^���Ȃ��A���̑��ɂ���ăA���e�B�t�H���Ƃ��ĉ̂���R�̃~�T�̃`�����g�iIntoroit�COffertory�CComunion)�̂����ŁA�����Ƃ��Â����̂ł���B���Ƃ��Ƃ́AIntroit�Ɠ����`���ł������Ǝv����B�����āA�����̃`�����g�͂��т��ѓ������т��g���Ă��邪�A�قȂ���antiphons�ł���B�������ACommunion�͂��̎��т��AIntroit��Offertory�ȏ�ɑ����A�������B������12���I�܂łɁA����͂قƂ�Ǖ��ՓI�ɁA�@��O���߂����ɐ��̔q��Communion������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁAantiphons�͌��炳��Ă������B �Ō�ɂ́ACommunion chant�́A�����̎�Ƃ������͌��тƂ݂Ȃ����悤�ɂȂ����B�����āAantiphon Communion���邢�͒P����Postcommunion�ƌĂ��悤�ɂȂ����i���݂�Postcommunion�́Areciting tone�ŏ�������Z���F��ł���BAMM,No.21�Q��)�B �@����͂����炭�A���̎���A�I���Ƃ��Ă̋@�\�ł͂Ȃ��ACommunion chants�̈�ʓI�Ȑ����Ƃ��Đ�������邾�낤�B�T���āA�����́A�Z���A��r�I�P���ȗl���ł���B�����͐������ۂ�antiphons�قǐ��k�ł͂Ȃ��B�������̓����X�}�ł��̒������g������Ă��邪�iPanis,quem ego dedero LU p1043).�B���������Â��̂����ЂƂ̒���́A������Communion antiphons�̐��@�Ƃ��āA�����̎����̊Ԃ̕s��v���A���@�̂����܂����ł���B RESPONSORIAL CHANTS OF THE MASS �O�o�̂悤�ɁA�����N�ǂ̌��responsorial psalmody(�������я�)�́A���_�����̃V�i�S�[�O�̎��H�ɂ܂ők��B�����̃L���X�g����ł́A�l�X�͒P���ɉ̂��A�\���X�g�ɂ���ĉ̂�ꂽ���т�verses �̊Ԃ̒Z��responds�i���X�|���T�j���������B schola cantorum�̓����ɔ����Aresponds�i���X�|���T�j��choral chants�ƂȂ�A�l�X���̂����Ƃ̂ł���P���ȃ����f�B�[���A�P�����ꂽ���̑��ɂ݂̂ӂ��킵���A��萸�I��chant�ɒu�������邱�Ƃɂ���āA�ŏI�I�Ƀ~�T�ł̉�O�̉̂�r�������菇�̍ŏ��̗�ƂȂ����B �|�p�I�l���́A�����ł��e���͂��������Ă��Ă����̂�������Ȃ��B��Augustine�̎���i354-430),�\���̉̂���͂��܂�ɑ����I�ȃ����f�B����邱�ƂŁA�����������݂ƂȂ��Ă������Aresponds�i���X�|���T�j�̑��ɂ䂾�˂邱�ƂŁA�\���ƍ�������̊Ԃ̗l���I�R���g���X�g���Ȃ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B �@���S�Ȏ��т́Aantiphona chantsl����̂��̂���������������A�~�T��responsorial chants�ł͌����Ȃ��Ȃ����B�������A�قȂ����A�����I�ȉ��y�I���R������B�t�����銈���ɂ���Đ���邱�ƂȂ��Aresponsorial psalmody(�������я�)�́A������x�̒����������Ă����B�ɂ�������炸�A���S�Ȏ��т́Aperformance�̂��Ƃ��Ƃ̂����ɂ����Ă͕s���ɒ����A���̑���\���̎�̂��߂̊g�債�������I�ȗl���̃`�����g�ɂ����ẮA���p�I�ł͂Ȃ������B�e�L�X�g��Z�����邱�ƂɊԈႢ�Ȃ��v�����������ЂƂ̗v�f�́AGradual��Alleluia�̊Ԃ̘N�ǂ̏����ł���B���ʂƂ��āA�Q�̃`�����g�́A�~�T�̊������傫�ȝR��I���o�̑O�ɏ��������̎��Ԃ��߂�悤�ɂȂ����B Gradual��Alleluia�́A�܂����������ă��[�}�~�T�̎���ł���A���̖L�����̒��ŁA�v���C���`�����g�~�T�͂��̂����Ƃ��̑�ȑs�傳�Ă���B GRADUAL ��P�N�ǂ̌�̃`�����g�́A���Ƃ��Ƃ�Responsory�iresponsorium)�ƌĂ�Ă����B��̎ʖ{�͂�����Aresponsorium graduale���邢�͒P����graduale�ƋL���Ă���B���̖����̎d���́A����responsorial chants�Ƃ̋�ʂɂ��Ȃ�B graduale�Ƃ����p��̋N���Ɋւ��ẮA�ӌ�������Ă��邪�A�����Ƃ�������Ă���l���́A���ꂪ�����d�̊K�i(gradus)�Ƀ\���X�g���ʒu���Ă������ƂɗR������Ƃ������̂ł���B �@ �@���̌��炳�ꂽ�`���ɂ����āAGradual��solo verse�ɂ���ď]����choral respond���琬���Ă���Bverse�̂��Ƃ�respond�̌J��Ԃ��́A13���I�܂ő��������A�܂��Ȃ��A�܂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���̍��ɂ́Aperformance�̕��@�͌�̎���Ƌ��ʂɂȂ��Ă����B�ʏ�̃\���X�g��intonation�̌�A���̑���respond�i���X�|���T�j�̑啔�����̂��B�ЂƂ肠�邢�͕����̃\���X�g��verse���I���̃t���[�Y�܂ʼn̂��A���̎����̑��́A����ۓI�ȏI�~���s���B�ߑ�̐��̏W�́Arespond�i���X�|���T�j"if the responsorial method is preferred"�̃I�v�V���i���ȌJ��Ԃ������Ă���B���������ꍇ�A�̂����verse�݂̂����������A���̌�ɐ��̑������ׂĂ�respond�i���X�|���T�j���̂��B �@ Gradual�́A���ׂẴ`�����g�̂����ŁA�����Ƃ����I�Ń����X�}�I�ł���B�����̉����ł����A20����30�̉����̃����X�}�͒������͂Ȃ��A�\���ɂƂ��Ă��Averses����胁���X�}�I�ł��邱�Ƃ́A�s�����悩�����B verses�͂܂��Aresponds�i���X�|���T�j�������̉���ɂ����āA��荂�������ɂ���X���ɂ������B�ɒ[�Ƀ����X�}�I���W�����Ă����Ƃ��āAGradual Clamaverunt justi(LU p1170)������B �@Gradual�̋����[���_�͂���centonization �e�N�j�b�N�ł���B����́A�������ۂ�responsorie�ɓ����I�ł���BGradual�ł͂������Acentonization�́A����т��Ďg���Ă���A���炩��responsories���������B�W���I�ȃt���[�Y�̐���莮�́A�^����ꂽ���@�ɂ�����Graduals�̂��߂̃����f�B�f�ނ���������B�����̒莮�́A������I���t���[�Y�݂̂Ƃ��Ďg����B���̑��̒莮�́A���R�Ɍ���������g�ݍ��킳�ꂽ�肵�������A���Ƃ��č�p����B �������̐��@�ɂ����ẮAcentonization��verses�ɂ����āA��{�I�Ɍ����Bresponds�i���X�|���T�j�ƂƂ��ɂ�莩�R�ł��邪�A���ɁA�W���I�ȏI�~�莮�����g���B��R�C�S�C�V�C�W���@�ɂ����Ă͂������Aresponds�i���X�|���T�j��verses�̑o���͕W���I�ȃt���[�Y���g�����ƂɂȂ�B����͂Ƃ��ǂ��A���ꂼ��̕���ɂ����āA�������������`�����g���Y�����邽�߂ɍČ������B ���Ƃ��ABenedicite Dominum LU p1654)�ɂ����āArespond�i���X�|���T�j���̍ŏ��́hejus"�̌�̃����X�}�́Averse���̌��t�hDominum"�̌�ɁA���̂܂܂ōČ������B����ɁA�ӂ��̕���̍Ō�̃����X�}�͓���ł���B 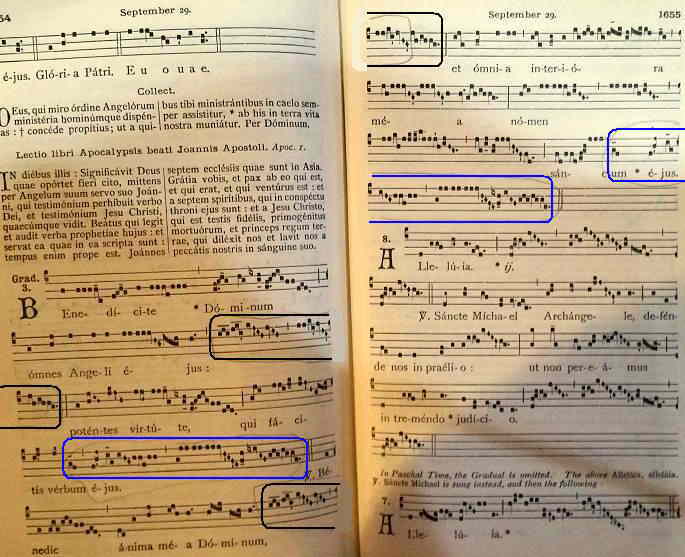 �@�g��A�ϑt�A���R�ȍ�Ȃɂ��p�b�Z�[�W�̑g�ݍ��킹�ɂ�����W���I�t���[�Y�̎g�p�́A���ꂼ���Gradual���A���̃O���[�v�̑��̃����o�[�ւ̋����ގ�����S���X�̃`�����g�ɂ���B�O�q�̂悤�ɁA����������Ȃ̕��@�́A�{���I�ɓ��m�I�Ȃ��̂ł���A�����炭�̓��_�����̉��y���H����̂�ꂽ���̂ł������B���ꂪGraduals�ɂ������т����؋��ł��邱�Ƃ́AOffertories��Acentonization�����m�Ɍ����Ă���A�������ł�������ׂ�N���X�Ƃ��Ă����̌Â����ؖ�����B �`�k�k�d�k�t�h�` Alleluia�́A�w�u���C���Hallelu Jah(���[�E�F���ق߂܂�j�̃��e����Â�ł���B�^���̕\���Ƃ��āA����͂��ׂăL���X�g���T��ɂ����ẮA���܂��܂ȕψق��o�Ȃ�������݂��A�g���Ă����B�����炭��Alleluia�̎��т́A���_�����̉߂��z���Ƃ̊֘A�̂��߂ɁA�����T��́APaschal Time�i�C�[�X�^�[����y���e�R�X�e�܂Łj�ɂ�����Alleluia�̓���Ȏg�p�������B �����������R�ɂ��A�������ۂ�~�T�̌ŗL���ɂ����āA���t�͂��ꂼ��̃`�����g�̏I���ɉ�������B����ɁA�C�[�X�^�[�̓y�j������y���e�R�X�e�܂ŁAAlleluia��Gradual�ɒu�������A�~�T�͂��̎��ɂ�Episle��Gospel�iLU p827�Q�Ɓj�̊ԂɁA�Q��Alleluia�������ƂɂȂ�B ���̑��̗��R�ŁAAlleluia�̎g�p�͂��}���I�ł���A�������A����̓��X����g�̓��X�������A��N��ʂ��āA�~�T�̌ŗL���̓Ɨ������`�����g�Ƃ��ċ@�\���Ă���B �@Alleluia�́A�����̂���悤�ɁAGradual�����͂�����Ƃ���responsorial(�����^���́j�ł���B�̎肪Alleluia���̂�����A���̑���������J��Ԃ��A�����L���ꂽ�����X�}�ł���jubilus�ƂƂ��ɑ����Ă���B�̎�͂��ꂩ��Averse�̑啔�����̂��A���̑��ƂƂ��ɁA�Ō�̃t���[�Y���̂��B�ēx�A�̎肪Alleluia���̂����Arespond�i���X�|���T�j���I������ɓ�����A���̑���jubilus�݂̂��̂��B Gradual�ɂ����Ă̂悤�ɁAAlleluia�̍��������͒�������ɂ͂����Ȃ��ȂĂ����B�Z�N�G���c�B�A��Alleluia�̂��Ƃɗ���悤�ɂȂ��Ă��iLU�@p780�j�܂��A����͒ʏ�̉ߒ��ł������B �������A�J��Ԃ��͂܂��A���̎��ɂ��Ȃ��Ȃ�X���ɂ������B���Ƃɓ���ȑ��������Ȃ����ɂ����ẮB���݁A��ȗ�O�ƂƂ��ɁALU�́AAlleluia�ɂ��ẴA�E�g���C���Ƃ��Ă�responsorial performance���L�q���Ă���B ���P�Q�X �@Alleluia�̗��j�I���W�ɂ��āAverses�̂��߂̃e�L�X�g�̑I���⓯�������f�B�ɑ���قȂ����e�L�X�g�̗̍p�ȂǑ����������Ă����B�Ƃ�킯�Ajubili�ɂ����鉹�y�`����Alleluia�̊Ԃ̃����f�B�̊W�A�����Ă���verse�͎�ɋ����[���A�ڍׂȌ����̉��l������B TRACT Alleluia��Tract�ɒu������邩�ǂ����i���邢�͂��̋t�j�́A�T��w�҂����Ɏc����Ă���^��ł���B�T��~�T�{���o������܂łɁAAlleluia�͖��炩�ɁA�����̋G�ߓ��l�A�����g����g�O�̋G�߂ɂ͕s�K���ł���ƍl�����Ă����B���̎��ɂ́AAlleluia�ɑ����āATract��Gradual�̂��Ƃɑ������B����́A�����̒��ߎ҂����߂����ƂƂ����킯�ł͂Ȃ����ATract�́A���ꎩ�g�A�K�R�I�ɁA�����I�A�ߜƓI�ł������B���Ƃ��A�l�{�߂̎���̂��߂�Tract�́A����100�т̍ŏ��̂R��verse���琬���Ă���B���y�j���Ɛ���~�Փ��O��ɂ����āA�N�ǂ̊Ԃ̂Q�̃`�����g�́ATract�ɏ]��ꂽAlleluia�ł���iLU�@p759-760,860,776II)�B �@Tract�̐��s�Ƃ��̖��O�̗R���̂��Ƃ��Ƃ̓��ɂ��Ă̈ӌ��͈قȂ�B�����̒��ߎ҂́Atractus�Ƃ������t�ɂ����āA�̂��ɂ����Ē��������X�^�C���A���邢�͌J��Ԃ��Ƃ��ċ�������āArespond�i���X�|���T�j��antiphon�Ȃ��̎����I�p�t�H�[�}���X�Ɍ��y���Ă���B ����͊m���ɁA��̃p�t�H�[�}���X�̂ɂ����Ă̂��Ƃł���A���̌��ʁA����̊w�҂����́ATracts�����[�}�T��ɂ�����H�Ȓ��ړI���я��̗�Ƃ��Ĉ��p���Ă���B�������A��������Tracts�͂��Ƃ��Ɖ����I�ɉ̂��A�����̎ʖ{�ł́Aresponsorium ���邢��responsorium graduale�Ƃ��Ĉ����Ă����B����䂦�ɁATracts�́A������������ɂȂ��Ȃ����������я��̏����i�K��\���A�ƌ����邾�낤�B���݂̃`�����g�u�b�N�́Averses���Q�̐��̑��A���邢�͉̎�Ɛ��̑��ɂ���Č��݂ɉ̂���悤�Ɏw�����邱�Ƃɂ��A�����������Ă���B �@���������Ō�̌`���ɂ����āATracts�́A�Q�`�P�S�ɂ킽�鎍��verses�̘A�����琬��B�߂����ɂ͂Ȃ����A���ёS�����g���邱�Ƃ�����B��������Tract�ɂ����ẮA���ׂĂ�verses�͓������т��痈�Ă���B�`����verse���w�肳��Ă��Ȃ����Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���Bverses�̃V���{�� �ȉ��Ɉ��p���ꂽ�R�̗�́A�����j���̂��߂�Tract�Ɛ����j���̂Q��Tracts�ł���B�iLU�@p614,695,697)�B�����͖��炩�ɁA�Z�k���ꂽ��������verse��Responsories�ł��邪�A�����Ƃ��Ẵp�t�H�[�}���X�̌J��Ԃ��������̂ċ����Ă��܂��Ă���B��������verses��Tracts�́A�ł������`�����g�ɑ�����B���Ƃ������g�̍ŏ��̎���ł́ATract�͎��тX�P�т̑S�Ăł��邪�ALU��p533-536�ɓn��A3�y�[�W�����߂Ă���B �@Tracts�𑼂̃^�C�v�̃`�����g�����ʂ���ЂƂ̓����́A���ꂪ��Q�A��W�̂Q�̐��@�Ɍ������Ƃ����_�ɂ���B�����������@�I�����̊ԂŁAcentonization�̃e�N�j�b�N���g���āA���̂ǂ������n���I�ȓK�p���s���Ă���̂ł���B �A�y���́A��8���@��Tracts��60��verses�ɑ��ẮA19�̃����f�B�莮���A��Q���@��Tracts��80��verses�ɑ��ẮA�Q�Q�̂��ꂪ����A�ƌv�Z���Ă���B���������莮�ւ̌Ŏ��͔��Ɍ����ŁA���ꂼ���Tract�́A�قƂ�ǑS�̓I�ɁA�W���I�t���[�Y�̋K���������A���ƂȂ��Ă���B �@�����f�B�Ƃ��āATracts�͂ނ���A�����I�ȌX���ɂ���B�`�����g�̂������͂����炭�͂����Ƃ��Â��Apsalm tone�̖��c��recitative�I�ȃp�b�Z�[�W�������Ďn�܂��Ă��邪�A�قƂ�Ǖs�ςŁA�����t���[�Y�͐��I�ȃ����X�}�I�ȏI�~�ƂȂ��Ă���B ���̗l���͂����炭�A���y�j���̂T��Tracts�ɂ͂�����ƌ��Ď���BTracts�̑命���́A�ɒ[�ȃV���r�b�N�ɂ������X�}�e�B�b�N�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ����A���̗���̓X���[�Y�ŁA�������Ȃ�̒����̃����X�}�ƂȂ�i�����j�B LU�@p533�@Tract �Ԑ��������X�}���� �܂��������炩�Ȃ��ƂɁA���������X�^�C���͂��Ƃ��Ƃ̓\���\���O�ɒ[���Ă����B����䂦�ATracts�́A����Graduals,Offertories,Alleluias�����O�Ƀ~�T�Ŏg��ꂽ�̂Ƃ��Ă̋@�\���������Ă���̂ł���B ��Tract��⁄�@�O���E�g�@���m���y�j��@�����K�O�A�ˌ��K������ �@��W���@��Tract�́A��Q���@�����Z���A��]�Ɗm�M�̌��t�ł���A��Q���@�Ƃ͑ΏۓI�ł���B����́A��Q���@���Z���n�ł���A��W���@�������n�ł��邱�ƂƊW������B �ATract�ɂ͋���̌Â����y���c����Ă��邱�Ƃ���A�W�̋�����@�����B���ȑO�ɂ́A���@�͂Q�ł���A����͒Z���ƒ����̐��i�������Ă����̂ł͂Ȃ����B ORDINARY OF THE MASS �ʏ핶�́A�ŗL�������|���t�H�j�[���y�ݒ肪�Ȃ���Ă������A�v���C���`�����g�̃��p�[�g���[�ɂ����ẮA�͑S���قȂ�B���ɁA�N�ǂ̊Ԃ̉����I�`�����g�i���K���ƃA���������j�ɂ����ẮA��������̊S��������Ă����B �@�ʏ핶�̉��y�����̂��ׂẮA���Ƃ��Ƃ́A��O�̉̂Ɍ������Ă����B�e�����͐����I�ɓn��A���܂��܂Ȏ���ɓ�������Ă����B�N���h�͌����ɂ́A1014�N�Ƀ��[�}�ɓ������ꂽ�B���������e�L�X�g���A���A��O����q�t��P�����ꂽ���̑��ɂ���ĉ̂���悤�ɂȂ����̂��́A�悭�킩��Ȃ��B�����������Ƃ��A�قȂ����ꏊ�ňقȂ�������ɋN���������Ƃł��������Ƃ͋^���Ȃ��B�������̃`�����g�ɂƂ��āA����͑����Ă��W���I�ł���A�傫�ȋ����C���@�ł̏o�����������ł��낤�B10���I����A���������ꏊ����A�ʏ핶�̃e�L�X�g�̐V���������f�B�̏؋����������ʖ{�������Ă���B �@��ȉƂ����������e�L�X�g�ɐV���������f�B�������@������Ƃ́A�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�ŗL���̃`�����g�͂�������Ɗm�����Ă���A�V�����j���̑n���ƂƂ��ɁA�V�����t�����Ȃ��ꂽ�B���������@��͋H�ł͂Ȃ��������A���������ŗL���̊��Ƃ́A�P�P�A�P�Q���I�̑n�������̋}���ɑ���K���ȏo���������炦���B����ɁA�ŗL���̃`�����g�́A�A���������̗�O�͂����Ă��A���̍��܂łɂ́A���Ɍ��łɂ��̓`���`�����ł߂Ă����B��ȉƂ����͂����A�V�����j���̃e�L�X�g�ɑ��āA�Â������f�B�����Ă����B �ʏ핶�̃`�����g�����̑��̏��L���ƂȂ������A���̂悤�ȗ}������ȉƂ����邱�Ƃ͂Ȃ������B����䂦�A��ȉƂ����͌��݂̐��̏W�ɑ��݂��鑽���̐V���������f�B���������B KYRIE�@ELEISON Kyrie�ɑ���Q�Q�̃����f�B�̂����A�R�O������LU�ɂ͎��^����Ă���B�ɂ�������炸�A���̐��̓��p�[�g���[�̏d�v�ȗl�����\���Ă���ƌ�����B ���ꂼ���3��̌Ăт�����3�x�Â̂��A�S���łX�Z�N�V�����ƂȂ�B���������e�L�X�g�̃A�����W�͖��炩�ɁA��ȉƂ����ɁA��Ȃ̂��߂̗��z�I�ȃt���[�����[�N�����B �ł��P���A�����炩�ɌÂ��`�́A�ŏ��̂W��̌Ăт����������f�B�Ƃ��A�Ō�̂X�Ԗڂ�ω���������A�قȂ��������f�B�Ƃ��邱�Ƃł���B���̌`���̗B��̗�́A���҂̂��߂̃~�T��Kyrie�ł���iLU�@p1807�j�B�Ō��"Kyrie eleison"�́A�V���������f�B�̃A�E�g���C���ł͂��܂邪�A�ق��̂W�̌Ăт����̍ŏI��ŏI����Ă���B�`���͂���䂦�Aaaa aaa aaa'�ƂȂ�B�Ō�̃����f�B��a�̕ό`�����J�n�A�Ƃ������ƂɂȂ�B ���̌`���̌J��Ԃ��̐����́A��O���̂����Ƃ��ʏ�ł��邱�Ƃ��������Ă���B�����Ă��P���ȃ����f�B�͂����炭�A�����ړI�Ȃ̂ł��낤�B���̌`����Kyrie�̓����́A��T�|�P�Ŏ�����Ă���B�ނ���ӊO�Ȃ��̏I�~�̃����f�B�́A�����Ƃ��Â�Gloria�ƃ����N���Ă���B�i�����̊��s�ł́A"Kyrie�@elsison"�͒ʏ�́A�U�V���u���ɐ�l�߂�ꂽ�B�G�{���Ȃ�V�V���u���ɂȂ�j �GGloria��15�Ԗڂ̂��́iLU�@p57)�����AKyrie��LU�Ŏ��^����Ă��Ȃ� �@�T���āA������̂�萸�I�ȃ����f�B�́A��蕡�G�ȉ��y�`���������Ă���B���ׂĂ�Kyrie����L�̂悤�ȒP���Ȍ`���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ʏ�͈ȉ��̂R�p�^�[���ɕ�������B LU������ƁA���������p�^�[�������͂��P�����������āA�s�m���Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A���y�\���̕\���̃~�X���[�h�������댯������B �@Kyrie�̃����f�B�ɂ́A�W���I�`���p�^�[���ł͎�����Ȃ��A�ӂ��̍\������������B��P�́A����荂�p�x�Ȃ��̂́A���ʂ̏I�~��ɂ����Kyrie�̂��ׂẴ����f�B�����ꂳ��Ă��邱�Ƃł���B Kyrie�V�iLU�@p22�j�Ɏ�����Ă���悤�ɁA��͒Z���B���邢�́AKyrie�U�iLUp19�j�ł́A����͋ɂ߂Ē����Ȃ��Ă���B��蕡�G�Ȍ`���Ƃ��ẮAKyrie�\�iLUp40�j�̂悤�ɁA�Q�̏I�~�傪���݂ɏo�����邱�Ƃ�����B ����l�̎��ɂ͊��������Ȃ����A�����������y���Y���̎�ނ́A��������ɂ͂����Ώo������B���̌�����Kyries�ɂ�����original�Ȃ̂��ǂ����͂킩��Ȃ����A����͘A���̉����̌J��Ԃ��I�����ɗR�����Ă���̂ł��낤�B�e�L�X�g�͂��ꎩ�g�A�heleison�h�������hKyrie�h��hChriste�h�̌��t�ƂƂ��ɁA���ʂ̏I�~�ւ̑ΏƓI�܂��͕ω��ɕx�ޖ`����̎g�p���������Ă���B �@��Q�̍\���I�����́A�Ō�̌Ăт����̓T�^�I�Ȑ��I���Ɋւ��邱�Ƃł���B�����A�����������I���́AKyrie�̃����f�B�iKyrie�U�@LUp19�j�ɐ旧�J��Ԃ������ɂ���ĂȂ���Ă���B�����������A�㔼�̃����f�B��Christe��Kyrie�̗�����̗v�f�̑g�ݍ��킹�ƂȂ��Ă���i�����j�B���������ߒ��͂����炭�A�L���G���A�t�����N�����i�L���G�̃����f�B�͂����ő������ꂽ�j�ň�ʓI�ł������O�ʈ�̂̃V���{���Ƃ���_�w�I���߂ɗR�����Ă���B�㔼�����̊��Ăɂ�����L���G�ƃN���X�e�̓��ꐫ�́A�m���ɂ��̂悤�ȉ��߂ɍ��v����Ƃ����悤�B�_�w�I�l�@�͂��Ă����A���y�I�ϓ_����̌��ʂ̖�������B GLORIA ���̍ŏ��̍s���A�N���X�}�X�̖�̓V�g�̉̂ł��邱�Ƃ���AGloria��hymnus angelicus(AMM, No.7)�Ƃ��Ēm���Ă���i����͂܂��A��h������Ƃ��Ă�Ă���B���h�������Gloria Patri�Ŏn�܂�j�B �e�L�X�g�̂��̑��̕����́A���Ȃ�_�ƃL���X�g��J�ߏ̂��A����݂𐿂��Z�傩��\������Ă���B���s��́A�`����hGloria inexcelsis Deo"�͏�Ɏi�����A��ɂ͏j�����ꂽ�i�Ղɂ���ĉ̂�ꂽ�B���̌�̌��͉�O�⏕�Ղ̍����A���邢�͌P�����ꂽ���̑��ɂ���ĉ̂�ꂽ�B��ɁA��O�̉̂��Ȃ��Ȃ�ƁA���̑����ʏ�A�A�����I��Gloria�𐋍s�����B �@Kyrie�ƈقȂ�AGloria�͂��ׂẴ~�T�ł̍\�����ł͂Ȃ��A�~�Ր߁i�ҍ~�߁j�ƃ����g�₻�̑��̉������A�T���̒ʏ핶�ł͏ȗ����ꂽ�B���������g�p��̐�����e�L�X�g�̐����ɂ���āA�����炭��Gloria�̐��͔�r�I���Ȃ��̂ł���B�T�U��Gloria�̃����f�B�݂̂��m���A����́AKyrie�̂Q�Q�U�Ɣ�r����Ɣ��ɏ��Ȃ��B���������������炩�AGloria�̃e�L�X�g���͎̂��R�ȉ��y�\���̉\���͌����Ă���B �@�����炭�́A�����Ƃ��Â��A�P���Ȃ̂�Gloria�]�X�iLU p57�j�ł���B�S�̂̃e�L�X�g�́AAmen�������A������psalm tone�ł���A�~�A�\�A�V�A�������g���Ă��Ȃ��i����reciting tone)�B���������P�����ɑ��āAGloria�Tad libitum(LU,p86)�́A�����Ƃ��ΏƓI�ȏɂ���B������12�x�ɂ���сA�����f�B�͑�_�ɍL��������A�ˑR������ς���������Ă���B�Ȃ��ł������[���̂́A���ׂĂ̋�͂ЂƂ������A�\���������ŏI�~���Ă��邱�Ƃ��琶���Ă���A���\���̋��͂Ȋ���ł���B �@Gloria�̃e�L�X�g�\���́A�����f�B�ݒ�Ɏ��R�Ȍ��E���ۂ��Ă���B�e�L�X�g�ɉ��y�p�^�[�����`������J��Ԃ��������Ȃ��̂ŁA��ȉƂ����͈�ʂɁA���ꂼ��قȂ郁���f�B��a���ł������ƂɂȂ�B�ăe�L�X�g�ɂ����āA�������̃Z�N�V�����ŕ��s�I�ȋ傪����A����͓����悤�ȉ��y�f�ނ̎g�p���������ƂɂȂ�B ������O�I�ɁAGloria�̃����f�B�́A�J��Ԃ��I�\���������A����̓e�L�X�g�̌`���Ƃ͖��W�ł���B �����炭�́A���̂����Ƃ��D���Gloria�[�ł���B�����ł́Aa,b,c,�̂R�̊�{�傪�����f�B�̑S�̂�substance���������Ă���B�i��T�|�Q�j�B�قȂ������t�ɓK�����邽�߂ɕω����Ȃ���A�����̋�͏�ɓ��������ŏo������B�������Ȃ���A�P��̋�͎��Ƃ��āA���̋傪�����O�ɌJ��Ԃ����B�hDeus Pater omniptens"��A��薾�炩�ɂ́hsucipe deprecationem nostram."�̂悤�ȂƂ���ł́A�Q���邢�͂��ׂĂ̂R�̋�͗���Ă������ƂɂȂ�B Gloria�[��15���I�̋N���ł͂��邪�A�����e�N�j�b�N�͂��ȒP�ȍ\���ł���Gloria�X�ł��g���Ă���B�����12���I�ɍ��ꂽ���̂ł���B�o����Glorias�ł́A���ꂼ��̃����f�B��͈�ʓI�Ƀe�L�X�g�̒Z����ɑ�������B�������A�S�̂̃����f�B�́A�R�̋�̂����ꂩ�ɂ����Ďn�܂�A�傫�ȕ��@�P�ʂƂ͖��W�ɁA�J��Ԃ����Ȃ����B���������P��̌J��Ԃ������f�B�̎g�p�́A���S�Ƀe�L�X�g�̍\���p�^�[���Ƃ͓Ɨ����Ă���A�A��������Ȃ��s����20���I�̃e�N�j�b�N�����l�����Ă���B p�P�R�U CREDO �j�P�[�A����c��Credo�̌`���������܂�����A���̍ŏ��̓T��I�g�p�́A�g�k�M�o�ibaptismal creed)�Ƃ��Ăł���B�Ȍ�A�P���`Credo�������`�Ɏ���đ������B�U���I�ɁACredo�͓����̓T���X�y�C���ɂ������悤�ɂȂ����B2���I�x��āA�A�C�������h��C���O�����h��ʂ��āA�t�����N�����̗̈�ɂ��o�������B10���I�ɂȂ��ď��߂āACredo�́A�k���ł���ʓI�Ɏg����悤�ɂȂ�A1014�N�ɂ�����A���[�}����Ŏ������悤�ɂȂ����B ���̂悤�Ȓx���̗p�́A�^���Ȃ��A�����ɂ�����Credo�̐ݒ肪�Ђƈ���̃����f�B�������܂Ȃ������ЂƂ̗v�f�ł������B�����ЂƂ̗v�f�́A��O�S�̂ɂ��Credo�̐M�����Ƃ��Ă̋@�\�ł���B�����̏ꏊ�ŁA�ق��̒ʏ핶�̃`�����g�����̑��Ɏ���đ���ꂽ���Ƃ͂邩�ɒ����ACredo�͉̂��A���邢�͒P�ɏ�����ꂽ�B���̃e�L�X�g�̒�����Gloria���������A�V����Credo�̃����f�B�̍�Ȃւ̒�R�ƂȂ��Ă����B �����Ƃ��d�v�ȗv�f�͒����ɂ����Ă�����ł���A��X��Credo�T�Ƃ��Ēm���Ă��郁���f�B�����͐^��Credo�ł���A�Ƃ������Ƃ��M�����悤�Ƃ��Ă���B�m���ɁA���̒ʏ핶�̃e�L�X�g�͂���قǂЂƂ̃����f�B�ɌŎ����Ă��Ȃ������B�����̎ʖ{��LU�̐^��tone�݂̂��ڂ��Ă���B �@Gloria�̂悤�ɁA�j�����ꂽ�i�Ղ�Credo�̍ŏ��̋�݂̂��̂��A��O��̑��͎���Patrem omniptntem����̂������B���̂悤�Ɉ�����̂͒ʏ핶�̃`�����g�ł�Gloria��Credo�݂̂ł���A���̏W�ł͂Ƃ��Ɍ��@���A������l�b�T���X�̃|���t�H�j�[�~�T�ł͕s�ςł��邱�Ƃ��������B ���̑��ɂ��Credo�̌����I�ȉ̂����́A�Ƃ��ɒ����ɂ͂܂���Ђ��߂��邱�ƂɂȂ����B�Ȃ��Ȃ�l�X�́A�S�̂̃e�L�X�g�������邱�Ƃ����҂��Ă�������ł���B�����������Ƃ͌��݂ł͋��e����Ă��邪�A���̑��͂��ׂāA�e�L�X�g��A���I�ɉ̂���������Ȃ��B�i�G�����w�@�����k��q�����̑��ł́A���a�T�O�N��ɂ͌����I�ȉ̂��������Ă����j�B �@Credo�T�̃����f�B�́A11���I�̎ʖ{�ɏo�����邪�A����͂����ƌÂ��A�M���V����N���ł���B���ׂĂ̓V���r�b�N�ł���A�����̈قȂ����z�u�ŌJ��Ԃ���鐔���Ȃ������f�B�莮��萬���Ă���B �`����Credo in unum Deum�̓��@�iformula)�́A���̏ꏊ�ł͕������ꂽ���S�ȃt���[�Y�Ƃ��Ă͎g���Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��P�O��͏o������B��T�|�R�Ŏ�����Ă���悤�ɁA����x�ω����邪�AEt resurrexit tertia die�̋�ɐڂ��āAoriginal�Ȍ`�ɖ߂�B���̗�ł́A�e�L�X�g�̍s�̐����́A���̓��@�iformula)�����炽�Ɍ���鏇���������Ă���B �����̓��@�̂��ׂẮA�ЂƂ������āA�~�t�@�\���邢�̓��~�t�@�\�Ƃ����C���g�[���̂悤�ȏ㏸���^�ɂ���ē�����Ă���B������"Et iterum venturus est cum gloria"�Ŏn�܂�Credono�㔼�ɂ����āA�\�����recitations���Ă���B �����������я��̓������`�����@�̕ω��ł͍���ȏꍇ�͒ʏ�A�\������ŏI�~������Z����Ŏn�܂�B �@Credo�T�ɂ����Ď��ɏd�v�ȓ��@�́A�ŏ��ɁA�`����ł���hPatrem omnipotentem"�Ɍ�����B��ɕό`�����o����邪�A���̓��@�͏�Ƀ��|�V��|���Ŏn�܂�A�t�@�|�\�ŏI�~����B���̓��@�ɂ́A��T�|�R�Ń��X�g�����ꂽ�`�����@��10��̏o���̂����A�V���]�����ƂɂȂ�B�����10��̏o���́A�O�ʈ�̂�L���X�g��incarnation,crucifixion,resurrection�̃e�L�X�g�̋�ƈ�v���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B �@Credo�X��Y��LU�ɂ��邻�̑��̗B��̒�������̃����f�B�ł���BCredo�X�̓��@�́A�^����tone�̂���Ƃ悭���Ă���B�����āA���я��Irecitative����̗R���ł��邱�Ƃ͂���ɖ����ł���B�����R���͂���ɁACredo�Y�ɂ����Ă����炩�ł���B�����̃����f�B�́A���y�I�t���[�Y�̌���ꂽ�����g�p���Ă���B��ɁACredo�Y�́A���̑啔���̕ω��̂Ȃ��J��Ԃ��́A�����A�P���ł�������B�����f�B���@�̑n���I���邢�͏_��ȑ���ɂƂ��āACredo�T�͖��炩�ɁA�D��I�n�ʂ�ۂ��A����͒����ɂ����āA����ɍ����ł��A�n�ʂ�ۂ��Ă���̂ł���B SANCTUS Sactus�̃e�L�X�g�́A����ƐV���̗��҂��������������̂ł���B�C�U�����i�U�G�R�j����A�V�g�̋��т�����Ă���B���[�}�T��́A�������������A�C�G�X���G���T�����ɓ��ꂵ�����̈��A�Ƃ��Ă̋��т�����ɕt���������B �@������L���X�g���T��ɂ����āASanctus�͍ŏ�����A���ׂĂ̐l�X�̂��߂̕s�ϓI�ȉ̂ł������B����́A���[�}�T��ɂ����ẮAPrefaces(�����j�ɂ���Ė��炩�ł���B����́A�l�X���h���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁh�ƌ����Ȃ���V�g�ɂȂ����Ă�����Sanctus�����̂ł���B�i�GPrafaces�́Asursum corda(�����ƂƂ��ɂ��܂����Ƃ��j����Sanctus�܂ł̈�A�̗�����w���j�B 7���I����W���I�̃��[�}�ł́A���Ȃ��Ƃ����c�~�T�̂��߂ɁA���Ձiassisting clergy)�̍�����Sanctus���p���ł������A�������̂Ƃ���ł́A��O�̃p�t�H�[�}���X��12���I�܂ő����Ă����B��ʓI�ɂ������Ȃ���A�i��O����j���Ղւ̈ڍs�₻�̌�̐��̑��ւ̈ڍs�́A�P�O���I����12���I�̊Ԃɍs��ꂽ�B���������ɂ̓~�T�ʏ핶�̂��߂̑����̐V���������f�B���Y������Ă����B���̌�̂Q�`�R���I�ł́A�Q�R�O����Sanctus���o���������ALU�ɍ̘^����Ă���̂́A�킸���ɂQ�P�����ł���B����قǏ����ł͂����Ă��A�`���̑��l���́ASanctus���~�T�ʏ핶�̂����ł����Ƃ������[���`�����g�Ƃ��Ă���B �@Sanctus�]�X�V�͖��炩�ɁA�T����Preface tone����̘A���Ƃ��č���Ă���B�iLU p109) �Q��́hSanctus�h�̂��ƂɁA�V�����recitation�̂S�̋傪����B�I�~�̓V���ƃ\�������݂ɗ���B�Ō��Hosanna�̂��߂̃����f�B��recitation�ł͂Ȃ����AAmen���܂ށA�T����tone�̍ŏ��̋�̒Z�k�ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă���B����Sanctus�̂��߂�13���I��LU�̕\���́A���ȑO�̎�����reciting tone�Ƃ��ă����������Ă������A�m���ɁA�ԈႢ�ł���B���݂̔ł́A�������A���̃����f�B�̌����̓v���C���`�����g�̓`���ɍ��t���Ă�����̂ł���B �@����Sanctus�͎��я��Irecitative�͎g���Ă��Ȃ��B�����́A��葕���I�l�E�}�I�X�^�C���ŏ�����Ă���B���P���ȃ����f�B�����Â��A�܂���O�p�Ɏg���Ă����ƍl���邱�Ƃ́A���ł��낤�B���̗l�����T��̖ړI�̂��߁A���邢�͂��܂肤�܂��Ȃ����̑��̂��߂ł���������̍�i�Ɠ��l�Ȃ̂ł���B�����Ƃ��P���ȃ����f�B�͂���ɁA���k���������ꂽ�`���\���������Ă���̂ł���B����́A����̂Ȃ����ӂ̉�O���L���ł��ĉ̂����߂̃j�[�Y�Ƃ͂܂������َ��Ȃ̂ł���B �@Sanctus�̃����f�B�́A��ȉƂ��������������A�\�����A���y�\���ɌŎ������Ӗ������̂���Ȃ錤���̂��߂̗D�ꂽ�f�ނ��������Ă���B�e�L�X�g�́AKyrie�̂悤�ȌJ��Ԃ��\���̂������͊܂�ł͂��Ȃ����A��ȉƂ����͂����A���y�I�J��Ԃ��̂��߂̖��炩�ȋ@��Ă����B Sanctus��3��̌J��Ԃ��́A������3�p�[�g�`���B�Q��Hossanna�͓������y�������邱�Ƃ����������B�����������H�ɂ����Ă��������A���S��Sanctusno�����f�B�̂��߂̍\���������m������̂ɂ͕s�\���ł������B �@�������������͂����A�e�L�X�g�̈قȂ����s�ɑ��Ċ�{�I�����f�B��t�^���邱�Ƃł���BSanctus�̑�Q�A��S�s�͂��Ƃ��A���������f�B�̈قȂ����`�ʼn̂��邱�Ƃ������BKyrie�Ɠ��l�ASanctus�̃����f�B�̒��Ӑ[�������́A�`���̒P���ȑ�\��������蕡�G�Ő��k�ɍ\�����ꂽ���y�\�����B���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���̂ł���B AGNUS�@DEI 3������Agnus Dei�́A�������̓_�ŁAKyrie�Ɗ֘A�������Ă���BKyrie�̍ŏ�������Agnus Dei�̏I��蕔���iLU�@p758)�ɂ����āA�����̃e�L�X�g�́A���Ƃ��Ƃ͘A���̕������`�����Ă����B���҂Ƃ��A���[�}�T��ɓ��������O�̓����T��ɂ�����W���I���ڂł������B Agnus Dei�ɂƂ��ẮA�������������́A�M���V���l�̋��cSergius1���i687-701)�̂��Ƃōs��ꂽ�B�ŏ��A���ׂĂ�3��̐����miserere nobis�ŏI����Ă������A10�`11���I�ɂ́Adona nobis pacem���I�~��ƂȂ����B���������ɁA���l�̕ω����A���N�C�G���~�T��Agnus Dei�ł��N�������B �ʏ핶�̂ق��̃`�����g�Ɠ��l�AAgnus Dei�͎���ɁA��O�̂Ƃ��Ă̋@�\�������Ă������B�W���I�̏I���܂łɂ́A���[�}�̋��c�~�T�ɂ����ẮA���̑������̋@�\��S���悤�ɂȂ��Ă����B���̂Ƃ���ł́A�l�X�͂��Ȃ����܂ŎQ�����Ă������A10�`11���I�܂łɂ́A�p�t�H�[�}���X�͎���ɁA���Ձiassisting clergy)��P�����ꂽ���̑��̎�ւƈڂ��Ă������B�����A��ȉƂ�Agnus Dei�̐V�����Ȃ����n�߂Ă����B�ŏI�I�ɂ��̐���300�قǂɂ��c��B �@�������̈قȂ��������f�B������ɂ�������炸�AAgnus Dei�́AKyrie��Sanctus�قǂɂ́A��ȉƂ������ە����Ȃ������BAgnus�̑����̃����f�B�́A�����̃`�����g�ł���A���̉��y�`���͈�ʓI�ɒP���Œ����I�ł���B �����ɓK����20�قǂ�Agnus Dei�̂����A�قڎO���̈�قǂ����ׂĂ�3��̐���ɂ����ē��������f�B���J��Ԃ��Ă���B����ʓI��3�����`����aba�ŁALU��Agnus�̃����f�B�̔��������̌`���ł���B�R�̃P�[�X�ł́A���ԕ������ŏ��ƂR�ԖڂƂ��犮�S�ɈقȂ��Ă���iNo.�P�Q�A�P�T�A�P�U�j�B�U�̃P�[�X�ł͂������A���ׂĂ����������f�B�I�~���Ă���iNo.�Q�A�S�A�W�A�X�A�P�R�A�P�S�j�B����ɁAAgnus�X��3�����͋��ʂ̎n�܂�ƂȂ��Ă���B���̂��߂ɁAQui tollis peccata mundi�̃����f�B�݂̂�aba�`���������Ă���BAgnus10�̋t�]�����́Aqui tollis�̃����f�B�����ׂē����ł��邱�Ƃœ�����B�����āAaba�\���́A�ŏ��ƍŌ�̋�݂̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���B �@�Q�̗�O�I�Ȍ`���ɂ��ďq�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��BAgnus�V�́Aaab�p�^�[���ƂȂ��Ă���B�R�̕����̏I�~�͓���ł���BAgnus11�ɂ�����abc�`�������l�ɓ��ꂳ��Ă��邪�A���ꂼ��̃Z�N�V�����̍Ō�̋�ɑ��郁���f�B�́A�܂���������ł͂Ȃ��B �@ �@��������Agnus Dei�̌`���Ƃ��Ẵ����f�B�͒P���Ȃ̂ŁA�R��ڂ̒Q��̏I�~�ɂ�����e�L�X�g�̕ύX�ʼn��y�̕ύX�����Ȃ���Ȃ����Ƃɂ́A���ӂ����ׂ��ł���B�I�~������ł����Ă��A2�Ԗڂ�miserere nobis�͈قȂ��Ă��邱�Ƃ�����B��ȉƂ����́A���y�`�����e�L�X�g�̍\���ɖӖړI�ɂ͏]��Ȃ����Ƃ��������̂ł���B ITE,MISSA�@EST �ŋ߂̃~�T�̂����ł́A�����́AKyrie�̃����f�B�����̂܂g���Ă���B���̗��R�́A�����炭�A�O���S���A���`�����g�̌������疳������Ă�������ł��낤�B �@�i�Ղ⏕�Ձideacon)�͏�ɁA�~�T�I����錾���邪�A���Ƃ��Ƃ́A�l�X��Deo gratias�ʼn������Ă����BIte,missa est�̐��I�ȃ����f�B�������̉������̂����Ƃ́A���̑�����O�̋@�\��S���悤�ɂȂ��ď��߂ē������ꂽ�̂ł���B �����������Ƃ����N�����̂��A�~�T�ʏ핶��`���̃`�����g������ꂽ�����f�B�ŏI������悤�Ȋ��K�͂��N�������̂��A�͎c�O�Ȃ���킩��Ȃ��B Benedicamus Domino���AGloria�̂Ȃ��~�T�ɂ����ẮAIte,missa est�ɒu�������B Ite,missa est��Gallican�N���ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�I��1000�N�O�̃��[�}�~�T�ł͂���͒m���Ă��Ȃ�����ł���B11���I�ɂ͂������A���̑��݂͈�ʓI�Ɋm�����ꂽ���̂ƂȂ����B�ߑ�̐��̏W�ABenedicamus Domino�Ƃ��̉���Deo gratias�ɂ����āAIte,missa est�Ɠ������y���̂��Ă��邪�A�ǂ̒��x���ꂪ����������킷�̂��́A�킩��Ȃ��B |