| MEDIEVAL MUSIC
��4�� |
| ��122(92) �b�g�`�o�s�d�q �W The Music of the Offices �@�L���X�g���̏����̍��\�����ƈ��S������\��̏W���O��̏W��D�܂�Ă����B�����Avigil���́A�y�j���ɂ̂ݍs���Ă����B�[��O������n�܂���j���̒��̎��ԂɏI���A�~�T��forerunner�Ƃ��ď����I�Ȍ`���ŁA���`�̏j���ƂƂ��ɁA�s��ꂽ�B �@�������̓��j���͂���䂦�ɏT���̏j���Ƃ��āA���_����Sabbath�i�������j�Œu��������ꂽ�Bvigils(�O��ہj�̗�q�́A��ɁA�F��ō\������Ă����B�������ǂ܂�A���т��̂��A���_�����̋F��̎��ۂł̓`���I�����ł���A���[�}�̐������ۂ̊�b�I�v�f���₵�Ă����B�����ɑ��āA�����ɂ́A�q�����̂��L���X�g���̊v�V�����炩�ɉ�������B �@�L���X�g���������␔�ɂ����Đ�������ɂ�Avigils�̏j���́A�i�ӉہA���ہA�^�ۂ́j�R�̐������ۂɐi�������B���̂P�j���Ƃ��Ƃ́A�������ۂ́A���v���̗�q�ƂƂ��ɁAvigils�ɐ�Ă����B�Ӊۂ̏����̌`���ł���B���̂Q�jvigils�̒��S�́A��̍Ō�̎��ۂɏj���A�̂��ɁA��ۂƂȂ����B�����s�����ł͂��邪�A���ۂɂ��Ȃ����B���̂R�j�����ĂR�Ԗڂ̗�q�́A�~�T�̑O�̑����ɍs���A�^�ۂƂȂ����B ���������R�i�̗�q�j�́A�~�T�ł͂ЂƂɂ܂Ƃ߂�ꂽ���A�L���X�g������̍ŏ��̐����I�ɁA�傽��T��`���ƂȂ����B����䂦�A�ӉہA���ہA�^�ۂ̂R�������Ƃ����O�ł���A���y�I�ɂ������Ƃ��d�v�Ȑ������ۂł��邱�Ƃ͋����ɂ͂�����Ȃ��B����ɁA�[�ׂɐ旧���ďj�����n�܂�Ñ�̎���ɏ]�����ƂɂȂ����B���ʂȓ��j����j���ɑ��鐹�����ۂ̈�A�́A��ɁA�j���̑O��̑�P�ӉۂƂƂ��Ɏn�܂�A�j���̑�Q�Ӊۂ̏I���ƂƂ��ɏI���B �@���Ƃ���3�����ł������旧��vigils�ɔ����~�T�̏j���́A���j���ɂ̂ݎ���s��ꂽ���A�܂��Ȃ��A�}���҂̏j���₻�̑��̐�����f�H���ɂ��g�傳�ꂽ�B�����āA�l���q�������̍݉Ƃɂ����Ă��т��яj�����ꂽ�B���ƂɂR���ہA�U���ہA�X���ہi���X���A���߁A�ߌ�3���ɑ����j�ɍs���A����͂قƂ�ǁA�`���I�ȃ��_�����̋F��̎��ۂɑ������Ă����B �@�����������オ�A�R�����A���Y���A�����ƂƂ��ɁA�L���X�g���k�̂��߂ɐ_�������ꂽ�B�������ۂ̂���Ȃ锭�W�̂��߂̂����Ƃ��傫�Ȍ����͂́A�������A�C���@��`�̖u���ƂƂ��ɂ���Ă����Bvigils�ƒ��Ԃ̎��ۂ̖����̊ώ@�́A�C���@�����̈�ʕ����ƂȂ����B4���I���ɂ́A����ɁA��������I��q���A���̐����ɂ����Ă͂邩���l�I�ł����������̋F��Ɏ���Ă����悤�ɂȂ����B �@�������ۂ̏����̔��W�̑����́A����̓�����ŋN�������B���ƂɁA�A���e�B�I�P��G���T�����ŁB���m�ɂ����邱�����������A���Ƃɔ�C���@�I����Ŋώ@���ꂽ���̂ɂ��Ă̂����̒m���́A�n��ŕs�m���ł���B ��X���m��A�������ۂ̑S�T�C�N���̍ŏ��̋L�q�́A�I���T�R�O�N���̐��x�l�f�B�N�g�K���ɂ����Č�����B��̕ύX�ƂƂ��ɁA�����̐������ۂ͂��₭�A���m�L���X�g���Љ�ׂĂ̕W���ƂȂ����B��X�̌��݊S�́A��̒����̎���ɏj��ꂽ�悤�Ȑ������ۂ̏����Ɠ��e�ɂ��Ăł���B�������������͕s�ς̂܂c����Ă���A���e�͍ו��ňꕔ�ς���Ă��邾���ł���B�W�̐������ۂ͈ȉ��̔@���ł���B 1�@.Matins�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S������t������ ��������r midnight 2.�@La��ds�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`t daybr������ 3.�@Pr������(fi��st ho����)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@6 �`.�l. 4. �s��rce�@(third ho��r)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@9 A. �l. 5.�@Se��t(si��th ho��r) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m������ 6. �m������( ������th ho��r)�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�R �o.�l. �V�@VesPers �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d��rly �������������� 8. �b����pli���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a��fore r��tlri��g �@����܂ŏq�ׂ��悤�ɁA������vigils����i�������R�̗�q���A�������ۂ̂����Ƃ������A�����Ƃ����O�Ȃ��̂ł������B�I�ہiCompline)�́A���炩�ɁA���̈�A�ɂ����čŌ�ɕt��������ꂽ���̂ł��邪�AVesper��Lauds������Z���B�������A���y�I�ɂ��܂��A���܂�d�v�ł͂Ȃ��BPrime����None�܂ł̐������ۂ́A���ꂼ��Z���ALittle ���邢��Lesser Hour'(�����ہj�ƌĂ�Ă���B ���Ԃ̎��ۂɂ́A��ʓI��Matin�͊܂܂�Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�AMatin�̗�q�́A�̂���Ƃ������͏�������̂ł���A���̂��߂ɁAAntiphonary����͂͂�����Ă���B�܂������A�T���Đ������ۂ́A�C���@�̊O�ɂ����ẮA����ł́A���y���Ő��s����邱�Ƃ͋H�Ȃ̂ł���B�����ƃ��l�b�T���X����ʂ��āA����炪���ԂɃt���ɉ̂���̂́A���ׂāA�C���@�{�݂�A�J�e�h�������w����Ȃǂł������B THE FORM OF THE OFFICES VESPERS ���j���Ƃ��̑��̏j�����O��̑�PVespers�ƂƂ��Ɏn�܂邽�߂ɁA�܂���Vesper����舵���B �@�������ۂ͒ʏ�́A�����̌l�̋F��ƂƂ��Ɏn�܂�B���̌�Averisicle��responsoriesDeus in adjutorium���̂���B���̃e�L�X�g�͎��тU�X�т̍ŏ���verse�ł���Bresponsories�́A�㔼�́A���h�N�\���W�[�������A�Z���A�������������A���邢�́A���{�߂̎���Ɛ��T�̐��j���̊Ԃ�Laus tibi Domine Rex aeernae gloriae���̂���B �@Deus in adjutorium���̂����߂ɁAferial,festal,solemn�̂R��ނ�reciitation tone������B�iLU p263,250)�B �@���̍ŏ���versicle�̌�́A���ׂĂ̐������ۂŋ��ʂƂȂ�A�Ӊۂł́A�T�̎��т������B���ꂼ��́A���g�̃A���e�B�t�H���ƂƂ��ɉ̂���B���R�ȃ����f�B�̂Q�̃^�C�v�̂ЂƂ́A���я��ƌ��т��Ă���B �Ӊۂ̎��̍��ڂ́AChapter�ƌĂ�鐹���N�ǂł���B���̌�Ahymn�������B�������A�����ł́A����痼���ڂ̊Ԃɑ�responsories�������Ă����B��responsories��responsories�I���я����i�������`���ł���A�ʏ�͂�蒷�������N�ǁA���邢��Lesson�̂��Ƃɂ���B����͐������ۂƃ~�T�̗��҂ŋ��ʂł���B���������Ӊۂɂ�����g�p�́AChapter�̊ȑf���ɂ�������炸�A�^���Ȃ��A��q�̑������𑝂����Ƃ���}����Ă����B�Ȃ��Ȃ�A������`�����g�̂����ŁAresponsories�͂����Ƃ����O���������ꂽ���̂�����ł���B �Ӊۂ�responsories���|���t�H�j�[�̍�Ȃ̊�b�ƍl�����m�[�g���_���y�h�̍�ȉƂɂ���āA����ɑ傫�ȑ�����������ɐ��s���ꂽ�B��������responsories���A�������̏C���@�ł̋V���������Ď����Ă��܂������Ƃ́A����Ɏc�O�Ȃ��Ƃł���B �@versicle�́A���y�ʂł͔Ӊۂ̏d�v�ȃ|�C���g�ł���}�j�t�B�J�g��hymn�̊Ԃɂ���B�R�̐V����canticles���������ۂɂ͂��邪�A�����}���A����i���J�ɂ�镟�����P�͂S�U�]�T�T�߁G�}�j�t�B�J�g�j�͔Ӊۂ�canticle�Ƃ��āA���_����ʒu���߂Ă���B�}�j�t�B�J�g���ꎩ�g�͎��т̃g�[���ɂ悭�����g�[���ʼn̂���B�}�j�t�B�J�g�ɑ���A���e�B�t�H���͂������A��ʓI�ɂ͑��̃A���e�B�t�H���������������A���O�ɉ̂���B �@�}�j�t�B�J�g�̌�́A���̐������ۓ��l�A�Ӊۂ̗�q�͏I�����邪�A�F��Əj��������B�Ӊۂő}���������̂Ƃ��āA�A���e�B�t�H��Suffrage of [petition to] All the Saints"��A�j����Octave(��j�Ձi�N���X�}�X�ƕ����Ձj�������Ƃ���8���ԁj�̋L�O������B�����̃`�����g�͌��ɒl����B�Ȃ��Ȃ�A�����͐������ۂ̐����Ȃ��A���e�B�t�H���̂����ŁA���݁A���т���͗���A�Ɨ����������f�B�ʼn̂��邩��ł���(LU p262-26211)�B �I����versicle�̂����ABenedicamus Domino�����́ALU p124-127�ł݂���悤�ɁA���R�ȃ����f�B�œ��O�ɉ̂���B�������������f�B�́A�Ӊۂ�^�ۂɂƂ��Ă͒���I�Ɏg���A���ɁA���̐������ۂł��g����Bversicle���ꎩ�g�͂������A�������ۂ̍Ō�ʼn̂��A�ʏ�͒P����recitation tone�ł���iLU�@p233)�B �@����܂ł̘_�c���܂Ƃ߂邽�߂ɁA�Ӊۂ̗�q�̃A�E�g���C����Table�T�Ɏ����Ă���B���ꂼ��̍ŏ��̌��t�̓��e����ł��邪�A�N���s�ςł���A�������ۂ̒ʏ핶�ƂȂ��Ă���B�����ő啶���Ŏ�����Ă���̂́A�ω����鉹�y�v�f�ł���B ������̂����Ƃ��d�v�ȏj���ɂ́A�Ӊۂ̂T�̎��тɑ��邻���ŗL�̃A���e�B�t�H��������B���ꂪ�Ȃ����ł́A�ʏ핶�̔Ӊۂ̃A���e�B�t�H�����g���Ă���B�Ӊۂ�hymn�ł��������Ƃ�������B�����j���͌ŗL��hymn������A�Ӊۂɋ��ʂ�hymn���g����iLU p256)�B�}�j�t�B�J�g�ɑ���A���e�B�t�H���ɂ́A�����A��ɌŗL�̃A���e�B�t�H��������A�����Ă��̃����f�B�͂���䂦�A�����k�̌ŗL�̃A���e�B�t�H�������߂��Ă���B 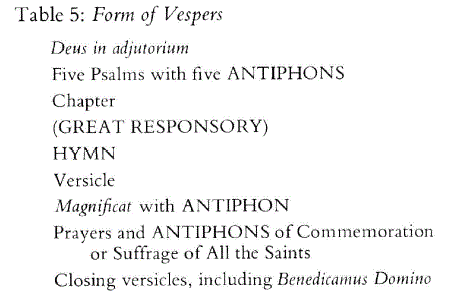 THE FORMS OF THE OTHER DAY HOURS:COMPLINE ���̌`���\���ɂ����āA�I�ۂ͔ӉۂƂقƂ�Ǖς��Ȃ��B�������A���y�I�ϓ_���猩��ƁA�I�ۂ͂قƂ�Ǐd�v�����������Ȃ��B���т͂T�ł͂Ȃ��R�ł���A�A���e�B�t�H���͂P�ł���BChapter��Hymn�̈ʒu�͋t�ɂȂ�AChapter�ɂ́A�����ł͏�responsories�ƌĂ��P����responsories�`�����g�������Ă���Bcanticle�̓V���I������( �k��ke 2:29 �|32)�ANunc dimittis�ƂȂ��Ă���B �I�ۂ̉��y�I�s�т́A�����Ȃ��`�����g��1�N��ʂ��ČJ��Ԃ��g���Ă��邱�Ƃł��킩��B�����Ƃ������ȏj���ł����A�I�ۂɑ��Ă͌ŗL�̃`�����g���Ȃ��̂ł���B �������ۂ̒ʏ핶�ł́A���T�̓y�j���琹��~�Ր߂܂Łi�o��s�������� �s�������j�������A�T���́A���тƂ̎g�p�̂��߂̈قȂ����A���e�B�t�H����p���Ă���B�o��s�������� �s�������ł́A�A�������A���e�B�t�H���iAllelia)���p������BNunc dimittis�̂��߂̃A���e�B�t�H���́Ahymn�̃e�L�X�g�Ƃ��āA���邢�͏�responsories�Ƃ��āA�s�ςł���B ��҂�2���ځihymn��Short Responsory)�́A�������A����N�̈قȂ����G�߂ɂ���āA�قȂ��������f�B��搂���B����䂦�ɁA�I�ۂ́A���̐�������鎩�R�ȃ����f�B�����P�Q�ȏ�̃`�����g�e�L�X�g���ւ��Ă���B�O���S���A���`�����g�̌����ɂ����邻�̒x�̗��R�͖��炩�ł���B �@�I�ۂ�Benedicamus Domino�ɑ����āA���Ȃ鏈���}���A�̃A���e�B�t�H���ƌĂ��A���e�B�t�H����������ꂽ�B����͋G�߂��ƂɂS����B�����͎��я��ƌ��т�������̓��Ƃ͖��W�ŁA�����A���O�ȃ`�����g�ł���B���Ƃ��Ƃ͂����͏I�ۂ̂��Ƃɉ̂���Ӑ}�͂Ȃ��ALU�́A����Ɏ^�ہA�O���ہA�Ӊی�ł������̂����Ƃ������߂Ă���B ����䂦�A�}���A�A���e�B�t�H�����I�ۂ̌�ł̂݉̂���ׂ��A�ƐM���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ̂ł���B���̂悤�Ƀ}���A�A���e�B�t�H���̎g�������������ꂽ�̂́A�����Ɋy���܂ꂽ�����̃����f�B�̐l�C�ƁA���l�b�T���X�ł�����ɂȂ����}���A�A���e�B�t�H���ւ̃|���t�H�j�[�̐ݒ�Ƃ͖������Ă��邱�Ƃł��낤�B LAUDS �^�ۂƔӉۂ͌`���Ɖ��y�\���ɂ����ē���ł��邪�A�e�L�X�g�Ɋւ��āA�Q�̌���I�ȈႢ����B�i��́j�}�j�t�B�J�g���A�^�ۂł̓U�J���A�����Benedicamus Domino Deis Israel�ƂȂ��Ă���B����͑O�q�́A�������ۂ̒ʏ핶�ŌŒ肳�ꂽ�R�̐V���ɂ��canticle�̂�����3�Ԗڂł���B�}�j�t�B�J�g�Ɠ��l�A�i�^�ۂʼn̂�ꂽ�jBenedicamus Domino Deis Israel�ƂƂ��ɉ̂�ꂽ�A���e�B�t�H���́A��Ɏ�����v�ȏj���ł͌ŗL�̃A���e�B�t�H��������B �@2�Ԗڂ̈Ⴂ�́A�T���鎍�т̂�����4�Ԗڂł���B���̂S�̎��т͎��ۂɎ��тł��邪�A�i�^�ۂł́j4�Ԗڂ͏�ɁA��������̈��p�ł���B��������canticles�͂P�S���邪�A�V�ÂA�Q�����ƂŏT��ʂ��ĕ��z����Ă���B�P�Z�b�g�͈�N�̑啔���Ŏg���邪�A�ʂ̕���7�{�߂��瞡�L�̓��j���܂łŎg����B THE LESSER HOURS 4�̏����ہAPrime Terce,Sext None�͒Z���������ۂł���A���y�I�ϓ_����͂قƂ�Ǐd�v���͂Ȃ��B�����͂��ׂē����\���ł���iPrime�����͑��̂R�ɂ͂Ȃ����ڂ����������邪�j�A����䂦�ɁA�ꏏ�ɋc�_�����BDeus in adjutorium�Ŏn�܂�Benedicamus Domino �ŏI���W���ŁA�����̏����ۂ́Ahymn�ƁA�P�̃A���e�B�t�H���݂̂��R�̎��тƁA��responsories��Chapter��versicle�Ƃ����\���ł���B ���y�����Ȃ����Ƃ́A�����ۂɓ��L�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A��N��ʂ��ĕs�ς̂܂܂ł���B���Ƃ��A���ꂼ��̎��ۂɈ�ÂŌv�S�̃A���e�B�t�H���́A�����ۂɂ����ẮA�����Ύ^�ۂ���̎����ƂȂ�Ahymn�͒ʏ�͒ʏ핶�̈ꕔ�ƂȂ�B�T���āA��responsories�݂̂��A�^����ꂽ�j���̓���Ȏ��ۂւ̌ŗL�A���e�B�t�H���ƂȂ�B 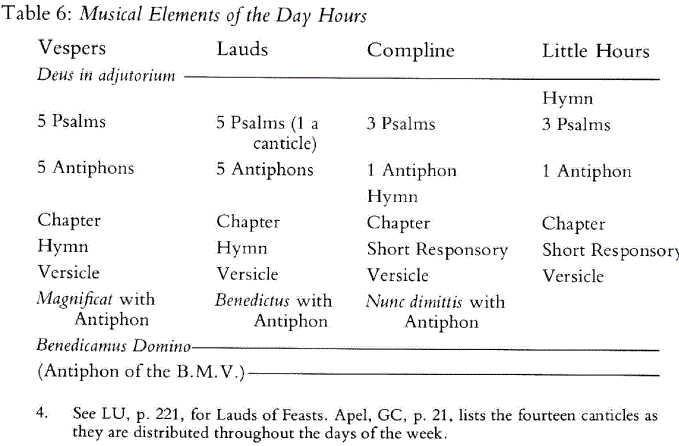 �@ �@MATIN�ip�X�X�j �G����YouTube�́A�J���g�D�W�I�C����̂��̂ł��邽�߁Avenite�̑O�Ɏ��ё�R�҂������Ă��� ���ۂ́A���̍\�������̐������ۂƂ͂��Ȃ�قȂ�A���̔�r���ł��Ȃ��B�A���e�B�t�H�������т��̂����Ƃ͋��ʂ��Ă��邪�B �@���ۂ́A���ꂼ�ꕪ�f���Ă͂��Ȃ��S�̕����ɕ�������B�`���Z�N�V������́A���ɖ��O�͂��Ă͂��Ȃ����A�R��Nocturns�i��ہj�������Ă���B���ꂼ��́A�����\���p�^�[���ł���B�S�̂͂��ׂĂ̐������ہiPater noster,Ave Maria,Credo,vesicle,Deus in adjutorium)�ɑ���ʏ�̓����ɂ���č\������Ă���B�����Ēʏ��Benedicamus Domino�ł����ďI���B�i�Gmatin�ł́A�B��A���ё�T�O�҂̈�߁ADomine,labia mea aperies(�揥�j�@Et nos meum annuntiabit laudem tuam(�����j���n�܂�j �@Deus in adjutorium�̂��Ƃ́AMatin�̓����I�`�����g�́A�A���e�B�t�H���Ǝ��тX�T�т�����BVenite,exsultemus Domino�i����āA������ق߂܂�j�Ƒ����B�����������t����AInvitatory Psalm�i�������сj�ƌ����A�A���e�B�t�H�����P����Invitatory�i�����j�ƌĂ��B����́A���тX�T�т����Matin�̐������ۂ��n�߂�ɂӂ��킵���e�L�X�g�ł��邪���߂ł���B���̂ǂ�Ȏ��т��A�������ۂ̒ʏ핶�̊m�ł���n�ʂ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��BInvitatory���тɏ]���āAMatin�̍ŏ��̃Z�N�V�����ɂ����錈��I�ȍ��ڂ�hymn�Ȃ̂ł���B �@�������ۂ́A�R��Nocturns�����ڑ������A���ꂼ��͓����p�^�[���ł���B���ꂼ���Nocturn�́A�R�̎��тƂƂ��Ɏn�܂�B���ꂼ�ꎩ�g�̃A���e�B�t�H��������B�����āA���̌�̂R��Lesson�ŏI���A���̌�ɑ剞���iGreat Resonsory)�������B���т�lesson��versicle�ɂ���ĕ�������A�����Pater noster��͍߁A�j���Ƃ��������̂ł���BNocturns�ɂ����ďd�v�ȉ��y���ڂƂ��ẮAanthiphon���X�̎��т�Alesson�ɑ����X��responsories����������BLU�ɂ����ẮA���ɗ��R�͂Ȃ����Aanthiphons�͂��ꂼ���Nocturn�ɑ��� �P����R��anthiphon�����邪�ALesson��responsories�͂P����X����B �@Nocturuns��antiphone��responsories�̌�ɂ́A����̏j���ɌŗL�̂��̂ł��邪�AThanksgiving��Hymn�ƌĂ��Te Deum �iLU�@p1832�j�������B�Ȃ��A�ߑ�̏ꍇ�A�������ۂ͎�Z���Ȃ�A9�Ԗڂ�resnponsory�̑����Te�@Deum�����Ă���B�����A���T�̊Ԃ⎀�҂̂��߂̐������ۂł́ATe�@Deum�͏ȗ������B 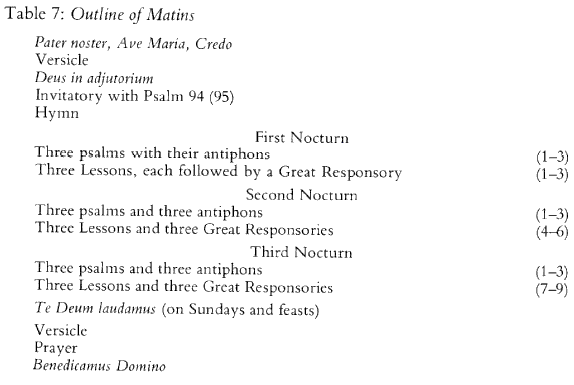 �@Matin�̌`���Ɋւ���Ō�̐����Ƃ��āA�d�v�x�̒Ⴂ�j���ɑ��ẮA���ꂪ���Ȃ�k������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���A�ƌ����悤�B���������j���́A��j���̂X��Lesson�̑���ɁA�R�ɂȂ�A���邢�͒P���Nocturn�ɂ����Ȃ�B�j���̃����N�́A���ۂ̐������ۂɂ�����Lesson�̐��ɂ���āA�����Ɏ�����Ă���B���̊ϓ_����AMatins�́A���̐������ۂƔ�r���āA���̍\�������Ȃ�_��ł��邱�Ƃ��킩��B���̑��̐������ۂł́A���̂悤�ȉϐ��͂��蓾�Ȃ�����ł���B �@Matin�̉��y�����L���ł���A�ω��ɕx��ł��邽�߂ɁA�����̂��߂̍ޗ����قƂ�ǎc���Ă��Ȃ��͎̂c�O�ł���B�������ۂ́ADay Hours�̂��߂�Antiphonary�ɂ��ׂčڂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ALU�Ɏ����ẮA�W�̏j����Matin���ڂ��Ă���ɉ߂��Ȃ��B �@���̂悤�Ȑ����Ȃ���ɂ����Ă����AMatin�̒��ڂ��ׂ��_��Ȑ����͎�����Ă���BNaivity��Corpus Christi�ɑ����q������Table�V�ō\���̃A�E�g���C�������m�ɋL����Ă���B�����ł́ATe�@Deum�͑�Xresponsory�̑�ւƂȂ��Ă���B���T�̂R�̗�q�́AInvitatory Psalm��hymn���ȗ�����ANocturn�T�̑�Panthiphon���璼�ڎn�܂��Ă���B �C�[�X�^�[�̎���ɂ́ATe�@Deum��Invitatory Psalm�͉̂��邪�Ahymn�͂Ȃ��A�ЂƂ�Nocturn�݂̂ł���BPentecost�ł́A�P��Nocturn�݂̂ł���A��Rresponsory�̏ꏊ�ɂ���Te�@Deum�ƂƂ��ɏI������B�������AMatin�̖`���Z�N�V�����͊��S�ł���B ����䂦�ɁA��X�́A���̐������ۂ����Ȃ킿�A�ЂƂ�Nocturn�ł���Matin�̌`���������ʏ�̂��̂Ƃ݂Ȃ��̂ł���B ���҂̂��߂̐������ۂɂ�����Matin�ł́Ahymn��Te Deum�������Ă���B�������̋@��ł͂������A�ЂƂ�Nocturn��I�Ԃ̂��A�R�̂����I�Ԃ̂��iLU�@p�P�V�V�X�j�Ƃ����I�����K�v�ƂȂ�B�قȂ����T��I�ȏ̒��ŁA��q�̂�肩����ω������邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ�����ł���B �@�������ۂ��c�_����O����A���і{�����̃e�L�X�g�̑啔�����������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł������ɈႢ�Ȃ��B�������ۂ͎��ہA���ׂĂ̂P�T�O�̎��т����T�̂��Ă���悤�ɂȂ��Ă���B���ꂼ��̗�q�ł́A���т͂��Ƃ��Ɛ����̏��Ԃʼn��t���ꂽ���A�����̏j���ł́A���т͂��̋@��ɓK������悤�ɉ��t�����悤�ɂȂ����B�������A���ɏ]�����t���܂��A�����Ɉێ�����Ă���B �@���т�canticles��recitation�`���ʼn̂��邪�A�����͂W�̋�����@�ɑ�������B����̎��т̎g�p�ɔ������@�̑I���͂������Ȃ���A���̃e�L�X�g��T��I�ʒu�Ƃ͖��W�ł���B���̑���A���̑I���́Acanticles�⎍�т��̂���annthiphon�̃��[�h�Ɉˑ����Ă���B��X�͂���䂦�A�������ۂ̎��я����K�������葕�������肵�����R�ȃ����f�B�ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B TYPES OF FREE MELODIES IN THE OFFICS : THE ANTIPHONS ���A���u���V�E�X�����m��antiphonal psalmody�������Ƃ��Ă��A�܂����т��ǂ̂悤�Ɍ��݂ɉ̂�ꂽ�̂��A�Ƃ������Ƃ͂悭�킩��Ȃ��Bverse��half-verse�́A�Ƃ��ɑf�ޓI�Y�t�Ȃ��Ɍ������Ă����Bantiphonal psalmody�̏����̗��j�ł́A�������A���т�verses�����R�ȃ����f�B�ɒu�������āA�e�L�X�g����サ�Ă������K�����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�e�L�X�g�������������R�ȃ����f�B�́Aanthiphon�Ƃ��Ēm���Ă����Bantiphon�͎��т̍ŏ��ƍŌ�ɂ�����邪�A���ꂼ���verse�̌��Averses�̃y�A�Ƃ��Ă��̂��Ă����B�`���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B �@ �@���������ߒ��̈�̗�́AInvitatory�i�����j���сi���тX�T�сj�̈ٗl�ɒ���verses�̎g�p����������B������verses�̌�ɁAInvitatory�@antiphon(�����A���e�B�t�H���j�̂��ׂĂ��邢�͑啔���́A�J��Ԃ����B����ɁA�ŏ��ƍŌ��antiphon�̌J��Ԃ�������B ���S�Ȍ`�Ƃ��Ă̗�Ƃ��āA�N���X�}�X��Invitatory�i�����j�iLU�@p�R�U�W�j�����グ�Ă݂悤�B�_�C�A�O�����͉��L�ł���BA�P��A2��Invitatory�i�����j�@Anthiphon�̂Q�Z�N�V�������\����BD�́A���h���ł���B�ʏ�́A���ׂĂ̎��т�canticles�ɕt����������B �@���炩�ɁA���ׂĂ̎��т̐��s�ɂ́A���ԓI���e�͈͂̍L���C���@�ł����A���Ȃ�̎��Ԃ����������B���̌��ʁA�`���ƏI���݂̂�antiphon�����Ƃ��A�������ۂɂ�����ʏ�̎��т�canticles�̉̂����ƂȂ����B ���݂̂���Ȃ�k���X���ł́Aantiphon��intonatio�i�n���j�݂̂��ŏ��ɉ̂��A���S�Ȑ��s�͍Ō�݂̂ƂȂ��Ă���B �������������́A�T��w�҂≹�y�w�҂�������͌����A���@�I�ɂ����y�I�ɂ��i���Z���X�ł������B���̂悤�Ȗ�؎�`�́A1960�N7��25���̕z��(decree)�ɂ���ċ֎~���ꂽ�iLU1961�N�ŎQ�Ɓj���ALU�̂��܂��܂ȏꏊ�Ŏw�E����Ă���B �@�������ۂɂ�����p�ɂȏo��������҂ł���悤�ɁAantiphon�̓`�����g�̑��̌^�������A�͂邩�ɂ��̐��ɂ����ď����Ă���B�����̖{�́A����ɂ��y��antiphons���܂܂�A1000�ȏ�̂��̂����ۂɎg���Ă���B���̂悤�Ȕ���Ȑ�����l���āA���̗l���A��������ʉ����邱�Ƃ͍���ł͂��邪�A�T���āAantiphons�͎��R�ȃ����f�B�^���ł͂����Ƃ��Z���A�P���ł���B�قƂ�ǂ��ׂĂ��V���r�b�N�ł���AJustis ut palma(��S�|�P�j�̂悤�ɁA���������ŁA���܂�2���l�E�}��������B 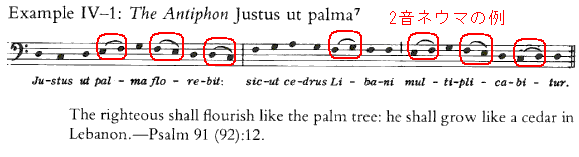 �����Ƃ������ȏj���ɂ����Ă����A���т�antiphon�̗l���͂قƂ�Ǖω��͂��Ȃ��B����́ABenedicitus��Magnificat�ɂ�����antihon�Ƃ͍ۗ������Ⴂ�ł����B�����ł́A��ɑ����ɒ����A���O�ł���A�j���ɉ��������S�ɔ��B�����l�E�}�X�^�C���������邩��ł���B�O���[�v�Ƃ��Ă͂������Aantiphons�́A�����Ƃ������^���̃v���C���`�����g��Ȃ̌����������Ă���ƌ����悤�B �@anthiphons�ɂ��Ă����Ƃ������[�����Ƃ̂ЂƂ́A�t���[�����`������psalms�̉����ɂ��Ă̊W�ł���Bantiphons�Ƒ��̃`�����g�����[�h�ɂ��������ĕҐ������ƁA����Ȃ镪����anthiphons������܂łɎg���Ă���psalm-tone�̏I�~�ɂ��������ăO���[�v������B ���������I�~��antiphon�̌J��Ԃ��ɑ��ăX���[�Y�ɓ������̂����A������antiphons�������I�~�����߂邱�Ƃ����������f�B�`�ԂƂȂ�̂��������ɂȂ邱�Ƃɋ����Ă͂����Ȃ��B�ЂƂ̏I�~�ɑ��鉹���ɑ��Ă����A�`�������f�B�̐i�s���x�[�X�Ƃ��āAantiphons�̈قȂ����O���[�v���m�������B �����̗��_�Ƃ����́A���������W�ɋC�Â��Ă���A����̊w�҂����́A����ɂ������anthiphons�������悻�T�O�́h�e�[�}�h�ɍi���邱�Ƃ������Ă���B��ʓI�ɁA��X�́A�^����ꂽ���[�h�ɂ����鐔������antiphons�ƈقȂ����e�[�}���Apsalm-tone�ɉ������قȂ�I�~�ƂȂ鐔�ƒ��ڂ̔��W�ɂ��邱�Ƃ𗝉����Ă���B �@�������ۂ�antiphons�ɂ��Ă̋c�_���I����O�ɁA����炪���������Ƃ��Ƃ̓T��I�@�\�ɂ��Č��Ă݂����B����͈�ʓI�ɁALauds��Vespers��canticles�̌�ɋN�����Ă���B���̓_�ɂ����āA�������ɓ���������茵�l�ȏj���ɂ���Ēu��������ꂽ�j���́Aantiphon,versicle,�F��̐��s�ɂ���ċL�O���ꂽ�B�������Aantiphons�͂��Ƃ��Ƃ͓Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A�ʏ�A�����͉̂�ꂽBenetictus��Magnificat�ɑ���antiphons�Ȃ̂ł���A���d�v�ȏj���ɂ́A������Ȃ������B ��Ƃ��āA�i�܂���������̉��y�ł���jantiphon�@Iste sanctus���A����}���҂̂��߂̋L�Oantiphon�Ƃ��āiLU p262)�A�����Ă���}���҂̐��l���ʓT�當�iCommon of One Martyr �@LU p1123�j�Ƃ��Č���邱�Ƃ����グ�悤�B �G�jLU�ł́A�O�҂́uthe common commemoration of saint for one martyr�v�ł���A��҂ł́ucommon of one martyr�v�ƂȂ��Ă���B��҂̕����i�������j���Ȃ̂ł��낤�B�܂��A��҂ł́AMagnificat�ւ�antiphon�Ƃ����w�肪����B ������antiphons�͓��ɖڐV�������̂ł͂Ȃ��B�Ɨ������`�����g�Ƃ��Ă̎g�p�͋����[�����A�����antiphonal psalmody�̍Ō�̒i�K�ł���A��X�͂�����A�~�T�ɂ�����`�����g�ł�����̂ł���B �@�������ƂȂ������A�S�̐���}���A��antiphons�Ɋւ��đ��݂���B������11���I�Ȍ�ɗR�����A�������ۂ̓T��Ɏc���ꂽ�ƂĂ��Ȃ����Y�I�Ȋ��Ԃ���̐����Ȃ��`�����g�ł���B���Ƃ��Ƃ����̃`�����g�͒ʏ��antiphons�Ƃ��ċ@�\���Ă������A�����͑f�����A���я��Ƃ��Ă̋@�\���������B13���I�܂łɁA�����͌��ݎg����悤�ȏƂȂ�A���̑������̐���}���A��antiphons���̂��I���ƂƂ��ɁA���ł��������ۂ͏I�����邱�ƂɂȂ����B �@��R�͂ň��p���ꂽAlma Redemptoris Mater�́A����}���A��antiphons�����Â��������ۂ�antiphons�Ƃ��Ȃ�قȂ��Ă��邱�Ƃ��͂�����Ǝ�����ł���B���̃e�L�X�g���悢���������łȂ��A��萸�k�ȃZ�b�e�B���O�ƂȂ��Ă���B������L���A���Ƀ����X�}�����F�߂���B �^�������A����̓}���A��antiphon���D�ʂȓT��I�n�ʂāA������l�b�T������ʂ��č�ȉƂ����ɉe���͂��y�ڂ����h�ߑ㐫�h�ł���B���̌�A�����f�B���e�L�X�g�͂����|���t�H�j�[�ƂȂ�A�����f�B�͒P�ƂŁA�����̑����~�T�Ȃ̊�b�ƂȂ����̂ł�B �@���l�b�T���X���̍�ȉƂ͖��炩�ɁAAve Regina��Salve Regina���D�݁A���̂Q��antiphons�́A�����ɖ������Ă����B��������ł͂������AAlma Redemptoris Mater�������Ƃ��l�C���Ă����̂ł���Bhemannus Contractus(1013-54)�ɂ���Ă�������A�����炭�͂S�̃}���Aantiphons�̒��ł͍ł��Â��̂ŁA�����ł͂����Ƃ��m��ꂽ�������̂ł��낤�B �@�����炭�́AAlma Redemptoris Mater�ɑ��钆���̊S�̂����Ƃ������ȏ؋��́A�`���[�T�[��Ƃ����AThe Prioress�fs Tale�ɂ�錈��I�Ȗ����ł��낤�B�����ł͋����[�����y�I���������Ă��Ă���B�`���[�T�[�̓`�����g���A���e�B�t�H���Ɠǂ��A�ނ́Aanthem�Ƃ����p����g���Ă���Banthem�Ƃ����ꂪ�P����antiphon�̉p��Ȃ܂�Ƃ������Ƃ͋����ł���B�@�����v�ȑO�́Aanthem�Ƃ�����́A�}���A��antiphon�Ƃ��Ă̓Ɨ������`�����g���Ӗ����Ă����B �����炭�͂����������R���炩�ALU�̉p��̃��u���b�N�ł́A�}���A��antiphon���hAnthems to the B.V.M�ƌĂ�ł���B������ɂ���A��X�͂����ɁA�ڂ����O���S���A��antiphons����v���e�X�^���g��anthem�̔��W�̂ЂƂ̃X�e�[�W��������̂ł���B GREAT RESPONSORIES ���R�ȃ����f�B�̍ł��P���ȃ^�C�v�A�������ۂ�anthiphon����A��X�͍���A�����Ƃ����G��Great Responsories�i�剞���j�ւƖڂ��ڂ��B����́A���a�A���e�B�t�H���̒P�����Ɣ�r���ċ����R���g���X�g������responsorial psalmody(�������я��j�̓Ƒn�I���ʂł���B��O���琹�̑��ւƉ������ڂ�p�t�H�[�}���X�Ƃ��āA���邢�͐��̑������Z�I�I�ɂȂ�ɂ�A�����͂�萸�k�ɂȂ��Ă������B���ɂ́A������responsories�ɂ����āA��X�����ݒm���Ă���悤�ɁA���a�����ƃ\���X�g��verse�Ƃ̊Ԃ̗l����̋�ʂ͌�������Ȃ��Ă��܂����B verses�́A���Ƃ��Ƃ͉����I�g�[���ʼn̂��Ă������Aintonation(�n���j�Ƃ��̃g�[���̏I�~�莮�͑����I�ł���A�����Ƃ�����verses���������������L�����g�����������Ă���B����ɁA�����莮�͏��a�����ɂ������B�Ō�ɁAverses�͂��ꎩ�g�A���R�ɍ�Ȃ��ꂽ�����f�B�Ŏn�܂�B �@solo responsorial psalmody(�������я��j�̐��k���́A��X��antiphonal psalmody�i�������я��j�ɂ����Ċώ@�������̂Ƃ͈قȂ�A����(�������я��j���Ǘ��\�Ȓ����ɂ�����@�������Ă���悤�Ɏv����B�A���e�B�t�H���̌J��Ԃ��̐������炷����ɁA���т��ꎩ�g���Aresponsories�ɂ�����,�P���verse�Ɍ�������̂ł���B ���h�N�\���W�[�́A���炩��responsories�̂��Ƃ��Ƃɂ͊܂܂�Ă��炸�A��ɉ���������̂����A�����炭��antiphonal psalmody�i�������я��j��͕킵�Ă����B����ł����A�h�N�\���W�[�̑O���\���Ǝq�Ɛ���ɉh������\�݂̂��g���A���ꂼ���Nocturn�̍Ō��responsory�ƍ��ł͔p�~����Ă���Ӊۂ�responsory�ɑ��Ă̂݁A�g���Ă���B �@��X�͂���䂦�Aresponsories�̂Q�̌`���𖾂炩�ɂ���B���respond+verse�A�������respond+verse+���h�N�\���W�[�̑O���A�ł���B���������`���p�^�[���̕����̐����͂������A�ȒP�Ȗ��ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�responds�͈�ʓI�ɁAantiphons���������e�L�X�g��ێ����Ă���A�ʏ�A�R��ނ̂����炩�ɒ�`���ꂽ���y�I�����ɕ�������悤�ɂȂ��Ă���B��������responds��4��ނ̒��������邪�B �S�̂�respond�́Averse�̑O�ɉ̂��邪�A�Ō�̂��̂����͊T���āAverse�̌�ɂȂ�A�h�N�\���W�[������ꍇ�ɂ́A���̌�ɂȂ�B�ȉ��̃��X�g�́ALU�ɂ�����responsories������p���ꂽ��ł���B 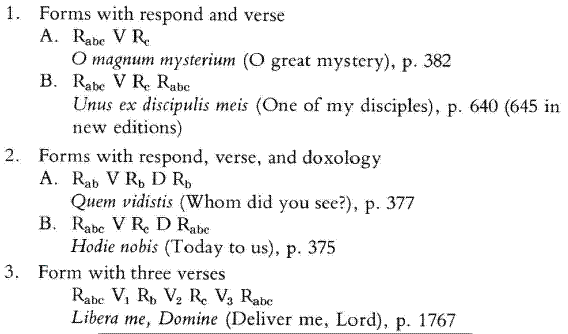 �@���ۂ̓T��ɂ����邱�������`���̗���́Aresponsories�̈ʒu�ɑ傫���˂��Ă���B Form1�DA�G���ꂼ���Nocturn�̍ŏ��̂Q��responsories Form2�DA�G�h�N�\���W�[���A���ꂼ���Noctun�̂R�Ԗڂ�responsories �@ �@Te�@Deum�ɂ��X�Ԗڂ�responsory�̒u������������ƁA�������AForm2�DA�ł�responsory��8�Ԗڂɗ��邱�Ƃɂ���B Naivity��Easter�̂��߂̍ŏ���responsories�́A�h�N�\���W�[�{�S�̂̐q��Ȃ��respond�̌J��Ԃ��̕t���ɂ���āA�ɂ߂ďd�v���𑝂����ƂɂȂ�iForm2�DB�j�BGloria Patri��Te�@Deum�����T�i�A���A�y�j�̊Ԃ̒��ۂł͉̂��Ȃ����AForm1�DB�́A���T��3���Ԃɂ����āA�R�A�U�A�X�Ԗڂ�responsories�ւ̋�ʂ���Ă��ꂼ���Nocturn�ɂ�����Ō��responsory�̏d�v�����������Ă���B ���҂̂��߂̐������ۂɂ�����responsories�ɑ��ẮA��͂�Gloria Patri�͕s�K���ł��邪�A�ʁX�̂��ꂼ��̎菇��Nocturn�ɂ�����Ō��responsory�̏d�v�����������Ă���iForm3)�B�h�N�\���W�[�̏ꏊ�́A�����ł͊��S�ȑ�Qverse�����Ă���A��ɓ����e�L�X�g�ARequiem aeternam dona eis Domine: et luxperpetua lucueat eis�ł���B�`���I�ɂ́A���̂悤��responsories�́A�h�N�\���W�[��responsorie�̃p�^�[���Ƃ͈قȂ��Ă���B �@�Ō�ɁAresponsory Libera me�̓��ꐫ�ɂ��čl���Ă݂����B�����ł͂���ɁA�h�N�\���W�[��responsories�ɂ����āAresponsorial psalmody�̂��Â����@�̖��c�肪���o�����B�����ł́A��������verses��S�̂̎��т��A���a�����ւƕω����Ă���BLibera me�̏ڍׂȌ`���́A�m���Ă̒ʂ�A��菉���̎��H�𐳊m�Ɏ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A���̖{���I�ȍ\�������́A�����炩�ł���B Libera me�͒��ۂ̂��߂�responsory�ł͂Ȃ��A���҂̂��߂̃~�T�ɂ�����͓����ʼn̂���B THE FREE MELODIES OF THE RESPONDS Great Responsories�i�剞���j���h���R�ȃ����f�B�ƌĂԂ̂́A�������̊ϓ_���猩�āA ����Ă���B�����̑����ɂƂ��ẮAcentonization�i�����̃����f�B���g���č�Ȃ����邱�Ɓj�̃e�N�j�b�N�̖��炩�ȗ�Ȃ̂ł���B���̃e�N�j�b�N�́Aantiphons�ȏ�ɂ�薾�炩�ɏؖ�������B�Ȃ��Ȃ�A��蒷���e�L�X�g���ʓI�ȃl�E�}�`�����A�����f�B�莮�����ȒP�ɓ��肳���邩��ł���B�قȂ��������̃e�L�X�g�̍s��K�������邱�Ƃ́A��ɂ���ɂ��A���responsory���瑼�̂��̂ւƂ����ω����قƂ�ǂȂ��W���莮�ł��낤�B ����ɉ����āA�W���莮�͎��R�ɍ�Ȃ��ꂽverse�ɂ�������Bresponsorial tones�̏I�~�莮�Ƃ��ĂƂ��ǂ����a�����ɂ��o�����Ă���B�ӂ��̃Z�N�V�����i�����ƌ����j�̃I���W�i���ȑΏƓI�ȗl���͂���䂦�ɁA��ʂ����������̂ƂȂ��Ă���B �@responsories�⑼�̃^�C�v�̃`�����g�ɂ�����centonization�̏ڍׂȌ����́A�����炩�ɂ����ł͂ł��Ȃ��B��X�́A���ꂼ��̐��@��resonsories���A���ڂɊW�����藣�ꂽ�肷�镪���������Ƃ��čl����ׂ��ł���B���̂悤�Ȍ����͔��ɕ��G�ł��邪�A�����Apel�́A��Q�A��W���@��esponnsories�̕W���t���[�Y�̕��͂Ɍ�����B���A�T���āAresponsories�̓����I�ȃ����f�B�l���ׂĂ݂悤�B �@Great�@Responsories�͑啔���A��r�I�Z�������X�}���܂݁A���������Ŋg�����ꂽ�l�E�}�`���ŏ�����Ă���B�����f�B�̉����9�x������ȏ�ł��邪�A�W���I�ɂ́A�����Ƌ����A�T�`�U�x���x�ł���A�����I�ȓ������ڗ��B �����A�I���W�i���ȃ����f�B��centoniation�̉ߒ��ŒǐՂ���郁���f�B�́A���܂��܂ȓ_�ɂ����āA��_�ł���B�X�̃t���[�Y�͂����Ɖ��悪�L���A�����Ƀ����X�}�I�ł���A�傫�����p�ɂȒ�����A�����f�B�̌`�́A�S�̂̉���ɘa�L��A�f������|���ꂽ�肷��B responsorial style�̐i���́A�l�X�̖����ɑ��ċL�q�����B��X�́Aoriginal�����f�B���A�W���I�ȃt���[�Y������ꂽ�����f�B�����K���V�����A�Ǝ咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ɂ�������炸�Averse��responds�ɂ����鎩�R�f�ނ̑傫�ȗ��p�ɑ���resonsorial tone�̔p�~�ւ̈�ʓI�X���͂���B �����炭�͊֘A�������W�Ȃ̂��낤���A���������X�}�́A��������responsories�ɂ����Ă�respond�̏I���ɋ߂��Ƃ���Ɍ����B���̂悤��responsories�́ALU�ł͂��܂茩���Ȃ����ACorpus Christi��responroeis�ɂ́A�����Ȃ��Ⴊ������(LU p926�`939�j�B�����̂��߂ɁA��X�́ACoenantibus illis(LU p931)�ɂ�����respond�̍Ō�̃t���[�Y�����グ�����B 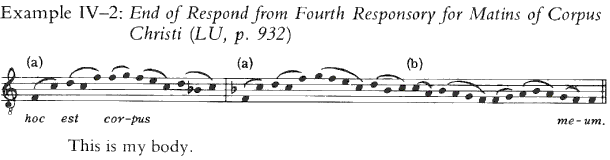 �Ƃɂ����ڗ��̂́A�hhoc est corpus"�ɂ������_���ł���B�����9�x�����܂ł���̂��B����ɒ��ڂ��ׂ��́A�����ȉ��y�`�����`������J��Ԃ��\���ł���B�iaab�j ��X�͂��̂悤�ȉߒ����~�T��Offertories��Alleluias�Ō��o���ł��낤�B �@��S�|�Q�̃����X�}�́A�܂���r�I�ɒZ�����A��������responsories�ɂ����ẮA�������������X�}�I�Ȉ����L���́A���͓I�Ȓ����ɂ܂ŒB���Ă���B��蒷�������X�}�̑啔����responsorial neumata�ƌĂ�Ă��邪�A�ߑ�̐��̏W�ł́A�ǂ�����啝�ɒZ���A�ȗ�����Ă���B�����̑����͖��炩�ɁA�d�v�ȏj���̂��߂̃`�����g�̑������𑝂����߂ɁA���Ƃ��Ƒ��݂��Ă���responsories�ɑ}�����ꂽ���̂ł���Bresponsorial neumata�͂���䂦�A�g���[�v�X�̈��Ȃ̂ł���B SHORT RESPONSORIES LU�ɂ́A3��short responsories(Christe Fili Dei)������B"during the Year�h�AAdvent,Paschal Time(LU,p229-30)�B�g�����̎菇�ɂ����ẮA�قȂ����e�L�X�g�������k�̌ŗL���ŋ��߂�ꂽ�����f�B�ʼn̂�ꂽ��������Ȃ��B �{���I�ɁA���ׂĂ̂R�̃����f�B�́A�������ꂽrecitation�莮�ł���ɂ������A����䂦�AShort Responsories��psalmody�̎��H�ɗR�����邱�Ƃ��m�F����Ă���B�����炭�́A���̕s�K�������ۂ���Ă��邱�Ƃɂ͂����Ƃ��傫�ȏd�v��������A�����炭�͔��ɐ̂ɁArecitation�����͎g���Ȃ��Ȃ����̂ł��낤�B �@�������̓���ȃ����f�B�́AApel�ɂ��A�u�i���̂悤�Ȏg�����́j�P��̃e�L�X�g�Ɍ��肳��Ă���悤�Ɍ�����v�B����͓��j���̎O���ۂ�ShortResponsory�iLU�@p237)�@Inclina co meum�ł悭���������B�Ƃɂ����A�O����recitation�̒莮�ł͂��邪�A����͈ȏ�̂R�̃����f�B�ɂ͊܂܂�Ă͂��Ȃ��B Apel�̌������Ƃ͔��ł��邪�AErue a frama�iLU�@p�Q�R�X�j�͓��ʂȃ����f�B�͎����Ă��Ȃ��B����́A��N��ʂ��Ďg���郁���f�B���g���Ă��邾���ł���B���҂̃����f�B�̊W��AMM�@No.3�Ɍ����邪�AShort Responsories�̌`���������Ă���B �@Christe Fili Dei�́A�h�N�\���W�[��responsories�Ƃ��Ĉ�ʓI�Ɏg��ꂽ�`���ł���B �@�@�@�@Rab Rab V Rb D Rab ���炩�ɁA�召��Responsoriews�́A�����\���p�^�[���������Ă���A���҂Ƃ��A�h�N�\���W�[�̑O�������g���Ă���BShort Responsoris�̂��J��Ԃ��I�Ȑ����́A�^���Ȃ��A�ɒ[�Ȋȑf�Ȍ��ʂƂȂ�B ���ׂĂ̌J��Ԃ��́A�������A�U���ہA�X���ہA���ɂ͂R���ۂɂ����ẮA�����������Ă���Bverse�ƃh�N�\���W�[�Ƃ��܂�Short Responsory�̌`���́A���̌�A�P���ɁAR V D�ƂȂ�B�iLU�@p�Q�S�R�Q�Ɓj�BErue a frama�iLU�@p�Q�R�X�j�Ƃ��ׂĂ̎��̐��߂ɂ�����Short Resonsories�ɂ����ẮA�h�N�\���W�[�͏ȗ�����A���̌��ʂ́ARab V Rb Rab�@�ƂȂ邪�A�����Form 1.B�Ɠ���ł���B�Q�̋�ʂ́A���̒����ƑΏƓI�ȉ��y�l���݂̂ɗR������B HYMNS �̑�ȏ@���͒ʏ�A���q�͎^���̉̂̒��Ŏ��g��\�����霒���I�M���ە�������̂ł���B�L���X�g�����܂��A���̗�O�ł͂Ȃ��B �������A�����ɂ����āA�L���X�g���̎x���҂́A�@�����̐^�̗���𒍂��ł����B���������ʼn�����̃��e����̐��Ȃ鎍�����܂�A��X�͂�����x��܂��Ȃ���A������Hymns�ƕ��ނ��Ă���B ���������̑�Ȑ��ʂ��l������A��������̌����T��ɂ�����hymn�̏d�v�Ȗ����͋����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B����܂Ō��Ă����悤�ɁA�����̐������ۂł�hymn���̂��Ă��邪�A����͌��݉̂��Ă���hymn�̐��������Ă���̂ł͂Ȃ��B �ЂƂ̃e�L�X�g�͑����̈قȂ����@�����A���������ɂ��ɂ����āA���E���ɏo������BLU�͂W�O�قǂ�hymn���܂�ł��邪�A�����̎��ۂ̂��߂̊��S��Antiphonary�͂S�O�ȏキ�炢�����Ȃ��B������̂����Ƃ��L���ȕ�̂ЂƂ��̂ċ����Ă��܂������Ƃ́A�s���Ȃ܂ł���B �@������肵�����A�����hymns�̏��F�ƕs���F�̊Ԃŗh�ꓮ���Ă����B���̕s���肳�́A2��ނ̓G�Ώ̌��ʂł���Ǝv����B ����ł́A�O�m�[�V�X��`�҂₻�̑��ْ̈[�@�h�ɂ��hymn�̎g�p�́A�����݂̂��T��̂��߂ɓK���ȃe�L�X�g��ł���Ƃ����ێ�I�M�O�����߂��B�����ɁA�����̋�����́Ahymns�̐l�C��F�߁A�������L�߂邽�߂̌��ʂ��������B ���ǁAChurch Councils�́Ahymns���̂����Ƃ����݂ɋ֎~���A����������Ȃ��i���������B �������A���������_���́A�����̋���ɂ͂قƂ�lje����^���Ȃ������Bhymns�͂����ɁA�T��ɂ�����x�z�I�A�i���I�n�ʂ��l�������B �����ł͎���قȂ��Ă����B�A���u���V�E�X�����e�����hymns���������ACouncil of Laodicea(c.360-381)�́A���������g�p���֎~�����B���������z����hymns�̎g�p���Ȃ��~�߂邱�Ƃ͂Ȃ��������A�����I�ɓn��A���[�}�T��ɂ���������Ȓn�ʂ͔ے肳�ꂽ�B �������A���[�}�͐����L���X�g���̈�Ɉ�ʓI�ł���������������邱�Ƃɂ͂����Βx���������Ƃ́A���ڂ����ׂ��ł���B �^���Ȃ��A�X�̏@���I�M���̕\���Ƃ��Ă�hymns�̐l�C�̃A�s�[���́A���[�}�T��̏d�v���Ɗ�����l�ԓI�ȑ���������Ɏ���邱�Ƃɍv�������B�������̓���ȃZ�����j�[�������āA���Ƃɐ��T�ɂ����āAhymns�́A�~�T�̓T��ɂ����ẮA�����̋��ꏊ�邱�Ƃ͂Ȃ������B�������A�������ۂɂ����ẮA���̋��ꏊ�͏�ɁApsalmody�̏]���Ƃ��Ďc����Ă����B ����䂦�Ahymns�ƁA�@�����Ɗ֘A�����`�����������y�̗��j�ɂ����ďd�v���������Ƃ������̂͋����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B���݂������A��X�́A�������ۂ̓T��ɂ����Č��o�������̂Ƃ��āAhymns�ɊS�����K�v������B �@���e����̐������E�ɂ�����hymnody�ɂ��Ă̋c�_�́A�A���u���V�E�X����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�ނ��m���������Ɖ��y�̎菇�́A���܂��ɁAhymn�̏��@�ւ̎w������������ł���B �A���u���V�E�X�̎��ォ�猻��Ɏ���܂ŁAhymn�̃e�L�X�g�́A���ׂĂ��������I�\�������A�Z���X�^���U���邢��strophes�ɕ�������Ă���B ���������\���́A����hymn���瑼�̂��̂ցA���������hymn�̂��ׂẴX�^���U�͓������̍s�������A����metrical�p�^�[�������߂��A�C������Γ����C���������Ă���B ����䂦�A�ŏ��̃X�^���U�̃����f�B�[���㑱�̃X�^���U����J��Ԃ����ƁAstrophic�`��������邱�ƂɂȂ�B�������I�\�������X�^���U�������ׂĂ�hymns�����������f�B�ʼn̂��邱�Ƃ�����B�Q�Ȃ�������ȏ�̈قȂ���hymns�ɑ����̃����f�B�̎g�p�́A���݂̎^���́ihymnals�j�Ɠ��l�A�����ł͒ʏ�̂��Ƃł������B �@�P��̃e�L�X�g�ɑ��A�قȂ��������f�B���g�����Ƃ�Apsalmody����b�Ƃ���v���C���`�����g�̂�����^������hymn����ʂ�������ɂ͑����̈ӊO��������B �����́AJustus ut palma�̂悤�Ȑ����̃e�L�X�g�ɁA�قȂ������y���t�����邱�Ƃ����Ă��Ă���B�����������y�̕t�����͂������A�e�L�X�g�������قȂ����T��ʒu�ɂ���Č��肳���B ���Ƃ��Aantiphons�̂悤�ȓT��`���ł́A�����e�L�X�g�ɂ͂قƂ�ǂ���̃����f�B�����t�����Ă��Ȃ��B�����A������hymn�́A�P��̃����f�B���������Ă��Ȃ����Ƃ͌����ĂȂ��B LU�ɂ���������Ƃ����ڂ��ׂ���́ASunday at Compline ,Te lucis ante terminum�ł���BLU�͂���hymn�̃`�����g�ɑ��āA�h�G�߂�j���ɏ]���ĕς�����h�P�Q�Ȉȏ�̃����f�B����Ă���B����hymn�ɂ͂���قǑ����̃����f�B�͌�������Ȃ����A�����̎����ł͂قƂ�ǂ̃e�L�X�g�ł́A���̂悤�ȉ��y�̂������͌����Ȃ��B �����Ԃ�قȂ������R�ł͂��邪�A�~�T�̒ʏ핶�̃e�L�X�g�́A������ނ̉��y�������Ă���B�����ł͂������A���������f�B���قȂ����e�L�X�g�ɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��Bhymns�́A�Ɨ������e�L�X�g�ƃ����f�B�����R�ɂȂ��Ă���B��̃v���C���`�����g�̌`���ł���ƌ����悤�B �@hymns�������Â��錾�t�Ɖ��y�̊ɂ₩�ȊW�́A�����炭�͓T��ɂ�����]���I�n�ʂ�A���̂��܂�͂����肵�Ȃ��N�����猋�ʂł���B �c�O�Ȃ���A��X�́A����hymn�̃����f�B�ɂ��Ă͉����킩��Ȃ��B�킸���ȗ�O�������āA��X���m���Ă��邻�̃����f�B�́A�x���Ƃ��P�P���I�Ȍ�̂��̂ł���B �A���u���V�E�X����ɉ̂��Ă���hymns�̍Č��̎��݂́A����䂦�A���ʂ̗]�n�������A�e�L�X�g�̉����\������b�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�A���u���V�E�X���g����iambic tetrameters�̎��`���ɂƂ��āA�s�͂S�O���[�v���琬��A�^�^�[�^�^�[�Ƃ����Z���V���u���̍\�����琬��B�S�̂̃e�L�X�g�͒ʏ�A���ꂼ��4�s����Ȃ�W�̃X�^���U���܂�ł���B ���I�[�K�X�`���̏،��ł́A�ȉ��̂S�̃e�L�X�g�͖��炩�ɁA�A���u���V�E�X�̍�ł���B�@Aeterne rerum Conditor�@�ADeus Creator omnium�@�BIam surgit hora tertia�@�CVeni Redemptor gentium �����̂����ŏ��������A���[�}�T��Ɏc���Ă���iSundat at Lauds)�B��������X�́Ahymn�̃����f�B�ɊW���Ď����オ���Ă��邳�܂��܂Ȗ���������邽�߂ɂ�����g�����Ƃł��낤�B p�P�P�R �@Aeterne rerum Conditor�̍ŏ��̃����f�B�iAMM No.4)�́A���݂�Roman Antiphonary�Ɏc����Ă�����̂ł���i����hymn��LU�ɂ͏o�Ă��Ȃ��j�B����͒P���ȃV���r�b�N�����ł���A�\�[�������_�ɏ]���A�����������ʼn̂��Ă���B��Q�̃����f�B�͓������P���ł��邪�A�R���q�ƂȂ��Ă���B�����̓e�L�X�g�̒��Z�V���u���ɏ]���Ă���B ���_�A���̉����̐^�����͏ؖ��͂ł��Ȃ����A�A���u���V�E�X���ނ�hymns�����̂悤�ȋK���I�����ʼn̂����ł��낤�ƐM���邱�Ƃɂ͏\���ȗ��R������B ���ǁA�����͉�O�̉̂Ƃ��ē������ꂽ�̂ł���A����䂦�ɁA�̂�����o���邱�Ƃ��ȒP�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���y�Ǝ��̉����̊W�͓��ɁA�V���r�b�N�`���ƌ��������ꍇ�A�������������ɑ傫���v�����邱�Ƃł��낤�B �@��X�̓L���X�g�҂̍ŏ���1000�N�̖��w��l�C�̂��������y�ɂ��Ă͂قƂ�ǖ��m�ł���B����͑��݂��Ă����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂ł��邪�B �@��X�͂܂��A���w���y�͒P���Ń��Y�~�b�N�ȃX�^�C���ł������ł��낤�Ɖ��肵�Ă���B������hymns���A�����ȂƓ��l�ɉ̂�ꂽ���Ƃ́A���蓾�Ȃ����Ƃł͂Ȃ������ł��낤�B�m���ɁA���������ߒ��͉��y�̗��j�̂���̊��Ԃł͏\���Ɉ�ʓI�ł������B�����Ȃ͂܂������A�����̒����ʼn̂�ꂽhymn�ɑ���G�ӂɖ����Ă����̂�������Ȃ��B������ɂ���A����ʼn̂��Â����P����hymn�̉��y�́A�����炭�́A�����̐��������f�B�[�ɍł��߂��A�v���[�`�����Ă������Ƃł��낤�B �@�A���u���V�E�X�́A�ÓT�I���e���ꎍ�̒��Z�V���u�������Ȃ蒉���ɕۂ��A�����Ă����ɁA�ނ�hymn�́A���R�ƂR���q�ɗ��������̂ł���B�A���u���V�E�X�̎���ł����A���e����̃A�N�Z���g�̊�Ղ́A���Z���狭��V���u���ւƂ����ڍs���n�܂��Ă������A���̂Q�̃V�X�e���͕K��������v�����Ă��Ȃ������B ����́AAeterne rerum�̑�Q�s�ɂ����Č�����B�����ł͋������e�L�X�g�ɂ����āA�Z�������ƂȂ��Ă���B �Q�̃V�X�e���̊Ԃ̂��̊������A��̎��l�����������邩�ǂ����A���邢�͔ނ炪�A���u���V�E�X�������ӂ��ѐ��ɑ���Ȃ��������ǂ����ɂ�����炸�A��������hymns�́A�����ȋK���������̉������ێ����邱�Ƃɂ́A�����Ύ��s���Ă���B �������������̈�E�́A�P����������邽�߂ɓ������ꂽ���A���l���������Ƃ��Ƃ́A���ꂼ��̍s�ɂ�����V���u���̐����������ێ����邱�ƂɊS�������Ă������Ƃ����������Ă���B �����̒�����hymn�̍�҂�����isosyllabism�i���ꂼ��̍s�ɓ������̃V���u�������j�Ƃ��Ēm���Ă����쐬������m���Ă����\���͏\���ɂ���BSt.Ephraim(306-373)�ɂ��V���A��hymn�́Aisosyllabism�ɌŎ����邠�܂�A���Z�V���u���ɂ��쎍���̂ċ����Ă����B��Ɍ���悤�ɁA�����������A�t�����X�̍쎍�ɂ����Ă͂܂�̂ł���B �@���������T�ϓI���W�̌��ʂƂ��āA�����hymn�̃e�X�g�ɑ���K���I�������̗p���邱�Ƃ�����ɍ���ɂȂ��Ă����B���ɂ����鉹���̕ω��́A���y�̂����݂����������A�A�N�Z���g�̈ʒu�́A����X�^���U����ʂ̃X�^���U�ւƈڍs�������B����ɁA����̒萫�I�A�N�Z���g�����ʂ̊��p�Ƃ��Ċm�������悤�ɂȂ�A�����̉̎肽���́A���Z�V���u���ɂ��쎍������悤�ɂȂ����B���傤�ǁALU�����݂������Ă���悤�ɁB ��X�͂ނ��A�O���S���A���`�����g�̃��Y���̖��ɖ߂��Ă������A���̊�b�͊댯�ł���A�����͕s�m���Ȃ̂ł���B�����炭�������Ahymn�̃����f�B�̓v���C���`�����g�̂���Ɠ����^�����o�������B�����̉��̘A���ւ̑I�D�ɂ�钷�Z���̕����ł���B ���̉����͂₳�������A�i�ʖʔ������̂ł��Ȃ��A�ЂƂ�hymn�̈قȂ����X�^���U�ɑ��āA���邢�͈قȂ���hymn�ɑ��ĂЂƂ̃����f�B���g�����Ƃ̍������菜�����Ƃł���B �쎍�̃V�X�e����ʏ�̉����p�^�[������̈�E�́A�d�v�ł͂Ȃ��B���ꂼ��̍s�̃V���u���̐��������͈ێ�����Ȃ���Ȃ炸�A�����f�B�̂킸���ȉ���ł��A���̂悤�ȗv������̈�E�ɑΉ����邱�Ƃ��ł���B �@�@�����̌��hymn�̃����f�B�̉��y�l���͂܂��A����A�����̉����ɂ�鉉�t�����y���Ă������Ƃ������Ă���BAeterne rerum Conditor(AMM No.4)�̃V���r�b�N�Ȑݒ�ɑ���A�����̃V���u�����Q�A�R�A���邢�͂���ȏ�̉��������ĉ̂��邱�Ƃ����o�����B �����������k�ȃ^�C�v�́A�~�T�̃`�����g�ł��܂�������̂����A���t����O����P���������̑���E�҂ւƈڂ������Ƃɂ������I�Ȍ��ʂȂ̂ł���B ���̗�Ƃ��āAprocessional hymn Vexilla Regis�̌��݂̉̂����������Ă݂����i��S�|�R�j�B����hymn�̂Q�̊ϓ_���L����Ă���B��Q�s�̋����V���u���iFulget Crucis)��iambic�ȍ쎍����n�܂��Ă���B�����āA�A�N�Z���g�̂���i���邢�͒����j�V���u���́A�P�`�T����i���Ă���B 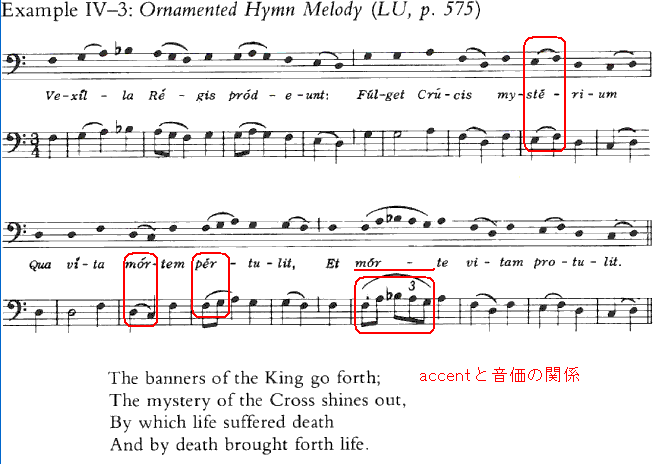 ����߂Ė��炩�Ȃ��ƂɁA�e�L�X�g�̖�肩�琶���Ă��鉹���̉��t�̍���́A�����f�B�̑����I�`�Ԃɂ���Ă���ɑ������Ă���B�R���q�����̂܂ܓK�p����A�Z���V���u�����A�Ō�̍s�������āA�P�̉����ȏ�ɓ��Ă��邱�Ƃ͋H�ɂȂ��Ă���B ����́A�����鑕���I��hymn�ɂ��Ă͐������͂Ȃ����A�����̑����́A�U���̃e�L�X�g�Ɍ����l�E�}���̃A�v���[�`�����Ă���B �e�L�X�g�̎��̍\���Ɏ����邱�Ƃɂ���āA�������̉��t�́Ahymn���̂��傽��ړI�̈�������A���[�}����ɂ��ŏI�I�̗p�ւƓ����ꂽ�̂ł���B �����������ׂĂ͂������A���_�ł���B�v���C���`�����g�̂�����^�C�v�ƂƂ��ɁAhymn�̃��Y���̉��t�́A�i���ɘ_���̓I�ł���˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@�Ō�̌��t�́Ahymn�̃����f�B�̌`���ɂ��Č�����ׂ��ł���B�S�s�X�^���U��hymn�̃e�L�X�g�ɑ��Ă͂����Ƃ���ʓI�ł���悤�ɁA�����f�B�͒ʏ�A�S�̈قȂ����t���[�Y���琬��B�`���Ƃ��ẮAabcd�ƂȂ�B���̌`���́A���Ɉ�ʓI�Ȃ̂ŁAhymn form�Ǝ��ɌĂꂪ�AAMM No.4�̍ŏ��̃����f�B�ɂ���Đ��������B������abcd�`���ł��邪�A���̑�P�C�Q�C�S�t���[�Y�͉��y�I�C�̎g�p�ƊW���Ă���B���y�I�C���Y����������I�ȏI�~�́A�����ɂ����Ă����Ƃ���ʓI�ȍ\���I�H�v�ƂȂ��Ă���B �@��S�|�R�̃����f�B�́A�������������ł́Aabcd�`���̂悤�Ɍ�����B�������A���ڍׂɌ���t���[�Y�Q�C�S�͂W�̃V���u���̂����̂U������ł���B�t���[�Y�̊��S�Ȃ��邢�͕����I�ȌJ��Ԃ��́A�ق���hymn�̃����f�B�ɂ��Ȃ��Ă���B�����Ƃ���ʓI�ȌJ��Ԃ��p�^�[����abca�ł��邪�Aaabc,abab,abcb,abba�Ƃ������p�^�[�������o�����B �@���������J��Ԃ��`����hymns�ɂ����Ă͋H�ł͂��邪�A�J��Ԃ��`���͔��ɏd�v�ȈӖ������������Ă���B�����́A��T��I�ȁA���e����̂�g���o�h�[����g�����F�[���̐����̂ɍēx�����������ƂɂȂ�B���������`�����A�ǂ��Ń��m�t�H�j�b�N�\���O�̂ЂƂ̃N���X����ʂ̃N���X�ւƔ��W����s���N���Ƃ����̂������肷�邱�Ƃ͕K�������\�ł͂Ȃ��B���ꂼ��̃N���X�͑��̂Q�̃N���X�ɉe����^���Ă���B�Ƃɂ����Ahymn�̃����f�B�ɂ�����J��Ԃ��`���̑��݂́A����炪���̂����ł͉i���Ɏ����Ă��܂����l�C�̂��������y�̓`�����珜������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ēx�������Ă���B |