| Machaut's Mass�Q�@Daniel
Leech-Wilkinson |
| 2 CONSTRUCTION
2.3 Gloria and Credo 2.3.1 Introduction The Gloria and Credo score Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image �O�����A�ƃN���h��,��i�̒��S���s��������2�̋���Ŗ��炩�Ɋ֘A�����y�͂ł���A�ꌩ�A�}�V���[�̃~�T�Ȃ̂��̑��Ƃ͂��ƂȂ��Ă���悤�Ɍ�����B����ɂ�������炸�A���y�I�\���ɑ��鋤�ʂ̏́A�T�O�I�ɂ́A������C�\���Y���̊y�͂ƌ������N���Ă���B �����āA��4�͂������悤�ɁA���ʂ̃n�[���j�[�I�Ȍ��t�́A���y�I�ɂ��A���@�I�ɂ��֘A����Kyrie�����łȂ��ASanctus�AAgnus�AIte�Ƌ��ɁA�����ׂ����x�Ɍ��т��Ă���B �@Gloria��Credo���P�Ȃ�\��������Ă��Ȃ��a���̈�A�ł͂Ȃ��A�����ꏭ�Ȃ���A�ړI�Ȃ��̃e�L�X�g�̃V���u���Ȑݒ�ł������Ƃ́AOtto Gombosi�ɂ���āA1940�N��I���ɏo�ł��ꂽ3�̃p�C�I�j�A�I���q�̃��r���[�ɂ���āA�ŏ��Ɏ����ꂽ�B22 22�@Otto Gombosi�C�e Machaut' s Messe Notre-Dame' �C MlIsical Qllarterly �C 36 ( 1950) �C��20 4-24 Gombosi�́AGloria��Credo���\���I�ɃX�^���U�l�ł���Ǝ咣���A�e�y�͂̒��̊e�߂͍L���ގ������f�ނō\������A���ꂼ�ꂪ�����p�^�[���̑��̂��̂Ɠ����ł���Ǝ咣�����B�ނ̕��͂̏ڍׂ̂������́A���W�����ꂽ���A �ނ̕s���ȓ��@�́A�����炭���̓��ʂȎd���ɂ��ĂȂ��ꂽ�ł��d�v�Ȕ����Ƃ��ėL���ł���B 2.3.2 Gloria Gombosi�́AMachaut��Gloria�ɂ����āA4�̃X�^���U����肵���i��������I-4����,�@I ��5�|29���߁AII ��30- 56���߁AIII ��.57-83���߁AIV ��84-I04���߁j�B ����ɁA�����̏I���J�f���c�ɂ���Ē�`���ꂽ3�́u double perio���v�ɂ��ꂼ��ו������B 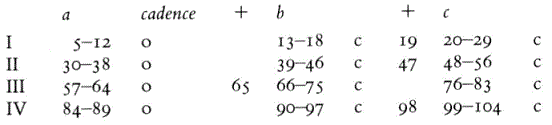 ���ꂼ��̃X�^���U�ŁAGombosi�́Aouvert-clos-clos�J�f���c�i�e�[�u����0��C�j�̍���ɂ���p�^�[�����������B�����ł́Aclos�i�����͒����̗p�ꂾ�����j�́A���@�̏I�~�̃J�f���c�ł���A���̏ꍇ�̓����ł���Aouvert�͕ʂ̉����Łi�̏I�~�j����i�����ł́A�~���邢�̓h�j�B ��i�́A�܂��A2���i1���߁j�p�b�Z�[�W�ƂȂ��Ă���B�㐺�����x���ł���ԁA���̐����̓����f�B�[�I�ɒP���� Gombosi�̏I�~���̃J�f���c�̑I���́i�����āAperio����span)�A���ꎩ�̘_���I�ł͂��邪�A���ۂɂ́A�ނ̃X�^���U���T�u��������ނ���قȂ���������������y�f�ނ́A�d�v�ȌJ��Ԃ��������Ƃ��Ă���i��T�j�B 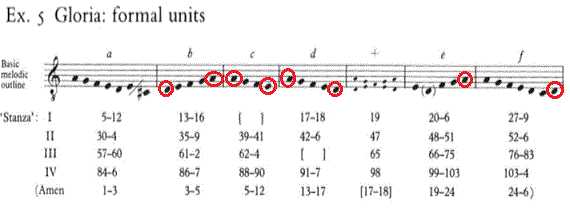 ���̃X�L�[���ł́A6�̃T�u�Z�N�V�����ua '-f�v�́A�J�f���c�^�ł͂Ȃ��A�����̃����f�B�[�I�n�[���j�[�I�A�E�g���C���ɂ���Ē�`����A���ԂɈ�т��ČJ��Ԃ����B 'a'�̑f�ށA 'a����c'�ւ̍~�������f�B�[���C���́A�ł��P����III�A��57�|60���߂Ɍ����B  ��57�|60���� ��57�|60���������āAII�̑�30�|34���߂ł́A����������Ă���B  ��30�|34���� ��30�|34��������ɁAI�̑�5�|12���߂ł́A��蒷�������iIV�ɂ����ẮA'a'��'���f�́A�o���Ƃ��A��O�I�ɒZ�k����Ă����j�B 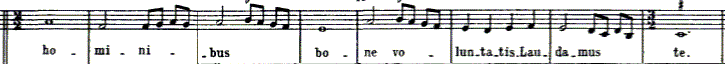 ��5�|12���� ��5�|12�����T�u�Z�N�V�����ub�v�̓������烉���ɏ㏸����B 'c'�̓�������~���ɁA' d '�̓������� ���I'�ɉ��~����B �T�u�Z�N�V�����ue�v�͍Ăу����ɖ߂�A�uf�v�͏I�~�������ɖ߂��B ������̏ꍇ���A�n�[���j�[�̊T�ς́A�i�K�R�I�Ɂj�㐺���̃s�b�`�̕⋭�Ɉ�ѐ�������B �����������߂̑��̓_�ł̋��݂́A�����N�I�ȏ����i��Ɂud�v�̌�j�̈�ѐ��̂���z�u�ł���A��ȉƂ̊ϓ_����ł́A���̂悤�Ȕ�r�I�P���ȉ��y���j�b�g�̊Ǘ����ł���B���ꂼ�ꂪ�Z���ĊȌ��ł���B ���̊�{�I�ȗ֊s�́A�ݒ肳���e�L�X�g�̗ʂɉ����Ď��R�Ɋg�����邱�Ƃ��ł���B �Ō�ɁA 'c'�� 'd'�̓���̍\���v�f�́A�e�L�X�g�̗ʂ��K�v�ɉ����āA�S�̂̉��y�\����ς���悤�ȓ���Ȃ����Ȃ��ŁA1�܂��͗����̃T�u�Z�N�V�����̎g�p�������Ă���B �@�}�V���[�͂ǂ̂悤�ɂ��̃X�L�[���Ɏ������̂��H Gombosi�ɂƂ��Ēm���Ă��Ȃ��d�v�ȗv�f���AGloria���A�ɂ₩�ł͂���Ȃ���AKyrie��Credo�Ɠ��������N�̍ՓT�Ɋ֘A�����A�ł���ʓI�Ɏg�p����Ă���Gloria�̃`�����g�Ɋ�Â��Ă����Ƃ������Ƃł���B ��6�́A�`�����g�Ɍ��y�����Ǝv���邱���̃p�b�Z�[�W�̉��ɁA���̃����f�B�̂R�̌����̔ł������Ă���i�����̂��ׂẮA�}�V���[�ɂ͐��m�ɂ͒m���Ă��Ȃ������j�B�����Ƃ��͂�����Ƃ��Ē������y�́A�����Έꂩ������ʂ̌��ւƎ��R�ɓ����A�}�V���[��Contratenor ��tenor�ɐ����Ă���悤�Ɍ�����B���̊ԁA���Z���c��́AMotetus��Triplum�ɐ����Ă���B ���̗�Ō����Ă��邱�Ƃɂ��āA���邢�́A��ȏ�̎菇�́A��3�͂Ŏ�����Ă���B���ʂ́A�Q�̓_�������������B ��P�ɁA���̊y���iGloria�j�́AKyrie�̂悤�ɁA �v���C���`�����g���g���e�m�[�����k�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�`�����g�́A�����̏ꍇ�A�e�N�X�`���̂ǂ����ɂ����悻�ł͑��݂��Ă������A�����̏d�v�ȓ����́A���ɂ��̃����X�}��J�f���c�ɂ����ẮA�����Δ������Ȃ��قǂł���B���ׂẴ`�����g�̃J�f���c�́A�I�~��'patris"���̂����āA�~���ƂȂ邪�A�}�V���[�́A�����ւ�clos�J�f���c�̋K���I�g�p�����Ă���B���炩�ɁA�ނ̃|���t�H�j�[�̂��߂ɍl�Ă��ꂽ�n�[���j�[�\���́A�`�����g�̐����I�ȓ��e�����D�悳���B ��Q�ɁA����Ɋ֘A���āA��������㐺�����f�B���C���ƃ`�����g�̌`���i�܂��͎g�p�j�Ƃ̊Ԃɂ͖��m�ȊW�͂Ȃ��B�\�Ȍ���A�`�����g�̃s�b�`��������邱�Ƃ͂ł��邪�A�}�V���[�́A�ނ̃|���t�H�j�[���`��邽�߂ɍl�Ă������ۓI�Ȍ`���\���ɗD�揇�ʂ�^���Ă���B �@�����ȍ\���ɍ��{�I�ȍ���������Ȃ�A����̓e�L�X�g�Ƃ̊W�ɂ����Ăł���ׂ��ł���A����́A�}�V���[���g�����e�L�X�g�ł������ɈႢ�Ȃ��B ����͂������A�U���ł���B���y�̌`�Ԃ��������锽���I�ȗʂ�C�̔����͂Ȃ����A�B �ނ̖ړI�̂��߂ɏd�v�Ȃ��̂Ƃ��ă}�V���[�ɗ^����ꂽ1�̔����I�ȃt���[�Y�́A'ihesu christe"�ł���A�O�����A�̃e�L�X�g�̎�v�ȃA�C�f�A�ł���A���R�ɂ��A�Ōォ��18�V���u���ŏo�����Ē��S�_�ɑ��āA�ł��߂����@�I�ȃu���[�N����18�V���u���ƂȂ��Ă���B �����̌��t�ɗ^����ꂽ���ʂȉ��y�I�����́A����炪�}�V���[�̍ŏ��̍l���ɂ��������Ƃ��������Ă��邩������Ȃ��B ���������Ȃ�A����́A�}�V���[���ނ̐ݒ�ɂ����ĂQ���q�\����^���������ƂȂ邩������Ȃ��B �@�e�L�X�g����X�Ȃ���@������ƁA�}�V���[�́A�e�L�X�g�̍ŏ��̔�����14�̍\����̃��j�b�g���琬�藧���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ă����B�㔼��12�̍\�����琬�藧���Ă���A�قړ����ł���B
����͏d�v�Ȃ��Ƃł���B�Ȃ��Ȃ�A����͑�܂��ȃV���u���ݒ�iMachaut�̍ł������̌���̂P�ł������͂��̂��́j�ł���A�e�L�X�g�t���[�Y���A���y�t���[�Y�Ɩ��ڂɊ֘A���Ă���Ƃ������肩��n�܂邩��ł���B ��i�́A�����̒Z���A�����炩�ɒ�`���ꂽ���y�P�ʂɂ���ē����Â�����ł��낤�B�����āA�e�L�X�g���_���I�ɔ����ɕ�������Ă���A'ihesu christe"�̏ꏊ�Ń����N����A����ɁA�����������y�t���[�Y���܂��A���ʓI�ɍ�i�̔����̊ԂɑΉ�����\����������B �@����Ȃ�e�L�X�g�\���̋��R�̈�v�́A���ꂼ�ꔼ�����A�Ӗ��_�I�ɂ��A�قړ�����2�������s����Ƃ������Ƃł���B�ȉ��̂悤�ɁB 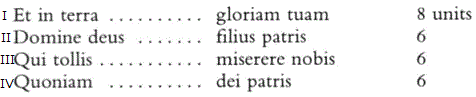 ������1�̍\���P�ʂ́A��L�̂悤�ɔz�u���ꂽ�e�L�X�g��1�s��Machaut�̐ݒ��1�̉��y��ɓ������B ��P�A�R�̃Z�N�V�����̕s�K�����i6���j�b�g�ɑ���8���j�b�g�j�́A�S�̂Ƃ���8�̃t���[�Y����邽�߂ɁA�Z�N�V�����R�i�e�L�X�g�Ɂ����t����Ă���j��2�̃��j�b�g���Q�ɕ����邱�Ƃɂ���Ă��̕s�K�������Ȃ��Ȃ��Ă���B �@����ɂ�������炸�A Machaut���A�ނ̖{���I�ȉ��y�Ƃ���6�̃����f�B�[�\�n�[���j�[�T�ρia����f�ցj�����e�L�X�g��6���j�b�g�Z�N�V�������s���n���Ă��邱�Ƃ͂��蓾��悤�Ɍ�����B correspondence�́A�Z�N�V����II�ƃZ�N�V����IV�ōł����m�ɑ�������i�����̓}�V���[���s�ϓI�ɂ��ꂼ��6�̃e�L�X�g�P�ʂŎc�����Z�N�V�����Ȃ̂ŋ����ׂ����Ƃł͂Ȃ��j�B ���������āA�P�e�L�X�g�P��= �P���y�t���[�Y�i�e�L�X�g�A���Y������уJ�f���c�ɂ���Ē�`�����j= �P�����f�B�[�\�n�[���j�[�T���́A�}�V���[�̃Z�N�V����II�̐ݒ�ł́A�w�ǕύX���ꂸ�Ɉێ������B 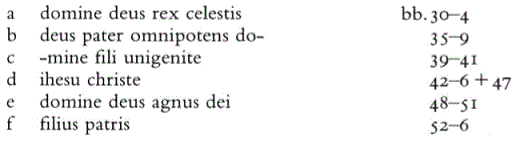 �@����A�Z�N�V����I��III�́A�K���I�ݒ肩��͂��Ȃ肩������Ă���B�����Ă����炭�A�}�V���[�͉��y�̕ύX���[�g��ς��邱�Ɓi�e�L�X�g�Ɖ��y�̂��܂��܂Ȋϓ_�̊Ԃ̊W��ς��邱�Ƃɂ���āj�ɊS���������悤�Ɏv����B���̒��g�́A��{�I�ȂS�~�U�̉��y�v�悪�A�h�C�\���Y���I�h�ȋK�������Ȃ��Ă��A�\���@�\����悤�ɁA�ł���B �@�h�C�\���Y���h�̗ގ����́A�S�̓I�ɁA�B�g�I�ł͂Ȃ��B���炩�ɁA�S�̃Z�N�V�����`���A���ꂼ��̃Z�N�V�����́A��{�I�ɓ���̑f�ނ������Ă���i�\�ʂ̏ڍׂ̕ψقɏ]���j�A�S�̃R�����̃C�\���Y���\���ɔ�r���꓾��B�����āA���ꂼ��̃Z�N�V�����̏I���(�fe,f)�Ɍ������āA�����f�B���^�ƃn�[���j�[�i�s�����̑��A���Ȃ킿�Af�f�ނ������m�ɋN���邱�Ƃ́A���ڂ��ׂ��ł���B �@  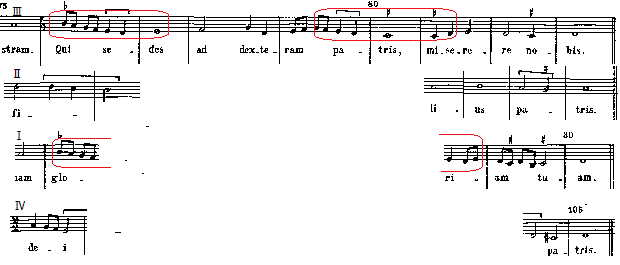 ������ �@�\�ʑ����ɂ���Ċg�傳���ׂ��ua�v - �ud�v�̑f�ނł͂��邪�A���y���e�Z�N�V�����̏I���ɋ߂Â��ɂ�āA�ue�v�Ɓuf�v�͑}���ɂ���Ċg�������X��������A ���̃n�[���j�[�ƃ����f�B�̏ڍׂP���Ă���i��L�̕\�ł́A�t���[�Y���c�ɕ��ׂăX�R�A���r���Ă���j�B ����͂����ƋL���Ɏc����̂ł���A���e�b�g�E�^���A�̏I���߂��ŕp�ɂɎg�p�����hocket�̂悤�ɁA���X�i�[�ɂƂ��Ė{���I��,�A�`�������ߓI�Ȑ������������Ă���B 'ihesu christe"�̐ݒ�́A���ȓI�ɐL���������ŁA���傫�ȃX�P�[���ł̓������ʂ�����B 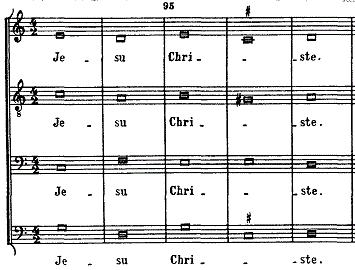 2�E3�E2.1�N���[���A�E�A�[���� �A�[�����́AGloria�y�̖͂{�̂������R�ɂ��̎Q�l�Ƃ����`�����g�����R�Ɏg�����Ƃ��ł��邪�A�v���C���`�����g�̂`�������̊�{�I�ȃ����f�B�̊T�ς́A�}�V���[�̃e�m�[���̃��\�t�@�~�����^�ɂ����܂��Ă���B �����āA���Y���l���ł́A�j���������Ȃǂ̃C�\���Y���̊y�͂Ƌ�ʂ����Ȃ����̂́AGlori a Amen�͎��ۂɂ͌����ɂ̓C�\���Y���ł͂Ȃ��B ���̍�i�́A�^���A�ł͂Ȃ��A2�̑ΏƓI�ȃZ�N�V�����ō\������Ă���B�ŏ��̂��̂́A�قڊ��S��breves��longs�����ō\������Ă���i���ɁA�e�p�[�g�ŏ��Ԃɑ�6-11���߂ɔz�u����Ă���j�B�㔼�̑�15-26���߂ɂ́A�����̒Z���������܂܂�Ă��āA�����V���R�y�[�g��z�P�g�D�X�̌`�ɔz�u����Ă���̂ŁA���̂��߂ɁA��i�̌㔼�́A�C�\���Y�����e�b�g��integer valor�i���f�̃e���|�j��k��Z�N�V�����Ɍ��y���Ă���悤�Ɍ�����B �@��i�ɂ����Ă͈�ʓI�ł͂Ȃ��A�l���ɂ�����C�\���Y���́AContratenor �ł���A�����銵�K�ɔ����āA����͍ł������ȃ��Y���������A����������4�̃p�[�g�����ł����Ƃ����̑��������������Ă���B�����āA�����̕s���a�����Y������̂��AContratenor �ł���B���������_�ł́AMachaut�̃��e�b�g�̂�������A�ނ̉� �i����I363�N��Voir Dit �̈ꕔ�Ƃ��č�Ȃ��ꂽ���́j�̂�ontratenor���ɍ������Ă���B �@��5���������Ă���悤�ɁA�`�������̃����f�B�\�����A�y�͂̎�v���̃����f�B�\����ʂ��āA���邢�͂`���������T�̃X�^���U�Ƃ��ė������邱�Ƃ͉\�ł���B Gloria�̑�1-4�y�͂�Gloria�̂`�������̑�1-5�y�͂Ƃ̊Ԃ̊֘A���͂��͂����肵�Ă���B�����āA���ꂼ��̃Z�N�V�����̍Ō�A Gloria�̑�100-4�y�͂Ƃ`�������̑�21-6�y�͂̊Ԃɂ́A�S�̂Ƃ��ẮA�e�Z�N�V�����̋����A�[�L�e�N�`���[�I�Z���X���w�E�ł��悤�B 2�E3�E�R.�b�������� Credo��Gloria�̍\�z���r����O�ɁATournai Mass��Credo�Ƃ̊W�ׂ邱�Ƃ��d�v�ł���B����́A�}�V���[�̂��̂قǂɂ͈�ۓI�ł͂Ȃ����A ���炩�ɐl�C�͍����B�Ȃ��Ȃ�A4�̌��T���������A�����̂����S�́A13���I�̂�菉���ɂ��̋N��������ł��낤�암����̂��̂�����ł���B ���̃z�����Y���I�l���Ɠ��l�A�����̒��ڂ��ׂ����̗ގ����́A�����̍�ȉƂ̗p����reduced-voice"link passages'�ɂ���B����́A�܂�A�`���̓���ƒ�`�Â�����B���̓����́A�ނ��A�}�V���[���f�����������ɂ����č̗p���Ă���B�����ATournai Mass�́A�K�������AMachaut�̃\�[�X�ł���K�v�͂Ȃ��A�ގ��̃p�b�Z�[�W�́A14���I�̃~�T�ȂɈ�ʓI�ȃ��p�[�g���[�Ƃ��ċ��ʂ��Ă���B���̂��߂ɁA�����������̂��g���Ȃ���A�}�V���[�́A�͂����炭�A�����̓`���Ɍ��y���Ă������B���̓������̂��A�����炭�́A�s���������������`���ł̃~�t�@�~���h�̉��^�Ɍ�����B����́A���̑��̂������̂b���������ݒ�ɂ����Ă�������B �}�V���[��Tournai Mas�����`�����g���p���t���[�Y���Ă��邩�ǂ����ɂ́A�_��������B�^���Ȃ��A�����̐ݒ�ł́A���݁A�b���������h�Ƃ��Ēm���Ă���`�����g���g�p���Ă���B�����Ƃ����炩�Ȃ̂́A�~�t�@�~���h�̖`���ł���B��т����p���t���[�Y�����肳���K�v�͂Ȃ����B�ǂ̍�ȉƂ��A�s��I�ɁA���̃����f�B���^���e�L�X�g�ɐݒ肵���ł��낤�b���������h�ɂ͐��ʂ��Ă����ł��낤���A�����łȂ������Ƃ��Ă��A�����ɂ͂�����Ȃ��B �@�}�V���[��Tournai Mas���̐ݒ�ւ̌��y�̔w��ɂ́A�����������ʂ������炭����̂��낤�B�sournai Mas���̈�т����g�p�͌����Ȃ����A���̃����f�B�I������n�[���j�[�i�s�́A�S�̓I�ɁA�\�����ʊ����ŏo�Ă���B���ɂ́A�}�V���[�ɂ����Ă��Ⴂ�g�[���ŏo��������A�قȂ����e�L�X�g�ɏo�������肷��B ����͂��ׂāA�}�V���[���A�sournai Mas���̃��f����̌n�I�ɍė��p���Ă����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ��݂̉��y�ƃe�L�X�g���֘A�t����K���ɂ���Ă������Ƃ������Ă���B�������A�����̗ގ��_�ɂ�������炸�AMachaut�̐ݒ�̂قƂ�ǂ́A�ł���ۓI�Ȑ����ƃn�[���j�[�̂���W�F�X�`���[���܂ޑS���V�������̂ł���B�L�ߌ`���͂������A���ׂĔގ��g�̂��̂ł���A�B�ނ̈ӎ��I�ȍ�Ȍv�悪�n�܂�������ł������ɈႢ�Ȃ��B �@Machaut��Credo�̂R�̃Z�N�V�����́A�y�[�W�߂���ɑ����f��d���h�ɂ���āA�ʖ{�ɂ͂�����Ƌ���Ă���B�����炭�́A���̃y�[�W�߂���́A�x�~�����̌�ɈӐ}����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����A�y�͂̂��傫�ȍ\���𖾂炩�ɂ��Ă���B ������3�̃Z�N�V�����̂��ꂼ��̒��ŁA3�̃T�u�Z�N�V�����́A��3����1��3����2�̊Ԃɔz�u���ꂽ�elink passages�h�ɂ���ċ���Ă���B �����̂��ׂĂ̌`���I�����́A�e�L�X�g�̍\���Ɋ֘A���Đ����\�ł���B �@Machaut�̐ݒ�Œ�`����Ă���3�̎�v�Z�N�V�����ɂ́A���l�̗ʂ̃e�L�X�g�iI07�F132�F118���߁j���܂܂�Ă���A�Ӗ��I�ɂ͘_���I�Ɏ��Ȋ������Ă���BMachaut���Z�N�V����II���uet incarnatus est�v�ŊJ�n���Ă����Ȃ�AMachaut�́A�����Ɠ����������̃Z�N�V�����i128�F111�F118���߁j�Ƃ��Ă����\�������������߁A���̌�҂͍ł��d�v�ȗv���ł������B �ނ́A�����Ƃ��_���I�ȃe�L�X�g�̕�����������߂˂Ȃ�Ȃ��������B �@�ނ̑I�������T�u�Z�N�V�����́A���͂̒��̘_���I�ȈӖ��l�ɒ��ׂāA�e�Z�N�V������ʂ��Ė�3����1��2/3�ɕ�������K�v������B ���̊�̗B��̈ᔽ�́A'secundum scripturas'�ł͂Ȃ��A 'dexteram patris'�̂��Ƃ�II�D2��II�D3�̊Ԃ̃����N���߂�u���Ă��邱�Ƃł���B �������A���̌���v���́A�e�L�X�g�ɂ�����uet iterum venturus est�v�ł̎��́A���ɖ��m�ȕύX�ł������悤�ł���B ���炩�ɁACredo�̃��b�Z�[�W�̓}�V���[�̌`������ɂƂ��Ċ�{�I�Ȃ��̂ł������B �@���l�ɁA�ނ��ݒ肵���n�[���j�[�I�\���́A�e�L�X�g�̕��͍\���ɑS�ʓI�Ɉˑ����Ă���悤���B ��̈�����ꂽ�e�L�X�g�̖��́AMachaut���s���S�J�f���c��ݒ肵�A�����̂��߂Ɏ��̃t���[�Y�ɓ����ꏊ�������Ă���B �قƂ�ǂ̏ꍇ�A�����͕��͂̕��@�I�A�����ƈ�v���邱�Ƃ��킩��B �@����́A�Z�N�V�������ƂɌJ��Ԃ����J�f���c�p�^�[�����A�e�L�X�g�̕��@�\���ɂ�������R�̌��ʂł���A�����̉ۂ��ꂽ���ۓI�Ȍ`���I�\������̌��ʂł͂Ȃ��B ����͂����炭�A�Ȃ�Gombosi'�̃t���[�Y��labellings�����ɐ����͂��Ȃ��̂���������Ă���B�F�ނ�I.1.���i��1-5���߁j�AII�B 1.���i��.55 -61���߁j��III.1.���i��116-21���߁j�́A�����̃J�f���c�̉������ċ��ʓ_�͂Ȃ��B �O�����A�ɍs�����Ƃ��A�N���h�͊e�Z�N�V������ʂ��ČJ��Ԃ��̉��y�f�ނ�傢�ɗ��p���Ă��܂���B ���l�̎�ނ̍Ĕ�������������܂��ibb�B25-33,85 --- 9 3,146-50�܂���bb.3 02,45-8,90-3,104-5,11 11-13�Q�Ɓj�B �A129-31,148-50,159-62�A����уZ�N�V����1�����3�̌��_�����Fbb.13-15,51-4,77-9,11-15,132-4�j���A ���̕����̍ޗ��̔����ȉ����߁A�e�Z�N�V�����̏I���Ɍ������ďW�܂�X��������܂��i�ʂ̗����I�ȃI���S�Y���j�B �S�̂Ƃ��āAMachaut �@�O�����A�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�N���h�͊e�Z�N�V������ʂ��āA�����I�ȉ��y�f�ނ��\���Ɋ��p���Ă��Ȃ��B���l�̎�ނ̍Ďg�p�́A�����͂���ibb�B25-33,85-93,146-50�܂���bb.30-2,45-8,90-3,104-5,110-13 �A129-31,148-50,159-62�A����уT�u�Z�N�V����1��3�̏I����Fbb.13-15,51-4,77-9,112-15,132-4�j���A��i�̑f�ނ̔����ȉ��ɉ߂����A�e�Z�N�V�����̏I���Ɍ������ďW�܂�X��������i�ʂ̃C�\���Y���Ƃ̗ގ��H�j�B Machaut�́A�S�̓I�ɁA�����f�B�[��n�[���j-�`�̋K���I�ȌJ��Ԃ������A�n�[���j�[�����Ɂi�ǂ̂悤�ɃJ�f���c�ɃA�v���[�`���A���������邩�j�����ƊS���Ă���悤�ł���B �@���̈Ӗ��ŁA�N���h�̉��y�́A�O�����A�̉��y�����`��������Ă��Ȃ����A���t�ɂ͂���ɖ��ڂɊ֘A�Â����Ă���B�������̊y�͂��A���t���ꂽ�����ŏ�����Ă���i�����Ă��̉ߒ��ǂ���ł����ė~�������j�A����́A�z���t�H�j�[�ƉC���I�ړI�Ɖ\���̐i���I�Ȍ����f���邩������Ȃ��B �@�}�V���[�̉C���I�ȏ_��̗��p�́Amoment�I�Ȍ����̉��l������B����́A����痼�y�͂̓����ł���A���ɂ͔ނ��x�z�����d�̉��l�̊ԂɁA1���邢��3�r�[�g�P�ʈȏ�̃p�b�Z�[�W��}������B �����͂������̗��R�Ō���邱�Ƃ�����BCredo�̑�25���߂ŁA�ނ͂P�����𑝂₵��Tripleum�̉��~�^���AMotetus�̓���̉��^�Ɉڂ��A�̎���unigenitum(���܂��j���������Ă���B��86�|95���߂ł́A�ނ́A�I�~�a���������L�����Ƃɂ���āA�d�v�Ȍ�����'et resurrexit ...tertiam die ... secundum scripturas '���������Ă���B �ŏ���6�̉��߂�3�̔����߂�ɂ�������炸�A���y���A�t�H���[���ׂ����d�v�ȃe�L�X�g�ɑ��ē����悤�ɂ��āA2�̐�s����t���[�Y�́A2���̏I�~�i5���̃t���[�Y������j�ŏI�������BAccording to contemporary notation rules this is indefensible�C and as such is an endearing indication of the composer's determination to create as flexible a means of text-projection as his ear could imagine . 2. 3�E3.1�N���h�E�A�����iCredo Amen�j �O�����A�E�A�[�����iGloria Amen�j�̖`���Ƃ̊Ԃɂ������̗ގ��_������ɂ�������炸�A���̃Z�N�V�����̃e�m�[���E�����f�B�[�̓`�����g�ɂ͗R�����Ȃ��悤�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����̓����Ŏn�܂�AKyrie�C Gloria and Credo�C�̑�P���@���������Ă��邪�A�ǂ�������ƃh���ɌŒ肳��ASanctus ��Agnus�̑�T���@��\�����Ă���B�����ɁAKyrieII��III�̃n�[���j�[�\���̊�b�ɂ���悤�ȃ����ƃh���̘a���̌��݂ɂ��Ȃ��Ă���B ���̈Ӗ��ɂ����āA�N���h�E�A�[�����́A�~�T�Ȃ�2�̐��@�̔����Â��Ȃ���@�\�����̂ƂȂ��Ă���B�O��ł̂����������y���}���Ă��邱�Ƃ́A����ɁA�N���h�E�A�[�����̑�23�|31�i180-188�j���߂ɂ�����i�h���ֈڒ�����Ă���j�A'Sanctus�̃`�����g�́edominus deus sabaoth �̊T�v�I���p�ɂ���Ďx������Ă���B �@���̍�i�̃��Y���`���́A���������Ȃ��B�O�����A�E�A�[�����̂�����͓`���I�ł͂��邪�B�{���I�ɁA�y�͔͂ăC�\���Y���I�ł���B���Ȃ킿�A���̏㐺���́A�e�m�[���ƃR���g���e�m�[���ƂƂ��ɁA���i�ȃC�\���Y���ŌJ��Ԃ����B�����Ă���́A�ᐺ���̃^���A�̏�ɍ\�z����Ă���B�|�}�V���[�̍Ō�̃��e�b�g�iNo.23 ,Felix/Inviolata)�̂悤�ɁB����́A���̒��S�ŁA��������������̂ł���B ��V�Ŏ�����Ă���悤�Ɂi�ЂƂ̃��Y���P�ʂ́A�ЂƂ̕����ŕ\�����j�A�㐺���́A�܂��A���ꂼ��̃^���A���ł̌J��Ԃ����܂�ł���B�����āA�����̌J��Ԃ����statements�́A���傫�ȃ^���A�̍Ō�ƃI�[�o�[���b�v���Ă���B�܂�A�C�\���Y�����̃C�\���Y���ł���B 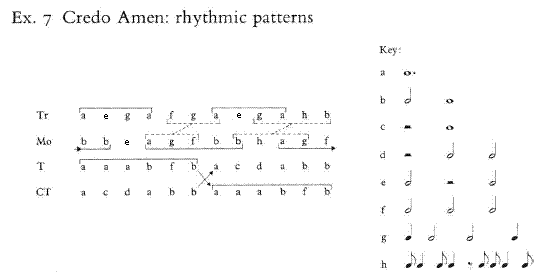 �@1�̕s�K�������������̂������肵���j�b�g�\��������������B���ꂼ��̃^���A�ɂ�����Contratenor�� �senor���Y���̌����̕s��I���ʂ́A�^���A�̔����܂��͂��������ɂ����āA�Q�̂s���������̉������AContratenor�̈���ɂ���ăn�[���i�C�Y����˂Ȃ�Ȃ����낤�Ƃ������Ƃł���i�����j�B Tenor�����f�B�[��Machaut�ɂ���č�Ȃ��ꂽ�Ǝv����Credo Amen�̏ꍇ�A����͒ʏ�A���������_�ɂ����āA����Tenor�̉����́A��ɁA�P���Contratenor�̉����Ńn�[���i�C�Y�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��m���߂邱�Ƃɂ���āA�P���ɔ�������ׂ����ł���B�������A�����������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���ł́ASanctus�̃`�����g�����p����Ă���A�s�b�`�E��-�\�i��27-8���߁A�����ɂ́A��28���߂ɊY���j������ȏヂ�f�B�t�@�C���邱�ƂȂ��AContratenor��1�̉����ɂ���Ĕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��낤�B ����͂����炭�AMachaut���Ȃ��A�I�~�̃^���A�Z�N�V�����ŁAContratenor�� tenor���������A������2�̃e�m�[���̃s�b�`���قȂ���Contratenor�̉����ɊȒP�ɓ]�p�������Ƃ������R�ł���B �@����ɁAMachaut�͑�35���߁i�̃e�m�[���j�ɂ����āA�Q��breves��s���Slong�ւƒu�������邱�ƂŁA����ɕω��������炷�@����B�I�~�J�f���c�֓����������P���邽�߂̌��ʂƂ��Đ�����s���a���ɂ�������炸�B 37 37�@���������ύX���e�m�[���ɉ����邱�Ƃ��A�}�V���[�͎��R�ɍs�����킯�ł͂Ȃ����낤���A�^���A���ύX����Ȃ���ATenor���`���I�ɁA2�̒ᐺ���̕s�N���������Ă������ƂɂȂ邾�낤�B �@�V���ɍ�Ȃ��ꂽ�R�����Ɍ������̂Ɋ�Â��Ă���\�����炭���̗��R�Ł\���A�N���h�E�A�[�����͂��낢��ȓ_�ɂ����āA�~�T�Ȃɂ����錵���ȉ��y�I�\�z���ł���B ���ƂȂ����y�͂̊�{�I�f�ނ̃C�\���Y���l�̃����[�N���Y������Gloria Amen�ɂ����āA���Ɏ��R�ɍ��ꂽ��ȑO�̎�������̑��ΓI���R���A�����ł͂ނ���A�ăC�\���Y�������z�I�ȃ��f�B�A���������������ȉ��y�\���ɂ��Ẵ}�V���[�̗͂ւ̒���Ƃ��Ď���Ă���B The relative freedom from pre-compositional restraints which in the Gloria Amen produced a quasi-isorhythmic reworking of the parent movement's basic material�C very freely used�C is here taken rather as a challenge to Machaut' s powers of strict musical organisation for which the (perhaps relatively new) technique of panisorhythm provides an ideal medium. 2..4�T���N�g�D�X Sanctus�̃`�����g�́A���i�ɁA���l�ȁA���邢�̓Z�~�_�u���j�Ղ̂��߂̑�T���@�ł���A�C�\���Y���ݒ�ɂ͔��ɕ֗��ȍ\���������Ă���B���ꂪ�A�}�V���[�����̐��@��I���������R�ł���B ����́A��8�̂悤�ɏ����t����ꂽ7�̉��y�t���[�Y�i1�A2 ,2a�A2b�A2c�A3�A4�j����Ȃ�B�t���[�Y2,2a�A2b�����2c�́A�����̋��ʂ̑f�ނɂ���āA�t���[�Y1,3,4�̊Ԃ̃��t���C������������B�t���[�Y�S�́A�t���[�Y�P�̊g��ƌ��A�`�����g�̊Ȍ��I�\�����������Ă���B Osanna��Benedictus�́ADominus Deus�ł��łɎg���Ă���f�ނō\������Ă���ASanctus��statements���A�y�͂̎c��̃X�L�[���̊O���Ɏc���Ă���B�����āA���̌`���I�z�u��Machaut�̃|���t�H�j�[�I�O�����ɐ��m�ɍ��v���Ă���B �@Machaut�������quantities�͈ȉ��ł���B Sanctus�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7 + 6 + 7 = 20 chant notes Dominus�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@45 Osanna �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@22 Benedictus�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@22 Osanna�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@22 Dominus Deus�͎c���3�Z�N�V�����̂��ꂼ��̒�����2�{�ȏ゠�邽�߁A11��������Taleae�ƏI�~�̉���������Machaut�̃C�\���Y���X�L�[���́A�A�S�����^���A���琬��y�͂̍Ō�̂S�̃Z�N�V���������e���邱�Ƃ��A�قڕs���Ɍ�����B ����䂦�A�`�����g�̌`���\����z�����Ă���BSanctus�̌Ăт����̖`���݂̂��A���������X�L�[���Ƒ��e��Ȃ��B�����āA�}�V���[�͂������A��C�\���Y���I�����Ƃ��Ĉ����A�`�����g�̃����f�B�[�I�ȓ����Ƃ��Ă̋@�\�f���Ă���B �@���̔��ɕX�I�X�L�[���ɓ�������Ă���B��̃o���G�[�V�����́A�ŏ���Osanna�̏I���ւ�Dominus Deus�̔�C�\���Y���I�I�~�̈ړ]�ł���A���̂��߁A���y�́A�T��I�ɁA���߂�ꂽSanctus�x������O�ɁA�t���\�������̏I�~�ɓ��B���邱�Ƃ��ł���B���ꂩ��Benedictus�������B 39�@�������āF �@�R������11�����O���[�v�ւ̕����́A�`�����g�̗ʂ̔z�������Ȃ���i�܂��͗��p���āj�A���̒��̎��R�Ȑ����̃O���[�v�ɂ͑Ή����Ă��Ȃ��B�^���A��statements�̑������^�����Ă��Ă��A�ǂ�Ȉ�ѐ��������Ă��Ă��A�e�m�[���ɂ����郊�Y������f�B�̃J�f���c�ɍ��v��������͐����Ȃ��B����ɂ�������炸�A�ᐺ����taleae�̍\�z�ɂ����āA Machaut�́AKyrie�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA���Y���Ƃ��ẴJ�f���c���^�Ɍ������č�Ȃ��Ă���悤�ł���B�e�m�[����Contratenor���Q�̃��Y���t���[�Y���`���A�����̃p�^�[���́AKyrieII��III�̂���Ƃقړ��l�ł���BContratenor�������N�������Ƃ̃^���A�̂S�Ԗڂ̏��߂�long�ւ̍ŏ���leading�A�V�Ԗڂ̏��߁i�Ōォ��Q�Ԗځj�ւ�2�Ԗڂ�leading�́AKyrieI�Ɛ��m�ɓ����悤�ɁA����statement�̃X�^�[�g�ɓ����BKyrieII��III�ł̂悤�ɁA2�Ԗڂ̃t���[�Y�́A�C�\���Y���Ihocket/�V���R�y�[�V�������^�ɂ���āA�㐺���ɂ����č��v�����Ă���B���̊ԁA�ŏ��̕��̓��Y���I�Ƀ^���A����^���A�ւƕω����Ă���B �@Sanctus�� Kyrie�̊Ԃ̏d�v�ȈႢ�́A��X���}�V���[��Contratenor�̃R�����iTenor�̃R�����ƃn�[���j�[�̌��ʂł̊W���āj��ڂ���������ɂ̂݁A����n�߂�B�ᐺ���̃y�A�́A�}�V���[���A���Y���ƃn�[���j�[�̃J�f���c�̊Ԃ̖��炩�Ȗ�����T�������������ɂ����āA�ނ̓�����̍�i�ɂ����Č��o�����������ɒ����t���[�Y�Ɍ�����ꂽ�n�[���j�[���Y�����邽�߂ɁA�����Δ��ɓ`���I�ł͂Ȃ��i�s�ɂ���āA�I����voice-leading�̗�����B ��20�|6���߂́A�����炭�A�����Ƃ��͂�����Ƃ�����ł���B�e�m�[���̃~������t�@���i��22�|4���߁j�ւ̐i�s�́A�ʏ�A�J�f���c���������邱�Ƃ����҂���邪�A�}�V���[���~���a�����^���AII�̖`���̉����ւƉ��������^���A�̍Ō�̋x���ɂ���đj�Q�����B����ɂ���āA���炩�ɁA�������N��������x���̈ʒu���A���ʂ��オ���ւƖ߂����ƂɂȂ�B ���������g�����ꂽ�i�s�́A���ꎩ�g�A�a���̘A���ɂ���ď�������Ă���B�n�[���j�[�̓�����I�K����j�邱�Ƃɂ���āA�旧�h�����j�]�����A�t�@���̃J�f���c�Ƀ����N�����Ă���B���������s���a���̎�i�ɂ���āA�}�V���[�́A�h������t�@���ւ̕������̂���i�s�����o�����B����͏��Ȃ��Ƃ�11���Ɋg�債�A���ꎩ�̂��h��'�ւƖ߂�悤�ɐi�s����i��24-6���߁j�B���̑S�̓I�ȗ���́A�����ł̐i�s���^���A�̈قȂ鉹���̏�ɂ���ɂ�������炸�A��POsanna�i��48�|52���߁j�̃`�����g�̕���̌J��Ԃ��ƂƂ��ɌJ��Ԃ����B �}�V���[�ɒᐺ���̎l�x���邢�͓�x�������邱�̃��Y���ɂ́A����^��͂Ȃ��BTenor��Contratenor�͔��ɃV���v���ł��肻�̂��߂ɁA�\���I�ȕs���a���͊ȒP�ɔ����邱�Ƃ��ł����B Machaut�́A����炪�A��葽���̋��a����1�̊g�����ꂽ�i�s�Ɍq���ĉ��t�ł�������Ƃ��āA������P�ƂŎg�p���Ă���B��3�͂Ŏ��������悤�ɁA������̑Έʖ@�̌���ꂽ�͈͂���̒ᐺ���̂��̂悤�ȊJ���̌����́A�Ђ낢�͈͂ɋy��ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���B 2.5 Agnu s Dei �}�V���[�ɂ���đI�����ꂽAgnus�̃`�����g�̑�T���@�́A�֘A���������f�B�f�ނ��猚�Ă��ASanctus�Ɠ����T�C�N���ɑ����Ă���BAgnus I�̃`�����g�́ASanctus�̃����f�B�t���[�Y�̗p��ɂ����āA�\�������B�P�{�Q�{�S�Ƃ��āB�ŏ��͂��Ȃ�ω����Ă��邪�BKyrie�̃`�����g�̂悤�ɁAAgnus�̃`�����g�́A�ȉ��̂悤�ȒP���Ȍ`���v�����Ŏ������B Agnus III�́AAgnus I�̌J��Ԃ��ł���B�����āAAgnusI��AgnusIII��AgnusII�̍ŏ��̂W�̉����̍��ق͂��邪�A�c���26�����͓���ł���B�����āAAgnusI��AgnusIII�ɂ����āA�Ō��11�̉����́A�ŏ��̂X�Ƃ͕ω������J��Ԃ��ƂȂ��Ă���B�����̐ݒ�ł́A�}�V���[�́ASanctus�̂���Ɣ�r�������C�\���Y���I�ȓ����Ƃ��āA�Q�̊y�͂̊Ԃ̃����N������ɋ������A���C���́eAgnus Dei"�̃e�L�X�g��ێ����Ȃ���A�ŏ��̂X�̉�����z�u���Ă���B �@�}�V���[�ɂ���đI�����ꂽ�C�\���Y���I�v��́A���������Q�̊y�͂ɑ��āA�^���A�Ƃ��āA���ڂɊ֘A���Ă���BAgnusII�̒Z���^���A�́A��蒷��Agnus I= III�Ƃ͏\���ɑΏƓI�ł���BAgnusII�́AABA�`���̂����̑ΏƓI�Ȓ��ԃZ�N�V�����Ƃ��ċ@�\���A�`�����g��ABA�`���ɂ����v���A���t����͂�����ƕ���������̂ł���B �@�ᐺ����Agnus�̃^���A�p�^�[���́A������O�̃C�\���Y���y�͂̃��Y�����^�ɑ��āA���l�̃��Y�����^���g�p���Ă��邪�A�Z���x���̎g�p�ɂ����āA���ɈقȂ��Ă���B���̋x���͌��݂ɁA���X���[�Y�ȃ����f�B���C�������e����悤�ȃn�[���j�[�̕ύX�́A��葁���x�������Y�����Ă���i�Ȃ��Ȃ�A�㐺���͒����Ԋu�ŒP��̘a�����ێ�����K�v�͂Ȃ����߁j�B ���ł�Sanctus�Ō����Ă��鏖���`�̑����X���������A���̑O�ɃN���h�E�A�[�����iCredo Amen�j�ɂ����̌X��������B���̂��߂ɁA���������y�͂����̊Ԋu�ō�Ȃ���Ȃ��̂ł���A�}�V���[���A�����������n�[���j�[�\���ɂ���Ďx�z���ꂽ�ŏ��̊y�͂���A�����f�B��������̖ړI�ƂȂ�����Ԃ��Ƃ̊y�͂܂ŁA��i��ʂ��Ă��̗l����ɒi�K�I�ω����������A��i�̃e�N�j�b�N�̘A����������ۂ�����邱�Ƃ͍���ł��낤�B �m���ɁA�P���ȃ��Y���Ɣ�r�I�p������Kyrie I�Ɠ�d�V���R�y�[�V�����iTriplum��Motetus�ɂ����ĈقȂ������x���Łj��Agnus I�̎��R�ȏ����`�̌`����̃R���g���X�g�͈�ۓI�ł���A�D�揇�ʂƍ�ȋZ�p�ɑ傫�ȕω��������炵�Ă���B �@Agnus II�́AAgnus I�̃^���A�Ɠ��l�̐ϋɓI���Y�����g���^���A�ɏ]��ꂽ�ŏ���6���߂̌Ăт����̎g�p�ɖ��ڂɊW���Ă���B�������^���A�͔ăC�\���Y���ł���A�ɒ[�ɒZ���A���̂U��statements�́A�e�L�X�g�������鐫�������A���̂悤�Ȍ��ʂ��������o���Ă���B�����āAAgnusI��AgnusIII�̂�蕷�����Ȃ��`���`���ɑ��āA�����ʓI�ȃR���g���X�g���������o���Ă���B Agnus I�Ō�����Tenor��Contratenor�̃s�b�`�̌��́A�����̒Z���x���ɂ���Ĉ����N������邪�A�����ŋɒ[�ɕێ�����Ă���B2�p�[�g�͒P��̃J�f���c�i�s�ł̂݉���A���̂��߂ɁA�����ɌJ��Ԃ����㐺�̃^���A�ɂ�������炸�A�n�[���j�[�Ɛ����̎��R�x���ő���ɂȂ�B Machaut�͂�������܂����p���Ă��邪�A���ʂƂ��ē�����R���g���X�g��₤���̂悤�ɁA�iAgnus II �́j4��statements�i��.9,12,15,18���߁j�ɂ����āA�i�㐺���́j�����悤�ɉ��~���郁���f�B���^�ic "-b'-a'-g '�j���g�p���āA���ꂼ��̃J�f���c�ŁA�㐺���̃t���[�Y���܂Ƃ߂Ă���i�����j�B���l�ɒZ���^���A���g�p����KyrieI�Ƃ̔�r���A�ēx�o�����Ă���B 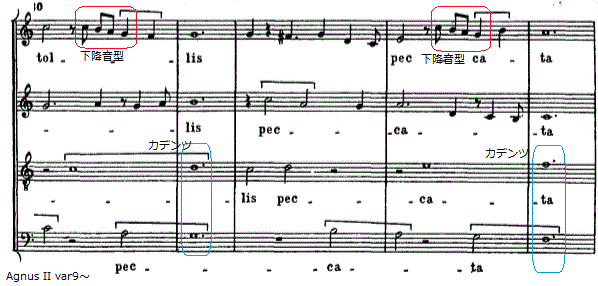 �@Agnus 1 = III��Agnus II�̊Ԃ̋��ʃ`�����g�f�ނ̑�ʂɂ�������炸�A�����̃n�[���j�[�[�V�����͔��ɈقȂ��Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�p�ɂȃJ�f���c��v������A���ɒZ��Agnus II�� talea�ɂ���Ē����R���g���X�g�̋������Y�����e�����邽�߂ł���B ���������āA�Ⴆ�AAgnus I = III�̑�11���߂̃e�m�[���̐i�s�~���t�@�́A��14���߂̃V���Ɍ������ᐺ���a���̑傫�ȗ���Ɉʒu���Ă��邪�AAgnus II�ɂ����ẮA�t�@���͎�v�ȃJ�f���c�i��12�|13���߁j�̉����Ƃ��āA�@�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�����j�B �t�ɁAAgnus 1 = III�i��17���߁j�̃J�f���c��\��Tenor �s�b�`�t�@�\�\�́AAgnus II�i��20���߁j�̂��傫�Ȑi�s�ł͂��܂�d�v�ȗv�f�ł͂Ȃ��B����A���Y���I���e������ł���ꍇ�A�n�[���j�[�������ł���i�Ⴆ�A�V���Ɍ������^�̃J�f���cAgnus 1 = III�A��13-14���߁AAgnus II�A��15 -16���߁j�A�����āA�ނ��A�Ō�̃J�f���c�Ȃǂ����̗�ł���B ����䂦�A���o���������̃J�f���c�̓���I�ꏊ�͂����炭�A1�ȏ�̂������̉\�ȑ�ֈāi���Ȃ킿�A 9+(8 x 3)+ 1 or 9+(5 x 5)�G���ۂ́A9+12�~2+1�iAgnus 1 = III�j�A�@9+4�~6+1�iAgnus II�j)���͂ނ���A���̂悤�Ɋ֘A����isoperiodic�Ȕz��ɂ��Ẵ}�V���[�̑I�������肵�����̂ɈႢ�Ȃ��B������O�̊y�͂ɂ����ă}�V���[�ɂ���Ď����ꂽ�����͈͂̃n�[���j�[�v��̊ϓ_�ɂ����āA����͂����炭���蓾�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B �@���K�͂ȃX�P�[���ł́ASanctus�iAgnus I = III�A��12���߁j�̂悤�ɁA���傫�Ȑi�s�̒��̒��ړI�v�f�Ƃ��Ă̒ᐺ�̕s���a���̎g�p��������B�Î��I�n�[���j�[�̌`���i����́A����breve�̋x����ʂ����ᐺ���̃s�b�`�̈Öق̉����ł���j�ł́A�܂��ɓ��ʂȓW�J�ɂ���ĕ���Ă��邪�B 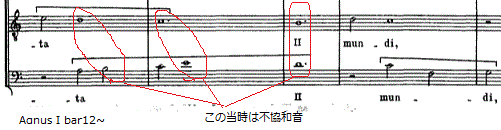 ���l�ɁAAgnusII�̑�12���߂ɂ����ẮA�R���g���e�m�[���̃����́A��Q���i��breve�̋x���j��ʂ��āA���߂̍Ō�Ń\���ւƈڂ�A��13���߂̃J�f���c�A�t�@���ƂȂ�B���ꂼ��̏ꍇ�ɂ����āA�}�V���[�́A�a���̕ύX�̂��߂ɃR���g���e�m�[���ɂ���Ē��ꂽ�\���W������̂ł͂Ȃ��A�ނ���A��z���āA�x����ʂ��āA����ȑO�̘a���̌p����I��ł����̂ł���B 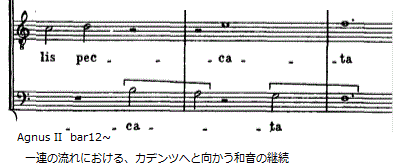 ���̌��ʂ͂������A���R��������Ȃ����A���������A���O�̊y�͂Ɍ�����n�[���j�[�ւ́A�ʏ�Ƃ͈قȂ��������������A�v���[�`�̏ؖ��ƂƂ��ɁAMachaut�̓�����l�̂����ꂩ�ɂ���đS���������x�ɂ͋��L����Ă��Ȃ��Ǝv���鋻���A����҂��a���̊W��m�o������@�̗�O�I�ȋ������w�E���邱�Ƃ́A�����炭�s�����ł͂Ȃ��B �Q�D�U�@ITE MISSA EST �}�V���[���ނ�Ite�̂��߂Ɏg�����`�����g�́A�����̎ʖ{�ł́A��v�ȏj���̂��߂ł���A�ƋL�^����Ă���B�����āA��T���@�ł͂Ȃ���U���@�ł���_�ɂ����āA�O�̊y�͂̃`�����g�Ƃ́A�����قȂ��Ă���B�������AMachaut�̂���̈����́AAgnus�̐ݒ�ɂ�������ƌ��т��Ă���B 10�������̃^���A�{�I�~���̑I���́A10�Ԗڂ̉����̌�̃`�����g�̎��R�����ɂ���Č��肳�ꂽ�悤�Ɍ����邪�A���ׂĂ̐����̃��Y����Agnus�̂��̂ɋ߂��B �����Č����ȍŌ��4���߂̃z�P�g�D�X/�V���R�y�[�V�����ɂ���Ė��m�����ꂽ�㐺���̃^���A��2�̃��Y���̔������AAgnus�̊y�͂̎��R�ȓ����ƃC�\���Y���̃Z�N�V�����Ɍ��y���Ă���Ƃ�����ẮA�ŏ��̃Z�N�V�����i��3�|4���߁j��Agnus I = III�i��5-6���߁j��Agnus II�i��4-6���߁j�̗����̓����Ɏ�������J�f���c�̗ގ����ɂ���Ă����炭�́A�m�������Ă���B �W���I�ȃ��Y����4���߂ƁA�����ɃC�\���Y���ł���z�P�g�D�X/�V���R�y�[�V������4�̏��߂Ƃ̕����́A���ꎩ�g�A�`�����g�̍ŏ��Ǝ��̔����̖`���̊Ԃł̗ގ����̎Y���ł��� �y�͂̃n�[���j�[�v�����ɔ��f����Ă���B�i��1�|4���߂͂قƂ�ǐ��m�ɁA��9�|12���߂��J��Ԃ��A���̊ԁA��5�|8���߂Ƒ�13�|16���߂̃R���g���X�g������j�B ���̍�i�͑S�̓I�Ȍ`�������łȂ��A���ꂼ��̃^���A�Ƃ��̃n�[����[�[�V�������̃o�C�i���\���ł��邽�߁AAgnus��ABA�`���̏ꍇ�Ƃ܂����������悤�ɁA�`�����g�̌`���͂��ׂĂ̍�i�ɔ��f����Ă���B �@Sanctus�̂悤�ɁAMachaut�́A���傫�Ȑi�s�����o�����߂ɒቹ�̕s���a���̘A�����g�p���i��6-8���߁j�A��Q�̔�`���I�p�b�Z�[�W�i��11�|12���߁j�ɂ����āA���@�̏I�~������b�Ƃ���full bar������邽�߂ɁA�p�ӂ��ꂽ�s���a���Ɖ����̊Ԃł̗]���ȃh�a���̓����ɂ���āA�t�@���ւ̐i�s�̉�����x�������Ă���B ��S���߂ɂ����āA�����悤�ȏł���B��1�|4���߂̓����I�@�\�ɂ���āB�������A���y����i���I�~��ւƓ����̂́A�����ł͂Ȃ��B ���_ ���̏͂ł́A�ו��̋c�_���ւ��Ă��܂��B�������A�}�T�E�g�̉��y�̗D�揇�ʂɂ��Ă̏d�v�Ȍ��_�������o�����̂́A�o�[�E�o�C�E�o�[�̌���̏؋����炾���ł���B�������́A�~�T�̂��ׂĂ̓��� - ��A�C�\���Y���̃O�����A�ƃN���h - ���������Ӑ[���������ꂽ�`�̎���ɍ\�z����Ă���̂����܂����B�m���ɁA�����̌`���������ɓK�p����Ă��邽�߁AMachaut�̍\���菇�̍č\�z���\�ɂȂ邩��ł��B�A�C�\���Y���̓����́A����炪���`����A�g�ݗ��Ă�ꂽ���ԂƁA�ו����ǂ̂悤�ɍ\������Ă��邩�A���̍\���v�f�̊Ԃ̂��̂悤�ȋٖ��ȊW���ێ�����i�r���A�Ⴂ���̃��Y���p�^�[���A�Ⴂ���̑Θb�A��ʂ̐��̃��Y���A�ȑO�ɍs��ꂽ����Ɉˑ����邠���郌�x���ŁA������x�m���Ɍ��肷�邱�Ƃ��ł���B�O�����A�ƃN���h�̏ꍇ�A�C���ƉC���̃p�^�[�����J��Ԃ����Ƃɂ���Č`�Ԃ��ǂ̂悤�ɒ�`����邩���ώ@���邱�ƂŁA�}�[�`���e�L�X�g�̈Ӗ��\������`�Ԃ�����葱���̍č\���ɖ߂�B�ǂ���̏ꍇ���A�e�N�j�b�N�͊��S�ɑI������Ă��܂��B�قƂ�ǂ̃e�L�X�g�������Ȃ��A�C�\���Y���̓����́A�ŏI�I�ɔނ�̉r���Ɋ�Â��ĉ��y�I�`����ɏ]���č\������Ă��܂��B�ݒ肳��錾�t���������铮���́A�r���̎���ł͂Ȃ��A�e�L�X�g�̌`�ɉ����Č`����܂��B�����̈قȂ�A�v���[�`�̒��� �����̈قȂ�A�v���[�`�̒��ŁA�������̌X�������炩�ɂ���Ă���B�������͂������̓_�Łi�ł��d�v�Ȃ��Ƃɂ́A���Y���ƃ`�����g�̎��Áj�AKyrie 1�͍ŏ��̓����̃��Y���ł���AMachaut�̌v�悪�����炩�i���Ƃ��������Ă��܂��B�����āA�������́AKyrie�̒�??���Ώ̐��ƌ��isorhythmic�^���̂���Ƃ̊ԂɗL�ӂȍ��ق����邱�Ƃ����Ă��܂����B����A���Y���̎菇�͔��Ɏ��Ă���悤�ł��B����͔N�\�̗��_���S�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�V�~�́A�O�����A�ƃN���h�̎葱���̊ԂɌ����閾�m�ȈႢ�����������܂����B���̃��C�^�[�́A���y�̗���╶�͂̌`�Ō`����Ă��܂���B�������A���̒����̒i�K�ł��A�ނ��������Ă���̂����m�ɒm���Ă����f���炵���X�L���̍�ȉƂɑΏ����Ă��邱�Ƃ����炩�łȂ���Ȃ�Ȃ��B����͈�ʓI�ɒ����̃~���[�W�V�����̌o�����������Ɛ������ꂽ���@�ł���Ă��� �X�^���U�@�����X�} perio���@ �C�\���Y���X�L�[�� �e�m�[���@�@�C�\���Y���@�e�L�X�g�@�����@Motetus�@Triplum statement�@Contratenor tenor �R���� �|���t�H�j�[ �v���C���`�����g �g�D���l�[�~�T�� �}�V���[ KyrieChriste SanctusAgnus GloriaCredo�@ ��� �y�� �~�T�� |