| Machaut's Mass�P�@Daniel Leech-Wilkinson |
| 2 CONSTRUCTION 2. 1. 1Introduction La Messe de Nostre Dame�́A���e����~�T�̑S�������y�ɂ��邱�Ƃ͂������A�Ȃ��B �ނ���AMachaut�͋������ʂ��āA�e�L�X�g�������ł�����6�̍��ځAKyrie�AGloria�ACredo�ASanctus�AAgnus Dei�AIte Missa Est��6�̍��ڂ� 'Mass of Ordinary of the Mass'����I�B �����āA�ނ�2�̑ΏƓI�ȉ��y�X�^�C�����g���Ă���B�ЂƂ́A���Ȃ킿�C���Y�����g�̌����Ɋ�Â��AKyrie�ASanctus�AAgnus�����Ite Missa Est���A ������́A�O�����A�ƃN���h�̂��ߎg�p���Ă�����̂ŁA�S�����ɂ�铯���Ƀe�L�X�g���̂����̂ł���B �܂��ŏ��ɁA��X�͊ȒP�ɁA����������{�I�Ȍ����I�����̂��߂̐�������K�v������B�Ȃ����������y�͂����������l���ɂȂ����̂��H 2. 1. 2 The fourteenth-century tradition ���̉�T�����m�ȏꏊ�́A��葁��14���I�����̃|���t�H�j�[�~�T�Ȑݒ�ɂ���B ����͂����ȒP�ł͂Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�A�ЂƂɂ́A�قƂ�Ǔ��t���킩��Ȃ�����A��ڂɂ́A�}�V���[�̗l���̂悤�Ȃ��̂��قƂ�ǂȂ�����ł���B�ʖ{�Ɍ������Ēm���Ă��郌�p�[�g���[�̑����́A�}�V���[�̎���̍Ō�Ɍ����ĕM�ʂ���Ă���B�����炭��1360�N�゠�邢��1370�N��ɁB3 �R�@���̎ʖ{�́A Ivrea �C Biblioteca capitolare 115 �A Cambrai�@Bibliotheque municipale 1328.�ł����B �����āA�����̂قƂ�ǂ́A���̒��O�ɍ�Ȃ���Ă���B����́A���悻1360�N���́A�O��̂Ȃ���Ȋ����̎����ɂ����āA��Ȃ��ꂽ�B �@���������� ��X�́A���[�Y�i�u���ȐM���������āA�}�V���[�͂�����n�������̂ł͂Ȃ��A�`���ɏ]���Ă����̂��A�ƌ������Ƃ��ł���B�������錴�T�ɂ���Ĕ��f���邽�߂ɁA����́A�~�T�ʏ핶����̂U�̍��ڂ̂قƂ�ǂ��ׂĂ̐ݒ肩�琬�藧���Ă����B���̎����܂łɁA��ȉƂ́A�ʏ�A�������ʂ��ĕω����邱�ƂȂ��ɍČ����ꂽ�A�ʏ�͉̂��Ă��邱���̃e�L�X�g�݂̂��|���t�H�j�[�i�����A�ݒ肷��K�v���������j�ɐݒ肵���悤�Ɍ�����B ���X�ω����Ă����u�ŗL���v�̕����́A�قƂ�ǖ�������Ă����B�����̍�i�́A��ʓI�Ȏg�p�̂��߂ɍ�Ȃ��ꂽ���̂ł���A����ȁA�܂��͖��N�̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��B�����͑Պ�����V����X�̐��l�̓��ɂ͎g���Ȃ��������A�|���t�H�j�[�����邽�߂ɁA���邢�͌��[�҂�������x�������Ƃ��͂��ł��g�p���邱�Ƃ��ł����B���̈�ʓI�ȃ��p�[�g���[�́A�X�̃A�C�e���Ƃ��Ă܂��͏����������e�L�X�g�i�O�����A�A�N���h���j�ŁA�ʖ{���ɃR�s�[����Ă��邱�Ƃ𗝉����邱�Ƃ��d�v�ł���B�H�ȗ�O�́A�قƂ�lj��y�I�ɂ͖��W��Kyrie�AGloria�̂悤�Ȑݒ肩��\������A�����institution�̂��߂̉��y���������邤���ŁA�����������炵�Ă���B �@�����������R�̂��߂ɁA�w�҂����́A�����e�L�X�g��2�̐ݒ�i�Ⴆ��Credos�AIV 46-48��55�|57�j�̊Ԃ����łȂ��A�y�͂̑n������y�A�i�Ⴆ�ASanctus IV 79��Sorbonne Agnus�j�Ǝ��ɂ͂��傫�ȌQ�iKyri-Credo-Sanctus�Q�AIV 27-IV 52-Apt 27�Aa �g�D���l�[�~�T�Ȃ�Kyr-Sanctus-Agnus�̊y�́j�Ƃ̊Ԃ̂悤�ȁA��ʓI�ȃ��p�[�g���[�̒��ɑ��݂��鉹�y�I�Ȃ���ɋC�Â��̂��x���B �}�V���[�͂܂��A�O�����A�ƃN���h�̃y�A�ASanctus�@Agnus�̃y�A�ݒ�Ƃ����`���ɂ��Ή����Ă���B ����ɂ�������炸�A�~�T�̂��ׂĂ̊y�͂���Ȃ����P��l���̊T�O�́A�����ɑ��āA���炩�̂����Ŏc���Ă���悤�Ɍ�����B 14���I�̃��p�[�g���[�ɂ́A�R�̗l������ʂ����B�@�C�\���Y�����e�b�g�ɊW����h���e�b�g�h�l���A�A�������ꂽ�㐺�����A���t���鉺�����Ŏx������h�f�B�X�J���g�h�l���A�����āA�B���ׂĂ̐������z���t�H�j�[�I�ɓ����h�����h�l���A�ł���B�}�V���[�������̂����̍ŏ��ƍŌ���g�������Ƃ́A���łɎ������������Ƃ���ł����i�FKyrie,Sanctus�@Agnus���@�AGloria,Credo���B�j�B �@�}�V���[�������ɂ��̂悤�ȓ�����I��舵���ɂ����Ă̂��������I���������̂��A���邢�́A�ނ��Ȃ��O�����A�ƃN���h�̂��߂ɓ����I�l����I�сA���̑��̊y�͂ł̓��e�b�g�l����I���A�`���ł͐��������Ȃ��B �����̌�����i�̒��ł́A����̃e�L�X�g�Ɠ���̗l�����֘A�t���閾�m�ȌX���͂Ȃ����A���l�̍�Ƃ́AMachaut�̃~�T�Ȃ��g�D���l�[�~�T�ȂƂ��Ēm����y�͂̃Z�b�g�Ƃ̊Ԃ̗ގ����ɒ��ڂ��Ă���B���̂��߂ɁA�}�V���[�̃��f�����A���̓���ȃR���N�V�����̗�Ƃ��ẮA��ʓI�ȓ`���ł͂Ȃ��\��������B �����A�i�g�D���l�[�~�T�ȂƂ́j�����������l���́A�N���h�ɂ����Ă̂݁A�͂����肵�Ă���B���҂́A���܂�ɊW�������A���̂��߂ɁA����͑����Ɋ�Â��Ă��Ȃ���Ȃ炸�A�����炭�}�V���[���g�D���l�[�~�T�Ȃł́A��҂̕����قڊm���ɑ��������ɍ��ꂽ�ł��낤�B �����������ʂ̓����i���ɁAformal units�����邽�߂́hlink passages"�̗��p�j�́A��ʓI�ȃ��p�[�g���[�ł͋��ʂł��邪�A�}�V���[�����̑傫���`����m���Ă����\���͔��ɍ����B ����A���̑���A�ނ̃~�T�Ȃ́A�e�����قƂ�ǎĂ��Ȃ��悤�Ɍ�����B 9 �X�@�}�V���[�́A���W���ꂽ��i�̈ꕔ�ȊO�A�ʕ����قƂ�ǃ����[�X���Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����B���ƂɁA�~�T�Ȃ������X�̓T��̂��߂ɈӐ}����Ă����̂ł���B ���̍�i�́AIte Missa Est�̃R�s�[��1�������ȊO�A�������Ă���ʖ{�ɂ͂ǂ��ɂ�������Ȃ��B �����āA���������y�͂́A�����悤�ȑO���iKyrie�ASanctus�AAgnus�AIte�j���Ȃ��A���m�Ȍ�p���Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�p���̍�ȉ�Leonel Power���A15���I�̏��߂ɁA�}�V���[��MS�@E�ɃA�N�Z�X�ł���悤�ɂȂ�܂łɂ́B10 10�@�}�V���[�̃y�A�����ꂽSanctus�AAgnus���A�I�[���h�z�[���ʖ{��No.118,141�i�Ƃ��Ƀp���[��j �Ɣ�r���Ă݂�B�p���[���}�V���[�̃Z�b�e�B���O�������������Ƃ��x�������ގ����������Ɍ��o�����BGloria��Credo���A15���I�̊֘A�����O���[�v���̔w��ɂ���\��������B�`�R�j�A�A���邢�͓��ɁAAntonius Zacharias de Teramo�ɂ��Gloria�]Credo�̃y�A�A�I�[���h�z�[���ʖ{���B �@�������A����𑼂Ɣ�r���邱�Ƃɂ���āA���y�Ə@���̕���ł�����ʒu�Â��A���ꂪ���݂��邽�߂̗��j�I�ȗ��R�������邱�Ƃɂ���āA���̍�i�ɂ��Ăǂ�قǗ����ł��邩�ɂ͌��E������B ���y�̈̑�ȍ�i�́A�����̂��ׂĂ̑މ��𑶑������A�����ɂ��Ă̏����ꂽ��ɁA���X�i�[�ɕA��������������B��X���m�I���@�ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ꂪ�����Ȃ�̂��A���̎���X�́A�����A�����A�`���́h�O�I�h�؋�����A���y���̂��ׂ̂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���Ƃ��Ō�̐��y�[�W�������N�����uWhys�v�ɂ�������ꂸ�Ƃ��A����͏��Ȃ��Ƃ��������������邩������Ȃ��B�����������[���uHow�v���������邽�߂ɁB 2. 2. 2 Chant �~�T�Ȃ́A����炪���ڂ����j�Ղ̏d�v���ɉ����ăO���[������A�j�Ղ̈قȂ铙���ɂ́A�قȂ����v���C���`�����g�̐ݒ肪�K�v�ł������B Machaut��Kyrie�́A�_�u���̏j���̂��߂̑�P���@�̃`�����g�ɂ��ƂÂ��Ă���B������Kyrie�`�����g�̂悤�ɁA�����Kyrie,�@Christe,�@Kyrie,�@Kyrie,��4�̋傩��\������Ă��܂��B�ŏ���Kyrie��3��̂��A ���ɁA2�Ԗ���Christe��3��̂��A�����3�Ԗڂ�2��̂���B�A4��ڂ̋�iKyrie�j�̓N���[�Y�Ƃ��ē����A���ʓI�ɁA9���\���ƂȂ�B Machaut�́A�ނ̃|���t�H�j�[�ݒ�ł��̕Ґ����̗p���A ���y���S�̋�ɕ����Ă���B���ׂĂ̎ʖ{�ɂ����āA�K�ȌJ��Ԃ��L�������āBKyreI��Christe�̂��Ƃ�.|||.�AKyrieII�̂��Ƃ�.||.�ŁB �@Kyrie�̃`�����g�́A�`���ɂ����Ă��Ȃ�̕ω��������X�������邪�A��ɁAKyrie-Christe-Kyrie �̃e�L�X�g�`�����]���A��{�I�ɁA�R����Ńv�����j���O�����B�䂦�ɁAKyrie�̍Ō�O���[�v�́A2�̉��y��ō\������Ă���B�����ł́A�ʏ�A��ʓI�ȑf�ނ�����A��PKyrie��Christe�̊Ԃɂ��A���邢�́A�����o���ƍŏI�I�ȃO���[�v�̊Ԃɂ��A�����Γ��l�̊W�����݂���B �����̈�ʉ��́AMachaut�ɂ���č̗p���ꂽ�`�����g�ɁA���Ȃ萳�m�ɁA�K�p�����B��1�Ɏ����悤�ɁAKyrie 1��Christe�́A�����ȏ�i�A�ŏ���4�̉��ƍŌ��11�̉��j�����L���Ă���B���̂��߂ɁA���ԋ�݂̂��A����_�Ƃ������ƂɂȂ�B 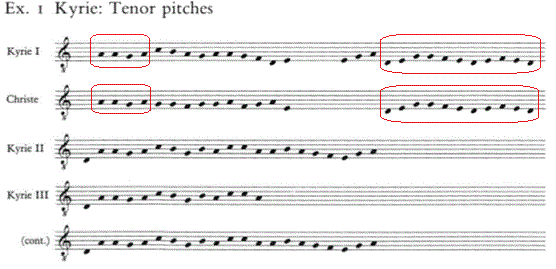 �������A�����̒������ɂ����鑊��́A���ꂼ����`�����g�̍\����{���I�ɕς���B Kyrie 1�́A�`���̂S�̃s�b�`�̌�A����9�̉����ł͎��x�����Ɋg����A2�Ԗڂ̃t���[�Y�̍Ō�̃~���ŏI�~���Ă���B�����Ă���ɁA�Ō��11�̉����̑O�Ń����ɖ߂�A�����ʼn������Ă���B ����Ƃ͑ΏƓI�ɁAChriste�́A�����̉��ŁA�O�x�ȓ��̉����ƂȂ��Ă���AKyrie 1�̂悤�ɁA���̒��Ԃ̋�̏I���ŁA�Ō��11�̉����̍ŏ��̃����Ɍ������B ��������Christe�S�̂̃`�����g�́A�ܓx�͈͓̔��ɂƂǂ܂�B Kyrie II��III�̃`�����g�́A�ŏ���2�̋�Ƃ͑ΏƓI�ŁA�݂��Ɍ��т��Ă��邪�AKyrie 1��Christe��a-d�̐i�s���t�]�����Ă���B Kyrie2�́A2�̃t���[�Y�ɕ�����Ă��邪�AKyrie3�́A�ŏ��̂��̂��J��Ԃ����Ƃ����_�����ł���B ���������āA���Ɉ�ʓI�Ȍ��t�Ō����A�`�����g�̔z��́A�ȉ��̂悤�ɂȂ�B 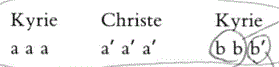 �����āA���̌`���́A�}�V���[�̃C�\���Y���\���ɂ����Ă��A���炩�ɕ��s���Ă���B 2.2.3 Kyrie �ނ̃`�����g��I�����A��ȉƂ̎��̃X�e�b�v�́A�P���ȎZ�p�I�Ȍv�Z�ƂȂ�B�e�m�[�������i�܂��́i�R�����j�̃����f�B�ƂȂ�`�����g���^������ƁA���z�I�ɂ́A�J��Ԃ����Y���p�^�[���i�^���A�j�̑S�̐����Z�b�g���邱�ƂɂȂ�B�R�����̃s�b�`���́A�^���A�̉����̉\�ȗʂƊ��S�ȃR������statement�ɂ�����^���A�̐��ƂɈ������������B �Ⴆ�A28���������`�����g�́A14�����̃��Y���p�^�[���̂Q��statement�ɁA���邢�́A7�����̃��Y���p�^�[���̂S��statemento�ɐݒ肳���B����ɁA�}�V���[���Ƃ��ǂ��̗p���Ă����A���ꂼ��X�̉��������R�̃^���A�i27�����j�{�C�\���Y������͗��ꂽ�ЂƂ̏I�~�����Ƃ����p�^�[���ł���B ���̑��̗��_�I�\���Ƃ��ẮA2�����Â�14�̃^���A���Ƃ��A4�����Â̂V�̃^���A�Ȃǂ������邪�A����͓����ɂ����āA���ۂɎg���邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B���ɒZ���A�����ΌJ��Ԃ����e�m�[���̃^���A�́A��{���q�ŗZ�ʂ������Ȃ�����ł���B ���̃G�f�B�V����������AMachaut��Kyrie 1�����������Ӗ��ł́A���ɒ��������Ƃ������Ă���B�Ȃ��Ȃ�Machaut�́A�܂��ɁA�`�����g��28�����A���ꂼ��4�̉�����7�̃^���A�ɔz�u��������ł���B ���̌��ʁA��O�I�ɒZ���^���A�ƂȂ�A���̃��Y���p�^�[���́A������Ars nova ��Le Roman de Faulvel�ɂ܂ők��A���̓����̃C�\���Y����i�ɂ����Č�����悤�Ȃ����Ƃ��P���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���i�������Ȃ���A���łɌ��Ă���悤�ɁA���̖��炩�ȕ��Î�`�́A���̑��̐����ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����A��i�̏����̓��t���w���E�x��������̂ł��Ȃ��j�B Tenor��Contratenor�̐����̉��y�I�@�\�́A���m�Ȍ`���\���ƁA2�̏㐺���iTriplum��Motetus�j���\�z���邽�߂̈��S�ȃn�[���j�[�̊�Ղ���邱�Ƃł���BContratenor�́A���̖ړI�̂��߂�Tenor�Ƌ��͂��Ȃ���Ȃ炸�A �e�m�[���̃��Y���ƃ����f�B�[��⊮����悤�ȕ��@�ō\�z���邱�Ƃ��ł���B Tenor�̃����f�B�[�͏��^�����ł���A���ۂɂ�Tenor��Contratenor�̃��Y���A������Contratenor�̃����f�B�[���A���ʂ��K�Ɉ�v����̂ł���A�P��̍\���v���Z�X�̈ꕔ�Ƃ��Ĉꏏ�ɍ\�z����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B ��ȉƂ̓e�m�[���̃����f�B�[���i������Ă��邩�A�z���͂̂����ꂩ�Łj�ݒ肵�Ă����Ȃ���Ȃ炸�A����ɑ��āA������2�����Έʖ@��Contratenor���R�����ō�Ȃ��A�A�����ɗ����̃��Y���ɂ��Č��肵�Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���Y���̊Ԃ̊W�́A�ǂ��ňꏏ�ɋ����A�ǂ��ŕʁX�ƂȂ邩���A���肷�邩��ł���B �@���Ƃ��AEx2�́A�e�m�[���i�������j��Contratenor�i���F�j�̃s�b�`�������Ă���B �����̏ڍׁ\ Contratenor�̉������A�e�m�[���̉����̊Ԃ̈ʒu�Â��A����уp�[�g�Ԃ̑Έʖ@�̊W�\�́A2�̐����̃��Y���Ɋւ��錈��Ɉˑ����Ă���B���l�ɁA�e���̃��Y���́AContratenor�̃s�b�`��2�̃p�[�g�̑Έʖ@�W�ɂ��Ċ��ɂȂ��ꂽ���肪�Ȃ��ꍇ�A�s���ł���B �@����������AContratenor�̃s�b�`��Tenor��Contratenor�̃��Y���̍�Ȃ́A�P��̃v���Z�X�A��Ȏ҂��e�m�[���̃s�b�`���R���g���[������悤�ȋ|�I�s�ׁAContratenor�������i�Ȍ�A 'contra tenor'�j�Ɍ��������悤�ȑΈʖ@�A����тQ�̃^���A�p�^�[���̏ڍׂł���K�v������B�Ȃ��Ȃ炻��́A�a���ƌX�̃s�b�`���ǂ��ʼn\�ł��邩�𐳊m�Ɍ��߂�^���A�̕s���ȌJ��Ԃ�������ł���B �@ �@ 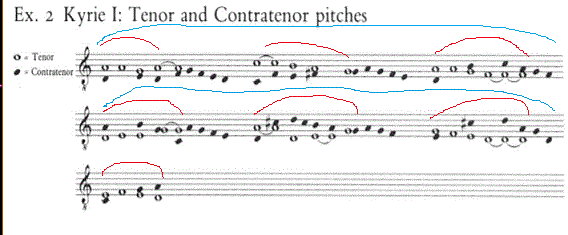 �@Kyrie1�́A���̃v���Z�X�̖��͓I�ȗ�Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�A����ɂ͂������̑Ë��_���܂܂�Ă��邩��ł���B �S�̉����̃e�m�[���̃^���A��I�Ԃ��ƂŁAMachaut���A�C�\���Y���I�ȋK�����̌����Ȕ͈͓��ʼn����������Ȃ��������g�ō쐬������ۂ�����B�ނ�talea pattern�́A3�̉����̃��Y�����^�i�e�^���A��̃e�m�[����2�ԖځA3�ԖځA4�Ԗڂ̉����j�ɏœ_�ĂĂ���B���^�́A�a���I�J�f���c�����邽�߂ɁA�C�\���Y�����p�[�g���[�ň�ʂɎg�p����Ă�����̂ł���B �����ł͂��̋@�\�����ƂȂ�B�}�V���[�́A�p�^�[�������������邽�߂ɁA���ʂ��čŏ��̉����ƂP�̋x��������lj�����K�v���������B���̉��y�I�Ȍ��ʂ́A�قƂ�ǁA���ʂ��Ă̌p������J�f���c�ƂȂ��Ă���B ���Q�Q �������A���ꂪ�ʏ���o���P�����́A3�̃e�m�[���E�^���A�ɂ܂�����]���I�łȂ�Contratenor talea�ɂ���Čy������Ă���B ���̔z�u�ɓ��L�̂��Ƃ́A�e�m�[�������̃p�^�[����7�́i6�ł͂Ȃ��jstatement���܂�ł���̂ŁAContratenor��3�Ԗڂ̃^���A��statement�́A�����3����1�����̂Ƃ���Ńu���C�N�I�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�ȏ��}������ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�B 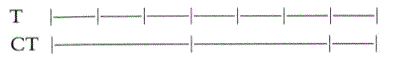 T;tenor �@CT:contratenor �����āA���̒��ŁAContratenor�ɂ�2�̏㐺�����]���A���̃C�\���Y���X�L�[���́ATenor taleae��3���ɑ�������B �Ō��Talea��́A���傫�ȃC�\���Y���̎d�g�݂̊O���Ɏc����Ă��邪�A��i�̌�̊y�͂̂������ɂ����ẮA�ނ���A�A�Ō�̘a���̂悤�ɂȂ��Ă���B �@�}�V���[���Ȃ����̂悤�Ȋ�Ȕz���I�̂��͕�����Ȃ��i���Ƃ��A�ނ���A���ꂼ�ꂪ�V�̉��������S�̃^���A�Ƃ��j�B 2�̑�K�͂ȃ^���A�̊Ԃ̃u���C�N���\�Ȍ���قڈ�v�����邱�Ƃ��Ӑ}����Ă��Ȃ�����A�iContratenor���j�ŏ���9�����̃t���[�Y�̊Ԃ̃`�����g�ɂ�����u���C�N�́Af-c '�͈̔͂ł���A����сA�c���2�̃t���[�Y�̊Ԃ̃`�����g�̃u���C�N�́Ad-a�͈̔͂ɐݒ肳�ꂽ�B ���̔z��ɂ���āA�������́AMachaut�̗D�掖���ɂ��Ă̓��@���邾�낤���H 14���I�̃C�\���Y���E���e�b�g�̃��p�[�g���[���画�f���āA��ȉƂ� �v���C���`�����g�̓�����ێ����邽�߂ɕs�s���ȃC�\���Y���I�d�g�݂��̗p���邱�Ƃ́A�����ĕ��ʂł͂Ȃ������B���������̌�A�C�\���Y�������e�b�g�ł��A�`�����g�͒ʏ�A���̃e�L�X�g�̌��̕�����������ꂽ�f�Ђɉ߂��Ȃ��Ȃ����B��ʓI�ɂ́A��̐����̃e�L�X�g�Əے��I�ȂȂ���������Ă������B �������A�C�\���Y�����~�T�Ȃł́A�͂��Ȃ�قȂ��Ă����B�����ł��A��ȉƂ́A�S�`�����g���g�p���Ă��āA���̖ړI�Ŏg�p���Ă����B���̍�i�́A���ۂɂ́A�`�����g�̐��k���ɉ߂��Ȃ������B���̂悤�ȏł́AMachaut��Kyrie�����f�B�[�̉��y�I�ڍׂɑ���A�ʏ�I�ł͂Ȃ��z���͗������₷���B 15���ɁATriplum�̃`�����g�̃p���t���[�Y�ɂ����āB ���Q�R �@�ނ̉��y�I�D�掖���ւ̓��@�́AContrateno���̂�薧�ڂȗ������瓾���邩������Ȃ��B �C�\���Y���Z�p�͔��ɏd�v�Ȃ̂ŁA�Ⴂ�����Ƃ��̏�̐����̃^���A�͐��m�ɌJ��Ԃ���A�����ȃC�\���Y������̂ǂ�Ȉ�E���������Ȃ��B ��ȉƂ��ގ��g�̃��[����j��ɂ́A������ׂ����R���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ꂪ����ł���A�ނ̉��y�I���l�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��悤�B �@Kyrie 1 ��Contratenor�́A�����ȃC�\���Y�������2�̈�E���܂�ł��邱�ƂŁA��O�I�i�قړƎ��I�ł���j�ł���i��6���߂Ƒ�18���߁A��8���߂Ƒ�20������Contratenor���r����j�B�ŏ��̃P�[�X�ł́A�s�K�����́A��2�̑傫��talea�i���Ȃ킿�A��18���߁j�ł��قڂ��̂܂������܂ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�ATenor a�̂�����̘a���̕ω������邽�߂ɁA��17���߂ɂ�����d��c '��Ɠ���Machaut�̌���́A ��19���߂�Tenor ���Ƃ̕X�I�a���̂��߂ɁA2�̉���������߂����Ƃ�����ł��邱�Ƃ�ނɎ����Ă��邩��ł���B�����āAisorhythmic�X�L�[���̒��ŋ��e����Ă�����葽����Contratenor�̉������g�p�����ɁA���ꂪ�����ɃX���[�Y�ɒB�����ꂽ��������͍̂���Ȃ̂ł���B �������A���̕s�K�����́A��P�̃^���A�i��8�����j�ւ́A�܂��͑�Q�̃^���A�i��20�����j�ւ̑o�����̕ύX�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�\��������B������2��Contratenor�̐ڑ���i�e�m�[���͋x���ƂȂ��Ă���j�̂��ꂼ��ɂ����āAContratenor�́A��s����Ⴂ�������痣��Ďn�܂�A���̘a���̒Ⴂ�������痣��ďI�~���Ă��邱�Ƃ�������B�����̐����̒��ŁA�����Ɍ�����ΏƓI�ȉ��^�́A�قȂ���e�ɂ����čŗǂ̐����i�s���\�ɂ��Ă���Ǝv����B16�@�����̃P�[�X�̂��ꂼ��ɂ����āA����ɗǂ��Έʖ@���l���邱�Ƃ́A�����ȃC�\���Y���̓`���I�ȉ��l�������ƂȂ邱�ƂɂȂ�B 16�@�j���������h�h�h�̑�U���߂́AContratenor�̂����ЂƂ̃C�\���Y���̏o���_�ł���B�s�K����Contratenor�̋x���́A�e�m�[���Ƃ̃��j�]�����ւ̑�ւƂ��Ďg���Ă���B �@�㐺���̃C�\���Y���X�L�[���́A�e�m�[���̃^���A�����AContratenor�ɏ]���B��10�|11���߁A��22�|3���߂̗������ɂ����āA�����Ƌx���̑f�������̋傪����Ă���B���̎�̉��^�́A���ꂪ����邽�тɕ�����ɔF���\�ł���A�`���I�ɂ͂��ׂẴC�\���Y����i�ŕς�炸�ɌJ��Ԃ���A13���I�㔼�́ehocket' �ɗR�����Ă���悤�ł���B�}�V���[�ɂ����ẮA���ɁA�����ł́A�V���R�y�[�V�����iTriplum�A��11�A23���߁j�Ƒg�ݍ��킹�����������B ���l�ɁA�`���I�Ȃ��Ƃ����A�C�\���Y�����e�b�g�ł́A�t���[�Y�̏I���ɁA�����ȏ㐺���̃C�\���Y�����ۑ�����Ă���B ���ꂪKyrie 1�ł͋N�����Ă��Ȃ��̂́A�P���ɁA1�̖��m�ȃt���[�Y�̏I�~�iTriplum�A��14�����j���A�y�͓��ɑ��݂��邽�߂ł���B ���ꂪ�A�e�m�[���̃s�b�`���J��Ԃ���邽�߂ɁA���㐺�����J�f���c��p�ӂ������������K�v���Ȃ���i��̏��߂݂̂Ŕ�������̂́A�����炭���R�ł͂Ȃ��B �����A��i�͂قƂ�Lj�т����J�f���c�̏����Ɖ����̘A������Ȃ��Ă���A����͒Z���A�J��Ԃ��̑����e�m�[���̃^���A�̂����Ȃ̂����A���̂��߂ɁA�㐺���́A�قƂ�Njx�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ł���B �@�����ЂƂ̋����[���㐺���̓����́ATriplum�̊Ԃ̃R���g���X�g�ł���B����́A���̂قƂ�ǂ��R�[�X�̔�r�I�����͈́id'-a '�j�ňړ����A����́A���ɂ���ĕp�ɂɓ����A������Motetus�́A�����Β���œ����A���L��������߂Ă���A���e '�������œ����ATriplum�������I�ɉ��ɂ���A�ȉ���Kyrie�y�͂̂���������������݂���B �����̗v���́A�㐺�����݂��ɕ������āA���ꂼ��قȂ�@�\���������Ă���悤�Ɍ�����BMotetus�́A�a���������݂Ƃ��Č���A���̊ԁATriplum�́A�`�����g�̃p���t���[�Y���������Ă���B����́A���ׂẴC�\���Y���Z�N�V�����̂��Ȃ�̒��x�̓����ł���B���̊y�͂ɂ����āA�}�V���[�́A�`�����g�E�p���t���[�Y��3�p�[�g�̔��t�A��蒷���^���A��_��Șa��������Ȃ�`���I�ȂQ�{�Q�̐����̕��z�ł̂����������ւ̎��݂��D�悤�Ɍ�����B �����Kyrie 1�����y�I�ȍ\���Ƃ��Ċ��S�Ɏ��s�����ƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B �������A����́A�~�T�Ȃ̎c��̕����ł��}�V���[�̍�i�S�̂Ƃ������I�ł͂Ȃ������̋L�O��I�ȍd�����������Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏͂̂܂Ƃ� 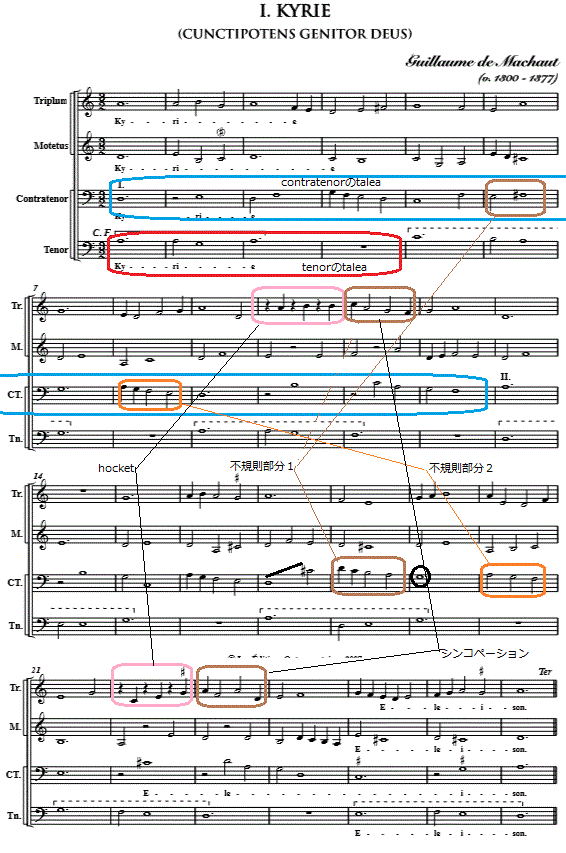 2.2.4 Christe Kyrie 1��Christe�̃`�����g���֘A���Ă���̂ŁAChriste��Tenor talea��Kyrie�p�^�[���i��3�j�̔��W�ł���悤�Ɍ����AChriste talea�̊e������Kyrie���Y���̏C���łł���A Kyrie�̂S�Ƃ͑ΏƓI�ɁA8�̉������܂ފ��S��talea�ł���B ����́AChriste�̃`�����g��25�������A���ꂼ��8�����Â�3�̃X�e�[�g�����g�ɕҐ����A�I�~�`���������悤���}�V���[�����Y���W��z���\�������邩������Ȃ����A�C�\���Y���X�L�[���̘g�O�ł̏I�~�Ƃ��Ă̎g�p�@�ł͂Ȃ��A�ނ���T�~�T�ƂȂ�悤�����Ă����A�h�ŏI�J�f���c�h�́Atalea���̂ɑg�ݍ��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����Ɍ�����悤�ȃo�C�i���W��W���Ă����͂��ł���B 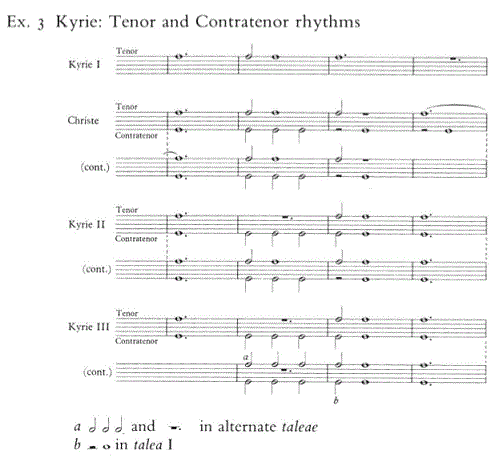 �@Contratenor -tenor�̃y�A�́A�傽��J�f���c�����ꂼ��̃^���A�Ő�����悤�ȂQ�̗̈�����B�ЂƂ́A�^���A�̌��іځi��7�|8���߁`�j������A�����ЂƂ̓^���A�̒��S�i��3�|4���邢��4�|5���߁`�j������B��҂́A�e�m�[���̃s�b�`�ɉ����ď����Ɖ����̃|�C���g��I�Ԃ��Ƃ��ł���B �����āA�㐺���̃C�\���Y���������������̂́A�����I�ɁA���������J�f���c�̏�ɂ����Ăł����B19 19�@���������C�\���Y���̗��p�@�́A�����炭�A�h�C�\���Y���́A�t���[�Y�\���̃J�f���c�_�ɂ��Ă����ĉ��Ƃ��Ďn�܂����h�Ƃ����A�r�������������̒�Ă��x������B ����́A�e�L�X�g�E���C���̏I�~�Ɉ�v����悤�Ƀ��e�b�g���Ŕ��W�����C�\���Y���t���[�Y�̏I�~���A�~�T�ȂɈ����p���ꂽ�ǂ���ł���A�e�L�X�g���Ȃ��Ă��A�����̘a���ɃW�F�X�`���[�ϊ����A�ᐺ���̃J�f���c�_�Ɉ�v����悤�ɂ���B ���ȏ�̐����} 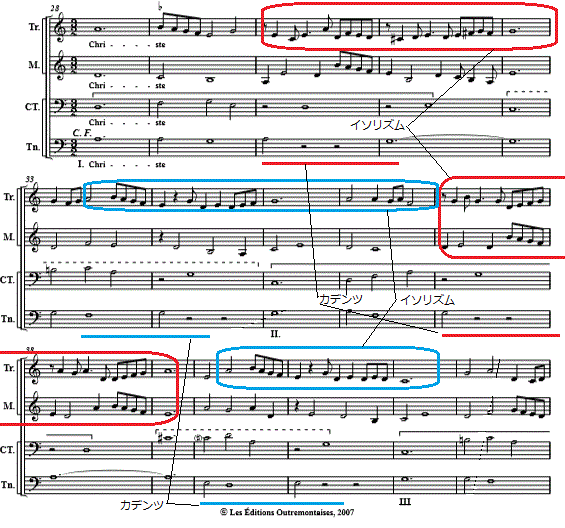 �@Kyrie 1�̂悤�ɁA�ł������ȃ��Y�����^�A�܂�Ahocket��syncopation�̃p�b�Z�[�W�́A�ω��Ȃ��ɏ㐺���Ō����B ��4�́A�e�����̃��Y���𒊏ۉ����Ă���B���ꂼ��R�̃^���A�͂��ꂼ��̐����̉��ɁA�h�h�C�h�h�h�̃��[�}�����ŏ�����Ă���j�B���Y���́A���ւ̂ЂƂ̃^���Astatement����قȂ�ꍇ�̂݁A�L������Ă���BMotetus�ATriplum�̐������́A�����ɓ����C�\���Y���������Ă���B��������A��i�̑啔���͌����ȃC�\���Y���ɂȂ��Ă������Ƃ��킩��B 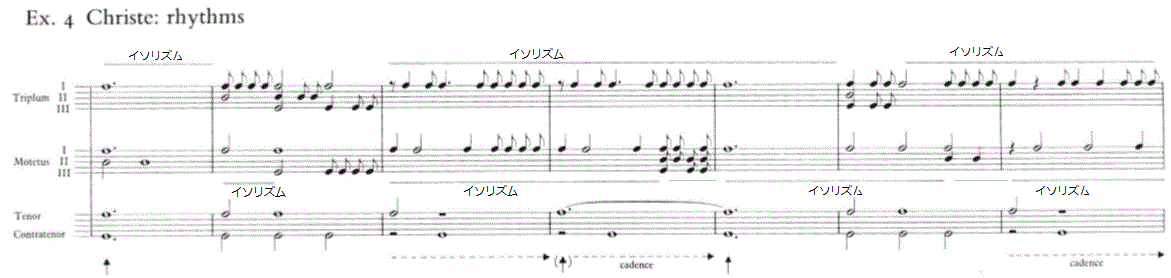 ��i�̍ŏ��ɂ́AMotetus���A���̍ŏ��̏��߂ɂ����ĂƁATriplum�̑�13���߁AMotetus�̑�U���߂ɂ����āA�P��̒��������Ŏn�܂��Ă���_�ŁA�����Ȋ��҂�������B�B����́A�`���I�Ȗ`���̃W�F�X�`���[�ł͂��邪�BTriplum�̑�13���߁AMotetus�̑�U���߂̂ǂ���ɂ����Ă��A�s�K�����͔������Ȃ����A���ꂼ��̃}�V���[�̏I�~�̑I���ɂ����āA�Έʖ@�͂���܂ł̉\�����͗ǂ��Ȃ�B �@Christe�ɂ�����n�[���j�[�̂���Ȃ鋻���[�������́AContratenor �ł̃����f�B�J��Ԃ��̑����ł���B����͖��炩�ɁA�`�����g�����ł̉����̌J��Ԃ��̘A���ɂ��̌��������߂���B�icf. bb.5 �� 7�C8 -IO �C 13 -14 �C I5 -I7 �C 20-I) �@�����āA����́A���̍�i�ɂ��Ẵn�[���j�[�̌�b��}������d�v�ȕ����������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����āA���ꂼ���b�I�Ȍ`���ւ̃����f�B�f�ނɂ��Ă��A���l�ł���B �n�[���j�[�̊ϓ_����AChriste�͔��ɋٖ��ɑg�D����Ă���B�����āA����̎�ȗ��R�́A�`�����g��isorhythmic�X�L�[���Ƃ̊W�ł���B ����䂦�ɁA�`�������ꂽ�e�L�X�g�̒��ŁA��ȉƂ��A�C�\���Y���E���e�b�g�ł͌����Ă����ł͂Ȃ��������@�ŁA�����ɉ��y�̍ו��Ɏ����̈Ӑ}�����R�ɏW�������邱�Ƃ��ł����Ƃ�����ۂ���B 2.2.5 KyrieII,III KyrieII�̒ᐺ���̃^���A�́AChriste�̂����ƁA���ɖ��ڂɊW���Ă���BKyrieI�̂���ւ̃e�m�[���p�^�[���̂悤�ɁB�i��R�́A�����A���ׂĂ�Kyrie�̃^���A���悭�֘A���Ă��邱�Ƃ������Ă���j�B�����āA���������W�̑n���́A21�����̃R�����ݒ�ɂ�����A���݂̂R�~�V�ɑR����悤�ɁA�P�O�̉����{�I�~�������^���A�̂Q��statement�ɂ��Ẵ}�V���[�̑I��������Â��Ă���B �@�������A���̃X�L�[���Ɋ֘A���āAKyrieIII�ɂ��ẴC�\���Y���`���́A�}�V���[�̈̑�Ȓ���������Ă���B���łɏq�ׂ��悤�ɁAKyrieIII�̃`�����g�́A�X���Kyrie�̍Ō�̌Ăт����Ƃ��Ă̂݉̂��邪�A�旧��KyrieII�ɖ��ڂɉ��y�I�Ƀ����N���Ă���B�Ȃ��Ȃ�݂��ɁAKyrieI��Christe�̂������o�����X������3��̃O���[�v���`�����Ă��邩��ł���B �����āA�����������т��́A�}�V���[�̃|���t�H�j�[�ݒ�ɂ����āA�d�v�Ȗ����������Ă���B��P�������悤�ɁA���̍ŏI�I�ȃ`�����g�́A�ŏ��̉��y�t���[�Y���J��Ԃ����Ƃɂ���āAKyrie II�����y�t���[�Y���L���Ă���B�}�V���[�̎d���́A�ނ��|���t�H�j�[�I�Ȑ��k���̒��ŁA�ς�炸��2�̃`�����g�̋��ʂ̑f�ނ�ۑ��������ƍl���Ă������߁A�`�����g�̍ŏ��̃t���[�Y�̌J��Ԃ��ɑΉ�����悤�Ɂi�������A�ނ��A���łɒ����\����j�邱�ƂȂ��ɁjKyrieII�̃C�\���Y���̃X�L�[�����g�����邱�Ƃł������B�����������Ƃ́A���͓I�Ȍ`���I���������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�R�S�̃`�����g�̉����iKyrieIII)�́A����A21�Ɏw�肳�ꂽ�\��(KyrieII)�ɐݒ肵�����K�v�����邩��ł���B �@Machaut�̉����@�́A���������p�I�ł���B �`���̃^���A�́A���̂܂܂�������c���ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�Kyries II��III�̃C���F���g�́A�r���܂ł͓���ł��邽�߂ł���B�������A10�����̃^���A�Ɠ������ł́A�R�S�̃`�����g�̉������\���ł��Ȃ����߂ɁA�}�V���[�́A�e�m�[���ɂ����āA�^���A���A10�����̂ƂV�����̌��݂ƂȂ�悤�ɁA�����������B10+7+10+7=34�ƂȂ�B 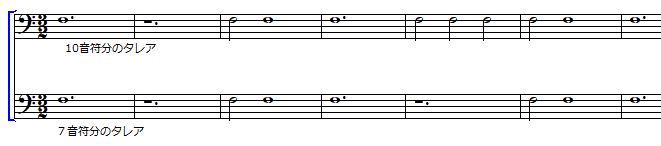 KyrieIII��2��ނ̃^���A ���̕ύX���s�����߂ɕK�v�Ȃ��ׂẮA�S�x���i��12�C26���߁j�ɂ����݂̃^���A�ɂ����Ēu��������꓾���R�̉����i�e�m�[����5�C19���߁j�̃��j�b�g�ł���B�������AKyrieII�̃e�m�[���̃^���A�́A���̃p�^�[�����܂�ł��Ȃ��̂ŁA�}�V���[�́A ��5�C6���߂��AKyrieIII�ŗn�����܂��ĂЂƂ̏��߂Ƃ��AKyrieII�̑�T���߂̍Ō�̔����������Ƃɂ���āA������Y�ݏo���Ă���B 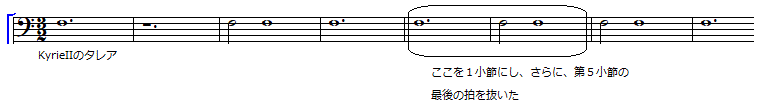 KyrieII�̃^���A �@KyrieII�AKyrieIII���Q�̊y�͂̋��ʂ̑f�ނɂ�����S�̂���Ȃ�ω��̂����A�R�͏������B�iKyrieII��7���߁FKyrieIII��U�����ATriplum���ŏ��̂Q�̉����ŁA�s�b�`���قȂ��Ă���G�@KyrieIII��Motetus��X������KyrieIII��Triplum��10���߂��A���ꂼ��KyrieII��10�C11���߂̑���j�@������4�ԖځiKyrieIII�@��10�͑�Q���j�́AKyrieII�����ʂ���Ō�̃`�����g�̉�����re-harmoniation�ł��邪�A����ɏ]���V���ȃs�b�`���K�v�ƂȂ邽�߂ł���B���̂悤�ɁA���ɊȒP�Ȏ�i���A�}�V���[�́AKyrieIII�̂�葽���`�����g�̉���������邽�߂�KyrieII�̍\����ϊ����邪�AKyrieIII��Abgesang(�����̉́GKyrie�̍Ō�j�Ƃ������ʓI�ł���ׂ������̂��߂�2�̊y�́iKyrie��Gloria�j�̊Ԃɑ��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��{���I�Ȍ`���I����ѐ����I�ȊW��ێ�����B �@����Ɋւ���̂́A�㐺���̃��Y���ŋN����ϊ��ł��B���̂��߂�Machaut�́A���ꂪ4��Tenor taleae��ABAB�`���f����悤�ɁAisorhythmic�X�L�[�������������Ă���B����́A�㐺���̃^���A�̂��ׂĂŌ������Bsecond�������āB���̃��Y���X�L�[���ɂ�����y�͂̑傫�ȃX�P�[���`���̌����ȓ����f���邽�߂ɁA�}�V���[�̃p�[�g�ł̗v���ȊO�ɁA���̂��߂ɕK�v�ȗ��R�͂Ȃ��B 2.2.6�@Conclusion Kyrie��4�̃Z�N�V���������ڂɊ֘A���邱�Ƃ��Ӑ}����Ă��邱�Ƃ́A��3���疾�炩�ł���E����ɁA����炪����Ă����Ă��鏇���ō�Ȃ���Ă���ƐM���鍪��������������BChriste��KyrieI���^���A���g�������AKyrieII�́AChriste�̃^���A���g�������Ă���BKyrieIII�́AKyrieII�́AChriste�̃^���A���g�������Ă���BKyrieIII�́A�g�債���`�����g�̓K�������邽�߂ɁAKyrieII�̍\�����̗p���Ă���B ���̈Ӗ��ŁA�}�V���[�́A�ނ����`�����g�̓����ɔނ̐ݒ�f�����Ă���B�������R����A�y�͂̊Ԃɂ͖��ڂȃn�[���j�[�̊W������B�n�[���j�[�\���Ō�����@�\�̖������́A�e�m�[���̃��Y���X�^�C���̌����ڂ̃V���v�����������Ă���B�����̌`���I�v���Z�X�̑��ΓI�Ȑ������́A �ێ�I�ȃ��Y������i�ނ�KyrieI�݂̂Ɍ��y���Ă��邪�j�́A��i�������̓��t���������Ă���Ƃ���Apel�̒�ĂɑR���Ę_�����Ă���悤�Ɍ�����B21 21�@ Willi Apel �C The Notation of Polyphonic Music �C 900-1600 5th edn. (Cambridge �C Mass . �C 1961 )�C p. 345 n. 1 �}�V���[��Kyrie1�ɂ����閾�炩���S�O�ɂ�������炸�A�����ɒ��ꂽ�؋��́A�����̊y�͂��A���o����ςA�Z�p�I�ɂ������I�ȍ�ȉƂ̍�i�ł��邱�Ƃ��A��苭�͂ɘ_���Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B �C�\���Y���X�L�[�� �e�m�[���@�@�C�\���Y���@�e�L�X�g�@�����@Motetus�@Triplum statement�@Contratenor tenor �R���� �|���t�H�j�[ �v���C���`�����g �g�D���l�[�~�T�� �}�V���[ KyrieChriste SanctusAgnus GloriaCredo�@ ��� �y�� �~�T�� |