| Machaut's Mass3 Daniel
Leech-Wilkinson |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |
| 前ページへ |
| 3 Elaboration 3.2 Four-part conception and composition 3.21 The problem score(このscoreは、GloriaとCredoにおいて、TenorとContratenorが逆なので注意) Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image 私たちは、イソリズムの楽章で、Machautの4つの部分全体の構築がいくつかの段階で進められていることを見てきた。 Tenorのピッチは既存のチャントから借用したものであり、TenorとContratenorのリズムが両方とも規則的に繰り返されるため、上声部の詳細が作曲される前に、2つの低声部が完成していなければならなかった。 マショーは、必ずしもすべてのテキスチャーを持つことがなかったが、それにイソリズムを作用させた。結果は、必ずしも、規則的ではなかった。同時に、このプロセスが連続する段階から構成されなければならない程度を誇張することも可能である。 理論的には、最初にチャントを取り上げることによって、その後にチャントのリズムを書き、次にContratenorのリズムを作成し、その後にContratenorのピッチについて考えるだけで、低声部を作成することは可能かもしれないが、結果は必然的に粗くなる。 これらの要素は相互に関連しているため、最も効果的な作曲手順は、互いに十分な歩み寄りが達成されるまで、さまざまなニーズが互いにバランスを取ったものの一つになることである。したがって、テノールとコントラナーのリズムの作曲は、かなりの程度、作曲家がそれらの間に作りたがっていた対位法の重要性に依存していた。 リズムが許容されていた場でのみ、ピッチは可能であったが、リズムは、ピッチがうまく働く場でのみ、有効であった。これらの要素の混ぜこぜは、我々が見てきたように、作曲家がContratenorのピッチに関する決定と、TenorとContratenorのリズムに関する決定を行き来する単一の操作として最もよく行われた。 低声部のデュエットが完成すると、TriplumとMotetusの作曲に同様のプロセスを適用し、良い声部導入の要求に対して、リズムの可能性をバランスさせることが期待される。違いは、作曲家が、3つのその他のパートに対するそれぞれの可能性を試していることであり、彼が始めたデュエットの場合のように、ペアの相手に単純に対抗することではない。 しかし、これは中世の作曲家にとってどれほど可能であったろうか?当時から現存する正確に整列されたスコア記譜法の不足から、作曲家たちが習慣的に、垂直的同時性を考えなかったことを我々は推測すべきであろうか?‐または反対に -これは、彼らの精神的なコントロールが完全であるために、スコア的記譜法が不要であったことを示唆しているだろうか? または、これはスコアが作曲用に使用された最も合理的な仮定のように見えるかもしれないが、音楽が羊皮紙に(部分的に)記譜されれば、消去可能または使い捨ての素材となり、拭き取られたり投げ捨てられたりするするだろうか? 数え切れないほどの仮定(例えば、理論家が作曲家を一度に1パートづつ書いてく存在として記述したり、作曲家が同時に2パート以上をその頭の中で操作することはできないなど)は、過去に、これらの質問の答えを曇らせる傾向にあった。 それにもかかわらず、作曲家がどの程度水平的に、一度に1パートずつを書いたのか、どの程度垂直的に、4声を互いに書いたのかの、本質的疑問には答えが必要となる。それぞれの作曲法には異なった回答があるかもしれないが、 しかし、それぞれのケースで、中世の音楽家が、個別に密着したラインの相互作用として音楽を聴いた程度と、それが和音の順序付けられた連続として彼に思い浮かんだ程度の影響と理解を得なければならない。 isorhythmicの楽章は、助けにならない。 なぜなら、それらは、どうしても、段階的に作曲されているからである。しかし、グロリアとクレドは、より有益であろう。 そのホモフォニー的、和声的テキスチャーにもかかわらず、我々が、それらが一度に1パートづつ作曲されたことを示すことができれば、我々は、作曲家の優先順位が線形である―響きよりも横のラインの問題―ということができるだろう。そして我々は、その光の中で、より明らかな、対位法的なイソリズム楽章を聞くことができる。 しかし、グロリアとクレドが、全体として、4つの部分から成り立っていると分かっていれば、我々の見方は、グロリアとクレドだけでなく、イソリズムセクションについても、変化させられるであろう。テクスチャの上部にあるメロディーラインは、他のメロディラインよりも重要に思えるかもしれない。 イソリズム的スキームと低声部デュエットがメロディ・デザインと特定のハーモニー進行を既に念頭に置いて配置されている可能性がある。 3.2.2 Gloria and Credo グロリアとクレドの4声が、一貫して独立した機能を持っていれば、言い換えれば、TenorがTriplum、Motetus、Contratenorのためのreferential lineとして振る舞えば、Contratenorが従来のcontratenorとして振る舞い、それぞれが正しい対位法を作り、Contratenorが伝統的なcontratenorとしてふるまい、Tenorに対する対位法を作るならば、云々。 声部は、連続的に書かれていると言われている。 少なくとも、それらが一緒に作曲されていることは絶対必要ではない。 p57「 しかしグロリアとクレドにおいて、4声部は一貫して、このような機能を持たない。不協和音(もっとも注目すべきはfourths)は、上声部と低声部のそれぞれの組み合わせにおいて生じる。 Triplumにテキスチャーのトップを供給する傾向がある(特にGloriaにおいて)。そして、Tenorに対して、その他の声部ともっとも協和するより注目すべき傾向がある。 しかし、こうしたペア(すなわちGloria 第32,76,86小節 Credo第11,25,44,118,139小節)の間でさえ、構造的な四度がある。 Tenorと協和する時でさえ、上声部が作る対位法はしばしば非伝統的であるがそれは、通常、本質的な進行がテキスチャーのその他の場に置かれるためである。 これは特に、カデンツにおいて、注目すべきで、本質的な六度からオクターブへの進行は、一貫して4声部のどの2声部にも割り当てられていない。構造的な六度からオクターブは、四声の間でしばしば生じるが、特に、Triplum と Contratenorの間で多い。(Gloria 第14,76小節)。そしてときどき、3声部間でさえ、見られる。たとえば、六度ミ‐ド♯のミ音が別の声部で、レ音として解決される。(Gloria 第15-16小節。Motetus-Contratenorの六度が、Motetus-tenorのオクターブとして解決される)、 41-2 (Mo-T to Mo -CT) , 69 ーヶ o (Tr-T to Tr-CT)). テノールが伝統的にカデンツでふるまうところでさえ、これは時々、フレーズのより早期に、不器用な声部交換によって、達成されている。(Gloria 11-12、27−9小節、Credo 55‐7小節)。そして、”声部交換”―すなわち、4声がラインを交換するために跳躍する場所―は、両楽章の一貫した特徴となっている。 上記の場所同様、それがTenorパートをもともとのテノール機能へと連れ戻す場では、それはしばしば、他のパートの歌手の手助けとして使われる。彼らに、♯や♭をつけるための正しい方向を教えるのである。 声部交換の第3の使用は、響きのためである。繰り返し和音はしばしば、テキスチャーを”生き生きと”させるために、単純に声部を交換する。2番目の和音は、異なって響く。そのピッチが変わらなくても。 p58 さらに驚くべきは、いくつかの拍に引き伸ばされた不協和音を含む比較的長い進行が、それらが始まった音以外の声で解決できるということである。Credoでは、第22−5小節ではたとえば、 前のサブフレーズ(第21小節)の解決でTriplumとMotetusによって到達されたe 'は、contratenor(第22小節)の不完全協和音程になるよう、移送される。それは、第23−4小節のContratenorとMotetus(ユニゾンで)によって再度取り上げられる。そこではさらに、レ和音への解決が待っている。そして、Trimplumへと移送され(第24小節最後の1/4)、最終的に第25小節で解決される。もしも声部が連続的に作曲されたのであれば、このような進行がどのように配列されたのかを知ることは、困難である。 もし我々がグロリアとクレドが一度に1声部ではなく、テノールの作曲が別個のものではなく、4つのパート全体として考えられたとすれば、こうした通常ではないパート書法の特徴は、説明し得る。 そして、テクスチャのすべてのレベルでのメロディラインが(ちょうどトップではなくても)声部の間を自由に移動するという事実は、それが、(全体が4つの個別の声部に割り当てられていた)作曲過程におけるよりあとの段階であったことを示している。 ユニゾンの多く((最終的なテクスチャを3つまたは2つに減らす)、バスにおける非伝統的跳躍の多くは、マショーの当初の概念が、いつでも、それぞれの声部の正確な働きを構成させるようには試みていなかったことを示している。(たとえばパート書法が、結果として得られるContratenorのメロディ形ラ‐ソ‐ラが歌手に、望ましくないソ♯感を与えるよう促すかもしれないことを知ったマショーにとって、十分にクリアになった時、Credoの第86小節の最後の和音は、最初のイメージであった3音符(Contratenorにおいて、現在の2+ラ音)から縮小されたのであろう。) それで、グロリアの第63小節、あるいはCredoの第43小節のようなパッセージのすべてのディティールは、パート書法のニーズからのみ生じ、始めから明らかであったことはあり得ない。これらの装飾的音型は、もともと生まれた響きから抜粋されたパートとして働いていた。しかしマショーは、非常に早くから、本質的な和音進行についての正確な考えを持っていたにちがいない。 この最初の概念から4つの個々の声部を分けるプロセスは、明らかに、単純ではない。マショーは、低声部のどれもがその他のすべての声部ともっとも協和したそれぞれの和音から、従来のテノールのように、同じパートに割り当てられた程度の慣習に従い、実用的に進めたように思われる。しかしこうした原理は、しばしば、より良いパート書法がその他の配列の結果となった時にはいつでも、脇に置かれている。 p59 たとえばGloriaの第15小節では、マショーは、ひとつの声部(テキスチャーの底から2番目)が、バスのホ音とmeetして、ラソファと降りる進行をイメージした。それゆえ、パート譜に記入する時には、テノールは、Contratenor によって空白になった”ハーモニーを満たすための”場に対して、五度跳躍するしか選択肢がなかった。その元々の位置に直接声部が戻り、第16小節で、バス(Contratenor)はレ音に降りるにもかかわらず、Tenorを繰り返す音高は避けている。 これは、マショーが関心を持った要素であったように見える。Gloria , bb. 7-9 , 72-3 ,101 , and Credo , I04-5 は、彼が2つの連続する和音で同じピッチ(調性)を持つ互いのパートを避けるために、2つの低声部の間で、バス(Contratenor )ラインと第2ライン(Tenor )を声部交換したその他の例である。すでに提案されているように、そこには、必然的に結果となる響きの変化を介して、テキスチャーのモバイルを維持する以外に、一貫した理由はないようである。 さらなる声部交換の明らかな例は、Credoの第35小節で、そこでは、Contratenorは、Tenorの上となっている。なぜなら、結果は、それ以前の小節のより良いメロディ的継続となっているからである。 Mahaut had no choice but to place either the Triplum or the Motetus as the third voice down , until passing notes in the middle of the texture allow it (in b. 36) to rise back towards the top. マショーは、Triplum or the Motetus を third voice downとして位置させる以外なかった。テキスチャーの中間の経過音が一番上に向かってrise backすることをallowするまで。 第37小節での繰り返し音符での声部声部交換で、TriplumとMotetusは、トリプルームを最終的にケイデンスの最高レベルに戻します。(以下略) それらの垂直なorderに従って和音を単純分離をmodifyする傾向にある別の要素は、作曲家が意図した以上のsolmization(我々が♯または♭と呼ぶ臨時記号については歌手によって決定された)を奨励するメロディ形を避ける必要性であった。 これは、マショーがGloriaとCredoにおいて発展させた伝統的なハーモニー語からはかけ離れた、特殊な問題である。そしてそこには、これを考慮してパート書法の立派なたくさんの例があった。 たとえば、グロリアにて、第81−2小節では、Contratenorと tenorは声部声部交換し、Contratenorのド-ナチュラル(Triplumでもある)を確実にするために、優れたテノールラインを壊している。  Gloriaの第93小節における声部のペアは、ド-ナチュラル和音の進行をド♯にするために声部交換をしている。 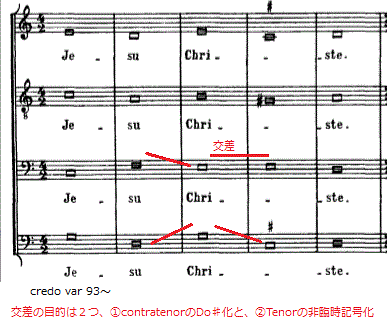 Gloriaの第101小節において、Contratenor とTenorは、最初Tenorのファ♯をそうさせないために、2番目の音符を交換している。同様に、Dredoの第27小節では、Contratenor とMotetusの交換(訳注ユニゾン。なお、テノールもユニゾンになっている)は、第26小節のド♯後のド-ナチュラルを容易にしている。さらに、Credoの第8小節では、 MotetusとTriplumの交換は、メロディのファ‐ナチュラル→ソ♯の増音程を容易にしている。その間、ContratenorとTriplumは、Contratenorのド♯を容易にしている。 p60 この要素に関連して、テノールラインをmusica fitaの付加が必要なピッチ(調性)にならないようにしたマショーの一貫した試みがある。GloriaとCredoのTenorは、すべて、♯、♭が含まれていないことが、校訂譜を見ただけで理解される。 これには、いくつかの理論的原理が、その背景にある。Tenorはどんな修正も受けるべきではない、という感覚である。しかし、歌手たちは、安全に、Tenorを記述されたライン(声部)として受け取ることができるという、価値ある結論があり、その要求に応じて、どのようにその他のライン(声部)をsolmiseするかを決定している。 これがマショーの意図であったことは、Gloria第11小節(第1,2拍の間)、27-8 ,95-6のような交換によって暗示される。その交換は、Tenorからド♯を守らなければ、何の目的も果たさない4。 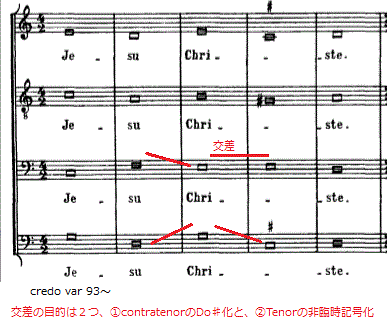 2つのより大きいextractsは、そのような因子がどのように組み合わされて、より延長されたパッセージにわたって最適なパートの配置を決定するかを示す。 Example 9 (system b) shows Gloria , bb. 30-46 as it would have appeared to Machaut if, as a first step , he simply laid out the parts in vertical order of pitch: Triplum , Motetus , Contratenor , Tenor-the order in which they begin at b. 30 in the final version (shown in system c). 例9(システムb)は、まず第一段階として、もしもマショーが単純にTriplum , Motetus , Contratenor , Tenorをピッチの垂直順で構成すれば、それが現れたであろうGloriaの第30‐46小節を示す。システムcは、第30小節からの彼の最終版を示している。 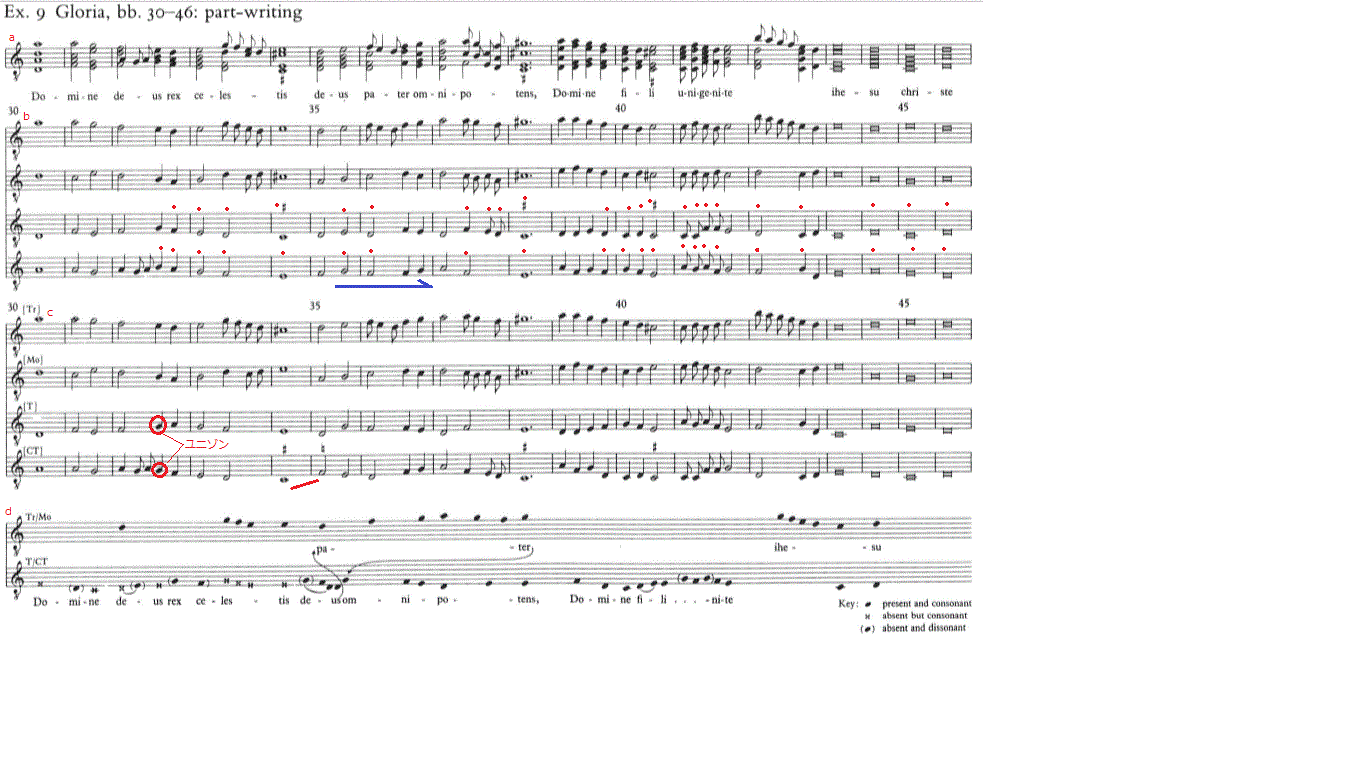 MotetusとTriplumにとっては、少なくとも、こうした配置で十分に満足すべきであると思われる。MotetusがTriplumの上にある数少ない機会(第34小節,40小節第2拍から第41小節第2拍、第43小節)は、オリジナル(aシステム)からの単純な垂直転写から得られる声部導入に、より良く示される。 しかし、Contratenor とTenorは、頻繁に交換しているのである。 第34小節においては、Contratenorのド(♯)は、マショーが臨時記号をつけない慣習としていたTenorから受け取られている。そして、それに(臨時記号をつけない慣習としていたように)容易に導くために、Contratenor とTenorは、前の方の音符と同様、交換をしている。そこでは、マショーは、Contratenor とTenorの間にユニゾンができる第32小節の最初の3声の和音まで戻っている。 (ユニゾンは無論、交差するパートにとっては、もっとも便利なポイントである。この場合、よりよい声部導入をするために、Contratenorはおそらく、(第32小節において)元々は、Motetusと共にユニゾンとなるシ音を持っていた。マショーは低声部の利益のために、Contratenorをソ音に変えたのである)。 この交換をすることで、低声部は、Ex.10aのようになる。この段階で、第36小節のtenorは、歌手には、Triplumとクラッシュするような、ファ♯を示すことになるかもしれない。 それゆえマショーは、第36小節において、ユニゾンのファ音の声部を交換している。そのために、Contratenorにおいて、ファ→ソへとなっている。 第35−8小節は、ここで、Ex.10bとなる。しかし最後の交換は、Tenorへのカデンツ、♯がつく可能性のあるドをもたらしているため、ド(♯)をContratenorに戻すために、さらなる交換が必要となってくる。それが、Ex10cである。 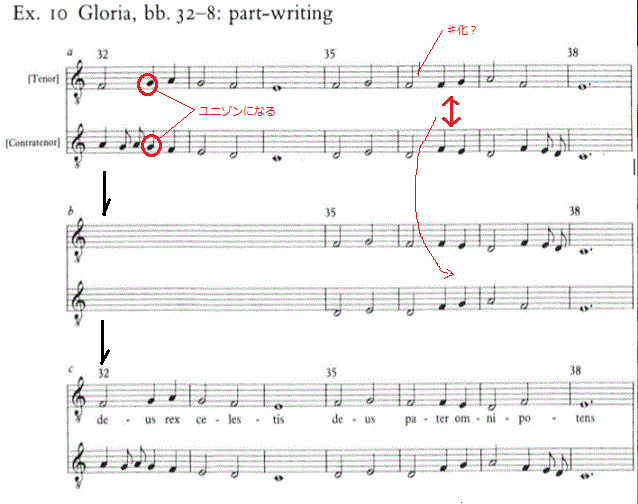 こうしてマショーは、さらなるもう一つの変更を行い、そしてそれは、もっとも興味深いものの一つである。最後の例が示しているように、Tenorラインは、退屈な繰り返しなだけでなく、単語'deus'が、ファソの同じピッチである2つの続くフレーズで始まっている。これは、歌手や書記に、 誤った部分をスキップし、それぞれ2回、’deus rex celestis’ として歌ったり、写譜したり、それをすべて残しておくような、古典的機会を差し出す。 マショーはそれゆえ、ContratenorとTenorのピッチを第35小節の第1拍を交換し、テノールラインに全く異なった様相を与えた。不器用なContratenorのド(♯)からファ‐ナチュラルへの跳躍という犠牲を払ってであるが。6 明らかに音楽は、歌手たちの慣習に則って、それを念頭に、アレンジされた。 より複雑な例が、例11で示される。Credoの第19−26小節である。Ex.9におけるように、system aは、マショーのもともとの概念を示しているのではなく、最終版である。これは最終結果の詳細を欠いているだろうが、それを確かめることは不可能である。 可能性のあるオリジナルな状態は、以下例11に示されている。system bは、ピッチの垂直配列の構成である。しかしここではすでに、マショーが、彼がもっとも効果的な構成と考えたような、自動的に行った種類のカデンツ(第25‐6小節)における、声部の再配列を含んでいる。 しかし、system bは引き続き、より文字通り念頭に置かれていたものである。Contratenorの第21小節のレドの経過音は、ミ音へ導かれる必要がある。それは、Motetusから取られることができる。その前にContratenorの前のラ音が取り去られている(ミ音になっている)。 この進行へのより良い声部導入に関して、マショーは、先立つ第20小節の4つの音符のために、こうした声部の交換も行った。それから第22小節において、MotetusとContratenorは、ミ音とシ音の間のピッチのがそのまま繰り返されるのを避けるために、交換がなされている。第24小節の3声部和音において、マショーは、ド♯‐ラ‐シ‐ドのメロディクラッシュ(対斜)を避けるために、Triplumのミ音を取るContratenorに、Motetusのド♯を置き換えた。 system cは、ここまでの限りでのものが書かれている。次に、こうした交代の結果むしろ鈍となったMotetusのラインは、第22小節からのMotetusとTriplumのあえての交換により、生き生きとすることになる。そのために、(第22小節は)4つの音符でオクターブをカバーしている。演奏において、我々は、Motetusの歌手が、ラ‐ソ♯‐ラへと跳躍する生き生きさを聴くことになる。 最後に、両上声部は、第25小節第2拍で、元の位置に戻っている。マショーは再度、繰り返しピッチや、今回は、2つのレ音がTriplumであるのを避けるようにしている。 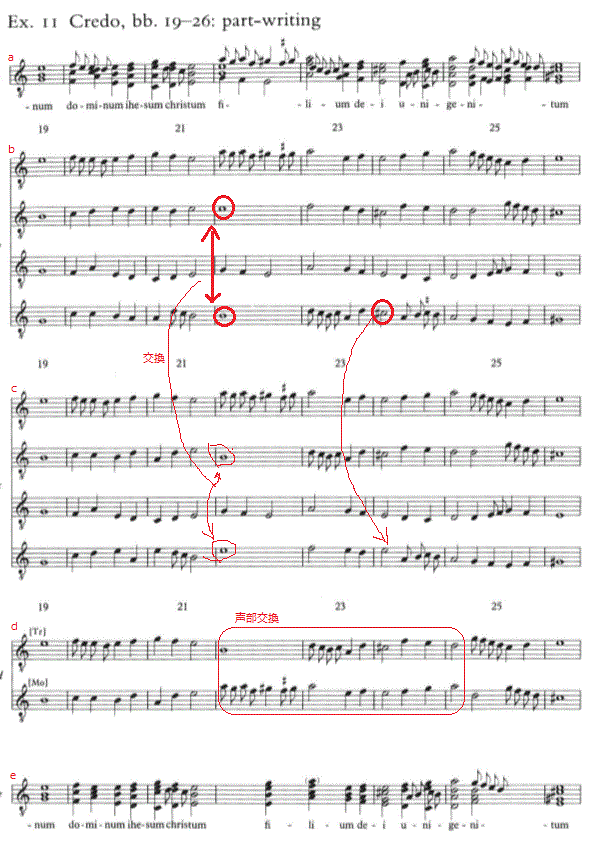 こうしたプロセスの結果は、非常に複雑なパート書法の集まりであり、複雑な音楽のスパンに適用され、その基礎となるハーモニー構造は、作曲上の精緻化のいくつかの層の下に隠されている。 これらの層のいくつかは、分離されている可能性がある。しかしこれまでの議論では、マショーの概念の統合にどのような詳細が不可欠であり、音楽を別々のパートに分けた時にだけ進化したかを決める試みはなかった。 パートへの分離が始まる前に、音楽は最終的な形式をとっていたと仮定していた。 しかし、これはあり得そうにない。 p64 正確には、Machautがパートで作曲を始める前にどれくらいを確定したかは決して分からない。 しかし、その詳細が仮説的でよけれれば、彼が従った可能性が高いプロセスの種類を示すモデルを提案することは可能かもしれない 例11e は、 まさにMachautが最初に想像したような形のものであった。 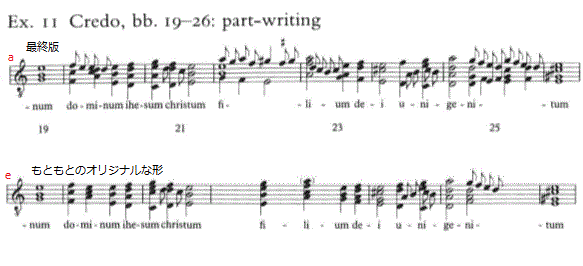 それにはすでに、和音進行を円滑にするために必要な経過音がすでに含まれているため、最初から出現する可能性があるが、第20小節の最初や、2番目の和音のContratenorのレ音のTriplumの音型などの詳細は含まれない。どちらも、その小節の2つの中間和音間の弱い進行を助ける。 そこには、より重要な2つの違いがあります。 TriplumとMotetusの‘unigenitum'のシンボリズムのために、そして、カデンツ前の余分な拍へのニーズのために、メロディの下降の繰り返しが可能性としてマショーに生じた時、「第25小節」は後の考えとして拡張された可能性が高い。7 そして、それは今度は、カデンツへの低声部のかなりの精緻化を含んでいたであろう。この縮小された形で見ると、第21小節から23小節の導入において、作曲上の問題があるように見える。第21小節の終止形が全体的に考えられた時、それはミ‐シ‐ミ(↑)‐ソ(↑)を介して第21小節のミ‐シ‐ミ(↑)‐ソ(↑)の和音から、第24小節のミ音へ降りる第23小節の残りへのむしろ弱い進行に擬すことに過ぎない。 しかしこうした偽装は、素晴らしい。既に言及した音声交換と結びついて、むしろミ音バウンドのハーモニーに新たな刺激を与える。 第23小節のスコアの詳細は、言い換えれば、その機能に固く結びついている。そして、それがパート書法の段階でのみ考えられた可能性は強いだろう。 p66 これは、例11e を精緻化するプロセスの一部として導入された不協和音によって裏付けられているように思われる。 ピッチミ音の延長は既に述べられており(p.58)、パート書法プロセスの議論は声部によるmigrationを説明している(p.63)。このラ音パッセージを通した延長はちょうど注意深く整えられている。 第20小節第2拍の傑出したバスの位置から、第21小節(Motetus)の不協和音として強化されている。そして再び、第22小節のテキスチャーのトップで。 それは第23小節冒頭の、不完全協和音程音のもっとも不安定であるだけでなく、次の和音の不協和音として保たれる(第23小節の5番目の音、Triplum)。それは、(不完全)協和音程であるが、第24小節の最初の和音は聞こえない。そして、再度、この小節の後半で、第25小節の最初の和音での最終的な解決に導びくContratenorの音型で取り上げられる。 しかし、仮説的オリジナル(例11e )にも根本的にかつ存在するミ音とは異なり、ラ音は、パッセージにおける強力な凝集力であるが、最終的な精緻化においてはそのようになる。第21小節の第1和音、第23小節の第2和音での不協和音ラ音、そして、第22小節のラ音は、最初から正しく想像されたことはほとんどない。それは、おそらく4つの個々のパートの産生に関連して、あとで行われる詳細に依存している。これは、Machautの最初のアイデアが、彼の最終的精緻化よりも必然的に慣例的であるとは言わない。しかし、それは、声部導入がパートとしてより精緻になったことが、特殊化され、テキスチャーとして、lifeに大国的になったことを暗示している。 Machautの最初の概念からの詳細な処理のこの観点は、より早期に起こった疑問を理解するのに役立つ。作曲プロセスで導入されたGloriaの チャントパラフレーズがどこに導入され、その詳細がどのように決定されたのか? チャントへの最も拡張された言及(第8-15,17-22,24 -8,35-40,57-63,68-74,88-,91,99-101小節-例6では)はほとんどの場合、2つの声の間でmigrateする。これは、当初、パートの処理の間で勃発したオリジナルのcantus firmusラインを示すように見えるかもしれない。しかし、第2章で見たように、チャントは常に存在するわけではない。そしてこれは、MachautがGloriaの繰り返すメロディ-ハーモニー構造を解明し始めた時点から、彼が、チャントメロディーを、継続的に存在する筋道として見ていないことを示唆している。 もともとの、和音的な概念の上に提示された明らかな効果を考慮すると、我々が暫定的に考慮する大部分は、その楽章が、チャントの和音的精巧さとして想起されることである。完成された作品のどの瞬間において、その存在、不存在よりも、メロディ-ハーモニープランのニーズが優先される。 このシナリオは、チャントが存在しないいくつかの点では、存在するピッチに(完全にまたは不完全に)協和することに注目することによって、支持されるかもしれない。これらのケースは、Ex.6において「x」記号で示されている。 p67 そして、これは、メロディを処理するプロセスが、より良いパート書法が得られるところで、和音を書き直すこと(そして、それによってチャント記譜を失うこと)を含むことを支持するかもしれない。 これはEx.9に示唆されたプロセスと結びついているようだ。 Ex.9dは、マショーの最後の版で、あるいは彼の最初の概念において(「x」記号で示されている)、チャントがどの程度現存しているのか、についてのいくつかの考えを与えるために、例6と9aの情報をまとめている。 一方、ポリフォニーとチャントとの最も近いマッチングは、シラブルをシフトすること(‘ deus pater omnipotens' と ‘ihesu') ,を伴う(下譜)。なぜならこれは、作曲家がチャントを、その”のこりもの”としてハーモナイズさせるほど重要ではないことを示唆しているからである。  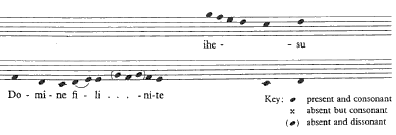 私たちは、作曲プロセスのどの段階でも、マショーが、チャントの単純な和声化を試みたとは確信できない。彼は非常に確信的に、テキストから、パート書法への和音の連続に対するメロディ-ハーモニー構造へと心がけていた。 この見解の利点は、メロディ構造がテキスト(第2章で示唆したように)と直接関係して発展し、その後、ポリフォニック・テクスチャー全体の初期概念を生じさせたということである。もしもポリフォニック・テクスチャーが最初に登場すれば、チャントの和声化として、テキストと音楽との密接な関係がどのように説明されるのかを知ることは困難である。 しかし、たとえこれが具体化されすぎても、メロディー構造、カデンツ形成、パート書法が許容される場合にのみ、グロリアがそのチャントに言及すると言うことができる。マショーは最初から頭に入れているかもしれないが、 作曲の詳細が確定されると、作曲プロセスにおけるこれら3つの支配的要因がすべてよりも優先されるのである。 ここで提案されているプロセスは複雑ですが現実的である。すべての詳細が、はじめから十分に形成されていたことは要求されないが、 パートが一度に1つ追加されれば、複雑で注意深く組織化されたテクスチャが生成されるとは考えられない。 現在の問題は、このMachautが頭の中でどのくらい作業処理をしたか、パートが完成したか、記譜の助けがどれくらい必要だったかということである。 p68 中世の作曲家の記憶力は、20世紀のそれに比べてより活発であった。 彼はより多くの音楽を覚えていただけでなく、結果的に、彼の音楽の想像力はより鋭かった。一度マショーの概念が和音について特別に具体的になったならば、彼は記譜法に頼ることなく頭の中でこれらの楽章それぞれの大部分を作り上げていた可能性がある(訳注;まるでモーツァルトのように!) 。 しかし、これが彼の力の過大評価であるならば、パートの詳細を処理する前にこの段階で使用されていたいくつかの記譜法は、スコア方式かあるいは1つの譜表であったに違いない。 これが必要だったかどうかを見積もるには、マショーがそれぞれの楽章を一度にどのくらい作業しなければならなかったかにかかっている。 パートの詳細が整えられる前に全体を考えなければならなかったのか? それぞれの楽章のための単一の全体的な形式的またはハーモニー計画の欠如は、そうではなかったことを示唆している。 より明らかに組織化されたグロリアでさえ、最大の形式単位は「スタンザ」であり、これはマショーが全体としてはっきりと産み出す必要があった最大のものである。 しかし、参照すべき最初のスコアがなかった場合、パート処理の過程は、幾分困難となる。マショーは、意識的に、必要以上に、より分離された段階を経ねばならなかった。彼の想像力がより鋭くなればなるほど、困難性は減っていった。 どちらの場合でも、パート化への取り組みは、単なる表記ではなく、多段階のプロセスであり、別々に個別に記譜されたパートよりもはるかに効果的に、スコアで管理されていたであろう。この必要性には決まったような形式はなかった。Machautは、消去可能なタブレットに容易に取り組むことができ、プロセスの各段階で変更を行うことができた。 パート書法の段階でのスコアの使用に対するいくつかの支持は、パート間のmi(シャープ)記号の矛盾する配置から来ている。これらは決して常に、必要とされるすべてのパートに配置されているものではない(例:Gloria、第28小節(下譜)、Credo、第76小節)。 現時点では、これについての最善の説明は、以下であろう。すなわち、♯はもともとはスコアシステムの上、下、または中央に配置され、それらが適用された和音に付随していたが、そのうちに(パート譜に分けられるうちに)、それにふさわしいパートのそばには必ずしも書かれなくなった、ということである。写譜者は、クワイヤーブックの形式に筆写した際に、あまりに文字通りに、これを行ったのかもしれない。 p69 同様に、Elizabeth Keitelは、「Amenの存在しないGloriaと Credo」とテキスト化された部分の「MS EのCredoとそのAmenの間」の混合パートとのcustodesは、スコアとしてそれらが存在した大きな証拠である」と記している。スコアの使用はおそらくあったことだろうが、それが仮定の過程であることは、本質的な問題ではない。 <まとめ> これまでの議論をまとめると、Machauはグロリアとクレドを各パートではなく、大まかな和音全体として考え、それをある程度再構築できる基準に従って、4つの声部に分けたと示唆されている。 Machautの元の概念の状態のモデルを提案し、使用されている記譜の種類に関する一般的な議論がいくつかある。 さらに重要なことは、4パートテクスチャの非常に洗練された扱いと、垂直的響きやそれらを産生する声部導入がよく制御されていることを示す蓄積されたエビデンスがある、ということである。 それは、この新しい証拠が我々の創造観にどのような影響を与えるかを知るために、イソリズム楽章をフレッシュにするように私たちを誘うのである。 3・2・3 isorhythmic Movements 我々は、イソリズム楽章において、TenorとContratenorが、満足のいくイソリズムや対位法のペアを作るために、大体一緒に作曲されていたに違いないことを見てきた。 上声部もまたペアとして作曲されていることは、hocketのパッセージにおける非常に密接な関係によって確認されるようである - 先行するパッセージの旋律的解決を提供するもの、時には他のもの(e.g. Kyrie 11, b.5 continuation of Tr and Moi n Mo; Ky rie III,b. 5i n Tr; Sanctus, b.60 Mo,a nd b. 36 Tr)は,相互に依存している−そして、互いに依存関係にある Kyrie 11,b. I2 or Agnus 1,b. Iのようなパッセージによっても。 p70 Kyrie,Sanctus,Agnus and Iteについては、マショーが、in 4パート全体を念頭にして上声部の作曲を終了したことを支持している。グロリアとクレドでの4声部のコントロールを見た後では、これは驚くべきことではない。 Kyrie IIとIIIはどちらも、注目すべきMotetusのメロディから始まっている。こうした進行(中略)が、Triplumの作曲からどのように分離して作曲されたのかを知ることは、困難である。4声の関係は、かなり初期段階から考慮されていたにちがいない。なぜなら、Contratenorの対位法は、マショーが上声部とともに計画したものに影響を受けているからである。 この議論は、TriplumとMotetusのイソリズムと4パートのハーモニーの関係を考慮をもう少し取り上げてもよいかもしれない。 Sanctus(第16小節以降)のイソリズムセクションでは、hocketの小節のペアが(第20−1小節)、2つの”pause小節”の間に位置している。そのために、それらの低声部は精緻化しているが、それらは、論理的には、それに続く3拍和音へと導かれる。(当然これはTenorとContratenorの間にも成り立つが、これらの小節でのより速い動きは明らかに固定されており、上声部のhocketsがその上に置かれていることはわかっている) それぞれhocketの小節で終わるTriplum -Motetusリズム音型は、こうした導入機能を見事に差し出している。この慎重にデザインされた金型に対し、マショーは巧みに、工夫した声部導入をしている。 例えば第83-86小節で、Triplum と Contratenorのそれぞれシ音とソ音は、hocketの終わり(第85小節の最後の音から第86小節へかけて)のみ解決される。その間、カデンツとしてのミ音は、その進行に強さが与えられ、テノールの第83小節からMotetusの第85小節へとmigrateする。 マショーは、Tenor-Contratenorのペアを、特に熟考もすることなく、このような小節に配置をした。しかしそれは、特にTriplumとMotetusのリズムに組み込まれた対位法的機能を考慮すると、そうは思えなくなる。 これらの同じ小節とその続きは、Machautの長い朗読のメロディック・シークエンスの1つで、今度は2つのレイヤーで同時に演奏されます。 Tenor bc 'の続編であるTenor -Contrator a(b.85)は、Motetus d'(bb.88-8)-e'f'sharp -g '(9 0-r)-a '(やはり最初のg点よりも1オクターブ上の位置)でトリプルムの最後の部分になる(b.93)。 The Tenor e '(b.83)、つまりeは、Motetus l'(b.86)に解決され、Triplumには「鋭い」(b.87)-g'(88)-a 'に変換される 90)-b '(91)、最後のメロディー・ディケン・イン・ザ・ア・プ・ア・ア・プ・グイン(b。 もう一度、これは低音のデザインとは何の関係もないことを証明していますが、マック・ハットがTripleumとMotetusを4つのパート全体に渡って継続的に構成し、 痛みを訴える p71 もっと興味深い例がAgnus Deiにある。 AgnusIでは、TenorとContratenorの休符は、連続して鳴っている音符との間で幅広い跳躍をもたらすような方法で配置されている。第16小節の四度、第4、11,12小節の五度、第9小節の六度、第9、11,小節の七度など。作曲家は、上声部を使ってどのように動作させるかが分からない限り、そのような低声部のデュエットを扱うことは考えられない。第9、12小節は、Machautが自分が行っていたことを正確に確認しているように見える。いずれの場合も、低いContratenorから高いTenorへの飛躍は、もしもそれが休符の代わりに音符となっていれば(第9小節ならミ、第12小節ならソ)、Contratenorにある音符に協和するピッチで、再度和音化することであろう。 言い換えれば、マショーはTriplumとMotetusを使って、低声部でのハーモニーを暗示しているのである。 (これは、Sanctus、bb。20-5(および49-50も参照)との比較で確かめられる。Tenor-Contratenor進行は逆に、すべて音符で満たされている)。TenorとContratenorは、上声部を念頭において作られたに違いない。 AgnusIIにおいて、マショーはさらに、低声部の音符と休符を交互にしながら、ひとつのラインを作っている。複合メロディは、2パートの対位法構造を暗示する。さらに、彼は絶対的に、上声部に休符があることを再び、絶対に確信しているに違いない。 p72 イソリズム楽章の声部パートは、それから、イソリズムのプロセスが要求する限り、連続的に作曲成される必要がある。Tenorと Contratenorは、それらを許容にするリズムスキームとの関係で、Contratenorのピッチを決定するためにのみ、十分ペアとして扱われなければならない。 しかし、これらの決定は、作曲家が上声部で何をしようとしているかによって、既に影響されている可能性がある。 低声部のリズムスキームは、休符のポイントで、上声部が1つのpauseから、それぞれに該当するテノールチャント上の次のpauseへと指示されることができることを知って、ハーモニー活動の領域を交互に変えるように形作ることができるかもしれない。(3拍のpause和音は、それぞれのタレアで2〜3回は生じている) 熟練した作曲家は、彼が低声部のデザインにどのような決定を下しても、上声部に満足できるものとできないものを予見することができる。したがって、TenorとContratenorの詳細を確定すると、彼はすでにTriplumとMotetusをどうするかということを、大まかに考えている可能性がある。 TriplumとMotetusのディテールを完成させるとき、彼はもちろん4声部を全体として考えている。これは、我々が観察した関係の暗示であるように思われる。 GloriaとCredoについてのMachautの手順を考慮すると、それは驚くべきことではない 3・3Prolongation Machautは4パートを一緒に作曲をしていたので、ハーモニーとそれを作り出す4パートを、それほど洗練されていない手順で可能だったよりも、一心的に、より長期的な目標に向けることができた。彼がこれをどのように管理しているのかは、さらなる調査に値する。11 11Sarah Fuller,‘On Sonority in Fourteenth-Century Polyphony Reflections',journal of Music Theory,3 0 (I986),3 5寸O .我々は、単一のメロディーライン(通常は内声)が音楽のいくつかの小節に4パートのテクスチャを通して導かれる方法のいくつかの例を既に見てきた。 これらのうちのいくつかは、単純進行であった(Kyrie II と III、第1-6小節、Sanctus、第85 -94小節)。 他のものは、しばしば、変化するテクスチャーを通して、単一の音程(または音韻)の延長と継続を伴い、しばしば、別のものへの最終的な進行に向けての作用を強める結果となった(Credo、第21-5小節、Sanctus、 第83-5小節)。 この技術の根底にある原則をさらにいくつか示す。 p73 最初に単純なケース。サンクスでは、第22-3小節は、 Contratenorのソ音とTriplumのシ音'は、ラ音の介在する和音によって延長されている。 TriplumとContratenorの双方のラ音は、ソ-シの響きとなり、前に戻るために、聴取者にとっては、その2つの小節を通して継続的な効果を飾るだけである。 さらに、第22小節の和音のTenorのミ音は、Motetusによってラ和音に取り込まれ、そのMotetusラインは、最初の和音(第23小節)にはないContratenor上の三度を満たすまで、ステップダウンしている。第24小節の解決は、三度と十度の間隔を導く。そこでは ファ音上の五度と12度に向かって、2番目のシ-ソ和音が作曲されている。 しかしテノールはまた、高いファ音は、これまでのミ音の解決として現れる。この解決のために、高いミは、たとえ鳴らなかったとしても、「存在」していたように見えるからである。 モテトゥスは中間声部を新たな地位に導いたというほどではなく、むしろ暗黙のうちに、暗示的なミ音のしたに、第4声部を生み出したようである。 したがって、イソリズムによって強制された3声部への減少は、カデンツの準備がこれらの2つの小節を介して解決する必要性を強めるにつれ、ほとんど見られなくなる。例12は、このような言葉の記述を保存するために、この分析をどのように記譜することができるかを示している。ビームは延長を示し、スラーはある音が別の音にどのようにつながるかを示す。装飾ピッチは、隣接の(または補助的な)音符については「N」、パッセージについては「P」とラベル付けされる。 同様のprolongationは、Kyrie、Gloria、Credo、Sanctus and Agnusの冒頭で、より大規模に見られる(Kyrie I、bb。I-3、Christe、I-3、Kyrie II、1-3、Kyrie III 1-3, 1-4, 5-8、Credo、3-5, 6-9、Sanctus、1-5, 48-51(Osanna)、AgnusI ,1-4、AgnusII、1-3)。確かに、次のセクションの焦点的響きを確立している。 これは、たとえば、Ballade 42や Rondeau21のようなMachautの曲のいくつかの開始時に同様の進行が生じたのではなければ、後の「循環」ミサ曲のモットーオープニングに匹敵する、各楽章の冒頭間のリンクの熟考的創造を示唆しているかもしれない。 . 例13はSanctus;の冒頭部を分析する。 例14は、3回の呼びかけ「Sanctus、Sanctu s、Sanctus」を設定して、非イソリズム的導入の全体が、ファ-ドの「響き」の枠組みの中でどのように働いているかを縮小した形で示している。 p74 同様に拡張された例は、Sanctus第30-45小節によるレ-ラの響きのprolongationである。 これは前の例よりもはるかに弱い連続性を提供する。 その(第30,35,42,45小節)のレ-ラの”支柱”間に介在する響きの少なさが、協和するピッチを表現するために。 それゆえに、この場合、音楽が基本的にあまねく存在することを示唆するのではなく、音楽がそこから離れていくにつれて、レ-ラ 'の響きが「‘kept in play'」になるのがより適切かもしれない。 最初の例では堅調に延長され、2番目の例では緩やかな「‘playing round about'」という、これらの極端さの間に、マショーは、焦点の響きの周りの音楽の大部分とと単純な進行を組織している。 Christeは、完全な音楽のセクションを作るために、prolongationsとprogressionsがリンクする方法の典型的な例を提供している。 例15は、マショーがチャント(bb.1-3)のラ音の繰り返しを利用して、次に、ソ音(第5-8小節)の反復をし、五度下のContratenorによって対位法的となった。互いにレ-ラとド-ソで結びつきながら。これらはマショーが不安定にした第4小節で結びついており、したがって第5小節に向かっているTriplumとMotetusの精緻化によって。 次のパッセージは少し複雑である。 Bars 9-11は、第12小節のラ音の不完全協和音へと導く。しかし、さらに安定したD和音についての第11小節の干渉は、さらにメロディのラ音をprolongし、第13小節に至り、D 和音と結びつける。そのために、これらの小節は、A、Dの響きともに結合されている。 Christeの残りの部分は拡張されたprolongationsを避けている(おそらく、第1-3小節(dに焦点を当てた同じリズム)が示すように、第17小節のContratenorがb.15と関連してド音を使用して)。 Machautは代わりに彼の進行を、第18小節のTenorのレ音に向ける。 18、再び高いa 'を支持する。その後、最終的なコードへの効果的な旋律的な降下を可能にするために、高い(「最後に導入される(b.20)」 p76 ここでChristeでは、Machautがほぼ完全に(「ダンJベースの響きの上)」と「g(上のc、e、gの上)」に焦点を当てているのを見て、拡張されたメロディーモーションの主な領域は、 -4、6寸、13-15)、最終的にはトリプルームがトップcになるまで "最後にもっと効果的に下に向かって最終的なaに導く"。そして、この焦点を中心としたメロディーな "ホバリング"ピッチやマッソーの治療の一貫性のある特徴は、トリプラムと九十テトスの一貫した特徴である。一貫して、モトゥスはトリプルームの支持として機能し、ιi1との平等な足場のメロディーラインではない。メトトスは、トリプルームと低い声の間の空間を埋めるだけで、旋律の糸を取り上げることはほとんどありませんが、それは十字架のどこかで、いつも良い声のためです(例:Christe、b。3 et seq 。b 'からの白降下物は、彼らが内部の声に導くときはいつでも)、または歌手からの誤ったソルミスを避けるために(例えば、 Sanctus、bb.2と12は交換所がTriplum b 'flatを失望させる)。マチュウがtrebl←ベースフレームワークの中でハーモニックとメロディックの延長を編成していることを、マッソーが結論づけているのを避けるのは難しいです。Agnus 1は、MassのFベースの半分から、これを特に明確に示しています。TriplumとTenor bbで。 8と10、bbのMotetusとTenorの間にある。 1,8、および10は、上位の音声が書き込まれなかったことを示します Agnus 1は、MassのFベースの半分から、これについて特に明確な例を示しています。TriplumとTenorの間の四つ目はbbです。 8と10、bbのMotetusとTenorの間にある。 1,8、および10は、テノールとの対立的な構造を作るために上の声が書き込まれなかったことを示しています。 TenorはContratenorと一貫して一致しています。この章で収集されたすべてのエビデンスが示唆しているように、基本的な基準線は低音です。上の声が構成されていたのは低音だった。同様に、上の声の間でも、一貫してTriplumやMotetusではなく、Machautが旋律的な一貫性を生み出すために一貫しているのではなく、一番上の声です。次のラインは、ギターのようなギターを犠牲にしても、等高線。従ってbb。 8と5) - 10 MotetusはTriplumに上がります アイリズム・スキームがTriplumの跳躍を下方に強制するKyrieのピッチの議論を比較し、同様にb。 15は前のBコードの分解能を提供し、そのリズムはトリプルムのリズムよりも長いクライマックc "である.19において、九十テラップは、最後のcの下に響きのある三番目の"いずれの場合も、結果として生じたMotetus線は、Triplumよりもあまりエレガントではなく、一緒に作る線よりも静かです。これを念頭において、私たちは p77 このことを念頭に置いて、Aglus 1のtrebl e-bass対面構造を調べることができます。例16のスタッフは、アウターラインの詳細の大部分を占めています。 テクスチャ Sta仔は、焦点の妙なつながりがどのようにつながっているかをより明確に示すために詳細を作り出しています。 p78 焦点J-c "の内部および間を移動する分析の中央部分は、3-taleaのアイソリズムフォームのほぼ全体を占めていますが、どちらの端にも5から5のメロディック降下によって境界が定められています。その境界線の下降はb 'flatを使用して音楽を決定的に1に向かわせ、最後の降下をより決定的にするコントラストa11ここではSanctusに興味深いpara11elがあります最初のオサナが内面の声で最後の降下を隠しているところで、マチュウはベネディクトゥスの結論のために白いHのメロディーな降下をb 'フラットに保っていた。どちらの場合も、トリプルームとモトゥスの建設の後ろに慎重な計画がある。これらの正式な効果が確実に生み出される部分であり、我々が見てきたように、MachautがTenorとContratenorを構築している間に既にそれらを計画していることは決して不可能ではありません。 Kyrie、Gloria、CredoよりもFベースの演奏ではかなり簡単に演奏することができます。ここではその曲が頻繁にそのモードで高くなるため、作曲家はその下の自分のベースラインを自由に動作させることができます。ハーモニックプログレッションとそれがサポートするボイスメロディーは好きな形に操作する方が簡単です。このような状況では、マサウトは、テノールが低いほど可能なものよりもタイトなメロディックな構造を選ぶということは、近代的なリスナーだけでなく、最近の音楽の経験を通してフィルタリングされているという重要な証拠です。これに照らして、 これは、グロリアの構造を理解しやすくなります。メロディーベースの枠組みの中で、その作曲家が習慣的に(随時、この作品では)考えていたことを理解すれば、一番上の行のパターンを繰り返すことによって、大規模な音楽の編成が完全に論理的に見えるようになります。 Machautの4つの部分の全体的な概念は、おそらくこのような枠組みの中で結晶化されているだろう。この枠組みの中で、 'とd'の間で下降して戻ってくる旋律の規則は、律動的な動きで見たものと密接に一致する。もし 同様にCredoでは、(最終的に)cadential e-e 'の響きに向かって下降していく進行への音楽の順序付けは、isorhythmicの動きに見られる延長と進行の過程を密接に反映している。しかし、グロリア出身のクレド・ディ・ミーサーたちは、トレブ←ベース企画のおかげで、まったく新しい考え方を取り入れて3つの点で取り組んでいます。第1は、d-a 'の響きの重要でない役割である。第2は、m勾配または焦点としてのc-fの出現である。 3番目はメロディック・リターンとリターンの相対的な位置付けの不規則性(グロリアと比較して) これらの要因は相互に関連している。グロリアでは、aとdの間のメロディックモーションは、多くのクロースリズムを生み出すベースの(多かれ少なかれしっかりとした)長さのdsによって支えられていたが、Credoでは、音楽がないouvertに多くの到着があるより決定的な解決策を探し続けることが重要です。ハーモニーはより一貫して指示されます。定期的なメロディー・パターニングは、連続したフレーズを編成する手段としてはあまり役に立ちません。ハーモニーは作業の多くを行い、正式な繰り返しは少なくします。メロディートップc "は、新しい降下物のための強力なジャンプ・ポイントを提供し、出現するたびにテクスチャーを活気づけます。これは、「cc」と「cg」をdaの安定した選択肢として新たに使用することです。 (例えば、b90 'et resurrexit'、b。104 'et iturum venturus est')、それを支えるcおよびfベースのコードは意図的に予想される - モード変更がもたらしたFおよび補助的なC焦点に向かう次の動きで14クレド・アーメンの「正義との魅力」は、それが主張する確率を高めるものであり、クレドの主体とは異なり、聖歌。 Machautは自由な手でそれを設計しました。その結果がCredoの傾向をD Centerから離れたままにしていると思われるセクションであれば、それはまさにMachautの計画であったはずです。要するに、Machautの延長技術と <まとめ> マショーのprolongation と progressionのテクニックは、表面的なレベルでは著明に異なって見える音楽のセクションを結びつけているように思える。4パート扱いへの態度、早い段階から上声部を計画する必要性、 焦点とする音響の使用、prolongationとその大規模なメロディ秩序、フォーカルソノリティの使用、延長とその大規模なメロディー秩序、そしてtrebleとbassの優位性はすべて、私たちが、伝統的に、ミサたるものはフラグメントであるとして見ていたような明らかな旋法とテクスチャの分断を超えて、一貫しているように見える。 結局のところ、私たちは全体を一体的に扱っているのであろうか? 14 スタンザ メリスマ period イソリズムスキーム テノール イソリズム テキスト 声部 MotetusTriplum statement ContratenorTenor コロル ポリフォニー プレインチャント トゥルネーミサ曲 マショー KyrieChriste SanctusAgnus GloriaCredo 作曲 楽章 ミサ曲 |