| Machaut's
Mass4 Daniel
Leech-Wilkinson |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |
| 前ページへ |
| 4
Coherence 4.1Introduction score(このscoreは、GloriaとCredoにおいて、TenorとContratenorが逆なので注意) Paris, Bibliotheque Nationale, fonds francais 9221 (MachE) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000795k/f352.image マショーのミサ曲は、全体にどの程度の統一性があるのか? その疑問は、この本の随所に現れる。そして、大部分の作家は、それはユニットごとに生まれた、と結論づけている。 写本と典礼的証拠を使用しての最新の研究では、Elizabeth Keitelは、それはおそらく、いくつかの分かれた作業であった、そして、マショーの人生の終わりになって編纂された完成作品の写本に集められたに違いない、と論じている。 多発的作業であったという仮説の証拠は、Gloriaと Credoは、Amenを区別して記譜されたであろうという、そして、マショーによって選択されたすべてのチャントは、聖母マリアに結びつくものであろう、Keitelの観察に含まれている。それらは典礼的な重要性によって結びついていたのではなく、すなわち、それらは、ひとつの典礼的な祝祭のために集められて使用されたわけではないのである。 しかし、記譜の論議は強くはない。マショー自身のGloriaと CredoのAmenの写譜は、そもそも異なった作曲手順のために、物理的に、それぞれの楽章の主体の彼の写譜からは分離されている。Amenは、イソリズム的構築と同様のやり方で取り扱われた。低声部が最初に、Tenorのコロルから始まり、それから上声部の詳細が書かれた。そして、それゆえ、パートとして記譜されている。 テキスト化されているセクションは、全体的に同時に作曲されており、その単一テキストについてのホモフォニー的な設定のゆえに、もっとも経済的に、最低部の譜表の下にのみかかれたテキストとともに、スコアにおいて取り扱われている。 異なったレイアウトは、分離した書法の表面を含んでいただけでなく、最終的にクワイヤーブックに収載された時には、Gloria と Credoのパート名の間の混乱によって証言されたものとして、パート順の一致しない選択を積極的に奨励した。それらがAmenとは異なった機会に書かれたと考える理由は特にない。 Keitelが記述したチャントの混合した典礼的な機能は、Gloriaは結局、チャントをベースとしているという発見とともに、幾分減少して現れる。そしてそのGloriaは、マショーによって選択された写本(その解釈は彼自身によっている)中のKyrieとCredoのチャントの一連の流れで生じている。 しかし、ポリフォニーは、典礼的妥当性に関しては、非常にあいまいな点がある。作品がranked liturgical occasionではなく、特別な祝祭に対して作曲されたのであれば、こうした妥当性は、とにかくきわめて不適切となる。選択されたあらゆるチャントと聖母マリアとの関連性についてのKeitelの主張は、祝祭は、マショーの意思に捧げられた土曜日の聖母マリアミサであった可能性を強めている。 しかし、ミサ曲がバラバラに作曲されたという事実を強いられるのであれば、それがユニットごとに作曲されたと提案するとはどういうことか? 我々はすでに、KyrieからIteまで変化した(特に、低声部での直接の対位法の使用において)様式の特徴を見た。しかしそこには、ずっと一貫した特徴があるのだろうか? そしてそれらは、この作品に、あるいは(少なくとも)マショーの人生の期間についてのユニークな特徴なのだろうか? 変化したこうした特徴は、相対的に素早くなされたのか?あるいはそれらは、多くの年月を要して発展したのか? 4.2 Mode change (Kyrie , Gloria 、Credoにおけるレ音(ドーリア旋法)からSanctus , Agnus、 Iteのファ音(リディア旋法)までの旋法の終止音の変化があるが、マショーのミサ曲の2つの旋法の半分づつのTenorのメロディは、特定の和音コレクションとともに精緻化されている。 レ音の終止は、通常のカデンツ的導音ミ音(Kyrie,Credo)あるいはド♯(Gloria)を付随させている。どちらの場合も、C sharps and G sharpsとハーモナイズしている。作成される和音は主として、8-5和音である。 ファ音の終止は、その導音としてミ音を持つ。旋法の焦点の変化にも関わらず、ハーモニー的語彙は、ミサ曲全体を通して、比較的安定している。4 4 上記でリスト化された和音のカテゴリーは、このサマリーにおいて、単純化される必要がある。しかし読者は、スコアより、その最低声部としてのピッチを持った和音のさまざまな形式の間の作品を通して維持された一貫した関係を確認できるだろう。 この当時では、旋法的エビデンスは、特に十分ではない。聖母マリアの多くの数のチャントからの選択において、特に第1,5、6旋法は一般的であり、マショーはこうしたことを頭に置いていた。彼は、Credoにおけるドないしファをベースとした音響間のコントラストを最小化することに細心の注意を払っていた。その間、レ音の重要性は減じていた。少なくとも、Credoを作曲する間、彼はすでに、Sanctusについての提案をしていた。 4・3Lower-voice counterpoint 基礎的音響の完全、不完全形式の頻度は、旋法が変化するCredo→Sanctusにおいて、唐突に変わるわけではない。Kyrieの低声部は、8v-5th, 5th-3th 、 3rd-unisonの進行を保ち、当時の理論にもとづいた、”古典的”な対位法に近い。 Gloriaは、伝統的かつより抑制的である。三度の進行がより多い。これは、4パートテキスチャーすべてから減じられる音域と結びついている。KyrieIIと IIのTriplumのメロディ的クライマックスの重要点であるトップのド''音省くようにしている。声部はより斜行となり、より不完全なハーモニーとなって、たがいに押しつぶされている。 Credoは、前楽章とともに、結びついている。TriplumのレベルへMotetusを引き上げることによって、テキスチャーを拡大しながら、Kyrieの広い音域に戻っている。そして、Tenorは、以前のContratenorのレベルへとなった。それは、Gloriaからも含めて、様式やテクニックのその他の大部分の特徴となっている。Gloria と Credoは、明白なペアではあるが、それゆえ、ハーモニー語の重要な観点において、いわば、Gloriaの頭越しで、CredoはKyrieとリンクしている。 SanctusはCredo Amenと、Tenor とContratenorの不協和音から協和音へ拡大したその同様の使用法を通してリンクしている。第35-6小節の二度-四度-五度-オクターブというCredo Amenの進行は、Sanctusの第20-6小節にもまた生じている。 こうした進行は、ミサ曲の成長していく特長であり、マショーの様式がその作品の作曲の間に発達をした重要な証拠である。Tenor-ContratenorとSanctus, Agnus and Iteのパッセージの分離は、基本的な協和音進行の使用におけるKyrieのそれと関係がある。これらの上声部装飾は、いくぶん精緻ではあるが。 低声部の対位法を見れば、互いにcoherentなパターンが見分けられる。その低音域のタレアのリズムにおいてのように、Kyrie, Credo Amen, Sanctus , Agnus and Iteは、その対位法的基礎において、様式の根本的特徴を分有している。Gloriaは、ミサ曲の半分を占めるドーリア旋法の中間で対照的である。Credoは両方の方向に向いているように思える。つまりCredoは、広い空間の低声部が許す和音の間隔とメロディ形成においてKyrieに向き、その表面的形式のその他の特徴においてGloriaに向くが、直接的な低声部の不協和音の使用において、あるいはその大部分がドをベースとしたAmenにおいて、Fベースの楽章(Sanctus , Agnus、 Ite)に向かっている。 4・4 Four-part harmony 4・4.1 Dissonance control すべてのマショーの作品のうちで、おそらくは、ミサ曲は不許和音のもっとも大胆な使い方によって、刻印づけされるだろう。これらはさらに、逸脱として退散させられるであろうが、垂直的関係の不十分な制御の結果、実際それらは、非常に重要なスキルを取り扱うこととなった。 例17は、声部導入の小さいが代表的例である。それぞれのケースにおいて、声部の楽章がどのように論理的に不協和音を導くかが理解できよう。そしてそれから、それを協和音への解決と向かわせることにも。 こうした14世紀の音楽の不協和音を聴くことことを期待するにせよしないにせよ、マショーは正確に彼が何をしたかを知っていたのである。 4・4.2 Changing dissonance treatment 不協和音の取り扱いは、ミサ曲の特殊なセクションで特徴的である。たとえば、Sanctus and Agnusのペアリングのひとつの要素は、経過音の不協和音に対するその特殊な愛着である。(see Sanctus ,bb.2, 29, 57 , 85; Agnus 1, b. 12 and Agnus II , bb.9, 12 as a representative selection)。 そしてこれは、Kyrieとの親戚関係のもうひとつの観点である。(たとえば、Christe , bb.4-5 and Kyrie III , bb.I 9-20)。Gloria and Credoは、不協和音をむしろ困難に取り扱う。Gloriaの不協和音は、下方または内方へ向かう傾向にある(e.g. Gloria , bb. 10 , 17 , 27, 54, et c.)。これに対して、Credoにおいては、外方に向かって解決する率が高い(see bb.4, 50, 81-2, etc.).。 こうした異なった傾向は、無論、異なった音域、カデンツ形、と結びついている。同様に、Kyrie , Sanctus , Agnus and Iteの楽章拡張された経過的な不協和音形は、それらのイソリズム語と関係している。それゆえ、そのような”ローカルな”特徴は、全体的に、マショーの様式に帰することはできず、作曲習慣は、時代を超えて変化している。この観点から少なくとも、GloriaとCredoの本質的な相違は、様式の時系列的ミスマッチとしての対照に対する賛否表示のようなものである。 4・4・3 Consistent dissonance treatment 統一性についての論議への重要さは、それぞれの楽章に同時的に生じる、不協和音の莫大な数である。もっとも多いのは、七度和音である。7 それは非常に広範囲に使われているために、マショーのミサ曲の”サウンド”に生き生きと貢献するほとんど不完全協和音程の地位を得ている。 7”七度”とはここでは単純に、バス上の七度である垂直の音響と理解すべきである それらは、旋法や音域制限に伴い、あらゆるピッチクラスに生じる。Cをベースとして、主として、Gloriaに生じる。音域のトップエンドでのそれらは、Sanctus,A gnus and Iteにて制限されている。 例18は、中間音域の七度が生じる一貫性を示している(Ex. 18a on D, 18b on E and 18c on F。 こうしたことは、14世紀の音楽の共通した要素ではなかったことを強調したい。これらは、マショーの音楽においても、一貫して使われていたわけではない。ここで取り扱われたように、これらは作品に対しての統一言語であるだけでなく、その生成に対する限局したタイムスパンでもある。 4・5 Rhythmic coherence ミサ曲はときどき、リズム的保守性として記述される。しかし、KyrieIを超えてどのように幻想しているのかをイメージすることは難しい。おそらくマショーは、幅広い冒頭は、こうしたスケールにおいて適当である、と感じた。おそらく彼は、最初にむしろ単純な設定を計画したが、最初のページを越えて、彼のリズム的潤沢さを抑えきれなくなったに違いない。 その始まりの理由はともかく、ChristeからIteまでのそれぞれのセクション(無論、GloriaやCredoの主としてホモフォニックな部分は除く)は、14世紀後半のモテットの特徴であった上声部のhocketsとシンコペーションで注目される。 一般的な文脈において、マショーが使った正確な音型は、驚くほどに、ひとつのセクションから次にかけてと同様性がある。例19のレイアウトに示されているように。こうした例は、それぞれの例の最初のイソリズム的statementである。 すべての反復がカウントされれば、一般的なリズム言語(計量記譜、低声部パターン、フレーズ決定、カデンツ音型)の一貫性において、例外的な音型もまた、そのあたりに一貫して存在していることだろう。そして、14世紀半ば頃のモテットとの比較は、こうしたニーズが別にないことを示している。それは作曲的決定であり、伝統の産物ではない。 4.6 Motives? さらなる問題点は、ミサ曲が、統一性を意味する、繰り返しメロディモティーフを使っているかどうか、である。これは偽の問題でもある。のようなメロディ音型がめったやたらあるからである。そしてこれらは、様式についての一貫した特徴である。 しかし、マショーがこれらを統一性の産生の意図で使ったのかどうかは、彼が使った限りにおいては、疑問である。いずれにせよ、それらは、特に構造的意味合いはない。メロディ構造についての重要な特徴、光彩において収められる限り。 Gloriaにおける作曲手順の論議として、その楽章は、公式的には、そのメロディラインの本質的形によって決められる。すなわち、ステップワイズな昇降である。同種の形は、Kyrieのメロディフレーズでも見られる。ここではもう少し狭い音域となる傾向にある(主としてラーミ)。Christeの終わりでは、特に強調的に、KyrieIIIの終わりでは、それらの最終の下降の前の最高音のド音まで開いている。 クレドはその最初の”スタンザ”(第1-54小節)において、ラーミの執拗なまでのplaying(e.g. bb. 3-4, 6-7, 10ー12 ,17-19 (-21) , 25-6, 32-3 ,35-8)で、その前の2つの楽章に対して言及する。スタンザIIとIIIにおいて、このトップのド音は上声部の焦点のピッチとなり、下のド音は低声部の焦点のピッチとなる。 同時に、ソ音やラ音上の和音は、Sanctusにおける旋法の上方へのシフトの予見における共通のものとなる。Sanctus, Agnus and Iteにおいては、同じメロディ原理が当てはまるが、異なったピッチ境界であり、異なった方向に対してである。 Sanctusは、レ-ラの領域において、いくつかのメロディ形を使用している。しかし、そのもっとも傑出した音型は、ソから上がり、ドに達する上昇形である。最後になってのみ、上昇形は、最終下降シ♭→ファで解決される。Agnusセクションはしかし、基本的に、ファ音への下降に関心が向けられる。シ-ナチュラルは、演奏においては、ファの終止を食い止めるに求められている。Iteについては、シ♭はContratenorにおいて、譜表に書かれており、ハーモニーを否応なく、最後のカデンツに向かうよう結論づけられている。 メロディ構造の深いレベルでは、ミサ曲全体に対するマスタープランの非常に近代的な感覚においては、統一性ではなく、むしろ類似のメロディ形や、それぞれの楽章を構成するフレーズを基礎においた進行であり、統一性の印象であることが避けられない。それは、テクニックの、そして様式の統一なのである。 4・7 Quotations? 他所参照の最後のグループは同様のイシューが持ち上がる。同じような音楽パッセージがひとつの楽章以上に生じている多くのケースがある。 例20は、その著例を示している。Kyrieからの素材がその他すべての楽章で、突然出現していることは興味深い。それらの関係は、明らかに、Gloria and Credo and (iso)rhythmic characteristics shared with Sanctus , Agnus and Iteとの単純な旋法的なリンクよりもさらにはっきりとした関係を持っている。さらに、Kyrie-Agnus、Iteのリンクは、明らかに、作品の最後からその最初の特徴にいたるまで、聞き取り得る言及を示している。10 10 より大規模なスケールの形式でのヒントは、Kyrie,Credo,Iteの同類の最終カデンツで垣間見ることができる。それぞれのケースでは、普通の導音は突然、最後の瞬間に♯がつけられている。KyrieIIIとCredo Amenにおいては、ソナチュラルはソ♯となり、Iteの最終では、シ♭→シ-ナチュラル→ドへと屈折している。 残念ながら、こうした関係から、6つの楽章の作品順を推論することは不可能である。AgnusIは、KyrieIIIへ言及あるいは,KyrieIIIからAgnusへと言及しているが、どちらも、こうした言及が引用であるとは言えない。あるいは単純に、作曲家が彼の頭の中でスタイルを考えた結果なのかもしれない。あるいは、異なった文脈のあらゆる種類において、何度も何度もその特徴的な抽出物を産生していたのかもしれない。どのケースにおいても、むろん、それらは偶然の一致なのである。それらは力強く、作品に対して作曲された統一性を示している。 こうした証拠の集まりが示し得ることは、ミサ曲の言語が一貫して、そのハーモニー語彙、構文、そのリズム言語、そしてメロディ構築という重要な観点に多くある、ということである。こうした種類の詳細は、作曲家の一生を超えて、正確に変化していく類のものである。そしてこうした安定性は、ミサ曲が比較的短い期間で作曲されたことを強く支持する。 4.8 Developments これはむしろ、週単位などより、月ないし年単位で計られる必要があることは、KyrieからIteまでの変化の特徴によって示される。もっとも重要な、低声部の不協和音の使い方である。 Sanctusの直接的進行は、それ以前の楽章を通して、しだいに到達される。KyrieからGloriaを経て、そしてCredo Amenにいたる。Agnusは暗示的なバスの記譜の優美さを導入する。 こうしたテクニックは、非常に基礎的なものであり、日ごとに変化したようなものではない。しかし、こうした作曲作業の漸次の拡大は、これほどのスケールの作品の作曲においては、非常にしばしば生じることである。Kyrie, Gloria , Credo and Sanctusの作曲敬虔により、Agnusの声部導入は、論理的な発展をしたように見える。 こうしたことは、ミサ曲がその6つの楽章の演奏順に書かれたことを示している。もしもそれが単一作業で生まれたのであれば、期待されていた通りであっただろう、、しかし、もしもその楽章が、ひとつの楽章あるいは楽章のペアが必要に迫られてマショーの人生の異なった時期に書かれたのであれば、必ずしも、そうではない。 4・9 Satellite works マショーによるその他の作品とこのミサ曲の比較によって、その日付の疑問が投げかけられるかもしれない。特に、2曲が、密接に関連していると見なされている。Motet 23、Felix / ln violataと、Ballade 32、Ploures、Dame、 である。前者は Siege of Reims (December 1359 Jaanuary 1360)の後からの日付であり後者は、1362年のマショーの病気と関連して作曲され、その年の11月にPeronneに送られた。 前のパラグラフの記譜が示すように、Motet 23は、ミサ曲のDベースの楽章とと同様であり低声部にて不協和音を使用している。さらに、低声部のイソリズム的交換が,Motet 23とCredo Amenで同一である。より拡大した同類性は、(例21aおよびb、c)で観察される。 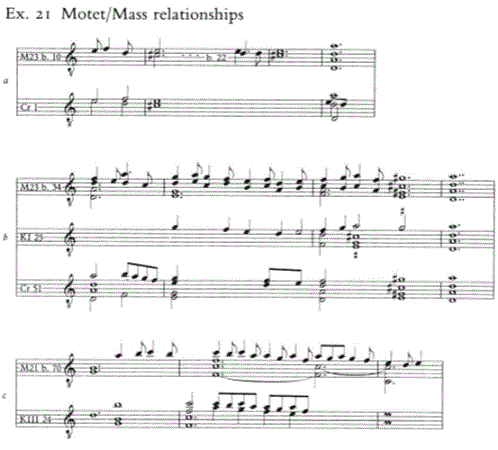 これらの関係は、低声部での不協和音の使い方において類似していると考えられ、モテットがミサ曲の最初のつの楽章と同じ時期に書かれたことを支持するのに十分な重要性を持っている(ミサ曲のための練習としてモテットを作ったのか?)。 ミサ曲とバラード32との間の類似性もまた、複雑である(EX.22).。Ballades 33 and 34 (Spring and Autumn 1363).1 にはこの様式の反響がある。  これらの作品の関係を引用として考えることは間違っているだろう。それらは、同じ時期に書かれた作品で見つかるであろう類の類似点にすぎない。 したがって、 Kyrie , Gloria and Credo へのconfinement は、おそらくマショーが1362年後半までになってやっとミサ曲を作曲したためであるがゆえであるという仮説を立てる試みがなされる。、おそらく旋法的な使い方のリンクの機能に過ぎないであろうが。 いずれにしても、作品は同時にまたは少なくとも連続して作曲されたと仮定することは妥当である。 ミサ曲の日付、 したがって、1360-5年はおそらくあり得るのであり、さらに1362-4年の間の可能性が高い。 それがMachautの記念碑的ミサ曲として意図されていたのであれば、 Ballade 32、Ploures、dames、ploure voostre servantの彼の「証言」を作り出した同じ病気が、ミサ曲作曲のきっかけとなった可能性は非常に高い。彼はもはや長くは生きられないことをよく知っていたのかもしれない。 4.10 Conclusion マショーのミサ曲は、循環ミサ曲であろうか? 確かに、15世紀後半のミサ曲は循環ミサ曲であったという感覚はない。あらゆる楽章を貫く単一の糸はない。 cantus firmus ミサ曲もパロディモデルもない。しかし、テクニックや様式、そしておそらくは意図において、統一はされている。 より重要であり、より確かなことは、中世の作曲家の偉大な業績の一つであるマスターピースとしての地位である。 私たちが歴史的な神話の中でそれに対する特別な主張をしなければならないならば、それで十分であるべきだろう。 スタンザ メリスマ period イソリズムスキーム テノール イソリズム テキスト 声部 MotetusTriplum statement ContratenorTenor コロル ポリフォニー プレインチャント トゥルネーミサ曲 マショー KyrieChriste SanctusAgnus GloriaCredo 作曲 楽章 ミサ曲 |