| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A
Case Study in Performance Practice7 by William Geoffrey Kempster |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p117 このセクションに続いて、新しい歌詞 Et iterum ventrus est・・・では、la Rueは、以下の例65のように、対位法における動機のペアを用いている。 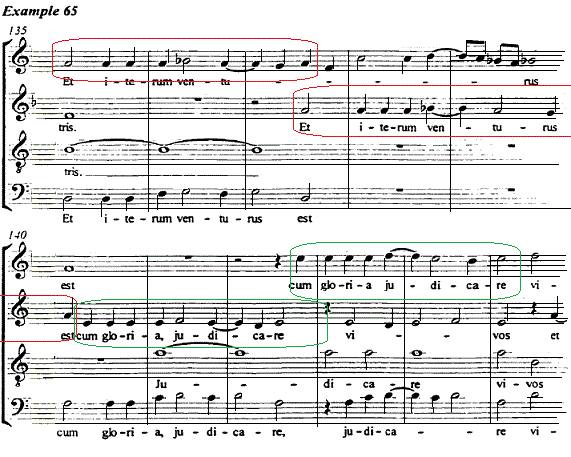 第139-140小節では、カデンツを装飾する典型的なルネッサンス期の繋留音的対位法が、A上のsuprasemitoneや、あるいは導音G♯のような変化を必要としている。 ソプラノの正確な模倣としてのアルトが第137小節から見られるとした場合、causa pulchritudinisを適用可能にして(例26[d] la Rueが、すぐに続く小節(第140-145小節)で、E(mi)上で開始された動機を移調すると、このパッセージを表現する決定mi-rni-mi-mi-fa-mi-re-miは、すぐに証明されることになる。 p118 以後のパッセージでは、これらの問題の多くが何度も出現し、同じ結論に至る。通常、B♭は全体を通して意図されている。 いくつかの例外があるため、ここでは「通常」と表現する。 これらの最初のものは、例66の第169~174小節の間で生じている。 そこでは、rectaの硬いBが戻っている。 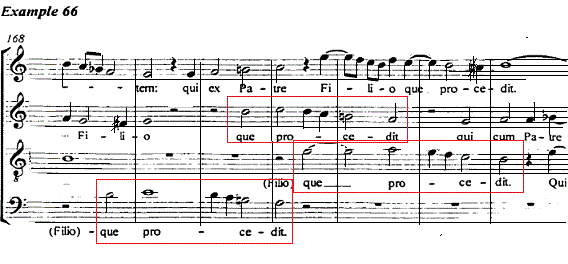 これまでのところ(第111小節以降)、このセクションの事実上すべてのフレーズ15の最後のバスの音符は、DまたはAのいずれかであることがわかる。 15 第138小節から148小節までのセクションは、もっとも低い音はAであり、旋法的には、ヒポドリア旋法となる。 ここのAは、que proceditのbass/alto/tenor motiveの動機のインパクトとともに、この短いパッセージを非常に印象的にしている。 この効果は、第111小節以降、L'homrne armeのメロディから引き出されたさまざまな動機が、テノールでcantus fimus の構造として連続して現れているというという事実によってもたらされる。 しかし、この時点で、la Rue は、例54 / 3a(p100)の曖昧さのない最初の声明を、そのまま転調した形でバスが入るように工夫している。これは、実際には「調性」の方向転換の手段として使用される。16 16 p119 上記で言及したもう1つの重要な例外は、例67での第211~216小節の間のパッセージで生じる。この場合、バスでの硬いヘキサコードの使用と、和声的三全音を回避する必要があるため、アルトでB 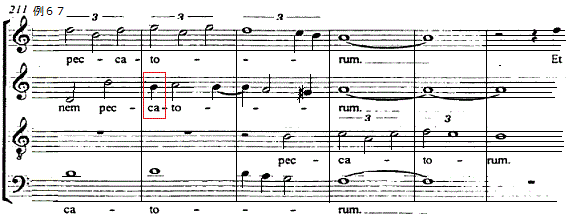 Bのアイデンティティに関して決定を下す必要があるもう1つの状況は、 Sanctusの冒頭で生じている。 第4〜5小節のソプラノパートの連続的な構成は、第4小節のB→F厄介な三全音が再度注意をひく。なぜこれが間違っているのか? 生のセクションは次のとおりである。 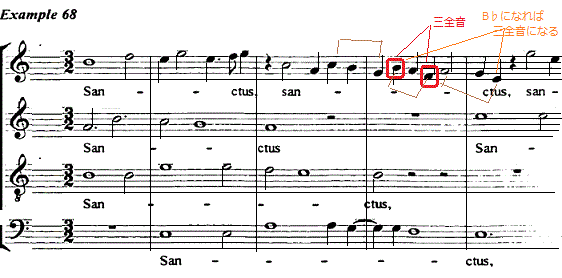 この例では、ソプラノにおいて、第3-5小節のメロディ領域はB→F,あるいはB♭→Eを含んでおり、メロディ上の三全音が不可避となっている。 p120 第4小節のオブリガートにおいてB♭を選択することは、このパートの連続する構造であり、バスとの関連でもある。これは、2通りのやり方で分析されることができる。 第3小節のBは、経過音としてよりは、機能的音調として響く。また、ここで明らかにされているのは、B♭が非常に説得力のある(そしてB これらの聴覚的印象は、ソプラノでの異なったフレーズの観点からの連続から支持される。17 17 したがって、潜在的なBからFへの音程はすぐ近くに配置されているので、この(連続で見られる)三全音を訂正するためには、B♭→E(の訂正)が優先されなければならない。(間に4音符が入っているB♭→Eと比べて、B→Fの三全音は、間に1つしか音符は入っていない)。これらのすべての側面が組み合わされて、下記で提供される解決が、唯一の満足できる解決となる。 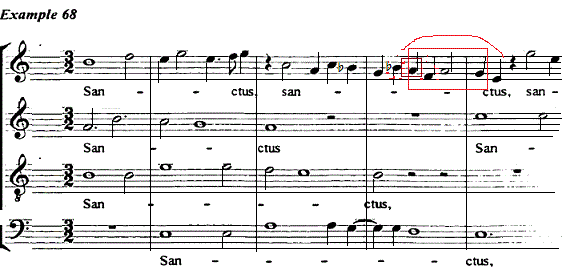 メロディ的三全音が避けられない同様のセクションは、以下の例70、Pleni within the Sancrusで行われているデュオの冒頭で生じる。 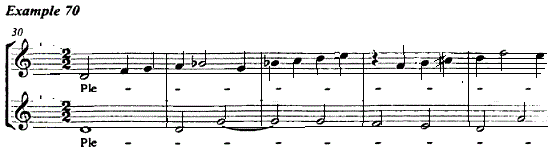 p121 最初の5小節を調べると、Bにどのようなrectaのアイデンティティが与えられていても、第30、31小節の間、または第32小節内でメロディーの三全音が生じる。 唯一の可能な選択肢は、第31小節から32小節で対斜を導入することになるが、硬いB このパッセージにおける2つのソルミゼーションの可能性を以下例71で見てみよう。 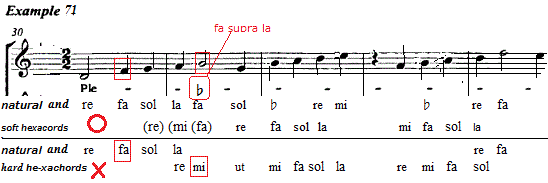 このような漸進的に上昇するパッセージでは、自然およびやわらかいヘキサコードが、自然および硬いヘキサコードよりも容易にインターロックするという通常のヘキサコード順序に従う。 さらに、第3章(ii)で説明されているfa super laの慣習は、B♭までのメロディラインの延長によって、mutatioが強制されるまで自然なヘキサコードを保持する、直接のmutatio、G sol reの代替を、実質的に提供する可能性がある。このmutatioのシームレス性は特に説得力がある。第2小節のB♭(自然なヘキサコードのfa super la)はやわらかいヘキサコードのfaである。 代替の解釈は、前者(やわらかいヘクサコードを使用する)がはるかに望ましいことを示している。 最初のBを p122 このメロディーの内容でも、2つのピッチでそれらを分離するだけで、それらの不安定な重要性を理解するために、論理を引き伸ばしすぎることはない。It does not stretch logic too far to realise their unsettling significance in this melodic context as well, with just two pitches separating them.20 20 Hughes、Ficta in Focus、p108も参考になる。「メロディの三全音を直接または介在音符とともに回避する場では、自身のメロディラインに戻るときには、垂直の五度、オクターブが不完全にならなければ、recta音符を使用せよ。」 この場合、メロディラインは、FからB♭への進行後に明らかにもとに戻ることになる。 このPleniには、musica rectaとmusica fictaの両方の分野で特定の課題を提示する別のパッセージが含まれている。 これらの中で最も魅力的なのは、例72の gloria tuaというテキストに設定された第52-66小節からの、拡張された模倣的対話にある。 例72 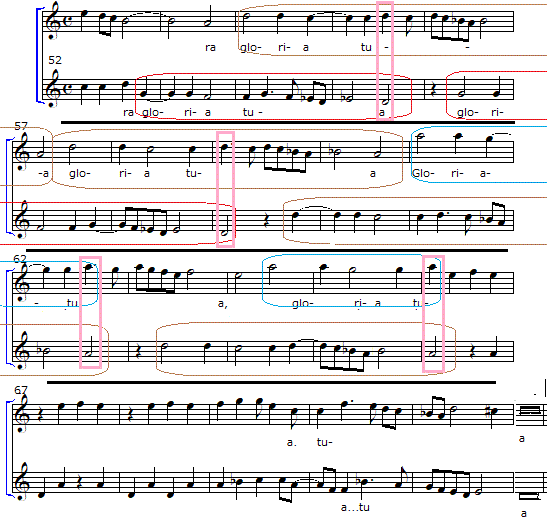 ここで最初に取り組むべき問題は、この旋律的構成が同じソルミゼーションを必要とするかどうか、またはデュオが純粋に全音階的に動作することが許容されるかどうかである。 問題は、その構造が、五度の上昇サイクルでの3つの異なったピッチドメインに存在することを観察することによって確信されることになる。 (i)G上で(第52小節および56小節から開始している)。 (ii)D上で(第54,57,59小節および63小節); そして、最も重要なものだが、 (iii)A上で(第61小節および64小節)。 全音階音域にとどまり、そして、五度での1回の模倣でこのパッセージに同じソルミゼーションを行うことは可能であるが、Fバージョン(やわらかいヘクサコード)は別のソルミゼーションを要求するために、この例において、連続する五度(G→D→A)とともにこのようにすることは、不可能である。 これが大きな関心事とは思われないかもしれないが、パッセージを詳しく調べると、la Rueにとって関心事であったことを示唆する証拠が明らかになる。 この点で、次のことを考慮する必要がある。 1. 動機が基礎となっているL 'hornme arme メロディ断片の旋法的な同一性。これにより、subsemitone の問題が顕著になる。 2 causa pulchritudinisの流れに沿ったオクターブユニゾンに一致するこうした動機の一貫した操作。 3 第69,70小節でのrectaB♭の不可避さ p124 これらの問題の最初の1のものをより詳細に検討しよう。 (iii)の動機のAバージョンは、自然なヘキサコード内に存在し、la-la sol-sol la-sol la sol fa mi fa-mi-として定着します。これは、L 'hornme armeの例54/3(iii)の1つのバージョン 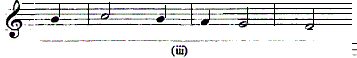 と一致している。それはまた、solではじまるその他の2つのピッチが目指すソルミゼーションとも異なっている。 と一致している。それはまた、solではじまるその他の2つのピッチが目指すソルミゼーションとも異なっている。これらをお互いに音程的に同一にしようとするのはなぜか? 1つの理由は、シャンソンのメロディーとの特に強い同一性にあるのかもしれないが、別の考慮事項がある。 この動機のGおよびDバージョンが活用されるが、それは、多くの場所での動機の操作が、ひとつかその他かどちらかのフレージングの重要な場所で、オクターブユニゾンで一致するように企てられているからである。 これらのオクターブは、第55、59、62、および66小節で発生している。それぞれの場合、問題は、sub-semitoneあるいはsupra-semitone進行が、オクターブの前に長六度を形成することを要求されるかどうか、ということである。 この例では、私は、sub-semitoneの可能性を破棄した(訳注;導音の排除)。なぜならそれを適用すると、L 'hornme armeメロディの旋法的な識別が破壊されるためである。この解釈は何を意味するのだろうか? まず、第56、59、60、61、62、65小節でのBの変更は、rectaの選択肢であり、これらのメロディの一般的な領域をやわらかいヘキサコード内にしっかりと配置している。 やわらかいヘキサコードの使用では、次の♭(E♭)がficta的変更として導入される可能性がはるかに高くなる。 "これは、このロジックがGバージョンでの動機に適用されたときに実際に発生する。第54、55、58小節で導入されている fictaのE♭である。 この解釈の結果は以下のようになる。 p125 1 動機は、すべての外見上、同一にソルミゼーションされる 2 すべてのオクターブの完全協和音程は、直近の不完全協和音程でアプローチされる 3 両声部の旋法的同一性は、ピッチの違いに関係なく同じである これらの要因がすべて偶然の問題として発生する可能性があると信じることは難しいと思われる。したがって、これが実際にこのパッセージを実行する正しい方法であることを示唆している。第69、70小節(の第2声部)を見ると、やわらかいヘキサコードは、使われてはいない直接的な三全音によってそれが強いられており、それへの親和性が強く示されている。 これは、上記の説明とは別に、デュオのその他のところとは明らかに一致せずして、Eが、第54-55小節および第58-59小節ではfictaE♭となることを示唆している。23 23 最後のカデンツは、Eとsub-semitoneのC♯となるべきだろう。アルトのB♭からの下降は、やわらかいヘクサコードからC上の自然のヘクサコードへのmutatioを要求する。デュオ内のそれ以前の使用におけるメロディーの構成音域(Gから開始)は、B♭上の仮想の(ficta)ヘクサコード内に十分収めることができる。 Benedictusは、選択肢がいろいろであり、複数の解決策が考えられる2つのパッセージを提示する。 これらのパッセージの最初のものは、変更なしでは、次の例73のようになる。 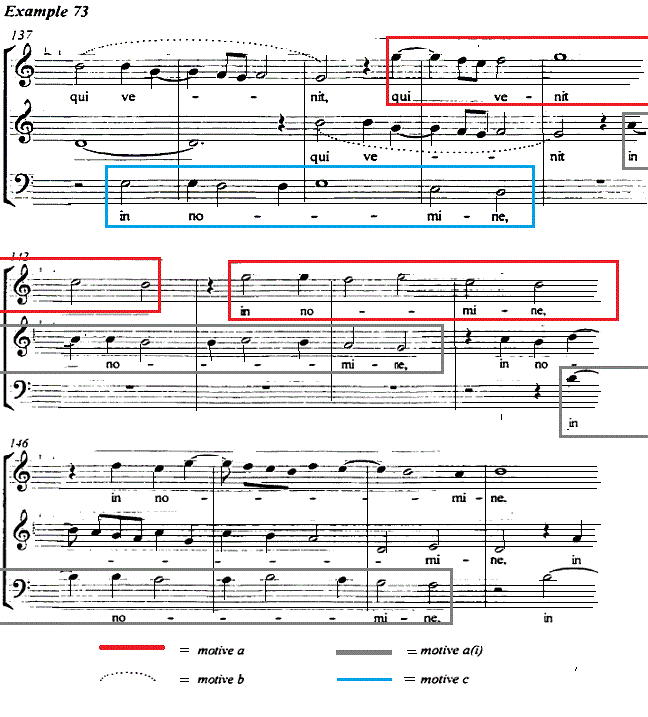 p126 L 'hornme armeメロディーに基づくさまざまな動機がここでは自由に使用されており、独創的な方法で使用されている。 第137-140小節のバス、および第139―145小節の間のソプラノ(2回)は、例54 / 3a(ii)-motive a 非常に密接に関連するmotive a(i)は、第141-144小節のアルトでそして第145-148小節のバスで、基礎を形成する。 一方、motive bは、例54/2 これらの動機の相互作用から多くのオクターブが生じる。 すべての場合において、これらは、それが含まれたパートのひとつのフレーズの最後の音符と一致する。したがって、確かにcausa pulchritudinisの原則に従った変更が必要である。 p127 特に興味深いのは、この(最初の)パッセージにおけるB♭の使用のfictaの広がりである。B♭は、例26[d] この動機の独特の性質と、それが139-141節でアルトですぐに繰り返されるという事実から、ここでは同じソルミゼーションが求められていることが示唆される。 これは、アルトとのmi contra faを回避するために、第140小節で、バスにfictaE♭を追加する必要性につながる。こうした決定は、パッセージの調査が続くにつれて、支持されるか反論されるだろう。 motive aの双方は、それぞれに同じようにソルミゼーションされる必要があると思われる。つまり、B♭とE♭のfictaヘキサコード上のla-la-sol-sol-la-fa-miである。 ゆえに、第144小節では、A♭アルトに示され、Fがソプラノで示され、長六度→オクターブと進行する。これにより、これらの動機の一貫性が保たれ、結果として、第141小節の終わりのアルトの入りから第145小節のソプラノの motive aの終わりまで、上位2つのパートでの五度の模倣が保持される。 第138小節のバスと第140小節のソプラノに加えられた追加的なfictaF♯のみが、このパッセージに対しての同じソルミゼーションの原則に対抗している26。sub-semitone とcausa pulchritudinisが対となった要求は、同じソルミゼーションのニーズよりも高いウェイトがあると考えられる。 26 However, all would still reference the same hexachordal layout. 加えて、第138小節のAがもしもA♭になったならば(ここではmotive bとして、五度の範囲内で生じる)、アルトのDとともに三全音が作られたことであろう。同じことが、第140小節でも生じたことだろう。どちらもあり得ない。 以上を総合すると、例74のようになる。 例74 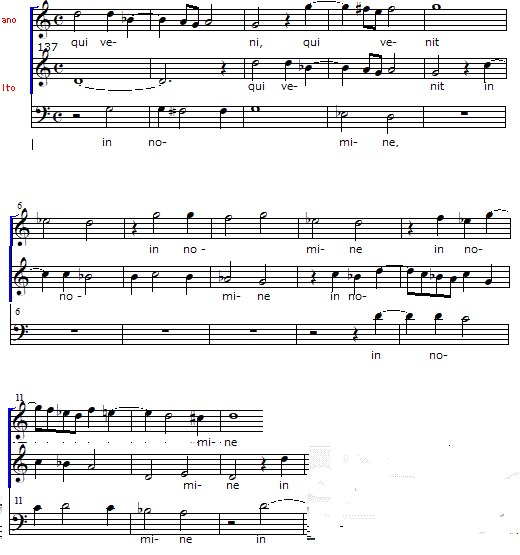 p128 上記の例74のすぐ後に続くセクションは、L 'hommne armeのメロディーに基づいたバスライン上の元の動機の操作が、ミサ曲全体で最も美しいパッセージの1つを生成するセクションである。 このパッセージでは、同じソルミゼーションが正しい選択肢であると思われるが、この解決策は、causa pulchritudinisの概念で必要とされるオクターブユニゾンへの動きの通常の方法が使われていない稀な例の1つになる。例75に、私が最終的な形にすべきだと思うものの一節を示す。 例75 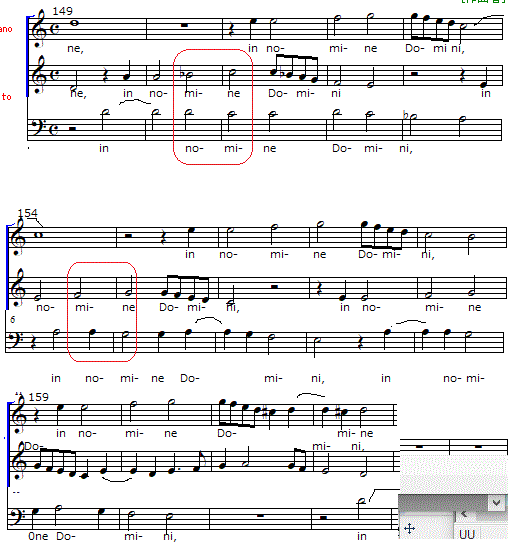 p129 テキストin nornine Dominiで特徴づけられた模倣は、再度五度を生じ、厳格な音程での模倣が2つのパートの間で企てられたことを可能にしている。 ただし、第150小節のアルトのB 第150-151小節および第154-155小節では、causa pulchritudinisに非常にうまく合う一方で、他の依存パートに大きな問題を引き起こす原因となるかもしれない。 p130 第151小節の(アルトの)メロディ上の三全音もまた-経過音的ではあるが-ここでの考慮事項である。まだ歌いにくいので。ここでの下降音型でB♭を歌う誘惑は非常に強い。(アルトでは)rectaB♭が、第151小節同様、第150小節で必要とされていることが明確に示されている。 したがって、この選択肢は、直接的な模倣的なソプラノとアルトパートのソルミゼーションに関して、パッセージ全体を一貫させている。そして、それぞれの例でパッセージが明らかにmi-mi-fa-sol-sol- fa-mi-re-utとソルミゼーションされる事実は、これがラ・リューの意図であると確信させる。 この解決策に対するさらなるサポートは、第153小節でのrecta B♭の同様な組み込みとともに、例54 / 3b(ii) Massの終わりの3回のAgnus Deiは 演奏慣行では、演奏者と観客の両方の心に徐々に浸透する動きの感覚の非常に穏やかで漸進的な抑制の感覚が顕著である。 作品の他のセクションでは、さまざまな旋法の利用を活用する作品の解釈を強く主張した。この最後の楽章で、しかしながら、 私が今説明した気分のコミュニケーションの本質的な側面は、これらの3つのセクション全体の一致の聴取者の認識に依存していると信じている。これは、いくつかの調性、B♭の選択肢の追加によってのみ成功した旋法的アイデンティティの一貫したコミュニケーションによって達成される。ここで証拠を見てみよう。 第2Agnusを形成する有名なメンスーラカノンは、パートごとでの調号で示され、アルトとバスパートの調号にはrecta B♭が表示されている。 したがって、2つのconcordantソースで、第1Agnusにも、バスではB♭の部分的な調号があることは興味深い。 この第1Agnusには、Davisonが使用した主なソース(Brussels MS 9126)もまた、第4小節のバスで生じる明らかな三全音を正すために、ミサ曲全体においてこの写本で記譜された3つの臨時記号のうちの最初の1つがある。 the principal source Davison uses (Brussels MS 9126) also has one of the only two signed accidentals notated by this manuscript in the entire Mass, occurring in the bass in measure 4, to correct an obvious tritone. ただし、この第1Agnusのその後の2つのBもまた、両方ともB♭であることが明らかである。 その最初のものは第7小節にあり、これはすでに示されたB♭を継続するだけでなく、アルトとの明らかなmi contra faを修正している。 したがって、第10小節の終わりまでに、バスは完全にやわらかいヘキサコード内にあることが明確になっている。 この時点以降も、音楽の進行は非常に似かよっており、バスはL 'hommne armeメロディーを正確に引用し続けているため、その次のものがある第14小節では、やはりB 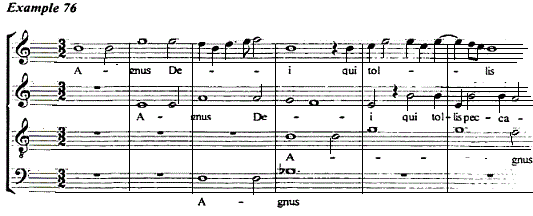 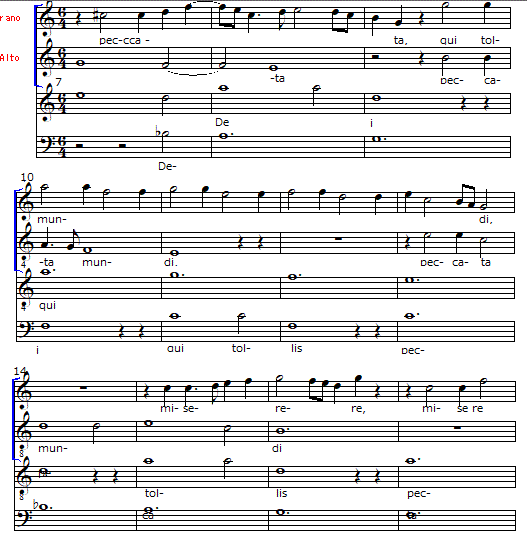 p132 したがって、第1Agnusのよりすぐれた編纂のオプションはおそらく、バスが、署名された♭を1つ持つことであることは明らかである。それは、最初の2つのAgnus設定の両方が、強くヒポドリア旋法と同定されることを意味している。では残された第3Agnusはどうなるのか? これら3つの”楽章”に特別な関係があれば、第3Agnusは、最初の2つの楽章の旋法的性格を持ち続けていると考えるのが自然なことだろう。 冒頭部分の精査により、これが事実であることが明らかになり、例26 [dii] これらの例の最初のものは、バスのfa super laのケースを表す可能性があるため、次のパッセージのために、第59小節以降、mutatioをやわらかいヘキサコードに変える。 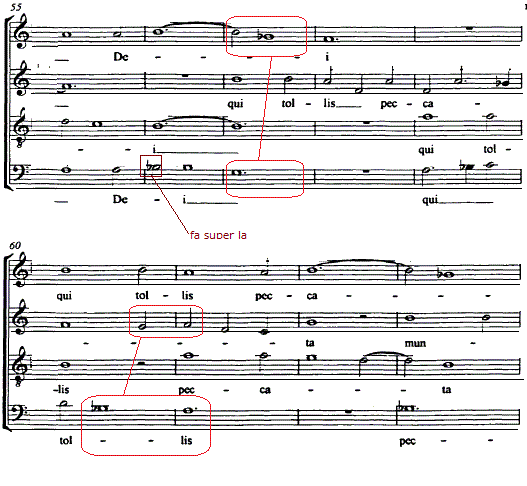 p133 ここから、B♭の他のすべての見込まれる例は同様に続き、各例はこの変更のケースを強化するだけである。したがって、B♭は、3つのAgnus設定すべてに対して独立して正当化され、1つの「楽章」から 次の楽章への進行は、これに対してより効果的で意味があることが明らかになった。 しかし、第67小節において、この状況に変化が起こる。ソプラノがL 'hommne armeメロディーの例54 / 3a(iii) 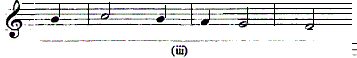 を取り上げるとき、Eが第68小節で明らかに要求されるため、第70小節では、B を取り上げるとき、Eが第68小節で明らかに要求されるため、第70小節では、B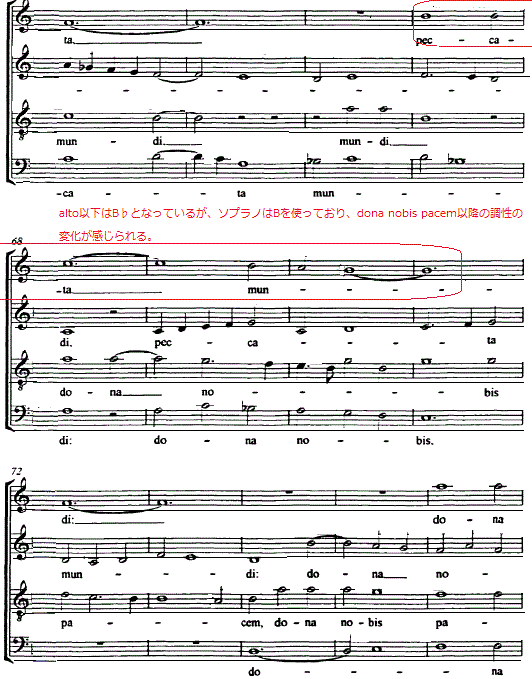 la Rueがここでのこの最終テキストのコンセプトの全体的な感覚に直接反応しているかどうかは議論の余地があるが、動機がどうであれ、B |